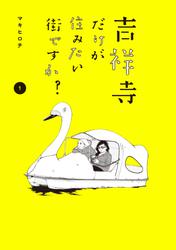
吉祥寺だけが住みたい街ですか?(1)
マキヒロチ
ヤングマガジン サード
吉祥寺に住みたい? ホントに?
住みたい街No.1という称号を長らく保持し続ける吉祥寺。 井の頭公園に新しい大きな商業施設、古くからの商店街や入り組んだ飲み屋街、古本屋に劇場などなど、 たしかに吉祥寺は魅力的な街ではある。 でも、そうした条件のよさが万人にとっての良さかというとそんなことはないのでは? という考えのもと、このマンガは進行していく。 両親が亡くなり、双子の姉妹は吉祥寺の小さな不動産屋を継ぐ。 まったく性格の違うふたりは、やる気がすごくあるというわけではないのだが、 お客さんの心を乱暴なようでいて丁寧にほぐして家を紹介していく。 電車の路線もまったく違う、吉祥寺以外の家を。 なんとなくの憧れとイメージで吉祥寺に引越し先を求める人々に対し、 希望を聞いた後、ここだという街へと無理やり連れて街を散策していく。 吉祥寺がイメージだったならば、他の街もまだ実際イメージでしかないのだ。 歩いて、話しをして、自分を見つめていくと街の風景は一変する。 街のおすすめ情報としても使える不動産マンガ。
4投稿日: 2015.11.13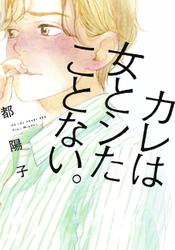
カレは女とシたことない。
都陽子
FEEL YOUNG
30歳を超えた奥手な男のかわいらしさ
タイトルだけ聞いて想像するのは、童貞かゲイかどちらかの話し。 答えは童貞なのだけれど、 8年間彼氏のいない32歳の女性が当時人気者だったイケメンの同級生と、 お見合いで出会い付き合っていく。 お見合いで出会っている以上、お互い積極的なタイプではないことが予想されるけれど、 彼は複雑にこじれた性格とかダメなやつというよりは純情さが祟ったタイプ。 ひねったタイトルで予想されるほど問題ばかりというより、 純情で奥手な男の子と付き合うしごくまっとうだけど、 30歳を超えた奥手な男のかわいらしさ、いじらしさは見どころである。
0投稿日: 2015.11.13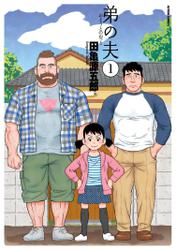
弟の夫 1
田亀源五郎
月刊アクション
ゲイ・エロティック・アートの巨匠、一般紙に降臨す。
雑誌「さぶ」や「Badi」といったメジャーなゲイ雑誌で活躍し、 世界でも名が知られるゲイ・エロティック・アートの巨匠、田亀源五郎。 そんな彼が一般商業誌にマンガを連載するというのは、 以前から知っている人にとっては大変な驚きだった。 主人公弥一の双子の弟がカナダで結婚していた男性のマイク。 彼が来日し、父娘ふたりで暮らす家に突然住むことに。 かつて愛した男と同じ姿形をした弥一を前に、 別人だとわかっているマイクも寂しくなったり、 弱気になったとき、どうしても重ねて見てしまう。 弥一はそんなマイクの行動に拒否反応を示しながらも、 愛する相手の性別が何であるかとは別の、 愛する存在を失ったことへの共感をもって接していくようになる。 いまだLGBTへの誤解や偏見が多い日本にあって、 偏見への理解が自然と進むよう、好奇心旺盛で純真な女のコを据え、 違和感を丁寧に馴染ませてくれている。 人を愛するとは何か、性別とそれをめぐる表現とは何か。 おもしろさとは別に気づきも多い作品だ。
7投稿日: 2015.10.06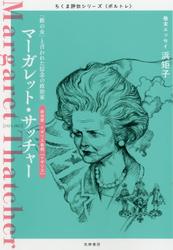
マーガレット・サッチャー ――「鉄の女」と言われた信念の政治家
筑摩書房編集部
ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉
サッチャーはいつから鋼鉄化したのか。
鉄の女と言われた欧州初の女性首相はいかに誕生したのか。 サッチャリズムと呼ばれた新自由主義、新保守主義を強く推し進め、評価の分かれるサッチャー。 イギリス経済を立て直した一方で、切り捨てられた弱者たちの存在もあった。 フォークランド諸島にアルゼンチンが侵攻した際には、艦隊をすぐさま派遣。 国にとって領土問題は何より大切だと強く民衆に訴えかけるできごとだった。 そうした彼女を作ったのは、敬虔なクリスチャンで真面目な父だ。 映画『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』を見た人は、 晩年の認知症は非常に痛ましく感じつつも、彼女のかつての強さを感じたかもしれない。 『トレインスポッティング』の労働者階級の厳しい現実を生み出した象徴でもある女性は、 どんな人生を歩み、”鉄の女”と呼ばれるに至ったのか。
2投稿日: 2015.10.06
お宝発掘!ナンシー関
ナンシー関
世界文化社
ナンシー関を受け継ぐ人間を待望
2012年、ナンシー関さんの没後10年を機に出版された、最後の単行本未収録本。 消しゴム版画家にしてテレビ評論家という稀有な肩書で活躍した、 ナンシー関はまさに稀代の才能だった。 我々の潜在意識を引っ張り上げるかのようなタレントを見る鋭い視線。最後に「知らないが」と突き放すように書いていたナンシー節がほんとうに懐かしい。 しかし、没後十数年経ってもなお、超える才能はもとより似た才能すら現れないのは実際なぜなのだろうか。 地上波テレビ以外にもネット局やユーチューブのオリジナル映像など、 見るべきチャンネルは増え、ナンシーが行きていたとしても 以前のように見ることはできなかっただろうが、 なぜもっと皆の集合無意識に訴えかける、あの毒舌を使いこなせる人は出てこないのか。 若者たち、ナンシー関を読んで、これから映像の海を批評的に乗り越えてくれ。そしてナンシー関に代わる最高の文章を読ませてほしい。
0投稿日: 2015.10.05
至高の日本ジャズ全史
相倉久人
集英社新書
私的だがこれが日本ジャズの現実
長らくジャズ評論会の長老として活躍していた相倉久人。 惜しまれつつも今年2015年、亡くなってしまった。 ジャズをただの曲として評論するのではなく、 社会の事象、個人の意志としてのジャズを語り続けた。 本書は1931年生まれの相倉久人が共に過ごしたジャズを体験として語っている。 音楽後進国であり、世界の流れとは別だと思われていた日本で、 アメリカのジャズ発生よりわずか後にジャズが奏でられていた。 戦前すでにスイング・ジャズも演奏され、 戦後日本は洋楽=ジャズと呼ばれもした。 駐留米軍との関係から進化した日本の音楽と音楽業界。 その後のジャズ喫茶や前衛芸術のひとつとしてのジャズなど、 日本が展開した独自のジャズ史を生で見続けた男の生涯の記録。
6投稿日: 2015.10.05
春山町サーバンツ 1巻
朝倉世界一
月刊コミックビーム
こんな渋谷もいいもんだ
東京渋谷といえば、いまや日本のどまんなかくらいのイメージです。 ところがこのマンガの舞台の渋谷区は、実にのどか。 渋谷区春山町にある区役所出張所に働くことになった巻村鶴子。 大きな事件のない街と日常にあって、 朝倉世界一らしい、何ともあやしい霞を食べて生きているような、 居場所なき人たちも。 タウン誌の編集長を急に任されたり、 何のお店をやっても潰れてしまうお店をどうしたらいいかと相談されたり、 ほっこりバタバタ楽しい世界一の世界。
1投稿日: 2015.10.05
サムライブルーの料理人 : サッカー日本代表専属シェフの戦い
西芳照
白水社
サッカー日本代表を支えた台所の番人
98年のW杯初出場以降、浮き沈みはありつつも個々の選手を見てみると、 確実に世界との差を埋めつつあるサッカー日本代表。 その裏には西芳照という福島Jヴィレッジ料理長の活躍があった。 西の最初の仕事は2004年のドイツW杯予選の帯同シェフとしての遠征だった。 シェフの仕事は選手のお腹を満たすだけでも、栄養を十分に摂らせることだけでもない。 同行したトレーナーからは、「選手はお客様ではないのだから、頼まれたことをサービスしなくてもいいよ。 あくまでも、選手が試合で十分な力を発揮できるようにマネジメントするのがスタッフの役割」だと言われたという。 海外長期遠征に疲れた選手たちにとって、気持ちも体もベストな状態で試合に臨めるよう、 食事が日々の楽しみになるようなものにしなくてはいけない。 そこで西はライブクッキングという方法を考え、どの遠征先でもそのための設備を必ず用意させる。 温かいままとはいえいくらビュッフェ形式で提供されるよりも、 目の前で自分の食べたい物を食べたい味で調理してくれる調理法に勝るものはないと西は考えた。 試合に勝つと、選手たちは「勝ったよ!」と仲間である西に喜んで報告してくれたという。 本書には描かれないが、2011年、東日本大震災による福島第一原発事故の対応拠点として、 Jヴィレッジは姿を変えていくが、西さんは作業員たちに腕をふるったという。
1投稿日: 2015.10.05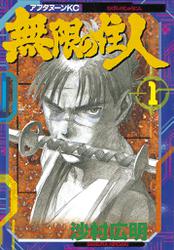
無限の住人(1)
沙村広明
アフタヌーン
不死身とは死なないだけではない。死ねないのだ。
2017年の映画化が発表された本作。 まさかキムタクとは想像もしていなかった。 圧倒的な画力と構成力、表現力で国内外を問わない 歴史もの歴史ロマンものを多く手掛ける沙村広明。 (もちろん現代ものやギャグものなども多数手がけている) 本書は、沙村のデビュー作。しかしその絵の持つ力は圧倒的だ。 残忍な剣客集団「逸刀流」に両親を殺された少女・凜が、 「100人斬り」の異名をとる不死身の剣士・万次を雇い、敵討ちの道を行く。 個性的なキャラクターや戦闘方法、エロティックな描写、 そして、扉絵や戦闘で秘技を繰り出した際の鉛筆に寄る1枚絵の迫力。 通常は印刷に適さない鉛筆で書かれたおそろしく繊細で勢いのある絵は、 額に入れて飾りたくなってしまうほどの完成度。 死にたいけど死ねない、死なないから死にたい。 死なない、死ねない、不死身の男・万次を、 キムタクはいったいどんな男として演じるのか楽しみだ。
3投稿日: 2015.10.05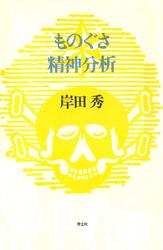
ものぐさ精神分析
岸田秀
岸田秀コレクション
自我、歴史、国家、神、性…全ては幻想である
「人間は本能の壊れた動物である」として、「史的唯幻論」を唱え、 個人の人間に限らず、集団や国家までもを精神分析の対象として分析してきた岸田秀。 心理学者、精神分析医である岸田は、 45歳という遅いデビュー作となった本書(77年)でそう宣言し、 その後のニューアカデミズムの萌芽ともいえる存在となった。 社会の様々な事象に応用可能な理論として当時大変な話題となり、 映画監督の伊丹十三は岸田に惚れ込み、精神分析の世界に入り込んでいったくらいだ。 黒船来航、太平洋戦争敗戦、資本主義などどんな話題であればっさりと切り、 解説をしていくさまは気持ち良い。 自我、歴史、国家、神、性…全ては幻想であるとして、 あらゆる営みを説明し尽くす岸田の論理にワクワクしるはずだ。
0投稿日: 2015.10.01
BACH/バッハさんのレビュー
いいね!された数446
