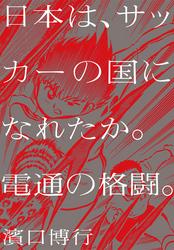
日本は、サッカーの国になれたか。電通の格闘。
濱口博行
朝日新聞出版
もちろんサッカーはお金じゃないけれど
日本サッカー史の背後には必ずと言っていいほど電通(ちなみに2013年までは、Jリーグは博報堂だけで、電通は日本代表を担当している)の存在がある。 この本の著者は72年に電通に入社後、02年にはFIFAワールドカップ日本招致委員会国際部長として活躍し、2006年からサッカー事業局長を務めた。そして今なお、2018/2022FIFAワールドカップ日本招致委員会エグゼクティブ・アドバイザーも務めている。 現代スポーツにおいて、ビジネスとしても成功することは言うまでもなく重要なこと。でもサッカー愛溢れるような人からすると、電通マンの役割を徹底すればするほど、選手や大会などをビジネスの対象として割り切っているような感じもしてきてしまうけれど、サッカーをビジネスとしていかに捉えるかは、サッカー界を盛り上げるために必要だと気付けば、むしろ発見が多いだろう。 例えば、「Know How(実践的知識)よりもKnow Who(人脈)が大切」だと書かれるこれは、おそらく正解なのだろう。サッカーの希望と未来をいかに作り出すか、それをお金とメディアの面で支える大切な役割を、私たちは無視できない。
0投稿日: 2014.06.10
新版 遠野物語 付・遠野物語拾遺
柳田国男
角川ソフィア文庫
名文家の文章として味わう民俗学
岩手県遠野出身の民話蒐集家であった佐々木喜善の語りによる、遠野地方の民話を、柳田が聞き、文字に起こし、編纂し自費出版した柳田初期の代表作。 官僚的な論文の多い柳田の著作にあって、極めて平易な語り口で、天狗や河童、座敷童子など妖怪に纏わるものから山人や神隠し、村に残る言い伝え、祀られる神々、そして年中行事などが語られる。 長短様々な119話からなる本書は、当時わずか350部を自費で刷ったのみだった。記録しなければ確実に失われてしまう。現代では信じられないような迷信のような出来事も、当時の人々にとっては、生きる現実だった。いまの常識が、未来の驚きや笑いの種になる、そう思いながら俯瞰してみて自分たちをみるきっかけになるかもしれない。
7投稿日: 2014.06.10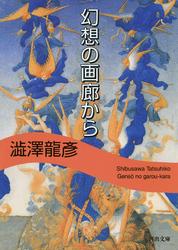
幻想の画廊から
澁澤龍彦
河出文庫
若者にダークサイドを植え付ける最高の1冊
ポール・デルヴォーとハンス・ベルメエル(ベルメール)、レオノール・フィニー、イヴ・タンギー、ルネ・マグリット、ゾンネンシュターン、サルバドール・ダリ、マックス・エルンスト、フランシス・ピカビア、アルチンボルド、ギュスターヴ・モロオ、ルドヴィヒ2世と郵便配達夫シュヴァル、そして現在展覧会が開催されている(2014.6現在)バルテュスなどなど。 知っている人にとっては、愛してやまない芸術家たちの名前だけれど、知らない人にはまったく知られていないであろう人々が、少女、機械、人形、玩具、仮面、迷路、狂気、夜、性といった要素から語られる。シュールレアリスムという、当時それほど知られていなかった芸術様式をいち早く紹介した澁澤龍彦という稀代のディレッタントの好みがひたすら反映されている。 「デルヴォーの絵はひそかに見る物の参加を要請する。私たちの視線が女たちの凍結した肉体を溶かしその内部の官能の火照りを解き放たなければならない。そこで初めてドラマが起る。しずかな戦慄が見る物の全身を走る」 6、70年代、日本の若者のダークサイドに多大な影響力を持った澁澤が、シュールレアリスムを一気に広めた名著。
1投稿日: 2014.06.10
21世紀を信じてみる戯曲集
野田秀樹
新潮社
小説では、これほど言葉を使い倒すことはできないかもしれない
書道教室が神話空間と化し、集団とその物語が変容する。物語全てが、ギリシア神話さながらの、変容(=メタモルフォーゼ)を繰り返す。信じていたものが姿を変え、違う様相へと移り変わる「ザ・キャラクター」。キャラクターは性格であり、文字のことである。書かれた文字が意味することは、読まれることで音となり、意味は変容していく。 アミューズメントパークを偏愛する父、アイドル系を偏愛する母、ファーストフードを偏愛する娘。3人家族の偏愛が世界の終末を招き寄せる、亡き中村勘三郎と野田秀樹がダブル主演した「偏愛=何かにハマっている」家族の肖像「表に出ろいっ!」。ハマることで、現在にどうにかしがみつきながら生きる現代の人々の戯画でもある。 火山観測所に赴任した男と虚言癖の女。大噴火の噂を巡って、情報と感情と信頼、個人と土地の歴史が交錯する「南へ」。なぜ女は嘘をつくのか。嘘がつくことで何が得て、何を失うのか。 2010年から11年にかけて上演された、「信じるとは何か」を問う三部作。縦横無尽に言葉を使い倒す野田演劇は戯曲だからこその楽しみに溢れている。
1投稿日: 2014.06.10
空飛ぶタイヤ(上)
池井戸潤
講談社文庫
真実の可能性は、小説によってまた描かれる。
脱輪事故によって人を死なせてしまった運送会社。 しかし、その責任は本当にドライバーのものなのか。 整備は十分になされていた。 自動車メーカー側に責任はないのか。 パーツは正しいものが使われていたのか。 三菱自動車のリコール隠し事件をもとに、 日本を支える大企業と小さな会社の争いと、正しさの行方を追う。 無理な値段で仕事を買い叩かれる街場の工場。 断れば会社は立ち行かないが、その値段で受けることはどこかでの妥協も意味する…。 それは何か不幸な未来を生み出すかもしれない。 論理的な正しさと人間的な判断のやむを得なさ、 働くという事、人間と人間が仕事をするということの困難が描かれる。 日本を支える基幹産業による失態が、なかなか大規模な報道にまで至らないとき、 真実の可能性は、小説によってまた描かれる。
11投稿日: 2014.04.29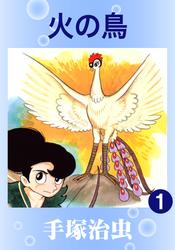
火の鳥(1)
手塚治虫
手塚プロダクション
マンガ史に輝く地球規模の傑作
日本を始め、ヨーロッパや宇宙までを舞台に、 時代も場所も縦横無尽に語られる、生命の本質や人間の業。 邪馬台国の“黎明編”から、物語は徐々に未来のできごとへ。 悩み、苦しみ、それでも生きる人間たちの姿。 これほど深く人間の苦悩や本質、生命や地球とのリンクを描いたマンガは、 2011年になった今でも『火の鳥』以外になさそうだ。 手塚治虫が26歳の時から描き始め、30年以上に渡りライフワークとして描き続けた。 それは手塚の思想の変遷を反映した、手塚治虫そのもののような作品になった。 大きな物語りを創造しながら、小さな命である昆虫を愛し、医学部にも通った手塚は、 小さな書ころから世界や人のあり方に思いを巡らせていたのかもしれない。 永遠の命の象徴であり、体現である“火の鳥”は、手塚にとって憧れでありながら、 永遠に生き続けることの恐怖をも表しているようだ。
1投稿日: 2014.04.29
ヒップホップの詩人たち
都築響一
新潮社
ラップをただの自分語りではないけれど、来歴を知るおもしろさは確実にある。
徐々に一般的なものになり、耳馴染みはよくなってきた日本語のラップ。 しかし、それらの多くはJ-POPと呼ばれる範疇で語られることが多いラップばかり。 アンダーグラウンドで続けきてたラッパーたちの姿は、まだまだ十分に知られているとはいえない。 日本のラップ黎明期から活動してきたラッパーを始め、日本語独特の訛りとフロウを身につけた新世代まで。 彼らの口から出る「詩」の成り立ちを、流行やテレビ、雑誌的な網からこぼれ落ちたもの専門の編集者都築響一が、 綿密なインタビューを通して明らかにしていきます。 登場するのは、田我流、NORIYUKI、鬼、ZONE THE DARKNESS、 小林勝行(神戸薔薇尻)、B.I.G.JOE、レイト、チプルソ、ERA、志人(降神)、RUMI、ANARCHY、 Twigy(マイクロフォン・ペイジャー)、TOKONA-X、ILL-BOSSTINO(ブルーハーブ)。 家族構成、生い立ち、時には犯罪歴など、その来歴を徹底的に取材。 かつてやんちゃをしてきた人が多いのはイメージ通りかもしれないが、しっかりとした学歴を持つラッパーもいる。 インタビューの間に挿入されるリリックは、その生まれや家族、友人、社会との関係を知った瞬間、また違った表情を見せ始める。 アイドルが披露するラップではなく、ラップだけをするラッパーたちの真摯な言葉と活動に丹念に向き合ってみることは、 決して無駄なことではない。
0投稿日: 2014.04.28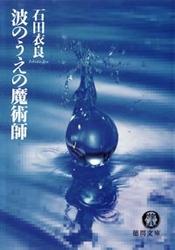
波のうえの魔術師
石田衣良
徳間書店
知識は命を救い得るか
『池袋ウエストゲートパーク』で知られる石田衣良が、 金融マーケットを舞台に繰り広げられるマネーゲームを、 専門知識を存分に盛り込んで描いた作品。 ちゃんと就職した同世代から取り残された就職浪人の青年は、 ジジイと呼ぶ老人との出会いで人生が変わっていく。 老人から月給三十万円でもちかけられたアルバイトにのり、 渡された住所を訪ねてみると「さあ、新聞を読みなさい」と株価チャートとにらめっこする日々。 金融市場とは無縁だった男が株取引を学び、習得はすることは可能なのか!? もがく青年を横目に銀行のチャートを見つめる老人はまるで、うねる経済の波に乗る魔術師。 灰色のデジタルの波が押し寄せる沖あいにすくっと立ち、濡れもせず、波に揺れもしない。 ただ波を見つめ、トラップを仕掛ける大手金融機関に狙いをさだめていく。 経済モデルから東証の値動き、投資技法や不良債権まで、 個人投資家へ道とも言えるマーケットを知ることができる小説なんて、珍しい。
2投稿日: 2014.04.28
娚の一生(1)
西炯子
月刊flowers
男の色っぽさ獲得法 難易度高め
30代半ば、理系女子。 東京の大手電機メーカーに勤めるビジネスウーマンの堂薗つぐみは、これまで仕事一筋。 やっと長期休暇をとり、祖母の家がある田舎へ戻るのだけれど、 そこで待っていたのは休暇の日々どころか、入院してしまった祖母が亡くなるという事態。 そして、葬式に来た謎の哲学者、海江田は祖母の家の離れの鍵を持っていて…。 在宅勤務に転じて、田舎にそのまま住むことにしたつぐみと、離れに居つく海江田との奇妙な生活。 女性なら誰でも考える、“結婚”や“旦那を見つけること”への焦燥感がリアルに描かれる一方で、 前代未聞の“一目惚れ”は類を見ない展開で驚きを隠せない。 過去の失恋から恋愛に踏み出せなくなっているつぐみだけれど 、一途に愛されることで彼女の気持ちは変わっていくのだろうか。 ちょっと強引で頑固な海江田の片想いの行方が気になる。
0投稿日: 2014.04.28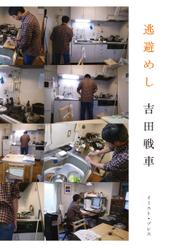
逃避めし
吉田戦車
イースト・プレス
逃亡先は台所
例えば夏休みの終わりでも良いのだけれど、何か〆切なるものがあることがわかっっていても人はなかなかやらない。 むしろ〆切をどこか逆算して、ギリギリ終わるか終わらないかレベルまで逃避するのである。 吉田戦車の逃避先は、料理だった。もともと駄料理と吉田自身が呼んでいたB級料理のようなものたち。 原材料高騰によってちくわの穴が広がっているというニュースを検証すべく、 「ちくわの穴確認弁当」を作り、穴に何らかスピリチュアルな味わいを感じたかと思えば、 嫁の実家がある長野県の八ヶ岳に敬意を評して、 ご当地名物を散りばめた自作駅弁「八ヶ岳鮭きつね弁当」を作ったりもする。 冷蔵庫にあった残り物、実家から送られてきた食材などを使い、さっと作られる料理は、 特に上手なわけではない自身撮影の写真とあいまって、おいしそうに見えるとは限らない。 ただ、その語り口は実においしそうで、料理をするということ、食べるということの哲学と喜びを感じるのだ。 大袈裟に言った。地味だけど本当に良い本。
1投稿日: 2014.04.28
BACH/バッハさんのレビュー
いいね!された数446
