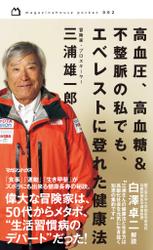
高血圧、高血糖&不整脈の私でも、エベレストに登れた健康法
三浦雄一郎,白澤卓二
マガジンハウス
自由でありながら、この男、不死身か。
1932年生まれのプロスキーヤー、三浦雄一郎。70年にエベレストのサウスコル8000m地点からの滑降を成功。その記録映像が『The Man Who Skied Down Everest』(「エベレストを滑った男」)というタイトルでドキュメンタリー映画化され、アカデミー賞記録映画部門で賞を獲得している。 そして昨年2013年、81歳でエベレスト登頂というギネス記録を打ち立てたこの人は、当然のように健康の塊だと想像していたのだけれど、それは想像でしかなかった。 60代前半は164cmで体重85kg。“高血圧”“高血糖”“高脂血症”“不整脈”、さらには“肥満”“糖尿病”という症状を克服しながらの登山であり、スキーだったのだ。102歳まで生き、100歳でもまだ登山とスキーを続けた三浦の父、敬三のストイックさとは異なって、三浦は自由(面倒くさがり)で、お酒とおいしいものが大好きな人間。 三浦家オリジナルの酢卵スペシャルドリンクやバランスのとれた赤ちゃん用粉ミルクで栄養分を補給する。登山は頂上にピークを持っていくため、麓で80kgあった人が、上では60kg台にまで落ちるという。100歳超えの父を模範にしつつ、ストイックになりきれない雄一郎も、食事、運動、生きがいという至極当たり前の三つがやはり重要なことには変わりはない。
1投稿日: 2014.07.25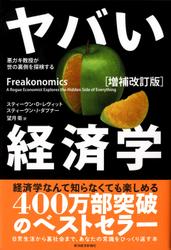
ヤバい経済学〔増補改訂版〕―悪ガキ教授が世の裏側を探検する
スティーヴン・D・レヴィット,スティーヴン・J・ダブナー,望月衛
東洋経済新報社
目からうろこの世界の理解をする方法
「90年代のアメリカで犯罪が激減したのが中絶の合法化のおかげとは?」「銃とプールと危ないのはどちらか」「麻薬の売人はなぜいつまでも母親と住んでいるのか」「相撲取りと八百長のインセンティブ」。 本書の項目は、こんな気になって仕方がない文言でうめつくされている。起こった出来事の表面をすくい、理解したつもりになっていることが、経済学的思考法を使うことで、一気に違った顔を見せ始める。 原因と結果を、インセンティブ(=人の意思決定や行動を変化させるような要因)を拠り所に論理的に考えれば、相撲取りが八百長をすることは必然的なことになってしまうのだという。 実際に八百長報道が明るみに出る前に、偶然にも本書はそのことを説明してしまっていた。神聖なスポーツと呼ばれる相撲の勝敗ですら経済学で分析できてしまう。なんとも恐ろしい…。 欲望と資本主義社会で働く強力なインセンティブは、経済の論理で可視化される。
1投稿日: 2014.07.25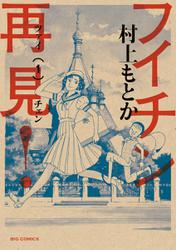
フイチン再見!(1)
村上もとか
ビッグオリジナル
日本にまだ女性漫画家が誰もいなかった頃のこと
現在マンガ好きと言われる人の中でも上田としこを知っている人はどのくらいいるだろう。おそらく1割の人も知らないだろう。 上田としこは1917年、満州のハルピン生まれ、長谷川町子よりも3歳、手塚治虫よりも11歳も年上の女性漫画家。ハルピンで様々な国籍、人種の人々と触れ合って育った、お転婆な少女は、高校から日本に戻り、漫画を描くことに熱中し始める。 中原淳一や松本かづちら抒情画がブームの頃。抒情画が好きではなかった彼女だが、一方で松本かづちが抒情画とは別に描いていたマンガが好きだった。何のめぐり合わせか松本かづちに弟子入りするチャンスを得た彼女は、松本の家に作品を持込、見てもらうようになる。 徐々に彼女は、イラストのカットを仕事をもらっていくが、絵の基礎がない彼女は、そのことに悩み苦しめられることとなる。お金持ちの家に生まれ、ハングリーさに欠けていたとしこは、長谷川町子というライバルの存在によって奮起。 日本にまだ誰も女性漫画家がいなかった時代、上田としこは長谷川町子とともに、その道を歩み始める。
1投稿日: 2014.07.18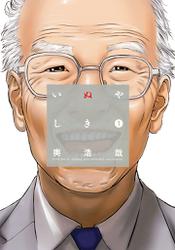
いぬやしき(1)
奥浩哉
イブニング
現代の父の寂しさを、圧倒的な物理的破壊力で補完する
なんて寂しくて悲しい男の物語だろうと、最初の数話は思うはずだ。 人によっては感情移入しすぎて辛いかもしれない。 犬屋敷壱郎は、嫁と高校生の娘、中学生の息子という家族から疎まれながらも、58歳にして一軒家を手に入れた。 にも関わらず、感謝もされず文句ばかり。居場所もなく、仲間は犬のはな子だけ。 突如余命3ヶ月と診断されるところから、この物語は想像もしていなかった方向へ転がり始める。 58歳にすら見えないいつも小刻みに震えている完璧な老人である犬屋敷が、まさかの『GANTZ』的展開に。 「何が楽しくて生きてるんだろうな」と中学生に言われる犬屋敷は、 生きる意味を人の命を救うために使おうと決心するのだ。 それがどんな方法かは、ぜひ読んでみてほしい。まさかの展開に驚くはずだ。
9投稿日: 2014.07.18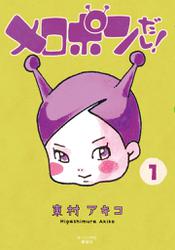
メロポンだし!(1)
東村アキコ
モーニング
マック赤坂はイプシロン星人である。
『海月姫』や『主に泣いてます』で人気の東村アキコ。彼女のもうひとつのマンガ家としての仕事はおもしろすぎる息子のごっちゃんを描くこと。これは『ママはテンパリスト』という子育てマンガとして最高の形で実現されている。 本作は、そのごっちゃん物語の変奏版とでもいおうか、地球の、それも日本のテレビを愛し、愛しすぎたがゆえに原宿にスカウトされにやってきたグリーゼ581のイプシロン星人「メロポン」のお話し。 まるでごっちゃんのメロポンは、小学1年(地球で言う)にしてすでに高度な自己プロデュース能力でもって、語尾を“でし”“だし”にして演じている。 宇宙人を信じる団体の教祖を母に持つ若様のもとで暮らすメロポンは、ウソと偽りと金と欲望が渦巻く汚すぎる芸能界に入り込み、成り上がることはできるのか。 大人のウソ、子どもの夢、何かを強烈に信じる人間の強さと弱さ、実はいろいろな要素が詰め込まれた東村アキコ作品は一読の価値がある。『ママはテンパリスト』と併読がおすすめ。
3投稿日: 2014.07.18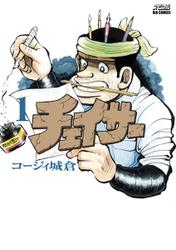
チェイサー(1)
コージィ城倉
ビッグスペリオール
手塚治虫を追い続け、真似し続ける男にどんな未来がやってくるか
「おれはキャプテン」の作者として、また「グラゼニ」の原作者(森高夕次名義)としても知られるコージィ城倉が、本作でモチーフとしたのはマンガ家。 昭和30年代、講談社の「マガジン」と小学館の「サンデー」という週刊漫画誌が発行され、劇画ブームが始まり、アニメの放送が始まる。そんな手塚治虫全盛期、手塚に憧れながら、ライバル視する戦記モノのマンガ家海徳光一。 ほぼ同年代である彼は、手塚の徹底的にライバル視し、その後ろを追い続ける。編集者には手塚のことなどほとんど知らないとバレバレのウソをつきながら、海徳は手塚がやっているあらゆることをマネしていく。 オーディオセットでクラシックを聴いているときけば、わけもわからず買い、手塚の生原稿を見ては、使う原稿用紙を真似し、うつ伏せで描いていると聞けばそうしてみる。全ての仮想敵であり理想が手塚なのだ。 有能な人間ですらこなすことが到底不可能は仕事量をこなし、時にこなせずに窓から逃げる手塚。そして海徳は逃げることすら大物の証と真似してみせる。 手塚の顔は出てこない。後ろ姿しか描かれない手塚の偉大さを、手塚ではない人間経由で描く“チェイサー=追跡者”の物語。
1投稿日: 2014.07.17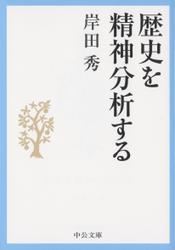
歴史を精神分析する
岸田秀
中公文庫
人間は本能の壊れた存在である=史的唯幻論
『ものぐさ精神分析』で国家や集団をひとつの人格として捉えて、精神分析をしてみせ、物質的、経済的条件で歴史を説明する“史的唯物論”に対し、壊れた本能に代わり幻想こそが人間や歴史の最大の動力であるとする“史的唯幻論”を唱えて一世を風靡した岸田秀。 この人の本は、恐ろしいほどのわかりやすさと納得をもたらしてくれる。腑に落ちるとはこういうことかと間違いないなく感じられるはずだ。 過去のことであっても、同時代であってもどうしても納得出来ない歴史的事件がある。岸田は本書でそれらを見事に考察、分析している。 “そもそも歴史をもっているのは人間だけである。それはなぜかと言うと、人間だけが過去を気にする動物だからである。なぜ過去を気にするかと言うと、一つには、人間には行動選択の自由があり、あのときああすればよかった、こうすればよかったといろいろ後悔するからである。なぜ人間に行動選択の自由があるかと言うと、本能にもとづいて自然のなかで調和的に生きている動物と違って、人間は本能が壊れ、その行動が本能によって決定されないからである。本能とは行動規範であるが、本能が壊れた人間は本能に代る行動規範をもたねばならない。それが自我であり、人間は自我にもとづいて、たとえば自分は男であるとか、社長であるとか、日本人であるとかの自己規定にもとづいて行動を決定する。ここに、人間が過去を気にする第二の理由がある。自我というものを構築した以上、人間は自我の起源を説明し、自我の存在を価値づけ正当化する物語を必要とするが、この物語をつくるためには過去を気にせざるを得ない。”(『二十世紀を精神分析する』) 国家という人格を正当化するために行われた、歴史のあれこれ。
2投稿日: 2014.07.17
すごい畑のすごい土 無農薬・無肥料・自然栽培の生態学
杉山修一
幻冬舎新書
科学的=トップダウン式ではなく、自然的=ボトムアップ式の農業
弘前大学農学生命科学部教授の杉山修一は、“野外における植物の適応プロセスを生理生態学的な方法やDNA解析をはじめとする分子生物学的方法により解明するアプローチ(研究室HPより)”によって、植物と環境の相互作用を研究している。 そして、『奇跡のリンゴ』で知られる木村秋則の自然農法を、科学的に解明することも研究のひとつとしている。 相当数のメディアに取り上げられ、映画にまでなった木村秋則の農法とそこに至るまでの苦労は、ストーリーとしてはとても美しく、諦めない人間の凄さを感じさせてくれる。 しかし一方で、科学の力を使わず、人間が手を入れることも最低限な自然農法に関しては、まだまだわからないことが多いというのが事実。杉山はそれを解明しようと木村の農園に通い始める。 分子生物学的にある特定の植物を分析しても、対処法としてはどうしても科学的な対応で解決するしかない。つまり薬品や遺伝子を変える方法になってしまう。 杉山はまだ解明途中ではっきりとした答えは出ていないとしながらも、いくつかの答えを見つけ出す。「生物の力」「植物-土壌フィードバック」「生物間相互作用ネットワーク」「植物免疫」などなど。トップダウンではなく、地道にボトムアップ式で作っていかなくてはいけないけれど、そこにはこれからの日本の農業だけでなく、国全体の未来を示唆するかもしれません。
0投稿日: 2014.07.17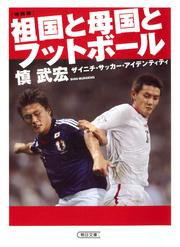
増補版 祖国と母国とフットボール
慎武宏
朝日新聞出版
在日サッカー選手たちの才能はどこへ向かうか
李忠成は在日の選手として初めて日本に帰化して代表になった選手だ。 かつてラモス瑠偉らも帰化して代表に名を連ねたが、日本における在日韓国、朝鮮人が代表入りするというのは、それ以上に大きな意味を持っているだろう。 戦後、差別を受け続けた在日の人々にとって、日本人と同じフィールドとルールで平等に戦い、勝つことができたサッカーは、常に仲間たちの応援と注目の的だった。在日朝鮮蹴球団は、日本リーグなどの創設によって日本が力をつけるまで、圧倒的な実力を誇る強豪チームだったにも関わらず、公式戦への参加は認められていなかった。 朝鮮高校がインターハイに出場が認められたのも、実に93年になって、やっとのことなのだ。本書は、そうした在日の人々が北朝鮮・韓国と日本の狭間でどうサッカーを捉え、向き合ってきたのかを李と鄭大世に至る道として描いている。在日の選手たちは、そうした苦しい背景のなか必死に勝ち残りを賭け、サッカーに打ち込んできた。 Jリーグを超えて、世界を視野に入れ始めた現在の在日サッカー選手たちは、北朝鮮代表もいれば、韓国代表もいる。そして李忠成のような選択肢もいよいよ、本格化してくるのかもしれない。
1投稿日: 2014.06.11
信頼する力 ジャパン躍進の真実と課題
遠藤保仁
角川oneテーマ21
遠藤のプレースタイルそのもののような本
ここ数年、ピッチ上の最年長サッカー日本代表であるボランチ遠藤保仁。 それだけ若返りをしているという意味でもあり、そういう意味では次のW杯まで期待ができるということでもある。だがその期待を現実にするためには、遠藤が下の世代に教えていくことがたくさんあるようにも思うのだ。 サッカー選手の本は、その人の性格がとてもよく出る。その意味で、本書は遠藤のサッカー観をそのまま反映したような本だ。この本の中で、遠藤はとても多くの選手に言及している。おそらく同行したほとんどの選手が登場するのではないだろうか。それはつまり、遠藤がどれだけ周囲の選手を見て、観察しているか、プレーで言うならば視野の広さと冷静な判断力、信頼関係が現れているかということだ。 世界を舞台に活躍する香川や本田などとは違い、国内にいながらも世界との差を冷静に感じ、分析する遠藤のような中盤の選手は重要だ。カテナチオから一気のカウンターで、大切なゲームスピードや緩急を調節するのは、広い視野を持った遠藤ら中盤の役割なのだから。 南アフリカW杯での躍進を振り返り、これからの日本代表への思いを書いた本書は、まさにいま読むべき一冊だろう。
1投稿日: 2014.06.10
BACH/バッハさんのレビュー
いいね!された数446
