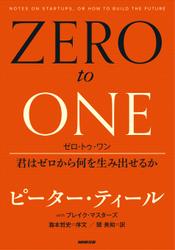
ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか
ピーター・ティール,ブレイク・マスターズ,瀧本哲史,関美和
NHK出版
水平に進むか、垂直に進むか、今がその分岐点
”君はゼロから何を生み出せるか” <こんな人向け> ・起業家や企業志望者 ・企画や計画立案者 ・自分を成長させたいと思ってる人 <こんな本> ○未来を作る進歩は水平進歩と垂直進歩がある。 ○新興国は未来があり、先進国は発展が終わった国と錯覚してないか。 ○ITバブルの終焉、そしてその反省は間違いばかり。 ○幸福な企業はそれぞれ違う。 ○独占を行ってる企業は自分を守るために、さまざまな嘘をつく。 ○イデオロギーとしての競争。競争に勝たないと富が得られないと勘違いしてないか? ○人生は宝くじではない。 ○人はみな投資家(生きていくうえで、選択や投資を行っている) ○人間は全てを知ってると思うことは、傲慢である。 ○すばらしいモノを作れば、みなそれを買ってくれるのだろうか? ○今こそ、人間と機械は手を組むべきである。 <感想> なかなか、面白い読み物でした。 企業における投資も自分自身への投資もなんら変わらない。生き延びていくためには、選択して成長をしていかなければ価値は下がっていくのですから。 では、自分の価値を下げないため成長するにはどうするべきか? 成長にも水平方向と垂直方向があります。 企業でいえば大量生産、グローバリズム、製品の改良といったものが水平方向のもの。個人でいえば、英語(いやゆる外国語)取得、仕事の改善とかいったところでしょうか。新しいことではありますが、他人が簡単に真似ることが水平方向。 これが垂直方向になると、タイプライターがワープロに変わったようにテクノロジーによって全く別物に変わるものとなります。個人でいえば国家資格をとって仕事に利用するとか転職するなどいったところでしょうか。 もうすでに、パイが無限に膨らんでいくという時代は終わりました。いまだにイデオロギーとして我々の思考は、利益は戦って勝ち取るものだという思考に汚染されたままであるとこの本は警笛を発しています。 簡単にいうと、ライバル企業がある商品でヒットを出したからといって、水平方向的な考えでライバル商品の改良で競争を挑む戦略は間違いということです。 競争の激化のすえ、シェアをとったとしても収益は悪化するからです。 この辺は、実際に液晶テレビやスマートフォンで現実に起きていることです。 では、戦わずして利益をどう得るのか? それは、新天地に旅だって独占を謳歌すればよい。 ええ!! 独占って悪いことじゃないの? はい、世間では悪いことです。ですから、あらゆる嘘を駆使して独占企業は自分を守るために自分は独占企業でないよう数字や統計を駆使するかを紹介しています。この本ではGoogleが標的としていろいろ分析しています。 カルトと常識の線引きはどこで決まるのでしょう。カルとの中で一般人が受け入れたものが、常識となり否定されたものがカルトのままとなる。 これには、ちょっと背筋がゾクッとなりました。確かに天動説や地球は球体でなく大きい皿のようなもの。これが常識である時代が確かにありました。 さてさて、今我々が常識だと思ってるものが、果たして未来でも常識であると誰が保証できるのでしょうか。 本当に面白い読み物でした。我々が未来へ成長するためには、時代の流れを感じる必要があり、大量生産大量消費の時代から新しい新天地へ旅立つために、我々は進歩しなければなりません。 今、日本を初め少子化が問題とされてますが、今後のエネルギーや資源のことを考えると少子化による人口減少はむしろ問題解決の糸口になるのではないでしょうか? 少子化だ!大変だ。人口が減る移民受け入れようは水平的考え、あるいみ問題の先送りに過ぎません。 この時、垂直的思考で動いたものが時代のパイオニアになれるのでしょう。
1投稿日: 2015.05.05
ポケット版 3分以内に話はまとめなさい
高井伸夫
かんき出版
長い話は嫌われる は 誰でも知ってるのになぜやってしまうのか?
<こんな人にお奨め> ・決められたスピーチの時間がいつもオーバーしてしまう人 ・スピーチを頼まれても、話すことがまとめられなく、結局思いついたことを延々と話してしまう人 ・自分ではいいこと言ったはずなのに、相手の反応がいまいちな人 ・人前であがってしまって困ってる人 <こんな本です> ”長い話は嫌われる” スピーチを聞く立場では、重々知っている真実があります。これが、なぜか話をする立場になるとこの真実を忘れてしまう世界の七不思議が存在します。 種明かしをすれば、立場変われば考え方が変わる。これが全てではありますが、分かっていても止められない。が、多くの人のジレンマだと思います。 まず、「話を短くする努力」が必要です。そう、話を短くするには努力が必要なのです。 ○800~1000文字を3分間で読む訓練 ○結論から話す(聴く人に対して話のゴールを教える) ○人は説教大嫌い、感動大好き ○成果主義とは可視化が必要。言葉よりも行動で示せは古いし評価されない。 ○話が納得できない三大理由 1)信じられない 2)理解できない 3)興味なし ○人に気に入られる話し方は、第三者の存在を意識しなさい ○沈黙も立派なスピーチのスキル ○「立て板に水」の話し方は、以外と評判が悪い話し方 ○「思い上がり」「見下し」は嫌われます。相手の面子を潰してませんか? <感想> 話を短くする努力として、技術的な訓練は800~1000文字を3分間で原稿を読む技術を養うこと。ただ、流暢に話をする必要はないそうです。逆に立て板に水な話し方は評判が悪いとのこと。人まであがってしまう人でどもったり、話がつまずいてしまう人には朗報ではないでしょうか。 結論を先に言うのは、着地地点を明確にすることで聞き手の負担を減らす効果があります。また、時間切れになったとしても、結論を伝えられなかったという最悪の事態は防ぐことができます。 この本でなるほどと思ったは、1対1の話でも第三者の存在を意識して話をするということです。自分の立場と相手の立場だけでなく、第三者がどう思うか? いわゆる観客的な視点を保ち続けるということです。 なかなか、難しいことですが、これは意識するしないだけで大きい差を生むのは確かなので実践していきたいです。 ソフトな話し方での効果として、ベンジャミン・フランクリンの話も為になりました。ベンジャミン・フランクリンという人は実用主義のプラグマティズムの権化みたいな人なんです。ある日、話し方が横暴するぎると指摘され、ソフトな話し方をするよう努力しました。 そうしたら、 「人との話がスムースになった」 「反対されることが少なく、自分の意見をよく聞いてくれるようになった」 「間違って恥をかかなくなり、説得力も向上した」 と、なったそうです。 話し方で、話の内容を聞いてもらえるチャンスを生かすか潰すかが決まる。本当に恐いことです。 話の内容さえ正しければ同意してもらえるという考え方を、根本的に改める必要をいっそう感じました。
0投稿日: 2015.05.04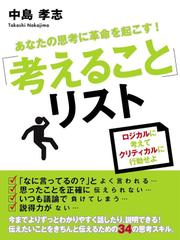
あなたの思考に革命を起こす!「考えること」リスト
中島孝志
ゴマブックス
論理と感情のバランスが大事
副題にあるように「ロジカルに考えてクリティカルに行動せよ」がこの本においての中核となります。 ロジカルとクリティカルは論理と直感、理知的と感情、「白と黒」とグレーと言い換えていますが、どちらも大切であり相反する存在ではないと訴えています。 ロジカルシンキングは倫理的に正解を導くために必要なスキルであり、発言に説得力を持たせるためになくてはならないものです。 ただ、人は「正しい」論理だけでは、納得はしてくれません。行動も起こしてくれません。 ・綺麗ごとをいいやがってー! ・正論を振りかざすんじゃない! ・言いたいことは、わかりますが。 日常的によく見られる光景ですね。 えっ? こんな台詞日常的に発生しないですって? それは、幸せな環境にいるのか、それとも言いたいことも言えない世知辛い世界に住んでいるかのどちらかです。 と、言われると感情的に反発したくなりませんか? そう、人は「納得する・しない」の判断は感情で行います。もっと正確に表現すれば、感情が共感すれば納得をし、感情が反発すれば拒絶します。 本書では、いくつか感情が人を動かす話を載せていますが、目を引いたのはフランスの詩人であるアンドレ・ブルトンのもの。 目の悪いホームレスが、「わたしは目が見えません」の看板を持って空き缶にコインを入れてもらおうとしてはいるが、誰しもが無視をしている状態。 そこにアンドレ・ブルトンが、そのホームレスに看板に一文を付け加えると、さっきまでと打って変わって空き缶に入りきれないほどのコインが投げ込まれるようになった。ビックリしたホームレスはアンドレ・ブルトンに尋ねました。 「だんなさん、いったいなんて書いたんです?」 「知りたいかい? こう書いたんだよ。」 「春はまもなくやってきます。でも、わたしはそれを見ることができません。」 「目が見えません」という事実の前には、「大変だな」という理解はできても、それだけでは行動には移さない。これは、人々が冷たいからではなく、行動に移してもらうにはインパクトが必要であることを示しています。 「誰にでも平等に訪れるはずの春が、この人には訪れない」という感情を揺さぶる一文が加わったことで人々は動いた。 「人は理解では動かない、感情で動く動物」と本書では言い切ってます。 少し前までは、猫も杓子もロジカルシンキングがもてはやされていましたが、感情の大切さが見直されているように感じます。これは急速なコンピューター社会になりビックデーターから論的な解を導くにはコンピューターの得意分野になってきたこと。それどころか「データーの見えざる手」という本では、仮説を立てるという分野でさえビックデーターの前では人間は敵わなくなっていると伝えていました。こういった空気を肌で感じているかもしれません。 肌で感じるなんて、ロジカルシンキングではありませんが、これが大事なことなんです。 ロジカルシンキングとクリティカルシンキングは、お互いを補うもの。ロジカルシンキングで思考を論理的に組み立てていき、クリティカルシンキングで組立てた思考をチェックしていく。 これが、本書の伝えたいことであり、これからの時代に必要なスキルであるとうったえています。
7投稿日: 2015.04.25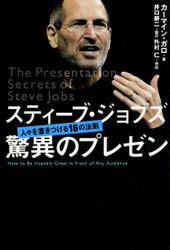
スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン―人々を惹きつける18の法則
カーマイン・ガロ,井口耕二,外村仁
日経BP
この本を一言で表すなら「君も技術を習得すれば、スティーブ・ジョブズになれる。」だ。
亡くなったスティーブ・ジョブズといえば、業績が悪化したアップルを立ち直らせた優秀な経営者。数々の魅力的な製品を生みだしたデザインセンスの持ち主。そして、彼が行う魅力的なスピーチからなるプレゼン。これらが、あげられるだろう。 我々が彼のように会社を興し世界的大企業に育てることも、iPhoneのようなヒット作を生み出すことも現実的には考えて非常に難しい。しかし、彼の魅力的なプレゼンだけは技術を学び練習することで実現できる。 iPhoneを真似て製品を販売すれば非難さるが、逆にプレゼンに関してはジョブズの真似をした方が評価される。プレゼンを素晴らしいものにしたいと頭を悩ませている者にとって、朗報のなにものでもない。 ジョブズがプレゼンを計画するうえで、どのような考え方をもっていたのか。実際のプレゼンでどのような技術を盛り込んだのか。そして、ジョブズの真似をして、プレゼンを成功させた話しが描かれている。 そして、もう一つ大事な要素が練習である。「えー、練習しないといけないの?」と、嘆いた人は諦めよう。なぜならば、ジョブズは、練習を非常に重要視しているからだ。練習を続ける秘訣はただ一つ。それは、プレゼンを大好きになることである。 さて、あなたがプレゼンを行う理由は何か。あなたの考えを相手に伝えるため。素晴らしいアイデアを知ってもらうため。それとも、素晴らしい商品を世に知らしめるためであろうか。それが理由ならばそこには、喜びがある。ならば、大好きになれるはず。 もう一度、繰り返そう。ジョブズのようなプレゼンを行う為には、カリスマは必要ない。必要なのは、技術であり、練習なのだと。
2投稿日: 2014.12.13
反論する技術 弁護士だけが知っている
木山泰嗣
ディスカヴァー・トゥエンティワン
反論は敵対行動ではなく、コミュニケーションのひとつである。
反論のイメージは、ほとんどの人が相手と敵対する行為と思っているのでないだろうか。本書では、反論とは敵対行為ではなくコミュニケーションの一つであると言っている。 確かに反論が敵対行為だと思い込んでいれば、相手の意見に異議があってもそれを口にすることができない。嫌われたくないから異論を口にすることができない。立場が対等ではないため口を挟むことさえできない。本書は、こんな経験がある人にこそ、手に持ってもらいたい。 反論の技術はシチュエーション毎に例が載せてあり、また著者も全ての技術を使う必要はないと言い切っている。そのため、難易度の低いものから行うのも良し、この技術は嫌いだから、使わないこともありである。 自分にとって役に立つと思ったのが、先方が都合が悪いところを隠してこちらを納得させようとする場合や、同じく都合が悪いから話を逸らそうとした場合の対処方法である。また、皆にも経験があるであろう、時間だけ消費して議論がまったく進まない会議にも反論する技術が有効である。 反論する技術とは、自分の意見を伝えるためのコミュニケーションに対する心構えと方法論であり、誰にでもすぐに行えるものである。
3投稿日: 2014.12.13
プロ弁護士の勝つための思考力
木山泰嗣
PHP研究所
思考は一つに固定するな!!
著者の木山氏は、弁護士であり弁護士の職業で培われた考え方、つまり思考についてのノウハウを本書で語られています。 まずは、思考は一つに固定をするな。物事の判断を下すためには客観的な思考は非常に大切だが、法廷では主観的な思考ができないといけないそうです。 この客観的と主観的を養う方法が、紹介されています。 思考は一つに固定するな!ですが、10通りの思考について語られています。「観察思考」「想像思考」「遮断思考」「客観思考」「立場逆転思考」「学習思考」「目標達成思考」「比較思考」「成長思考」「予測思考」の10の思考です。 観察思考は、目に見える物が必ずしも本当に大切な物とは限らない、それを観察から予測するということです。事例としてTVでのスポーツで観客数を当てたり、タクシーを乗るの時に運転手の性格を当てるなど薦めています。こういう定点観測を行うと、球場の観客動員数が地域によって違う。タクシーの運転手の傾向が地域によって違うなど見えてきます。その時初めて、おもわぬ発見ができます。 想像思考は、人の話を聞く場合は必ず相手の立場をは何かというフィルターを通すことです。例えば、自分と反対の意見を述べている人が必ずしも自分と敵対していると決まっていませんし、逆に自分の意見に賛同してる人が、自分と同じ理由で賛成しているとは限らないということです。 遮断思考は、意味の無い思考は捨てるということです。昨今は情報社会ではなく、譲歩過多社会となっています、全ての情報を網羅することは不可能であり、それを行うことは他人の人生を生きることに繋がります。まずは、自分の人生に集中するため何が必要か明確にすることが大切です。 客観的思考は、動かしがたい事実を認めることです。本書では、自分を客観的に認めるために自分の発言を録音や録画で見直すことを推奨しています。 立場逆転思考は、所謂、自分が相手の立場にたって考えることです。試験を受ける時、出題者はなんでこのテストを御作成したのか考えると、解答のみつける一つの手がかりになるという例題あげていました。また、男女の立場の違いは、男目線ならば渡辺淳氏の本を、女目線ならば林真理子氏の本を読めと薦めています。 比較思考は、両極端から考えることです。二項対立とも言われており、「現在」と「過去」、「基本」と「例外」、「大きく」と「小さく」、「刑法」と「民法」等です。思考の初期には非常に有効な考え方です。 成長思考は読書を勧められていました。初読で達成感を得られる本は基本的に素晴らしい本とのこと。そして、つまらない本は時間の無駄であるため、読むのはやめろと言われています。 また、成功者の努力はしてないという言葉は真に受けるなとも忠告しています。成功者はこっそりと自己啓発の一環として、思考トレーニングは必ず行っている。 予測思考は、自分が発表やレポートを行う時は、必ず聞き手や読み手の反論を予測して織り込むことです。 この本からは、相手の立場を考えろと二項対立の考え方が非常に参考になりました。 特に、相手の立場を考えろは相手の言葉の真偽や何を伝えたいのかに集中していた自分にとっては、立ち位置に無頓着だったことに気づかせてくれました。 二項対立ですが、両極端から思考するという考えは今までありませんでした。即、問題点はどこだとスポット的に考えるクセが当たり前になっていたことに気づかせてくれました。 この二点を発見できた時点で、この本は自分にとっては良書です。 最後に弁護士という職業の見方もこの本は変えてくれました。
0投稿日: 2014.12.07
レビューネーム未設定さんのレビュー
いいね!された数47
