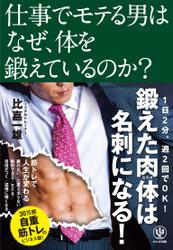
仕事でモテる男はなぜ、体を鍛えているのか?
比嘉一雄
かんき出版
『努力は必ず報われる』と前向きに信じられる人が、体づくりを成功させ、さらに人生の成功者となっていく
人間の体は負荷を掛ければ、それだけで体は応えてくれる。 ボディビルダーのような体を目指すのではないのならば、ジムに通う必要が無いのは朗報ですね。 ただ注意なのは、負荷が軽い筋トレは時間の無駄だということ。 例えば、腕立て伏せ10回が限界ならば、9回までの腕立て伏せは意味がないということです。つまり、10回目の腕がプルプル震えて腕が限界ってところまで追い込まないと筋肉が増えません。 俺、腕立て伏せ得意で100回やっても疲れないぜ!! という方は、筋肉が増えない筋トレを行っていますので、やり方を変える必要があります。 では、筋トレは疲れれば疲れるほど、筋肉が増えるのでしょうか? 残念ながら、これも間違いです。 疲れた筋肉は休憩が必要なのです。それも、2日です。 つまり、毎日同じ筋トレを行うのも間違った方法だったのです。腕立て伏せを行ったら2日間は別の筋トレを行わないと腕の筋肉は増えません。スクワットや腹筋を行いましょう。 大部分のページが割かれているのが「バウンドトレーニング」です。バウンドトレーニングとは、ストレッチと筋トレと有酸素運動の効果を狙ったものとなっています。複雑な動きよりもシンプルな動きこそ効果があるが、著者の持論ですので本当に簡単な動きです。 写真で動きを再現して、鍛える筋肉はここだと表示をされています。また、ポイントも同じく写真で表していますのでとてもわかりやすいものとなっています。 また、ながらトレーニングとして電車に乗ったときのトレーニングやオフィスで座りながらできるトレーニングも紹介されており、まとまった時間がとれない人にも優しいものとなっています。 食事の話では、「タンパク合成」と「タンパク分解」で簡潔に説明されています。 人間は体内でエネルギーを作り出して生きています。もし、無理な食事制限をしてまうと、タンパク分解つまり、筋肉を消費します。そうするとかえって太りやすい体質になってしまいます。怖いですね。 タンパク合成はこの逆で筋肉を作られます。要するに消費カロリーが自然とあがっていきます。そして、タンパク合成に必要な栄養素は「糖質」と「タンパク質」となります。 エネルギーに変わる栄養素は、先の「糖質」と「タンパク質」に加えて「脂質」が加わります。「糖質」と「脂質」は取り過ぎると脂肪に変わりますので要注意ですから、何を食べるのかが問題となります。 特にお酒のおつまみの「枝豆」はNGですので、注意ですよ、皆さん。 さて、若人でない人にとっての良いニュース P186(電子書籍版)から抜粋します。 「100歳を超えてからでも、適切なトレーニングで筋肉は大きくなる、という論文報告があります。また実は、筋肉がついていくスピードは、若い人と高齢者とで、あまり変わらないとも言われています。」 ああ、人間の体って素晴らしい。 最後に、著者はラグビー経験者でラグビーを通じて、いろんなことを学んだそうです。 例えば、ラグビーは試合が中断すると必ずイーブンの状態で試合が再開されます。要するに常に力勝負となるため力が強い方が勝ちます。野球やサッカーと違ってまぐれ勝ちといわれる「大番狂わせ」がおきにくいスポーツです。 これは、先のラグビー日本代表が南アフリカ代表に勝利した時の衝撃が物語ってますね。 話がそれました。そんなラグビーは普遍の原理原則を教えてくれたそうです。そしてらラグビーが教えてくれたものが、原理原則の重要性だけでないそうです。 ラグビーボールは楕円形ゆえに、どこに転がるか分かりませんが、ラグビー選手と監督はある一つのことを信じてるそうです。 「ボールは努力してきた方に転がる」と。 これこそが、この本のもう一つの主旨となります。 「『努力は必ず報われる』と前向きに信じられる人が、体づくりを成功させ、さらに人生の成功者となっていくことです」 さあ、体を動かしましょう。
0投稿日: 2015.11.15
「思いこみ」という毒が出る本
蓮村誠
さくら舎
人はみな性格も違えば体質も違う。他人の健康法がそのまま自分に当てはまることはない!!
常識的に考えて、幸せとは健康とはと考えている時点で「思いこみ」の可能性があるという話。人それぞれ性格や体質が違うのだから、幸せや健康が人によって異なるのが本質なのではないか? 考えてみれば、当たり前の話ですが、これをアーユルヴェーダというインドの「生命の科学」という英知を伝えているのが本書となります。 人はみな日々決定して生きてますが、それが必ずしも正しい決定とは限らない。 なぜなら、自分は自分を見たままの姿で判断しないから、それは親からの教育や社会通念やらで自分を歪めて、求められている自分になろうとしているから。 ちなみに、日々の決定とは「無意識」や「習慣」も含まれています。本来人はみな「理知」という能力を使って健康に幸せに生きるように出来てますが、「思いこみという毒」の為に誤った判断をしてしまう。 冒頭では、ヨーグルトは健康食といわれていますが、全員にとって健康食であるとは限らず、害となる場合もある。そんな人がヨーグルトは健康にいいという思いこみでとり続けることは果たしてどうなのか。 また、血圧は絶対値によって正常な状態を決められていますが、絶対値では正常でも特定の人にとっては高血圧だったという話が載っています。 自分にとって益になるもんが、他人にとっては毒にもなる。 いわゆる、小さな親切大きなお世話どころが大きな害悪になり得ることも、考えなくてはならないと思いました。 http://yamakatsuda.blog.fc2.com/blog-entry-60.html
0投稿日: 2015.11.08
ガンも生活習慣病も体を温めれば治る! 病気しらずの「強い体」をつくる生活術
石原結實
角川oneテーマ21
健康でいたければ、体の免疫機能の邪魔をするな
なかなか、考えさせられた本でした。 全部が全部、信じるわけにはいきませんでしたが、無視できない説得力がありました。 発熱や下痢になるのは、体が体内の病原菌の殺傷や毒物の排除を行う生理現象なのは周知の事実ですが、実際には直ぐに薬を使ってその症状をとめてしまうのは、体に害があるものを排出しきれない問題が残ります。 また、発熱して体温が上げるもう一つの理由が、免疫力の代表格である白血球の活動を活発にするためです。 最近は、活性酸素が体に悪いという情報が飛び交ってますが活性酸素はもともと免疫機能の一つなのです。白血球が攻撃相手に活性酸素を使って相手を弱らせてから捕食する。この時に、体の組織も活性酸素に晒されるのでダメージを受けます。したがって、白血球が活躍するような身体の状態を改善しない限り、活性酸素だけに着目しても意味がありません。 「今まで病気一つしてこなかったのに、よりによってガンになるなんて」こんな話をよく聞きますが。 今まで病気一つしてこなかったから、ガンになったと著者は言っています。 病気の症状である発熱などは、体の浄化を行っている現象であり、熱を出したことが今までないのであれば、体内の老廃物や有毒物が貯まることで大病の原因となると主張されています。 確かに清潔な場所にはばい菌の繁殖は抑えられ、不潔なところにはばい菌が繁殖する。これが、体内でばい菌が繁殖する条件がそろっていたらと考えると、一理あるように思ってしまいます。 清潔や不潔の話では、身の回りや体臭などを気にしたことはあっても、そういう意識を持って体の中を気にしたことがある人はどのくらいいるのでしょう。少なくとも自分は、腸内細菌までしか思いに至りませんでした。 さて、ガンの話に戻り、体温が35.度で一番増殖し、39.3度で死滅するそうです。したがって、体温が低めの人がガンになりやすい。新陳代謝が亢進し、発汗・発熱が激しくなるバセドウ病疾患の患者がガンになりにくいことや、イタリアのポンティン湿原の周辺に住んでいた人々は、数百年の間ガンにかかっていなかったそうです。その湿原にはマラリアの病原菌をもった蚊が生息しており、マラリアで高熱を出していたことがガン予防になっていたそうです。 免疫の観点から考えて、体を冷やさないことが大切になりますが、現実的には冷え性の方が増えています。5つの原因が考えられています。 一つ目は、筋力不足。二つ目は、必要以上の水分の取り過ぎ。 三つ目は、塩分不足。四つ目は、食べ過ぎ。五つ目は、ストレス。 本書の後半では、健康のための食事について書かれています。基本は、体の体質にあった食事を行うことが重要であり、過食は体に悪く逆に少ないくらいが丁度良いと仰っています。 なお、サプリメントは次の要素「便通、小便の出が良くなる」「体が温まる」「気分がよくなる」が満たされれば摂ってもよい、だそうです。 さて、最近著名人がガンで亡くなったり、乳房の切除をしたニュースで「ガン」についてクローズアップしていますが、残念ながらガンについては未だによくわかっていないのが真相みたいです。 ただ、生活習慣や食生活でなるべくしてなったガンは例え切除しても、その環境を変えない限りは再発は免れないということ。 そして、体の免疫機能はガンに対してもともと対応できるようになっていることから、その免疫力を衰えさせない生活を送ることが大切である。 その生活を送る上で、本書は一つのヒントを与えてくれています。
3投稿日: 2015.11.07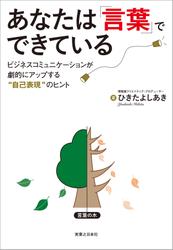
あなたは「言葉」でできている
ひきたよしあき
実業之日本社
人は「言葉」でできている。人の思考は言葉を使って行われ、感情さえも言葉に翻訳される。その言葉が積み重なって自我が構築され自分となる。
著者が小学校3年生に「言葉」という字を習った時の話。 「言葉という漢字は『言う葉っぱ』と書きます。奇麗な言葉を使えば奇麗な木に見えます。汚い言葉を使えば汚い木になっちゃうよね。 みんなだって同じだよ。奇麗で正直な言葉を使えば立派な木に見えます。嘘ついたり、汚い言葉を使えばみすぼらしい木になりますいい言葉を使いましょうね。」 このエピソードはプロローグで紹介されていますが、この本の伝えたい主旨の全て伝えているといっても過言ではありません。 本書は、単なる言葉使いや文書を書く上でのテクニック本ではありません。 冒頭でエピソードを紹介しましたが、随所随所に他のエピソードが必要は発明の母のごとくな感じで、著者の話には説得力があります。 また、「チャンスは、怠け者が嫌い」。これは、自分から動かないとチャンスはつかむことが出来ないと意味もありますが、人との出会いこそ言葉を磨くチャンスそのものだと気付かされるでしょう。 あなたは「言葉」でできている。人の思考は言葉を使って行われ、感情さえも言葉に翻訳される。その言葉が積み重なって自我が構築され自分となる。粗悪な材料では粗悪な製品が生まれるように、粗悪な言葉は粗悪な人間しか生みださないとしたら、漠然としてではなく言葉に気をつかって生きていかなければならない。 そう、感じた本でした。
0投稿日: 2015.11.07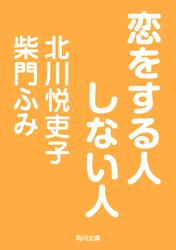
恋をする人しない人
北川悦吏子,柴門ふみ
角川文庫
作家と脚本家の織りなす人間観察を行った本
脚本家の北川悦吏子女史と作家の紫門ふみ女史による「テーマ」において、お互いの考えをぶつけあう、もしくはリレーで引き継ぐ形式の本となっています。 対談の形式ではないので、言葉のキャッチボールは起きませんがお互いが「文章」を生業にしていることもあり、対談形式よりも練られたものとなっています。 当たり前の話ですが、人の考え方や好みは人それぞれで全く同じ考えの人など存在しない。と、頭では分かっていても感情ではなんの根拠もなく分かりあえると思ってはいないでしょうか。 恋の話を題材にしてますが、そういう根拠も分かりあえることは幻想なんだなと。 自分の人生観を元に恋愛の話をしているだけですが、いろいろなタイプの人間像が出てきます。 例えば、「愛される女性」と「もてる女性」は明確に違うという話では、愛というものは瞬間的なものではなく「熟成」が必要でありそれが「もてる」と「愛される」の根本的な違いになるということです。 坦々と分析を続けていくのですが、自分を幸せにしてくれる相手を見つけるためには、自分がどのような幸せを望むのかを知らなければならないのです。そして概して人間は、自分のコンプレックスを満たしてくれる相手を望んでしまうことがある。 この本は、自分がどのような人間なのか? それを知る手助けになります。
0投稿日: 2015.11.07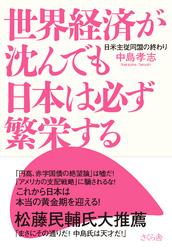
世界経済が沈んでも日本は必ず繁栄する 日米主従同盟の終わり
中島孝志
さくら舎
タイトルに経済とあるが、政治を問題とした本である
タイトルに経済とついてますが、かなり政治色が色濃い本です。 また、米英に対して恨みがあるのか? と、いうくらいに辛辣な書き方をしています。 まあ、恨みではなく単なる「事実」ではありますが、問題は他の国なら信頼に値すると勘違いしてしまわないか心配です。 まずは、日本の問題点をおさらい。それは、日本の政治の問題でもあるし、GHQ統治時代の置き土産が元凶であることをあげています。 まず、数ある政治の問題の中で取り上げたいのは消費税です。これこそ、子や孫に甚大な負担を強いているものであり、今現在無税である宗教団体に課税を施すべき、人々の幸福を祈る宗教団体にふさわしいではないかと提案してますが、全くもって同感です。 GHQの置き土産としては、英国流に撤退時には紛争の火種を置いくものを米国も踏襲していることです。領土問題でいえば、北方領土、竹島が他国に占領されている状態。そしてこれからは、尖閣、沖縄、対馬が入ってくるかもしれません。 さて、国益とは一体何か? 米国の上院と下院で議論があったことを日下公人氏から教えてもらっています。重要な国益の順番が5つのレベルで表します。 レベル1:たとえ1国で戦争をおこなっても守るもの。 レベル2:同盟国と一緒になって守るもの。 レベル3:なるべく戦争以外の手段で解決するもの。 レベル4:国連等の国際機関による国際的合意をつくって守るもの。 レベル5:恫喝や嫌がらせ、交渉、抱き込み、友好親善などの手法を使って守るもの。 すでに、日本ではレベル1とレベル2はないも同然。そう、日本には武力行使に訴えても守るべき国益は存在しないということである。 P49より 「日本は絶対に戦争しない国です」この発言は、どう控えめに考えても平和を愛好しているとは思えない周辺国の政治家たちは、どう解釈するだろうか? 「絶対に戦争に訴えないと大臣が保証しているのだから、領土を少しくらい奪っても攻めてこない。真剣に起こって武力を行使しそうになったら、少しだけ返せばいいと考える」 まさに、現実にその通りになっています。 この状況に米国が貶めたのは、米国の国益に敵うため。 日本が窮地に陥れば、米国は絶対に日本を助けないと著者は考えていますが、ここは著者とは考えが違います。 世界的にみて、日本ほど米国に貢献してる国はないわけで、そんな国を土壇場で裏切る真似をしたら他国は国防において米国外しで動くことは必然。それこそ、米国のいう潰す勢力が生まれない保証は何処にもありません。この辺、著者に突っ込んで聞きたいところです。
0投稿日: 2015.09.06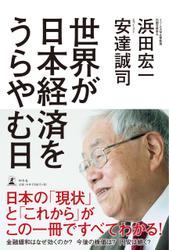
世界が日本経済をうらやむ日
浜田宏一,安達誠司
幻冬舎単行本
『経済学派の仁義なき戦い』
不況脱出に金融緩和が効くか効かないか? マクロ経済における「貨幣」の役割について、喧々諤々の議論がされてきた歴史があります。 経済の父であるアダム・スミスは『国富論』で有名な「神の見えざる手」が働くから介入は行わない方が好ましいから、それに異議唱えたのがケインズでした。ケインズはマクロ経済学を立ち上げ、不況時には神の見えざる手に経済を委ねず、金融財政政策を用いることを主張しました。 ここで一つケインズ経済学の弊害として、不況時には金融政策よりも財政政策が効果があるとケインズが結論づけたこと。なぜなら、ケインズの時代は固定相場制であったから、金融緩和を行うと為替レートは通貨安の方向に動きますが、固定相場制の維持をすると外貨準備が枯渇するために、金融政策は封じられていた事実が無視されていることです。現在、変動相場制になったというのに、未だケインズ経済学の教科書に旧時代の記述が残されたことが弊害となっています。 このあと、フリードマン、トービン、ルーカス、プレスコットを紹介しながら、要点を交えて経済学の歴史をおさらいしていきます。 経済学の論争の歴史は「金融緩和は効くか否か」であり、金融緩和は経済に効くという考え方は少数派どころか、異端扱いされていたことにビックリしました。 そして、この状況で著者が怒り心頭なことが2点あります。 ひとつは、経済の歴史を真摯に学ばず、「デフレは、生産年齢の人口の減少によって生じた現象である」などという本がベストセラーになる日本の情けない現状。 もう一つが優秀な日本の若者がアメリカに留学して、新しい古典派的な経済学に毒されて帰国する現状。 事実、著者はこう言われたこともあるそうです。「浜田は昔の経済学を学んだ人間であって、私のほうが新しい経済学を知っている」 さて、現実問題としてアメリカ経済の復活は、FRBの金融緩和政策が正しかったことを示していますし、 「なぜ、これまで金融政策が効かなかったといえば、それは金融政策がアメリカですらまもとに実行されてこなかったからです。効かない、効かないと言って、試されたことがなかったからです。」 と、経済学者のクリスティーナ・ローマーが身も蓋も無いことを言ってます。 さて、デフレは生産人口の減少による減少を著者は否定してましたが、本書ではデータを用いて反論しています。単純に人口減少している日本以外の国と比べるとデフレが起きているのは日本だけという事実です。 したがって、外国人労働者の受け入れで労働人口を増やせば、デフレ脱却に効果があると短絡的に考えることは危険だと感じました。 このあと、浜田氏、安達氏の共同著者が対談形式として、アベノミクスを反対している勢力分析とヘッジファンドの投資戦略を語っていきます。 なぜなら、日本の経済復活した富を奪われないためには我々も知恵をつける必要があるからです。知恵がないといくら情報が目の前にあっても、正しい決断ができませんから。 本書は、アベノミクスに対しての記述がメインではありますが、今回はあえてそこは省いての感想文にしました。なぜなら、そこを抜きにした「経済学の仁義なき戦い」が面白く、また為になったからです。
0投稿日: 2015.08.18
土井英司の「超」ビジネス書講義 これからのビジネスに必要なことはすべてビジネス書が教えてくれる
土井英司
ディスカヴァー携書
ビジネス書は時代を映す鏡である。それが、著者である土井氏の持論であり、自分のビジネスワークに活かしています。
<こんな本> 前半は、ビジネス書って一体何か? ビジネス書の役割とは? 土井英司氏のビジネス書の思いの丈を書き綴っています。 後半、いやこの本におけるメインディッシュは、数々のビジネス書の書評です。 <こんな人にお勧め> ビジネス書は数あるし、どれも為になりそうで結局どれを選べば分からない人。 一通りビジネス書は目を通したが、もっと違う観点の本を読みたい人。 <感想> ゛ビジネス書、それは時代を写す、鏡゛ 冒頭で、ビジネス書は陳腐化するもの。なぜなら、時代を映すものだから。と、うたっています。 どんな時代でも生き残れる人とは、時代の先読みが出来る人であることは間違いないことでしょう。 そして、時代を読むのにビジネス書が最適であると言い切っています。では、なぜ言い切ることができるのか? 「ビジネスパーソンという名の゛実務家゛として、時代の変化にどう適応するか?」 「自分自身、あるいは携わっているビジネスを成長させるには何をすべきか?」 その答えを書いたものがビジネス書である。 すごいぞ、ビジネス書。 エッセンスを凝縮して読者の負担を軽減したものが、ビジネス書の為効果がある反面、時代が変わったりツボが外れると効果が全くなくなるのもビジネス書。これが、陳腐化であり、土井氏の言う役割が終わったということ。 この辺は、松下幸之助氏と佐藤可士和氏を対比させており、売れてるから飛びつけば良いわけではないと説明しています。 高度経済成長期真っ只中で物を作れば、発展できた時代と情報産業真っ只中では、ビジネスの価値観と求められてるものが変わってくるという話になります。 この変化によって、組織のあり方がピラミッド型から専門家が集まるフラットな組織が増えてきてると、面白い事を言ってます。 また、バブル崩壊前後でビジネス書のあり方が変わり、バブル期は日本最高!のビジネス書が、バブル崩壊後は翻訳本が増えたのもこの時期だそうです。 そして、21世紀になると黒船来航します。拝金主義といいますか、正直にお金大好きという、ビジネス書の出現です。 また、ITベンチャーという海賊がやってきました。 ITベンチャー企業を海賊と呼ぶとは、物騒だなおもいましたが、「海賊の経済学」なる本があるんですね。 「海賊の経済学」より 海賊は、私掠船と違って掠奪した分け前を船主に渡す必要がない。 この考えをとりあげると。 既存のルールに縛られず、株主に頼らず、社員だけで分け前分担してる。 まあビックリ、グーグルを始めとしたIT企業がやってることである。 そして、かの、スティーブ・ジョブズも「海軍に入るくらいなら、海賊になれ」と、言っちゃった、とか。 数多く、ビジネス書読むと、ここまで自由な発想が出来るのか? ワクワクしちゃいました。 このあと、リーマンショック後のビジネス書の話が出てきますが。ビジネス書を一つの報告書として位置付けると時代が読める力は、確かに養えます。 ビジネス書を読むことを躊躇してた人は、新しい視点を手に入れることは間違い無しです。
0投稿日: 2015.08.15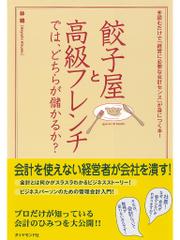
餃子屋と高級フレンチでは、どちらが儲かるか?
林總
ダイヤモンド社
会社は現金製造機!!
会社活動とは「現金を製造することだ」この考えを基本として、会計と会社経営の神髄を伝えているところが面白いです。 本書は、亡くなった父親の後を継いで会社を再建する主人公と一緒に会計を学んでいく形式をとっています。 会計とは会社の写した合わせ鏡ではあるが、その鏡に写った姿は真実ではない。と、言い切ってます。 主人公はびっくり仰天。 「会計が会社の真実を現さないなんて、許されるのですか?」 ビックリを通り越して怒り出す主人公。会社経営の基本として会計を学ぶ矢先に、こんなこと言われたら当然の反応でしょう。 「会計とは真実を追究するものではない。ルールに則ってそれを続けていくのが大切なのである」 逆にいうと、ルールに則ってさえいれば何をやってもかまわないのが会計なのです。 本書ではこれを「女性が化粧をするものだ」と表現しています。 会計は会社の主観が入ってる。したがって、だまし絵があるように一つの絵の中に別の絵をみつける眼力を養うことが大切だと冒頭で伝えています。 そう、主観によって利益は変動するのです。(ここポイント) 各章ごとの物語を通して「バランスシートの読み方」、「キャッシュフロー計算書」等のレクチャーがあり、章の締めとして解説が入ります。自然な流れで復習ができる構成にしてあるのは、素晴らしいアイデアです。 また、この本の面白いところは、粉飾決済を使った詐欺に騙された話が出てくるところです。 所謂粉飾決済の見破り方のレクチャーも出てきます。 この話をみると、いったん粉飾に手を出したら後戻りはできないことがよく分かります。 世の中の経営者の方々は、ご注意を。 それから、逆粉飾という手口もあるそうです。 なんで、わざわざ会社の経営を悪く見せる必要があるの? と疑問を持つ人もいるでしょう。答えは簡単です。 前期の決済を実態より悪くみせれば、今期の経営回復のインパクトを強くできる。いわゆるV字回復をよりいっそう強調できるのです。 著者は、日産のゴーン社長がこれをやったと推測してます。 会社経営の金の流れに特化した本となってる分、非常にわかりやすいです。 会社は現金製造機ということで、現金を生み出さないのなにか? ストレートに考えることができます。 そして、会計は万能ではないことも戒めています。異常な点を見つけることはできても、真の原因は現場に出て現物を見て、現場の人間の意見を聞くことが大事だと伝えています。 会社は現金製造機!
0投稿日: 2015.08.15
なぜ、この人と話をすると楽になるのか
吉田 尚記
太田出版
毛繕いみたいな会話があってもいいじゃない
<こんな本> ラジオ局である、ニッポン放送アナウンサーが自身の体験を踏まえて「コミュニケーションとはなんぞや」をラジオ番組で話したことをまとめた本。 コミュニケーションの本ではあるが、「自分の考えや意志を正確に相手に伝える」方ではなく「相手との距離感が近くなる」に焦点をあてています。 <こんな人にお勧め> ・伝達事項がある会話は難なくこなせるが、いわゆる雑談が苦手なひと。 ・自分語りが長すぎると、相手に良い印象を与えないことは理解しているが、止められないひと。 ・会話がない間が耐えられないひと。 <感想> コミュ障という言葉が市民権を得て随分たちます。コミュ障とは、コミュニケーション障がいを略したものですが、一向に数が減る傾向にありません。 コミュニケーションが不得手な人を障がい者扱いすること事態が間違っていると、目の付けどこが違います。 もともと、出来て当たり前のことが怪我や病気で出来なくなった状態を障がいと呼びます。 コミュニケーションが出来ない状態を障がいと呼ぶ、裏を返すと「コミュニケーションが出来て当たり前」だという考えが浸透している証拠でありますが、この考え方がコミュ障と呼ばれる人が少なくならない原因だと考察しており、私もなるほどなと納得しました。 例えば世の中には泳げない人がいます。世間ではこれらの人をカナヅチとは呼んでも、水泳障がい者とは呼びません。 なぜなら、ほとんどの人は習わないと泳げないからです。 教育や練習が必要なものは、たとえできなくても障がい者とは呼ばれないのです。 元来、コミュニケーションは「教育」されて始めてできるものなのに、そう思われていないことが不幸となっているのです。 さて、著者の吉田氏はラジオ局に入社したとはいえ、アナウンサー希望ではなかったそうです。そして、話をするのは得意どころか不得手で、コミュ障だったと暴露しているくらいで失敗談も書かれています。 <こんな本>でも書きましたが、本書は如何に相手と仲良くなれるか! を目指しています。 ○相手に興味を持つ ○自分は二の次 ○誇張は良いけど、ウソはダメ ○ウソを吐くくらいなら、黙秘権を使え 相手に興味を持つ、自分は二の次にするは特に目新しくはありませんが、誇張は良いけどウソはダメの考え方は面白かったです。 倫理的には誇張はダメなのでしょうけど、あくまで会話における技術における誇張はドンドンやれというスタイルです。 映画の宣伝によくある、「全米が泣いた」も、友人のアメリカ人が全員泣いていたなら大げさなだけでウソにはならないわけです。 「兄ちゃん、アメリカ人の友人なんかいたんかい?」 「そりゃ、架空のアメリカの友人くらい、みんないるでしょ?」 「架空かよ」 「架空が気に入らないなら、一方的に知ってるアメリカの友人でもいいのよ」 「それ、友人じゃない」 うむ、話は盛り上がるかもしれない。 誇張は良いのに、なぜウソはダメなのか? 経験や知識がある人の前では、一発でばれるからです。 そして、吉田氏のウソがダメの基準はけっこう厳しい。 番組編成のため、アシスタントが変更になった状況での話し。 既にアシスタントが誰になったかは知られてはいるが、外部には知らせてはいけない場面。 「吉田さん、もう新しいアシスタントが誰か決まったんですか?」 「ごめん、まだ知らないんだ」 これは、アウトだそうです。 私の中ではかなり厳しいラインだと感じましたが、ウソは吐かない為に世の中には「黙秘権」がある。この話で納得しました。 本では、もう少し深い話をしていますので、気になる人はお手にとってください。 電子書籍でしか、本を読まないという方は本を購入してください。 最後に。 会話はスポーツと同じです。練習しなければ失敗するのが当たり前。 プロ野球選手やJリーガー、オリンピック選手を見て、素人が同じプレイができないことを嘆かないのと同じように、会話が上手な人と同じように喋れないと嘆く必要はないのです。 スポーツと同じで、正しく練習すれば会話は上達するのです。 会話の上達は出来て当たり前という呪縛から、目が覚めた瞬間から始まるのです。
10投稿日: 2015.07.10
レビューネーム未設定さんのレビュー
いいね!された数47
