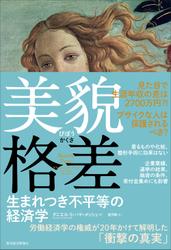
美貌格差―生まれつき不平等の経済学
ダニエル・S・ハマーメッシュ,望月衛
東洋経済新報社
ピケティなんて目じゃないぞ、この格差
美形の方が収入がよいだなんて・・・ 美形の人はモデルや俳優などの職業に就くから、収入が良くなるのも当たり前では? と、思った人は甘い甘いですぞ。同じ仕事をして貰えるお給金に差が出るという話なのです。 これは、美形の人に仕事ができる人が多かったため、たまたま美形の方が収入が高いという結果がでてしまった。確かにその可能性は考えられます。しかし、その儚い願望は、実験と統計にとって導きだされてしまったのです。 とはいっても、データはこういう傾向を示しているが、本当のところはまだよく分かっていない。と正直に話していたりする。 とはいえ「エピソードの複数形はデータだよ。」は含蓄溢れた言葉です。 データが少ないからといって、傾向があるのならば、それを無視するのは得策ではないということです。 (吟味した結果、その傾向は取り上げないというのは、もちろん有り) では、なぜ美形が収入が高くなるのか? それは、雇い主が「美形」が大好きだから。 「神様、ウチのスタッフと来たらなんてステキなんでしょう。わざわざブサイクな連中を雇って働かせる人たちのきがしれないわ」 by ミックジャガーの娘、ジェイ土・ジャガー では、なぜ美形を雇うのでしょう。だって、美形の方が会社に利益を与えてくれるから。 「思い込みを砕くよりも、原子を砕くのが簡単だ」by アインシュタイン 実際問題として、容姿が整ってると有利な仕事は存在しますが、容姿が整ってる社員が多い方が必ずしも利益を叩きだしているわけでないという話です。 つまり、同じ成果をだしても、美形の方が収入が良くなるという恐るべし結果が・・・ では、頑張って身だしなみで差を埋めようと考えたあなた、ちょっと待って下さい。 美貌と体型や身だしなみは独立したものなのです。 つまり、いくら着飾っても「美人」とか「美男子」とは認識されません。いや、ま、知ってましたけどね。 では、美形という価値は何と交換する又は置換することができるのだろうか? そのヒントが、次のエピソードです。 他の人が自信の利益のためにこうどうしでもその行動の悪影響が間接的にあなたにも及び事例があるかどうかの問いかけに対して。ある女子学生の答えがこれです。 「とても可愛いルームメイトが、大きく引き延ばした彼氏の写真を天井に貼ってる。寝る時にその写真が目に入って気分を害します。」 「なぜ、気分を害するのです?」 「だって、その彼氏本当にブッサイクなんだもの」 「なぜ、その可愛い彼女はその男性と付き合ってるのかな?」 「彼、もの凄く頭がいいです」 さあ、世のブサイクな知識と知能を身につけようぜ!! とはいえ、現実問題して、容姿が当程度の方が夫婦になる確率が高いことには変わらないのである。 こんな可哀相なブサイクは、法律で守るべきか? という話に発展する。 いやゆる、人種や民族、信仰等々の人たちと同じように保護ができるかという話である。 問題点としては下記の通り ・美貌は主観的であり、判断はどするか? ・ブサイクを守るあたって、筋は通るか? ・どのような政策を施すか? アメリカにおいては、法律で守ることはそうそう的外れではないそうです。 最終的に最小の努力で最大の効果を求めるならば、己の容姿を念頭に考える必要があります。
0投稿日: 2015.06.14
セックスと恋愛の経済学―超名門ブリティッシュ・コロンビア大学講師の人気授業
マリナ・アドシェイド,酒井泰介
東洋経済新報社
隣の芝生は青かった、アメリカのおける格差と特権は日本人からして洒落にならない酷さである。
アメリカの話であって、全てが全てこの本に書かれていることが、日本に当てはまるとは到底思えませんでしたが、日本人には思い描けない格差社会という片鱗を知ることができます。 アメリカでも昨今、若年層の性生活の乱れやシングルマザーが問題になっています。親の監視が薄れてる等の問題もありますが、本書では経済学からの観点から費用対効果を持ち出して分析を行っています。 費用対効果の計算を使って、リスクを金額に換算する。リスクを被った時にかかる金額より行為が上回れば、人はその行動を起こし、下回れば行動を起こさない。 この考えを当てはめると、若年層の性の乱れはリスクを被った時の金額がもの凄く低いことが起因であると看破していています。 このリスクの金額の換算は別の面も浮き彫りに出している。「貞淑な女性であればあるほど、結婚どころか彼氏さえできない」という事実。これは、あくまでアメリカの闇の部分でです。 また、日本には誰彼も目的がなく大学に進みすぎるという批判が度々あがるが、これはアメリカのように大学進学が「特権」ではないからできること。の事実を知って衝撃を受けました。 また、民主主義で先進国の国々は、なぜ「一夫多妻制」を制度として組み入れなかったのか? も、経済学の観点から分析していて納得しました。 有能で、財力がある一個人においては、「一夫多妻制」はメリットが大きいのですが、一族の当主となると話が変わってきます。 自分の息子達において、自分の全てを継ぐ長男は一夫多妻制のメリットは受けることができるが、次男三男以降はデメリットになり得ます。なぜなら、次男坊や三男坊に嫁ぐよりも、長男の二番妻や三番妻になる方が女性にとってはメリットがある可能性が高いからです。 冒頭の話の格差の話でもそうですが、費用対効果という観点でリスクをお金に換算しての行動様式をみると、見えないモノが見えてくる。そんな本です。
0投稿日: 2015.06.07
世界最強の交渉術
ローレンス・サスキンド,有賀裕子
ダイヤモンド社
個人的な交渉ではなく組織の代表者に向けた交渉術
<こんな人にお勧め> WinWinの考えは理解できるけど、利益をあきらめないといけないの?と疑問に思ってる人。 会社では事業部間での調整者 同業者による寄り合い等の組織の議長 サークル、グループの代表者 セールス、バイヤーの方 <こんな本> 交渉においてWIN&WINを築くのが当たり前という風潮の中、実際問題相手に何処まで譲っていいのか? 組織の仲間にこの判断が納得するのか? 新しい問題が浮上してきた事に対する指南書。 各章毎にまとめられています。 <感想> プロローグでは、著者が何の準備もなく別荘の買取の交渉の場に立たされて難儀した昔話から始まります。 普通は、これは個人の交渉のスキルあげるものだと思いますよね。でも、実態は違います。 組織の交渉を滞りなく進める為の、思考と手段と仕組み作りに焦点を当てています。 個人的な交渉においては、第三者を代理人として交渉に挑め的な話です。 スキル向上を考えていた人は、肩透かしを食らうと思います。 とはいえ、個人的に生かせる話もあります。 順調に契約更新されていたものが、ある日突然無理難題の条件を突きつけられた場合。 担当者の手柄欲しさによるスタンドプレーなのか? それとも、組織的プレッシャーが担当者に掛けられているのか? 目先の条件に振り回されたから、交渉は失敗するのでその対処方法が書かれています。 組織的プレッシャーに晒されている担当者は、個人的に敵対関係となっているわけでない事に気付くことが大事であり、そこを突破口にするわけです。 目に見えている問題が、実は本質的な問題に気づけるかどうかが、交渉を成功させられるかが鍵となります。 再度繰り替えますが、この本は組織間の交渉をメインに書かれています。 個人の交渉と組織での交渉では、考え方から心構えも異なってきます。 今まで、交渉に関して本を読んだけど効果がない!! と、いう方には思わぬ発見があるかもしれませんが、個人のスキルをアップすることを目的にしてる人には合わないと思います。
1投稿日: 2015.05.27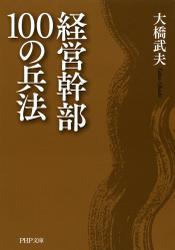
経営幹部100の兵法
大橋武夫
PHP文庫
もっと早く出会いたかった本である
<こんな人にお奨め> ・会社の経営者はもとより、起業家を志す人 ・社会人における人間関係を見直したい人 <こんな本> 経営とは会社という組織を運用していくための「統率力」が肝である。 経営幹部が取り組む必要がある「統率」を中心にした諸問題を、古今東西実例や著者の経験をテキストにしたものである。 <感想> 目から鱗が落ちました。 古典は人生のバイブルとよく言われますが、昭和四十年代に書かれた本とは思えないほど、21世紀の今の時代にも十分に活用できるものとなっています。 ドラッガーと同じように、この本が最近執筆されたのでは? と、勘違いしてしまいそうになります。 著書の大橋氏は戦中では陸軍中佐、参謀を経験、戦後では倒産した時計会社を再建したという経緯をもっています。 陸軍の参謀となれば、作戦が漏れれば部下が死ぬ。という立場にあったためか、情報漏洩に関しては他の本とは比較にならないほど丁寧かつ詳しくそして、量も割いて書かれています。 ・社長の意図を探るには、社長の行動(車の追跡)を行えば見えてくる。 ・新しい行動を起こすには、通信相手通信量が普段と異なる。 ・他社の動向を探るために外部の組織を使用する時、欲しい情報をそのまま伝えると、その動向を相手に売られる。 ・情報収集は中途半端が一番よくない。些細で価値のない情報でも対価を払うことに抵抗があると情報収集は失敗する。 などを、本当に懇切丁寧に具体例をあげて説明してくれています。 本著は古いですから、SNSについては書かれていませんが、SNSに絡めて考えると恐い発見があります。 最近の情報は、盗まれたことさえ気付かないことがあるため防衛することが本当に難しくなっています。 この辺は、コスト削減の旗印でクリティカルな部分である部署を外部に委託する経営者に本著を読ませたい。 話は変わりますが、著者は会社の経営の立て直しで相談を受けることが度々あったそうです、相談の内容を聞いて大半はこう思ったそうです。 「あなたが経営から手を引けば、会社は建て直しますよ」と。 会社経営者は常に勉強することが必要である。時代や会社の規模が変われば経営を代えなくてはならないが、経営者が勉強不足だとそれができない。故に経営者は誰よりも勉強を続けなければならない、そしてそれができない場合は、引退するべきだと。 この辺は、スポーツで顕著ですね。選手の入れ替えをしなくても監督を代えただけで、戦績が大きく向上することは珍しくないのですから。 そして、リストラ策による経営立て直しも全体的な目で見れば、失業者が増やす政策である。つまり、市場のパイを小さくする経営判断を行っていると、どれだけの経営者が気が付いて行っているのか? 【悲報】人間は成長やめた瞬間、陳腐になる運命からは逃れられない。 【朗報】勉強やめなければ、成長は止まらない。 特に、黒字で会社が成長している時は、一番危険な時である。部下は苦言を言いにくいし、銀行はお世辞を言ってくるようになる。 チェック機構を設けるには、お金があっても銀行から金を借りること。金を貸す時はどんな銀行でも真剣になって真実を言ってくれるから。 これは、銀行を顧客と見立てての事業を売り込むためのシミュレーションとして活用すれば、甘い見通しでの見切り発車は防げそうです。 最後に、電子書籍化されて初めて本著と出会えた自分が言えることではありませんが、もっと多くの人に読んで欲しいと切に願わないでいられない本と出会えました。
0投稿日: 2015.05.24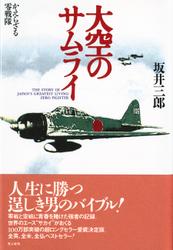
大空のサムライ
坂井三郎
光人社NF文庫
第二の天性を育てるこそ、強み
<こんな人にお奨め> ・漠然と戦争は悪いもので、思考が止まってる人。 ・仕事や人生において、自分の壁にぶつかっている人。 <こんな本> 坂井氏が戦争中の半生である手記をしたためたもの。 世界が坂井氏の存在を知らしめた本であり、「日本人だって人間なんだ」と、当事敵国だったアメリカに衝撃を与えた本。 <感想> 『「あとがき」に代えて』は絶対に読んで貰いたい。 ドラッガーでも「自分の強みを生かす」が大切だと説いてますが、まさに坂井氏の半生はこれの実践でした。 当事、レーダーがない戦闘機どうしの戦いでは、相手より先に見つけることが非常に大切です。 いわゆる「視力の良さ」が強みなわけです。 そういうわけで、視力が悪くなるような生活はしない。視力が良くなるように生活に目が良いものを取り入れたそうです。 遠くの緑のモノを見るのが目に良いならば、時間を作って遠くの緑色のものを眺め。 視力がよくなれば、昼間でも星が見えると聞くと、昼間に星が見えるように訓練を施すなど。 (ちなみに、視力がよくなると昼間でも星を見ることができます。私は小さい星こそ見ることはできませんが、昼間の青空に浮かぶ白い影である月は見ることができます。視力が良くなると星もあのように見えるそうです。) 視力の他にも、戦闘機で必要な能力があれば、日常の生活に取り入れていったそうです。 また、心構えの点でも「1対15」という圧倒的劣勢でも、状況を冷静に分析することと「最後まで諦めない」ことが生き残ることができたと仰られています。 「あきらめたら人生終了」の場面はそうそう体験はしないでしょうが、「あきらめたら試合終了」や「あきらめたら信用失墜」は生きている上で、そういう場面に遭遇するでしょう。 「あきらめない」為にはどうすればいいのか? やはり、日々、自分に自信をつけるための「自分の強み」を成長させる必要がある。 これに、つきるのでしょう。
4投稿日: 2015.05.17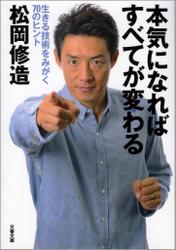
本気になればすべてが変わる 生きる技術をみがく70のヒント
松岡修造
文春文庫
自分を幸せにできるのは、自分だけである。だから、人間は誰よりも自分という存在を知らないといけない。
<こんな人にお奨め> ・日々ストレスと闘ってる人 ・自己コントロールを行いたいと思いつつ、どうすれば分からない人 <こんな本> ・自分自身を理解するためには、「自分の取扱説明書」を作成するのが早道。 ・ストレスが貯まることは当たり前のこと、ストレスからのリカバリーが肝心。 ・決断力は日々の生活で鍛えれる。 ・「頑張る」ことはカッコいい。 ・「真剣」と「深刻は」紙一重 ・良い条件が良い環境とは限らない。 ・「坦々と同じことを反復していける人は強い」。繰り返しを新鮮に感じるコツとは。 ・「立ち止まり」の時こそ気付きがある。 ・自身がテニスプレイヤーだった時の経験だけでなく、キャスターとして世界と戦ってるスポーツマンを通して戦いとは、最終的に自分とどう向き合うべきかを教えてくれる本。 <感想> 松岡修造さんは暑苦しいというイメージがありますが、このご時世にエネルギッシュでありながら、礼節を重んじる人柄が好かれているかと思います。これは、本著においてもその人柄の良さがでています。 少し古い本ではありますが、東日本大震災直後に書かれており困難に打ち勝つためにエッセンスが詰め込まれています。 人はみな自分のことが分かっているようで分かってない。家電製品も取扱説明書を読んで初めて気付くことがあると思います。この例のように「自分の取扱説明書」を読んで初めて気付くことがある。では、どうすれば「自分の取扱説明書」を手に入れることができるのか? 松岡さんは、日記をつけることを推奨しています。 ・気分が落ち込んだこと。 ・気分がよくなったこと。 ・何をしたら体調がよくなり、又は悪くなったか。 時系列でまとめておくと、客観的に自分のことを知る手助けになるとのこと。 「真剣」と「深刻」は紙一重のことですが、プロスポーツで「楽しんでプレー」をすることにおいて怒る人がいるそうです。怒る理由が、「真剣」にプレーを行っていないと感じてるそうなのです。松岡さんは、「真剣」と「深刻」が紙一重であると感じおり、不安や恐れを払拭して集中するために必要である。そのため、「楽しんでプレーをする」行為を批判するのは間違っていると論じています。 この辺は、自分も同じ考えです。「楽しむ」ことは、仕事を行う上でモチベーションや努力する上で必要なことだと日々感じています。本番において「楽しむ」くらいの心の余裕を持つことは非常に大切なことだと思います。 良い条件が良い環境ではない。これは、北京オリンピックで銅メダルをとった松田丈志選手のエピソードで語られています。本当の自分がやりたいことを聞くことを怠ると、自分探しの迷路に陥ってしまうとのこと。 日記や「自分の取扱説明書」を用いて自分と向き合う時間を作ると、自分の心の声を聞く力が養われるそうです。 この辺は、本当に反省の反省を行わなくては。特に昨今ですね、自分の心の声を聞くようになったのは。 己を知り敵を知れば百選危うしからずという言葉あります。この己を知ることは、非常に大切です。自分を過大評価もしなければ過小評価もしない。自分の欠点は自分の長所を伸ばすことで欠点を克服していく。 長所を伸ばすために、頑張ることはカッコいいことであり、頑張るということは坦々と反復することを惜しまないことである。 ・・・まったくもってその通りだと納得してしまいました。 言葉は願掛けでもあり、呪いでもある。だから、ポジティブの言葉は口にだしてはいけない。 やることをやって、それでも状況が変わらなかったら。リズムやテンポに変化つけるという全く新しいことを行う勇気も必要である。 「有り難う」と「難有り」 松岡さんの交友の中でプロ意識が高い人ほど「感謝する」気持ちがあるそうです。困難とは出会いたくないは「本音」としてはそうです。しかし、困難があるから、知恵を絞りたくましくもなるという事実も忘れてはいけない。 そして、その困難に乗り越えたのは自分自身だけの力だけではない、だから感謝する。 本書では、イチロー選手の話が出てきますが、イチロー選手は本当にグローブやバットを大切にするそうです。イチロー選手の練習はストイックで有名ではありますが、彼が活躍できるのはグローブやバットという道具があるから。 感謝の言葉である「ありがとう」は漢字を入れると「有り難う」。「難」が「有」る時ほど感謝の気持ちを忘れないことが大切であるということでしょうか。 そういえば、イエスキリストも「汝の敵を愛せよ」という言葉を残しています。 人としての心持ちとして、本当に大切なことなのかもしれません。
3投稿日: 2015.05.10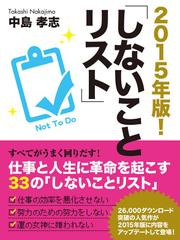
2015年版! しないことリスト
中島孝志
ゴマブックス
まさに逆転の発想
やらないことを決めるのも、戦略です。 <この本を読むべき人> ○優先順位をつけてToDoリストを作ってるけど、それでも時間が足りない人。 ○生活を抜本的に変えたいけど、何から手を付けたらいいのか分からない人。 <こんな本> まさに「コロンブスの卵」発想の転換で「戦略的に間違った行動」をリストアップして、それを実行しようが本書の言いたいことです。 従来のToDoリストはやるべきことの優先順位を決めてリストを作成します。 これは、優先度の高いものから行動を移せ、重要度の高いもののやり残しを防げるという非常に強力なツールでした。 非常に強力なToDoリストですが、これには一つ思わぬ落とし穴がありました。 本書では、アイビーリーとチャールズシュワップの話で紹介されてます。それは、大胆な革新や革命が起こせずに時代の流れに取り残されてしまったのです。 発想の転換で、「~しなくてはいけないこと」から「~してはいけないこと」に注目して、ピックアップしたリストを作り、現在の生活に取り込まれている「やってはいけないこと」や「しなくても影響がないもの」を排除していく考え方なのです。 <感想> 著者の中島氏は、プロならばサービス残業をするな、残業代を請求しろと断定しています。仕事を家に持ち帰るなんてとんでもないとも。そう言いながらも、家に持ち帰るべき仕事のヒントは教えてくれています。 仕事にはプランニングとオペレーションに分けることができます。 プランニング=企画、計画、設計 オペレーション=実施、行動、展開 プランニングであるアイデアを考える、そのための勉強、人と会って情報収集や議論は家でやれと言ってます。これを企画書の形にするのがオペレーションでオフィスでやれと。 この辺、全面的に賛成できるものではありませんが、確かに考え方がいびつになると余計な仕事を抱えこむというのは経験上体験してきました。今は、休日に仕事のことは考えることはあっても休日に実務を行うことはなくなりましたね。 「運」とは人と出会うこと。これは、「データの見えざる手」でも「運」とは人との出会いだと科学的分析を行っていました。運とは人が与えてくれるもの。 この辺は、自分の実体験で納得できるところがあります。 ・自分と似た価値観の人からは、励ましてもらい。 ・自分と異なる価値観の人からは、気付きをもらい。 読書の感想文をあげるようになったのも、その人達のおかげなのですから。 最後に「努力は掛け捨て保険のようなもの」について。 努力は必ずしも報われるものではありません。しかし、努力すること事態はムダにはなりません。 努力は例え目的が達成できなかったとしても、貴方の血と成り肉になっているのですから。 そして、努力とはもしもの時のミスや失敗を防ぐものだと認識すれば良いのです。
0投稿日: 2015.05.09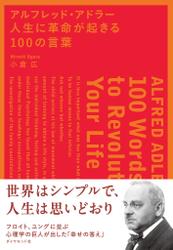
アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の言葉
小倉広
ダイヤモンド社
”世界は信じがたいほどシンプルだ。では、何が複雑にしているのか?”
<こんな人にお奨め> ○アドラー心理学に興味があって、アドラーがどんな言葉を残したかを知りたい人。 ○アドラー心理学の辞書的なものが欲しい人。 <この本は避けた方が良い人> ○アドラー心理学の本質を深く知りたい人。 <こんな本です> アルフレッド・アドラーが残した言葉に著者の小倉氏が解説をつけている本です。 <感想> アドラー心理学の考えはいたってシンプルです。 世界に意味づけしているのは、すべて人間である自分。 そして、すべての問題は対人関係に起因すると。 私によっては、前書きの「自己啓発の父・アドラーはなぜ無名なのか?」を読んで引き込まれました。 そして、なぜ無名なのかは次のエピソードで納得しました。 アドラーの講演を聴いた聴衆の質問 「あんたの話は、あたりまえの話(コモンセンス)ではないか?」 アドラーの答え 「それで、コモンセンスのどこがいけないのか?」 最後に気に入った言葉を紹介して感想を終わります。 『怒りなどの感情をコントロールしようとするのは無駄である。 感情は「排泄物」なのだ。 「排泄物」を操作しても何も変わらないだろう。』 思い切り、泣いたり、笑ったり、怒ったりした時はスッキリしますからね。 怒りの感情は悪いといいますが、怒った後は排泄物をトイレで流してそれっきりすれば良いこと。 確かに排泄物を流さないでいじり回すことは、不健全です(笑) 感情は暴走させて、人を傷付けさえしなければ、大いに発散するべきものですよ、感情は。
3投稿日: 2015.05.07
パワー・クエスチョン 空気を一変させ、相手を動かす質問の技術
アンドリュー・ソーベル,ジェロルド・パナス,矢沢聖子
CEメディアハウス
会話から得るためには、絶妙な質問が必要不可欠
≪こんな本です≫ これも一種の会話術。 相手から情報を引き出すためには、こちら側が的確である質問を投げかける必要があります。 著者であるソーベル氏とパナス氏が自分の体験や、いろいろな著名人からのインタビューしたものを分類と分析して、シチュエーションごとに使える質問をまとめた本となっています。 質問の活用法、質問をいつ使うのか、質問のバリエーションといった感じです。 頭から読む必要がなく、ある意味目次から興味をそそられるページから読むのがベストでしょう。 ≪感想≫ 空気を一変させ、相手を動かす質問の技術は、まず相手を知ることから始まる。 実は、質問の重要性は前回紹介した「データの見えざる手」でも、スティーブ・ジョブズが的確な質問でビックビジネスをものにしたという話が載っていたことから、この本を手にした次第です。 質問をする前に相手のことを知る、人間関係を構築するが非常に重要になってきます。 なぜならば、自分のことを知ろうとしない、ましてや信用できない相手に本音など話そうという気にならない。言われてみれば当たり前ですが、自分を売り込もうという考えに支配されるとこの当たり前のことができなくなります。この辺は、著者の失敗談もあげていますので、反面教師的にも使えます。 基本的にこれは強力な本ではありますが、自分にとってはもうちょっと論理をこねくり回した本が読みたかったので物足りないというのが正直な気持ちです。 ただし、30以上の質問がドラマ→解説→要点という流れの構成ですので、強力かつ分かりやすくなっています。 この本と相性が良い方には、人生のパートナーになってくれるでしょう。
0投稿日: 2015.05.05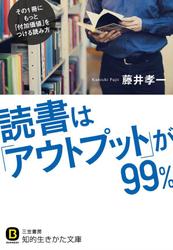
読書は「アウトプット」が99%
藤井孝一
知的生きかた文庫
読書は行動(アウトプット)してなんぼです。
読書の比重は100%インプットである現実は変わりません。 ただ、読んだ本の知識を知恵として自分に対して組み込みことを考えると、アウトプットという作業が必要になってきます。 アウトプットといっても、大げさに構える必要はなく、本の感想を言ったり、本の要約を人に伝えたりすることだけで良いのです。自分にとってはこのブログがアウトプットになっていますが、本の通販を行ってるところは、読者のレビューをアップできる場所があるので、それを活用すれば良いのです。 なぜアウトプットが必要なのか? それは、記憶力とは覚える力ではなく思い出す力が大切なため。この思い出す力はアウトプットすることで鍛えられるからです。 また、アウトプットすることを念頭におくと、「この本から何が役に立つものが得られるのか」という意識を持つことができます。 これは、確かに私もブログをやるようになって、そういう意識を自覚するようになりました。 また、本著では、斜め読みでもよいから乱読せよ。と薦めています。 本の選定としてまえがき、目次、著者のプロフィールを重要視しています。特にプロフィールはいったいこの人は今までどのようなことを成し遂げてきたか?に注意しており、履歴書のようなプロフィールを書いてある本は敬遠しているとのこと。 世の中の流行はベストセラーで、世の中の本質はロングセラーで、いわゆる古典やビジネス書ならばドラッガーに当たりますね。 あとは、好きなものを好きなように読む。これが、長続きの基本です。 読書というは、簡単お手軽にできる自己投資です。仕事のヒントの得られる事例の一つとして「ロス・チャイルド」の小説をあげています。「ビジネスにおいて情報を制したものが勝者になれる」は誰もが思い立つでしょうが、じゃあどうすればいいのでしょうか。 小説では、ロスチャイルド家の三男のネイサンが、新人の仕事として郵便物と帳簿の整理という雑用から、商取引と金銭のやり取りがすべてわかり、情報の重要性が理解できたという場面があります。 これをただ読んで終わりにするか、自分なりにアレンジして実行するかによって、得られるものは格段に違ってくるはずです。 最後に読書を行い、微力ながらも誰かの力になれることを信じて、このブログを続けていきたいと改めて思いました。 おまけ 子供の頃の嫌だった、読書感想文も本質的には「読書はアウトプットが99%」を狙っていたのだろう。 でも、やり方が悪いよね。と、最近思った次第です。
0投稿日: 2015.05.05
レビューネーム未設定さんのレビュー
いいね!された数47
