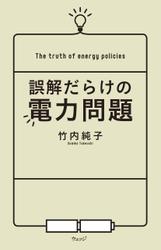
誤解だらけの電力問題
竹内純子
ウェッジ
電力自由化で目先の利益で電力会社を選ぶ前に、電気のことをもっと知った方がいい。
本著を読んで、電力神話というものはかなり根深いものだと痛感しました。 電力には「神話」が生まれやすいと論じられていますが、確かに間違った固定観念が植え付けられやすく、思考をするにあたって、間違った情報を元に判断したら結果は必ず間違うのは当たり前です。 そして、日本と外国とは電力事情が違いますから、外国がこうだから日本もそれに習った方が良いという考えは非常に危険だというのも認識できるかと思います。 今年から、電力業界が自由化されていろいろな企業が参入しています。しかし、実は日本の電力業界の黎明期は今のベンチャー企業に相当する企業が入り乱れていたことを知ってる人はどれくらいいるのでしょうか? 交流電流の周波数が東日本と西日本では異なりますが、これもベンチャー技業が自分に有利になるように好き勝手にやった結果であったりします。 じゃあ、お前は電力自由化は反対なのか? と、問われたら、「競争がない分野は発展しない」と思っていますので基本的には賛成です。 しかし、電力自由化が必ずしも電力料金が下がるとは限らないということも知っておくべきです。 この辺は、電力事情で日本の遙か先を進んでいるドイツの事例で説明されています。遙か先というと「輝かしい未来」を想像してしまいますが、現実は「誰も幸せになれない地獄」となっています。そして、ドイツの失敗と同じ失敗を日本も犯そうとしています。 ドイツの失敗とは? 一つは、家庭で発電した電力を買い取る仕組み(FIT)の問題点をあげてます。著者は実際に「太陽光発電」導入して明細書をあげてます。注目するのは2点、売電での収入とコスト負担の省エネ発電賦課金です。売電の基本金額は年々下げていくのに対して、コスト負担は年々上がっていく仕組みとなっています。初年度はペットボトルのジュース程度の負担が、レストランの昼食の料金まであがっていくのです。 実際ドイツでは、憲法違反と裁判沙汰になっています。この問題点が顕在化していたのに、日本はこれを導入してしまいました。 二つめ、自由化の弊害についてです。 競争原理が働くとサービス向上されるのは確かですが、それは盤石な経営基盤があってこそなんです。特に太陽光や風力発電は晴れなければ発電をしない、風がなければ(風速がありすぎても)発電しないとなれば、補完として火力発電に頼ることになります。特にドイツは再生可能エネルギーによる発電を率先して使わないといけない法律があるため、火力発電所の効率が非常に悪い状態となっています。 また、電力は供給と需要のバランスが非常に大切で、太陽光や風力が頑張りすぎて電気を大量に作られ供給過多になった場合も停電の可能性が高くなるそうです。こうなると電力会社はお金を払って電気を捨てることになり、経営が圧迫しています。実際にドイツでは2000年から2010年の間に電気料金が1.8倍に膨れあがりました。そして、今は、倒産した電力会社もあり税金を投入している現状となっています。 あと本著は、電力事情を歴史を踏まえて完結にまとめられています。各国の産業用と家庭用の電気料金を購買力平価換算や為替レートで比較を行っていたり、環境問題に対しても記述があります。 ーーーーここから抜粋 ーーー 実は日本政府は、日本と相手国政府の2国間で協定を結び、日本の技術を導入して温室効果ガス削減を図る、柔軟で実効性のある仕組みを構築しようとしています。この新たな枠組みには、多くの途上国が興味を示しています。 ーーーー 抜粋ここまで ーーーー でも、なぜか日本では報道されません。 なぜなら、「日本が孤立の危機」と書かないと、本社のデスクに記事を取り上げてもらえないそうです。 こんなところにも、報道しない自由が蔓延っているとはビックリした次第です。 今後、電力会社をかえるかえないを考える上で、電気ってどうやって作られて、家庭にはどうやって運ばれているのか? 海外と比べて日本は本当に劣っているのか? 電気を安くなるのは歓迎だけど、引き替えに何を失うのか? この電気のことを考える為の材料が、よくまとめられている良書です。
0投稿日: 2016.04.23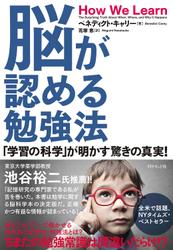
脳が認める勉強法
ベネディクト・キャリー,花塚恵
ダイヤモンド社
勉強のみだけでなく、人類が脳の解明の歴史も学べるところが良いです
この本の良いところは、勉強法のみならず脳に関わる研究の歴史も学べるところです。 そして、この歴史の部分で何度歯ぎしりしてしまったか。 エビングハウスの「忘却曲線」は有名ですが、一方のバラードの「レミニセンス」はほぼ無名です。 簡単に説明すると「忘却曲線」とは時間が経てば、思い出せる記憶が段々減っていくことを実験でグラフ化したものに対し、「レミニセンス」は「一度忘れたことでも、何もしなくても思い出す」という現象のことです。 このバラードの「レミニセンス」発表後しばらくは、追試されてましたが、「幻想だよ」と数十年放置されてしまいました。そんな話が珍しくありません。 この手の話は、学者の話を無批判に信じるのは危険だなと感じます。そして、そういう考えを持つ人が新しい発見ができるということも、教えてくれます。 この本の構成としては、脳はどうやって記憶をするのか? その仕組みはどうなってるの?から始まり。 脳科学の歴史を踏まえて、勉強法を紹介していくスタイルとなっています。 勉強時間、復習の間隔、勉強をする上での環境、反復練習、小テストの活用方法、考えなくても学べる方法が紹介されてます。これは、学習側のものだけで無く、教育指導していく人たちにも読んで頂きたい本です。 学生時代にこの情報は知りたかったものが一つあります。それは「復習するときは、授業の時にとったノートは最初は見ないで行うこと」です。 いわゆる、記憶を強化するのは「思いだそう」とする時なので、ノートを最初に見てしまうと効果が薄れてしまうのです。 そして、「流暢性の幻想」にも気をつけたいところ。いやゆる、下線を引く、マーカーを付ける、覚えた直後に同じ勉強をする、他人が作ったまとめで理解する。これらは、「自分が簡単に覚えたから、もう知っている」という幻想を抱いて、本番のテストで大失敗する原因となります。 また、絵画や美術の審美眼を鍛える、画期的な方法もこの本に載っています。驚くことに審美眼を鍛えるには考えることは必要がないのです。これも、驚くべき脳の仕組みを利用しています。 今まで、勉強しても身につかなかったのは、けして頭が悪いわけではないのです。原因はたった一つ。 ”勉強をして「覚えられない」原因の大半は、勉強方法が間違っていた。” この本をそれを教えてくれています。 人間、生きている限り、学ぶことをから逃げることができません。したがって、今からでも正しい学習方法を知ることはとても有益なことです。 一人でも多く、この本を手にとって頂けると幸いです。
0投稿日: 2016.04.02
コトバを変えなきゃ売れません。
齋藤匡章
サンマーク出版
言葉は無料で使えるからこそ、ちゃん使わないと価値は生まれない
言葉は誰にでも平等に使え、使用料は無料。だからこそ、ちゃんと使わないと価値のある言葉は生まれない。それどころか、言葉をいい加減に使えば効果をあげるどころか、逆効果にもなりかねない。 価値を生みだすために、「その言葉が自分自身で生みだしたもの」「相手を思いやったもの」が本当に大切だと説いています。 確かに言葉を伝えるためのテクニックは存在します、それがハウツー本が山のように売られています。ハウツー、そうテクニックは必要です。しかし、テクニックだけでは人の心は動かせないが本著の伝えたい内容となっています。 『言葉を伝える』とは、誰に伝えるのか? そう、言葉を伝える「相手」のことを第一に考えないといけない。言葉とはコミュニケーションの道具なのですから、「相手」のことを第一に考えるの当たり前の話なのですが、テクニックに拘るとこれを忘れがちになります。 特にハウツー本は、「自分をどう相手に伝えるか」がメインになりますから、それが顕著になりがちです。 もう一度、会話の目的意識を考え直すことが必要です。 この本はビジネスを言葉を使ってビジネスを成功させようという話の本です。では、ビジネス秘訣とは何か? 「利益の高さ?」「粗利の確保?」 いえいえ、ビジネスの本質は「人を行動に駆り立てる」とのことです。 人を行動に駆り立てる4つの要素。それは、「好奇心」「信用」「信頼」「安心」これを常に意識して言葉を使えば大きな力になります。ただ、その言葉の通りに行動しないと相手に見破られます。 相手の為に言葉を使うということは相手を騙さないということが大前提です。 次に言葉を伝える相手の話になりますが、商売なんだから不特定多数を想定して文章を書く。これは、100%失敗するそうです。極意は恋愛した相手にラブレターを書くように、商売用の文章も書くことを誰か特定の人をイメージすると良いそうです。特定の人がいなければ、理想のお客さんを作り出してもよいそうです。 「言葉が世界を自分と世界を決定付けている。」 と、書くと大げさに聞こえますが、本書では虹の話で説明しています。日本人なら虹は何色か?と、尋ねられたら「7色」と答えますが、ヨーロッパでは「6色」なんだそうです。 なぜなら、ヨーロッパでは虹の色は6色しかないから。同じ現実世界を見ていても「内的世界」が違えば現実世界も異なって見えてくる。 つまり、「言葉によって世界の見え方が変わる」ということです。 これは、日頃の言葉使いによって自分の世界が変わるという意味でもあります。ポジティブな発言とネガティブな発言。一言一言だけなら対して差はありませんが、長い年月で自分や相手に言葉を浴びせつつけたらどうなるでしょう? 「だって、人間だもの悪口ぐらい口に出ちゃうよ」なら、それを打ち消す為に「人の良いところも口に出して褒めましょう」 これは実体験ですが、人の長所を見つけられる能力を養う訓練にもなりますし、思わず悪口が出ちゃった駄目だ! というネガティブ思考のスパイラルを断ち切れます。 それから、文書の上達はやはり文章が上手い人のマネを行うこと。著者はこんな体験したそうです。 「川端康成や夏目漱石といった文豪の作品をすすめてくれたのは、大学の先生です。 『きみね、外国語をやるんだったら、夏目漱石と森鴎外を読んでおきなさい。昔、日本で一番、英語ができたのが夏目漱石。一番ドイツ語ができたのが森鴎外。そのあたりの文章を読まなくて、どうするんだい?それで本を読んでいる気になっていてはダメだよ」といわれました」 このあと、今更、夏目漱石かよと思いつつも実際に本を読んだら、グイグイと引き込まれて無意識に文章を真似ていたそうです。 文章を上達するためには、文章が上手い人を真似て文を書く。スポーツを上達する為に秘訣と同じです。スポーツよりも敷居は低いですが、こうやって文章を書いてますと、上達するには根気は必要だと痛感しています。 最後に、言葉を使うことで大事なのは「イメージ」すること。自分がイメージできていない言葉には「力」ありません。力のない言葉は相手に伝わらないですし、相手も協力したいと思いません。 そして、人は「同調」しようとする力が絶えず働いています。それは、より力の大きい方へと同調する傾向にあるので、イメージを具体的に持つことがとても大切です。 言葉は、誰にも無料で自由に使えるものです。 ゆえに、ちゃんと使えないと力を発揮できないどころか逆効果になってしまう。 言葉をちゃんと使うためには、誰に言葉を伝えるのかを明確にし、イメージを持つことが大事である。 この本質をちゃんと抑えていないと、テクニックをいくら覚えていても意味がない。 これが、この本の伝えたいものとなっています。
0投稿日: 2016.04.02
仕事の速い人が使っている 問題解決フレームワーク44
西村克己
学研
世界をどう切り取るか、どう見方を変えるか、それだけで見える世界が劇的に変わる。
世界を変える道具がフレームワークです。 この本、最初に読んだ時は初心者向けであるため購入して失敗したかと思いましたが、あれ、そうでもないかな?と、読み進めていくうちそう思うようになり、最後には自己流改善の指針に使えるなと感じました。 この本は、フレームワークの根幹部分を系統立てて紹介しています。そして実際のフレームワークの使い方は、架空の会社や人物を登場させて解決させていく手法をとっていますので分かりやすく説明しています。 4月から新社会人になられる方は、購入して損はしない本であると太鼓判を押しましょう。 企業に入ったら、研修や実習は行いますが実際には「ミッシー」や「SWOT分析」なんて教わりません。少なくとも自分は教わった覚えはなく、自分で勉強して初めて知った単語だったりします。ちょっとでも、知ってる単語や考え方の概念が頭にあるかないかで理解力が大幅に違いが出てきますし、思考するまえに必要な情報はそろっているか、何のために思考をするのかを知って思考するのとしないのとは雲泥の差になります。 非効率な仕事のやり方が身に付く前にも、新社会人には手にとってもらいたいです。 次にこの本の欠点です。それは、2011年に発刊されたため、時事ネタとは古く下手をするとこの本自体の信憑性が損ねかねないというところでしょうか。まあ、液晶TVやスマートフォンが全盛期の話ですから、ああそんなこともあったかなと懐かしい思いをする人が多いですかね。。 ここの下りは、『「再建・売却・撤退」は既存ビジネスの経営改革の基本』を絡めて読むと面白いです。液晶TVでブイブイいわしていたシャープやスマートフォンのサムスンをみると「事業の転換」は非常に大事なんだということを肌で感じます。 逆に、カメラ業界を牽引していたコニカとミノルタ(あえて、コニカミノルタとは言いません)がカメラをあっさり捨てたのは、大英断だったのでしょう。富士フイルムの化粧品分野への進出は最近スポットがあたっていますが、フィルムの脱却はフィルムの売り上げがまだ右肩上がりの時に初めていたそうですから、本当に脱帽です。(コニカミノルタと富士フイルムの話は本書には記述ありません) 最後に、フレームワークは仕事だけに応用するのは勿体ないです。 フレームワークは思考を補助するための道具です。いろいろな情報を集めて思考し判断を行うことに関しては仕事も日常も大差はありません。 問題解決トレーニングとして、ダイエットが問題としてとりあげられています。 カロリーの高いものを食べないようにしているのに、いっこうに体重が減らない問題です。 使用したフレームワークは「ペイオフマトリックス」。本当にカロリーの高い食品を食べないようにしているか。思い込みだけで食品を選択していないか。これを使って無駄な努力とおさらばしようという話です。 インターネットとスマートフォンの普及で様々な情報が簡単に引き出すだけでなく発信もできる世の中になったことで、情報過多という状況になりました。情報過多ゆえに本当に必要なものが見つからない、情報が抜けていたのに気づかない、声が多いから耳を傾けていたら実は有害な情報だった。そんなことも珍しくない時代になってしまいました。 いくら、機械が発達しても最終的に判断を下すのは私たち人間です。 世界を切り取る、つまり情報を如何に取得選択して思考を下すかが、より大切な時代になんだなと実感しました。
1投稿日: 2016.04.02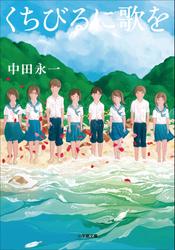
くちびるに歌を
中田永一
小学館
運とは人との出会いで切り開かれる。
いやー、面白かった。単純に合唱部の男女仲が悪くなったのが、ある出来事で一致団結してハッピーエンドを迎える作品ではないからです。そして、この作品に出てくる大人は決して格好良くありません。良くも悪くも子供達より経験があるだけの一人の人間として脇を固めてる存在であるため、子供達の心情の変化が「大人」の干渉で歪められた印象がないのも楽しめた要因だと思います。 物語は合唱部がNHKの合唱コンクールに挑戦することを軸にして進んで行きます。 合唱の構成が女子のみと男女混合では、コンクールの課題曲が変わるというのも初めて知りました。 男女混合の課題曲は「手紙」。歌詞の内容は15年後の自分に宛に手紙を出すという内容なので、歌詞の内容を深く感情移入できるよう、合唱部全員に15年後の自分に手紙を書くよう宿題を出されます。この宿題が物語後半に深みを与えています。 生徒一人一人が主人公ではありますが、たぶんメインの人物を一人あげろと言われたら、「桑原サトル」が最有力でしょう。 彼はある意味事故で合唱部に入部することになりましたが、人と出会いを重ねることになります。出会いを重ねる事に彼は成長していきます。 スティーブ・ジョブズの言葉に「運とは人と出会うこと」や科学的に運を検証した矢野和男氏の「データの見えざる手」でも運は人との出会いでもたさらされると結論付けています。 彼は、この作品の前と後では立ち位置や人生そのものはなんら変わっていませんが、見える世界は確実に光り輝いていることでしょう。 読後は、本当に心地より気持ちになれました。
1投稿日: 2016.04.02
中国4.0 暴発する中華帝国
エドワード・ルトワック,奥山真司・訳
文春新書
キーワードは逆説的論理。国家間の戦略は逆説的論理で考えないと足下をすくわれる
中華人民共和国の戦略の変遷を1.0から4.0と呼び分けています。 1.0の時は平和的台頭で、諸外国とは摩擦はありませんでした。 リーマンショックによってアメリカ経済が失速した時、中華人民共和国は大きな勘違いをしました。 それが、中国2.0と3.0の攻撃的な戦略です。 小国に対して金で顔を叩くような対応し、大国に対しては市場を餌にして横柄な態度に変わっていったと・・・普通に成金の嫌なおっさん状態に。 それだけでなく、この時期から南シナ海の軍事的衝突が始まってきました。 なんで、中国がこんな戦略をとったかというと、「超大国の中国に刃向かう国なんて存在しない」と思い込んでいたのだそうだ。 ルトワック曰く、「相手を発明」してしまったから、これは中国だけでなく、過去には至る国で同じ間違いをしてました。 湾岸戦争時のアメリカは「民主化を望んでいるイラク人」を発明して、フセインを排除すればイランは民主化して万々歳というストーリーを作っていました。 ルトワック自身、イラン人は民主化なんて望んじゃではいないという発言をしたら、人種差別主義者の烙印を押されたそうです。 相手を創造する根幹は「感情」に起因しており、中国の感情は、アヘン戦争、西洋の列強の進出、日本の台頭へのコンプレックスをこの期に晴らそうととルトワックは分析しています。 中国が遅れてきた列強主義と揶揄される行動が、納得できました。 中国が各国の反発を招いたのは、「逆説的論理」が理解できていなかったこともあります。 「大国」と「小国」が激突したら、絶対に1対1の対決とはならない。 なぜなら、「小国」を援助する国が現れるからです。 ルトワックの持論の一つ「大国は決して小国に勝てない」。日露戦争時のロシアやベトナム戦争時のアメリカもこれに当てはまります。 「ロシアは戦略を除いてすべてダメで、中国は戦略以外はすべてうまい」 中国の戦略は行き当たりばったりなので、ルトワックは日本に対してこう提言しています。 計画的に対応しようとしても、それはうまくいかない。全ての可能性に対して受動的に対応するべきだと。
1投稿日: 2016.04.02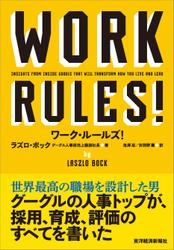
ワーク・ルールズ!―君の生き方とリーダーシップを変える
ラズロ・ボック,鬼澤忍,矢羽野薫
東洋経済新報社
人事方面からGoogleの失敗例を紹介した希有な本
Googleの人事のトップがGoogleという会社を如何に育てていくために悪戦苦闘したことを赤裸々に綴った本です。 Googleを育てるとはいっても、技術方面の話ではなく、人事、文字通り人を雇う為に行ってきたこと、社員教育、昇級、そして福利厚生の方面の話がメインとなっています。 世間一般の会社は見習うべし。と、いったものやら、これは会社の業種によっては真似したらかえってマイナスになりかねないといった話まで臆面も無くさらしてくれています。 Googleの凄いところは、新しいシステムを自社に用いるのに、必ず検証を行うところ。 そして、実験的システムを実行するのに一番大切なことは「サービス期間で永続的なものではない」ということを社員全員に告知することです。 過去に、この告知をしなかったら、Google社員が暴動を起こしたそうですから・・・(笑) また、Googleの意外な一面として、社員教育に重きを置いてないことです。 本書では「がんばれベアーズ症候群」と呼んでいますが、教育さえ施せばどんな社員もエリートに負けないという幻想に囚われていると切って捨てています。 「がんばれベアーズ」とは、自分が子供の頃に放映していた、アメリカのドラマです。落ちこぼれ集団である、少年野球チームが幾多の試練を乗り越えて、最後にはエリートチームに勝利する話です。 Googleでは、質の高い人物を入社させることがなによりも大事だと結論付けています。 ただ、質の高い人物は、必ずしも学力の高い大学出身者ではないところが肝でもあります。 この本を読んで、Googleは挑戦者なんだなと改めて思いました。 どのくらい挑戦してるかというと、経営陣でさえいつの間にか知らないプロジェクトが立ち上がって、知らない間にプロジェクトが閉鎖されているそうですから。 会社を買収して大きくなった会社というのは、一側面だったというわけです。 成功例ではなく、失敗例を多く載せていることから、会社の人事の人は一度読まれた方がいいです。 一つの成功例は、他の会社には適用できないことは当たり前ではありますが、一つの失敗例は多くの会社に当てはまりますから。
0投稿日: 2016.01.17
虐殺器官
伊藤計劃
早川書房
言葉はツールじゃない、進化の過程で手に入れた器官だ
著者である伊藤計劃氏のことは、全くもって知りませんでした。そして、既に他界されていることを知って本当に残念でなりません。 テロを防ぐために、生体認証であらゆる生活活動が管理された世界、そしてテロで当たり前に核爆弾が使われた世界。我々の今の世界が、このまま突き進めば、この世界は本当の世界になるのではないか? そんな恐怖をうまく演出してくれています。これは、2015年のパリのテロがあった後に本を読んだからより一層そう感じたのは否めません。作者が作品を手がけた時代背景も大切ですが、読者が本を読む時代背景によっても作品の評価が変わる。文章にしてしまえば、当たり前のことですが、それが手に取るように実感してしまいました。 主人公はアメリカの情報将校で主な仕事は暗殺。ストーリーはある小国の広報担当を受け持っている民間人の暗殺を行うところから始まります。ここではこの世界の技術水準の高さを説明しているのですが、形だけのセキュリティの弊害を笑い飛ばしているようにも感じられました。 結果的にターゲットはこの国から脱出しており、主人公の作戦は失敗してしまいます。そして、このターゲットを追いかけることから本当の物語が始まります。 ターゲットが暗殺される理由。それは、ターゲットが侵入した国は、必ず自国民を虐殺し始める。 それゆえに、世界の警察たるアメリカは、ターゲットを暗殺する。 実際はそんな簡単な話ではありませんが、本を読む楽しみを奪うことになりますのであらすじの紹介はここで終わります。 私がこの作品で気になった部分、「言葉はツールでなく、器官そのものである」。これは、学術的根拠は一切ありませんが、この考え方に衝撃をうけました。 言葉が器官だなんて、ネタバレもいいとこ? と、ならないようには配慮していますから、安心して読み進めてください。 遺伝子によって、ある細胞が脳や腸や心臓が生成するように、言葉も遺伝子によって作られる。 また、人間の思考は言葉によって遮られない。認識をする上で言葉を利用しているだけであり、思考そのものは言葉などの制約に邪魔されない。 作中では上のようなやり取りがされて、そんな馬鹿な−! と、思いながらも、アインシュタイン等の天才達は「イメージで思考をしていた」数式や言葉は思考した結果をまとめるのに使っただけに過ぎない。と言われ、思わず納得。 結局は「卵が先か、鶏が先か」として扱われ結論は出してませんが、現実の世界でも脳の機能は謎だらけ。いまだに「幽体離脱が現実として確認されてるから科学として扱うべき」「脳を介さない精神活動なんてナンセンス、それは非科学」が争っている中、真面目に言葉は遺伝子から生まれたと話をしても良いのかもしれません。(ブレーンストーミング的な感覚で) 最後に、ターゲットが侵入した国を虐殺させる理由が明かされます。 それは、反戦作品の永遠のテーマに直結していると思えてなりません。 ターゲットが行った行為はとうてい許されるべきものではないのですが、心情的には同情してしまいます。 余談 昨今、人口知能やロボットに関する書籍が増えてます。これらの本は、昔と違って人間のサポートではなく、人間に置き換えることができるがメインとなってきてますね。「虐殺器官」では人工知能の研究が進めば進むほど、置き換えは不可能であるため「人間は高価」なものと位置づけされています。 将来どうのように未来が進んでいくのか、見物です。
1投稿日: 2016.01.11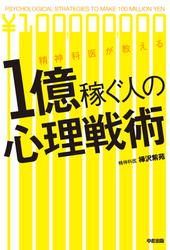
精神科医が教える 1億稼ぐ人の心理戦術
樺沢紫苑
中経出版
自分を幸せにするには、自分しかいない
まず最初に、タイトルの”1億稼ぐ”は本書の内容には完全に関係ありません。 お金儲けが目的の人は、買ってはいけない本です。では、本の感想に入ります。 自分を幸せにするには、自分しかいない。 「はじめに」では、映画の『カンフーパンダ』の究極の奥義は、すでに自分の中にある。 「おわりに」では、映画の『幸せのレシピ』、「幸せになるレシピがあるのなら、教えてほしいわ」「それは君が一番よく知ってると思うよ」 自分の外にあると思っていたものが実は自分の『内にある』これを気付けるかどうかが、より人生を歩くことができるかが決まる。 では、どうすれば気付きができるのか? 気付きを得るためのアドバイスとして、心理学や映画のエピソード、または社会事件や現象をからめて話を進めていきます。 初めて心理学系の本を読む方にはとっつきやすいかと思います。逆にこの手の本を読んでる人には物足りなく感じるでしょう。そういった意味では、タイトル付けが非常に残念でなりません。 とはいえ、なるほどな。と、思ったところもありました。第3章の失敗の心理学です。 経営者が手元にイエスマンだけ残した会社は駄目になるのは、「ディスカッション」が起こらないことから発展しないという切口には、なるほどそういう考え方があるのかと納得しました。 ブレーンストーミングで、気に入らない意見を尽く排除していくようなものですからね。 また、この手の輩は「自己愛性パーソナリティ障害」の可能性が高く、敵は排除するそうです。 経営者ならばその人物を「クビ」にし、国の支配者ならばその自分を「処刑」する。 ちょっと、薄ら寒い話ではあります。 また、暴言・失言については、「日頃からそういうこと口に出してるから」と思っていましたが、心理学的に分析すると「公的自己意識」が働いていない状態、いわゆる、誰も見てない場所で『本音』をぶちける状態になっているそうです。 そして、その「本音」が「侮辱」になっていたら、さあ大変です。 ラッセル・G・ギーン氏の心理実験でジグソーパズルを完成させる課題を与えたところ。 1.絶対に完成できない組 2.対人妨害を受ける組 3.やり方に対して、非難、侮辱して屈辱感を与える組 4.いっさいの妨害のない組 一番攻撃的になったのが、3番の「屈辱」を与えられた組でした。 そう、口は災いの元は科学的に立証できたのです。人を呪わば穴二つもこの原理なんでしょう。 それから、ストレス発散としてお酒を飲んでる人は要注意。 お酒を飲んでの愚痴というネガティブの思考は特に危険です。アルコールが回った酩酊状態は催眠状態に近いため、ネガティブの思考が自分の潜在意識にインプットされてしまいます。 潜在意識は、「主語」と「否定語」は理解できませんから、他人への悪口であっても、潜在意識は自分に対しての悪口だと認識します。本当に恐いですね。 また、アルコール依存症について私は勘違いしてました。アルコール依存症はアルコールの量とは関係なく、回数が問題だそうです。なんだかんだ、理由をつけて毎日アルコールを飲んでる人は予備軍かもしれません。 アルコールを飲まない日を作るのは、肝臓だけでなく心身にとっても安らぎを得られるでしょう。 金儲けに関係なく、<書籍説明>でちょっと興味を持たれた方ならば、この本を購入しても損はしないでしょう。 自分は学びました、例え無駄な時間を過ごしたとしても「感想」をあげれば有意義な時間に生まれ変わるのだと。 「この世で最悪な状況」を経験しても「よーし、これをまとめて本にしよう」と出版してヒットしたら、1億稼ぐのも無理じゃ無いような気がしました。
0投稿日: 2015.11.28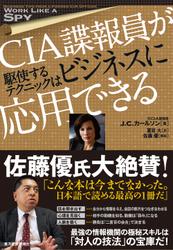
CIA諜報員が駆使するテクニックはビジネスに応用できる
J.C.カールソン,夏目大,佐藤優
東洋経済新報社
CIAがもっと頼りにするのは、人間の知性である。人間の知性がすべての基礎だといってもいい
この本の柱は二つ、危機的状況に陥った組織のありようと個人における情報の収拾と漏洩の防止におけるCIAにおけるノウハウです。 あくまでもビジネスに応用できる範囲でありますので、国家規模における手段や法を破るようなことがらは書いてません。一応、この本はCIAの検閲を受けてるそうです。 危機的状況に陥る組織とは、いわゆる倒産の危機に直面した会社を指してます。 このような企業は、下記のような特徴を持つそうです。 1.経営陣が雲隠れ(対外的だけでなく、社内に対しても) 2.命令系統が混乱(忙しいだけで、生産的活動ができない) 3.正当な評価がされなくなる(愛社精神がなくなる) これに対して、CIAは9・11のテロの時にアメリカの至る所から、このテロは未然に防げたのではないかと総攻撃を受けてたそうですが。 上記の1・2・3のような事は起こらずに、トップの人間は現場の様子を伺いに顔を出し、縦割りや現場組とディスクワーク組の仲の悪さが改善され、「お前のがんばりはちゃんと見ているぞ」というバックアップがあったため、仕事へのテンションが下がらずに済んだそうです。 次に個人が持ってる情報について。 どんなにテクノロジーが発達しても、人間が面と付き合わせて入手する情報には敵わない。 サダム・フセインが「大量破壊兵器」を所持しているという事前情報をもとに軍事活動を行いました。 イロイロ憶測があって、「大量破壊兵器を持ってる」はでっちあげて軍事行動を行ったという話もありますが、本著では「本当に大量破壊兵器を所持してる」と思い込んでいたと告白しています。 衛星写真を使い通信を傍受し、施設では博士号を持った科学者が勤務し衛兵が施設を護衛し、真夜中に物品を軍に納入する。これは、黒だなと現場に行ってみれば、その施設は単なる食塩生成の工場だった。 ”本当に理解するには、ただ現場に行くだけでいい、ということも少なくないのだ。” これは、「インターネットで情報収集して分かった気になる」ことへの戒めとしたい。 さて、情報を入手するには「人と会う」が最適だと言ったように、CIAでは次の4つの基本を徹底的に鍛えられるそうです。 「協力者の候補を決める」 「候補者と接触する」 「協力者として適切かどうか見極める」 「候補者と親しくなり、信頼関係を築く」 この中には、スキルとして相手から警戒されないよう情報を得る話術なるものありますが、 『人と確実に親しくなるテクニックなど存在しない』とバッサリ切ってます。 なぜなら、誰かと信頼関係を築くことはスキルではないからです。 そういうわけで、諜報員というと「嘘」だらけってイメージを持ちますが、『嘘は極力つかない』ことをCIAでは重視して、「嘘」をついたことを謝ることも行うそうです。 ちなみに、「嘘」と情報操作は明確にわけてます。情報操作とは「確信は話さない」「誤解されるように話す」などのことです。 また、自分から情報を取られないための注意事項も本著では一つの章使って警告を与えています。 今の時代は国よりも産業スパイの方がお金になるから、情報を盗まれる危険性が高くなっています。 情報の価値は人によって違います、自分には価値がなくても相手にはお宝の山かもしれません。 特に、SNSは情報を共有するためのものであり、情報を保護するものではないことを頭に入れる必要があります。 CIAでは、個人の王国を作ることを奨励してます。 別にこれは、組織のトップになれということではなく、あらゆる情報が耳に入るようなネットワークを作れということです。 CIAでは将来出世が見込めるような若手にネットワークに引き入れることが当たり前だそうです。なぜなら、偉くなってからだと会うことすら困難になるからです。 そして、自分が偉くなっても、このネットワークの面々には態度を変えてはいけないそうです。なぜなら、真っ先に現場の異変や危機を告げてくれるのは彼らだから。 ビジネスにおいても諜報活動においても、信用と信頼は裏切ってはいけないのです。 そして、本当に情報が欲しいなら情報を持ってる人に会いに行け! なのです。 これらを確実に実行するに一番大事なのが、”知性”なのです。
0投稿日: 2015.11.23
レビューネーム未設定さんのレビュー
いいね!された数47
