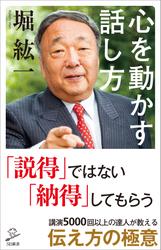
心を動かす話し方
堀紘一
SB新書
テクニックより大事なもの。話下手を免罪符にしてないか?
話をする上での最終目的は、「説得」ではなく「納得」してもらうこと。テクニックはあった方がよいが、それよりも大切なことは「相互尊敬」と「相互信頼」を構築すること。 貴方は「話し下手」を免罪符にしてないか? 自分は「話し下手」であると、言い訳している人ほど自分本位で相手のことなど微塵も考えてないと切り捨てています。 そして、「話下手」な人ほど相手の話を聞かない傾向にあるとのこと。 まっこと、耳が痛い思いをしました。
0投稿日: 2016.12.31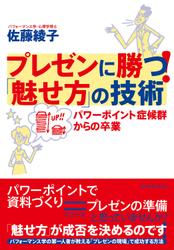
プレゼンに勝つ!「魅せ方」の技術
佐藤綾子
ダイヤモンド社
人間の本質へのアプローチだから、古さは感じられない。
最近、電子書籍化(2016年)されたので購入。出版そのものは2006年と10年前の本ですが、人間の本質について書かれているためか、古さは感じられません。逆にいえば、時代の流れやトレンドを取り入れていたなら、陳腐化が激しく見るに堪えないものになっていたかもしれませんね。 とは言っても、プレゼンが上手い人の例で「小泉純一郎元首相」が登場しますので、それなりに時代は感じます。 タイトルから分かるとおり、プレゼンテーションを「見せる」のではなく「魅せる」方法として。プレゼンテーションの準備は「パワーポイントによる資料作り」ではない、ということです。 プレゼンテーションは、「説得」ではなく「納得」させることですから、相手側の意思表示を如何にキャッチできるか。そして相手が複数いたら、誰が決定権を持っているのか。非常に大切だと力説されておられています。 頭では理解できていても、本著のことを実際に実行できているのか? と、聞かれたならば、「出来ていなかった」と答えざる得ないです。そのくらい、細かく実施しなければならないことが書かれています。 本著では一切このような資料を作れという話しはされてません。では、何の話しをしてるかというと、相手に「納得」してもらうのにスピーカーである我々が身に付けるべき、「考え方」「話術」「身だしなみ」に関わる「技術」的な話しです。 技術的な話しですから、センスではなく練習で能力が向上するものばかりとなります。 さて、小泉純一郎元首相ですが、当時はともかく今はそれ程評価を高く上げる人はいないかと思います。これは逆説的に「プレゼン」の大切さを示しているのではないでしょうか。 「説得」ではなく、「納得」して貰うためには相手に受け入れてもらう必要があります。そのためには自分をどう魅せるかを体系的に書かれたのが本著です。
0投稿日: 2016.12.23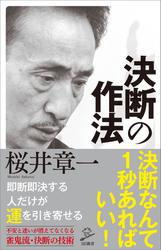
決断の作法
桜井章一
SB新書
しがみつかない人生を送るには
これは、とある人から薦められた本です。 某所のレビューだと、評価はビックリするほど低いのですが、評価が真っ二つに割れる本はかえって興味がそそられましたので、購入しました。 本を読んだ感想では、評価を高く付けた人の意見も理解できますし、評価を低く付けた意見も理解できました。 この本に「何を見つけられるか?」で、判断は180度違ってきます。基本「自己啓発」の範疇で評価するなら、自分も価値はなしと評価を下します。 ただの「雀荘の親父」である著者が、「自分なりの信念」を貫いてきたことで、読み手がどう感じるか、そして自分とは違った世界を見ている存在を知って、自分はどう考えがあるのか? そういう起爆剤にはなりました。 「友人」と「仲間」の違いは何か? など、改めて考える人はなかなかいないと思いますが、本著を読み進めていくとそういうことを否応なく考えてしまいます。「仲間」はともかく、「友人」の考えは残念ながら著者とは違う見解になりましたが、そういう気付きができた点でも読んだ価値はありました。 タイトルにある「しがみつかない人生」も著者に反発や共感を持ちながら、いじめや労災認定された「自殺」について考えてしまいました。
2投稿日: 2016.12.04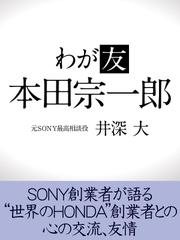
わが友 本田宗一郎
井深大
ゴマブックス
まるで、預言書みたいだ。
本著は、本田宗一郎氏が亡くなった事が契機で書かれたものでありますが、「本田宗一郎は世間から正当な評価がされていない」ことが我慢ならなかったことが、動機となっています。 著書の井深氏の主観による本田宗一郎氏の生き様や人柄について語っているので、本当に生き生きと描かれており、「ああ、本当に大好きな人」だったんだな。と、感じる作品になっています。 さて、タイトルの預言書みたいだなに関しては、井深氏と本田氏の対談が掲載されています。簡単に内容を紹介すると ・日本は国家による貿易戦略を行っていない。貿易で儲けたかったら、相手国を豊かにしないといけない。 ・通産省(当時)の保護政策は間違い。子供を保護するならいいが、大学出てからも保護するという考えがよいわけがない。保護されれば、独自性を打ち出して企業を発展させていくという考えにならない。(当時、日本のオートバイが保護政策を受けずに世界シェア40%とったのに対し、日本の自動車がまったく振るわなかったことに対しての話です。現在、プリウスというハイブリットで独自性を打ち出したトヨタを見ると・・・) ・企業に利益が出ているから、良い会社だと判断するのは間違い。土地を売って利益が出たのか、金利で儲けたのか、輸出で儲けたの、国内で利益が出たのかを区別して考えないといえない。逆に、利益が出なかったのは「企業体質が悪い」からなのか「将来のために、整理をした」からなのかを見ないといけない。目先だけで判断や批判する風潮に苦言を呈しています。現代の株価で一喜一憂する事への戒めでしょうか。 ・学校教育について、過去のことを教えるだけにとどまっている。本来「人を育てる」ということは、未来に「予想もしなかった事」が起きた時にそれに対応できる応用力を身につけさせることが、学校の先生の使命であるはずである。 ・「教えられたことだけ覚えたら成績がよい」これが、教育ならば人間をコケにしている。教えられたことを覚えるだけなら電子計算機はみんな覚えちゃうよ。学校の成績が良くても仕事ができないやつはたくさんいる。 この対談は1966年に行われたものです。今現在のことを言ってるようで、ビックリしませんか?
0投稿日: 2016.11.27
世界が憧れる日本人という生き方
マックス桐島
日本文芸社
古い本ではありますが、アメリカ人の鋭い分析には舌を巻きます
まず最初に説明を、自分が読んだ本は電子書籍版で昨年に発行されたものです。元は2012年に発売された「世界が憧れる日本人という生き方」を再編集されたものです。 著者はハリウッドでプロデューサーをしており、東日本大震災を境に仕事仲間の日本に対する評価が変わった話。そして、彼らと話をすることで、著者自身が日本の再発見をしていく様子が描かれています。 特に日本に対する評価が変わった話は、単純に日本が凄いで終わらすのではなく、「日本人とは何なのか?」という分析を彼らなりに行っていく行程が、他の同様な本と一線を越えた価値を与えてくれています。その価値というのは「彼らの主観が入った分析」です。主観が入ってますから、もちろん偏った考え方も見受けられますが、それだけに本音が感じられるところがありあます。 また、著者の仕事仲間であり友人の従兄弟が、アメリカ海軍のでの作戦中のエピソードに衝撃を受けました。オペレーショントモダチで、福島での行方不明者の捜索活動で、見知らぬ老婆がお礼の言葉とおにぎりを差し入れてくれたのです。任務とはいえ、瓦礫の山から行方不明者を捜すのは重労働であり、疲労も蓄積するでしょう。その時に、そんな時に被害者から施しを受ける。米軍の若い兵士は本当に感動したそうです。そして、自分がその老婆の立場だったら、自分の水や食料が乏しい時に、見知らぬ人に食事を分け与えることが出来るのか? 思わず自問しつつ、こういう高潔な人間でありたいと思わずにはいられませんでした。
1投稿日: 2016.10.15
翁長知事と沖縄メディア 「反日・親中」タッグの暴走
仲新城誠
産経新聞出版
日本の報道は、戦争の危機に対して意図して無視をしている
本著を読むと如何に正しい情報を入手するのが、大切であるのか。そして、自分の思い通りに事にするためには悪意をもって人を陥れようとする人間が正義の味方面をしている。そういう恐ろしさを垣間見ることができました。 現在、尖閣諸島の領海は中国の海警による領海侵犯を受けていますが、尖閣諸島の目と鼻の先にある石垣島の住民にとっては既に生活が脅かされている現状があります。例えば、日本の領海内であるにも係わらず、漁船がまともに航海することができない。そして、漁船を海上保安庁が護衛すると、「過剰防衛」だと非難する勢力が日本にいるという事実があります。 また、中国脅威論はいたずらに沖縄周辺の緊張を高める行為であり即刻やめるべきだと、元外交官の孫﨑享氏が筆頭に声を張り上げています。しかし、この考えは全くもっておかしな考えで、「中国脅威論」とは無縁におとなしく漁業を営んでいたのに、「領海侵犯」を繰り返して「緊張」を高めたのは、他ならぬ中華人民共和国側であることを完全に無視しています。 米軍が沖縄県民に負担を強いるのは許さないが、中華人民共和国が沖縄県民に負担を強いるのは我慢しろ。これが、沖縄で反米・反日運動を行っている人間の本音であります。 そして、中国脅威論の話で外してはいけないのが、尖閣諸島関連の話となります。中華人民共和国が尖閣を執拗に狙いだしたのは、尖閣を日本の国有化が原因であると思い込んでいませんか? そう思い込んでいたら、それは尖閣諸島のいざこざの原因を作ったのは、日本側だというプロパガンダにしてやられている証拠です。 さて、本のタイトルにある沖縄メディアですが、主に「琉球新報」と「沖縄タイムス」を差しています。作家の百田尚樹氏がこの2紙を潰さなきゃいかん。と、発言し、百田氏を批判する2社とその2社を擁護する言論の戦いがおきました。 著者の仲新城氏は、この言論の戦いにおいては公平なスタンスで見ていましたが、あることがきっかけで「言論を封殺」されかねない事態に陥ります。 それは、米軍基地反対デモの取材にデモ側の陣営に恫喝を受けます。反基地派がキャンプ・シュウワブ周辺で違法駐車や交通妨害で住民が迷惑しているという記事を書いたことだけで、恨まれるとは著者も思ってもみなかったそうです。 八重山日報が自衛隊や米軍に賛成とみるや「自衛隊や米軍基地を八重山へ持って行け、八重山日報が先頭に立ってキャンペーンを張れ」と言われたそうです。彼らのスローガンと明らかに矛盾した発言をする。結局のところ、反基地派が好んで使う「沖縄差別反対」とか「反戦平和」というフレーズは建前に過ぎず、本音は米軍や自衛隊を標的にした単なる反米、反日運動ではあり、日米両政府がやることに何でも反対するのが、彼らのメンタリティであります。 上記では米軍基地反対の問題点を指摘した。では、基地賛成派の保守側ではどうなのか? 実は保守側にも問題点があると指摘する。 その問題点とは、米軍基地を経済復興の道具と考えてしまっていることです。 本来、基地が必要か必要かないかは、国防を絡めて考えなくてはならないはずが、それが保守側の政治家の頭から抜け落ちている。だから、選挙における争点が、国防からそれてしまっているのが実情です。 最後に、石垣島出身の特攻隊員である、伊舎堂用久中佐の話をします。彼は沖縄戦の特攻第1号として戦死し「軍神」と呼ばれたそうです。そんな彼の顕彰碑が、2013年の終戦記念日である8月15日に地元の石垣島に建てられました。 この顕彰碑の建立の意義は2つなんだそうです。 「戦後教育の中で価値観が変わったからといって、今の価値観で特攻隊を断罪してはいけない」 「新しい空港が開港し、空前の観光ブームに浮かれて、尖閣の危機に対して何処吹く風に対しての警鐘」 特に、今の沖縄の子供に対しての平和の教育は、「戦争は絶対にしてはダメ」で終わっていて、「戦争については聞きたくもないし、考えたくもないという思考停止に陥った」子供の大量に生み出している状態になっています。これを憂いた石垣市の玉井教育長が、平和教育を見直しに関する発言をしたら、琉球新報と沖縄タイムスが社説で攻撃。教育の現場でも言論の自由が踏みにじられている現状があります。 沖縄の教職員組合から脱退した仲村氏は沖縄の平和教育は「反日教育」だと断言しています。中国共産党が国内向けに行っている反日プロパガンダと質的に同一、国民に「思考停止」させるのは独裁国家の常套手段であると。 「反日教育をやること自体が共産主義革命思想につながる。組合は教え子を革命の闘士に育成するようなことをやってきた。沖縄独立論も一緒」と仲村氏は危惧しています。
0投稿日: 2016.09.22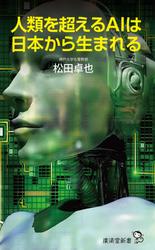
人類を超えるAIは日本から生まれる
松田卓也
廣済堂出版
人工知能は21世紀の産業革命となるのか
人工知能が人類を超える。まさに、SFさながらターミネーターのスカイネットが人類に対して宣戦布告する話を想像するかもしれませんね、この本のタイトルだと。(そういえば、スカイネットを作った会社と同名の会社が日本に存在してました。) 確かにこの本には、SFで人間に反旗を翻す(一部例外もあり)映画を紹介してますが、著者を始め人工知能の専門家は、そういうことは起こりえないと断言しています。 人工知能といっても、その知能をどこまで人間に近づけるのか? 実は人工知能の専門家によって知識、感情、人格の全部、または一部と求めるものが大きく違い、したがってアプローチも違っているのです。 人工知能はチェスに続いて囲碁の世界チャンピオンにも勝利しました。ただし、この人工知能はチェスや囲碁への特化型であります。 特化型は決められたある分野では人間の能力を超えてきましたが、それしかできません。 なので、汎用的な人工知能の開発がこれからのメインとなってきます。有名どころでは、Google、IBM、フェイスブック、マイクロソフトがインターネットを元に情報を集めて人工知能に資金と技術を結集して、本気を出してきました。 特にIBMは、渡辺謙がCMで会話している「ワトソン」が有名ではありますが、これとは別に人間の大脳新皮質の再現を目差しているジェフ・ホーキンスと共同開発を始めています。 ちなみに、人工知能の開発者のなかには、「宇宙の神秘を解明」が目的で手段として人工知能を生み出そうとしている人がいます。先のジェフ・ホーキンスやGoogleに会社を買収されたデミス・ハサビスがそうです。 さてさて、日本での人工知能の取り組みはどうなっているのか? 日本は過去、国家プロジェクトで第5世代コンピューターというものがありました。「○○の場合は、○○する」というルールを積み上げていけば、人工知能ができるのではないか? そういう考えで1980年代に研究されていましたが、このプロジェクトは失敗します。もっとも、同じ「ルール型人工知能」を研究していた外国勢も失敗してましたが。このプロジェクトの本当の失敗は、人間の知能を過小評価していたからだと言われています。 では、21世紀の日本では、どのようなアプローチで人工知能を開発されているのか? 「全脳アーキテクチャ勉強会」というグループで汎用人工知能の開発が始められています。人間の脳の機能は、実はいろいろな部位からなりたっています。大脳、小脳、海馬、基底核、扁桃角などです。これらの同等の人工脳機械学習器を作って組み合わせれば、人間の脳と同等かそれ以上の人工知能を作り上げることができるという考えをもとに、全脳アーキテクチャ勉強会は活動を行っています。 冒頭では、人工知能が人類に反旗を翻すとは専門家は考えてもいないといいました。 でも、そういう考えは蔓延しています。例えば、起業家のイーロン・マスクや物理学者のスティーブン・ホーキングは人工知能における危険性を訴えています。著者はこれを「ハリウッド的世界観」と切って捨ててます。 なぜ、ここまで温度差は大きいのか? それは、ハリウッドに出て来る人工知能を作り上げることがほぼ不可能なことを、専門家は知ってるからにほかなりません。 ただ、人工知能が発達すると、別の意味での危険性は存在します。 まず、人間は仕事を奪われます。下手すると芸術家も仕事を奪われます。ただこれは、ギリシャ・ローマ時代の再来になると予想している人もいます。いわゆるギリシャ・ローマ時代は労働を奴隷が行っていました。この奴隷の部分を人工知能が担うことで、人間は遊んで暮らせる世界が来るという予想です。 もう一つの危険が、格差の拡大です。いわゆる、人工知能を手に入れた国家はより発展をしていき、人工知能を持たざる国は支配されていう世界です。 これらは、どちらも人工知能がもたらす問題ではなく、人間側の問題ではありますが。 人工知能は21世紀の産業革命になり得るでしょう。なぜなら、生活が想像絶するくらいに一変するからです。 産業革命に乗り遅れた国は、世界の主流から取り残されました。この流れに乗れなければ、日本も今の世界的立場でいられる保証はありません。 そして、日本はこれから少子化の影響で人口は減っていくでしょう。でも、これはある意味チャンスなのかもしれません、少ない人口で社会を回るように社会変えていくのに人工知能は手段の一つとして有用なのですから。 世界は2030年を目標にプロジェクトを走りだしています。日本がこれに追いつき追い越す為の切り札が、齊藤元章氏の人工知能プロセッサ「NSPU」です。最後の章は著者と齊藤氏対談が載せてあります。
0投稿日: 2016.08.21
非言語表現の威力 パフォーマンス学実践講義
佐藤綾子
講談社現代新書
コミュニケーションの効果を狙って、あえて間違った文法を使うのもあり!
コミュニケーションにおいて、言葉だけでなく表情や仕草といった非言語の情報を受け取り判断するといった話はいろいろな書籍が出ており、根幹の部分では本著には目新しいものはありません。 とはいっても、欧米で確立した学問が、言語も仕草や文化が異なる日本人にそのまま当てはめていいのか? そういう疑問をもった方には一読する価値はあります。なぜなら日本人を相手にした追試を行われた上で、執筆されているからです。 また、オバマ大統領や安倍首相の演説やSTAP細胞で一躍有名になった小保方氏の謝罪記者会見の分析を行っています。特に、阿部首相は第1次と第2次の比較もしており科学的に分析しています 1次とくらべて2次では格段に身振り手振りや表情の生かし方に磨きがかかており、また言語のほうも「より分かりやすい」言葉と文の構成となっています。なぜなら、コミュニケーションとは、相手に理解してもらうことが大前提なのですから。 この辺は、「同じ内容」の話をする上で「相手」によって「単語」や箇条書きのように話す必要が出てくるということです。 特に最近は「カタカナ」の一言で片付ける風潮がありますので、気をつける必要がありますね。 さて、相手に納得させるには「分かりやすい言葉を使って」理解されることが大事なのですが、もう一つ大事なのが「相手の感情を逆なでない」ことも大切だと説いてます。 相手の感情を損ねないなんて当たり前の話ではないか! と、怪訝に思う人もいるでしょうが、これは謝罪をする場面で多くの人がやってしまっている過ちではないでしょうか。 それは、謝罪の言葉を発したあと申し開き(又は弁明)を行ってしまうことです。 これは、かなりの方は身に覚えがあるのではないでしょうか。少なくとも私は、自分のミスの報告でこの手の失敗をやった覚えがあります。 本著では小保方氏の謝罪を題材にして説明していますが、「謝罪の言葉のあと、直ぐに申し開きを行う」ことは、単純に「言い訳」にしか聞こえないということです。 「申し開き」は、あくまで先方が「謝罪」を受け入れてから行うべきであると、著者は語っています。 ここで、重要なのは「申し開き」を行うことが問題ではなく、「自分は悪くない」という態度だと思われ、「謝罪をしていない」と判断されてしまいます。 また、「怒りの地雷」を避けるために、あえて間違った文法を使うことも推奨されています。 例えば緊急の仕事を依頼された場合。 「分かりました。しかし、この仕事の後に取りかかります。」 「分かりました。そういうわけで、この仕事の後に取りかかります。」 どちらも、緊急の仕事を直ぐに取りかからないのは同じですが、「しかし」を使った正しい文章の方が反感を持たれるそうです。 なぜなら、「しかし」「だけど」「ただ」といった言葉は否定されたと、判断されるからだそうです。 これは本当に有効なのか、変な日本語と突っ込まれないか、試すチャンスが訪れないのが、目下の悩みではあります。
0投稿日: 2016.06.04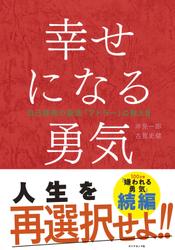
幸せになる勇気
岸見一郎,古賀史健
ダイヤモンド社
アドラー心理学は宗教なのか?
前著「嫌われる勇気」から3年後の話です。 青年が図書司書を辞め、教師としてアドラーの教えを貫こうとしたが、挫折をしました。 やはり、アドラーの教えは間違いであることを認めさせるために、再び青年が哲人の元に現れたところから物語が始まります。 嫌われる勇気」ではアドラー心理学の神髄を語り 「幸せになる勇気」では、アドラー心理学の実践する上での苦難を語っています。 「アドラー心理学ほど、誤解が容易で、理解が難しい思想はない」 この一言につきます。 青年は「褒めるな」「叱るな」を実践したら、子供達に嘗められて教室が混沌としてしまった現状を嘆きます。 哲人は「子供のことをちゃんと見ていましたか?」と尋ねます。 この場でいうちゃんととは、「一人の人間として対等に、そして尊敬をして信頼していたか?」です。 人間関係においての「信用」と「信頼」の違い。 「信用」とは条件をつけて相手を信じること。 「信頼」とは条件なしで相手を信じること。 『相手を条件なしで信じることができなければ、相手は貴方を信じませんよ。』 ここで、ある漫画が頭によぎりました。 松井優征氏の「暗殺教室」です。 「ある日突然、謎の超生物がある学園の落ちこぼれ教室の担任になった。しかも、生徒達はこの担任を暗殺しないといけない」という突拍子もない設定ではありますが、ストーリーはよくできています。 青年は、子供達を愚劣な愚かな存在として扱っていますが、暗殺教室の担任は生徒とひとくくりにせず、子供達一人一人対等に接していきます。 この担任は子供達から信頼を勝ち得ますが、子供達は「大好きなこの担任を、自分たちは殺さないといけないのか?」と・・・・ 苦悶しながら、自分たちで解答を見つけていく。 作品自体は子供向けなのですが、根底に流れている問題は果てしなく深いので一読されることをお奨めします。 さて、アドラー心理学は全ての悩みは対人関係が原因であると考えています。 対人関係の問題を解決するには、如何にして「人から愛されるか」、「愛されるための技術」を磨けばいいのか? 否、必要なのは愛することが大切だとアドラーは説いています。 しかも、自分にとって都合の相手ではなく、ただ全ての対象を愛することが大切だと。 アドラーは「恋に落ちる」現象をだいたんに否定しました。前巻の「嫌われる勇気」では「トラウマ」を否定してましたが、今度は「恋に落ちる」ことの否定です。 大好きで大好きでしょうがない相手といざ恋人になったら、ぞんざいになるという話は珍しくない。 これは、「相手を征服して、自分の思いのままにしたい」衝動を恋だと勘違いしていると言い切ってます。 「怒り」のみならず「愛」も、自分の意思で出し入れできるものだと言えば、反感をかいアドラーの元を離れる人がでるのも納得です。 ちなみに、アドラーの元へ訪れる人の大半が、恋愛相談だったとか。 「先生、どうすればあの人から愛されるようになれますか?」 「愛されようとは思わず、貴方が愛しなさい」 アチャー、「まさに、話がかみ合わない」状態です。 ユングやフロイトとの心理学とここまで違うのは、人は真の意味で相手をコントロールすることが出来ないからです。コントロール出来るのは、自分のみ。 今、自分が出来ることは何なのか? これが出発点なのです。 アドラー心理学は机上の学問でなく、今利用可能のものを使って実践していくものなのです。 信頼されたかったら、自分から信頼する。愛されたかったら、自分から愛する。しかし、前著の「嫌われる勇気」のテーマであったように迎合する気持ちがあったら駄目です。 相手に気に入られれば、相手は「私」を信頼してくれるだろう、愛してくれるだろうと期待をしているのですから。 「信頼」や「愛」は見返りを求めない、無償の行為でなければならない。 アドラー心理学と宗教の違いは、決して弟子をとらず、自らキリストやブッタ如く、目の前にいる人に無償の愛を与えることであろうか。
0投稿日: 2016.05.07
仕事のスピード・質が劇的に上がる すごいメモ。
小西利行
かんき出版
メモは腐るもの、そして未来の自分は今の自分よりモノを知らないと思え。
メモをとっても、後でそのメモを読んでみてもチンプンカンプン。そんな経験ありませんか? なぜ、そんなことが起きるのか? メモを書いてる時は記憶が鮮明なため、記憶を補助する程度の内容でも要は足ります。 しかし、未来の自分は記憶が曖昧であり抜け落ちているため、記憶の補助を目的としたメモを見ても内容が理解できないといった事態に陥ります。 では? どうやってメモを書けば、そんなことにならないのか? 目的意識とテクニックを本書で紹介されています。 巻末の小説家の伊坂幸太郎氏とのメモ書き対談も、なかなか楽しく読ませて頂けました。
1投稿日: 2016.05.01
レビューネーム未設定さんのレビュー
いいね!された数47
