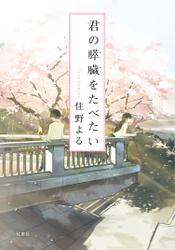
君の膵臓をたべたい
住野よる
双葉文庫
人生に偶然はない、それは日々の自分の判断の結果
不治の病にかかり、余命1年となった時、人はどう生きるか? これをテーマにした物語です。 膵臓の病気になり家族以外には親しい人には誰にも打ち明けず、死ぬ瞬間まで日常を守っていきたいと少女が、ふいに日記をほとんで接点のないクラスメイトの男子に見られてから、物語が動き出します。 ちなみに、その日記の名前は「共病文庫」。闘病でなく共病なのは「病と闘う」のではなく「病と一緒に生きていく」こと選んだからです。 主人公からは、病気で死ぬことが確定したことで、改めて人生設計をするヒロインの気丈な姿をみて、自分とは正反対な生き方に尊敬の念を抱いていくのです。 ヒロインの方は、親友や友達には病気を秘密にして日常を謳歌しつつ、好きでもない男の子とイケナイことをするという欲望に主人公を巻き込んでいきます。 クラスメイト達は、今まで接点のなかったこの二人が急接近している様子を訝しみます。 特にヒロインの親友は、主人公に対して敵意をむき出しにしていくのですが、彼女は要所要所で物語にアクセント付けていってくれます。 主人公とヒロインは、腹の内を余すこと無く話せる仲になっていくのですが、そんなおりヒロインは亡くなります。 主人公は、ヒロインが自分に対して本当はどう思っていたのか気になり出します。そこで、「共病文庫」の存在を思い出します。 ヒロインは家族に、「共病文庫」の存在を知ってるクラスメイトに渡すよう遺言を残しているのでした。 この作品に第2部があるとしたら、「共病文庫」を読みながら過去を振り返えるところでしょう。 そこには、主人公が知らないヒロインの姿がありました。 なぜ、ヒロインはあの時あんな行動をとっていたのか? なぜ、ヒロインは主人公に心を許したのか? 性格はまさしく正反対の二人なのだけども、似たもの同士の二人。 そして、本の題名である「君の膵臓をたべたい」は、主人公がヒロインへ送った言葉であり、ヒロインが主人公へ送った言葉でもあります。送ったタイミングは別々ではありましたが、その言葉に込めた気持ちは・・・・ 読後は心が洗われた気持ちになりました。理由を考えると、人は必ず死ぬ。 これを大前提に考えれば、この作品はまさしくハッピーエンドだからだと気付かされました。
0投稿日: 2017.11.05
データを正しく見るための数学的思考 数学の言葉で世界を見る
ジョーダン・エレンバーグ,松浦俊輔
日経BP
目に見えるモノだけが真実ではありません。
ジョーダン・エレンバーグ著の「データを正しく見るための数学的思考」を読みました。世の中に出回っている数字やデータは加工されたものです。そこには、集計者のなんらかの意図が含まれている場合があります。したがって、生データが同じでも、集計者が異なると集計結果や分析結果が真逆いなる場合があります。でも、それらはどちらかが間違っているとはいえないのです。 どちらも間違っていないのなら、自分にとって都合が良い方を選ぶというのも正しい思考方法でしょう。しかし、待ってください。自分にとって都合がいいものが、本当に継ごうがよいのか? そう、思い込まされているのではないか? この時の使用する思考が、数学的思考です。 本著のプロローグでは、学生が教師に対して、「数学がなんの役に立つというのです?」と疑問を投げかけます。 数学が役に立つ具体例が、この本に詰め込まれています。 実例の中で自分が気に入ったのは、確実に儲かる宝くじの話と、世論は存在しない話でした。(残念ながら、日本の宝くじには当てはまりませんが)
0投稿日: 2017.09.25
欧米の侵略を日本だけが撃破した
ヘンリー・S・ストークス
悟空出版
奇蹟とは日本列島という環境そのもの。
東京裁判を信じ切っていて、第二次大戦後は日本が一方的に「悪い国」と疑っていなかった方が書かれた本です。 かなりご高齢の方で、三島由紀夫氏や映画の「海賊と呼ばれた男」のモデルになった、出光佐三氏ともされており、かなりビックリしました。 さて、この本の出版の目的は2点あり、あらましに掲げられています。 一つは、第二次世界大戦における日本が世界に与えた意味について。 一つは、反日の源である「従軍慰安婦問題」や「南京大虐殺」はプロパガンダだということ。 この二つを証明するために、日本という国の成り立ちや中国(中華人民共和国にあらず)と朝鮮の国の成り立ちから、説明がなされています。 中国では基本、滅ぼし滅ぼされる歴史であるため、民族を超えて手を結ぶには「外敵」の存在が不可欠なことと、基本外国人に支配されることになれていることです。秦の始皇帝から淸、そして中華人民共和国の支配層はみんな外国人であるのですが、日本では「中国」と片付けてしまい、特に日本は建国から現在まで「同一の国」であることから、「中国」も同じだと考えてしまい、本質から目を反らしてしまっている問題点があります。 また、「日本最古の文化」は縄文時代だと思われてきましたが、縄文時代よりも前に土器や磨製石器が出土の話や、青森では15mの建造物が発見された話が振られており、新発見の昂揚が伝わってきました。 また、「道徳」と「モラル」の違いについては目から鱗が落ちました。「人に迷惑をかけても、法令遵守であれば、それはモラルのある人」という事実に衝撃を受けました。この事実は、「モラル」を持っていても「道徳」がない社会は荒んだ社会になるということです。前述の出光佐三氏との対談で「モラル」と「道徳」の違いを語っておられます。 出光氏は、哲学者の鈴木大拙氏より「モラルは支配者が制定した規則や法律であり、道徳は皆が上手くやっていくための決まり事」といったことを教わったことです。端的にいうと、「モラルはルールさえ守っていれば他人の迷惑まで言及しない。道徳は人に迷惑をかけないための決まり事。根本的な違い」があるのです。この道徳とモラルが違いは、まさに日本の皇室と世界の征服者の違いでもあるのです。そして、この違いこそが日本建国から21世紀の現在まで現存している理由でもあるのです。 神道にも触れられています。これからは神道が世界の信仰となる。と、予言めいた書き出しで始まるのですが、ちゃんと根拠を示して説明されています。 従来、神道はアニミズムという原始的な宗教に分類されてきました。アニミズムは「高等宗教」とされる「英知を持つ人格神である創造主の解き明かす世界観」と比べるとレベルの低い教えだとされてきましたが、人格神の説く教義は人間が頭で考えたような諭しさがあり、大自然が教えてくれるような叡智が感じられない。と、訴えています。 敬虔なクリスチャンの一人である、サンマリノ共和国のマンリオ・カデロ駐日特命全権大使がこう語ったそうです。 「大自然こそが、神ですよ」 まあ、この人もかなりの親日家ではありますが、大の皇室好きでありますが、本音だと思われます。 キリスト教では創造主が、人間のために自然や他の動植物を創造したことになっているが果たしてそうだろうか? 神道では神々や自然でさえ大宇宙の中で生かされている。これは、古事記の世界創世の中で神々が生まれていく姿を描いており、それは物理学者の間で定説になっている「ビック・バン理論」と近似していることに、著者は驚いています。 「古代日本人はどうやって、このような宇宙創成の物語を思い描くことができたのだろうか。想像力によるのか、それとも霊感によるものだったのか」 と、感慨に耽っていますが、本当にどうやってご先祖様はこれらのことを思いついたのでしょうね。
0投稿日: 2017.09.10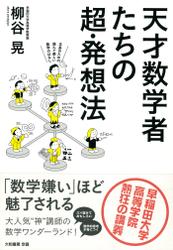
天才数学者たちの超・発想法
柳谷晃
大和書房
学問とは違う、数学の顔
タイトルを見て皆さんは、どのように感じましたか。 世間一般では学問である数学は一部の天才達が造りあげてきて、一般人には縁がないもの・・・・・と、思ってないでしょうか。 本著では、この考え方を真っ向から否定しており、現在、そのような考えが蔓延しているのは数学者の怠慢だと手厳しく批判しています。 また、数学の一般への応用について「機械を使えば簡単」という考えは、現代人のうぬぼれとだと、数学者以外に対して手厳しくもあります。 この本は、数学の歴史を紹介していますが、生活にどのように役にたってきたかに焦点を当てています。 「0」を発明したのはインド人ではあるが、それより遙か昔、バビロニア人は「ゼロの概念」を使って計算をしていた。という話を、小学生向けの講演で行うと、「混乱する」とクレームを入れる親。子供が理解できればいいのだからと思っていると、同じ教育関係者からもクレームが入るそうです。大丈夫か日本? 小学生向けの授業は「簡単」だから行っているのではなく、「学問の基本」を小学生に教えている事実に気付いていない人が多すぎるとのこと。 このことで思い出したのが、「小学生がかけ算を使って回答した問題に、教師が「×」に対して「これなに?」とコメントをつけて不正解」した話です。 この投稿に対して閲覧者のほとんどが教師を批判していましたが、誰も「テストの目的が足し算を理解を計るもの」ではないのか?と、誰も言及していないことに恐怖を覚えました。 テストとは行った授業に対してのフィードバックの一つです。いくら正解だからといって、答えを導く過程が授業となんの関連性もなければ、授業を理解できていないと見なして不正解にしたことは批判される謂われはないと思うのですが。 ネットの声を後押しされて、学校にクレームを入れる親御さんがいたとしたら、他人事ながら恐怖を感じてしまいました。 話を元に戻して、論理思考についても語られていました。「数学の論理」と「スピーチの論理」は、全くの別物であるから、数学を一生懸命にやっても、論理的に話せるようにはならないそうです。「数学を勉強すれば、論理的思考が身につく」という発想は短絡的なのだそうで、皆様気をつけましょう。 本著では、「歴代の数学者達が、頭を抱えて込む発言だ」と表現をしており、それはあんまりだと読んだ瞬間はそう感じましたが。よく考えれば、「論理的思考」と「相手に理解できるように話す」技術は別物ですね。 この本を読んで、数学の歴史を学びつつ著者のボケ・ツッコミを堪能していくと、今まであった数学のイメージが粉々になっていく感が、読んでいて楽しかったです。
0投稿日: 2017.08.27
7日間勉強法
鈴木秀明
ダイヤモンド社
試験対策のテクニックを学ぶ本です。
試験や資格取得の為に特化した勉強法です。著者である鈴木秀明氏が、自身の受験勉強と趣味と化している500資格の勉強方法を1冊にまとめたものとなっています。 著者自身が言っていますが、思考力を高めるための勉強法ではないので、ご注意を(笑) 社会人であれば、試験勉強をとる時間をとれないことを考えれば、戦略としてテクニックを磨くことも大事なことだと思うのです。
0投稿日: 2017.08.12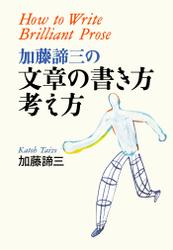
加藤諦三の文章の書き方・考え方
加藤諦三
PHP研究所
精神論的なアプローチで掘り下げた一冊
本著は技術的な話は皆無です。著者は心理学者なので、ある意味根性論に近いものを感じるでしょう。しかし、人間の本質に基づく観点から文章を書くために必要なものをあげますので、役に立つと思います。少なくても、文章が書けなくなった人にとっては、反省点を見つかるかと思います。 こういう性格の本ですので、誰もが読んで良かったと思えない本かもしれませんが、加藤諦三さんの本が好きならば、どんな風に文書を書いてるか感じてみたい方には手にとってもらいたいです。
0投稿日: 2017.06.17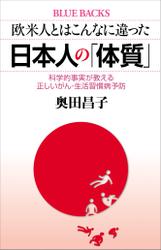
欧米人とはこんなに違った 日本人の「体質」 科学的事実が教える正しいがん・生活習慣病予防
奥田昌子
ブルーバックス
悪玉コレステロールと善玉コレステロールは同一人物?
タイトルの通りに、この本を手に取ったら「衝撃的」な事実が結構待ち受けていると思います。 コレステロールの種類は1種類だけ。じゃあ、善玉と悪玉の違いはなに? 欧米人と日本人とは体質が異なるから、欧米人の体によいものが日本人に合うとは限らない。特に、アメリカは人種によって病気の原因や仕組みが違うことは常識ではありますが、日本人がどこまでそこを理解しているか? よく、海外の臨床試験に合格したモノを、早く日本でも使えるようにしろという意見が聞かれますが、その考え方は非常に危険だと認識できるようになります。 また、ガンが増えた理由の一番の要因は寿命が延びたから。でも、日本人の死因の原因ががんなのは、実はがんが増えたからでない。統計のトリックもあかされています。 一つ一つの情報には、嘘がなくても。その情報を元にして行動することが正しいことなのかは別物だと認識させてくれた、良書です。
0投稿日: 2017.06.03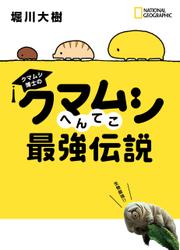
クマムシ博士の クマムシへんてこ最強伝説
堀川大樹
日経ナショナル ジオグラフィック
飼育日記ならぬ介護日記なのです。
クマムシの愛すべき、エクストリーム・ポイント 1.凍ったままでも30年間生きられる。 2.乾くと宇宙空間の真空や超低温にも耐えれる。 3.転ぶと自力で起き上がれない。 4.ヨコズナクマムシはメスしかいないので、交尾をせずに子供を残せる。 5.培地の上で立ち上がる。すると、顕微鏡越しに目が合う。 6.高線量の放射線を浴びても絶えられる。 目次の前に、上のことを書いてます、おわり。 ではなく、今回のメインは観察日記ならぬ、介護日記がメインとなっています。 真面目な話、観察を続けるために環境整えるのに悪戦苦闘をしており、「3.転ぶと自力で起き上がれない」ことより、餌を食べることが出来なくなり、衰弱して死んでしまうのです。そんな介護日記の大変さが「32日目 悪夢」です。 「クマムシの飼育で一番大切なこと。それは、愛である。(中略)ついに愛の供給が限界に来てしまった。」 そんなことを呟いた著者は夢を見ます。体が溶けた強大なクマムシが部屋の壁や天井を歩いており、そのクマムシ達が顔の上にバタバタと落ちてくる夢を。 スプラッタですよー。精神的に疲れ、仕事に追い立てられてるとそういう夢見ますよねー。でも、この本ではそんな様子を挿絵にして載せてますが、キャラクターが可愛いので恐怖が伝わりませんよ、これ(笑) 可愛いといえば、クマムシのぬいぐるみも存在しており、お台場の未来科学館で売ってました。 「クマムシ ぬいぐるみ クロノス」検索すると某ラジオ番組がヒットしますが、そこでぬいぐるみの可愛さと大きさが分かります。 さて、飼育日記の最終日が「グッバイ人類」となかなか凄いタイトルであります。クマムシの数が増えたことで面倒をみきれないことから、乾燥させて眠らせます。これを乾眠状態というそうですが、この状態のクマムシは呼吸も代謝も無い状態、つまり老化をしないそうです。じゃあ、乾眠状態のクマムシは不老長寿なのか?とおもいきや長くても数年で死んでしまうそうです。その原因は酸素。体が酸化すると体が損傷していくそうです。 乾眠状態のクマムシが半永久的に生き続けていられる環境は、宇宙空間。そこは酸素がなく低温でないから、著者の手によって宇宙空間に放り出され、宇宙空間をさ迷い水のあふれる惑星で、再び目を覚ますクマムシ。その時は地球が消滅して人類が滅んだ後のはなしかもしれない。 なんとも、ロマンチックに日記を終わらせる著者であった。 さて、クマムシが最強であることがご理解できるよう懇切丁寧に説明されています。しかし、クマムシ最強説に異議を唱える人達もいたりします。その異議を唱えている微生物学者の一人、海洋研究開発機構の高井研博士の紹介をしています。高井博士は極限環境微生物こそ地上最強の生物であると提唱されているそうで、著書の中でクマムシを名指しで否定してたりします。 しかし、我らが著者は高井博士が所属する海洋研究開発機構の「しんかい6500」によって、海底に沈められるかもしれない危険性を覚悟しての反論を行っています。 『それだけではない。クマムシの愛らしいフォルムや歩行するさまは、見る者の心を打つ。クマムシは「かわいい生物ランキング」で常にトップに君臨しているのだ(筆者調べ)。それに対して、申し訳ないが細菌は、お世辞にもかわいいとは思えない(筆者の主観)。』 なんて記述もあったりしますから。これは、しんかい6500で海底に沈められるかも。 著者に向かって合掌。
0投稿日: 2017.05.05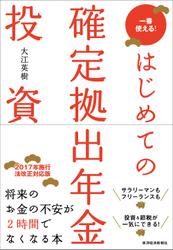
はじめての確定拠出年金投資
大江英樹
東洋経済新報社
入門編としてパーフェクトな本
本書は大まかに3つのことを教えてくれてます。 1つ、確定拠出年金とは何か? そのメリット。 1つ、確定拠出年金を利用するにはどうすれば良いのか? 1つ、確定拠出年金を運用するための考え方。 確定拠出年金と言われてピンと来ない人の方が多いかもしれません。 かくゆう私も、勤めている会社の退職金がこの確定拠出年金に切り替わって、その存在を知った口であります。 乱暴な説明では、「退職金の元本は会社で出すが、あとは社員が運用してお金増やしてね。」 という制度です。 本当に乱暴な言い方ですが、税金の控除と勤めている会社が倒産しても退職金が無くならないのは大きなメリットというでしょう。 特に資産の運営において、税金の控除に関しては最強だと本著では言い切っています。 企業の退職制度なら自営業の俺には関係ないじゃんと思われた方、ご安心下さい。企業型の他にも個人型というものがありますので利用できます。 自営業の場合は月に6万8千円が上限で積み立てる事ができ、年額81万6千円が控除対象となり、20万近くが還ってくる計算となります。 次に運用に関してですが、根本的な考え方を示してくれており参考になります。 「多くの人は手っ取り早く、自分が購入する銘柄をどれにしようかということから考えはじめます。でも、実はこれが間違いなのです。」 では、何を最初に考えないといけないのか? それは自分の「リスク許容度」だと言います。 このリスク許容度と資産の配分を得てはじめて購入する銘柄を選ぶという手順となります。 ちなみにこの資産の配分とは、「貯蓄」「国債」「株式」への資産の振り分けです。 ここ資産運用配分(アセット・アロケーション)が運用成績の9割を決めるのだそうです。 また、この資産配分は「確定拠出年金」無いだけで考えてはいけないそうです。例えば貯金や土地を持っていれば、確定拠出年金では攻め行くべきであると。理由はいくつかありますが、大きく儲けても税金が掛からないというのが一番の理由です。 さて、この制度の要は運用もさることながら「お金を受け取る」ことも非常に大切です。 「一時金」として受け取ると退職所得扱いになって税制上得をしますが、年金のように分割して受け取るとことも可能だそうです。この場合は運営時の運営益に税金が掛からないので得ではありますが、振り込み時にかかる手数料を忘れないように注意喚起しています。 なんにせよ、資産運用の手段を多く持つことは悪い事ではないと思います。自分は企業型の確定拠出年金を運用してるので、個人型は利用出来ませんが、こんなものがあるんだと知って貰えれば僥倖です。
1投稿日: 2017.03.25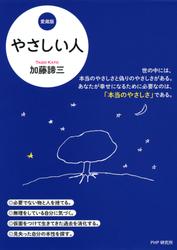
やさしい人(愛蔵版)
加藤諦三
PHP研究所
本の後半は、「人類愛を口にする人」が、なぜ残酷な理由を述べています。
加藤諦三氏を知ったのは、建設業の業界紙にコラムを読んだ時の話でした。 自分はそれまで、言動は嘘をつくけれども行動は嘘はつかない。と、盲目的に信じていました。 本書でも書かれていますが、「犯罪を犯した少年」を扱った記事では、「あんな優しい子がこんなことをするなんて・・・」 犯罪を犯す前の「少年の優しさ」は、他人の為だったのか、それとも周囲に受け入れて貰うために自分を偽って優しく振る舞っていたのか。 同じ行動でも、「心を見れば」違いが明らかになる。 心を偽っている人、自分を受け入れられない人は、けして「やさしい人」にはなれない。 アンデルセン童話に出てくるヒナギクは、人間の目からみるとキレイな花壇からあぶれて、雑草の中に埋もれている存在。 でも、ヒナギクは太陽の光を浴びて幸せなのです。ヒバリの歌声を聞けて幸せなのです。 ヒナギクは他の花と比べて色艶やかでないことを知ってる。ヒナギクのように歌えないし、飛べもしないことも知ってる。にもかかわらず、ヒナギクは自分に価値があることを知っている。 ヒナギクは自分に価値があることを知ってるから、他者の優れた部分を素直に褒めることができる。他者を受け入れることができる。 だから、ヒバリは他の花のところにいかないで、ヒナギクがいる場所で歌を歌う。 人が本当の幸せになるためには、ヒナギクのように生きて、本当のやさしさを手に入れなければならない。
0投稿日: 2017.02.04
レビューネーム未設定さんのレビュー
いいね!された数47
