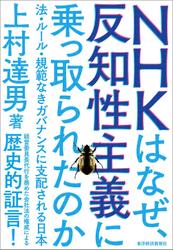
NHKはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか―法・ルール・規範なきガバナンスに支配される日本
上村達男
東洋経済新報社
後半の法人論が熱い
いま日本で目立つ独善的組織運営の1つの象徴であるNHKで、経営委員として対峙し翻弄されたガバナンス専門家からの渾身の発言。 現会長の件は最初の会見で罷免すべきだったに尽きる。 組織運営上の同様の問題は日銀や内閣法制局などにも見受けられるが、これらは独立・牽制システムを軽視して無化する点で、戦時経済と同じであると説く。それはそうなのだが、それを「良いことだ」と信じ込んでいる人に話が通じないのが危うさの根本のように私は思う。 このようなことを踏まえて後半に展開される法人論が、熱く興味深かった。
3投稿日: 2015.11.04
世界はこのままイスラーム化するのか
中田考,島田裕巳
幻冬舎新書
誤解や無理解の厚い皮を、ぼちぼち剥いていく試み
前に出た内田樹氏と中田氏の対談本では踏み込まれなかったイスラームの成り立ちや特質を、様々な宗教・信仰との比較・対照を通して浮き彫りにしていく一冊。クルアーンに繰り返し出てくる一神教の本質が次第に見えてきたような気がして、とても面白かった。
1投稿日: 2015.10.20
戦前回帰 「大日本病」の再発
山崎雅弘
学研
人々の善意に食い込む巧みな言説の解剖
1945年までのほんの10年ほど、この国の人々を形式的な愛国主義に酔わせ、史上初の破滅を招いた思想。それが国家神道であった。悠久の伝統を装い、面白くない世界情勢にベールを掛け孤立へと導いた傲慢さの蔓延は、まさにいま私自身が感じている気味悪さと重なる。また、現在に蘇ったそれの背景にある保身の構造解析が見事でした。 戦後に発行された文部省の民主主義テキストのところだけ、ホッとできました。
3投稿日: 2015.10.17
医療の限界(新潮新書)
小松秀樹
新潮新書
第一線で考え続けている外科医の貴重な提言
医療過誤を過度に問うことは巡り巡って社会全体の不利益になる、システムこそ問うべし、という2015年現在では受け止めやすい内容を8年前に問うた本。引き合いに出された警察・検察の方は…困った話が今もなお。 医療改革で引き合いに出されがちなアメリカ医療自由主義の成り立ちと特殊性に関する考察が興味深かった。当然のことながら、医療制度にもひとつの理想型があるわけでは無い。
2投稿日: 2015.10.14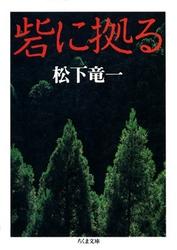
砦に拠る
松下竜一
ちくま文庫
いろいろな意味で、往年の物語
筑後川の下筌・松原ダム建設にあたり室原知幸氏が起こした阻止闘争の聞き書き記録。運動は1958年から13年に亘り、本書の初刊は1977年で、様々なものごとが洗練されていない時代(ネット上の外野の騒ぎなんて無い時代)の剥き出しのぶつかり合いがすごい。 封建的地主と国家に挟まれた地元農民、大衆から遊離した党派的左翼との距離感、国家側の矢面に立った建設所長らの逡巡などの様々な構図の中で、引くに引けないものが渦巻く様がつらかった。
1投稿日: 2015.09.22
慢性頭痛とサヨナラする本
岩間良充
講談社+α文庫
いかにも効きそうなストレッチの数々
著者の鍼灸整骨院で確かめられてきた、頭痛の原因になる筋肉の解説と、頭痛のタイプ・場所ごとの予防ストレッチ運動の数々の図解。お薬を頭から否定するのでなく、有効な別解をやって見せている感覚に好感が持てます。 これまでに見たことのない、いかにも効きそうな体操をぼちぼち試してみたい。ただ、体操の参考にするには印刷書籍の方が扱いやすいかも知れません。
3投稿日: 2015.09.18
反知性主義―アメリカが生んだ「熱病」の正体―(新潮選書)
森本あんり
新潮選書
切ないほどの変節の歴史
反知性主義という言葉は、元来は新天地・アメリカにおける教会の権威に対し本来の福音を説く相当の覚悟の要る立場であった。それが次第に布教パフォーマンスになり、やがて巡回セールスのモデルにさえなっていく経緯が克明に語られる。ここから現状の日本型政治利用へは、一直線ではないが地続きだと感じた。
3投稿日: 2015.09.16
浜村渚の計算ノート 6さつめ パピルスよ、永遠に
青柳碧人
講談社文庫
レビューじゃなくてすみません。コメントです。
「試し読み」機能で目次を見たところ、電子版の6さつめ(1)〜(4)を合本したものです。付録も前に載っていたものです。 加筆修正等されているかも知れませんが、新しいお話と間違えないようにご注意下さい。 さて、 新展開、特に後半にかけて面白かったです。エジプト数学の内容は初耳続きでした。
6投稿日: 2015.08.14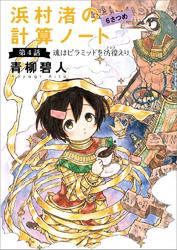
浜村渚の計算ノート 6さつめの第4話 魂はピラミッドを彷徨えり
青柳碧人
講談社
ずっと読み継いでます
今回のテーマはエジプト数学。 通分しない分数や、薄さの単位など、知らないことが多くて久々にプラスアルファの面白さがありました。
1投稿日: 2015.08.09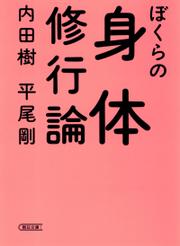
ぼくらの身体修行論
内田樹,平尾剛
朝日文庫
あたり前だけど、効率的と科学的は別物です
8年前の対談の増補版で、いま読んでも新しい話に、最新の知見のおまけ付き。 一時に集中的に鍛えるより、正しく時間をかけることに技を進化させる秘訣がある。それは効率的にしようと云うとき捨象し方向性を違えることがあるためで、その典型が特定の箇所に負荷をかける練習をしてしまう筋トレ。受験勉強や記録会のような短期的なパフォーマンスにも一定の意味はあるにしても、それが全てだと思い込むのはもったいないですね。
1投稿日: 2015.08.08
パドラッパさんのレビュー
いいね!された数200
