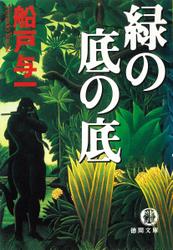
緑の底の底
船戸与一
徳間文庫
初期の船戸氏作品で初々しさを感じる中編小説2作品 後半の『メビウスの時の刻』が面白い。
船戸氏の初期の作品(2作)で、それなりに面白かった。『緑の底の底』:人間のむき出しの欲望がテーマ、登場人物の大部分が亡くなるというストーリーは、その後の船戸作品に流れる“滅びの文学”のはしりか。『メビウスの時の刻(1989年)』:私としてはこちらの小説の方が面白かった。登場人物の各々が、段落毎に一人称でストーリーを綴っていく中で、時間の異なる段落が含まれており、最終段になって順次語られた段落が、実は前後して繋がることになる。貫井徳郎氏の『慟哭(1993年)』を彷彿とさせたが・・・船戸氏の作品の方が早い。
0投稿日: 2014.09.17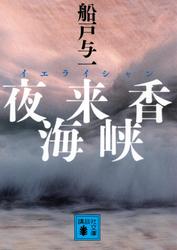
夜来香海峡
船戸与一
講談社文庫
船戸氏作品にしては、重厚なテーマに欠けるが、暇つぶしの読書には手ごろ
東北地方農村部の花嫁不足故の中国人妻の失踪に端を発した、日本・中国・ロシアの暗黒社会を巻き込んだ展開は、のっけから船戸氏ワールド全開。ストーリーとしては面白く、暇つぶしの読書には丁度良いと感じた。一方、船戸氏作品につきもののストーリーの底部を流れる独特のテーマがなく、骨太感は感じなかった。船戸氏作品であれば何でも読むという方には、移動中の読書にお勧めします。
0投稿日: 2014.09.17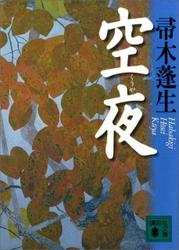
空夜
帚木蓬生
講談社文庫
帚木氏の小説にしては、何が言いたいのか良くわからなかった。単なる恋愛小説!?
今まで読んだ帚木氏の小説に外れはなかったのだが、珍しく焦点の良くわからない小説だった。精神科医の立場から、底知れぬ男女の情念というものを“きれいな”表現で書きたかったのかもしれないとの思慮はできるが・・・。九州の田舎を借景にした(風景描写はまさに帚木氏の真骨頂)、ダブル不倫の小説と言われてしまえば、それまでのような気がする。
0投稿日: 2014.09.01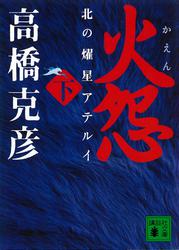
火怨 下 北の燿星アテルイ
高橋克彦
講談社文庫
色々な側面をもつ小説家 : 高橋克彦氏の歴史小説
写楽殺人事件のような推理小説、竜の柩等の伝奇小説が主体の作家だと勝手に思っていたが、この小説は高橋氏に対する印象をがらりと変えることになった。上巻は痛快な蝦夷の戦争戦術で終わったが、下巻で坂上田村麻呂が登場するあたりから、田村麻呂一派(朝廷側)とアテルイ一派(蝦夷側)の交流と戦における裏読みを中心に展開される。史実通りに、最後はアテルイ・母礼らが投降して戦の終了となるが、『蝦夷全体を救済するために、あえて負け戦を戦い投降するアテルイ』というストーリーには真実味を感じる。各登場人物の描写も丁寧にされておりリアリティーは十分。思わず涙という場面も多々あった。
3投稿日: 2014.08.24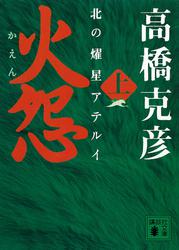
火怨 上 北の燿星アテルイ
高橋克彦
講談社文庫
上巻は、痛快なくらいの蝦夷(アテルイ)陣営の朝廷に対する勝ちっぷりに喝采
氏が東北の出身ということもあろうが、歴史の教科書では、東北の蛮族(蝦夷)が坂上田村麻呂に平定されるというそっけない記述しかないものを、平定された側である蝦夷側から丁寧に書き込まれている。当初は各地域で縄張りをもって独立していた蝦夷の各長が、アテルイ・母礼を中心に一体となり、朝廷のしかける戦争に立ち向かい、再三にわたり勝ちまくるという痛快なストーリー。各地域を代表する長たちの性格がしっかりと書き込まれており、リアリティーたっぷりに読んでいける。
1投稿日: 2014.08.24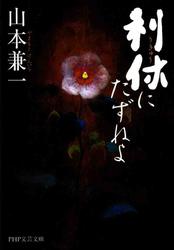
利休にたずねよ
山本兼一
PHP文芸文庫
切腹の日から若き利休までさかのぼって記述するという構成は面白いが
作者の文体の巧みさ・構成には面白い点が多々あったが、私自身が茶道に興味がないためか、読むのに時間がかかった。歴史の裏に女ありとはよく言われるが、利休の研ぎ澄まされた茶道の裏側にも、やはり思いを遂げられなかった女性(その代償としての緑釉の香合)がいたというストーリーは頷ける。利休の後妻である宗恩が、最後に緑釉の香合をたたき割るシーンは、小説の後半部分からなんとなく想像ができた。
1投稿日: 2014.08.24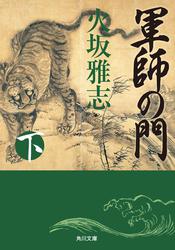
軍師の門 下
火坂雅志
角川文庫
淡々と紡がれる歴史物語、最終章の官兵衛の回想が秀逸
上巻は竹中半兵衛、下巻は黒田官兵衛を中心に据えた歴史小説(歴史物語)。上巻と同様に淡々と時間軸に沿って史実が記述されていき、作者の思いはほとんど投影されていない。最後の最後で官兵衛の独白(回想)が語られるが、この部分が秀逸。『大将は政治家であり、時に暗愚にふるまう必要があるが、軍師は芸術家である。一切の妥協を許さず、このため敬遠されることにもなる。己は一流の政治家(天下取り)になれなかった。』それでも、これを良しとした官兵衛の人生に合掌。
0投稿日: 2014.08.10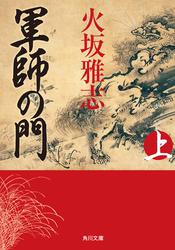
軍師の門 上
火坂雅志
角川文庫
上巻は、黒田官兵衛の師であり、友である竹中半兵衛に主眼を置いた小説
火坂作品の初読。作者の創作部分も相当に入っていると思うが、情緒を極端に配して淡々と時間軸に沿って記述されている小説で、純然たる歴史書を読んでいる感じ。文章力があり、滑らかに読み進められるので決して苦痛ではないが、大河ドラマと比較しながら読んでみるのも面白いかもしれない。
2投稿日: 2014.08.01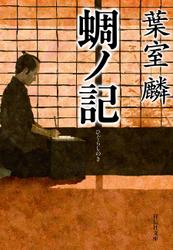
蜩ノ記
葉室麟
祥伝社文庫
登場人物たちの感情を抑制した“凛”とした文体、読後にじわっと来る感動が味わえる
私としては初めて読む葉室麟氏の小説。さすがに直木賞受賞作ではあると思う。氏の文章の特徴であろうか、一貫して凛とした文体であり、特に前半は登場人物たちへの感情移入を抑制したセンテンスが続く(人によっては退屈に感じるかも)。終盤に入り、村の少年の死をきっかけに一気にクライマックスに突き進んでいくが、ここでも抑え気味の文体がむしろ心地良い。一気に涙腺が崩れることなく、読後にじわっと涙腺が緩む小説を久しぶりに味わった。
3投稿日: 2014.07.21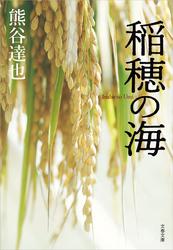
稲穂の海
熊谷達也
文春文庫
熊谷小説の初読の方には、ピッタリな入門書
2007年~2009年にかけてオール讀物に掲載された短編集。熊谷作品の代表作と言えば直木賞受賞作の『邂逅の森(2004年)』になるが、この本を読む前に熊谷作品の入門書として『稲穂の海』は最適だと思う(ただし、こちらの方が後の作品だが)。東北の方言で書かれた短編あり、ユーモアチックなものあり、子供目線で書かれた重松作品を彷彿とさせる佳作ありで、短編集ながら熊谷氏の作品の魅力が凝縮されている。
0投稿日: 2014.07.19
ナチ_コチ_ショチさんのレビュー
いいね!された数92
