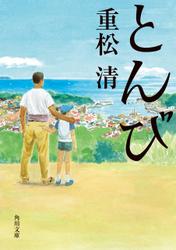
とんび
重松清
角川文庫
久しぶりに出会った『屈抜きでいい』と思う本
『この本はいい』理屈抜きの感想である。文学作品としての完成度がどうか、ストーリーテリングとしてどうか云々は別として、とにかく良かった、そして随所で涙をこぼした。私自身が、主人公・ヤスさんの後半生と同年齢であるかもしれないが、本を読んでいて、思わず涙が出たのは久しぶり。今一度、自分は親として、あるいは子としてどうなのかを考えてみたい。
1投稿日: 2014.12.07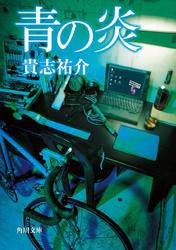
青の炎
貴志祐介
角川文庫
高校生(未成年)の犯罪過程にぐいくい引き込まれるストーリー仕立て。最後はこれで良いと思うが、もう一工夫があっても。
才気煥発な高校生・秀一の完全犯罪を狙った2つの殺害方法が、かなり現実的で面白かったが、それにもまして秀一の心の葛藤を描く場面が良かった。少なくとも第一の殺人は究極の選択として、私自身でもこのような選択がありかなと思う。第二の殺人については自己防衛の我儘以外の何物でもないが、人は一度悪事を働くと、後は際限なく繰り返すものなのだろうか。最終的に、秀一に宿った青い炎は、彼自身に向けられた。同級生・紀子、妹・遥香の健気さが切なく、今後の彼女らの人生に幸多かれと祈る!
1投稿日: 2014.12.02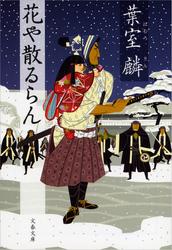
花や散るらん
葉室麟
文春文庫
葉室氏は性善説の立場か・・・いのちなりけり、花や散るらん、いずれも読後感がいい。
前作“いのちなりけり”の続編であり、忠臣蔵とのコラボというより、忠臣蔵を架空の人物である雨宮蔵人・咲弥の視点からとらえ直したものともいえる。時代小説をあまり読まない私にもわかりやすい文章で、読み応え十分だった。他の数作品もそうだが、葉室氏の小説には根っからの悪人が登場しない。この小説でも、吉良上野介・神尾与左衛門の最後もきれいな散り方だった。葉室氏の性善説・・・これはこれで氏の小説の根幹をなしている一つだと思う。私にとっては、続けて読んでみたい作家のひとり。
1投稿日: 2014.11.07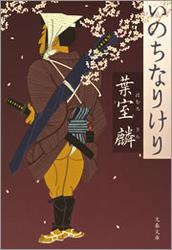
いのちなりけり
葉室麟
文春文庫
武士の時代だからこそ書き得るストーリー、分かっているけど最後は涙を禁じえない。
時代小説だからこそ書き得るストーリーがあると思った。まずは、雨宮蔵人のキャラクターを現代小説で設定するのが難しい(小説末尾にあった葉隠れ精神そのものである、やはり武士を前提にしなければ難しい)。最後の方は、江戸時代版の走れメロスであるが-友情ではなく愛情だが-、分かっていても、寛永寺での再会は涙を誘う。終章でちょっとだけ登場する草加又六のキャラが際立っていて、これぞ名脇役という感じ。水戸のご老公も最後に良い味を出した。喝采!
1投稿日: 2014.11.02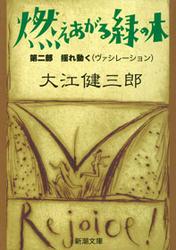
燃えあがる緑の木―第二部 揺れ動く―(新潮文庫))
大江健三郎
新潮文庫
難解だけど小気味のいい文章のリズム:第二部は総領事の死とサッチャン(第一人称)の旅立ち
第一部(救い主がなぐられるまで)と比較すると時間の経過がゆっくりと流れて、観念的な文章が多く、より難解になっている。主人公のひとりであるギー兄さんの実父・総領事が、命数が限られた後、外交官の第一線を引いて『魂のこと』の作業に没頭しながら亡くなるまでがメインストーリーになっている。そして、いよいよ『燃え上がる緑の木』教会が全体として第一歩を踏み出す時、本編の第一人称であるサッチャンが、まさに故郷から出ようとするところで終わる。混沌としながら第三部へ。 1年半ぶりの再読(精読)、それでもこの作品は良く分からない。ギ―にいさんの実父・総領事(外交官)は、人生の締めくくりで『内なる森』に帰り、在にいた亀井さんはギ―にいさんへの糾弾の後、資産を投じて『内なる協会』に所属することになる。外部からやってきた伊能三兄弟・泉さん・亀井さん等の献身もあり、いよいよ教会らしい体裁が整ってきたが、意にそぐわない(?)拡大に対してギ―にいさんは蹲ってしまう。本来から内にいて転換を遂げたサッチャンは、逆に『外へと出て』いくが。それぞれのヴァシレーションを抱えながら話は終盤へ。
0投稿日: 2014.10.29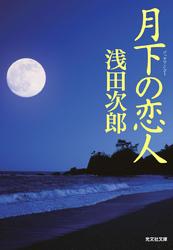
月下の恋人
浅田次郎
光文社文庫
短編の名手・浅田氏の気軽に読める作品集
浅田氏の短編集はいくつかあるが、『鉄道員』や『霧笛荘夜話』と比較して重苦しさはなく、時間つぶしに読むには手ごろな作品。浅田氏お得意の“泣かせもの(人情もの)”ではなく、ちょっとしたミステリー(怪談)も加味して物語を読ませる作品になっている。個人的には『情夜』と『あなたに会いたい』が良いと思ったが、この2つは主人公がいずれも自分と同じような年(50代)だからか、この2編を対比して読むと面白い。
0投稿日: 2014.10.13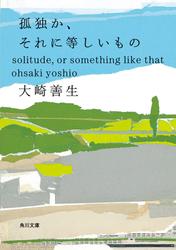
孤独か、それに等しいもの
大崎善生
角川文庫
大崎氏の感性や透明感は発揮されているが、内容に賛否両論ありそうな短編集
“パイロットフィッシュ”や“アジアンタムブルー”を読んで無条件に良いと思う人たちでも、賛否が分かれそうな5作の短編集。5作のうち3作が女性を一人称として書かれているが、いくら大崎氏の感性が優しいといっても、女性の側から書くのは難しいと感じる。それでも、『八月の傾斜』と『ソウルゲージ』はお勧め。表題の『孤独か、それに等しいもの』は最後にポッと温かく終わるところが良い。
0投稿日: 2014.10.08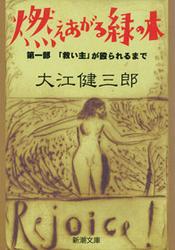
燃えあがる緑の木―第一部 「救い主」が殴られるまで―(新潮文庫)
大江健三郎
新潮文庫
ノーベル賞受賞前後の大江作品としては最も長編となる”森(閉鎖空間)と神話(文化の伝承)”三部作の始まり
大江氏の作品は興味はあるが、さすがに立て続けには読めない。半年ほど前に『さようなら私の本よ』を読んで以来の挑戦。四国の森林に囲まれた閉鎖社会で神話と現実のはざまに揺れ動く人々を描く。一人称で描かれる語り手が“半陰陽のうら若き女性”(少し前までは少年)&神話世界の代表オーバーの後継者である“ギー兄さん”を中心に、これらを取り巻く人々が、それぞれの役割を秘めて登場する。第一部のクライマックスは副題の通り、神話性を纏ったギー兄さん=救い主が、神話に幻滅した村人から総すかんを食い、殴られるまで。小説の後半ころから、独特の大江節にも慣れてきて、一気に読み進められる。引き続き第二部に取り掛かりたい。 <1年半後に再読> この物語の重要なテーマは〖外と内〗になるのだろう。四国の閉鎖空間(旧・甕村)とその象徴ともいえるオーバーの死から始まる物語。空間を存続させるための、“外から来たギ―にいさん(隆)、ずーっと内側に留まりながら転換を遂げたサッチャン(1人称の主人公)との対比”“空間から出て行って東京で暮らす小説家Kおじさんとその妹で内側に留まり続けるアサ(空間の内に居続ける最も常識人)さんとの対比”。オーバー亡き後の空間・伝承を守るための象徴であるギ―にいさんが、“在”という若干外側にいる人たちから糾弾されて第一部が終了する。第二部ヴァシレーションで、いよいよ外と内が混沌となってくるのか。
0投稿日: 2014.10.08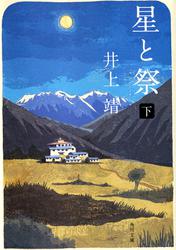
星と祭 下
井上靖
角川文庫
エベレスト麓のタンボチェの観月行程の記述は、さすがに山岳に精通した大家だと思う。
架山・大三浦とそれぞれ娘・息子を失った親の悲しみは、かくも深く、長く続くものかと思う。下巻の前半は、エベレスト麓での観月行程に大部分を割いているが、井上氏得意の山岳ものであり、山麓に暮らす人々の生活・村の様子が生き生きと記述されていて読み応えがある。『永劫』という言葉を使い、山の自然・そこで暮らす人々を称したのは良くわかる気がする。最後に琵琶湖の満月を観ながら架山・大三浦のそれぞれの仮葬が明けるが、”星と祭”という小説名が分からなかった。
1投稿日: 2014.09.30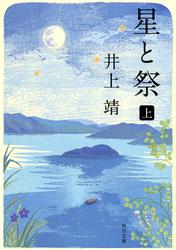
星と祭 上
井上靖
角川文庫
井上靖作品は、古典ではなく現行の小説としても十分に読み応えあり!
何十年かぶりに読む井上靖小説。文体がきちんとしており(奇をてらうことなく)、非常に読みやすい。娘を亡くした男親の切々とした思いがつづられている場面は、少々くどいと感じることもあるが。下巻では、娘さんへの追悼あるいは懺悔なのか、はたまた自身の心の平穏を求めてか、いよいよ“ヒマラヤの月”を見る旅に。上巻では、『星と祭』とした小説名が分からない。総評は下巻を読んでから。
0投稿日: 2014.09.25
ナチ_コチ_ショチさんのレビュー
いいね!された数92
