
僕だけがいない街(1)
三部けい
ヤングエース
アニメ化に続いて映画化にもなっている話題のマンガ
3年連続で「この漫画がすごい!」と大変好評を博して現在放送中のアニメ化に続き、先日より藤原竜也くんと有村架純さんとの共演にて実写版の映画化もされている作品の原作的な本です。 まだマンガは最終巻が発刊前で完結はしていないようですが…すみません。私はすぐに犯人が分かってしまいました。 (別に自慢しているのではなく、私のようなものでも実際にすぐに分かってしまったので推理マニアの人がそれを期待して読んでしまうと凹まれるのではと思って書きました) 推理マニアとかは好きそうな本作ですが(もちろん当方もその一人なのですが)実際の犯罪だと全くの無関係な人が犯人であったり、計画性というよりも偶然が重なってより難解になってしまったという事件もあると思います。 昨今の現実の事件や、犯人逮捕後のその後の裁判での内容を伺っていると、こういう推理モノって所詮はその枠の中の限定された人の中に犯人がいることが前提になっているので現実と比べると分かり易いですね。 (ただし、作者が立案時の最初から犯人を特定せずに、ぶっちゃけ適当&唐突に犯人として逮捕させる展開なのにもかかわらず推理サスペンス小説では長年ベストセラーになってドラマ化されてシリーズ化にもなっている内田康夫氏の作品もありますから「推理モノ」なんて読者は実際は求めてはいないかもしれませんけどね) まぁ、意味深な怪しさばかりがてんこ盛りなのに視聴率が良いとズルズルと延長されて駄作化して結局、犯人なんてどうでもよい状態になり最終回もいい加減で終わってしまうアメリカのドラマよりも良いかもしれませんけどね~ 設定を多少アレンジしていますが基本パターンとしては筒井康隆先生の「時をかける少女」と同じですね。 時空を超えて過去の殺人事件の犯人を追うお話です。 まぁ犯人が私ごときが分かったからと言ってイマイチなんていう漫画でもありません。 むしろ順当=犯人として不合理なところが無いからこそ当てたまでですので、そういう意味では作品としては読んだ後になって落胆されたり、疑問ばかりで消化不良になることも無い佳作だと思います。
1投稿日: 2016.03.12
真夜中のX儀典1
馬鈴薯,山口ミコト
電撃コミックスNEXT
マンガ版の「双子の山頂」となるか、佳作と讃えられるか…
前置きとして、この連載が終わっていない(少なくともその結末までが刊行されていない作品)は薦め様がありません。 だって最後の最後で駄作になるかもしれません。 途中まで興味が魅かれまくる作品でも終わってみたら駄作だったら薦めるにも気が引けます。 ドラマで言えば例えば…ローラ・パーマーが殺された「双子の山頂」とか(笑) なので本作はまだ未完ですからお勧めは致しません。 以上を前置きとして… 本作は肉体交換にて巻き起こった主人公の姉の殺害事件の犯人探しのストーリーです。 女の方が得な人生だと溢し厭世の主人公がネットの他人と入れ替われるというサイトを利用してみると、人気アイドルと入れ替わっていてその実情を目のあたりにして更に厭世感を深めたものの、自分の肉体に戻ってみると目の前には姉が刺されて殺されていた…はたして犯人は誰なのか?!というお話。 えー…冒頭に記載し前置きの通り、本作はまだ未完ですので今後どう進展するかは分かりませんし、当方がこの様なところでどう書いたところで結末が変わるとは言いませんが当方にはおおよその見当がつきました。 おそらくは●●だと思います(ストーリーとしては別の順当ともいえる▲▲という結論もあり得ますが…) 私個人的には描かれている絵も好きですしストーリーも推理心を掻き立てられますので最後まで良い展開と結末で終わってほしいです。(最終巻が出てから再読したいです)←もちろんそれで結論に無理が無ければお勧めですが…肉体交換とかSFモノ要素もありますからこじ付けの結末という第三の結論じゃないとは言い切れないのが不安でなりません。 なので、結論=犯人が捕まる最終巻が発売されるまではお勧めしません。つまり、発売後でしたら(結論次第ですが)大変お勧めの作品だと思います。
1投稿日: 2016.03.12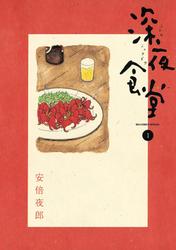
深夜食堂(1)
安倍夜郎
ビッグオリジナル
歓楽街のネオンに疲れた人たちが集う店のお話
書かなくても知っておられると思いますが、ドラマ「深夜食堂」の原作マンガです。 ドラマでも店主はもちろんクセだらけの客たちが実に味があり、私は大ファンのひとりだ。 ドラマを観たから読むのを迷ったくらいだったが…原作はさすが原作でドラマにない味がありました。 自分にもこういう食堂に通っていた時期があった。 新卒で入った今でいうブラックな会社に真夜中を回るまでこき使われるだけでなく、仕事を終わったら上司や先輩につき合わされて飲み屋を梯子し、帰宅するなり手狭な部屋の入り口や座ったトイレでそのまま寝入って朝を迎える日が続いていた。 仕事のストレスも良くないが、脂っこいものばかりを夜中に食べるばかりではもちろん身体によいはずも無く、悲鳴を上げていた。 そんな時期に歌舞伎町にも近いが都庁近くのこの作品に出てくるような夜の定食屋に通うようになっていた。 絵に描いた様なビルとビルの間の店で奇跡みたいな店で、言っては失礼だが場末なのになんでも無い普通の定食から一品まで美味い店だった。 (品書きの札にない常連が頼むメニューを頼むときはちょっと勇気が言ったものだ) あの焼タラコやアジフライやサンマ定食は今思い出しても涎が溢れるし、裏メニューの山芋の擦りおろしに何度となく精力を回復させてもらったものだ。 小洒落たところもなく、また営んでおられた老夫婦もさしたる愛想も無かったが、私には重宝な存在だった。 家業を継ぐ為に東京から都落ちするときに誰に挨拶をしたわけではなかったが、その店主とおばさんには最後ながら最初に声をかけて御礼を言うと実に気さくに話が出来たのは私の思い出で、結婚後に嫁を連れて一度だけだが訪れたことがある。 今もあるのだったらまた食べてみたいものだ… さてマンガだが、ドラマ版の方が良い部分もありますし、原作の方が(御時勢なのか)ドラマ化出来難い部分が描かれていたりでどちらも面白いです。 ドラマとマンガを比べたら店主からはさしずめ、 「ドラマとマンガとどっちが面白いかって…そりゃ目玉焼きとゆで卵をくらべるみたいなモンだよ」 と言われそうです。 なに?!ドラマなんて観たことが無い…だったらこのマンガから楽しんで下さい。
0投稿日: 2016.03.09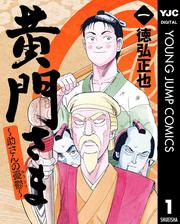
黄門さま~助さんの憂鬱~ 1
徳弘正也
グランドジャンプ
黄門様の諸国漫遊部分を除いてはほぼリアル(勘違いの先生と教科書よりよっぽどリアルな)な江戸時代のお話です。
ノッケからですが、トトラッシュさんのレビューが一番的確です。私が書こうとした同じ内容です。 (歴史を知ることも無く、教科書に書いてあることを疑問にも思わずそのまま教えるというよりも伝えるだけの先生から) 歴史の授業で江戸時代ってなんて習いました?! 「士農工商の徹底したカーストと同じ身分社会でその頂点に立つ武士からそれ以外は搾取され蔑まれ続けるおよそ400年だった」 と事実から大きく歪曲したことを習いませんでしたか!? 実際の江戸時代はインドのカースト制のような生涯不変の絶対身分が存在しているのではなく、縁故と資産があれば農民から武士どころか御家人にすらなり得る時代で、実際に幕末に幕府の全権代理で米国大使と交渉した人は祖父の代まで農民と言う出自でしたし、「金治郎」で知られている二宮尊徳も生れは農家ながら出世して認められて武士になった一人です。 もちろんこのマンガのもとになる水戸黄門の諸国漫遊記は講談本の作り話で史実の水戸光圀はおそらく関東圏どころか水戸藩内と江戸を除いては鎌倉と日光くらいしか行ったことはないようですし、描かれている内容の詳細では作者特有のデフォルメされた内容がありますが、こと風俗や庶民の感覚などについてはよく史実を勉強されて描かれていて変な教科書よりもよっぽど良い江戸資料になると思います。 教科書で勘違いを教えられているよりも江戸時代は制度が整備され、治安も雇用も安定していて、情報社会でした。 例えば江戸の町には治安の為に町ごとに木戸があり夕刻から夜明けまでは閉門されて門番がいいたので長屋以外の夜間の人の移動は不可能でしたが赤穂浪士の討ち入りでも庶民はいつやるかと待ち望んでいたくらいで噂されて周知だったからこそ赤穂浪士たちは武装した格好で吉良邸までの移動が可能であったり、討ち入り後の泉岳寺までもすんなりと行けたのです。(鼠小僧などの盗人が屋根を伝って移動する理由はそこにあります) 史実ではないですが本作品中に水戸の御老公の諸国漫遊が庶民には周知だったというくだりがありますがもしも諸国漫遊が本当だったら実際に庶民には周知だったことでしょうね。 風俗の特に男女の風俗も風情があり楽しめる時代でした。 現代用語と勘違いされていますが「ヤバイ」とは、弓矢の射的場の女性店員が実は風俗の現代で言うキャバクラみたいなお店になっていて、そんな所で働く女のことを「矢場い女」と言っていたのが語源と言われています。 知れば知るほど魅惑的な江戸時代。 戦国時代ならまだしも関ヶ原から80年近く経っていた太平の時代に人を殺傷できる刀を常に腰に下げていたとはいえ人を殺傷などしたことなどない時代ですからね。 現代感覚でリアルでもなんでもない時代劇ドラマ「水戸黄門」よりも実に江戸時代をギャグ満載で(そしてちょっと?Hに)それでいてリアルに描いているのが本作品です。 内容としては主人公が採用試験を生き残り採用されて「助さん」になるまでを描いています。
0投稿日: 2016.03.09後門に入れた指でペニスをなぞれ!
安達瑶
後門に入れた指でペニスをなぞれ!
安達瑶
マガジンハウス
タイトルに騙されるな!
この作品をただのエロ小説と思って読むとちょっと違和感を感じると思う。 もちろん感じない人もいるでしょうが、良い意味で私は思わず唸ってしまいました。 勘違いされると困るのですが、「タイトルに騙されるな!」と感想タイトルに書きましたが、お勧めな作品であることは間違いないことは最初に明言しておきます。 別に小難しい話ではないのですが、ただの喘ぎ声ばかりのセックス小説というだけ以外を私は感じてしまいました。 題名を読んで、アブノーマル(というか今では当たり前にも思える←病気だなぁ)なアナル・セックスかそれに類する小説なのかと思って購読しましたが…覆いに裏切られました。 エロ話です。それは間違いないです。 ただそれ以外の内容を含み感じ取ってしまい私は少し感動に近いものすら感じてしまいました。 自分はこの主人公になっていたかもしれない。 そして自分だったら別の行動をするかもしれない。 言い訳になりますが、今はハッキリ言って内容の無い三文エロ小説ばかりということもあり、そういう小説ばかり読んでしまっていますが昔はそうでもなかったんですよね。 やたら小難しいストーリーで、性的な扇情を冷まされ読んでも「何故、エロ小説に?ここ要る?!」と必要性どころかワケがワカラン、社内抗争とか、ハードボイルドを真似た内容の小説もありますが、それとも違います。 そして「男と女の」というよりも、ただの「アウン」「アハン」の内容の無い、非現実な性的妄想満載の喘ぎセリフばかりの小説でもないです。 「なぁ~んだ、だったら読まねぇ」と思って素通りすることは損とだけは書いておきます。 エロエロで喘ぎ声ばかりの文章が読みたいならどうぞ他へ御回り下さい。 でも、エロい「小説」が好き。とか、「作品」と言える小説が好きという読書家の方でしたら素通りは損だと明言しておきます。 ハッキリ言ってこの価格以上の内容だと私は思いました。 結構、脳裏に残る”作品”でした。お勧めします!
0投稿日: 2016.02.27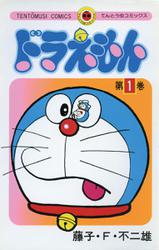
ドラえもん(1)
藤子・F・不二雄
月刊コロコロコミック
問題!この第一作目で最初に登場する近未来のお助け装置とは?!
ドラえもんの第一巻です。 日本全国民知らない人を探す方が難しい未来から来たお助けグッズを取り出す四次元ポケットを持ったネコ型ロボットのお話。 日本語が使えるPCなら文字変換でも「ドラ衛門」とは出ずに、一発で「ドラえもん」と出ます。 他にも、スネ夫からジャイアンジャイ子、出木杉まで一発で誤変換せずに出ました。 (ちなみに所有の海外製スマホでは、ジャイ子や出木杉はダメでした) のっけから蛇足だか照れ隠しである。 もう懐かし過ぎて途中から…いや第一話の前後不覚に陥ったのび太を慰める子供の未来を信じるパパさんママさんのシーンから涙がジワジワ出てしまった。もちろん数ページめくった段階で笑って読んでいましたが…。 この第一巻はもう本当にいったい何度読んだことだろう。 ボロボロになっても読んでいましたが読み飽きたことは一度も無かったです。 それでもいつしか本箱の奥に入ったままになり…今では、子供が読んでいます。 さて、題名の問題の答えですが、正解は…「ドラえもん」です。 書き方が嫌らしかったから気付く人は多かったかな?! 四次元ポケットから最初に出てくる未来のグッズはタケコプタ―ですが、未来の機械はドラえもんです。 ドラえもんってマンガ内でも野比家でも家族の一員の扱いですが、正式名称の通り=子守用ネコ型ロボット、つまりは機械(ロボット)です。 人型ロボットと言えば、他にも有名なものが3つあります。 御存知まずは、アトム。次に、ガンダム。そして、エヴァンゲリオン。 ドラえもんも入れてこの4つは実に面白い違いがあります。 まず一番歴史が古い、アトムは人型の人工知能と自我を持ったロボットで、自分の思考で動きます。 アトムの作品内ではロボットとは人間に従う機械の”物”=奴隷であるが、高度化したロボットたちがいつしか自我に目覚めて権利を主張し始め人間に反旗を翻します。 そんな暴徒化したロボットたちを本来仲間であるアトムは人間に命じられるまま退治=処分していき、作品内でも自分の立ち位置に悩みます。 アトムとは近未来の機械に自我と言う意志が出て来た時の人間の混乱を予見した警告書なのです。 次のドラえもんは最後として、次はガンダムです。 ガンダムは単純です。装置です。意志はありません。プログラムされた場合は自動では作動しますがそれだけであくまでも形状が人型以外に人間的な要素は皆無であり、現代の車やフォークリフトなどの作業装置や工作機械となんら変わらない実にアナログな存在です。 最後のエヴァンゲリオンは一見、人型のロボットですが実は(超簡単に言えばですが)人造生命体を制御装置の装甲で覆ったいわば半ロボットであり、基本的に制御されていれば操縦者が動かしますが、そうでない場合も自分の意思でも動きます。(ただし自我については…たぶん無いと思います…たぶん) 何が言いたいのかと言えば、つまりはドラえもん以外はあくまでも人間が作り出した機械であるということ。 もちろんドラえもんも最初の動機はそれで、御主人の命令でのび太を守れと指示されて働くのですが、物語少し進んだ時に、いったん任務が解除されたのちに再登場してから自分の意志でのび太を助ける存在なのです。 さらに注目すべきは同じ人型で意志と自我を持っているのに家族の一員とされていないアトムの比べると、ドラえもんはまるで家族同様に溶け込んでいるのです。 作品の物語が進んでいくとギャグ要素が減ってテーマ性がある様な展開にもなりますが、ドラえもんはといえぱロボットだからプログラムされているハズですが、徹底した完全な善なる存在でもなく、時に悩んで、時に勘違いし、場合によっては仕返しをするなど人間に必ずしも害なさない存在ではないのです。 (それは「ドラえもんが元々、不良品だったからだ」とドラえもんマニアからツッコミが入りそうですが)ドラえもんがのび太など人に害なす場合は、のび太や仲間を思っての行動だっりして、ともかく一貫して人のように行動します。 自分の幼少期にも、こんな(曖昧ながらも)時にアドバイスしてくれ寄り添ってくれ、そして助けてくれる存在がいてくれたらなぁと思ったりします。 そう思うとそのドラえもん的存在って時に親だったり兄弟だったりするのが、高度成長期で人同士の触れ合いが無くなり、学力偏重社会になったりと、そんな存在が身近にいなくなったのも、読者がドラえもんを求めた理由の一つなのかもしれませんね。 (それにしても作品中でも問題になっていますが、遊び場になる空き地って無くなったよなぁ~…)
1投稿日: 2016.02.22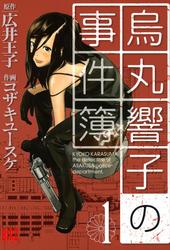
烏丸響子の事件簿 (1)
コザキユースケ,広井王子
コミックバーズ
国家がひた隠しにしている鬼の存在
鬼の所業としか考えられない事件が続く現代ですが、本作はその鬼などの”異形のモノたち”の犯罪捜査になります。 警察内の御荷物部署扱いながらトラブルを処理していくのは、『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』に似ていますが、本作品は舞台はほんの少し先の時代で、対象物=被疑者は鬼などの゛”異形なモノ”になります。 (鬼の存在について屁理屈…いや、解釈で存在を解き明かす「宗像教授異考録」を読んだ直後でしたのでより楽しめました) 本作は実際に鬼などの”異形のモノ”たちが存在していても、それを認めない国家(社会)という設定で、ある意味で異形に親しい存在で活躍する刑事、烏丸響子の事件解決の話になります。 (いや、解決しても結果的に揉み消されるから試験解決ではなく事件対応かもしれません) 響子が解決しても証拠もすべて処理されてうやむやになる事件がそれをひた隠しにする人たちも介入し、これからどう展開するのか興味津々になります。 隠され続けてきた存在が今の日本にも世界にもいるのかもしれません。
0投稿日: 2016.02.19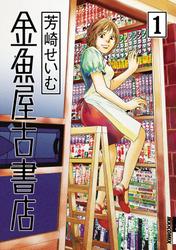
金魚屋古書店(1)
芳崎せいむ
月刊IKKI
子供の頃に好きだったマンガって何ですか?!
のっけからですが…このマンガの書籍説明は間違っています!このマンガの素晴らしさを全然伝えていません。 (かと言って私が伝えられる文才はないのですが…すみません) もう読んでいる途中から魅了されて、そして作者の着眼点に悔しい思いすらしました。 皆さんにとってマンガってどんな存在ですか?! マンガとか子供の頃のTVアニメって同世代だったり、世代を超えての共通言語なんですよね。 (もちろん家庭の教育方針や個人の趣向でそうならなかった人もいますが…残念なことに自分の愛妻もその一人なのですが) マンガに限った話でもないのですが、それでもマンガって年代で言えば1965年前後くらい以降の”元”子供にとっては共通言語だと思うのです。 たとえ時間だったり距離を隔てたり格差があってもそれを縮められる共通の話題になります。 そんなマンガ好きな人たちが引き寄せられる古本屋が本作のメインの金魚堂です。 本作はそこに集い関わる人たちで、マンガを捨てようとしてその存在を再確認した人や、マンガで切れそうだった心が救われた人たちのストーリーです。 マンガ本に関わる人、マンガが好きな人、マンガをいつか描きたい人、マンガに人生を見出した人にとってのまさに、フィールド・オブ・ドリームスみたいなお話。 私が書いていても違和感があります。 だってこの作品は作品自体がそれぞれのマンガのレビューになっていて、いわば私はレビュー本のレビューを書いている訳なのです。 この作品は、マンガが好きの人だけでなく、かつて幼少期に読んでいたという、すべてのマンガ好きの人たちにとって夢のストーリーだと思いました。 ツボ突かれますよ。本当に。お勧めします。 補足:「百日紅」の解説で作者の杉浦向日子さんのことを「今では江戸文化研究家として活躍されている」としているが本が発刊された2004年の翌年の2005年に早逝されました。憧れの人で目標の一人で今でも悔やまれます。合掌。
0投稿日: 2016.02.17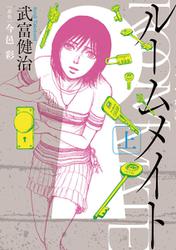
ルームメイト(1)
武富健治,今邑彩(中央公論社)
ビッグスピリッツ
謎の失踪を遂げた同居人…ルームメイトとは…
深田恭子さんと北川景子さんで映画化もされた「ルームメイト」のマンガ化本です。 (原作は小説で、映画版とは結末が違います) 小説だと違和感を感じる人もいる部分が、マンガだとうまく溶け込んでいてよりストーリーが楽しめました。 小説版はもちろん原作ですから原作としての表現だったり行間の楽しみもありますが、武富健治先生のオドロオドロシイ画風がより作品の怖さを表現してくれています。 本音を言えば最初はどうかな?!とも思ったんですが最後まで読むまでも無く、この作品のテーマというか(凡人の自分には理解できませんが)狂気の様は武富健治先生の絵ではないと表現しきれなかったのではとすら思えてきました。 人の殺害シーンよりも人の狂気の様子の方が私には怖かったです。(もっと怖いのは結末にあるのですが…) 最初は謎の失踪を遂げたルームメイトが多重生活をしていたことはまだしも、ルームメイトが実は春海たちが思っていたのと実年齢が違っていたという部分に疑心暗鬼でした。 しかし読み進めていくと、そんなことはどうでもよくなる展開でした。 ルームメイトはいったい!? 全三巻です。 しかし三巻以上に内容が濃いマンガでした。お勧めです。 読んだら止まれなくなると思います。 え、止まる?!止めようとしているのは気付かれると困るあなたの別人格かもしれませんヨ。
0投稿日: 2016.02.17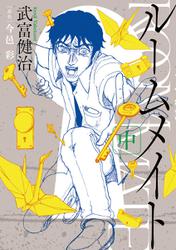
ルームメイト(2)
武富健治,今邑彩(中央公論社)
ビッグスピリッツ
二重ではなく多重人格者たちのお話です。
あなたは自分自身が二重人格者ではないと言い切れますか?! 二重どころか多重人格者ではないと言い切れますか?! そして、あなたの身近な人たちがそういった人たちではないと言い切れますか?! 自分だってそうですし、人はそれなりに辛い思いもして成長していると思います。 世界的には認定されているのですから存在するのでしょう。 しかしもちろん辛い思いをしているからと言って目の前で見せ付けられたり、実感しない限りはそうそう信じられない(実際に私も懐疑的です) それでも自問自答はしたことはありますし、辛過ぎる経験をすると別の人生(人格)も考えたりもしたことは否定しません。 二重人格者がかならず犯罪を犯すわけではないと思いますが、そんな自分がもしも二重とか多重人格者で、もちろん別人格の犯す犯罪に自覚も無くて巻き込まれたら… 想像するだけで、この作品は寒気を覚えました。 さて、この第二巻は第一巻で最初に麗子と名乗ってなんと三重生活いた女が殺されているところから始まります。 もう読んでいて最初から「どういうこと??」の、?ばかりです… 最終巻まで一気にどうぞ。読まずに夜は越せません…
1投稿日: 2016.02.17
竹桜さんのレビュー
いいね!された数31
