
スティーブ・ジョブズ I
ウォルター・アイザックソン,井口耕二
講談社
アップルはジョブズなしにはありえなかった!
アップルの創業者にして最大のカリスマ、スティーブ・ジョブズの伝記の上巻。生い立ちからトイ・ストーリーの成功までが語られる。 正直なところ、アップルの製品は独特の世界観があり、それ故に特にマッキントッシュにはあまり魅力を感じてこなかった。iMacもデザインや割り切った性能など魅力的な部分はあったが、買おうと思えなかった。iPodで初めてアップルの製品を所有することになるが、これもどちらかといえば「持っているCDをすべて持ち歩ける選択肢がこれしかなかった」という消極的な理由からだ。 しかし、こうした個人的なアップル製品に対するマイナスイメージも、本書によって語られるスティーブの考え方に触れると、すべてが必然の結果もたらされているのだと認識でき、アップル教といわれるほどの熱狂的ファンを生み出していることにも納得がいく。 スティーブは奇人・変人であることも赤裸々に語られている。言動の揺れ動き、独特の美への執着、工業製品にアートを見いだす目。これらが洗練されていく中で多くの確執を生み、しかしやがてiPhoneやiTunes Store、iCloudに繋がる土壌が形成されていくのがよくわかる。
1投稿日: 2013.12.07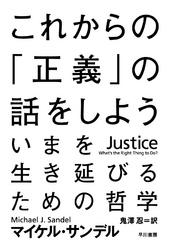
これからの「正義」の話をしよう ──いまを生き延びるための哲学
マイケル・サンデル,鬼澤忍
早川書房
NHKでの放送などがきっかけで大ヒットした哲学書
内容は「正義」というものの考え方の変遷が、時系列ではないにしろ大まかな考え方の流れに沿って論じられ、最終的にサンデル教授が考えるコミュニタリアニズムに基づく正義論へと収斂する。その過程はわかりやすいようであり、しかし奥深く、ときに難しい用語が混じったりしながらも何とかついて行くことが出来るように配慮されている。 とはいいつつも、そこは哲学書である。一度読んでわかったようなフリは出来ても、実際にはちんぷんかんぷんなところもないわけではなく、二度三度と読むうちにきっと腑に落ちるところや逆にサンデル教授の論理の穴が見えてくるなんて事もあるのかもしれない。まだ一度読破した程度の頭ではとても浅い理解しか出来ていないだろうけど。 なんにせよ、腰を落ち着けてじっくりと探求の旅に出たいときにふさわしい一冊であることは間違いない。
0投稿日: 2013.12.07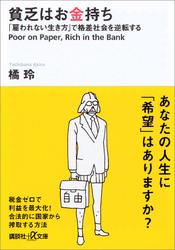
貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する
橘玲
講談社+α文庫
橘玲氏による「マイクロ法人のすすめ」の文庫化加筆版
例によって非常にドライなというか、感情を交えないストイックな物言いとともに、サラリーマンであることの非合理性と法人化によるメリットを詳説する。途中、サザエさんの家庭をモデルケースに、マスオさんがサラリーマン法人化したらどうなるかを検討するなど、おもしろおかしく、それでいて身近に感じられるように工夫しているが、ファイナンス理論が解説される段になるとたちまち難しくなる。 この人の他の著作もそうだが、ある意味わからない人はわからなくて結構、というような突き放し感がそこかしこに見られる印象が強い。それが「実用的でない」などの批判を受ける一端になっているように思う。 実際には本書の「マイクロ法人」にしろ、「残酷な世界で生きのびるたったひとつの方法」で紹介されていたロングテール理論にしろ、他の人が提唱している考え方をより実践的に紹介しているのだが、それまでの考え方を変えられない人が理解できないために批判している、と言えなくもない。 ただし、本書のあとがきに書かれていたように、幾ら有利だからといって、サラリーマン法人が増えたという話は寡聞にして知らないし、むしろ雇用の安定化をめざして「社畜化」する方向性が強まっているようにもみえる。サラリーマン法人が増えない今こそ、そのメリットを最大限享受できる、といえそうだが、自分に当てはめてみてもなかなかその一歩は踏み出せないものだと思う。
3投稿日: 2013.12.07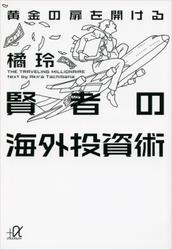
黄金の扉を開ける賢者の海外投資術
橘玲
講談社+α文庫
資産運用に関する情報をちょっと違う視点から
リーマンショック以降の情報も盛り込み、投資信託やREIT、FXなどの組み合わせ方や運用における考え方など、いわゆる世間一般に知られている情報とはちょっと違った視点で紹介している。相変わらずニヒルな語り口で、軽快に、しかし毒っ気たっぷりに語られる様々なストーリーが、今の自分の立ち位置を振り返る上では非常に危うい気持ちにさせる。 橘玲氏の本はいずれもどちらかというと後ろ向きで、「こうすれば簡単に儲かる!」的な楽観さに欠けているが、それが実は本当の世界をある意味正確に映し出しているのではないかという思いにさせられるほど説得力のある書き方をしているので、ついつい新刊が出ると手に取ってしまう。しかし、一般人にはあまり参考にならない話も多く、自分もその仲間入りが出来ればいいなあという夢物語で終わりかねない危険性は常にある。
0投稿日: 2013.12.07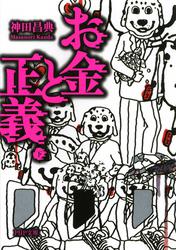
お金と正義(下)
神田昌典
PHP文庫
カリスマ・マーケッター、神田昌典による初の小説の下巻
いろいろと手を広げすぎてどう収拾させるのかが気になる展開となったが、そこはある意味強引にあるべき姿に収斂させていくその展開には唖然とさせられる。裏切り者だったのか、仲間だったのかさえよくわからない主人公の周りの人たちの言動もさることながら、結局主人公の姉は何を残したのかは解明されないまま。謎は謎のままのこり、しかし何となく物語は大団円を迎えてしまっているという、不思議な結末となっている。 説明がかなりはしょられていて、どうしてこうなったのかわからない、という部分があまりに多く、物語としてはかなり完成度は低いが、戦略的に物語に起伏を作ることで何となく読ませ切ってしまうというあたりも、神田昌典流の実験だったのではないかと思ってしまう。 不満は多く残るが、意外にも読後感は悪くない。このあたりも計算されている展開にまんまと載せられているのかもしれないが。
0投稿日: 2013.12.07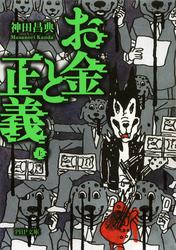
お金と正義(上)
神田昌典
PHP文庫
カリスマ・マーケッター、神田昌典による初の小説
自身がマッケッターだといってはばからない肩書きの通り、初の小説でも物語の起伏や意外性などに随所にその自身のこれまでの経験が生かされたつくりになっている。一方で、最近の小説にありがちな蘊蓄も適度にちりばめられ、飽きさせない工夫を施している。 とはいえ、もともと物語を書くことを本職としているわけではないので、そこはひいき目に見てもかなり稚拙な部分がある。とはいえ、スピード感溢れる展開はそれなりに面白いし、下巻の作者による解説でも述べられているように、適度なタイミングで訪れるピンチは計算されているとわかっていても思わず食い入ってしまう。 矢沢永吉ファンなら共感できるところもあるだろう展開もクスリとさせられる。
0投稿日: 2013.12.07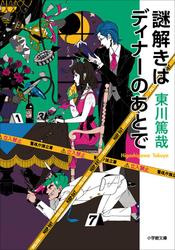
謎解きはディナーのあとで
東川篤哉
小学館文庫
ユーモアミステリの旗手が放つ、著者の名声を高めた一冊!
短編なのでそれぞれの話が短く、それでいてきちんと安楽椅子探偵ものとして成り立っているところはさすがといえる。一方で、いわゆる推理モノマニアからすると納得がいかないくらいにライトで、本格推理などに手を出していなかった読者をミステリの世界に引き込むための橋渡しとしてちょうど良いタイプの作品に仕上がっている。 ドラマでも話題になった毒舌キャラの執事がいる大金持ちのお嬢様が刑事という、今時の少女マンガでも絶対に設定しないようなあり得ない世界観といい、不必要に無能な上司といい、こんな人たちがホントにいたら治安はホントに守られるのか心配になってしまうが、そんな設定すらも何となく受け入れてしまうのも著者独自のユーモアのなせる技か。
1投稿日: 2013.12.07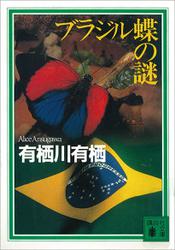
ブラジル蝶の謎
有栖川有栖
講談社文庫
作家アリスと火村英生が活躍する国名シリーズ第3弾!
あとがきで作者が述べているとおり、作品の順番は時系列ではなく、蝶にまつわる話で本書全体がサンドイッチされる構成となっている。 有栖川有栖の本格ミステリ好きには肩すかしを食うようなものもあり、個人的には若干残念なイメージのある本書だが、それぞれにきちんと「そうだったのか!」と思わせる仕掛けは用意されており、一定のレベルは保証されているあたりはさすがである。 個人的に印象に残ったのは「彼女か彼か」と「蝶々がはばたく」の2本。前者は証言の嘘をそんなところで見破ったの?という、明かされてみれば当たり前なのになぜか盲点になってしまっていた点が、後者は地震国・日本を象徴する物語であり、ラストは胸にぐっとくる点が、それぞれ自分としては印象に残った理由かなと思う。
0投稿日: 2013.12.05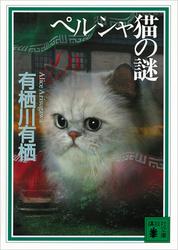
ペルシャ猫の謎
有栖川有栖
講談社文庫
有栖川有栖の国名シリーズ第5弾!
基本的には作家アリスシリーズではあるが、アリスも火村も活躍しない短編があったり、ミステリですらないものも含まれていたりと、バリエーションは豊富。 特に、本格ミステリにこだわらなければ、森下刑事が活躍する「赤い帽子」が痛快である。犯人がわかっていても、それを論理ではなく証拠から突き崩そうとする森下の姿勢が実直で、警察小説としても秀逸な作品だ。 表題作「ペルシャ猫の謎」は何度思い返しても「そんなのありか!」と思ってしまうが、作者の猫好きがそこかしこから感じられて、それはそれで微笑ましい。そのためか、火村も猫好きという設定になっており、ラストの短編は火村の普段からは垣間見えない裏側が見られるということで、ある意味貴重な作品かも。
1投稿日: 2013.12.03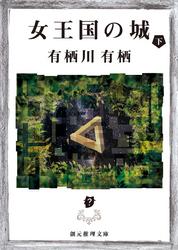
女王国の城 下
有栖川有栖
創元推理文庫
本格ミステリ大賞を取った、学生アリスシリーズ第4弾の下巻!
作者もあとがきで書かれていたように、上巻が静の作品だとするとまさしく動の作品。解決編でものの見事にピースがはまっていくさまもさることながら、そこに至る過程までのアクション小説さながらのやりとりにも手に汗握る迫力がある。 一方で、なぜ人類協会の面々はあんなにもかたくなに警察への通報を拒むのか、江神二郎はなぜこんなへんぴなところに一人でやってきたのか、といった疑問にもきちんと解答が用意され、それがすべて無駄なく、おさまるべき形でおさまっており、ストーリー全編を見返してみるとその伏線の張り方の見事さが改めてよくわかる。新興宗教、UFOといった、人によっては受け付けないであろうネタをベースにして、見事な物語世界を構築しており、そこはさすがである。 しかし、前作から16年という時間はあまりにも長過ぎはしないか。そのせいなのか、こころなしか、火村英生と江神二郎がダブってしまう印象もないわけではなかったが、やはりなんといってもモチ、信長、マリアといった魅力的なキャラクターが脇を固めていて、その軽快なやりとりもこのシリーズの魅力だと思う。ファンとしては長編5作なんていわず、もっと書き続けて欲しいところである。
0投稿日: 2013.12.03
あっくんさんのレビュー
いいね!された数429
