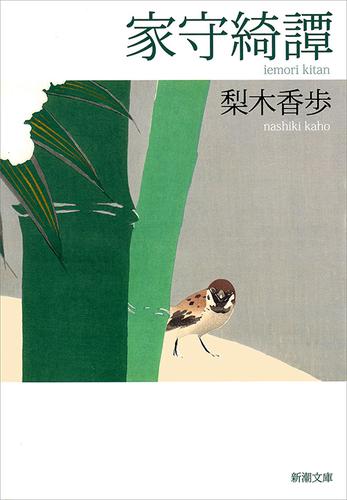
総合評価
(679件)| 313 | ||
| 202 | ||
| 87 | ||
| 6 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログあぁ私が読んでいたいのはこういう本だとしみじみ感じた。ちょっぴり?昔なだけなのに今では失われた、日本人と自然との素敵な関係が織りなす綺譚。大好きな時代の大好きな空間を味わった。
0投稿日: 2012.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さんの「家守綺譚」読了。友人の家を守ることになった物書き「綿貫征四郎」が庭で目にした様々な植物に関わる出来事をまとめた物語。友人「高堂」と飼い犬「ゴロー」が物語に良い味出してます。時代設定が明治くらいで全体的に落ち着いた雰囲気で描かれてます。綿貫の誠実さ、優しさに心温まる作品でした♪
0投稿日: 2012.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログひょんなことから、亡くなった友人の実家の管理を任される作家希望の主人公が、亡くなったはずの友人をはじめ、花の精(のようなもの)や小鬼や、龍に出会ったり、植物と意思疎通を取ったり、狸に化かされたり、という体験をする短編集。 短編とはいえ、話はずっと繋がっており、主人公の考え方や経験値が少しずつ、成長のような変化を遂げていくのが分かるのも面白い。物語の最初には普通の人と思えるよう描かれている隣人や後輩なども、徐々にこの世のものではないような知識や力を持っているらしい言動を取り始め、だんだん「普通のニンゲン」なのは主人公だけのような気さえしてくる展開。 時代設定が「ほんの」百年ほど前、となっているとはいえ、「綺譚」であるには違いない。おそらくは彼岸と此岸を繋ぐ場所として登場する家や池や湖の描写は、リアルであると同時にどこか別次元を思わせる。 どちらかといえば、メルヘンやファンタジーは苦手な部類である私が、さほど違和感もなく面白がって読んでしまえるのは、この本が前述のどちらでもないからだろう。人間には分かり得ない世界があって、それは当然であること、人間がすべきなのは、それらを敬い、受け容れることなのではないか、と静かに訴えかけられている気がする。
2投稿日: 2012.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
期待通り!! 非日常な不思議なものが出てくる話なのに、 主人公はひょうひょうとしてるし、隣の奥さんは普通に対応してるし、 この物語の世界に住んでみたいと思いました。
0投稿日: 2012.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
昔懐かしい古屋の香りのする美しい綺譚。 現れる生き物達は皆、味わい深く、情感豊かで、それに対する家守・綿貫は悠然と時折茫洋としている。ゆったりとたゆたう様な世界観が良い。 風情のある味わい文章を一文一文、じっくりと吟味して読みたい物語でした。 左は、学士綿貫征四郎の著述せしもの。──pg.8 という最初の一文は危うく読み飛ばすところでしたが、つまり綿貫は高堂の物語を書くことが出来たのだと読後思い当たって暖かい気持ちになれました。
2投稿日: 2012.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ留守中の家を預かることになった主人公の身に起こる不思議なお話を集めた短編集です。 湖で行方不明になった友人は掛け軸から現れるし、河童が羽衣を盗まれて泣いているし。狸に化かされるなんて普通の話の方かも…と思ってしまいます。 そんなの当然でしょ?知らないの?という周りの反応がまた面白いです。時代が少し昔の設定なので、ほのぼのと読めます。
2投稿日: 2012.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ天国に行くなら、どうかその実を頬張って、そしてその夢の国でお幸せになって。 もうすぐお迎えを待つ大好きな人を想いながら、そんなことを考えました。
2投稿日: 2012.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これも装丁が気に入って購入した。 何の予備知識も無く、装丁だけで選んだ本は何故か外れが無い。 貧乏文士の主人公が早世した友人の家の守を頼まれる。 その家や界隈で遭遇する異形の者達。 (早世した友人の幽霊、狐狸、子鬼、人魚、河童、等々・・・。) しかし文士は淡々とその者達と交流してゆく。 人であろうと無かろうと、分け隔て無く。 庭や里山、四季折々の風景描写が美しい。 そして日本は、日本語は美しいと再確認させてくれる一冊。 腹ドス黒い自分も少しは浄化されたやもしれぬ。
0投稿日: 2012.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本、たまらなく好きだ。 四季折々の草木や花の描写が印象的。 「目の前に景色が広がるよう」とはよくいうが、まさにそれ。 人だけでなく、ゴロー(犬)も狸もサルスベリも、 出てくるすべての草や木がそれぞれに個性的で魅力的。 好きなエピソードはいくつかあるけど、散り際に暇乞いにくる桜の話が特に好き。
2投稿日: 2012.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ日常に、不思議なものたちがやってくる。彼らは素朴で、しかし色濃く、落ち葉のような儚さをもち、そして愛おしい。やさしく流れるようなやさしい日本語と、あっけらかんとした世界観。ありえない出来事をも日常のなんとない風景にしてしまうその風情が、うまい水のごとくすっと喉を流れ、浸みわたる。
3投稿日: 2012.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ大好き和製ファンタジー。『それはついこの間、ほんの百年前の物語。サルスベリの木に惚れられたり、飼い犬は河童と懇意になったり、庭のはずれにマリア様がお出ましになったり、散りぎわの桜が暇乞いに来たり。と、いった次第のこれは、文明の進歩とやらに今ひとつ棹さしかねている新米知識人の「私」と天地自然の「気」たちとの、のびやかな交歓の記録――。』 わたしも、しずかな山里に庵を結びたい・・・と心から思いました。
0投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログあまり普通とは言えない状況を、なんとも優しい雰囲気で進んでいく物語。 亡くなった親友や、妖たちが主人公に絡んでくる。 この作品の魅力に気がつくには、もう少し、読み込む必要があるかな。
0投稿日: 2012.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ私的梨木作品ダントツ№1。 もう好きすぎて、 何度読み返しても作品への愛が止まりません。 なんとなく、 夏目漱石『夢十夜』を思い出すのは私だけでしょうか? さらさらと水が流れるように 日常も非日常も同じ速さで流れていきます。 今のデジタルな世の中にはもはや存在し得ない世界。 でも、私たちの心の中のアナログな部分が忘れていない世界。 日本という舞台だからこそ書ける作品なのでしょう。 ラストの綿貫が格好いいんだよなぁ、ホント。
2投稿日: 2012.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからは外の草木のざわめく理由を考え直す必要がある。読み終わってすぐそんな事を思った。 そうである理由も、そうでない理由も、まだ確かなものがないのなら。 夢も現も明確な境目はないのかも。そんなスタンスで物事を見ていきたい。
0投稿日: 2012.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間と動植物と子鬼や河童が一緒に暮らしているのに、違和感を感じさせない。 犬のゴローがかわいすぎる。 トルコの村田さんは、村田エフェンディの村田さん? 次読んでみよう。
0投稿日: 2012.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ短い文章の中に空気が詰まっています。 内容はファンタジーなのに、 少し昔の日本ならこんな風景があったのかも、とつい思わせてくれます。ありそうでないんですよね、残念です。 私も百日紅の幹をなでたいです。
0投稿日: 2011.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み応えがある妖怪の類の本です。 妖怪の本ではなく、類の本です。難しい。 一章ずつの題が花の名前になっていて、それぞれが作中で出てくる。 けれどそれらはテーマではなく、あくまでキーワードのように思える。 花々を知らなくても場面の風が想起されてゆく不思議な文章。 花じゃなくて風が吹く。 一番最後の章の、「葡萄」がとても好き。 場面が、想いが、心に残ります。 そして、解説の文章も素敵。 本当にこの本が好きなんだなあ、と思う。
0投稿日: 2011.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の虫SさんとKさんから物凄くお勧めされていた本をようやく読みました。す…すんごい良かった…!大好きですこれ。何度も読み返してます。
0投稿日: 2011.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ庭が好き。 なんだろうね、広義で家の中と言えるのに、その懐の中に異様なのが入り込む感じ。だから庭って外の遠く離れたところよりも異境。内と外との境で、いろいろ入り乱れたグレーゾーン。 なんだか自分の内部が反映される空間だけど、動物も鳥も飼ってに入ってくるし、勝手に巣を作るって、幻想的じゃないだろうか。そんな庭の根源的な魅力を思い出させてくれる作品。 読みやすいのに、わからない部分もちゃんとわからない部分を置いてくれる。続編が読みたい。
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ洗練されたユーモア。 クスりとしてしまう。 身の回りの植物の名を知りたくなった。 普段、小説を読んでも決して思わないのだが、 この本は「実写化が出来たら、面白いだろうな」と思った。 あくまでも、“出来たら”のお話。
0投稿日: 2011.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議な感じ。なんかすごく可愛らしく大事にしたくなる本だった。この感じは表現出来ない。興味ある方は読んでみて下さい。しかし、わたしがもう少し植物のことを知っていればもっとよかったなーと思う。しかも私は漢字もやや、いやだいぶ苦手なので微妙に読めない漢字も多々出て来てしまって少しつっかえながら読む羽目になってしまった。情けない。
0投稿日: 2011.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んだら帰ってこれなくなりそうな雰囲気。 私はあの葡萄を食べに行きたい。あと和尚にだまされたい。
0投稿日: 2011.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ心が凝り固まった時に読んだので(初の梨木さんです)、この独特の不思議さとそれを自然に受け入れる器の大きさに救われました。不思議のありようをそのまま認めるのが自然の流れなんですね。 続いて村田エフェンディも読みましたが、同じ気脈があるようで、夜光る壁を眺める村田とムハンマド、それぞれの神たちが車座のように並んで考え事をする場面やら。そういう不思議が手の届くところに自然と存在していると考えると、至極幸せな気分になります。 そして鸚鵡・・・ 小さな怪異と神々と自然と共存することがこんなに不思議な空気を作り出す、それを描く梨木さんの文章はとても美しいと思います。
0投稿日: 2011.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ舞台が地元なせいもあるんでしょうが、とても懐かしい気持ちにさせてくれる一冊でした。 ほんの百年前の、龍や河童がごく当たり前に人の生活の傍らにあった日本がここにあります。
0投稿日: 2011.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の四季とは、こんなにも様々な草木に囲まれ美しいのかとしみじみ思った。 全体的に不思議な雰囲気に包まれていて、始終狸か狐に化かされているような気分。けれどそれが心地よかった。 『村田エフェンディ滞土録』を読んでいるとより楽しめる作品。
0投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは著者の《村田エフェンディ滞土録》と同じ世界で少しリンクした物語になっている。静かな静かな物語だ。とある家の主である人間と微妙な存在のものたちの日々の物語だ。静かでつかみどころがないが、それがいい。この世界に浸って読書を大いに楽しんだ。
0投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいると、ふっと自然に口角があがっている、そんな本がある。 そんな一冊。 不器用に、ただ物書きをすることで生きていきたい主人公と、そうして「どこか遠い場所」にいて、時折やってくる、友人。 主人公のもとをおとずれるものは、人だけではなく……。 梨木ワールドへ、どうぞ。
0投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ友人に貸したまま帰ってこないので再購入。植物の名前がこれでもかこれでもかと登場して楽しい。人も、動物も、怪異?も、もちろん植物もみんな愛おしい。綿貫が最後、カイゼル髭にもう一度会いに行くところが好きだ。
0投稿日: 2011.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ20111107 読了 移ろい行く日本の四季とともにゆっくりと頁をめくりたくなるような素敵なおはなしでした。 読んでいると心穏やかになり、時にはくすりと頬がゆるみ、時にはすこし涙腺がゆるみ・・・・・・ 人間くさい主人公が触れる彼らが愛おしくなります。
0投稿日: 2011.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ20111016 再読 続編ちょう希望! やさしい空気! 2016410 再読 梨木先生作品は『裏庭』で心を撃たれたときからだいすきなのですが、やはり本作も群を抜いてすきですね! 高堂もゴローも和尚も隣のおかみさんもダァリヤの君も山内も小鬼もサルスベリも面白すぎる。
0投稿日: 2011.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ勿体なかったのは、私自身がこの本に出てくる草木や花の実際のすがたをあまり知らなかったことだと思う。 そのかたちや色や匂いを知っていたらきっと、綿貫になって庭を歩くような感覚を体験できるみたいに読めたんだろうな…さるすべりのヒヤリとすべすべしした感触は読んでいて鮮明に浮かぶみたいだった。 知らないはずなのに、言葉から手ざわりや匂いを感じることが出来るような、みずみずしくて綺麗な文章でした。ぜひ梨木さんの他の本も読んでみたい。
0投稿日: 2011.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ小さい頃に感じていたような夢うつつな世界が小説の中に広がっている。 葉擦れの音が話声に聞こえて怖くて眠れなかった頃のような。 それでいて祖父母から聞かされた迷信に従順だった頃のような、規律がある世界。 日本人であれば懐かしみ憧れる世界観があった。 さるすべりに懸想される主人公、掛軸から昔と変わらない姿で現れる友人、仲裁犬のゴロー。登場人物にも興味をひかれる。
2投稿日: 2011.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治中期を舞台にした日常とファンタジーを描く短編集。各編にはサルスベリ、ダァリヤ、萩、葛、南天など、植物の名前がついている。手元に置いておきたい本になりました。
0投稿日: 2011.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ夢とうつつの狭間が曖昧な話なので、主人公がどちら側に居るのか、 また、読んでいる私はどちらに居るのか? 読後にぼんやりとその世界観に浸ってしまいました。
0投稿日: 2011.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆秋の夜長、読むにふさわしい本◆ 売れない文筆家綿貫征四郎は、亡き親友の実家で暮らすことになる。 庭の草木が伸び始め、栄耀栄華を極めると、おとなしかった庭は自由な振る舞いをするようになっていく…。 日常との境界が危うくなり、うっかり「河童とヒツジグサは間違えやすい」と覚えてしまいそうだ。 サルスベリから始まり葡萄で終わるこの綺譚集は、「しん」という趣が強い。秋の夜長にオススメする。
0投稿日: 2011.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ古風でありながらユーモアもあり、くすりとさせられるところも。装丁も好き。 葡萄の誘惑、「私の精神を養わない」と言った後、踵を返して自分の気持ち伝えに行くところが秀逸。 そして、高堂さんがこの世を去った理由・・・。 無駄がなくて、きれいな文章でした。知らない言葉も多々あり、辞書をひきながら読んだ(私の持っている辞書に乗っていない言葉もいくつかあった)。
0投稿日: 2011.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さんの作品に初めて触れて、大好きになった一冊。男性が主人公なのに、全編通じて薄青のセロファンのような透明感。
0投稿日: 2011.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログゆっくりとした時間の流れとゆったりとした雰囲気、そして不可思議を受け入れる主人公がとても素敵な作品です。
2投稿日: 2011.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ人々の日常生活に溶け込んでいる不思議の数々。たった百年ほど昔には、こんな事が当たり前だったのかもしれない。 田舎で暮らした事なんてありませんが、なぜか懐かしさと郷愁を誘う内容でした。 私も縁側があったり、床の間があったりする家に住んで、庭を眺めて暮らしたいな〜・・・なんて思ってしまいました。素敵なお話でした。
0投稿日: 2011.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかくこの雰囲気が大好きすぎる なんだか心がすっと落ち着く こんな生活も登場人物も妖怪も全てが愛おしすぎる
2投稿日: 2011.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ文体が古風で、独特のリズムと世界観を作り上げています。表紙の通りのイメージの本だと思ってもらえれば間違いない。 自然も怪異もあるがままに受け入れて、日常を穏やかに暮らしている青年が優しくて端正で格好いい。
0投稿日: 2011.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治のころの、琵琶湖付近を舞台とした物語。此方と彼方の境界が交じり合い、近所の人はもちろん、亡くなった人、化け物、植物、動物などと自然に交流していく感じが、すごく面白い。そういえば、我が家のサルスベリは、いま満開だ。
0投稿日: 2011.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ相変わらず、やさしい物語。静かに穏やかに、のびやかな四季と怪奇と魂の交流について語られる。異質なものを異質なまま、とても自然に受け入れて共存する。その寛容と温かさが何より美しい。
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ古き良き日本の趣と、あたたかな笑いと、湿っぽくない哀愁が満ちていました。 そこで起きる出来事に、交わされる言葉に、登場する人物や動物や植物や妖怪たちに、何とも言えず癒されます。「受け容れる」とは尊いことです。
0投稿日: 2011.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログしとしとと雨の降るこの時期にぴったりのお話、と聞いて初めてこの作者の本を読みました。 しっとり落ち着いて品のある和風ファンタジー。四季がとても瑞々しく描写されている。 梅雨時に限らず、どの季節に読んでも、それぞれの四季のよさを感じられそう。
0投稿日: 2011.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログゆったりと、淡々と、それでいて不思議な世界。 ただよう雰囲気をそのまま文章にしたような、不思議な空気を楽しめる本です。
0投稿日: 2011.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ亡き友人の縁で、古い庭付きの家の守人=家守となった学士・綿貫征四郎と、異界のものたちとが織りなす物語。 各章は植物の名を冠されているが、動物も多く登場。それぞれが化身となり、現実と夢世界のあわいを漂っているかのよう。 摩訶不思議で魅惑的な世界である。 生きているものは儚いから懐かしいのかもしれないとふと思う。 狸谷山不動尊・疎水・竹生島といったキーワードから、舞台はおそらく京都・比叡から琵琶湖にかけて。なるほど、京都になら、精霊も魑魅魍魎も多かろう。 *以下、無粋でないものねだり、または的外れなのかもしれないが。この美しい世界を描くのに、もう少し迸るような言葉の奔流があってもよいのではないか・・・? 行間を読むことにこの本の醍醐味があるのかもしれないとは思いつつ、いくつかの話で説明不足・尻切れトンボな思いを抱いた。 *ちょっと漱石の『夢十夜』を思い出した。とはいえ、『夢十夜』を読んだのはずいぶんと前なので、連想が妥当なのかどうかは読み返してみないとわからないな・・・。
2投稿日: 2011.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ亡くなった友人の家の家守をする主人公の目の前に狐・狸・竹の花・仔竜・小鬼・桜鬼・人魚等等がそっと現れる静かな和風ファンタジー。一編は数ページずつでできていて、話も淡々と進んでどんでん返しのようなやま場が無いから隙間時間に気軽に読めた。 これは雰囲気を楽しむ小説。 犬のゴローがとてもかわいい。
0投稿日: 2011.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ長さもちょうどよく、他の人に読むのを薦めたくなる本。 仕事中の昼休みに近所の本屋へわざわざ立ち読みしに行ったこともあった。
0投稿日: 2011.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ百年前の京都の疎水近くの家を守る話をBook1stで昨日買って読んでしまいました。良い本です。 著者は名前を出したり、伏せたり、変えたりして雰囲気を作っています。
0投稿日: 2011.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ雰囲気勝ち。和モノ不思議系特有のどっしりねっとりといた読後感がないというか。ものすごくさらっとしてる。大好きです。
0投稿日: 2011.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこの作者の作品は割と読んで居るのですが個人的にダントツの1位! 全体的な雰囲気がとてもいいです。 人外含めた者達とのどちからというと淡々としたやりとりの中に愛情や友情が感じられます。 この本は何度も読み返してしまいます。
0投稿日: 2011.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ異界のものも理解できないが受け入れる。そんな寛容さを身につけられたらいいなと思うのです。心のゆとりがなくなって、せかせかしている時に手にする本。この本に出てくる植物たちに目を向けられるようなゆとりを身につけたいと思う年度末の今日この頃。(2013/03/07) 『春になったら苺を摘みに』というか梨木さんが大切にしているものがちりばめられている物語だと思う。この本を読んでいると、さざ波だっている自分の心が穏やかになる。なぜか白黒の世界、たまにちょっと渋めのさし色が入る、そんなイメージを思い浮かべながら読んでいる。サルスベリ、ヒツジグサ、木槿、桜、葡萄が特に印象深い。(2011/04/19)
0投稿日: 2011.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ定期的に読み返す作品。ちょっと奇妙な世界だけど、どこか懐かしく、 不思議。ストーリーも劇的な展開があるわけではないけど、 すーっと心のなかに入ってくる。一話一話にちょっと驚いて、ふふふって なって、懐かしくてそして、読んでいるうちに不思議な事が当たり前に なっていたりする。 読んだ後には自分の生活にも気づいたらしばらく「家守綺譚 」の世界が 当たり前にあるような感じになる。
0投稿日: 2011.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ一見短編集なのかな、と思ったのですが、少しずつ繋がっていて何とも不思議な感じがしました。何気ない風景や交流があたたかく、読み終えた後も、家守綺譚の世界に触れている気分になれる素敵なおはなしでした。
0投稿日: 2011.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議な世界感で引き込まれた。 感じるのは日本人の心の奥底にある懐かしい風景であり、身の回りのあらゆる物に命が宿るような日本独特の感覚。 読後は『なんだこの話は、、、』なんだけど不思議と凄く読んで良かった気がする本です。
0投稿日: 2011.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう話大好きです。 死んだ親友が帰ってくる、サルスベリに惚れられる、犬と河童が仲良くなる……。 不思議な事が不思議と認識されない、夢のような世界。 いいなあ。
0投稿日: 2011.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ癒されます。 1話がとても短く読みやすかったのですが、さくさく次の話に移ってしまってあんまり余韻を味わえなかった気が。もっとゆっくりじっくり読めば良かったとちょっと後悔。 サルスベリがとてもかわいいと思うのです。 怪異におろおろするのが綿貫だけで、周囲の人たちは平然として解説してくれるのがなんとも可笑しい。
2投稿日: 2011.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2008年度最高の本。 一編数ページで、全てに草木の名前がついている。 100年程前の、京都? 手にとってよかった。 読み終わるのがもったいなかった。 眠る前に一編ずつ読みたい本。 いつも一緒に居たい本。 昔、『西の魔女が死んだ』で大泣きした以来だけど、 ほんとに素晴らしい! 是非!!
0投稿日: 2011.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログここにレビューを書きました。 http://blog.goo.ne.jp/luar_28/e/d20f30cbade24766d9401b15cef64113
0投稿日: 2011.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文章がとても綺麗で すばらしかった。 特にホトトギスの最後が 印象に残っている。 一編ずつ本にして 持ち歩きたいくらいだ。
0投稿日: 2011.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最後まで読み進められなかった…。そんな本が2000件以上登録されているのに驚き! 作品の紹介 庭・池・電燈付二階屋。汽車駅・銭湯近接。四季折々、草・花・鳥・獣・仔竜・小鬼・河童・人魚・竹精・桜鬼・聖母・亡友等々々出没数多...本書は、百年まえ、天地自然の「気」たちと、文明の進歩とやらに今ひとつ棹さしかねてる新米精神労働者の「私」=綿貫征四郎と、庭つき池つき電燈つき二階屋との、のびやかな交歓の記録である。―綿貫征四郎の随筆「烏〓苺記(やぶがらしのき)」を巻末に収録。
1投稿日: 2011.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ百年と少し前の、日本のどこかにある地方が舞台。もの書きの主人公・綿貫が、亡くなった友人の住んでいた家に、持ち主に頼まれて住み着くようになったところから話が始まります。 雨が降ると、最近逝ってしまったはずのその友人が掛け軸を通ってふらりと姿を現す。庭のサルスベリの木に懸想(!)されてしまって「どうしたらいいのだ」といいながらも、ときどき庭で本を読んでやる。床を突き抜けて部屋の真ん中に生えてきてしまったカラスウリを、伐らずにそっとしておく。河童が庭に迷い込む。狸に化かされる。 主人公の人柄がなんとも言えずいいんですよね。清廉潔白だとか器が大きいだとかいうことではなくて、小人なので、見栄を張ったり、失敗したり、慌てたり、迷ったりと忙しいのだけれども、でも人がいい。 掛け軸から出てくる友人・高堂も、ものすごく魅力的です。他にも犬のゴローとか、ちょっとだけ出てくる小鬼や河童といった脇役たちも、それぞれに味があって。 登場人物の魅力だけにとどまらず、描き出される四季折々の情緒もたまらない。何度でもくりかえして読みたくなる一冊です。
0投稿日: 2011.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「コレ!お薦めの本だから読んでみて!きっと気に入ると思う。」 と言って妹が貸してくれた本「家守綺譚」は 「西の魔女が死んだ」の著者、梨木香歩さんの小説でした。 といっても「西の魔女が死んだ」は読んだことがなく、 映画にもなりましたが映画も見てないんですが… ところでこの本、学士であり物書きである主人公:綿貫征四郎が 書いたストーリーという設定になっている。 四季折々の花の小見出しがつけられていてどんな話かと思い 読み進んでいくと現実もあり現実離れした感もありで、 いつしかまるで夢うつつの中に居るような感覚に陥り 気がつくと一気に一冊読んでしまってましたw 空の向こう側や水底の景色、普段と変わらない町の裏側… そんな想像でしか知らない世界がある日当たり前の顔をして 近づいてくる。 この主人公の綿貫は作家の性なのか、 それとも元来の性格なのかさほど驚くこともなく そんな奇妙な出来事を受け入れる事ができる器量を持っていて 又、起きる出来事に惑わされないだけの「自分」というものを しっかり持っている人物。 だからこそ奇妙な状況の方から綿貫を好んで 近づいてくるのかもしれないのだが… 目に見えないモノの存在の有無をはっきりさせることは難しい。 有ると思えば有るし無いと思えば無いのかもしれない。 見ようと思えば見える(目で見るのではないかもしれないが) 心が拒絶すれば何も見えないのだろう。 ただ私は目に見えないモノの存在や法則を信じてる方なので そう思うのかもしれないが私にとってそれは生きるという意味での プラスのエネルギーになっていることは間違いない。 そういうのを「スピリチュアル」と呼ぶのかもしれないけど。 昔の人たちは今の人より何倍もそういうことを 生活にうまく取り入れて生きていたんだと思う。 自然との共存。 大きな力の中での人間という生物のちょうどいい位置も 解っていたのだと思える。 この本の内容のように… 読み終わって顔を上げたら少し視界が変わったような気がした。 感覚的なものをどう説明していいか分からないのだけれど… ほんの少し、答えの端っこが分かったような気がした。
0投稿日: 2011.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログすでに設定が不思議世界ありで話がすすむ。 それはいい。好きな設定。でも物語の起伏?がない・・・。 主人公の不思議日記。
0投稿日: 2011.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの本を読むと日本語というのは、 なんて奥床しい言語なんだろうと、 まるで語学を学び、親日派に転ずる外国人のように気づきます。 ただ、個人的に(というか、ここで書いてることは全て個人的なことばかりなんだが) 寓話的な展開は苦手ではあります。
0投稿日: 2011.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011.02.04 最初の数行を読んで「この本はいい」と感じた。 こう思う本って意外と少ない。 『ホテルカクタス』以来か。 この薄い本を読むのに、2週間もかかった。 しかし、それだけかけて読んでもいい本だと思う。 そして、何度読んでもいい本だとも思う。 言葉が、描写が、とても美しい。 風景がすぐそこに現れるかのようで。 梨木香歩作品は『西の魔女が死んだ』しか読んだことがなかったが、これを読んで他のも読んでみたいと思った。
0投稿日: 2011.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ情景描写が多く、また人外キャラも多数出演で、随筆調の短編の連作。勢いでものを読むクセのあるわたしには、中盤までちょっとつらい。おもしろくないというわけではなくて、ばーっと飛ばしてよめないのでつらかった。 キャラがつかめ、すこしストーリーが動きだした後半からは一気に面白く読めた。
0投稿日: 2011.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議なこともそのまま受け入れる、懐の深さ、優しさがにじみ出ている文章だ。文明開化後、徐々に文化人へ、近代人へと進んでいこうとしながらも、まだ旧時代の精神を残している、そんなあわい。黒でもない、白でもない、あやふやさへの愛おしさに溢れている。
0投稿日: 2011.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ前から気になっていた本だったので文庫で買いました。 単行本のデザインも良かったんだけどなぁ。 河童や人魚がいても平然としているご近所さん達と、綿貫の優しさが大好きです。 一番好きなのは白木蓮の章かな。
0投稿日: 2011.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初に読んだのはいつでしたか。 再読をほとんどしない私ですが、何年かぶりに 読みました。 何度読んでも、好きなお話。 自分の言葉で「好き」を説明しがたいのですが 不思議の世界なのだけれど、 もうなくしてしまったもの、 大切にするべきものが描かれていて 心つかまれるのかもしれません。 「わたしの精神を養わない。」 痛いほどに、分かってしまいます。 言葉をもたないものたちの「声」が聞こえる やさしいお話。
0投稿日: 2011.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構真面目な本かと思い、読み始めてみれば河童や人魚などを既に信じようとしない近代を時代背景にどこか馬鹿げながらも、登場人物はその迷信的生き物を信じざるを得ない方向で物語は進んで行く、読んで居て思わず顔がにやついてしまう作品。 そんな迷信もありうるかもと思わせるのどかな田舎で繰り広げられる不思議な正に綺譚集。 気持ち良く読みきる事が出来ます。
0投稿日: 2011.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう雰囲気好きです。 なんだろう、短いけど章がものすごく細かく分かれてるせいか結構「読んだ!」って気になる。 サルスベリがお気に入りです。
0投稿日: 2010.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ女友達の『コトリさん』とは、なんだかんだいって長いつき合いになる。 小田原にいた時からだから、もう7年くらいだすかな? とはいえ、会わない時には平気で1年くらい経つこともあり。 1年ぶりだとしても、昨日もそこに居たように、当たり前に話す。 その関係は『トクベツ』な気もするだすが、とても近い存在とはいえない 「だったらきっと、恋人にでもなってるだすよ。」 のんびり屋の彼女。 走る姿は、2度しか見たことがない。 (意外に早い)。 つかず 離れず 遠くで気になる。 コトリさんとネコは、【野良猫の距離感】に似ているだす。 ただ、『本』に関して言えば ネコと彼女は嗜好が合わない。 「いや、そうじゃないな。」 今から二人で本屋に行くとする。 一乗寺の恵文社なんかがいいだすねぇ。 そこでたとえ同じ棚を覗いていたとしても 目に止まる物は、決してシンクロしない。 でもネコは・・・・。 コトリさんが手にしたその本が気になってしまう。 どうしてかな? 感性が違うからこそ、その面白さを知りたくなるような、いわゆる野次馬根性のなせる業? ふと、テーブルに置いた本を手に取る。 『家守奇譚』 数年前にコトリさんから譲り受けたものだす。 この、優しい色の本 きっと、コトリさんから貰わなかったら、死ぬまで手に取りそうにないなぁ。 スルスルと猫に擦り寄られるように、物語は、はじまる。 軽く読むつもりが・・・。 ついその世界に引き込まれただす。 柔毛の奥に感じる生暖かい物語は、むしろ今の季節に潔い。 おもむろに、自分で漬けておいた『浅漬け』を冷蔵庫から取り出し、ポリポリやりながら酒を飲む。 ……ポリポリ………ポリポリポリポリ…ポリポ…リ…。 窓の外で、野良猫が・・・『にゃあ』と、ひと鳴き。 ハッと気がつけば、「もうこんな時間?」 ヤラレタ~。 化かされたように呆然と押さえる目頭の奥で、コトリさんが「ニャハハ」と、笑っていた。 ふと思う。 猫は・・・ 『気まぐれ加減』や『仕草』に見立てて 女性と重ねることが多いけど 『臆病加減』と『だらしのなさ』は どちらといえば、やっぱり男に近いんじゃないかにゃー?
0投稿日: 2010.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ奇譚という話が好きで、これまでにそういうものを幾つか読んで来たけれど、この本に入っている話はそれまでの奇譚と比べて、分かりにくく言えば、なにも起こらないのです。少し言い方が悪いかもしれないけれど、例えば河童の皿が出て来たとき、こちらとしては少し構えてしまいます。いつ脅かされるか分からないから。でも、物語はそのまま、寿命間近の電球がぽっと切れるように、そのまま終わってしまう。頁も変らないまま次の物語に移ってしまうから、うっかりしていると話が終わったことも気付かないほどに。ゆるやかに、連綿と、蓮の葉が池の畔に続いていくように、ひっそりと。と言ってみて、まだ最後まで読んでいないんですけどね。へへ。
0投稿日: 2010.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「それは、ついこの間、ほんの百年すこしまえの物語」 帯の紹介に思わず引き込まれて読んだ『家守綺譚』。 しがない物書きの綿貫は、亡くなった友人高堂の家に住む「家守」でもある。 庭のサルスベリの木に恋され、亡くなった友人の高堂が掛け軸から頻繁に現れ、木蓮の木から竜が生まれ、池にはカッパが流れ着き、桜が暇乞いにやってくる・・・・。 綿貫の、その何とも柔らかく愛情に満ちた視線の先にあるいつもの「日常」。 大きな事件があるわけでもなく、さりとて単調でもなく、静かに過ぎゆく季節を綿貫は淡々と語り継ぐ。 そうそう忘れてはならないのが、犬のゴロー。 彼の活躍もまた見逃してはならない。 ささくれだった気分の時に読むと不思議と心が穏やかになれる、私にとって大切な一冊です。
0投稿日: 2010.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ庭の木に恋され、狸に化かされ、河童が家で脱皮する。 そんな非日常と日常が重なり合っていた頃のお話。 湖で亡くなった学友・高堂の家に、 家守として住まうのが、売れない物書きの綿貫。 この家はとても変わっている。 カッパが訪れ、小鬼が木々を走り回る。 綿貫は庭のサルスベリに好かれる。 非日常的な出来事が次々と起こるのに、綿貫は淡々としている。 自分はしがない家守というスタンスがいい。 日々いろいろなことが起こるのだけど、当たり前のように日常が過ぎているように読めてしまう。 何なんだろう、この本・・・・。
0投稿日: 2010.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ綺麗な本を読んだ。 昔の日本はこんな風にゆるりと時間が流れて 植物にも気持ちがあり、いろんな物に命があったんだろうなと思わせる。 犬のゴローが可愛い。
0投稿日: 2010.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこの作品の雰囲気が大好きです!! 季節の植物が題された短篇が淡々とさらりと綴られている。 http://feelingbooks.blog56.fc2.com/blog-entry-79.html
0投稿日: 2010.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログここに描かれた、主人公綿貫征四郎さんの「日常」には、奇妙なものがたくさん登場する。 それも、当たり前の顔をして。 河童、主人公を好きなサルスベリ、掛け軸から出てきた亡くなった友だち・・・ 挙げだすとキリがない。 でも、ぜんぶが普通の顔をしてそこにいるから、あぁ、そういうものかと思ってしまう。 この小説に描かれた世界は、本当に不思議。 懐かしいようで、不気味でもあり、温かくて、優しいのに、切ない。 本の厚さとしては薄い小説なのに、すごく内容が濃くて、色んなことが起こってるのに何も変わってないかんじ。 不思議。
0投稿日: 2010.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログさるすべりが住人に恋をする。 そんなところからストーリーがはじまる。 不思議な世界。登場人物がひょうひょうとしていて、 おもわずくすりとわらってしまう。。
0投稿日: 2010.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「今1番好きな本は?」と聞かれたら、この本を答える。 何せ、ここ1ヶ月で4回ぐらい読みなおす程だ。 自分が京都に住んでいたことも、多分影響しているが。 「ホトトギス」の、何度でもさすってやる、 のくだりで、いつも涙が出てくる。 丁寧で、優しくて、美しい、幻想的な京都の話。
0投稿日: 2010.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さんの小説はどれも好き。 現実とあの世?!の境があいまいで、本作でも主人公の綿貫は、 庭に咲いているサルスベリに恋をされたり、 死んだ親友がかけじくの絵からときどき遊びに来たり。。。 ゆるやか~な気分になる一冊。 梨木さんの小説は、精神安定剤。
0投稿日: 2010.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ亡き友の実家で家守をする事になった新米小説家と 彼の周囲で起こる不思議の数々。 目次に並ぶ植物の名前を見るだけでも”四季のある国に生まれて良かった”としみじみしてしまいます。 ちょっと気が弱くておろおろする時もあるけれど 芯は毅然と凛々しい主人公と 不思議をあっさり受け入れる懐の広い隣人とのやり取りが愉快です。
0投稿日: 2010.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログひとつひとつの話が短くて読みやすい。 日本人ならではの感性と視点。 なぜか懐かしい。癒されます。
0投稿日: 2010.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「四季折々、草・花・鳥・獣・仔竜・小鬼・河童・人魚・竹精・桜鬼・聖母・亡友等々々出没数多…」と裏表紙に書かれているように、早世した友人の家に「家守」として住まう若き物書きの主人公と植物や不思議な生き物たちとの交友の話です。 不思議な生き物たちにも顔の広い主人公の飼い犬のゴロー。情報通のお隣のおばさん、おしょう、美しいダァリヤの君…人間達も変わった面々がそろっている。 終始ゆったりとしたテンポで物語りが進んでいくのに、なかなか緊迫したラストがまっています。 いちばん好きなくだりは狸の恩返しの話です。
0投稿日: 2010.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログスピードとリズム重視?の本を続けて読んだので、ゆっくり落ち着いて読める作品が心地よい。日本語がきれい。
0投稿日: 2010.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ好みじゃないと思って一度読むのを辞めた本でしたが、半身浴しながら読んだらとても心地よく読めました。ゴローがかわいい。
0投稿日: 2010.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ友人から去年の誕生日に戴き、なかなか機会がなかったのですがやっと読み終えました。 私的にはすごく好みなお話でした。 日本人は四季と植物と共に生きている。人間と動物と妖怪とも。 植物との関わり、四季の描写がとても好きです。 どこか怪奇で不思議な体験を自然体で当たり前にように受け入れていく生活がとても魅力的だし、日本ならではの感性で習慣で、どこか懐かしい気さえした。 天気や季節に左右される生活は少し不便で、たまにいたずらに関わる人や人以外の存在に困らされることもあって、でもそれを仕方がないと楽しめることの良さ。 綿貫と高堂の友人関係にも憧れる。 わたしも素敵な庭を持ちたい。
0投稿日: 2010.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ連作短編、かな。お話は繋がってるけど1章ずつ軽く読めます。 ほんの100年ちょっと前の、日常と不思議がすぐ隣に同居してた日本のお話。 四季折々の素敵風景を舞台にした、主人公さんといろんな人ならざるひとたちとの交流記録、です。 淡々と美しくてほわほわ。憧れる!
0投稿日: 2010.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今から100年ぐらい前の設定で、主人公は売れないもの書き。 家にある掛け軸から死んだ友人の幽霊がボートに乗ってやってきたり、河童や狸が出てきたり、サルスベリに惚れられたりする、不思議な小話が集まった本。 またこのサルスベリが可愛い!ヤキモチを焼いて拗ねたりする。主人公も自分の書いたものをサルスベリに読んでやったりして、何ともほのぼのした光景。 他の登場人物(妖怪、精霊の類も含む)も面白い。和風ファンタジーという感じ。 それに植物の名前がたくさん出てくるからか、四季の移ろいが感じられてとっても綺麗。本当に綺麗。 読んでいるとしみじみと、「日本」っていう雰囲気が漂ってくる。 大好きな小説。こんな生活したい。
0投稿日: 2010.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ珍妙な出来事がいくつも起こるのだが、主人公を取り巻く環境はいつも悠々としている。とうの主人公も、驚いたりムッとしつつもやはり悠々としている。彼らの懐のふかさや押し付けがましくないところがなんともいいんだよなあ。ひらり落ちてきた吹けば飛ぶような花びらを愛でている感覚。
0投稿日: 2010.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログどこか懐かしくて切なくて、けれど還りたい場所はここにある。 夢幻と幻想が同居して一つの現実世界になるのかもしれない。
0投稿日: 2010.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログとても素朴で可愛らしいお話。 全体としてゆるりとした流れで無理がない。 私もこのような生活がしてみたいと心底憧れる。 そして、主人公の人柄が好きだ。 しかし、オチはぐっと胸にくるものがある。 読んだあとに、「いい話だなあ…」と素直に思える作品。
0投稿日: 2010.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ亡き友の実家で家守をする事になった駆け出し作家の綿貫征四郎の物語。 元家主で亡き友人高堂が掛け軸の中からぬっと出てきたり、 庭のサルスベリが征四郎に恋をしたり、 とにかくそんな"人でないもの"が多数登場し、主人公と交流する不思議なお話でした。 犬のゴローが妖怪達の間でどんな役割を担っていたのか、 番外編で書いて欲しい気がしました笑
0投稿日: 2010.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしい本に出会えたな、 というのが一番の感想。 こういう雰囲気の作品は これまで読んだことがなかった。 とても日本らしい「和」を感じさせる ファンタジー。 和むし、美しいし、不思議だし、 笑える。 自然の描写がとても印象的。 これまで植物には全く興味を 持たず生きて来たけれど、 随分勿体ないことだったと痛感。 征四郎と一緒にもっと多くの 不思議な体験をしたかった。 読み終えてしまうのが 残念に感じられた一冊。
0投稿日: 2010.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログある種のファンタジーだが決して派手な話ではない。どちらかといえば淡々と物語は進むのに、気がつけばその世界に引き込まれている、そんな作品。 縁あって亡くなった友人の家を預かることになった主人公が出会う摩訶不思議が描かれている。不思議が当たり前の事として受け止められている事に、主人公は最初は戸惑いを覚えていたが、自然となじんでいく。 文章の流れる感じがとても綺麗で、私は読み終わった後、ほんわり、そしてちょっとせつなくなります。大好きな作品の一つです!
0投稿日: 2010.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代も場所も主人公の年齢も不明の小説。ちょっと昔の不思議なお話。だけどすんなり入り込めて、想像を膨らませてしまう。 主人公のひょうひょうとしたキャラクターも魅力的だけど、周りの登場人物たちがとてもいい。 主人公に恋するサルスベリや、犬のゴロー。なんでも知ってる隣のおかみさん。 心がほっこりする作品だった。シリーズで読みたい。
0投稿日: 2010.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ綿貫征四郎は、学生時代に亡くなった親友・高堂の実家に住んでいる。 高堂の父親から、年老いたので嫁に行った娘の近くに隠居するから、 この家の守をしてくれないかと頼まれたからである。 綿貫は、文筆家だが、決して売れているわけではない。 非常勤で働いていた英語学校正職員の話があっても、 本文は物書きだから、そちらの方に精を出したくないと思ってしまうような性分。 住まっていることで月々のものがもらえる家守の話は、渡りに船だったのだ。 ここは、「此方」と「彼方」の境界線が実にあいまいにして、 それでもやはり境界はある、という世界。 『西の魔女が死んだ』を読んだ時も、 「異なる考えをどれも包み込むように共存させているような 穏やかな力が作品世界全体を支えている」と感じたのだが、 この家守綺譚にも同様のものが流れている。 学生時代ボート部だった高堂は、山を一つ越えたところにある湖で ボートを漕いでいる最中に行方不明になっていた。 その高堂が、掛け軸の中から現れる。 ボートを漕いでやってくる。 ―どうした高堂。 ―逝ってしまったのではなかったのか。 ―なに、雨に紛れて漕いできたのだ。 ―会いに来てくれたんだな。 ―そうだ、会いに来たのだ。 高堂はこともなげに云うが、綿貫も自然とこの出来事を受け入れている。 本書は、すべて植物や鳥の名前で章題が立てられており、 全体で、綿貫が家守を始めてからちょうど1年の季節がめぐる。 サルスベリに懸想されたり、犬のゴローに懐かれたり、 ヒツジグサが「けけけっ」と鳴くと思ったら河童が迷い込んでいて それをゴローが滝壺まで送り届けたり。 不思議なことが淡々と起こる。 綿貫の受け入れ方が淡々としているから、 その不思議な出来事が日常として起こっていても 全くおかしくないように思えてくる。 それらの出来事を普通に受け止めるのは、綿貫だけではない。 綿貫に季節のものを持ってきたり、おすそ分けをしてくれたりと なにくれなく面倒見てくれる隣の奥さん。 (実は、犬のゴローのことを気に入っていて、 綿貫の方がゴローのついでだという説もある。) 彼女は、ゴローが持ってきた、綿貫には何だかわからないものを見て、 河童の抜け殻に決まってますと自信満々に、一目見ればわかるというような人。 「おかみさんの論理は、机上で組み立てたものではなく、 すべて生活実感から出てくるものであるので、 非常な説得力と迫力を持つ」 と綿貫は思っている。 このお話の世界が「生活実感で出てくるもの」である不思議。 でも、読んでいるうちに、こちらも意識をふっとずらせば この物語の世界は実感のある出来事になるんじゃないかと思えてくる不思議。 綿貫のところに原稿を取りに来る後輩の山内も、 そういったことを当たり前に思い、説明までしてくれる。 山内は、綿貫がサルスベリに懸想されていることも自然に受け止め、 サルスベリを入れ替えてリサベルと女性の名前を付けて 呼んであげたらどうだなんて言ってきたりする始末。 高堂が此の方にボートでやってくることを知ると、 先輩に湖の底のことを聞いて、ぜひにもそれを書くようにと頼むくらいである。 高堂は、掛け軸の中からだけではなく、いきなりふっと現れたり、 しばらく来なかったりするが、現れて綿貫と言葉を交わすたびに、 高堂自身のことを、読者もだんだんわかってくる。 綿貫は、山内から頼まれた湖の底のことを、高堂に訪ねる。 高堂は、それはやはり自分の目で見るのが一番だろうという。 綿貫はそれができるのかと半信半疑で訊くが、 お前の覚悟次第だと言われるのみだった。 高堂の存在は、「此方」と「彼方」は それほど遠いものではないのではないかと思わせる。 だが、確かに綿貫は「此方」の者で、高堂は「彼方」の者なのだ。 かたや肉体を持って今を生きる者、かたや肉体を手放した者。 高堂は語れないものについては、 「おまえにそれを語る言葉を、俺は持たない。人の世の言葉では語れない。」 と説明をしないが、 綿貫は、高堂に無粋だと言われても、 「しかし俺はそれを言葉で表したいものだと思う。」 綿貫は、これが高堂と自分との決定的な差異なのだと悟る。 高堂と綿貫の違いをはっきりと示すのが、 最終章の葡萄に登場するエピソードだ。 綿貫は、「私は与えられる理想より、 刻苦して自力でつかむ理想を求めているのだ」と気づく。 そして、同時に、それでも彼方に憧れる気持ちもあることも認めている。 これは、『西の魔女が死んだ』で、 おばあちゃんが語っていた、魂の本質の話ともつながる。 魂は身体を持つことによってしか物事を体験できないし、 体験によってしか、魂は成長できないんですよ。 ですから、この世に生を受けるっていうのは魂にとっては願ってもない ビッグチャンスというわけです。成長の機会が与えられたわけですから。 そして・・・。 いちばん大事なことは自分で見ようとしたり、聞こうとする意志の力ですよ。 こんなおばあちゃんの声が、どこかから聞こえてきそうである。 最後に、綿貫を此方に留めたものは、いかにも綿貫らしい。 「私には、まだここに来るわけにはいかない事情が、他にもあるのです。」のあと、 彼がなんと言ったのか、ぜひ読んでみていただきたい。 不思議な者たちに見入られながら、 彼方の者と言葉を交わしながら、 それでも、確かに綿貫が此方の者である理由が この葡萄の章に集約されている。 本書の綿貫の気づき、そして、『西の魔女が死んだ』で おばあちゃんからまいが学んだことは、 「魂と身体の合体であるわたし」を味わって生きることの大切さであろう。 それは、常に梨木香歩作品の根っこに存在するものに思えた。
0投稿日: 2010.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ四季折々の植物と共に、季節の移り変わりを感じながら過ごす綿貫が羨ましく思えるほど、なんとも情景描写が美しい作品でした。 そして、物語の途中に出てくるゲーテの詩は思わず声に出して読んでしまうぐらい素敵でした。 いつも通勤の電車の中で本を読むのですが、この本を読んでいる時は、田舎の家の縁側でくつろぎながら読んでいるような気分にさせられました。 紅葉が綺麗な秋になったら、再読したいです♪
0投稿日: 2010.07.16
