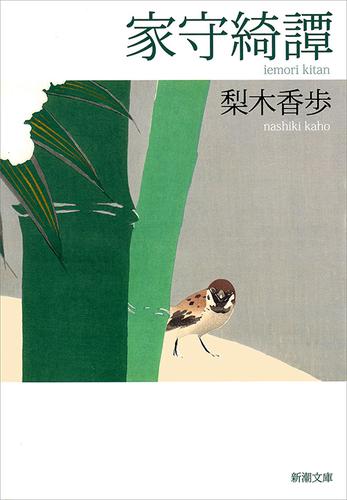
総合評価
(679件)| 313 | ||
| 202 | ||
| 87 | ||
| 6 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ文庫化で書下ろし有とのこと。単行本で読んだけど話を忘れてる・・・(-_-;)後日談発売したので再読します。
1投稿日: 2013.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ和風ファンタジー連作。舞台は懐かしの京都。綿貫のような高等遊民的生活に憧れる。犬も死人も河童も花も鬼も出てきてほんわかゆったり時が流れてゆく感じ。よい。
1投稿日: 2013.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと昔の、自然が豊かな日本が舞台です。 豊かすぎて、植物は嫉妬してくるし、妖怪が人間に混ざって商売したりしています。 私はこの方の自然の風景の描写が大好きです。 一話一話が短いので、通勤や寝る前の一冊にちょうどいいのも嬉しいです。
1投稿日: 2013.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公のぼんやりしているところが若いおたく女子に受けそうと思いつつも不思議を不思議に書かない梨木香歩の無邪気な(それでいてしたたかな)筆力に舌を巻く、ほのさみしい、でもいとしい、すこしくすぐったい、やさしいかわいい綺譚だと思う。f植物園のぞくりとした感じの方が好きだけれどこれもまた違った雰囲気で好き。梨木さんはぼんやりとしてまじめだけれどだめな男性を主人公に据えて書くのがすごくうまい。
1投稿日: 2013.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的にあたりはずれの激しい梨木さんなのですが、これはあたりでした。 植物、動物と意思疎通ができたら人間はこんなに横柄にならなかっただろうに。 植物も動物ももっと大切にできただろうなあなんて、ちょっと筋違いですが感じてしまいました。 偶然ですが近々続編が出るらしいのでそちらも読みたい。
4投稿日: 2013.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ四季折々の風物や植物、どこか憎めないあやかし達と交歓し過ごす素敵な日常。どのお話も短いのに豊かで濃密な雰囲気が満ちていて、それがとても心地よく味わいながら読みました。昔は当たり前だった旬の物を愛で食し、例え河童や人魚、亡き友が現れてもすっと受け入れ馴染んでしまう懐の深い彼だから沢山の人や妖怪に愛されているんだろう。そんな日々に心が惹かれ、懐かしく感じました。きっとこれからも此方と彼方の中で様々な物に出会い、驚き、それを楽しみながら家守として優しく温かく、生活を営んでいくんだろうな。大好きです!
1投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ話自体は静かに静かに進行し、大きく盛り上がる事もない。 でも何かしら惹かれるものがある気がする。 この小説のどこが良いのか、自分には上手く説明できないけれど。
1投稿日: 2013.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ何を見聞きしていればこのような作品が書けるのかと、驚嘆の念が心を突いている。作家とは、げに恐ろしきものである。 花鳥風月に怪異を加え、人情味あふれた物語を、どこかとぼけた語り口で描いている。体裁は講談のように達者であり、洒落っ気が効いていて、本当に読んでいて楽しかった。 明治の私小説を範としているのか、実に男らしい女々しさが主人公に表れていて、よく出来ていると思う。語彙の選び方も、文章の端正さも、非常に優れたものだ。 小さなエピソードで、少ない言葉で、これだけ雄弁に語れるのは童話作家ゆえのことなのだろうか。語りすぎない語り口が、物語にふくよかさを添えている。 素晴らしい作品だった。初めて読んだこの方の作品がこれで良かったのか、どうなのか。 ああ、一つ。惜しむらくは解説かな。愛情のある良い解説だが、少し中身を語りすぎている。もったいないところだ。
2投稿日: 2013.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「日がな一日、憂いなくいられる。それは、理想の生活ではないかと。だが結局、その優雅が私の性分に合わんのです。私は与えられる理想より、刻苦として自力で掴む理想を求めているのだ。こういう生活は、--私の精神を養わない。」
1投稿日: 2013.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのユーモアは独特だ。くすぐりが堪らない。古風で質朴で豊穣な世界。大好きな本。巻末の「烏〓(草冠に斂)苺記(やぶがらしのき)」がまたいい。
1投稿日: 2013.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さんの小説で一番好きな本。 梨木さんの作品では鳥がよく出てくるし、自分が小鳥好きなので、表紙の絵にもやられてしまった!
2投稿日: 2013.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。 書き下ろしがあるということで文庫本を購入しました。 いやほんと、なんど読んでも面白いですね。 単行本の方の装丁も、お話の雰囲気に合っていてよかったのですが、こちらもかわいくて好きです。 カバー装画:『雪中竹』神坂雪佳 梨木さんの文庫本は、どの作品も装丁に統一感(色彩など)があってとてもステキです。思わず全部そろえたくなります。
0投稿日: 2013.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ緊迫した場面は少ないが、生と死を越境する深い意識層の物語が区切りよく進む。胸踊ると言うより静けさ、動じなさを味わう。トルコの教会、下宿の婆さん、筆が進まないと言う表現、私の精神を養わない、に興を覚える。
1投稿日: 2013.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治の所謂書生さん的な主人公が、亡き友の実家の家守をしながら物書きをして暮らす、一年間のお話。 「百鬼夜行抄」のような、河童、小鬼、かわうそ、桜鬼、狐、狸などが、ごく身近に存在する世界。 主人公だけに見えるのかと思いきや、 隣のおばさんに尋ねると「そんなことも知らないのか」といった調子で何でも教えてくれる。 主人公のぼんやり具合と相まって、恐ろしさは全然なく、ほのぼのとしたユーモラスな世界観が素敵です。 大人の童話といった雰囲気です。 「小さな恋のものがたり」みたいに季節の花々が取り上げられ、四季の描写は枕草子のよう。(恋物語はないです) とても日本的な小説です。 筋書きを追うような話でもないし、暗い気持ちになることもないので、旅行のお伴にぴったりな一冊だと思います。
2投稿日: 2013.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこの作品、大大大好き‼ 私のツボをこれでもかというくらい確実におさえている。 「サルスベリのやつがお前に懸想をしているのだよ」 出だし数ページ目ででてくるこの台詞でこの作品に夢中になると確信した。 河童や小鬼が出てくる類の奇々怪々な話はどうしても児童向けな印象だけれど、この「家守奇譚」はちょっと大人な雰囲気。 レトロで色気ある文体が雰囲気作りに大きく貢献している気がする。 各話に登場する四季折々の草花の名前を毎回タイトルに持ってきているのも粋。個人的には「葡萄」という話が印象的だった。 こんなにも読後感が良い作品は久しぶり。子どもの頃、夏の終わりに感じた懐かしいようなどことなく切ないような感覚が後を引く貴重な一冊となった。
1投稿日: 2013.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ日がな一日憂いなくいられることは、 私の精神を養わない。 この言葉に心うたれた。 自然との不思議な関わり方。小鬼や狸や掛軸からでてくる亡き友人、さまざまな者との関わり合が、彼を豊かにする。
2投稿日: 2013.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ家をあずかる人の周りで起こる、すこし不思議な物語。題名どおり、この「家守奇譚」はそんな物語です。 舞台は関西方面の湖のほとり(滋賀もしくは京都?実在する寺の名は出てきますが、正確な舞台はないかもしれません)、季節は梅雨時期から始まり、桜が散ってまた梅雨に入るまでの一年です。時代は明治末から昭和初期といったところでしょうか? 売れない若手作家・綿貫を主人公に、庭に生い茂る植物、それを目当てにやってくる動物、高堂家周辺の自然、近所の知人友人、化けて出る親友。日本の四季を通して、これらが美しく書かれています。僕が感じた本書の魅力は、この美しさです。短編一話を読み終えるたびに、読み終えたばかりの一話分の風景描写を追いかけながら瞼の裏に主人公が見る世界を想像することができます。 主人公のいう「教養」を少しは育むことができたかもしれません(笑) 「どれくらいの不思議まで人はそういって許せるものなのか、ふと気になった。」
1投稿日: 2013.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最初、タイトルを「やもりきたん」と読んでいた。この雀の表紙絵に一目惚れして購入。 亡くなった友人の実家の家守(読みは「いえもり」が正しい)として住み込むことになった主人公。幽霊と対話したり、狸に化かされたり、サルスベリに惚れられたりと「現実的」とか「科学的」ではない日常が、主人公の語りで淡々と綴られているが、ちっとも恐怖はなく道で猫に出くわしかの如く自然に語られている。 「サルスベリのやつが、おまえに懸想をしている」 と幽霊に言われても、主人公は「ナンだそりゃ?!」なんて目を丸くして言い返すことはない。「実は思い当たることがある」と考え込む。 「家守」では主人公が庭に植わっているものを伸び放題に任せつつも花のほころびなどの変化を敏感に感じとっている。植物にはまったくといっていいほど興味はないが、こんな生活もいいと羨ましくなってしまうのである。 この本、文庫本の表紙絵も一目惚れだったが、単行本もまた綺麗な装丁なのでつい購入。 同じ本の文庫・単行本を持つのは初めてだがちらっと中身を見ると文庫本だけについてるおまけ以外にも違いがあった。単行本にはほとんどルビがないのである。単行本を先に読んでいたら亡くなった友人の名前も読めなかっただろう。 ・・・と、ちょっと感想から脱線したが、この不思議な世界にひたすら浸りたくなることがあり、折にふれて読みなおすことの多い本。
1投稿日: 2013.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログそれをそのままに受け入れる。ただその作品。納得よりもわかると言った感じ。主人公は見たものを聞いたものを不思議とは思っても、そうなのかではなく、ああ、あれかと取り込んでしまう。時の移り変わりさえも、自分の一部であり、身を置く風景なのだろう。
0投稿日: 2013.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ枕元に置いて毎晩少しづつ読んだ。季節のうつろいは恵み。人ならざるものたちとわかちあっていることを忘れかけていた。
0投稿日: 2013.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
主人公は片足のつま先だけあちら側に触れたような世界にとまどいながらも「そんなものかな」とふんわり受け入れている。その距離感が絶妙で、読者である私たちも彼のおだやかな筆の走るままにもう少しあちら側を覗いてみたいという気持ちになってくる。物語をそっと閉じるのは「こちら」と「あちら」を天秤にかけることになった彼の決断なのだけれど、これがまた優しくて美しい。 主人公を取りまく人たち(と動物その他)もみんな魅力的だし、近畿地方、特に京滋の風景がかなり鮮明に描かれているので、そのあたりも面白いです。鯖の匂いのする街道とか狸谷のたぬきとかね。
0投稿日: 2013.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの小説は自然の草花がよく出てきたりファンタジー要素が沢山あり癒やされます。 きっと一昔前は当たり前だったんだろうなぁ。 先に読んだエフェンディ隊士録と繋がってたんですね。
0投稿日: 2013.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログとても不思議な話である。 と同時にとても心持ちのいい世界である。 しみじみとした、温かい涙が何度も滲む。 文章が、とてもいい。 すばらしいと思う。 心のなかで絶賛する。 これからの人生で、折にふれて読み返したい。 表紙は神坂雪佳。 宝物のような一冊になった。
0投稿日: 2013.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
他の本で一話目を読んでいた事を思い出した。 派手さはないのに、それだけ印象に残っていたという事。 読み始め、ひょっとして怖い話…?と思わせつつ ふわりと決着させるこの雰囲気が好き。 最終話の「精神を養わない」のセリフは秀逸と思う。 ゆるゆると物語が流れて、最後にタイトルに辿りつく感じ。 なるほど、と思った。
0投稿日: 2013.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ今では見えなくなってしまったもの。でもほんの100年前には当たり前に見えていたもの。「移ろふことは世の常である」こう綴る征四郎の世の行く末についての懸念が、そこはかとない哀しみを帯びて伝わってくる。四季は一巡し、また巡る。四季の植物を愛で、共に生息する生き物を当たり前に受け入れる。ここにある世界は日本の四季と共に生きてきた者ならばきっと共感出来るのであろう。それはもう理屈ではなく本能的なもの、潜在するものなのだろう。ここに綴られるものを読むにつれ、何とも不思議で懐かしい感覚が広がってゆく。
0投稿日: 2013.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公が家の管理のために住み、そこの庭に生息している植物(しゃべる)や犬、亡くなった友人の交流の話。 植物が人間のように書かれているが、ひとつひとつ性格があって面白い。ファンタジーみたいなの苦手かと思ってたけど、読みやすかった。 短編集だから?心地良い。 さるすべりやかっぱのとこの話が好き。
0投稿日: 2013.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ四季折々の草花を絡めて描く、連作短編集。 早世した友人の家に移り住んだ駆け出しの作家の不思議な生活を描く。 掛軸から船を漕いで現れる死んだ友人、恋するサルスベリ、只者ではない犬・ゴロー、池に現れる河童。 不思議な出来事ながら、あるがまま受け入れる静清とした筆が心地いい。 日本的な懐かしさが漂う作品。 静かで優しい話でした。
2投稿日: 2013.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
淡い色で描かれた絵本の世界に入り込んでいくような作品だった。 友人の家を引き継ぎ、そこを中心に起こる非現実的な諸々を自然と有り様に受け入れていく征四郎。屋内につるを伸ばす植物にも抗う事のなかった征四郎が、最後の最後に「家を守らねば」と誘惑をしっかり断ち切る台詞は朗らかに時間の流れる本作品の中ゆえ、際立ってピリリとしている。 物語がひとつの方向に進んでいく作品(推理小説など)は一度読んでしまえばなかなか再読まで辿り着かないが、家守綺譚のような日常を昇華した作品は度々手に取りたくなる。抑揚が優しいだけ一度のインパクトに欠けるが、随分ほっとした気持ちで本を閉じることが出来る。
0投稿日: 2013.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログサルスベリ、白木蓮、ダァリヤ、南天、ツリガネニンジン・・・・・ 亡友の家守りを任された主人公と、 庭先の義理堅い忠犬ゴローと、 ひょっこり庭の池に現れる河童や桜の精霊、 ひょっこり掛け軸から現れる亡友との物語。 そして、物語を彩る季節の草木。 季節の移ろうこの時期に読むことをおススメします。 ところで、ツリガネニンジンについて、 てっきり朱色の植物だと思っていたら、 まるきり違いました。 ツリガネニンジンは8-10月に花を咲かすそうなので、 その時は実物を見たいと思います。 2013年4月
2投稿日: 2013.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログうぐいさんよりお勧め。 少し古臭い言葉遣い、世界観がよい短編集。非日常の中の日常という感じで、蟲師を彷彿とさせる雰囲気。 どんな超常現象も受け入れる主人公の淡々とした文体がよい。高堂のキャラがとてもおいしい。短いので、たまに読み返すのにいいと思う。人にも勧めやすそう。 正直植物の題に結び付けているのは、無理やりなものも結構あった気がするが、作者のこだわりなんでしょうか笑 秋にもう一度読みたい。
0投稿日: 2013.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ庭・池・電燈付二階屋。汽車駅・銭湯近接。四季折々、草・花・鳥・獣・仔竜・小鬼・河童・人魚・竹精・桜鬼・聖母・亡友等々々出没数多……本書は、百年まえ、天地自然の「気」たちと、文明の進歩とやらに今ひとつ棹さしかねてる新米精神労働者の「私」=綿貫征四郎と、庭つき池つき電燈つき二階屋との、のびやかな交歓の記録である。(内容紹介より) 朗読会で出会った本です。美しくどこかほっとするような世界観に引きつけられて購入。四季の移り変わりをゆっくりとかんじながら不思議な世界が溶け込んでいる小説です。「葡萄」に出てくる湖の中の世界が印象深いです。
0投稿日: 2013.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本のことばと自然、そのうつくしさを凝縮したような本だった。 季節はうつろい日々は慌ただしく流れていくけれども、そのことをいとおしみながら暮らせるような気持ちになる。
0投稿日: 2013.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の気分にどんぴしゃ! 素敵な本やった* きっとこの先、何度も読む本になるんじゃないかなと。 終わり方が最高によい。
0投稿日: 2013.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ湖で行方不明になった親友の実家に守を頼まれた物書きのお話です。サルスベリに惚れられたり、掛け軸から親友が会いに来たりもしますが、それを皆が普通に受け入れる不思議な世界観にはまります。
0投稿日: 2013.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し昔の日本の不思議なお話 色んな植物や生き物と共に季節を感じながら生活していた時代 どんな事が起きてもとても自然に受け入れる主人公 もしかしたらうちの庭にも何かあるかもしれないと探したくなります とくに鳶からゴローが飛び出す所が好き
0投稿日: 2013.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ美しくて幻想的。 四季折々の植物に情緒があって、この一冊で春・夏・秋・冬を 主人公と一緒に過ごした気分。 難しい言い回しに、頭をフル回転させながら自分なりにイメージ。 また素敵な本に出会ってしまった!
3投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログあ、いいな。すごくいい。 文章がどうのとか内容がどうのとかじゃなく、すっとその世界に引き込んでくれて包み込んでくれる、そういう話。まあもちろん、自然に囲まれて摩訶不思議も体験しつつ自然の一部として静かに暮らすっていう生活に、そもそも私自身が憧れてるから、ってのもありますけどね。 いいなー、こういう生活。 10/22/2012
3投稿日: 2013.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはすごく好きな作品でした。久しぶりにまた一つ良い本に巡り合えたなと嬉しく思いました。 確か、何かの雑誌の特集でこの本が紹介されているのを見て興味を持ったんだったと思います。 梨木香歩の作品は多分『西の魔女が死んだ』を読んだことがあると思うので初めてではないと思うのですが、実は良く覚えていません…。 内容は、文庫の裏表紙の説明がやはり上手く表していると思うので…。 「本書は、百年まえ、天地自然の「気」たちと、文明の進歩とやらに今一つ掉さしかねてる新米精神労働者の「私」=綿貫征四郎と、庭つき池つき電燈つき二階屋との、のびやかな交歓の記録である。」 なんて言えばいいのだろう、不思議が日常におりてきているタイプの作品。 植物に心があったり、擬人化したり、狸が化けたり、河童・人魚・鬼が登場したり。 雰囲気は、真っ先に思ったのは『夏目友人帳』。他に『蟲師』や『xxxHOLiC』にも似ているかも。あと、森見登美彦の作品にもちょっと似てるかもと思った。 多分、これらの作品が好きな人は『家守綺譚』もきっと好きだと思います。 あらすじは無視して読み始めたので、予想に反してファンタジックでちょっと驚きました。本当にどんな話か知らないで読んだので、目次でいろいろな植物の名前がずらりと並んでいることにまずわくわくして。 本当に、とっても雰囲気の良い作品でした。 深い味わいがありながらも親しみやすい。 ひとつ目の「サルスベリ」から心奪われましたね、「懸想」するサルスベリが可愛らしくて。 また、主人公・綿貫と床の間の掛け軸からボートに乗ってやってくる亡き友人・高堂の掛け合いが心地よい。 全部好きでしたけど、サルスベリ、ドクダミ、白木蓮、ツリガネニンジン、紅葉~萩、ホトトギス、サザンカ、檸檬、ふきのとう、が好きでした。たくさんです。「檸檬」が一番胸がきゅうっとなった気がします。(こんな表現ですみません…) どの話も読後感がとても良く、最後の「葡萄」は特に読み終わりの余韻が素晴らしかった。 今、調べてみたら「奇譚」は珍しい話、不思議な物語という意味らしいですね…。タイトルは「綺譚」だけど。うん、「綺」の方が合ってる気がする。 「家守」は漢字で見ただけでは「いえもり」か「やもり」かどっちだろうと思っていて、表紙や奥付の読み仮名は「いえもり」となっているから、ああそうかと思ったのですが、どっちでも読むのが正しいみたいですね。 本当に素敵な作品でした。 何度も読んで大切にしたい。
2投稿日: 2013.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログほんの100年ほど前の日本は、こんな風に現実とふしぎなものたちが普通に交わる毎日だったのだろうか。そう思うとわくわくします。 一つの話が短くて読みやすいからどんどん読んでしまう。でも、読み終わるのが、もったいない。そんな気持ちになる本でした。
0投稿日: 2013.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログゆったりとした時間が流れる小説。 主人公が現実には起こり得ないであろう奇妙な出来事を淡々と受け入れている姿に好感が持てる。 小説でしか表すことの出来ない独特の世界観。 時間がある時に、何度も読み返したくなる。
0投稿日: 2013.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ終始穏やかな調子で淡々とお話が進んで、不思議なこともまるで当たり前のことのように描かれているのが素敵。葡萄でストンと物語が収斂されるのもよい味!
0投稿日: 2013.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議な物語のつまった本。 掛け軸から登場する友人、恋するサルスベリ、化ける狸、フキノトウを集める小鬼、・・・ 主人公がマイペースだからか、 自然の中で暮らしているからか、 驚きの展開にもなぜか癒されるお話ばかり。 夢の中にいるような感覚で読み終えた。
2投稿日: 2013.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本昔話を読んでいる時のような気持ち。 奇妙だけどわくわくするような不思議と出会いながら、それに動じない主人公がとても好き。 あまり見ない漢字も多かったけれど、それが分かりづらさを引き立てるものではなく、本の世界観を作り上げる一部のとなっていてよかった。 また、心地よい緩さに思わず笑ってしまうところもあって、穏やかな気持ちになる。 この本の季節の移り変わりが素敵で、できれば暖かい日に、風情のある庭の縁側でのんびり読たいなあと思いました。
2投稿日: 2013.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「上月君、君は、死、とはどんなものだと思うかね?」 ソファに座った途端にそんなことを問いかけられたのだから、はあ?と不躾な声を上げてしまっても失礼ではないと思う。 死。Death。この場合はdiedの方が良いのだろうか?それは生物学的な死か、それとも比喩か。文学には『生と死』をテーマとした作品はそれこそ五万とある。数秒だけ考えたが、都子の望む答えがいまいちよくわからなかった。 「哲学ですか?」 「好きに解釈したまえ。生物学上の意味でも、倫理的な意味でも、文学としてのテーマでも構わない」 「はあ。…死、ですか。まあぱっと思いつくのだと、もう目を覚まさなくて…、とか、葬式とかのイメージですかね」 「ふふ、まあそんなものだろうね」 にやにやと笑いながら都子が差し出したのは一冊の文庫本だった。太い青竹から小さな雀が顔を覗かせている素朴な表紙である。ごく薄い文庫本で、一日もあれば読み終わりそうだった。とても『死』だとかそういう物騒なテーマを扱っている本には見えない。 「家守綺譚」 簡潔なフォントで記されたタイトルを読み上げると、都子は実に満足そうに笑って、テーブルの上の茶を指し示した。 「飲みたまえ。今日のお茶は日本茶を用意したよ」 確かに机の上には言われたとおり、素朴な湯呑に鮮やかな新緑色の液体が満たされていた。文庫を机に置き茶を口に含む。からりとしたどこか懐かしい味が口内へと広がる。 「旨いですね」 「ヨモギの生茶だよ。穂先を摘んで熱湯にくぐらせたものだ。家守綺譚を読むのなら、こういった古くからある民間の茶が良い。素朴であり、親しみ易く、手頃な存在でいなければ」 「はあ」 ず、と音をたてて啜ると、鼻の先に特徴のある香りがぬけていく。なるほどこれはヨモギか。初めて飲む代物だったが意外にもクセはない。 「さて、先ほどの命題だけどね。深い意味はないよ。――――…ただ、そう、例えばね。私が既に死んでいる存在だとしよう」 「はあ?」 「例えば、だよ。例えば。今ここにいる私はすでに死んでいるのだ。母から貰った肉体はすでに朽ちて存在しなくなっている。けれど今こうして君の目の前にいる私はこうして喋っていて、君が触ろうと思えば触ることができる。この場合、私の死という定義はどうなると思う?」 「…質問の意味がよくわからないんですけど。それは生きているという状態と変わらないですよね」 「ふふ、この物語の本質はね、そこだよ」 「はあ」 「この物語は明治後期を舞台とした連作短編だ。主人公はとある片田舎に住む貧乏小説家だ。彼自身はなんの不思議もない人物だが、彼の周囲には少々変わり者が多い。例えば、庭に咲くサルスベリの木。彼女は主人公に懸想している。彼が飼っている犬は近隣で人格者と評判だし、近所の和尚は信心深い狸と知り合いだ」 「…そういう人種と知り合いってだけでなんの不思議もない人物ではないですよね」 「そうかい?そしてね、極めつけは彼の親友だ。高堂、という名前で、主人公と大学の同期なのだけれどね。数年前に死んでいるはずなのに、ほとんど毎話登場して、主人公と会話をして去っていく」 少し、考え込む。それは、さきほど彼女が健太にした例え話に似ているような気がした。 「死んでいる――――…とう事は、この物語ではさしたる障害ではないのさ。生と死、種族の差、そんなものの垣根がごく薄い世界の物語だ。古き良き今昔の民俗の描写は実に美しい。――――…神秘がごく当たり前に隣に存在する世界の日常の物語、とでも称するべきだろうね」
6投稿日: 2013.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログとても情緒溢れる一冊なんだけど、 読み進めるのには、大変な日数を要した。 単に読んでいるとウツラウツラしてしまうだけですが・・・。
0投稿日: 2013.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木作品はどれも大好きだけど、これが一番好き。 読み終わった後も一時ずっとカバンに入れていて、人待ちなどの少し時間が空いたときに読んでいた。 一度通しで読み終わったら、どこからでも読めそうなので好きなところから読もうと思うのだけど、結局いつも最初から順番に読んでしまう。 何が起きても割と淡々としている主人公を取り巻く不思議な事柄がどれも美しい文章で描かれている。 もう何度も読んだけれど、これからも度々思い出しては読むだろう一冊。
15投稿日: 2013.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
面白い! こういう不思議な世界、といっても全くの ファンタジーではなくって、日常にふっと 訪れる異界のものとのやり取り。 感応性の高い主人公が呼び寄せてる としか思えないけれど。 異界? でもないのかな… 実は1つの世界で起きていることで 限られた人だけが接触する? 高堂に何があったのかは知らないが まあ裏の世界の住人になってしまった のね。自ら、望んで。 それにしても綿貫、動じな過ぎでしょう。 鈍感で、人がいい。 だからいろんなもの見えたり聞こえたり するのね。 湖の底に行ったときのセリフ。 「私は与えられる理想より、刻苦して 自力で掴む理想を求めているのだ。 こういう生活は、--- 私の精神を養わない」 貧乏でちょっとプライドが高くて鈍感で 意地っ張りなとこもあって、 でも、こういう芯の強さが、孤高の精神が この男の人知れない魅力なのだろう。 普段のうすらとぼけたところも帳消しに するくらいの。 そしてゴロー! いい仕事してますね。 高堂は、これからも現れるだろうか。 ボートに乗って。
2投稿日: 2013.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ亡くなった友人の家を管理する青年が、 不可思議な生き物(妖怪というか・・・)や死んだ友人と織りなす日常劇。 少し不思議なお話が、淡々と描かれている小説。 初梨木さん作品だったのですが、とても気に入りました。 ゆっくりとした、暖かい気分を味わえる作品です。
0投稿日: 2012.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章も情景も世界もうつくしい。植物の表題がついた短い話がいくつか入っているので読みやすい。日本の庭を見に行きたくなる。
0投稿日: 2012.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログおよそ100年前の日本を舞台とする、絵巻物のような物語。その日常には摩訶不思議な現象や事物(例えば妖怪や霊、八百万の神や感情を併せ持つような動植物たち)が存在するが、それを主人公たちが当たり前のように受け入れ、ゆっくりと季節が流れていくという、独特の雰囲気が素敵だった。主人公の綿貫征四郎が書いたとする、巻末の書き下ろし「烏蘞苺記」は必読だと思う。
0投稿日: 2012.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ季節に合わせた美しい植物の名前がつけられた28章からなる話。 表紙もかわいらしい(^^♪ なんとも不思議な世界にどっぷり浸れます☆
0投稿日: 2012.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学の学士であり物書きである綿貫征四郎は、早世した高堂の実家に「家守」として住むことになった。 しかし、それからの生活は不思議ワールド。床の間の掛け軸のなかから、死んだはずの高堂が現れたり、河童が出てきたり、狸にだまされたり。。。 書くとホラーっぽいんだけど、読んでみるとそれがとっても親しみのある文体で書かれてるので、良い感じです。 主人公の綿貫氏の性格もゆったりしてて、心落ち着けて読むことができました~。 こういう欲のない環境の中で、好きな者・物たちとのんびり暮らす。ご隠居っぽい生活もいいな~。って思いました。 今の世の中、忙しすぎて周りを見失っていくことが多い。 でも本当は自分の近くに、こんな小さな発見やミステリーがあるのを見落としているのかもしれない。 梨木さんは、植物関係が好きなのかな~? 章ごとに、植物の名前が書かれてたのが、とっても粋でした~。
2投稿日: 2012.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ和ファンタジー、って感じの、素敵な本です。こんな世界に行ってみたいな、と憧れてしまいます。現実逃避したい時には重宝してます。
2投稿日: 2012.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログあたたかく不思議で、優しい物語。この不思議のなかにいつまでも浸っていたいと思える、そんな幸せに出会えました。
0投稿日: 2012.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ文庫版で再読。 さらさらとした綺麗な文章で物語にすっと入り込める。植物や精霊と過ごすゆるやかな日々。
0投稿日: 2012.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログやさぐれた気持ちの時に読む本です。 濡れた靴下を乾いたウールの靴下に履き替えたような 穏やかな心持ちが戻ってきます。
3投稿日: 2012.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの作品でもとても好きなもののひとつです。 おすすめの本としてよく自分の仕事場でも押しています。
0投稿日: 2012.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ手元に置いておきたいと、初めて感じた本。 図書館で装丁に惹かれて借りて読み、梨木香歩さんのファンに。 数年後また読みたくなり、購入。
0投稿日: 2012.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ初、梨木作品。他のものも気になる。 漂う空気感とか主人公の浮世離れした感じとか、すごく好きな作品。 こういう本は、繰り返し繰り返し読みたいです。
0投稿日: 2012.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ欲望 ・河童衣の入手と、それを掛ける 衣紋かけが是非欲しい。 想像 ・隣りの奥さんの話を基に、河童の 脱け殻の行程を真剣に検討。 実践 ・隣りの奥さんの話を基に、河童の 脱皮方法を真似てみた。 野心 ・あの家へのルームシェアのお願い 及び高堂の舟に乗る事。 結論 ・やはり、隣りの奥さんと親しくなる ことでしょうか?
2投稿日: 2012.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ植物と関連した怪奇の不思議なお話で読むのが良い意味で楽。1つの話が短めなので少しずつ読み進めてほのぼのできる作品。
2投稿日: 2012.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ100年ほど前の日本が舞台で、なんともいえない不思議なファンタジ^ーでした。まだ不可思議なものがすぐ隣にあって、その境界線がたまにあいまになり、向こうの世界がこちらに流れ込んでくる感覚がうらやましく感じられました。私もこういう世界に入り込んでみたい…大好きな本です
0投稿日: 2012.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ草木やら動物やら足元薄い人やら、人間とは違う存在と仲良くしたっていいじゃないか。 人ばっかり見てるより、ずっといろんなものが見えるよきっと。
0投稿日: 2012.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい!レビューの五つ星がこんなに多い本は初めて見た。たしかにすばらしい!文体も好き。表紙も好き。もちろん内容も。きっと再読するだろう。
0投稿日: 2012.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読or再々読。時代は明治か昭和初期か。 古ぼけた一軒家の「主」としてやってきた綿貫。俗物なのがいい。そんなことだからお前は…。と、持ち主の高遠にあきれられるが、そんな綿貫だからあの家の「主」でいられるんだ。と。 どちらが夢かうつつか。儚く危うい世界が、夏にむいている。
0投稿日: 2012.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ現実にいながら、時折非現実の世界に迷い込み、身の回りの植物や動物たちの声が聴こえてくる。そんな中、淡々と生きる物書き綿貫征四郎と犬のゴロー、“掛け軸の向こうから度々出てくる”高堂、犬好きな隣のおかみさん。実に巧みな日本語で書かれた文章は美しく、読み終えるのがもったいないほど。そのあたりの木や花にも全て性格があり、彼らのストーリーがある気がして、愛しく思えるようになる本。
0投稿日: 2012.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治30年代ぐらい話らしい。 亡くなった友人の家の家守をする主人公綿貫征四郎は、文を書く仕事をたまにするくらいで、あとはのんびり何をするでもなく生活を送っている。 その家で次々におこる不思議な出来事が、庭にある植物と共に語られていく作品である。 死んだ友人が現れて話したり、木に好かれたり、河童が出たり、狸に化かされたり、小鬼が出たり、とにかく非現実的なことばかりおこるが、主人公はとりたててびっくりせず受け入れていく。 死んだ友人が登場する場面と最後の場面がいいな、と思った。 これは読んで良かった本の一つになりそう。
2投稿日: 2012.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログファンタジーのちいさなるつぼ。 この作家は「西の魔女が死んだ」から入っていたので、当時は「こんなものか」と思っていたけれど、この本は違った。 解説されている通り、きっと 「分かっていないことは分かっている」 「理解はできないが受け入れる」 である。読んだらいいと思う。 次の作品を是非読みたいと思った。
0投稿日: 2012.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語としての起伏が乏しく、読むうちにこれは「時間」あるいは「人生」の少なくともどちらかにゆとりのある「大人」が、休日にゆったりと一文一文を噛み締めて味わう小説なのだと悟るに到った。 少なくとも切羽詰まるあまり物語の奔流に溺れてしまいたいなどと考える若造が読むべき本ではなかった。 だが、愛すべき小説であるとは切に思う。 読む時期を明らかに誤った…。 種々の事柄がしっかりと落ち着いてから、改めて読み返そうと思う。
0投稿日: 2012.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと早く読んでいれば良かったと後悔。 季節感とファンタジーがほどよく混ざっていて好きです。 読み終わってすぐに読み返したくなりました。
0投稿日: 2012.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解しなくても受け入れることの大切さを分かっていた、100年前のおおらかな暮らし。 不思議ものたちと季節を楽しんでゆっくり流れる時間がよい。
0投稿日: 2012.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ美しい日本語の中でゆっくり流れていく、静謐な時間。 四季の中で自然を慈しみ、ともに生きてゆく。 そんな古き良き日本の世界を心ゆくまで味わえます。 少し冷える静かな夜に読みたくなる、幻想的で素敵な本でした。
0投稿日: 2012.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大学生の夏休み、田舎の実家に帰省している、ちょうどサルスベリの花が盛りの頃に読んだ。 一年の季節の移りに合わせて進む短編。 まるで、メモ書きのような脈絡のなさが、逆に心地良い。 この作品では色々な季節の草木が登場する。 たいていは知っているものだったけれども、知らないものも出てきて、自分の知識不足が少々残念だった。それぞれにまつわる話が出てくるところ、この作者の知識はすごいな、と。 それぞれの話にはとくに教訓めいたところがあるわけではないけれど、どこか徒然草を連想した。タツノオトシゴの話や、月の話、雨と共に掛け軸から人が現れる描写とかが好き。 草木についての知識を補充して、もう一度読み返したい作品。
0投稿日: 2012.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
図書館から借りました ファンタジー。 いまよりちょっと昔。百年前ぐらい。 おおらかな時代。 死んだ友人の父親から、家の留守を頼まれた綿貫征四郎。その庭のサルスベリに懸想されたり(助けてくれたり、焼き餅焼いたり、詩を朗読されると喜んだりする実に存在感のある庭木)、池に人魚がきたり、掛け軸のサギが池の魚をかすめ取ったり、掛け軸の中から死んだ友人が頻繁に遊びに来たり。 綿貫はとてもとても心が広く優しい。 結局、全部受け入れてしまう。 信心深い狸にであった話が特に、印象に残る。狸は山の中の救われない霊をたくさん負って、苦しくなると寺に来る。お坊さんはちょうど出かけていて、綿貫しかおらず、彼に「南無妙法蓮華経といってさすってくれ」と言う。綿貫はさすってやる。苦しんでいるのを捨て置けないから。 そして狸はお礼に松茸をこっそりと置いてゆくが、綿貫は「回復したばかりなのに集めてきたのか。そんなこと気にしなくて良いのに。何度だってさすってやるのに」と思う。 こういう人間だから、桜の花が散るときに人の姿になって暇乞いにきたりする。サルスベリに愛されて、カッパに妙になつかれたり、変な犬が住みついたり、死んだ友人が飄々と尋ねてきたりする。 ほんわかとして、せちがらい世の中を忘れさせてくれる。 タイトルは「いえもり」だが、終わりの方にヤモリの絵がある。これが可愛い。
0投稿日: 2012.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログゆっくりとした時間の流れで進んで行くお話。 読み終わった後、綿貫さんの印象が私の中では変わっていました。 侮ってたのかも(^^;) 描写が美しく短編だったこともあり、とても読みやすかったです。
0投稿日: 2012.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ友人の家を守ることになった作家が主人公のお話。 短編ごとに区切られてるので読みやすかった! でもなんだか不思議なお話。 古典調、、というか… この感じ、すごく好きでした。 優雅な環境は精神を養わないって言葉、印象的だった。 また読みなおそっかなー
0投稿日: 2012.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ解説で述べられていたが、「理解はできないが受け入れる」ことの大切さを常々感じた。 奇異なものへの畏怖を感じながらも自分もそれらも「一つ」として扱い、四季を混ぜながら美しい風景で彩られていて本当に染み入る作品。
0投稿日: 2012.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【感想】 梨木香歩が好きなら絶対オススメ. 読むと,ゆったりとした時間が本の中に流れているのが実感として伝わってくる. 主人公,綿貫征四郎が怪異?(カッパや亡くなった親友が出てくること)に対して「なぜこうなるのかわからないが,そういうものなのか」と受け入れているスタンスが,面白い. 例えば, 亡くなった親友が掛け軸から現れて 親友「サルスベリのやつが,お前に懸想をしている」 に対し 綿貫「……ふむ」 と受け入れて, 綿貫「どうしたらいいのだ.」 親友「時々本でも読んでやることだな」 綿貫「そうするよ.」 親友「そうしたまえ.」 本を読んでやるくらいなら無理のない仕事だ この調子で,四季折々と怪異と周囲との交流が重なって,綿貫のゆっくりとした日常が進んでいき,読んでいる方も悠然と構えることができる. 1話1話で区切りがあるので,少しの空いた時間を使って読めた.
2投稿日: 2012.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ黒い小さな虫が腕の辺りを歩いていて肘の近くで止まった。そのままそこに馴染んだ、と思ったらほくろになってしまった。 (葛)
0投稿日: 2012.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の評価基準 ☆☆☆☆☆ 最高 すごくおもしろい ぜひおすすめ 保存版 ☆☆☆☆ すごくおもしろい おすすめ 再読するかも ☆☆☆ おもしろい 気が向いたらどうぞ ☆☆ 普通 時間があれば ☆ つまらない もしくは趣味が合わない 2012.7.20読了 なかなか、いい本でした。 特有のかほりがあって、頁を開くとすぐに、本の世界に引き込まれます。これは、満点。 いつも読んでいるミステリーやSFと比べると、物語性はちょっと弱いかも知れませんが、それを補って余りある世界の構築があります。 文庫本で読んだんですが、作中の植物に疎いので、綺麗なイラストなどあれば、完璧でした。巻末の書き下ろしもなかなか味があった。 梨木香歩の他の作品も読んでみよう。
0投稿日: 2012.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議なことが当たり前のように語られる世界。 語り口がとても美しい。 まったりしすぎて読んでると眠くないときでも眠くなってくる。 面白かった。
0投稿日: 2012.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ毎日少しずつ移り変わっていく季節の美しさ。その中に入り込む不可思議な出来事。 それらが淡々と静かに綴られている。 庭に植わっている植物たちの生き生きとした有様が目に浮かび、和の麗しさを堪能出来ます。
0投稿日: 2012.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
再読。 一夜一夜、寝る前にちょっとずつ読む。 文章が好きだ。 口調とか、表現の仕方とか。なんとゆーか、めっちゃ好み。 高堂の登場シーンが意外と少なかった。 あれ、そうだったかな、と。掛け軸からでてくるイメージ強かったからなあ。 隣のおばちゃんとか、編集の山内とか、和尚さんとかの方が登場は多い。 そしてなんといってもゴローである。 いやーいいなあ。 仲裁犬、ゴロー。しゃべったらおもしろそうだ。 河童やら龍やら小鬼やら、そーゆーものたちが あたりまえにいて、それをあたりまえのように語るおばちゃんとか この作品そのものの雰囲気が大好きだ。 落ち着くような、わくわくするような。 何度でも読みたくなる。 んで、再読してると、ちょうど続編の連載も始まったことを知り、なんだか嬉しくなった。 村田さんのも再読したくなってきた。
2投稿日: 2012.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ綺譚であり奇譚。”物語”の中で”物語らしい物語のない”話を書いているつもりが結局は”物語”してしまっているような小説。梅雨や晩秋の静かな時間に読みたくなる一冊。
0投稿日: 2012.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ怪異を不思議に思いながらも「そんなもんか」と受け入れているところとか,ゆったりと「たゆたうように」流れていく時間とか,静かな空気感とか。作品の雰囲気がとても好み。主人公の優しさにも癒された。 かつての日本全てとは言わないがこんな風に暮らしていた人々もどこかにいたのではないだろうか。 こういうの読むと,花や動物を見る目が変わってきそうだけれど,現代とかつての世の中との落差も同時に感じるかもしれない。
0投稿日: 2012.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい読むのに時間かかった;でも少しずつ読み進めていくうちにじんわりとほのぼの感が伝わってきた。知らない植物も色々出てきたなー。実物を知ってから読むとまた違うと思う。
0投稿日: 2012.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ京都東山の麓あたりにある、亡くなった同級生の留守宅に住みながら、文筆活動をする男の話。 季節の移ろいや、動植物との触れ合いに加えて、河童や龍・鬼などが当たり前のように登場し、またそれに違和感がない生活が無理なく描かれています。 100年前の日本ではこんな生活が普通だったかもと想像すれば楽しく、また羨ましくなりました。 各章が僅か数ページというボリュームの中に、これだけの情緒と夢を盛り込むことができるとは驚きです。
2投稿日: 2012.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログまさに「綺譚」。明治時代の想定で書かれた文章である。テーマとなるものが自然界の草花、樹木、動物、そして実際には存在しない河童のような化け物、そして幽霊である。それぞれの章はそれほど長くはないが、文章を味わって読んでいく本だ。旧仮名遣いではないが、明治時代風のたおやかな文章で、一つ一つの言葉を吟味して連ねている。この世の出来事ではないことを書き表していながら、なぜかおどろおどろしくなく、その当時の美しい日本の京都の情景を表現している。梅雨時にゆったりとした気分で味わいたい作品だ。
0投稿日: 2012.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ文筆家・綿貫征四郎が、友人の家で暮らすようになってからの日々の徒然の話。 不思議なものを不思議なままに。河童も人魚も人を騙す狸も、誰も奇異とは捉えない。「私が知らないだけか」と、現象をありのままに受け止める主人公の、超然とした態度そのままに文章が続く。良いなぁこの日常。日本が異国みたいだ。「ホトトギス」の回が好きだな。
0投稿日: 2012.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
坊ちゃん的な主人公の周りで起こる不思議な出来事。 物語の設定も雰囲気も大好きだけど、あまりに坦々としすぎて、少し中だるみしました。
0投稿日: 2012.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログSS形式の短編連載なのねとても読みやすい。 不思議な現象を不思議なことと書いておらず、あるがままに語られる印象。 不思議なそれが、起こることが当たり前すぎて、日常の一つであると言われてるかのよう。 やさしくてあったかい物語
0投稿日: 2012.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日参加した読書会での参加者のおすすめの一冊。 その時の紹介で、日本を舞台にしたファンタジーとあり興味を持ち読みました。 非常に日本語が綺麗で、昔の日本の情景が思い浮かびました。 家で読んだんですが、田舎の家の縁側でのんびりと読めば良かったかなと思いました。 「春夏秋冬」、「花鳥風月」、自然を表現した良作でした。
0投稿日: 2012.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ5/8読了。 この物語はファンタジー?と一言では括れない 全く新しいジャンルの小説ではないだろうか。 そもそも綺譚とは、美しく優れた物語という意味らしいが、 その名の通り、美しい。 不慮の事故で若くしてこの世を去った同級生の生家で 家の守りを仰せつかって住むことになった主人公綿貫が 庭の花や草木や動物や人魚や河童(!?)・・・に出逢う。 この風情ある家で出逢う四季折々のそれは、 なんとも可愛らしく、時にいじらしい。 たとえば、百日紅の木に惚れられるなんてのは普通で、 他にも奇想天外摩訶不思議な出来事が次々と起こるのだが、 それでも結局は 100年くらい前の日本は、なんて美しかったんだろうと感動する 本当に美しいお話。 100年前は美しかったんだろうと思うのと同じように 今この現代が100年後の未来に美しいと思えるよう願いたい。
0投稿日: 2012.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログとても美しい日本語で周りを取り囲む自然を丁寧に描いている。 湿り気を帯び、ひんやりとした空気までもが漂ってきそうな気がした。 読んだあと、通り過ぎる人の影を思わず注視したくなった。 どこにでも持って行って、繰返し読みたい。
0投稿日: 2012.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本語の美しさに、心が洗われました。文章も、一つ一つ選ばれた漢字も、うっとりするくらい、綺麗なもので。。 日本人が持つ、自然界に存在する花や木への愛着を、主人公の綿貫さんを通じて共鳴できた様に思います。 人とは違うけれど、親しい隣人のような存在。 くすっ。とほくそえんでしまう、愛嬌を登場人物たちは持っていて、読み終えるのが惜しくなるほど、大好きな本です。
0投稿日: 2012.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
普通に考えるとありえないようなことなのに なぜかすぅっと日常のひとこまのように描かれる『私』の生活。 四季折々の季節感を盛り込んだのはやはり梨木ワールドという感じで 静かに縁側なんかで読みたい一冊。 絶賛されてたので随分前から読みたいと思いつつも なんとなく堅苦しいイメージを受けて、なかなか手をつけずにいた。 読み始めてからも正直最初はその雰囲気に慣れるのに時間がかかったけど 気づくとなんともいえないこの世界観のなかに入り込んでしまっていた。 なんだか飄々とすべてを受け止めて 共存していきている『私』を通して 世界を見る目がちょっと変わるような、そんな感じ。 たまにふっと読み返したくなりそう。
0投稿日: 2012.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
動植物・人ではないものがたくさん出てきて、 動植物が好きな私には堪らん(・∀・)!! 京都、水道橋あたりが舞台になっていて、とても親近感を覚えます* また読みたいなあ
0投稿日: 2012.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ友人の家を守る男と、 その家に自分の家ながら客として度々訪れる、遠い昔に神隠しにあった友人。 昭和初期を舞台としながら、なんとなく 神代の風景を思わせる短編集です。 一線を越えた男と、越えない男の対話が 緊張感をはらみつつ、のんびりと、のどかで穏やかで、 ただ寝るだけの休日の午後などに手元に置いておきたい小説です。
0投稿日: 2012.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ記憶にある限りの本の中で 一番いとおしい。 万人受けするかどうかはわからないけど、一章ごとに日本人であることの幸せを感じられる。
0投稿日: 2012.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本語がとても綺麗。 河童や龍が当たり前に日常に描かれている不思議な一冊。 琵琶湖南が舞台です。
0投稿日: 2012.03.27
