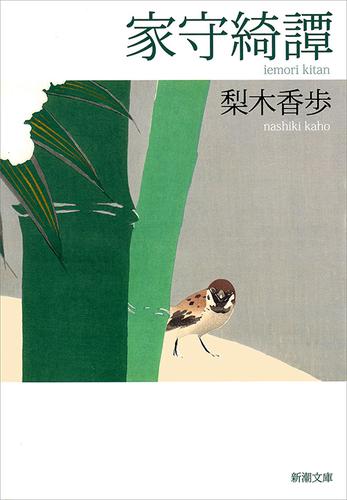
総合評価
(679件)| 313 | ||
| 202 | ||
| 87 | ||
| 6 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人の不思議(河童 狸 などなど)が日常の中に溶け込んでいる生活が見られる物語。綿貫はその不思議を当たり前のように受け入れているのが印象的。 ラストの葡萄で、綿貫があちらの世界をとらず、こちらの世界に戻ってくるシーンがいい。「精神を養わない」と。
2投稿日: 2016.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
梅崎春生の未発表原稿をリライト!と言われても信じちゃうかも。 ハイカラなお名前から、蛇にピアスしたり背中を蹴ったりする世代のヒトかと思いました。 「綺譚」って荷風の造語だそうで。 「向島寺島町にある遊里の見聞記をつくって、わたくしはこれを墨東綺譚(ぼくとうきだん)』と命名した。 ”きたん”じゃなくて、”きだん”なんですねー! ユルスナールは「とうほうきたん」のはずだけどなあ。 白鹿亭綺譚とか黄昏綺譚とかパノラマ島綺譚とか 頸飾り綺譚とか覗機械倫敦綺譚とかはどうなんでしょうか〜??
1投稿日: 2016.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログゆっくり流れる時間を楽しんでいるような感じ(#^.^#) あこがれの生活だなぁ~‼ サルスベリに恋されていて 友達は掛け軸からあらわれて ゴロー(犬)はカッパと友達に… 人魚や鬼や神様まで出てきる不思議な話です 植物もたくさん出てきます。
1投稿日: 2016.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ河童や狸とのささやかな関係に憧れる。 もう少しグイグイからんでくれてもと思った。 でもそれだとなんかイヤだとも思った。 「吾輩は猫である」から毒気を抜いたような。 妖怪話からエンタメ性を排除したような。 印象に残ったエピソードはとてもベタなシーンだった。 はかなげでけなげなものによわい。 話がドンドンドンと展開するタイプの物語ではない。 それゆえ深夜に雨の音をBGMに読んでたら寝てしまった。 もう少しグイグイ展開してくれてもと思った。 でもそれだとなんかイヤだとも思った。 会話文が「」でなく――なのが、スバラシイ。
1投稿日: 2016.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生時代にボート部の活動中、行方不明になった高堂の家を、卒業後家守をする事になった綿貫、自称物書き。とても貧乏で渡りに舟と住む事にしたが、不思議な事が立て続けに起きる家だった。行方不明の高堂さん、河童、薬売りが現れるわ、動じないお隣さんがいるわ、庭のサルスベリに惚れられるわ、犬を飼ったらやたら賢すぎるわで、本来ならもっと驚いていいはずなのに、一番動じない綿貫さん。全て受け入れていきます。読み終えてしまうのがもったいないくらいで、もっと高堂さんとの会話も聞きたいと思います。続編も出ているようですが、評価が微妙なのと、高堂さんがあまり出ないようなので、少しさみしいですね。
2投稿日: 2016.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ隣の世界、とでもいうべき存在がごくごく自然に立ち現れる。 隣家のおかみさんやお寺の和尚さん、後輩の山内くんまでが”隣人”たちの存在やその習慣を知っていて、当然のように受け入れているのに対し、語り手の綿貫だけがすこぅし戸惑っている、そのアンバランスさがなんだかいい。 ゴローとサルスベリがいいな。 最後の「葡萄」はとびぬけて奇異な世界に入り込む。そこから還ってくることで、日常が雨に洗われたように新しく見え、また循環が始まるんだな・・・という感じがした。 『そうかこいつは葡萄を食べたのだ、と思った。』
2投稿日: 2016.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ何事も全て説明、証明しなくてはならない理由はないのにせっせと証明式書いてたりするのが現代で、でもそこから溢れたそれを「まぁそういうものか」と受け容れるのは昨今じゃあ難しいよね、という感想。しかし、かつてはありふれた話であった、かもしれない。草葉の陰に潜むのは何も蛇だけではない。
3投稿日: 2016.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議な雰囲気の話で面白かったです。 SS集みたいな感じなので読み易いのも良いですし、日本の四季折々と美を感じられる作品でもあると思います。 梨木さんの作品は初めて読んだのですが他作品も是非読んでみたいです。
1投稿日: 2016.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
100年くらい前の田舎を舞台に、植物をモチーフとした寓話風ストーリー。が、読後感はよく、続きを読みたくなる。 登場する植物で知らないものがあり、ネットで調べたりしながら読んだ。絵本などの作品も多い著者だが、ほかの本も読んでみたくなる。夏の夜に読むにはちょうどいいかも。
1投稿日: 2016.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治の頃の京都の山科を舞台にした不思議な作品。普段読む小説とテイストが異なる内容だったのが新鮮だった。日本語が美しい。
1投稿日: 2016.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログすごくすきな一冊 魅力的な登場人物(だけではないけれど)に惹かれるようにしてするすると読んでいたら、最後がとても味わい深かった 彼方と此方 選んでしまったひとと、選ばなかったひと
2投稿日: 2016.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ生き物や植物への優しい眼差しを感じる、丹念な文章でした。ちょっと昔の日本の、ちょっと不思議なお話。こんな土地のこんな家に住めたら、世界をもっと広く深く、感じるようになるのかなあ、なんて思いました。読み終えて、じんわり、こう、ゆっくり静かに息を吐いて肩を緩めるうな、そんなお話だったように思います。
3投稿日: 2016.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ売れない物書きである綿貫は、早世した学友・高堂の父親に彼の実家の家守りを頼まれ、移り住むところから物語は始まる。ある日床の間の掛け軸の中から高堂がボートを漕いでこの世にやってくる。再会した二人のやり取りで心を掴まれて、あとは幻想的でどこか懐かしい日本の風景を感じられる梨木さんが創った世界に、しばし現実から逃避してどっぷりと浸ることができた。
1投稿日: 2016.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ100年前の日本が舞台。まだ人と自然、神様や人外のもの達が近くにいた時代の話。 風景や空気感まで見事に想像できる素晴らしい文章。木や花も全て今の日本にあるもので、春夏秋冬が手に取るようにわかる、日本人として大切に大切にしたい素敵なお話です。主人公の守っている屋敷や庭のレイアウトを想像するのも楽しいです。 ベスト3の中の一冊に選ばせて頂きました。
5投稿日: 2016.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ河童に竜に桜鬼…そして今は亡き友。 主人公の周りに集まってくるのは、人ならぬものばかり。でも、百年前の日本ならこんな日常もありえたのかもしれないと思える不思議な世界観のお話です。
5投稿日: 2016.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ** 草花をテーマとした 不思議なお話し 「普通ではあり得ない事を 当然の様に受け入れる」 そんな スーーッと 心に入ってくる ファンタジーが好きです ** しかも日本の美しい情景を 四季折々に綴ってあり 癒されます 特に私が好きなお話しは 狸の謝罪と恩返しの場面 小さな優しさが 心に沁み渡るんです。
1投稿日: 2016.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公を女性だと思って読み始めたら男性だった。 土地や空気やそこに宿るものたちまでもが、まるでみな同居人であるかのよう。 ごくごく自然で、地続きにつながったような隔たりのなさ。 おだやかで優しく、どことなくユーモラス。 「白木蓮が○○を孕んでおります」には思わず吹いてしまった! ああ、やっぱり植物図鑑用意しておくべきだった。 私たちが忘れかけている世界かも。 また読み返したい。
3投稿日: 2016.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ題名から引きこもりの話かと思ってました。 物書きを目指す主人公【綿貫征四郎】はニート以上フリーター未満。 そんな彼の元に家の管理人をやって欲しいという渡りに船のお話が! 家の管理【家守】をする事で綿貫が体験する、ちょっと不思議なお話し。 100年ほど前の世界観なので今では不思議な事も当時はまだ常識という世界観! 河童や小鬼が季節と供に訪れる優しいお話しです。
1投稿日: 2015.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログいつも雨のにおいのするお話し 主人公と飼い犬と大家さん そして、たまに訪れる友人と 煙る景色のなか 現れては、消えて行く、 異界のモノたち。 いつか自分もその迷宮にはまっていく
1投稿日: 2015.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ綿貫さんの動じなさったら…見習いたい。 真夜中に何かの気配で目が覚めて、枕もとに見知らぬ着物の女がこっち向いて座ってるの見て、なんだろう知り合いかな?って普通思えないわ。 そのうち女がぼんやり透き通って消えちゃったの見て、なんだったんだろう?しょうがない寝るかって普通思えないわ。 私もこう在りたい。
2投稿日: 2015.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログひょんなことから亡き友人の実家の家守をすることになった新米精神労働者の征士郎とユカイな仲間たちが繰り広げる不思議で楽しい日々の記録。 設定は若干少女漫画風味だが、庭の植物たちや動物たちの描写が風雅を添える。
1投稿日: 2015.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み始めたばかりだけど 大好きな1冊になる予感❗️ 非日常のありえない話なのに 「もしかして 私の知らないところでこういう事がおきてるのではないか?」と思わせる 不思議な話を 大袈裟でない文章で 淡々と綴ってる感じが好きです ゆっくり大事に読もう
2投稿日: 2015.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログサルスベリのふさふさとした豪華な花房を見るたびに思い出す本です。 淡々としているようでも、若さを隠しきれないところがある主人公の好ましさが素敵。
2投稿日: 2015.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者はボクと歳がそう変わらない。なのに何故こんな物語が書けるのか不思議でならない。 とてもきめの細かい条件描写で映し出されているのは、まだ、妖怪や幽霊や動物たちが共生している日本の原風景だのだと思うのだけれど、ボクが物心ついた頃には田舎にもそんな風景はもうなくなっていた。そんな風景を想像だけでここまでリアルに描けてしまうのが凄いと思う。
1投稿日: 2015.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ亡くなった友人の実家の家守をする主人公:征四郎。 家守をしながら文筆業に励む一方、いつのまにか住み着いた愛犬ゴローととも生活する。庭の植物や、亡くなった友人との語らい、河童や狸、和尚などとのふれあいは、不思議な世界観ながらも、ゆったり、ほっこりさせられてしまう。しばらく、この著書を追ってみるか。
1投稿日: 2015.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書に季節感がほしい、再読したい本に出あいたい、と思ってWEB検索していたら、この本のことが紹介されていた。 BOOKasahi.com「再読 こんな時 こんな本 書店員にきく 雨を楽しむ」 http://book.asahi.com/reviews/column/2011071700351.html 最終閲覧日2015年6月28日 TV「アメトーーク!」の読書芸人の回を観て、本を買って読みたくなり、書き下ろしの収録されているこちらの文庫を購入した。 物書き・綿貫征四郎は、亡き友・高堂の家守をすることになり、亡友、小鬼、河童、聖母、さまざまなものたちに遭遇する。 それぞれのおはなしの題に四季の植物の名をとっている連作短編集。 「懸想」にやられ、くらくらした。 確かにこれは、間違っていなかった!、という感じ。 こちらとあちらの境が曖昧、Sukoshi Fushigi。 個人的には、小鬼がかわいくて好き。 植物の名がわからないので、ググりながら読み進めるのも、楽しかった。 犬のゴローがいい味を出しているので、犬好きにもおすすめ。
1投稿日: 2015.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなに心共振できる小説を、まだ、読んでいなかったと、とても幸せな気持ちになりました。ふと現れるあやかしたちと当たり前のように共生する日常を淡々と綴ります。怪異譚の系譜に香り立つ文章で継承されました。憶えのある京都や滋賀の地名が小出しされ、家守のお宅を探しましたが、どうやら県境辺りのどちらとも言えない処にされたようですね。
7投稿日: 2015.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生時代に湖で死んだ親友の実家の家守をする駆け出し作家の話。竜だの河童だの死んだ親友だのが登場するわ、庭のサルスベリに懸想されるわ、狐狸に化かされるわと字面にすれば色々事件が起きているのだが、何の事件も起きていないような淡々とした語りのせいか"日常"といった印象が強い。
1投稿日: 2015.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ綺麗な話だったなー。自然と会話したくなる。 最後の解説を読んで、題名に納得。 うーん。読後感が素晴らしい。
1投稿日: 2015.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議なものとわたしたちの境目がないころの話。今ではへたしたら恐れられる存在が、普通の生き物のように存在しているのがいい。その前提があるからか、作品全体から漂うのはただただ静謐な日常に思える。 高堂と綿貫の関係は、BLではないと思うが…。女性の描く男性のいいなあと思う関係をちょっと凝縮した感じだと思った。
1投稿日: 2015.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ100年とちょっと前、明治の頃、琵琶湖のほとりにある和風建築の屋敷に暮らす物書き・綿貫征四郎が綴る自然豊かな、摩訶不思議な、物語。 ずっと読みたいと思って気になっていた1冊ですが、鳥肌が立つのとも違う、肩甲骨の間がくすぐったくなるような、切ないくらい懐かしくなるような、夢を見ているような、不思議な読み心地でした。これは桃源郷の物語だと言われても頷けてしまうような、描かれているのはなんとも不思議な世界です。なにせ、まだ河童や鬼の存在が信じられていた頃の物語で、自然の「気」を色濃く感じます。 懐かしさを感じるのはきっと、小さい頃草木にまみれて遊んだ時と同じ自然との距離感を至るところから感じられるからかもしれないですね。小さなコミュニティで不便なことが多くても、とても豊かな世界が広がっているのがわかります。 作中の表現も普段見慣れないような美しい日本語が並んでいて、新鮮かつわくわくします。ちょうどもう少し先の季節になりますが、「新緑だ新緑だ、と、毎日贅を凝らした緑の饗宴で目の保養をしているうち、いつしか雨の季節になった」なんて表現もすごくきれい。 たまにひょいと登場する高堂と綿貫の掛け合いも好きです。親しい間柄だからこそ取り交わせる遠慮のない言葉かけが心地よくて。高堂の弱くも孤高で、誰よりも誇り高い人柄も好きだし、高堂側からの物語も読んでみたくなります。 「西の魔女が死んだ」でも感じたけれど、特定の宗教に対してではないけど自然や祖先に対する信仰心のようなものを強く感じ、そういった部分に感銘を受けたりもしました。一人旅のおともにもいい本だと思います。
18投稿日: 2015.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ『西の魔女が死んだ』の梨木香歩さんのファンタジー小説とは言え、明治・大正あたりの匂いを感じさせる小説『家守奇譚』を読了。亡くなった友人が住んでいた一軒家に移り住んだ主人公が経験する、亡き友との交流と家の周りで出会う不思議な存在と交わる経験を書き綴った形になっている小説なのだが、まず最初に感じたのが作者が女性だと感じなかったこと。森見登美彦氏の作り上げる不思議世界にも共通する部分があるのだが、女性が書き上げた世界であるとは承服しがたく底がまず第一の印象だった。もちろんとても面白く読めたし、もっと彼女の作品を読まなければ分からないのだろうが男性の感覚を併せ持つ作者もきっと不思議な人なんだろうと思わせる小説だった。
1投稿日: 2015.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ先に冬虫夏草を読んだので。こういう雰囲気を出せる作家さんはなかなかいないのだろうけれどどうにも苦手。
1投稿日: 2015.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議な味わいの小説。読みながら思い出されたのは『蟲師』の世界観。作者の物語には初めて触れたけど、なかなか興味深かったです。とりあえず次は『西の魔女』も読んでみようかな、と思います。
1投稿日: 2015.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログここ数冊エッセイが続いたので少し現実離れした物語をと思いこの本に手をかける。 何もそこまで、離れすぎ。 タツノオトシゴ 人魚 河童 小鬼 桜鬼…もぅ天晴れ、なんでもこい。固定概念?何ソレいらない。 竹と格闘したサルスベリのいじらしさったらもぅ。 知らない植物が出てきたらその章を読み終わってから画像検索で想像との答え合わせ。想像できるところが小説の醍醐味。なかでもカラスウリは圧巻だったな。 読み終わるのが勿体なくゆっくりゆっくり読みました。想像が追いつかない処もあったけど今度読み返した時はどういう風に読めるのかな。それすらも愉しみ。しばらく熟成させてからまた読みたいな。 心が豊かになる一冊。 この本は私の好きな本です。
1投稿日: 2015.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ亡くなった友人の家に住む人の不思議な話。自然豊かな昔の日本を思い出させる話だった。読んでいると落ち着く。
1投稿日: 2015.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ奇麗なお話だな~ というのが読み終わった感想 私がこれまで読んだ小説とはあまりに違うテイストなので 正直読み進めるのが結構つらかった。 作品が悪いのではなく、作者さんが持ってる世界とそのリズムが 自分の中に無かったものなので。 一度読み終えたわけだが、まだ消化しきれてない感じがする。 もう二度三度、繰り返すことが必要かな。
2投稿日: 2015.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログどうしても、歳とともに、読む本の振れ幅も放っておくと狭くなって来るなあ、と思っていました。 基本、物語小説本が好きなんですけど、ノンフィクションも読みたいなあ、読んだことのない人の本を読みたいなあ、と思うのですが。 本屋さんに行くにせよ、ネットで買うにせよ、どうしても「あ、この人の新刊が」「この本、読みたいと思って読んでない」と、安全牌や心の中の「積読」消化に流れてしまうんですよね。 それはそれで良いのだけど、ちょっと物足りない。 という気持ちもあって、あとは何よりたまたまなご縁があって、お友達と「ゆるい読書会」を始めたばかりのところです。 互いに「推薦図書」を1冊、あるいは2~3冊出して、その中で1冊決める。3人なら3冊になります。その内1冊は自分が推薦しているから、未読は2冊。 それを、2か月くらいとか、ゆるく期間を決めて読んでおく。 そして、不定期に都合の合うとき、2か月に1度でも3か月に1度でも、「読んだ本について語り合う」ことをゆるい口実にして集まって、ゆるく食べたり飲んだりする。 まあ、あまり読みにくいもの、専門的なもの、そして何より長いものは互いになるたけ遠慮する、というゆるいモラルで。 そんなゆるい読書会の課題図書。 やっぱり嬉しいのは、自分独りのアンテナでは引っかからない本と出会えること。 あるいは、「知っていたし読もうかな、と思ってたけど今一つ踏み出せなかった本」を読むきっかけになること。 梨木香歩さんは、「西の魔女が死んだ」だけなんとなく書名を知っていた程度でした。 この「家守奇譚」は実に薄くて読み易い。連作短編の構成になっています。1篇はそれぞれ、ほんとに文庫本で5ページくらいとか。 するすると読み終わり、そして大変に面白かったです。 舞台は100年くらい前の日本。なんとなく琵琶湖周辺のようですが、地名は明かされないし、方言は誰も使いません。 100年前だから、明治末期か大正初期くらいの感じですね。夏目漱石さんの時代と思えば良いのでしょう。 主人公は、恐らく30代くらいなのか。売れない小説家/物書きの男性。 若い頃、学生時分だったか?の、お友達が水難で死亡。その友人のご両親とご縁があって、空き家の「家守」として一軒家に住みます。 そこの一軒家には多くの植物がいて、池があって生き物がいる。 そして、奇譚、ですから、いろんなトンデモないことが起こります。 死んだ友人は掛け軸から時折現れて会話して去ります。 河童は出てくるし、小鬼は出てくるし、サルスベリの木は意思を持ち、鮎の人魚も出てきます。 狐も狸も化かします。 なんだけど、それが実にナントモほのぼのと、淡々と、びっくりしている主人公すらあまり度胆を抜かれず受け入れます。 つまりなんというか…児童文学畑の人らしいというか、これ、ジブリの味わい。「となりのトトロ」「崖の上のポニョ」のテイストです。 ところが別段感傷的でもなければ、教条的でもなくて。かと言って、枯淡、淡々、とあまり言うと間違っていて。どこかラブリーなんです。 そして、全体を漂う、絶妙な個人主義的佇まいと、その上に成立している共同体というか、ヒトに限らぬ生物間の「つながり具合」なんですね。 この匙加減がすごいのが、だからと言って、「出会って、反発して、惹かれあって、友情があって」という熱い風味は一切ないんです。 そこの、「近いようで遠いけど、淋しいようで淋しくない」という人間関係(ていうか、幽霊とか樹木とか動物とか化け物なんですけどね)が、素敵なんだろうなあ、と思います。 そして、僕が感心するのは、そういう味わい、狙いを体現するための、実にがっちり腰の据わった文章力。 うどんでいえばコシがあるといいますか。 安易に堕さず、気取らず、素直だけれど気品が香る。 会話体をカギカッコではなく、 ---どうだい ---なんでもないよ というように棒線で表すなど、実はきっちり、仕込みも味付けも、一流の手間、時間のかかる仕事がさりげなく詰まっている小鉢の惣菜のような。 個人的には、犬がラブリーに出てくるのも好きでした。 なにかと猫が全盛のこのご時世、ちょっと犬の旗色が悪いですものね。 都会暮らしの身の上としては、ちょっとこう、ほっとする古い街並みに出かけたような。 京都みたいな圧倒的な観光地じゃなくて。 そこで別に、有名でもなんでもない饅頭でも食べて、飲んだほうじ茶がほっと美味しかったような。 出会えてうれしい1冊。続編が出ているそうなので、それも遠からずの愉しみです。
3投稿日: 2015.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ温かく美しい画集を眺めているかのような感覚で読んだ。起伏のある物語、というわけではないので商業的な意味で安易に映画化してもいまいちそうだけど、例えば私が絵を描くのが好きだったら、または作曲ができたら、映像作家だったら、盆栽とかガーデニングが趣味だったら、、、何らかの手段でこの世界観を再現したくなるだろうなあ。 優しい雰囲気で彩られてはいるが、怪しい長虫屋や世慣れた和尚やからかい癖のある亡友など、やや毒気のあるキャラクターの配置が絶妙。 科学では説明できない、もののけ(とは呼んでないけど)的な現象が、ほんとうにあったのかもと思わせる「百年ちょっと前」という時代設定がにくいっすね。
2投稿日: 2015.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ100年ほど前は本当にこんなことがあったかのような錯覚をおこしてしまう不思議でほっとするお話。疎水が流れ込み池やたくさんの木々、草花が溢れる庭。暖かい人との交流。すべてが優しい。
1投稿日: 2015.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ2005年本屋大賞3位 亡き友人宅で家守として暮らしていると、狐や狸、草木に化かされたり、河童、人魚、小鬼が現れたりと、滋賀と京都の境目辺りを舞台としたお伽噺。 「日本昔ばなし」のような仄々さ。 温かく懐かしい匂いのする素敵な世界観でした。
1投稿日: 2014.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議なでも自然に受け入れている自分がいる世界。日本人ならではの空気感なのでしょうか。気持ちいいです。
1投稿日: 2014.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ何かいいな。とじんわりしました。解説に「日本人DNAに響いてくる」と言うのがまさに、で。優しさだけでなく、強さのような物もあるのが胸を打たれます。
2投稿日: 2014.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログラジオ文芸館 2009年7月4日 アナウンサーの朗読だからもちろん、はきはきして聞きやすいんだけど…。演技に期待をする番組ではないんだろうな。 聞き取りづらくて演技もいまいちな俳優よりはアナウンサーの朗読の方が良い。アナウンサーよりは声優の朗読の方が好きだ。
1投稿日: 2014.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ四季を二十四節季ではなく二十八の草花で題し、どことなく懐かしい生き物達との怪異な話。 昔話のようなどこかで聞いたような物語。 知らない植物の名前が多々あり、その都度調べながら楽しく読みました。 ふきのとうに雄花と雌花があることを知りました。 ホトトギスの狸の恩返しと野菊でのリサベルが好きな場面です。 それにしてもゴローの悠々とした雰囲気がとても楽しい。
2投稿日: 2014.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ亡き友の家の家守となった主人公征四郎が、四季と通じ合うゆったりとした空気の中で出会う数々の怪奇、でもそれに対して恐れたり疑ったりすることなく受け入れてしまう主人公がとっても良いなと思う。出てくる自然とのエピソード(サルスベリに嫉妬されたり、河童を助けたり…)が想像力をかきたてられる。又、亡き友がふら~と現れてぼそっつとつぶやきまたあの世へ帰っていくのも心くすぐられる。さすが、本屋さん大賞ノミネートされただけある。手元に置いて心を軽くしたいときに読みたくなる一冊です。
4投稿日: 2014.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログようやく読みました! レビューを書いてくださったみなさん、紹介してくださりありがとうございます。 いつもお邪魔させていただく読書ブロガーさんや、ブクログのみなさんの絶賛のレビューにより、いつか読みたいと思って書いた走り書きのメモが何枚も見つかり、ずいぶん前に、アマゾンで注文したものの1年以上放置したまま。 家の本だとついつい後回しになり、また、すごくおいしいと評判のスイーツをお取り寄せして、期待が膨らみ過ぎたためにがっかりしたくないと食べるのをためらってしまう心境にも似ていた。 たまたま図書館で借りた本もなく、機が熟した!と決意して手に取ってみたところ、1ページ目からあっという間に梨木さんの世界の虜に! 著述業で収入を得る青年・綿貫が、亡くなった友人・高堂の家の守をその父親から頼まれたことにより、話は始まる。 時代は明治の頃か。先代の頃は丹精込めて手入れをされていたであろう庭を持つ和風建築の屋敷に、お隣の奥さんや近くの寺の和尚と付き合いながら、犬のゴローと暮らしている。 庭の草木の描写を通して、過ぎゆく季節の移ろいや隣人たちとの交流が丁寧に描かれていく。これだけであれば、エッセイ風の小説ということになりそうなところなのだが、草木は心を持ち、意志があり、綿貫の暮らしに小さな事件や彩りをもたらす。そこへ亡くなった高堂が床の間の掛け軸を通じて、こちらの世界にやってきては綿貫とごく当たり前のようにやり取りをし、その上、河童やら、琵琶湖の姫様まで登場するから、ファンタジーに分類されそうだけれど、西洋風にそう呼ぶのは躊躇われる。なぜなら、そういった暮らしが、日本には何十年か前まで当たり前のように存在していたと思わせる筆致だからである。人々が自然がもたらしてくれる豊かさや情緒、更には災害などの脅威まで含めて、「ともにある」ことを受け容れているさまがごく自然に描かれている。 現代では「河童伝説」というように、日々の暮らしとは切り離されているけれど、恐らく高度経済成長以前までは身近なものだったんだろうなあ。 端正な文章でありながら、ユーモアも忘れない。 明治の人々の間に流れるゆったりとした時間や、知性的な会話。選び抜かれた言葉が整然と並ぶすがすがしさ。 ふふっ、と柔らかな笑みが溢れるのを押さえられない。 そこには、あたかも外国から取り入れた今風のコミュニケーションという言葉にひとくくりにできない、思いやりや近所付き合いを含んでいる。 ずい分前にごく小さなゴールドクレストを買って育てていたことがある。本来北の国で育つこの木は、日本の気候では暖か過ぎてあっという間に大きくなった。数年でベランダの天井に届きそうになり、この先持ち出すこともできなくなりそうになったので、当時住んでいたアパートの庭に勝手に植えてしまった。木にも魂があるような気がして、塩とお神酒でお浄めのまねごとをして植え替えたのだが、今はどうなっているだろう。 DNAが北の地を恋しく思わせてはいないか? 人間の勝手を少し申し訳なく、思い出した。
15投稿日: 2014.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログある古い家を友達から借りて住んでる人の日常物語なのだが、世界観がいい。木が人に懐いたり、家に河童が出たり、掛け軸の中の舟が床の間に乗り上げたりする。美しい夢を見るような読み応え。 文体が厳しめなのがまた渋くていい。 これは欲しい小説。
1投稿日: 2014.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説の舞台の近くに住んでいる友達がいて、 私も親しみ深い場所だから あぁ、やっぱりこんなことがおきてたの、 うなずけるわ、って感じだった。 あの付近の桜にはやっぱり花鬼がいるんだなっと思ったし。
4投稿日: 2014.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ続編『冬虫夏草』がようやく借りられたので、まずはこちらの再読から(2014.8.29) 夏の終わり百日紅の花を見て、読み返したいと思っていたところだった。ところがこの本では百日紅の花が満開という話から始まるが、よくよくみるとそれが4−5月頃という設定になっているのが不思議。あとは初夏から梅雨を経て夏、秋、冬、桜の季節、と順当にめぐっていくのだけれど。 それはともかく、何度読み返してもいい作品。うつろう季節のなかで、淡々飄々として感情の動き豊かな綿貫征四郎とともに知らず知らず異世界にまぎれこんでしまう。どこからどこまでが夢か現かわからない登場人物(人と限らず、生きとし生けるものから家までも)とできごとばかりだけれど、ふしぎとおそろしさよりも親しみを感じてしまい、こんな体験が自分にもできたらなどと思ってしまう。
1投稿日: 2014.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ独特な質感。怪異にさして驚くこと無く、かといって日常として受け流すでもない主人公がいい。また、高堂の存在が安心を与えてくれて安心して読める。
1投稿日: 2014.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ【本の内容】 庭・池・電燈付二階屋。 汽車駅・銭湯近接。 四季折々、草・花・鳥・獣・仔竜・小鬼・河童・人魚・竹精・桜鬼・聖母・亡友等々々出没数多…本書は、百年まえ、天地自然の「気」たちと、文明の進歩とやらに今ひとつ棹さしかねてる新米精神労働者の「私」=綿貫征四郎と、庭つき池つき電燈つき二階屋との、のびやかな交歓の記録である。 ―綿貫征四郎の随筆「烏〓苺記(やぶがらしのき)」を巻末に収録。 [ 目次 ] [ POP ] 駅近、庭・池・電燈付二階屋。 家守求む。 ただし人にあらざるもの千客万来。 私はこの家に住みたい。 今はなかなか感じることの出来ない、四季折々の自然がこんなに様々な姿でむこうからやって来てくれるなら、多少の怪異は我慢できると思うのです。 [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
1投稿日: 2014.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014.8.20 pm6:45 読了。 なんとなく消化不良。もう少し間をあけてまた読みたい。植物の名前がいっぱい。雑草だとか花だとしか思っていなかった植物の名前を知るだけで、それはもうただの植物ではなくなる。確固とした個を持つ。なんとなく眺めるだけでは、気づけないそれぞれ。景色を綺麗と思うとき、景色を景観とみる、または構成するモノの名前を知っていたら、全く違って見えるだろう。地元の行き慣れた道を通るとき安心するのは、その道がどんな道か知っているから。構成要素を知っているから。その土地に長く住むということは、その土地をつくるモノについて知っていくということか。進学するとき、県外に行きたかった。けれども、地元で学ぶというのもひとつの道だったのかもしれない。でもきっとことことには外に出ないと気づけなかっただろうから、結果的にはこうなるべくしてこうなったのかな。 植物の名前を知らなくても生きてはいけるが、知っていた方が絶対楽しい。知ることで、知っていることで、うつる景色がかわるから、本を読むのはやめられない。消化不良だが、続編は気になる。
1投稿日: 2014.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログうつりゆく季節を、四季折々の草花や生き物をまじえて、せつせつと感じさせてくれる。不可思議であるのに、それが、さも当たり前のように通り過ぎていく。何度も読み返したくなる作品。
1投稿日: 2014.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ四季と時候と犬と暮らし、そして不思議なこと。 ああ、そうか、って不思議なことなのにすとんと受け入れてしまうことはとても素敵。私も庭をじっくり見てみようと思う。
1投稿日: 2014.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログふしぎなものがいっぱい出てきて、どことなく異世界にいるような感覚が素敵だなあと。おはなしが季節に沿ってるのもとても好み!
1投稿日: 2014.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ゆったりした時間、のんびりした怪異この季節にはぴったりな読書体験。 恒川作品とはまた違った和風ファンタジー。 恒川作品ほどシャープさはなく柔らかく女性的な物語。
2投稿日: 2014.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
このような古風な気が流れ出す文章を、私とは3歳差の作者がものしたという事実より、明治か大正の文士の卵、綿貫征四郎の手によるもの、と素直に受け止める方がしっくりとくる。 全編に流れる気脈に酔いしれた。 俗世に住まう身ならば気づきもしない数々のものの気配を、(おそらく)山科の気に身をどっぷりと沈め、その気脈に感応したに違いない征四郎というパラボラアンテナが寄せ集める。 季節の移ろうままに、まれに乗せられるひと色以外は墨絵のような幽玄の美を、私は確かに感じたと思う。 昭和生まれの私だが、いくつもの原風景がこの小説の風物に重ねられて心に浮かぶ。しかし、友人・高堂の生家の家守である征四郎が、いかなる特権で、この地の結界の内側にすべりこみ得たのかは、わからない。ただ、それが何気なくできてしまった征四郎が、うらやましい。人は銭のために生きるべきではないのだな。それも資格の一つではないかと、漠然と納得する。 私には、水の底をのぞくことすらもできないだろう。いや、サルスベリに懸想されることも、決してない。 征四郎を羨む自分の隣に、自分には到底無理であると理解している自分がいることを理解して、私は少しだけ安堵する。 人の世に生まれて…人の生き場所をこれほどにうらやましく眺めたことはない。高堂ほどのよき友人を持ったことも、宿命を悟ったことも、ない。 それゆえにこの物語はすべてが茫洋として、夢のようでいて、なのにそれを受け容れてしまう。もちろん、ガラスケースに収まった箱庭のように何度でも眺めることはできるけれども、私自身はそのガラスに顔を寄せてみることしかできないのではあるが。 私が征四郎なら、よかったのに。でも、私は征四郎にはなれないのである。 冬虫夏草へ。
2投稿日: 2014.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ冬虫夏草よりも前の時系列の話? 順番を間違えて読んでしまった(^_^; 以下、感想は冬虫夏草と同様。 表題を含め、植物に関連するちょっとした話が、短編集のようにちりばめられている。 著者は学士の綿貫征四郎という形態をとっており、彼が体験する日々のちょっとした事々が記述されている。 ほんわかした話で、暇つぶしに読むにはいいと思う。
1投稿日: 2014.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ行方不明の友人高堂宅に頼まれて住み始めるようになった作家志望の主人公綿貫。そこは植物、動物、物の怪など、さまざまな来訪者がやってくる不思議な家だった。綿貫・高堂、そして飼い犬ゴローを中心とした連作短編。 言葉を発することのないはずの植物や動物たち、死んだはずの高堂…普通に考えれば不可思議な現象を、綿貫をはじめこの世界のすべてがごく自然に受け入れる。少し不器用ながらも実直な綿貫と、そんな彼をからかいつつも見守る高堂のやりとりも微笑ましい。 あらゆる生き物の交流を通じて、自然を慈しみ、四季を感じられる作品。一篇一篇は短い話だけど、一冊を通してなんとも言えない贅沢な時間を過ごせた。なんて調和の取れた柔らかい世界なんだろう。読むと自然にどっぷり浸かったように心が安らぐ。 続編「冬虫夏草」も読まなきゃ。
9投稿日: 2014.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段の生活の見方を少し変えてくれるような、ああ良い本読んだなあとにやっとさせてくれた。 ちょっと疲れた、という時にまた読み返したい。 蟲師とか好きな人はツボに入りそう。
2投稿日: 2014.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ草木に疎いせいか、 シュロ、クスノキ、キンモクセイ、サツキにサザンカ…… と続いても各々のイメージを湧かせにくく 序盤はやや読みにくく感じました。 (でもキンモクセイくらいは知ってるよ!) だが読み進めていると これが滅法に面白い。 いかにも自然体に(ときにはやせ我慢であるが(笑)) 超常現象を受け入れていく主人公の懐の広さが 作品に奥行きを作り出している。 素敵だなー。 この世界も、主人公も、友情も。 なんとなく夢枕獏氏の『陰陽師』を思わせるのは 伝奇的な内容で、短い会話がテンポ良く進んでいくからかな。
3投稿日: 2014.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログいいか、この明るさを、秋というのだ、 と共に散歩をしながらゴローに教える。 ゴローは目を閉じ鼻面を高く上げ、 心なしその気配を味わっているかの如く見えた。 私がゴローで一番感心するのは、斯の如く風雅を解するところである。 犬は飼い主に似るというのは、 まことにもって真実であると感じ入る。 亡き友人の家を守ることになった 綿貫 周辺で起こる奇怪なできごとに 驚きつつも すべてを受け入れる 達観 植物の名は 章タイトル 掛け軸から出てくる高堂を切っ掛けに 植物の蔓が伸びて 物語をつないでいくような。 ゴローの活躍にも 注目です。
4投稿日: 2014.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
明治中期の琵琶湖近辺で早逝した友人宅の家守をしている作家の著述という設定で、文章もやや古めかしい。梨木さん作品としては少し異色の奇譚モノですが、100年少し前はラフカディオ・ハーンが怪談書いたのと同時代の設定。急激に近代化が進みながら、まだ妖怪やら自然の気やらが残っていた最後の時代かもしれません。
2投稿日: 2014.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ庭・池・電燈付二階屋。汽車駅・銭湯近接。四季折々、草・花・鳥・獣・仔竜・小鬼・河童・人魚・竹精・桜鬼・聖母・亡友等々々出没数多……本書は、百年まえ、天地自然の「気」たちと、文明の進歩とやらに今ひとつ棹さしかねてる新米精神労働者の「私」=綿貫征四郎と、庭つき池つき電燈つき二階屋との、のびやかな交歓の記録である。
2投稿日: 2014.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語の舞台は滋賀、京都の周辺か。琵琶湖に注ぐ水の流れと、自然とともに暮らす懐かしい日本の原風景が感じられる。自然への畏敬と共に暮らしていたはずの私たちの感覚がよみがえる。 サルスベリの木が人に懸想したり、竜は踊り、小鬼が行き交う不思議な世界。怪異と人が入り乱れ、日常的に存在することをひょうひょうと受けとめながら過ごしていく物書きの主人公。時に異界に紛れ込んだ友人が、当たり前のように掛け軸から出現してくる。まさに奇譚。 あまりにも異界との交わりが面白く。最後まで一気読みでした。他のレビューにもありましたが、坂田靖子の作品に登場する、常識を超越した友人と、現実からちょっと足を踏み出す主人公の物語にも似た感じ。あの、ほんわかしたシュールな世界は大好きです。 続編の「冬虫夏草」は図書館で予約中。期待しております。 久しぶりに坂田靖子のコミックも見てみたい。
29投稿日: 2014.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ早世したはずの友人がひょっこり現れ、サルスベリには惚れられ、犬のゴローは河童に懐かれ…泉鏡花の作品のように、日常のなかに巧みに入り込んでくる異界の者。 なんでもない生活のつもりが、狐狸に化かされ、ふわふわと執筆も進まず。しかしなんだか愉快なお話でした。
4投稿日: 2014.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議な懐かしさを感じる作品です 主人公の綿貫征四郎さんは売れない物書き 早くこの世を去った親友の高堂さんの実家に[家守]として暮らしている 亡くなった高堂さんが掛け軸から現れたり、さるすべりに好意を寄せられたり、カッパの脱け殻を拾ったり。。。 でもね、100年くらい前だったらこんなこともあったかなぁっていう気がします 大人のファンタジーなか…
1投稿日: 2014.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ淡々と話がすすむ。 坂田靖子の漫画と空気が似ているかなとか、いや漱石とか百閒先生の毒や棘を抜いた感じ?それかモリミーのきつねのジットリとした艶をなくしたような? 湖で行方不明になった友人の家の守を頼まれた綿貫氏。 物書きの本分はあまりお金にならないけれど、家守の仕事はなかなか賑やか。 友人の高堂が掛け軸の中からフラリとやってきたり、サルスベリに懸想されたり、河童や竜田姫の侍女が迷い込み、狸に化かされている。 「おまえは大体己というものが見えていない。ものごとの機微というもの分かっていない。こんな了見でものを書こうと言うのだからつくづくあきれたやつだ。」 「まあ、誰でも見えていないと云えばそうなのだが、おまえのようなやつも珍しい。しかしだから僕なんぞを引き寄せたのだろう。」 と高堂に言われてしまう綿貫氏。 綿貫氏やこの世界の秘密が最後に明かされるのか? 季節が移ろう描写が美しく、綿貫氏が目を留める植物や風景がフラリと出かけてみてみたくなる。 綿貫氏とダァリヤの君もとても気になる。淡々とフワフワと、さて着地した先は。 「埋めてもらいたい場所…自分の場合はどこだろう、と考える。ふと、思いついて、 ーーおまえはどうなのだ。埋められたい場所があったのではないか。」 「その件は果たした。」 「思い込みというのは恐ろしいな。」 「だがとりあえずは思い込まねばな。」
7投稿日: 2014.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ幻想的で儚げで現実と非現実の境目のような物語。とっても素敵でした。表現が丁寧で情景がありありと浮かび、不思議な事柄もあたり前のようにすっと描く文体も好き。ちょっと昔の日本にはこんな世界が広がっていたのかなーとか想像するのも楽しい。日本の自然の豊かさや昔から伝わる妖怪などの伝説にも興味が湧いた。
4投稿日: 2014.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログステキな文章なんだろうと思う。草木やらファンタジー生物の描写が素晴らしいんだろうと思う。 読者にそれを楽しむ高尚な心が無かっただけなのだ。
0投稿日: 2014.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ幻想的で、どこか夢見心地な気分に浸らせてくれる一冊。文章が美しく、読む人を現実とは離れたところに連れて行ってくれる。主人公と高堂の気心が知れた者同士のやりとりも面白く、ところどころに出てくる空想の生き物の描写も美しかった。どこかに本当にこういう場所があれば良いなと感じた。四季折々の植物をテーマにした短編というのも、自然から離れている現代人に、自然の大切さを思い起こさせてくれる。ページが少なくなっていくのが惜しく、読後は夢から覚めたような心地がした。
2投稿日: 2014.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本人の精神世界。土と草木の香り漂うお話。 中勘助の『銀の匙』を読んだ時のように、澄んだ気持ちになる。あの本を読んだ感想は確か「ビー玉を覗き込んだような読後感」だったか、そんな感じ。 『夏目友人帳』のような空気感、『××HoLIC』のような妖しさ、『蟲師』のような自然との調和、この辺の作品が好きな人はこれも好きになると思います。そういえばこれもワタヌキが出る。 でも、やはりどこか本物ではない。銀の匙を読んだ時ほどの清涼感がない。だから最高評価にならない。 なんだろう。明治の文学はもっと淡泊で愛想がないんだよな。これはちょっと気が利きすぎている感じがする。まぁ、別に昔っぽさに囚われることはなんだが、そっちを目指しているような雰囲気だったから物足りなさを感じたのは事実。 関西ってスピリチュアルだなと再認識。これは琵琶湖周辺だろうか。せせらぎが常に連想される。 島根とか神戸への旅行で感じた東日本との空気の違い。なんなんかなー。アニミズム感じるのは仕方ないって気になる。 琵琶湖の周辺に聖地巡礼したくなりました。 ・真野川 ・安寧寺川(安祥寺川) ・竹生島 etc どうやらほかの読者も同じようなことを考えていたようで、検索すればその手のブログがいくつもww
1投稿日: 2014.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ緩い感じがしました。そしてうっすらと物語にモヤがかかったような不思議な感じがしました。古風な感じが綺麗に思えていい作品だと思いました。
1投稿日: 2014.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ語り口がユーモア溢れていて、何気ない一文にもこみ上げるような笑いがある。かと思えば、はっとするような徳の高い一文も多々ある。 清貧を貫き贅に甘んじない生き方を問われ「私の精神を養わない」と言ってのけたのはとてもかっこよかった。
2投稿日: 2014.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然の中にちょっと不思議なものたちが当たり前のように存在している、おもしろさ。物語のいくつかを寝る前に、息子によみきかせをしながら読んだ。このちょっとふしぎさ、寝る前のおはなしにぴったりで、自然と眠りに誘われる。
2投稿日: 2014.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ妖怪や不思議なものたち、人間に想いを寄せる百日紅(花)との穏やかでちょっぴり不思議な日常。犬のゴローさんがかいがいしい。
2投稿日: 2014.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ夏目漱石かなにかを読んでいる気分。異界のものとの遭遇が絵巻物でも見ているように綴られているが、結局、なんやよくわからんかった(笑)
1投稿日: 2014.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ初読。自然の描写がとても美しかった。自分は「ススキ」が特にすき。繊細な描写なのに、掴み切れないという印象は先に読んだ『滞土録』以上に感じる。不思議が普通にあって、境界が曖昧。曖昧だけど確実にある境界のごく近くで、こちら側にいるのが綿貫であちら側にいるのが高堂。似ているけど対照的。個人的には『滞土録』のほうがすきかな。
2投稿日: 2014.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体に霧に包まれたようなボーッとした雰囲気なんだけど、最後の征四郎の一言で、その霧がスカッと晴れたような気がしました。あの7行を読んだ時、この本読んでよかったって、はっきりと思いました。
2投稿日: 2014.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログハードカバー版を図書館で借りて読んでいた。 『水辺にて』を読んでから文庫を購入。再読。 吉田伸子さんによる解説もよかった。 後日談 なんと、本棚の奥から複本がでてきたのである。 ということで、8日の一箱古本市にて自信をもっておすすめしたい。
2投稿日: 2014.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ素敵だった~~ 我輩は猫である、とか森見登美彦とかの雰囲気があって可笑しい 超然とした高等遊民に憧れます 事象を受け止め咀嚼し、返す。疲れない程度に、急がずに。 高堂には会いたいね、また 百日紅も。
1投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さん著の「家守綺譚」を読んだ。 梨木さんの作品は「西の魔女が死んだ」に次いで、二作目になる。 一話一話は短い内容で、サルスベリに始まり、葡萄で終わる全28話。 今は亡き友人・高堂の家守をする物書き、綿貫征四郎の目線で書かれている。 掛け軸からやってくる高堂とのやり取り、愛犬ゴロー、お隣のおかみさんのはなさん、 囲碁好きの和尚、長虫屋、河童、カワウソ、小鬼など、登場人物(?)が愉快である。 また、草木の人間のような描写も面白い。 草木は話せないが、 きっとこの本のような思いを抱いていると思う。 非科学的な話であるが、 面白くて、あっという間に読んでしまう。 続編である、「冬中夏草」も文庫化されたら、 是非読みたい。
1投稿日: 2014.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログうつつと夢とを行き来しながらの何と無く居心地のいい世界観に浸れた。かなり好みです。なんか、xxxHOLiCと感じが似てる気がする。
1投稿日: 2014.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。しかし、良いですね。 友人の幽霊、恋するサルスベリの木、仲裁犬、河童、人魚。様々に不思議なモノたちが、淡々と現れる不思議な話。 この作品を読むと「賄い料理」という言葉が頭に浮かびます。 お客さん(読者)に出すものでは無く、料理人(作家)が自分や身内のために気取りなく作った料理(作品)。しかし、それが余りに美味しく、裏メニュになってしまった。 私の勝手な思い込みなのですが、なんだかそんな気がするのです。
2投稿日: 2014.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ四季折々の植物,飼い犬のゴロー,河童,狸,子鬼,人魚... 少し不思議な出来事を、そのまま受け入れる征四郎が 微笑ましいというか、なんだかすごくいい。 ほっとするような、懐かしいような、 この雰囲気が好き。 続篇もでたようなので、ぜひ読んでみたい。
1投稿日: 2014.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログもう私のバカバカ!なんでこれを今まで読んでなかったんだろう。苦手なファンタジーだと思って敬遠してたんだよね。でもファンタジーには時々すごく私好みの大当たりがあるのだった。もっとアンテナを敏感にしておくべきだったと、後悔しきり。 本屋さんで見かけた「冬虫夏草」の装幀に心をわしづかみにされて、躊躇なくジャケ買い。「家守綺譚」の続編だということは知っていたので、こっちは文庫で買って、まずはこちらから、と読み始めたのだが、もう出だしの数ページで完璧にその中に入り込んでいた。 読み進むほどにどんどん作品世界に没入していく。静かで、豊かな植物の世界は梨木さんならではだ。雨の描写がとてもいい。自分も一緒に霧雨に濡れているような気がする。雨にうたれる草木のさまや、ひんやりとした空気まで感じ取れるようだ。 ああ、この世界に入りたいなあとしみじみ思う。あら、これは河童の衣ですよ、とか、なんでもないことのようにお隣のハナコさんと言い合ったりして。二度と再び帰ることのない、いろんなものが判然としないままでいられた暮らしに郷愁を感じないではいられない。山や川にいろいろなものの気配が濃くあり、人も生きものもその気配とともに生きた時代はそれほど昔ではないのだ。 読み解いていけば様々なものが潜ませてあるのだろうが、それをいちいち考えるのもちょっと野暮な気がして、ただ絵巻を見るように楽しむ。うーん、なんて贅沢な読書だろう。 読みながらしきりに、漱石の語り口が思い浮かぶ。ちょっと「夢十夜」風なところがあるように思う。また、杉浦日向子さんの絵柄で場面が浮かんでくることもしばしば。杉浦さんがこれを絵にしてくださっていたらどんなに素敵だっただろうか。 征四郎の住む高堂の家は、京都山科にあると思われる。疎水べり、琵琶湖畔、吉田山、征四郎は実によく歩くが、この頃の人はこれが普通だったのだろう。時にお供する犬のゴローがかわゆい。
4投稿日: 2014.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「私の精神を養わない」 主人公の綿貫征四郎が、死んだ友人、高堂の家の管理を任される。植物、隣人、妖怪、畜生など、様々な出会いと問題に巻き込まれるなか、死んだはずの高堂も幽霊?となって家の掛け軸から現れて……。 サルスベリに懸想されたり、犬のゴロー(昔隣人のハナさんが飼っていた犬と同じ名前)が住み着いたり、狸に化かされたりなど、自然や怪異との共存がまだ普通だった時代を、どこか間の抜けた(本人に自覚はない)征四郎が生きていく様を軽やかに表現している。
1投稿日: 2014.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ絵のない絵本を読んでいるような、文章を読んでいるけれど、読みやすくて ほんわかする本でした。キャラクターのみんなが愛すべき感じだから、決着がつくお話じゃないけど、面白かった。また読んだら違う感想を持ちそう。2013.7完読
1投稿日: 2014.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近どうも梨木香歩さんが気になります。 ゆったりした雰囲気と、その雰囲気を支える細部へのこだわりが心地いいからかもしれません。 こちらはポヤポヤした作家志望の(ほぼ)無職男と、 彼が管理人名目で住み着いた家を取り巻く生き物たちの物語。 生き物には、植物・動物・妖怪・死んだ友人を含みます。 なんか大変なことが起こってる気がしても、 ポヤポヤ男の目から見れば「あ~、あるある……。」と納得しそうになる。 小さな物語が積み重なっていく感覚も楽しい。
1投稿日: 2014.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクロググイグイ引き込まれるというよりも、まったりとその世界に浸る、という感じ。この世界観、すごく好きです。冒頭の数ページですっかり虜に。 サルスベリがすごくかわいい!!! 河童とゴローの話もびっくりの展開。 ただ、かなり短い短編からなる構成なので、読み進めるのに時間がかかってしまいました。序盤の話がとにかく面白かったので、中盤は私の中でやや盛り上がりに欠けました。薄いので持ち運びに良かった。 続編を、現在図書館で予約中。回ってくるのが楽しみです。
2投稿日: 2014.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011.12.25 推薦者:修造(http://ayatsumugi.blog52.fc2.com/blog-entry-70.html)
0投稿日: 2014.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「冬虫夏草」の前に再読する。ゆっくり想像して、情景を思い浮かべないと、心に入ってこないので、時間がかかる。ファンの方が、この本に出てくる植物の写真を集めてホームページを作ってくれていて、それを観ながら読むと、さらに情景が浮かんできてよかった。
9投稿日: 2013.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
再読。 多分これまでの人生で最も再読を繰り返している、私にとって特別な作品です。 静謐な空気を纏い織り上げられた文章の美しさと、様々な境界が揺らいでいる様に、何度読んでも感嘆の溜め息が出ます。 読む度に心に響くものがあるのです。 因みに装丁は単行本の方が好きなのですが、残念な事に綿貫の手記はこちらの文庫版にしか収録されていないので、再読は専らこちらで。
2投稿日: 2013.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ劇的なことが起きるわけでもない。 (いや、かなり特殊なことは起きているけれど) それでも淡々と日常が過ぎていって、一年が過ぎる。 強烈な印象ではないのに、心の奥底にしっかりと残る独自の感覚。 自分の心のずっと底の方にある湖に、この物語が完全に沁み込んで同化してしまったような印象。 とても大切なことを思い出した気がする。 庭に出てのんびりしたくなった。 個人的に木蓮の話が一番のお気に入り。
1投稿日: 2013.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ冬虫夏草が面白いと勧められた。 しかしシリーズらしいので先に読んだのだが、こういった雰囲気が好きなので、最初の一編「サルスベリ」の段階で打ち抜かれた。 厚くもないので持ち運び易く、毎日のように読める。 別作品ではちょっと、と思っていた作者だけにしてやられたという感想が大きい。 とはいえ冬虫夏草は単行本なので当分は読まないだろうなあ。
1投稿日: 2013.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ情景描写が美しくてすてき。起きる不思議な出来事を淡々と分析していくのがまた不思議でおもしろい。日常のなかの非日常。
1投稿日: 2013.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ優しくて、ちょっと不思議な世界。 たぶん京都の、なんだかちょこっと不思議な話。不思議と現実の層が溶けちゃっている。少し昔の雰囲気も、それを推し進めている。明治っていいなあ、と思った。「私」=綿貫征四郎の、不思議に振り回されつつ、穏やかに受け止めている感じがいい。サルスベリとゴローがかわいい。 『村田エフェンディ滞土録』も同じ世界観なのかな。読んでみたい。
1投稿日: 2013.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
続編がでたということで・・・久しぶりに読み返しました。 よかった。 静謐という言葉がよく似合う作品でした。静かな気持ちになって、心がほんのりあたたかくなります。 植物の名前の章題でそれにちなんでお話が進んでいく形も好きだなぁと思いました。 高堂が出てくる場面はなんとなく可笑しくて少し切ない。湖、雨、ローレライの話もちらと出てきましたが、水と高堂との結びつきがなんとも言えずミステリアスです・・・。 綿貫が人間、動物に、妖怪(?)、どんな相手に対しても対等に接しているところがよいなと思いました。 最後の夢のなかでの綿貫の毅然とした態度がかっこよくて、優しくて、力強かったです。 サルスベリと小鬼がかわいい(笑) 狸にうっかり化かされたり、高堂にからかわれたりする綿貫もほほえましいです。
6投稿日: 2013.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ花の名前が沢山出てくるのが嬉しい。ひとつひとつ調べながら読みました。 サルスベリがもっと好きになりました。
2投稿日: 2013.11.07
