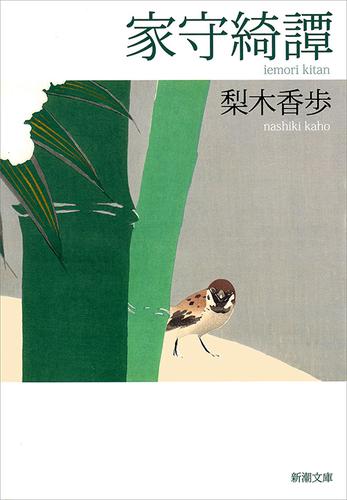
総合評価
(679件)| 313 | ||
| 202 | ||
| 87 | ||
| 6 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ先に近藤ようこさんの漫画を読んだのだけれど、セリフ回しもそのままで、そうか漫画化されるべくしてされたんだなと。 狸、ちゃんと筍の手土産持ってきたり、お礼に松茸置いて行ったり、なかなかできるやつ。
0投稿日: 2025.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の昔ながらの自然を感じられる風流なお話だった。 主人公は若くに亡くなった友達の古い家に、家守として住むことになるが、そこで見聞きした摩訶不思議な面白い話が次々と出てくる。 狸に化かされたり、花の精に想いを寄せられたり、家の掛け軸から出入りする亡き友達の亡霊と話したりと何かと忙しい。 この世とあの世を行き来する感じが不思議で、意外と心地よく、するすると読み進められてよかった。
4投稿日: 2025.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ何とも形容し難い不思議な世界観と空気感。ファンタジーが日常に溶け込んでいて、読んでいるこちら側も自然とその日常を受け入れてしまっているような感覚になる。 ゆったりしていてどこか物悲しい。秋にぴったりの物語。
0投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログとても世界観が好きで良かった。梨木香歩さんが素晴らしいと思って調べてみたら、『西の魔女が死んだ』の作者という事が分かり再度購入し、再読する。
0投稿日: 2025.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログとても不思議な物語。なのになぜか懐かしいような、ずっと浸っていたいような気持ちにさせられる。 この空気感が好きすぎて、久しぶりにこれから何度も読み返したい一冊ができた。
3投稿日: 2025.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議な物語 物書きの綿貫征四郎は亡くなった高堂の家のもりをすることになる 亡くなったはずの高堂が時折り現れたり サルスベリとの対話がなされたり たぬきやきつねに化かされたり 河童の抜け殻が落ちてたり 日本的な、目に見えない五感で感じれるものを大事にしたいと思う
6投稿日: 2025.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログヤッッッバ、どストライクすぎて死んだ。梨木香歩、実ははじめて読んだのだけど、こんなにすばらしい文章をお書きになるの???やばすぎん???(語彙力消失)うつくしい日本語の使い方もさながら、物語もすっごくよかった。まさに家守綺譚。妖しく、ふしぎで、やさしいのかやさしくないのかときどきわからなくなるような、けれども穏やかな非日常。この世界観にいつまでもずぶずぶと沈んでいたくて読み続けていたら、一気読みしてしまっていた。はああ、わたしが死んだらこの本もいっしょに棺桶にぶち込んでほしい。
0投稿日: 2025.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログジャパニーズファンタジー。 身近な植物や動物と、四季折々の少し不思議な出来事と。美しい情景と、主人公の素朴さがなんとも言えず良い。
0投稿日: 2025.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩『家守綺譚』は、静かな不思議が詰まった物語でした。 庭の木が主人公に恋をする場面など、奇妙なのにどこか落ち着いています。 死者との再会も、自然との会話も、日常の延長のように描かれていて驚きました。 大きな事件はないけれど、季節や植物の描写が心に残ります。 読んだあと、身のまわりの自然が少し違って見えるようになりました。 静かな時間に、また読み返したくなる一冊です。
0投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ一つ一つの話がとても短く、ストーリー性はあまりない。 不思議な世界観で、爽やかな雰囲気の話が多い。 最後の主人公の随筆は古典的な文体で読みにくく、意味を十分に把握できなかったが、本編自体は難しくない。 ただ、全体的に自分とは相性の問題もあり、あまり好んで読むタイプの作品ではなかった。
7投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わった!すごく好きな雰囲気のお話だった!満足読書体験ありがとう!!! 帰ってこない友の実家に住んで家を守るやで〜な短編集。カワウソのオジジとか、小鬼とか、カッパとか色々出てきて楽しかった!! 短編のタイトルが全部植物名になってるから、知らない草木について調べてこれがお話の中で咲いてるんだ〜となるのもまた良いね。 夏目友人帳とか好きな人に良さそう。 私もカスミンとかミヨリの森好きなタイプのガキンチョだった過去を持つので、なんかそういうのを思い出した面でもとても好きだなこの作品。 個人的には木槿・リュウノヒゲ・ホトトギス・ふきのとうが好きだなー。 ホトトギス、たぬきいいやつすぎる!!いいやつが出てくるのは読んでいて心にいいよね〜。ふきのとうのお話も小鬼がなんか可愛くてよかった。 最後の話はちょっとしんみりしたりもしたけど、基本的にいいやつしか出てこないし、そもそも主人公の人間性が私は好きだしとても理解できるものだったので読んでいてストレスなくてよかった! 途中に名前が出てくる村田のお話なのかな?スピンオフらしい村田エフェンディ滞土録も一緒に借りてきていたので今から読みます。読書の秋やで!
6投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。勧められて最初に読んだ時は刺さらなかったが、今読むと面白すぎてびっくりした。好みって変わるなぁ。
1投稿日: 2025.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ(備忘)売れない作家の主人公の周りで起きる日々の不思議な出来事(奇譚)を、こんな事はさも当然ですよと言わんばかりのタッチで淡々と描かれる短編集。幻想的であり現実的でもある不思議な世界観が堪らない。様々な価値観で押し潰されそうになる昨今の生きづらい世界において、どんな事でもありのまま受け入れる姿勢は大事だよなあとしみじみ感じました。
7投稿日: 2025.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ時は明治。場所は京都疏水べり。湖で消息をたった旧友の実家の「家守」をすることになった青年文士が、その家での日常を語る、それぞれ植物の名前を題とする28の短編。その殆どの日常にするりと印象的な怪異が起こる。しかし淡々とした語り口と主人公の周りの人々がそれを何の不思議もなく受け入れているせいで、少しも驚異や異様さはなく、とても自然に感じられる。筆の妙。古風で端正な文体が素晴らしい。何度も読み返すべき一書。買ってよかった。
3投稿日: 2025.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログはじめのサルスベリの話から引き込まれてっぱなし。 心地よいリズムの文体でとても優しくて、マジックリアリズムな世界なんだけれど本当に日常で背伸びもない等身大の登場人物。自然と季節の描写も美しく、 漫画化の発表もタイムリーにあってそちらも読んでみようと思う。
0投稿日: 2025.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩に触れたくて読んでみた。 高堂のサラッとしている感じが好き。感動の再会になりそうなものなのに普通に受け入れる綿貫も良い。 植物の描写にこんなに心惹かれることはない。 綿貫を取り巻く人たち(人、犬、植物、河童?鬼??)の描写が何とも言えない暖かさを出している。 梨木香歩の文体が好きだ。と再確認した一冊。
0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ幻想的な世界に魅了されて物語に引き込まれた。 現実と異界が絶妙なバランスで主人公が遭遇していく。 薄い本なので何度も再読するのだろう。
0投稿日: 2025.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログあっという間に読んでしまったけど、これはゆっくりもう1回読み直したい作品であった…… いろんなことをすんなりと受け入れる綿貫がとても好ましくて良い奴で、前後して読んだ「村田エフェンディ」にも登場した訳知り顔の犬、ゴローもまた可愛らしい。 普通にこっち側の世界に来ちゃう高堂も、この作品てもあまりにも普通に出てきていて、笑ってしまった。 この絶妙な“あっち”と“こっち”の境目の感じ、どストレートに好き。まだ続編を楽しめるようで嬉しすぎる。 この本が好きな人は木内昇「奇のくに風土記」「よこまち余話」もぜひ。
7投稿日: 2025.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本、腑に落ちすぎて、読み終えたくなかった 読み終えたら、僕はこの本をどう処理すればいいんだろう?と思った。 好きな人に貸すか?むしろ黙るか? とにかく素晴らしくて、大好きで、この感性って、とても限られてしまうから、本を貸したりして、 読んでもらわないと、どう感じるか反応もわからない。 梨木果歩さんはすごく素敵な方だ。好き。会いたいと思った (続編「冬虫夏草」あるみたいなのですぐ読む)
14投稿日: 2025.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルからなんとなく気が進まなかったが2005年本屋大賞3位なのと薄かったのでなんとか読めるかなと思って手に取る。売れない小説がの綿貫征四郎が、知人の家の守りを頼まれる。収入が安定しない征四郎にとっては渡りに船の話であり、早速、その家で暮らすようになった春から話は始まる。庭の木々、植物や様々な生き物、そのほか自然との交わりが描かれており、やや難解だった。
1投稿日: 2025.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったな〜。現実世界と異世界を行ったり来たり、霧が漂う湖に小舟を浮かべ、風に吹かれるまま揺蕩うような心地よさがとても良かったです。 表紙をめくって1頁目を読み始めると、あえて古い語調を使っているし、女性作家なのに主人公の男性に語らせているので、「お、やるねぇ!」とニンマリしてしまいました。 様々な植物を主題に季節を感じながら話が進んでいくので、その自然描写の美しさがこれまた、とても魅力的です。梨木先生ならではですね。 続編の「冬虫夏草」、姉妹編の「村田エフェンディ滞土録」をこれから読むのが楽しみです。
4投稿日: 2025.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ古風で悠然とした、美しいリズムの文体。 植物への造詣がそのまま自然と物語として紡がれている構成 朧げで、儚げで、それでいて親しみを感じる登場人物(?)たち。 とてもとても、心地の良い読後感。
1投稿日: 2025.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ●2025年6月9日、もう15年以上前から持ってる。橋本駅にあった当時の彼氏(クズ)が借りてたアパートに行ったときに帰りを待ちながら読んだ思い出。 ●2025年6月9日、グラビティの読書の星で紹介してる女性がいた。 「「西の魔女が死んだ」でおなじみの梨木香歩さんの「家守綺譚」、オススメです 亡き友人の家守をすることになった男の周りで起こる、不思議な出来事のお話 事もなげに不思議が話しかけてくるような、それでも心はなんだか浮ついて癒されるような、言葉にするのがむずかしい、しっとりとした読了感です 続編に「冬虫夏草」もあります」 ●2025年7月24日、昨日23日に精神科通院で病院に着く手前でサルスベリがたくさん咲いてる家があった。それをみて母に「梨木香歩さんの本で、家守綺譚というのがあってね。サルスベリが擬人化されたお話なんだよ」とこの本の存在を教えた。
0投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて猫に読み聞かせた本(なんちゅう紹介や) ずっと、この本は素敵だと、読む前からそう思ってました。なぜか。そして、本当に素敵な物語でした。不思議な存在を除外・嘲笑しない世界。良いなぁ。この時代に生まれたかったなぁ。 知らない植物と高堂君に出会える物語。また読み返したい。
7投稿日: 2025.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前読んだことがある気がするがいつか思い出せない。 四季折々の草花、綿貫と人ならざるものたちとの邂逅が緻密に描かれている。
0投稿日: 2025.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生時に亡くなった親友の高堂(こうどう)。 卒業後、執筆だけでは食えず学校の非常勤をしていた主人公が、亡くなった高堂の父親から実家を出て空き家になってしまうため、家の守をして欲しいと頼まれる。 高堂の実家は随分広く、庭にある植物ごとに短編で一冊になっている。内容は普通の植物の話というより少し違う。…亡くなった高堂がボートで掛け軸から出てきて話をしたり、河童が出てきたり…少し現実離れしていて理解しにくいところもあった。 河童が冬越しして固くなった皮を、5月の陽気で乾かして梅雨に脱皮をするという設定はおかしくて面白かった。
12投稿日: 2025.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本版不思議の国のアリスでした。 四季折々の草木や鳥などが登場する美しい描写があるかと思えば、河童や人魚が登場したりと、現実なのか夢なのか不思議な世界が描かれています。 普通だけど普通じゃない世界が面白かったです。
0投稿日: 2025.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ行方不明になった友人の家を管理する事になった作家。その庭では不思議な事が日常のように繰り広げられる。まるで夢を見ているような、でもそれが当たり前の世界なのか、そんな細かい事は気にせずゆったりと季節を廻りながら過ごす生活がとても贅沢に感じる。 ゴローは賢いね、沢山ヨシヨシワシワシしてあげたいね
0投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ湖にボートを漕ぎ出して以来行方不明となった友人の父親から庭付きの家の家守を頼まれる事になる。 四季折々の花、亡くなった友人、草花の精霊、河童、小鬼、人魚など、自然と精霊たち、昔の日本に居着いている妖怪とも言えるものとの交流を不思議な世界観で描いている。
0投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「左は、学士綿貫征四郎の著述せしもの」 と始まるこの物語、粋です。 全てのネット記事にこういうの書かれているといいのに。 時代背景は明記されていませんが、今より昔です。 でも、今の時代とリンクしていて共感できる表現が散りばめられています。 この小説を読もうと思ったのは名取佐和子さんの 「金曜日の本屋さん」の作中で取り上げられていた作品で 書かれているのは「梨木香歩」さん。 図書館で名取佐和子さんの本を借りようとして、同じ本棚に並べられていて 「これは読んでおかなくちゃ」と使命感が湧いたため。 こういう出会いもあるものなのですね。 心が揺さぶられた彼の言葉は、やはり 「私は与えられる理想より、刻苦して自力で掴む理想を求めているのだ。 こういう生活は、私の精神を養わない」 自分の精神を養う生活を今、私はしているのかな?と考えました。 河童の話なんて、今の時代にピッタリだと感じました。 間違った内容を流布して、迷惑がっている人がどれだけいるのか。 私の中で大切にしたい一冊です。
6投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ植物の知識が少ないため、知らない植物が登場するたび画像検索をしていました。 カラスウリの花は印象的。 NHKで10分程度のアニメにしてほしいなとか思いました。 この独特な世界観を視覚的に味わいたい。
29投稿日: 2025.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ何も知らない状態で読み始めたため、まず第一に 「なにかの現代語訳…?」と混乱しました(笑) そのくらい自然に、摩訶不思議な世界のお話が紡がれていて、気づけばその世界に没入し一気に読了しました。おとぎ話や日本むかし話に近い感覚で楽しめると思います。 本書では、亡くなった友人をキーパーソンとして異世界感満載なお話が続きます。それでも、昔ながらの田舎の温度感や、お盆で故人を忍ぶ風習に親しんだ日本人にとって、何故か自然と肌に馴染むので不思議な一作です。
1投稿日: 2025.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初から最後まで不思議な世界観。庭の植物や近所の山や、道すがら奇妙なものが出てくるものの正体は、西洋であれば植物の妖精のようだが、その植物は日本に自生する植物であり、妖精も日本らしく風流でしっとりしていて、時には子憎たらしかったり、いたずら者もおり、そして妖しい。 いわゆる海外のファンタジーに出てくるキラキラした妖精も好きだけれど、この小説に出てくる妖のような存在は、肌馴染みがある感じがし、生と死の世界観もなんだかしっくりくる。 出てくる植物の姿を知って読むと、より一層世界観が楽しめる。
1投稿日: 2025.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
山を一つ越えたら湖がある家の守をしている売れない作家・綿貫征四郎の非日常的な日常の話。 隣家のおかみさん、犬のゴロー、サルスベリ、河童、ダァリアの君、人ではないものも交えた生活の中で、しばしば亡くなった友・高堂が訪ねてきてさらなる非日常に巻き込まれ日々が過ぎていく。 サルスベリとゴローがとても可愛い。 湖は琵琶湖、舞台は京都山科から滋賀(P93の牛尾山は京都と滋賀の境目)、時代は↓のHPがとても参考になった。 http://furusato.la.coocan.jp/kagamiyama/bungei/sanpoiemorikitan.html ゴローが河童を返しに行った朽木は滋賀県高島市、山科からはけっこう遠いなー…。 今回登録しましたが以前から何度か読んでいて、心を落ち着かせるため24年12月に本棚から取り出して2回読みました。
1投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ目に浮かぶ風景はとても色鮮やかで美しく、庭の草花から四季を感じられ、でも透き通っていて、奇異な世界観に引き込まれました。とても素敵な奇譚でした。 犬のゴローが頼もしい。
0投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『村田エフェンディ滞土録』と繋がっている世界線の物語。(というか『家守綺譚』のスピンオフが『村田エフェンディ滞土録』というのが正しい。) 征四郎が、人だろうが人ではない怪異や精霊、獣だろうが、とにかくなんであっても、真面目に真摯に向き合う姿勢に心が洗われた。 湖の底での征四郎の台詞が好き。 「私は与えられる理想より、刻苦して自力で掴む理想を求めているのだ。こういう生活は、私の精神を養わない。」 ちょっと振り回されたり、騙されたり、恩返しをされたり、そういう生活の中でこそ征四郎は美しい文章を書けるのだと思う。
4投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し前に名取佐和子さんの『金曜日の本屋さん』という小説の中で、この『家守綺譚』という作品を知りました。 なので河童にまつわる描写や、ちょっと癖になる言い回し(気骨がある等)があるのは前情報として持っていました。 古風な文体や難読漢字が少し読みにくいけれど、じっくり向き合って読むことで勉強に繋がった気がしています。草花について調べながら読むのもとても楽しかったです。その情景をイメージする助けになるし、作品全体の持つ魅力を味わいやすくなる!
0投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
不思議な話。 なんかゴローがかわいかった(笑) 吉田伸子さんの解説にもあったけれど、カイゼル髭さんに謝りに戻るとこ、よかったです。
1投稿日: 2024.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ最高に面白かった サルスベリ(木)に好かれる主人公 河童や掛け軸から出てくるサギなど 奇妙奇天烈なお話なのにどこか不思議と受け入れられる 主人公、綿貫の心意気がなんだか私自身のパートナーによく似ていてなんとも心がほっとする
9投稿日: 2024.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
卒業後、売れもしない文章を書いて相変わらず学生時代の時の下宿に居座り続けていた。高堂の父親から、嫁に行った娘の近くに隠居する、この家の守をしてくれないかと頼まれ、学生時代の親友の実家に住んでいる。 高堂 ボート部に所属していた湖でボートを漕いでいる最中に行方不明になった。掛け軸から出てくる。 ハナ 隣のおかみさん。 ゴロー 犬。 和尚 長虫屋 蓑笠を被った男。 ダァリヤの君 髪を三つ編みにした娘 河童 キツネの女 タヌキ 村田 土耳古に行っている友人。 白いベールを目深に被った女人 肉屋 鮎 山内 後輩。 尼さん サル カワウソ 烏 佐保 倫敦に留学している友人 札屋 長虫屋の弟。 小鬼 鳶 百合 日本髪に結った女人。 桜鬼 妙齢を少し過ぎたぐらいのご婦人 カイゼル髭を蓄えた中肉中背の男性
0投稿日: 2024.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ雅で瀟洒な世界観と古風な文体 新感覚だが描き手が現代の人間だから価値観が少し現代的でリアリティに欠ける 内容は良いが好きではない、感覚が僕とリンクしない 解説が的外れ
0投稿日: 2024.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ本編は単行本で読みましたが、巻末に載っている綿貫の随筆『烏蘞苺記(やぶがらしのき)』を読みたくて文庫版を借りてきました。 本編でいうと「紅葉」と「葛」に登場する、「後輩の山内」が取ってきてくれた「西陣の織物業界が出している得意先配布用月刊誌の随筆」で、「竜田姫が晩秋の綾錦の衣を仕舞い込む、というような寓話的な終わり方をした」原稿ですね。 『家守綺譚』を読むまで知らなかったのですが、「竜田姫」は秋の女神。「竜田山」を神格化させたものということで、竜田山、竜田川は和歌にも多く詠まれています。 ちはやぶる 神世も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは (在原業平) 嵐吹く 三室の山の もみぢ葉は 竜田の川の 錦なりけり (能因法師) 『家守綺譚』には春の女神、佐保姫もダァリヤの君の幼友達「佐保ちゃん」としてサラッと登場してます。 綿貫の随筆ですが、なるほど編集者である山内が「呉服屋の娘さん」は「業界誌の綿貫さんの随筆」を読んでいるはずだから「この縁談は流れるだろう」と言った意味がわかりました。 ──落ち着いて下さい。この原稿もきっとそうに違いないが、今までのだって面白いには違いなかった。けれど、この著書と生活を共にしようという気になるような内容だったでしょうか。 非常な説得力だ。 (180ページ) 生真面目で浮世離れしていて、経済的なこととは縁遠そうで、普通の社会生活送れない人な感じが短い随筆から伺えてしまいます。 「風変わりな呉服屋の娘さん」なら竜田姫の衣替えを描いてみせた随筆を気に入りそうですが、綿貫征四郎さんはやっぱりサルスベリに懸想されたり、花鬼に暇乞いされたりしていてほしいです。
0投稿日: 2024.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ売れない作家と日常生活の中で出会う不思議なもの達との交流のお話。風流な文体とほんの一匙の不思議さがあいまって独特の世界観に没入できます。主観ですが、文章の雰囲気は夏目漱石、不思議さは宮沢賢治、といった感じかな。なんとも良きであります。
0投稿日: 2024.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ奇譚:珍しい話や不思議な話。世にも珍しく不思議な伝説 喋り方や書き方からで、わりと昔の時代の設定なのかな。 植物が喋ったり、私たちが知る生物になったり、狸が化かしてきたり、花が姫に変わり、小鬼がいたり 読んでいて思ったのは、昔の人はスマホも何もない時代だから、考え事や妄想の世界の対象が自然や生き物だったのではないかと思った。 今の私たちには、自然や生き物を対象に、こうだったら面白いと思うことなんて無いに等しい。 植物の描き方や、不思議な体験を少し固めの文章でつらつらと書かれている。 なんとなしに、自然と触れ合った気でいるのは私だけのかな。 漢字が難しくて調べながら読んだけど、なかなか勉強になりました。
0投稿日: 2024.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルのルビも読まず裏表紙も確認せず “ヤモリの物語だ!”と手に取った。家守の話なんだけど。 手元に置きたいほど良き。
9投稿日: 2024.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ俗世間を離れた地での気品ある日常系不思議物語。高貴で深遠な世界観。尊い。どうやったらこんな物語書けるんだろうと思う。
2投稿日: 2024.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログだいぶ前に単行本では読んでいたけれど、すごく好きだったことしか覚えていなくて再読。 ちょうど今、散歩道のサルスベリが満開だ。 高堂が来て、「──サルスベリのやつが、おまえに懸想をしている」と言ったあたりで、もう心をつかまれた。 ああ、これやっぱり好きなやつだと思った。 続編があると知ったので、そちらも読みたい。 会話文はかぎ括弧がなく、「──」で始まっているからか、征四郎に共感しながら読むというより、一歩後ろから眺めているような、夢の中の出来事のような感覚になった。 川に遊びに行く時、祖父に「河童に尻子玉を抜かれるから深いとこに行ったらあかん。」と言われたことを思い出す。 山あいの小さな村にある祖父母の家は、妖のものがいてもおかしくないようなところだった。 山道のお地蔵様、お寺の境内での盆踊り、ひぐらしのなく夕暮れ、あぜ道に舞う蛍。 懐かしいなぁ。
0投稿日: 2024.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ琵琶湖に消えた親友の高堂の家を借りる物書きに起きるさまざまな不思議。 家守シリーズはファンの人も多いのではないかな、と思います。初めて読んだのはずいぶん前になりますが、あっという間にこの世界観に引き込まれました。ちょっと漱石を思わせるリズムの雅な文章と馥郁たる世界観に酔いしれたことをおぼえています。 梨木さんはその土地に埋もれた歴史・ストーリーを掘り出して物語に埋め込むのが得意ですが、色々エッセイを読むとこのシリーズを書くために(あとカヌー)琵琶湖の辺りに事務所を持っていたそうで、それだけ力を入れて書いたのかなあ、と思いました。実際に地図を眺めながら読むととても楽しいのです。 寝入り端にこの本を開いていくつかエピソードを読んで寝落ちする。そんな数日を過ごしましたが、まさに至福の再読でした。
26投稿日: 2024.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ人もあやかしも動物も そして夢も現実も ぼんやりと同じ世界に 漂うように存在していた感が 読んでいて心地よい そんな時代を知らないけど 知っているような気がする 100年くらい前のお話 しまぶっくにて購入
6投稿日: 2024.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024.6.22 読了 舞台は約100年前、身の回りで起こる様々な事象が科学で解明される以前の自然がもっと身近で人々の想像力が豊かだった時代 綺譚というだけあって河童や人魚はでてくるしサルスベリは焼きもちを焼き狸は恩返しをする。 不思議だけどどこか懐かしい昔話のような心がほっこりする短編集でした。
0投稿日: 2024.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ芦奈野ひとし先生の コトノバドライブみたいな 少し不思議な雰囲気のように感じて 一気によみました 続編があるようなのでこれも探して 読んでみようと思いました
6投稿日: 2024.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ家守奇譚とは‥‥家の番をする人の不思議な物語、くらいの意でしょうか? 怪異(全然怖くありません)を交えた身辺雑記ともとれる、とても不思議な味わいの小説でした。 時代は百年前、主人公は駆け出しの物書き・綿貫征四郎。物語は、学生時代に亡くなった親友・高堂の実家に、綿貫が「家守」として住み込むところから始まります。自然を中心に、ほのぼのとした日常が描かれたエッセイ風の24の掌編が綴られ、その全てに草木のタイトルが付けられています。 床の間の掛け軸から高堂やサギが現れ、庭のサルスベリが綿貫に想いを寄せ、(高堂のお告げで)犬にゴローと名付け‥。さらには、人に化けた狸、狐、小竜、小鬼、河童、人魚などが登場し、現世と異界の境界が曖昧になりながら、綿貫の毎日が過ぎていきます。 四季の移ろい、風や草木の音、匂い、光と影の描写が、どこか温かみと可笑しさのある文体と相まって、懐かしい原風景を観るようです。多様な草木の情景をこれだけ描けるのも、すごいの一言です。 「木槿(むくげ)」の編に、「土耳古(トルコ)に行っている友人の村田〜」のくだりがあり、『村田エフェンディ滯土録』を直ぐ思い出しました。あぁ、同じ百年前当時の和と洋の対比なんだなと、その乙な趣向も興味深かったです。
87投稿日: 2024.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ移り変わる四季の描写の美しさ。 自然に在る異端のもの達との交流。 花、小鬼、狸、河童…。 主人公、「私」が彼方の世界へ迷い込む幻想小説短編集。 面白かったです。
0投稿日: 2024.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さんの小説を読んだのは初めてでした。実は『西の魔女が死んだ』を読みかけているのだけれど、先に『家守綺譚』を読んでしまった。目次を見たら全て植物で、季節が移ろう感じに惹かれた。内容もすごくよかった。「蟲師」とか、「陰陽師」になんとなく雰囲気が似ているな、と思って親しみを持ったので、これらの作品が好きな方なら容易に『家守綺譚』の世界へと入っていけるはず。
3投稿日: 2024.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ不思議な世界。 人と幽霊と動物と草木、プラス妖怪? これらが共存共栄してるというか一体化して結び付いている。 最初は「何これ?」「どういう話?」と意味不明で、読み続けられないかもと思ったが、 ただ単に、この世界に浸っているのも悪くないと感じ始めたら素直に受け入れられた。 怪奇現象はヒトの心が創り出すが、誰もが持っている深層心理を具象化した物語といった感じ。 特別なストーリーもなく、喜怒哀楽の起伏も少ないファンタジー。 植物の名前をタイトルにして物語が綴られているのに「ホトトギス」が出てきた。 鳥だと思いきやホトトギスの腹に化けたような花の植物だった。 梨木香歩さんの作品は「西の魔女が死んだ」しか読んでいないが、 あの魔女の魂もどこかにいそうな気がして「アイノウ」という声を思い出した。 このような雰囲気の作品は少ないと思うが、串田孫一さんの「鳥と花の贈りもの」は似た感じだったかな。
52投稿日: 2024.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ家に住むだけでお金が貰えるなんて羨ましい。 亡くなった友人と、亡くなってからも会えるなんていいな。狸に化かされるって、こういう、割と自然なことなんだ。おかみさんも、和尚さんも、とてもいい人。
8投稿日: 2024.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ大好きな作品です。 生きとし生けるもの、そうでないもの、全てを愛しく感じます。 梨木さんの作品からしか得ることが出来ない栄養のようなものがある気がします。
1投稿日: 2023.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ他の方のレビュー、他の小説の中でも紹介されていてやっと読めました。 感想は難しいです。 知らない言葉、花の名前、調べながら読み進めました。それがまた楽しかったです。 内容は読んでみないと良さが分からない世界で、残念ながら私には感想が書けません。 でもこの本を読んでいる間の時間はとても気持ちの良いものでした。
22投稿日: 2023.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
とにかく奇妙で、綺麗なお話だった。 明治頃の京都あたりの物語で、昔っぽい語り口調が特徴的。だから意味がよく理解できていない部分もある。 インターネットとか近代的なものがないから、そういったものに時間を取られることなく、自然と共にゆっくりと時間が過ぎていくのを眺める生活をしていて羨ましいと思った。できないこともないけど、便利だからやっぱりスマホは使っちゃうよね。 主人公の綿貫は怪異についての知識がないから読者目線の人物だった。怪異に驚きつつも受け入れる綿貫は素直な人物なのだろうなと思った。鈍感なところもあるけど、そこも愛らしい。 長虫屋の親がカワウソなのが衝撃的で面白かった。腹違いの弟がいるところも、複雑な家庭でとても気になる。 黒い虫が腕にとまって、それが黒子になったという話も不思議だった。私の黒子ももしかしたら虫だったのかもしれない。 竜田姫と佐保姫のところがちょっと理解できなかったからもう一度読みたい。二人とも伝説上で実在してるみたいだから事前に知識をつけてから。 高堂はあの世の狭間に行ったときに、葡萄を食べてしまったみたいだけど覚悟がなかったのだろうか。 これからも、掛け軸から高堂が遊びに来て、二人で話すんだろうなと思うと微笑ましい。 私が見えないだけで、この本に登場したような怪異は周りにたくさんあるのかもしれない。私も見つけてみたい。もう一度読みたいと思えるお話だった。
0投稿日: 2023.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ綺譚だけあって、不思議な話ばかり。それが話の中で淡々と、自然に受け入れられている書き方なので何故か違和感がなく読める。そして季節感があり、動植物にも心があることを感じさせる世界観がとても好き。読んでいて、何だか心が落ち着いてくるのは何故だろう。各章の最後はどれも心地良い余韻がある。出会えて嬉しかった本。
2投稿日: 2023.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりにこの作者の本を読んだ。一時はよく読んんでいたのだが、なんとなく遠のいてしまっていた。 亡くなった親友の家に家守として住み込むことになった。広い庭には池があり、多くの樹木や草花が生い茂る環境。時代は多分1890年頃、場所は琵琶湖の周囲のよう。池にカッパが流れ着いたり、不思議なことがたくさん起こるけれど、近隣の人や動植物に助けられて、なんとなくやり過ごしていく主人公。各章のタイトルは植物の名前で、季節が一巡りする間のできごとと連動している。大きな出来事があるわけではないけれど、不思議な感覚を残す物語。この作者の本を、また読んでみようかなと思った。
2投稿日: 2023.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ(借.新宿区立図書館) 仙境的小説。明治の京都・滋賀県境付近が舞台か?様々な動植物の化身が登場する連作短編集。なお、家守はヤモリではなくイエモリと読む(実際にヤモリも出てはいる)。
1投稿日: 2023.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ薄い1冊なのに中身が濃く、読了するのにいつもの倍ほど時間がかかった。言葉の使われ方がやや昔ながらで馴染みがあまりなかったことも原因か? 一つ一つ出てくる植物がどんなものだろうかと調べ(残念ながらすぐ忘れてしまうのだが!)、物語の世界観に浸る。これは一気読みをするよりも一話一話丁寧にその時期ごとに読むのが相応しい本かもしれない。 河童や小鬼、化けた狸などが出てきて驚いてもどこかそれをすっと受け入れる主人公が良かった。
2投稿日: 2023.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ植物を題材にした不思議なショートストーリーがいくつも途切れる事なく年間を通じて綴られていく物語 主人公のボーッとしたゆるさ、しかし実は芯がある人柄が好ましい 不思議な犬のゴローや明治時代までは普通にあった田舎の光景が目に浮かび知らないはずのノスタルジーを感じる 最後に友がなぜ消えたか判明するが納得いく終わり方だった
0投稿日: 2023.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ家族に勧められて読み始めたのが1月、読まない期間も経てやっと読み終えた。穏やかな暮らしの中での自然のものたちとの交友記録、こういう世界観は好き。
0投稿日: 2023.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ童話のような不思議な世界。 短編でタイトルが植物、その植物にちなんだ話になっている。 のんびりしたいときに1話、1話大事~に読みたい本。
0投稿日: 2023.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
亡くなった友人の家に家守として住む主人公。時は明治の最後のほう、場所は京都と滋賀の間の疏水沿いのどこか。毎回異なことのおこるファンタジー。穏やかで雰囲気良し。ちょっと切ないところも夏目友人帳みたいな読み心地です。
0投稿日: 2023.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログんんんぜったい素敵な話なんだからもうちょいちゃんと読めばよかった、、 読み返したいリストに入れておこう。 読みながら口角上がっちゃうくらいに楽しいのに、どこか切ない気持ちもする不思議な小説だった。
1投稿日: 2023.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ植物や動物と触れることで人間は生きていけるのかもしれない。何となく受け入れて、それとなく面白がって過ごしている感じがとてもよい。
2投稿日: 2023.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ雰囲気がすごく好きだった。サルスベリとゴロー可愛い!決して笑わせにきているわけではないのだが、愛嬌のある行為に愛しさが込み上げてきて、思わずクスッとしてしまう感じ。ゲーテの「君知るや…」の詩はこれで初めて知ったが、物語の雰囲気にマッチしていてとても良い。 ☆勝手にイメソン Bye for now(藤井風)
3投稿日: 2023.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ狸にばかされたり、早生した友人が部屋を訪れ話しをしたり、河童の脱け殻を拾ったり。身の回りで起こる摩訶不思議な出来事を当然の如く受け入れる主人公綿貫征四郎。というより、そんな事が普通にある世界の物語なのか。 この世界観が、不思議さよりも、懐かしさ、というか心の落ち着きの様なものを感じさせてくれ何とも魅力的。 征四郎の、長虫屋との遣り取りで別に感じる必要の無い引け目を感じてしまう様な繊細さ、小物っぽさが可愛い。 どこか地方を列車でのんびり旅する時にちょいちょい読み進められたら良いな、って感じの本でした。
1投稿日: 2022.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログのんびりゆっくりちょこちょこ読めた本。 不思議なことを「そういうもの」と受け入れている人々……というより時代なのかな。今現代にはもうない世界、空気感。
0投稿日: 2022.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ和風ファンタジーとでもいうのだろうか。ごく身近な植物をモチーフにした不思議な短編集。 ファンタジーは苦手なジャンルなのに、スッとその世界に入り込んでしまった。 それはファンタジーとは対極な融通の効かない主人公、綿貫という男の、振り回されながらも全てを受け入れてしまう飄々とした語り口のせいだろうか。 時代背景もいい塩梅なんだよなぁ。今よりずっと四季や自然が人々の生活に入り込んでいた時代。その風景は実際目にしたことはないものの、その古風で美しく、妖しい情景描写がリアルなのか架空なのか曖昧な世界に没入させてくれる。 自然と人間も生と死もこの物語における境界線は曖昧だ。その世界は理屈と時を超え、私のDNAに刻まれた日本人としての感性を呼び覚まし、俗世との境界線を曖昧にしてくれる。 どこか物憂く、懐しく、優しい。郷愁の時間を過ごした。
15投稿日: 2022.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2005年。第3位。 100年前の話? 旧友を湖でなくした作家。旧友の家にすむ。ヤモリの話かと思ってた。 サルスベリに懸想され。旧友はボートに乗ってやってくる。狸に化かされ。それを淡々と受け入れる。天狗や河童も。飼い犬のゴローが良い働きをする。 知らないことを知らないと理解するべき。意訳。 ほわんほわんと異世界を楽しんだ。
0投稿日: 2022.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログとても味わい深い1冊だった。 本書は、駆け出しの物書きである綿貫征四郎による随筆のような体をなした作品。 物語は、ひょんなことから綿貫が、学生時代に亡くなった親友・高堂の実家の家守となるところからスタートする。 死んだはずの高堂が出てきたり、植物であるサルスベリに慕われたりするのに、綿貫も物語も慌てふためくこともなく悠々と進んでゆく。 ちょっぴり面白い。 「夢十夜」のような独特の浮遊感の中で、「雨月物語」のような不思議な出来事が、美しい季節の移り変わりと共に描かれている。 風土記や古事記にある、伝説を読んでいるようでもある。 季節の神や動植物の精霊たちとの、交流とも言えぬ程のちょっとした出会いやすれ違い。 ほんの少し前、もっと人々のペースがゆっくりで野山の自然と近かった頃なら、こんなこともあったかもしれない。 それぞれのタイトルが季節の草花なのも趣がある。 植物がお好きな方だったら、その花の佇まいを思い浮かべることが出来るので、世界観に入っていきやすいと思う。 (白木蓮とホトトギスは好きな花の1つであったので、どんなエピソードだろうと楽しみだった。) タイトルの草花だけでなく、本文は野草や庭木たちの名前で溢れている。 日本家屋の土間や硝子戸、旅籠や山寺など、見える景色にも風情がある。 また、「ざぁーという雨の音が縁の回り、家の回り、庭のぐるりを波のように繰り返し繰り返し…。…さながら雨の檻の囚人になったような」や、 黄昏時の葛の花を「赤紫の闇」と言い表し、その花を池に落とすシーンでの「赤紫の闇が、鏡のような池の面に浮いた」など、 豊かな表現力に読み手の心も潤う。 パッとその植物や物の容姿が浮かばない方は画像検索などしながら、 浅井姫や竜田姫・天女の羽衣伝説の云われ、二十四節気、花の時期などをご存知なければチラリと検索しつつ、 どうかゆっくりと時間をかけて読み進めることをお勧めしたい。 例えば本文では、葛の花が萩の花に入れ替わることで微妙な季節の移り変わりや侘しさを表現していたりと、読み手の知識がある程にこの物語の奥行きが広がるからだ。 他にも、ぽろりと南天の実がこぼれ出てくるシーンがあるが、南天は「難が転じる」→「災い転じて福となす」ということで縁起物だ。 それを知っているだけで、その章の味わいも増す。 そしてこの世界観にどっぷり浸れば浸る程、読み手は癒されるに違いない。 まるで、お寺の境内で深呼吸したような。 目を閉じれば、季節の風や鳥の鳴き声まで感じることが出きるような。 初めて梨木香歩さんの作品を読むにあたり、やっぱり「西の魔女が死んだ」を読まなくては!と思いそうしたけれど、一緒に手にした「家守綺譚」の方がずっとずーっと好みだった。 正直「西の魔女が死んだ」を読んだ時は、この作風で他の作品も書かれているのなら、私はちょっと好みと違うかな…と思っていた。 もし「家守綺譚」も同じタイミングで手にしていなかったら、そう思い込んだまま他の作品は読まなかったかもしれない。 こちらも入手しておいて良かった! 何度も読み返したい大切な1冊になった。 続編である「冬虫夏草」も、きっと近いうちに読もう。 【備忘録】 「佐保姫」 春の女神 佐保山の神霊 「筒姫」 夏を司る神 「竜田姫」 秋の女神 竜田山の神霊で、元は風神 秋の季語 「宇津田姫」 冬を司る神 「春は竹の秋」 新緑の頃は、いっそうまぶしいその姿。しかし実は、竹にとっての新緑の頃…つまり「春」は、春夏秋冬で言うと「秋」に当たる モウソウチクやマダケにとっての春から初夏は、竹の子を育てるのに栄養をとられる、いわば「実りの季節」でもあります。また、竹の葉は1年で生え変わりますが、5~6月に黄色く色づいて落葉します。竹の子が大きくなった後なので、まるで子どもを育てた親の竹が疲れて枯れていくようにも見えますが、実際は、新芽に日光を当てるために古い葉を落としているのだと考えられます。 「竹の秋」は春の季語、「竹の春」は秋の季語 「般若湯 はんにゃとう」 僧侶などの隠語の一つで、「お酒」を表す言葉。 本来僧侶は「不飲酒」といって飲酒は禁じられているため、こういう間接的な表現になったらしい
16投稿日: 2022.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔の人の自然との関わり、近所の人との関わりの描写が興味深かった。中でも印象的なのは、狸狐が人を化かすはなし。日本昔ばなしみたい。
1投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ植物、自然を通して不思議が起こる話。 単語が難し鋳物が多く、植物も知らないものが多かったからあまり入り込めなかった。
1投稿日: 2022.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生時代に読んだ本なので登録してなかったけど残しておきたいと思った。 春夏秋冬、過ぎ去りし季節の描写や空気感が丁寧に描かれていてこんな風に日常を大事にしていきたいと思わせてくれた本。
0投稿日: 2022.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログサルスベリってどんな木だったかな?とかネット調べながら読んだので時間がかかった。内容もゆったりしているので、それくらいが丁度いい。 木に好かれたり、カッパの世話を焼いたり、たぬきに騙されたりするのに、主人公が淡々受け入れているところがまた面白い。そしてゴロー。こんな犬がいるなら、私も飼いたい。
19投稿日: 2022.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
私が初めて読んだ梨木さん作品です 何事もなかったかのようにボートで帰ってくる亡くなったはずの友人高堂、綿貫に恋慕を寄せるサルスベリ、 仲裁犬ゴロー、信心深い狸、河童や小鬼と 不思議なことが日常の一部となって物語が紡がれています 解説の吉田伸子さんが書かれていた、読後の「間違ってなかった」との感想はまさにその通りで、 一遍一遍は短い物語なのですが、ずっと浸っていたい気持ちになりました 明記はされていないものの、滋賀と京都の県境のあたりが舞台になっており、安寧寺川(安祥寺川)の記載などから山科のあたりではないかと推測されている方もいました 疎水縁に咲く桜、美しい山並み、いつか訪れてみたいものです
0投稿日: 2022.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本にまだ不思議な生き物が沢山いて、人と生きている話だった。 犬のゴローが不思議の世界に通じているみたいで面白いし、隣のおかみさんは何を聞いても知らないと言わずに答えをくれる。 狐やたぬきは、きっちりと人を騙すし、川にはカッパが来る。 こんな世界に居てみたい。 また、忘れた頃に読んでみたい。
3投稿日: 2022.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログみなさんの評判が良かったので読んでみました。 最初は面白かったのですが、途中で飽きてしまいました。私には合わないんでしょうね、そんなこともあるんだなとちょっとびっくり。
1投稿日: 2022.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本家屋や庭園、日本の自然に興味がなさすぎるため読むのに時間がかかったが、おもしろかった。波津先生の『ふるぎぬ屋紋様帳』が好きな人だと好きだと思う。
2投稿日: 2022.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ好きだ〜〜〜〜 彼女といえば、『西の魔女が死んだ』が代名詞だろう。でも私は、この本の方が、彼女の良さをじっとりと味わえるような気がした。 百年前、もしかしたら存在していたかもしれない景色。もう二度と手に入らないからこそ、羨ましく美しく感じられる。太太宰治や夏目漱石が好きな人、きっと気に入りますよ。
2投稿日: 2022.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2022.8.15) 十数年ぶりの再読。 犬を飼いたい今の心情に、ゴローの登場は少しニンマリした。 出てくる植物でいくつか知らないものがあったので、検索して画像を見て読む、という、少し変わった楽しみ方をしてみた。 続編「冬虫夏草」は未だ読んだことがない。ゴローを探す旅とは…。読んでみよう。
1投稿日: 2022.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本昔ばなしのようにゆるくほんわかするお話でした。恥ずかしながら各章の表題、すぐに連想できない植物もあり、調べつつ読み進めました。その方が入り込みやすくて良かったです。またこのようなお話が読めれば…と思います。
2投稿日: 2022.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「私」のまわりの優しい話。「私」以外は知っている不思議が受け入れられている世界。 今は失われつつある四季が、花の移ろいや気温の変化などから穏やかに感じられる物語。
1投稿日: 2022.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。不思議な現象が当たり前のように描かれているのが、日本人の自然観っぽい気がして好き。癒されたくて読んで期待通り癒された。
1投稿日: 2022.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ優しい怪談といった感じ 何となくこういうファンタジックな話のヒントは日常に転がっているのかなぁと感じた
1投稿日: 2022.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みたい本の一冊でした。まったりとした時間の流れの不可思議な物語。良い話でした。征四郎、なかなか筋の通った男です
1投稿日: 2022.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
舞台が明治あたりで、文体が古く、個人的に少し読みにくさがあった。 ただ、四季折々の自然の成長は文体から手に取るように感じられた。 また、主人公である征四郎の周りで日々怪怪な出来事が起こるのだが、まずは受け容れること、どんな生きものに対しても愛情を持って接することの大切さを学んだ。 あの世とこの世の狭間で、あの世の美しい葡萄を食べずに断った後、もっと相手を想う断り方があったのではないか、と再度あの世に戻り、そのことを伝え、謝罪する征四郎には心から尊敬の念を覚えた。
1投稿日: 2022.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ綿貫さん、なんだかんだ優しくて面倒見がいい。非現実なものに驚きながらも受け入れてしまうところ。サルスベリが惚れるのも分かる気がする。 明るくて可笑しい世界観、登場する生き物たちのキャラクター、会話のリズム感、すべて味わい深い。絶対活字で読みたい小説。
4投稿日: 2022.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ新米物書きの綿貫征四郎は、ボートに乗ったまま行方不明になった同級生・高堂の家を守っている。100年くらい昔の、河童や狸が恩返しに来たり、サルスベリに好意を寄せられたり、そんな不思議な世界が舞台。そんな人ならざるものに取り囲まれていても、(後輩の言葉を借りると)彼は"超然"としている。 それもこれも、掛け軸の中から高堂が、雨に紛れてやってくる。ボートに乗って。 私はこの夢か現か、境のあわあわとした不思議な世界が大好きだ。 もう会えないと思っていた友人が、会いに来るあっちとこっちが融け合う間(あわい)の世界。 もしかしたら、身の回りに起こる現象に疑念を持てば、たちまちその道は閉ざされてしまうのでは、と考えたり。 ーまた来るな? ーまた来るよ 願わくば、このやりとりがずっと続いてほしいと本を閉じる。
23投稿日: 2022.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ新米作家・綿貫征四郎が、亡くなった友人宅を下宿とし、家守となる。 日本古来からの天地自然の気や精霊と家守と認められた綿貫との交歓記。 九星気学では、世の中の物は九星の何処かに属するんです。影響しあって存在するんですね。 夢枕獏の「陰陽師」の安倍晴明邸より 緩やかでのびやかな自然との折り合いを描いて、若い世代のたくさんの方々に読まれている。こういう世界観が受け入れられるのは良きです。
28投稿日: 2022.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ四季折々の描写があるので、それぞれの季節に合わせて読みたい1冊。少し読みにくい昔の言い回しなどがあったが、それも風情と思って読んだ。頭の中で映像化するのが楽しい作品だった。
1投稿日: 2022.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治辺りの時代背景で亡友の家守をすることになり、庭に棲む様々な植物その他に翻弄される青年主人公。読み始めは好印象だったが、様々な件の種明かしをせずに終わり評価が下がって行った。
1投稿日: 2022.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の手元にあるのは2004年に発行されたハードカバーです。最近はむかしの本を本棚から掘り出して読み返すのが日課になってます。内容はほぼ忘れてるので支障はありません。本作を読むと必ず姉妹編である「村田エフェンディ滞土録」も読みたくなりますね。
2投稿日: 2022.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「季節の営みの、まことに律儀なことは、ときにこの世でゆういつ信頼に足るもののように思える。」 なによりも信じられる心の拠り所のようなもの。厳しい寒さも、寝苦しい夏の夜も、さわやかな秋風、色とりどりの春も、なぜか心地よく安心感を生む。 物語の中のひっそりと潜む一文だったが、なぜか心にスッと入ってきた。
3投稿日: 2022.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログいいなあ、征四郎の生活。と思ってしまった。 作家としては鳴かず飛ばずっぽいけど、仲裁犬ゴローがいて、行方知れずの高堂が会いに来てくれる。 サルスベリに懸想されたり、河童やタヌキ、小鬼など異界のモノに遭遇する日常。 それでいて怖さはないし、このゆったりとしてとらえどころのない世界観が心地良かったです。
2投稿日: 2022.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ”些細なことであるから、まあいいだろうと鷹揚に構えていたが、どれくらいの不思議まで人はそういって許せるものなのか、ふと気になった。” 本作の中の一文だが、かくいう主人公の綿貫は、かなりの不思議を許している。周りの人達も相当な部分許している。というより、彼ら自身が不思議な存在である。そうでないのは駅前の肉屋の主人ぐらいなもので、彼は文明開化の波に乗っていち早く肉屋を開業したぐらいの人だから、近代化の洗礼を終えているのだろう。そして、令和を生きる我々は、更にそのずっと先にいることになる。 そんな我々から見れば不思議でしかない日常が、あたりまえの日常として、淡々と語られる。少々の気味の悪さも残しつつ、そのくせ、ずっと読んでいたくなるような居心地のよさをもった、不思議な作品である。続編である「冬虫夏草」を入手せねば。 ※文庫版解説には時代を特定されていないと書かれているが、「木槿」という話を読むと、エルトゥールル号の遭難が「先年」とされている。この事件は1890年(明治23年)のことなので、その数年後(明治の半ば頃)が描かれているということになる。
1投稿日: 2021.12.31
