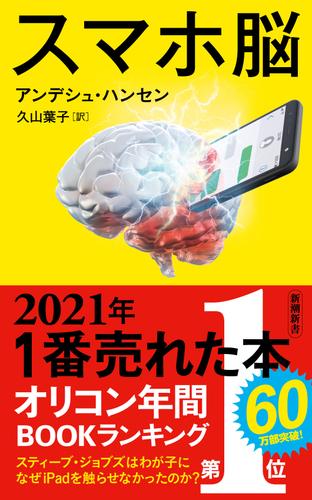
総合評価
(1525件)| 597 | ||
| 586 | ||
| 224 | ||
| 23 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現在生きている人間の脳は、石器時代の脳と考えることは同じであり、現時点ではデジタル社会に対応しきることは難しいとのことだった。 狩猟社会の事を考えながら脳について考えるのは非常に新鮮な体験だった。 アンデシュハンセンさんは大ヒットした前作の一流の頭脳でも同じことを言って今回はスマホに関連させた話になったのかなと推測した(前作は読んでないです)。 私は中学生の頃は運動部に入って忙しかったけど勉強がすんなり入ってきた。 高校生になり、運動部に入らず、かつスマホを手にした。勉強が以前よりすんなり入ってこなくなった。このことに関して、勉強のレベルが上がったからだと思っていた。しかし、本書では運動することで脳が活性化するとの話があった。仕事でへとへとになったあとでもランニングするとストレスが減るらしい。そこが足りなかったのかなと思い出した。 週に3回、45分の運動、息を切らし汗をかくレベルの運動をするのが望ましいとのこと、実践しようと思う。 スマホは集中力を減らす。勉強するときは触らないことを心がけたい。
1投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ今やスマホは私たちの生活になくてはならないものになっているが本当に必要なものなのか。 まだスマホを持っていなかった頃は、暇さえあれば外で遊んだり本を読んだり友達とおしゃべりしたりしていた。しかし、手元にスマホが常にある生活に変わるとそうした時間はいつの間にか無くなり、一人で過ごす時間が増えたような気がする。 今、極力スマホを触らないよう不必要なアプリを削除したり、主電源を切ったり、ちょっとした外出には持ち出さないようにしたりしているが、そうすると今まで散々過ごしてきた生活圏内で新しい発見が沢山あるのだ。これもまた面白い。 人によるのかもしれないがスマホの存在は私たちの生活を大きく変えていることは間違いないと痛感した。
0投稿日: 2025.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
家にいる時間が減ってスマホを使う時間が減り、なんとなくイライラや疲れが軽減されたような気がしたのがきっかけでこの本を読んだ。 手薄になる自己検閲について、自分もそういうところがあったなと思い、注意しておきたい。 運動が知能にいい影響を与えることに納得した。 理由は、受験勉強で部活やっていたときより部活引退後のほうが勉強の量や時間を確保できているし実際勉強しているけれど、なんとなく吸収が悪い感覚があったからだ。 これからスマホのなんとなくの使用と運動について考えたい。
1投稿日: 2025.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホなしでは生活できないが減らすことはできる! そう感じ、実践していきたい本でした。 最後のデジタル時代のアドバイスは簡単そうで難しいことがたくさん書いてあったのでまずここをこなしていきたい。 幸福になるためにはスマホから離れることが1番の近道。
0投稿日: 2025.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ生物学的に見ると、我々の脳はまだサバンナにいる頃から進化しておらず、飢餓にならないようカロリーの高い食べ物に飛びつくようにできている。 同様に、周囲を警戒しないとライオンに襲われるし、カモシカを捕まえられないので、我々には新しい情報を得たいという欲求が備わっている。 ドーパミンという、人間の原動力になる(何に集中すべきかを与える)存在が、私たちにもっといい情報を求めてSNSの画面をスクロールさせる。 「もしかしたら」の瞬間に多くドーパミンが出るので、Facebookなどはいいねがつくのを保留することがあるのだという。まんまと企業の掌で踊らされている。 最初から最後まで面白かった。面白すぎてものすごいスピードで読んでしまって残らなかったので続けてもう一度読んで、それでもメモしたい箇所が多すぎて一旦メモは諦めた。また読む。 自分のSNSとの向き合い方、睡眠改善、職場での若手の育成、子育てなど、色々なものに活かしていけるし、周りの人たちにもおすすめしたい本。
9投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ前から気になっていた本でようやく読むことができました。 スマホやタブレット(パソコンも)を一日に何時間も使い続けるのが、いかに危ないことかがよくわかりました。 運動が脳や精神に影響するのも、納得できます。
0投稿日: 2025.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ4.0 初めて読んだ新書。 自分のことすぎて耳が痛い。 読んだあと、スマホからゲームのアプリを全て消した。
0投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報自体ではなく、情報の保存場所を覚えてしまうという「デジタル健忘」という現象が起こってしまうため、学習内容を"メモ"として残すのではなく、 "アウトプット"出来るよう、使える情報として残さなければならないと感じた。 マルチタスクをすると本来記憶するのに使われる脳の部分使われるのではなく、他の部分使われる。 →うまく記憶できない? マルチタスクはワーキングメモリにも悪影響を与える。また、マルチタスクは集中を頻繁に切り替えているだけであり、切り替えた際、脳は前の作業が頭に残っている"注意残余"という状態に陥る。これではパフォーマンスは低下し、注意残余を抜け出すには数分間時間ががかかる。切り替え時間が必要。 →チャットやメールは頻繁にチェックしない方が良い 〇運動の効果 だった5分の運動(ラジオ体操程度でも)で集中力、記憶力、情報処理、さらに一つのものに集中しやすくなっていた。ゲームも上手くなる。 特にADHDの人に効果が顕著に現れた。
0投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「スマホ」それは我々の生活にはなくてはならないものになっている。しかし、スマホがなくてはならない存在である一方で多少の害をもたらす存在であることも否定できない。スマホを使用することによって精神状態が悪化したり、集中力が減少したりする影響が研究によって明らかにされつつある。実際にスマホが”絶対に“悪い存在であるかは断定できない。しかし、その可能性があるなら我々はスマホとのこれからの向き合い方についてじっくりと考えていくべきだと思う。このままスマホに依存した人々によるスマホに依存した社会が拡大していけば、社会全体の活力が失われていってしまわれかねない。私は人生をスマホという人類における”新種“に奪われたくない。スマホによって死ぬ時にもっと豊かな人生を送りたかったと後悔したくない。だから私は考え続けるし、今を生きる現代人も考え続けるべきだと思う。
0投稿日: 2025.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ電車の中でふと見かけるとスマホを触っている人が多いですし、人によっては一緒にご飯を食べててもスマホを気にする人も多いと思います。 そんな時、スマホ依存なんだと警告を示してくれるし、なんとなくスマホがダメなんだと思うことを合理的に教えてくれるので、一度読んでみるのをおすすめです。
0投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログいまの考え方に大きな影響をくれた本の一つ。"私たちの脳はまだサバンナにいる"、確かにそうだ。通知やいいねが気になってしまうのは、昔ならば茂みのわずかな音や赤色は危険信号であり、命に関わるシグナルだから。なにかを我慢するのが難しいのは、サバンナにおいて何もしないのは死を意味するから。孤独が辛いのは、サバンナなら1人で生きていくことができないから。 進化論って面白い。いまの生活が100万年続いたら、どんな性格や体格を持った人が人類の多数を占めるのだろう。 あとfacebook(メタ)のCEOが、いいね機能を後悔していた話は印象的だった。メーカーの分業化の怖さはこんなところにもあるんだなと。
0投稿日: 2025.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
▶︎ 動機 ・最近スマホを見すぎっていて、対策を取りたい ▶︎ メモ・感想 → 対策:物理的に距離を置く、モノクロ設定する、朝にラジオ体操する ・SNSは、人間の本能をハックして中毒にさせるようできてる ・新しいものを欲する(狩猟採集の名残り ・人と繋がりたい(人は社会的な生き物 ・自分のことをしゃべりたい(同上 ・人類(の脳)は、スマホなどのテクノロジーが溢れる現代社会に適応していない(今だにサバンナを生きている)。 ・長らく、人類の主な死因は、飢餓・干魃・感染症・出血多量・他殺 ・人類(の脳)は、生存・繁殖に最適化している ・感情は、生存・繁殖のための行動をとらせるための、大まかなリスク・リターンの見積もり ・ネガティブな感情はポジティブな感情より優先される(死んだら元も子もないから。対処を後回しにできない) ・”闘争か逃走か” ・不安は人間特有なもの ・脳は新しいものを好む(狩猟採集時代の名残り)・ドーパミン ・SNSは人間の脳をハックしている
0投稿日: 2025.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログたしかにデジタルデトックスしてる時は調子がいいし、インターネットにのめり込んでる時の焦燥感やばいと思ってたけど確信出来なかったからこの本で確信できてよかった。人間の本能やドーパミンが出る場面が原始時代の生存競争のままあまり進化していないから、明らかに非生産的なのにスマホにのめり込んでしまう理由が面白かったな。他には昔は発見した飯を即食べたほうが生存率が上がるから自然淘汰で食いしん坊が生き残り、その名残で現代には肥満がのさばってるだとか、情報を知っていた方が生存率が上がるから、も同じく。 そして文章をぶった斬る形でコラム入れてるのは集中力を測る実験なのか、本の主題になってるドーパミンを利用して読み続けさせるためなのか、ちょっと邪魔だった。
0投稿日: 2025.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【脳は現代社会に適応していない】 ・人間は生存のために「共同体から追い出されないこと」が重要 ・職場でプレゼンに失敗しても職を失って餓死することはない ・洪水のようなデジタル情報を処理する脳は1万年前から変わっていない ・うちでは、子どもたちがデジタル機器を使う時間を制限している(ジョブズ) 【感想】 2020年の本ですが、今からでも読む価値アリ◎ 無駄な時間だな、と自分でも思っているのに1日何時間もスマホのスワイプ、動画視聴が止められない自分…。 スマホは人間のアドレナリンを出すように研究されて作られてるので、当たり前!自分のせいじゃない(笑)と1つ免罪符を得て、スマホ依存から脱却したいと強い気持ちにさせてくれます。 このレビューもスマホで書いているわけですが、やることを決めてからスマホを手に取りました。 精神科医の著者独自の「人間の進化の見地」に基づいた説明が、説得力を持たせます。現代人が感じる身心の不調は主に脳のせい。 仕事によるあらゆるやストレスや緊張も、脳は大昔の人間のままだからな~とゆるく俯瞰できそうです。脳とからだのことを知り少し楽に生きられそう。 自分で納得しスマホを減らし、運動して健康にもなって余暇が増え読書もできる、最高です。
0投稿日: 2025.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ本来SNSは人の結びつきを強め、幸せにすべきもののように思われるが、その実利用時間の多い人が孤独感を増幅させたり精神状態を悪くさせる傾向にあるとのこと。 SNSに限らず、スマホアプリや広告はヒトの本能を利用していかに利用時間や試聴時間を増やすか考え抜かれたモデルとなっているため、適切な距離感が必要だと思った。 人の脳は原始時代から対して変わっていないのに、生活のあり方が大きく変わっているからこそ、そこに適応できていないのだと思う。だからこそ、意図的に脳にとって「自然な」運動であったり、対面でのコミュニケーションが結局は大事で、それらに割く時間を意識しないといけない社会なのだと痛感させられた。
0投稿日: 2025.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んで早速SNSの使用時間に制限を設けるなど、スマホとの向き合い方を真剣に考える良いきっかけとなった。 また、スマホがどうして手放せなくなっているのか、人間の進化論を元に説明されているのだが、その根拠が明確で分かりやすく、すんなりと納得させられた。 スマホは使い方を誤らなければ、非常に便利で暮らしを豊かにしてくれる世紀の大発明とも言えるだろう。しかし、スマホ依存に陥り精神疾患の患者数が激増しているのが現状だ。幸い私自身はスマホ中毒とまではいかないものの、休日など暇な時間があると無意味なデジタルカロリーを摂取する時間が多くなってしまう傾向にある。1日に使用する時間を本書で推奨されている2時間くらいまで減らしていくためにも、スマホの使用法を改めて考えていきたいと思う。そんなきっかけを与えてくれたこの著書に感謝しかない。 ぜひ、スマホを使いすぎてしまっている自覚のある方には一度手に取ってもらいたい。
0投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ全人類が読んだ方がいい名著。 人類が火を発明し、船を発明し 人類が印刷を発明し、電気を発明し 人類が原爆を発明したように、 人類が発明した、ネット、スマホ、SNSの影響を知る人はまだいない。 もちろん良い部分もあるが、悪い影響を与えている部分も少なくない。 人間の長い成長の中で築かれた生理システムを、スマホがいかにジャックしているか、鬱やストレスの問題がどういうメカニズムで発生しているのか、を分析した、一目置かないわけにはいかない書物。 とりあえずSNSはほどほどにして、運動習慣を身につけよう。 スマホ脳 スマホは現在のドラッグ 睡眠運動、そして他者との関わりが精神的な不調から身を守る3つの重要な要素 感情と言うのは、自分を取り巻く環境への感想ではない。周りで何が起きているかに応じて体の中で起きる現象を脳が反応としてまとめたもの。 適度なストレスは、精神を研ぎ澄ましてくれるが、度が過ぎると、頭が明瞭に働かなくなる。 ストレスは驚異そのものに対する反応だが、不安は脅威になり得るものに対して起こる ドーパミンの重要な役目は、何に集中するかを選択させること。つまり、人間の原動力 満足感は体内のモルヒネであるエンドルフィンが関わる。 ドーパミンが増えるのは、家庭が目的であって、不確かな未来への期待。 ドーパミンの重要課題は、人間に行動する動機を与えること。 人間に組み込まれた確かな結果への平愛 常に気が散る人は、ほぼ確実に脳が最適な状態で動かなくなる。 手書きの場合は、一旦情報を処理する必要があり、内容を吸収しやすくなる。 長期記憶を作るためには集中が必要。 固定化は、脳が最もエネルギーが必要とする作業。 Google効果とかデジタル性健忘 本当の意味で何かを深く学ぶためには、集中と塾講の両方が求められる。 ネットサーフィンは脳に情報、消化するための時間を与えていない マルチタスクによって間違った場所に入る記憶。 記憶は記憶の中枢と呼ばれる海馬に入る。体で覚える技術の習得には、大脳基底核の線条体と言う場所に入る。 影響を受けるのは、睡眠を促す。メラトニンだけではなく、ストレスホルモンのコルチゾールと空腹ホルモンのグレリンの量も増やす。 人生の5年間をSNSに費やす計算。 の周囲の人のことを知っておきたいと言う人間の欲求をネットワークしたのがFacebook さらに、自分のことを話したいと言う欲求の表れ。 人間は先天的に自分のことを話すと報酬をもらえるようになっている。 脳のミラーニューロンを最大限に機能させるためには、他人と実際に会う必要がある。 IRL(インリアルライフ)で人と会う時ほどミラーニューロンが活性化される。 心の理論の能力は、他人の表情や行動仕草を繰り返し観察することで得られる。 ナルシズムと言う伝染病が、いかにSNSの誕生と共に広がったのか、なぜ自分のことばかり気になり、他の人の事はどうでもよくなったのかを論じている。 共感的配慮と言う辛い状況の人に共感できる能力。 対人関係における感受性 が悪化している。 SNSは、あなたの注目こそが、彼らの製品 報酬を先延ばしにできる力は、生まれた時からあるわけではなく、生活環境の影響受けるし、訓練で伸ばすこともできる。 脳が文章に集中するよりも、報酬がないことを無視するのに、貴重な書類能力を費やしてしまい、結果として学びが悪くなる。 現在の子供に足りないのが集中力と希望されない能力。わずか5分体動かすだけでそれが改善された。 脳の大部分は、サバンナでの日々から変わっていないから、体動かすと集中力が高まる。 ストレスの大部分が「闘争か逃走か」危険に結びついていた。現代はパニックにならなくて良くなっている。 火災報知器の原則→体の状態が良い人は、ストレスシステムを事前に作動させる必要がない。 認知バイアス。 私たちに安全を確保する猶予を組み込んだ。近づいてくる音の認識の違いが体のコンディションに起因している。 目の前の情報を精査するためには、ある程度の知識が必要。 考えるのは、パソコンやスマホに任せてしまうこともできる。それがIQ低下の傾向につながっている。 人間残される仕事はおそらく集中力を要するもの。 鉄道酔いとデジタル酔いの決定的違い。 鉄道に毎日7時間乗る人はいないが、デジタルは1日7時間皆が使っている。と言う大きな違い 人間はまだ進化するのか その環境下でメリットにならない特質をふるいにかけること。人間の成長はゆっくりなっている。 自然主義的誤謬 自然に近い方が良いと言うのは、思考の罠。 スウェーデン社会庁のデータベースによると、2018年12月 16歳以上の大人の9人に1人が抗うつ薬の処方を受けている。
0投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間にはすぐに気が散るという自然な衝動があり、スマホはまさにそこをハッキングしたー スマホをとりあえず触ってしまうとなんだかやめられないと思っていたけれど、こういうカラクリだったのかと目から鱗でした。 様々なものがアプリ化し、否応なくスマホを触らなければならないことも増えた。役所の手続きや契約の解約など、対面や電話で対応してくれたらと思うことがある。スマホで出来ることは、素晴らしいように見えて確かに新たなストレスの種ともなる。 また、子どもの教育にも親切な顔してiPadがやって来た。学校で買わされるChromebookは本当に恩恵を受けているのだろうか。必要な時に自宅PCで済むレベルのことではないのか。 最近になり、スウェーデンやフィンランドが紙の教科書に戻したとか、オーストラリアではSNSを規制するとか、プロアクティブに動くことが出来ている国が出始めた。日本も自分の頭で考えて、国としてどうするかを決めてほしい。学校Chromebook総選挙があれば、間違いなく、否を投じる。インターネットですぐに調べられることよりも、どうやってインタビューしたら聞きたいことが聞けるのかを学んで欲しいから。
0投稿日: 2025.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の脳を進化の過程から解析し、ここ数十年のデジタル化が人類の歴史の中でいかに異例か分かりやすく解説してくれている。 スマホの使用を控え、運動や読書、睡眠に充てる時間を増やそうと思った。 スマホが悪いとただ批判して終わるのではなく、アドバイスまで掲載されているのが良い。
0投稿日: 2025.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の脳はデジタル社会に適応していない。 未来を予測した不安は人間特有のもの。 自分のスマホ利用時間を知る。 スマホでなくてもよい機能はスマホを使わないようにする。 プッシュ機能はオフ。 表示はモノクロにする。 人と会っているときは、スマホを遠ざけて、一緒にいる相手に集中する。 どんな運動も脳に良い。1番良いのは心拍数を上げる運動。
0投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログベストセラーになっただけあって簡潔でわかりやすい。翻訳本にありがちな不自然な言い回しもないし。タイトルからゲーム脳的な決めつけの説が列挙されているのかと思いきや、反論の余地も残してある。エビデンスまでは掲載されていないけれど説得力はあるし、アドバイスに従ってみても損はない内容だった。
0投稿日: 2025.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログiPhoneを開発したスティーブ・ジョブズが、自身の子どものスマホ利用時間を制限したのはなぜか? 技術の革新に貢献した数々の研究者、開発者たちが自分たちが及ぼした影響の何に後悔したのか? いつも手元にあるスマホと私たちの関係について、多くの研究から見えてくる事実の本。 ————————————————————————- 読めば読むほど目の前のスマホが憎たらしくなってきて、自分の生活を改めようと言う気持ちになる笑 実際に私は睡眠前に通知がオフになるように設定したし、必要な時以外は画面が見えないようにすることにした。 塾講師をしていて、子どもたちのスマホ利用時間には頭を抱えていたし、その依存具合に呆れていたけど、大人も例外ではない。 スマホ使いすぎだなぁとか、子どものスマホの使いすぎが悩ましいとか思う人はぜひ読んでください。目の前のスマホ(やらないけど)捨てたくなります。笑
1投稿日: 2025.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なんとなく でもかなり強く 違和感は感じていた スマホ 便利 楽しい 『スティーブ・ジョブズはわが子にiPadを与えなかった!? うつ、睡眠障害、学力低下、依存症……最新の研究結果があぶり出す恐るべき真実。 教育大国スウェーデンを震撼させ、社会現象となった世界的ベストセラー、日本上陸。』 友人の薦めで遅まきながら読んでみました おー! 進化とズレているんだ とても大きく カフェで向かい合った二人が会話なくそれぞれのスマホに 電車では9割の方がスマホ 自分を語るとドーパミン ご褒美が出てうれしいんだって このブクログもそうなのかしらん バーさんは認知症とスマホ脳のダブルパンチなんだ 運動して スマホなしの時間をつくって ゆっくり寝よう ≪ 狩りのヒト 脳はそのまま 今のヒト ≫
22投稿日: 2025.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログドーパミン、マルチタスクの話が特に面白かった。改めて、スマホから距離を置かないとな,と思った(物理的にも)
0投稿日: 2025.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読む前から自分でSNS経ちをし、その効果を実感していたからか、大きな衝撃は受けなかった。 ただ、人間の歴史がその影響に及んでいるとは…! この本を読んでそこに気づけたのが良かった。 自分に将来子どもが出来たら、スマホやタブレット以外のことに一緒に取り組んでいきたいな。
1投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホに時間を奪われているのは気づいていたが、改めてスマホを触る時間を減らそうと思った。 メモ ・デジタルデトックスをする ・SNSを見ることで他人と比較して嫉妬する →鬱やストレスにつながる ・週に2時間の運動をする ・スマホを隣の部屋においておく →目に見えるところにあるだけで集中がなくなる
8投稿日: 2025.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホに依存している自分を感じて、これはまずいと意識的にスマホから離れたり時間制限をしたという体験があっただけに、本書で書かれていることはわかるわかる!と自分ごととして読めた。 スマホに依存してしまう仕組みとして、人間の生存本能が関係していること、そしてiPhoneや facebookを作り出した人たちが、それを後悔し自分の子供たちには制限しているという事実は、一つの答えでもあるように思う。 自分自身今ここ、に集中するのがすごく難しくて、集中力が昔より欠けているように感じている。それは明らかにスマホの影響力が大きいと思った。目の前のことを感じて、集中することは人に幸せをもたらすことだと思う。結局、使い方は自分次第というところに落ち着くのだろうけど、リアルなコミュニケーションを大事にして、スマホの時間を減らしていきたいと改めて感じた。
7投稿日: 2025.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ訳者あとがきにあったように間違いなくこの本は人生のバイブルになった。 手元に置いておきたいし読み返したい。もう少し早くこの本と出会えていたら、と思わずにはいられない内容だった。人生を変えてくれる存在だった。大切な人たちにも是非勧めたいと思う。
3投稿日: 2025.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代人の生活がスマホに支配されていることはなんとなく危機感として認識していたが、それらがいかに巧妙に論理的に人々を支配しているかを生物学的に紐解くことでより一層危機的に感じるきっかけを与えてくれる。スマホは使われるのではなく使う側として上手く付き合おうと感じることができた。 集中モードはおすすめ
1投稿日: 2025.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログSNSのいいねやフォロワー数が自分の価値のように思っている時期がありました。 何度もSNSを開く日々、まさに脳がスマホにハッキングされている状態でした。 もっと早くこの本に出会っていればなぁと。 今はSNSより本を読む方が楽しいので以前より健康的になったと思います。体も動かさねば!
1投稿日: 2025.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホ社会の問題点を端的にまとめてくれている。自分もスマホの刺激の影響を受けている部分が多分にあるので使い方について考えたい。
0投稿日: 2025.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初の出だしが秀逸。 一面に渡り点だけのページ。 そこから、人類の歴史から紐解きスマホが人類に与える影響を語り出す。身近にあるものの手放すことが難しいことの問題もあり、最後には距離の置き方を伝授している。参考にし、便利なものを正しく使おうと思った。あと、個人的な話だが著者がイケメンで驚いた❣️
0投稿日: 2025.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間の脳はスマホに適していないーー この本には、スマホ時代の今こそ改めて考えたい「スマホとの付き合い方」が紹介されています。 スマホを触りすぎている方、触る時間を減らしたい方は読むことをおすすめします。 「現代の脳はスマホに適していない」 スマホはドーパミンを発生させ、新しいモノ、出来事が大好物な脳を刺激する。そのため、人は無意識にスマホ中毒になってしまいます。 僕自身、この本を読んでから今まで意識していなかったスマホとの関わり方を見直すきっかけになりました。スマホを触る時間を減らし、読書に費やす時間が増えた気がします。 ぜひこの本で学んだことを実践してみてください。
0投稿日: 2025.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代を生きる上でストレスや不安に感じることが、人類の進化を踏まえて説明されており、説得力があり面白かった。 私のスクリーンタイムは平均7時間であり、流石にスマホの使用時間を減らしたいという思いからこの本を読んだ。スマホは私達の脳の報酬系を利用し、より長くスマホを使用するように造られていること。スマホがあるだけで集中力を削ぐことは衝撃的だった。自分のスクリーンタイムが長いことやその悪影響を自覚し、これからスマホの使い方を改めようと決意した。また、運動や睡眠、他者との直接的な交流の大切さを再確認した。これから生活習慣を改善していこうと思った。
6投稿日: 2025.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログとても興味深く読むことができた。 人間の脳は狩猟採集民として生活してきた時代からあまり進化はしておらず、その脳にデジタルデバイスがどのように侵食していくのか、また侵食した結果どのような変化が起きるのか、そしてそのデジタル社会にどう対処すれば良いのかが書かれている。 個人的にはデジタルデバイスを使い続けていくことで、脳の構造がどのように変化していくのかを知りたかったので、そこの部分がとても興味深かった。 結局デジタルデバイスが依存症を引き起こしていて、人の興味を引きそれにあらがえない。 脳内では生命の危機とギャンブル依存症とデジタル依存症などの区別がついていないんだなと感じた。 最近デジタルデトックスとして睡眠時にスマホをスマホロックの中に入れてしまいこんでいるが、そうするとなんだかよく眠れた気がしていたのは気のせいではなかったのだなと。 毎日パソコンでデータ集計している仕事をしているので、今後気を付けようと思った。
14投稿日: 2025.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ刊行から5年が経っている本書を今更読みました。 現在では幅広いメディアでスマホの問題点が取り上げられており、本書の内容はほとんど聞いたことがあるトピックが多かった。復習というか、やっぱりそうだよねという再確認が主だった。 とはいえ、衝撃的なデータや研究結果も多く、自分の身にもよく当てはまることがあって非常に参考になった。 本書の終盤で述べられているように、自分でスマホ依存の自覚が少しでもあれば、スマホをはじめとするスクリーンタイムを減らして定期的な運動を習慣にしていこうべきだと思う。
1投稿日: 2025.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類が誕生したばかりの時まで遡り、なぜ現代人がチグハグなのか、なぜ悩むのか、なぜ鬱になるのか、説得力を持って語られた。SNSを沢山見てしまった日は確かに気分が良くない日が多いなと感じていたことが言語化された。そして運動しなきゃな定期
0投稿日: 2025.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホが良くないのは分かっているけどついつい触ってしまう…我ながら意志が弱くて情けない状態でしたが、この本を読んで少し意識を変えることが出来ました。 結論自体は「まぁそうだよね」という内容。 しかしそれを裏付ける多くの研究と、そもそも何故スマホに取り憑かれてしまうのか?を遥か昔まで遡って我々の脳の作りから解説している点で面白かったです。 悪いのは分かっている、だが何故か辞められない。この理由が分かったように思います。そして、きちんと納得した上で、やはりスマホ依存を辞めたいと強く思いました。散々テレビやSNSでデジタルデトックスのメリットを見てきても何の効果もありませんでしたが、ようやくスマホ以外の楽しみにも目を向けられそうです。
0投稿日: 2025.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の脳は数十万年前の狩猟採集時代から進化していない。 にもかかわらず環境が大きく変化して脳の進化が追いついていないのが今の状況。 ついついスマホを触ってしまうのも、通知に反応してしまうのも、SNSやニュースをチェックしてしまうのも、大昔に生き残るために獲得した脳の機能だという。 脳の癖を巧みに利用して商売をしているのが、SNSやゲームを開発する企業。 自分が漠然と感じていたスマホの危険性が言語化された感じ。 子どもへは自主性を重んじるスタイルだが、衝動コントロールを司る前頭葉が発達してない子どもに対して、依存症になるような原因は大人が管理するべきとの意見は一理あり、管理方法を考えてみようと思う。
0投稿日: 2025.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類の進化の観点から、なぜスマホ依存してしまうのか、非常に分かりやすいし面白かった。我が子だけではなく夫にも意識して欲しいな。まずは自分自身から。
0投稿日: 2025.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログなんでスマホを使わないほうがいいのかがよく分かった。 ホルモンとかが関係しているみたい。 自分も毎日何時間かスマホを触っているので、 読書にもっと充てたい! 面白かったのですぐ読めた。
0投稿日: 2025.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書を読んで、スマホのスクリーンタイムを確認、 普段何気なく使っているスマホだが、スクリーンタイムを見ると6〜7時間使っていることがわかった。酷い時だと、10〜12時間使っている。自分のスクリーンタイムに愕然とした。 スマホに費やしている時間を、家族や友達と過ごしたり、運動、読書、勉強したりする時間に充てたい。 スクリーンばっか見る人生ではなくて、現実世界で自分が体験体感できるような生活がしたいと強く思った。
5投稿日: 2025.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間の脳は、何万年前から、狩猟採集民族として暮らしていた時代に適応している。現代の急速な社会変革、デジタル化には適応していない。 それが、ストレスや不安の原因である。 誰もが知っておいた方がいいような、脳科学の基本的な話を非常に簡潔にわかりやすくまとめている。 今すぐ実践できることが多く、為になる。 ・運動が集中力を高める(心拍数を上げる運動なら尚良し) ・スマホが近くにあるだけで集中力が低下する。 特にこの2つは仕事に活かせる。
0投稿日: 2025.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かに目の前にスマホあると,触りたくなる・確認したくなるものだなと思った. ちかごろはフツーにスクリーンタイムを計測する機能はあるが,とりわけ数値で確認はしていないし,寝る直前まで触っているのは間違いない. →特にそれが原因で不眠になっているとは思っていないが 15分でもよいから,散歩でもよいから定期的に運動するべきだ,と書いてあって改めてそうなんだと認識した.
0投稿日: 2025.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ随分と後回しにしてきた感じ 何冊か最近の本を読んでから ベストセラーの初期にたどり着く 太古からの生き残るための軌跡が 今の我々の本能的行動に繋がっている だからそこは そう言う行動の現れが 依存的だったりになると言う事 意識しておくことからだな 身体を動かして持っている機能を活かして バージョンアップしてみましょう!
0投稿日: 2025.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホがどれだけ人体に悪影響を及ぼすのか説明されているのにも関わらず、スマホで感想を書く矛盾。 でも、子どもにはできるだけスマホを渡したくないですね。
3投稿日: 2025.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログスクリーンタイムが1日だったので読みました。スマホがいかに害悪なのか、論理的にエビデンスに基づいて説明されており、納得感があった。最後には、こういう使い方をしよう、という記載がまとまっていて読後すぐに実践しました。
0投稿日: 2025.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読んだ。タイトルからもいろんな書評からも大体内容はわかるしな…。と読んでなかったのだが、図書館にあったのでパラパラと読了。 内容は思っていた通りだったが、問題提起としては大事。スマホはやはり、時間を決めて見る時間、見ない時間を作らないといけない。自分がスマホにどれだけ費やしているかを自覚することも重要。大人になってからスマホが普及した自分たちはともかく、これからの子どもたちには特にスマホとの関わり方を考えないといけないと思った。
32投稿日: 2025.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ恥ずかしながら、スクリーンタイムが5時間超える日もあった私。 これを読んでスマホとの向き合い方を変えました。 SNSのアプリは取り除き、ゲームも削除。 SNSのアカウントは残しているものの、ブラウザでしか見ないようにしたので頻度は減りました。 今では平均2時間台をキープ。代わりに読書時間が増えました。
0投稿日: 2025.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ当たり前と言えば当たり前の内容にエビデンスをつけて説明してくれている内容。 スマホ関連の論文を読んでいるわけではないので、著者の主張や説明の正当性の判断はできませんが、一説として捉え、生活を見直そうかなとは思えますね。 機会があれば他の同テーマの本を探してみるのも良いかも。 漠然とスマホを触りすぎて罪悪感を感じているのであれば、本書を読んで見直す機会に充てるのは良いかな、と思います。
0投稿日: 2025.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ脳の報酬系に作用するソーシャルメディア。"like"が投稿者に反映される時間を制御し、即時でないように。報酬系を煽る。 大人は1日4時間をスマホに費やしている。この10年で起きた変化は人類史上最速。 甘い果実を食べるとドーパミンが出るような進化は、カロリーを蓄え、生き延びやすくする意味があったが、現代ではカロリーがあまりに多く、むしろ糖尿病や肥満で不健康をもたらしている。
0投稿日: 2025.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ悪いことはわかっているけど、近くにあるだけで脳が処理能力を割いているとは驚愕。 いつも読書をしている間も近くにスマホがあるけど、もし電源を切ったり別の部屋に置いたらもっと本の内容に集中できるということか。 身体的にも精神的にも学力にも悪影響なら、どうにか使用制限されるシステムを国をあげてつくってほしいけど、無理だろうな。 種の存続に関わらないから人がスマホに対応するべく進化をすることはないらしい。 もうとにかく人類がデジタルから身を守るには運動しかない。 スマホを使い続けたいなら運動しよう!!
32投稿日: 2025.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。すごく読みやすい。SNSは使いすぎるとメンタルが悪化するし、気がつけば膨大な時間を奪われていることも多々あるので自ら制限することもあったけれど、これを読んでさらに強化しようと思った。
6投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「うわっ……私のスクリーンタイム、長すぎ……?」 と不安に感じたらまず手に取るべき一冊。 こちらの新書、以前読んだものなのですが、最近意識してインターネット離れに取り組んでいるので改めて読んでみました。 人間の脳は未だに狩猟採集していた時代の構造なままなこと、そして「気を逸らしやすい」という人間の特徴にいかにスマホが入り込んできたのか。あらゆる研究結果や論文から、スマホとの付き合い方について警告する内容です。 私自身、ほんの2週間前の休日のスクリーンタイムは7時間。 それを「ながらスマホをしない」「本を読む時は視界に入らない場所にスマホをしまう」などの工夫をして3分の1以下まで減らすことができました。 大人はまだ自己責任だからいいものの、街中でスマホを使いこなしている乳幼児を見かけると、この子たちは将来どうなってしまうのだろうかと勝手に心配になります。 適度な運動、バランスのとれた食事、適切な睡眠時間、そしてリアルでのふれあい。 今年は一層意識して、紙の本を読んでいきたいなと思います。
14投稿日: 2025.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューをスマホで書いてしまっていることに、若干の罪悪感を感じつつも、この本はスマホを手放せない現代人にとって、非常に大切な学びをくれる本だと思う。 他の著書含め、アンデシュハンセンさんの主張の中で1番斬新な点は、脳は人類の歴史の大半を占める狩猟と採集の生活から進化できておらず、急激な技術の進化に追いつけていないということだ。 運動をすること、良質な睡眠をし、朝起きて太陽の光を浴びること、リアルな社会的付き合いをすることといった、先人達が行ってきたことが脳にも好影響を与える(ように人類は進化してきた) 逆に言うと、スマホの長時間利用により、それらは阻害され、うつやストレスといった影響を少なからず及ぼしていることが科学的な根拠を持って説明され、わかりやすい。 僕自身1日10時間以上スマホを使ったりもする依存症であるが、少しでもスマホと上手く付き合っていけたらと思う。
6投稿日: 2025.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ第3章のタイトルは「スマホは私たちの最新のドラッグである」だが、スマホは人間の報酬物質ドーパミンを放出させるように作られていて、そしてそれはIT企業が意図的につくったものだという。実際にフェイスブックの初代CEOはそれを認めているそうだ。 人間は、新しい情報を得るとドーパミンを放出させる。それは新しい情報を得ることで生存の可能性が高まるから。祖先はそういった生存戦略で生き残ってきたのだが、今はそれが利用され、依存させられている。 著者は「テクノロジーのほうが私たちに対応するべきであって、その逆ではないはずだ。スマホやSNSは、できるだけ人間を依存させるよう巧妙に開発されている。そうではない形に開発されてもよかったわけだし、今からでも遅くはない。もっと違った製品が欲しいと私たちが言えば、手に入るはずなのだ」と記している。私も同意だが、人間はこの依存から抜け出せるのだろうか。 道を歩いていると歩きスマホをしている人を見かける。それが当たり前の光景だと受け入れてしまっているが、それ自体よく考えるととても怖い事だと思う。 私も何かにつけてスマホを触ってしまうし、集中力が低下しているとも感じている。 この本を読み、スマホに支配されないよう努力したいと感じた。
1投稿日: 2025.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなく薄々感じてたスマホと言うものを使いこなす事は自分にとって困難であると言うことを色んな視点で教えてくれて良かった 自分の中で鬱にならず幸せになるためにスマホは適すのかどうかって事も含めて向き合わないといけないなと感じた
0投稿日: 2025.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ★★★★★ フルプライスの価値あり 現代社会(特にスマホ)がいかに進化的適応をしてきたサピエンスの生息環境を急激に変化させ、破壊してきたかについて。かなり興味深く、自制しなければと焦燥感をかきたてられる。 以下、感想箇条書き ・鬱は体を休める機能があることは知っていたが、免疫機能の向上や、それ以上の攻撃を受けることを予防するという効果があることは初めて知った。 ・運動は知的能力を高めるだけでなく、集中力つまり他の誘惑を無視する力を高めることにも貢献している! ・『無視する』のにも労力が必要。無視しなければならない対象が近くにあれば、自ずと能力も下がる。 ・一度注意を他に移すと、戻すのに数秒かかる →注意を変えるたびに使われるニューロンの回路が変わり、脳への負担が大きくなるのは知っていたが、コストだけでなく、時間もかかるとは! ・スマホがここまで依存性を持つ理由は『次に何があるのか』という期待感を煽るため ・ブルーライトは、本来空の青。
1投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ脳は原始人時代とほぼ変わっていないため、注意散漫であることが当たり前。SNSはそこを上手く突いてくる。脳をドーパミンでハックしてくるものだと理解できた。とにかく自分含めて子供に対してもスマホとの接し方をしっかり考えないといけないと思う。 スマホに支配されないように気をつけたい。
0投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで、なんとなくスマホは良くないんだろうな、運動はメンタルヘルスにも良いんだろうな、と漠然に思っていたことを、生物学的視点で説明してくれており、スッキリした。 デジタル社会に生きる私たちが読むべき一冊。
0投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜスマホを見過ぎることが人体に悪影響を及ぼすのか、その悪影響はどういったものなのか、といったことが書かれています。今の世の中、社会構造自体がスマホがないと生きていけないようになってしまっているのに、スマホ依存はダメよねと言われてもね、と思いましたが、人体の歴史的に確かにあってない、というか、社会変化が早すぎて人体適応が間に合ってないために色んな支障が出るんだなあ、というのはよくわかりました。すぐには難しいけど、少しずつスマホを見る時間を減らしていこうと思いました。
2投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「スマホによって集中力がなくなってきている」というのは恐ろしいな。 集中力を失うと、色々なことに影響がでてくる。 運動ですねぇ、やっぱり。 運動しましょう。
16投稿日: 2025.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の脳とは、先祖から(昔から)創りは変わらない。 今はスマートフォンという便利なアイテムが世の中に広がっているけれど人間の脳はスマートフォンに追いつこうとしても追いつけないのが現状。 その為色々な実験の結果がこの本には書かれている。 この本を読んでる大半がスマートフォンの何が悪いかを気になって読んでると思う。 簡単にザックリこの本をまとめると、スマートフォンによる影響は、良い影響だけではなくデメリットが沢山ある。スマートフォン触るぐらいなら他の事に目を向けて見ればより良い事がある。って事
1投稿日: 2025.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホを使うことでの日常生活への影響について書かれた本。 大人だけでなく、子どもを持つ親にこそ是非読んで欲しい1冊です。 この本を読んで、自分もスマホとの関わり方を見直そうと思いました。
1投稿日: 2025.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間が生物として持っている生理的な反応から何故スマホ(特にSNS)が現代人にネガティブな影響を与えるかを説明した本。SNSを見たくなる理由はドーパミンが影響しているとのこと。 スマホを長く利用している中高生が読むといい。 【メモ】 ・人間は強いストレスにさらされると「闘争か逃走か」の判断しかできなくなる ・スピーチ恐怖症は「共同体から除外されない」ための生得的反応 ・スマホもドーパミン量を増やす ・ペンだと早く書けないために一旦情報を整理する必要があり、記憶に定着する。 ・「脳は体を動かすためにできている」
0投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログSNS利用時間が増加するとともに鬱の発症確率が増加する。 特に子供に対しての悪影響が多い。 重要なのは運動。特にランニングが効果的。心拍数が上がる運動には抗うつ効果がある。 人間の脳は押し寄せる情報の波を全て処理できる作りにはなっていない。
5投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ数分おきにスマホに手を伸ばしては、目的もなくダラダラとオススメに出てきた動画を見てしまう。 脳に何かしらの悪影響があることは間違いないはずであるものの、それが何なのかはよく分からない。 この本を読んで、スマホ利用による悪影響が科学的な根拠をもって明示されました。意識的にスマホから距離をおいていきたいと思います。
17投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホ依存者を救う本。 旦那に勧められて読みました。読んでいてグサグサと刺さりつつも、救いを与えてくれたと感じています。 私は20代なのですが、まさにスマホ依存者で、一日の殆どをスマホに費やし、スマホが視界の範囲から外れようものなら焦りと不安に心がかき乱されるくらいです。高校生の頃からスマホを持ち始めたことを正直後悔しているし、もし当時にこの本を読んでいたら人生は変わっていたのではないかと思います。 この本は、人間がスマホにハマってしまう理由を、脳の仕組みからわかりやすく解説してくれています。私は元医療従事者なので、人間のホルモン等にはもともとそれなりに知識がありますが、知識がなくても大丈夫。例えを用いながらわかりやすく解説されているため、誰が読んでも頭に入りやすいと思います。そして、読めば読むほど、スマホひいてはSNSは、我々がハマるように設計されていることがとてもよくわかります。設計者すら自分の子供にスマホを持たせるのを躊躇うほど、スマホとは人間にとって魅力的なものらしいのです。ですから、ハマってしまうのは最早当たり前であり、意図的にスマホから距離を置かないといけない…そのための具体的なアドバイスも、この本には記載されています。 スマホにハマってしまうこと自体は仕方がない、だってそのように作られているのだから。そう知るだけでも十分に救われるし、だからこそ、現代社会に適応していない脳を、スマホに支配されるのではなく自分自身でコントロールしていきたいと思います。この本は本当に親切で、具体的な方法まで書いてくれていますから、時間が無い人は最後の数ページ読むだけでも明日からの行動が変わるのではないかと思います。
2投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、スマホを長時間使用し続けることの弊害について書かれており、また、スマホの使用時間を減らすための具体的な策を読者に提供する。たとえば、マルチタスクは記憶の定着にかかわるワーキングメモリの低下に繋がったり、紙の書籍は電子書籍と比べて記憶に残りやすい、さらに、心拍数を上げるための運動や実際に人と会うことは、脳の活性化に必要不可欠な行為だという。
1投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログモニター系のデバイスとの付き合い方を精神科医の立場から明確に提示してくれたので、信憑性のある基準を自分の中に持つことができて安心した。 自分や息子のSNSやアニメ等に費やす時間が長すぎるのではないかと普段から心配をしていたからだ。 自分も息子も毎日5時間以上スマホやテレビにかじりついていて、楽しさを感じたり、知識が増えたりとポジティブな面もある一方、他のことに取り組む時間が減ったり、体力低下や思考力の低下、不安感の増大などネガティブな面も多いのではないかと心配していたが、その答えが全て記されている。 これから生活する上で、ある程度の自信をもって規制したり理由を伝えることができるようになり、読んでよかったと思う。
1投稿日: 2024.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ例の闇バイトで強盗や人殺しをした人たちが、ネットにあることをなぜあそこまで信じちゃうのかが不思議でこれを読んだので。 そのことに理解を深められるようなことは特に書かれていなかったので、「あー、つまんなかったw」と★3つにしようと思ったんだけど(^^ゞ 訳者のあとがきで、この本の著者が“スウェーデンで今もっとも注目されているメンタルヘルスのインフルエンサー”と書いていたので、一つ減らして★2つにした(爆) だって、結局は著者も、アンチ・スマホ教、アンチ・SNS教の教祖さまとして、世の迷える人たちが求めている通りの正解をスマホでバラまいて金儲けしてるヤツってことじゃんw 今の世においては、あかの他人が自分が求めている通りのことを言っていたり、あかの他人が自分の気持ちを代弁してくれていると感じたら、「それは100%デタラメ」と思わなきゃ絶対ヤバイ。 なぜなら、そのデタラメをバラまいているヤツらというのは、世の人が求めている通りのことを言ったり、世の人が気持ちを代弁してくれていると感じることを言うことを「金儲けの種」としか考えていない連中だからだ。 そういう人たちというのは、昨日自分が言ったことと正反対のことでも平気で「それが正解です」と言える。 金儲けのためなら何でも言えちゃう、デタラメヤローなのだ(^^ゞ ただ。 だからって、この本に書かれていることが全てデタラメってことではない。 この本の帯には「2021年一番売れた本」」とあるが。 それは世のそれだけ多くの人たちがスマホやSNS、ネットとその業界というものに何とも言えない胡散臭さと、自分たちがそれらの金儲けにいいように利用されているんじゃないか?と薄々気づいていたからこそだと思うのだ。 おそらく、その感覚は正鵠を射ていて。 だからこそ、著者は「あなたのその感覚は正しいんだよ)」という内容のこの本を書いた。 この本を読んだ読者は、「自分の感覚は正しかった」と自らの考えを再確認。 再確認出来た快感(著者の言葉を借りるなら、大量のドーパミンが出たw)にSNS等で他人におススメ。 その結果、2024年12月21日現在ブクログでは紙の本で2023人。電子書籍では362人の人がこの本の感想を書いているくらい本が売れまくっている。 おかげで著者も出版社も大儲けヽ(^o^)丿 この本を読んで、スマホに費やす時間を減らす等、デジタル・デトックスをするのはとても有意義なことだと思う。 ただ、結果的にそれは著者の金儲けに利用されているだけなんじゃないだろうか? ……と、一度は考えるべきだ(^^)/ 2024年のアメリカ大統領選挙であんなデタラメに投票する人が多いことにも驚いたが、その直後に(おそらくは)それとほぼ同じデタラメなことが日本の県知事選挙で起きたことにはもっと驚いた。 選挙結果につながったSNSの内容と、辞めた前知事を応援しだしたどこの人とも知れない人の言っていることが同じという時点で誰もがそれを疑わなかったのはなぜなんだろう? 自分は他県の人間だから、当選した知事をめぐる一連のことはニュースで見ていたくらいのことしか知らない。 ただ、当選した知事が、仮にちゃんとした人であるなら、いろいろよくないウワサのある人が選挙で自分を応援してきたら、その関係を断固拒絶するのが知事という人の上に立つ人に求められる資質であるはずだ。 あの手の輩の応援を断固拒絶しなかった時点で、知事には不適格な不誠実な人間だと自ら証明したようなものだ。 もちろん、「パワハラを糾弾するのは絶対正しい」という安直な社会通念の元に、例によって「悪いヤツとして糾弾しちゃえば一般庶民は大喜びで情報を見たり買ったりしてくれるよね」とばかり、いつも通りに批判報道したマスメディアや、そこに出てきたコメンテーター(と称するタレントたち)にも責められる面があるのは確かだろう。 ついでに言うなら、そのいつも通りのマスメディアの報道に拍手喝采していた世間にも問題があったのも確かだ。 ただ、マスメディアやそこに出てくるコメンテーターというのは世間に媚びたことを言ったり報道をすることで金儲けしている連中だし。 デタラメでもなんでもその瞬間の憂さが晴れれば拍手喝采、それが世間だ(爆) であるにしても、(おそらくは)同じ県民である県の職員たち、つまりリアルな隣人よりも、どこの誰とも知らない胡散臭い人が応援で言っていることと同じ内容のSNSを真実と飛びついてしまう世の中は、どこか狂っていないだろうか? もし災害が起きたら…、災害とまでいかないまでも、何かが起きた時に県民を助けてくれるのは県の職員たちだ。 でも、突然知事選に立候補して前知事を応援したあの人はその県の人がどんなに困っていたとしても見て見ぬふりだろう。 なぜならば、あの胡散臭い人はそういったことには全く興味がないからだ。 何かで心が塞いでいる時、ネットの世界にはその塞いだ心に寄り添った言葉をかけてくれる人がいるのは確かだ。 一方、親や身近なリアルの人は仕事や学校等で忙しい。 忙しいから、その人が今、心が塞いでいることに気づけない。 気づけなければ、塞いだ心に寄り添った言葉はかけられない。 ただ、普通の人間関係というのはそういうものなのだ。 でも、その人が本当に困った時。 例えば、その人が病気になって入院することとなったら、ネットの世界で塞いだ心に寄り添った言葉をかけてくれる人が入院費を払ってくれたり、保証人なってくれたりすることは絶対ない。 なぜなら、ネットの世界で塞いだ心に寄り添った言葉をかけてくれる人は、ネットというリアルから切り離された世界にいる人に寄り添ってあげる、ヒューマニストな自分というものにしか興味がないからだ。 入院費を払ったり、保証人になったりしてくれる、つまりその人が困った時に助けてくれるのは親や身近なリアルの人だけだ。 他人のSNSに「いいね」をつけることで毎日が忙しかったとしても、それだけは忘れてはいけない(^^ゞ スマホ(に限らずネット)というのは、それを使う人をフィルターバブルの中に閉じ込めるために作られたものだと個人的には思っている。 フィルターバブルの中に閉じ込められるということは、楽しく面白いと感じる情報をいくらでも得られる反面、その人の意に沿わない情報からは遮断されるということだ。 つまり、スマホ(に限らずネット)を使うということは、自らを情報弱者にしてしまうということ……、 …か、どうかはその人の使い方次第?(^^ゞ ていうかー、何よりいいのは、リアルに体を動かすこと! だよね(^^)/ 著者が書いているそれは100%その通りだと思うw ただなぁー。 体動かすのって、メンドクサイんだよなぁー。 そもそも、体を動かすのが好きだったら、ブクログで本の感想なんて書いてねーよ(爆)
8投稿日: 2024.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートフォンやSNSの登場による害について、人類の進化と関連付けながら論理的に述べられており、大変分かりやすかったです。 今の世の中の異常性を再認識させられました。電車に乗っていると、乗客の9割はスマホに夢中になっています。未来ある若者が1日に何時間もスマホと向き合うのは広告を出している企業が儲かるだけで、集中力を失ったりうつ病になったりします。これは世界の損失だと思います。 自分のスマホとの向き合い方を見直そうと思いましたし、子どもとのルール作りも工夫が必要だと思いました。
10投稿日: 2024.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜスマホに魅せられるのか、を科学的な切り口から教えてくれる本。 依存性の話や報酬系の話、脳の変化の話、どれもおもしろかった。運動や睡眠の大切さ、健康的な生活へのつながりも意識させられた。 ゲームも消したことですし、脱スマホ依存を目指したいところです。
13投稿日: 2024.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホは確かに楽しいし気になるし魅力的。その場にあったらそっちに気を取られる。 でも、なんかそれって、スマホ以外の楽しみを反故にしてるってことじゃん?って読んでて思った。 本書はスマホの負の側面と進化した結果もはやアホになってる人間について触れている。なお私も漏れなくアホであり頭の良さなんてたかが知れてる。 こんなアホなんだからスマホばかりいじってないで、Twitterなんて見てイライラしたりしてないで、少しは身体を動かしてごらんよ。アホなら経験や体験は数多く豊富にこなしてかないと! 気づいたら自分を叱咤激励してた。
0投稿日: 2024.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログカル・ニューポートさんの「デジタル・ミニマリスト」と内容的には随分重なります。こちらの方が以前に出版されているので、私にとっては復習のような感じでした。 趣旨は同じでも切り口や紹介されている研究が違うのですが、カル・ニューポートさんの、より文学的で、生きるとは?を問い直すような、少し過激な語り口の方が好みかな。アンデッシュ・ハンセンさんの方がDr.だけあって、より科学的な切り口でした。若者の方が依存症になりやすいことが、アルコールを早くに覚えることが規制されている大きな理由である、というあたりはなるほど、と思わされました。スマホ依存もまた然り。 運動の大切さについての章は、アンデッシュ・ハンセンさんの他の本と同じですが、少し体調を崩したり、季節が悪くなったり、忙しくなると運動を後回しにして、そのうち運動習慣ってなくしてしまいやすいので、もう一度警笛を聞けて良かったです。 スマホの使用時間を減らす内容の実践となると、知ってはいても難しい。 人間のドーパミン欲求によるスクリーン依存について意識的になった上で、ただ時間を減らす、だけでなく、運動、読書などの代わりにする活動を決めておいて従事する、ということが鍵なのですね。 スマホ依存について一度も読んだことがない方には、「デジタル・ミニマリスト」と合わせておすすめです。
1投稿日: 2024.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい売れた本らしいと知って期待して手に取ったが、期待した内容とは少し違っていた。 1日どんなに減らしても10時間はスマホを使うので、それをどうにか減らすヒントになる本を期待していたのだが… 人間の脳がどう進化して来たかとか、祖先はどう生活していたかとか、最初の方はスマホの話はしてないから読む本間違えたかと思った。 スマホの話にようやくなったかと思ったらこうゆう実験と結果があって、という実験の話が多くて同じようなことを何度も繰り返し言ってるようでもういいよと思った。 この本を読んでもスマホのやめ方は書いてないです。
1投稿日: 2024.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近仕事の時もプライベートの時も集中力が欠けているのが気がかりになっていた。 思い当たるのはスマホを触る回数や使用時間が比例して長くなっていること。 もしかして…と思いこの本を読んでみるとまさにその答えがこの本に書いてあった。 LINEの通知、SNSの更新、ネットニュースetc… これらが目に入った数分後には無意識的にスマホを触ってしまう。 その後不要と理解している5〜10分を1日のうちに何回も過ごしてしまう。 これは理論的にかつ本能の観点から説明できる事象であることを、この本は教えてくれた。 読み進めていくうちに、スマホに向き合う意識が明らかに変わってきたと思う。 自分の時間、そして自分の体、そのいずれも今より大切にするためにスマホとどう付き合うか。 そんな問いをこの本は投げかけてくれたように思う。 この本は『私的読んでよかった本ベスト5in2024』に滑り込んできた!
1投稿日: 2024.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024/6/17読了 ビブリアから移行 衝撃的だった、、! まず、スマホが利便性を高めるだけの、素晴らしいものだと思っていたのが、覆された 確かに、便利になってよかったところも山ほどある! けれど、天才が依存性をいかに高くするか考えられて作られた賜物かと思うと、 SNSもスマホもめちゃ怖くなった。 なぜ人はスマホに取り憑かれてしまうのかを、納得のいく形で説明されてた。 この本に書かれていることを知ってるか知っていないかで、スマホとの付き合い方全然違うな。 私はとりあえずスマホの通知全部オフにしました
0投稿日: 2024.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホは最大1日2時間 近くにあるだけで集中を妨げる 週2時間くらいの運動で脳が活性化する 鬱や不安の原因とスマホは関連している SNSのいいねを発信するタイミングはアプリ側がコントロールして、ドーパミンが最大になるようにしている facebookを作った人の中にとんでもないものを作ってしまったことを後悔している人がいる とはいえ、 スマホも付き合い方次第で、 食欲をコントロールすべきとするように スマホ欲もコントロールすれば美味しい栄養になるとも思った
0投稿日: 2024.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこれを読んで衝撃を受けました、、、普段無意識にスマホに手を伸ばしてる。それは私の問題というよりもスマホ自体にそういう魔力があるということは目から鱗でした。自分の意思でネットショッピングをしてると思っていましたが、それもDMが来たことで気になってまんまと買わされているんだなと思いました。昨今電車の中を見渡すとほぼ全員がスマホをいじっていて異様な風景だなと思います。意識的に読書をしようと思います!
0投稿日: 2024.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ怖い本ですね。 果たして私は、この本に書いてあることが実践できるのか…? と言いつつも、既に今お布団に潜ってこれを書いている状態。
0投稿日: 2024.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「スマホが人間の脳に悪影響を及ぼすのかどうか」という人間の疑問の答えを与えてくれた。結論、スマホ等の電子端末は、我々人類に悪影響及ぼすと断言できる。 人間の進化の見地に立ち、スマホと人類の関わりを生物学的にアプローチしている。著者の主張は全て研究や論文に基づく説得力のあるものだった。 私たちが抱えるストレスや不安の原因を明らかにし、神経伝達物質とスマホやSNSの特性を照らし合わせ、その危険性を根拠をもって提示してくれる。したがって、「スマホから離れる」というシンプルな最終的な提案を、すんなりと受け止めることができた。 人々の日常に寄り添い、エビデンスを持って知識と助言を授けてくれた本だった。 スマホって恐ろしい。
2投稿日: 2024.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の小児科で「人間はとにかく運動。運動した分だけ発達する」と言われたけれど、本書でも同じことを言っている。仕事でモニターばかり見て、チャットやメール返信が合間に挟まると業務ミスも増えやすい…身に覚えがあることばかりで。一日6分軽く動くだけでもかなり違うようなので気楽に運動しようと思った。
2投稿日: 2024.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スマホ脳 著者:アンデシュ・ハンセン 訳者:久山葉子 発行:2020年11月20日 新潮新書 遅ればせながら読んだ。僕は元々スマホが嫌いだし、あまり使わない。ガラケーからスマホにしたのも、この本の出版と同じころ(4年前)で、周囲よりはだいぶ遅かった。それも、ガラケーが故障したので厭々。だから、半ば他人事のように思っていたが、読んで分かった、そうはいかない。もっと深刻に考えるべきだと思った。 深刻って言ってもデジタル化は必然のことだし、人間が合わせるべきものだろうと考えがち。でも、著者の見解は違い、冒頭からやられてしまう。人類が地球上に現れてから今日までの99.9%の時間を、狩猟と採取をして暮らしてきたから、脳はこの1万年、変化していない。おいそれとは合わせられないし、合わせているつもりでも実は大変なことになっている、と言わんばかり。 例えば、こんな面白い話。 10万年前、サバンナに生きるAは甘い木の実を1つ食べ、お腹を膨らませて帰る。翌日、また来て1つ食べるつもりで。 一方、Bは甘味認識遺伝子に突然変異が起きてドーパミンが大量に出る。甘い木の実を食べるとそれが出て、実を全部食べてしまいたいと激しく欲求し、食べてしまう。 翌日、木の実はもうない。Aは飢えて死ぬかもしれないが、Bは前日たくさん食べたのでカロリーが体に残り、生きのびられる。 この2人をそのまま現代に連れてくる。 マクドナルドへ行く。Aはハンバーガーを1個食べて帰る。ところがBはハンバーガー、フライドポテト、コーラ・・・欲望のまま食べる。数ヶ月後に体を蝕み始める。 人間の脳は大して変わっていないとしたら、これは大変。スマホ生活は一瞬にしてこのような大変化をもたらしているかもしれない。だから、分からないところで何かを蝕んでいるかもしれないと思える。 ドーパミンは「報酬物質」だといわれるが、実はそれだけではないという話も面白かった。何かをして、成功体験ではなくてもいいようである。実を求めて木に登り、そこに実がなくてもいい。隣の木にあるかもしれない、という楽しみが湧いてくる。そんな次を期待するように脳をもって行くのもドーパミンの働きらしい。これがギャンブルにもつながっていく。次はいけるかも! スマホにおいては、SNSに「いいね」がついているかもしれない、との期待が通知の度に働く。あるいは、そろそろ通知が来ているかもしれない、とスマホを頻繁に見てしまう。 集中力の実験や調査もおもしろい。 大学生500人の記憶力と集中力を調査。スマホを教室の外に置いた学生の方が、サイレントモードでポケットにしまった学生よりもよい結果が出た。本人は意識していないのに、ポケットに入っているだけで集中力が阻害された。 PC上でワード形式の文章を読んだあと、単語いくつかにクリックできるリンクが貼ってあった文章も読んでもらった。その後、読んだばかりの文章について質問すると、リンクを張った文章の方が内容を覚えていなかった。リンクをクリックしたわけでもないのに。 スマホと精神状態との因果関係を調べるのには、ある壁があるという。 例えば、SNSを使っている人たちの方が、使ってない人より悲しい気分の度合いが大きいとする。そこでは、どちらが先かという「因果律」の問題にぶつかる。原因がSNSにあるのか、悲しい気分の人たちがFBやインスタに引き寄せられるのか、ニワトリか卵か? それならスマホを使っている人から一定期間スマホを取り上げて、それで変化があるかどうか調べればいいではないか、と思う。ところがそれがうまくいかないらしい。被験者たちに途中で〝禁断症状〟が出てしまい、脱落する人が多いから。 最後に、スマホを使うに際してこうしよう、という著者からのアドバイスや提案が書かれている。全部で23項目。 ・目覚まし時計と腕時計を買おう ・毎日1~2時間、スマホをオフに ・プッシュ通知もすべてオフに ・集中力が必要な作業をするときはスマホを手許に置かず、隣の部屋に ・スマホからはSNSをアンインストールして、パソコンだけで使おう など具体的に書かれている。 面白かったのは、友達と会っているときの注意にある次の1文。 ・あなたがスマホを取り出せば、周りにも伝染する *********** (以下、章別の内容) 第1章(脳は1万年変化なし) 自動車や電気やスマホは人類の歴史のほんの一瞬に過ぎない。地球上に現れてから99.9%の時間を、人間は狩猟と採取をして暮らしてきた。脳はこの1万年、変化していない。人間に睡眠や運動の必要性、お互いへの強い欲求が、なぜ備わっているのかを理解すべき。こうした欲求を無視し続けると精神状態がおかしくなる。 10万年前、サバンナに生きる人間。 カーリンは甘い木の実を一つ食べると満足し、翌日お腹がすいてまた来ると誰かに食べられてもうない。飢餓で死ぬかも。 マリアは甘味認識遺伝子に突然変異が起きてドーパミンが大量に出る。甘い木の実を食べると出て、実を全部食べてしまいたいと激しく欲求する。翌日来ると木の実はもうないが、前日たくさん食べたのでカロリーは体に残っている。生きのびられる。 2人が現代に来てマクドナルドに行く。 カーリンはハンバーガーを1個買い、ほどよく満腹で帰る。 マリアはハンバーガー、フライドポテト、コーラに・・・数ヶ月後、暴食がマリアの身体を蝕み始める。 現代社会に適応できないのは身体だけでなく、精神面でも。常に危険への不安を感じ、それを避けるために常に周囲を確認し、異常なほど活発ですぐに他のことに気を取られる。かつてはそれで危険を避けられた。今ではそんな衝動や感情で集中できないと、ADHDの診断が下る。 恐怖を感じた瞬間に、脳はコチゾールとアドレナリンの放出指令を出す。空腹時に食べ物を見ると、ドーパミンを放出して食欲を促す。ドーパミンはオキシトシンと同様、性的に興奮するときにも放出され、他人との絆も感じさせる。だからテレビではなく隣にいる人に集中できるのである。 第2章(HPA系&コチゾール) HPA系(視床下部、下垂体、副腎系)システム。 視床下部(hypothalamus)という脳の部分から、下垂体(pituitary)という脳の下部にある分泌器に信号が送られる。すると腎臓の上にある副腎(adrenal glands)へ、コチゾールというホルモンを分泌するよう命令する。コチゾールは体に最も重要なストレスホルモン。 コチゾールはエネルギーをかき集め、心臓の拍動を強く速くする。ライオンと闘うのか、逃げるのか。「闘争か逃走か」。どっちも血液が大量に必要。だからストレスに晒されると心拍数が上がる。 長期にわたってストレスホルモンの量が増えていると、脳はちゃんと機能しなくなる。睡眠、消化、繁殖行動、すべて後回しにしようとなる。些細なことでも強い苛立ちを感じるようになる。住宅ローンやSNSに「いいね」がつかないストレスに長期にわたって晒される現代。 このHPA系を作動させるのが、脳の扁桃体。扁桃体は「火災報知器の原則」で作動する。間違えて鳴らないよりは、鳴りすぎる方がいい。だからゴムホースを蛇と見間違え、かたまることになる。 うつを引き起こす原因として一番多いのは長期のストレス。うつに関わる遺伝子を調べていくと、驚くべきことが判明。うつのリスクを高める遺伝子には、免疫を活性化させるものがある。 免疫機能の一つにあるのが、感染症や怪我のリスクがある状況から逃げだそうとするメカニズム。うつを引き起こすリスクに影響する遺伝子には、役割が二つある。ひとつは、免疫機能をきちんと作動させること。もうひとつは、危険や怪我、感染症から距離を置くこと。後者は、その人間をうつにすることで達成される。 第3章(ドーパミンの正体、なぜクセに?) ドーパミンの役割は、報酬物質だと言われるが、実はそれだけではない。 最も重要な役割は私達を元気にすることではなく、何に集中するかを選択させること、つまり人間の原動力。 進化の観点からは、人間が知識を渇望するのは不思議ではない。周囲をよく深く知って、生存の可能性を高める。脳には新しいことだけに反応してドーパミンを産出する細胞があり、よく知るものには反応しない。ということは、新しい情報を得ると脳は報酬をもらえることになる。食料や資源が常に不足していたなか、「新しい場所に行く、新しい人に会う、新しいことを体験する」という欲求が、人間を突き動かしてきた。 木に登ってみて実がなかった。別の木に登る。見返りを欲する報酬探索行動と情報を欲する情報探索行動は脳内で密接した関係にある。ドーパミンが快楽を与える報酬物質ではなく、何に集中すべきかを伝える存在。ドーパミンの最重要課題は、人間に行動する動機を与えることだから。 「もしかしたら」がスマホを欲させる。 通知音がなると、スマホを見たくなる。「いいね」がついているかどうか確かめたくなる。何か大事な連絡かもしれないから確かめたい。スロットマシーンやカジノテーブルから離れられなくなるメカニズム。次はいけるかも、確かめたい。 第4章(集中力を奪うマルチタスク) マルチタスクは集中力が低下する。 脳には切替時間が必要で、さっきまでやっていた作業に残っている状態を「注意残余」と呼ぶ。数秒メールに費やしただけでも、犠牲になるのは数秒以上。 並行して複数の作業をできる人もいる。ほんの一握りだが「スーパーマルチタスカー」と呼ばれる。人口の1~2%。女性の方が男性よりもマルチタスクに長けている。 マルチタスクは作業記憶にも影響。 いま頭にあることを留めておくための「知能の作業台」。 スマホをサイレントモードにしても低下する。 大学生500人の記憶力と集中力を調査。スマホを教室の外に置いた学生の方が、サイレントモードでポケットにしまった学生よりもよい結果が出た。本人は意識していないのに、ポケットに入っているだけで集中力が阻害された。 テストの最中に実験のリーダーからメールが届くか電話がかかるかした。それに返答したわけではないが、メールや電話が来た被験者のほうが多く間違えた。 PC上でワード形式の文章を読んだあと、単語いくつかにクリックできるリンクが貼ってあった文章も読んでもらった。その後、読んだばかりの文章について質問すると、リンクを張った文章の方が内容を覚えていなかった。リンクをクリックしたわけでもないのに。 メモ書きはPCに勝る。 手書きはPCほど文字数をメモできない。だから、手書きだと記録すべき情報を厳選する傾向にあるため。 グーグル効果(デジタル性健忘) 別の場所に保存されているからと、脳が自分ではおぼえようとしない現象。脳はその情報がどこにあるのかを優先して記憶する。情報を思い出せなくなるわけではない。「○○にあるのだから、記憶には残さなくてもいいじゃないか」。脳は近道を選ぶ。 マルチタスクにより間違った場所に入る記憶。 事実や経験は「記憶の中枢」と呼ばれる海馬に入る。 自転車に乗る、泳ぐ、ゴフルボールを打つといった技術習得は大脳基底核の線条体という場所が使われる。 テレビを見ながら本を読むなど複数の作業をしようとすると、情報は線条体に入ることが多い。つまり、間違った場所に送ることになる。ひとつに集中すると、情報はまた海馬に送られる。 脳は連想が大得意で、何らかの形でその出来事を思い出させるような小さな手がかりを頼りに、記憶を取り出すことができる。 第5章(睡眠に与える影響) 脳の掃除、健康の維持、情報の安定、記憶と学習のために睡眠は大事なのに、なぜ枕をした瞬間に眠りに落ちないのか。それはおそらく、近く情報を完全オフにするのが危険だったから。狩猟採集民だった祖先は、サバンナで眠るときに誰かに殺されたり動物に食われたりしない安全を確保することが重要だった。 松果体でメラトニンを合成して分泌量を左右するのは、浴びた光の量だけではない。どういう種類の光なのかも関係する。ブルーライトにはメラトニンを抑える特殊効果がある。人間の目にはブルーライトだけ強く反応する細胞が存在するが、祖先にとってブルーライトは晴れ渡った空から降ってくるものだったから。昼間だ、油断せず警戒を怠るな!とメラトニンを作らせない。 眠る前にスマホを使うと、メラトニンの分泌を抑えるだけでなく、分泌を2~3時間遅らせる。体内時計を巻き戻す。今居る場所から時差が2~3時間の場所に戻ることになる。 小学高高学年の児童2000人にベッド脇のテーブルにスマホを置いて寝てもらったところ、スマホを側に置かなかった児童よりも睡眠時間が21分短かった。 ある実験で、寝る前に本を数ページ読んでもらう。一部は普通の紙の本、残りは電子書籍で。同じ内容で。後者の被験者は眠りに落ちるまでに10分長くかかった。電子書籍でメラトニン合成が現象し、分泌が遅くなる。著者個人としては、電子書籍がスマホを連想させるのも一因だと考える。興奮が収まらなくなる。 ブルーライトに影響を受けるのはメラトニンだけでない。ストレスホルモンのコチゾールと、空腹ホルモンのグレリンの量も増やす。グレリンは食欲を増進させる上、身体に脂肪を貯めやすくする。 第6章(SNS) 人間の脳は悪い噂が好き。悪い情報があると、誰が信用でき、誰と距離を取った方がよいのかを把握できる。同じ理由で、争いごとに強い関心を持つ。敵がいる人にとって、他にもその敵を嫌っている人がいるというのは貴重な情報。同盟を組めるかもしれない。 人口の1~2割が他の人間に殺されていた世界では、誰が誰に恨みを抱いているかといった情報は、食べ物がある場所の情報と同じぐらい重要。 一方で、いい噂もモチベーションが生まれるという意味では無意味ではない。 FB、2004年~ 常に周囲のことを知っておきたい、自分のことを話したい、という欲求。 自分のことを話しているときの方が、他人の話を聞いているときより、脳の複数箇所で活動が活発に。 ・内側前頭前皮質:主観的な経験にとって大事な領域。 ・側坐核:報酬中枢とも。セックス、食事、人との交流に反応する領域。 SNSを通じて常に周りと比較することが、自信をなくさせているのではないか。FBとツイッターのユーザーの3分の2が「自分なんかダメだ」と感じている。10代を含む若者1500人を対象にした調査では、7割が「インスタグラムのせいで自分の容姿に対するイメージが悪くなった」と感じている。20代対象の別の調査では、半数近くが「SNSのせいで自分は魅力的ではないと感じるようになった」と答えている。 SNSの調査では、どちらが先かという「因果律」の問題にぶつかる。原因がSNSにあるのか、悲しい気分の人たちがFBやインスタに引き寄せられるのか、ニワトリか卵か? 精神状態が悪くなるような使い方がある。他人の写真をみるだけで、自分は写真をアップしないし議論にも参加しない消極的ユーザーは、積極的ユーザーよりも精神状態が悪くなりやすい。FB上のアクティビティで積極的なコミュニケーションはわずか9%。 心理学者のジーン・トゥェンギーとキース・キャンベルは「ナルシズムという伝染病」を論じていて、70件以上の研究をまとめてみると、彼らと同じ結論が示される。1万4000人に及ぶ大学生を調査したところ、80年代から共感力が下がっていた。特に2種類の能力が悪化。①辛い状況の人に共感できる「共感的配慮」、②別の人間の価値観にのっとり、その人の視点で世の中を見る能力である「退陣関係における感受性」。80年代よりもナルシストになっている。 狩猟採集民のうち10~15%が別の人間に殺されていたと言われている。原始的な農業社会になってからはさらに悪化し、5人に1人。人間を「自分たち」と「あいつら」に分類する。知らない相手に対する不安、特に見た目が異なる人に対して不安が湧く。扁桃体が「火災報知器の原則」を働かせる。インターネット上では、人を「自分たち」か「あいつら」かに分類しようとする強い衝動が効果を発揮する。 アメリカで150人近い大学生に精神状態について質問、予想通り元気な人と軽いうつ状態の人がいた。彼らを無作為に2グループに分け、一方はSNSを普通に使い、もう一方はFB、インスタ、スナップチャットを1日最大30分、1サービスにつき10分までと制限した。3週間後、制限したグループは精神状態が改善した。 第7章(子供たち) 2017年10月発表「スウェーデン人とインターネット」(ここ20年間のインターネット使用習慣を調べた過去最大の調査)によると、月齢12ヶ月までの乳児は4人に1人がインターネットを使っている。2歳児は半数以上がインターネットを毎日使っている。 ドーパミンシステムの活動は生きている間に減少していき、10年間で1割減ると言われている。年ととみに不幸になるという意味ではなく、若い時ほどの興奮を感じることはなく、リスクを冒すこともなくなる。一番活発なのはティーンエイジャーの頃。カロリンスカ医科大学付属病院小児科のヒューゴ・ラーゲルクランツ教授は、タブレット端末が子供の脳の発達を助けるというアイデアには批判的で、むしろ小さい子供の場合は発達が遅れる可能性もあるという。 米国の小児科グループも、ラーゲルクランツと同主張。普通に遊ぶ代わりにタブレット端末やスマホを長時間使っている子供は、のちのち算数や理論科目を学ぶために必要な運動技能を習得できないと警告。 将来もっと大きな「ごほうび」をもらうために、すぐにもらえる「ごほうび」を我慢するのは非常に重要な能力。マシュマロをすぐに1個もらうより2個もらうために15分待てる4歳児は、基本的に数十年後に学歴が高くいい仕事に就いている。 複数の調査では、スマホを使う人のほうが衝動的になりやすく、報酬を先延ばしにするのが下手だと判明している、しかし、これも「ニワトリか卵か」の問題が。数年前の実験では、スマホを使っていない人に持たせたら、報酬を先延ばしにする能力が3ヶ月後に下手になっていることがわかったが・・・ 英国の複数の学校で、スマホの使用を禁止した。朝スマホを預け、学校が終わると返してもらえる。その結果、成績が上がった。 若者の精神不調が増えている問題との関連では、調査、分析が難しいものの、ここ数年である傾向が具体的に。スマホやパソコンの前で過ごす時間が長いほど、気分が落ち込む、パソコン、スマホ、タブレットを週に10時間以上使うティーンエイジャーがもっとも「幸せではない」と感じている。その次が6~9時間使用する若者。ただし、これも「ニワトリと卵」の問いがある。研究の結果、スマホが原因であると臭ってきてはいる。 何かが影響しているかどうかを調べるには、それを取り除いてみるという方法があるが、スマホの場合はなかなか難しい。10カ国の学生を1000人集め、スマホをなくせばどんな影響があるかを調べようとしたが、半数以上が実験を中断してしまった。理由は全員、禁断症状のせいだった。 第8章(運動で対抗する) 不安に陥りやすい大学生を2グループに分け、片方にはきついトレーニング(ランニング)、もう片方には緩いトレーニング(散歩)を週に3回、2週間させた。ただし、どちらも普通の人にできるレベルのトレーニング。どちらも不安の度合いは下がったが、特に効果が顕著だったのはランニング組だった。運動直後だけでなく、24時間続いた。1週間後も。 ストレスのシステム事態はサバンナ時代から変化していないため、結果として、身体のコンディションがよい人ほどライオンから逃げるのが得意なだけでなく、現代社会のストレス源に対処するのも得意になる。あらゆる種類の運動が知能によい効果。散歩、ヨガ、ランニング、筋トレ。運動によって一番改善されたのは、知能的な処理速度。頭の回転が速くなる。一番いいのは、6ヶ月間に最低52時間身体を動かすこと。週に2時間、45分が3回。それより長く運動しても、さらに効果があるわけではないようだ。 第9章(脳とスマホ) ロンドンでタクシー運転手になるには、道路を2万本と場所を5万ヵ所記憶できないといけない。「ザ・ナレッジ」と呼ばれているほど。学習量があまりに多いため、ザ・ナレッジのテスト勉強をしている志望者と一般的な同年代の人を比較したところ、学習前には違いがなかった「海馬」が、テスト合格者は成長して大きくなっていた。記憶の中枢である海馬、特に「後部」が成長。そこは空間における自分の位置の把握を司る場所。一般人と不合格者は変化がなかった。 学習によって海馬が物理的に大きくなる、可塑性があることを示している。海馬が成長する理由を解明する研究が始まっている。知らない場所でGPSを使わずに運転すると、記憶と空間把握を司る海馬と、決定を下す前頭葉の両方が活性化する。三差路のように選択肢が多い状況に直面すると、これらの領域が特に活性化する。 脳は使わないでいると知能の一部が失われる危険性がある。脳にとっては「使うか捨てるか」。スマホやパソコンに多くのことを任せるにつれ、それを捜査する以外の知能が次第に失われるのではと怖くなる。 「インターネットのせいで頭が悪くなり、うつになる」というタブロイド紙の見出しを頻繁に見かけるが、実際にはそれよりずっと複雑な問題。デジタル化は人類が経験したなかで最も大きな社会変革ではあるが、私達が見ているのは「ほんの始まり」に過ぎない。 第10章 目覚まし時計と腕時計を買おう 毎日1~2時間、スマホをオフに プッシュ通知もすべてオフに スマホの表示をモノクロに 集中力が必要な作業をするときはスマホを手許に置かず、隣の部屋に 友達と会っているときはスマホをマナーモードにして少し遠ざける あなたがスマホを取り出せば、周りにも伝染する 鳴るときは、スマホやタブレット端末、電子書籍リーダーの電源を切ろう スマホを寝室に置かない 寝る前に仕事のメールを開かない スマホからはSNSをアンインストールして、パソコンだけで使おう
0投稿日: 2024.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログスクリーンタイム減らして、自分の人生を取り戻す!あと運動もしないとなー。週2時間目標だったらできそうかも。
0投稿日: 2024.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ他の種と同様に、人間の身体と脳を形成してきた唯一の基本ルールは「生き延びて、遺伝子を残す」事だ。 つまり「闘争か逃走か」。どちらにしても、筋肉に大量の血液が必要になる。その為に拍動が速く、強くなるのだ。この反応が今も私達の身体に残っていて、ストレスに晒されると心拍数が上がる。 「ドーパミンの最重要課題は、人間に行動する動機を与える事だから」 貴方の為に特別に誂えた位置に配置されてるのだ 運動は進化上のライフハック(仕事術)だ お菓子の棚に並ぶ栄養の無いカロリーに手を伸ばすのと同じ位、無意味なデジタルなカロリーに対処出来なくなってしまう。スマホというテクノロジーが、人間を2.0バージョンにするよりも、寧ろ0.5バージョンにしてしまうのだ。
0投稿日: 2024.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ確実にスクリーンタイムを意識する時間が増えた。 ドーパミンを放出させるアプリの仕組み。スマホを作った人が後悔してる。 スクリーンタイムが増えれば増えるほど、ストレスが増える。
0投稿日: 2024.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホ依存の人は一度は読んだ方がいいと思いますほんとうに。 snsの闇を知ることができてxなど少し見る目が変わりました あとこの作者の本は一貫して〇〇が悩み?運動しろ!!って感じです
2投稿日: 2024.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログいっぱい運動をした方がいいみたい❕まゆちは運動が苦手だけど、がんばってみようと思った❕ スマホ依存していなくてもみんな予備軍になりうるから学校とかにも置くべき1冊って感じ❕
2投稿日: 2024.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んだ感想をスマホで記録するって‥汗 スマホと脳の関係をわかりやすく書いた本。 学術書あるあるだと思うが、一部極端なところはあるが全体としてわかりやすく、スマホ利用について考えさせられる。思わずスクリーンタイムを確認してしまったし。 スマホはつい使いたくなるようにできているとの論。何かを期待する時に一番ドーパミンが出るそうで、いいねがついていることを期待する→ドーパミンが出る→快楽を感じる→スマホをみる=スマホを使いたくなると、いうことらしい。納得。 運動ね〜。なんかしなきゃと思いつつ。 まずは、スクリーンタイムを減らすところからやろうっと。
10投稿日: 2024.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホを長時間使うと睡眠障害、うつ、記憶力・集中力の低下を招くらしい。これから子供を育てる人にはぜひ読んでほしい本だ。とスマホのアプリに書き込む自分は…。
1投稿日: 2024.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ狩猟時代に外敵の驚異に脅えて生活してきた時から人間の脳は基本的に変わっていない 起きるかもしれないという脅威に対して闘争か逃走かのメカニズムが作動 SNSによって不特定多数の人と比較出来るようになってしまい、その影響を特に受けるのは女性であり自己肯定感が下がる 整形が一般化してきたのもその影響? デジタルデトックスしながら運動するのはとても大切
1投稿日: 2024.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ数百万年かけて進化してきた脳の仕組みに、急速に発達するデジタル技術の影響がどれくらいのものなのか、メリット・デメリットがどうなのか、とてもわかりやすく書いてあって面白かった。そして、デジタル技術との関わり方を考えさせられた。この本は何年か前に書かれたものだけれど、この書かれた当時よりデジタル技術が発達した今こそ読むべきものだ。災害大国の日本ではスマホは重要な位置に来ているが(3.11の時のTwitterや緊急地震速報の技術)触れる時間を減らすのは作れる。自分の脳やメンタルのためにも。
4投稿日: 2024.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ急速なデジタル社会へ変化している現代で、人間としての自分がどう向き合っていくべきかを考えさせられた1冊だった。 人間の脳は狩猟採集時代に完成されており、現代の環境と脳が認知している環境がまったく違うというのが本書の前提。 そのうえで ・なぜ悪いストレスが現代人に精神疾患という形で発現するのか? ・スマホが私たちの脳へどのような影響を与えるのか? などを研究とともに示してくれている。 デジタル化は間違いなく我々の暮らしを効率化してくれる良い面があると同時に、人の集中力をいかに奪うかを本気で考えてコンテンツ作りをしている、という事実に気付けたことが収穫だった。 そしてそれらが我々の脳には合わないことであり、いかにして利用すべきとこを利用するかを一歩引いて見ることの大切さを学んだ。 進歩主義に囚われていることを認識し、自分にとってなにが必要かを考え、行動していこうと思う。
1投稿日: 2024.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の脳はスマホを長時間使うことに適した作りになっていないと説く本。長らく狩猟生活を送ってきた人類にとっては、新しい情報が次々と入るスマホは刺激が強すぎるとのこと。 SNSには脳の報酬中枢を煽る仕組みがあり、それを導入した人でも後悔している人がいること、スティーブ・ジョブズは自身の子供のスクリーンタイムを制限していたこと、長時間スマホを使用していることで人々の集中力が低下していること、心の病が増えていることなどが書かれている。 自分自身もスマホを長時間利用している方だったので、早速使わないときは別の部屋に置いておくなど実践し、まだ1週間程度ではあるが以前の2/3〜1/2程度まで減らせるようになった。今後も続けていきたい。多く紹介してくれている各研究の出典が明らかになっていればより良かったが、スマホの利用時間を減らすきっかけを与えてくれたので星5。
8投稿日: 2024.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホの危険性を人類の進化の過程、脳の仕組みという観点から述べていた。脳は不確かな期待が大好きで、新しいものを探してきた歴史の上にスマホというドラッグが入り込んで我々の時間と健康を奪っていく。便利な物であるが、適切な距離をもって接した方が身のためになると思わされた作品であった。
1投稿日: 2024.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代におけるスマホの危険性を十分に謳った一冊。その中でも精神疾患患者が増えてきているメカニズムは精神科医である作者により、より納得させられた。スマホが無いと生きていけない現代の人間全てが読むべき本。
2投稿日: 2024.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の生活において良くないことの原因は全てスマホだった、と偏った意見を持ってしまった。 が、この極論が不思議ではない、正しいだろう、と本気で信じてしまっている自分がいる。 本書では、人間の脳がどのように出来ているか、そしてそれは現代においてどのように働くか、を知れる。そして、恐ろしいことが現在進行形で起きている、と警鐘を鳴らしてくれる。 書いてある事例は日本以外での出来事だが、実際読んでみるとあまりにも身近すぎてついついのめり込んでしまった。 途中途中に出てくる調査結果の参考文献は載っていないが、それでも自分の身近に起きている現象を考えると信じざるを得ない。 明日から行動を変えよう、と本気で危機感を持った。 追記: スマホ脳を読んで欲しすぎてnote書いた→ https://note.com/moroball14/n/nc03f32fe46c6
7投稿日: 2024.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
島崎和歌子さんがオールスター感謝祭頑張ってる間にテレビ観ないでずっと読書してたことが心苦しく申し訳ないのですが、さておきめちゃくちゃ面白かったです。 スマホ依存は良くないよ、なんてことは改めて言われなくてもわかってるわ、そういう当たり前のことを長々と説明してる本なんだろう、とナメきった態度で読み始めたのですが、一気読みしてしまうほどのめり込みました。 大昔の人間の十人に一人は人間に殺されていたみたいな話とか、考えてみればルールがなくて人間が死ぬ頻度も多くてしかも大きめの動物を日常的に殺してたら殺人のハードルもぐっと下がるもんな、と今の自分が当然としている価値観が今自分が置かれている環境によって植えつけられてるもので普遍的なものではないことを、それこそ言われてみれば当たり前のことなんだけども、新しい未知の情報を教えられるというより「あ、そういやそうか!」「たしかに!」「なるほど!」といった思考の盲点を次々に突かれる快感がある本でした。 読み終わってすぐこの感想をSNSに書いてる時点で「お前本当にこの本読んだのか」と著者の方に言われかねないですが、本に書いてあったことを実行に移すかどうかは一旦置いといて、取り急ぎ超面白かったことをご報告しておきます!
1投稿日: 2024.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分自身でスマホ依存だとは分かっていて、時間を減らした方がいいのかなとは思いつつ、でも目の前の報酬系には抗えず使い続けていました。 根拠がとてもしっかりしていて、初めて、本当に行動変容してみようかなという気持ちになりました。 また、小さい子どもの子育て中ということもあり、将来子どもとデジタルスクリーンの関わりをどうしていこうかなと思っていましたが、考えの助けになるようなことが時間や他のものに集中する時間をつくるなど、具体的に書かれていてとても良かったです。 時間確認のためスマホを使っていましたが、まずは、電池の切れた時計を、時計屋さんに持って行って電池を変えていただいて使おうと思います!!!
1投稿日: 2024.10.04
