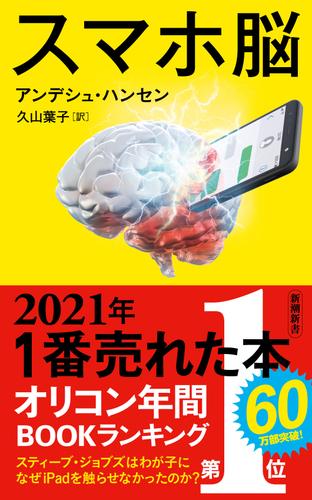
総合評価
(1488件)| 580 | ||
| 575 | ||
| 219 | ||
| 23 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ・とにかく目の見えないところにスマホを 手の届かないところに置くのが1番。ポケットもダメ。 睡眠の際は特に。時計をつけて画面を開かないように デジタルのメリーゴーランドにまわされてしまう 人は今の内容より、次のリンクをクリックしたくなる ・マルチタスクは多くを吸収しない 知識が固定しないため、1度に多くのことをやるのは意味がない。久雄監督のいうように、今やる役割を明確にしてプレーする •不確定要素への興奮 ロード時間は敢えて待たせてる。スロットマシーンの原理。下にスワイプすると、クルクル期待させて、新しい投稿が出てくる。この待ち時間にドーパミンが出まくる。大企業の開発担当の心理行動学者達の優秀さ。 いいね!が付くタイミングも、押した時間とはわざとずらして反映させている。そうすることで、小刻みにSNSにアクションが起こり、また永遠のフィードバックループにはいる ・スクリーンタイムの活用 自分がどれぐらいスマホを触っているか定期チェック ・6分の運動でいい 長く走る必要はない。5分外でジョギングするだけで健康へよ影響は計り知れない
0投稿日: 2021.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ画面を眺め続けるのではなく、実際に人と会ってコミュニケーションを取ったり(今は難しいですが)手に触れて感じたり見ることが脳に取っても良いのだなと感じました。 スマホを使い過ぎていると前々から気にしていたので、やっぱり制限しようという気になりました。 2時間以内に抑えるのはなかなか難しいですが、実践してみようと思います。
0投稿日: 2021.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
あなたも薄々危険だと思っているのではありませんか、スマホ。 人間の脳はデジタル社会に適応していない。この本の結論はこれである。人間の脳が狩猟採集をしていた頃と変わっていないという主張は、自分では確かめられないのでさておき、集中力の低下、イライラ、不眠、鬱な気分などはなんとなく自覚があり、スマホを一日中使っていることも自明なので、ああ、スマホの害だ、と受け入れてもいい。他に原因があるかもしれないけれど、スマホが悪影響を及ぼしていることに、異を唱える気はない。これは確かにベストセラーになりそうな本である。 睡眠を優先しよう。積極的に体を動かそう。コロナ禍の今だけど、できることをして、自分をスマホに奪われないようにしていこう。
0投稿日: 2021.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは、売れてる本だなというのと、スマホが害になることが段々と分かり始めて、でも制限をかけられない、戒めになるのうるような、害になることが書かれていたら習慣を変えられると期待して。期待通りだし、子供への影響が恐ろしく、即刻スクリーン制限を設けた。
0投稿日: 2021.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログめちゃくちゃ勉強になった。当たり前に持ってるスマホが与える影響はしっかり理解しておく必要がある。これはスマホを待つ全ての人が読むべき一冊。 人類の進化のスピードと技術革新が並走出来てないから、人間に無理が生じるのは当然かなと。 仕事以外はアナログが良いよ。
1投稿日: 2021.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ私たちが使う道具が、どのような影響をもたらし、なぜそのようになるのかが、わかりやすく書かれている。スマホの影響は大きい。自分だけでなく、息子がどう使うかにも注意していかなければならないと感じた。息子にも、ぜひこの本を読んでもらいたい。
0投稿日: 2021.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで99.9%狩猟と採集で生きてきた。 だから今でも脳は狩猟と採集時代のまま。 by.人間の脳(本書にこんな記載はありません) 本書はこの考えが軸。ここがズレることなく、理論として納得させてくれるため気持ちよく読み進められる。 ・飢餓脳が残ってるから高カロリーに手が伸びる。 ・注意散漫(狩猟時代脳)現代ではADHD。 ・高い所やヘビは未だ怖いのに、現代死率が高いタバコやシートベルトは怖くない。など。 過去人間が生きていく為に必要な"脳力"の名残があると。 そしてキーになるのがストレス。 生き延びるために必要だった瞬時の反応。狩猟時代にストレスを感じれば=死の危機。『闘争か逃走か』状態になり、それ以外のすべてのことを放棄する。 現代でも名残があるので、ストレスがかかると睡眠や消化すべて後回し。そして身体に負担。 またストレス=危険な環境にいる。と脳に認識されるのでその環境から遠ざけるために、感情や気分を落ち込ませ引きこもらせる。不安や現代うつの多発である。 そして脳を今、ストレス状態に晒すものは何か。 そう、それがスマホだ。 1日平均4〜5時間のスマホ。SNSのいいねがほしい。欲求もストレスに変わる。人が羨ましく見える。自分は最下層だと勝手に認識する。過去も今も人間は競い合うが、今は見る、競う相手が多すぎる。9人に1人が鬱の時代。さらにスマホによって睡眠、運動など無視し続けより悪くなってしまう。 なにより、スマホはドーパミンらしい。 ドーパミンの最重要課題は行動する動機を与えること。 そこに木の実ができてるか行ってみようとさせる役割。過去の生きる為の重要な物質。ドーパミン。 新しい知識やわからない不確定なものに、よりドーパミン報酬は活発になる。スマホはその役割を果たしている。無意識に10分に1度触る=10分ごとに情報をスクロール、ドーパミンを補給してくれる。 なのでスマホを失ったらストレス。無くさなくてもスマホ依存者はストレス過多。ガンジガラメ。 この人間特性をわかった上でのSNS企業の策略、スマホ依存の対処法など、こみいった話は是非本書を手に取って確認してほしい。 明日からきっと、スマホ触らなくなるよ!
1投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ私たちはスマホを見てしまうのか。進化の観点から説明され、とても納得ができる。それと同時に、スマホを使うことに恐怖も感じた。スマホが脳をハッキングしてる。とても響く言葉であった。
0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログsnsをさわるうちに自分の時間は失われ、集中力も欠くようになった。改めてデジタル社会との生き方について考えられた。
0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホ認知症という言葉が気になりだしたので、タイトルに釣られ購入。 この系統の本は読むのが得意ではないですが、面白く一気読みしてしまいました。 スマホはとても便利だけれど、節度を弁えなければ悪影響を及ぼしてしまう。 読みながら、自分も暇さえあればスマホを触ってる事を思い出し、自分も十分に末期かなーとか思いました。 何気なく使ってるもの、便利なものほど注意が必要だと教えてくれた一冊。 とりあえず子供が出来たら、スマホを持たせたとしても、使い方はしっかり教育していきたいと思いました。
0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の体がデジタル時代とミスマッチを起こしていることを進化生物学の観点から解説するもの。橘玲さんの本など読んでる人にはお馴染みの展開かと思います。 またスマホに関する警告については「デジタル・ミニマリスト」と極めて類似。
0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神科医が書いたスマホの使い方に脳科学や人類科学から警鐘を鳴らす本。専門的な内容を分かりやすく説明している。 ミラーニューロンは脳の複数の領域に跨っていて、その一つが体性感覚野で、他人がどう感じているかを理解する領域だ。ミラーニューロンを最大限に機能させるには他人に会う必要がある。次に活性化するのは演劇鑑賞だ。 人間は元々マルチタスクが苦手。二つの作業をこなしてると思っていても、その間で集中の対象を変えているだけ。 集中力を回復させるには切り替え時間が必要で、元の作業に100%集中できるまでには何分も時間がかかる。チャットやメールを、チェックするのは1時間に数分と決めた方が良い。
0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログまさにスマホ脳なので、読んでいてスマホの怖さをとても感じることができました。すぐに実践できることも少しではありますが書いてあったので、早速実践しています。
1投稿日: 2021.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん 脳の働きを根拠に影響を論じているので説得力がある。 ・現代の状況に人間の脳は対応できていない ・ストレスの時間が長いため闘争か逃走かという選択しかなくなる。そのため睡眠、消化、繁殖行為が後回しになる。 ・うつは感染から身を守る現象 ・脳は確定報酬より不確定なことによりドーパミンを出す。人を行動させるために出すものだから。 ・ギャンブルとSNSの通知は同じメカニズム。SNSの製作者はその脳の機能を理解して中毒にさせている。 ・自分のことを話すとき、セックス・食事と同じ報酬中枢の側坐核が活性化する。 ・ネガディブな話題が好きなのは、太古の危機管理。 ・SNSで不幸になるのは、人と比べてしまうから。セロトニンが減る。女子は常に他者の”完璧な容姿や人生”にさらされている。 ・共感力/対人感受性を担う体性感覚野はリアルに人に会う、その次にリアル演劇を観る、で養われる。スマホだけでは成長しない。 ・前頭葉が成熟するのは25歳以上、子供はスマホの報酬まみれを浴びると衝動を抑える能力が育たず先延ばしにできなくなる。 ・どんな少しの運動でもストレス解消、集中力アップに役立つ。
0投稿日: 2021.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代のストレスとスマホによる影響を進化論をベースに考察した本。 大昔の人間におけるストレスは肉食獣に接近した数分であったにも関わらず、現代では長期化しているが、人間の体は変わっておらず、それに対応出来ていない。ストレスを感じた時は「闘争か逃走」の選択を迫られ、思考・睡眠・性欲等の機能が一時的に抑制される。長期的ストレスは人間の体にマッチしておらず、意識的・戦略的に防御していく必要がある。 一方、スマホは触るたびにドーパミンが分泌され、依存度が高い。何をしていてもマルチタスク的にスマホを触るようになる。これにより過度な情報が絶え間なく流れ込み、思考が停止する。 スマホを触る回数は、意識的に少なくするべきである。
0投稿日: 2021.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ脳科学や精神医学の知識がなくても、スラスラと頭に入ってきてとても読みやすかったです。 今までの歴史がこうだったから、現代の人間にこういう影響があると因果関係を示していたので、すごく納得できました。 何気なく使っているスマートフォンだけど、とても恐ろしい効果があるのだと知り、筆者の推奨するスマートフォンとの距離感を実践していきたいと思います。
0投稿日: 2021.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホ、SNSに依存するのは生物としての性をいいように利用されているからなんですね… 一番恐ろしいと思ったのは【共感性の欠如】や【ナルシズムの加速】部分ですね。
0投稿日: 2021.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
脳がどのように作用し、人間に快楽を与え、またストレスを感じるかなどの脳の仕組みを始め、どうして人間はスマホの虜になってしまうのかが理解できる本。
2投稿日: 2021.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ改めてスマホやSNSの使い方について考えさせられた。ちょっとひとたびスマホを触り始めると様々なSNSを一通りチェックしてしまうが、まさにサービス自体、人間が依存するように作られているのいうので納得した。これを読んで、スマホのスクリーンタイムの上限を設定して、より健全な使い方をしようと決めた。
0投稿日: 2021.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想、私だな。と思った。 振り返ってみると、いつも携帯を気にする日々。 暇さえあればインスタを見て、ネットサーフィンをして、彼氏の返信が来ないか気にしている。 脳の報酬系の仕組みや脳の成長の仕組みをよく学べた。 スマホはドーパミン報酬を手に入れやすく、依存しやすい。 客観的に自分の行動を脳の仕組みから分析することで、なんとなくしていたネットサーフィンをやめようと思えた。 刺激を求めすぎて集中力が欠けてしまう。 元の脳のパワーを発揮させるためにも、スクリーンタイムを決めて、うまくスマホと向き合えるようにしたいし、適度な運動や生体験を大事にしたいと思った。
0投稿日: 2021.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ購入して読んだ本。 スウェーデンの心理学者が書いた本で話題作。 スマホやSNSが人間に与える影響について学ぶことができた。 具体的には「子どもにはスマホ使用の制限時間を設け、あまり使わせないようにする」逆にいうと、スマホを扱う時間を与えないくらい運動や睡眠を推奨する。 適度な運動には記憶力や集中力を高める効果がある。 自分も1日1万歩を意識しているが継続していきたい。 たまにはスマホデトックスしたいと思うがなかなか難しい。できるだけ、通知をオフにしスマホに乱されないようにしたい。
1投稿日: 2021.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこうした本をちゃんと読んだのははじめて。脳の働きから説明されるとなるほど納得と思う。いくつもの実験が紹介されているのが良かった。
0投稿日: 2021.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ジョブズが自分の子供にデジタル機器を触らせないようにしたのは有名な話ですよね。子供への悪影響はよくわかる。
0投稿日: 2021.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホ(を含むデジタル機器)の使用がヒトの脳にどのような影響を及ぼすかを、最新の研究から明らかにした本。自分は依存とは無縁だと思っていたが、読めば読むほど思い当たる部分がありすぎて怖くなった。スマホの魅力は、それが人間の原始的な欲求を巧妙に煽るからだという。しかもスマホの刺激には際限がなく、「あと少し」を繰り返すうちに時間や心身のエネルギーを奪い取ってしまう。教育関係者や子どもを育てている人にはぜひ読んでほしい1冊。
1投稿日: 2021.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ一部、本当にそうなのか?論理の飛躍では?と思わざるを得ないところもあります。しかし、自分や周りの人々の行動を振り返ってみると、当てはまることも多いのも事実。とにかく自分の行動をコントロールすることの大切さを感じた。
1投稿日: 2021.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段の自分の内容を内省する、自制するという意味では必読の1冊です。 スマホに関して、がっかりな研究結果が連投されていき、読んで行くうちにどんどん不安になってくる点では、存在価値の高い本です。 そらゃ、世界中で売れますよ…
0投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最近スマホの使いすぎに気づき、読んでみた。結論はスマホは遠くに追いやった方が良い。デバイスを操るのではなく、操られている事が問題。しかも、まさかドーパミンが出ているとも知らず。本書の内容が本当ならば毎日中毒になるようにさせられているだけで、中毒になるのも当たり前の結果。 人類はそろそろこの事に気づき始めると思うが、早めに対処したい。
0投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や必需品となったスマートフォン。しかし、使いすぎてしまうと、人間の脳に支障が生じてしまう。この作品では、脳科学の観点から、どのように情報が脳に入っていくのか。それによって生じるストレスや鬱、睡眠障害などを紹介し、現代の人間に警笛を鳴らしていきます。 作者は精神科医なのですが、脳についてのメカニズムも書かれてます。難しい専門用語もありましたが、実験データも紹介しているので、より具体的で、身近に感じました。 頭では、体に影響するということは理解しているのですが、動画やSNS、ネットなどついつい見てしまいます。常に新しい情報を欲してしまう。そういったことも書かれていて、共感するところが多くありました。 また、驚いたのは幼児にもタブレットを使用していることでした。便利かもしれませんが、早すぎなのでは?と思ってしまった自分がいました。持たせることは良いかもしれませんが、その辺のバランスが親の見せ所かもしれません。 全体的に思ったことは、「何事も程々に」が大切だと感じました。ネットを使用するというデジタルな部分と睡眠や運動といったアナログな部分をどうバランスを維持するか。 実際に体験してみないと、なかなか実感がわかない部分はありますが、起きたからでは遅いので、今のうちに睡眠や運動など少しずつ習慣を変えていこうと思いました。 色んな方に読んでいただきたいなと思いました。特にスマホを使いすぎている方におすすめです。
1投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ日頃、スマホの使いすぎを感じていたため、読んでみた。研究結果を用いて、スマホの使用がもたらす影響が示されており、自身のスマホの使い方を見直すきっかけになった。
1投稿日: 2021.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ①この本を読む目的 ・1日4,5時間、多い時は10時間もスマホに時間を費やすことを止めたい。 ②読んで感じたこと ・脳はなんと1万年前から変わっていない。 生き延び、遺伝子を残すことを目的に 感情を起こし、行動させようとする。 ・だから原始時代と同じ生活が脳には合っていて 精神的にも良い。 明るくなったら起きて、日中は運動(狩り)して、 他人と関わりながら、暗くなったら寝る。 ・脳は新しいもの好き。周りの人よりも新しい状況 を知った方がより生き延びる可能性高まるから。 だから何か起こるかもという期待が人間を動か す。SNSやニュース速報を何度もチェックしたく なる本能的な理由。 ・人間は一度にひとつのことしか集中できない。 同時にこなしていると思っても実は行き来してる だけで効率悪い。スマホが目に入るだけで無意識 に集中力と作業記憶が削られる。 ・睡眠、運動、他者との関わりを軸に生活習慣を 考える。スマホはすぐ手の届かないところに置 く。
1投稿日: 2021.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログiPhoneのスクリーンタイム機能の必要性をここまで理解させる本は初めてかも。 私たちは日々多くの情報に囲まれ、必要な情報を逃すのではないかという恐怖を感じてしまいがちである。 しかし、もっと危険なのはその恐怖に漬け込んで私達をスマホ中毒へ誘うさまざまなサービスだ。 AIが人間の代わりに仕事をやってのけることができる今、人類に残される仕事は集中力や思考力を要する仕事なのに、スマホのせいでそれらが奪われてしまっている。 電車に乗ればほとんどの人がスマホをいじっており、これは明らかに大型の人間がスマホ中毒に蝕まれていると言える。本来はスマホから離れて思考を巡らせることで生まれるはずのアイデアも、今の生活スタイルでは蓋をされてしまう。 まずは一人一人がスマホ中毒であることを自覚する必要がある。この本はその助けになる有益な情報を提供してくれる。
0投稿日: 2021.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史的な経緯からデジタルの成長に人間が追いついていない。 スマホの使いすぎで心身にさまざまな不調をきたす可能性がある。 スマホ利用を見直し、運動、睡眠、健康を意識した生活を心がけるようにする。
0投稿日: 2021.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログオリジナルのタイトルはスクリーン脳といった感じ。人類が人類である前から築き上げてきた生き残るための能力が、スマホにというよりはそこで金を儲ける企業にハックされてしまいつつあること。子供たちが無防備にそれにさらされていることへ脅威を改めて明らかにしてくれる。たしかにその通り、という部分は多い。集中、記憶、そのようなものは時代遅れになってしまうのか、その代わりのものが現れるのか、精神活動のこれほどまでの転換は人間が経験していないのは間違いなく、我々は大きな実験に立ち会っている。
0投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の脳の進化の結果と現代のデジタルデバイスとの ミスマッチが引き起こす様々な弊害について書かれた本。 狩猟のために培われてきた神経系が、 今の世の中ではむしろ足枷となっているのだなぁ… 「近くにあるだけで集中力が低下する」 「着信を期待するだけでドーパミンが出る」 あたりは衝撃的だった。 上手く距離を作って、スマホやデジタルガジェットと 付き合っていく必要がありますね。
0投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ生物学的な進化と人類の生活環境の変化の速度差に着目し、スマホ依存の弊害やデジタル化社会での我々の振る舞い方について、問題提起した名著。 我々の祖先は周囲の情報を得る事で、生存の可能性が向上した。そのため、新しい情報に対し、脳内報酬物質(ドーパミン)を出す。スマホはほぼ無尽蔵に情報を与え続けるため、人はスマホ依存になりやすい。 そして、スマホ依存は、以下のような症状を引き起こす。 ・ストレスや鬱 (新しい情報があるかも知れない状態の継続で脳が常にonな状態が継続するため) ・集中力・記憶力低下 (マルチタスクの常態化のため) ・睡眠障害 (上記精神状態に加え、ブルーライトの影響) 例えば、食べ物のように昔は、いつお腹いっぱいになるまで食べられるかわからないため、出来る限りカロリーを摂取しておく事が生存のために必要であった。しかし、実質カロリー無料の現代においては、心臓病や高血圧などの原因となり得る。情報も同じで、世界中の情報がボタン一つで手に入ることは、我々の祖先とってはこの上の無い幸せであるが、無尽蔵に手に入る今、その取り扱いについて考える必要がある。 著者は、デジタル化の急激な広がりの中、人間が本来備えている機能を有効に働かせ、肉体的・精神的に元気にやっていくためには、 ・睡眠を優先し、 ・身体をよく動かし、 ・適度なストレスに自分を晒し、 ・社会的な関係を作り、 ・スマホの使用を制限する 事が必要と説く。 脳科学、生物学、社会学的な実験結果や根拠も豊富で非常に説得力のある本でした。 2017年に公開されている著者のTED TALKの「why the brain built for movement?」(英語字幕付)も短時間で著者の論点の立ち位置が確認でき、眼から鱗の講義ですので、オススメです。 https://youtu.be/a9p3Z7L0f0U
3投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の日々の行動の背景が理解できて参考になる。 「なんとなく嫌だな」と思っている自分の癖が、 「自分の脳は今こう作用しているからこの行動を取っちゃうんだな」と明文化される。 癖は即時に変えられるものじゃないけど原理がわかることは重要な一歩だと感じました 平易でわかりやすい、2時間程度で読み終わりました
1投稿日: 2020.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いし納得できるけど、スマホというよりもSNS脳とかweb広告脳とかの方がタイトルとしては正しい? ソシャゲとかもそうだから、結局スマホを通じて提供されてるものがそうなのかな 人間の脳はサバンナ時代に最適化されたままであり、その最適化により未知のものに対してドーパミンを使って意識を向けさせる。それが最大効率化されたものがスマホであり、脳の構造をハックされる。
2投稿日: 2020.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020.12.30 最近、ランキングに入ってるのをよく見るので買ってみました。なかなか、良かったです。、世間でスマホに関して言われていることの、研究とか数値とかその理由がちゃんとかかれてあって、納得。 スマホというより、鬱傾向にある人へ みたいな本になっていると思いました!
2投稿日: 2020.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人類の歴史を考えたら、人間の体は急激なデジタル化社会に適応するために急激に変化している、というわけではないよ、というのが著者の大前提。狩猟社会では注意散漫になることであらゆる危険を回避してきたが、現代社会では物事に集中することが求められる。そのため、マルチタスクをこなして脳が快感を得ているような場合でも、それは集中できておらずあまり実にならないことが多いと言うのはなるほどなぁと思った。実際スマホをつつきながら映画を観たり音楽聴きながら勉強するとき、内容が頭に入ってこない場合がほとんどだ。 加えて、運動が大切と言うのもとても共感。今年は週3でテニスができたおかげで受験がうまく行ったと言うのもあると思う。 私は「すぐにLINEの返信しなきゃ」とかなることはないので、スマホとは距離を置けると思う。切替時間がもったいないので、たんびにスマホを見るような習慣を試しにやめてみようかと思う。
2投稿日: 2020.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の脳の機能をもとにした解説で、表題にある「スマホ」の悪影響みならず、デジタル化によって劇的に進んだマルチタスクや、うまく長期記憶化できないデジタル健忘症、運動の機会が減ることについても警鐘を鳴らす。 本書で特にインパクトが有るのは「子どもにスマホを持たせるべきか」だろう。 衝動に歯止めをかけ、報酬を先延ばしにする脳機能を持つ前頭葉は、10代ではまだ成熟仕切っておらず、25~30歳頃に完全に発達するらしい。 前頭葉が成熟した大人ですら、報酬の先延ばし、我慢にはそれなりの意志が必要になる。 まして10代以下の子どもたちであれば、ドーパミンが溢れてくる情報のご馳走を我慢できるのはどのぐらいの割合になるのだろうか。
1投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類の歴史から ・ヒトの脳が何を好むか ・そしてスマホがそれをどう刺激するか ・スマホによる刺激によってヒトの感情や行動がどうなるか という観点で、スマホ中毒・スマホ依存症を解説。 シンプルで分かりやすい。 日本語訳も上手だと思った。
0投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタルのメリーゴーランドに振り回されていて、それを自覚しているものの、自分が情報の生産者側に立ちたいと思うと、現代ではデジタルと共に生きることを突きつけられる。 集中力やIQが下がるリスクを知りながらも、デジタルと共に生きざるを得ない私はどうすれば良いのだろう。個人的な答えはこの本の中で見つけることはできなかったけれど、試行錯誤してこの問題に向き合っていくことを覚悟した。 私が恐れているのは、何かをしているつもりで、何も成し得ない人生を送ること。この本で自分の恐怖が浮き彫りになった気がする。
0投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「スマホの使い過ぎは体に良くない」というなんとなくわかっていたことを脳の構造や人類の進化の歴史などから詳しく説明してくれる本。 自分も気がついたらSNSやYouTubeなどを見ることに時間を使っている。その時間は何も生産性がないだけでなく、脳や体にも悪い影響をもたらしているということを普段から意識して生活していきたい。また、適度な運動など最低限”人間的”な生活を送れるように心がけていきたい。
1投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホの影響、人類に未踏の変化をもたらしている。 進行中の中でわかっていることと想像できること。どうやらあまりよい状況ではないが、対策対応も教えてくれる。注意点と距離感を掴むにもよかった。
0投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログドーパミンは人に行動する動機を与える。スマホは見ないようにするために意識をしたり、SNSをずっとみていたりと人の思考を妨げる。私のスマホのスクリーンタイムを見て、どれだけスマホに依存していたのか実感した。スマホは悪ではないが、使い方を考える必要がある。 人の感情を感じるために、ミラーニューロンが活性化される。これは、直接人と関わるからこそ発揮されるものであるから、直接コミュニケーションの良さは共感力をも育成できると思う。 集中しているつもりでもマルチタスクは本当はできていない。やるべきことに集中できるよう、自分の中で区切りをつけてスマホと向き合っていきたい。
1投稿日: 2020.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が実生活で薄々感じていた部分を、綺麗に言語化してあって共感する部分が多かった。 スマホの扱いを見直す良い機会となった。
0投稿日: 2020.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味深い本です。 スマホを中心としたデジタルツールの脳への影響。 人間が本来もつ本能とのギャップ、また本能ゆえに依存してしまう。 楽しめるはずのSNSがストレスや鬱を引き起こしてしまう、ただそれは自分を守るために本能が働いていると思うと少し気も楽になる。 スマホに自分を乗っ取られることなく、うまく付き合っていくこと。 人は睡眠、運動、人とのつながりが大事。 コロナ禍の今だからこそ、読むべき本。
2投稿日: 2020.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホが子どもに与える影響が気になり購入。 自分にとっても、スマホの使い方を見直すきっかけになった。 たしかに読書をしていても、最近集中力が続かなくなったように感じる。 スマホ利用時間の制限・睡眠時間の確保・適度な運動は実践したい。
1投稿日: 2020.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読み終わった後電車に乗る機会があった。9割はスマホをいじっている。スマホは人間に大いなる行動変容をもたらした。しかしその悪影響はまだ解明されていない。ただ幾つかの調査報告では子供の睡眠時間の減少、集中力の低下、報酬系に効果的に作用するSNSの実態が明らかになっている。悪影響に有効な対策を講じぬまま、我々はすっかりスマホに搦めとられたのである。
0投稿日: 2020.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ進化の歴史や仕組みから、やはり私たちはこの急激なテクノロジーの変化に適応できていないのだと知った。それを人間としての知能を使いながらどうコントロールしていくのかが重要である。 一方で、企業は人類が進化の歴史の過程で作り上げた、脳の機能に対して広告を流してくるなど私たちの脳は日々ハッキングされている。こういった本を読み知識をつけることでそのハッキングからどう自身を守るのかが試される。
0投稿日: 2020.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホを触る時間を減らして努めて運動しようと思いました。 それにしても子供のスマホ中毒を何とかできないものか?
0投稿日: 2020.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログFacebook、Twitter、InstagramなどのSNSは我々にどんな影響を及ぼしているのか。 毎日5~7時間以上もスマホを使用している人もいるようだが、それは社会生活や健康上の面などに対して問題はないのだろうか。 私自身も今はスマホの使用時間は毎日平均1時間くらいだが、昔はずっとスマホをいじっていた時もあった。 1日24時間しかないのはみな同じ。 昔スマホに使っていた時間は読書と運動、そして睡眠にあてている。 スマホとうつとの関係についても書かれているが、ちゃんと付き合い方を考えないとスマホは毒にも薬にもなりそうな存在ですね。
0投稿日: 2020.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなくスマホが身体の健康等に良くなさそうだなというイメージは多くの人が持ってると思いますし自分もその中の一人でしたが具体的にどういう影響が出ているのかを理解することができました。特に人間の進化の過程で脳がどのように発達してきたかの観点から分かりやすい実例や多くの実験データを用いて記されている点が良かったです。 また、翻訳本は時折読みにくいこともありますが本書は文章が読みやすかったです。
1投稿日: 2020.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に示唆に富み、考えさせられることばかり。スマホをどのように使うか、描写されてるシーンはまさに私の使い方そのもの。グサグサきました。ブクログさんのこの感想もスマホで書いてるし、今やテレビよりも動画サイトを楽しんでいるので、スマホにお世話になりっぱなしの毎日。でも、スマホを使っても使われるようにはなりたくない。ましてや思考力、集中力を奪われるなんて言語道断なので、本書のアドバイスを胸に刻み使い方を見直します。もともと電話だったんだから!戒めの言葉を抜き出してノートにメモして、いつも目にとまるようにしました!
0投稿日: 2020.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログヒトの進化の速度とテクノロジー発展の速度のギャップが大きなストレスを脳に与えている。集中力はなくなり、創造性も欠如してくる。もう、便利すぎて手放せないだろう。そして、人間らしさを失ってくる。アナログの大事さ、運動の大事さを知った。
1投稿日: 2020.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ樺澤先生推薦 読んでおいたほうが良い本 ・うつを引き起こすリスクに影響する遺伝子の2つの役割 ①免疫機能をきちんと作動させること ②怪我や病気、感染症から距離を置くこと ・不確かな未来への期待の過程が ドーパミンを放出させ依存症になる ・スマホは集中力を阻害させる ☆夜遅くスマホを使うと、 食欲が増進する可能性がある。 ブルーライトの影響を受けるのは、 睡眠を促すメラトニンだけではない。 ストレスホルモンのコルチゾールと空腹ホルモンのグレリンの量を増やす。 つまりブルーライトは、 身体を目覚めさせ(メラトニンとコルチゾール) 行動に出る態勢を整え(コルチゾール) エネルギーの貯蔵庫を満タンにして脂肪を蓄える(グリーン) に長けている。 ・自分のことを話すとき、脳は活性化する なぜなら、自分のことを話すと報酬がもらえるから 報酬とは、 周りの人との絆を強め、他者と協力して何かを得られる可能性を高めるため ・共感的配慮と対人関係における感受性が デジタルライフで失われる可能性が高い ・頭の奥にある前頭葉は衝撃に歯止めをかけ、 報酬を先延ばしにすることができるが、 成熟するのが1番遅い。 25から30歳なるまで完全に発達はしない。 一方で、衝動的になる脳の部分は10代の頃は大変活発 ・紙とスマホを使って小説を読んだ場合、 紙の方がよく内容を理解していた ・アルコールは禁止するのにスマホは禁止しない ・スマホを使ってない子供の方が、 よく寝るし、運動している ・スクリーンに向かっている時間が 1日2時間を超える人はうつリスクが高まる ・運動すると成績は良くなる、集中力が増す、 ストレス解消になる 理由は、祖先がよく体を動かしていたから。 ・週に2時間(45分を3回) 運動でOK ・SNSを社交生活をさらに引き立てる手段、友人や知人と連絡を保つための手段として利用する人は良い影響 対して社交生活の代わりにSNSを利用する人たちは精神状態を悪くする (鬱症状になる) ・デジダルライフが精神状態を悪化させる ・睡眠を優先し、体をよく動かし、社会的な関係を作り、適度なストレスに自分をさらし、 スマホの使用を制限することが 心の不調の予防につながる
1投稿日: 2020.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
テレビはどこでも持っていけないが、スマホはどこでも持っていけるという箇所が非常に心に残った。 自分が小中高校生の頃、スマホはなかった。だからと言って、勉強に集中できていたかと言うと怪しいけれど、親 や友達に返信をしなくてはならないとか、そういったストレスはなかったように思う。絶えず情報に晒されて、レスをしなくてはならない世界は窮屈だなと思った。 今、道を歩いていると、殆どの人がスマホをみている。(小さい子供よりも!)子供も成長し大きくなれば、きっと同じように親とも話をせずスマホに夢中になると思うとゾッとした。よって、生活を改めることにした。 定期的に読み返したい本・・・
9投稿日: 2020.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕らの脳は、スマホにハッキングされている。 僕らがスマホを支配するのではなく、スマホが僕らを支配している。 原始の時代から変わらない人間の本能や性質に巧みに働きかけるように作られたスマホは、開発側の幹部の人間が罪悪感や後悔を抱くほど。 まずは自分自身が使い方をコントロールすること、そして将来自分の子どもができたときには、どのように使わせるか慎重に検討することが、絶対に必要だと思わされた。
6投稿日: 2020.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホに関して警鐘を鳴らしている本は色々あるけれど、その中でもとても分かりやすくまとめられていた。 脳の報酬系という人間の構造上から理解していくアプローチ。 機械に支配されないように自戒を込めて。 とても興味深い示唆に富んだ一冊だった。
4投稿日: 2020.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
<目次> まえがき~コロナに寄せて 第1章 人類はスマホなしに歴史を作ってきた 第2章 ストレス、恐怖、うつには役目がある 第3章 スマホは私たちの最新のドラッグである 第4章 集中力こそ現代社会の貴重品 第5章 スクリーンがメンタルヘルスや睡眠に与える影響 第6章 SNS~現代最強の「インフルエンサー」 第7章 バカになっていく子供たち 第8章 運動というスマートな対抗策 第9章 脳はスマホに適応するのか? 第10章 おわりに デジタル時代のアドバイス <内容> スウェーデンの精神科医のスマホへの警告書。第1,2章では、脳科学の成果が盛り込まれ、スマホが脳にどう反応し、我々の生活のどこを蝕むかが綴られていく。つまり、スマホがドーパミンを過剰に出させ、ストレスシステムのスイッチを入れ、運動を奪っていく。対応策は、スマホをできるだけ使わずに(出来たら完全にデジタルデトックスを)、軽運動を続けていくしかない。小中学生はスマホと無縁に生活させる方がよい、ということ。わが校の研修で、日本だけがデジタルライフがスマホで始まっていることを紹介していたが、スウェーデンよりも実際は日本の方がもっとひどいのかもしれない。
6投稿日: 2020.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ストレスを感じるにも理由があって、それは私達の祖先がそうやって警報を出すことて生き延びてきたから。私たちの脳は、人間の歴史から見たらごく僅かな期間で起きた情報化社会に適応していない、という考え方になるほどと考えさせられた。 人間はもはや地球上で万能かのような錯覚に陥るけど、所詮他の動物と同様環境にゆっくり適応してきただけ。この先のヒトがどういう進化を遂げていくのか興味深く思いながら読めた。 とりあえず子供にはまだ暫くスマホは与えない。
4投稿日: 2020.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
アンデシュ・ハンセン 「スマホ脳」 [著者のプロフィール] アンデシュハンセンは、スウェーデン生まれの精神科医。名門カロリンスカ医科大学で医学を学び、ストックホルム商科大学でMBAを取得。他の作品には「一流の頭脳」がある。 [概要] 第1章 人類はスマホなしで歴史を作ってきた 人類は長い歴史の中で環境に適応するために進化してきたが、ここ数百年の環境の変化に適応するための進化はしていない。つまり、人類は現在の社会的環境に追いついていない。 第2章 ストレス、恐怖、うつには役目がある 人間にはHPA系というシステムがある。これは、ストレスを感じると「闘争か逃走か」という合図をくれる役割をしている。ただこれは、短期的なストレスを感じる昔の人間に対応したシステムであり、現代の長期的なストレスを抱えやすい人間には対応していない。つまり、ストレスを感じたとき「闘争か逃走か」という選択を迫られ、それ以外のことを放棄してしまう。これが鬱などの原因になる。 第3章 スマホは私たちの最新のドラッグである ドーパミンは報酬物質と呼ばれる。このドーパミンはスマホを使用している時より、通知や着信音聞こえた時に大量に放出される。通知や着信音が聞こえた時、私たちは「期待」している。SNSに「いいね」や「ハート」がついていないか、という期待である。つまり、この「期待」が報酬システムを作動させ、ドーパミンを放出するきっかけなのである。 第4章 集中力こそ現代社会の貴重品 私たちは1つの物事にしか集中できない。マルチタスクはただ、1つのことに対する集中を瞬時に切り替えて2つのことをしているにすぎない。そして、脳には切り替え時間が必要であり、再度集中するには数分を要する。そのため、マルチタスクは集中力を低下させる。また、何かに集中することにエネルギーが必要なように、何かを無視するというのもエネルギーが必要である。だから、スマホが見える範囲で何か作業をすれば、スマホを無視するエネルギーと作業に集中するエネルギーが必要となり、これもマルチタスクと同じで集中力を低下させることとなる。 第5章 スクリーンがメンタルヘルスや睡眠に与える影響 スマホの使用とストレス・不安には相関性があり、スマホの使用量が多い人ほどストレスや不安を感じやすい。 眠りにつく時間を知らせてくれるメラトニンというホルモンの働きがある。メラトニンは夜に分泌量が多くなるが、光を浴びすぎるとメラトニンは分泌を中断する。そして、ブルーライトにはメラトニンの分泌を抑える効果がある。だから、夜遅くにスマホを使うと眠りが妨げられ、また睡眠の質も悪くなる。 第6章 SNSー現代最強の「インフルエンサー」 脳内にはドーパミンのように私たちの気分に影響を与える伝達物質、セロトニンがある。これはこれまで、心の平安、バランス、精神力に関わるとされてきた。しかし、これだけでなく集団の中の地位にも影響するのだ。例えば、ある集団のヒエラルキーの上層に位置するものは下層に位置するものよりセロトニンの分泌量が多い。これは自分に自信があるといえる。ただ、もしその地位を失うとセロトニンの量は減る。それに加えて、鬱状態になる可能性もあるのだ。 第7章 バカになっていく子供たち 前頭葉は衝動に歯止めをかけ、報酬を先延ばしにできる機能がある。つまり、自制の役割を持つ。ただ、前頭葉は25〜30歳になるまでは完全には発達しない。 自制心は将来性にも関わってくる。それは生活の影響を受けるし、訓練で伸ばすこともできる。ただ、現代の若者はスマホの使用により自制する力が欠けていることは研究でわかっている。 第8章 運動というスマートな対抗策 運動はストレスや不安に対抗するための最適な手段である。また、運動をすると、集中力や記憶力の向上につながる。これらは、多くの研究から明らかになっている。運動自体の種類は問わずにこれらの効果が期待できる。また少しの運動でも効果はでる。ただ、1番いいのは、6ヶ月間に最低52時間身体を動かすことだ。つまり、週に2時間である。また、心拍数は上げないより上げたほうがいい。 第9章 脳はスマホに適応するのか 私たちは長い歴史の中で進化してきた。だから、これまでのように進化することで脳がスマホに適応するのではないかと考えられる。ただ、進化の基本は生存や繁殖にメリットになる特質が一般的になることである。だから、スマホが生存や繁殖に必要になるとは考えられないため、脳がスマホに適応することはないのではないのか。 第10章 おわりに デジタル自体のアドバイス ・自分のスマホ利用時間を知ろう ・毎日1〜2時間、スマホをおうに ・スマホを寝室に置かない ・どんな運動も脳に良い [感想] 現代ではスマホは人々にとって欠かせないものとなっている。インターネットやSNSなど他社と簡単に繋がる手段である。その反面、スマホは悪影響を私たちに及ぼす。不安や鬱病の原因になったり、ストレス負担にもなる。スマホの利用者のほとんどがこれを知らずに使用している。どんなに恐ろしい時代か。本書ではスマホと不安、鬱病、ストレスとの関係について詳しく解説している。また、それに対する対処法も書かれている。これからのデジタル時代を生き抜く上で必須の知識といえる。ぜひ年代問わず読んで見てほしい。
0投稿日: 2020.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホ脳(新潮新書) 著作者:アンデシュ・ハンセン 発行者:新潮社 タイムライン http://booklog.jp/timeline/users/collabo39698 教育大国スウェーデンを震撼させ、社会元賞となった世界的ベストセラーがついに日本上陸。
1投稿日: 2020.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタル時代に警鐘を鳴らす一作 今や当然のように側にあるスマホが、どれだけ異質で、どれだけ世に影響を及ぼしているのか、気付かされる 膨大な調査、研究の引用を大いに活用していて、具体的な数字も多く、説得力が高い 「こうしよう」という啓発もあるが、それよりは、その論拠や裏付けの語り色が強い
0投稿日: 2020.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホの危険性を知るにはベストな一冊。 TVや新聞などのマスメディアでは、よくスマホ依存症の危険さが報道される。 が、なぜスマホが危険なのかというところまできちんと理解している大人は、きっと少ないのではないだろうか。 本書は、人間の脳の仕組みとスマホが与える影響について丁寧に教えてくれる。「スマホ依存」だけでなく「脳科学の知識」まで手に入るというおまけ付きの一冊になっている。 内容をざっくりいうと、ボクらの脳は一万年前の太古の昔から変わっていない。ここに現代人を蝕む様々な問題の原因がある。肥満、うつ病、睡眠障害、依存症、パーソナリティ障害など、数え上げればきりがない。 本書を読めば、あなたも確実に変わろうと思うはずだ。 それはスマホとの付き合い方だけでなく、自身の脳との付き合い方、ひいては周囲の人との付き合い方にまで及ぶ。 本書を読むことで人間性を取り戻すきっかけにもなり得るように思う。 このまま何も学ばなければ、スマホに僕らはコントロールされる。いや、もうすでにスマホにボクらの脳は乗っ取られている。 本書は、スマホとのいい間合いを掴むための必読の書。過渡期にあるこの時代にこそ読むべき一冊だと思う。オススメ。
14投稿日: 2020.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログSNSで他人と比較することにより幸福度が下がるという話が印象的でした。 スマホの使い方を考えるきっかけになる本です。 ・睡眠を最優先する ・人とコミュニケーションを取る ・スマホを触る時間を短くする (SNSではなく連絡を取るツールとして利用する) ・よく運動する これらを意識して生きていきたいです。
4投稿日: 2020.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学がどれだけ進歩しようと、脳は進化してない。 たしかに1日の3分の1以上スマホを使っている今の状況は異常だね。
1投稿日: 2020.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ、ビルゲイツやスティーブ・ジョブズやTwitter CEOが自分の子どもには、スマホ・SNSを触らせないか。 ・スマホの電源を切る ・よく寝る ・よく運動する ・ストレスを溜めない クオリティオブライフがなにかと向き合う必要を感じる。
0投稿日: 2020.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
始めから面白い、どんどん引き込まれる。 日常には欠かせない存在となったスマホやiPadが、特に子供や若者にどういった影響を与えるかという問いを真っ向から捉え、数々の研究結果を照らし合わせた上で、私たちに明確な答えを与えてくれる。 便利ではあるが、こんなふうに使っていて長期的な悪影響はないのだろうか。かといって今の時代、子供にスマホをもたせないわけにはいかない。わからないままITの革新に流されているのが現状だ。 言いっぱなしにしないでデジタル時代のアドバイスを最後に述べている。 特に良かった点を一部要約して抜粋する。 自分のスマホ利用時間を知ろう 1日に何度スマホを手に取り、どのくらい時間をかけているのかを把握するために、 スマホに奪われている時間が一目瞭然だ。 自分を知ることが、変化への第一歩になる。 目覚まし時計と腕時計を買おう スマホでなくてもいい機能は、スマホを使わないようにしよう。 運転中はサイレントモードに 危険な瞬間に気が散るリスクが減る。悪いタイミングでお知らせや通話が来ると、いちばん必要なときに集中が妨げられる可能性がある。それに応答しなかったとしても、だ。 職場で集中力が必要な作業をするときはスマホを手元に置かず、ロッカーにでもしまっておこう チャットやメールをチェックする時間を決めよう 例えば1時間ごとに数分など。 人と会っているときはスマホをマナーモードにして少し遠ざけておき、一緒にいる相手に集中しよう あなたがスマホを取り出せば、周りにも伝染する 子供と若者へのアドバイス 教室でスマホは禁止! 学習能力が低下する スクリーンに費やしていいのは最長で2時間 8歳未満の子供なら1時間が限度 宿題をする、運動をする、友達に会うなど、それに集中する時間を決めよう。 よい手本になろう 私たちは相手を真似ることで学ぶ。 子供は大人がしているようにする。 寝る直前 仕事のメールを開かない ストレスの対処法 どんな運動も脳に良い 中でもいちばんいいのは心拍数を上げる運動
9投稿日: 2020.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ大切な考え方。寝る、運動する、リアルに時間を使う。早速実践してみようと思う。なぜ、この行動は人間の心理や身体に悪影響なのか、もともとの人間の体の作りからに関する考察から説明していてわかりやすい。 現代人にとって貴重なのは集中力!
6投稿日: 2020.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログどれくらいスマホを触らないでいられるだろうか。 現代人は、スマホの存在が気になって、集中することができなくなっている。筋トレと同じように、脳をデジタルに慣れさせることはできないのである。 スウェーデンの精神科医である著者は、ここ10年でうつ病、不眠症に悩む人が増えたと言っている。 たしかに、デジタル機器のメリットはたくさんあるので、時間を制限したり、運動したりするなど、上手く付き合うことがこれからは必要になってくる。 また、私たちが不安を感じたり、悪い噂を気にしたりするのは、狩猟採集民の脳を持っているからである。未だに、危険を探知しようとして、ストレスを感じ、気が散り、複数の作業をするのが苦手なのである。
4投稿日: 2020.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログあまり文章が多くないのですぐ読み終わる。 しかしスマホがどんな影響を脳に与えるのかがわかる。この本自体は数年前に書かれた物の訳なので研究が少し昔のものだと思うのでほんとに最新の研究が知りたかったら日本人が書いた本を読むと尚いいと思う。
0投稿日: 2020.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分の長期的にやりたい事をサポートするには スマホやアプリはとてもいいツールである だが 扱い方誤れば短期的な快楽を与え依存させるものでしかない。 今スマホで、行っている事は 自分の人生の中で本当にやりたい事の道の途中なのかと 考えさせられる本だった。
0投稿日: 2020.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の行動には全て理由がある。脳の動きにも理由がある。妙に納得がいく本であった。この本の内容をもとにしてこれから行動すると良い生活が送ることができるのではないかと思う。これからの時代の必読書ではないかと思う。
1投稿日: 2020.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログここ最近で1番興味をそそられる内容だった。スマホの与える影響は、まさに諸刃の剣であり、最高の魔法を使える道具か、それまた無意識のままに支配される動物となるかは、自分次第だと感じさせる。とりあえず、運動しよう、これが収穫でもある笑
4投稿日: 2020.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホに依存しすぎるのは、あまり脳や身体によろしくないのはなんとなくは分かっているがやめられない「スマホ依存症」について解説された一冊(著者はアンデシュ・ハンセン)。故スティーブ・ジョブズがわが子にiPadを触らせなかったのは有名な話。それもそもはず、「スマホ依存」は人の集中力や記憶力を削ぐからであり、本書では「スマホ依存症」の実例を大量に用意。スマホに依存することの危険性について警鐘しつつ、スマホによって失われた集中力を取り戻すための手法も紹介される。
1投稿日: 2020.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログスティーブ・ジョブスは我が子に、iPadは使わせなかったらしい。なぜか?おそらく、子供の育成上よろしくないと考えていたからで、その判断が正しいことが本書を読むとわかる。 SNSを利用することで、鬱になる傾向がある。他者との比較は喜びを奪うから。 スマホ利用時間を制限し、適度な運動をすることで集中力は向上し、良質な睡眠を取ることができる。私達は、急激なデジタル化に進化が追いついていないのか?はたまた、自ら退化の道を歩んでいるのか? 使われているのは、便利なテクノロジーの産物の方ではなく、私達自身のほうかもしれないということに気づかせてくれる一冊でした。
15投稿日: 2020.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホを触ることで快感を得つづけようとし、私達の時間がどんどん奪われていく 「モモ」とは別の、もっと身近に”受け入れている”泥棒についての話でした。 読んだ理由:「FULL POWER」を読んでSNSのアプリを消したのに、別のアカウントで、またSNSを始めて読書仲間を増やしている, 。 「SNSを利用することが読書時間を妨害している」ってことに、薄々気づいていながら黙認してきたけども、やはりスマホがそばにあるだけで集中力が途切れる。 (あるだけで!) それを何とかしたいと思い、試し読みやレビューを読んだところ「スマホやSNSを開発した人物たちは、自分の子供には与えていない」という内容に衝撃を受け、読み始める。 まず初めに私たちの祖先が、過酷な状況に生きてきたなかで ・ 食欲についての進化(カロリーを摂取することで、食糧が確保できないときの飢餓状態を乗り切る) ・ストレスに対する進化(うつになる事でストレスからの回避をする)をする必要があったことについて触れる。 そして時代が変わっても、その時の防御反応「より多く栄養をとっておかねば」「危険なものを察知して回避せねば」と反応した結果、栄養をとりすぎて肥満になるなど現代でも同様の反応をして行き過ぎた状態になってしまうことを説明している。 「時代と進化が合っていない、ではスマートフォンと言う進化にはどうか?」 スマートフォンの様々なアプリに仕掛けられた「快感」を生む仕組みについての説明、他の人からの「いいね」(報酬)やWeb上の変化を知ろうとする欲求への“じらし”について、夜間にブルーライトを見る事の睡眠への影響、電子書籍で読むことについても触れられている。 電子版で読んだのは間違いだったのか…中身が入ってこない様な感覚になる。 毎回ほかの本でも、やけにスラスラ読みすぎてる様な感覚にはなってたけど、うーん。と、このあたりで紙の本を買う。(今後、何度も読む様な気がしたので…) SNSを利用し、他の人がおすすめしている本を読むのも楽しいのだが、だんだん自分が欲しいものを買っているかすら、SNSの影響なのかわからなくなり選択が出来なくなる。 この本に書いてある事を理解し意識したのであれば、適度にスマホを利用できる! と言い切れない人間なので、少しSNSを開かない様に再チャレンジしよう! スマホの目覚ましアラーム機能を使っているのだが、枕元にスマホを置かないために、目覚まし時計は買わなきゃと思っていたところダメ押しが…これは買おう。 自分の今の状況にドンピシャ過ぎて、落ち込むくらい内容が突き刺さってきました。 唯一の救いは「運動」がストレス解消になるという研究結果だけ… ウォーキングを1年以上続けていることぐらいか… 結局、スマホを使うことは悪なのか? と言うと、そうではないが、今は(特に体に対する影響が未知の部分が多い状態で発売されたことで)全人類で実験中なのにひたすら毎日長時間触り続けるのはどうなの?と言う問題提議の本でした。 リビングにこの本を置いておくだけでも、スクリーンタイム削減に 効果があるかも(※個人の感想です。)
62投稿日: 2020.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間のメカニズムとしてスマホに追いつけず、振り回されている。かと言って、「生存」に対してスマホは害はないので人間がスマホに適応することはないだろう。思考するのに知識が必要である以上、人間の「能力」や集中力には害である。若者のアルコールに対して規制があるのなら、若者のスマホにこそ規制をするべきという論はかなりの説得力を持つ。教育とスマホとのあり方を見直さなくてはならない。
1投稿日: 2020.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ職場でみんなに勧めた。40代以上には概ね好評。若い人には受け入れ難いことが多いらしい。30歳くらいにならないと前頭葉が育ち切らない、という本書の内容の通りでした。怖っ!
3投稿日: 2020.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ漠然とスマホが脳に悪いことは誰しも思っていると思いますが、それをちゃんと言語化した内容となります。必ず知っておいた方がいいないようかとおもいます。
0投稿日: 2020.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホがどれだけ人間の生活に影響を与えているか。 もちろん便利になっているが、その分人間が本来できたり、考えたりできることが少なくなってきている。 正直自分も何気なくスマホを手にして触ってしまっていることが多いから、意識的に変えてみてスマホを触る時間を他のことに使いたいと思った。 と言いながらもスマホでブクログを書く(笑)
2投稿日: 2020.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホのさまざまなサービスはは脳の報酬快楽に呼びかける仕組みとなっている。スマホを身近に置いておくだけで、脳の意識はスマホへといってしまい集中力が低下する。 スマホでsns を活用している人ほど、うつ病患者が多い。SNSで常にスマホを見ていると報酬快楽により脳への負担が大きい。そして人間の脳は脳や身体を休ませようと働き、うつ病になる。 少なくとも寝る前にはスマホを見る時間を減らそうと思う。
16投稿日: 2020.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は、ガラケーからスマホに換えたのが、大変遅く、まだ換えて3か月ほどです。 パソコンは1999年から使っていましたが、スマホの音声入力や、カメラ、マップ、LINEその他の機能を知るうちになんて便利なものだろうかと思いました。 そしてまだ2カ月ではありますが、友達に誘われてFacebookまで始めてしまいました。 そこで、この本の出版を知り早速読んでみました。 昨今のコロナ危機でスマホが外界とのライフラインになった今読むべき本であるとまえがきにありました。 内容を読むと、スティーブ・ジョブズの10代の子どもはipadを使ってよい時間を厳しく制限されていた。 ビル・ゲイツの子どもたちはスマホを持たない2%に属していた。 などのスマホに対してかなり否定的なことが書かれています。 私は、スマホでFacebookを(まだほんの多少ですが)使い出したのでSNSとの関係のところを興味深く読みましたが、使い方次第で、SNS以外の所でもしっかり支えられている人々は社会生活をさらに引き立てる手段となり、そうした人たちの多くは良い影響を受け、社会生活の代わりにSNSを利用する人たちは精神状態を悪くするということでした。 今は、コロナ禍で、社会生活が尋常の状態と違うのでどうかと思いましたが、使い方を間違えなければ大丈夫だと思いました。 また、今の中学生は毎日7時間スマホを見ているなどという言及もありましたが、本当かと思いました。 スマホ依存から精神障害へと移行しないためには週に二時間程の適度な運動と、7時間から9時間の睡眠をとっていればよいということもわかりました。 Facebookやブクログをやっているからといって、自分はスマホ依存ではないと思います。 10分に1回スマホをチェックしたり、就寝時にスマホを隣に置くことはしません。 これからも、適度に上手く、いいところを活用していけたらと思いました。
85投稿日: 2020.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ【本書の概要】 人間がスマホ、特にSNSの中毒になるのは、狩猟採集時代の脳が現代社会に適応できていないからである。外敵から身を守るための感情的な反応――マイナスの感情を強く感じる、新しい情報を欲しがるといった反応――が、現代社会においてはデジタルコンテンツへの依存症をもたらすのだ。スマホ依存症によって学力や集中力が低下し、うつ病患者が増加している。スマホは長くても一日2時間までとし、週に45分×3回の運動をして病気を予防することが大切である。 【詳細】 ①人間の脳は狩猟採集時代のままである 人間が誕生してから20万年の月日が流れたものの、現代のような高速の生活様式になったのはせいぜいここ数百年の間である。人間の進化はそのスピードに追い付いておらず、脳は狩猟採集時代のまま変化していない。 狩猟採集時代においては、感情は生存のための戦略であった。目の前に迫る危険に対して敵意を抱いたり恐怖を抱いたりすることが、我々の生存率を大きく左右していた。そのために、人間はプラスの感情よりもマイナスの感情(ストレス)を強く抱くようになっている。マイナスの感情の役割はもっぱら緊急避難(闘争と逃走)のためであった。 しかし、現代においては、命を脅かす瞬間的なストレスこそないものの、緩慢的なストレスが長期に渡って続く。しかし、こうした長期のストレスに人間の脳は対応できていない。長期のストレス下でも身体は闘争と逃走を優先するので、自分を取り巻く環境内での些細なエラーにも激しく反応してしまう。 また、短期的なストレスは、緊急避難以外の身体の機能(食べ物の消化や睡眠)を蔑ろにする。死を目前では生き延びることが最重要だからだ。これが現代社会の長期ストレス下において作用し続けると、精神状態や身体の調子を悪化させてしまう。 ストレスは、今起きていることだけでなく、「起きるかもしれないこと」を考えてもスイッチが入る。これが「不安」だ。不安も危険への予備動作であり、人間を死から守ってくれるシステムとして作用し、生存率を高めてきてくれていたものの、不安に晒され続けると、脳が「ここから逃げろ!」という指令を出して体を守ろうとする。これが「うつ」の正体だ。 ②なぜスマホは人間から集中力を奪うのか われわれが「〇〇したい!」という欲求はドーパミンの分泌によって引き起こされる。同時に、ドーパミンは何が重要で何に集中すべきかを伝える役割も持つ。ドーパミンはさまざまな状況で放出されるが、「新しい情報を得る」ときに多く分泌される。周囲の環境に対する情報を得ることで、生存の可能性が高まるからだ。ここでも狩猟採集時代の痕跡が見られる。 中でもドーパミンが一番分泌されるのは、報酬が貰える「かもしれない」瞬間である。ギャンブル依存症のように、報酬がゲットできる可能性を見せられれば人はいつまでも欲しがり続ける。 そして、同様のことがスマホのスクリーンでも発生するのだ。クリックやタップでネットの新しい情報を得る時、フェイスブックでいいねを告げる「通知」が流れてくるとき、人間は報酬を期待し、ドーパミンという麻薬が分泌される。 そしてこの麻薬が、我々から集中力を奪っている。 人間の脳はもともと、一つのことにしか集中できないようになっている。2つのタスクを行ったり来たりしていると、効率がどんどん落ちていくが、これはタスクを切り替えても、脳は異なる作業への「切り替え時間」が必要であり、エンジンを切ったり温めたりし続けてどんどん効率が落ちていくからだ。 この低下現象は、なんと自分の目の前にスマホが置いてあるだけでも発生する。スマホの存在自体が作業の気を散らし、集中力を低下させ、記憶の定着を阻害する。 ③子どもへの悪影響 子どもは大人よりもスマホ依存に陥りやすい。その理由は、前頭葉にある「衝動を抑制するシステム」が完全に発達するのが25歳以降だからだ。 子どもとスマホの関わりにおいてプラスの影響をもたらすものとして、タブレット学習が挙げられることがある。だが、タブレット学習は紙とペンより効率が悪いという研究結果もある。例えば、子どもは数字の勉強をするとき、指を折る、字を書くというふうに身体運動と記憶を一体にして学習している。それがiPad上では失われる危険性があるのだ。 恐ろしいことに、既に子どもへの悪影響が確認されている。2011年――iPhoneが本格的に普及し始めた年――に、米国の若者のうつ病が増え、眠りが悪くなった。米国だけでなく、全体的に今のティーンは昔ほど宿題に時間を使っておらず、運動時間も減っている。 ④スマホ中毒から身を守るために スマホ中毒から身を守る方法は、スマホを意図的に遠ざけることと、運動をすることである。 スマホのスクリーンは、仕事や勉強以外では一日2時間までにする。特に寝る前にスマホを遠ざけ、ブルーライトを浴びないようにする。これにより睡眠の質が改善し、日中の集中力が上がる。 また、脳において一番大切なのは運動だ。全ての知的能力は運動によって向上する。運動とは身体のコンディションを上げることであり、コンディションが上がればストレス源に対処することが容易になる。何故ならば、脅威かもしれない対象を攻撃したり、逃げ出したりする体力がつくことで、ストレスシステムを事前に作動させる必要がなくなり不安の軽減につながるからだ。 運動の目安としては、6ヶ月で52時間、つまり週に2時間であり、より細かくすれば45分を3回である。あらゆる種類の運動が知能によい効果を与えてくれる。脳にとっては運動できれば何でも構わないが、できれば心拍数が上がる少しきつい運動が望ましい。 【感想】 スマホ依存という現代病を人間の本能の観点から探る本である。 筆者が提唱しているのは、スマホを捨てて石器時代のような生活に戻るべきだということではない。むしろテクノロジーの恩恵を認めつつ、「テクノロジーのほうが私たちに対応するべきであって、その逆ではないはずだ」と述べている。そう言わざるを得ないほどまでに、スマホが人間の欲求を煽ることで発展を続けてきた証拠と言えるだろう。 社会はかつてないほど平和になったのに、われわれ自身は未だに強く不安を感じている。飢餓に陥るかもしれない不安からカロリーを摂りすぎる、迫害されるかもしれないという不安からLINEに張り付く。本能と現代社会との折り合いをつけるためにも、デジタル機器との関係を見つめ直す――酒やタバコのように、年齢制限を付けたり、課税したり、害を強調する――ことが、この先起こり得るかもしれないと感じた。
1投稿日: 2020.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートフォンの人間に与える影響について、様々な研究を引用しながら論じた本。人間の脳はスマートフォンのない世界で進化してきたが、ここ十数年のスマートフォンの普及は今までのどの生活様式の変化よりも急激だった。人間の脳はまだスマートフォンに適応できていない。 まだまだ終わりそうにないコロナの拡大の中で、授業も飲み会もオンラインになっている。家から出られない生活でテクノロジーへの依存は深まっている。テクノロジーとの生活をどう捉えればいいのかのヒントとなる本だろう。
0投稿日: 2020.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく面白かった! 今読むべき本だったー。 今年に入ってずっとスマホ依存気味なのが気になっていたけど、この本を読んで、「デジタルデトックス」しよう。って決定的になった。
1投稿日: 2020.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スマホやSNSの使用で、大人や子供の精神状態や認知機能、そして脳にどのような変化が生じているか、研究成果を踏まえながら議論した本です。スマホに焦点を絞った本を読むのは初めてで、興味深く読みました。集中力を欠くなど、取り上げられている症状は思い当たる節があるものばかりで、自分も大きく影響を受けているんだなと再確認した。スマホがないとイライラしたり、不安になったり、またスマホ頼りで人の脳機能が衰えているなど、どのように付き合っていくべきか考えさせられました。参考文献が載っていないので、裏がとりにくいのは、新書ではやむを得ないのかな?
0投稿日: 2020.11.22
