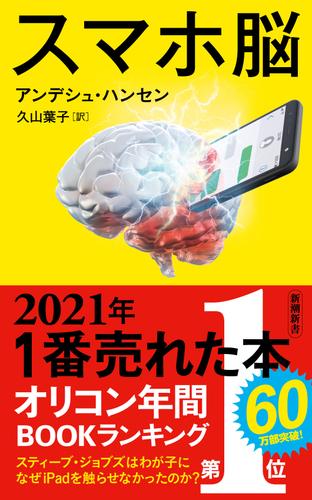
総合評価
(1515件)| 593 | ||
| 582 | ||
| 223 | ||
| 23 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホの使用という最近では当たり前になっていることに対して人間の古代からの本能などを交えてわかりやすく書かれているためとても読みやすい作品
0投稿日: 2026.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホのデメリットを記憶力や集中力、ストレス、睡眠など様々な観点から述べている。 デジダルデトックスの重要性がわかった。 色々な実験の研究結果から意見を述べていたり、説明はあるが専門用語を使用していたりして、想像していたより難しい内容だった。
1投稿日: 2026.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年まだ4日目だから今年の目標は「スマホ触り過ぎない」で。 (たぶん無理) 今読んでいるページ(画面という意味で)よりも次のページに夢中になっている、という表現が面白かった。 次のページで、どんな本を購入した、読んだという投稿を期待してスワイプしているのは言うまでもない。 #読了
0投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホの普及は人類に利便性や他者との繋がりなどを提供してくれる。しかしながら、人類の脳は狩猟採集をしていた原始時代の生活に適応するように発達しており、「期待」を与えてくれるスマホはドーパミン供給装置とも言える。スマホがもたらす心理的な影響を多数の研究結果を用いて説明しており、今後の向き合い方を見つめ直すきっかけとなった。
0投稿日: 2026.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んで、自分のスマホや他人のスマホに対して嫌悪感を持つようになった。スマホを使い過ぎているので、制限し続けていきたい。家族に読ませたい。
0投稿日: 2026.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ人々は「スマホを使う」と言うが、果たして本当にそうか?「スマホに使われて」いないか?電車に乗ってまわりを見渡せば、下を向きスマホを見つめている人ばかり。大の大人が寝ても覚めても鉄の板を一生懸命見つめている。大人ですらこんな状況で、だれがスマホ中毒になった子どもを責めることができよう。中毒というものは自らの意思でどうにもできないから中毒なのであり、一度も触れないに越したことはない。ジョブズですら11歳になるまで自分の子どもにiPhoneを持たせなかったというのだから納得である。刹那的な快楽に溺れスマホに操作されている人間を見ると、ハリガネムシに寄生されたカマキリを思い出す。カマキリの意思とは関係なく、ハリガネムシの利益のためだけに水辺に向かわされ、そのまま水に溺れて死んでしまう。人間は選択することができる、スマホに誘われ情報の海に溺れさせられるのか、自分と向き合うのか。この本を読むまでは自分もスマホ中毒でありました。一般的に言われているいくつもの方策を駆使して改善を試みても結局は解決しなかった中毒が、科学的な理論で知ることができると大いに改善され、今では以前のスマホ時間が映画鑑賞や読書や勉強に置き換えられ、豊かな時間を過ごせています。必ずまた再読します。オススメです。
0投稿日: 2025.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ○主題 『脳は原始時代のままで、デジタル社会に対応できていないということを意識して生活していく必要がある。』 ○対処法 『睡眠を優先し、体をよく動かし、社会的な関係を作り、適度なストレスに自分をさらし、スマホの使用を制限すること』 ○1章:人類はスマホなしで歴史を作ってきた ・人類が生まれてから20万年だがコンピューターが生まれたのが60年前、スマホやインターネットが当たり前、SNSができたのが20年前とめちゃくちゃ最近 ・環境に適応しているわけではなく、適応できているタイプが生き残る。能動的に変わっているわけではないので時間がかかる(しろくまやきりん)。それができるほどの時間は立っていない。 ・昔は高カロリーのものが貴重だったため、現代でも高カロリーのものに惹かれる。 ・感情は生存戦略。判断を下すときの材料になる。感情により決断させられる。ネガティブよりポジティブの感情が勝る。 ・負の感情の方が気になるのは、生存に関係することが多かったから。 →負の感情の根源はストレス。 →ストレスについては次章。 ○2章:ストレス、恐怖、うつには役目がある ・脳にはHPA系というシステムがある。 (視床下部→下垂体→副腎) ・HPA系は簡単にいうとコルチゾールを分泌するシステム。 脊椎動物であれば基本持っている。 緊急性の高い脅威に遭遇したときのために発達した。 ・コルチゾール:ストレスホルモン。これにより心臓の動きを速くする。 Q.なぜ速くするのか? A.速く反応して、攻撃するか or 逃走するか選択しないといけないから。 心臓が速くなる→血液量UP→筋肉への血液量UP→素早く動く →『闘争か逃走か』という状態。 ・昔のストレスはライオンなどの天敵からの脅威だけだからその名残。 ・ずっとストレスにさらされると『闘争か逃走か』という状態にずっとなる。 →原始的な選択しかできなく、心の余裕がなくなる。細かいことが気になるようになる。 ・しかし、適度なストレスは必要。ないと無気力になる。 ・『火災報知器の原則』:扁桃体の作用の仕方(HPA系にどう指示を出すか)。鳴らないよりも、多く鳴って間違う方がいい。(例:ホースを見て蛇と見間違うとき) ・扁桃体のスイッチは基本ONになっている。 →昔は良かったけど、今はあらゆるもの(SNSなど)に反応しすぎてしまう。 ・不安(起きるかもしれない)と恐怖(起きて怖い) →不安は人間特有のもの。未来を予測する力だから。 ・不安の時も『闘争か逃走か』が働く。 ・体の仕組みは「現実」の脅威と「想像(未来)」の脅威を区別できない →そのため、不安を抱えている人はずっとストレスシステムが働いている状態。 ・「うつ」は長期的にストレスを感じると発生する。そこらじゅうに危険があると思うので家に引き篭もるようになる。 ・体が出すサインを見逃さないことがポイント。 ・また、体は『闘争か逃走か』を一番に優先させる。セックスや食事、睡眠よりも。なぜなら、身の危険を守るためのシステムだから。 ○3章:スマホは最新のドラッグ ・ドーパミン:行動動機を与えるのがいちばんの役割。元気にするだけでなく。何に集中するかを選択させる(=人間の原動力)。 ・何かをしているときではなく、何かをしようとするときに働く。 ・何かをしているときに働くのはエンドルフィン。 ・新しいものを見るとドーパミンが放出される。 →スマホでニュースを見ると次々に読みたくなるのやショート動画の原理もこれ。 ・脳は「もしかしたら」や「期待」に強く反応する。 ・スマホに依存する仕組み ①通知で期待→②スマホ見る→③別のが気になる→④別のを見る→③④を繰り返す 「いいね」機能もいいねがついた気になるという期待を利用したもの。 ○4章:『集中力』こそ現代における資産 ・現代人の集中力を急速になくなっていっている。注意持続時間は12秒から8秒に。 ・マルチタスクの増加(例:動画見ながら家事したり) →マルチタスクはは集中力が低い。マルチタスク能力さえも低い。 →気が散ってしまう。そのため記憶力が低い。 ・2つのことを同時にしていると思っているけど実際は一つのことしかできていない。切り替えてやっているだけ。本当にできるのは人口の1〜2%だけ。女性の方ができやすい。 ・さっきやってたことに注意が残る(=注意残余)。 ・昔の名残でマルチタスクをするとドーパミンが放出されてしまい、できていると錯覚してしまう。 ・デジタル機器にメモするよりも手書きのほう頭に残る。 →デジタル機器だと入力スピードに脳が追いつかない。手書きだと脳の整理する時間が作れるから。 ・マルチタスクはワーキングメモリにも悪影響を与える。 ・長期記憶には、「集中」と「時間」が必要。次々と新しい情報を入れると記憶を「固定化」する時間が作れない。 ・Google効果(デジタル性健忘):別の場所に保存されているからと脳が自分で記憶しなくなること。 →脳は情報そのものよりも、情報がどこにあるかを優先して覚えるため、グーグルばかり使うと知識として残らない。次から次に検索すると情報を自分と結びつける時間が与えられない。ショート動画など。 ・スマホは近くにあるだけで、人間はドーパミンが出る?!期待するから。 ○5章:スクリーンがメンタルヘルスや睡眠に与える影響 ・スマホを手放しただけで「コルチゾール」増加。近年は睡眠不足も増加している。 ・睡眠は「短期」→「長期」記憶へと定着するために重要。 ・「メラトニン」分泌量が多いと眠りやすくなる。しかし、ブルーライトはメラトニン分泌を抑制する。メラトニンは、光の少ないところで分泌量が増える。スマホが寝室にあるだけでも悪影響。 ・スマホは、空腹ホルモン「グレリン」の分泌量も増加させる。 ・どうしてもスマホを寝室で見るなら、画面を暗くして目から36cm以上離す。 ・基本はスマホは寝室以外に置いて寝る。 ・また、週に3回以上は運動をすると睡眠の質UP! ○6章:SNSは現代最強の『インフルエンサー』 ・人間の会話のほとんどは「ゴシップ」。特に悪い噂が好き。 →これも昔の名残。知っておくことで自分の身の危険を守れた。昔は結構の割合で人間同士の争いで命を落としていた。関係性を知ることは生存戦略の上で重要だった。 ・人は自分のことは話したい生き物である。SNSはさらにそれを可能にさせた。昔は少人数だったけどSNSを使えば何万人以上の人に発信ができるようになった。 ・リアルで人に会う人ほど幸福度が高く、SNSばっかり使っている人は幸福度が低かった。他の人のいいところばかり見ているから。 ・「セロトニン」の量はボスやリーダー(社会的に高い地位)ほど多く分泌される。 ・SNSで特に悪い使い方は見る専門の人。投稿や積極的にSNS上で交流を行っている人はそれほど幸福度は低くない。交流のツールと思っている人にとっては。 ・スマホでの交流は共感力が身につかないため、最近は共感力が低下している。 →SNSの時間を抑制するだけでも効果がある。 ○7章:バカになっていく子供たち ・子供にはタブレット学習は向いていない。 ・報酬(ご褒美)を我慢できなくなっている。 ・紙で学習する方が勉強の成果がいい。 ・運動を勉強前にするのも効果あり。 ・睡眠の質も落ちている。 ・脳のブレーキ役である「前頭葉」は25〜30歳で完全に発達する。 ○8章:運動というスマートな対抗策 ・デジタルによる「ストレス」「集中力低下」「情報量過多」に対応できるのは運動 ・何かの作業や勉強前に運動をするだけで「集中力UP」に効果あり。 →これも昔の名残。運動するタイミング=集中力が必要なタイミング(狩りなど) ・ストレスも運動をしている人の方が低かった。 →ストレスの大半が『闘争か逃走か』に結びついている。 →運動をしてコンディションが良ければパニックにならず焦らないためストレスも低くなる。 →事前にストレスシステムを作動(=火災報知器の原則)させる必要がない。 ・最低6ヶ月に52時間(1週間に2時間)心拍数が上がれば良い。 ○9章:脳はスマホに適応するのか ・現代人のIQは下がっている。 ・使われない知識は失われる。脳にとっては「使うか捨てるか」。エネルギーを節約しようとする。スマホが代替することでその能力が失われていく。 ・スマホの使用時間は1日の3分の1や4分の1になることもあるほどで、過去にこんなものは存在しなかった。 ・スマホの台頭スピードが速いため、研究結果が追いついていない。通常研究は何年もかかる。それより速いスピードで進化している。 ・そのため、スマホなどが私たちに与える影響は未知数。スマホ依存かもと思った場合は控えた方がいいと思われる。 ・人間は元来幸せな生き物ではない。 →なぜなら、「不安」を抱えてきた子孫の方が生存してきた確率が高い。 ・幸せになるためにするべきこと →『睡眠を優先し、体をよく動かし、社会的な関係を作り、適度なストレスに自分をさらし、スマホの使用を制限すること』 ・心の不調には「予防」が大切。 ・デジタルな道具はデメリットを理解して、賢く使う必要がある。 ○10章:終わりに ・私たちは、これまで人間が適応してきた世界とはかけ離れた世界にいる。 ・そのことを理解し、配慮した上で生活を送ることが大事。 ■デジタル時代のアドバイス • 自分のスマホ利用時間を知ろう 1日に何回スマホを手に取り、どれくらい時間をかけているか自分を知ることが変化への第一歩。 • 目覚まし時計・腕時計を買おう スマホでなくてもいい機能は、スマホを使わないように。 • 毎日1〜2時間はスマホをオフに 毎日1〜2時間オフにすることを周囲の人に伝えておく。 • プッシュ通知をすべてオフにしよう • スマホの表示をモノクロに 色のない画面のほうがドーパミンの量が少ない。 • 運転中はサイレントモードに 危険な瞬間に気が散るリスクが減る。 ◯ 職場で • 集中力が必要な作業をするときは、スマホを手元におかず、隣の部屋においておく。 • チャットやメールをチェックする時間を決めよう。 ◯ 人と会っているとき • 友達と会っているときはスマホをマナーモードにして少し遠ざけておき、相手に集中する。 • あなたがスマホを取り出せば、周りにも伝染する。 スマホを取り出さないようにすれば、周りも見習う ◯ 子供と若者へのアドバイス • 教室でスマホは禁止! でなければ学習能力が低下する。 • スクリーンタイムを制限し、代わりに別のことをしよう 大人も子供も仕事・勉強以外でスクリーンに費やすのは最長2時間まで。8歳未満なら1時間。 • よい手本になろう 私たちは相手を真似ることで学ぶ。子どもは大人がしているようにする。大人に「しなさい」と言われたようにではなく。 ◯ 寝るとき • スマホやタブレットの電源を切る ベッドに入る1時間前には。 • スマホを寝室に置かない。 朝起きるための目覚まし時計を買おう。 • 寝る直前に仕事のメールを開かない ◯ ストレスの対処法 • ストレスの兆候を見逃さない ◯ 運動と脳 • どんな運動も脳に良い 心拍数を上げるものがベスト。大事なのは運動することなのでマラソンなどのきついものでなく、散歩などの簡単なものでいい。 • 最大限にストレスレベルを下げ、集中力を高めたければ、週に3回45分息が切れ汗をかくまで運動をすると良い。 ◯ SNS • 積極的な交流したい人だけフォローする。 • SNSは交流の道具と考えて 他の人の投稿に積極的にコメントをすることで親近感が生まれ、関係も深まる。 • スマホからはSNSをアンインストールし、PCだけで使う。
0投稿日: 2025.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ『一流の頭脳』が面白かったので、こちらも読む。 タイトルで想像できる通り、スマホやSNSが人間に与える悪影響を書いた本。 主な影響は、睡眠障害、うつ、記憶力低下、集中力低下、学力低下、幸福感低下、依存症など。 睡眠が長期記憶に必要ということは知っていたが、1時間ほどの昼寝でも効果があるのは初めて知った。 自分はSNSとしてはブクログしか利用していないので、かなり影響が少ない方だと思うが、非常に興味深い内容だった。 特に、子供の学習に関するスマホの影響に関してもっと知りたい。 学校へのスマホの持ち込み、タブレット端末での勉強、家庭でのスマホの使用時間など、もっと社会で検証され、議論されなければならないと思う。
1投稿日: 2025.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ私たち人間は本能で、ほんのちょっとの時間でも何か情報を得ようとします。 私の場合は目下、推しサッカーチームの移籍情報。 何か新しい動きがないかと、気づいたらスマホを手に取り、Yahoo!ニュースやXを無限スクロールしてる始末。 数年前に話題になったアンデシュ・ハンセン『スマホ脳』を読んでみると、“脱スマホ”は思っている以上に難しそうです。 今この瞬間も新しい情報があるかもしれないというギャンブル的な欲求。 それに耐え、スマホを遠ざけることに余計カロリーを使うという皮肉。 本書では対抗策として運動を推奨してますが、私はデジタルとの付き合い方にもっと理性を持ちこみたいです。 スマホを求めている一瞬を自覚し、本当に見るかどうか、一拍置いてみる。 見ない選択がとれるような、ホッと一息の選択肢を増やす。 先日は無性にスマホを見たくなった時、とりあえずお香を焚いてみました。 静まれ、我がスマホ脳よ。
0投稿日: 2025.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ数年前のベストセラー、しかし状況は当時よりむしろ悪化しているだろうから、全く古いイシューではない。 ライトな本に仕上げるため、論理の積み上げの部分は多少雑だが(本人もそう書いている)、その分主張はとてもシンプルにまとまっていて、読みやすい。 以下、無理やり要約。 生物の進化はとても緩やか。例えば、現代に肥満が多いのは、飢餓が頻繁に起こっていた時代の名残で私たちは(食べ物が十分あるのに今も)高カロリーな食べ物を欲しがるから。 かつての人類は、獣や他の人間に殺されることが多かったので、何か別のことをしていても常に周囲の物音や気配に敏感だった(そういう個体が生き残って子孫を残した)。つまり人間は、生き残るために注意散漫になった。 同じように人間は、新しい知識や見たことのないものに興味を示し、そのようなものを見ると脳内報酬系が働くようになった。 これらの人間の性質は今も変わらず私たちの体に残っていて、そしてそのことをもちろん理解した上でSNSは設計されており、新しい画面をスワイプするたびに脳内報酬系が働き、不確実ないいねが押されるとさらに拍車がかかり、仕事や勉強に集中しようにも注意散漫なので誘惑に勝てない。この性質は簡単には変わらない。 スマホを触らなくても、テーブルに置いているのが見えるだけで影響がある。実験によると、テーブルにスマホを置いているだけで、IQテストの点数が下がったり、目の前に座って会話した相手への印象が悪化したりした。 更に、SNSをよく見ている人ほど、自己肯定感が低く、うつ症状で精神科にかかる人も多くなる。他人と自分を比べ続けているからだろう。 だから、スマホを触る時間は限定すべきだし、勉強や仕事をするときはスマホを別の部屋に遠ざけておくべきだ。
3投稿日: 2025.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かに心身の不調、思い当たる事がありこわくなる。人間の進化の過程からの説明はとても分かりやすかったので余計に説得力あり。 今の生活はスマホは切り離せないため、スマホの特異性をきちんと考えてうまく付き合っていかないといけない。 とりあえず、スマホから離れる時間を多めに取り、適度な運動をしよう。
1投稿日: 2025.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホの負の影響を脳の特性や人間の進化から説明している。分かりやすく著者のアドバイスも心に留めておこうと思った。論拠となっているデータや論文の参照が載せてあるとより良かった。
0投稿日: 2025.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「スマホをたとえ触らなくても、目の見える範囲にスマホがただ置いてあるだけで、その場への興味・関心・集中力が下がる。」 これはかなり衝撃的でした。これを読んでから、食事中はスマホを鞄にしまうようになりました。 自己啓発本のようなテイストではなく、ただ事実を知識として教えてくれているような書き方がとても読みやすいです。 また、全ての項目に過去の実験のデータベースなどが書かれているので、ソースがはっきりしていて信頼できました。
0投稿日: 2025.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホが集中力を下げる理由を脳の構造から理解できた一冊だった。 ながらスマホやドーパミン依存が精神面に与える影響は大きい。 ただし、スマホやAIは使い方次第で思考を深める道具にもなる。 危険性を理解した上で主体的に使うことが重要だと感じた。
0投稿日: 2025.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ私はスマホ脳だ。 きっとこの本には、 スマホ脳であることのの、 精神科医からみたメリットとデメリットが バランスよく書かれているのだろう。 と思って読み始めたら。 ほぼデメリットやないかーい。 うんうん。そうだよね。 人間の長い長い歴史を1万個の丸に例えるならば、 スマホが登場したのなんて丸1個分にも満たないの。 だから、脳がそもそもスマホに適応できない。 ドーパミンをもドバドバ出させて、 なるべく滞在時間を長くさせる。 それかスマホ。(特にSNS) 私たちの脳は、まだドーパミンが出るような誘惑 に打ち勝てるほど強く進化できてない。 だから薬物だってギャンブルだって規制があるんだ。 スマホが近くにあるだけで、 テスト結果が悪くなる。 スマホを多く使う人達は、 うつ病や睡眠障害が多く発生している。 IQが下がっていく。 そんなスマホを、大人よりもさらに自制が効かない子供たちがつかう事の危うさは計り知れない。 あのスティーブ・ジョブズだって、自分の子供にはスマホこ使用時間制限をかけてる。 まずば自分のスマホのスクリーンタイムを見て。 2時間を超えてたらスマホ脳。
1投稿日: 2025.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々な研究データや人間の脳構造、進化の過程で得た人間の特性と関連づけながら現代社会で直面する「ストレス」「不安」についても言及されており、どれも目から鱗だった。 確かに、何で自制と欲求が抑えられない未成年に対して、お酒やタバコはダメで、脳にハッキング作用があるスマホの制限はかけられていないのだろう。 現代社会に少しでも浸透してほしい価値観だと感じた。
0投稿日: 2025.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログスウェーデンで精神科医をしている著者の話題作。 興味深い実験やデータがたくさんあって、今までで一番メモが止まらなかった。 ・世界中の多くの国でこれまでにないペースでうつ病、不眠症が増えている。 →なぜか?人類が誕生して99.9%は狩猟と採集で生きていた。そんな人間の持つ脳が急速に進んだデジタル化に対応できていないから。 ・ストレス、不安、緊張…これらは長い狩猟と採集の時代に、人間が生き延びるために進化した脳の自然な反応。(このメカニズムがめちゃくちゃ興味深かった!) ・強いストレスを受けると脳が周囲に危険がいっぱいと解釈 →その環境から身を遠ざけるため、脳は気分を落ち込ませて引きこもるように仕向ける =うつ病は危険な世界から身を守るための脳の戦略 ・スマホはマナーモードでテーブルに置いているだけで集中力を奪う(影響: テストの結果が悪くなる、睡眠時間が短くなる傾向など) →なぜか?スマホ=ドーパミン(報酬)を放出し続けるものと脳が認識して、スマホの存在を無視するために脳の容量の一部を使うから。 ・SNSに費やす時間が長い人ほど孤独感・不安・気分の落ち込みが増し、「自分はダメだ、不幸だ」と思いやすい傾向。(思春期女子は特にこの傾向が強い) →なぜか?脳は集団のなかで自分の地位が下がるとセロトニンの分泌が減り、うつ病になりやすい。SNSの利用で、常に何百万人と自分を比較しやすくなり、何においても自分より上がたくさんいることを思い知らされ、自信を失いやすいため。 ・SNSの仕組み 人々の「注目」は黄金の価値。どうすれば1秒でも長くSNSに留まるか、脳の専門家を雇って研究し、ドーパミンを刺激する作りにしている。 →SNSはその「注目」を広告主に転売し、モノを買わせる機会を作っている。 例: 下にスワイプして1秒待つと更新され、新しい投稿が現れる(脳にとって報酬)=スロットマシーンを真似ている。 狩猟と採集の時代になぞらえて考えてみると、ストレス・不安・緊張・不眠など私も含めて多くの現代人が悩んでいることの根源がよく理解できた。 そして今や当たり前になった、スマホとSNSの利用を見直すきっかけにもなった。 実際にやったこととしてはとりあえず、スマホをグレースケール(モノクロ表示)に設定し、あらゆる通知をオフにして、Instagramを見えないところに追いやり、目覚まし時計を買ってみた。 スマホばかり見てメンタルを病みながら一生を過ごしたくはない。それよりも、いま目の前にいる大切な人やモノ(本とか本とか…)に時間を注いで、自分が本当の意味で満たされる過ごし方をしたい。
37投稿日: 2025.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこの後スマホを使うのが怖くなるくらい、いろいろ考えさせられた。問題提起型の本なので、皆さんまずは読んでみて、思いを巡らせるのがおすすめです。
1投稿日: 2025.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スマホ依存症、といった言葉は最近よく耳にするし、精神疾患患者が増えていることも知っていたけど、人間の脳が一万年前から変わってなくて、科学の進歩が人間の身体に追いついていない。という視点から分析するのがとても面白かった。 なるほど…、これ自分に当てはまっているよな、無意識のうちに脳がハッキングされていた、、、とか、読書中何度思ったことか… これを読んでから、スマホがとても恐ろしいものに思えてきて、その嫌悪感から手にとる時間が減った気がする。 SNSがあることで、沢山の人に繋がれるメリットも私は大いに感じているから、良い塩梅で付き合っていけるようにしたい。 本書の伝えたいメッセージ軸とは違うかもしれないが、以下のフレーズが印象に残った。 ↓ 精神科医として働く中で気づいたのだが、患者が、自分の感情が果たす役割を理解するのはとても重要だ。不安が私たちを危険から救ってきてくれたことや、うつが感染症や争いから身を守るための術だったと知れば、患者たちもこう考えることができる。 「うつになったのは自分のせいじゃない。ただ脳が、進化したとおりに働いているだけ。 その世界は、今いる世界とはまったく違ったのだから」
1投稿日: 2025.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログコロナの時期に、スマホゲームを勧められて始めたことがあり、その時はクリアすべき課題に1日の時間をほぼ取られていた。 本を読むことが趣味で、普段は全くゲームをしない自分でも、こうなるのかと思ったものだ。 今も、本を読みながら調べたいことが出てきたらスマホを取り出して調べたりする。 すると、いつの間にかスマホで別のことも始めてしまい、いつの間にかSNSを長時間見ていたこともある。 自分に限っては、と思っていたのに、身体としての脳はかくもスマホに翻弄されるのだと知った。 そのわけがこの本に書いてあるのだが、自分の体験だけでももう十分スマホの影響が知れたので、もう早く次の本が読みたくて、つい早読みしてしまった。 うつや睡眠障害も、スマホだけの影響ではない気がする。 それでもスマホに囚われてしまう人はいるだろし、そうでもない人もいる。 子供には確かに良くないとは思う。それは確信している。
2投稿日: 2025.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ質の低いドーパミンに支配されている現代。 ドーパミンの最重要課題は「人に行動の動機を与える」。 フリック操作ではなく、人生を豊かにするための行動にドーパミンを使っていきたい。
2投稿日: 2025.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログそりゃあ人類の進化のペースとあらゆる物事の発展のペースって合わないよね〜 合わせられてるように見えてかなり振り回されている。 あと運動と読書はあらゆる面で効く。
1投稿日: 2025.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本が発売になった時、とても気になっていた。 やっと読むことができた。 とっても、よく分かった!!! 著者はスェーデンでの精神科医。 現代の、鬱や精神障害の多くはデジタルが原因と書いてある。 人間の脳は原始時代から機能は変わらず、デジタル時代に追いついてないとのこと。 わかりやすい文章で、サクサク読めた。 巷でもスマホ依存症が問題になっている。 未だ脳が発達段階の幼い頃から、スクリーンを見続ける影響も読んでいて怖いくらいだ。 訳者のあとがきにもあるが、 この本は子供や若者だけでなく、物忘れが増えた大人や集中力が無くなった大人、ストレスを感じる大人にも読むべき本。 特に、教育関係者、保護者はデジタルに対するメリットデメリットを知るうえでとても参考になる。 読書をするにしても、オーディブル、電子書籍より、 やっぱり紙の本が頭に入る気がする。 脳の為にも、睡眠時間を取り、運動をしっかり頑張って、 たくさんの本を読めるようにしたい。 「一流の頭脳」をぜひ読みたい。
41投稿日: 2025.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。なるほどなーを100回くらい言った。 人間は現在のデジタル社会に適応できるよう進化していない。それは現代社会というものが、ここ数十年で急激な進化を遂げているため。 本来、種の大きな変化というものは何万年という時間をかけて行われるため、人間の本質は現代社会に適していないそう。この説から始まり、ストレスや不安からくる精神の不調のメカニズムを、人間の特性から説明している。これがめちゃくちゃタメになる。 ストレスや不安にさらされるとき、今までは自分はなんで弱いんだろう、とか、自分ばかりが不幸だ、と思っていた。こうして体の仕組みとして客観的に考えると、今後は状況を冷静に俯瞰できるかも知れない。 あとは、運動ってやっぱり大事なんだ。動こう。
1投稿日: 2025.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログまた読みたい。 教育的影響、運動脳との関わり、ストレスを与える人与えない人、スマホとの付き合い方、スティーブ・ジョブズは子どもに距離を取れせていたことなど驚愕の話が多く、1日6〜8時間、数年で寝る時間を抜けば1年程度使い続けている=支配されていることなど驚いた
1投稿日: 2025.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログリアルにどんな影響があるか知りたくて読んだけど、あまりnewはなかった 「闘争か逃走か」など、人間の進化に関する前提知識の方が面白かった
0投稿日: 2025.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日常生活に欠かせないスマホによる脳への影響が示された一冊。 私は依存症までなっていないが、不安や悩みが増大した際についスマホに取りつかれてしまう自分がいるのも事実である。 スマホに依存せず、スマホとどう向き合っていくかの本書最後にのっている。 心身を退化させないためにも、最低限ここに書かれたことは実践していきたい。 まずは手始めにスマホを寝室に持ち込まない、寝る直前にメールやチャットを開かないことからスタートする。 かのスティーブ・ジョブズも子どもたちに対してスマホやタブレットの使用を制限し、ビル・ゲイツも子供が14歳になるまでスマホを持たせなかったという件は衝撃を受けた。 IT時代の申し子と呼ばれる方々がこぞって、自ら作り出した製品の利用に制限をかけようとするのは、使い方を誤ると心身に大きな影響が生じると思っているからではないか。 時代遅れといわれるかもだけど、 ・チャットやメールチェックは1時間に数分 ・自分や子どもたちが勉強するときは紙とペンを使う(スマホやPCでメモを取らない) ・自分の子供たちには毎日1時間は体を動かしてもらい、9時間以上の睡眠をとってもらう といったことを実践していきたい。 今のスマホ全盛の時代に、手に取って繰り返し読みたい一冊である。
0投稿日: 2025.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホを使い始めてから、特にSNSを使い始めてから、思い悩むことが増えた感覚があったが、それをさまざまな研究結果をもとに説明してくれた。 スマホから離れるのが良いのはよくわかったが、運動が効果的とは知らなかった。 育児にも自身のメンタルのためにも生かしていきたい内容だった。
1投稿日: 2025.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、現代人にとって非常に衝撃的な一冊でした。普段何気なく使っているスマートフォンが、私たちの脳にどれほどの影響を与えているのかを、精神科医である著者が最新の科学的知見に基づいて冷静に、そして鋭く指摘しています。 特に印象的だったのは、「人類の脳はスマホの利用に対応していない」という警鐘です。集中力の低下や睡眠障害、さらにはうつとの関連性など、思い当たる節がありすぎて背筋が凍る思いでした。スマホ依存は意志の弱さではなく、脳の進化の歴史に根ざしたメカニズムだと知ることで、自分を責める気持ちが少し和らぎました。 しかし、単なる警告で終わらず、デジタル社会でどう脳を適応させ、スマホと賢く付き合っていくかのヒントを与えてくれる点も良かったです。スマホを手放せないすべての人に、一度立ち止まって自分の脳と向き合うきっかけを与えてくれる、必読の書だと思います。読後、私は無意識にスマホを手に取る回数が減りました。
0投稿日: 2025.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと気になっていたが、スマホ依存症についてぼちぼち書いてあるだけだろうと思っていた。実際に読んでみると、これはベストセラーになっているのに納得。 「今あなたが手にしている本はデジタル人間の脳は社会に適応していないという内容だ。」7 なんてことだ!!読み進めると、スマホやSNSを我々が使用しているのではなく、使用させられているのだと理解できる。本書では一日3時間を超えると様々な心身への影響があると述べている。現代ではもっともっと一日にスマホを使用しているだろう。若ければ若いほどその傾向は強いと考えている。若者こそ読むべきであり、若者こそ読まないだろう。大人がこのような知識をこの本を論拠に伝えていくしかない。もしくは、国や地域をあげてこの問題に取り組んでいかなければならないと思う。 以下はメモ 長期にわたってストレスホルモンの量が増えていると、脳はちゃんと機能しなくなる。常に「闘争か逃走か」という局面に立たされると、闘争と逃走以外のことを全て放棄してしまうのだ。45 ストレスは脳の扁桃体が関与しており、「火災報知器の原則」で機能する。つまり、間違えて鳴らないよりは、鳴りすぎるほうがいい。 ポケットの中のスマホが持つデジタルな魔力を、脳は無意識のレベルで感知し、「スマホを無視すること」に知能の処理能力を使ってしまうようだ。94 グーグル効果もしくはデジタル健忘症 別の場所に保存されているからと、脳が自分では覚えようとしない現象 スマホが及ぼす最大の影響はむしろ「時間を奪うこと」で、うつから身を守るための運動や人づきあい、睡眠を充分に取る時間がなくなることかもしれない。117 他の人が何をしているのか、互いにどんな関係にあるのか。これを知っておくと有利だったため、人間にはそういう情報を得たいという欲求がある。私たちが生き延びるのを助けたのは、食べ物とゴシップだった。130 基本的にすべての知的能力が、運動によって機能を向上かせるのだ。203
9投稿日: 2025.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホ依存を心配して本書を手に取った。読むとなるほどと腑に落ちるとともに怖くなりました。特に子育てではもっと配慮しないといけないと反省。自分もジムで運動始めました。
0投稿日: 2025.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホがいかに人体に良く無いかを徹底的に論じた本を読み終えた後、こうしてスマホを開いてブクログに感想を書いている。でも、それは自分に必要な事だから。 Xのアカウントは作ってない。 Youtubeはキリがないので見ない。 インスタは写真わざわざとってあげるのが面倒なのでアプリを入れてないし、他人の投稿をわざわざ見たいとも思わない。(Facebookのアカウントを持ってるからWebから必要な時は見られる) 。 そのFBも去年ぐらいに思い立って、誰にむけて発信しているのか分からないこれまでの投稿すべてを非表示にした。 新規友人の承認も停止し、なんならアカウントも削除しようかと思ったけど、メッセンジャーでしかやり取りしてない友人もいたので、それは思い留まった。 でもこの本を読んで、FBのアプリを削除した。 ついでにyahoo newsアプリも削除。 スマホのスクリーンをグレースケールにして1週間、確かに不思議なほどスマホに触る気が失せるし、たまにカラーにすると、酔いそうなほど画面が眩しく感じてイヤになる。 スマホはなるべく玄関に置き、リビングには極力持ち込まず、子供の前では触らないようにしている。 目覚まし時計も家にあったものを引っ張り出して、寝る前はスマホを触らず、玄関に置いたまま距離を置いて寝たら、眠りの質も上がった。 幸い、ずっと書いたいと思っていたタブレット端末は未だ購入しておらず、小2の息子はテレビは良くみるけど、それと同じくらい工作とお絵描きと作文に夢中。 そんな息子の前で無駄なスマホ触る自分を戒めたい。 自分の人生の変化と、息子の成長を楽しみたい。 ブクログと共に。
2投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代人との比較の連続に疲れてしまって、後半はパラパラ読みました。一日のスクリーンタイムをできる限り減らそう。今までスマホが近くにあったから集中できてなかったのかと気付く場面が多々あった。スマホは別の部屋に置き、通勤時間は読書しよう。 スマホとはうまく付き合っていきたい。
0投稿日: 2025.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
個人的に結構面白かった。 研究結果を根拠として、こうするべきだという意見が述べてあって納得しやすかった。 そうでなくても、自分自身スマホの使い方に関して思い当たる節が多々あったので、改善していこうと思えた。 日本だけではなく、海外でも似たような事例があることを知り、スマホの影響は人種の性格からくるものではないのではと感じた。
0投稿日: 2025.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ私はスマホ依存症だと思う。 何時間もスクリーンを見て、SNSを見て、YouTubeを見ている。でも、最近調子が悪い。目も悪くなったし、ケアレスミスが増えている。 一大決心をして、SNS をログアウト、スマホを隣室の指定の位置に置くようにした。 でも気になる!どうして?大した情報はないのに。 と思っていた時に本書に出会った。 脳のドーパミンは何かあるかも!となると気になる。しかも毎回あるわけじゃない方がいっぱい出る。 スマホは私たちの集中を全力で奪うように出来ている。 ジョブズ始め、スマホを作った人たちはその危険性に気づいて、スクリーンタイムを制限している話なんかも興味深かった。私も気をつけなければ。 人類の進化過程と現代社会の違いを見比べる良書だが、難点が一つ。途中に登場するコラムがなぜ文の途中でぶちこむんだ?読みにくいけど、理由があるのかなあ?
0投稿日: 2025.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を大学生の早い時期に読めたことは、自分の人生にかなり大きな影響を与えた。 SNSはできるだけ触らないようになったし、集中して本を読んだり作業する時は、スマホを見えないところに隠す習慣ができた。 スティーブ・ジョブズが子供にスマホを渡さなかった事がかなり説得力ある事例。
0投稿日: 2025.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
★★★☆☆星3【運動で解決】 最近は本当に集中力が続かなくて困ってる。スマホを少し遠ざけてみようと思った。そしてやはり運動が大切。運動が全てを解決してくれるのなら手っ取り早い。運動しよう。
1投稿日: 2025.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ小3の娘のお友達は既にスマホを持っている子も多い。 娘も遅かれ早かれ持つことになるであろう。 わが子の前に親である私自身がスマホとの付き合い方、そして運動や睡眠といった生活の基盤の安定をはかるべきだと思った。 さらに興味深いのが、スマホの本題に入る前のうつ話。脳の進化がまだ現代の長期的なストレスや不安に追いついてないようだ。たまたま【疲労とはなにか】というタイトルの本を読んだ後に本書を手にとったので繋がりがあって面白かった。2冊同時に2周目を読んでいる最中。 長期的なストレスと疲労からくる、心身の不調を見過ごさないように過ごし、早期に適切な対策を日々模索していこうと思う。
7投稿日: 2025.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホとの付き合い方について考えさせられる本。 昨今の「スマホ=悪」というような風潮は、一世代前に言われていたゲームやテレビを一括りに悪者扱いするのと同じ、メディアが煽り立てる逆張りトンデモ理論だと思っていた(なぜならどれもブルースクリーンが悪いと思っていたから)が、人間の進化の見地から展開される説明には、「なるほど」と唸らされる。一番の違いは、SNSの存在か。 自分自身のスマホの付き合い方を変えようと思えただけでなく、子供のスマホの付き合い方もちゃんと考えていかなければならないなとも思わされる。 これからデジタル化がより一層進む中で、スマホは必須のアイテムだからこそ、子供にはどんどん使わせたいと思っていたし、「使用時間に制限を設けるなんて、なんてローテク人間なんだ」と思っていたけれど、考え方が180度変わった。上手な付き合わせ方、バランスを大切にしていきたい。
1投稿日: 2025.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホがいかに人に害をなすか。人類の進化の過程や数々の研究から、なぜ不安や集中力の低下、うつ病などになるのか、わかりやすく書かれていてためになった。スマホの使い方を見直そうとも思った。
1投稿日: 2025.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間って思ってる以上にマルチタスクなんてできないんだなーっと あと、SNSの見過ぎって本当に良くない鬱病のリスクを高める 適度に運動しながら好きな人間とリアルに関わっていきたい〜
1投稿日: 2025.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホが脳に悪いのはなんとなく感じていたが、研究結果を元に解説されていて納得できた。 SNSなどは無料で使用できている、ではなく広告のターゲットになっているだけだった。 ⭐️学んだこと •長期にわたってストレスホルモンの量が増えていると、脳はちゃんと機能しなくなる。常に闘争か逃走か、と言う局面に立たされていると闘争と逃走以外のことを全て放棄してしまう。 •扁桃体:HPA系を作動させる。返答。体の作動の仕方は、火災報知器の原則。→間違えてならないよりはなりすぎる方が良い。 •ドーパミン:報酬物質とも言われるが。何かに集中するかを選択させる、つまり、人間の原動力。 ※満足感は、エンドルフィンが大きな役割を果たしている。 •記憶は、脳の様々な場所に保存される。 事実や経験:記憶の中枢と呼ばれる海馬に入る。 自転車に乗る、泳ぐ、ゴルフクラブでボールを打つといった技術を習得するとき:大脳基底核の線条体。 テレビを見ながら本を読むなど、複数の作業を同時にしようとすると、情報は線条体に入ることが多い(間違った場所) ⭐️TO DO •マルチタスクをやってるようで、複数の作業を行ったり来たりしているだけ。脳には切り替え時間が必要でさっきまでやっていた作業に残っている状態を注意残余と呼ぶ。集中する先を切り替えた後、再び元の作業に100パー集中できるまでには何分もかかる。 →特に仕事においては1つの作業に集中する。 •手書きメモはPCに勝る →一度メモに書いて、後々検索できるようにExcelやWordにまとめる。 •週に2時間位運動する。脳に対してはこれぐらいでオーケー。心拍数上がると良い。 →ジム続ける。 •元気になれるコツを実践する。 →睡眠を優先し、体をよく動かし、社会的な環境を作り、適切なストレスに自分をさらし、スマホの使用制限する。
9投稿日: 2025.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ・スマホやSNSは人の注意を引くように 作られていて、集中力が奪われる。 ・論文研究には、時間がかかるので、スマホ使用 の人体への影響は、まだ詳しく分かってない。 ・スマホは依存性が高いので、前頭葉が未発達な 子どもにはスマホを使用させない方が良い。 ・IT企業トップは、子どもにスマホを与えない ・スマホの使用は、最長2時間/日にする。 ・運動は、集中力の回復、ストレス予防に効果的
0投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の脳は石器時代から変わってないため、運動することがストレスにも集中力にも記憶力にもいいということが、わかりやすく説明されていて、 本当に運動しようと強く思った。 それからデジタルデトックス(とくにSNS)も始めた。 また時間を無駄にしてしまった、と思うことがなくなったし、とくに問題ない。それほどおもしろくなくても、ドーパミン求めて開いていたんだなあと実感。 寝るときは寝室に持ち込まず、目覚まし時計を使うことにした。 時間をみるために取り出さないために、久しぶりに腕時計を使おう思う。 スマホを横において置くだけで、集中力が下がるのも納得。 喫茶店とか、とりあえずテーブルに出して置くのもやめることにした。 今のところとても穏やか。 読んでよかった。ありがとうございます。
1投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと前の本だけど、めっちゃ思い当たる節がある。SNS を使うとドーパミンが出てドーパミン依存症になるとか衝撃的。最近メンタルの調子が悪いこととか、睡眠が浅くなってることとか、いちいち思い当たることが多すぎて怖くなった。 YouTubeで動画を見てるだけで、1日終わってしまうこととかあるもんな。すでに手遅れかもしれないが、デジタルデトックスやってみるか。
0投稿日: 2025.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ気になるタイトル、読了 これは私だけの感覚かもしれないけれど、なんとなくいつもスマホに集中すると感じる罪悪感、この感覚はどこから来るものか疑問であったのだけれど、なんとなくいくつかその理由が思いついた。 1番は多分、子どもに使う時間を控えるように常から言っていること(といってもあんまり言うこと聞いてるようには思えないが) 2番目は、なんとなく良いものではないという思い込みがあること(に気づいた まぁ、その根拠となるデータはまだ多くはない。 というのも、スマホなるものが庶民の手に入りやすくなってからそう時間が経っていないからである。 確信はないものの、スマホ依存症という言葉を聞くようになってから、上手に付き合わなければいけないものである、という感覚に間違いはないだろう ‥テクノロジーが人間に合わせるべきである、という言葉が繰り返し出てきたのが印象的だった。 確かに10年足らずで、ほとんどの人が一台もしくは二台以上のスマホを保有しているのは恐ろしい普及率であると感じる 道具は使い方次第、という言われ方をするけれど、それはそうなんだと思う。 実際、上の子はともかく、下の子に与えるのは早すぎたと後悔している。 これは完全に個人差だと思うので、年齢は関係ない けど、子どもに理解してもらうのは難しかっただろうなとも思う 不安が人類の歴史でとても重要な役割を果たしてきたという話も興味深かった 報酬探索行動と情報探索行動による欲求を満たすことと引き換えに、何を失いかけているのか、見極めないといけないだろう。 私は一生ボタンを押し続けるラットにはなりたくない 本もできるだけ紙のものを読み続けようと思う 備忘録 必ずしも1番強いものが生き残る、というわけではない 人前で話すのが怖いのは、仲間外れが怖いから マルチタスクができるって実はすごくない
2投稿日: 2025.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ1967年生まれの私は、コンピュータそしてインターネットの普及段階に生きてきた。我が子にはデジタル技術に早くから接した方が良いと思い、中学生の頃からパソコンを買い与えた。さすがに携帯電話は高校生になってからだが。今、私の周りでは小中学生がスマホを持っている。本書を読むと、それらが空恐ろしくなる。脳は石器時代からさして進化していない。デジタル技術の進展が脳の適応速度をはるかに凌駕してしまった。だがしかし「脳は身体を動かすためにある」という言葉に目から鱗が落ちる思いがした。
0投稿日: 2025.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ・人間の適応スピードは現代の進化よりも遅い。例えば、クモやヘビには危機を感じる扁桃体が反応するが、喫煙やシートベルト未着用には扁桃体が反応しない。人間の環境に対する適応は現代の変化のスピードよりも遅い。むしろ、現代の変化のスピードが早すぎるのかもしれない ・メンタル不調の人がスマホをよく利用するのではなく、スマホ利用時間が長い人がメンタル不調になる研究結果が多数ある。基準はI日2時間以上利用する人がメンタルに不調をきたし始める。総じて、大人が自分で管理できない事柄を子供たちが管理できるはずない。親がきちんと利用時間を制限した方が脳の発達に支障をきたさない。研究結果では、スマホの利用で脳の発達が遅れる事例も多数確認されている。 また、研究者達は子供のタブレット学習に懐疑的であり、ペンで文字を書く動作に学習の意味があると考えている。電子機器では立体空間の認識にも繋がらないし、実際に手を動かして、感触や肌触りなど五感をフルに利用した方が学習効果が高い。 →そりゃそうだと思う 頭を良くしたければ、1週間に2時間の運動と読書をする事
0投稿日: 2025.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
明確な答えというより全体的には問題提起の本。 ですがそうやって自分の頭で考えたり情報の取捨選択をする事が現代の人間に必要な事かと思います。 私自身がスマホ中毒者なのでもっと革新的な解決法を提示されるかと期待してしまった部分がありましたが、こちらの本では人間の進化の過程による脳の仕組み、それがいまだ現代の急速な発展についていけていないなど、「なぜこうなってしまっているのか」の具体的な説明により、現在の状況についていろいろ腑に落ちました。 脳の仕組みを少しでも理解する事により、自分で自分の行動を制御できるようにならなければいけないと思います。
0投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホが人間の注意力を向けさせるのに長けているのは、ブクログの感想を書くためにスマホを手に取ったときにも感じた。 ブクログを開く前に無意識のうちにYahoo!ニュースを検索していたからだ。 スマホが脳に与える影響やそれに対する運動の効果の説明がわかりやすかった。 著者の主張で 「テクノロジーは好き嫌いにかかわらず受け入れる天気とは違う。テクノロジーの方が私たちに対応するべきである。スマホやSNSはできるだけ人間を依存させるよう巧妙に開発されている。そうではない形に開発されてもよかったわけだし、今からでも遅くはない。もっと違った製品が欲しいと言えば、手に入るはずなのだ。」 は全くその通りだと思う。 パートナーは一緒にいる時でさえポケモンGOに夢中になっている。注意しても直らない。どうにかしてくれ...
4投稿日: 2025.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホ脳。まさにそれで睡眠不足、集中力切れ。 スマホ一日中平日6時間、休日18時間触ってた。 それで仕事も辛くなって辞めることになった。 そんな私が、デジタルデトックスをしようと思ったきっかけになった動画で紹介されてたので、買って読んでみた。 人間の過去からの積み上げてきたものが今のデジタル社会にはまだ適応できていない。 仕方ないから離れるしかない。 運動しよう。 そんなうすっぺらい感想しか今は持てないけど、でも、納得のいく内容で読んでて面白かった。 少しずつでも、離れていこう。頑張ろう
1投稿日: 2025.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なにげない普段の生活で、徐々に蝕まれていることに気付かされる作品。 スマホを使いすぎてはいけないことはわかっていても自制できない自分に、分かりやすく論理立てられた説明から生活を見直そうと決心した。
0投稿日: 2025.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分だけでなく子どもとスマホの付き合い方も考えるきっかけになった。ダラダラとsnsを見続けてしまう(無意識に開いている…こわい…)のも、新しい情報を得たいという人間の欲求に基づくものなのだと思うととても腑に落ちるし、結局その瞬間のドーパミン放出のためにやっているのだと理解できると争おうという気持ちになる。 スマホがそばにあるとソワソワしてしまうのは本当にわかる。通知きっかけでネットサーフィンを始めてしまうし…。そう考えると最低限の機能しかない&つけていることを意識せず済むApple Watchって素晴らしいアイテム!と思った。 在宅勤務の時はなるべくスマホを別室に置いて、Apple Watchだけ身につけて仕事しよう!
0投稿日: 2025.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホの影響力について、研究の結果を元に伝えてくれている。そもそもの人間の機能とスマホがどう繋がるのか分かりやすい説明だった。研究の精度や継続研究中などの課題はあるが、私たちにスマホ問題を提起してくれている。これを読むと、スマホについての条例を出そうとしている自治体の気持ちもなんとなく分かる。スマホを使うことは避けられないけど、程よい付き合い方と運動を欠かさず過ごしたい。
0投稿日: 2025.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ脳が持つシステムを、スマホはこれでもかと刺激する。故に人々はスマホを手放せない。 興味深いと思ったのは、人間は基本注意散漫(しきりに周囲のことを気にする)という事だ。だか、生き残るためには時に「集中」しなければならず、だからこそ、「集中」と「集中の解除(息抜き)」のバランスが重要である。しかし、スマホはそのバランスを最も容易く崩す。スマホは人間の「集中」を向けさせることに長けている(例えば通知)。 この本を読んで、ますますスマホとの付き合い方を考えなければならないと思った。とりあえず、少しは運動しようと思った。
1投稿日: 2025.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログお化け屋敷バイトの社員がTikTokを延々とスクロールしている横で読み終えた。一層身に染みた気がしたのは錯覚か。 SNSはいいね等の通知のタイミングすらコントロールしている、ってところでゾッとした。 集中力を武器にしたい!
1投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホがいかに中毒になるように巧妙に仕組まれているかがわかる。 運動をするのがいいという。 漠然とスマホを見ないように意識しようと思いました。
1投稿日: 2025.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度目かの再読 ゲイツもジョブズも、子供のガジェットの使用に制限をかけていた。 なかなかこの逸話の原典に出会えないので、この本が私にとっての唯一の情報源になっている。 説得力がとてつもない逸話である。
2投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログスウェーデンで注目されているメンタルヘルスのインフルエンサーの著書。スマホに支配されがちなこの世の中だが、簡単に言うと運動するだけでストレスに強くなり、記憶力や集中力がアップすることを唱えている。 一番良いのは6ヶ月に最低52時間身体を動かすこと。→週に2時間→45分×3回/週
0投稿日: 2025.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ電車に乗って周りを見渡すとスマホを見ている人ばかり。私もその1人である。そんな今の時代に生きる人々は大切な何かを失っているのではないか。今生きている時代と人間の脳の不和、ストレスへの向き合い方、何かに取り憑かれたようにスマホに見入ってしまう理由。また、失われた集中力を取り戻す術について知りたい方に是非読んでいただきたい。
1投稿日: 2025.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直なところ、思いの外良い本だった。 当初からよく売れていて見かけて、著者の露出も増えて、だからスマホをわかりやすくセンセーショナルに否定しているのかと思っていた。 が、前半はシンプルに心理学、ストレスの話題であり、ためになり。メインはスマホの影響、そうでなかったらどうなるのか、避ける方法はあるのかが書かれていた。 この感想も当たり前のようにスマホで書いているし、何度もSNSを途中で見たりする。しかし、本を読む、映画を見る、そんな当たり前の集中力が低下してきていることを実感し始めてきたところでこの本を読むと、それはやはりスマホの影響なんだろうと思わざるを得ない。 そして、この本ではほとんど出てこないAI、一部人工知能は出てくるが、がスマホの中で当たり前に使われるようになった今、このスマホ脳はどうなるのだろうか。スマホよりも強烈な影響を与えるのではないだろうか。そんな恐怖を感じた。
2投稿日: 2025.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供を持つ親は必ず読むべき本。 スマホを触るリスクを十分理解できる。 スマホを作った偉人たちは、彼らの子供にスマホを使用する制限を必ずかけている。 それは、スマホはその画面を、見続けるように天才達が作り込んでいるからだ。 スクリーンを見続けると集中力は下がり、学力も下がる。 その簡単な解決策は、運動すること。 また、メモは手書きのメモに限る。 とても良い本。
8投稿日: 2025.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ私がスマホを使ってるのか。 スマホに私が使われてるのか。 スマホについては自分の意志だけでは出来ないことあると分かった。 自分の意志ではできないなら。。。。
0投稿日: 2025.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強になりました。脳は原始時代から大きく進化していない。そんな脳が現代の膨大な情報を処理できるのか、できるわけがない・・確かに。
0投稿日: 2025.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ目覚まし時計を買い、適度な運動をします 遺伝子やこれまでの人類の進化をもとに、スマホ中毒になる必然性を説き、そこから脱却すためには意志だけじゃなく、物理的隔離が必要なのだと分かった。
0投稿日: 2025.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代人はスマホに依存しすぎている。進化の過程で現在ではまだ脳がスマホで得られるドーパミンに対応できていないため、スマホ依存というものが起きるのだと思った。 「うつになったのは自分のせいじゃない。ただ脳が、進化した通りに働いているだけ。その世界は、今いる世界とはまったく違ったのだから」 「できるだけ長い時間その人の注目を引いておくには、人間の心理の弱いところを突けばいいんだ。ちょっとばかりドーパミンを注射してあげるんだよ。」
6投稿日: 2025.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホは寝室に必要ないと思い、別の部屋で充電するよつになった。 脳がスマホにハッキングされているということを実感した。 多分SNSの利用は向き不向きがあるんだと思う。
0投稿日: 2025.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ脳科学をはじめとする科学的な視点から「なぜスマホが良くないのか」が解説されており、非常に学びが多かった。私は大学時代、卒業論文で「ストレス耐性」について研究した。その中で、「長時間SNSを利用している人ほどストレス耐性が低い」という結論に至ったが、本書でも同様の研究結果が紹介されており、自分の研究内容が裏付けられたように感じた。
8投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
長時間のスマホやタブレットの利用が身体にどのような影響を与えるか、進化の過程と比較しながら解き明かされていく。その対処法として運動が一番有効というのは分かったが、もっと他の対処法があれば知りたい。
0投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホのブルーライトからの睡眠時間減少で能力低下というのは納得できる。それに集中力の欠如というのもその通りだろう。過剰な情報量に対して脳がいかなる影響を後年受けるかはまだ分からないが、ジョブスを始めとするテック企業の主たちが子どもに使用を制限しているのはやはりなぁという印象。
6投稿日: 2025.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログただのスマホ警告本だけにとどまらず、心理学や行動原理なども教えてくれるためになる一冊。まずタイトルがストレートで潔く、結論「スマホは人類にとって危険」と言い放ちその根拠を丁寧かつ慎重に解説してくれる。最初の1万個のドットが1万個は説得力があります。人類は1万年前の進化から本質変わっていないがスマホを含めた環境は激変していて順応出来ず、特にスマホは1万年前の人間が生きるために身につけた好奇心を上手く利用して依存させていく怖い存在である。 最後に対応策として運動を勧めてくれるが、これをきっかけにより運動を意識するようになったのは収穫といえる。
5投稿日: 2025.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログそんな分厚くないからと思って油断してたら濃密な内容…! 時々、あれっさっきと言ってたこと違うくない?って思うところがあるけど、まさか著者が間違えるはずないと思うので、私の頭が追いついてないだけなのかなと…(笑) とにかくスマホはやっぱりやばいということはよくわかった。 それにしても私もスクリーンタイム設けて読書したりするようにしてるのに記憶力悪いままなのはなぜ…?(笑)
7投稿日: 2025.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現代人の脳機能は、狩猟時代と変わらないらしい。つまり、外敵や未知のものが近づくと脳が危険信号を発し体を緊張させ(長期間続くとストレスが溜まる)、飽食の時代でも飢餓に備え必要以上に食べたいというカロリー摂取欲求を抑えられない(結果、糖尿病や肥満が増える)。 スマホの弊害については、実はスマホ機能の拡充ぶりが速すぎて、研究自体が追いついていない状況。 しかし、ITの最前線にいたスティーヴ・ジョブズやビル・ゲイツなどは既にその中毒性について気づいていた。彼らの感覚的な危険性の理論的裏付けを試みたのが本書の肝。 以下は、私の備忘録。 ・人前で喋る恐怖も、進化の過程で「失敗して共同体から追い出されないこと(仲間外れ回避)」が脳にとって重要だったから→過剰な危険察知能力でもある ・フェイスブックの《いいね》は、利用者の承認欲求を満たし、スマホ依存を助長する ・IT会社は、いかに利用者のスマホ利用時間を増やせるかを研究→スマホ依存症が増加 ・ブルーライトの青は、私たちの祖先にとって晴れ渡った空から降ってくるものだった。睡眠物質であるメラトニンを作るな、油断せずに警戒を怠るな、と脳は指令を出す→睡眠不足もしくは睡眠の質の低下 ・これらの負のスパイラルを断ち切るには、スマホは必要最低限の使用とするのと同時にとにかく体を動かす(週2時間で良い) ・筆者の不調改善策は、睡眠を優先し、身体をよく動かし、社会的関係を作り、適度なストレスに自分を晒し、スマホ使用を制限する ・幼児にタブレット学習が向かない理由は、記憶力や集中力が低下するため 現代人にとってスマホは生活に無くてはならない存在となっている。しかし、その利用時間を制限することで依存性を低減し、よりよい睡眠が確保できるとしたら…もちろん選択するのはあなたです。
3投稿日: 2025.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホを使うデメリットわかりやすく書かれていました。 今心の病気の人が増えているのにも要因があるとの事。 少し離しておかねばと思いつつも つい手が出てしまう。 とにかく子供にはなるべく遅く与えねばと思いました
10投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホを排除すればいいとも思えない。 スマホ依存は確かにあるけれど、スマホほど、使いこなせば人生が豊かになるものはないと思う。 と、言ってみたけど、子供が休みの日に朝から晩までタブレットを離さなくなって、タブレット依存症になってしまったので、タブレットを隠してしまった。 タブレットもスマホと同じようなものだよね。 本当に、どうやって、スクリーンタイムをコントロールすればいいんかわからんよ。 制限かけても、子供は、制限をくぐり抜ける技を身につけてきたぞ。 子供に「『スマホ脳』読んでみて」って言ったら、「『スマホ脳』と『ミニマリスト』はちょっと受け入れられない」だって。 『スマホ脳』という新興宗教に洗脳されてる扱いされた。 私が暇さえあれば、タブレットやスマホで電子書籍みてるのも、子供からしたら、同じ依存症でしょうしね。 紙の本に回帰したいけど、ミニマリストにもなりたいしな。難しい。
43投稿日: 2025.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホを使うことによるデメリットやスマホ依存にならないための対策を知ることができて、上手くスマホと付き合いたいと思える作品で面白かった。
0投稿日: 2025.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホ使う時間が増えてから、前みたいに集中力が続かないなと感じていたので、この本を読んで自分だけではないのだとわかって少し安心した。
0投稿日: 2025.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今では電車に乗って本を開いているのは私一人、稀にもう一人いる程度で、社内の老若男女のすべての人はみんなスマホを弄っている。一人だけ時代の流れから取り残された気分になる。 なぜこのような風景が当たり前になったのか?ということに前々から関心があり、その答えを出してくれたのが本書だと思います。 著者は、スウェーデンの精神科医で、人間の脳は、近年急激に発展した社会に適応できていないという考えをベースとして現代社会の問題を読み解いていこうとしている。 原始時代の人間は、食べ物を探すときに、その報酬を得られるかどうかわからなくても、食物を探し続けた。その人間を突き動かす衝動により我々の祖先は、生き延びてきた。 人間に組み込まれた不確かな結果であっても前に突き進む事への衝動。その理由の一つに「ドーパミン」があるという。ドーパミンは報酬物質と呼ばれるが、実はそれだけではなく、最も重要な働きは、何に集中させるかを選択させることだ。つまり人間の言動力の源泉とも言える。 報酬系システムを激しく作動させるのは、金、食べ物、セックス、承認、新しい経験のいずれでもなく、それに対する期待で、何かが起こるかも知れないという期待は、最も報酬中枢を駆り立てる。つまり脳にしてみれば、成果を勝ち取るまでの過程が目当てなのであって、その過程というのは、不確かな未来への期待で出来ている。 その一つの例がギャンブル依存症。脳の報酬システムが、不確かな結果になるのは分かっていても報酬を与えてくれるのだ。 このメカニズムをうまく利用しているのは、ゲーム会社やカジノだけではなく、ソーシャルメディア、SNSも同じだという。 チャットやメールの着信音が鳴る、何か大事な更新がないか、「いいね」がついていないか確かめたいという欲求を起こさせる。その上、報酬システムが一番強く煽られている最中に、デジタルな「承認要求」を満たしてくれるのだ。 ソーシャルメディアのような企業の多くは、行動科学や脳科学の専門家を雇っている。そのアプリが極力効果的に脳の報酬システムを直撃し、最大限の依存性を実現するためにだ。 人間がドーパミンを与えてくれる対象に、意識を集中させるのは、生き延びるために大切なことだった。それが現代のように、一日中、数分おきにちょこちょこドーパミンを補給してくれる対象(スマホ)が出現した。そしてそれをを失ったら、当然ストレス反応が起きる。「ギャンブル依存症」ならぬ「スマホ依存症」だ。 金儲けという意味で言えば、これらの企業は脳のハッキングに成功したのは間違いない。 その結果、現代人は、睡眠障害や鬱病やストレスの障害が発生している。 解決策は、以外と身近なところにあると著者はいう。 ★睡眠を優先し、身体をよく動かし、社会的な関係を作り、適度なストレスに自分を晒し、スマホの使用を制限すること。 この本を読んで、自分の身の回りに起きている事と、人間の進化の過程で組み込まれた脳の仕組みがよく理解できた・・・さあ、出来るだけ屋外での活動に専念しよう・・・とも思うが、この夏の暑さを考えると憂鬱になるのも現実だ。
1投稿日: 2025.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題になった本「スマホ脳」 ジョブズ同様に子供のスマホは制限しないと! 合理的を好む私ですらそう思いました スマホ依存 ・人が1分毎にスマホを手に取りたくなる衝動には理由があった ・記憶力や集中力はスマホのせいで低下する ・眠れない、不安に、鬱に、なりやすい 人間の脳は、1万年以上前から闘争か逃走を選択するように出来ていて ポット出のスマホに対応できるようには出来ていない 麻薬やギャンブルのような特性をもつ魅力的なスマホ 所詮道具ではあるが危険なものでもある 発展途上の子供達の能力に大きな影響も与えてしまう もちろん大人にも 依存しちゃいけない、使われるのではなく道具として使う スマホと脳の危険な関係が理解できるお話でした お子さんの居る若いお父さんお母さんにはぜひ読んでもらいたい
0投稿日: 2025.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホによって失われてしまう時間を惜しまなければならないなと感じた。 情報があふれるほどあるけれども、取捨選択をしていかなければならないし、なにより運動は必要ww
0投稿日: 2025.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「衝動を抑制する前頭葉の発達には時間がかかる。遺伝子よりも環境に影響を受けるので、経験を重ねるための時間が必要」。子ども時代、スマホがなくてよかった。もし1日2~3時間スマホを見た場合、1週間のうち1日を費やしたことになるって怖い。著書は医者でMBAも取得している。知識を得るために使った時間はスマホから離れている時間。これって依存に対する強力な説得力だ。スマホ時間を少しでも身体を使うことに置き換えていきたい。それでも誘惑には勝てないので、自宅ではスマホ置き場を決める(玄関とか)等対策を講じることにする。
0投稿日: 2025.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ記念すべき育休1冊目。 1冊目には自分の生活から切っても切り離せないスマホに関する本を選んだ。仕事をしていない分、スマホを触る時間が増えたので… ①スマホは薬物と同じ。 この本では、スマホの中毒性について様々な研究を根拠に書かれていた。読めば読むほど本当に恐ろしい内容ばかり、、、 スマホやSNSを作り上げたきた人たちの魔の手にこれまでまんまと引っかかっていたのだと痛感。 ②しかし便利なもの。使い方次第。 ジョブズの家庭では、スマホに関わるルールがあるそう。やはり、今の時代、スマホやSNSは生活から切り離せない。だからこそ、ルールが大事。 正直、将来子どもがスマホばかり見ていたらがっかりすると思う。自分だってスマホばかり触っているのに笑 だからこそ親である自分がまずは行動で示そう! ルールも大事。親がスマホばかりなところを見せないことも大事。できるかな? 育休1冊目にふさわしい本だった。
0投稿日: 2025.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間には、「〜かもしれない」という漠然とした不安がある。→HPA系 これがストレスになる 身体は、三代欲求よりも「闘争、逃走」を優先 うつ、は人間の本来の防御システム ドーパミン→選択するまでの誘惑 エンドルフィン→選択して、してる最中のこと 改めてスマホの恐ろしさを認識させられる内容だった。 自分のスクリーンタイムを見てみると、恐ろしかった。。。
0投稿日: 2025.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者、アンデシュ・ハンセンさんは、ウィキペディアによると、次のような方です。 ---引用開始 アンデシュ・ハンセン(Anders Hansen、1974年1月24日 - )は、スウェーデンの精神科医、作家。 ---引用終了 で、本書の内容は、BOOKデータベースによると、次のとおり。 ---引用開始 平均で一日四時間、若者の二割は七時間も使うスマホ。だがスティーブ・ジョブズを筆頭に、IT業界のトップはわが子にデジタル・デバイスを与えないという。なぜか?睡眠障害、うつ、記憶力や集中力、学力の低下、依存ー最新研究が明らかにするのはスマホの便利さに溺れているうちにあなたの脳が確実に蝕まれていく現実だ。教育大国スウェーデンを震撼させ、社会現象となった世界的ベストセラーがついに日本上陸。 ---引用終了 中々の内容ですね。 気になった箇所を一つ挙げると、p142~p144に書かれている箇所で、「デジタルな嫉妬」。 要約すると、昔から人間は競い合ってきたが、かつては、その対象は20~30人位。 だが、SNSがある今では、競う対象が、何百万人? 周りと比較することにより、自信をなくし、自分はダメだと思うようになる。 という感じ。 ま、便利になった反面、生きにくくなったというか。
73投稿日: 2025.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近どん底にいるような気分で、思えばスクリーンタイムが再び長くなっているような気がしていた。どこまで因果があるのかは不明だけれど思考力・集中力の低下も感じる。 これはいけないと萎びた脳が微かな電気信号を発して、この本のところまで連れていかれ、再読に至った。結果的にまた、アンデシュ先生に助けられた。 あたりまえのことで、「スマホが及ぼす最大の影響はむしろ『時間を奪うこと』...」(p. 117)と先生がおっしゃるように、放っておくとスマホは時間を食い尽くそうとする。 そして私たちの多くは人生の限られた時間をスクリーンタイムなんかに費やしたくない。スマホに集中しているときは何か現実を生きていない感じがする。迫力がない。 もちろん、大切な家族・友人とのコミュニケーションのためとか、仕事のためとか、調査のためとか、人生にとって意義のあるスクリーンタイムなら許容できる。 でも私の場合は無駄なスクリーンタイムが多すぎる。直近1週間の記録によると、1日平均で、Youtubeの視聴に3時間。ゲームに1時間。ネットサーフィンに1時間。すべて習慣化サポートアプリ「AppBlock」の記録で、嘘いつわりのない正確な数字。総毛立つほどの絶望。実に5時間以上も毎日スマホを触っているのである… (気づいてから3時間は絶望を続ける) はい、絶望はもうおしまい。早速、不毛な時間の改善プランを考えた。巻末に整理してあるアンデシュ先生おすすめの方法も取り入れ、次のようなアクションになった。 ・「minimalist phone」(一括購入)でスマホのUIを退屈なものに変更 ・「AppBlock」(Premier年額プラン)でYoutube、ゲームの時間を1日あたり1時間に制限(最大でも合計2時間)。またその他見たくないWebサイトの閲覧を禁止に。 ・寝室、仕事部屋にスマホを持ち運ばない まだできることはたくさんあるのだろうけれど、とりあえずここから。スクリーンタイムを減らして、自分の価値に沿った行動に集中していきたい。危なくなったらまたこの本を開く。 なお、この読書特化SNS(?)のブクログの利用時間は有意義だからよしとする。
13投稿日: 2025.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログホントは再読。 脳の報酬系に巧みに取り入るデジタルな誘惑、衝動。ついスマホを触ってしまうという行為がいかに人類にとって抗い難いことであるかわかる。 同時にデジタル化された現代が人類史上いかに特異な時代であるかということも...。大事なものはどんどん見えなくなっていくように思えた。 遅れてるとか、逆行してるとか、ローテクだとか言われても、デジタルな刺激に思考や感覚、感情を売り渡してはならない。 それは適応ではなく飲み込まれているだけだ。
0投稿日: 2025.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スマホを見すぎてるな…って、思ってても、つい開いてしまう。 読書に集中できなくなったり、なんとなく気が散ってばかりの日ってありませんか? 『スマホ脳』は、そんな日々のモヤモヤを、ちょっと距離を取って眺めさせてくれる本でした。 発売は2020年。でも、むしろ今読んでちょうどいい。 内容を一言でまとめると、「脳は1万年前から変わってない」という前提で、スマホに振り回される現代人の行動をやさしく“解剖”してくれます。 印象に残ったのは、「集中力は現代における貴重品」という視点。SNSや通知に反応してしまったり、忙しくてマルチタスクをやってしまう。それは集中力を無駄遣いし、脳を疲れさせるが、脳はそれを“良きもの”と勘違いする。 そして、集中力って努力でどうにかするもんじゃなくて、環境や脳の仕組みを知っておくことが大事なんだなと。歩くとか、運動するとか、寝るとか。一万年つづいた当たり前が大事。 この本を読んだからといって、スマホを手放せるわけじゃないけど、「あ、今ドーパミン出てるな」って思えたら、それだけで気持ちの距離がちょっと変わる気がします。 スマホの時代を生きるために、“人間の原始設定”を知っておく。 そんな感覚で読むと、意外と面白い発見がある一冊でした。
89投稿日: 2025.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ2021年の大ブレイク新書。 タイトル通りの内容となっており、読む前も、読んだ後も「スマホを触りすぎるのは良くない」という意見は当然変わらない。 しかし、確かな科学的根拠に基づいて、人間の体そのものはまだこのデジタル時代にまったく適応しておらず、それとうまく付き合っていくことがこの本のメインテーマとなっており、大変に説得力がある。 運動した方が良い スマホは触り過ぎないほうが良い となんとなく感じていても行動変容が難しい私たちの、最初の一歩を応援してくれる本である。 新書ではあるが、同じことをリフレーズして、また要約して何度も本書の中で提示してくれるので、私のような鈍い読者でも大変読みやすい。 10代必読の一冊。
0投稿日: 2025.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかくスマホが悪影響だということはわかった。併せてデジタル、ブルーライト、等のスマホに関連した悪影響についても記載されていた。 印象的なのは、ポケットに入っていたり机の上にあるだけで悪影響を及ぼすということ。 今となっては結構有名なことが多いかなという印象。運動を続けつつ、ただスマホ自体は便利なので(娯楽抜きで)、ある程度触りつつ距離を取りたいと思った。例えば私は語学学習なんかは明らかにデジタルを使う方が効率がいいので活用している。
0投稿日: 2025.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ進化心理学の観点から感情について考察されていたのが面白かった。 もう何回も読み直しているくらい良い本。 最初に読んだ時より、SNSとはだいぶ距離を置くことができた。
0投稿日: 2025.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
精神的な不調から身を守る方法は3つある。「睡眠」「適度な運動」「他社との関わり」である。 ドーパミンが人間に行動する動機を与えるものであり、それを活用したSNSは脳のハッキングを行っている。 SNSだけでなく、人間のストレスや集中力を高める研究についても触れられており、説得力のある本だった。 本書の最後にはストレスを取り除くためのtipsもある。 個人的にはSNSを意図的にやめたこともあり、それによって自分の時間が増えたこと、心が安定し、やるべきことに集中できた経験もあったので実体験とも照らし合わせることができた。
1投稿日: 2025.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現在生きている人間の脳は、石器時代の脳と考えることは同じであり、現時点ではデジタル社会に対応しきることは難しいとのことだった。 狩猟社会の事を考えながら脳について考えるのは非常に新鮮な体験だった。 アンデシュハンセンさんは大ヒットした前作の一流の頭脳でも同じことを言って今回はスマホに関連させた話になったのかなと推測した(前作は読んでないです)。 私は中学生の頃は運動部に入って忙しかったけど勉強がすんなり入ってきた。 高校生になり、運動部に入らず、かつスマホを手にした。勉強が以前よりすんなり入ってこなくなった。このことに関して、勉強のレベルが上がったからだと思っていた。しかし、本書では運動することで脳が活性化するとの話があった。仕事でへとへとになったあとでもランニングするとストレスが減るらしい。そこが足りなかったのかなと思い出した。 週に3回、45分の運動、息を切らし汗をかくレベルの運動をするのが望ましいとのこと、実践しようと思う。 スマホは集中力を減らす。勉強するときは触らないことを心がけたい。
1投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ今やスマホは私たちの生活になくてはならないものになっているが本当に必要なものなのか。 まだスマホを持っていなかった頃は、暇さえあれば外で遊んだり本を読んだり友達とおしゃべりしたりしていた。しかし、手元にスマホが常にある生活に変わるとそうした時間はいつの間にか無くなり、一人で過ごす時間が増えたような気がする。 今、極力スマホを触らないよう不必要なアプリを削除したり、主電源を切ったり、ちょっとした外出には持ち出さないようにしたりしているが、そうすると今まで散々過ごしてきた生活圏内で新しい発見が沢山あるのだ。これもまた面白い。 人によるのかもしれないがスマホの存在は私たちの生活を大きく変えていることは間違いないと痛感した。
0投稿日: 2025.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
家にいる時間が減ってスマホを使う時間が減り、なんとなくイライラや疲れが軽減されたような気がしたのがきっかけでこの本を読んだ。 手薄になる自己検閲について、自分もそういうところがあったなと思い、注意しておきたい。 運動が知能にいい影響を与えることに納得した。 理由は、受験勉強で部活やっていたときより部活引退後のほうが勉強の量や時間を確保できているし実際勉強しているけれど、なんとなく吸収が悪い感覚があったからだ。 これからスマホのなんとなくの使用と運動について考えたい。
1投稿日: 2025.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログスマホなしでは生活できないが減らすことはできる! そう感じ、実践していきたい本でした。 最後のデジタル時代のアドバイスは簡単そうで難しいことがたくさん書いてあったのでまずここをこなしていきたい。 幸福になるためにはスマホから離れることが1番の近道。
0投稿日: 2025.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ生物学的に見ると、我々の脳はまだサバンナにいる頃から進化しておらず、飢餓にならないようカロリーの高い食べ物に飛びつくようにできている。 同様に、周囲を警戒しないとライオンに襲われるし、カモシカを捕まえられないので、我々には新しい情報を得たいという欲求が備わっている。 ドーパミンという、人間の原動力になる(何に集中すべきかを与える)存在が、私たちにもっといい情報を求めてSNSの画面をスクロールさせる。 「もしかしたら」の瞬間に多くドーパミンが出るので、Facebookなどはいいねがつくのを保留することがあるのだという。まんまと企業の掌で踊らされている。 最初から最後まで面白かった。面白すぎてものすごいスピードで読んでしまって残らなかったので続けてもう一度読んで、それでもメモしたい箇所が多すぎて一旦メモは諦めた。また読む。 自分のSNSとの向き合い方、睡眠改善、職場での若手の育成、子育てなど、色々なものに活かしていけるし、周りの人たちにもおすすめしたい本。
9投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ前から気になっていた本でようやく読むことができました。 スマホやタブレット(パソコンも)を一日に何時間も使い続けるのが、いかに危ないことかがよくわかりました。 運動が脳や精神に影響するのも、納得できます。
0投稿日: 2025.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ4.0 初めて読んだ新書。 自分のことすぎて耳が痛い。 読んだあと、スマホからゲームのアプリを全て消した。
0投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報自体ではなく、情報の保存場所を覚えてしまうという「デジタル健忘」という現象が起こってしまうため、学習内容を"メモ"として残すのではなく、 "アウトプット"出来るよう、使える情報として残さなければならないと感じた。 マルチタスクをすると本来記憶するのに使われる脳の部分使われるのではなく、他の部分使われる。 →うまく記憶できない? マルチタスクはワーキングメモリにも悪影響を与える。また、マルチタスクは集中を頻繁に切り替えているだけであり、切り替えた際、脳は前の作業が頭に残っている"注意残余"という状態に陥る。これではパフォーマンスは低下し、注意残余を抜け出すには数分間時間ががかかる。切り替え時間が必要。 →チャットやメールは頻繁にチェックしない方が良い 〇運動の効果 だった5分の運動(ラジオ体操程度でも)で集中力、記憶力、情報処理、さらに一つのものに集中しやすくなっていた。ゲームも上手くなる。 特にADHDの人に効果が顕著に現れた。
0投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「スマホ」それは我々の生活にはなくてはならないものになっている。しかし、スマホがなくてはならない存在である一方で多少の害をもたらす存在であることも否定できない。スマホを使用することによって精神状態が悪化したり、集中力が減少したりする影響が研究によって明らかにされつつある。実際にスマホが”絶対に“悪い存在であるかは断定できない。しかし、その可能性があるなら我々はスマホとのこれからの向き合い方についてじっくりと考えていくべきだと思う。このままスマホに依存した人々によるスマホに依存した社会が拡大していけば、社会全体の活力が失われていってしまわれかねない。私は人生をスマホという人類における”新種“に奪われたくない。スマホによって死ぬ時にもっと豊かな人生を送りたかったと後悔したくない。だから私は考え続けるし、今を生きる現代人も考え続けるべきだと思う。
0投稿日: 2025.05.11
