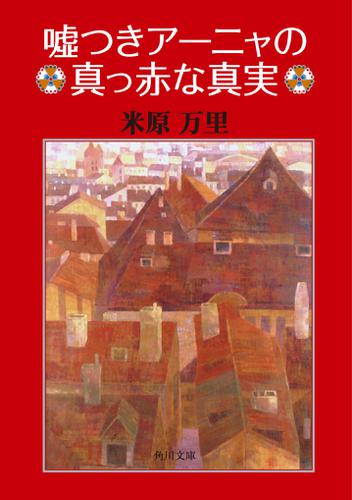
総合評価
(394件)| 197 | ||
| 109 | ||
| 43 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ耳にバナナのコピペの元ネタは「ヨーロッパ退屈日記」だったけれど、「人体の器官にはある条件下では六倍にも膨張するものがあります」ってコピペの元ネタがこの本だったのはびっくりした。 エッセイというよりは小説を読んでいるような心地にさせられる本でした。少女時代を振り返り、友人たちに会いに行く。それがドマラティックでめっちゃ面白い! それと、作者の文体がすごく好き。 章の終わりは友人たちの筆者と会わなかった間の月日を感じて感慨深くなります。 特に好きだったのは白い都のヤスミンカ。所々涙腺にくるところがあった。そういえばユーゴスラビアのこと全く知らないな…。歴史の勉強をしよう
0投稿日: 2019.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者が、共産圏で過ごした少女時代を振り返り、当時の友人3人をそれぞれ訪ねに行く。三者三様。皆、国や時代に翻弄され、それぞれの人生を歩んでいた。 「ちゃんと会えるのか?」「そもそも生きているのか?」と、ドキドキしながら夢中になって読める。 筆者の行動力と感受性の豊かさ、文章による表現力が素晴らしい。友人のキャラクターがしっかりと脳裏に残る。 そして自分の共産圏に関する無知も知った。世界史をきちんと学び直そうと思う。
2投稿日: 2019.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ共産圏に過ごした子ども時代を振り返りながら、また再び友に会いに行ったノンフィクション。共産圏で実際に過ごした方の話を聞いたのは、私にとって初めての経験であり、共産圏の国に住む人、特に子どもたちがどのような考え方をしているのかに触れることができて、新鮮な驚きを感じた。
4投稿日: 2019.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初は下ネタがすごいと思いましたが、1960年代の幼少期の記憶を、周りの友人やその家族の思想まで含めて思い出して書けるのは圧倒的な才能だと思いました。今まで共産主義下の人々について身近に感じることはありませんでしたが、この本を読んでます中・東欧に行ってみたくなりました。
1投稿日: 2019.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ米原さんがこんな過去を持つ人だとは知らなかった。ロシア語通訳で面白い文章を書く人、と言うことしか知らなかった。 共産党とか赤旗とか聞くと、ちょっと避けて通る感じがあるのだけれど、米原さんは堂々とご自身のことを書かれている。 幼少期のプラハでのこと、その同級生との話、困難を極めた再会。 物凄い記憶力!私は小中学生の勉学の内容なんて全く覚えていない! それだけでも目が回りそうなほどなのに、彼女はその年頃でしっかりと同級生の話に対し意見を持ち、なあなあですませずに大人になってからでも、再会の感動に紛れさせずにドンと言うべきことは言う。 読みながら、涙を浮かべながらも凄いなぁ〜と感動した。 そんな友人がいることにも感嘆しかない。
1投稿日: 2019.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代の少女時代をプラハのソビエト学校で過ごした著者。それから30年後、大人になった著者がソビエト学校時代の同級生3人を探しに行ったノンフィクション。 ノンフィクションではあるけど、信じられないくらいに劇的な展開をする。文章の強さも有るだろう。とにかく、最後までページをめくるのを止められない。 リッツァ、アーニャ、ヤスミンカ。3人の友達の思い出と現在を追う話なのだけど、30年の月日にはいろいろなことが有る。特に所謂、"東側"に分類された国をルーツに持つのだから、この30年の激動は想像するのも難しい。 米澤穂信『さよなら妖精』を読んで、ユーゴスラヴィアに興味を持ったのをきっかけに手に取った本だけど、読んでよかった。
1投稿日: 2019.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ大宅壮一ノンフィクション賞、解説:斎藤美奈子 リッツァの夢見た青空◆嘘つきアーニャの真っ赤な真実◆白い都のヤスミンカ
0投稿日: 2019.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい本。これまで日本で教育を受けてきて、歴史とかも日本とか資本主義目線でしか勉強したことなかったけど、世界が広がる本。 ソ連での生活を子どもの目を通して日本語で残してるすごく貴重な話。 中欧での人種差別の話とか国を転々とした同級生の話とか、祖国に憧れ続けた友人の話とか、海外に行ったことのないわたしにはすごくキラキラした話だった。明るい話が多いわけではないのに。
1投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ共産主義時代の東欧諸国それぞれの国の大まかな雰囲気を感じられた。歴史すべてや、またそれらの国の人々それぞれの受け止め方を全て理解するのは難しいけど、理解しようと努めることの大切さを感じられた。共産主義も平和と平等を目指した高い理想のままに進むことができたなら現在の世界はどんな風に変わっただろう?
0投稿日: 2018.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ今現在、アフリカからヨーロッパに難民が押し寄せ世界的な問題となっている。民族や宗教で争いが起きている。そうだった。ソ連崩壊に伴い東欧では民族紛争があったんだとこの本で改めて思い出す。自分の属性に囚われず友人隣人達を一人の人として仲良くすることが大切と米原氏は教えてくれたような気がします。
0投稿日: 2018.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ。米原さんがプラハ・ソビエト学校で学んだのは10歳から15歳の1960〜64。約50カ国もの国籍を持つ子供たちが学んでおり、子供たちはそれぞれに自国を愛する気持ち強くを持っていた。チェコにおけるプラハの春は米原さん帰国から4年後の1968年。ワルシャワ条約機構軍の戦車がチェコを占領し改革派を弾圧。各共産国の中でチャウシェスク政権初期のルーマニアはソビエトと距離を取り始めており、プラハの春弾圧にルーマニアとアルバニアだけは加わらなかった。当時アルバニアは中国寄りであり、当時日本共産党はソ連、中国との関係が最悪になっていたので東欧諸国の兄弟等の中でルーマニア労働者党は日本共産党にとって唯一おつきあいの成り立つ党であった。しかしその後チャウシェスク政権による独裁と国家の私物化により混乱、1995年に米原さんがルーマニアを訪れた時の国の荒廃ぶりは1989年に終わりを告げたチャウシェスク政権の名残りであった。チャウシェスク後も共犯の証拠隠滅のためチャウシェスク夫妻を急いで処刑し、党幹部は特権を持ったまま。1989年12月21日の建国記念日の大集会がチャウシェスク政権打倒の暴動に変わった。ビロード革命。 イディッシュ語は、ユダヤ人のもともとの母語であるヘブライ語と彼らが住み着いた中部ヨーロッパの言葉を融合させてできたとされる。 ユーゴスラビア連邦初代大統領はチトー。1960〜63まではソ連は反ユーゴ。「ユーゴは社会主義を騙るほとんど資本主義国である」という理由。 本文はもちろんのこと、斎藤美奈子さんの解説がとても良かった。
1投稿日: 2018.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ中欧での激動に揉まれた青、赤、白の3人の友達の昔と現代が、米原万里本人の経験からミステリーのように解き明かされていく。民族とは、普段日本にいる限りではあまり考える事がないテーマだが、この本を通じて大きく考えさせられた。 軽快な語り口を通じて、普段触れる事がないテーマにたくさん触れることができ、非常に心に残った名著であった。 あとがきの、「我々に求められているのは、具体的に生きる誰かに対する想像力」と言う文章はまさしく、対立の世界を和らげるために重要な事だと感じた。
0投稿日: 2018.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログどんどん引き込まれていく文章であった。 ただ自分に世界史の知識が不足しているためイメージがなかなか膨らまない部分が多かった。 物事の本質を掴むにはやはり知識が必要だと改めて痛感した。
0投稿日: 2018.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ソ連邦が崩壊していく時代。 音信不通となってしまった同級生達は激動期を無事に生き抜いたのだろうか…。 子供の頃、1960年からの5年間をチェコスロバキアの在プラハ・ソビエト学校(なんと50ヶ国以上の国の子供達が通っていた)に通っていた米原さんの体験記。 特に仲の良かった3人の少女との付き合いは、ごく普通の日本でもありそうなたわいもないもの。 けれど日本と決定的に違うのはみんなの故国への愛着の強さ。 愛着の強さで印象深かったのは、内戦が続く南米ベネズエラから来た少年の言葉「帰国したら僕らは銃殺されるかもしれない。それでも帰りたい」。 日本に帰国した米原さんが、30年ぶりに女友達3人を訪ねて行く場面はドキドキしながら夢中で読んだ。 生死も不明で情勢も未だ不安定な国でも、とことん調べあげて逢いに行く米原さんの行動力には感服する。 戦争や紛争により否応もなく意識せざるを得ない己の属する「民族」。それまで仲の良かった仲間ともギクシャクしてしまい壊れてしまう人間関係。 民族、文化、宗教等様々な問題について考えさせられる。 米原さんのリアルで生き生きとした文章に頁をめくる手が止まらなかった。
10投稿日: 2018.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が1960年から1964年までを過ごした在プラハソビエト学校の同級生の友達3人に30年後会いに行くエッセイ。解説にもうひとりの主役は歴史、とあるように激動の東欧共産主義国の歴史を語るものでもある。特にルーマニアで特権を享受している共産党幹部の娘アーニャとユーゴスラビアの民族紛争に巻き込まれたヤスミンカの話はイデオロギーや権力の争いに巻き込まれた人間が運命の荒波に揉まれている有様が強烈に迫ってきて圧倒された。 異国の地で異国の人々と出会うとナショナリズムに目覚める、という節は印象に残った。 シリアスな話が多いが子供心や冒険心・背伸びした下ネタ・他愛ないやり取り・ユーモアがたっぷりあってとてもいい本である。
0投稿日: 2018.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ少女時代を父親の仕事の関係から共産国に住むことになった作者。いろいろな国の友達に出会い影響を受けたのだと思う。大人になって自分が置かれた特殊な立場を実感し、友達の現在を探す。複雑な環境の中で、それぞれが仕事を持って、強く生きていく姿に感銘した。
0投稿日: 2018.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ親の仕事や都合により子供がその世界をどう受け取るのか…。外国と左派という点ではコルシア書店の話にも似ているが、多感かつ語学能力の伸びる(らしい)時期にロシア学校という特殊な環境に置かれた著作の話、面白かった。でもソ連の崩壊やそれに関連して生じた諸所の問題を受けてソ連に反感を抱くわけではなく、当時を愛おしい気持ちで眺められるのは、彼女が父親の仕事や姿勢へ尊敬の念を抱けていたからに違いない。
0投稿日: 2018.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ地図を開いて、都市や国の名前をたどりながら読んだ。だけど、とっつき難い本ではなく、10代前半をともに過ごした同級生を大人になってから訪ねる物語だ。 ただし、母校はプラハのソビエト学校で、同級生はそれぞれの祖国を持ち、父親が共産主義者として高い地位にあるという家庭出身だ。 筆者である主人公が帰国してから、東側諸国は様々な動乱を経験し、同級生たちは、その荒波の中、それぞれの人生を歩んでいる。国の騒乱が個人の人生を大きく左右することを見せ付けられ、平和ボケの身は冷や水を浴びせられたよう。そして、彼女や彼女の家族の無事を祈りたくなる。 歴史を精密に記録した物語としても、人生を生き抜くひとりの女性の物語としても、読みごたえのある作品だと思います。 そして、この本が世に出てから、さらに歳月が流れ、彼女たちがどこでどんな人生を送ったのかと思わずにはいられない。
0投稿日: 2018.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログオーディブルで聞きました。 まったく馴染みのなかった、東ヨーロッパの社会体制や、それにまつわる影響について、思いがけず知ることができました。 プラハの子ども時代の視点と、大人になって再会しその後の人生についての語りで、多くの驚きがありました。 国や民族に翻弄されるとはこのようなことかと、知ることができました。
0投稿日: 2018.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代日本という資本主義国のただ中に生きる私にとっては、想像もできない特殊な環境・特殊な世界を生きた米原さんと3人の友人の、当時と今を追ったノンフィクションエッセイ。エッセイに分類されているようだけれど、エッセイではない。かといってご本人だからルポやドキュメンタリーでもないし、読み物としても下手な小説なんか足元にも及ばないほど面白い。 ちょうど直前に読んだ本もプラハのお話だったので(米原さんのプラハ時代から20年くらい前のお話だったけど)そのころの時代の流れが上手く繋がってすっと時代に入っていけた。私はあまり共産主義のことは詳しくないけど、その時代の空気や米原さんの過ごしたプラハの美しさ、政治的な背景などを行間からありありと感じることができたし、友人たち3人の個性もとても丁寧に描かれていて素晴らしかった。1日で一気に読んでしまったけど、最後のヤスミンカのお話の終わりに差し掛かると、終わってほしくないという気持ちが大きくなっていったなぁ。共産主義と時代に翻弄された登場人物ひとりひとりが愛おしくなる、優しい作品。 米原さんはお名前は存じていた、けど、ロシア人通訳者としてお名前を知っていただけで、こんなによい文章を書かれる方だとは知らなかった。他の作品も読んでみよう。 ちなみにYoutubeに、米原さんのこの東欧・中央探訪の動画があるのを発見(本当に、時代に感謝!)したので、そちらも追って拝聴します。 -- 一九六〇年、プラハ。小学生のマリはソビエト学校で個性的な友だちに囲まれていた。男の見極め方を教えてくれるギリシア人のリッツァ。嘘つきでもみなに愛されているルーマニア人のアーニャ。クラス1の優等生、ユーゴスラビア人のヤスミンカ。それから三十年、激動の東欧で音信が途絶えた三人を捜し当てたマリは、少女時代には知り得なかった真実に出会う!大宅壮一ノンフィクション賞受賞作。
0投稿日: 2018.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が暮らしていた状況とは全く異なるが、私も海外で生活する者として共感できる部分がたくさんあった。 中・東欧の歴史や地理に触れる良い機会となった。
0投稿日: 2018.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2018年7冊目。笑って泣けて、そして勉強になりました。「白い都のヤスミンカ」が特に好き。中・東欧の現代史にもとづく小説かな?と思っていたら、少女時代をプラハのソビエト学校で過ごした著者の実話でした。 冷戦下、50か国以上の子どもの中で暮らすと、中学生くらいでも世界情勢に詳しく、敏感になるものなのかなあ?たまたま、米原さんや周りの友人たちが、大人びていただけのようには感じられません。 30年ぶりの、それも奇跡的な再会には、思わずうるうるしてしまいました。少女時代の楽しい思い出も、悲しかった出来事も、別れた後それぞれが歩んできた人生も、全部ひっくるめての再会。 異国、異文化、異邦人に接したとき、人は自己を自己たらしめ、他者と隔てるすべてのものを確認しようと躍起になる。自分に連なる祖先、文化を育んだ自然条件、その他諸々のものに突然親近感を抱く。(p128) なぜ、差別無き平等な理想社会を目指して闘う仲間同士のはずなのに、意見が異なるだけで、口汚く罵り合い、お互いが敵になってしまうのか。(p212) どんなに悲しいことも一緒に悲しんでくれる人がいることは嬉しい。(p231) 爆撃機の操縦士たちは、トルコ軍の兵士のように、「白い都」の美しさに魅了されて戦意を喪失することはなかった。(p292)
1投稿日: 2018.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ私にとって、珠玉の本の中の1冊。 ロシア語の通訳として長年仕事をされていた方が晩年、作家さんになって書かれた本。ノンフィクションです。 1960年代、まだ資本主義と共産主義で世界が割れていた時代 主人公のマリは、共産主義の理想を信じた家庭に生まれ、父の仕事の関係で、共産主義の大国であったソビエト連邦で幼少時代を過ごします。 マリの通った学校は、世界各国からソビエト連邦に集まって来たそれぞれの国の「共産党幹部」の人達が自分の子供を通わせていたところでした。 マリはそこで、いつの時代も変わらない「男の子にモテるための方法」を女の子同士で話し合ったり、授業に使う素敵なノートを探しに行ったり、今の私達にも共感できるような「青春一歩前の少女時代」を過ごします。 時代が変わってもきっと普遍的に存在し続ける、思い込みや恥じらいや見栄などがたくさん混じった、子供と少女の境目の世界の中に、今のわたしたちにはけして体感できない世界情勢が複雑に入り混じります。 「国に帰ったら、きっと家族全員殺される」と言いながら故郷の美しい景色を夢見るように語る子がいる。 共産主義の「平等」の理想を誇りをもって語りながら、家に住み込みのお手伝いさんを雇い、ブルジョワジーな「特権階級」としての生活を送る子がいる。 ちぐはぐで、あやうくて、だけどみんな信じているものがある。 やがてマリは、父の仕事の都合で日本に帰ります。 帰国の時、泣いて手紙を交わそうと約束した友達たちとも、もうすっかり縁の薄くなってしまった30年後。 マリはかつての旧友たちに会おうと決意し、各国を訪ね歩きます。 子供の頃には見えていなかったこと、信じていたこと、そして気付いていなかったこと。子供の視点で語られていた世界は急に大人の現実と30年の重みをもって「マリ」にたくさんの嘘と真実を見せます。 タイトルにもなっている「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」と「白い都のヤスミンカ」 どちらも本当に秀作です。
0投稿日: 2017.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の知識不足を恨みながら読みました。 3人の友人との再会を、激烈な現代史とともに。 少女時代の友情の気配はとても懐かしく感じられました。
0投稿日: 2017.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年プラハ。マリ(著者)はソビエト学校で個性的な友達と先生に囲まれ刺激的な毎日を過ごしていた。30年後、東欧の激動で音信の途絶えた3人の親友を捜し当てたマリは、少女時代には知り得なかった真実に出会う!
0投稿日: 2017.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ作家であり、ロシア語の同時通訳者でもある著者。1950年生まれの彼女は、10代にさしかかろうとしていた1960年から1964年まで、父親の仕事の関係でチェコへ。プラハにあるソビエト学校に通いました。本作はそのソビエト学校で仲の良かった3人、リッツァ、アーニャ、ヤスミンカとの思い出とともに、後に著者が彼女たちに会いに行ったときのことを語っています。 ギリシャを故国に持つリッツァ。ルーマニアの要人の娘であるアーニャ。ユーゴスラビアから来た転入生ヤスミンカ。著者と彼女たちは仲良し4人組だったわけではなく、『リッツァの夢見た青空』、『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』、『白い都のヤスミンカ』の3編に分けてひとりずつとの関わり合いを。思い出といっても、激動の時代だった東ヨーロッパ。共産主義に振り回された彼女たちの日々は知っておきたいことばかり。一語一語を噛みしめて読もうという気にさせられます。愛国心についても考えさせられる珠玉のノンフィクション。
1投稿日: 2017.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
多感な少女時代をチェコのソビエト学校で過ごした著者による私小説。「リッツァの見た夢」「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」「白い都のヤスミンカ」の三編を収録し、各編のタイトルに採られている人物が著者の友人であり、彼女達のバックグラウンドや心情から、見事に当時の時代を切り取っている。下手な歴史教科書を紐解くよりもダイレクトに伝わってくる一市民の生活が重い。ちょっとこれ、本人が読んだら怒るんじゃないという程の本音が覗けるのも当事者ならではだろう(特にアーニャ編)。この人でしか書き得ない経験と感情は実に貴重。よくぞ本にしてくれたという気持ちである。
0投稿日: 2017.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ両親が共産主義で、その関係で、少女時代をプラハのソビエト学校で、過ごした。変わった経歴を持っています。そのソビエト学校では、世界中から、子供たちが集まって、勉強をしていた。その中で、親しい友達がいたが、日本に帰ってから、ソビエト崩壊、東欧の変動を経て、かつての友達を訪ねていく話、実際の話であるが小説のように面白かった。政治的な対立が学校生活の中にも影響を及ぼしている部分が面白かった。また、このような変動を経ても、それなりに生活している。また、以前の特権階級が、共産主義の崩壊によって、困っているかというとアーニャのように、特権生活を享受しているところが面白かったです。
0投稿日: 2017.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ米原万里さんの少女期を書いたエッセイ。社会主義、共産主義の理想と現実を多感な時期に経験し、その後の世界情勢の激変に翻弄される人々。オリンピック後のサラエボの激変に 驚いた事を覚えている。
0投稿日: 2017.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイストでありロシア語通訳だった、米原万里さんの少女時代のお話で、米原氏が通っていたチェコスロバキアのソビエト学校が舞台の作品。 日本人のマリ、ギリシャ人のリッツァ、ルーマニア人のアーニャ、ユーゴスラビア人のヤースナ、彼女たち4人は同じ学校に通うクラスメイトだった。国籍も民族も母国語もバラバラなのだが、彼女たちの絶対的な共通点は、親が各国の共産党員という事である。 作品はマリの友人3名分のエピソード3章で構成されている。プラハソビエト学校時代の出来事や、マリが帰国してからの手紙を通じた交流の様子。そして様々な理由によって音信不通になってしまうまでの経緯と、大人になってから友人たちを探す旅の様子が綴られている。 音信不通となった大きな理由は、社会主義大国だったソ連と中国の対立、ソビエト連邦の崩壊、そしてボスニア・ヘルツェゴビナ紛争、などである。一部指導者の歪んだイデオロギーや、過剰な民族感情が罪のない人々を巻き込み、少女たちの人生を狂わせてゆく理不尽さにとても切ない想いがした。旅の結果については、ネタバレになってしまうので詳しくは書かないが、マリがヤースナを探しに紛争中のバルカン半島へ渡り、真相に迫るシーンは非常にスリリングだった。 そして、アーニャが嘘つきだったのは決して保身のためではなく、複雑すぎる体制や家庭環境からの自己防衛だったのではないだろうか、マリにもわかってほしかったと思う。
0投稿日: 2017.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2004(底本2001)年刊。 10~14歳まで(1960~64年)、プラハ・ソビエト学校への通学歴を持つ著者(生前はロシア語通訳者)。本書は当時の学友、つまり①ギリシャ系チェコスロバキア人のリッツァ(西独地域で開業医。父はギリシャからの亡命者)、②ユダヤ系ルーマニア人のアーニャ(英国男性と婚姻後同国で編集業。父はルーマニア高官)、③ボスニア・ムスリム系ユーゴスラビア人のヤースナ(元外務省通訳・翻訳官。父はユーゴのチェコ公使、後にボスニア最後の大統領)との交友回想録。 加え、旧交を温める旅と彼女らの人生行路を描く。 これほど広範なかつ稀有な交友を有している著者に驚くとともに、この3名の来し方が激動の東欧(これは嫌がるらしい。中欧と称してもらいたいとのこと)の現代史を浮かび上がらせる。 ①はプラハの春とその崩壊、②はベルリンの壁崩壊に引き続くチャウセスク政権崩壊、③はユーゴ解体とボスニア紛争。 当時の東欧としては豊かな階層に属していたからかもしれないが、知性・教養溢れる少女らの精一杯の生き様もまた本書の魅力の多くを構成している。 もっと早く読んでおくべきだった。 亡命しないのとの問いに「ボスニア・ムスリムとしての自覚は欠如…。ユーゴ…愛着…。国家としてではなく、たくさんの友人、知人、隣人…。その人たちと一緒に築いている日常がある…。…それを捨てられない」との回答。 一方で「異国・異文化・異邦人(ただし、これは国境の内外で区分したのとは限らない。受け手の年齢や経験で異別・隔意の存在と認識・直感した場合も同様)に接したとき、人は自己を自己ならしめ、他者と隔てる…ものを確認しようと躍起に…。自分に連なる祖先や文化を育んだ『自然条件』…に突然親近感」と、含蓄ある表現が随所に表れる。
0投稿日: 2016.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログかつてプラハのソビエト学校で著者の同級生だった3人の少女とその後の人生を通じて、 20世紀後半の中東欧の歴史的・民族的な混乱を描く。実在する人物だけにリアリティがある。 貧富の格差や紛争、思想的矛盾が浮き彫りになる。ただ、どんな形であれ家族を持ち大切な人らに囲まれて懸命に生きている姿が印象的だった。 ある時代の流れに少女達の運命が決められていく。これは、この本に登場している人だけでなく、同時代を生きた同世代の人達にもあったことなのだろう。日本でこれほどお国の事情を意識したことはなかった。
0投稿日: 2016.12.13嘘のような、本当の話。そして人生は続いていく。
当時の共産圏の様子を、子供目線で綴った貴重な回想禄。賛否はあれ、大好きだった個性的な3人の友人。それぞれの人生の足跡を辿った旅の記録です。フィクションのようではありますがこれはノンフィクション。ぐいぐいと引き込まれて久々に一気読みをしてしまいました。某ドキュメンタリー映像でこの時の旅の様子が見れますがリアリティはこの本の半分くらいにしか満たないかも。クラスには一人はいそうな、おませで憎めない陽気なリッツア。数々の矛盾を抱えるユーゴスラビア高級官僚の娘、アーニャ。自分の意志に忠実な、一見クールなヤスミンカ。三人三様で彼らの性格や家庭環境は違うのですがその仲良しだったマリ。限られた時間で、各自の足跡がよくここまで辿れたと思います。映像では描ききれなかったアーニャの矛盾が、詳細に書かれています。題名にもなっている「真っ赤な嘘」は共産党の赤、の意味も込められていますね。この作品を読んで、米原万理という魅力的な人をもっと知りたくなりました。
1投稿日: 2016.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ惜しくも2006年に死去した著者の代表作。1960~64年の間に滞在したプラハでのクラスメイトの思い出と後年の再会の模様を描いている。 文章が読みやすく、人物描写がうまいので、話にどんどん引き込まれていった。 今更ながら惜しい人を亡くしたと思った次第。
0投稿日: 2016.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ作品の舞台であるプラハのソヴィエト学校は各国の共産党エリートの子弟が通う学校。作中では触れられていないけれど、著者の父である 米原昶だって、プラハ赴任の時点で元衆議院議員の経歴を持った政治エリート。そのような特殊な環境が舞台だから、描かれた日常からも歴史の重みを感じることができて、惹きつけられました。 イデオロギー、ナショナリズムや民族意識といったテーマも、一般の日本人の感覚とは違う角度から掘り下げられていて、一読の価値ありだと思います。
0投稿日: 2016.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
素晴らしいエッセイ。著者とその友人の関係という狭い社会と、冷戦時代の国際関係という大きな枠組みが絡み合って物語が紡がれていく。日本人にしてみるとソ連はまだ教科書などで見覚えがあるが、チェコなど東欧の衛星国となると何も知らないという人が大半だろう。そんな認識すらされていないような国でも、そこにはそれぞれの暮らしがあって、学校があって、著者をはじめ50を超える国の子供たちが学んでいたという事実になぜか感動した。 社会主義国の政治、暮らしにはマイナスイメージしかなかったが、このエッセイを読むことでそのような表面的な知識、認識から一歩先に進んでリアルな人々の生活や考え方を知ることができた。そこには社会主義が抱えていた貧富の格差という矛盾も確かにあったが、日本と変わらないところも多いと感じた。 そして何より著者と彼女の友人との友情に胸が熱くなった。
0投稿日: 2016.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ多感な時期をプラハという極めてややこしい場所で過ごすことが、これほどドラマチックな学友との再会ドラマを生む。多様な人種のるつぼの中、国家、民族、宗教…の差異は容赦なく人間関係を引き裂いていく。自分も含め、日本人は総じてこのような差異に鈍感だと思うが、それは良くも悪くも幸福な場所にいることの証左なのだろう。 「幸せは、私のような物事を深く考えない、他人に対する想像力の乏しい人間を作りやすいのかもね」と。この幸福のつけが我々に回ってくることは、今後無いだろうか。
0投稿日: 2016.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ中華学校に通っていた友達からお勧めされた本。 なんでだろう、その友達のことがもっと好きになった。 作者の3人の友達それぞれ、とても素敵で魅力的。 珍しい少女時代を送った作者が、プラハの春を経て成長した旧友に会い、感じたこと。 ナショナリズムとか、繊細な話だけれど、ただ感じたことを素朴に書いただけで、分かりやすく、考えさせられる本だった。 リッツァみたいな無二の親友とか、アーニャみたいな友達思いな子とか、ヤスミンカみたいに魅力的な人とか、良い友達ってこういうことだと思う。
0投稿日: 2016.08.04現実は小説より奇なり?
リッツァ、アーニャ、ヤースニ、それぞれと長い年月を経て再開する内容の小編集。どれも、東西冷戦下のプラハで学んだソビエト学校時代、冷戦崩壊後の現実を生きる再会編という流れです。 ソビエト学校の面々は、様々な国から集まっているだけに国際色豊かで、それぞれを生き生きと描写しているのが興味深いです。 また、共産主義社会に生きる人々の現実を、作者さんの皮肉を効かせたユーモアを交えて書かれていて、無味乾燥とは無縁で、自然とページを繰る手が早まってしまいます。 作者さんは、父親への想いから、やや共産主義に対して教条的なところがあり、社会の矛盾や建前には厳しいです。それだけに、うまく立ち回った観のあるアーニャへは若干突き放してます。そのアーニャを表題に持ってきたのはなぜか、ということは、読み進んでいけば自然にわかるようになっているように思います。 しかし、作者さんのバイタリティには脱帽です(笑)。
1投稿日: 2016.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に面白くためになった。 著者の日本人を含め、様々な国のバックボーンをもつ少女たちの交流を描いた自伝的ノンフィクション。 共産主義やイデオロギーの対立などの大人の都合で翻弄される様子やそれぞれの少女がいかに捉えて生きていったのか。 まるで自分がその場にいるかのように追体験する事ができる。 歴史書を読むよりも現場に生きた人の声の方が遥かに生々しい。
0投稿日: 2016.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の知らない現実についても少しは知らなきゃいけないと思い、フィクションだけでなくノンフィクション小説にも手を出すことにした。その第1冊目である。 最近はずっと自分個人に意識が向かっていて、読む小説も個人的な葛藤を描いたものに偏っていた。そのため、民族や国家という大きな規模の問題に巻き込まれる人々の生の声を書いた本書は、より俯瞰的な視点を与えてくれるように感じた。旧友との感動の再会にも喜びだけでなく価値観の相違を目の当たりにするなど、フィクションにはない現実の味わいがあった。 社会主義と資本主義の対立、民族紛争、人種差別。在プラハ・ソビエト学校時代の旧友との対話により明らかにされるのは、こうした大きな枠組みの問題に人生を左右されることの理不尽さと不幸である。当事者の口から語られる体験や想いにはずしりとした重みがあった。枠の大きな問題も細かく拡大して見れば、そこには常に一人一人の生身の人間がいて、個々の信念や立場があり、それぞれの感情を抱えているということを実感させられる。『抽象的な人類の一員など一人も存在しない』という言葉に大切にすべきことがすべて詰まっていると感じた。そして、社会というのは巨大すぎて抽象的なものと捉えがちだが、個人からなる具体的なものであると気づかされた。
3投稿日: 2016.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ帰国子女だった経験があったり、激しい転校や転居をしたことがある人には、特別に心に沁みる1冊だと思います。 ...って、そんなに間口の狭い本ではありません。 子供時代を思い出す時に、子供時代だけではなくてその後それぞれ大人になって、色んなことが歳月を味つける。 甘かったり苦かったりする、そんな当たり前な想いを抱ける人は、全て共感できるのではないでしょうか。 外国、プラハで過ごした子供時代。色んな国の子どもたちとの友情。 異国だからこそ、自分の国に誇りを持ちたい子供たち。 自分の国を「素敵な国」だと思いたい子供たち。 でも、それぞれの家庭にそれぞれの事情があって。 あれから数十年。 ため息がでるほど素敵な暮らし、恵まれた暮らし、一部の人から見れば腹立たしいくらいにセレブでカッコいい暮らしをしている人もいます。 一方で、流転の運命、傍から見れば没落...みたいな人もいます。 そして、意思的に、ずるをせず、自分の国や町の運命とともに歩んでいる人もいます。 少女たちは、東ヨーロッパという場所で過ごしました。 少女たちの、10代から40代という時間は、哀しいくらいに政治的な季節でした。 本来、政治的なることのど真ん中にいることない、女性たち。(その頃はまだまだ、女性政治家など激レアだった訳です) でも、政治的なることというのは、そういう彼女たち、そしてその子供たちの身に大きく降りかかってきます。 そんな当たり前のことが、とてもドラマチックな一冊。 2001年に発表された本だそうです。 米原万理さん。2006年になんと56歳で逝去されてしまった作家さん。 もともとは、通訳さん。政治家の会議の同時通訳とかされていたそうです。詳しくないですが、ということは、相当に通訳者の中でも最高レベルの人だったんでしょうね。 職業が、それなりに「へー、面白そう」という変わった職業だからか、 エッセイ、雑文みたいなものを90年代から書かれていて、それがもう、大変に面白くて、事実上作家さんになられたようですね。 あまり読んだことがありませんでしたが、この「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」、びっくりしました。傑作でした。 「自伝的エッセイ」とも「自伝的小説」とも言えるような内容です。 語り部は、米原万理さん自身。 お父様が、日本共産党所属の国会議員さんだったそうです。過剰に共産党を嫌う人もいますから、「セレブな育ち」と言っていいのか、微妙なところですね。 そして、お父様がの仕事の都合で、9歳から14歳まで、チェコスロバキアのプラハに住んで、現地で「各国から来たそれなりにVIPの子どもたちが通うような学校」に通っていたそうです。 この体験と言うのは、ご自身が望んだわけではありませんが、ドラマチックなんですね。 だって、1959年~1964年、くらいの時期な訳です。 世界史的に見て、冷戦マックスばりばりの時期なんですね。 その時期に、「思いっきり東サイド」で、あどけない時期を過ごすなんて、とてもレア体験です。 そしてこの本は、この少女時代に、このプラハの小学校で過ごしたお友達との再会を描いています。 全て、東欧革命以降、つまり価値観がガラガラポンになっちゃった、そんな後の時代での再会です。 三つの中編からなる、1冊です。 どのお話も、なんというか... 「重くなり過ぎないような語り口」。 怒りもあるでしょう。悲しみもあるでしょう。でも、感情的になりすぎない様な、実に叙事的な文章。 何しろ、実話です。その重みがあります。 そして、大変にドラマチックな人々の、ドラマチックな季節の話なのです。 そこで抑制された、言ってみれば小津安二郎さんの映画のような話法を守り抜く矜持が、美しく、それが、この本を「あたしにこんな事件があったのよ」という自慢エッセイではなく、 何かしら普遍的なブンガクという芸術に持ち上げていると思います。 トリュフォーの映画「思春期」。 小津安二郎の映画「生まれてはみたけれど」。 木下恵介/高峰秀子さんの「二十四の瞳」。 ジョン・フォードの「わが谷は緑なりき」。 子供の目線を通した、素晴らしい物語がいっぱいありますが、「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」、も、その行列に並ぶ美しい本でした。 こんな本を21世紀の日本人が書いたんだなあ、と思うと、何だかとっても嬉しくなりますね。 同時に、米原万理さんの早世が惜しまれます。 つくづく。 ###以下、備忘録### 「リッツァの夢見た青空」 ギリシャから来ていた、「リッツァ」という女の子。 ませていて、イケメンのお兄さんもいて、性の知識も豊富だった。 そしていつも、自分自身良く知らないギリシャの青い空を賛美していた。 ようやく探し当てたリッツァは、ドイツで医者をしていた。 リッツァの父は、「プラハの春」への武力介入、まあつまりソ連のやり方に反対したせいで、家族もろとも白眼視された。 兄は悪い女と結婚して、人生がめちゃくちゃになっていた。 憧れていたギリシャは、男尊女卑のひどい、リッツァには耐えられない国だった。 「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」 細かい嘘をついてばかりいた、アーニャ。 チェコスロバキアの支配者層の娘。 子供のころから、バリバリの社会主義者みたいなことを言っていた。 つまりは、独裁者チャウシェスクに近い位置に父親がいる。 革命がおこり、チャウシェスクが殺され、国が滅茶苦茶になり。 さぞ苦労しているかなあ、と、思ったら。 ロンドン留学、ロンドンで結婚、実にリッチに幸せにしていた。 そして、両親も、大邸宅で何不自由ない暮らし。 つまり実は、「権力者、支配者ほど、チャウシェスクは長くない、と見切って、特権を利用して家族を西側で育てていた」 「チャウシェスクが裁判を受けず殺されたおかげで、チャウシェスクの権力構造は残った。残党が相変わらず、不当に豊かに暮らしている」 ということが判ってくる。 そして、アーニャは、そんなことを、見て見ぬふりというか、自分が不当に恵まれている、という自覚なく、暮らしているのだった。 「白い都のヤスミンカ」 ユーゴスラビアから来ていた、ヤスミンカ。 地理の時間に、ベオグラードのことを美しい白い都、と語っていた。 絵が好きで、北斎が好きだった。 ユーゴスラビアは、ソ連と方針が合わないことが多く、学校でも差別された。 ユーゴの混乱の季節の後、数十年ぶりに巡り合う。 内戦がはじまって、ムスリムの家系だった彼女は、外務省の仕事も居づらくなって辞めた。 ヤスミンカは、つつましく家庭を持ちながら、自国の運命と向き合って暮らしていた。 「特権階級アーニャ」に疲れた米原さんは、ほっとします。 だけど、そんなヤスミンカのベオグラードに、NATOが爆撃をすることになる... 大まか、そういう内容だったはずです。 ######## ※角川文庫版、表紙の絵が素敵です。
2投稿日: 2016.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生の頃に読んだ米原万里は難しくて挫折した。10年の時を超えて彼女の文章に触れたら、なんだこんなに面白いなんて。 外国といったら洋も欧も東も西もぜんぶ一緒だったあのころ、知識と興味が大きく欠如していたのだな、と自覚する。 友人たちも、マリも、なんて魅力的なんだろうと一気に読みふけってしまった。
0投稿日: 2016.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと気になっていた、近代中東欧のノンフィクション。 狭い世界で、この目で見て肌で感じ、信じられるものは限られていると思うけれど……歴史はいつでも地続き。繋げてくれる一冊。
0投稿日: 2016.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログぼちぼちでしたね。 ノンフィクションの作品ということでよんでいましたが、きっと良いことだと思いますが、なんとなく物語的でとてもよみやすかったですね。 ただ、読むタイミングが悪かったのか、政治や国際情勢にあまり知識がなかったからなのか、気持ち的に、はまることができずに読み終わりました。 それでも、それぞれの友達との再会のシーンは理想と現実のギャップの重さが感じられてよかったですね。
0投稿日: 2015.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ政治、宗教、民族の影響を受けて、大人になって再開した米原さんの友達。 大きな力に翻弄され、その力への怒りを始めとした思いを持つ彼女たちと、大きな力がそれほど強くない日本で育つ私たち。どちらが幸せなのかは決められない。でも、両方の存在を知っておかなければいけないと思う。 また社会主義が破綻してしまったことに、人間がどうしても自己利益に走ってしまう、弱さを実感した。 単純にエッセイとしても楽しめるし、考えさせられるところも多い一冊。
0投稿日: 2015.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ中欧・ユーゴスラビアにきっかけを持つための一冊として良い本。自分の知っている世界と違う光景が見えておもしろかった。
0投稿日: 2015.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が少女時代過ごしたプラハ、ソビエト学校で出会った親友3人を30年後に探して会いにいく物語。 国籍、言葉、文化が異なる子供達が通う学校で、各自が祖国を説明する授業では皆それぞれが生き生きと自慢気に語っていた。先生たちが個性を尊重する教育、生徒の才能を見出した時には歓喜の声を上げ、他の先生を呼びに行くなど、才能は国の財産という考え方は、日本にはあまり無い感覚で、ただただ羨ましい。 不安定な社会情勢の中、明日にも爆撃されるかもしれない場所に居る友を案じ、亡命しないのか?と聞く場面は涙なしには読めなかった。祖国とは何か?ルーツとはなにか?を改めて考えされらた。
0投稿日: 2015.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が少女時代の一時期を過ごした、プラハのソビエト学校での同級生の当時のエピソードとその後久しぶりに再会したときの話をまとめたもの。 東西冷戦という時代について体感として分からないのですが、日本人としてこんなにも冷戦の影響を「直接」に受けて育った人はあまり多くないのではないでしょうか。 クラスはとてもインターナショナルで、インターナショナルで故国を離れている人が多いからこそ、愛国心も高まる。そして国と国との関係が変わると同級生同士でも付き合いづらくなったり、また仲良くなったりする。少年少女にとってはかなりしんどい部分もあったんじゃないかと思ってしまいます。とくにヤスミンカの話ではそう感じました。 ただ辛いこともありつつ、著者の語り口の中には、当時の学校生活を楽しい思い出と感じてるのもひしひしと伝わってきます。そうやっていろんな国の友達と仲良くなって、いろんな国の文化を知ることができる、なかなかできない素敵な環境だったんだろうなと思います。 約30年ぶりの再会のシーンもそれぞれ感動的であり、悲喜こもごもでした。
0投稿日: 2015.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ『ジョコビッチ』の(また)翻訳者が、『ジョコビッチ』を理解するために読んだ本の中の一冊。旧ユーゴスラビアのことがわかるというので借りて読んだ。 この著者の本が初めてで、一章読んで、著者の思い出話?(中二のときにチェコにあるソビエト学校へ通っていた)と思ったが、三賞の、まさに旧ユーゴスラビアの話に感動した。 当たり前のことだけれど、『空爆なんてしてはいけない』と改めて思った。普通の人が普通に生活しているのに、と。 そして、あまりにも自分が世界の歴史を知らないことに愕然とした。
0投稿日: 2015.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ冷戦時代にプラハのソビエト学校で過ごした作者が出会った東欧の国のクラスメート達。彼らに対する作者の思いも素敵。色んな要素が詰まっている一冊。当時の歴史を振り返りたくもなった。
0投稿日: 2015.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ米原万里を知ったのは、佐藤優の本からだ。政治家のロシア語通訳を務めながら、下ネタも平気なスゴイ人。実際に本を読めば、よく分かる。彼女オリジナルな人生は、そしてまた稀有な友人を獲得し、彼女自身を成長させたのだろう。共産党員である父にドップリと影響を受けた学生時代に、これだけの貴重でタフな人生を歩んだ。それは正に財産だ。本著は、その学生時代の友人を訪ねながら回想するというタッチで描かれている。面白く無いわけがないのである。
1投稿日: 2015.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
--- 一九六〇年、プラハ。小学生のマリはソビエト学校で個性的な友だちに囲まれていた。男の見極め方を教えてくれるギリシア人のリッツァ。嘘つきでもみなに愛されているルーマニア人のアーニャ。クラス1の優等生、ユーゴスラビア人のヤスミンカ。それから三十年、激動の東欧で音信が途絶えた三人を捜し当てたマリは、少女時代には知りえなかった真実に出会う! 大宅壮一ノンフィクション賞受賞作。
0投稿日: 2015.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説にしては妙に淡泊な構成と思ったらノンフィクションだった。何を勘違いしてたんだ。さておき、起こっている歴史的事件とそれに振り回される人々の話は読み応えがあるのだが、前述の通り淡泊に「え、ここで終わり?」となりもったいない感。
0投稿日: 2015.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ男の良し悪しの決め手は歯である(リッツァ) 日本人は当人の人間としての本質とは無関係な、容貌上の特徴をあげつらって呼ぶ。チェコ、プラハのソビエト学校では、最低の恥ずべきことであるという暗黙の了解があった 他人の才能をこれほど無私無欲に祝福する心の広さ、人の好さは、ロシア人特有の国民性 良いエッセイだった。 「不実な美女か貞淑な醜女か」も読んでみる
0投稿日: 2015.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログいわた書店の一万円選書に入っていた本。 装丁はピンクで帯には「逢いたい、嬉しい、早く逢いたい。」と書いてあったのでチックリット的な女子女子した恋愛小説なのかなぁと思いきや、歴史に巻き込まれた当時の東欧の人々のリアルを映し出したようなしっかりした内容だった。 こういう小説は初めてでとても新鮮だった。 この小説に出てくる女の子の名前が米原マリなので著者の自伝的小説なのかなぁなんて思った。 ルーマニア、ユーゴスラビア…と聞いても日本人はあまりピンとこない。 日本で流れている海外ニュースは一にアメリカ、二にアジアなので東欧が取り上げられることはほぼないから、と本文中に書いてあった。 この本を読んで、そんな壮絶なことがあったんだぁと知ることができた。 私はもともと歴史や政治に弱いので、共産主義がどうとか社会主義がどうとか言われてもあまり分からない。。。 それが作用するとどうなるのかよく分からない(恥ずかしながら)。 そんな私が読んでも面白かったので、政治や歴史に一般程度の知識がある人が読めばもっと面白いと思う。 政治的策略で犠牲になった子供の話など結構しっかりしている小説だ。
0投稿日: 2015.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログとても興味深く面白い。作者の豊かな経験を羨まずにはいられないし、海外と日本の教育方法の違いには驚かされる…のたが、私には作者の共産主義的な考えが理解できない。昔がどうであれ、友達に自分の考えを押し付けそうになっているのがいただけないというか、腑に落ちないというか。 ただマリの同級生たちが、彼らのルーツについて関心を持っていて、それについて熱く語り合う場面には感動した。私にはこういった経験はないので。
0投稿日: 2015.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログノンフィクション、エッセイと言うが書かれた時点でそれは虚構である。という前提を踏まえるまでもなく、そこら辺の小説は裸足で逃げ出すか平伏すレベルの完成度の高さ、抜群の面白さ。同著者の長編小説である『オリガ・モリソヴナの反語法』よりもこちらを推す。
0投稿日: 2015.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆5 水無瀬 ノンフィクション、エッセイと言うが書かれた時点でそれは虚構である。という前提を踏まえるまでもなく、そこら辺の小説は裸足で逃げ出すか平伏すレベルの完成度の高さ、抜群の面白さ。同著者の長編小説である『オリガ・モリソヴナの反語法』よりもこちらを推す。 ☆5 容 歴史は文字ではなく人生の集積である、ことについて雄弁に物語る一冊。国籍とルーツは等価なのか?愛国と排外は同義か?この時代このタイミングで自分の人生傍観してる輩は全員読むべき。
0投稿日: 2015.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公マリを取り巻く少女たちの様々な人生が語られている。 生まれた国、環境で、角も人間というのは違うものになってしまうのか。 増して彼女たちはクラスメイトである。 人の世界の残酷さをまざまざと見せつけられ、背筋が寒くなった。 ヤスミンカと友達になりたかったマリの気持ちが痛いほど分ります。 マリの気高い魂に共感できますが、それは平和な日本人ゆえの驕りなのでしょうか。 人生で一度は読んで頂きたい本です。
0投稿日: 2015.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログプラハのソビエト学校で出会った三人の同級生と、激動の東欧で音信が途絶えたその後の再会劇が赤裸々に綴られたエッセイ。たとえ親同志の思想が違っても友人と仲良くなることで「論争と人間関係は別」であることを周囲に示したかったという著者の信念に胸を打たれた。多感な少女時代に果たして同じことを考えられたであろうか。三人の同級生のうちタイトルにセレクトされたのがなぜ、「アーニャ」なのかそこにもう一つの著者のメッセージを感じた。
0投稿日: 2015.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代にプラハのソビエト学校で学んだ時のこと。子供の目線で国や立場の違う友だち、先生や周りの大人のことを書いているのが興味深い、そして大人になって友人たちに会うとそれぞれの事情がまた見えてくる。そういう人たちがいたことさえ知らなかったのでいろんな世界があるんだなと思った。
0投稿日: 2015.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ20171215蔵書 20141203読了 2001年出版。米原万里のエッセイを読むのは2冊目。つくづくこの人のエッセイはおもしろい。そしてこの題名が秀逸。●1960年1月~1964年19月まで通っていたプラハのソビエト学校で、ともに勉強した友人たちとの日々から大人になって再会するまでの3編。ギリシャ出身のリッツァ、ルーマニア出身のアーニャ、ユーゴスラビア出身のヤスミンカ。なぜソビエト学校かというと、共産党の理論誌編集局に勤める職員の子どもたちだから。●いまやソビエトは崩壊しており、21世紀のプラハには共産主義の犠牲になった人々を追悼する像や共産主義博物館が建ち、完全に過去の遺物扱いだったのを思い出した。エッセイに描かれる、当時のルーマニア幹部層と一般人の貧富の差が強烈。富の偏在ってこわい。P152~ルーマニアの国際結婚は妨害や嫌がらせが凄まじかった P162 党幹部のインテリ層は体制の救いようのなさを察知して子どもを海外へ逃がしていた ●この人のシモネタの歯切れの良さはプラハ時代に培われたんじゃないだろうか…。
0投稿日: 2014.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代のプラハ。10代の著書は、そこで、様々な国の様々な事情の友人たちと出会います。母国を追われた少年、両親と外国を移り住む少女など。 当時と、35年後の大人になった視点を絡めながら、祖国、家族、自己について語られています。時代をこえて10代の人に通じるものを感じます。高校生の方へ。
0投稿日: 2014.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ異文化に身を置くこと、異文化を受け容れること。 ちょうど国籍について考えていたので、いいタイミングだった。今もっと広く読まれるべき本。
0投稿日: 2014.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア語通訳者だった著者が少女時代を過ごしたチェコのソビエト学校での、ルーマニア人、ギリシャ人、ユーゴスラビア人の級友たちの話と31年後の再会を記したノンフィクション。中欧の情勢に詳しくないので、いろいろ勉強になった。 読み終えてから知ったことだが、著者が再会するところはテレビのドキュメンタリーになっていたらしく、ユーチューブで本書に出てくる本人たちを見ることが出来た。 チェコという国で、小中学校の級友もみな外国人で、それぞれの祖国への思いを抱えながら、そして自分のアイデンティティを育てながら成長していく。30年後に会う友人の中には、亡命してロシア語を忘れてしまった人もいたが、子供たちの絆は固く結ばれていたようだ。努力して医者になったギリシャ人の友人、特権階級であることを見てみぬふりをするアーニャ、ユーゴスラビア人でボスニア紛争のもとに生きるヤスミンカなど、それぞれの人生模様が非常に興味深い。作者の文章もとてもうまく、最後まで引き込まれた。 オススメの1冊。
1投稿日: 2014.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔の友達を訪ねる記録。 しかも東欧。時代背景やら、政治情勢やらまったくわかっていなくても、ぐいぐい読めてしまった。それだけで読まずにきたとしたら、ちょっとソンだった。読めてよかった。
0投稿日: 2014.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログユーゴスラビア、クロアチアなど、十数年前の紛争の時にちらと名前を聞いた程度の知識だったが、あらためて地図を見ると、思ったよりずっと西にあって驚く。”西欧”なイメージのギリシャやブルガリア、フィンランドよりもずっと西。イタリア、ドイツなど馴染み深い国のこんな近くで、つい最近まで空爆が行われてたといたとは。 そんな日本から見て死角に位置するような東欧諸国の生活を想像できるだろうか。本書はチェコ、ルーマニア、ユーゴスラビア、ギリシャ、そして日本他各国の人々が共産時代のプラハのソビエト学校で過ごす日々と、その後の人生を辿るエッセイ。小説ほどドラマティックな愛と感動の悲喜劇が起こるわけではなく、誰もが淡々と動乱の情勢に飲み込まれ、人生を動かされる。背伸びしたがる噂話好きの耳年増な女の子。正々堂々と嘘をつく目立ちたがりで自信家な女の子。澄まして孤立しても揺るがない毅然とした強い女の子。子供の性格の違いは家庭とその周囲のミクロな環境で決まるのだろうが、例え僅かな距離の差であろうとも、マクロな国家間の思想の違いが個人に与える影響というものを思い知らされる。 日本にいると、自分は強制されない思想を持っていると思いがちだが、そうではなく、ただ思想の違いを実感できない環境に自らを置いているだけなのかもしれない。技術が発展し、世界の物理的距離が縮まっても、地域の背景を理解し、指向性を持って対話を進めない限り、精神的距離が近づくことはないだろう。
0投稿日: 2014.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ買いっぱなしでずっと積まれてた一冊。海外旅行に行く時、飛行機の中で読もうと思って本棚から出した。 最近、反韓や反中という言葉を本のタイトルでもよく目にするようになって、民族とか文化について真剣に考えなければいけないな、と思う。 そんな中でこの本を読めて良かった。 民族の対立ってなんだろうな。 どうしてそんな争うことになるんだろう。それに翻弄される子ども達は、人々は。 祖国から離れている分だけ愛国心が強くなる、という文が印象的だった。 また自分がソ連を知らない時代を生き、資本主義の国に居るからかもしれないが、ロシア、東(中)欧のイメージが今まで思っていたものから少し変わった。 やっぱり思い込みは良くないなあ。自分の目で見たり、色々な事実を認識して、様々な意見を聞いた上で、自分の考えを持つようにしたい。
0投稿日: 2014.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ激動の東ヨーロッパを少女の目線から。そして大人になってから知る真実。旧友たちのその後。 共産主義や歴史には詳しくないけれど、ぐいぐいひきこまれた。
0投稿日: 2014.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ明るい少女時代の頃のエッセイが、オトナになってから会ったらあの時の事情がわかったり、それぞれの共産圏にいる彼女達を息を飲んで追いかけるところにすべて同じ視点で入り込める作品 読みやすく天真爛漫なのに3本とも胸がキュっとなる 世界の知らない影のところが見えた 少女達もその影を見つつ見えない見せないようにしていたことを知る 選ばれて産まれた我が資本主義 幸せに生きていたんだなぁ私
0投稿日: 2014.08.30素晴らしい「物語」を読んだ後の読後感
1960年代のチェコのソビエト学校の思い出と、そこで一緒に過ごした友達3人との30年を経た後の「再会」が描かれた「ドキュメント」でしたが、素晴らしい「物語」を読んだ後の充実した感覚と同じものを感じる事が出来た素敵な一冊でした。チェコ、ルーマニア、ユーゴという、私とは全く縁のない世界で生きる人々をこれ程までに身近に感じる事が出来たのは、作者の端正かつバランス感覚優れた描写の力の素晴らしさに依るものだと思います。複雑な政治状況に翻弄されながら「それでも」生きていく人間を描いた傑作だと思います。
8投稿日: 2014.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ嘘つきアーニャの真っ赤な真実。 共産党、社会主義、旧ソビエト、ルーマニア…。平成の日本に生まれた私たち世代にとって馴染みの無さすぎる言葉がポンポン出てくるのに、読みやすい。まさしく引き込まれる。 世界はひとつ、差別もなく、世界中のみんなが平等な世界へ…。そんな価値観がのさばる今を当たり前で理想的なもののように思ってたけど、人にはバックグラウンドや言語や信条など様々なものが絡んでいて、もっとシビアなものであると言うことが、作者の体験を元に描かれていて、価値観をひっくり返された思いがする。 20世紀の激動の一片を描いたような作品だと思わず、21世紀だからこそ、読みたい。そんな作品である。
0投稿日: 2014.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は、共産党員であった父親の仕事の都合により1959年から1964年にかけてチェコのプラハで小中学生時代の約4年間を過ごした。それだけでも特別な体験だ。著者は、そのときに身を付けたロシア語の同時通訳者を職業としている。 本書は、チェコを離れて約30年後、当時の級友たちを探し訪ね、その話をまとめたノンフィクションである。小中学生時代の友達なので昔懐かしの話なのだが、エッセイというには軽すぎる。彼女らが交流を絶っている間に、プラハの春やソ連邦崩壊を経て、それぞれ重い体験を経ているからだ。 最終的にリッツァ、アーニャ、ヤースナの3人の同級生に会うことができるのだが、アーニャは崩壊した悪名高きチャウシェスク政権内の有力者の娘だし、ヤスミンはユーゴスラビアの集団大統領制のボスニア選出の最後の大統領の娘だ(ということが30年後にわかった!)。リッツァの父は、チェコの共産党編集局の職をソ連に批判的な行動を取ったおかげで解職されてチェコにいられなくなった。 物語はその異なる背景を持つ3人のエピソードから成るが、一つ目にはリッツァ、二つ目にはリッツァとアーニャ、三つめにはリッツァ、アーニャとヤースナが登場するという形式になっている。それぞれの子供時代のエピソードと、会って(もしくは電話越しに)その後の人生を聞き、子供時代の思い出との関係や疑問と知らなかった背景と真実とが結び付けられる。人物の登場に制約を設けながらも、とても自然な語り口になっており、うまいなと思った。エピソードにも重みと深みがある。 彼女らの人生はその時代背景を受けて波乱万丈で濃密だ。そして、そのおかげで彼女らの考え方もまたそれぞれ独自のものになっている。そして、それぞれが自分の人生とその考え方をよくも悪くも自ら選択している。おそらくは、その必要と必然性があったからだろう。その機微をエピソードを通して表現する著者の手つきは鮮やかだ。タイトルで『嘘つきアーニャ』とされているアーニャへの視線も厳しくもあるがまた同時に愛もある。「真っ赤な真実」には「赤」=共産主義という意味が含まれているのだが、当のアーニャはそのことに対してほとんど意識的ではない。 格差をなくすといいながら圧倒的な格差を生んだ共産主義の矛盾。詐称癖のあるアーニャ。どこかでそのことを知りつつ隠しているからなのかもしれない。著者は必ずしも共産主義者を否定しているわけではない。彼女自身の父や、リッツァやヤスミンの父には非常に好意的だ。しかし、共産主義というシステムはそういう人を厚く遇するシステムではなかったということだ。 時代に翻弄されながらも、自らのアイデンティティとして国を思いながらも、国境を越えて強く生き、また生きざるをえなかった女たちの物語。東欧の近現代史の知識がなくても楽しめる。おすすめ。 ------ 著者が3人に会ったのと同じころ、1993年夏に学生だった自分は東欧を一人で巡っていた。 アーニャの故郷で、著者も訪れたルーマニアのブカレストは、文中にもあった、工事中で止まったビルの群れと静寂の中にたたずむ巨大な人民宮殿はこの目で実際に見た。チャウシェスクが捕えられた広場に面した建物にはまだいくつもの銃痕が残っていた。腐敗はまだ続いており、荒んでいる人の心を感じた。自分が行った当時の東欧諸国(ブルガリア、ハンガリー、チェコ、ポーランド、東ベルリン)の中でもルーマニアは最も沈んでいた。 彼女らが通った学校のあるプラハも行った(著者も再訪している)。とても素敵な街だった。ブカレストと比べると為政者により大きな差ができていることを肌に感じた。 ユーゴにも行きたかったが、行けなかった。本書の中でも触れらていたが、ヤスミンとその家族の身を案じたユーゴ紛争のために入国を強く止められていたからだ。他の国がそれぞれソ連邦が解体した冷戦後の世界にまがりなりにも歩み初めていたが、ユーゴだけは別だった。 リッツァの祖国で彼女があこがれたギリシアの青い空もとても懐かしい。東欧旅行の前に一ヶ月半ほど過ごした。 あの頃のことを思いだした。特別な本になった。 3人を訪ねる旅は、NHKの番組として企画製作されたものらしいが、編集された映像を本当に見てみたいものだ(NHKオンデマンドにはなかった)。 ---- 1990年代初め、携帯もインターネットもSNSもない時代だからこうやって人づてに辿っていっていたわけだが、今ならSNSであっという間なんだろう。違う物語になりそうだ。まだたった20年ほど前の話なのにね。
0投稿日: 2014.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ角川のプレミアムカバーがかわいくて購入。タイトルは知ってたけど、こういう本だって知らなかったー!! 自分とか友達とか周りのものだけでなく、国や生き方やそういうものにもこの年齢から触れるっていうのは、安易な言葉だけどすごいって思ってしまうなー。表題作がやっぱり印象的でした。
1投稿日: 2014.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
氏の在プラハソビエト学校時代の三人の友人たちにまつわるエッセイ。当時の東欧社会主義国の暮らし興味深く、その後歴史の中で翻弄される彼女たちの生き様が哀しい。瑞々しい文章で一気に読んだ。
0投稿日: 2014.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学校中学年から中学の約五年間プラハに住んでいた筆者。私が海外に住んでいた年齢とかぶる。 共感したところ。 「異国、異文化、異邦人に接したとき、人は自己を自己たらしめ、他者と隔てるすべてのものを確認しようと躍起になる。自分に連なる祖先、文化を育んだ自然条件、その他諸々のものに突如親近感を抱く。」 「お国自慢をしても当たり前のこととして受け入れる雰囲気があった」 自分が日本人であることを当たり前のように意識していた。日本で暮らしていると、みんなそれに違和感を感じているみたい。 アーニャ 時代の流れは人の考えや行動を変えていく。ただ、その人の本質は変わらないのかもしれない。アーニャはルーマニアの愛国心がとてつもなく大きかった。が、今はルーマニアを捨て、イギリスに住んでいる。そのことに対してあまり罪悪感を感じていないような発言をする。が、その目は誠実そのもの、アーニャが嘘を付く時にする目だ。ただ、もしかしたら本当に心からそう思っているのかもしれない。
1投稿日: 2014.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログリッツァの夢見た青空、嘘つきアーニャの真っ赤な真実、白い都のヤスミンカ、3篇ともタイトルに入っている「色」に印象付けられる物語。 日本で生まれ、育った私にはカルチャーショックを受けるくらい、3人の人生は「国」や「政治」、「民族」に左右されている。 この本を読んで、普段意識しないそれらのことを考えるきっかけをもらって本当に良かった。
1投稿日: 2014.07.16ノンフィクションでありながら良くできた小説を読んでいるような感覚
ロシア語の通訳者として活躍し、少女時代をプラハで過ごした著者が大人になって少女時代の友人に会いに行くというストーリー。 と書くとほのぼのした話のようだが、政権を追われた為政者の家族や、空爆下のボスニアに暮らすかつての大統領の娘など、かなり激動の人生を歩んでいるクラスメイトをテレビ局の力によってようやく探し当てるのだ。 東欧という日頃なじみのない場所、様々な国から集まったクラスメイトの豊かな個性、そしてソ連という国が存在していた時代という、現代の日本からはかけ離れた世界がこの作品の中に描かれている。 文章は軽妙洒脱でユーモアがあり(時々下ネタもあり)、ぐいぐいと惹きこまれる。とても面白い。 作者自身もそうだが、外国の人々は自己表現に優れている。故に彼女らは物語の登場人物の様でもあり、逆にそこから感じられるリアリティもある。 米原氏の作品を読むと、いつも世界の広さを感じる。その国で実際に過ごした人が語るからこそ、その国の魅力を身近に感じられる。自分も行ってみたいと憧れてしまう。 自分にとって米原氏の作品で語られる外国は、実在するファンタジーの世界に他ならない。
13投稿日: 2014.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログノンフィクションとは思えない。物語のようだが、現実に起きたこと。当時を生きた著者による記録。世界史や近代史における自分の知識の欠如を痛感。もっと知っていれば、もっと入り込めたろう。日頃勉強しようと思うだけで勉強しない自分を改めて認識した。毎日少しずつでもやろう。今度こそ。閑話休題。ロシアや旧ソビエトに対する認識が変わった。良いイメージを持っていなかったが、少しプラスへ転換した。その国民全員が全く同じ思想を持つことは限りなくあり得ない。当たり前だが、気づいていなかった。無意識に全員がそうだと思っていた。恥ずかしながら、「中欧」という言葉も初めて聞いた。東欧と中欧は区別する必要があるという事実も。ロシアは才能ある人をみんなが愛するという民族性も興味深かった。ロシアはなんとなく頑固だという先入観があったためだ。結論。国際関係と言語についてもっと学ぼう。
1投稿日: 2014.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ米原万里さんが在プラハ・ソビエト学校で出会った同級生たちとの思い出、そしてその後の姿を追ったドキュメンタリーエッセイ作品。 かつての同級生、リッツァ、アーニャ、ヤスミンカはそれぞれ個性的な人間性を持ち、抱える背景も今の日本人から見れば特徴的である。 リッツァは、故国ギリシャの青空を夢見ながらも、30年後には幼い頃の夢とは違いドイツで医者として暮らしていた。 アーニャは、共産主義に対する純粋無垢な気持ちを持ちながらも、自分の矛盾した言動に何も感じていない。 ヤスミンカは、成績優秀で芸術的才能もありながら、戦争と隣り合わせの生活を強いられている。 最近の日本で書かれる作品には、私的な、個人の中の気持ちにフォーカスした作品が多い気がするが、個人の気持ちを変えたところでどうにもならない問題は世界のここかしこにある。 社会の動きに翻弄され、様々な問題を抱えつつも、精一杯に生きている人たちがいる。 「事実は小説よりも奇なり」とは、まさにその通りで、現実をもとに描かれるドラマは、小説よりも面白い。 そして、翻訳の仕事をしていた米原さんならではの東西戦争の裏話もあり、非常に興味深い。 戦争に正義はない。日本では西側諸国が「正義」だと報道されていたが、現実はそうとは限らない。 様々な視点を与えてくれ、真実はひとつではないことを教えてくれる。 自分のいる共同体を、「国としてではなくて、たくさんの友人、知人、隣人がいる」という考えで愛する思想は、とても大事だと思う。 多くの日本人は、異国の人間と触れ合う機会が多いだろう。 その時に、自分の共同体のアイデンティティをどう考えるか。 世界には様々な文化があり、様々な人間がおり、様々な現実がある。 そのことを、改めて考えさせられる一冊。 「セカイ系」の物語では、個人の気持ちを変えることで世界が変わる。 確かに、そういう面もあるかもしれない。 だが、それは根本的な解決にはなっていない。 世界を変えるには、周りを動かす必要がある。 中には、動かせないものもあるだろう。 動かせない壁にぶち当たった時に、どうするか。 「セカイ系」の物語では、そこまで考えられていないように思われる。 それが、「セカイ系」が浅い理由であるように思う。
2投稿日: 2014.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が10代のはじめを過ごしたプラハ、そこでの級友に約30年を経て再会する話。話は3編あり級友も3人。 我ながら東欧の歴史をほとんどなにも知らないなと気付かされた。
0投稿日: 2014.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代はじめ。在プラハ・ソビエト学校には、当時社会主義体制に組み込まれていたすべての国の子どもが通ってきていた。外交官の子弟、故国の共産主義者弾圧から逃れて東欧諸国を転々と移ろう両親の間に生まれた兄弟たちが。 日本共産党員であった父親の海外勤務に伴い、このソビエト学校で10代の数年間を過ごした著者。 生涯忘れがたい友人を得、しかし父親の海外勤務終了とともに日本へ帰国したそのあとに、東欧に激動の時代が訪れた。 ギリシャ、ルーマニア、ユーゴスラビア。 リッツァ、アーニャ、ヤスミンカ。プラハの曇天のもと、それぞれまだ見ぬ、または遠く離れた故国を愛し、無邪気に社会主義体制の理想を信じていた3人の少女たち。 しかし故国は彼女たちの安住の地にはならず、社会主義体制は崩壊した。 かつての友人を探す著者の旅。そして革命と内戦、30年の歳月を超えて再会した“老いた少女”たちの人生に涙するエッセイ集。
0投稿日: 2014.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイなのにドキュメンタリーのようでした。アーニャの描き方が絶妙です。著者はロシア語の翻訳者ということで言葉のプロ、さすがです。万里ちゃんお気に入り決定。
0投稿日: 2014.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ人に優しくなれるし、何にも知らないんだ。 プラハのソビエト学校で個性的な友達に囲まれて過ごすマリ。 様々な国の同級生がホントに個性豊かッ! 日本とは違うなー いいなーこういうの。 ませてるリッツァ 嘘つきアーニァ クールで聡明なヤスミンカ その彼女たちに大人になったマリが会いに行くのだが… 世界は白黒でハッキリ分かれてない 全てはグレーであること… 境界が曖昧だからこそ、みんなと仲良くなれるのかも。でも、「よろしくねッ!」ってあいさつしても拒否する人もいる。そこで、その人を嫌いになってはならない。嫌われはしても、嫌ってはいけない。辛いなー。そんな事をポカーンと考えてしまう。 私が正しいのだと思わない方がいい。 いろいろと発見ができる本。 プラハの春、チャウシェスク独裁政権、民族主義
0投稿日: 2014.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログシモネタから幕をあける3つのエピソード。 米原さんが少女時代を過ごしたチェコでの学園物語とその後。という軽いものではない。 自らのルーツと一緒に異国にやってきた背景多色な同級生の言葉はおませとかでない大人の空気を感じさせる。日本だけで生まれ育った人にはピンとこなかろう世界は存在するのだ。 米原さんが成人し、ギリシャ(?)のリッツァとルーマニア(?)のアーニャとユーゴスラヴィア(?)のヤスミンカに再会を果たしていく実話。 自分が日本人だという事に疑いを持たない当たり前さを一考させられた。 …と、難しそうですが、かなり、楽しく読めます。
0投稿日: 2014.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者が、プラハのロシア学校に通っていた時の友達との思い出と、近年彼女たちを訪ねて行ったお話。 情勢が、わかりやすく共感しやすく書かれていて良かったです。 『リッツァの夢見た青空』 一度も見たことのない祖国ギリシャを夢見ていたリッツア。大人になって住んでみると、青空以外は自分の理想ではなかった。 『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』 平等を目指した民衆の力を利用して現政権を倒した後、今度は自分たちが強い力を持った特権階級の娘アーニャ。 その地位が危うくなるや、特権で得た知識と特権で得た外国人との結婚許可を持って国外へ出たアーニャ。 共産主義の平等の建前と自分の受けている特権の矛盾から逃げるように「そのうち国境はなくなるのだから」と話す。 『白い都のヤスミンカ』 「西洋」の側の仲間になりたくて、この地域の自分たちは上なんだと誇示したくて、近隣と争いを起こす人々。 紛争の片側からの目線でしか語らない報道。 「西側では才能は個人の持ち物なのよ、ロシアではみんなの宝なのに。だからこちらでは才能ある者を妬み引きずり下ろそうとする人が多すぎる。ロシアでは、才能ある者は、無条件に愛され、みんなが支えてくれたのに」
1投稿日: 2014.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ童話のように可愛いタイトルに惹かれジャケ買いならぬタイトル買いだったが、 まさかのドキュメンタリー。 大宅壮一ノンフィクション賞受賞作。 1960年から5年間作者が通っていたチェコの在プラハ・ソビエト学校で 同級生だった3人の異国の友達を、約30年の時を越えて訪ねて行くというストーリー。 この30年間彼女らが過ごした東欧は 民主化闘争・社会主義体制崩壊と激動の時代だった。 その波をかぶりながらも生き抜いた彼女らとの再会。 そして、真っ赤な真実とは? 各章とも前半の子供時代の可愛いエピソードと、後半の細い細い糸を辿りながらの スリリングな捜索が対比となるストーリー運びが素晴しく、読み始めてすぐに心を鷲掴みに。 ノンフィクションゆえのドキドキする緊迫感は、最後のページを閉じるまで止むことがない。 読書冥利につきるとは、こういう本を言うのだろう。
6投稿日: 2014.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本に住んでいると、アメリカと中国、韓国、北朝鮮の ニュースが中心で、東欧諸国のことは漠然としたイメージしかないけど、 小中学生時代にチェコスロバキアのプラハで過ごした 著者の経験を読むと、普段意識することのない世界事情を考えさせられる。 大人の視点によるその国の政治体制・経済状況を踏まえて ロシア・東欧を考察したものではなく、 いろんな国から集まった子どもたちが通う学校の友達の話が中心。 ただ、いろんな国から来ている分それぞれの国の事情もあって 子供時代の話の後にお互い大人になって再会する話になると それぞれ大人の視点で向き合い、矛盾をぶつけてしまう展開になるのが 悲しく思えてくる。
0投稿日: 2014.02.01東欧世界の描写が新鮮
表題作「嘘つきアーニャ~」含む、中編三編。いずれも著者・米原氏が少女時代を過ごした東欧の同級生の思い出と、その後の再会が描かれる。 「嘘つきアーニャ~」は、旧友アーニャへの著者の当たりがちょっとキツイかな、と感じた(それはひとえにバックグラウンドの違いに依るものだと思うが)。 日本で感じることは難しいであろう近現代の東欧、いわゆる「東側」の社会や文化・思想を、実際に現地で生活していた方の体験を通して読むことのできる稀有な書籍。
4投稿日: 2014.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容紹介 1960年プラハ。マリ(著者)はソビエト学校で個性的な友達と先生に囲まれ刺激的な毎日を過ごしていた。30年後、東欧の激動で音信の途絶えた3人の親友を捜し当てたマリは、少女時代には知り得なかった真実に出会う!
0投稿日: 2013.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者米原万里が幼少に通った「在プラハ・ソビエト学校」での思い出。そして当時の友人を訪ねた時の体験を綴ったノンフィクション・エッセイ。 米原さんの文章は流石ロシア語同時通訳の第一人者という感じで、知らない文化圏での様子がありありと伝わってくる。それでいて表情豊かで裏表のない実直さがある。 社会の変動に運命を翻弄された少女たちが、その激動の東欧の中でどのように生きたかを辿っていく米原さん。かつての友人を想うばかりに肝を冷やす場面は読んでいるこちらまでハラハラしてくる。友人の一人アーニャを訪ねた際にルーマニアを案内してくれた青年の言葉が印象に残る。 “「人は自分の経験をベースにして想像力を働かせますからね。不幸な経験なんてなければないに越したことはないんですよ。」”(161ページ) この言葉を受けて、この日本で当たり前のように平和を享受している自分がいかにノー天気かを痛感した。リッツァ、アーニャ、ヤスミンカ、そして「在プラハ・ソビエト学校」に通う子どもたちは故国の文化と歴史を背負ってやってきている。そしてその意識は子どもとは思えないほどに強烈な信念である。(むしろ大人になって再会した時のほうが若干柔和されているように感じた。)そう感じるのもまた僕自身にそこまで高い愛国意識がないことと、ナショナリズムにしても批判できるほどに至っていない、つまりなんとなく生きてきてしまっているという恥じらいがあるからだ。 この本は米原さんでなければ書けなかったし、彼女が書かなければこうして知りうることも無かったかもしれない東欧の現代史である。友人との再会をテーマにすることでこうもわかりやすく歴史文化というものに入り込ませ考えさせようとしてくれる米原さんが若くしてお亡くなりになられたことは心底悔やまれる。もし彼女が今の日本を見たらどのように思い、感じ、そしてどんな言葉を吐いただろう。それがどんな言葉であろうともう聞こえてはこないのである。ならばせめてマリに怒られないような一人の日本人としてありたいと思うのだ。
3投稿日: 2013.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ何故この本を買ったか覚えてない。 気がついたらKindleライブラリに並んでいた本だけど、気がついた時には夢中で貪るように読んでいた。 1960年代のプラハで、様々な国の社会主義者を親に持つ子供達の、波乱に満ち、それでいて何気ない懐かしさに満ちた学校生活を描いた物語。 この本との偶然の出会いに感謝。
0投稿日: 2013.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログすぐ近くで空爆が行われているユーゴスラビア。そこに暮らす著者の友人のエピソードが胸を刺した。彼女はかれこれ5年間物を一つも買っていない。なぜなら壊されると辛いものが増えるだけだから…。 子供に宿題をさせ、夜ご飯を作る日常をおくりながら、戦争という非日常が常に隣にある辛さはもしかしたら戦時下以上なのかもしれない。
0投稿日: 2013.12.18私は東欧を知らない
西は東南アジアを超えたことがない私は、東欧以前にヨーロッパに行ったことがない。知っているのは世界史の教科書だったり、子供の頃なら児童書伝いで知るその空気だったり、今ならメディアやネットだったり・・・ ただ、10代のころ、少なくともメディアを通して見る東欧諸国はいろいろなものをかかえて生きている人が多く、その分大人になること(現実をたくましく生きること)が早い人も多かったのかな~ということ。 著者の作品で一番好きなのは別の作品です。
3投稿日: 2013.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読む前にYou tubeでこの本の元になった『わが心の旅』を観た。それで、興味が沸きこの本を読んだ。 アーニャの兄とのイタリアレストランでの会話が印象的。 共産主義というのは、みんなが平等に貧富の差がない生活を目指すべきなのに、幹部とその家族だけが特権階級の恩恵を享受し、とても豪奢な生活を続けている事に憤りを感じているようだった。 そして、あんなにも愛国心の強かったアーニャが、祖国をいとも簡単に捨ててイギリスへ渡ってしまった。 軽蔑が入り混じった複雑な気持ちになったのであろう。 そういうことがものすごく、はっきりと書かれていた。 今後の友情は大丈夫なのか。。。 小説のようなノンフィクションのような内容は非常に面白く、一気に読んでしまった。
2投稿日: 2013.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ先々月にプラハを訪れたこともあり、米原さんの描写に町並みを思い浮かべながら読みました。表紙もプラハを描いた絵、まさにあの通り赤い屋根が続く景色だったなぁ。
2投稿日: 2013.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログそのまま小説としても楽しめる、実話。幼少期をチェコスロバキアで過ごすなんて経験は、レア中のレア。それも激動の時代の東ヨーロッパというのは私の想像の及ばない、壮絶な経験をされたことでしょう。それでも作中の少女たち、特に米原さんは、純粋。下ネタもやや出てはきますが、全体としてピュアで優しい心根が感じられました。
0投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者がチェコのソビエト学校時代の3人の同級生をたずねるエッセイです。社会の変化や戦争があっても生きてゆく人々の姿に心打たれました。 九州大学 ニックネーム:浅野総一郎
0投稿日: 2013.11.01激動の東欧のノンフィクション
著者が少女時代を過ごした1960年代のプラハの物語。 その時代の東欧の様子や彼女たちのその後の物語を通じて激動の時代の空気を感じることのできる作品。
0投稿日: 2013.10.07
