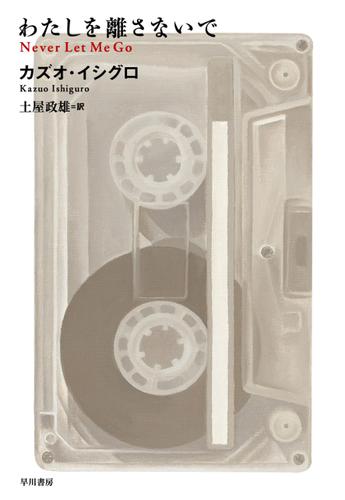
総合評価
(1355件)| 404 | ||
| 456 | ||
| 285 | ||
| 45 | ||
| 12 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わってしばらくはぼ〜っとしてしまいました。自分の運命を受け入れるしかなかった¬°はどんな気持ちだったんだろう。切ないとか悲しいとか…この本の感想は上手く言葉にできません。だからこそ、多く人に是非読んでもらいたいです。
0投稿日: 2010.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログカズオイシグロ初体験読んでいるときはイングランドの空のような薄曇りな気分だったのに、読み終えるとそういう全てがキラキラしていたように感じられる。まさに一代記。ちょっと筆力が別格。翻訳モノでこんなに響いたのは『ロケットボーイズ』以来。解説が柴田元幸じゃなかったら最高だったのに。
0投稿日: 2010.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ31歳の「介護人」キャシー・Hが「ヘールシャム」を回顧する形で展開する異質な小説。 「何」を語ろうとしているのか分からないまま、ヘールシャムでの生活や友人との交流が語られていき、この世界の中の現実に気がついた途端、心が凍り付く。 キャシー・Hの視点で、最後の最後まで「何か」をギリギリまで抑えた描き方にもかかわらず、その描いた物は強烈。 行間を読むというのではなく、小説後を読みたくなる希有な作品でした。 ……ネタバレでは書きたくないので、是非ご一読を。
0投稿日: 2010.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本生まれのイギリス帰化人カズオ・イシグロの作品。 ノーベル文学賞をそのうち受賞するだろうと言われている人なので期待して読んだのだが、正直この作品からはそこまで優れた作家であるとは感じなかった。 途中でネタバレがあり、そこからの展開によっては面白くなったのだろうけど、何だか凡庸というか尻すぼみだったような気がする。 設定そのものは面白いと思うのだけど、基本的に軽い。 自分に課せられた使命を淡々と受け入れていたけど、その必然性についてもっと書けなかっただろうか。 個人的には大いに葛藤するくらいの方が良いと思うのだが、その辺も中途半端なような気がした。 伏線めいたものも弱い。 エンタメ小説として読む分には出色だとは思うが、文学的にはそこまで評価されるような作品ではないかと。
1投稿日: 2010.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んだとたんに引き込まれてしまいました。 キャシーという31歳の女性が語る回想録の形をとっているからでしょうか、ひとつひとつのエピソードが的確に描かれているからでしょうか、引き込まれて読んでしまって展開がどうなってゆくのかを想像する隙もありませんでした。 フィクションで久しぶりに夢中になりました。 予備知識として、臓器移植が大きなテーマになっていることだけは知っていました。 でもこの本はストーリーよりも、ものがたりの静かな展開と収束が素晴らしいのです。 設定はややサイエンスフィクション的ですが、意外な出来事はまったくありません。日常の、ちょっとした思いがけない出来事程度が起こってゆくだけ、そういう風に描かれています。 作者がおおきく広げた展開について行ってはみたものの、収集がつかないまま置いてきぼりにされる、というのは良くあります。ほとんどのストーリーがそうだと言ってもいいかもしれません。 しかし、この本は違います。圧倒的な度量を感じさせます。これが小説というものかもしれません。 「新しい世界が足早にやってくる。科学が発達して、効率もいい。古い病気に新しい治療法が見つかる。すばらしい。」・・・マダムの平易な言葉が深い感動をもたらすのも本書が小説だからでしょう。
0投稿日: 2010.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ心が震えました。 淡々としながら、執拗なまでの繊細な観察眼を持った一人称の筆致が鬼気迫る。 そのせいか、上質の心理サスペンスとしても秀逸だと感じました。
0投稿日: 2010.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ-外にはマダムのような人がいて、わたしたちを憎みもせず害しもしないけれど、目にするたびに「この子らはどう生まれ、なぜ生まれたか」を思って身震いする- カズオ・イシグロの現時点の最高傑作と名高い一冊。 精緻なリアリズムを追求した作風の「日の名残り」でブッカー賞を受賞。その後、評価された作風をあっさりと棄て、ミステリー風の「わたしたちが孤児だったころ」を上梓し、さらにまた、この「わたしを離さないで」まったく違う作風。しかも、作者の最高傑作ともたたえられる出来栄え。作品中、きっとだれもが大なり小なり「心が震える」瞬間があると思います。
0投稿日: 2010.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初、何の事だかさっぱりな語り口からか 購入してから約3カ月、20ページもよまずにストップ・・ 改めて時間がたっぷりあったときに じっくり時間を込めて読むと、 後から後からじわじわと、疑問が解決していき 解決するたびに何とも言えない悲しさがこみ上げる ちょっと切ない・・というか悲しい本でした この本のようなことが起こらなければいいと思います。
0投稿日: 2010.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間は一度覚えた旨味は二度と忘れられない、 歴史は巻き戻せないという話。 搾取されるために生み出された人たちの視点から、極めて抑制的に語られる人生と恋の物語。 これだけぐんぐん読ませるんだからすごい力なんだと思うけど、しかしそんなに無抵抗でいられるのかと思うほど淡々と主人公たちの人生が刈り取られてゆく。 「欺瞞に満ちた幼年期だったと今になってわかっても、ふりかえれば微笑ましい思い出ばかり」って、そんなに何の恨みも怒りもないなんて?? 自分と同じ境遇の同士には怒りも罵りも呆れもするのに、『外の人』へのその淡白な態度はなんなんだー と思ってしまうのは、私が主人公のように教育されていないからなのか、恨み骨髄に徹する質だからなのか。 でもラストシーンの美しさは、もう、際だってます。 日本の小説は終わり方が下手とかいう話を時折聞きますが、イギリスの小説がみんなこんなに美しい終わり方なら、較べられてかわいそうと思うほど。 (私の中では高村薫の『黄金を抱いて飛べ』の文庫版はラストシーンの美しい日本の小説としてこの小説と俄然張り合えると思うんですけど) (続き) カズオ・イシグロの『私を離さないで』では 主人公に感情移入して読むことは抑止されている。 常に報告調の主人公のいる世界の外側に『外の人』がいる世界があって、読者の椅子は皆、そこに用意されている。 どうして外の世界の人々に対して、怒りを表現しないのか理解できないという読者と主人公の感覚のもどかしい乖離が、 提供者となったルースやトミーと、介護者である(あった)主人公のキャスとの距離と、構造として類似しているように最後の最後までみえている。 ラストシーンで、今やさらに『外の世界』から遠く離れて、トミーと同じ地平に立ったキャスが、イギリスのロストコーナーへ失くしてしまったものに会いにくるとき、 キャスと読者の間に、絶対に重ね合わすことができない断絶があることにはっきり気づかされる。 構造の類似は単なる形の上での類似で、 今からキャスが赴く施設について思いを馳せるとき、 自分の疑問のあどけなさにぞくりとさせられる。 『なぜ外の世界の人に怒れないのかわからない』のは、読者が『外の世界の人』だからなのであって、この作品は構造的に読者が主人公に己を重ねることを禁止するつくりになっている。 前半の『微笑ましい』幼年期で描かれる、私たちの誰でもが必ず通るような焦れったい人間関係での様々な問題を主人公たちが同様に通り抜けてきていることで、 『外』とヘールシャムの子どもたちのラストシーンでの埋められない断絶が、実際には語られないヘールシャム以前にあることがわかる
0投稿日: 2010.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ背景設定や、物語の切り口はおもしろいのだが・・・ どうにも感情移入できなかった・・・ 自分にはこれを読んで泣ける感性は備わってなかったようで。
0投稿日: 2009.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「面白い小説ある」と聞かれて、相手の事を良く知らない場合に。 誰でも受け入れるけど、衝撃もあるイシグロ・カズオ。
0投稿日: 2009.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ苦手な翻訳ものを友達に借りて読みました。本当のことは主人公たちにも読者にも隠されている、見えそうで見えない、わかったふりをして、苦手じゃないと言い聞かせて読み続けましたが非常に疲れました。素直じゃないとだめかも。悲しい話です。
0投稿日: 2009.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ圧倒的な構成力 フィクションでありながらリアリティ溢れる描写 読み終えたときに切ない気持ちになりもう一度読み返しました
0投稿日: 2009.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ静かな語り口なのに妙に深淵とする闇を伺わせる何かが常にある話だった。「ヘールシャム」「介護人」「提供者」この単語の意味が気になって気になって…結局この意味がわかった時、物語は完結するような感じだったのだが…始終「何なの〜〜??」というもどかしいモヤモヤを抱えて読むハメになった。イギリス独得の世界に吸い込まれるんだけど常に違和感を感じたお話だった。面白いのかもしれないんだけど…ゾッとするんだよなあ…
0投稿日: 2009.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ英米で絶賛の嵐を巻き起こし、代表作『日の名残り』を凌駕する評されたイシグロ文学の最高到達点。 「人生は短い」ということを書きたかった。あらゆる人がいずれ死を迎えます。誰もが避けられない「死」に直面した時に、一体何が重要なのか、というテーマを浮き彫りにしたいと思ったんです。byカズオ・イシグロ
0投稿日: 2009.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログネタバレ必須!読んでない人は読まないで! この小説内の「提供者」というのは、健常者に臓器を提供するためだけに生まれてきたクローン人間たちのことである。つまり、我々「本当」の人間のために臓器提供を目的として生まれてきたクローンの人々の物語。この小説が恐ろしいのは、設定はSF的内容であるにもかかわらず、今我々が生きる現実は、それ自体を凌駕しようとしていることである。カズオ・イシグロは、ディテイルを書き込まず、淡々とした文体を駆使し、読者の想像力にある程度任せることで、その恐怖を増幅させる。たとえば セックスしても子供を妊娠しないという「提供者」の設定のように所々に覗く、「提供者」の不可解さが怖い。「本当」の人間が「提供者」を操作しているんじゃないか?と…。 「提供者」たちの置かれる状況は、言ってみれば映画「ブレードランナー」のレプリカントたちと同じ状況なのだけど、こちらの「提供者」たちは、「反乱」を起こそうとはしない。むしろ、その境遇を受け入れている。にもかかわらず生きる証を探そうともがく「提供者」たちは、我々となにも変わらない心を持っている。ゆえに切ない。 中身はまったく違うけど、村上龍の「半島を出よ」と同じ、今、読まなければいけない小説。現在読むことによってその衝撃を味わうことが出来ると思う。土屋政雄氏の翻訳は、非常にこなれていて翻訳調の文体と言う感じがない。とにかく考えさせられる小説。必読。
0投稿日: 2009.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ装丁がテープだったのか!といま写真をみて思った。遅すぎ。鈍すぎ。歪んだ水玉模様かと思ってたよ。視力低下が著しいなあ。生命倫理に興味があるという話を友人にしていて、すすめられて読んだ一冊。この人の本は前もなんか読んだのだけれど、なんか文章がカクカクしている気がする。おそらく翻訳がどうのではなくて、それも味の一つなんだろうけど。どうもなあ。クローン人間にも魂はあるかということは、動物や植物にも魂はあると考える日本では問題にならないと思うけれど、西洋ではやはり作られたものには魂は存在しないと考えるので、問題になるのかなあと思った。臓器を摘出するためだけに作ったクローンに良い環境や教育を与えるのか、動物のように飼うのか、ということが作中の先生達の問題点だけれど、それ以前にクローン人間を作っていいのかという問題について考えさせられる。私たちはどこまで生きればよいのだろうか。どこで生きることをあきらめるべきなのだろうか。
0投稿日: 2009.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋さん絶賛、村上春樹関係者!?ということで購入。 ・・・いまいち盛り上がりに欠け、オチも見えてたし、特にびっくりすることも、 感動することもなく、読了。 期待しすぎたかな・・・
0投稿日: 2009.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログカズオ・イシグロ氏は初めて読みました。 「提供者」と「介護人」って? 「提供者」の意味がわからず、悶々としながら読んでいくと……ああ、まさか…! こんな衝撃を受けたのは久しぶりです。 他の作品も読んでみようと思います。 ただね、こういう話が苦手な人もいるかな、と。
0投稿日: 2009.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ凄く衝撃的!!の一言に尽きます! 長編小説で 読むのにまるまる4時間費やしちゃいました… だけれども、現代の科学的、そして社会風潮を反映したような本…、 つまり「クローン人間」 薬中、浮浪者、売春婦、犯罪者を親に持つ主人公たち しかし、主人公キャシーたちは幼少のころからある外の世界から 隔離されたヘールシャムという施設で幼少から青年時代を過ごし、そこでの友人たちとの 友情を育み、恋愛を経験します 最初は粗筋を読んでいなかったので、孤児たちのほのぼのとした日常を描いているのかと思っていました しかし、徐々に真相が明かされていくにつれて そのほのぼのとは程遠い結末です ジュディーウォーターブリッジの「Never let me go(私を離さないで)」を思わず検索してしまった読者の方々もいるのではないでしょうか? 私はそうで、実在すると思っていましたが 皆さんのレビューを見て架空の人物だとわかりました でも実在しているような描写です 是非この曲を聴いてみたい!!笑 しかし翻訳がもう少し口語的なら読みやすかったのですが…。。
0投稿日: 2009.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ日系英国人、ブッカー賞受賞作家である、カズオ・イシグロの小説。 一人称で淡々と語られる物語は、読んだあと、読者に深い感慨を抱かせる。 英語で最初読んだが、挫折して、日本語で読んだ。 そのあともう一度英語に挑戦。内容がわかっていたので読破。 もし英語が得意な方なら、英語で読むことをお勧めする。 カズオ・イシグロの英語は、美しい。
0投稿日: 2009.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこの人と同じ時代に生きていることを感謝したい、と思った1冊。 テーマは重いが、とてもおもしろかった(おもしろいという言い方は不謹慎かもしれないけれど、ものすごいエンタテイメントだと思った)。
0投稿日: 2009.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリス作家のカズオイシグロさんは、ひたひたと迫るようなサスペンスな雰囲気を前半に折込ながらも、精神的な感傷を痛いほど後半に描く。「私達が孤児だった頃」とは似ているようで、また違った感動を与えてくれる。設定を飲み込むまでに時間がかかるかもしれないが、集中して一気に読み進めたい本。子供の時の話など忘れていたような小さな感情を思い出して、読む人を揺さぶる。去年文庫版がやっと発売されましたが、カバーも新書版と変わらずカセットテープのイラストなのが、とても嬉しかったです。
0投稿日: 2009.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ広告に偽りなし!この本を読んでいて、なんとなく感じてた違和感が、ラストで明らかになります。 クローンは人になりえるか、そして人が人たる定義とはなんなのか、考えさせられました。
0投稿日: 2009.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ一つの世界が緻密に書かれていて、リアリティがあった。 たんたんとした文章で綴られているために迫りくるような感動はなかったけれど、深く考えさせられる一冊。 もう少し自分が成長したら再読したい。
0投稿日: 2009.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
(ネタばれ注意です)失われてしまったもの、知らないうちになくしてしまうもの、もう今では間に合わない気持ち。カズオ・イシグロはそういったはかないものを描くのがとても上手な作家だと思う。 淡々とした語り口調ながら、結末を予期させる諦めや切ない気持ちがにじみでてきていて、胸が締め付けられた。 何も知らず、大人を信じていればよかった少年少女時代。大人の欺瞞に気づき始める大人になりかけのあの時期。そういったものがメインの話と絡み合って懐かしいような、苦しいような気持ちになる。 うまいなあ。 大人になって、全てが子どもの頃思ったことや、願ったこととは違った様相を見せはじめる。それは、提供者達だけに限ったことじゃない。そう感じた。子どもの頃は自分の前にいくつもの道があって、どれでも選択してよくて、迷ってうろうろおろおろするほどだったけど、ふと今、前を見ると、限られた道しか目の前にはなくて、行き先もうすぼんやり見えるような気がする。道じゃないと思っている場所に一歩踏み出したら、違う道はあるのかもしれないけれど・・・そういうことを考えた。 それにしても、提供者や介護者は何で逃げ出さないんだろう。逃げても無駄なシステムなのかなあ。 エミリー先生のやり方には全く賛成できない。欺瞞としか思えないし。というか、子ども達をちゃんと愛することはできると思うんだけどなあ。愛したら、その分、つらいだろうけど。 あと、翻訳がしにくいんだろうけど、一番重要なところで、意味がぶれる感じがしてわかりにくかった。タイトルにもなっている「わたしを離さないで」の歌をマダムが語る部分、意味がわかりにくい。原文にあたってないので、わからないけど、Never Let Me Go. 自体も訳しにくいんじゃないかなあ。こういうところ、翻訳物はつらいなあ。せっかくいい話なのに。
0投稿日: 2009.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログいろいろな人の感想が、内容は語れないが、衝撃的、呆然とする、ショッキング、すごい、なんてのばっかりで、いったいどんな恐ろしい小説なんだ、となかなか読む勇気がでなかった本。勇気をだして読んでよかった。ビクビクしながら読みはじめたのに、どんどん引き込まれて止まらない。訳文を、キャシーのひとり語りで、ですます調にした翻訳もすごいと思った。最初は寄宿舎モノみたいな感じで、なんとなく不穏な感じはありながらも、甘ずっぱい青春モノの雰囲気もあって。わりにすぐに、これはSFの近未来の話っていうのがわかって、その内容は確かにショッキングで重く、悲しいけれど、書き方がすごく上品というか、あからさまなところがないので、いやな怖さはなかった気がする。キャシーもトミーもルースも、「作品にあらわれる」、じゃないけど本当に魂がきれいで純粋なのがよくわかって。その純粋さがまた悲しくて。わたしは衝撃とか恐怖っていうよりむしろ、人生のはかなさ、みたいなものを感じてずっと悲しかった。結局、生きていくうちに、時間が経つうちに、いろいろなものが失われていく、というか。それはキャシーのような人たちだけではなく、だれでも人間はみんな。ため息が出るような、息苦しくなるような。でも、少しだけ、失われたものはノーフォークに、ロストコーナーに集まってくるから大丈夫、みたいな、救いのようなものも感じて。予想していたよりは読後感はよかった。どの場面も印象が強くて、さまざまなことを考えさせられる、心に強く残る小説。
0投稿日: 2009.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本、評価が高いですよね。 翻訳家の柴田元幸はカズオ・イシグロの最高傑作、 と絶賛しているようだし。 抑制された文章、 考え抜かれた構成、 は、 確かにそうだと思う。 なかなか心を打つ物語だと思う。 それでも何故★3なのかは、 単純に私の好みではない手法が多用されていたからです。 冒頭で読者は唐突に置いていかれてしまう。 何の説明もなく語られる世界。 意味不明な言葉は読み進むうちに徐々に解明していき、 その静かな語り口から悲しい現実が浮き上がってくる。 この明かされ方がまた決して衝撃的ではなく、 静かに、 しみ込むように(まさに保護官が生徒にしたように)、 ごく当たり前のことのように言葉に組み込まれる。 もちろんこれは作者が意図したことに違いないし、 それは技術的に素晴らしいと思うのだけど、 本当にシンプルに、 その描き方がどうも私には合わないらしい。 加えて、 「あの出来事がおこってから」とか 「あの日のことをお話ししましょう」とか、 こういう勿体つけた言葉が多すぎる。 私はこういう言葉が(日常でも)はっきり言って好きではない。 回想とこの勿体付けの繰り返しで、 なんだか結局最後も何かくすぶるものを残してしまう。 と私は思うです。 でも言葉は訳者(土屋政雄)のものなので、 原語で読むとどうなのかなあ (そのニュアンスを汲み取る英語力の有無は置いておいて)。 物語自体は素敵なので、 私的には★3が妥当かな、と。 しかし私が最も特筆したいのは、 epi 文庫はサイズが文庫サイズじゃないのがメーワクです。 出版社はどういう意図でこういうことをするんだろう…。
0投稿日: 2009.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは良質。 前半退屈だけど後半一気!って意見もあるみたいだけど、私は淡々と全貌が見えてくる前半こそ好きだw 個人的には、もっともっと書き込んで欲しかった。 一部、二部に引きこまれてたが故に、三部がどうしてもちょっとあっけなく感じてしまったんですよ。
0投稿日: 2009.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログフィクションなのかノンフィクなのか途中でわからなくなった。 自分の心とか想いとかそういうもんじゃなくて、 ダイレクトに臓器を提供するために生まれる人間。 最近クローン牛流通とかそういうお話ききますが、 人間には使わないでほしいですね。
0投稿日: 2009.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ壮大な回想譚。幼少期の輝かしくも脆い思い出と、現在の仕事や心持。耳慣れない言葉が出てきても、読み進むうちに自然としみこんできて、違和感なく彼女の話に耳を傾けることができました。気がついたら引きこまれていて、最後まで読み終わっていました。読後感の強さは去年読んだ本の中で1番深いかも。淡々と進む、ファンタジーやSFとは言い切れないリアルな世界。
0投稿日: 2009.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリスの田舎にある全寮制の学校での日々。 その中で成長するにつれ、少しづつ現れる疑問・・。 成長した彼らの現実。
0投稿日: 2009.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ『coyote』の冒険文学特集にあったので読んでみる。 「提供者」「介護人」・・・設定が、後半、それもかなり終盤にならないとわからない。 クローンとして生まれ、臓器を「提供」することが使命である キャシー、トミー、ルース他、ヘールシャムにまつわる人々の話。 ありえない設定と、翻訳の日本語があまりしっくりこなかった。 「これは後で申し上げますが・・・」みたいな文句が大量に出てくるのが好きじゃない。 他にも―・・・―を使った但し書きが多いのがいまいち。
0投稿日: 2009.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公キャシーが幼少期から現在までを語っていく。 曖昧にキーワードだけ散らかしてその意味が説明されないというスタイルゆえ、ミスリードを誘って最後に大どんでん返しのパターンかと思ってしまうが、イシグロ自身が、帯に「これは…についての物語である」と書いてくれてかまわない。と述べているように、そもそもこの物語にミステリ的な醍醐味は用意していない。 外界から隔たれた施設で育つ登場人物たちが「教えられているようで、教えられていない」教育を読者も同じ目で追うことになり、うすうす感づいていたショッキングな事実が明らかになったときは読者同様、登場人物たちもいちいち驚き騒ぐようなことない。むしろ結果的に彼らが「驚かなかった」ことが、この小説の不条理なテーマに繋がっている。 ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」と同趣向のSF小説といえるが、主人公が悲劇的な運命からどうにか逃れようともがく活劇とは対極の構図に抑制された文体がよく似合っている。文学作家ゆえの良作。 08.12.26
0投稿日: 2008.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ原書で買って3ページ読んで二年放置。 日本語訳で文庫になったのでリトライー この本はミステリーでもありSFでもありヒューマンドラマでもあり哲学書でもあり一言でカテゴライズできません。 最初はまったく状況がつかめないまま、静かに始まり少しずつ彼らがおかれている状況が明らかに 血が出るーとか内臓飛び出すーとかそんな残酷さではなく、たんたんと主人公の口から語られる物語に心の底からじんわり悲しみがにじみでてきます この本読んで小説がある意義が少しわかったような気がするー 小説がなくなるということは、イマジネーションも崩壊してしまうということで。 どんどん発達する科学技術、そのおかげで私たちの生活は便利になって、食料は世界中で大量にあまるぐらい十分で、結果働かなくてもよくなって、犯罪も戦争も差別もなくなって、どんな病気もよくなって、200歳ぐらいまで生きることができるような世界になっちゃうことがはたしていい世界なのか、ということが問われなくなっちゃうんじゃないかなー 完璧に見える世界のウラにあるものに対してのイマジネーションが干からびちゃうのは恐ろしいこと。 小説の意義の一つにはそんな世界にならんよーに警鐘ならすことができる力があるんじゃないかなー なんちゃってー こんなつたない考えが頭を1日中ぐるぐるしちゃいました
0投稿日: 2008.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。 まえに読んだときは残酷さばかりを感じとっていたけど、 今は、こういう叶わなかった希望、指の間をすり抜けていった願いって、辛いだけじゃない贅沢な記憶として死ぬときに思いだされるのかなあ…と疲労と紙一重の穏やかさを感じる。 つい最近まで、運命を受け入れる…って何かに負けたような気がして嫌なフレーズだと思っていたけれど、歳を重ねるごとに、受け入れる強さが必要なこともあるよなあと。思うことが多くなってきた。 そんなときに思い出す小説です。 温室の中で管理されるこどもたちっていうエコールものによくある設定と、たんたんと進む回想作業のような語り。その背景にある「残酷な真実」の正体は、結構早くに明かされます。 登場人物たちは、悟りを開いたような優しさをもつわけでもないし、彼らをとりまく環境も決してやさしいものではない。 それでも彼らの生命に穏やかな色を見るのは、生きることに対する、そのまなざしのせいなんだろうか。 劇的な救いが用意されてないのに勘付きながらも、願うような気持ちでページをめくりました。 激しい感動はなかったけども、余韻が残る、素敵な作品だと思います。
0投稿日: 2008.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ多少ショッキングな設定ではあるものの、 読み終わってみると、ふるさとと仲間を失う孤独、哀しみの方が強く心に残った。 クローンでもやっぱり普通の人間のように当たり前に人をいとしみ故郷を慕うのだろうか 語り手であるキャシーも試験管の中で生まれた一人であることにあらためてはっとする
0投稿日: 2008.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わって、はじめて表紙に描かれているのは テープレコーダーだって気づいた。何回も目にしていたのに…
0投稿日: 2008.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の尊厳とは何か… ありえないと思いながらも、何処かでありえているのかもと云う恐怖が残る。 物語の最大のミステリが早々に明かされ「え?ここへたどり着くまでの物語じゃなかったの?」 と思いましたが、大事なのはプロセスとライフでした。 同じように命を与えられ、私たちとは違う人生を送る同じ人間。 考えたら苦しくなるのだけど、もしかしたら…。 当たり前のことを当たり前にできることに感謝しよう。
0投稿日: 2008.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ恋愛モノではありません。最初から最後まで女性の一人称で話が進みます。 近未来SF?パラレルワールド?どちらでもいいのかな、なかなか恐ろしい話だと思います。 にしてもハヤカワepi文庫は文庫サイズじゃないので困ります。
0投稿日: 2008.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログNever Let Me Go(2005年、英)。 表紙に惹かれて購入。内容は、正直、あまり好みではなかった。話が進展しないので、かなり飛ばし読みしてしまった。そういう読み方をする物語ではないだろう、とは思いつつ…。とはいえ、少女の微妙な心の揺れを綴るシーンなど、フィクションであることを忘れるくらい、心に迫るものがあるのも事実。プロットよりも抒情を味わうべき作品なのだろう。野暮を承知でカテゴライズするなら、SFではなく純文学寄りの読者にうける、通好みの作品ということか。時間を置いて再読しようか…。
1投稿日: 2008.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ経験、体験に感じ入る いうのはまさにこういう書を読んでのことだろうと思う。みなさんのコメントの通り、一気に読める本でありひさびさにいいものを読んだと思う。
0投稿日: 2008.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに読んだ本。あらすじ紹介の段階から面白そうだったけど、期待通り。学校とかの描写はいかにもな海外での生活らしいんだけど、やっぱり不穏でどうしようもない未来がちらちら見える。
0投稿日: 2008.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ登場人物たちの、生々しさがたまらなく辛い。これでもか、と書き連ねられる彼・彼女たちの気持ちが痛い。こんなに、まるで現実のことのように、胸が痛むなんて。カズオ・イシグロの力量のおかげなのか、同じようなことが世界で起こっていると、ぼんやりと感じるからか、それとも将来こんなことになりそうだと漠然と思うからか。もしくは、イシグロがいうように、彼らの人生は、実は、わたしたちとそう変わらないからなのか。こんな感じのまとまらない思考がもやもやして、重いけれど、名作。
0投稿日: 2008.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ11/6 物語感が圧倒的。ひさしぶりにガツンとした本を読んだ。ミステリでもないのにじわじわと謎が大袈裟でなくこちらに伝えられるところや、その根本にある価値観。あと時代設定や詳細がはっきりしていないところもいい意味で世界観を形成している一因だ。ほかの本も読んでみようと思います。
0投稿日: 2008.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログドコにでもあるような学園の日々が 介護人、提供者、回復センター、保護官 ドコにでもあるような、でも少し違う言葉で描きながら 淡々と明らかにされる異様な少年少女の日々。 静かに思い出し、運命に抗うことを思いながら、 夢を見ながらも、現実を突きつけられると 静かに受け容れてしまう。なぜ?疑問。 だからトミーの久しぶりの発作は「ココロ」の叫びが 共振するように伝わってきた。 作り出したものの運命には、創造主がどんなに 苦心して心砕こうともいかんともしがたいのか。 人が過去を思いながら、現在の姿を重ねて これからを、現在の自分と変えることのできない定められていたものとして 許容していくことは、 なにも教えられていないなかで、動揺もなく平静に進められるものなのか。 だから(だけど)、「ワタシ」自身のために腕を磨くのでは。 しかしキャシーのDon't Let Me Goとマダムのソレは異なっていた。 終始、落ち着いた語りのなか トミーの最後の打ち明け話とその姿が 強く心に焼きつき、胸を撃った、射た。
1投稿日: 2008.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年読んだ海外文学の中ではもっとも高い点数がつけられる。抑制された語り口の中に、徐々に明らかにされる謎と彼らの運命。SFでもありミステリーでもあるが、SFやミステリーはこのような感動は呼びにくい。日常的な感情のやりとりを緻密に語ることで、登場人物たちに感情移入を促し、逆にこの小説は恐ろしくなる。「提供者」たちの運命は、私達自身の生のメタファーでもある。最後の一行を読み終えると、めまいがするような感じで、しばらくは動けなかった。
0投稿日: 2008.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログあまりに予想外な題材を、心の準備もできないうちにただ知識として与えられ続ける。だから‘教えてもらっているようで、実はなにも教えられていない’。 使命を果たすために生み出されたのだ。でもせめて、子ども時代くらいは…という先生方の理想が、優しさなのか欺瞞なのか、その両方なのか。結局、誰の心も本当には教えられないまま、ぼんやりとした霧の中で物語も、彼らの人生も幕を閉じていく。人生?彼らの人生って、これまでって一体なんだったんだろう。決められた運命があってただそこに向かっていくだけの人生に、つらいとか哀しいとか幸せな記憶が何をもたらしてくれるのか。そんなことはない、必要なんだと彼ら自身は言うんだろうか。 そういう運命を背負って生まれた彼らの気持ちははかれない。でも私には、自分と彼らとの違いも、分からないままである。 タイトルが、あまりにきれいだ。 わたしを離さないで。
0投稿日: 2008.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ(メモ) 主人公キャシーの回想で話は進む。『提供者』は臓器提供のために作られたクローン人間で、複数回の提供で使命を全うする。その間に行われる介護も提供者の役割で、(ここはいいなと思った)キャシーは同じ施設に生まれ育ったトミーとルースの介護をし、ルースの最期を看取る。 トミーとは、提供を猶予してもらうために規則を破って施設の先生に会いに行くのだけれど、猶予は与えられない。規則は変わらない。それどころか、会いに行った先生から二人は恵まれている方だとまで言われる。(ヘールシャム以外の施設で、提供者は酷い扱いを受けていることになっているけれど、話の中でほとんど触れられていない)結局トミーとは最後の提供の直前に別れてしまう。それでも、一緒にいられた三人は幸せな気がした。静かな話だと思った。 キャシーの回想は施設でのこと。噂話があって、宝箱や交換会があって、打ち明け話があって、気楽な生活。守ってくれる保護官がいる。 マダムが、寮の部屋で踊るキャシーを見たとき思っていたことが最後明らかになるけれど、キャシーの頭の中には、施設(ヘールシャム)も、ルースとトミーの記憶も消えずにちゃんと残る。(マダムは悲観しすぎ?)
0投稿日: 2008.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ待望の文庫化。落ち着いていて、じわじわと魅力が浸透してくるような小説なのは相変わらず。かといってテンションが低いわけではない。とても緻密な小説。よかった。
0投稿日: 2008.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログものすごい期待のせいか? 翻訳に違和感があるのか? なんか言葉しか、文章しか頭に入ってこない。 情景もイメージできるし声も聞こえるのだけど、 だからなんなんだ!と苛ついてしまうこと何度か。 臓器提供のために培養された子ども達を、 「提供者」っていうのとか、訳がいやらしい。なんか。
0投稿日: 2008.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初から最後まで、キャシーという女性が自分の過ごしてきた過去のことを静かに語りかける、という構成。最初少し戸惑いましたが、そのうち自然に物語の世界に入ってゆけました。”ヘールシャム”というところの出身で、自分は介護人になり、親友と恋人は提供者になった、ヘールシャム時代はこうだった、そこを出た後のコテージに居たときはこんな風だった、と、子供同士でグループが出来たり無くなったり、リーダー格の子の気分でお気に入りやみそっかすが入れ替わったり、先輩や友達に見栄を張りたくてどうでもいい小さな嘘をついたり、それをだいなしにすることを言ったり言われたりしてケンカしたり、、、という、自分の小学生時代を思い出すとああわかるわかるわかります、という、そういうことが満載の本でした。 キャシー、ルース、トミーがどういう生い立ちでどういう人生を送っているのか、、、という設定とそこから湧き上がってくるジレンマなどが後からジワジワとボディブローのように効いて来る、不思議な話。地味でしたがおもしろかったです。
0投稿日: 2008.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ深く染み渡るような感じですね。読み終わった後の余韻が静かに続いています。 ところどころ話が他の思い出に移ったりして、本当に主人公の話を聞いている(読んでいる)ように感じました。読み進めていくと、彼女らの置かれていた状況に対しての違和感が明らかになります。臓器提供とか、クローン人間とか・・・。一見「えっ!?」と思うようなことでも、主人公視点の日常として書かれているためか本全体の雰囲気と調和しています。でも、最後は・・・運命の理不尽さというか動かし難さというか。どことなく切なく、物悲しい気持ちになりました。しかし、それが良いのかも、と思ってみたり。
2投稿日: 2008.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本のことは一度どこかで噂に聞いて、強く印象に残ってはいたものの買う機会もなく、そんな日にふと本屋に出てみると文庫版が発売されていたので、胸を高鳴らせながら買った、というエピソードがあります。 カズオ・イシグロという作家自体の異邦性(日本人でありながら英語で著作をしていること)にも興味があって、どんな作品を書くんだろう、リアリズムに徹底したものなんだろうかと勝手に予想していたら、それを見事に裏切られました。 気付けばいつも、へールシャムを探している―――。 主人公は介護人・キャシー。彼女は「提供者」の世話をしていて、へールシャム出身である。 へールシャムというのは、臓器提供者を集めて育てる施設のひとつのことで、物語の大半はここでキャシーやその友人たちがどのような日々を送ったか、という細部の描写につぎこまれる。 そこでは創作活動が強く奨励されていて、ときどき「マダム」が外からやってきては優れた作品を選んでいく。 彼女はそれを「展示館」に持っていっているのだ、という噂もある。 そんななか、創作活動が苦手な少年、トミーはキャシーと深い友情を育み、へールシャムの秘密についていろいろと話し合う。 この二人に、トミーの恋人でありキャシーの親友であるルースを加え、彼らは青年期を経て大人になっていく。 そして大人になって自分たちが提供者となったいま、知ることとなる。へールシャムとは、何だったのかを――。 最初に読んで数行、へールシャムでの回想シーンに移ってすぐに、「これは、マーガレット・アトウッドの『侍女の物語』に似ているな」と直感したのを覚えています。 そしてその印象は最後まで揺らぐことなくわたしのなかに残り続けました。 外界から隔離された場所、さらに、社会とは切り離されそれよりもさらに「下位」とみなされる存在たち、といった設定が類似していたためと思われます。 ついでに言うならば、その書きぶりも、かなり似ている。アトウッドのような比喩の多用は決してないものの、緻密な構成と丁寧な描写が似ている。気がする。 とにかくそういうわけで、この二つの物語から受ける印象は未だに近い。 わたしはたぶん、この物語が内包するものの、10分の1程度くらいしか汲めていないのだと思います。だからよけいなことは書けない。 人間の残酷な自己本位性とか、合理主義への批判とか、つきつめて考えればそれっぽいことはたくさん言えるだろうけど、言いたくない。 これだけ計算されつくした物語を、そうやって言葉でさっと片付けてしまっていいものだとは思えないので。 だからひとつの文章を引用するだけにとどめます。 「新しい世界が足早にやってくる。科学が発達して、効率もいい。古い病気に新しい治療法が見つかる。すばらしい。でも、無慈悲で、残酷な世界でもある。そこにこの少女がいた。目を閉じて、胸に古い世界をしっかり抱きかかえている。心の中では消えつつある世界だとわかっているのに、それを抱きしめて、離さないで、離さないでと懇願している」(p415-416) 翻訳は非常に美しく読みやすく、翻訳ものを読んでいるという意識はほとんどありませんでした。 一度読み始めたら世界にどっぷり耽溺すること間違いなしの本です。
0投稿日: 2008.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなく先が気になってぐいぐいと一気に読んでしまった。カズオ・イシグロの「わたしを離さないで」。 単行本が出た時から気にはなっていたが、ビミョー…という感想も出ていたので、なんとなく文庫本が出るまで待っていた。 謎解きという要素があるのでミステリーといえなくはない。現実を越えた世界の物語だからSF(Science Fiction)といえなくもない。3人の男女の青春時代と人間模様を描いたある種の恋愛小説といえなくもない。なんとも不思議な味わいの作品。 いろいろな書評で言い尽くされてはいるようだけれども、私が惹きつけられたのはやはり抑制された文体の美しさ。 テーマからすれば、もっと感情的に迸る、激情的な作品になってもおかしくない。そこがイシグロの巧さなんだろうな。 最初はなんだか唐突にわけのわからない話が始まって戸惑う。なんだかわからないのに、話は淡々と進むので、不安な気持ちで読み進めるしかない。ここで挫折せずにちょっと我慢して読み進めると、わりと早い段階でこの世界のカラクリは見えてくる。 だけど、別にミステリーではないので、そんなことはこの物語の中ではたいしたことではない。やはりそこにも「人間」が生きている。そのことを受け止めながら、いつしか「自分だったら…?」と考えずにはいられない。 不思議な世界観に「テープ」という古めかしいメディアがなんともマッチしている。 ちょっと伸びたテープが奏でる音楽が聴こえるような気がする。 あのなくなったテープは本当に「世界のロストコーナー」にあったのかもしれない。 「Never let me go(わたしを離さないで)」。タイトルが沁みて哀しい。この世に「Never」なんてないんだ。(2008/Aug)
0投稿日: 2008.08.28
