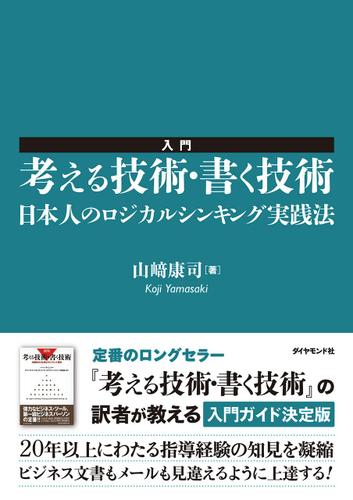
総合評価
(217件)| 76 | ||
| 84 | ||
| 35 | ||
| 4 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会人一年目に出会いたかった。 このやり方を知ったおればどれだけ無駄な時間や会議を削減できただろうか。 知ってるだけでは役に立たない、トレーニングとフィードバックを繰り返して価値が出る本 2018に読んだ中でもトップ10に入る候補
0投稿日: 2018.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ本家の『考える技術・書く技術』は、翻訳がイマイチで頭に入ってこないところがあった。一方、本書は同書のエッセンスが
2投稿日: 2017.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログマーカーとペンを片手にチェックしながら完読。 とても分かりやすい内容で仕事でも実践できる事例も豊富。 今も職場のデスクに常備して書類作成に活用しています。 機会があれば原典にも挑戦してみたい。
0投稿日: 2017.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
バーバラさんの本を読み、ピラミッド原則を理解してから読むほうがよいかも。 バーバラさんの考えを日本語で実践する場合におとしこんだ内容。 書く前にきちんと考えられていなかったことがよく分かった。 OPQ分析で、読み手の望ましい状況、問題、疑問を考え、その答えが主メッセージになる。 そこから、ピラミッドがつくられていく。 文章を書く際はしりてが禁止、ロジカル接続詞を用いる。レポート、メールの書き方など。 今から役立つ内容で読んでよかった。 バーバラさんの本を読んで更に理解を深めたい。
0投稿日: 2017.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まであまり手をつけていなかったロジカルシンキングの本を読み始めてみました。 とりあえずとっても読みにくいです(読み進めるのがつらい) ですが、人に伝えるポイントであったり 考える際のの流れが日本語ベースでかかれているので ロジカルシンキングが苦手な私でもイメージしやすかったです。 ロジカルシンキング系を重きにおいて、今後本を選定したく思います。 実際、人と会話しているときに使えそうなたとえが載っており私生活でのイメージがしやすかったです。
0投稿日: 2017.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングを身に着けるシリーズ。 OPSの考え方やそれに対する答えの導き方を学べた。 学んだことをアウトプットし、習慣化することで、ロジカルシンキングを身に着ける。 O 目的、P問題 S質問
0投稿日: 2016.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ問題(Problem)と疑問(Question)を分けて考える。 例えば、 P:事業がうまくいかない に対しては複数のQが考えられ、 Q1:事業を続けるべきか Q2:どうすればうまくいくのか
0投稿日: 2016.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログあくもでもロジカルシンキングの型の一つを紹介する内容となっているが、重要なポイントを突いており参考になる内容が多い。同時に実践しやすい形式になっているため、有用であると言える。
0投稿日: 2016.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラさんのより、わかりやすい。 どちらかというと書く方に重点が置かれている。 報告書、提案書、メールはこの本で事足りる。 入門とあるがロジカルシンキングをある程度知ってないとキツイ。 あとは、いかに実践するかだなー。
0投稿日: 2016.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社のライティング講座に行ったら先生が、バーバラミントさんの本を推していた。でもちょっと難しそうだったので、こちらの本を先に読んでみた。 ピラミッドの外側を解説してる本ははじめてかも。 薄くても大事なことは網羅されているように感じたので、ピラミッドを自力で書けるようになるまでは座右に置いておきたい。 4ヶ月間毎日ってわりと大変だぞ(笑)
0投稿日: 2016.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ尊敬する先輩からオススメされた本。 もっと早くにこの本と出会いたかった。 自分に足りていなかった考えを知ることができました :pray:
0投稿日: 2016.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的には超良書。 考えをまとめてピラミッドで書き、OPQ分析を利用することにより文章を書くスピードが上がったような気がする。
0投稿日: 2016.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラ・ミントの日本語向け版。簡略にまとまっている。日本語特有の逃げ切れてしまう曖昧性に対して手を打つもの。ポイントは以下 ・OPQベースのピラミッド原則 ・名刺表現、体言止めは使わない ・曖昧な言葉は使わない ・メッセージは一つの文章 ・しりてが接続詞(and)は使わず、ロジカル接続詞を使う ・帰納法は繋ぎ言葉で繋がっているか確認 ・演繹法は前提が本当に正しいのかチェック
0投稿日: 2016.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログアマゾンのレビューで、借りる価値はある一方、買う価値があるかは微妙、という内容で高評価を得ていた。確かにその通り。内容としては読む価値がある。しかし、フルプライスで買うとなると少し高い気がする。図書館で借りるか、古本屋で買うくらいがちょうどいい。
0投稿日: 2016.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ原作の邦訳は難解なので、読み終えても実践が全くできなかった。こちらの本は大変分かりやすく、ビジネスでいかに使うかをレクチャーしてくれた。感謝の言葉とPDF。
0投稿日: 2016.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ#読書開始 ・2015/11/26 #読了日 ・2015/11/27 #経緯・目的 ・企画書、報告書、プレゼンなど考えを整理し、アウトプットする機会が多くなったため、参考図書として購入。 ・文書作成の軸となること、後進育成への活用を期待。 #達成、感想 ・まさに考えること、書くことの基本かつスキルを学べた。 ・当著の内容にふさわしく、シンプルでわかりやすい構成になっているため、説得力もある。 ・ビジネス文書やレポートの書き方などの本を買うなら当著から始めて学ぶ方が効率的で効果的だと思う。 ・当著の内容をさらにまとめて自分のものにしたい。 #オススメ ・ビジネスマンだけでなく、学生にも薦めたい。入門書とすべき。
0投稿日: 2015.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ◼︎考えることと書くことを別のプロセスに分ける ◼︎読み手が読みたいことに答える ◼︎結論から書きだす ◼︎帰納的か演澤的かどちらか意識する
0投稿日: 2015.04.18ひとランク上のレポート作成力を求める人に最適
まず、読み手が何を知りたいのかを知ろう。そのためのツール【OPQ分析】 書く前に、メッセージをわかりやすく整理しよう。そのためのツール【ピラミッド構造】 キーワードは「いったい何がいいたいの?」と思われないよう、so what? を自問すること。 読みやすく、短時間で読めます。
0投稿日: 2015.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
バーバラミントの「考える技術・書く技術」日本人向けの入門書 ビジネス文書を書く技術が満載である。 書くためには考えるプロセスを重視する。 その技術として、 読み手の疑問を明らかにすること それをOPQ分析すること メッセージをグループ化すること それをピラミッド化し、ロジックを展開 あとは文書で表現するが、そのコツが示されている。 個人的には「しりてが」接続詞禁止が役に立ちそうである。 この本のいいところは、練習問題として具体例が多いことである。具体的に文書を書きながらこの本に戻れば、よいビジネス文書となるであろう。
0投稿日: 2015.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ冬の四冊目。楽しんで読んでいます。 ビジネスで使える書くには、学校では教えてくれなかった「技術」と「発想の転換」が必要だということがこの一冊でよくわかります。 書く前に、まずは、自分の頭で考えること。 そのために、ピラミッド原則やOPQ分析といった技術が必要であること。 学校で教えてくれなかったものは、こうやって習得するしかないのか、という悲しさは残るものの、アウトプットの仕方を考えている自分にはタイムリーな一冊でした。 是非読んでみてください。
0投稿日: 2014.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ①選定理由 上司のススメ ②サマリー 読み手を意識したライディング技術について書かれている著書。 ③感想・気づき 読み手が誰なのか、何を求めているのか、どのような立場の人なのか、どのタイミングで読むのかなどを常に意識して、資料作成などの仕事に取り掛かることがいかに重要か再認識しました。 また、複数の事実をもとに結論を導く帰納法やその逆の演繹法などのロジックの立て方なども参考になりました。 ④今後、活用できそうなポイント "読者視点"を忘れそうになったときに、常にこの本を読み返しすことで、自分に対して意識付けしていこうと思います。
0投稿日: 2014.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ論理的な考え方とそのアウトプット方法が具体的に書かれていて、わかりやすいし読みやすいです。 バーバラ・ミント著の『考える技術・書く技術』は専門過ぎて読むのが大変だったけれども、こちらは日本人向けのためか理解しやすかったです。
0投稿日: 2014.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ考えるプロセスと書くプロセスは違う。 書きたいことを書くのではなく読み手の関心、疑問に向けて書く。 まずは状況把握(OPQ分析) アンサー(結論)の組み立て ー帰納法 (なぜならば、例えば、具体的にはのつなぎ言葉) ー演繹法
0投稿日: 2014.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章のわかりやすい書き方が書いてある本。物事を分解し、成分でわけるとわかりやすいと書いてあった。書き方だけではなく、ロジカルシンキングにも役立つ。
0投稿日: 2014.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキング・ライティングの教科書。 物事を論理的に考え、分かりやすく伝える為のコツとして「OPQ分析」と「ピラミッド構造」の使い方を説明している。 分かりやすい文章の作成プロセスは、 ①OPQ分析で読み手の疑問を明らかにする ②答えるべきメッセージをピラミッド構造に落とし込み、根拠や論理展開を整理する ③ピラミッドのメッセージをそのまま文章化 という流れ。 要は読み手の疑問・関心に答えることを意識し、考えるプロセスと書くプロセスを分けることが大切。 研修で習ったピラミッド構造の使い方がやっと腹落ちした気分だった。 しかしあくまで本書は論理展開の矛盾を確認するツールの紹介に重点が置かれている。 よって提案内容に直結する、主メッセージを決める仮説設定の部分はこれから更に勉強する必要がありそう。 ともかく使いこなしていくために、 ①1日一回ピラミッド ②感謝の言葉+PDF を習慣化していきたい。
0投稿日: 2014.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ入門書としてお勧めです。その理由は以下の三点です。 ・考える技術書く技術と比べ、日本語が分かりやすい点 ・練習問題と解説の内容が非常に明快な点 ・分量がそれほど多くない点 先にこの入門書から学び始めることをお勧めします。
2投稿日: 2014.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読んだきっかけ】 ビジネス文章力を見直すきっかけになればいいなと思い購入しました。 原作となる『 考える技術・書く技術―問題解決力を伸ば すピラミッド原則(著者:バーバラ・ミント)』を、日本語特有の問題点に配慮した『日本人による日本人のための実践ガイド』として刊行したそうです。
0投稿日: 2014.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ結果をまず書くことが大事。そのあとに説明すればよい。 考えるプロセスと書くプロセスに分けること。 考えるプロセスでは、読み手が何を知りたいのかを考える。
0投稿日: 2014.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ・コンパクトにエッセンスがまとまっている。少ないページ数なのに、内容が濃い。非常に良書。 ・ロジカルシンキングにある程度慣れ親しんでいれば、すっと入ってくる。 ・汎用的な型と状況に合わせたパターンが学べる。状態か行動か。WHYかHOWか。帰納と演繹どちらで下から支えるか。さほど観点は多くないが、非常に多彩な表現ができる。
0投稿日: 2014.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラ・ミントの名著、考える技術・書く技術を噛み砕いて分かりやすく記載してくれている。 この入門編も名著として一押し!
0投稿日: 2014.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングの本の入門書決定版。良書。 図など盛り込まれていて、ロジックを可視化する事の大事さが理解できる。
0投稿日: 2014.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書はそのタイトルのとおりロジカルシンキングの実践方法が書かれた本です。 それも、日本人のため,私のようなロジカルシンキング・ライティングが全然できていない人のための入門書でもあります。 私もこれまでロジカルシンキングに関する本は何冊も読んでいるし、その中にはもちろん照屋華子,岡田恵子(著)『ロジカル・シンキング』も入っているのですが、イマイチ理解しきれなかったし、自分で”できる”というとこもまではいきませんでした。 でも本書は『入門』というだけあってかなりやさしく書かれているし、図解や例題,練習問題もあり非常にわかりやすい内容でした。 本書で紹介されていた文章の構成(ピラミッド)を考えたり、「しりてが」を使わない,主語を入れる、などを実践して人に伝わりやすい文章が書けるようになりたいと思います。
0投稿日: 2014.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログピラミッド構造で考え、書きましょう、という有名な本の、日本語版を翻訳した著者による入門編。 本編と違って最初から日本語で書かれているので、わかりやすい。 日本語の構造ゆえにピラミッド構造が難しいということにも言及しています。そこから始まるのですが、具体的な説明や例示は、自分でもできるかな?と思わせてくれます。 本編に出てくる情報のみをインプットするより、こちらを読んでからの方が効果はかなり高いと思います。むしろ、まずはこの本だけでいいのかも?なんて思ってしまいます。まだ本編も途中まで読んでるだけですけどね。 巻末の、ピラミッドの基本パターン4つに関する解説がとても有用だと思います。状況のWHY、方針のWHY、行動のHOW、WHYとHOWの三段論法。論理構成を考えるときにあてはめやすい定型ですね。 あと、メールの書き方は、「感謝の言葉にPDF」だそうな。メールは毎日書いてるからすぐ実践できますね。明日からやる。
0投稿日: 2013.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事(研修)に使えそうだと思ったけど、あまり参考にならなかった。内容は悪くないが、理解力のある人向けの言葉を使っているような気がする。
0投稿日: 2013.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ考える技術・書く技術を読む前の本当しては良いと思う。簡潔にすべきことが記載されており、文書を書く時に自然とその意識が植え付けられる。
0投稿日: 2013.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログwritingにおもてなしの心を。 とある読書会の課題図書として購入した。コンパクトにまとまっており、原著及び訳書より手軽に読める点がよい。 ビジネス文書を書く手順をシンプルにまとめると、以下のようになるそうだ。 1.相手の知りたいことを予測する又は聞く 2.相手の関心が低い事柄について書きたい場合は、相手の興味を引く仕掛けを最初に据える 3.相手の疑問に答えるように結論を用意する 4.結論の根拠を複数提示する ロジックも大事だが、私が今回1番反省させられたのは、2の仕掛け不十分だった。 ビジネスでは実際大抵の場合において、自分が書きたいテーマについて相手の関心が低い場合が多いのではないだろうか。そんな中で2を十分に仕掛けることができないと、相手に退屈でめんどくさい時間を強いることになる。あるいはスルーされる。 1も2も詰まるところ相手をどれだけ考えられるかに掛かっている。これは、相手に満足感や有意義な情報を提供しようという、書き手側のおもてなしの心があってこそできることではないかと感じた。
0投稿日: 2013.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の中で特に重要だと感じた要素は 1.読み手の疑問を明らかにすること:OPQ分析 2.主メッセージをわかりやすくすること: ①名詞表現、体言止めを使わない ②あいまい言葉を使わない ③メッセージは一つの文章で収める ④「しりてが」接続詞は使わない
0投稿日: 2013.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログOPQ分析、感謝の言葉にPDF。報告書、メールで意識して使ったら理解してもらえた。実践的な超良書。 バーバラミント「考える技術・書く技術」の入門ガイドというコンセプトであるが、ミント氏のは分厚いハードカバーで読了するのが辛いが、本書は、薄くて読み通せるのと、日本語用アレンジされ実践的、そして万人向けという面で優れており、コンサル以外の通常サラリーマンに広くおすすめできる。
0投稿日: 2013.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ大元の考える技術〜に比べるとピラミッド思考に関する記述が少なく、説明も腹に落ちないものが多いが、メールの書き方等直接的に役立つ箇所は多かった。
0投稿日: 2013.11.10入門 考える技術・書く技術 日本人のロジカルシンキング実践法
ビジネス文書に自身のない方は勿論、使い慣れているという方にもオススメの一冊です。わかりやすく、すぐに実践出来ます。
0投稿日: 2013.11.07良いのですが
内容としては良いのですが、 もう少し具体例もあると分かりやすかったです。 考え方としては参考になります。
0投稿日: 2013.11.05ロングセラー
考え方と書き方をトータルでレクチャーしてくれているので、ロジカル思考が身に付きやすい。 経営入門書として最適。
0投稿日: 2013.11.04大学生から若手社会人まで必読の一冊
仕事をすると、避けては通れない文書作成。そこに求められているのは決して美文ではない。 三島由紀夫や川端康成の調子で文章を書かれても、業務上では困ってしまうだけである。 文章の機能は、間違いなく情報を伝えることが第一である。それには伝えるべき内容を吟味して、論理的に構成する必要がある。つまり、考える方法論が重要なのだ。 すぐに役立つ本を求めているなら、本書は必読です。
0投稿日: 2013.11.04一読して頭に入れてもらうライティングのために
マッキンゼーのコンサルタントであったバーバラ・ミント女史の『the Pyramid Principle』を基に、日本語での運用を念頭に入門書として書かれたのが本書です。 仕事での必要上何年も前に原著を原文で読みましたが、具体的に文章を作り上げていくには本書のほうがかなり使いやすそうです。ツールとしてすぐに適用できるテクニックが多数挙げられています。 また、主語の省略や接続語の使い方など日本語に特有かつ頻発するライティングの問題を推敲しながら取り上げているのでイメージも沸きやすいです。 本書に書かれているトレーニング法、10分ミラミッド×4ヶ月をこつこつと実践すれば型を習得するようにライティングの基礎を改善できるはずです。 あ、あと念のために付言しておきますが、ピラミッド状の論理構造自体は欧米の人には特別なものではなく極々自然なもののようです。しかし、それを膨大に複雑に展開するにはやはりトレーニングが必要であるということみたいです。
3投稿日: 2013.10.23文書作成に自信のある方にも一読の価値あり
文書を書くのが苦手な方や、社会人になりたての方にはもちろんオススメですし、更には日常業務で文書作成する機会がすでに多い方でもスキルアップのために一読されることをお勧めします。 私自身はそれなりにレポート作成に自身はあったのですが、 おぼろげに経験則で身につけていたコツをうまく整理できたと思います。
2投稿日: 2013.10.12ビジネス文書を書く人に必携
報告書やメールなどのビジネス文書を書くために必要な技術を具体的に解説した本。 社会に出ると他人を納得・説得するための文書を書く機会が増えると思うが、 本書では提案書や報告書など、具体的な文書を例に文書の考え方と書き方を解説してくれる。 わかりやすい文書をなんの訓練もなく書くことは難しく、本書で解説する技術を身に付けることで どのような文書構成、展開で文書を書けばよいか、どんな表現を利用すべきか、利用すべきでないかがわかるようになる。 自分も本書を活用し、わかりやすい文が短時間で書けるようになったという実感がある。 新社会人などのビジネス文書ではどのような点に注意すればよいかわからない人、 自分が書く文書がわかりにくい・なかなか書ききれず時間がかかると感じている人にぜひ読んで欲しい。
2投稿日: 2013.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログプレゼンテーション、企画書、メール、それから口頭でのやり取りにおいても、ピラミッドプリンシプルの考え方は絶対的に必要。 今まで意識していなかったことが恥ずかしい。
0投稿日: 2013.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラ・ミントの 『考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』 ――ロジカルライティングの本として有名―― の導入本,要約本という感じ。 著者は『考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』 の翻訳者である山崎康司です。 ただし,副題に「日本人のロジカルシンキング実践法」とあるように 日本人(日本語)向けにアレンジしてある。 読みやすいし,よくまとまっている。良書です。
0投稿日: 2013.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログさすがに、読み手にとって、要点が掴みやすい本。 ロジカルシンキング系の本を読んでいれば、それほど目新しいことはないが、分かりやすい文章ってのはこう、というのを確認できる。 読み手の目標、現状、そのギャップを埋めるには?という問いがあって、その答えを、読み手に伝えるって事から文章がブレないこと。 その答えってのは、so whatでより具体的で、その問題に合った答えである事。 答えには、why根拠となる事実、howどうやって、を、3つずつくらいの分類で、紐付けること。演繹法であったり、帰納法であったりで、答えと行ったり来たりさせて、見つける。 接続詞は、使う意図を意識して使う事。 メールは、感謝の言葉、主メッセージ、詳細、次の行動。という組み立て。
0投稿日: 2013.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラミント著「新版 考える技術・書く技術」は読んだことはないが、翻訳者である著者が、主語が明確ではないなどの日本語に即したビジネス用の入門書。 本のレイアウトもよくみやすく、本書内に実践的な問題も書いてあるので、本書の趣旨を短時間で理解できた。巻末の基本パターンも有効に活用できると思う。 本書の内容を要約をすれば、読み手に必要な情報・意見を絞り、自分の考えをピラミッド構造でまとめ、文章化することである。 具体的な絞り込みはOPQ(Object 望ましい状況 Probrem 問題・ギャップ Question 疑問) → Answer という形で何を明らかにするかを明確にする。 自分の考えを形にするためには帰納法・演繹法などを使いながら、ピラミッド構造を作っていく。短期記憶5~9までの構造にする。しりてがの接続助詞に気を付けながら、So whtatを常に問いかけること等を気を付ける。 考えのピラミッド構造ができれば、それを段落等のレイアウトに気を付けながら文章化するということになると思う。章末には、メールを書くときに、感謝の言葉、メッセージ、詳細、今後のアクションとすればよいことがわかった。
0投稿日: 2013.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ文書を書く際の思考の纏め方と効能が分かりやすいために、実践すべきと感じる本だった。 本で紹介されているOPQ分析は相手目線で文書の主題を定める手法であるため、読み手が意欲的に文書を読んでくれる。 ピラミッド構造を作る際に意識すべき事を纏めているため、本に習った実践に向いている。 練習問題やテンプレートが用意されているため、思考の整理法としてスタートしやすい。 毎日の実践方法が例示されているので、簡単なところから始めやすい。 読んでみて実践してみようと思う1冊でした。
0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、書く・考えることのグローバルスタンダードである「ピラミッド原則」について説明し、実際に読者が例題を解いていくことで理解できるように書かれています。 ピラミッド原則は、ロジックツリーとも呼ばれます。論理的に考え、文章構成を作っていくために不可欠な、そして、書いた文章を相手に読んでもらい、理解してもらうためにも役立つ考え方です。いわゆる「レポートの書き方」といった他の書籍は、レポートの構造・実際に各段階にどのような形式で書けば良いかが説明されていることが多いように感じます。そのため、形式は整っていても、中身が伴わないものになる可能性も。 一方で、ピラミッド原則などの考え方を身につけてしまえば、大学のレポート、社会に出てからのビジネス文書、メール、と幅広く活用できます。 春休み中に、自分のライティングを見直してみてはいかがでしょうか。 (2012ラーニング・アドバイザー/生命 TSUBOYAMA) ▼筑波大学附属図書館の所蔵情報はこちら ☆中央図書館2F「アカデミック・スキルズ図書コーナー」にもあります。 http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1431746&lang=ja&charset=utf8
0投稿日: 2013.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラミントさんの考える技術・書く技術ではわかりにくかった、「結局どう活用すればよいのか」がわかる本。 日本語固有のこうまとめる、こうまとめてはいけないもわかってすっきり。
0投稿日: 2013.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、メールの書き方を指導する機会があり、自分のスキルを確認するために求めた書。 読みてに訴える読みやすい文書の書き方を、改めて再確認できた。 思えば、TwitterやFacebookに日々書いているのも文章術向上につながっているのかもと…
0投稿日: 2013.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラ・ミントさんの『考える技術・書く技術』が日本人用にリメイクされています。 比べてみると、『入門編』とタイトルにあるように、こちらの方がかなり分かりやすい構造になっているため、ロジカルシンキングを学びたい人にはこちらから入ることをオススメします。 例や練習問題なども豊富なので何度も読み返すことで理解が深まると思います。
0投稿日: 2013.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ★★★☆☆3 役に立つけど、面白くない本だよ。 文章やプレゼン資料作成の際にはこの本の方法は使えると思う。なぜなら、前に読んだ別の本で似たような方法を知り、仕事の提案資料作成の際に実際に試してみたことがあるから。 この本は練習問題が多くて、セミナーを受講しているみたいな気分になるよ。練習は読み飛ばして、ピラミッド図のページと巻末付録だけ見ても充分だと思ったよ。
0投稿日: 2013.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
バーバラ・ミント著「考える技術・書く技術」の訳者がだしている入門書です。 バーバラ版も読みましたが、正直頭にのこってません。翻訳書なのでかなり難解に感じ、こんがらがってしまいます。 しかし、本著・「入門~」を読んだあとにはもう一度チャレンジしてみたくなります。その意味でも入門の位置づけとしては的確です。 また、普通にビジネス文書を作成する分には十分すぎるほどのノウハウがきれいに説かれています。 まず、書くプロセスと、かく前に考えるプロセスを分けることが大事と述べられていて、本著では考える(書く事を整理する)プロセスについて主に書かれています。 考えるプロセスとして、最初に文章とは読み手の興味に答えるものであるべきと記されています。そこでOPQ分析が提唱されています。 ・0:objective(望ましい状況) ・P:Problem(問題、現状とObjectiveとのギャップ) ・Q:Question(読み手の疑問) ここで、自分(書き手)と相手(読み手)の意識のすり合わせを行い、それに答える(Answer)を提示します。ここで大切になってくるのが、読み手を主語にして「書く目的」を考えること。そりゃそうなんですが、なかなか見失いがちなので気を付けようとおもいます。 OPQ分析で質問を確認したあとはAnswerが当然主題となり、それを支える形でピラミッドを作成していきます。 ピラミッドの作成時に注意することとして次のようなことが述べられています。 ・一つのボックスには1つの内容のみ書く。 ・上のボックスの内容が下のボックスの要約になるようにする。 ・帰納法でプラミッド作成する場合、同じグループ(1つ上のボックスにぶら下がる下のボックス)は要約との関係を同じにする必要がある。 下部メッセージの主部が同じ→要約メッセージの主部と一緒になるので、要約の述部を推測 下部メッセージの述部が同じ→要約メッセージの主部を推測 下部メッセージの意味するものが同じ→意味するものが要約メッセージとなる ・帰納法とは、複数の特定事象(前提)から要約(結論)を導くロジック。結論は、常に推論となります。絶対的な真実ではなく、前提から導かれた「論理的に」正しい推論。 ・帰納法は前提部分はかならず複数となる。(5つ以内) ・演繹法は、絶対的に正しいことや、一般的に正しいと判断されること(前提)から、妥当と思われる結論を導くもの。(三段論法など) ・演繹法は帰納法と違って、すべての前提(下部メッセージ)が正しければ、結論は絶対的に正しくなる。推論ではない。 ・前提の正しさのチェックは入念に。 ・ビジネスの場合は絶対的に正しい前提があまりないため、一般的には帰納法のほうがよく使われる。 ・ピラミッド内でわかりきったことを書かない。 ・ピラミッドの構造はそのまま文章の構造とする。(文章を書く段階で変えない)
0投稿日: 2013.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ■序章 誤解だらけのライティング ・考えるプロセスと書くプロセスは分ける ■1章 読手の関心・疑問に向かって書く ・読み手の中でターゲットを設定する ・読み手の疑問を明らかにするにはOPQ分析を行う。OPQとはObjective,Problem,Question。 ・問題のレールは合わせる。(ex.(ダメな例)売り上げと在庫の2つを問題とするケース) ・(読み手の立場に立つには?)自分にとって読みにくいメールのわるい部分を認識する ■2章 考えをかたちにする ・ジョージミラーの「マジックナンバー7、プラス・マイナス2」という論文が話題になった。ビジネスでは下限の5とする。 ・メッセージは1つの文章(各章・段落)で1つとし、それ以上になる場合は2つに分ける。 ・ピラミッド化は「要約メッセージ」「グループ化」から、つなる。 ・メッセージが一般論にならないようにきをつける。 ・ピラミッドをつくる際の4つの鉄則。「名詞表現・体言止めは使用しない」「あいまい言葉を使用禁止にする」(意図的な場合はOK)「メッセージは1つの文章とする」「(しりてが)といった非論理的な接続詞はしようしない。単文がベスト」(※1) ※1 ~し、~であり、~して、~だが、~せず、~なく、など非論理的な接続詞。英語の場合はandを避ける。「にもかかわらず」「ことにより」「ために」などのロジカル接続詞を使用する。 ・So whatを繰り返すことにより、要約メッセージを明確にする。 ■ピラミッドをつくる ・帰納法と演繹法 ・帰納法は前提から結論を導く。結果として、推論となる。 ・前提は常に複数かつ5つ以内とする。 ・ピラミッドのチェックは「つなぎ言葉」を下部メッセージの文頭に入れてみる。(なぜそう判断するかというと、たとえば、具体的に)など。上下でうまくつながるか、横で同じつなぎ言葉が入るかをチェックする。 ・演繹法は複数の事実(下部メッセージ)から結論(上部メッセージ)を導く。結論は常に正しい。 ・ビジネスでは絶対的前提はあまりない。結果として、帰納法がよ く使われる。 ・演繹法は、過去や現在の事実に正しい法則や妥当な過程を適用するというかたちで使われる。 ・演繹法は前提をチェックする。加えて第一文の主語や述部が第2文に引き継がれているかをチェックする。 ・ピラミッドをつくる際は以下に注意する。 ・ピラミッドに文章を書こうとしないこと。 ・主メッセージとキーラインを早めに決める。 ・読み手の既知の事項は書かない。 ・例外的に1つのキーラインを掘り下げるという「イメージによる説得」を用いる場合もある。 ・ビジネスライティングは書くプロセスには比例しない。考えるプロセスをこなした回数により向上する。
0投稿日: 2012.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ先輩に勧められて購入。具体的に何が書かれているかわかりにくいタイトルだけど要は、主にビジネスにおいて、どんな文章にすればちゃんと読み手に読まれるかを書いてる本。それのめちゃ入門。よって「それ当たり前じゃね!?」と思うようなこともたくさんありました(例:結論を先に持ってくるなど)。でもなるほどと思わせる部分もちらほら。わかりやすくすぐ読めた。しかし、いつも無意識にやってること(例えば、読み手の気持ちになって書く、など)を意識的にやるよう書いているので、ちょっと内容が入り込みにくい感はある。
0投稿日: 2012.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ文書を書くときは、考えるプロセスと書くプロセスに分ける。 ピラミッド原則は、考えるプロセスに役立つ。 常に読みての関心、疑問を意識する。
0投稿日: 2012.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
〈内容〉 学生時代にライティングの技術について教育を受ける機会は全く無かっただろう。考える技術、書く技術を正しく身に付けるべき。 〈著者〉 山崎康司氏。東大卒。 〈感想〉 読んで良かった。有名な本チャンの方は何だか分厚い本だったので、こちらの平易な入門書から読んだのだが、それでも十分エッセンスを教えてもらった。 この本で紹介される基本技術を無視して、「何とかわかりやすい文章を!」という気合で突破しようとしていた自分が恥ずかしい。 〈備忘録〉 ・まずOPQ分析。読み手にとっての望ましい状況;Objective、読み手にとっての問題、Objevctiveとの;Problem、読み手にとっての疑問、どうすればPを解決できるのか;Question。 ・QへのAnswerが文書の主メッセージ。 ・メッセージの鉄則4つ、体言止め禁止、あいまい禁止、一つの文章で表現、「しりてが」接続詞禁止。 ・「しりてが」ではなく、ロジカル接続詞。する時に、前に、後に、迄に、である一方、であるけれど、の結果、であるがゆえに、であるにもかかわらず、する為には、もし~ならば、等々。 ・で、主メッセージを説明するキーラインを作成する。マジックナンバー7±2→5を心がけよう。主メッセージとキーラインの関係を、So What?で確認。 ・使えるフレーズ、「同意いただければ早急にアクションします」。 ・感謝の言葉にPDF。Purpose statement、Dtail、Follow-through。 ・1日1回ピラミッド。 ・ピラミッドの基本構造、状況のWHY、方針のWHY、行動のHOW。 以上。
0投稿日: 2012.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み手に伝わりやすい文章を書くための実践方法が具体的に書かれている。 OPQ分析による問題の整理、ピラミッドによるロジックの整理、それをそのまま文章にすることでわかりやすい論理展開の文章が書ける。 まずは日々のメールで意識してみたい。
0投稿日: 2012.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラ・ミント氏『考える技術・書く技術』で挫折し、この本へ。日本人向けに書き直した分、読みやすい。OPQフレームワークは有用。いずれ子供にも読ませたい。
0投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ目新しいことが書いてあるわけではないけれど、意識しないとおろそかになってしまう、「きちんと考えること」の見直しに。 「読み手の立場に立って」とか、「テーマがぶれないように」とか良く言われるけど、意識を変えようとしてもなかなか難しい。 ロジックツリー(本書では「ピラミッド」)という便利な道具も知っているけど、いまいち使いこなせない。 そんな状態で読んだところ、プロセスが簡潔かつ丁寧に説明されていて、とても分かりやすかったです。 人に話して説明することは自分で理解するより難しく、文書に書いて伝えることは話して説明することよりはるかに難しい。 日々トレーニングあるのみ。
0投稿日: 2012.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ【表現】考えることと書くことについて分かれてはいるが、ページが割かれているのは「どのように考えるか」についてだ。他者に自分の考えを伝える際にはいろいろなミスリードの危険性がある。それをなるべく少なく、かつ受けての負担が少ないように配慮するのが伝える上での基本である。最後の章の「感謝の言葉にPDF」(①感謝の言葉②P(主メッセージ部分, Purpose Statement)③D(詳細, Detail)④F(今後のアクション, Follow-Through))は、読んだ後に誰でもすぐに実行できるようにまとめられていたためとても良かった。
0投稿日: 2012.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ私のように、バーバラ・ミント氏の原著が頭に入らない人向けです(笑) 原著の導入書として、上手くまとまっていると思います。 当初、原著を読んだものの上手く頭の中が整理できなかったので、この本を読み、改めて原著を読み直すアプローチに変えたところ、すんなりインプットすることができました。 コンサルティング・ファームへの就職や転職を考えている方は、まずこの本から入ってはいかがでしょうか。
0投稿日: 2012.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス文書の書き方紹介。 こうした文書を書くようなことが今後あるかという疑問はあるが、 わかりやすかった。 「しりてが」接続詞を極力さけるというのも勉強になった。
0投稿日: 2012.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書でメインとして書かれているのは、コンサルタントで言うところの'As is,To be'である。 ①現状認識(発生している問題) ②本来あるべき姿 ③①と②の差を埋めるにはどうすべきか(対策) こうしてみると、「なんだ、簡単じゃないの」と思われるかもしれない。だって、3つのステップを踏めば問題解決できちゃいうんだから。しかし残念なことにそう簡単にはいかない。実際にやってみればわかるが、①のステップが難しい。だって、「証拠がないものは信じてくれない」から、事実認識とそれを裏付ける証拠が十分にないといけない。これが結構骨が折れる。ただ、この事実認識がしっかりしていると誰よりも強力な武器となって、味方になってくれるのは間違いない。 バーバラ・ミント女史の著書など、ロジカル系の本は読みなれない人には分厚くて内容が退屈で挫折した人も多いかもしれない。けれどこの本は、薄くて内容も平易に書いてくれているので、考え方や文章の書き方の「とっかかり」として読むにも、すぐに実践できて役立つと思う。
0投稿日: 2012.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングとロジカルライティングについて合わせてまとめられている。結果として考えをまとめ、それを文書に書くことができるようになる。 まず、読み手を意識する、という観点でOPQ分析が紹介される。 その後ピラミッドに関して解説されていくなど、構成がはっきりしておりスラスラと読める。 また、「しりてが」接続詞の禁止や「So What?」の利用など細かなテクニックも充実していた。メールのPDFは早速利用していきたい。
1投稿日: 2012.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングを実施するために。 考えるプロセスと書く(話す)プロセスを分ける。 アウトプット(書く、話す)がわかりにくい原因は、『考えるプロセス』にあり。 その考えを組み立て、チェックするツールが、ピラミッドである。 読み手の視点 Objective 望ましい状況 Problem 現状とのギャップ Question 読み手の疑問 Answer 文書の主メッセージ 要約メッセージ作成のポイント 名詞表現、体言止めは禁止とする 曖昧言葉は禁止とする メッセージはひとつの文書で表現する 『しりてが』接続詞は禁止とする So what? それで、何が言いたいの? 今は、考えるプロセスの作業中! Why so? なぜ、そう判断するかと言えば なぜならば たとえば 具体的には 書いて始めて、考えの曖昧さに気づく。考えを明快に構成できれば、文書作成プロセスは終わったも同然です。 ピラミッドのメッセージがうまく文書に置き換えられないときは、いったん考えるプロセスに戻ってピラミッドを修正するところからやり直す。 メールで実践できるポイント 感謝の言葉にPDF purpose statement detail follow-through
0投稿日: 2012.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログとても便利な点は、間違えそうな点を強調してくれているところ。例えば、考えるプロセスと書くプロセスは分けるんですよ要約は書くときに婉曲化させればいいんだから考える時はピシッと端的につくれと言ってるところが、あ~そういうことなのね、と理解を助けてくれた。
0投稿日: 2012.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は明解なビジネス文書を書くための基礎となる考え方を示した本です。本家「考える技術・書く技術」を読む前の入門として読みました。 内容は以下の通りです。 ・書く前に読み手の関心・疑問を明らかにする ・読み手の疑問を明らかにするための手法として、OPQ分析が有効である。 ・考え方の基本として、まず要約メッセージを探す ・So what? それで何が言いたいの? は要約メッセージを探すための呪文 ・ピラミッド原則を用いて考えをまとめる ・ロジックの基本は帰納法と演繹法の二種類がある ・しりてが言葉は可能な限りロジカル接続詞に置き換える ・日々のメールは「感謝の言葉にPDF」を意識する ・一日の終わりに、その日書いたメールをピラミッドで表す練習をする
0投稿日: 2012.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ•具体的なターゲット(読み手)設定、徹底した読み手目線! •文書の主メッセージとは、読み手のQに直接かつ簡潔にAで答えるもの。 •書くプロセス≠考えるプロセス。考えるプロセス→書くプロセスの順。考えるプロセスとは、主メッセージを見つける作業に通じる。ここに問題があるとき、書くプロセスが分かりにくくなる原因となる。 •OPQ分析
0投稿日: 2012.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ論理的であるということをテーマとして扱うには、少し記述内容に厳密さが足りていないのではないかと思った。この本において論理の基本として位置づけられている帰納法と演繹法の説明に納得しがたい部分がある。 帰納法について、作者はこう説明している。 > 帰納法とは、複数の特定事象(前提)から要約(結論)を導くロジック展開です。結論は、常に推論になります。絶対的な真実ではなく、前提から導かれた「論理的に」正しい推論です。 論理的に正しい推論というものはどういうものだろうか。もし前提から3段論法のようなもので導かれるような推論のことだとすれば、演繹に分類すべき。そうでないとするなら、前提との間で矛盾を起こさないとか、主観的にもっともらしく感じる、という程度の意味しか持たないのではないか。そのような消極的な意味を「論理的に正しい」と表現するのは、議論を混乱させるだけだと思う。 また、演繹法については作者はこう説明し、以下のような例を挙げている。 > 演繹法の場合は、すべての前提が正しければ、結論も絶対的に正しくなります。推測ではありません。 > … > 前提1:X事業は、今のコスト構造のままでは、売上100億円が損益分岐点となる > 前提2:X事業は、来期の売上はどう楽観的に見ても95億円止まりと見られる > 結論:ゆえに、X事業は、コスト構造の改革に着手しない限り、来期は大幅な赤字になるだろう しかし、この例で行っている論理展開は演繹ではなく帰納である。前提1と前提2から、結論を演繹することはできない。例えば、コスト構造の改革をしなくても為替変動によって95億円の売上で黒字になるというケースもあるかもしれない。この結論の正しくなさは前提の間違いに由来しているのではなく、論理展開が演繹になっていないことから生じている。そもそも演繹の結論は「絶対的に正しい」と定義しているのに、その例で出している結論は「…だろう」で終わる推論になっているのだから例としてふさわしくない。 これらの説明に共通して感じたのは、作者は論理的な正しさというものの適用範囲を過大に表現しているということだ。帰納法は正しさを担保するものではないし、演繹法は適用できるケースが少なすぎてビジネス文書の論理構造としてはほとんど使えない。これらの注意点については著者自身も指摘しているけど、これらと矛盾するような説明も同時に見受けられる。 論理性というものは強力なものだけど、この本が題材としているようなビジネス文書の世界では限定的にしか役に立たない。ビジネス文書というものは何らかの意図を持って書かれるものであり、客観的事実と論理的な正しさだけでは組み立てられない。必ずなんらかの飛躍を含むものだ。しかしそれは悪いことではなく、その飛躍にこそ文書の価値が宿るのだと思う。ならば「もっともらしさ」を積み上げていくことでその飛躍を論理的に補強してやり、読み手がその飛躍を追体験しやすくしてやろうというのが現実的な態度だと思う。
0投稿日: 2012.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ入門編だったおかげか読みやすく、ポイントも分かりやすかった。 改めて自分の文章に、曖昧言葉や“便利な接続詞“が多いと実感(^^; 考えをまとめて、簡潔に文章に落とすって奥が深い。。。
0投稿日: 2012.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ロジカルライティング」シリーズの上下巻の前にこの入門編を読んで良かったです。私はい和文・英文問わず日常のメールで情報を詰め込んだ一方的なスパゲッティメールを書いてしましがちなため、簡潔かつ相手のわかりやすい文章を書けるようになるための手引き書を探していたところ、たまたま本書を読みました。事務的なコミュニケーションは別として、何らかの問題に共同で対処する時や相手との交渉の場合などは、本書で書いてあるシンプルな原則に戻るようにしています。
0投稿日: 2012.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログメッセージはただ1つの文章で表現する、など一見当たり前なのだけれど、大切な事柄が分かりやすく掲載されている本でした。
0投稿日: 2012.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジネス文書(報告書や提案書など)に特化した「わかりやすく」「読み手の要望を満たす」ための文書作成指南書。ピラミッド展開などの技法を使った図解説明が親切だ。 著者がコンサルティング畑の人らしく、「顧客から○○事業の分析を依頼された」みたいなシチュエーションを元にレクチャーが展開される。そんなにシンプルでいいの?と拍子抜けするほど、要素を整理して組み立てられた例文は、すっきりしている。 NG接続詞とかの例示もあり、改めて自分のビジネス文書を見直してみるいいきっかけになった。
0投稿日: 2012.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログOPQ分析(Objective:理想、Problem:問題、Question:問題解決のための疑問) しりてが使用禁止「…し、…」「…であり、…」「…て、…」「…だが、…」などは文章が長くなってわかりにくくなるから使わない 感謝の言葉にPDF(PurposeStatement:目的文、Detail:詳細、FollowThrough:今後のステップ・結び) というのがわかりやすい。これ読んだら、ダラダラと長い文章は書かないようになると思います。
0投稿日: 2012.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分はメールの文章が苦手です。しかし、本書の「感謝の言葉にPDF」を真似することで、少し良くなってる気がします。 本書では、わかりやすいビジネスのレポートの作成方法を学びます。 自分がためになったポイントは、 ・伝えたいメッセージ→その根拠→その詳細説明の層にする。 ・層の間は、つなぎ言葉でチェックする。「なぜそう判断するかと言えば」、「なぜならば」、「例えば」、「具体的には」で層を文章にしてみて、おかしな場合論理的に間違っている。 ・Andは使用しない、ロジカル接続詞を使用する。「~する時に、~である一方、~であるがゆえに、もし~ならば、」で文章をつなげる。 説明がシンプルで図を多用し、誰にでもわかるように本書は書かれています。 普段、何も意識していない方は、一度、本書を読んでレポートの作成方法を学ぶことをお勧めします。 でも、感謝の言葉をメールの先頭に書くのは恥ずかしいです。。
0投稿日: 2012.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書に出会うまで、考えをロジカルにまとめるノウハウは習った覚えがなかった。とても実践的でわかりやすい。習慣化して血肉にしよう。
0投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジネスの文章は、相手に要点を整理して論理的に伝える必要があるとともに、なぜそうなのか、といった根拠や判断基準を盛り込む必要があります。 ここでは、相手の気持ちや立場を良く考え、伝えるということはひとまずおいておきますが、要点を整理して相手に伝えないと、時間がかかったり、誤解されて伝わったり、ということになってしまいます。 しかし、相手に要点を的確に伝えるために論理的に考え、そして論理的に書くためにはどうすれば良いのか?ということはあまり学ぶ機会がないため多くの人はあまりこれを意識しないまま、論理的でない散文的な文章を書いてしまうということが起こります。 では、いったいどのようにすれば論理的で相手に誤解を与えず、かつ短時間で要点を伝えることが出来るように書くためにはどうすれば良いのか、ということになりますが、事実や論点を整理し、文章に落とすためのスキルとして「ロジカル・ライティング」があります。 この、具体的な方法としては、バーバラ・ミント著「考える技術・書く技術」で紹介されていた、文章に書きたいことの要点をまずピラミッド構造に整理し、伝えたいメッセージとその根拠を帰納法か演繹法で確認して文章に落とすというような方法があります。 ただし、「考える技術・書く技術」は英語を日本語に翻訳した著作であるため、日本語特有の曖昧な表現に注意しないときちんとした論理的思考が難しいとして、日本語で考える時の落とし穴について解説してあるのが本書「入門 考える技術・書く技術日本人のロジカルシンキング実践法」です。 著者は、日本語は特に、1) 主語が省略されることが多い、また 2) 接続詞が曖昧で、例えば「~であるが」というような場合、因果関係が不明確になるためこのような部分に気をつけておかないとロジックが曖昧になってしまう指摘しており、こうならないための対処法が書かれています。 本書では、ミント本で導入されていたSCQA(状況、複雑化、疑問、答え)をシンプルにしたOPQA分析が導入されています。そして著者は読み手の視座からどう見えるかについて考える必要性を強調します。 O:Objective(望ましい状況) P:Problem(問題=現状と望ましい状況とのギャップ) Q:Question(読み手の疑問) A:Answer(答え=文書の主メッセージ) それで、各メッセージをピラミッド状に配置しメッセージの構造を明らかにする、メッセージの数が多くなる場合はジョージ・ミラーの7±2 から数を要約する必要があるというのはミント本と同様です。 それで、各メッセージを文章にする時のやり方としては、 名詞表現、体言止めは止める。 曖昧な言葉は避け、具体的な表現にする 1メッセージを1文章で表現する 曖昧な接続詞を使用せず、因果関係、時系列が明確に接続詞を使う ビラミットの下位のロジックを帰納法にする場合は接続詞で関係を明示する ピラミッドの下位のロジックを演繹法にする場合は前提を確認する その他 基本はミント本と同様ですが特に日本語に特有な注意点に書かれている本書は秀逸です。
0投稿日: 2012.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングの入門書。ビジネスライティングのコツがよく分かります。大変役に立つ名著。ミントの考える技術・書く技術への橋渡しにもなりそうです。というか勢いづいて、考える技術・書く技術とワークブックも買っちゃいました。
0投稿日: 2012.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「相手の問題を的確に捉えて、自分の考えをわかりやすく伝えたいあなたに」 この本ではライティング能力を向上させるために、以下の3つツールを紹介している。 1.相手の抱えている状況を把握する、OPQ分析 2.自分の考えを構造から知る、ピラミッド・ストラクチャー 3.日本語独特の”文章のつなげ癖”を正す、ロジック接続詞 これらのツールは、ライティングの名著「考える技術・書く技術(バーバラ・ミント/著)」から重要なエッセンスを抽出して、日本風にアレンジしたものだった。エッセンスが絞られている分、丁寧な説明と演習問題がのせられており、「バーバラの本を読んだけど難しい!」という人にはお薦めのライティング入門書です。 また本書を一読すれば、就活サイトに載っているESやメールの書き方が正しいのか、なぜ正しいのか、を判断する一助になるだろう。
0投稿日: 2012.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ロジカルに物事を考えたいと思ったので、この本を手に取った。 自分が使っている言葉がいかに曖昧であるかということを思い知った。 何故かというと自分の言葉には具体的なアクションが伴っていないからだ。 例えば、よく自分は「担当者との関係をしっかり構築する」とかいうことを書いていた。(今も) 当然だが、「では、『関係を構築する』って、具体的にどうするの?」っていうツッコミが入る。 そこで自分は考えていないから、何も答えられない。 そうではなくて、「Aという問題があるので、Bをします。Aという問題があるのは、C、D、Eだからです。Bは具体的にはF、G、Hをします。」ぐらいのことをスラスラ言えるようならなければ。 このようなことができていない自分をふがいなく思う。 しかし、できていないのは間違いないから訓練するしかない。 訓練というのは具体的には「1日1回ピラミッド」である。 詳細は本著に任せる。
0投稿日: 2011.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラミント氏の本を理解しきれず困っていたところ、この本を見つけた。なんてわかりやすい本なのだろう。よく見たら、著者はバーバラミントの翻訳もやってらっしゃる方なのですね。ご本人としてもあちらの本は難しいと長年お感じになられていたのか。こちらの本は解説がとても明解で理解しやすかった。 しかし、実践でこれを貫き通すのが難儀。考える前に書いてしまう悪癖。あっ、このレビューも勢いで書いてしまった。修行あるのみ…
0投稿日: 2011.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ一見難しそうな「ロジカルライティング」について、本書はとても分かりやすく解説してくれます。 5冊くらい買った関連書の中で、個人的には一番分かりやすく、実践的な本でした。 特に仕事でeメールを書く際の心得、『感謝の言葉にPDF』(まず感謝、その次に「要点」、「詳細」、「補足」の順に書くこと)は、仕事にとても役立っています。 この本を読んで、主語や接続詞を曖昧にする日本語の特性(そこが美点でもあります)について、改めて考えさせられました。
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログOPQ O 望ましい状況 P 問題 Q 読み手の問題 (A 答え) まず読み手の気を引く 結論から書き、箇条書きでぽんぽんぽん 相手の立場に立って、相手が何を要求しているのか考える、または直接聞いてみる 要約メッセージは名詞表現、体言止めは使わない 「問題」「再構築」など曖昧な表現は使わない and を使わない(何と何を結んでるのか分かりづらい) So what なぜそう判断するかを考える
0投稿日: 2011.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス文書を書くヒトは誰もが知っておいたほうがいいと思う内容だった。文書を書く際にはObjective, Problem, Question + Answerを書く、またピラミッド構造ができなければ文書は書かない、最後にメールでは「感謝を込めてPDF」構造が大事という点は頷けた。(冒頭に感謝を言い、そしてPurpose Message, Detail, Followの3つを念頭に置く)
0投稿日: 2011.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトル通り、考え方/書き方について書かれた非常に解り易い本です。6年程前に、著者にお会いした際に、バーバラミント著の「考える技術・書く技術」(著者翻訳の本)が難しくてよく解らなかったことを話したら、「あれはコンサル向けの本だから、普通の営業マンには難しいかも…」と話されていました。この本は、その問題に応えて下さったのではないかと思えるほど、私にも解り易く、すぐに実践したくなる内容でした。以前読んだ「オブジェクティブ&ゴール」(山崎康司著)も解り易い本で、著者の伝え方の巧さを改めて感じさせられました。本にあるように、今日から毎日ピラミッド構築を実践することにします。
0投稿日: 2011.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ日常の業務でメールを書いたり、企画書を書いたり。でもなかなか上手く書けなくて添削で直されてばかり。そんな自分とってこの本はまさに基本的な考え方から正してくれる本でした。 内容としては、まず最初に、なぜ日本人がロジカル表現を苦手としているのか原因からふれており、ビジネス文に必要な、根本的な考え方の違いに付いて説明されています。 具体的には、ピラミッド構造を中心としたOPQ分析、接続詞の注意点、またPDFのフレームワークでなど、今すぐに実践でくる要素がちりばめられています。 あの分厚いバーバーラ・ミント著はハードルが高いなと感じた方、 この本は読みやすくまとめられているので、是非おすすめの本ですね。
0投稿日: 2011.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ・バーバラ・ミントの著作を翻訳している著者が、そのエッセンスを簡単にまとめたもの。 ・内容は分かりやすく、図も多い。後はピラピッド作成を継続する力が必要なだけだ。
0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「非常に読みやすい。」この一言に尽きる。この本は、バーバラミント著「考える技術・書く技術」の入門編にあたり、前出の本の訳者が執筆したロジカルシンキングの必読書の1つである。本来、「入門編→原版」といった流れで読むべきところを、都合により「原版→入門編」という流れで読んだ。本書の内容は、「原版の内容の要点を更に読みやすくし噛み砕いて表現した」という印象を受けた。実際、原版では「SCQ分析」を紹介しているのに対し、本書では「OPQ分析」というビジネス用の簡易版SCQ分析を紹介している。また、それでいて、根本的な概念は変わらず、別の視点から考えるようにしただけなので、十分実用的な方法であると思う。ただ、本書は入門編で、原版の要点を紹介しただけの内容ではあるが、根本的な考えも知りたい人は原版を読むべきだと思う。(原版はかなり読み応えがあった。)
0投稿日: 2011.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルなライティング技術、すなわちピラミッド構造を会得する為の本。本家?考える技術・書く技術の入門版の本。「いいか、海外営業はロジックが必要なんだ」と上長に口酸っぱく言われているので、なんかの足しにしたく購入。 うん、ピラミッド構造はまぁよく理解出来ました。一例として、文章を結論を先に書いて、続く箇条書きにした根拠理由を帰納法で構成することのメリットも実感出来ます。 だけれども、どうにも内容を簡略化したぶん、テクニック的な内容に偏重しているようにも感じたのが不満。また、理論ポイントとなる部分にキーワードとして名前が付けられているのだけれど、これがバズワードになっていて逆に理解の阻害になっていると感じた、 まぁむしろそう感じたならば、入門本でお茶を濁さず本家版を読めということなんでしょう。この考え方を深めたいという気持ちにさせてくれた、ということだけでも本書を読んだ価値がありました。
0投稿日: 2011.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ要約をしてみました。 企画や提案などビジネス文書を書くときは、聞き手の疑問に答えること。 聞き手の疑問とは、現状と問題のギャップをどうすればいいのかという疑問。 疑問に答えることはずれてはいけない。意外とずれていることが多い。 ロジックは帰納法が7、8割。次は演しゃく法。 ロジックは、ピラミッドで構成する。 ピラミッドの頂点は上記の「聞き手の疑問に対する回答」にする。 このピラミッドは日頃から10分考えると鍛えることができる。
0投稿日: 2011.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングとビジネスライティングの基本が分かりやすく学べる。「考える技術・書く技術」(バーバラ・ミント)の入門書。ビジネスメールの書き方も参考になった。
0投稿日: 2011.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログピラミッド原則に基づく思考法と作文技術について書かれた本 バーバラ・ミント氏の「考える技術・書く技術」に興味があったが, ページ数がやたら多いので,躊躇していた. この本は,その「考える技術・書く技術」から要点を抽出したもの. 今まで文を書くときに構造を明確に意識していなった人には, 極めて有用な本だと思われる.
0投稿日: 2011.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ所謂HowTo本。意識して論理的に書く事の大切さを、改めて実感しました。仕事をしている人なら、一度は読んでも損は無いと思います。
0投稿日: 2011.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に分かりやすく書かれた一冊。 バーバラ・ミント著の「考える技術・書く技術」は内容が濃いですが、お世辞にも読みやすいとはいえないです(英語と日本語の問題もありますが)。しかし本書は日本語話者を想定して書かれていることもあって、非常に読みやすいです。 内容はそこまで濃くないけれど、おすすめです。
0投稿日: 2011.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ良書 95年のバーバラ•ミントの著書『考える技術•書く技術』を日本語で分かりやすく書かれた本。 原書が分厚く抵抗感がある方は、こちらを先に読んでみるといいかもしれません。
0投稿日: 2011.07.08
