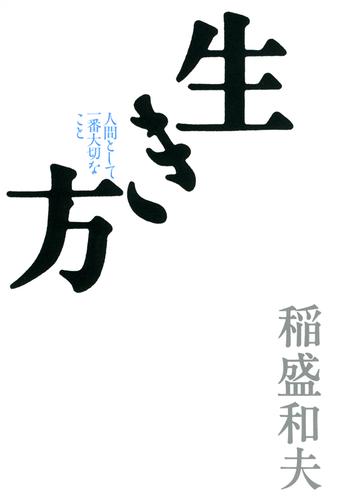
総合評価
(799件)| 319 | ||
| 231 | ||
| 157 | ||
| 23 | ||
| 10 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログどういう生き方が世のため、人のため、そして何より自分のためになるかを教えてくれる本だった。 生きる目的は魂を磨くこと。魂を磨くにはとにかく働くこと。働くことが嫌ならば、とりあえず、目の前の仕事を一生懸命こなしてみる。そうすれば楽しくなってきて、成果も出てくる。 誠実に真面目に生きていればいいことがある。 要は、子供の頃に学校で教わったように、良い子で生きていれば自分のためになるのだが、そう生きていくことはとても難しい。 「知恵の蔵」の話は、映画「2001年宇宙の旅」のモノリスを彷彿とさせた。 魂や宇宙の話などが多く、人によってはスピリチュアルっぽく感じると思うが、並々ならぬ努力をしている人は、そうでなければ説明がつかないような体験をしているのだろう。 著者のように成功している人の本を読むと、仏教の教えに従っている人が多く、自分も仏教のことをもっと勉強したいと思った。 人生に迷った時などにまた読もうと思った一冊だった。
0投稿日: 2020.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆概要 稲盛和夫さんが考える人生観、 ビジネスへの思いが書かれている本。 人のために、と利他の心で動くこと、 ひたむきに頑張ることの大切さをまとめている。 ◆得た学び 仕事を一生懸命やることは、 楽しいことなのだと知るきっかけになった。 要領は良くなくても良いから、 真剣にやることの大切さを学んだ。 ◆どう活かすか 目の前の仕事に集中する。 ◆おすすめポイント 働き方改革が叫ばれている昨今。 「長時間労働=悪」と囚われがちだが、 働く時間が短くなれば人生の満足度は増えるのだろうか? そんな問いに答えてくれる一冊だ。
1投稿日: 2020.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会に出てからはまとまった時間が取りづらくなり、一章ごとに読んでは本を閉じます。何度読んだかわかりませんが、毎回、戒められ、初心に戻してくれる本です。
1投稿日: 2019.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ生きる意味や価値を見出せず人生の指針を失っていないか。 魂を磨いていくことがこの世を生きる意味。 苦しみは魂を磨くための試練である。 「人間として正しいかどうか」という哲学を持つことが大切。 思考が業(カルマ)を作り結果が生じるため、「決して悪い想念を描いてはいけない」 求めたものだけが手に入るという人生の法則。 寝ても覚めても強烈に思い続けることが大切。諦めずにやり通せば成功しかありえない。 ただ今この時を必死懸命に生きる。 常に内省せよ、人格を磨くことを忘れるな。 どんなときも「ありがとう」と感謝する。 感謝の気持ちが湧き上がってなくても「ありがとう」と言える習慣をつける。 人を惑わせる三毒「貪瞋痴」欲望、怒り、愚痴を捨てる。 利他の心で生きる。 結果を焦るな、因果の帳尻はきちんと合う。 一生懸命働くこと、感謝の心を忘れないこと、善き思い、正しい行いに努めること。 素直な反省心でいつも自分を律すること。 日々の暮らしの中で心を磨き人格を高め続けること。 そのような当たり前のことを一生懸命を行っていくことにまさに生きる意義があるし、それ以外に「生き方」はない。
0投稿日: 2019.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ自由や個性が拡大解釈され人々は生きる指針を失っている。 だからこそ、古くからの教えやそもそもの原理原則を思い出し、因果応報であることを意識して常に徳を積むことが必要! そんな思いが詰まった本。 「マインドセット」のために読むのがオススメ! 定期的に読むことで自分の心の振り返りに使える。 人生、仕事の結果=考え方×熱意×能力 考え方はマイナスもあるからこそ、一番意識すべし。 寝ても覚めても思い続けるほどの熱意があるかどうか。
1投稿日: 2019.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ何かを決断する時、損得感情ではなく、自分の決断は 人として良い事か悪い事か、それを判断基準としなさい。 人としてどう生きるべきか、道徳心、己の欲とゆう感情を制し、世界、宇宙まで見据えて利他に尽くせ。 仏の道に入った方だけあって、話のスケールは壮大過ぎて やや現実味がなく、今の私には到底難しいな、と感じたことも多々あった。そちらの道に引っ張られる訳ではないが、それでも私も神や仏様は見ておられる、と思う!いや 、思いたい!! 信念を持ち、ただひたすら努力をれば必ず報われる。とゆう稲森氏の教えを胸に感謝の気持ちを持ち、足るを知り、精進しなくては。
0投稿日: 2019.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的に覚えておきたいこと。 ・強く願わなければ叶わない ・哲学を持つ ・考え方×熱意×能力
0投稿日: 2019.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ仏教の教えの影響を感じる。 →https://ameblo.jp/sunnyday-tomorrow/entry-12111241218.html
0投稿日: 2019.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ何事も一生懸命やる…それはとても大切なことなんだなと感じた。 この本に書いてある生き方は自分的には凄く感銘を受けたので、定期的に読み返してこの生き方を貫こうと思った。 特に何事も一生懸命やることと他人を思いやる心は極めたい。
0投稿日: 2019.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ立派な精神論、儒教的な倫理観など、高尚な考えを学ぶことができる。 ホリエモンやひろゆきなどとはいい意味で違うタイプの勉強になりました。
1投稿日: 2019.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ稲盛和夫さんの本です。京セラとKDDIの前身のDDIを創業し、JALを建て直した人です。 読んだ印象として、ものすごい心が清らかな人で、宗教チックな考え方です。かつ組織統制の上手な人であり、さらに情熱を持った人です。 さすがこの人なら一代で大企業の創造も、JALも立て直すのもできると思いました。 でもこの人の元で働くのは大変そうだと思いました。。。 「稲盛和夫」がどんな人か、ビジネスであれだけ大成する人がどんな人かがよく分かります。
0投稿日: 2019.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間は何のために生まれてきたのか。そんな答えをみつけることは、永遠にない。だから、心の持ち方、生き方が大事。邪心なく、純粋に、利他的に、そして 地球と共生。
0投稿日: 2019.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログよく売れている本の割にはないようは今ひとつ。一般向けにわかりやすくしているようだ。 全部で5つの章だてがされているが、 1・思いを実現させる 2・原理原則から考える 3・心を磨き、高める 4・利他の心で生きる 5・宇宙の流れと調和する というもの。わかりやすい自己啓発本と言える。
0投稿日: 2019.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分のためではなく、誰かの為に生きるもいうこと。 他利の為に生きれば必ず返ってくるということ。 仕事や人生に対して、人格や熱意や能力がかけ算で影響すると言うこと。人格はプラスにもマイナスにもなる。リーダーの素質にもなる。熱意や能力があっても、人格なく者はリーダーの資格を問う。 熱意は人に影響するとこもあるが、中には冷ましてしまう人もいる。 私の仕事ぶりに一部の人間が熱を帯びてきている。 仕事のことは、一心不乱に考え続けること。願い続ければ、成功しかあり得ない。明確なビジョンで目指し続けるということ。 完璧を目指さなくても、やることに意味はある。 真面目に、決められたことをきちんと、皆のために何かをしたい。世のため人のためになることをする。必ず自分に返ってくる。 稲森さんも長谷部選手も私の父親も言っていること。凄い人達の言う言葉。 辛いと思うことも、自分に課せられた試練だと受け入れて、堪え忍んでみよう。人生には辛いこともある。 晩年になり 人間の本質は、透明で透き通ったもので、五感はなくても「存在」のみ。花も人もテレビやソファーも、「存在」が形を変えたもの。 人間の深さは 知性、本能、魂のような順番で深さを増す。 魂は美しく、他愛、優しい。誰もが持っている道徳心のようなもの。 今本能が強くなっているときは、理性という機能でブレーキをかけるが、 全てを許し、優しく、美しく魂が心にはある。そこに触れると、深い癒しがある。全ての人の幸せを願えるようになる。
0投稿日: 2019.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生をどのように生きていくか、どうやったら幸せな人生を歩めるのか、そのヒントが散りばめられた一冊だと思った。ビジネスの世界において、自分さえ良ければ何をしても良い、ということは絶対にない。たとえ一時的に成功したように見えても長続きはしない。世のため人のためを想って、生きる軸をもって行動していくことが何よりも大切だと感じた。
0投稿日: 2019.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ続編が出たのをキッカケに、積んでたことを思い出して読みはじめ。仕事のモチベーションに迷走してたころに縋るように購入した気がする。 働き方改革とか、合理化とか色々あるけど、稲盛さんの言ってるような自分の仕事に真摯に向き合い、バカ真面目に仕事をするスタイルが日本人には合ってるのではないかと思う。少なくとも、自分には合ってると思うし、冷めた大人たちを見ながらこういう仕事の仕方に憧れている若い世代も多いと思う。残業が善だとは思わないけど、やらされ感満載な残業と、熱ある残業は人生における価値が違うよね。今一度、自分の人生の目的と、自分がしている仕事の意義を考えて、情熱ある人生を歩みたいと思う。 ただ、後半の宗教に感化された章は読むのが面倒くさかった。一方、稲盛さんみたいな人ばかりに世の中なるなら宗教も悪くないかなと思った。
1投稿日: 2019.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【気になった場所】 混迷の時代は、人生観の欠如に起因する →人間は何のために生きるのかを問い直す 著者の生き方に対する回答 →心を高めること、魂を磨くこと =生まれたときより少しでもマシな人間になること →試練を機会としてとらえることができる人が、限られた人生を自分のものとして生きていける 人格=性格+哲学 必要な哲学 →人間として正しいかどうか=原理原則 例) 事業の原理原則=社会や人の役に立つこと 原理原則はシンプルである →知っているだけでなく、貫くことが重要 人生の真理は懸命に働くことで体得できる →日々の精進を通じて、自ずと魂が磨かれていき、厚みある人格を形成していく 人生や仕事の結果=考え方×熱意×能力 熱意は好きから生まれる →嫌いな仕事もまずは打ち込んでみる →好きと打ち込むは表裏一体で循環する 考え方とは →心のあり方や生きる姿勢 →プラスだけでなくマイナスにもなり得る プラス方向の考え方 ・つねに前向きで建設的である ・感謝の心を持ち、協調性を有している ・明るく肯定的である ・善意に満ち、思いやりがあり、やさしい心を持っている ・努力を惜しまない ・足るを知り、利己的でなく、強欲などない 人生は心に描いたものが実現する →なにか事をなそうと思ったら、まずこうありたいと強く思うこと 成功するための準備の秘訣 →楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行すること できないことは、いまの自分にできないだけ →将来の自分になら可能であると考えること →少しずつ創意工夫する心を持つこと リーズナブル=正当である、という判断基準 →外国人に多い印象 人としての美しい心 ・謙虚さ 心を磨くために必要なこと ・誰にも負けない努力をする ・謙虚にして驕らず ・反省ある日々を送る ・生きていることに感謝する ・善行、利他行を積む ・感性的な悩みをしない 素直な心とは →自分の至らなさを認め、そこから惜しまず努力する謙虚な姿勢のこと 結果を焦るな、因果の帳尻はきちんと合う
0投稿日: 2019.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔に一度読んだことがあったが今回HONZのレビューで紹介されていたので再読した。著者本人も書いてある通り言ってることはしごくまっとうな普通の事を言ってるのに過ぎない(例えば一生懸命働くだとか嘘をつかないとか謙虚に生きるとか感謝をするとか)のだが、実際にそれを実践するのがいかに難しいのか、それを着実に実行してきた自負と迫力が文章からも窺える。そういう意味ではもう成功する方法をわれわれは知っているのだ。あとは雨が降ろうが槍が降ろうがただただ実践するのみ。JUST DO IT.それが何より一番難しい。
0投稿日: 2019.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会的に成功を収めるためには誠実に生きていくことが大切であると気付かされた。 人間として正しい行いをしていきたい。
0投稿日: 2019.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ全てを実践出来なくても、そうなるように努力することが大切なこと。 人生の方程式 人生・仕事の結果=考え方✖️熱意✖️能力 最も重要なのは考え方である。マイナスもあるため。
2投稿日: 2019.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ書いてあるのは、人間として当たり前と思えること。 嘘をつかない、真剣に取り組む、欲を捨てる、など。 でも、これが難しい。 「他を利する」 目新しさはないけど、生きる上で大切なことを再確認できた。 中国古典や仏教からの引用もところどころあるけど、結局大切なことって古今東西、不変で普遍なんだよな。
0投稿日: 2019.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生の指針となる本と言える。稲盛さんの人生経験を通じた言葉は重みがあり、説得力がある。人間として一番大切なことは何かを考え直した。 生き方について示した本は、自分にとって読みたいと思える本ではなかった。何が人生の目的で、何が自分の幸せか、今まで考え、わかっているという思いがあった。 だから最初は読んでも自分は自分の考え方があるという感じで読み始めた。しかし、毎朝の通勤時間に読んでいると、明らかにモチベーションが高まるのを感じた。 それは、毎日の人生・仕事に対する意義と、あるべき考え方の方向性・取組み方について、書かれているからだと思う。 労働の意義とは、経済的価値を生み出すのみならず、人間としての価値を高めてくれるものである。仕事の現場が、一番の精神修練の場であり、働くこと自体が修行である。一日一日を「ど真剣」に真摯に真剣に生きることが、平凡な人を非凡な人に変貌させる。また、考え方の方向性については、もっとも大事な要素で、 人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力であり、考え方の方向が間違っていれば、マイナスにしかならないと説明している。 では、プラス方向の考え方とは何か、 難しいことではなく、子供のときに教わったような「よい心」であるということ。前向きで建設であること。感謝の心を持ち、みんなと一緒に歩もうとする協調性を有していること。明るく肯定的であること。善意に満ち、思いやりがあり、やさしい心を持っていること。努力を惜しまないこと。足るを知り、利己的ではなく、利他的であること。 他にも人生の指針となる、取り分け私にとっては、仕事への取組み方に対しての面で影響を受けた。迷った時は何度も読み返したいと思う。
1投稿日: 2019.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ稲盛さんのイメージすることの大切さや、 人として正しいことを追求すると言った考え方は、 素晴らしかったし、自分の行動を見つめ直すいい機会になった。 耐えることが素晴らしいと言った考えには賛同できなかったが、自分の考えと照らし合わせるきっかけにもなったし、言いたいことが物凄くわかった。
0投稿日: 2019.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ【一つでも欠けたらダメ】 本書の著者は現在の京セラ・KDDIの創業者、稲盛和夫氏である。著者が従業員として現場で活動していた頃から、経営者として会社経営をするまでの経験をまとめてある。そこから人としてどのようにして生きるべきなのかを説き、最後では「人とは何なのか」とその起源を探るような内容となっている。 私が特に印象を受けた一節として「人生・仕事の成果=考え方×熱意×能力」。これはプロローグそしてp95ℓ5にも説明があり本書では「人生の方程式」と表されているものである。この方程式のポイントは右辺が掛け算であることと、その中の「考え方」にはマイナスの概念があるところだ。 方程式が意図することは日ごろから体感することが私たちにもあると思う。私が真っ先に思いついたものとして犯罪をすることがマイナスの考え方にあたる。どんなに能力があって高い熱意を持っていても、間違ったことをしていては世間から評価を得ることはできないし、むしろマイナスをあたえてしまうだろう。また、熱意と能力においても身近な例として勉強について置き換えてみる。勉強する内容が興味の無いもので本人の意欲が低ければ、たとえ努力をして能力が一時はあったとしても、すぐに忘れて時間が経てばしていなかったのと同じになってしまう。反対に意欲があっても努力しなければ(これを熱意が高いと言うのかは置いといて)こちらも成果は見込めないことが多い。方程式はしっかりと的を射ていると思う。 「考え方」「熱意」「能力」の3つの要素を高めていく方法について全5章を通して細かく書かれている。それぞれの章には大体3ページ毎に小見出しがあり、色々な話が次々に展開されているため飽きることなく読むことができる。また端的に書かれてありダラダラしてないので内容も読み取りやすく、読者への配慮がよく見える。タイトルの通り今までの人生を振り返り、これからの「生き方」を考えるためには非常に適した本であると自信を持って言える。 本書については自分に必要な要素だと思った箇所だけを何度も読み返す読み方も良いと思う。本書中には著者の体験談や著者が影響を受けた人物の言葉などもあった。私は著者だけではなく本書で紹介された人のことも気になり本を読んでみようとなった。
0投稿日: 2019.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
昔から読みたい本の1冊だった。 利益ばかりを追うのが良くないと気づいた大切な1冊。 『良い思いを描く人は 良い人生が開けてくる。悪い思いを持っていれば人生はうまくいかなくなる。』とのことだが、 良い思いが画一していない人はどうすればいいんだろう。 稲森さんに聞いてみたい。
0投稿日: 2019.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ橋本さんから勧めて頂いた本。 「仕事の完成よりも仕事をする人の完成」 社会に出て、自分が真面目すぎるんかなとか頭が硬いんかなと思うこともあるけど、やっぱり正しいと思うことを、真面目にまっすぐやっていこうと思った(というかそこから逸脱することが良心の呵責的にできないなと思う)。 今までたくさんの人に救われてきた分、人を救いたいと思うし、その救った人がほかの誰かを救えるように働いていきたいと思った。
0投稿日: 2019.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
★読もうと思ったきっかけ 本屋さんで立ち読みして、読みやすそうだと思った。稲盛和夫の本が読んでみたかった。 ★感想 生き方全般というより、仕事よりな言葉が多い。 落ち切ってる私にとっては、「分かってるから言わないでぇ」という感じ。 少し落ち込んだな、という状態で読むと背中を押してもらえそう。 自己啓発本読み過ぎた気がする。 インプットしたこと、経験から自分でミッションステートメント+説明を出産までの間に作ろう。 アップデートや迷った時にピンポイントでまたインプットしよう。 ・人生の目的は、生まれてきた時よりも魂を磨いて少しでもましな人間になる ・一生懸命働く、感謝の心を忘れない、原理原則、心を磨き人格を高め続ける ・素直とは、従順ではなく現状とあるべき姿の差を正面から見つめて人のせいにせず、努力する謙虚な姿勢。 ・三毒(怒り、欲望、愚痴)には理性のワンクッションを!! →今の仕事、もっとやりようはあるのかもしれない。一生懸命、誠実さをもって。 でも職種、変えてみたい(興味)んだよなぁ…
0投稿日: 2019.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人が生きる指針。仏教思想を強く受けているようだが (おそらく日本人としての)自分にとって、とても 聞きやすく、受け入れやすい(いい意味での)説教が つまっている。 大人になった自分は、魂も成長しているのか? 仕事に対する考え方、接し方。 人生をいかにプロデュースするかを改めて考えさせる のに、たいへん良いきっかけとなる本。 ○ 人格とは、「性格+哲学」である ○ シロウトの考えた経営方針 ・ウソをついてはいけない ・人に迷惑をかけてはいけない ・正直であれ ・欲張ってはいけない ・自分のことばかり考えてはいけない ○ 人生をよりよく生きる方程式 人生・仕事の結果 = 考え方 × 熱意 × 能力 ○ 願望を成就(じょうじゅ)するには ・漠然と「そうなればいいな」ではなく 「すさまじく思う」ことが大切。 ・成功のイメージを克明にカラーで目の前に見えるまで考えること ○ 努力をつみかさねれば、平凡は非凡にかわる ○ リーダーには、才よりも徳が求められる ○ 心を磨くために必要な「六つの精進」 ・だれにもまけない努力をする ・謙虚にしておごらず ・反省ある日々を送る ・善行、利他行を積む ・感性的な悩みをしない ○ 仏教 「なんまん、なんまん、ありがとう」 「神様、ごめん」 ○ 地獄も天国も世界はいっしょ どちらも大きなかまのうどんと大きな箸がある。 地獄は、我先にとうどんをとろうとしてだれも食べれず、 みな、飢えている 天国では、みな、だれかに食べさせてあげており みな、幸福な気持ちで過ごしている。 ○ 人をまどわせる仏教の「三毒」 断崖絶壁まで虎に追われて、1本の木の上に上ってしまった 旅人は、1本の藤づるがたれているのを見つける。 この藤づるを使って脱出を試みるが、崖の下の海には、赤・黒・青 の3匹の竜が待ち構えており、なんと藤づるの上は、白と黒のねずみ が藤づるをかじっている。 ねずみを追い払おうと藤づるをゆすったら、上にあった蜂の巣から 甘い蜂蜜がたれてきた。 あまりにおいしいので、旅人は、藤づるを何度もゆすってしまう。。。 この旅人が、まさに浅はかな人間のこと。 ネズミは、時間。白・黒は、昼・夜を表している。 3匹の竜は、赤が「怒り」。黒が「欲望」。青は「妬み」 これが釈迦いわく「人生をだめにする」「3毒」であり、 108つの煩悩の中でも、最も人間を苦しめる元凶である。 子どもや赤ん坊でも、兄弟にお母さんをとられると、嫉妬のそぶりを みせる。この歳でも、すでに、一人前の煩悩に毒されている。 大事なのは、できるだけ「欲を離れる」こと。 3毒を消せなくても、自らコントロールして抑制するよう努める。 誠実、感謝、反省としった「平易な勤行(へいいなごんぎょう)」 を地道に積み重ねるしかない。
0投稿日: 2019.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ○今の時代に最も必要なのは「人間はなんのために生きているのか」という問い ○人間が生きている意味→心を高めること、魂を磨くこと(生まれたときより少しでもマシな人間になって死ぬ) ○労働には、欲望に打ち勝ち、心を磨き、人間性を作っていく効果がある ○人生、仕事の結果=考え方×熱意×能力(考え方次第で人生が決まってしまう) ○継続が平凡を非凡に変える(継続と反復は違う。「創意工夫する心」が重要) ○仕事を通じて人生を豊かにしていく唯一の方法は、仕事を好きになること ○人の上に立つものは才覚よりも人格が問われる ○心を高めること→利他の心が生まれる状態 ○何があっても感謝の念を持つということを理性にインプットする ○物事の成就、人生の充実に必要なことは「勤勉」 ○他人から「してもらう」立場でいる人間は、足りないことばかり目につく、社会に出たら「してあげる」側に立ち、周囲に貢献する ○人生には見えざる2つの力が作用している。それは「運命」と「因果応報の法則」 ○因果応報の法則の方が、運命よりも強い力がある。つまり日頃の行いで運命は変えられる ○悟りの状態になるよりも、理性と良心で感性や本能を抑え、コントロールしようと努めることが重要 ○何よりも私欲に走るのではなく、周囲への貢献や利益を優先する
0投稿日: 2019.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ京セラ創設者、稲盛和夫氏の哲学書。 スピリチュアルな内容ではあるが、著者の熱意がよく伝わってくる。 本文にも幾度と出てくる、結果は個人の能力如何だけでなく、熱意と考え方に左右されるのだ。という旨の方程式がありそこに著者の言わんとすることが集約されていると感じる。 少々、高尚で綺麗事すぎる内容である為、私には全てを共感することはできなかった。実際に成功したのだから言えることだろうし、この通りにやれば必ず結果がついてくるのかといえば、そうとも言い切れない気がする。 ただ物事に取り組む心構えとして素晴らしい内容なので、できるだけ取り入れ自己研鑽に繋げたいと思った。
1投稿日: 2019.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人生」や「働くこと」の基本に立ち返らさせてくれる本。その基本は、「人間として正しいことを追求する」という当たり前だが難しいこと。 若干スピリチュアルな表現もあるが、「生きること」に対する基本を振り返る機会をくれた一冊だった。
0投稿日: 2019.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間としての生き方を熱い言葉で綴った著書であり、その熱量が読者に十分に伝わってくる。 人として当たり前のようなことでも、当たり前にしていないのかできないのか、何かにつけてやらない理由をつくってしまったりする人がいる中でしっかりとした生き方を提唱してくれている。 考え方ひとつでどうにでもなり、考え抜く必要性を感じた。
0投稿日: 2019.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ京セラ創業者の稲盛さんの有名な本です。 読んでみましたが、私が未熟なのか新しい発見はそれほどなかったです。 ただ、『利他の心』。『上に立つものは能力よりも徳が重要』。これは響きました。 今、私も課長になり、会社に部下がいますが、見返りは求めずに自分の知っていることをとにかく伝えようと心がけています。 たしかに、他人に対して無心で何か相手に対して成長できる機会を提供するのは、自分の成長につながります。 また、能力主義になりやすい日本の企業社会において、徳のある人物が上になることが、企業全体に対しての成長効果が大きいことは自分の考えにも合致しました。 この本は、経営者が読む本ですね。経営者があるべき心構えが書かれていると思います。早くこの真髄を分かるようにしないといけないと思いました。
0投稿日: 2019.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログオーディブルで完了。 京セラっていい会社だなって思う。 こんな素晴らしい教育者、指導者の下で働くことができたら本当に幸せだ。 稲盛さんの本はどの本も同じようですが、繰り返し読んでも 納得できる。ありがたい本です。
0投稿日: 2019.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
初めて触れた稲盛和夫氏の本。日本を代表する経営者の「生き方(仕事への心構え)」はシンプルだが、刺さるところがあった。 【継続と反復は異なる】 「継続は力なりといっても、それが「同じことの繰り返し」ではあってはいけない。昨日と同じことを漫然と繰り返すのではなく、今日よりは明日、明日よりは明後日と少しずつ、必ず改良や改善を付け加えていくこと。」 →今の働き方や自己研鑽のあり方に近い。1週間で学習サイクルを回しているので、今日より明日がより会社や人間として成長できるラインに乗れている。 【畳水練のばかばかしさ】 「無我夢中で手足を動かすこと、現場で自ら汗をかくこと。自らが体を張って取り組んだ実体験こそが、もっとも尊い経験になる。」 →行動を起こすということだろう。制約(物理的、金銭的、肉体的とか)はある中でも、考えたことを行動に起こして成長をしたい。 【6つの精進】 1.だれにも負けない努力をする:人より1mmでも前に進む努力をする →これは測るのが難しいな。質×量だと思うけれど、測りがたい。結論としては、「個」として昨日より今日が成長していることが1つのチェックポイントか。それでも「相手」の方が成長しているならば、その成長のコツを盗もう。(本を毎週2冊読んでいるとか、ライフハックで15分刻みの生き方をしているとか) 2.謙虚にして驕らず:謙虚であること →謙虚すぎて、自分の意見を引っ込めるのとは違う。謙虚に戦う。あとは、褒められた時に自分を下げすぎないけれど、お世辞だとも思って自信家きどりをしないこと。 3.反省のある日々を送る:自分の行動/心のありようを振り返る時間をもつ →毎日の日記、毎週末の振り返りを大切にする。 4.生きていることに感謝する:小さなことにも感謝する心を育てる →心からの感謝。相手の発言に注意資源を向けていないと、感謝の声はでてこない。 5.善行、利他行を積む:思いやりのある言動を心がける →相手の気持ちにたったコミュニケーションを心がける 6.感情的な悩みをしない:不安・不満を抱いても仕方ないに捉われない →ものの味方を変える。80際からの自分にして見たが、すべてが小事だよ。
1投稿日: 2019.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ痺れた。一番印象に残ったのは、切れば血の代わりに「思い」が流れる、の一文。言葉の深み、広がりがすごい。就職前に読めて良かった。利他の精神で、がむしゃらに働きたい。
0投稿日: 2019.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ・哲学書(ビジネス書ではない。) ・仏教に根付いた、かなり宗教色も強い哲学書だった。稲盛氏の仏門での修行経験にも起因しているのだろう。 ・哲学、倫理観は、歴史的に宗教に根付いて発達してきた。そういった意味でも、確固たる哲学を持つにはある種の宗教的信念も必要なのかもしれないと感じた。 ・宗教、とはいったものの、その思想や考え方をビジネスマンとして昇華して、書き下ろされていたので、単に盲信するのではなく理解に易い、仏教徒ではない人でも納得感の得られる内容だった。
0投稿日: 2018.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代版「経営の神様」的存在である稲盛氏が生き方を説く本ということで、評価も高かったし購入しておりました。 なぜか後回しになってしまっていて、購入後2年くらい経過してようやく手にとって読むことにしました。 しかし、序文で唖然として読む気が消失してしまいました。 すみません、よく知らずに手にとったのですが、本書は誰を対象に書かれた本なのでしょうか。 稲盛氏を、一代で京セラを起業して世界的企業にし、さらにはKDDIの設立、JALの再建まで手がけた敏腕経営者として評価し、その生き様や哲学を知りたくて本書を手にとった人は、おそらく私のような反応となるのではないでしょうか。 また一方で、自分の生き方を見失い、どう生きてどう死ぬかが見えない人たちは、道徳的に正しくあり続けただがむしゃらに働くべきだ、と社会的成功者である稲盛氏が説いたとしても逆効果に思います。 言わんとしていることは大変良くわかります。 道徳的に正しいことをすることで世の中の人が味方になってくれるため、私生活もビジネスも好循環となるでしょう。 また、利他の精神で生きることによって、他者から感謝される喜びを得、承認欲求が満たされ、達成感を持って人生の最期を迎えることができるでしょう。 全く同感です。 しかしそれを極めて宗教的な用語を用いて記述することにより、なんとも言えぬ違和感や不快感を覚えました。 ただ、あくまで個人の感想なので、得るものが多い方も多いと思います。 本書のそのような言い回しは抜きにして、純粋に稲盛氏の哲学、生き様を知ることは大変得難い経験でしたので読了した価値はあったと思っています。
3投稿日: 2018.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ稲盛さんの名言集。ゼロを読んだばかりだからかも知れないが、世の中で成功したと言われる人の思考はそれほど変わらないのだと思った。ホリエモンと稲盛さん、違っているようで本質は似ているのかも知れない。 [private]・凄まじく思うこと ・現実になる姿をカラーで見る。 ・見えるまで考え抜く[/private]
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わりました。 「引き寄せの法則」に関して稲盛さんも同じことを書かれているなというのと、仕事に対する考えの持ち方が刺さりました。
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
多くの経営者が尊敬する経営者、稲盛和夫氏。 その半生から語られる生き方。 とても心が洗われました。 運命を変えてゆく。 運命は変わっていく。 努力研鑽を惜しまないと見えてくる世界。 その可能性を教えてくれました。 他の本もぜひ読みたいと思います。
0投稿日: 2018.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容は、ごく当たり前ではありますが、 私にとって、また最初から見つめなおす必要があるのかもしれない。 誠実に、勤勉に、またこれからできるだろうか。 誰かが見れくれるとはよく言うけれど、 見てくれる人はたしかにいるかもしれないが、 でも助けてくれる人がいるとは限らない。 今ひとたびそうならないように
0投稿日: 2018.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ感謝や誠実、一生懸命働くことや素直な心、反省を忘れない気持ち。恨んだり、妬んだりしない心、他人を思いやる利他の精神、、、(これらが因果応報の法則となり、)人は成功発展の方向へ導かれる。逆に悪い行いをしている人は、必ず相応の運命をたどる。忘れないようにしたい。 ただ、働くということは人生を豊かにすることであるという考え方には同意するんだけど、一生懸命働きなさい、仕事があってのこその束の間の休日や趣味であるといった部分はちょっと時代がもう古いですよと言いたくなるかなぁ…。真っ向から否定はしないけど、日本には労働を人格形成の精進の場と捉える文化があった、とか、日本人は遊んでいるときより働いているときのほうが幸福であると考えていたとか… それただの奴隷の正当化。。と思ってしまうのはゆとりな私だけでしょうか。 真っ当に生きなさい、だとか、夢を強く願って実現させなさいとかっていう部分はもちろん賛成です。
0投稿日: 2018.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ著著より「生まれてきたときより、少しでもきれいな魂になるために、つねに精進を重ねていかなければらない。それが、人間は何のために生きるかという解答である。」 「一生懸命働くこと、感謝の心を忘れないこと、善き思い、正しい行いに努めること、素直な反省心でいつも自分を律すること、日々の暮らしの中で心を磨き、人格を高めつづけること。すなわち、そのような当たり前のことを一生懸命行っていくことに、まさに生きる意義があるし、それ以外に、人間としての「生き方」はないように思う。」
0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生の方程式。人生・仕事の成果=考え方×熱意×能力。考え方にはプラスとマイナスがある。どんなに能力が高く、熱意があっても、人の為にならない方向の考え方をしている人の成果はマイナスである。仏門に入り得度されたとか。仏教的な考え方がよく現れている。心が全て。心の持ち方で出来事が変わってくる。
0投稿日: 2018.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ生き方 稲盛和夫 混迷を極め先行きの見えない時代、必要なのは「人は何のために生きるのか」という問い。真正面からこれに向き合い、哲学を確立することが必要。 心を高めること、魂を磨くこと 現世は修養の場。哲学として必要なのは、人間として正しいか。 一つのことに打ち込む、一生懸命働くことでわ
0投稿日: 2018.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
会社辞めようかなと思ってたときに、これを読んで思いとどまり、結果的に辞めないことで得られた様々な経験と現在の幸せをこの手にすることができた。仕事とは苦しみながら生み出すものだという趣旨のことが書いてあり、時代には合わないかもしれないけど、サラリーマンとしてしか生きていくすべを持たない私のような凡人にはすがりたくなる生き方だった。
0投稿日: 2018.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書は京セラ名誉会長の稲森氏の人生の哲学が語られている書です。稲盛氏といえば、京セラだけでなくJALの再生にも貢献された方で、どうやって成功してきたのかと期待して読み始めましたが、仏教の教えを踏まえた、人間として当たり前の道徳をきわめてシンプルかつストレートに述べられています。いつのまにか現代社会では失われつつある基本といえるかもしれません。 人間が生きている意味は心を高め、あの世に持ち越せるたった一つのものである魂を磨くことだとしています。(財産、地位、名誉は現世限り)そして人生・仕事の結果は「考え方」(生きる姿勢)、「熱意」(後天的な情熱・努力)、「能力」(先天的な才能・知性)の掛け算であり、とくに考え方は最も大切なもので、これはマイナスにもなりえるため、どんなに努力し、能力があっても考え方がよくないとぜんたいがマイナスとなるとしています。 六つの精進として、①誰にも負けない努力をする、②謙虚にしておごらず、③反省ある日々を送る、④生きていることに感謝する、⑤善行、利他行を積む、⑥感性的な悩みをしない、としています。とりわけ稲森氏は利他を強調しています。一言でいえば「世のため人のためにつくす」ことです。またそのために「足るを知る」という生き方が重要としています。人生は運命と因果応報の法則によって決まり、後者の影響の方が若干強いとしています。つまり、よいことをすればよい結果が生じ、悪いことをすれば悪い結果が生じるということです。結果を焦ってはいけない、因果の帳尻はきちんと合うということです。 この本は現代人が忘れている当たり前の道徳や謙虚さについて思い出させてくれ、何か少し心が洗われた気持ちになりました。
1投稿日: 2018.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ働き方と似ている部分はあったけど、良い事が書いてあった! 会社での働く姿勢、人としての考え方が書いてありとても為になると感じた!! 1日1日を大切にし、工夫していくことが重要であり また 仕事を好きになれば頑張れるといったことが書いてある!
0投稿日: 2018.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みにくいのでざっくり読み。「成功」した方に「生きていくことは苦しいことの方が多い」と言われるとスッと入りますね(*^o^*)心を前向きに保っていきたいです。
0投稿日: 2018.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログとても参考になる本だった 仏教の教えが色濃く出ていた 人生でやらなければいけない事は単純なこと 嘘をつかない 人のために生きる 利他の心
0投稿日: 2018.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「稲盛さん」とは、宗教である。彼は仏教を心に持っている。どちらの宗教にせよ、人生の訓えを知っており実行している人は、芯がしっかり通っている。やはり普通の人とは違う。 私が彼を知ったきっかけは、お気に入りの本の一つである「沈まぬ太陽」からであった。御巣鷹山事故を起こしたNAL(実際はJAL)再建に白羽の矢が立ったのが、何を隠そう稲盛和夫氏なのだ。私はこの人物に興味を持ち、偶然本書を見かけて読むことになった。稲盛氏は京セラ・第二電電(現KDDI)の創業者であり、数々の慈善事業にも積極的に参加している。 彼は「前世の業が垢としてへばりついている」「生まれた時よりも、魂を少しでも崇高なレベルにして死んでいくことが目的である」と仰られているが、私の両親も仏教徒であったため、この言い分には大変納得である。本書は胸に迫るものがあり、涙ぐんでしまった。また、稲盛さんの書く文章には驚いた。一切難しい言葉が使われていないのだ。終始、簡単で分かりやすい言葉遣いを徹底されており、読みやすい。常時謙遜され、傲慢さがまったくない。これほど読んでいてスッと素直に聞ける本は珍しいと思う。稲盛氏の顔つきも柔らかく、左右平等で、優しいお顔をされている。
2投稿日: 2018.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事で困難があったとき、仕事がつまらないと感じるとき、頑張ろうと思える本。 それだけじゃなく、人生において何が大切か教えてくれる。また上司に無茶振りされたら読もう。(笑)正しい理想論だけじゃなく、御本人の経験から苦い部分とか自省の部分もあるから、より納得できるし、頑張ろうと思える本。
0投稿日: 2018.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終えたとき、思わず涙が出そうになりました。 死ぬまで「心を磨いていく」 この本に出会えた以上、実践します。
1投稿日: 2018.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
気に入った箇所 そういう時代にもっとも必要なのは、「人間は何のために生きるのか」という根本的な問いではないかと思います 「才子、才に倒れる」といわれるとおり、才覚にあふれた人はついそれを過信して、あらぬ方向へと進みがちなものです。 一つのことに打ち込んできた人、一生懸命に働きつづけてきた人というのは、その日々の精進を通じて、おのずと魂が磨かれていき、厚みのある人格を形成していくものです。 人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力 「プラス方向」の考え方とは、どんなものでしょう。むずかしく考える必要はありません。それは常識的に判断されうる「よい心」のことだと思っていただければいいでしょう つねに前向きで建設的であること。感謝の心をもち、みんなといっしょに歩もうという協調性を有していること。明るく肯定的であること。善意に満ち、思いやりがあり、やさしい心をもっていること。努力を惜しまないこと。足るを知り、利己的でなく、強欲でないことなどです。 心が呼ばないものが自分に近づいてくるはずがない まずダムをつくりたいと思わなくてはならない。その思いがすべての始まりなのだ。 同じような能力をもち、同じ程度の努力をして、一方は成功するが、一方は失敗に終わる。この違いはどこからくるのか。人はその原因としてすぐに運やツキを持ち出したがりますが、要するに願望の大きさ、高さ、深さ、熱さの差からきているのです。 完成形がくっきりと見えるようになるまで、事前に物事を強く思い、深く考え、真剣に取り組まなくては、創造的な仕事や人生での成功はおぼつかないということです。 すみずみまで明瞭にイメージできたことは間違いなく成就するのです。 新しいことを成し遂げられる人は、自分の可能性をまっすぐに信じることができる人です。可能性とはつまり「未来の能力」のこと。現在の能力で、できる、できないを判断してしまっては、新しいことや困難なことはいつまでたってもやり遂げられません。 できないことがあったとしても、それは今の自分にできないだけであって、将来の自分になら可能であると未来進行形で考えることが大切です。
0投稿日: 2018.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて読んだときは経験値が浅く私には難しく感じましたが、目標を決め経験を積めば積むほど理解が増えることに喜びを感じる本です
0投稿日: 2018.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人生の方程式: 人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力 「最初に考え抜いて「見えた」理想とする水準にまで達していない製品は、いくら基準を満たしていても、いいものとはいえないのです。」(45頁)…現実になる姿がカラーで見えているか。 「自分の仕事がどうしても好きになれないという人はどうすればよいか。とにかくまず一生懸命、一心不乱に打ち込んでみることです。」(109頁) 「そうであろうと努めながら、ついにそうであることはできない。しかしそうであろうと努めること、それ自体が尊いのだということです。」(231頁)
0投稿日: 2018.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ稲盛氏の生き方の原点が詰まった本。改めてその考え方に触れたが、自らの軸にもすべき事が多くあった。 ど真剣に生きる、仕事をすることで自らの人格を高める。
0投稿日: 2018.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ仏教の内容と今までの仕事に対する取り組みがかいてあり、稲盛氏の考えで、以下の等式をみたときは胸が熱くなった。 人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力 本の後半は宗教の話なので、難しくてわからなかった。
0投稿日: 2018.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログKindle版実際の京セラがどうなのかはわからない。おそらく部署によりけりなんだろうけど書いてあることは、前提として十全に機能していればいいなと思える。支点をしっかり持っている感じ。トップにこういう人文的な素養と理念、実行力があればおそらく仕事に対するイメージや取り組みは大きく違った風景になると思う。道徳、公共の福祉、利他、こういうことを意識しつつ、隷属的でない建設的な貢献を求めることは悪く無いと思う。つまる所、実践の場においては調整する者の意識次第かもしれないけど経営のトップがこれを語り理念とすることは経済界全体にとっては悪く無いと思う。無原則、無節操な合理の前に本来、あるべき心構えだと思う。
0投稿日: 2017.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近読んできた本の内容とは、価値観が異なるところもあります。 それでも共通項が多く見つけられるあたり、スゴイ人はスゴイと思うし、僕もそうなりたいと思いました。 例えば「仕事に専念する」「周りに教えを請う」「分業」…など。 他とアプローチは異なるものの、手段として同じ答えが出てくるのが新鮮でした。 生きる目的が「よりよく死ぬこと」というのは、シンプルですがそうかもしれないと思います。 またついつい近道を求めがちな僕ですが、愚直に一歩ずつ…というのも(これも共通項の一つ)、大切にしないとと我が身を省みるのでした…。
0投稿日: 2017.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
成功体験などは書かれていない。 人生の意味について、稲盛氏の見解が述べられている。 人は何のために生まれて死ぬのか。 人格、魂を磨き、生まれてきたときよりもよりよい魂の状態となって死ぬためである。 また、人は常に善い心、善い行いに努め、善い状態よりもそうなるために努める事によって磨かれるとある。 宗教的なお話も多かったが、非常に勉強になった。
0投稿日: 2017.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
元から少し合理主義に寄りすぎているところがある自分にとって、人間の社会で生きるからにはやはり人間として他の人間から評価されることが重要であるということを実感させられた本だった。 ただ仕事を神格化している部分についてはやや説得力が足りなかったように思う。
0投稿日: 2017.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味深い内容だったが、自分が共感するには今以上に仕事に対する心持ちを、変える必要があると感じた。 自分の主観が変わればネガティヴな事象もポジティブに捉えられると書かれている、が、過去この言葉を何度か聴いてきて、自ら気づく、心を許した人から言われると受け入れることができるが、上の立場にいる人からだと都合のいい人間になれと言われているように感じた経験がある。 この様に下っ端ナメクジ精神が根付いている身としてはすんなりとは共感できない。
0投稿日: 2017.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ松下幸之助氏の『道をひらく』然り、或る道を極めると宗教論的達観に行き着くのかもしれない。現に稲盛氏は仏門を叩いている。京セラやDDIの創業、JALの再建などその卓越した経営手腕は然ることながら、自身の持つ強烈なカリスマ性もそうした宗教的思想から醸し出されるものなのだろう。 稲盛氏の語る生き方は非常にシンプルだ。強い志を持ち原理原則に忠実に利他精神で高みを目指す。明瞭ながら行うは難し、故に本質を突いている。 一般論として大物経営者は若かりし頃はそれこそ狂人と変わらぬ態度で経営拡大に邁進するわけだが、後年聖人君子として崇め祭られ当人もそれを良しとする傾向になりがちである。稲盛氏自身も例外ではないであろうから(一方新卒時の邪念に溢れたエピソードは人間味があり相当好感が持てる)曇りなき人物として神格化すべきではないと思うが、尋常ならぬ実績を残した人物の至言として嚙み締めていただきたい。
5投稿日: 2017.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めの方は、同じことばっかり言っているし、どこかで聞いたことのあるような感想ばっかだなあと思って手が止まっていた。 最近読み始めたらあら不思議。読めば読むほど、味が出る。 それに、同じことばっかり言っているし、どこかで聞いたことのあるような感想ばっかというのは、成功者が同じ法則の下にいるということ。 心の底から、ああそうかと納得する場面もしばしば。人は、経験したことのないことには敏感に反応できないけど、経験したことのあることは 強く反応することができる。「魂」の話は特にそれを実感する。以下、ビボロク。 【印象的だったフレーズもしくはセンテンス】 宗教の信心を失ったことが、道徳論を教えない時代へ繋がっている(194-199) →確かにそうかもしれない。正しい道筋を教授してくれる対象がなくなったことで、人間の思想が自由になった一方で、道を失った人も多いのでは。私もその失いかけている人の一人だった気がする。仏教の教えはなるほど、しっくりくる。 稲盛さんの言う、「六波羅蜜」の教えも全然違和感なく取り込むことができる。お坊さんになった理由、すごくよくわかる。今の人は小さなことに惑わされすぎなんだって。学歴やお金名誉。小手先のスキルではなく、心を教えられる人になりたい。 本当にそう思った。 40年ごとに同じ歴史を繰り返している(199-202) →1868明治維新 1905日露戦争に勝ち、列強の仲間入り。 1945第二次世界大戦に敗戦。焦土から奇跡的な成長を遂げる。 1985円高導入、プラザ合意 物質的な豊かさを追い求めて、他国との競争をひたすら繰り返してきた。1985年から40年後だから、2025年が次の年か。 欲望を原動力にして優勝劣敗の競争を続ける、「覇道」の道を進んでばかり。このままだと何年後かにWWIIと同じ道を進みそう。 40年が大きな節目であることを実感した。 結果を焦らない。因果の帳尻は必ず合う。(215-218) →何時因果の帳尻が合うかはわからない。ただ、信じ続けること。それが、最高の方法。まあ、信じ続けるのは本当難しいんだけどもね。 不完全でもいい、精進を重ねることが尊い(229-231) →悟りの境地には我々凡人は辿り着くことはできない。と稲盛さんが書いていたのには、ああなるほどと思った。 確かに完全に私欲を断ち、常に利他を考えること。本当に難しいことだと思う。そういう意味で、先人たちの偉大さを肌身をもって実感した、
0投稿日: 2017.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ私個人的には、なんで多くの日本人は一生懸命働いているのに、豊かさを感じられないか、 長い間、疑問に思っています。 稲盛氏の言葉を引用します 「日々の仕事を精魂込めて一生懸命に行っていくことがもっとも大切で、 それこそが魂を磨き、心を高めるための尊い「修行」となるのです。」 労働の大切さを諭していますが、私自身海外で働いている経験もあるので、 いろんな国の労働観を実際見てきていますが、日本人が一番真面目に働いている印象があります。 所得を指標にすると94年に世帯所得は640万になりました。 それが15年には480万になっています。25%の減少です。 多くの識者が指摘しますが30年には世帯所得が300万近くなると言われています。 一方名目GDPは増えています。16年度には名目GDP537兆円になっています。 それを政府は「日本再興戦略2016」で名目600兆円にしようとしています。 アメリカ並みの一人当たりにGDPにしようと躍起になっています。 おかしいと思わないでしょうか?GDPは増え続けているのに、所得は減る。 また、これから人口減少の加速化(30年1億116万 16年比20%の減)、 生産年齢の大幅な減少(15年で1300万減少)が起こります。 所得の増加云々は企業の再分配によるものですが、 上記の変化から、これから、もっと仕事上で効率性を求められます。 つまりストレスが増えます。 しかし、一生懸命やっても給与は増えない状況が、多くの人に確実に訪れます。 正直言うと、今までも頑張っても所得に結びつかず、 これから、もっと頑張っても、所得が減るという、その社会状況がおかしく、 日本人の労働=美徳、そして「一生懸命働く」という倫理感自体を私は改善した方がいいと思います つまり、もう、すでに一生懸命やっているのに、なんで、 もっと一生懸命やるのか、カラダ、精神が壊れてしまうんじゃないかと思います。 今の日本社会のあちこちで、その軋みが出現しているように思います。 たしかに、私自身も豊かな心を修養するのは、大事だと思いますが、 生活がどんどん貧しくなっていく方が、もっと問題だと思います。 頑張って、工夫すれば、良い結果が出るならば、 多くの日本人は、豊かさを既に享受しているはずです。 今の社会の閉塞感が、まさにそういう所から出てきていると感じます。
0投稿日: 2017.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
念ずれば花開く、うんうん「思いの強さを何度も説いたから成功した」…高名な経営者の俺様論に不穏な空気。35歳未満で読めば仕事に打ち込む!と洗脳されただろう。仕事してる自分の姿が家族の喜びに繋がる!みたいな。本書に社員の幸せ、育成、他人との関わり、友人、家族、近隣は無い。最後は仏門?彼の生き様をひとつの創作として読むと、あくまで感想として仕事に没頭することで他の全てから目を背けていたと思えてやまない。
0投稿日: 2017.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ・人格=性格+哲学 ・「すさまじく思う」ことが大切。 ・すみずみまで明瞭にイメージできたことは成就できる。 ・判断の基準はつねに、自分の胸に手をあてて 「人間として正しいかどうか」におくべき。 ・おのれの才を「公」に向けて使う。 ・心を高めるとは、生まれた時よりも少しでも美しい心になって死んでいくこと。
1投稿日: 2017.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ生まれた時より良い魂で死ぬこと。 地位や名声、お金はあの世には持っていけない。あるのは魂のみ。だから魂に磨きをかけることが生きる意味。昨日より今日、今日より明日、良くなること。 人として正しいことをする。 稲盛さんも経営は素人であった。素人の時に、何を判断基準にするか考えたら、「人として正しいことをする」であった。小さい頃に親や先生から教えられ、大人になると忘れてしまう「嘘をつかない、人に親切にする・・・」そういう原理原則が何においても大事。 楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する。 イメージを抱ければ実現するのみ。例えば、稲盛さんは、まだ携帯電話がない頃、携帯電話の電気料金メニューまで想像できていた。 「世のため人のために尽くす。」「足るを知る。」これに尽きる。 でも忘れてしまうんだな。
0投稿日: 2017.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事の結果=考え方×熱意×能力 単純だが、この言葉が仕事を始めていく上で、一番重要となる言葉であると感じた。 仕事を始める前に読むことでマインドセットできる要素がたくさんあるが、1年前後、自身の振り返りとして読むにも最適な本だと思う
0投稿日: 2017.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は人間の本質的な生き方を学べる本です。特に日本人が日本人から学ぶ最良の本の一つでははいかと思います。 沢山の学びがありますが、今の自分に刺さる三つの学び。 1、人生、仕事の結果=考え方×熱意×能力 これは漠然と感じていた事と式が合致した衝撃だ。今まであった成功体験を継続して重ねる人にはこの式がぴったりあてはまる。 2、なんまん、なんまん、ありがとう 何についても、誰に対しても、いい時は勿論悪い時もありがとうと感謝し、正しく生きようと努める。 どうしても苦しい、理不尽に感じる事に対して、恨みつらみが出てしまうが、困難は成長への糧だと発想を変える方が現実を乗り越える力になる。 3、利他の心 社会人は「してもらう」側から「してあげる」側に立ち周囲に貢献するという考えを常にもつ。「してもらう」立場でいる人間は、足りない事ばかりに目がつき、不平不満ばかりを口にするというのは会社にいて、職位に限らずあることだ。 不足していることは自分達で努力し獲得していかなければいけない。 成功を収めた人達は共通して人間の原理原則を理解し、努力し続けているのだなと実感した。
0投稿日: 2017.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ敏腕経営者の稲盛和夫さんの生き方についての本。 終始感じたのは、稲盛さんの仏教という宗教観が色濃く出ているということ。もちろん人の宗教の自由はあり、それぞれが尊重されるべきである。 しかしそういった観点から、賛同できる点できない点もある。 稲盛さんにとって生き方は「魂を磨く」という点である。人生という宇宙や世界ベースで考えると小さなもので死んでしまったら地位や金は何もなくなってしまうのだから、次に持ち越される魂を磨くべきであるという論理である。 そしてその生き方は経営者として結果的にどう繋がっているかというと 人間として正しくある という、そこの一点のみである。人として正しい選択、意思決定をし続ければ長期的なプラスマイナスの総和はプラスになるということである。 逆の例として、人として正しいことをしていない場合はいずれその利益が損に変わるということがある。 ここで稲盛さんが提示する 人生の結果を導く方程式がある。 結果=考え方×情熱×能力である。 能力は持って生まれたもの 情熱は後天的に身につけられるもの 考え方は生きていく上で磨かれて行くもの この【掛け算】式であることで結果は現れる。考え方はマイナスになりうることもあるので、稲盛さんは人として正しくあれ、と言う理由である。
0投稿日: 2017.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ今更ながら読了。さすがに120時間の講義を受けた身にとっては新しいことはない。良い復習になりました。
0投稿日: 2017.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ楽観的に行動し、悲観的に計画し、楽観的に実行することが物事を成就させ、思いを現実に変えるのに必要。 利を得るにしても人間として正しい道でなくてはならない。
0投稿日: 2017.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログカリスマ経営者として大変著名な方であり、実積も申し分ありません。 でも根底に流れているのは、宗教や自然の摂理を大切にする魂で、これがなければ正しい事業は進まない、とのお考えでした。 以前読んだプロ麻雀師の桜井章一さんの「負けない技術」という本にも「必要以上に勝とうとすると、必ず最後は負ける」と書いてあったのを思い出しました。 偉人はそういう風に達観できるのかなぁ。
0投稿日: 2017.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本を読み進めていくうちに、何かの雑誌で田原総一朗が経営者とのインタビューで「稲盛さんは宗教だからな」という発言を思い出した。正直、私は宗教が苦手である。とはいえ、この本で語られる我々日本人に哲岳、道徳と呼ばれる分野の必要性は理解出来る。かつて日本資本主義の父と呼ばれた渋沢栄一は、道徳と経済は合一しなければならないという理念のもと、論語の精神を取り入れようとしたのは有名な話だ。幕末から明治にかけて猛烈に世界へ追いつこうとした姿は、戦後の日本が富を求めていく姿に似ているのかもしれない。時代は異なっていても偉大な経営者は同じ危機感を抱いたのかもしれない。稲盛氏は自分の哲学を極め、それを実践され、さらには本当に宗教家(僧侶)になってしまわれた。そこまで意思を突き通す精神力はさすがである。そんな稲盛氏も社用車を私用に使おうとして奥さまに諫められるエピソードが微笑ましい この本が語る重要なポイントは極めてシンプルだ。「自分の哲学を持ち、それを突き通す」だろう。その哲学として稲森氏は仏教を選んだ。私の空っぽの心に何を入れていくのか。それが問題だ
0投稿日: 2017.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間として正しいことをするという稲盛哲学が貫かれた本。世の中に様々なビジネス書や自己啓発本があるが、この一冊にそのすべてが凝縮されていると思う。 単純なことですが、これを実践するのが、人生難しい。稲盛さんの生き方に心底憧れます。
0投稿日: 2017.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ年始のちょっと時間があるときに読んでみた。色んなビジネス書や自己啓発本にも出て来る、人生哲学の古典(かと思っていたら2004年の本。意外と新しい)。稲盛氏と京セラという会社を私が知ったのは2003年。大赤字を抱えていた近鉄バファローズの買収先として名前が上がったときだ。懐かしい。そして巡り巡って今大阪ドームは京セラドームなのだから面白い。 書かれていることは当たり前。しかし、実行するのは難しいことばかり。「利他」という概念を稲盛氏はよく話すが、それを心の底から実践していく事のなんと難しいことか。 仏門に入っていたことは知らなかった。文体から仏教的な匂いがするのはそのためか。一度俗世から離れて想いを巡らし修行する時間を持つと、人生の見え方は変わるのかもしれない。 人生80年を、社会に出るための20年・世のため人のために尽くす40年・この世を離れる準備をする20年、と考えるのは個人的にはとても感銘を受けた。シンプルだが、心に響くものがある。
0投稿日: 2017.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ-新卒で入った会社を辞めた時、一番かわいがってもらっていた上司にもらった一冊。ずっと読もう読もうと思って読めなかったが、風邪引いて時間ができた隙に読んだ。 -確かに説教くさい感はある。決めてかかる感じの言い回しは俺の嫌いな大人像とかぶってしまう。そして謙虚さの中に自己顕示欲が見えてしまうのがどこか悲しい。「昔の人だ」と読むのを辞めてしまう人がチラホラいるのはそうゆう理由な気がする。 -ただ学ぶことが多かったのも確か。 -「人として正しいことをしなさい」自分が生まれてきた世界とこなかった世界があって。人類全体の幸福度の総和が、生まれてきた世界の方が低いのであれば、もし世界に負の影響しか与えていないのであれば、その人の価値というのは負になるのではないか。例え自分の幸福度が正だとしても。これは自分が強欲になってるなーと思った時には思い出そうとしている考え方。 -「功績にはお金で報いればいい、人格の高潔な者こそ高い地位に据えよ」元は西郷隆盛の言葉らしいけど。優秀なプレーヤーと優秀なリーダーの明確化を言い得ている。 -「臆病さ、慎重さ、細心さに裏打ちされていない勇気は単なる蛮勇にすぎない」ビビらないということとリスクを取れるということは違う。要は、ビビってることを受け入れて、どこまでその回避に準備できて、最終的にgoが出せるか。
0投稿日: 2017.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人はなんのために生きるのか」 著者は「魂を磨くこと」と定義されてます。 中村天風さんも命の本質は魂(気)と言われてます。 「身体」を鍛える。 「精神」を鍛える。 観念できるものは鍛えることができますがなかなか「魂」を磨くのは難しいです。 著者は魂を磨くには懸命に働くことだと仰ってます。 仕事に没頭することが精進となると。 「仕事の結果=考え方×熱意×能力」 1日1日をド真剣に生きることが魂を磨くことになります。 「思いを実現する」 ナポレオンヒルも中村天風さんも仰ってます。 凄まじく思うことで現実になる姿がカラーで浮かぶくらいに思わないといけません。 「有意注意」とは自分の意識を意図的に凝集させることだそうです。 中村天風さんの教えに「有意注意の人生でなければ意味がない」とあります。 潜在意識に問題意識があれば何事も見逃さないということです。 著者は「6つの精進」を勧められてます。 「努力」「謙虚」「反省」「感謝」「善行 利他行」「感性的な悩みをしない」 これは人生の指針になります。 著者は「運命」と「因果応報」が人生の縦糸と横糸と仰ってます。 「運命「には抗えませんが善行を積むことで人生の因果を変えることができます。 それが魂を磨くということになるのかなと思いました。
1投稿日: 2016.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ真摯、愚直に仕事に取り組む姿勢が大事であるということが読んでいくうちにわかったことだか、働き方も時代によって変わって来るのでは?と考えされられる一冊。
0投稿日: 2016.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ今までの自分の生き方、考え方を深く反省させられるとともに今後の行動の指針となる考えを示してくれる。仏教の教えも随所に出てくる。生きている間に少しでも魂を磨く、徳を高める、今からでも遅くは無い。意識して努めていこうと思った。
0投稿日: 2016.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
宗教を進めているわけではないが、人間の魂の話が多く、そこについては共感できなかった。(ただし、実際に宗教がなくなって道徳心が失われていると書かれていた。) しかし、心の持って生き方には共感できるものがあったし、その通りだと思うこともたくさん書かれていた。 この本の題名にもなっている「生き方」については、特に仕事に対して得られることが多かったように思える。 稲盛和夫(いなもりかずお) 京セラ、KDDI設立。日本航空の会長に就任した。 国際賞、「京都賞」を創設した。 「生きていくことは苦しいことのほうが多いものです。労苦とは、おのれの人間性を鍛えるための絶好のチャンス。試練を「機会」としてとらえることができる人ーそういう人こそ、限られた人生をほんとうに自分のものとして生きていけるのです。」 「昨日の努力に少しの工夫と改良を上乗せして、今日は昨日よりもわずかならがらでも前進する。その、よりよくしようという姿勢を怠らないことが、のちに大きな差となって現れてくる。けっして通い慣れた同じ道は通らないということが、成功に近づく秘訣なのです。」 「どんな遠い夢も、思わない限りはかなはないし、そうありたいと強く心が求めたものだけお私たちは手に入れることができる。そのためには潜在意識に染み込むまで、思って、思って、思い続けるー夢を語ることは、その行為の一つである。夢を描き、創意工夫を重ね、ひたむきに努力を重ねていくことを通じて、人格は磨かれていくからです。」 「何事も「言うは易く行うは難し」で、実行していくのは容易なことではありません。それだけに原理原則は、それを強い意志で貫かなくては意味がない。原理原則というものは正しさや強さの源泉である一方、絶えず戒めていないとつい忘れがちなもろいものでもあります。だからこそ、いつも反省する心を忘れず、自分の行いを自省自戒すること。また、そのことさえも生きる原理原則に組み入れていくことが大切なのです。」 「物事をなすのは、自ら燃え上がり、さらに、そのエネルギーを周囲にも分け与えられる人間なのです。けっして、他人から言われて仕事をする、命令を待って初めて動き出すという人ではありません。言われる前に自分から率先してやりはじめ、周囲の人間の模範となる。そいういう能動性や積極性に富んでいる人なのです。「仕事を好きになる」「好き」こそが最大のモチベーションであり、意欲も努力も、ひいては成功への道筋も、みんな「好き」であることがその母体になる。どんな分野でも、成功する人というのは自分のやっていることに惚れている人です。仕事をとことん好きになれ。それが仕事を通して人生を豊かなものにしていく唯一の方法。」 「日本人は道徳について何も教えられていない。昔から、そういった生きる指針となる哲学というものを人々に教えてくれていたのは仏教やキリスト教に代表される宗教でした。科学文明の発達に伴い、こうした宗教はないがしろにされてしまいました。哲学者の梅原猛先生が「道徳の欠如の根底には宗教の不在がある」といっているが、とくに戦後の日本社会では、戦前の国家神道を核とした思想統制の反動から、道徳や倫理がふだんの生活や教育の場から排除される傾向が強まった。「個性教育」を重視するあまり、人間として身につけるべき最低限のルールやモラルをきちんと教えない。まだ心身ともに成長過程にある少年期にこそ、「人間としてどう生きるべきか」を学び、じっくりと考える機会を与えることが必要なのではないでしょうか。
0投稿日: 2016.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログなんというか当たり前のことばかりが書かれている気がして途中で飽きてしまった。ある程度社会で揉まれてから読むと、そういう当たり前のことが一周回ってありがたく感じるんだろう。
0投稿日: 2016.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆きっかけ 『鏡の法則』p64でおすすめの本として挙げられていた6冊に入っていて。2016/10/20
0投稿日: 2016.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログモウコリタ?: Meet Up 大阪 @ blog http://meetuposaka.seesaa.net/article/442248109.html
0投稿日: 2016.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営とは何か を考える上で、松下幸之助の本を 読んだ。 そして、クロネコヤマトの小倉昌男の本も読み 現在の 経営の神様 稲盛和夫の本を読まないのは 良くないなぁと思って、 『生き方』がベストセラーというので、読んでみた。 マスコミで知らされている 稲盛和夫のイメージがかなり違うことに驚いた。 稲盛和夫は、仏門に入り、僧になっている。 いわゆる 出家である。 日本の経営者は 功なり遂げて、坊さんになるのか ということが、いかにも 日本らしいなぁと思った。 仏教の教えを 現代風にアレンジして とくとくと説明。 実にわかりやすく こころの中に 入り込んでくる。 道徳的なシンプルな基準と言葉。 ニンゲンとして間違っていないか? 根本の倫理や道徳に反していないのか? ウソをついては行けない。 人に迷惑をかけていけない。 正直であれ。 欲張ってはならない。 自分のことばかり考えては行けない。 まさに 日本の道徳ですね。 ダム式経営について どうしたらダムがつくれるのか? という質問に対して 松下幸之助は言う 『そんな方法は私も知りませんのや。 知りませんけども、ダムをつくろうと思わんとあきまへんなぁ。』 松下幸之助の言葉に 稲盛和夫が共感したのが この本の核心ですね。 それを核として 稲盛和夫的な思考的な発展 ということなのかな。
0投稿日: 2016.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ宗教で軍隊(会社)を作る話? あなたが個人の生きる意味を決めるの? 働いていた社員の方は幸せでしたか? 原理原則って結局宗教のことですか? 現代ではそれをブラックと呼ぶんだぜ?
0投稿日: 2016.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者視点での学びが2割、人間的視点での学びが8割くらいの内容を占めた本。 ものすごく上質な道徳の教科書という印象。 ## 経営的な学び ### 「手が切れるようなものを作れ」がモットー * 中途半端なものを作ったって意味が無い。あまりに完璧で、手で触れたら切れてしまいそうなほど非の打ち所がなくなるまでクリエイティブを高めよ。 ### KDDIの成功 * 携帯電話が普及する前、当時の半導体の技術革新のスピード、処理速度やサイズの変遷を観察していると今後携帯電話が一気に普及することは容易に想像できたという。技術的知見を普段からプールしておいて、将来の流れを的確に予測する才能こそが稲盛さんの成功者たる所以だと感じた。 ### 不可能だと思える仕事ほど引き受けよ * 一見不可能に見える仕事をよく引き受けた。最初は不可能に見えても、勉強することで徐々に出口が見えてくる。この繰り返しこそが自分自身の成長になる。これは、ホリエモンが言ってたことと同じや。 ### 継続と反復は違う * 継続は最も重要なこと。しかし、同じことを毎日繰り返すだけの**反復**とは似て非なるものである。毎日改善を重ね、昨日よりも今日、今日よりも明日という風によくしていくことこそが真の継続である。 ## 人間的な学び ### 会社経営に関する知見は全く無かった * 会社を始めた当初、経営に関する教えを受けたこともなく知見が全く無かった。そこで、指針にしていたのは**「その事業は、人間として正しい行いなのか」**ということ。 ### 才能は天からの授かりものだと思え * 自分の才能に甘んじて、それを私物化してはいけない。自分に与えられた才能は、公のために使うべきである。 ### 人の上に立つものは、才覚よりも人格が問われる * 昨今では、学歴を尊重するあまり才覚に長けた人ばかりが人の上に立つ世の中になっている。しかし実際は、才覚よりも**人格**に優れた人こそが人の上に立つべきである。 * 人間にとって重要なことは、 1. 人格 2. 勇気 3. 能力 の順に並ぶ。 * 人の上に立つものは、**偽りがあってはいけないし、私心があってはいけないし、わがままであってはいけないし、奢りの心があってはいけない**。稲盛さんは事業の行き先で大きな決断を下す時、**「その思いには己の欲が働いていないか。私心が混じっていないか。」**というのを自問自答していたという。 ### 良いことがあったなら必ず感謝せよ * 何か良い結果が得られたとき、そのことには必ず感謝すべきである。ところが、人は良いことがあると、**それを当たり前だと考え、あわよくばもっともっとと欲張ることも少なくない。** ### 素直な心 * どれだけ人の上に立とうとも、奢らず、**生涯一生徒の気持ち**になって学び続ける心を持て。これは、松下幸之助さんがまさにそういう姿勢の持ち主だったらしい。 ### 仕事の喜び * 仕事における喜びは、飴玉のように口に入れたらすぐに甘いというようなものではない(プライベートの趣味などはこれにあたる)。**「労働は苦い根と甘い果実を持っている」**というように、じわじわと時間をかけて甘い部分がにじみ出てくるものである。 ### 足るを知るものは富めり * これだけあれば十分だ、という基準を明確に自分の中に持っている人は、人生が豊かになるという話 * 例えば、何も考えずにいると給料の額はあがってもあがってもそれに応じて生活水準をあげつづけ、結局際限なくお金を求めることになる。これではいつまで経っても心が豊かにはなれない。 * 実際は、例えば15万もあれば人として最低限の暮らしはできる。これを理解できていて動ける人は強い。 ### 因果報応の法則 * 因果報応、というと胡散臭いと思われがちだが、これは世の中に存在する絶対に揺るがない普遍的な法則なのだ。 * ただし誤解されがちなのが、今日善い行いをしたから明日自分に善い結果が返ってくる、というわけではないということ。実際は、10年〜20年単位で考えるべきである。そのスパンで善い行いを日々続けていると、必ず自分にも善い成果がもたらされる。
1投稿日: 2016.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
京セラ会長の稲盛さんの作品。すごくすごく広い視点から「生きる」ということを捉えていて、ただただ刺激的で感動する本だった。 利他の精神を大事にすることや足るを知るということ、魂を清めようと努めることなど、シンプルではありながらもすごくパワーに満ちた言葉たちで紡がれていた。 自分も堂々と生きられるようにしていきたい。
0投稿日: 2016.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ心に響くフレーズがたくさんありました。 素直に、誠実に、ど真剣に生きる。 まさしく、このように生きていきたいものだと思いました。
0投稿日: 2016.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容的には、生き方、道徳、倫理など、納得・共感できる部分が多かった。 だが、一方で「宇宙の意思」のような似非科学を挟んできたのが残念。 科学と結び付けない方が、本当の内容は深まったように感じる。 安易な似非科学で説得力を増そうと考えるのはまさに煩悩ではなかろうか。
1投稿日: 2016.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ■ポイント ・「人生、仕事の結果=考え方×熱意×能力」。能力なくても熱意や考え方が勝れば、能力だけの人に勝てる ・思いを実現させるためには、「こうありたい」と思うこと。それも身が焦げるほど強く。「こうなればいいな」ではなく、四六時中、あたまのてっぺんからつま先まで考え抜く。そうすることで潜在意識にまで刷り込ませる。 ・イメージは白黒なうちは不十分で、カラーで見えるくらい、執拗に思い描く。 ・できないことがあってもそれは現在そうなだけで、未来の自分ならできると未来進行形で考えることが大事 ・継続が平凡を非凡に変える ・判断の基準となる原理原則を持っているかが人生を決める ・原理原則をもって生きるのは、おのれを律することなにでつらいこともある ・仕事が好きになれない人はまず一心不乱に打ち込むことで好きなる ■気付き ・「思考は現実化する」を体現した人が稲森さん。しかも、カラーで浮かぶくらい執拗にイメージする、というのはすごい。
0投稿日: 2016.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ現世とは心を高めるために与えられた期間であり、魂を磨くための修養の場である。試練を機会として捉えることができる人、そうゆう人こそ限られた人生を本当に自分のものとして生きていける。 才覚が人並みはずれたものであればあるほど、それを正しい方向に導く羅針盤が必要。その指針は理念、思想、哲学。 人格=性格+哲学 人生、仕事の結果=考え方×熱意×能力 思いを現実に変えるのに必要なこと 楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する 忘己利他 もうこりた 足るを知る いまもっているもので足りる心がなかったらさらに欲しいと思っているものを手に入れたところで、決して満足することはできない 運命と因果律 運命を縦糸、因果応報の法則を横糸 運命より因果応報のほうが若干強い
0投稿日: 2016.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ生まれた時よりも 魂をより良く 磨きあげるために 生まれてきた 何事にも感謝すること 震災があったら 業がなくなったと思え
0投稿日: 2016.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の本は初めてです。 国内外でロングベストセラーとなっていますが、圧巻の内容でした。 仏教の部分は、今の私には少しついていけないところもありましたが、結果の方程式、労働による人格の陶冶、自燃性の話等が特に興味深く、やっぱり努力が大事なんだと背中を押され、また勇気付けられました。 与えられることが当たり前だと思っている人は不満ばかり言うといった話や、リーダーには才覚より人徳が重要といった話など、具体的で身近に感じることとのできる内容も多く、これらはストレートに響きました。 日常では目先の利益、合理、効率が論ぜられがちですが、この本にあるように、それよりも倫理、道徳、哲学を大事にしたいと思います。 繰り返し読んで理解を深めたいです。 また、著者の作品または著者に関して記載された別の作品も読んでみたいです。
0投稿日: 2016.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログまさに、生き方。 生きる上で1番何に重点を 置けばよいのか。 成功するためにはなにが必要なのか。 よくわかる
0投稿日: 2016.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
京セラ、KDDIの稲盛さんの自書。 仕事に対する純粋でまっすぐな取り組みがわかる。お金のためでなく人のため、人類のための仕事。 シンプルな言葉だが、改めて子供たちには伝えたい言葉も詰まってる。 宗教的な要素も強いが、シンプルなことで本質が伝わってくる。 p.19 人間として正しいことを正しいまま貫いていく。 嘘をついてはいけない、人に迷惑をかけてはいけない、正直であれ、欲張ってはならない、自分のことばから考えてはならない、 p.27よい心 つねに前向きで建設的であること、感謝の心を持ち、みんなと一緒に歩もうという協調性を有していること、明るく肯定的であること、善意に満ち、思いやりがあり、やさしい心を持っていること、努力を惜しまないこと、足るを知り、利己的でなく、強欲ではないことなど p.33 何かを絵嘔吐、一生懸命頑張る p.43 成功する人と失敗に終わる人は、願望の大きさ、高さ、深さ、熱さの差 思って、思って、思いぬくこと p.142 どんなときも ありがとう といえる準備をしておく。常にありがとう。という p.144 何があってもありがとう。困難な機会に成長できてありがとう。 p.162 修養 布施、持戒、精進、忍辱、禅定、智慧 p.183 私心が混じっていないかを、自分に厳しくとく p.198 少年期こを、 「人間としてどう生きるべきか」を学ぶ。正しい職業観も学ばせるべき。 例えば、小学生のときから、世の中にはこれだけ多くの職業があり、それぞれの分野でたくさんの人が働いている、だから、社会や人間の暮らしが成り立っている。 p.228 自分の人生を三つの期に分けて考えていた 0〜20(独り立ちして人生を歩き始める), 20〜60(社会に出、自己研鑽に努め、世のため人のために働く期間), 60〜80(死への準備):人生とは何かを学び死への準備をしたい。
1投稿日: 2016.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間がこの世に生まれてくる理由と、人生どのように過ごすべきなのか、自分の生き方を見直す機会を与えてくれる本。バイブルになると思います。
0投稿日: 2016.01.30
