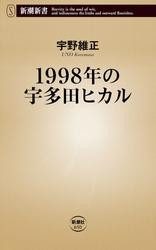
1998年の宇多田ヒカル(新潮新書)
宇野維正
新潮新書
東芝EMIガールズ復活
1982年家庭用CDプレーヤーが発売された年は歌謡曲、アイドル全盛時代だった。ミリオンはあみんの「待つわ」で売り上げ20位以内には「ジェームス・ディーンのように」のJohnny のみが横文字だった。因みにマッチの2曲以外は全て唄える。サザンのチャコもこの年だ。マッチと松田聖子が3曲、中島みゆきが2曲ランクイン。 1988年日本人が最も多くのCDを買った年、GRAYの「誘惑」、SMAPの「夜空のムコウ」以下ミリオンは14枚。全て横文字でKiroroやkinki、B,zなどデュオはいてもソロと言えそうなのは「ピンクスパイダー」のhide with…くらい。L'Arcが4曲、SPEEDとkinkiが3曲ランクイン。JーPOPの時代だった。おそらく半分は今でも唄える。 さらに16年後の2014年ミリオンはAKBの5枚で46と48で13曲、ジャニーズが嵐、関ジャニ、Sexy Zoneで6曲、それ以外はEXILEのみ。名前を見ても全く知らない曲ばかり。CDはゴミと化した。しかしライブをやればサザンや中島みゆきだけでなく満員にできるアーティストは他にも多い。 日本の音楽業界のピークの年であった1998年にデビューしたのが本書の主人公達、宇多田ヒカル、椎名林檎、aikoー著者が年齢、性別を問わず日本のトップ3と評価する音楽家ーそして浜崎あゆみだ。この年にはKiroro、モー娘、MISIA、鈴木あみもデビューしている。当時は小室哲哉がB級アイドルを次々とプロデュースしアーティストに仕立て上げていた。著者は82年のアイドル全盛期からアーティストへの流れが1998年の奇蹟の鍵だったと見ている。 82年のアイドルは聖子ちゃんカットから始まった。その中から抜け出したのが自己プロデュース能力に長ける中森明菜と小泉今日子であり、アイドルがアーティストと呼ばれだしたのが工藤静香からだった。必ずしも自分で詩や曲を書いたり演奏するからアーティストと呼ばれる訳ではない。身もフタもない事実は、同性からの支持を受けるかどうかだ。それを一番うまくプロデュースしたのが小室哲哉であり、デビュー当時から自己をプロデュースしてきたのが主人公達だった。 宇多田ヒカルのデビューは一家により周到に準備されたものだった、主戦場はテレビではない。FMとクラブであり、あの印象的な「AUTOMATIC」のテレビスポットが流れたのはデビューから1ヶ月以上たちラジオでいい感じになってきたからレコード会社が慌てて打ったものだ。一家が東芝EMIにつけた条件は宇多田が自由に製作できる音楽環境を作り、彼女の作品に第三者が手を加えないことだった。宇多田は極端なレコーディングアーティストであり、これまでにステージに上がったのは僅か67回。その中の一つが椎名林檎と組んだ東芝EMIガールズで、このコンビの復活が本書で予言されていたと話題になっている。スタジオで育った宇多田は編曲に始まり全ての音を統括していくようになる。 人間活動に入り作品の発表を止めた宇多田に対し椎名林檎は「ヒカルちゃん、ずりいよ」と言いながらも日本のポップスシーンの席が空いちゃうからと作品を作り続けている。スタッフを抱える個人事務所を持ち、コンサートも贅沢に作るためという経済的事情もあるが「現状誰もやってないと感じるからやっているだけで、誰かがやっていればパタンと辞めます」と、そしてその危機感はオリンピックへ及ぶ。「大丈夫なのか東京」しかしリオの閉会式の見事な演出の理由でおそらくその危機は回避されただろう。「絶対に回避せねばならない方向性はどういうものか、毎日考えています」と言うのが何かは2014年のヒットチャートを見ればわかる。 1995年、椎名林檎も出たヤマハの10代のコンテストでグランプリを獲ったのがaikoだった。その後aikoは事務所もレコード会社も決まる前からラジオのDJに抜擢されローカル・スターとなっていた。翌年aikoはヤマハと軽い気持で契約するのだが、自主制作もライブもできない窮屈なものだった。契約が切れ、インディーズデビューの後今度は映画主題歌でメジャーデビューを果たすが、これまた小室哲哉の出来損ないのような曲に歌詞をつけるという制約の多いaikoにとってはどうでもいいようなものになった。セカンドシングルでようやく自己プロデュースによるセカンドデビューを果たしたaikoの頑固な世界はその後全く変わらない。「曲とか詩とかはね、ぶっちゃけ全部おんなじなんですよねこの人。」 そして今年、宇多田ヒカルが帰ってくる。それでもCDが売れないとすれば、とどめを刺されたことになる。
0投稿日: 2016.09.25
国のために死ねるか 自衛隊「特殊部隊」創設者の思想と行動
伊藤祐靖
文春新書
不審船は止まっちまった、そこへお前は「ですよね」で行ってしまうのか
ほぼ同年代ながら価値観にだいぶ差がある。それでも読んで損はない。非武装平和主義で自衛隊を認めない人にとってもそうだと思う。 1999年3月自衛隊の最新鋭イージス鑑「みょうこう」は北朝鮮の不審船を発見した。追いついた海上保安庁の巡視船はパラパラと上空に向けて威嚇にならない威嚇射撃をした後帰投する燃料に不安があると引き上げて行った。逃げる不審船に対しみょうこうは127ミリ炸裂砲弾を着弾点を近づけながら威嚇射撃を繰り返し前方50mで船橋窓ガラスが吹き飛んだがそれでも船は止まらない。船を飛び越えて100m先の弾着でようやく船が止まる。 「止まっちまった」拉致された日本人を発見したら、是が非でも救出しなければならない。だが、無理だ。なぜなら、1回も訓練をしたことがない。防弾チョッキもなく、立入検査隊員達は拳銃を握ったこともない。船が自爆すれば隊員達は全滅する。闇夜の中で行く意味が有るのか尋ねる手旗要員に航海長だった伊藤氏が答える。「つべこべ言うな。今、日本は国家としての意思を示そうとしている。あの船には、拉致された日本人のいる可能性がある。国家はその人たちを何が何でも取り返そうとしている。だから、我々が行く。国家がその意思を発揮する時、誰かが犠牲にならなければならないのなら、それは我々がやることになっている。その時のために自衛官の生命は存在する。行って、できることをやれ」「ですよね、そうですよね。わかりました。」これには伊藤氏の方がめんくらってしまう。それでいいのか?私に反論しないのか?お前は、「ですよね」で行ってしまうのか・・・ 彼らを政治家なんぞの命令で行かせたくない。そしてもう一つ「彼らは向いていない」向いている者はほかにいる。世の中には、「まあ、死ぬのはしょうがないとして、いかに任務を達成するか考えよう」と言う者がいる。向いていない者にこの厳しい任務を強いるのは、日本国として、これを最後にしなければならない。これが伊藤氏が特殊部隊の創設に関わるきっかけだった。 伊藤氏が自衛隊に入ったのはバブル前、自衛隊はまともな奴のいくところだとは思われていなかった。確かに防衛大学に入れば学費はいらないとか、夜明けの新宿を歩いていると声をかけて来るのが自衛隊の勧誘だとかそんな話はあった。ではそんな自衛隊の実力はどうか。兵力の比較はよく知られているが組織戦闘力の強弱については「バックに国家があるか」「生命を失う気があるか」で比較されることが多い。よく言われるのは生命を失う覚悟がなく、法的な根拠に弱さがある自衛隊の実力は4段階で下から2番目の弱い方だ。上から順に特殊部隊、自爆テロ、通常の軍隊で一番下は海賊。しかし伊藤氏は日本の特殊性により違うと言う。 日本はトップレベルに特出したものがないが、ボトムのレベルが非常に高い。優秀じゃない人が極端に少ない。モラルのない人がほとんどいない。一般的な傾向として軍隊にはその国の底辺の人材が集まる。だから戦争とは国の底辺通しの戦いなのでボトムのレベルが極めて重要になる。部隊の大多数を占める下士官が優秀な日本は他国の将校からは非常に優秀に写る。アメリカはその逆で下士官はだnめで、特殊部隊の技量も低いと言う。その米軍がが世界最強な理由は兵員の役割を分担して負担を軽くし、システマチックに運用することで交代要員を量産できることだ。 伊藤氏が自衛隊を止めるきっかけが、特殊部隊創立以来の各国とのコネクションを維持し、そこから得る技術や知識を日本で必要とする後輩に伝えるためだった。そのためには身寄りがない場所で「撃てて、潜れて、平和ボケしない緊張感」が必須だった。そこで知り会って弟子の-本当は師匠のような-若い女性にこう言われて窮する。「あなたの国はおかしい」「掟というのはこの土地で本気で生きる者のために、この土地で本気で生きた祖先が残してくれたもの」「あなたの国の掟は誰が作ったの」「他人が作った掟に従って生きていくような者がこの土地に生きることを、誰も絶対に許しはしないわ。12時間以内にあなたは生き物じゃなくなるわよ」殺害予告だ。「祖先の残してくれた掟を捨てて、他人が作った掟を大事にするような人を、あなたは、なぜ助けたいの?そんな人たちが住んでいる国の何がいいの?ここで生きればいいじゃない。」 守る価値のある国であって欲しいと言うのが伊藤氏の願いだが、価値観は人それぞれだ。昔から日本は掟や言葉を海外から取り入れて来た。押し付けられた掟だろうが残るものは残り、なくなるものは何れなくなるだろうよ。
2投稿日: 2016.09.07
原油暴落の謎を解く
岩瀬昇
文春新書
油断は再び起こるのか
日々の原油価格は在庫が増えたとか、増産の可能性がとか後付けとしか思えない理由で動いている。原油価格はいつかは上がるのか、またその時期はいつか。長年取引の現場にいた著者からの解説がこの本だ。 今は50ドル近くに戻ってきているが2月11日には26.12ドルの最安値をつけた。年明けから3週間ほどで価格が3割下がった理由は3つと考えられている。サウジとイランの断交により減産合意の可能性が当面なくなった。そして経済制裁の解除によりイランには増産の動機が生まれ供給過剰が予想より早く進む。そして1月19日に発表された中国の2015年のGDPは6.9%、金融市場は実際にはもっと低いのではと色めき立った。 中国の需要は本当に減るのか?8月末の時点まで粗鋼の生産は対前年比マイナスを続けているが、不動産投資、固定資産投資、セメント生産量は今年に入って回復している。成長率は低下するとしても需要は伸びると見た方が硬いようだ。 予想以上に競争力が有ると見られてシェールオイルは暴落の原因なのか?著者の見立てでは最も競争力のあるリグは50ドル台でも稼働する。在来型の油田が取り続けないと効率が悪くなるのに対しシェールオイルは比較的簡単に採掘を止められ、価格上昇時には増産に対応できる。将来価格が上昇する時にはシェールオイルがシーリングの役目を果たしそれが60ドルというのが著者の予想だ。 では最大の問題は何かと言うと2年にわたる供給過剰で積み上がった膨大な在庫だ。2016年始めで100万〜200万バレル/日の供給過剰で2月末のOECD全加盟国の在庫は30億バレル、日本の需要の2年分を超える。この在庫はいつかは市中に放出されるため価格の下押し要因となっている。 投機筋の影響はどうか?NYMEXでは日当たり9000万バレルの生産量に対し、10億バレルが取引されており未決済の残高も17億バレルある。原油生産業者は将来の価格下落に備え先物は売り越し、航空会社が買い越す結果実需グループでは売り越しとなっている。一方投機筋と呼ばれる金融業者は買い越し将来の価格上昇にかけている。 では原油価格はどうなるのか。米EIAは膨大な在庫が有るので原油が高騰することはないと予想している。しかし、著者は市場参加者が将来の需給バランスを重視するため価格は上昇すると予想する。在庫のリバランスはいつかは目立たないように進み、いつか需要が供給を上回る日が来る。OPECが減産を決めなければ、中東で地政学上のリスクが暴発しなければ価格は上がる。日本は今こそ国家備蓄を進める時だというのが著者の提言だ。
0投稿日: 2016.08.27
宿澤広朗 運を支配した男
加藤仁
講談社+α文庫
南ア戦を見たらなんと言っただろうか
宿澤ジャパンがスコットランドに勝った試合を見た記憶はない。1989年5月28日何をしていたんだろう?第一回のワールドカップも見ていないので日本代表の試合をまともに見たのは第2回ワールドカップの宿澤ジャパンだった。今から思えばスコットランド戦もアイルランド戦も前半は健闘していた。林、梶原のタックルは記憶に残っている。時々チャンスを作るがノックオン、スローフォワード、オーバーザトップがもったいないのと、後半タックルミスで突き放されたと言う印象だった。 宿澤が代表監督を打診されたのはこの年の2月中旬、前年11月のアジア大会で韓国に破れ代表監督の日比野は辞意を固める。当時ラグビー協会の専務理事であった白井善三郎は宿澤がいた早稲田が日本選手権を二連覇した時の監督であり、早稲田では日比野の3年先輩に当たる。その白井が日比野に対し「お前、宿を口説いてくれ」と言った。89年2月、呼び出された宿澤は開口一番「早稲田かと思いましたよ」と言った。当時住友銀行のロンドン駐在から帰国し引き続き為替ディーリングの仕事をしていたのだが、当時会長でラグビー好きの磯田一郎の鶴の一声で決まったようだ。監督になってからも朝一で出社し今日の為替はどう?と声をかけそれから練習に出かけた。翌年には銀行の配慮で法人部に移る。 代表監督に就任した宿澤は「外国人に通用する強さかスピードがある」「ディフェンスが強い」を基準に選抜をした。wikiでは他にラインアウトとゴールキックを重視したとも書いており防御を中心に走り回る事ができるチームだったようだ。梶原もここで抜擢され右プロップの田倉とともにスコットランド戦が初キャップを得た。また当時大学生のラトゥ、吉田、堀越(平尾が断ればキャプテン候補だった)、青木などがレギュラーに抜擢されている。しかしスコットランド戦まではわずか6ヶ月と時間がない。勝ちに拘る宿澤は具体的にどうやって勝つかに集中する。ロンドンでの為替ディーリング時代もポジションはその日のうちに手じまいし翌日には残さず、ばくちではない負けないディールと瞬間での判断が宿澤のスタイルだった。 宿澤は情報、分析、活用に力を注ぎスコットランドの防御の弱さに着目する。「スコットランド戦は勝ちにいく。相手は第二線防御が甘く、ジャパンのバックスで25点は取れる。だから失点を20点以内に押さえれば勝てる。」繰り返し言い続けた。「お約束どおり勝ちました」宿澤の試合後の第一声だ。宿澤はどういう条件が揃えば勝てるか具体的な状況を想定し、練習を重ねたのだ。その後の銀行時代の話を見ると意外な事にパソコンは苦手で、本も読まず、新聞は目を通す程度。宿澤の言う情報は自分で見たり会ったりしたことを重視している。ワールドカップの準備ではジンバブエまで偵察に言っている。 銀行員としての宿澤はバブル崩壊後の不動産処理と言う傷を比較的追わず、大塚駅前支店長時代もここぞと言う場面で行動力を見せ見違えるような業績回復を果たした。平成2年イトマン事件で構内が沈んでいる時には宿澤の代表監督での活躍は銀行の励みにもなった様だ。市場営業部時代には債券の運用でリスクを取り「攻めの宿澤」は2002年には銀行の粗利の1/3にあたる5815億を稼ぎだした。この時の他行の稼ぎは3千億台だった。 911テロではその夜事件を知ると銀行にかけつけすぐに指示を出している。先ず第一に「ドル資金の調達」次に「お客さんのためにできる限りの事をする」そして「勝機を逃さない」。1と2はセットでドル資金が足りなければ銀行の信用は失墜し、お客さんを助ける事もできない。そして緊急事態では大損する可能性があるディーラーに対しても「レートを出せ、逃げるな」と指示している。「勝機を逃がさない」と言うのはどさくさで儲けると言うのではなく金利低下のポジションをとると言う事で、あくまで論理的な思考に基づいている。宿澤はラグビーと仕事は関係ないと言うがこういう一瞬の判断はスクラムハーフの面目躍如でありキャプテンシーの発揮もさすがだ。 アマチュアリズムに限界を感じラグビー改革に情熱を注いでいた宿澤だが協会理事を事実上解任されたのが2005年の6月、急逝の一年前の事だった。2004年の欧州遠征で惨敗し、萩本監督解任と外国人監督(エディ・ジョーンズが候補だった!)の招聘が理事会で固まったのに直後の報道では監督続投。早すぎる改革に反対する守旧派の抵抗だった。
0投稿日: 2016.07.15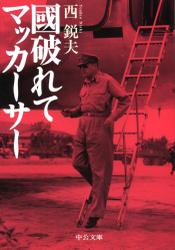
國破れて マッカーサー
西鋭夫
中公文庫
富か誇りか
著者の西氏はフーヴァー研究所の研究員でアメリカの日本占領期間の公文書や一次文書を発掘し書き上げた論文「unconditional democracy (無条件民主主義とでも訳すのか)」を元に再構成したのが本書で、マッカーサーのアイデアから出た日本国憲法と第9条、「民主主義」を拡げるために最重要視した教育の改革そしてサンフランシスコ平和条約を取り巻く環境と言う3部構成になっている。 日本は「富」を追求する代わりに最も大切にしていた「大和魂」を失った。「誇り」を、アメリカは敗戦直後の虚脱状態にあった日本国民の心の中から、永久平和と民主主義という甘い言葉で誘い出し、アジア・太平洋の「征夷大将軍」マッカーサー元帥の密室で扼殺した。 その死体が憲法第九条。 憲法第九条は「愛国心」の墓。 我々の「誇り」は第九条の中に埋葬されている。 西氏の政治姿勢はこれでわかるだろう。この本に対する評価も人によって180度違うだろう。内容はともかく読みにくい、わかりにくい日本語だとだけ言っておこう。 1945/5/11すでにナチス・ドイツは敗れ日本へ休戦と和平を模索していた。しかし天皇につき曖昧にしておけば日本は受け入れやすいと言うのがポツダム宣言におけるアメリカの狙いだったが裏目に出、トルーマンに原爆を使う口実を与えることになった。そして無条件降伏した日本にマッカーサーが降り立った。アメリカ史上でも最大の絶対的な権力を持って。連合国はワシントンに極東委員会を置いたがマッカーサーは自分より強力な権限を持つ極東委員会を事実上無視した。そのため日本にもたらされた民主主義はマッカーサー個人のアイデアによるところが大きい。 マッカーサーの言う民主主義は「アメリカの政治、社会文化及び経済体制」であり、日本の敗北を軍事だけでなく「信仰の崩壊」と見、この空白の中に民主主義を注ぎ込んだ。この背景にはキリスト教の信仰がある。 一方で天皇の地位を守ったのもマッカーサーと言える。ソ連、イギリス、中国、オーストラリアに加えアメリカ国内でも天皇を戦犯として裁けと言う意見が強くなっていたが、「天皇を葬れば日本国家は分解する」「憎悪と復讐」が連鎖するのを恐れマッカーサーは陸軍省に極秘電報を打ち天皇の命を救うことになる。この電報を発掘したのは西氏の功績だろう。これは付録に載っている。とは言えマッカーサーが天皇に敬意を払っていた様子は見られない、あくまで自分の理想に日本の社会を作り変えるためだ。 マッカーサーが全体主義を破壊し、民主主義を植え付けようとした副作用の一部はマッカーサーにも向った。共産主義者は合法化されたが以前国民には嫌われていた。憲法改正において保守主義者は出来るだけ明治憲法を守ろうとした。この時GHQ案に最も近いのは「主権は人民にある」とした共産党案だった。しかしスターリンとつながる共産党案を褒めることはできない。政府案はこうだ。「天皇は至尊にして侵すべからず」どうせ後から修正されるので出来るだけ明治憲法から変えないほうが良いと言う政府案はマッカーサーを怒らせ、マッカーサーの直筆のノートを元に民政局は憲法草案を6日間で書き上げた。そして2週間後これを元に政府草案が提出された。 1946/6/28衆議院の憲法草案審議の際、スターリンのスパイ共産党の野坂参三と吉田茂は戦争放棄について議論した。この時自衛のための戦争を良しとしたのは野坂であり、正当防衛が戦争を誘発するとしたのが吉田だった。戦争放棄を訴えマッカーサーと吉田はその後朝鮮戦争の勃発とともに自衛隊を創設し、レッドパージにより共産主義者を公職から追放するようになる。 教育改革もうまくいったとは言えない。マッカーサーから見ると天皇制と切り離せないのが教育勅語であり、民主主義と平和教育は教育勅語の廃止とセットになっている。まず軍国主義に賛成したものを追放し、教育委員会の選挙を行ったが例えば大阪では立候補したのは闇市のボスと共産主義者ばかりだった。まともな候補者は彼らと争うのを嫌がったからだ。予算不足から教員の給与は安く抑えられ食うや食わずだった。昇給を求める教員たちが育てたのが日教組だ。食料や予算の不足はアメリカの責任ではないのだが。結局いろんな問題を朝鮮戦争での好景気が覆い隠したことになるが、それすらも著者にとっては富と誇りの交換として捉えられている。
1投稿日: 2016.06.20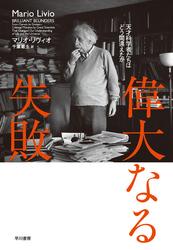
偉大なる失敗 天才科学者たちはどう間違えたか
マリオリヴィオ,千葉敏生
早川書房
歳をとって自説に固執すると最先端にはついていけなくなる
天才科学者も間違いは起こす。その多くの間違いの中から選ばれたのがダーウィン、ケルヴィン卿、ポーリング、フレッド・ホイルそして「最大の過ち」が有名なアインシュタインだ。ダーウィンとアインシュタイン以外は普通の人は知らないような気もする。 ダーウィンの過ちとは自然選択が働くための条件についてだ。種の起源の発表は1859年、メンデルのエンドウマメの実験は1853ー1868で発表は1865-66のマイナーな学会でだった。メンデルは種の起源を読んでいたがダーウィンがメンデルの実験結果を知っていたかは微妙だ。メンデルの実験結果が書かれた本をダーウィンは持っていたが、そのページは閉じられたままだった。 ダーウィンの考えた遺伝は融合遺伝というもので突然変異は次世代に受け継がれるがそこに遺伝子の概念はなく、獲得した形質がそのまま引き継がれる。ススだらけのロンドンでは黒い蛾が生き残っていたのだが、融合遺伝の場合100匹の白い蛾の集団の中で1匹の黒い蛾が生まれて子孫ができたとしても2代目は灰色になる。1匹の黒い蛾は100匹の中で薄まっていき元と比べて少しだけ黒い集団になる。遺伝子と優性遺伝の考えを取り入れないと黒い蛾の集団は生まれない。ダーウィンは融合遺伝のもとでは自然選択がうまく働かないことを充分に考慮しなかった。 ケルヴィン卿は絶対温度のkに名を残し、熱力学第二法則を生んだ物理学者だが地球の年齢を計算した地質学者でも有る。ケルヴィンは岩石の熱伝導率などを調べ、溶融状態の原始地球が現在の温度に冷えて固まるまでの時間から地球の年齢を計算した。ケルヴィンは岩石が凝固した時点であらゆる場所が同じ温度だったと仮定したのだった。その結果は約1億歳だ。一方で核融合が知られてない当時太陽の熱源を重力として計算するとやはり1億歳が出てくる。 地質学者達は地球内部の構造が一定でなかった場合に何倍も伸びる可能性を指摘したがケルヴィンは取り合わなかった。この話でいまいちよくわからないのが均質で熱伝導率が一定の地球が1億歳だとした場合にマントル対流がありより熱伝導率が高い実際の地球の方がなぜ何十倍も年寄りになるかだった。 ポーリングは二重らせんの発見にあと一歩のところにいながら有名なロザリンド・フランクリンの写真を機会がありながら見なかったためにワトソン・クリックに先を越された。 そしてアインシュタインの最大の過ちとは一般相対性理論に美しくない宇宙項を付け加えたことというのがよく知られる話なのだがこの本の結論は間逆で後に宇宙項をなくしたことが最大の失敗だったと結論づけている。最近の研究から宇宙の膨張は加速していることがわかってきた。重力が働けば普通は膨張は減速するはずだ。加速するということは斥力が働いているということであり、これがどこから来るかというと真空にゆらぎがありそこにダークエネルギーという莫大なエネルギーが隠れている。宇宙項はこのダークエネルギーを表すのにちょうどいいのだ。宇宙学者や物理学者がどういってもこのあたりの理解はいつまでたっても追いつかない。 この本から読み取れるのは歳をとって自説に固執すると最先端にはついていけなくなるということだが、それを失敗と呼ぶのか?
1投稿日: 2016.05.29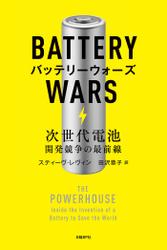
バッテリーウォーズ 次世代電池開発競争の最前線
スティーヴ・レヴィン,田沢恭子
日経BP
電池のイノベーションには期待しているが
アメリカの電池研究のハブとなったアルゴンヌ研究所とベンチャー起業エンビアそしてそこで働くバッテリーガイたちが目指すのは日本や韓国企業に差をつけられている電池のイノベーションを起こし電気自動車をきっかけに巨大な電池産業を生み出すことだ。この本では技術的な内容も語られるがむしろテーマはもっとドロドロした人間関係やバッテリーガイたちのエゴむき出しの姿だ。 1991年ソニーがリチウム電池を発表し現在に続くモバイル機器の誕生のきっかけが生まれた。この電池の開発にはMITのジョン・グッドイナフが大きな役割を果たしていた。グッドイナフはそのころアイデアが生まれたばかりのリチウム電池の性能をもっと上げられると考えた。ここで採用した酸化物の正極と炭素の負極という組み合わせはその後のリチウム電池の基礎を築いた。グッドイナフは最初のリチウムイオン電池で中心的な役割を果たしたにも関わらず、特許料を一切受け取っていない。所属したオックスフォードが正極材の特許取得を拒否したためだ。1980年代電池は儲からずその権利を買い取り改良を重ねた日本企業がリードしていく。 リチウムイオン電池の概念はそれほど難しいものではない。放電する際にリチウムが正極材から負極材に移動する。移動速度がパワーで移動する総量が電池の容量だ。問題は金属酸化物の正極にどれだけリチウムを詰め込めるのかとそれをどれだけ引き抜けるのか。正極材のほとんどがリチウムだと引き抜いた際に正極材がすかすかになり崩壊してしまう。つまり正極材は繰り返しの充放電で物理的な構造を保ち続けなければいくら初期性能が良くても使い物にならない。過放電でバッテリーが死ぬのは正極材の構造が変わりもはやリチウムを取り込めなくなるからだろう。 南アフリカ出身のサッカリーは独自のアイデアで酸化鉄の電極を開発した。グッドイナフの計算では構造中にリチウムが入る隙間はなかったが電圧をかけてリチウムを押し込むと構造が変わり有望な材料に生まれ変わった。サッカリーはさらに有望な材料系としてニッケル、マンガン、コバルト系のNMCを正極材として開発した。基本的にはこれが現在のリチウムイオン電池の基礎になっている。 グッドイナフの研究所に来た日本からの研究者が同僚の発見を持ち帰りNTTが特許を出願したとこの本では描かれている。日本は知財権ではやられっぱなしのイメージだが、この本では抜け目なく材料技術の改良に労力を惜しまない強力なライバル扱いだ。権利化はその後も泥沼の様相で、MIT教授の蒋がグッドイナフの材料に手を加え特許を取得しA123というベンチャーを設立した。ここから流れた技術が中国のBYDに流れたとの噂を著者は示唆している。 サッカリーと並ぶスターとなったのがモロッコ出身のハリール・アミーンだ。京都大のポスドクをへてアルゴンヌに加わったアミーンは研究に情熱を燃やすサッカリーとは異なり市場に製品を送り出すことに関心を持ち自分の権利を徹底的に主張する攻撃的な人物だった。アミーンは見過ごされていた電解液に目をつけ新たな分子を導入することで発火の危険が減ることを突き止めた。アミーンは後に日本式のやり方を取り入れた。どこかで手に入れたアイデアに手を加え部下の研究員をチームとしてまとめ片っ端から研究させる。アミーンチームは論文数、特許数で実績を積み10年間で120件の発明を生み出した。。このやり方は一部の研究者から批判を読んだが日本などではフェアであると認められ、結果を出せば賞賛される。「日本、中国、韓国は、他者のアイデアを平気で足場としながら経済的優位を保ち、いずれ収益性の高い産業が生まれると確信して何年間も金を注ぎ込み続けた。アミーンはただ日本式のやり方をまねしているだけだった。」やけに批判的だが産業スパイとは次元が違う普通の企業活動だと思う。 2012年ボルトの販売台数は7671台、中国でも1万台に届かず、日産リーフも同様だった。一方でトヨタのハイブリッド車は累計400万台、勝負はついている。アメリカには長期的な計画に予算を組む企業はなく電池関連の会議は静まりかえっていた。30年後EVがまだメジャーになれないもう一つの理由は車体価格の差だ。電気が安くても初期費用の差が埋まらない。 しかしテスラの登場から雰囲気ががらっと変わる。テスラは最先端の技術は選ばず枯れた技術を工学的に磨き上げる方法を選んだ。そしてわずか4ページの最終章は楽観的な見通しに終始する。「テスラは平均的な乗用車よりやや割高だがもはやニッチな存在ではない。EVを100万台走らせるといったオバマの目標はまもなく達成されるだろう。」「アメリカはきっと勝てる。」どろどろのバッテリーガイの描写はよく書けているが、電池の未来はまだまだ先にありそうだ。
3投稿日: 2016.05.19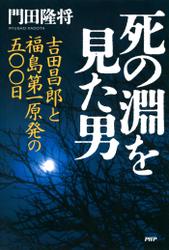
死の淵を見た男
門田隆将
PHP研究所
吉田昌郎さんへの感謝を込めて。
主人公は吉田氏だけではなくいわゆるFUKUSHIMA50と言われる人たち。東電本社はともかく現場の人たちは限られた条件の中で出来ることはした。よくあの状況の中で自発的に必要な判断を出来たと思う。 一例に挙げると福一を最悪の事故から救ったのは津波と全電源喪失直後に1号炉に冷却ラインを作り消防車の応援を呼んでいたことだった。事故直後の報道ではわからなかったが吉田所長の最悪の想定はチェルノブイリの10倍の規模の放射能漏れであり、班目氏はさらに福島第二と東海原発への連鎖まで想定していた。彼らは専門家でありその想定は重い。しかし、全電源喪失については防げる事故でもあったのが残念だ。 一号、三号が爆発した3月15日の明け方席に戻った吉田所長はゆらりと立ち上がり、机と椅子の間に胡座をかき目を閉じて座り込んだ。その時周囲の人間はプラントの「最期の時」を感じたのだが、吉田は腹を決めている。「私はあの時、自分と一緒に”死んでくれる”人間の顔を思い浮かべていたんです」「やっぱり、一緒に若い時からやってきた自分と同じような年嵩の連中の顔が、次々と浮かんで来てね。頭の中では、死なしたらかわいそうだ、と一方では思っているんですが、だけど、どうしようねぇよなと。ここまできたら、水を入れ続けるしかねぇんだから。最期はもう、(生きることを)諦めてもらうしかねぇのかなと、そんなことをずっと頭の中で考えていました」 その吉田にテレビ会議で管が言う。「事故の被害は甚大だ。このままでは日本国は滅亡だ。撤退などあり得ない! 命がけでやれ」「撤退したら、東電は百パーセントつぶれる。逃げてみたって逃げ切れないぞ!」 逃げる?誰に対して言ってるんだ。いったい誰が逃げると言うのか。(なに言ってんだ、こいつ) 厳しい批判を受けた中では班目氏はどうやら限られた情報の中で想定される事態を把握していたようだ。少なくとも官邸に対しての助言は間違ってはいない。しかし、どうしようもなく当事者意識が無く官邸が自分の言うことを理解しなければどうなるか薄々わかっていながら怒れる管に何も言えないでいた。伝わらなければ正しいことを言っても意味が無い。 最終段階では出来ることはないとわかっていても残ろうとした若者もいた。残ってくれると信じていたが退避したものもいた(彼らを責めるのは筋違いだが)。そして新潟から応援に来てそのまま残った協力業者もいた。一旦退避してから戻って来たものも多い。「ヤクザと原発」によれば協力業者の中には必ずしも使命感だけで残ったのではなく、その場のノリで残ったものもいる。それもこれも含めて彼らに救われたんだろうと思う。 個人的には今でも使える原発は使うべきだと思っています。例えば原発安全神話と温暖化は怖くないというのは対象が変わっただけで構造的には変わらないし、石炭は私の理解では原発以上に明らかに健康や安全に対してマイナスだし(例え高効率の発電が出来、PM2.5が解決できたとしても採掘事故の問題は残る)、単純に燃料費が上がるという経済的な損失も人によっては直接健康や安全に危害を及ぼす。それでも原発を無くしたいと言う素直な感覚は理解できるし、それを否定する気はない。いろんな問題をイノベーションが解決するかもしれないがまだ時間はかかるし、その上で何を選択するかということだろう。今後日本で新しい原発が稼働できるとは思えないので当面は天然ガスに頼り再生可能エネルギーのイノベーションを待つというのは一つの答えだと思う。その間のトレードオフを理解した上で原発を止めるというのはそれも一つのもっともな選択だ。
0投稿日: 2016.05.18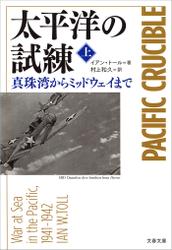
太平洋の試練 真珠湾からミッドウェイまで(上)
イアン・トール,村上和久・訳
文藝春秋
禍福はあざなえる縄のごとし。そして、奢れる平家は久しからず・・・。
帯には日本が戦争に勝っていた180日間と有るが、ウォールストリート・ジャーナルの紹介文は我々が負け犬だったときだそうだ。日米戦争を両海軍からの視点で書いた三部作の1作目は真珠湾からミッドウェイまで、上巻は負け続けた米海軍がマーシャル諸島で初めて一矢を報いるところで終わる。 アルフレッド・マハン。本人にその気が有ったかどうかは知らないが地政学のシーパワー理論の創始者になっている。マハンは歴史家で海洋戦略の大家であった。その思想は大艦巨砲主義と集中の鉄則、そして一度の決定的な海戦による敵艦隊の殲滅で有る。米海軍も日本海軍もマハンの信奉者であったのだが真珠湾攻撃により主力戦艦部隊を失った米海軍はやむなく空母機動部隊が太平洋艦隊の主力となる。 日本海軍がマハンに傾倒した理由はよく分かる。あまりにも成功した日露戦争でバルチック艦隊を破った日本海海戦がこのマハンの教義にぴったり当てはまるからだ。しかしポーツマス条約では賠償金は無く、樺太の併合も半分だけと知った国民は激怒する。日本政府が借金をして戦争をしており資金的には戦争継続能力は無かった事は知らされてなかったのだ。新聞に煽られた国民は戦争継続を支持しており、この空気は第二次大戦まで続く。軍部の独走とばかりは言えなさそうだ。一方のアメリカは流入の続く日本移民に対し反日感情が増していた。カルフォルニアで拡がる日本移民差別にも拘らず海軍の増強に反対する態度はローズヴェルト大統領をいらだたせた。そして開戦前夜太平洋艦隊は皮肉にもマハンの教義に従い、真珠湾に二列にきちんと並んで停泊していた。 連合艦隊司令長官山本五十六は軍縮交渉で海軍の代表をしばしば務めた事も有り、ハーヴァード留学中はアメリカを見て回りその経済基盤と軍事的潜在力に敬意を抱いていた。彼はかつてこう言っている。「デトロイトの自動車工場とテキサスの油田を見ただけでも、日本の国力で、アメリカ相手の戦争も、建艦競争も、やり抜けるものではない。」山本は軍縮条約を支持しナチス・ドイツとの同盟放棄と和平を政府に訴え続けていた。太平洋の戦争はマハン流の決戦ではなく消耗戦になることを見越していたのだ。日本の勝機について近衛から直に聞かれた彼はこう答えている。「やれといわれれば、最初の六ヶ月か一年はアメリカさんを相手に大暴れしてみせますが、二年、三年となると、どうなるかまったく自信は持てません。」 真珠湾攻撃は大艦巨砲主義の決戦思想から外れる所から生まれた。戦術的には奇襲を成功させる事と浅い湾内で使える魚雷の開発が鍵になっていた。山本は攻撃前の宣戦布告に拘っており攻撃前に文書を国務省に渡すとの確約を得ていたのだが、ワシントンの大使館が暗号解読に手間取り宣戦布告が無いままの奇襲攻撃となったと言う資料が残っている。 真珠湾奇襲についてはアメリカ側もいくつかの兆候は掴んでいたらしい。ただこの後もしばしば現れるように艦隊発見の報告は玉石混淆で正確な情報とは言えず、何よりアメリカは日本海軍をなめていた。奇襲攻撃そのものは史上最大の成果を上げたと言っていいだろう。海軍は1999名の戦死者と710名の負傷者をだし、戦艦8隻を含む約30万tの艦船が戦闘不能になった。188機の航空機がほとんど地上で撃破された。しかし日本軍は修理工場をたたき忘れ戦艦6隻は修理され戦列に復帰することになる。そして450万バレルの燃料はそのまま残った。また空母エンタープライズは帰投中で攻撃を避ける事ができた。 アメリカと同じくイギリスも日本軍をなめていた。すぐに撃退できると考えたチャーチルはアメリカを対独戦に引き込めると喜んだのもつかの間マレー半島から引き上げることになる。イギリスの最新鋭の旗艦プリンス・オブ・ウェールズが完全な戦闘態勢で航行中に日本の航空機部隊に沈められたことはマハンの教義を書き換え戦艦の役割は決戦ではなく陸上攻撃用の艦砲射撃と空母を守るためのハリネズミとなる。チャーチルはアメリカ議会を籠絡し先ずドイツをたたく方針を確認させる。一方アメリカの合衆国艦隊司令長官キングは太平洋の最終防衛戦をハワイとオーストラリアにおく。ミッドウエイからハワイと本土の海上交通路の防衛はそれにつぐ優先事項だった。ワシントンではまだ認められてなかったがフィリピン、マレー半島と東インドの陥落、太平洋に残る米英欄の連合艦隊の崩壊とアメリカのアジア艦隊の全滅までキングは受け入れていた。ヨーロッパ優先の方針の元でアメリカーブリティッシューダッチーオーストラリア連合軍は発足しイギリスの指揮下に入ることになる。この試みは後に国連の多国籍軍に発展するのだがこの時は機能しなかった。それでも日独伊が同盟と言いながらバラバラだったのに対し戦時生産での意思統一は果たした。
0投稿日: 2016.05.18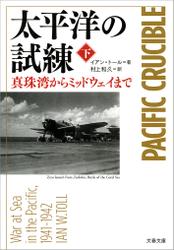
太平洋の試練 真珠湾からミッドウェイまで(下)
イアン・トール,村上和久・訳
文藝春秋
珊瑚海からミッドウェイへと続く布石
下巻に入っても日本軍の侵攻は止まらずABDA司令部は崩壊する。アメリカはインド洋はイギリス軍太平洋はアメリカ軍が受け持つ事を提案し英連邦のカナダ、オーストラリア、ニュージーランドをアメリカの影響下に置く事をチャーチルは不本意ながらも受け入れた。キング提督はヨーロッパに向けるはずだった戦力を太平洋に割りふり太平洋艦隊司令長官のニミッツと南西太平洋地域司令長官マッカーサーに率いさせた。 戦争開始4ヶ月後日本艦隊は事実上無傷で国民は浮かれていた。しかし山本五十六は休戦の可能性を妨げる勝ち誇ったプロパガンダー「国内の軽薄なる騒ぎ」ーを忌み嫌っていた。事実日本軍はアメリカ軍はたいした事が無いとなめはじめあまりにも早く侵攻が進んだために次の計画は立てられていなかった。日本としては消耗戦は避け連合国に壊滅的な打撃を与え1942年末までに講和を求めざるを得ないようにする方法を見つけなければならなかった。海軍の一部はオーストラリアやインド攻略を提案したが陸軍は大陸から大規模な部隊を動かす全ての案に反対した。陸軍はドイツがロシアを破った際にシベリア侵攻できることを目論んでいたからだ。陸軍は米軍の海上交通路を遮断するポートモレスビー攻略を主張する。一方海軍はオーストラリアの孤立化には同意し、ニューカレドニアからフィジーまでを占領することを提案する。ここで山本五十六はミッドウェイ攻略を主張する。この本当の目的はアメリカの空母部隊をおびき寄せ撃破する事だった。4月16日大本営は次の3ヶ月の目標の順序を説明した。5月ポートモレスビー占領、6月ミッドウェイとアリューシャン列島占領、7月ニューカレドニアとフィジーを占領。 4月18日アメリカはB−25による帝都攻撃を実行した。空母に着陸はできないがなんとか発艦はできる。飛んでしまえば中国におりる事はできるというギャンブルにも似た作戦だった。空母に気づいた漁船はB−25には気がつかず日本軍はまだ米空母が攻撃距離に入るには時間が有ると見積もった、B−25を発見した哨戒艇の報告も誤報と片付けられている。進入機を発見した目撃者は敵機と気がつかず手を振って迎えている。山本はミッドウェイはアメリカの脅威の要で有るとし6月1週にミッドウェイ攻撃が実施されることになる。 アメリカ軍は着々と反攻の準備を整えていく。ひとつがハワイの暗号解読部隊でミッドウェイ海戦における日本の機動部隊の情報はかなり正確に掴んでいくことになる。もう一つは新たなレーダーの開発で日本軍より索敵範囲が広くなった、そしてゼロ戦対策は単独での空戦を避け2機がセットで1機のゼロ戦に対峙する。 日本軍のポートモレスビー攻略では珊瑚海で史上初めて空母同士の海戦が行われた。空母レキシントンを沈め、給油艦と駆逐艦も沈め空母ヨークタウンに損害を与えた。軽空母翔鳳と軽巡洋艦1隻、駆逐艦2隻、輸送船1隻と砲艦4隻を沈められた。損害は米軍の方が大きかったように見えるが航空機とパイロットは日本の被害の方が大きかった。珊瑚海海戦は戦術的には日本の勝利、戦略的にはアメリカの勝利と言う昔からの評決に著者のイアン・トールは異を唱える。珊瑚海からミッドウェイを一連の戦闘と見た場合、 ヨークタウンが修理されミッドウェイ海戦に参加したのに対し、空母翔鶴は損傷し瑞鶴は艦載機を失いミッドウェイ海戦には参加していない。そして元々の目標のポートモレスビー攻略にも失敗している。戦術的にもアメリカの勝利だったというのがその評価だ。 ハワイの暗号解読部隊は6月3日のアリューシャン列島、4日のミッドウェイ攻撃を読み取り戦力はミッドウェイに集中させていた。ヨークタウンはそれに合わせわずか3日でとりあえず動かせる程度に修理された、つぎはぎを当てたと言った方がいいかもしれないがそれで充分だった。ミッドウェイ海戦もアメリカ軍が洗練されていたわけではない。いくつものドタバタ劇が有ったが重要な点は先制攻撃を仕掛けたのはアメリカ軍で爆撃や雷撃は外れ続けたがやがて当たり、日本の空母に損害を与えるたびに戦力の均衡は傾いていった。 何が勝敗を分けたのか?アメリカ軍にいくつもの幸運が有ったのは確かだが、持てる航空戦力を結集し、先に敵艦隊を見つけ、先制攻撃を行った。そしてアリューシャン列島の攻撃には目もくれなかった。 この本には多くの実際に戦闘に参加した日米両軍や市井の一般人など様々な人の見方で当時の出来事が綴られている。主人公と言えるのは山本五十六やニミッツやスプルーアンスであり暗号を解読したロシュフォートだが同じくらい名も無き人々の様子を描いている。
0投稿日: 2016.05.18
okadataさんのレビュー
いいね!された数197
