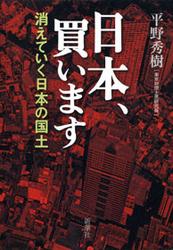
日本、買います―消えていく日本の国土―
平野秀樹
新潮社
大阪の92%、東京の79%は地籍が確定していない。
①日本は地籍と言う基盤インフラが未整備な中、②利用規制が緩々であるにもかかわらず、③当事者間だけですべての売買行為が完結でき、④外資規制も皆無である。 第4章のまとめにこう有るが本書の内容はこれでほぼ言い表されている。 提言としては安全保障上重要な土地は区域設定をし、利用規制、売買規制、国有化を行う。地籍を明確にするとともに売買の事前届け出を義務づける。所有者が不明な資産については時効をもうけ一定期間で公有地にできるようにする。地方に関しては地域特性に応じて条例等の規制を設ける。 外国、特に中国の土地取得を合法的なものでありながらいたずらに問題視し、いかにも中国が侵略しようとしている様な書き方をしているのはいただけない。上にある様な制度をほっておいた方が問題なのは明らかであり、中国人からすれば自国では土地は買えない(工場50年、住居70年の借地権が買えるだけ)し場合によってはすぐ立ち退きに合うのに、すぐ隣に買いやすい国が有るなら買っておけと言うことだ。変なリゾート開発なんかはされたくないので利用制限をとっとと着けましょうよねえ。これは相手が日本人でも同じだが最近の日本はそんな元気無いからなあ。 今まで知らなかったが日本の土地法政は ①地籍(土地の境界、所有者の情報)が未だ5割しか確定しておらず、 ②売買届出や不動産登記が不備であり、 ③国境離島、防衛施設周辺など、安全保障上重要なエリアの土地取引や開発に関する規制が不十分である。一方で、 ④民放では土地の「取得時効」等が保証され、 ⑤個人の土地所有権が現象的には行政に対抗し得るほど強い。 だそうだ。 地籍の問題は根が深い。大都市圏は特にそうで大阪の92%、東京の79%は地籍が確定していない。どういうことかと言うと登記上の公図がいい加減で漫画にしか見えないものが混ざっており、実際の地図と場所がずれていたり、面積が違っていたりするのだそうだ。一番でたらめな所は形も全然違っている。2004年の新潟県中越地震の際には地籍調査の完了区域の道路復興は2ヶ月で終了したが未了の地区は復興に1年を要した。境界がはっきりしないと手が付けられないのだ。 どうも太閤検地の昔から測量の際に巻き尺を目一杯ひっぱり登記上の面積を減らして年貢(固定資産税)を少なくする手が使われたのが始まりのようだ。また終戦後はどさくさ紛れに何でもありだったようだし。 日向では小学校の校庭にみかんの木を植えた男がいた。どうもこの男の祖先が小学校の拡張の際に畑を売ったのに登記を変更せず、庁舎が火事にあって契約書が消失。日向市役所は気がつかずにこの男に固定資産税を払わせ続けていた。裁判になったが20年以上の占有が強く男の負けだった。 大阪では「大たこ」裁判があった。時効取得により占拠していた屋台の有る土地は自分のものと訴えを起こしたがこれは「大たこ」の負け。逆に不法占拠の訴えを起こされ撤退することになった。永らく不法占拠を認めて営業許可を出していたのも大阪市なのでどっちもどっちである。 地籍は民事が絡むので難儀な話だが利用規制なんか地方条例でさくっと縛ってしまえば簡単に住むだろうと思うのは単純すぎるのだろうか?
0投稿日: 2014.01.01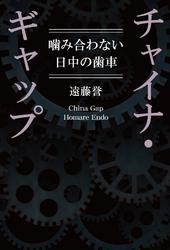
チャイナ・ギャップ
遠藤誉
朝日新聞出版
蒋介石は沖縄割譲を断わっていた
本書の目玉は新華社が報じたカイロ密談でルーズベルトが蒋介石に沖縄を割譲する提案に対し蒋が断った事実をアメリカ公文書館のHPから見つけたことだ。 尖閣諸島の帰属について例えば孫崎享氏はポツダム宣言受諾により尖閣諸島は中国に帰す地域に含まれる可能性が有るとしているが、このカイロ密談の際に沖縄に尖閣が含まれているというのが日米共通認識であり、蒋介石が尖閣は中国固有の領土と主張していれば間違いなくそうなっていた。沖縄が中国領にならなかったのは幸運だろう、米軍がいかに問題が多くても大躍進〜文革時代に中国の一部になっているよりは遥かにましだ。 題名はチャイナ・ギャップでテーマは何が原因で日中関係がこれほど悪くなってしまったか。例えば昨年のデモの際にも「ガス抜き」などと言う人がいるが遠藤氏はそう言う見方では中国を理解できないと言う。第一次世界大戦で日本、中華民国は共に連合国側であったが終戦の結果、日本は中国に対し対華21か条の要求をつきつけ16か条を飲ませた。この結果起き上がったのが五四運動でベルサイユ条約調印拒否に至りその後共産党が生まれるきっかけになっている。毎年五月四日は抗日デモが起こりやすいのはこういう理由だ。 共産党革命やその後の文革は暴力の肯定という面があり、江沢民が進めた反日教育もあり反日デモが許されやすい土壌が出来上がってしまっている。一方で半日デモはすぐに反政府デモに変わりかねないので暴走しないように押さえつけている面も有る。遠藤氏が「ガス抜き」に反応する理由はこういうことらしい。 江沢民がここまで反日に走った理由は父親が日本の傀儡政権の官吏だったからだ。文革は家族がブルジョアだったり国民党に協力していたなどの理由で「反革命的」としてつるし上げに会う時代だった。北京閥との権力闘争で父親のことを指摘されたため反日を表に出して自分の権力基盤を守ろうとしたのがその後の反日教育につながってしまう。その江沢民もどうやらひっそり引退らしいが習李体制になってもすぐには対日方針は変わらないだろうと分析している。 この本の上梓は2/28だが3/5から始まる全人代でチャイナ・セブンから外れた李源潮が国家副主席になると予想して当てている。この辺りの分析はさすが。チャイナシリーズはこれで一段落だというのが少し残念。チャイナ・ジャッジ、チャイナ・ギャップの連作には遠藤氏の執念を感じた。
2投稿日: 2014.01.01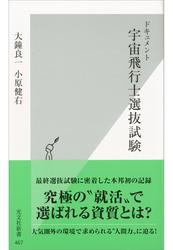
ドキュメント 宇宙飛行士選抜試験
大鐘良一,小原健右
光文社新書
リアル宇宙兄弟の世界
2008年2月JAXAが10年ぶりに宇宙飛行士を募集、2008年6月から始まる選抜試験をNHKが密着取材し2009年3月にNHKスペシャル「宇宙飛行士はこうして生まれた ~密着・最終選抜試験~」が放送された。放送直後は他のマスコミからの非難轟々だったらしい。ちなみに宇宙兄弟の連載は2008年1月から2009年3月には第五巻が発刊されており最終選抜試験の閉鎖環境は連載と実際の試験は同時進行だったようだ。 応募者は963名、書類選抜ならびに健康診断、英語の筆記、ヒヤリング試験合格者は230名、一次選抜の一般教養や科学の専門知識の試験で48名(JAXA合格者数発表は50名)にしぼられた。二次選抜の面接では宇宙飛行士になぜなりたいのか、あなたは宴会の幹事をしたことがありますかなどの質問を含め一人あたり40分の試験で最終選抜に進む男性9名、女性1名が選ばれた。 最終選抜候補者を選ぶ選考基準は国際宇宙ステーションの船長になれること。若田光一さんが国際的に高い評価を得たことから将来のリーダー候補を意識した選抜となった。最終候補者の年齢は30~39、職業はパイロット4名、医師2名、研究者1名と技術系の民間会社員が3名。 候補者の一人白壁弘次氏はキムタクのドラマGOOD LUCKのモデルの一人でもあり自然とリーダーシップをとる辺りは宇宙兄弟の真壁ケンジのモデルかと思ってしまう。 宇宙飛行士に要求されるのは健康、語学力はもとより閉鎖環境でのストレス耐性、リーダーシップとフォロワーシップ、チームを盛り上げるユーモアそして危機を乗り越える力。最終試験後半で面接を主導したNASAのリンゼー氏は「我々は、技術的な経験もさることながら、チームとして活動できる能力、そして誰とでも仲良くなれる資質、また、必要な時は指導力を発揮し、場合によっては誰かに従う能力のある人を探しています。その力がある人物なのかを見極めるためには、個々の候補者の”本質”を理解しなければなりません。誰にも人生の物語がある。その物語を聞くことで、候補者が成長してきた背景を理解し、また、どのような選択をしてきたのかを質問することで、その人の”本質”を理解することができます」と説明している。 これをよく表しているのが候補者の一人安竹氏に対する面接のエピソード。「ヨウヘイ、なぜ君は今ここにいるんだい?」安竹が1冊のノートを出してした話は面接官すべてを引き込んだ。高校生の頃恩師が持ち帰ったNASAの英語のビデオをヒヤリングして翻訳しその全てをまとめたノートがこれだ。「たぶん君は、この部屋にいるだれよりもスペースシャトルに詳しいよ」面接室は、大きな笑いにつつまれた。 合格者は最終試験で危機に見舞われた際のリーダーシップとNASAでは思わぬ不得手な実技を落ち着いて処理した油井、常に冷静で油井のリーダーシップに対し必要なときには意見を言うフォロワーシップや意外なユーモアを見せた大西、そして目立たぬながら全ての要素で60点をキープした金井。油井は第44次/45次ISSの長期滞在クルーにフライトエンジニアとして任命された。 http://www.jaxa.jp/press/2012/10/20121005_yui_j.html
2投稿日: 2014.01.01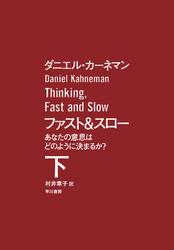
ファスト&スロー (下)
ダニエル・カーネマン,村井章子
ハヤカワ・ノンフィクション
後半もやはり紹介しきれない
プロスペクト理論 問題1 あなたはどちらを選びますか? 確実に九〇〇ドルもらえる。 または九〇%の確率で一〇〇〇ドルもらえる。 問題2 あなたはどちらを選びますか? 確実に九〇〇ドル失う。 または九〇%の確率で一〇〇〇ドル失う。 問題3 あなたは現在の富に上乗せして一〇〇〇ドルもらったうえで、次のどちらかを選ぶように言われました。 五〇%の確率で一〇〇〇ドルもらう、または確実に五〇〇ドルもらう。 問題4 あなたは現在の富に上乗せして二〇〇〇ドルもらったうえで、次のどちらかを選ぶように言われました。 五〇%の確率で一〇〇〇ドル失う、または確実に五〇〇ドル失う。 問題3と4は選択の前後の状態は同じだが、最初にもらえる額が参照点として折り込まれるので損得に関わる感情が選択に影響する。 損失回避は、二つの動機の相対的な強さを表すと言うこともできる。すなわち、利得を手に入れようという動機よりも、損失を避けようとする動機のほうが強いのである。このとき損得の参照点は現状であることが多いが、ときには将来の目標が参照点になることもある。 A 六一%の確率で五二万ドルもらえる、または、六三%の確率で五〇万ドルもらえる。 B 九八%の確率で五二万ドルもらえる、または、一〇〇%の確率で五〇万ドルもらえる。 期待値はどちらも先の選択が高いが、問題Bは確実にもらえる事から多くの人が100%を選ぶ。ノーベル賞経済学者も同じだった。ー また、多くの人が得をする場面ではリスク回避的に、損をする場面ではリスク追求的になることが知られている。 サンクコストの呪縛(元の題は錯誤だが、呪縛の方が感じが出る) ある会社があるプロジェクトにすでに五〇〇〇万ドル注ぎ込んでいるとしよう。このプロジェクトは計画通りに進んでおらず、最終的なリターンも当初予想されたほどには大きくないことがわかってきた。このプロジェクトを進行させるには、あと六〇〇〇万ドルの追加投資が必要である。しかしその一方で、その六〇〇〇万ドルを新規プロジェクトに投じるという案もある。こちらのほうが予想リターンははるかに大きい。さあ、この会社はどうするべきか。
1投稿日: 2014.01.01
ファスト&スロー (上)
ダニエル・カーネマン,村井章子
ハヤカワ・ノンフィクション
2000文字では紹介しきれない
著者はノーベル経済学賞をとった心理学者。似た様なテーマの選択の科学、錯覚の科学も良かったが1冊だけ読むならこちらがおすすめです。ただしボリュームはあるけど。 まずはシステム1(fast)とシステム2(slow)という本書の主人公?の紹介から。 システム1は自動で働き直感的な判断を支配する。話をしながら歩いても前から来た人とぶつからないのも、人の顔をぱっと見て感情を読み取るのも簡単な計算に即答するのもシステム1。難しいことができないと言うのではなく訓練によって高度な技能もシステム1が支配できるようになる。例えば羽生さんが一目で指し手が見えたり、イチローが瞬間的に打球の行方を判断したりといったこともできる。ただしシステム1は注意深くなく簡単な結論に飛びつきがちである。自信満々の政治家は頼もしく見えるが統計的には自信たっぷりの態度と成果にはなんら関係がない。 システム2は注意力を要する雑音の中で特定の人の声を聞き分ける、2桁のかけ算をするなど。例えば歩きながら1桁のかけ算は問題なくできる。しかし多くの人は歩きながら2桁のかけ算をしようとするとリソースがシステム2に集中するため足が止まってしまう。難しいことをするかどうかではなく集中力を振り向けることに関連する。面白いことにシステム2が働くときには瞳孔が開くらしい。 人の話を注意して聞いているか、聞き流してるかは目を見りゃわかると言うことですな。しかしシステム2は怠け者で疲れてくるとシステム1の直感的な答えを受け入れるようになる。 問題1 バットとボールは合わせて1ドル10セントです。 バットはボールより1ドル高いです。 ではボールはいくらでしょう。 直感的に浮かんだ答えが間違っていたとしたらそれはシステム2が怠けてシステム1に判断を任せてしまったからだ。 認知容易性 中身が全く同じだとしても手書きで字が汚かったり、フォントが小さく改行もなくて読みにくかったりすると印象が悪く、中身自体の評価を落とされてしまう。見た目の悪さがシステム2を呼び起こしてしまうようだ。 単純接触効果 繰り返し聞かされた言葉にはなんとなく好意を持ってしまう。コマーシャルや選挙演説もこれを狙っている。好きなコマーシャルを見て笑顔になるとシステム1の働きで何となく商品に好意を覚えるが、名前を連呼するだけのおっさんの話は無意識にしかめ面になり、きちんとシステム2が監視するので好意は持てないということか。ざまあみろ。 結論に飛びつくマシン 本文中で時々実験をさせられる。 ABC,ANN aproached the bank,121314と3つの文字が並んでおり、さあどんな仕掛けだろうと見ていたが気がつかなかった。 Bと13が全く同じ字だったのだ。システム1は自動連想でBと13をそれぞれ認識してしまった。 アンカリング効果 未知の数字を見積もる時にある数字が提示されるとその数字がアンカー(いかり)となって見積もり結果に影響を与える。昔タイに行った時にパッチもんの時計を買ったことがある。3000バーツと言うので一声300バーツと言ったらあっさりOK。ふっかけられるのは分かっているが3000がアンカーで、1/10と見積もったわけだ。ではスタートが5000や1000だったらいくらと答えたのだろうか。あるいは100や30000だったら?多分それ以上相手にしなかったと思うあまりにも外れた数字はアンカーにならない。 じゃあどうやって交渉するのか? 「そこで私は交渉術のクラスで、次のように教えている。相手が途方もない値段を吹っかけてきたと感じたら、同じように途方もない安値で応じてはだめだ。値段の差が大きすぎて、交渉で歩み寄るのは難しい。それよりも効果的なのは、大げさに文句を言い、憤然と席を立つか、そうする素振りをすることだ。そうやって、そんな数字をもとにして交渉を続ける気はさらさらないことを、自分にも相手にもはっきりと示す。」
1投稿日: 2014.01.01
野茂英雄 日米の野球をどう変えたか
ロバート・ホワイティング,松井みどり
PHP新書
野茂に国民栄誉賞が与えられる日は来るのか
松井に国民栄誉賞が与えられた。ワールドシリーズのMVPを取りNYの優勝パレードでは史上初めてニューヨーカーが日本人に声援を送った。一般のアメリカ人に最も愛された日本人かもしれない。国民栄誉賞いいんじゃないですか。 では野茂には国民栄誉賞は与えられる日が来るのか?本書の最終章では野茂が野球殿堂入りするかどうかに1章裂かれている。野茂がいなければ後に続く日本人大リーガーの出現はもっと遅れ、WBCも無かったかもしれない。94年のストライキとロックアウトは野球離れをすすませ、バブル期の日本のイメージはロックフェラーセンターやコロンビアの買収など貿易摩擦もあり一般的なアメリカ人の対日感情は必ずしもよくない。野茂が大リーグに行ったのはそういうころだ。 当時日本プロ野球から大リーグに挑戦するには相手球団の許可が必要というのが常識だったが日本で任意引退した選手がアメリカで契約することには制限が無いと言う抜け穴が有った。94年肩の故障で8勝7敗に終わった野茂は契約更改で20億、6年契約を申し込む。却下したフロントに任意引退を告げ大リーグ挑戦を表明する。マスコミや球界関係者は野茂を批判したが野茂は揺るがなかった。その後の活躍はNOMOマニアを生み出した。 大リーグ挑戦後野茂は2度の復活を果たしている。98年以降成績が低迷し球団を渡り歩いた後BOSで2度目のノーヒッターを達成、02−03は各16勝を挙げている。04、05と低迷しマイナーやベネズエラリーグに行った後08年にKCのテストを受ける。キャンプ当初はストレートが130km以下、39才で体重はKC担当のレポーターよりも重く世間は失笑した。しかし後半調子を上げ開幕時には25人枠に入った。残念ながら成績は残せなかったが著者のホワイティングはこの最後の復活をもっとも賞賛すべき業績とたたえている。 野茂は無口でマスコミには無愛想、選手同士ともあまり話さなかったようだがインタビュー内容からは大リーグに適応しようと努力し、コーチたちからも評価されている様子がうかがえる。例えば復帰したLADで前半線防御率が4.00まで落ち込んだ際にはコーチのジム・コルボーンが野茂に「ツーストライクをとったあとに、続けてストライクを投げてみないか」「君は今まで、コーナーぎりぎりのアウトサイドに投げていたけど、それを変えてみるんだ」と助言され野茂はそういうやり方は自分の好みではないが、お望みならやってみてもいいと答えた。その年最終的には16勝6敗防御率3.39と好成績を挙げている。 野茂の通算奪三振率は9.28(MLBでは8.74)、1イニング1三振以上の数字であり大リーグを通じても2000イニング以上投げて9を上回っているのはノーラン・ライアン、ランディ・ジョンソン、ペドロ・マルチネス、サンディ・コーファックスの4人のみ。両リーグでノーヒッターを達成したのも大リーグ全体で5人。そして12年間で323試合に登板し内先発は318試合、7年間先発ローテーションを守り3回の開幕そして95年のオールスターの先発をつとめた。
0投稿日: 2014.01.01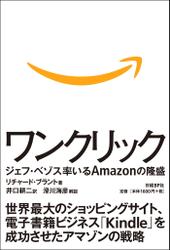
ワンクリック
リチャード・ブラント
日経BP
ベゾスも時間があれば本屋を利用する
ジェフ・ベゾス率いるアマゾンはどうやって生まれたのか。比較されるのはスティーブ・ジョブズだろうがベゾスはジョブズほど不思議な人ではなさそうだ。ジョブズの情熱がアートと技術の交差点で飛び抜けたものを作るというのに対し、ベゾスからはそこまでの執着は感じない。もちろんアマゾンの焦点は顧客へのサービスという点に集約されるのだが。 ベゾスの印象は非常に優秀な人、元々技術者でありながら早くから起業することを考えていたようだし、インターネット取引で書店という所に目を付け、シェアを取れば後から利益はついてくると拡大路線にひた走る。恋人をさがすのにもディールチャート(取引条件を予めリストアップしたもの)を使い、ロス・ペローの様な女性を捜したのは巧く機能しなかったようだが、インターネットの可能性に気づき同じくディールフローチャートを用いて書店を選んだのは当たった。また当初は地域は拡大せず電子取引のシェアを上げることに集中しあっという間に世界最大の書店を作り上げた。よく知られるワンクリック特許もアマゾン=ベゾスの特徴をよく表しているが、正直な所これを特許と認めるのはどうかしてる(利用者としては素晴らしいデザインだが)と思う。 ベゾスは当初利益に焦点を当てなかったが、一方で顧客にどう見られるかと言う評判は凄く気にしている。自分たちのためには金を使わず顧客サービスに使っていると思わせることだ。また従業員も一部を除くとアマゾンで働くことに対するロイヤリティが非常に高い。時給10ドルちょっとのために推薦状3枚、論文2通にSATの点数と大学の成績証明を提出させる。そういうアマゾンカルトに入信できない人は早々に退社するらしい。 アマゾンは調べるのには便利なのだが個人的には本屋が好きなので共存してくれればいいね。ちなみにベゾスも時間がある時は本屋を利用すると言っている。
2投稿日: 2014.01.01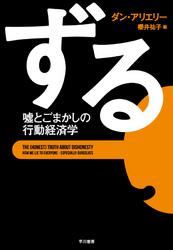
ずる 嘘とごまかしの行動経済学
ダン・アリエリー,櫻井祐子
単行本
ずるをする際に最初にすることは自分をだますこと
ダニエル・カーネマンのファスト&スローが認知、判断など広く扱っているのに対しこの本で扱うのは「ずる」の心理学、そうは言っても重なる部分はかなり有ります。 どういうときに人はずるをするのか、アメリカのゴルファー1万2千人の調査ではライの改善について「平均的なゴルファーがボールを10センチ動かすと非常に有利になる場合動かす可能性はどのくらいか?」聞いた所、クラブを使って動かす場合23%、ボールを蹴る場合14%、手で動かす10%と言う回答だった。(日本のプライベートコンペだとそもそもリプレースOKとしている場合が多いので質問自体が成り立たないかも・・・)手を使うと心理的抵抗が大きいというわけである。また、マリガンルール(打ち直しOK、一説によるとマリガン大統領からきている)の場合平均的なゴルファーがスタートホールでのマリガンは40%、9番ホールでのマリガンは15%が打つと言う回答だった。そもそもわざわざ平均的な・・・と質問するのも意味がある、あなたはどうしますかだと自分はフェアだと信じたがる人はライの改善はしないし、マリガンもしない。平均的な他人は自分より不誠実だというのは本当だろうか? ずるをする際に最初にすることは自分をだますことなのだ。例えばダイエット中なのに少し食べ過ぎた際どうせ今日はだめだから自分を許して食べよう。朝からがんばればいいとか。自分が受け入れやすい言い訳を作り自分を納得させるのと同じ心理が働いているのだ。例えばニセモノブランド品を身につけるだけで不正行為(ちいさなずる)に対する抵抗は大きく下がる。みんなで渡れば怖くないというのもある。心理的な抵抗のハードルを下げるとずるに抵抗する力が弱まるのでずるは感染するものらしい。 ではずるを無くすためにいい方法はあるのか?これも以外と簡単な答えで例えば宣誓をする、署名をする、見張られていると思わせるなど。いろいろな申告書で署名を取るのはエビデンスを残すためだと思ってたが、署名すること自体に抑止効果がある。ただし、できれば申告前に正直に申告しますと署名をさせる方が効果が高い(心理的な抑制効果が働く)と言うのが著者の実験結果であった。この話は保険会社に進めたがどこにも採用されなかったらしい。道徳心を定期的にリセットする仕組みは宗教などにも取り込まれている。行動心理学関係の本はお勧めできるものが多い。
0投稿日: 2014.01.01
アグルーカの行方 129人全員死亡、フランクリン隊が見た北極
角幡唯介
集英社学芸単行本
北極圏1000km60日間 アグルーカの行方を探す冒険
北西航路探索の歴史は15世紀に始まった。当時スペインはアメリカ大陸に到達しマゼラン海峡を抑える一方でとポルトガルは喜望峰を抑えていた。中東経由でアジアに向かうには高い通行料を課せられロシアの北を回る北東航路とカナダの北を回る北西航路の探索が始まった。しかし結果は報われずカナダの毛皮貿易や捕鯨が副産物として流星を迎えた。スペインとポルトガルの国力が弱まり北西航路の重要性は弱まったがイギリスは国家事業として探索を続けそこで生まれた英雄がジョン・フランクリンだ。フランクリンは1819年から3年間のカナダ北岸探検でカヌーと橇と徒歩で8900Kmを踏破して生還し"The man who ate his boots"靴を食った男として不撓不屈のイギリスの象徴となった。そして1845年の北西航路探検で最新鋭の2隻の船を擁すも北極海の氷に2冬閉じ込められ、船を捨てて生還を目指すも129名が全滅し北西航路探索の最大の悲劇となった。一方で探検隊の一部はイヌイットの助けを借りて生還したと言う逸話が残っており、作家の角幡唯介は北極探検家荻田泰永とともにフランクリン隊が生還を目指した道をたどる旅にでた。北極圏1000km60日間を無補給で前半は重さ90Kmの橇を引き、後半はツンドラの湿地帯を歩きそして時には携帯ゴムボートで河をわたる過酷な探検の記録が本書だ。 2011年3月17日、スタートはコーンウォリス島のレゾリュートと言ってもカナダ北部の地理なぞ頭に入ってないのでグーグルマップの衛星写真を見ながら想像するのがお勧め。カナダ北部は多島海になっていて冬は氷で閉ざされるため歩いて渡ることが出来る。しかし平面な氷ではなく吹き溜まった雪が堅く凍り乱氷帯と言う所では高さ数mの氷の固まりや氷山が流されて出来た高さ2〜30mの氷の丘が行く手を阻み氷の壁を乗り越えるために橇を押し上げ一番ひどい所では1時間にわずか50mしか進めない。また零下40度の世界では体調が狂い出発わずか2日目に角幡は寝小便をしてしまう。低温化での行動ではカロリー消費がすさましく、1日5千Kカロリーをとっても次第に痩せていく。体温を保つ基礎代謝だけでも猛烈な消費だ。 動物との遭遇では麝香牛を撃ち食べた話が印象的だ。撃った牛は出産直後でようやく立ち上がったばかりの親を亡くした子牛がビェーッ、ビェーッと絶叫しながら何度も突進を繰り返してくる。食欲に勝てず撃ち殺したのだが罪悪感がこみ上げる一方、このままでは生き残れない子牛も撃ち殺すことにしている。他にも雷鳥を撃ったり、鵞鳥の卵をとったり80センチもあるレイクトラウトをとったりしているがこちらでは罪悪感を感じた様子が無いのはやはり牛の大きさと子牛がいたことだろうか。 最新に装備を備えているとは言え二人で同じ時期に踏破できたコースを129人のフランクリン隊が出来なかったのはなぜか。一番大きいのはフランクリン隊が船を捨て歩くことを想定していなかったため充分な防寒着を持たずまたイヌイットの知識を学ぼうとしなかったことだ。フランクリン隊は船を捨てるときでさえ銀の食器や陶器のティーカップなど北極では役に立たないものを持って移動していた。同時期の冒険家でアグルーカ(大股で歩く男)と呼ばれたジョン・レイはイヌイット式の毛皮の服と靴で全く同じ時期に同じ地域を歩き回っておりイヌイットの伝説の故郷に帰ったアグルーカは自分のことだと言っている。 作者の角幡はこの探検にGPSや衛星携帯電話を持っていってるのだが、特に携帯については後半の湿地帯行では置いていくなどつながった状態では自然に入り込めないと否定的だ。一方でGPSはコンパスの効かない極地での効果は絶大で、一日の移動距離をGPSで決めた通りにするなど依存してしまう部分も書かれている。そもそもフランクリン隊には十分な地図も無かった。軽量のゴムボート、防水服、熊よけスプレーやコンロそして当時恐ろしい病気だった壊血病を防ぐビタミンCなど通信が無くても現代文明にはつながっているので携帯やGPSだけを否定しても仕方ないと思うのだがこればかりは探検の目的そのものに関わるのだろうか。一方でフランクリン隊も当時の最新技術であった缶詰を持ち込んでいるのだが、この缶詰のハンダによる鉛中毒がフランクリン隊が数をへらした原因として上げられている。フランクリン隊が当時のイギリス文化を重視しイヌイット式を否定したために全滅したのに対し、現代文明を極地探検に持ち込むことを忌避しつつ助けられている角幡、そして人肉食に追い込まれながら全滅したフランクリン隊と罪悪感を覚えなが麝香牛を撃って食べ生還した角幡となかなか皮肉なものなのだ。
2投稿日: 2014.01.01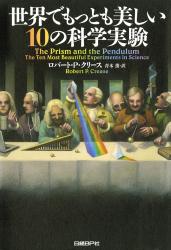
世界でもっとも美しい10の科学実験
ロバート・P・クリース,青木薫
日経BP
美しい実験」というのはぱっと見てきれいと言うのではなく、シンプルで、一目で結果が分かり理論の正しさを示すもの
フィジックス・ワールド 誌上のアンケートで世界で最も美しい科学実験に選ばれたのは二重スリット実験、リンク先のヴェガのオンラインプログラムで日立の研究者だった外村彰氏が英国王立協会で行った1994年の講演のビデオを見ることが出来る。(ちょうど30分の辺り) http://vega.org.uk/video/programme/66 電子が当たった場所が星のように光る点になり、次々とランダムに光が増えるのはプラネタリウムの様だが最後に現れるのは銀河ではなくスリットを波が通ることによりできる干渉縞。電子は一つ一つの粒子として検出されるのだが数多くの電子は波としての性質を見せる。干渉縞は波の重ね合わせなので一つの粒子で干渉するというのがピンと来ないのだが、時間をずらしても波の性質は変わらないので重ね合わせたのと同じ結果になるのか。この本で言う「美しい実験」というのはぱっと見てきれいと言うのではなく、シンプルで、一目で結果が分かり理論の正しさを示すものでしかも実験を構成する要素が無駄無く組み合わされているものだそうだ。訳者の青木薫さんは最初にこの本を読んだ際には自分こそが適任だと思い、後にはこの美しいに含まれる哲学のバックグラウンドを理解するために哲学者の旦那さんに質問しまくったとか。青木さんは上の光の干渉縞の写真を見て涙がこぼれたと言うが、それももの凄い感性だと思う。 他の実験は年代順に エラストテネスによる地球の外周の測定 ガリレオのピサの斜塔から重さの違う二つの物を落とすデモンストレーション 同じくガリレオの斜面を転がるボール ニュートンによる太陽光のプリズム分解 キャベンディッシュの地球の重さを量る実験 トマス・ヤングの光と言う波を見せるプリズム フーコーの振り子 地球の自転を見る ミリカンの油滴実験 電子の電荷が見える ラザフォードによる原子核の発見 地球をはかり、重力と重力加速度を目に見えるようにし、光の性質から量子力学の世界へ。 美しい実験結果を見せるためには精密で考え抜かれた実験技術が必要で、再現するのは簡単ではないものも多い。単純そうに見えるフーコーの振り子もすきま風の影響で逆に回ることも有ると言うのだ。ただ上のビデオを見るとこの本の内容については映像の方が合ってるのだと思う。それぞれの実験の背景の理論はちゃんと理解できるわけじゃないけど、実験自体は直感的にわかる部分もある。
1投稿日: 2014.01.01
okadataさんのレビュー
いいね!された数197
