
官僚の責任
古賀茂明
PHP新書
官僚を変える政治は選ばれるのか
前半は政治家と官僚のダメさ加減を攻撃、ちょっとしつこいが鬱憤が溜まってたんでしょう。 最終章で、ではどうすればという提言でここは大筋意見が会う。 既得権益の構造を破壊しろと言うのが根底に流れ、官僚が自力ではやれないので政治が介入しろと言う。 しかし、それも既存政党にはできんだろうということなので政界再編と選挙制度から変えないとできそうにないと思います。
2投稿日: 2014.01.01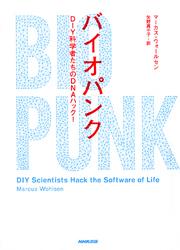
バイオパンク ―DIY科学者たちのDNAハック!
マーカス・ウォールセン,矢野真千子
NHK出版
イノベーションは必ず起こる
アップルのコンピューターはガレージから生まれ、リナックスはオープンソースと言う新しい取り組みでプログラムを進化させた。バイオテクノロジーと言うと閉ざされた世界というイメージだが、バイオハッカーはコンピューターとバイオテクノロジーは似ているという。DNA検査はガレージで出来るし、ヒトゲノムのような遺伝子情報もオープンソースにしたほうが解読が進み世界に貢献すると言う立場だ。 今では自分の遺伝子情報を調べたければ、キットを買って綿棒で口の中をこすりそれを送るだけで出来る。さらにはDNAを複製することはそれなりの専門知識があれば自宅ででき、ケイ・オールは中古のサーマルサイクラー(温度を上げたり下げたりを繰り返す装置、炊飯釜と大差ない)100ドルちょっととwebで注文したDNA断片で自分で遺伝子検査を行った。 遺伝子組み換え作物に関するエピソードではインドの農民がモンサントの足元をすくった話が面白い。Btコットンと言う害虫を寄せ付けない成分を作るようになった綿はインドでは禁止されたが、ある種子はBt遺伝子を含んでいた。この種子を売った会社、インド政府、モンサントそれぞれの言い分に関係なく農民たちはこの種子をさらに交配させ元々のBtコットンより安くBestコットンという名で売られ続けている。インドでは遺伝子は特許性がなく政府もなすがままに遺伝子組み換え綿を承認し、Bestコットンは農民たちの共有財産となった。 バイオテクノロジーに対しては強硬に反対する人も多い。この理由は宗教的なものと、知らないものは怖いと言う心理、また新しい技術に対して慎重な立場などが有りそれぞれの言い分も理解はできる。しかしイノベーションは必ず起こるし一度起こればインドの農民同様成果を享受するだろう
1投稿日: 2014.01.01
ガリア戦記
カエサル,近山金次
岩波文庫
固有名詞がちょっとつらい
ローマ人の物語の塩野七生さん絶讃のガリア戦記を読んで見たのだがそこまで熱中出来なかった。 巻頭に訳者が「どう見ても古くさい昔の訳文を改め、簡素な原文の体裁をできるだけ生かそうとつとめた。」と有るが、初版は1942年で改版が1964年。やはり言葉遣いがやや古い。 もう一つは固有名詞が頭に入りにくい。ローマ人の物語では所々地図と進行方向が有りイメージしやすかった。 写本がいくつかあるとは言うものの2000年前の文書がそのまま残ってるのは凄いことだけど。
0投稿日: 2014.01.01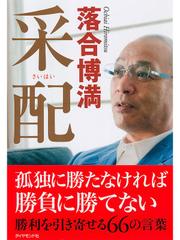
采配
落合博満
ダイヤモンド社
GMになったら現場には口を出さないのか?
何故か人気のなかった落合監督、我慢強いいい監督だと思ってました。 この本は昔の種明かしはあるものの基本的にはサラリーマンに向けたビジネス書です。 簡単に目次と小見出しの一部のみ紹介。 1章 「自分で育つ人になる」 明日の「予習」ではなく、今日経験したことの「復習」がすべて 2章 勝つということ すべての仕事は契約を優先する。 3章 どうやって才能を育て、伸ばすのか 相手の気持ちに寄り添いながら、自分の考えを伝える 4章本物のリーダーとは 任せるところは、1ミリも残らず任せきる 5章 常勝チームの作り方 オレ流ではない。すべては堂々たる模倣である。 6章 次世代リーダーの見つけ方、育て方。 誰をリーダーにするか。尊重すべきは愛情と情熱。 色々言いたいこともあったろうに、チームの勝利をすべてに優先して何も言わなかった落合監督でした。
0投稿日: 2014.01.01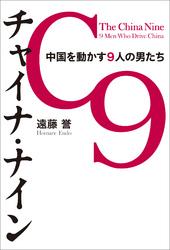
チャイナ・ナイン
遠藤誉
朝日新聞出版
チャイナ・セブンになってしまったが
日経ビジネスオンラインで中国ネタはいろいろ有るが抜群に分析が鋭い遠藤氏の現在進行形の解説書。中身は先のサイトに書かれたものも有るがまとめて読む方が理解しやすい。 中国を動かしているのは9人の中央政治局常務委員で、25人の政治局委員から選ばれる。重大な決定は9人の多数決で行なわれるので、誰が選ばれるか熾烈な派閥争いが続く。失脚した薄熙来はパフォーマンスでアピールしたが、毛沢東時代に戻る気がない胡温に見放された。 今年の秋メンバーが入れ替わり習近平と李克強以外の7人が新たに常務委員となる。25名の内67歳以下が時期候補で9人いる。この中で誰が入るのかがこの夏の一つのポイントで、もう一つは習近平の次は誰か。先の9人のうち2017年に引退しないのは習、李以外に 李源潮、汪洋で習は上海閥だが、後は胡錦濤派の中共青年団派。江沢民の影響力は習近平を次期国家首席にするところまでだったと分析している。 2022年を睨むと習の次は現在52歳以下つまり1960年以降に生まれたものが候補であり、もしこの秋いきなり常務委員入りすれば胡錦濤、習、李と同じ路線であり胡春華、周強、孫政才の名が上がっている。 胡温体制は行き過ぎた経済発展からバランスの取れた社会への変換を目指しているが一方で現体制の安定が第一である。結果としては温家宝が民主的な発言をし一方で胡錦濤が締め付けるという役割分担をしていると言う。 これからの中国ではネットの力が無視できなくなる。広東省の烏坎村事件は村民の勝利がネットで瞬く間に拡がり民衆が勝利した画期的な事件だという。いつ迄も武力鎮圧一辺倒とは言えなくなってきている。また、胡温体制は何度か親日的なメッセージを出したがその度ネットの批判に晒された。尖閣についても08年5月7日の日中共同声明でガス田の共同開発を発表して売国奴とまで批判されたらしい。 こういったネット世論を作るのは主に30代迄で高卒以下の5億人。平均月収2000元未満が半数で5000元未満が9割を占める。一方で日本のアニメや漫画にはまっていたり、北京でSMAPを歓迎しているのも彼らだ。
2投稿日: 2014.01.01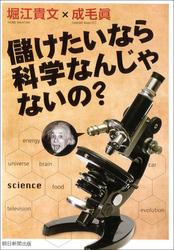
儲けたいなら科学なんじゃないの?
堀江貴文,成毛眞
朝日新聞出版
気楽に読む本
お二方とも文系で興味の有ることは妙に詳しかったり、そうでないところは結構適当だったりする。 ホリエモンの宇宙開発はマジだったりするが要は安く衛生軌道まで上げられるロケットを開発すればビジネスになるし、民間がやった方が安くなるだろうからと。一方で深海には興味がない。 成毛氏はとにかくノンフィクションはよく読んでてHonzで紹介されてる本は当たりが多い。 何となく一杯やりながらこれが面白そうとかどうとか言ってるような感じの対談なのでお気楽に読むくらいがちょうど。
1投稿日: 2014.01.01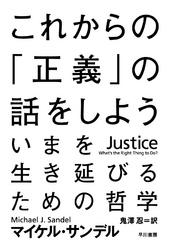
これからの「正義」の話をしよう ──いまを生き延びるための哲学
マイケル・サンデル,鬼澤忍
早川書房
こういう講義で議論するのであればただ板書するより面白いのは間違いない。
ハーバードの講義「正義」を元に書き下ろされた。 正義のアプローチ3つが主なテーマ。1.社会全体の幸福の最大化は正しいか?個人の権利への制限が度を超えると正しいとは思えなくなって来る。2.では個人の選択の自由を最大限尊重するのは正しいか?これに反対しているのが最近の反格差デモだろう。3.サンデルの立場は善や道徳的なアプローチを重視する。しかし、そもそも道徳観自体主観的なものだ。サンデルはこの違いを乗り越えられると考え、乗り越える様に努力すべきだと結んでいる。 しかし、現実の世界では総論としては賛成しても、いざ自分のこととなると簡単では無いよなあ。 こういう講義で議論するのであればただ板書するより面白いのは間違いない。
0投稿日: 2014.01.01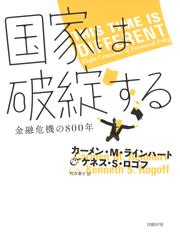
国家は破綻する―金融危機の800年
カーメン・M・ラインハート,ケネス・S・ロゴフ,村井章子
日経BP
一部データーに誤りが指摘されたがそれでも読む価値が高い
原文の題名は「今回は違う」であり筆者のデーターは今回も違わなかったことを証明するのみ。 金融危機のパターンは金融規制緩和と資本流入から過剰投資。住宅価格の急騰の後の急落が銀行危機の前触れとして非常に相関性が高い。 日本の借金は対内債務なのでデフォルトはしないとの説を唱える人がいるが、本書を読む限りいつか実質的なデフォルト(例えば高インフレによる債務の希薄化)が来ると覚悟すべきなんだろう。早くローンを返さねば・・・ 中国も地方政府がインフラ整備と不動産販売をセットで行い投機資金が流れ込んで高騰。地方債務の担保が不動産なので住宅価格が下がると地方銀行はかなりヤバい。最後は国が助けるんでしょうが。ソフトランディングを祈るのみだが一方でインフレ退治をしているのでかなりの綱渡りの気がする。
1投稿日: 2014.01.01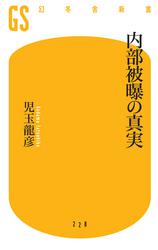
内部被曝の真実
児玉龍彦
幻冬舎新書
忘れないでおくべきこと
原発事故の一番の問題は放出された放射性物質の総量が莫大で必ず濃縮が起こり、高線量のスポットができること。対策は食物は全数検査と、地域は学校などを優先して、高濃度スポットを測定して、除染する。わかりやすく書いてあるのでおすすめです。
1投稿日: 2014.01.01
日本の未来について話そう -日本再生への提言-
マッキンゼー・アンド・カンパニー
小学館
マッキンゼーがまとめた65人の提言
3.11を受けての本なのだが原発はほとんどテーマとして取り上げられてない。 一部の製造業を除くと生産性が低いのが競争力低下の原因となってる気がする。そのまま生産人口が減ればそら経済も停滞しますわなあ。 人口減少と高齢化を前提に生産性をあげようとするならば、既得権益に手をつけない限り無料なんじゃないかな。農協、漁協だったりある種の年金だったり。
0投稿日: 2014.01.01
okadataさんのレビュー
いいね!された数197
