
スティーブ・ジョブズ I
ウォルター・アイザックソン,井口耕二
講談社
Think different Stay hungry , stay foolish
完璧主義者のジョブズが自ら企画した伝記。 ジョブズにかかると人は天才かまぬけだし、製品は完璧かゴミだ。 大きな邸宅を買っても完璧を求めるあまり家具が買えない。全てを自分の意のままにコントロールと我慢ができず微妙な違いにこだわり続ける。 ジョブズの意思はすごい製品を作ることに集中し続けたが、必ずしも成功ばかりではなく失敗を繰り返してもいる。 例えばCDはスロットインが美しく、トレイは美しくないから使わない。 書き込みができないために音楽CDを焼くというニーズを取り込めなかった出遅れはipodとitunesで音楽業界そのものをひっくり返した。 次にデジカメが携帯に浸食されるのを見てipodも携帯にやられないためにiphonに集中する。 製品へのこだわりは特に凄い。装置の中身の美しさにもこだわり、デザイン、ハード、ソフトの一体化した統一された世界にこだわる。 禅の影響を受け考え抜かれ得たシンプルさを追求する。製品デザインのコンセプトは無くせる物を全て削り落とした上で直感的に操作できること。 部下のそれは無理だと言う声はことごとく無視し現実歪曲フィールドを使う。まるでフォースだがこの人が暗黒面に落ちたら大変なことになっていただろう。 そして間に合わないはずの改造は間に合うことも多いが、やはり無理な物もあるがジョブズはそれを認めようとしない。 部下のアイデアをくそみそにけなした1週間後にまるで自分が思いついたかの様にどうだ凄いだろうと触れ回る。 自分は世間のルールを守らなくて言いと思っていて身障者用駐車場に止めたり、2台分に斜めに停めたりする。パーク・ディファレントと呼ばれたらしい。 itunesがウインドウズに移植されipod miniが出たときがappleを使い始めたきっかけだったがその後ipodは故障含めて3台、iphon2台、ipad、Macとバックアップ用のタイムカプセルと完全にappleに取り込まれてしまった。正直中国の携帯もiphonにした方が楽なのだが・・・ 技術と芸術の交差点を目指したジョブズの製品は使い慣れると空気のようにあたりまえになってしまっている。
2投稿日: 2014.01.01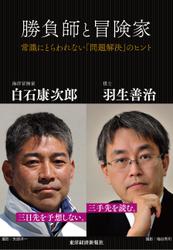
勝負師と冒険家―常識にとらわれない「問題解決」のヒント
羽生善治,白石康次郎
東洋経済新報社
三手先を読む。三日先を予想しない
ヨットで世界一周する冒険家と羽生との対談。 将棋に対する羽生はなんでもやる(先方を決めない)あまりこだわりは無いと融通無碍。 一方のヨットの白石は野生の勘とエンジニアとしての冷静な判断という両立が求められる世界にいる。 ヨットレースと言うのは1億くらいの金が簡単にかかるのに世界的な大会の優勝賞金が400万円とかとても普通の人には行けない世界。 白石もようやく世界の入り口に日本人として初めてたったばかりで、乗るのは中古艇で壊さないように完走する所から。 早く走るのは簡単だが無理をすると艇が壊れてリタイアになると。 1レースの中で1日くらいは飛ばせる日がありその日は勘を信じて飛ばすとか。 羽生の方は経験とともに負けにくい手はわかってきているがそればかりでは勢いがつかない部分が有るので普段は意識してアクセルを踏んでいる状態だそうだ。 序盤からえいっと決めに行くと息切れして続かないと言うのはなんとなくわかる。 若い頃はリスクがわからずに指してたところもあるがそういうのも必要なのだろうと言っている。
1投稿日: 2014.01.01
日本の医療 この人を見よ 「海堂ラボ」vol.1
海堂尊
PHP新書
CS朝日ニュースターの自主制作番組「海堂ラボ」を文書化、医療に関わる様々な人を紹介している。
國松孝次 いわずとしれた警察庁長官狙撃事件の被害者だが救急医療に助けられたことにより、NPO救急ヘリ病院ネットワークの理事長に乞われてなっている。成果としてはドクターヘリ特別措置法の成立のための働きかけで元行政官としてどこを動かすかがわかると言うのがポイントだったようだ。ドクターヘリは運用に1機2億かかるのだが、救命率が上がることにより例えば千葉北総病院のケースでは救急車に比べ医療費が110万円/人削減できた。入院日数も16.7日短い。出動回数は2009年に748回なので結果として収容人数が増え医療費も削減できた。 赤星孝幸 白内障手術の第一人者で手術写真が載っているがまず角膜のみを1.8mmダイヤモンドカッターで切開。プレチョッパーという独自開発した道具で水晶体を切り分けて吸引。直径6mmのアクリル性眼内レンズを1.8mmの傷口から差し込み中で拡げると後は角膜をぴったり閉じる。手術時間はわずか3〜4分ですぐに物が見え歩いて帰れる。また道具の特許は取らず、学会内で術式を披露し合い、新たな改良が加えられている。 他にも法医学者、議員、病院長、医療弁護士・・・と様々な立場の人が出てくる。
2投稿日: 2014.01.01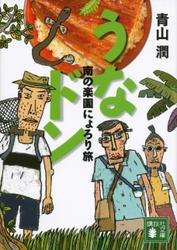
うなドン 南の楽園にょろり旅
青山潤
講談社文庫
うなぎバカ一代
ニホンウナギの産卵場所はマリアナ海溝付近にあると発見した東京大学海洋研究所のもう一つの姿は世界中のうなぎを探して回るうなぎバカ達でもあった。 ウナギ界のドン・キホーテ略してうなドン。 アフリカにょろり旅と言うのが面白そうで読みたかったが、偶々古本で2冊目のこちらを見つけた。 インドネシア編ではラマダンを勘違いし、他の人たちが食事する夜明け前はぐっすり眠り、昼間は出かけてウナギを探しラマダン中の人々の冷たい目に迎えられ、夜他の人たちが食事を終えた後で帰ってきてひもじい思いをする。 ウナギ取りに連れて行かれた近所のボスの所では電気ショック漁では漏電のため魚より前にボスの手下が感電しまくり、 最後の手段は川に毒を流して魚を一網打尽にする提案に対し、その場の空気を読まずに「ウナギウナギウナギ」を連呼し、なんでやめると言わないのだと言うボスを押し切りウナギをとる。 まあむちゃくちゃです。 タヒチ編では同僚を置き去りにして四駆を調達したついでにビーチのカフェでまったり。 ウナギ取りの川では白人観光客の目(魚取ってると自然破壊だとかうるさいらしい、一方でその白人たちも普通に四駆で川を渡って遊んでたりするのだが)に耐えかね、ウナギ取りではなく川遊びをしている風を装ったり、 タヒチの奥地の川を遡上し意地を張って野宿するわ、今は使われてないマフィアの屋敷に忍び込んでヤシの実をとるわで最後は遭難したと間違われ近所の子供にバナナをごちそうになったり、 そうしながらも目的の種類のウナギはとれずに別のウナギは捕っては捨てを繰り返す。 なんでそこまでするかと言うと最初は博士号の論文目的のはずが、途中からはほとんど知られていないウナギの生態を知りたいからということのみ。 しかしその続きがウナギの産卵場所の発見につながりそれまで18種と知られていたウナギの新種をフィリピンの干物で見つけたり(この話はまだ刊行されてないらしい)につながっている。
0投稿日: 2014.01.01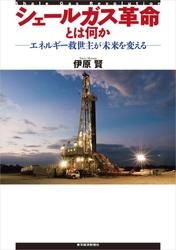
シェールガス革命とは何か―エネルギー救世主が未来を変える
伊原賢
東洋経済新報社
わかりやすい入門書
2009年の天然ガスの技術的回収可能量は在来型404兆m3に対し非在来型230兆m3。この内約半分が経済合理性を持って取り出せるとして年間消費量の3兆m3で割ると106年。在来型天然ガスの確認可採埋蔵量が60年あるため経済的に利用できる天然ガス資源量は160年を超える。非在来型ガスの可採量だけ見ると40年分増えただけだが、この本を見る限り産地が変わることの政治、経済的な影響が大きそうだ。 天然ガスは石油と違い相対取引が中心で統一された市場が形成されていない。日本の天然ガス価格は欧州の2倍、アメリカの7倍、LNGで比較しても中国の3割増の17ドル弱/百万BTUで2000年代半ばの5ドルから3倍近くに上がっている。日本の天然ガス調達価格は長期契約で石油価格に連動させているためなのだがこの間得に北米でシェールガスが増産したため06年以降石油価格と天然ガス価格は関連しなくなってきている。長期契約の間はスポット調達を除くと日本はシェールガスの恩恵を受けられない。またパイプラインではなくLNGでの輸送のためLNG化に3ドル、輸送に3ドルかかっており価格の1/3が輸送費となっている。 アメリカは天然ガスの輸入国から輸出国に変わるが今の所TPP参加国向けのみとなっている。また石油依存度を減らし、天然ガスの調達をカナダ、メキシコ、アラスカ、ブラジルなど南北調達を推進している。軍事費の削減を果たすためにも中東から手を引きつつ有ると言うのがシェールガス革命の一つの側面だ。 ヨーロッパはロシアのガスプロムからの天然ガスだよりからの脱却を目指している。中国は四川盆地を中心に世界最大の埋蔵量を持ち開発を進めるとともにロシアからの調達価格の交渉材料として使っている。 日本にもどると発電が天然ガスシフトするのはほぼ間違いない。しかしエネルギー総需要の25%が電力であり、発電効率45%と比べると入り口の省エネの効果が大きい。コージェネで発電を分散して発電の熱をそのまま利用するのがどうやら効率が良さそうだ。それと自動車をはじめとするエンジン向けにも利用を拡げ、石油依存度を下げ、調達先の多様化を図って燃料費を削減するというのが著者の意見だが肝心のパイプラインの整備が遅れている。
0投稿日: 2014.01.01
日本大沈没 明るい未来を迎えるための資産防衛術
藤巻健史
幻冬舎単行本
この本を読んだ後円安はすすんだが
デフレが原因で円高と言う認識だったが、藤巻氏は円高が原因で安く輸入できるのでデフレになったと言っている。 ではなぜ円高になったかと言うと本来海外の投資に向かうはずだった金が日本国内で眠っているから。 世界最大の銀行であるゆうちょ銀行を筆頭に日本の銀行が国債を買っているためだと。他に年金、保険なども日本国債がメインの運用になっている。 暴落しない間はただみたいな預金金利で集めた金を国債に回せば1%ほどは確実に儲かるので薄利であっても横並びで国債を買うのでしょうかね。 この説が正しければチキンレースと同じで資金が逃げるときは一気に逃げるはず。あまり明るい予想ではないがむやみに大丈夫と言うよりはまともな予想だと思います。 ハイパーインフレが起こるかどうかはわかりませんが、保険として外貨建て資産を買っておけと言うのがこの本にある資産防衛術です。 絶対大丈夫と信じてる人は別にそんなことをする必要は無いが可能性があると思う人はやっておけばと、保険と書いてるのはそう言う意味でした。 新興国よりもシェールガス革命のメリットを受けるアメリカの株を推しています。 不動産については藤巻氏も借金をして保有しているらしいので、銀行への返済が続けられるのならば良いではないかと。 ただ地震のリスクも有り外貨建て資産が優先で余裕が有ればと言うスタンスのようです。 最後の方は日本は社会主義国で悪平等がひど過ぎ、活力をそいでいると言う話が延々と。 しかしアマゾンレビューでは藤巻本は結構ぼろくそに書かれてますねえ。 サブプライムローンの問題では相関の強いパッケージはリスクヘッジにならないと言うことがわかったはずなので、 日本国債x銀行預金x日本株と言う組み合わせよりは外貨を組み合わせる方がリスクヘッジとしては妥当かなと思います。 短期で円高、円安どちらに振れるのかはどうせだれにもわからないにしても。
0投稿日: 2014.01.01
大学教授が考えた1年で90を切れるゴルフ上達法!
城戸淳二
角川SSC新書
城戸教授にはぜひ一度下手になってこんなはずじゃないと言う思いをしてもらいたいものだ。w
有機ELの城戸教授。実際に1年で89。 使ったクラブはドライバーと7番以下のみ。学生時代競技スキーをやってたので運動能力はたかいのでしょう。 内容はなかなか理屈っぽい。 練習場で3割しか打てないクラブを使わない理由は成功率3割(歩留まり3割でもいいかな)の製品は市場に出せないから。パー5での2打目のクラブの選択もこの調子。成功率7割のクラブでナイスショットが2回続く確率は5割。一方で成功率3割のFWと8割のアプローチの組み合わせだと1/4なのでFWは使わず7番で2回打つ。 教授のおすすめはビデオを見ること。ただ本を読むより視覚からの方がイメージわくから。またレッスンだと先生は変えにくいがビデオなら変えれると・・・ ゆるゆるグリップを推してます。アマチュアのミスの原因の多くは力が入ることで、力を抜くにはグリップを緩くするのが良いとまず頭で納得し、コースで試して(実験と言ってる)効果を確認する。
0投稿日: 2014.01.01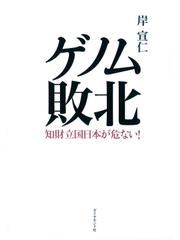
ゲノム敗北
岸宣仁
ダイヤモンド社
ヒトゲノム解読で先行した日本はその後出遅れる
1980年代にヒトゲノム解読の先鞭を付けた日本だったが日米貿易摩擦によるバイ・アメリカン、いまだに続く物理学と生物学の領域争い、少ない予算、文部省と科学技術庁に分かれた管轄争い、そして何よりも大学教授の発明に対して特許を認めない当時の方針もありプロジェクトは進まない。 一方のアメリカはプロパテント政策を推進しまたヒトゲノム計画ではDNA二重螺旋発見のジェームズ・ワトソンが中心となり予算を獲得し日本を抜きさる。元々親日家だったワトソンだがヒトゲノム計画への資金供出をしぶる日本の官僚機構に対しては怒りを隠さず、金を出さなければ解析データーの利用は認めないと脅しにかかり、一方でアメリカ議会に対しては当時進んでいた日本の脅威をたてに研究予算をぶんどる。 最終的に全ゲノム解読の日本の貢献は6%とアメリカ59%、イギリス31%に比べるとごくわずかとなった。 ゲノム解読の高速化の転換点となったのがそれまでのx線に変えてDNAの塩基に蛍光体で目印をつけてレーザーで読み取る方法で埼玉大の伏見教授が1982年10月に学会発表している。83年4月に特許出願するが科学技術庁から国家予算による発明に対して特許による独占権は認めないと待ったがかかり84年1月に特許を取り下げる。(ちなみにこれが法的に認められるのは1998年、アメリカのバイ・ドール法が発明は大学に帰属すると決めてから20年遅れている)その後、日立製作所の神原が蛍光式シークエンサーを発明し84年に特許出願するが奇しくも84年1月にカリフォルニアl工科大学が同じ特許を出願していた。特許はアプライド・バイオシステム(ABI)に譲渡され、日立はこの特許をすり抜けることができずライセンスを受け共同開発をするが日本の販売権のみでそれ以外の販売権はABIを買収したパーキンエルマーが握った。 ヒトゲノム解読は2003年に解読がすんだが実際にどの遺伝子がどういう機能を果たしているかの研究はまだまだこれからでタンパク質の立体構造を解析するタンパク3000プロジェクトでは日本が先行している。
1投稿日: 2014.01.01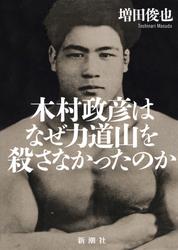
木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか
増田俊也
新潮社
700ページ二段組み それも気にならないほど熱中できる
柔道史上最強と詠われる鬼の木村政彦と力道山の昭和の巌流島決戦を中心に木村の歩んだ道が綴られている。 もう一方の主役力道山以外にも大山倍達、塩田剛三など伝説のあるいはマンガの主人公が話に絡む。 戦前の木村は柔道日本一をめざし激しい修行に明け暮れる。今の柔道より実践的で寝技、関節技以外に当て身、つまりパンチや蹴りもある総合格闘技に近いものだったようだ。足払い一発がとにかく痛いらしく得意技の大外刈りも切れが鋭く受け身がとれず失神者続出、とうとう練習では禁止になり又グレイシー柔術ではキムラロックと名付けられた腕がらみは立っても寝てもかけることができ、通常とは逆の左手を極めながら投げる一本背負いなどもあった。寝技でも下からの三角締めなど当時開発された技は多くレベルは非常に高かった。 師匠もすごい何せ名前が牛島辰熊だ。自らが果たせなかった天覧試合での優勝を弟子の木村に託す。また思想家でもあり東城英毅暗殺を試み、柔道が強くなること以外には興味がなく一方で師匠には逆らえず実行犯にさせられそうな木村がなんとか逃げ回っていたようでもある。 1日9時間の乱取り、うさぎ跳びで風呂に行き、腕立て1000回、巻き藁突き左右1000回、立ち木への打ち込み数千回が日課でとうとう木が枯れてしまい、眠る前にはイメトレまでこなすのが日課で、その結果畳の端を持ってあおいだり、100Kgのバーベルを腕の上を転がしたりとエピソードは満載だ。 また精神力もすごい、負けたら腹を切ると思い詰め実際に本当に切れるか確かめている。この結果日本選士権を3連覇し、戦争を挟んで15年間負けなしであった。 戦後は師匠の牛島の興したプロ柔道に参加するが客は入っても出る方が多く興行は行き詰まる。そのころ妻の結核の薬代を稼ぐためにハワイに渡りプロレスと出会った頃から運命が変わり始める。木村は師匠とは違い金があれば使いやりたい放題の悪ガキのままでもあった、簡単に金が入るプロレスについては勝負だとは考えていなかったようだ。 ブラジル遠征では伝説のエリオ・グレイシーとの一戦が行われた。会場は前年のワールドカップ地元開催の為にたてられたマラカナン。決勝でブラジルは悲劇の逆転負けを喫しており、ここで行われたブラジルの英雄との一戦はワールドカップの決勝と同じほどの熱狂ぶりだったらしい。 練習していなくても自力が違い過ぎ試合は一方的になる。ついてキムラロックでエリオの腕を折るがそれでもタップしないエリオにセコンドの兄が代わりにタップした。木村はエリオの執念をたたえ、エリオは後年この唯一の敗戦を生涯忘れられない屈辱であり誇りであると語っている。 一方の主役力道山も同時期にプロレスを始めている。実力もあったようだがそれ以上にスターにのし上がったのはプロレスというショーを理解し、またあらゆるものを利用したしたたかさにあるようだ。シャープ兄弟を呼びタッグに木村を口説き落としたが自分が主催者として木村に負け役を押し付けて行く。 金を稼ぐためにプロレスを受けた木村だが負け役が続くにつれ世間の評判が落ちて行くのに耐えられなかった。力道山に対して真剣勝負なら負けないと挑戦状を叩き付ける。しかしそれでもプロレスの範疇であり、力道山と同格の結果を出せればいいと思っていたらしい様子が見える。 第一回の日本選士権は引き分け、二回目は勝ちを譲るとの念書を出すが力道山はのらりくらりと自分は出さないまま契約が決まった。試合前トレーニングに精を出す力道山と酒ばかり飲んでいる木村。木村はいざとなれば寝技に持ち込めば勝てると思っていたようだがコンディションの差は大きい。途中まで八百長を信じていた木村に対しいきなり仕掛けた力道山。右ストレートがまともに入るがその後もまともにガードせず一方的に打たれ続けた木村はKOされた。試合後も木村が八百長を持ちかけたと念書をマスコミに流す力道山。マスコミに叩かれる木村。リング内でも外でも木村は負けた。何があっても負けないと準備していた木村であれば油断はなかったろう。しかしプロレスは勝負と思わず準備を怠ったために負けたのだ。 怪我の見舞金という形で力道山と木村は手打ちをする。しかし写真撮影が終わると力道山は帰る木村を見送りにも来ない。この後木村は短刀を持って力道山をつけ狙うがそのうち恨みを抱えたまま田舎に帰り、この後の半生を苦しみ続けることになる。 東京五輪ではヘーシンクに対抗できるのは当時47歳の木村しかいないという意見もあるほどで実際に練習に来たメダリストたちも寝技ではおもちゃにされていたらしい。最後のエピソードでは弟子の岩釣が地下格闘技のチャンピオンとなり誰も知らない世界で木村の柔道が強いことを証明したと遺言代わりに伝えている。
1投稿日: 2014.01.01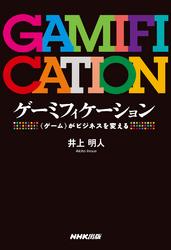
ゲーミフィケーション―<ゲーム>がビジネスを変える
井上明人
NHK出版
ビジネスやいろいろなものにゲームの要素を取り入れるという話。
この本を書くきっかけは震災後の節電をしながらこれはゲームになると気づいたところから。 冷蔵庫以外のコンセントを全て抜けば何Whとか、#denkimeterと言うタグでツイッター上でつぶやくところからゲームが広がり、iphoneアプリまでできてしまった。 オバマは選挙活動にゲームの要素を取り込んだマイバラクオバマ・ドットコムという選挙支援サイトの中で電話勧誘や戸別訪問をするとサイト内でのランクが上がって行く。RPGで経験値を積むとレベルが上がるのと似た様な設計である。 スターバックスでは紙コップ削減キャンペーンにあるアイデアが使われた。マイカップ持参でポイントを付与するのであればだれでも思いつくところを店に黒板とチョークで来店者がマイカップを持ってくるごとにチェックを入れる。記念すべき10人目はタダというゲームだ。 Facebookは従業員の満足度が非常に高い。その秘密として取り上げられるのがリップルという社内システムで、社内のメール、進捗管理、さらに評価制度にもつながるシステムになっている。インターフェースはfacebookと似ており簡単な連絡はチャットの様なやり取りができる。(そういえば中国のQQもそんな感じらしい)いいねボタンだけでなく特別な際にはサンクスボタンがありこれが評価に直結するらしい。 ゲーム要素を入れれば何でもうまく行くということではないらしい。 敷居を低くし入りやすくすること、ハマる要素をうまく盛り込むことなどいくつか条件はある。 40代前半以下は子供の頃から普通にゲームに慣れ親しんでいるので受け入れられやすくなっているんじゃないかと言ってるがまあわかる気はする。
1投稿日: 2014.01.01
okadataさんのレビュー
いいね!された数197
