
メルトダウン ドキュメント福島第一原発事故
大鹿靖明
講談社文庫
事故の全体像をまとめたドキュメンタリー
福島第一原発事故の後,おそらくもっとも早く出版された,事故の全体像をまとめたドキュメンタリー. 私はこの本で,あの事故がどういう進展を辿っていて,東電,政府などの関係者がどう動いていたかの概要を知りました. なお私が読んだのは,2012年に出版された,同じ著者による同名の電子書籍の方で,表紙のレイアウトは同じですが色がグレーでした. 気づいたらSony Reader Store からその本がなくなっていて,替わりにこの本(表紙が水色)になっていました. ひょっとしたら私が読んだ方とは内容が変わっているかもしれません. 非常に深刻な事故なのに,思わず失笑してしまう箇所がありました. 東電の説明を「こんにゃく問答」と揶揄したり,対応の遅い東電を「尻を叩かれないと動かない」と批判したり, もちろん笑っていられる状況ではありません. あの時も,2年半以上たった今も.
1投稿日: 2013.09.27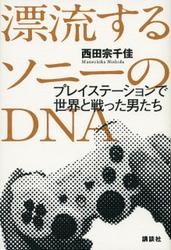
漂流するソニーのDNA プレイステーションで世界と戦った男たち
西田宗千佳
講談社
ゲーム市場を席巻したPS2と,優位に立てなかったPS3
大量生産によりゲーム機1台当たりのコストを下げるとともに一気に普及させる. すると良質なゲームソフトが数多く生み出されることとなり,さらにゲーム機の販売増につながる. これがゲーム市場における勝利の方程式. PS2ではこの勝利の方程式を使ってみごとに市場を席巻したソニーは,同じことをPS3で繰り返し, 一転こちらは苦戦することになる. 要因はいくつもあるのだろうが,そのうちいくつかを挙げるなら,高性能半導体セルの開発に莫大な投資をしたためゲーム機の価格が高くなり普及にはずみがつかなかったこと, 作れば作るほど赤字が膨らむ状態が3年以上も続いたこと, そして任天堂のWii,MicrosoftのXBOX360といったゲーム機だけでなくiPhoneという強力なライバルが出現したこと. 大成功のPS2と苦戦するPS3. 高性能であることに徹底的にこだわったプレイステーションの生みの親である久夛良木さんと,消費者に受け入れられることが大事だと考えた平井さん(現ソニーCEO). 周辺機器キネクトが大ブレイクしたXBOX360とそれほど振るわないPS3. 読み終えてみるとそれらの対比がとても印象に残ります. 今年の冬にはソニーからPS4が,MicrosoftからXBOX Oneが発売されます. これらの新しいゲーム機は,この先にどんなストーリーを描いてくれるのだろうと,今から楽しみです.
3投稿日: 2013.09.27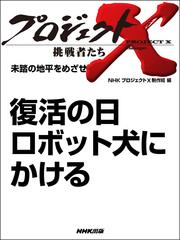
プロジェクトX 挑戦者たち 未踏の地平をめざせ 復活の日 ロボット犬にかける
NHK「プロジェクトX」制作班
プロジェクトX 挑戦者たち
ソニー創業の精神
「土井君.人の真似はするな.新しいことをしろ.それがものづくりの原点ですよ.」 作中に出てくる,ソニー創業者井深さんの言葉です. この言葉にも込められている,創業の精神が失われようとしている西暦2000年頃のソニーの中で,ロボット犬「AIBO」が生み出されるストーリーです. 「AIBO」自体は完成し,そこでこのストーリーは終わるのですが,その後10年以上に渡ってソニーから革新的と言える エレクトロニクス製品が出ない歴史を知っているせいでしょうか,読み終えた後,言いようのない淋しさが残りました. ソニーが再び創業の精神を思い出して復活してくれることを願っています.
2投稿日: 2013.09.26
ソニーの革命児たち
麻倉怜士
ワック
エンジニアの好奇心をくすぐる1冊
PS1,PS2 とそれを生み出した久夛良木さんの物語です. 当時任天堂の独壇場だったゲーム市場に斬り込んでみごとにその牙城を崩していますが, その背後に緻密な計算と戦略があり,任天堂の牙城は崩れるべくして崩れたということを 感じます. 開発者の興味をそそる技術と開発しやすい環境を用意してゲーム開発者を味方につけ, 在庫リスク,欠品リスク(販売機会損失リスク)と隣り合わせだったカセット式のゲームソフトを CDに置き換えることで在庫リスクを極限まで低減させて流通業者を味方につけ, 当時としては破格のマージンを提供して小売業者を味方につけ, そして絶え間ない製品原価のコストカットを製品自体の値下げの原資に振り替えて消費者を味方につける. その実現の背後にはPlayStationの心臓部ともいうべき半導体の技術進歩に関する的確な見通しがある. PlayStationが製品として秀逸なのは誰もが認めるところだと思いますが, それを世に出すための周到な準備,戦略,それを実行する力もまた卓越していると感じました. 製品としてのPlayStationについても,それを生み出し,世に送り出す過程についても 詳しく説明された良書です. ただ,それゆえに少し難解なところもあります. 「ライブラリ」「ポリゴン」「テクスチャマッピング」「レンダリング」などのカタカナが頻繁に登場したり, PlayStation がどのように映像を生成しているかの説明では座標計算,光源計算,行列演算など, 画像処理について多少の知識がないと何をしているのかちんぷんかんぷんな説明が出てきます. 逆にそのあたりの前提知識を持っていると非常に面白く,興味深く読めます. そしてこれほどの機能を1990年代半ばに実現していた(1990年代半ばというと,Windows95が出たか出ないかという頃ですよ)ことに 驚嘆を覚えました. 最後に,技術的にはとても興味深いということでもないですが,「へえ,そうなんだ」と思ったことを1つ書きます. PlayStationは画像生成エンジンなので,テレビ画面に出す映像すべてをゲームソフト(CD-ROM)に入れておく必要がありません. 画像を生成するのに必要なデータだけ入れておき,映像自体はPlayStationが演算によって作成します. ということで,ゲームによっては500MBを超える容量を持つCDの大半が「空き」状態になります. このためPlayStationがゲームデータをロードした後は,ゲームCD-ROMを音楽CDと入れ替えて,好きな音楽を聴きながらゲームを楽しむ,なんてことができるのだそうです.
3投稿日: 2013.09.26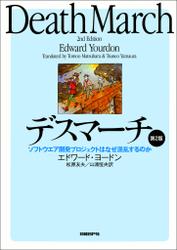
デスマーチ 第2版 ソフトウエア開発プロジェクトはなぜ混乱するのか
エドワード・ヨードン,松原友夫,山浦恒央
日経BP
笑いごとではないけれど,なぜか笑えてきてしまう
ソフトウェア開発はとても難しいものです. もともとキツいスケジュールでアップアップのところに,想定していなかった技術的な問題,仕様の漏れ,などが出てきてスケジュール遅延の要因となってさらにヒイヒイ言い, そこにお客様から追加仕様や仕様変更が持ち込まれて悲鳴を上げる... これは追加項目だからと予算が上乗せされても〆切は変わらず,人員増加で乗り切れと言われても,機械でできる作業と違って人を増やせば生産能力が2倍になるわけではない... 今まさにそんなデスマーチの真っただ中にいる(?)身としては,この本に書いてあることにいちいち大きくうなずきたくなります. ですが,笑いごとではないのに,この本を読むとなぜかものすごく笑えてきてしまう... デスマーチのまっ最中で時間が惜しい時ほど,この本を読む価値があります. デスマーチを解消することはできなくても. ちょっとは気持ちが軽くなるかもしれません.
4投稿日: 2013.09.25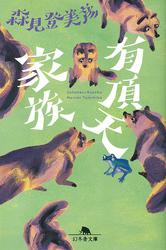
有頂天家族
森見登美彦
幻冬舎文庫
リズミカルで読みやすい文章
話の内容もさることながら. 文章がリズミカルでテンポ良くすいすい読めました. アニメ化されてテレビで放送されているので(2013年9月現在)そちらも観ていますが,ナレーションの端々が耳に残っています. ちょっと日本語ってきれいだな,って思ってしまうほど. 「声に出して読みたい日本語」と言えるのではないでしょうか. 狸が人に化けてふつうに居酒屋で呑んでいたり,天狗が空を飛んでいたりしますが, なぜかまったく違和感を感じません(笑). 人に化けた狸と人間が同じ鍋を囲んだり,狸が天狗に弟子入りしていたりと, 3つの種族が入り乱れてふつうに人間っぽく生活しています. そんな中で私のいちばんのお気に入りは淀川先生(人間,大学教授,50歳くらい?). 「狸はかわゆいな」と言いながら「食べちゃいたいほど好きなのだ」から「狸鍋を喜んで食う」と言ってみたり, すき焼きの肉を大人げなく取り合ったり,鍋を食べたすぐ後で「腹が減ったね」とおにぎり(自作)を食べてたり. 淀川先生も「かわゆい」なあと思っちゃいました.
31投稿日: 2013.09.25
福島原発事故はなぜ起こったか 政府事故調核心解説
畑村洋太郎,安部誠治,淵上正朗
講談社
配電盤が津波で被水したのが致命的だった
福島第一原発事故に関連する書籍は多数ありますが,特にこの書籍を選んで読んだ理由は,「何が最大の原因で発生したのか(どうすれば回避できたのか)」 「どういう過程を辿って事故が進展したのか」を,技術的な視点から,且つプラント全体を展望した視点から知りたかったためです. その意味では関連する内容は6章立ての最初の2章分しかありませんが,知りたいことはひととおり知ることができました. 個人的には,6章全部技術的内容だったらもっとよかったと思っているので,星4つです. たとえば以下のようなことを知れたのは有意義でした. ●原子炉の設計思想の違い 1号機では電源喪失した場合にはすべての弁が閉じる仕様だった. 2号機,3号機では電源喪失した場合にはその時点での弁の開閉状態が維持される(何もしない)仕様だった. つまり1号機と2号機以降では設計思想が異なっていた. 結果として1号機では電源喪失時に原子炉が外界から隔離され,熱が放出できず炉心溶融を早めることとなった. ●非常用ディーゼル発電機は全滅していなかった 津波に襲われた後でも各号機とも稼働できるディーゼル発電機は残っていた. だが発電機が発電した電気を原発を動かす各種機器に伝達・分配するための配電盤が被水したため,ディーゼル発電機だけ残っても意味がなかった. 後知恵かもしれませんが,電気がないとなにもできないにも関わらずその電気を確保するための努力が 足りないんじゃないかと思わずにいられません.
0投稿日: 2013.09.24
井深大がめざしたソニーの社会貢献
宮本喜一
ワック
改めてソニーのファンになりました
ソニーといえばウォークマンなど革新的な製品を生み出してきた会社ですが,その「革新的」な精神は製品だけでなく会社の在り方にまで及んでいる,ということをこの本を通して感じました. 資源のない日本の将来を支えるのは子供たちであるという考えから学校に理科教育のための資金を提供したり,身体障害者が自立できるようにと雇用機会を設けたり, おそらく当時としては非常に革新的なことをしています. 企業というのは利益を追及する集団ですが,ソニーだけでなく社会全体の利益になることを,ごく自然体で実行しているように感じられました. 特に印象的だったのは「障害のある人はむしろ健常者よりもひとつのことに集中することができる」ということを見抜いてウォークマンの組み立てという非常に難しい仕事を任せています. ふつうに考えたら,障害者だからという理由で簡単な作業を任せそうな気がします.この点だけでも井深さんが人をよく見てその人が最大の力が出せるようにしていることがうかがえます. 井深さんの人を生かす力も,ソニーが輝いていた理由の1つなのだと思います. 革新的な製品,サービスを生み出す風土を持つというのもソニーの一面だし,自然体で社会貢献できるというのもまたソニーの一面です. ソニーは,もちろんその製品が素晴らしいから好きだという人が多いのだと思いますが,その会社の在り方も含めて好かれているのではないでしょうか.
1投稿日: 2013.09.24
Maxwellさんのレビュー
いいね!された数154
