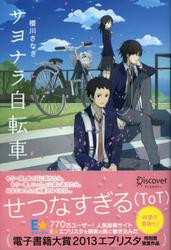
サヨナラ自転車
櫻川さなぎ
ディスカヴァー・トゥエンティワン
Very Good
This is the best story to me in the last one year. The story and the characters who care for each other impressed me very much.
0投稿日: 2024.01.03
マイナス金利―ハイパー・インフレよりも怖い日本経済の末路
徳勝礼子
東洋経済新報社
日銀のマイナス金利政策の意図と影響を推測する手がかりにはなるかも
この本の出版は2015年10月で、日銀のマイナス金利導入の発表よりも前です。 本書では「名目金利はプラスでも、為替取引を介せば事実上マイナス金利が発生する」メカニズムを説明し、「事実上のマイナス金利の影響」を評価しているのであって、日銀のマイナス金利政策について直接論じているわけではないです。ですが、いろいろ考えるヒントにはなると思います。 ※以下の記述は本書の内容と私が思ったことが混在しています。 <別の基準で考えることの重要性> 日本国内で暮らしているとどうしても「円」を価値の基準として考えてしまうが、ドルを基準に考えてみるとまたちょっと違う景色が見えてくる。たとえばアベノミクスが始まる前の日経平均株価は1万円弱で、アベノミクス後は一時2万円を超えたが、為替は1ドル80円から120円になっている。ドル換算で見ると125ドルから166ドルへの上昇。円で見れば2倍でもドルで見れば1.3倍。これは価格の例だが、金利についても2つの基準(円、ドル)で考えてみると、円だけを基準に考えるのとは違った景色が見えてくる。 <貨幣の基本機能に鑑みて> 少なくとも日本国内では「円」が価値の基準として認識されている以上、「円」の価値が目に見える形で目減りするマイナス金利は、「価値の保存手段」という貨幣の重要な機能の1つを失わせる(あるいは人々にそういう不安を抱かせる)のではないか?(本書では「保存機能が弱まる」と言っているが、その程度で済むのだろうか?) 通貨の番人たる日銀がそんなことして大丈夫なのだろうか? <とは言え日銀は自らの責務を放棄しているとも言えない> 日本銀行の責務は物価と金融システムの安定を図ること。マイナス金利は、借金を実質的に減らすという形で日本最大の債務者であり日本の安定した統治の要である政府に最大の利益をもたらす。最大の目的はデフレ脱却ではなくそっちなのだろうか?
1投稿日: 2016.02.26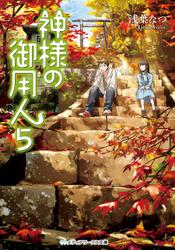
神様の御用人5
浅葉なつ
メディアワークス文庫
心がふわりと暖かくなります
前巻は1冊まるごと1つのお話でしたが、今回は3巻以前と同様、短編集(4柱の神様のお話)になっています。1つ1つのお話はそれほど長くなく、疲れた時に気楽に読めるので、これはこれでいいかなと思います。 本書に限らず、このシリーズは読むと心がふわりと暖かくなります。優劣つけ難いですが、本書の中では特に「四柱 えべっさんの草鞋」がお気に入りです。海に捨てられたエビス様が漁師のキスケに助けられ、というところからお話が始まりますが、お互いほんとに大切に思っている様子が伝わってきます。 その一方で、思わず笑ってしまう描写も健在で、黄金さまの食い意地はますますエスカレート…ではなく、食に対する飽くなき探究心はますます冴え渡ってきている気がします。 ところで毎度思うのですが、神様の名前は読めないです。 たとえば「倭建命」で「ヤマト・タケルノ・ミコト」 とか、歴史や古典の知識が乏しい私にはルビがないと読める気がしません。以前のお話で登場した神様が再登場することもあり、「…読めない。ついでに、誰だっけ…?」という事態に遭遇することもしばしば。そろそろ「神様一覧」のようなノートが必要そうです。
0投稿日: 2016.02.14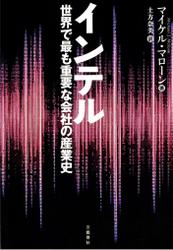
インテル 世界で最も重要な会社の産業史
マイケル・マローン,土方奈美
文藝春秋
私がこの1~2年の間に読んだ本の中では最高の本でした。
「インテル、はいってる」のキャッチフレーズが有名なインテル。 私がパソコンに触り始めたばかりの頃(その頃はCPUとメモリとハードディスクの区別もついていなくて、パソコンの速度を上げるためにハードディスクのデータを消そうとしたこともありました(焦))、ペンティアムというCPUの名前を頻繁に聞くと同時に、その評判やカタログスペック、ペンティアム搭載のパソコンにはなかなか「いい値段」がついていたことなどから、「ペンティアムは超高級なブランド」というイメージを刷り込まれました。 そんなペンティアムを製造している会社が、インテルという名のアメリカの会社だと知ったのはずっと後になってから。今使っているパソコンにも当然のようにインテルのCPU(今はCore i7 とか Core i5 というブランド名ですが)が使われていて日々お世話になっているものの、そういえばインテルのこと何も知らないな…と本書を手に取ってみたのですが…この本はすごいです。 日本の戦後の産業史や、ソニーやホンダを始めとする戦後誕生して世界的なブランドにまで育った会社の歴史を御存知の方は多いと思いますが、同じ時期のアメリカの産業界や企業の歴史をご存知の方はそれに比べれば少ないだろうと思います。インテルはシリコンバレーに誕生した半導体メーカーです。本書を通して、インテルの歴史はもちろんのこと、その周囲にあるシリコンバレーの歴史やアメリカ半導体産業の歴史、日本との関わり、さらに半導体の進化の歴史を知ることができます。知的好奇心が刺激され、またソニー発展の歴史を知った時と同じような感動もあり、私がこの1~2年の間に読んだ本の中では最高の本でした。 ちなみに相当分量が多いです。 登場人物や企業も多いため、「この人、誰だっけ?」ということもよくありました。 また時々ですが「SRAM」「DRAM」「RISC」「CISC」のような技術用語も出てくるので、これもまた「これ何だっけ?」と思ってGoogleで調べてメモしておくことが何度かありました。 手元にメモ帳とペンを用意して、腰を据えて、じっくり読むことをお薦めしたいです。 繰り返しになってしまいますが、本当にそれだけの価値がある本です。
3投稿日: 2016.02.13
週刊東洋経済 (2016年1/30号)
東洋経済新報社
東洋経済新報社
メインのソニー特集の内容には一部不満があるものの、シャープの行方や電機業界再編シナリオなどの特集もある、電機業界に興味のある人には垂涎ものの1冊
メインのソニーの他、シャープの行方やルネサスエレクトロニクスの記事もあり、電機業界に興味のある人には嬉しい内容です。 ただ、ソニー特集の内容については全部ではないですが事実と違っていたり、ちょっと恣意的過ぎる気がしたりする内容がありました。 例えば、2014年9月にスマホ事業で1800億円の減損損失を計上し且つ無配にするとソニーが発表した時のことについて、「(この後)投資家はソニー株を買いに走った」という記述があります。 長期的に見ればそういう傾向があるのは事実ですが、発表の翌日には株価は大きく値下がりし、もとの水準に回復するのは1か月以上経過した中間決算発表後なので、「買いに走った」という表現が妥当とは思えません。 また、来年6月に社長交代するのでは?という趣旨の記事もありますが、その根拠が平井社長が年末年始に家族とゆっくり過ごしたから。 やるべきことをきちんとやっていれば(少なくとも今ソニーの業績は回復しています)休むべき時にきちんと休んで有事に備えるのはCEOとして当然の責務であると私は思います。わざわざセンセーショナルな内容にするために強引にそういう結論に結び付けている印象が拭えません。 この他、内容自体ではないですが「書き方」に疑問を感じるものもありました。 「ストリンガーは退任ではなくクビだった」という記事について、あたかもスクープのような書き方をしていますが、当時すでにそういった内容は雑誌に掲載されていました(東洋経済ではなかったかもしれませんが)。私にとっての新しい情報は、この時に創業家親族も動いていたという1点のみで、とてもスクープとは受け止められませんでした。 もちろん、「イノベーションを再び起こせるか」のような、満足できる内容の記事もありました(この記事の執筆者は西田宗千佳氏)。 が、上記のとおりちょっと行き過ぎに感じられる記事があったのも事実。 雑誌とはそういうものだと言われればそれまでですが、「週刊東洋経済」という看板をつけた雑誌にしては、今回はちょっと…と思いました。 これを減点要因として、星4つとしました。
2投稿日: 2016.01.26
検証 財務省の近現代史~政治との闘い150年を読む~
倉山満
光文社新書
鵜呑みにはできないが、読んでおく価値はあるかな、と。
まず最初に。 財務省の立場で正しい悪いの価値判断がされているので、そこは割り引いて読む必要があります。 また、私はあまり近現代史に詳しくないですが、「え~、そうなの?本当に?」と思うような歴史解釈もあります(著者も「通説とは違うものもある」と認めていますが)。通説が常に正しいとは限りませんが、ある程度知識を持って、批判的な視点を持って読むのがよさそうです。 ただ、財務省(昔は大蔵省)が「健全財政」の方針のもと近代日本の発展を支えてきたのはたぶん間違いではなく、その歴史的事実と「健全財政」の意味するところをこの分量で知ることができるという点で、読んだ価値はあったかな、と思います。 かなり意外だったのは、もともと大蔵省は「増税は最悪の手段である」と考えていたということ。 財務省というと「財政規律」(=「歳出≦歳入。そのためには増税必須!」 )を振りかざして消費税増税したくて仕方がないというイメージがありますが、本来の財政規律とは「何も考えずに歳出>歳入にしてはいけない」ということであって、増税がセットではないのです。
1投稿日: 2016.01.02
政治改革の熱狂と崩壊
藤井裕久,菊池正史
角川oneテーマ21
発端は「時事放談」
著者の藤井さんがTBSの番組「時事放談」(日曜朝6時~)に出演しているのをたまたま見かけ、 その時の説明がものすごくわかりやすかったので読んでみたのがこの本。 期待を裏切らず、ものすごくわかりやすく、且つ内容の濃い本でした。 著者の大蔵官僚+政治家としての歩みを辿る形で話が進みますので、田中角栄元首相以降の日本の政治の流れが把握できます。 特に前半は近現代政治史の流れを辿る色彩が強いです。 読み進めるにつれ、政策上の主張(「消費増税は必要である」など)やそう考える理由といった内容も増えてきますが、わりとすんなり納得できます。 もちろん、説明がわかりやすいから、というのもあると思います。 ですが、それ以上に、言葉の端々に信念(私利私欲とは無縁で、且つブレない軸)を感じました。 本書から読み取った、政治家藤井裕久氏の信念は、「弱い者、恵まれない者に目を向けるのが政治である」です。 だからこそ、増税などの嬉しくない主張も含めて、すとんと胸に落ちたのだろうと思います。 ちなみに本稿冒頭の、「時事放談」でのすごくわかりやすかった説明、というのは、 「集団的自衛権とは、(アメリカ合衆国と)対等の軍事同盟を結ぶことである」 です。 安保関連法について総理の説明とか何度聞いても残念ながらよく理解できずモヤモヤしていましたが、この一言でスッキリしました。 ということで、安倍総理の言っていることが理解できなかった時は、藤井先生の意見を検索してみるつもりです。
2投稿日: 2015.10.24
神様の御用人4
浅葉なつ
メディアワークス文庫
次回作への期待が高まりました
3巻までは1冊の中に「神様の御用聞き」案件が2~3件入っていましたが、4巻は1件だけです。その分だけお話も深く、心に染み入ります。 主人公の良彦も良い意味で変わってきていて(以前から兆候はありましたが)、神様の依頼に真摯に取り組む姿勢も好感が持てます。 3巻までも読み物としては良いですが、印象に残ったことを思い出すと、たいがいが、黄金さま(キツネの姿の神様)のお茶目な言動、でした。 一方、4巻で印象に残っているのは、依頼主の神様のなくした記憶を取り戻すために少しずつ歴史を紐解いていく過程、辿りついた結末です。この神様が人として生きていた2600年前の情景、人の営みが目に浮かぶようで古代日本の歴史にちょっと興味が出てきたり、神様の御用人1~3巻を読み返してみたくなったりしました。 いわゆる続き物にはマンネリ化して面白みがなくなっていくものがありますが、本書の場合は、次回作への期待が高まりました。
2投稿日: 2015.09.05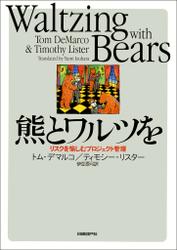
熊とワルツを リスクを愉しむプロジェクト管理
トム・デマルコ,ティモシー・リスター,伊豆原弓
日経BP
ナノパーセント日!
おもしろおかしく書いてあるのでついつい笑って済ませてしまいたくなりますが、本書の内容を知らずにある程度規模の大きなソフトウェア開発をすると、たぶん相当イタイ目に遭います。 ただ、一度くらいイタイ目に遭っていた方が、実感を持って本の内容を受け止められそうなので、ある程度開発経験のある人向けの「リスク管理」の本なのかなと思います。 でも、駆け出しのプログラマであっても「ナノパーセント日」は知っておくときっと役に立つと思います。 「ナノパーセント日」は、プログラマが予想するプログラムの完成予定日。 ナノは10億分の1であり、ここではほとんどゼロ、という意味。 つまり、この日までにプログラムが完成する可能性は限りなくゼロに近い、と言う主張です。 実際にプログラムが完成するまでにかかる期間は、経験的に、予想の1.5~3.0倍と言われています。 プログラマはリスクを織り込まない楽観的な見通しを立てる傾向が強い(技術者の性?あるいは神ならぬ人間の能力の限界?)、という戒めです。 自分は慎重だと思い込まず、計画は楽観過ぎないか、自分に都合のよい仮定をおいていないか見直してみる、これがきっとリスク管理の第1歩です。
1投稿日: 2015.08.31
放射能汚染の現実を超えて
小出裕章
河出書房新社
20年以上前に出版された本なのに、まったく色あせていない
川内原発の再稼働を機にもう一度読み直してみました。 本書が出版されたのは1991年、タイトルにある放射能汚染の焦点はチェルノブイリ原発事故です。 福島原発事故が起きた後の今読んでもその内容に古臭さのようなものは一切ありません。 福島原発事故後、小出先生の著作を読んだ方、講演を聞いた方も多いと思いますが、本書との違いは焦点が福島かチェルノブイリかの違いくらいしかないと思います。それほど、先生の主張は一貫しているし、明快です。 チェルノブイリの事故は地理的には福島よりはるかに遠く離れていたとは言え、福島と同じように食品の放射能汚染が問題になっています。また、福島では放射能汚染のためいまだに自宅に帰れない方が多数いますが、本書では、仮に九州でチェルノブイリと同じ規模の原子力事故が起きたら汚染地帯がどこまで広がり、そこに住む人は着の身着のまま逃げなければいけないということまで指摘しています。 事故が起きてしまった場合の代償がいかに高いかこの時すでに判っていたわけだし、事故後に発生する(社会的)問題の予想は恐ろしいほど的中しています。 20年以上前に、そう警鐘を鳴らしてくれる人がいたのに、どうして原発をやめられなかったんだろう(やめられないんだろう)と思います。
1投稿日: 2015.08.16
Maxwellさんのレビュー
いいね!された数154
