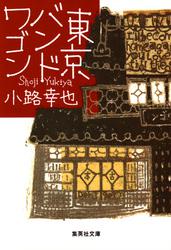
東京バンドワゴン
小路幸也
集英社文庫
ついに「東京バンドワゴン」を読んだ。そこには《LOVE》があった。
古書店と喫茶店を営む大家族堀田家が繰り広げる物語である。私も子供の頃一番多い時で7人家族だった。まさに《LOVE》と規律がなければ大変なことになる毎日であった。それから月日は経ち私も親となった頃世間では叱らない子育てなるものが流行った。叱ることの是非もそこに《LOVE》があるかどうかが問題ではないのか…などと考えながら読んでいると…堀田家の父、我南人は語る「LOVEを感じるままに進んでいけばいいんだよぉ。それなら絶対に後悔しないねぇ」 特別な大きな事件が起きるわけではないが何故か引きつけられる。それはやはりそこに《LOVE》があるからなのだろう。とにかく《LOVE》を連発する家族でレビューも《LOVE》だらけになってしまった。久々にミステリー以外の(殺人事件が起きない)面白い小説を楽しんだことは事実である。
0投稿日: 2017.02.11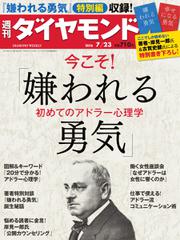
週刊ダイヤモンド (2016年7/23号)
ダイヤモンド社
ダイヤモンド社
他人が自分をどう評価するかをコントロールすることはできない。
嫌われる勇気の著者である岸見一郎さんと古賀史健さんの対談、スピンオフ作品、公開カウンセリング、具体的な話や読者の事例などが多くてわかりやすかった。古賀史健さんは岸見先生の「アドラー心理学入門」を読んで天地がひっくり返るような衝撃を受けた。それから10年経ってお2人は仕事で出会い「嫌われる勇気」の執筆に繋がった。哲人と青年はお2人の実体験をもとにしているとのこと。最近は課題の分離に言及する人が増えてきたがそれだけ誰にとっても大きな問題なのだと感じた。他者の課題に踏み込まず自分の課題に踏み込ませない。 他人が自分をどう評価するかをコントロールすることはできない。しかし自分が目の前のことにどう取り組むかは自分の手でいくらでも変えられる。相手の指摘は有益であろうとなかろうと一旦感謝の意を示し、その上で決めるのはあくまでも自分であるという毅然とした態度をとることで課題を分離する。自分で決めているルールを相手に伝えてそれに合わせるかどうかは相手の課題なのでこちらからは介入しない。相手がどう思うかも気にしない。アドラー心理学の基本は「対等な横の関係」であり女性のほうが理解しやすいという話も納得である。
0投稿日: 2017.02.09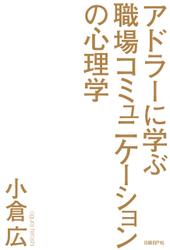
アドラーに学ぶ職場コミュニケーションの心理学
小倉広
日経BP
近すぎず遠すぎず背負わず押しつけず。
おもに人との距離感について書かれている。近すぎず遠すぎず背負わず押しつけず。アドラー心理学はシンプルでわかりやすいが実践が難しいと言われている。本書は心の持ち方をまず学び次に技を学び、習慣としていく方法の指南書である。重要なことは「誰の課題か」を明確にして他人の課題に踏み込まないこと。勝ち負けにこだわらないことである。 後半の技については残念ながら「心が変われば行動も変わる」という視点で考えていった方が近道ではないかと感じた。とくに共感・傾聴・沈黙などのスキルはそれぞれの専門書に頼ったほうが良さそうである。 一番大切なことは相手に土足で踏み込まれたらきちんとNOということ。相手の領域に土足で踏み込み返さないこと。課題の分離=自分の課題に集中することである。 DESCという具体的な提案の仕方や「何を」を要望しても「どうやって」は任せる等のスキルはすぐに役に立ちそうなので実践してみたい。結論にあわせた証拠集めや自己正当化のための認知バイアスという考え方も参考になった。
0投稿日: 2017.02.03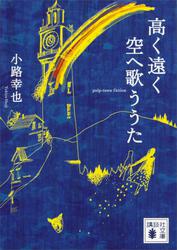
高く遠く空へ歌ううた
小路幸也
講談社文庫
不思議な雰囲気をもった作品
不思議な雰囲気をもった「空を見上げる古い歌を口ずさむ」の続編。またまた不思議な世界にひきずりこまれた。何かのきっかけで違う道に迷い込んだ人(タガイモノ)を元の場所に呼び戻す物語。言葉で語ることのできない感性、肌で感じ取れる同じ人間だけが理解できる世界。偶然なんてことは実はないんですよと言いながら偶然の出会いを重ねていく。一番怖いのは都合の悪いものを排除するという考え方。感性豊かな子供時代に読みたかったという気がするが、生きてみないとわからないことが沢山あることを知ってしまった今読んでも大いに共感できる。 小路さんの作品の中で一番人気のある「東京バンドワゴンシリーズ」が《第2回吉川英治文庫賞》の最終候補作となった日に読了。
1投稿日: 2017.02.01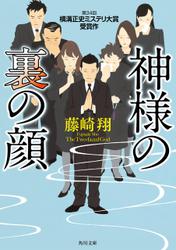
神様の裏の顔
藤崎翔
角川文庫
重くならない文体と語り手が次々と変わっていく構成の面白さは素晴らしい
元教師、誰からも慕われた神様のような男、坪井誠造の通夜での出来事。参列者同士の会話の中から故人には裏の顔があったのでないかという疑惑が浮上する。人間とは温厚すぎることも周囲の人を追い詰めてしまうものなのだ。としみじみ感じた。その対極にある嫌われ者のスパルタ体育教師が所々で不思議と魅力的に見えてくるのも事実。後半の通夜ぶるまいの席での議論は空気に飲まれ二転三転する人間の弱さが丸見え状態。教師であるが故の子育ての難しさも露見する。それでも重くならない文体と語り手が次々と変わっていく構成の面白さは素晴らしい。
3投稿日: 2017.01.29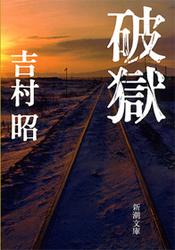
破獄
吉村昭
新潮社
全く違った視点で描かれた戦争の悲劇に驚くばかりであった。
かなり前のことだが網走監獄博物館で脱獄囚の人形を見た。獄舎の天井の梁を伝って逃げようとしている姿は強烈に印象に残っている。北海道の開拓の歴史は壮絶である。札幌からオホーツクまでの幹線道路には過酷な労役で亡くなった囚人の骨が埋まっていると言われている。北見から網走へ行く途中の道端には鎖塚という慰霊碑が今でも残っている。この本は小説というより戦争と刑務所のドキュメンタリーである。戦時中の軍需工場での労役や空襲で亡くなった方の遺体処理まで囚人が駆り出された実態や軍国主義の下での監視体制などが詳しく書かれている。 網走刑務所の囚人は氷点下30度の冬でも暖房なしで眠った。それでも脱獄は少なかったと言われている。一般市民のほうが食糧事情が悪いうえ戦時中は健康な男性が外を歩いているだけで目立った。しかし、この本の主人公は戦時中も2回脱獄している。普通では考えられない方法で手錠をはずし3メートルも上にある窓から逃走している。その執念は看守に対する憎しみとしか考えられない。終戦直後、札幌刑務所を脱獄、これが4回目である。札幌郊外を転々とし鉱山に潜んでいたこともあった。 計4回の脱獄のあと府中刑務所の所長と心が通じ合い人間らしさを取り戻していく姿は素晴らしい。子供のころ、私の周囲には戦争を語る人が居なかった。戦争よりも開拓の苦難のほうが大きかったのだろうと思う。戦争の悲惨さは大人になってから小説やドラマや報道で知ったことがすべてである。この本を読むきっかけは網走監獄博物館で見た脱獄囚の人形と「破獄」という題名がすぐに結びついたからだ。しかし、読み進むうちに今までとは全く違った視点で描かれた戦争の悲劇に驚くばかりであった。
0投稿日: 2017.01.26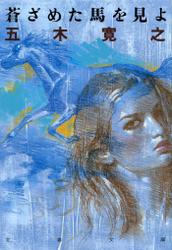
蒼ざめた馬を見よ
五木寛之
文春文庫
ソビエト…スパイ…意外な結末
短編5篇。直木賞受賞の表題作「蒼ざめた馬を見よ」は群を抜いている。新聞記者の鷹野は上司に呼び出されて突然「この社を辞めてもらえまいか」と言われる。終戦から20年、ユダヤ人の暗い真実を描いた小説を出版したい。だがソビエトの体制下では出版できない。原稿をソビエトから持ち出してほしい。そのために新聞社と無関係な人間になれというのだった。言論の自由をポリシーとする鷹野はのめりこんでいくが意外な結末に。スパイ小説は現実離れしていて面白いと思っていたが「サイバー攻撃が珍しくない時代になったな」などと考えながら読了。
0投稿日: 2017.01.26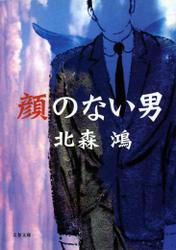
顔のない男
北森鴻
文春文庫
久々に手ごたえのあるミステリーを読んだ。
トリックは出尽くした感がありミステリーを読む楽しみはもうないのだと思っていた。しかし、本書はトリックではなく構成の上手さという面で謎解きの面白さが堪能できる。大ドンデン返しというほどの結末ではないが騙されないように注意して読み進める必要がある。最後はこの人が犯人でなければこの人かという消去法になってしまったのが少し残念。被害者が交友関係なし、恋愛対象なし、周辺住民との接点なしで調べても調べても何も出てこない「顔のない男」という設定がまず面白い。
0投稿日: 2017.01.26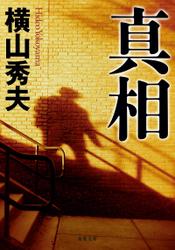
真相
横山秀夫
双葉文庫
「真相」は時として残酷だ。
重い過去、重い秘密を抱えてしまった人々を描いた何とも切ない短編5篇。息子を殺した犯人が10年たって捕まった。犯人の供述から息子の別の顔が明らかになっていく。これは父親の立場で読むか、母親の立場で読むかで大きく読後感は変わってくると思う。父親は「息子は被害者なんだ」と周囲に怒りをぶつける。母親は「だからって、あの子があの子でなくなる訳ではない」というふうに考える。私はやはり母親の考えに共感してしまった。
1投稿日: 2017.01.26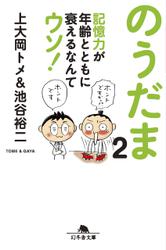
のうだま2 記憶力が年齢とともに衰えるなんてウソ!
上大岡トメ,池谷裕二
幻冬舎文庫
この本は啓発書と違い脳科学の立場で説明しているので理論的に納得できる。素晴らしい。
記憶力は衰えない。大人は子供より記憶の貯蔵量が多いので探し当てるのに時間がかかる。そのうえ勉強が仕事だったころと比べると日々の勉強量は減っている。大人になるにしたがって何でも簡単に片付けてしまって感動も好奇心も薄れる。このような理由から年齢と物忘れは結びついてしまう。全く返す言葉もございません。結局は「尊い好奇心を失うな」ということなのだ。ということは次々と読みたい本が出てきて積読本が増えるのも良いことなのだ←自己弁護です。
1投稿日: 2017.01.26
shohjiさんのレビュー
いいね!された数34
