
創価学会と平和主義
佐藤優
朝日新聞出版
佐藤氏による創価学会研究
集団自衛権行使の閣議決定が公明党により、どの様に骨抜きにされたのか?また、その公明党及び創価学会の思想・教義の中に、どの様な歴史的な背景が有り、平和主義が育まれ、今回の動きとなったのかが、丁寧かつ簡潔に述べられている。宗教としての創価学会の今後、記号としての「池田大作氏」、救済宗教としての役割と、公明党の中道左派としての脱皮・躍進の可能性等が、好意的に書かれている。根源には、佐藤氏のキリスト教信者としての、創価学会に対する共感が有ると言うのは言いすぎか?ただ「公平」な立場で創価学会・公明党を理解するには、最良の書である。
1投稿日: 2015.04.05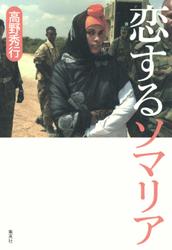
【電子特別カラー版】恋するソマリア
高野秀行
集英社文芸単行本
ソマリアの草の根レポート
日本にはなじみの無い、ソマリアと言う地域を理解する上では、必読の書。国家としての政府の崩壊した現状と、古くから残る氏族社会と言う形で保たれている最低限の秩序が興味深い。本書の作者が、生活者としての視点を重要と考える民族学的なアプローチが、ソマリア人の深層を理解する上で有効に作用している。地政学的に、アフリカとアラブの文化の衝突地点として、過去イギリス・イタリアの植民地であった同地域が、徐々にイスラム化されており、意識としてイスラムを西欧文明を高位に置いていると言う部分は感慨深い。
3投稿日: 2015.04.05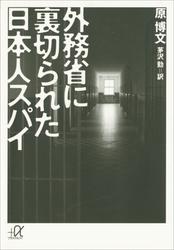
外務省に裏切られた日本人スパイ
原博文,茅沢勤
講談社+α文庫
日本のインテリジェンスの実態
残留孤児二世が、外務省の依頼にて、中国政府の情報収集活動に従事、最後は中国政府の知るところとなり、北京出国間際で逮捕され、有期徒刑の判決が下る。名前は、実名で書かれており、非常に面白い。中国の拘置所、監獄の具体的な状況や監獄の状況がとても詳細に書かれている。筆者は、中国育ちである為、コミュニケーションには不自由は無かったと思われるが、他の外国人の場合にはかなり厳しく、場合によっては精神的な面がやられてしまうのもうなずけた。 中身自体は軽く読めるので、日本の中国に対するインテリジェンスの実態を知る上では基礎資料として参考になる。
1投稿日: 2015.01.11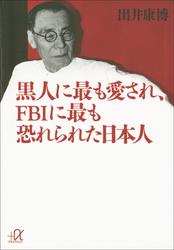
黒人に最も愛され、FBIに最も恐れられた日本人
出井康博
講談社+α文庫
明治の若者達のアメリカでの生き様が描かれていて面白い
丁寧な取材を元に、アメリカ大陸の日系移民の姿を掘り起こし、アメリカの過去の人種差別の状況を元に、中根中 氏の黒人解放運動への係わりを描いている。ビンラディンよりFBIが恐れたかどうかは別にして、同氏を含めた一部の日本人が黒人解放運動を利用し、黒人も日米関係を利用した、相互の利害の一致した局面が戦前にあった事は非常に興味深い。また、志を持った明治の若者達が、外人宣教師の布教を通じたアメリカへの夢を持ち、渡米するが、その後、白人優位の現実を見て失望した後、どの様にその人生の方向性を変えていったのか、その生き様、時代に翻弄される様が数多く描かれていて、とても感動的である。
1投稿日: 2015.01.04
資本主義の終焉と歴史の危機
水野和夫
集英社新書
行き詰った資本主義の現状とその処方箋
資本主義の行き詰まりの原因、国家機能の喪失、民主主義という政治体制の終焉等、先進国からの観点でかかれている。特に、日本は1990年初頭のバブル崩壊以降の経済政策の迷走により、他先進国に比べてよりその行き詰まりが突出しており、その意味で、現在の資本主義の解消、新しいシステム構築の先駆者になれるのでは、との期待を筆者はしている。少なくとも、今行われているアベノミクスに関しては、プライマリーバランスを損ない、その行き詰まりを更に深刻化しするだけで、実効性は全く無いとの立場を取っている。今後の引き金は中国での過剰生産設備のバブル崩壊と予言しているが、そうなれば冗談では済まされまい。
3投稿日: 2014.12.28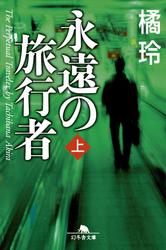
永遠の旅行者(上)
橘玲
幻冬舎文庫
素直に、読み物として面白い
素直に面白い 縦糸に税制、横糸に物語。物語自体は兎も角、これにタックスプランニングを加える事で、非常に興味深いケーススタディとなっている。プライベートバンクや、国税当局とのいたちごっこ等、本当の世界を垣間見る事が出来、現実性と、非現実性の間で、読み物としても面白く、また気が抜けない展開となっている。書かれた時期は若干古いので、現在そのまま適用する事は出来ないと思われるが、それでも考え方自体は変わっていないのではと思われる。
1投稿日: 2014.12.28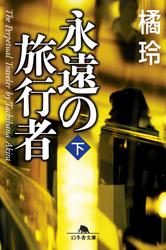
永遠の旅行者(下)
橘玲
幻冬舎文庫
素直に面白い
縦糸に税制、横糸に物語。物語自体は兎も角、これにタックスプランニングを加える事で、非常に興味深いケーススタディとなっている。プライベートバンクや、国税当局とのいたちごっこ等、本当の世界を垣間見る事が出来、現実性と、非現実性の間で、読み物としても面白く、また気が抜けない展開となっている。書かれた時期は若干古いので、現在そのまま適用する事は出来ないと思われるが、それでも考え方自体は変わっていないのではと思われる。
2投稿日: 2014.12.28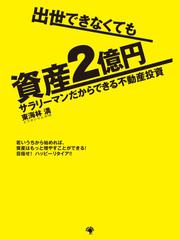
出世できなくても資産2億円 サラリーマンだからできる不動産投資
東海林満
ゴマブックス
内容はとっても正直だが...
さっと、読めました。 フルローン 15000万円の借金をして、入居率 85% での税引前 手取りが 360万円。 築年数 15年 / ローン 30年 / 金利 2.5% / 満室時表面利回り 11% / 経費 売上 x 20% の計算となっている。 どれだけ償却が取れるか判りませんが、ざくっと残り30年建物=銀行ローン期間と一緒。 返済には、土地も込みとすると、土地代/30+360万円/年が資産増も含めた手取りと言える。 リスクは、空室や資産デフレや金利増等、500万強の収入の為に、1億5千万も借金して リスクに見合ったリターンが取れているのかと言うと疑問。 金利がノンバンク等の高利ローンであると、ほぼチャラになるので、つきつめると、会社員 の時の与信(低金利)を利用して、足元利益が出ているに過ぎず、真の意味で、「サラリー マンだから出来る不動産投資」と言える。 不動産投資の構造を見る上では、非常に参考になるが、これで不動産投資を考えるのは危険。 語弊を恐れず言うと、ローンで家が持てない貧乏人が、資金の有り余る金持ちに家を建ててもらって住み、 その対価として家賃を払うビジネスで、いわゆる金持ち(土地持ち)の余剰資産の有効活用の側面が強い。 そこに、与信が高いサラリーマンが「鴨葱」で入っていくのは、業者に食い物にされ、資産下落時に(Loan to Value に引っかかり)銀行の貸し渋りに遭い、身ぐるみ剥がされて、マーケットから退場させられるのがおち である。 この著者の実際の不動産は、利回りは更に良いものの、北海道にあるらしい。本当に大丈夫?? この著者も含めて、大きな借金をして、不動産で Cash Flow を得ていると豪語している人が10年後、どう なっているかを見てみたい。
3投稿日: 2014.11.23
知的幸福の技術 自由な人生のための40の物語
橘玲
幻冬舎単行本
自由主義・国家の役割・個人の経済的合理性
本自体は、2004年と10年前に書かれたもの。5年後に若干の書き直しはしているらしい。とは言え、2014年の現在に有っても、全く古さを感じさせないし、むしろより問題点がハッキリしてきたとも言える。政治が10年前の問題を全く解決出来ず、むしろより一層深刻化している事が判る。海外との対比を行いながら、民主制と自由主義の相容れない政治体制の中、悪い部分が増幅している事を説得力を持って、綴っている。筆者は、極論も多く、実行不能な論も少なくないが、この極論を提起しなければ、現在の問題を解決出来ない事も、よく判っており、その上での極論だと思われる。経済的な面でも、示唆が多く、大きな流れを見て今後の投資方針を決める上でも、良書と考える。
1投稿日: 2014.11.23
消されゆくチベット
渡辺一枝
集英社新書
中国の少数民族の運命について
筆者が長く取り組むチベットについて、その定点観測を通じて、チベットがどの様に変わってきたのかが書かれている。中国の経済力が増す中、チベットへの飴と鞭の政策も強化され、現在では少数民族のアイデンティよりも中華人民共和国を構成する国民としての一体感を持った教育が重要視されると共に、固有の宗教への圧力も強まっている事が描かれている。また、鉄道の開通による漢族の流入や西部大開発の影響も大きく、孤立した地域が、北京中央と一体化していく様子が分かりやすい。 ゆるぎない実効支配の下、今後のチベットがどの様になっていくのかは、非常に興味深いが、独立は難しい事は明白だ。
0投稿日: 2014.11.09
kurosukeさんのレビュー
いいね!された数56
