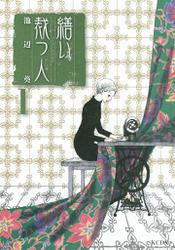
繕い裁つ人(1)
池辺葵
Kiss
唯、あなたのためだけに生まれ死にゆく服をつくるひと。
静かにミシンをふみ針を進める洋裁店の店主と、彼女に服を求めてやってくる人々との、どこか絵画的に静かな物語。その素朴で優しくどこか寂しげな空気に、フェルメールの絵画「レースを編む女」を思い浮かべます。 職人肌で頑固ジジイな女店主。職人モノ、というそれだけでもう好きになりそうなんですが、採寸し、服をつくるに至る背景を紐解き、裁断して、そして卸した服を着るまでの一連の流れが丁寧にゆるゆると描かれていてたまらない。それぞれが抱える物語はありふれたものなんですよ。だけでも飽きずに静かに見守りたくなる。 最初、表情のつけ方がとても淡白な描き方だなぁと思ってたんですが、物語に没入すればするほど、味わい深いというか、仕草や行間に目が惹かれる気持ちになります。不思議。
9投稿日: 2015.01.06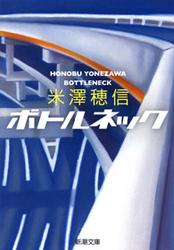
ボトルネック(新潮文庫)
米澤穂信
新潮文庫
ただ思うのは、それは諦めに慣れない若さ故の絶望なのだと。
亡くなった恋人を偲びに東尋坊を訪れた「ぼく」は、断崖から墜落した・・・はずが、気づくと見慣れた街にいる。しかし自宅には見知らぬ「姉」。その姉と共に過ごすうちぼくが見せつけられた残酷な「IF」の世界とは。あり得たかもしれない「可能性」と実際あった「現実」が逆転する、どこまでも苦い青春パラレルミステリー。 著者が「最後の一撃(フィニッシング・ストローク)」をテーマに書いた作品には短編連作の「儚い羊たちの祝宴」がありますが、こっちは長編な分ズドンと衝撃と余韻の残る一撃。 選んだ未来が必ずしも正しい訳はないはずで、それでもなんとか進めるのは、やり直せない「たられば」が実際にどうなったのか分かるはずがないからこそ。にもかかわらず、「最適解ばかり選んできた姉」視点で、選べなかった/選ばなかった選択肢の行方を見せつけられる主人公。畳み掛ける伏線と回収劇、それが収束してラストに現れる主人公の絶望と決意が、予測はつくのに救いを求めて頁を繰る手が止まれない。
13投稿日: 2014.12.13
多眼思考
ちきりん
大和書房
答えを探すためではなく、思考するために読む。
群盲象を評す、という寓話があります。真実は多様であり、一方面だけを切り取ってそれをすべてと思うのはいけない。何かを知ろうと思ったら、多方面から知らなければ本質には近づけないのだと。とても納得の教訓です。 そんな訳で、Twitterの呟きからいろんなテーマにおける思考プロセスを抽出して、多角的に社会派ブロガーちきりん氏を知る本です。一言で言うなら本人編集によるTogetterまとめ。本当にTwitterから抜粋しただけなので、良くも悪くもちきりん氏に興味がある人じゃないと楽しめないのは言うまでもない。個人的には「小説家になろうの書籍化」的ファン買いに近いとも言えます。 なんて言いつつも、140字の制約が余分なものを削ぎ落として、ほぼ本質のみになってるのもきっとその通り。省かれた説明分、行間を想像して自分で思考する感じの読み物です。自分のTwitterのアカウントを開いて、呟きながら読むのが正しい読み方ですよきっと。
2投稿日: 2014.12.12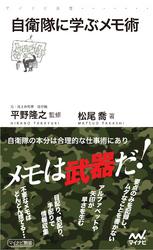
自衛隊に学ぶメモ術
松尾喬,平野隆之
マイナビ新書
メモ取り下手さん必見の、明日から使える自衛隊式メモ術。
議事録を起こそうとメモを読み返したら、何が結論か頭を抱えたことはありますか?板書を必死に写していたら、先生の話を聞き逃した経験は?そんな、メモが早く取れない、正確に取れないという全ての人に贈る、即効性高めな自衛隊式メモ術の本です。 有事の瀬戸際で正確で迅速な判断が求められる自衛隊だからこその「正・早・安・楽」(=正:ミスの最小化、早:スピードアップ、安:安心とコストダウン、楽:もっと楽に出来ないか)なメモ術+α。実例がセットで覚えやすく、文中の自衛隊のエピソードも興味深いです。 「情報が生命線」な現場で培われた、記号や数字、HND法(母音を抜いた表記法。例:HaNeDa(羽田)=HND)を駆使し、短く正確にメモする技術は、普通の企業でも新人さんには即効性高め、ベテランも目から鱗があるかと思います。「2014年12月7日日曜=141207 SU」の日時表記とか、当たり前なのにやってなかったです、自分。
17投稿日: 2014.12.07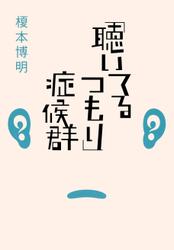
「聴いてるつもり」症候群
榎本博明
集英社ビジネス書
言った言わない水掛け論への処方箋。
言った、言わない、聞いてない。 ビジネスでは二度三度どころか百度は出くわす水掛け論。トラブルの八割はこれが原因なので、まともな人なら三度目あたりの失敗で文書主義に趣旨変えしてると思われます。自分も上司に「聞いてないよ!」と梯子外され、鞍替えした一人。 そのくせ自分も、時折「聞いてないよ」が喉から出かかることがあり、興味深く「聴いてるつもり」のメカニズムと処方箋を読みました。知ってるつもりになりがちですが、受動的な「聞く」と能動的な「聴く」は違うのですよね。聞き流したりせずに、相手に意識と興味を向けるのが「聴く」ということの難しさ大切さ。 最近は「聞く力」として頷きやミラーリングをスキルとするビジネス書もありますが、本書ではこうしたスキルも中身が伴わないと「聴いてるつもり」と同じだと言ってます。誠意のない頷きに意味はないと。そんな訳で、ミイラ取りがミイラにならないようにも気をつけたいな、と思う今日この頃です。
10投稿日: 2014.12.02
なんでコンテンツにカネを払うのさ? デジタル時代のぼくらの著作権入門
岡田斗司夫,福井健策
CEメディアハウス
キュレーターやバイラルメディアが儲かる世の中で、著作権の意味を考えている。
著作権の未来に関する、ある思考実験の話。著作権はなぜ生まれたか、今どう作用しているか、その課題は、からはじまり「今の著作権法の守り方はジリ貧」なので代替手段を考えよう、という対談もの。 思考実験の中心は、現在の著作者が権利を管理する方式から、フリー化して、ファンからスポンサーを募る(岡田氏)/利用料から一定率を還元する(福井氏)方式。いずれもその方がコンテンツが流通しやすく、著作者も世にコンテンツが知られやすく、ユーザーもコンテンツを使用しやすくなるだろう、という。著作権法は変わっていくべき、は両者一致しても、そもそも著作権で守るべき対象、が両者違っているのが面白い。 後半は日本のコンテンツ戦略や米国のプラットフォーム覇権まで扱ってます。日本鬼子(ひのもとおにこ)やヘタリアを、日本の戦略として「冴えたやりかた」と呼ぶのはとても納得だしもっと広がれば良いと思う。
5投稿日: 2014.11.13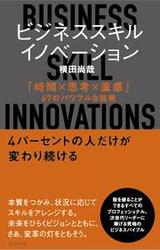
ビジネススキル・イノベーション 「時間×思考×直感」67のパワフルな技術
横田尚哉
プレジデント社
時間を置いて読み返したいビジネス書というのも珍しい。
言わずと知れたビジネススキルの名著。「ビジネス書大賞2013年」入賞ですしね。当時、紙で購入して衝撃を受けつつ「今後ビジネススキルの執筆者はやりづらくなるなー」と思うくらいには、色褪せにくい体系的かつ本質的なスキルの本。 電子書籍で再読ですが、当時とは違った箇所が目を惹かれて面白い。昔は「仕事には想定の1.4倍の時間がかかる」「知的熟成の時間を持て」「ルールはマニュアルに、モラルはガイドラインに」辺りに感動したのですが、今は「根回しはインパクトを和らげるために行う」や「感性でジャッジし、論理的に検証する」に薫陶を受けます。特に後半の「感性でジャッジする」については、前後の文脈含め「当時の自分はなぜここを面白いと思わなかったんだろう?」と不思議になるくらいです。言い換えればデータを信頼するな、データで信頼させろ、になるのかな。 一旦読んだ方も、知的熟成した今一度、再読はいかがですか。
4投稿日: 2014.11.09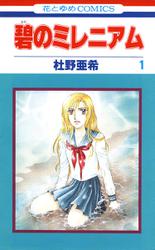
碧のミレニアム 1巻
杜野亜希
別冊花とゆめ
少女マンガ的歴史トリップwith仲間集めin戦国(中国四国)がツボを突く。
謎解き要素と仲間集め要素を合わせつつ少女マンガ的心の揺れも織り込んだ、少女マンガ的戦国時代タイムスリップもの。 自分の中では、上田倫子の「リョウ」とこれで迷って、結局「碧のミレニアム」を押す訳ですが、理由の一番は、華やかな関東関西を避けつつ、陰に隠れることの多い中国四国、村上水軍とか毛利家とかのワードがドツボだからと思ってます。小早川隆景がメインで出てくるとか、トキメクる。それに、里見八犬伝的に鈴を持つ運命の人たちが集う展開とか、皆が慕う鶴姫にどこか似た主人公とその謎とか、定番を手堅く書くのがとても好き。 ちょっとだけ、後半の駆け足展開にもにょる部分もあるんです。でも、ミステリも描く漫画家さんだけあって、伏線バラまいて回収の謎解き感が味わえてそれはそれで好きだったりする。
3投稿日: 2014.11.08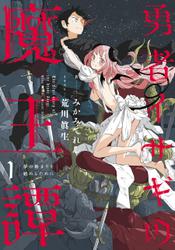
勇者イサギの魔王譚1 夢の始まりを始めるために
みかみてれん,荒川眞生
ホビー書籍部
「小説家になろう」的王道ど真ん中で、匠の技も光る異世界冒険譚といえば、
「小説家になろうといえば、王道設定をアウトローにチーレムするのが定番」の、ど真ん中ストレートを突いた小説がこちら。召喚勇者な少年が、20年後の世界に魔王候補として再召喚、初恋の少女に会いたい一心でゼロスタートを切る冒険譚。 WEB版からの設定変更多めで、具体的には主人公弱くなってます。中二病度も上がってる。なのに、そのギャップが却って、ピンチにおける主人公の格好良さを際立たせ、熱さの温度を上げてます。やっぱり勇者は弱いから勇者たり得るのだと再認識。最初から強くてもねー。 あと、プロローグとラストの魅せ方がずるい!否が応にも盛り上がった直後に過去話挿入とか「泣くよね?切ないよね?」と強制されてるみたいで本当に卑怯だと思う。もちろん泣きます。WEB版も面白かったのに、書籍版は「一冊の本」前提に練り直され、とても読み易くなった感じです。「WEB小説の書籍化」手法的にも匠の技が光ってて好き。
7投稿日: 2014.10.27
30歳キャリア官僚が最後にどうしても伝えたいこと
宇佐美典也
ダイヤモンド社
根回しの神髄とその難しさをキャリア官僚の回顧録的な中から垣間見る。
東大卒・経産省キャリアが「三十路の官僚のブログ」で給料を公開して話題騒然に。そんな著者が民主党政権末期の2012年半ば、経産省を退職直前に書いた本です。 前半で不覚にも泣いた箇所があるのですが、著者が官庁訪問で入省を決意したくだりで、「尊敬できる先輩ってどんな人ですか?(著者)」→「信頼を持ちながら、相手に不利な条件を呑ませられる人かな(面接官)」。次の章で「最終的には『すべての関係者が平等に不満を感じる』程度の落とし所を慎重に見定め」るのが必要と言い、その後続く壮絶な省庁間折衝の話とか、根回しの神髄を見た気がします。そんな訳で、自分的一番のハイライトはここ、根回し力でした。 本文中で引用される文章や経験談が素晴らしく心に刺さる&響く内容で、誰かのために何かしたくなります。あと、優秀な個人も組織では〜、の難しさはどこもあるのだなぁと。船頭多くして、が故事として今に伝わるくらいですしね!
7投稿日: 2014.10.26
三森雪さんのレビュー
いいね!された数893
