
古代オリエントの宗教
青木健
講談社現代新書
東 方 の エ ヴ ァ ン ゲ リ オ ン
目次を開くとまず強烈なパワーワードが目を引きますが、「オリエント」における「福音(書)」の受容、あるいは否定が本書の主題なので、間違いではありません。 旧約聖書を否定したユダヤ人のマンダ教から始まり、真なるキリスト教を自称したマーニー教(マニ教)、ゾロアスター教、イスラム教イスマイール派、シーア派など、二世紀から十二、三世紀くらいまで(あまり古代ではない)オリエントで興隆しては衰退した(どちらかといえば)マージナルな宗教の特徴を、『旧約聖書』、『新訳聖書』、『クルアーン』、それぞれの受容とグノーシスの影響から論じています。 新書ということもあり、同じ著者の講談社メチエの本と比べると、かなり取っつき易くなっています。その分、各宗派の詳細や複雑怪奇なグノーシスの解説などは少なめになっており、興味のある方はそちらをどうぞ、ということなのでしょう。 入門書としてはかなりお勧めですし、各論を読んだ後に全体的な関係を把握するために読むのも良いと思います。
0投稿日: 2017.12.22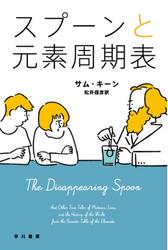
スプーンと元素周期表
サム キーン,松井 信彦
ハヤカワ文庫NF
ノーベル賞狂想曲
元素の性質だけでなく、新元素発見に奔走した科学者やノーベル賞選考にまつわるあれこれのエッセイです。面白いけど、やや話があちこちに飛び過ぎという印象。科学エッセイというより、科学者エッセイですね。
0投稿日: 2017.12.16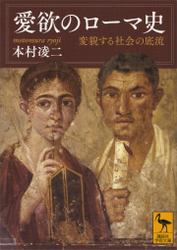
愛欲のローマ史 変貌する社会の底流
本村凌二
講談社学術文庫
むしろ夫婦観、家族観の変遷
元々は『ローマ人の愛と性』いうタイトルで講談社現代新書から出ていた本が文庫化(講談社学術文庫)の際に改名されたものです。どちらのタイトルもやや誤解を招く、というか、前半の内容しか反映していません。 古代ローマ人の欲望から始まり、愛情へとタイトル通りに論は進むのの、そこから先は家族、道徳、心性へと更に議論は進んでいきます。あまりエロ目線だと、後半はついていけないかもしれません。
0投稿日: 2017.12.07
比較史の方法
マルク・ブロック,高橋清徳
講談社学術文庫
1928年の講演記録
アナールの雄、マルク・ブロックが1928年にオスロで開かれた学会のおいて行った講演の内容を纏めたものとのことです。「ただ闇雲に比較すればいいってものじゃないよ。金枝篇は良い比較」というのがおおまかな内容になります。金枝篇、読んでる前提かよ。 本書は特に優先度の高い本という訳ではありませんが、100年近く前の講演にもかかわらず、アナール系の、特にフランス人研究者による中世史の本などで時々言及されています。短くて比較的分かり易い(同じ著者の他の文献に比べ)ので、その辺の文献をよく読まれるというのであれば、読んでおいた方がよいかもしれません。
0投稿日: 2017.12.05
アーリア人
青木健
講談社選書メチエ
中級者向け中東・中央アジア史
イランという国名が「アーリア」から来てるって知ってました?恥ずかしながら、私は知りませんでした。 本書は紀元前8世紀頃から20世紀のイラン革命まで、「アーリア系」民族の分裂と栄枯盛衰を概観しています。ここで言う「アーリア系」とはざっくりペルシャ系と考えてそれほど外れはないと思います。本書のタイトルだけ見ると誤解しそうですが、20世紀前半、盛んに喧伝された「アーリア人種」概念については本書の主題ではありません。一応、なぜそんな風にとらえられたのかは、少しだけ解説はされています。またコナン・ザ・グレートでお馴染みの「キンメリア人」についても初期に分かれた(そしてすぐに消息不明になった)一派として少し出てきます。しかし、本書の主なテーマは中央アジアから中東にかけて興亡を繰り返した諸民族の歴史になります。非常に広い範囲の時代・地域を扱うため、読み手に或る程度の基礎知識が必要となります。中東史の入門書として手に取ると、ちょっと厳しいかもしれません。 基本的な流れを抑えた上で、紀元前から現代に至る騎馬民族の一大派閥の歴史を紐解きたい、という中級者の方におすすめです。
0投稿日: 2017.12.05
昨日までの世界(下)―文明の源流と人類の未来
ジャレド・ダイアモンド,倉骨彰
日本経済新聞出版
三部作完結編?
『銃・病原菌・鉄』、『文明崩壊』に続く三部作?完結編です。『若い読者のための第三のチンパンジー』で提示された論点は上記二作と本書で網羅されたはず(多分)。 前の二作と比べると、著者の文化人類学者としての側面が前面に出てきており、フィールドワークでの体験やそこからの気付きに基づく内容も多く、学術的でないとまでは言いませんが、あまり硬い感じではありません。むしろ取っ付き易いです。前作を未読の方でも問題ないどころか、むしろ本書から入ってみるのがよいかもしれません。
0投稿日: 2017.11.04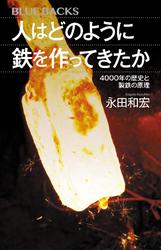
人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理
永田和宏
ブルーバックス
実験・フィールドワーク中心
タイトルの通り、歴史的な製鉄法(材料の入手も含む)中心の内容です。著者が実際に実験してみた内容やフィールドワークが充実しているのが特徴。反面、分子構造の変化などは文章での説明では分かりにくく、他の本と併せて読むのが良いかと。
0投稿日: 2017.09.26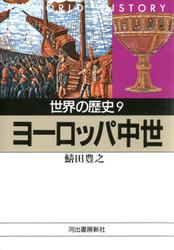
世界の歴史〈9〉ヨーロッパ中世
鯖田豊之
河出文庫
一般(非専門)向け通史
出版されてからかなり時間が経ってはいるが、一般向けの概説ということもあり、内容にそこまで古さは感じられない。文体はあまり硬くなく、初学者、専門外の人でも分かり易いように意識して書かれている。古くなった文庫版より文字がはっきりしており読みやすいが、タブレットなど大型端末での閲覧がおすすめ。
0投稿日: 2017.09.26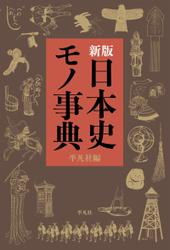
新版 日本史モノ事典
平凡社編
平凡社
知らないモノを調べるために
百科事典からピックアップされた日本史関連の挿絵4000点。索引はついているものの、好きな分野を最初から順に眺める方がおすすめです。説明は短い簡易版なので絵で見て、名前を知るところまでが本書の役割で、あとは自分で詳しく調べるのがよいかと。
0投稿日: 2017.08.21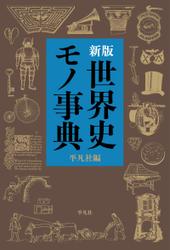
新版 世界史モノ事典
平凡社編
平凡社
百科事典の挿絵をピックアップ
平凡社の百科事典に記載されていた図版を中心に3000点ほどを収録。文字情報だけだと分かりにくい事柄が良くわかります。項目数3000と考えると、事典としては少ない気がします。調べたいと思ったことがたまたま載っている確率は低いので、割り切って興味のあるテーマごとに順ぐりに読んでいくのが良いと思います。物理書籍版は2800円で400円ほど差がありますが、見開きの図などもあるため、見やすいのは物理版。大きめのタブレットなら電子版でも大丈夫かと。
0投稿日: 2017.08.09
iciさんのレビュー
いいね!された数95
