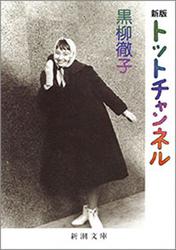
新版 トットチャンネル(新潮文庫)
黒柳徹子
新潮文庫
テレビ黎明期の忘備録
昨春NHKにて公開されたドラマの原本である。テレビ黎明期の物語である。この視点の新しさは彼女の個性もあるが、この世界に長年いても流されず、業界の慣習に飲み込まれなかった彼女の意思の強さが明示させたと思われる。永六輔氏や大橋巨泉氏が亡くなり、この時代の生き証人であり語り部となる人が少なくなった今だから楽しめる一冊であった。 様々なエピソードは、楽しめるものであったが、出版した当時には支障のあるものもあったので、登場人物を匿名にしていたが、歴史公証と捉え実名に敢えて替えても良かったのではないかと思われる。
0投稿日: 2017.03.08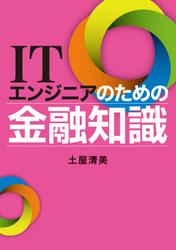
ITエンジニアのための金融知識
土屋清美
日経BP
金融系SEの読むべき基本情報
私は金融系のSEではないが、金融システムには興味がある。なぜなら、金融システムはリスクの宝庫だし、リスクをどうコントロールするかが命題のシステムだからである。 また、ブラック=ショールズの公式のなんと美しいことかと魅了されるのは、数学マニアだけではないだろう。この本は、そうした金融システムの基本的なバックグランドから、最新の国内システムの開発状況を網羅しているが、国際金融システムがどうなっているかまでは触れられていないので、少し物足りなさを感じる。とはいえ、金融システムの基本知識を習得するにはお勧めの本である。
0投稿日: 2017.02.27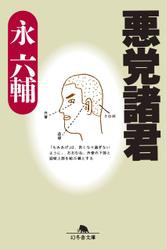
悪党諸君
永六輔
幻冬舎文庫
七夕に星を見上げて
著者が亡くなったことは、私にとって昨年のエポックメーキングであった。小学生の頃、彼と同じ病であるパーキンソン病で亡くなった母が良く彼のラジオを聴きながら、手仕事をしていたのを良く覚えている。著書と母は同学年ということも有り、良くラジオを聴いていたものであった。なので、その横でなんとなく聞いていた私も彼のファンとなり、中学・高校生の頃には、彼が出演する深夜放送やエッセイを読んだものであった。 この本は、彼が生前に全国の刑務所に慰問してきた際の講演をまとめたものであるが、良くテープが残っていたものであると感心するとともに、彼の人生哲学が滲み出る話しの内容であった。亡くなる数年前から、彼が出演していたラジオで何度か聞いたことのある話もあったが、改めて文書で読み見返すと感慨深いものがあった。
2投稿日: 2017.02.15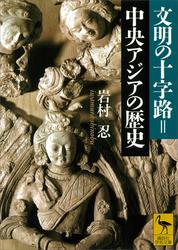
文明の十字路=中央アジアの歴史
岩村忍
講談社学術文庫
オリエントの風を感じたくて
西アジアに興味を持ったのは、井上靖、司馬遼太郎のエッセイに惹かれたのと、NHKのシルクロード、世界史の授業での混沌として切貼りだった内容を整理したい欲求に駆られてである。東西のトルキスタンとペルシャ(イラン)、モンゴルに伸びる広大な大地に跡形もなく消滅した文明にはロマンが漂い、映画や冒険小説の舞台としても華がある。しかしながら、ここの歴史を語る文字が無かったために、細部は良く分からない世界であることは間違い無い。なので、一度読んだだけでは、全体像が分からない。特に、人や町の名称が複雑過ぎる、中国名、ペルシャ名、トルコ名、モウコ語、それらの亜流が輻輳するので同じ町の名前がいくつも存在し、いったいどこのことかと地図を片手に読み進むのには苦労した。 入門書としては、ちょっと難しいと思われるので、もう少しコナれた本を読んでから、読むことをお勧めする。久保田早紀や庄野真代の世界観を感じることは出来なかったが、ロシアが南下してきた背景や歴史については、よく理解出来た。
1投稿日: 2017.02.15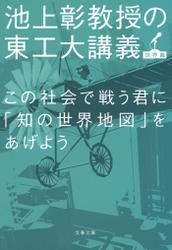
この社会で戦う君に「知の世界地図」をあげよう 池上彰教授の東工大講義
池上彰
文春文庫
理系学生は、世の中とズレていると言われないために、この本を読みましょう。
東工大講義集の3部作の最初の本である。とかく、理系学生はオタクだと思われ、世間とのズレがあると誤解されがちであるが、その誤解を払拭するためにも、池上さんからの問いに答えられる人になりましょう。 また、理系だからと言って、歴史から目を離さないで欲しい、戦後70年を過ぎて、戦争が風化されつつある中で、歴史への興味を持つことが近隣諸国との関係性の基本を理解することに繋がることを池上氏は学生に伝えたかったのではないだろうか?
1投稿日: 2017.01.24
データサイエンス超入門 ビジネスで役立つ「統計学」の本当の活かし方
工藤卓哉,保科学世
日経BP
確かに入門書でした
データサイエンスの概要と、技術者として何を目指すべきなのか、どう向き合えば良いのかを解説している入門書であった。この分野は、流行の職業でもあるが、日本には馴染み慣れない分野、文化であると感じているので、この様な啓蒙的な書籍が広く読まれることに期待したい。一次のブームに終わらせたくないし、バズワードに成らないことを期待したい。
0投稿日: 2016.11.28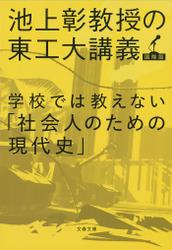
学校では教えない「社会人のための現代史」 池上彰教授の東工大講義 国際篇
池上 彰
文春文庫
3部作を読破する
東工大講義3部作を読破した。基本的には、テレビで解説されている内容を繰り返しているに過ぎないが、普遍的な問題を掘り下げているので、社会情勢や近代史を復習するには良書と言える。 学生の社会性を育む教科書としては最適なのではないかと思われる。
1投稿日: 2016.11.12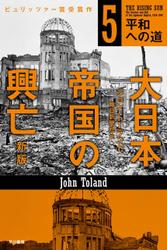
大日本帝国の興亡〔新版〕5──平和への道
ジョン トーランド,毎日新聞社
ハヤカワ文庫NF
日本のいちばん長い日
硫黄島、フィリピン、沖縄からの撤退、広島、長崎、終戦に向けた模索とマッカーサー上陸と一気に駆け抜けた一冊であった。いちばん長い日は、あっさりと過ぎてしまった感がある。一応、当初の目的は達したが、物足りなさを感じるのはなぜか?広島・長崎だけで一冊になっても良かったはずだし、終戦に向けた海外での活動ももっとあっても良かったのではないか?ソ連参戦とシベリア抑留に関しても知りたかったことは何も書かれていなかった。消化不良というよりも、物足りなさが残ったしまったのは、著者のせいではなく、歴史の重みのせいだろう。
0投稿日: 2016.10.28
あの日
小保方晴子
講談社
無知と無防備は悪か?
彼女を初めてテレビで観た時、この人はこれから他人の妬みと嫉みに苦労するのであろうと思ったが、こんなに早く現実化するとは信じられなかった。 予感があったのは、岸宣仁の「ゲノム敗北」やJ.D.ワトソンの「二重らせん」や「DNA」を読んでいたからであろう。 それにしても、ねつ造の新聞記者と数字地上主義のNHK記者には不快感を覚える。 確かに発端は、彼女の無知と無防備さによるものであるとは言え、ねつ造と歪曲とミスリードで公開処刑の様な状況を作り、煽る体質というのは、いじめ社会の典型であり、日本人特有の他人の成功を妬む体質なのかも知れない。 ポスドク成り立ての彼女に、自分の保身から上司である指導教官が、ここまで責任を押しつける神経が異常としか写らない。また、彼女が間違いを起こしたことは確かであるが、それを追及する方向があらぬ方向へ向かったのは、日本人社会のひずみかも知れない。このままでは、この分野もゲノムと同じ結果になることは明らかだ。 それにしても、彼女は強かった。褒めてあげたい。彼女のこれからの人生に幸のあることを祈ります。
1投稿日: 2016.10.06
図解 使える統計学
涌井良幸,涌井貞美
中経出版
統計の復習本としては最適でした
世の中、AIだ、ビッグデータだ、データサイエンストだとか、騒がれているので、統計学の復習のために拾い読みした。この著者の本は、大体3~4ページで1節(1テーマ)になっているので、必要なところから拾い読みするには最適な本でしたが、図表が各節の最後にまとまっているので、電子書籍の場合には操作が不便であった以外はベスト本ではないでしょうか? 復習するだけでなく、初心者にとっても分かりやすい本だと思います。
0投稿日: 2016.09.27
Starboさんのレビュー
いいね!された数11
