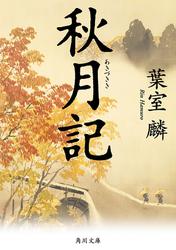
秋月記
葉室麟
角川文庫
清濁併せ呑まなければ、政というものは…
蜩ノ記が静とするならば、こちらは動と言うことが出来るでしょうか。剣を交えるシーンなど、手に汗を握ります。この作者の小説を沢山読んだわけではありませんので何とも言えませんが、どちらかと言えば「銀漢の賦」の系統と言っても良いでしょう。 舞台は、実在した秋月藩。そこで起きた出来事をダイナミックに描いた作品です。小気味よい描写と表現は流石であり、いったい何が起こっているのか、そしてこの先どうなるのかと、ページを捲る手は休まることがありません。友情、裏切り、暗躍する陰、誰が味方で誰が敵なのか、そして何が正義で何が悪なのか。誰かが汚れ役をひっかぶらないと、政は成り立たないのか?弱小藩を運営していくと言うことは並大抵なことではないですね。 主人公は、幼き頃、妹を死なせてしまったというトラウマに苛まれながら、清く正しく、そして強く生きることを望み、自分の信念を貫き、いつしか藩の中枢に位置するようになります。でも、それが本当に正しい生き方だったのか?そして、幸せな人生だったのか。これは誰にもわかりません。でも、自分だけは、納得できる一生だったのかな。「青田を渡ってくる風がさわやかだった」という一文でラストを迎えますが、さわやかさというより、どことなく寂しさを感じました。 どこからどこまでが史実なのかは解説がないのでわかりませんが、かなり読み応えのある時代小説であります。
8投稿日: 2014.10.26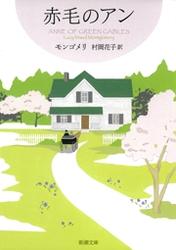
赤毛のアン―赤毛のアン・シリーズ1―
モンゴメリ,村岡花子
新潮社
今更ですが、恥ずかしながら初めて読みました!
私事ですが、我が生涯で最も多く本を読んでいたのは、小学校時代です。当時住んでいた市営の図書館で2冊、学校の図書室で2冊、子供会の図書室で1冊と、週に5冊の本を読んでいました。昼間は草野球に興じ、夜は読書。当時は子供向けのテレビ番組など、そうはありませんでしたし、テレビは親父が見るモノでしたしね。当然、学業成績は悪く、先生からは読書を控えさせるようにと親が言われたとか言われなかったとか。。。でも、そんな中でも、「赤毛のアン」は女の子が読むモノと決めつけていました。また、高校時代に児童文学に傾倒し、佐藤さとる等を読みふけったこともありましたが、それでもアンを読んだことはありませんでした。 今回遅ればせながら手を出したのは、勿論、朝ドラの影響です。で、読んでみて、正直、もっと早く読むべきだったと後悔しております。そして、朝ドラ「花子とアン」の台詞やエピソードのネタは、ドラマ冒頭からすべてここから引用されていることもわかりました。まだ1冊読んだだけですのでエラそうなことは言えませんが、ファンの方にとってあのドラマは、まさに「赤毛のアン」そのままだったんですね。 孤児だったアンがある人に引き取られ、初めて「家」というものを持ち、成長していく姿という設定そのものも、面白いのですが、特筆すべきは、その情景描写にあります。美しい自然の風景は勿論、普通、小説は心理描写に長けた媒体であると思うのですが、極端な話、この小説では、登場人物の表情の描写でその心情を描くという感じです。だから、アンの見ている景色や人々の表情まで、まるで目に見えるように展開します。つまり、読者は自然とその場の情景を想像できてしまうわけで、想像の翼を広げているのは、アンだけではなく、読者の方もということになります。これはモンゴメリがすごいのか、村岡花子の訳がすごいのか、なんて思っていると、どうしても原文に触れたくなる気持ちもわかります。 そして会話の部分が多いのも特徴です。ほとんどアンがしゃべっているんですけどね。兎に角、見るモノ触れるものすべて、この世は輝くモノに包まれているって感じがほとばしっているようで、確かに元気になれます。 しかし、まだ私は一冊目です。アンとの旅は始まったばかりであります。今後の展開が楽しみでなりません。 今回の本で一番印象に残った台詞は、朝ドラの中では朝市が言ったコトバです。「一生懸命にやって勝つことの次にいいことは、一生懸命にやって落ちることなのよ。」ま、朝ドラの中では「負けること」とアレンジしてましたけど、そこここに珠玉のフレーズが散りばめられている、児童文学というだけではもったいない、まぎれもない世界の名作でありました。
1投稿日: 2014.10.26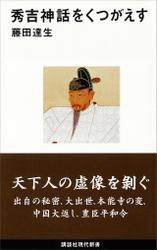
秀吉神話をくつがえす
藤田達生
講談社現代新書
太閤さんの実像とは?読み物としても面白い
歴史学者の著作ですが、順序立てて論が進められ、当然の事ながら、信長や光秀のあの事件、本能寺の変の謎にも迫っており、単なる読み物としても、面白く読みました。 ただ、たぶん著者は、軍国主義の中で神格化されていった秀吉について、もっと詳しく書きたかったんじゃないかなぁ。それについては、あまり紙面を割くことが出来なかったようです。また、私自身の一番の疑問は、秀吉が本当に百姓の出だったのかということ。と言うのも、彼が希代の天才だったとしても、その弟である秀長までが、あのような人物ってのは合点がいかないんだよね。これについては、存外サラッと触れているだけのような気がしました。 一方、力が入っているのは「忽無事令」の解釈について。これについては、納得のいく論説だったと思います。それにしても歴史学者というモノは、邪馬台国論争にしてもそうですが、自分と異なる意見については、結構辛辣に批判するモノですねぇ。第三者的には面白いのですが、理系の私には、ここまで批判することはとてもできません。 ま、なんにせよ、戦国動乱を終わらせたのが、信長のような軍事カリスマではなく、賤視された非農業民である秀吉の合理的精神であり、これが古い時代の壁を打ち破ったという結論には、十分うなずけるモノがありました。
1投稿日: 2014.10.26
「痴呆老人」は何を見ているか(新潮新書)
大井玄
新潮新書
いずれ私も歩む道、と読み始めたのですが…
タイトルから、自分もいずれそうなるかもと軽い気持ちで手に取ったのですが、あに図らんや、とんでもない内容の本でした。1度目は、そのまま通読。すぐに読み返し、今度はメモを取りながら熟読。でもまだ足りません。近いうちに、今度はノートを取りながら、読みたいと思っています。それほど含蓄のある、私がここ数年読んだ本の中で、最も知的好奇心をかきたてられる一冊となりました。単に痴呆老人について書かれた本では、決してありません。 まず、認知症とはなんぞやの説明から始まります。そこでは、認知力の低下と知力の低下とは異なることが語られます。そして認知能力に衰えがないとうぬぼれているのは私たちの方であることが示唆されます。認知している世界は、我々がつながっている世界でしか通用しない世界なのです。それはただ、本質を見ず、そう思い込んでいるだけかもしれません。 次に、日米の認知症に対する考え方の違いが示されます。これはよく言われていることですが、日本では他人に迷惑かけたくない、というのが第一義になりますが、アメリカでは自立性を失うことへの恐れが一番となります。そして、そこから話は日米の文化の差に及んでいきます。 またコトバは重要な要素であり、それは情報を伝達手段であるとともに、情動を伝える手段でもあることが、ゲラダヒヒの事例を挙げて説明され、話はいつしか9.11のブッシュ大統領の振る舞いにまで及びます。 さらに、ニンゲンは、最小苦痛の原則によって行動することが論ぜられ、昨今の「自立」を強制される欧米文化の弊害が語られます。「ひきこもり」という英語では正確な訳さえない行為は、自立したニンゲンを育てる教育を、その訓練さえしてこなかったオトナが進めた結果であるとします。「ひきこもり」も、そして徘徊や夜間せん妄も、最小苦痛の原則による防衛手段の一つなのでしょう。一方、そもそも日本は、「つながり」を重視してきた環境であったことが、大化の改新後の律令制度における班田収授の法によって説明がなされるところなどは、もはや脱帽以外のなにものでもありません。 論の結びは、現在の日本社会で正しいと思われている人間観は、アメリカという開放系の世界で創られたモノで、そこには、長い江戸時代という、まさに平和かつ閉鎖社会で培われた「つながり」というものを軽視していると、警鐘を鳴らします。 これらの事柄を、膨大な引用資料を提示しながら、細かく論じられていきます。仏教、哲学、心理学などが駆使されていて、私にはかなり難解な部分もあり、とても一度読んだだけでは把握しきれないモノでした。近いうちに3度目となる読み直しをしたいと思っています。
3投稿日: 2014.10.05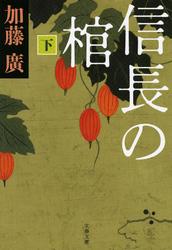
信長の棺 下
加藤廣
文春文庫
信長の「棺」ではなく、「遺骨」でしたね
タイトルから、「失われた聖櫃」って感じになるのかなと思いきや、棺はどうでも良くって、遺骨が問題でしたね。なぜ棺を問題にしているのかなと思って読んだのですが、やはり日本の話なら、こうなるでしょうね。 とはいえ、本小説は、それなりに面白かったですよ。暦の問題を出してくるところ等は、私にとって斬新でした。暦そのものに関しては、冲方 丁の「天地明察」の方がはるかに面白いですが、信長と朝廷との関係に暦がでてくるとは思っていませんでした。ましてや、安土城がそれに関係していたとはね。 小説としては、時代小説でありながらミステリー的要素もあって、最後まで読者を引きつけると思います。ただし、これまで、このテーマの本を沢山読んでいる人にとっては、ちょっと肩すかしかもしれませんし、ミステリーファンとしても、食い足りないかもしれません。 それから、牛一と若い忍者くずれとの情交は、必要ないですね。初期の伊丹十三映画を見るようです。どうしてもこういうシーンをいれたがるんですよねぇ。初めての作品だと尚更そうみたいです。あなたも好きでしょ?って言われている感じがします。伊丹監督も、「お葬式」以降は反省したのか、直接的な描写は避けるようになりました。この小説においてもヒロインを設けたかったのだとは思いますが、これは余分でしたね。ただ、ひょっとすると、老齢の男に若い女性という組み合わせは、筆者の願望だったのかも。
5投稿日: 2014.09.21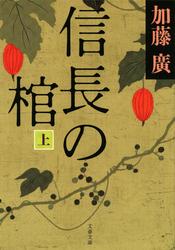
信長の棺 上
加藤廣
文春文庫
書き手は、太田牛一
この書き手がミソですな。架空の人物ではあまりにウソ臭い。かといって光秀、秀吉、家康が語り手では、それが必然的に現実にあった事になってしまう。これに対し、あの信長公記を書いた太田牛一が、見聞きしたり調べたり、そして想像したりした物語であると言うことにしてしまえば、その制約からは逃れられます。だから、信長は、こう思った。ではなく、信長様は、こう思ったはずだ。というスタイルになるわけで、実際の所どうだったかは関係なく、より想像の翼を広げられると言うことです。日本史最大のミステリーの一つである、本能寺の変に対して、これはうまいシチュエーションを考えたモノです。 ただ、私がそもそも昔から疑問だったのは、なぜ光秀は、信長の本物の遺体にこだわったか、という点です。 焼き討ちにあって、その上、消火設備がない木造建築。この状態では、消防にたずさわったことのない人でもわかるとおり、もの凄い熱と上昇気流で、現場は無茶苦茶だったはず。ならば、すべての遺体は見るも無惨な状態でしょう。最新のDNA鑑定でもない限り、どれが本物か、わかりっこない。となると、なぜ、光秀は、遺体をでっち上げることができなかったのかなぁ、と思うのです。これに対する答えを教えてくれる小説は、読んだことないなぁ。 ま、それはそれとして全体の感想は下巻にて。
7投稿日: 2014.09.21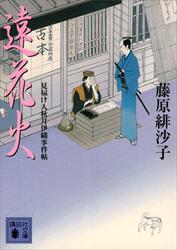
遠花火 見届け人秋月伊織事件帖
藤原緋沙子
講談社文庫
お江戸の私立探偵?そしてラストは日本晴れ!
人情時代劇は、映画でもTVドラマでも、そして小説でも、もっとも好きな分野の一つ。 そして、この小説は、主人公達の立場が面白い。お奉行様でも、岡っ引きでも、同心でもなく、ましてや、悪を断ち切る闇の組織でもありません。それでいて、単なる市井に住む人ともちょっと違う、古本屋を表看板に掲げる情報屋というのが、とても新鮮で面白い。 主の吉蔵、看板娘のお藤、旗本の次男坊の秋月伊織、浪人土屋弦之介、どうです。このラインナップ。テレビドラマ化したら、誰にどの役をやらせるか、考えるだけでも楽しいじゃありませんか。 涙あり、笑いあり、ドタバタあり、そして勧善懲悪の後は、必ずお空は日本晴れ!これぞまさしく、時代劇エンタの醍醐味ですね。この本には4つの話が収められていますが、通勤電車の中で読むにはちょうどよいサイズだと思います。
1投稿日: 2014.08.31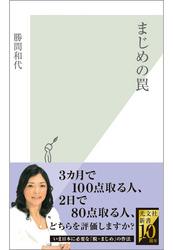
まじめの罠
勝間和代
光文社新書
「ナマケモノのススメ」では、ありません
「まじめ」に生きなさい。たぶん誰しもそのように教えられて育ってきたでしょう。でもそれは、誰か権威のある人から言われたとおりに、生きることでは決してないんですよ、自分の力で物事の本筋を見極めないと大変なことになりますよ。と勝間女史は、主張しています。確かにその通りなんですよね。話の持って行き方が、彼女特有なので、また自慢話かよと、思われるかもしれませんが、一読の価値はあります。 言われたとおりに従って、何か事が起こればすべてを「お上」の責任にする、というのは昨今のあらゆる事象に共通する点かもしれません。これに対し、「お上」の方は、現行法規に従っただけで我々には責任はありません。想定外でした。と言います。ま、よくある話です。ただ、勝間女史が言うように「お上」は、今そんなに信頼されているのかな、という気がします。 特に、戦争を体験した年代は、嘘ばかりならべた大本営発表を聞かされ、昨日まで鬼畜米英といっていたにもかかわらず、一夜明ければ、やれ民主主義だといわれ、使っていた教科書を墨で塗りつぶされた時代を経てきた人は、そうは思っていないでしょう。また。60年安保を体験した世代は、賛成であれ反対であれ、決め方に疑問を呈するあれだけの国民闘争があったにもかかわらず、あっさりと強行採決されては、もはや、あきらめの気持ちしか持っていないでしょう。 だからこそ、どちらも体験していない、これからの世代がどう考え、どう生きるかが問題となります。この本はその一助になるかもしれません。 ただね、この手の本は、どの本も結局最後は経済的に成功することを勝者?とする傾向があります。これは、日本の昔話のラストが、長者様になって何不自由なく暮らしましたとさ。となるのに合致しますね。最終目標はコレというわけです。でもすでに、我々は、それが真の豊かさに繋がらないことに気がついています。 これに対して、アイヌの昔話のエンディングは、「何も欲しいとも、何を食べたいとも思わなくなりましたとさ。」で終わるモノが数多くあります。○○長者とは異なるものを理想としていたんですね。 さて、ここまで来てしまった先進国は、どちらの生きる道を選ぶべきでしょうか?すべての欲望から解脱することは不可能にしても、「吾唯知足」、これが必要なのかもしれません。何をもって幸せとするか。選択するのは「お上」ではありません。我々です。
1投稿日: 2014.08.31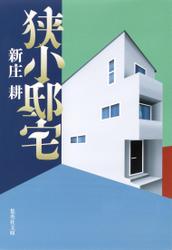
狭小邸宅
新庄耕
集英社文庫
過酷な世界を垣間見せてもらいました
私の住んでいる家は、住宅公団が大規模造成したニュータウンの一角にあります。購入するのも抽選、購入する場所の選択も抽選でしたが、そこにいたるまで両親が多大な時間をかけて、各所を歩き回り調査研究をしていたのを、子供心に覚えています。だから、この小説に書かれた、不動産売買における売り手の心情は勿論、買い手の心情についての描写は、少々衝撃でありました。 また、主人公は、ろくに就職活動をすることもなく、苦し紛れにこの会社に入ったことを独白していますが、これについても、大学四年生の1年間が、公務員試験対策の自主ゼミと卒業論文の執筆に、寝る間もなく完全に費やされた私には、理解しがたいものがありました。 仕事というモノは、どのような仕事でも楽ではないと思いますけど、数字だけがすべてという営業の過酷さは大変なんですね。一方で、土地付き一戸建てというものは、終の棲家という意識が私にはありましたが、そのように考えている人ばかりではないことも初めて知りました。それにしても、主人公が蒲田の家を売ることに成功したときは、私もホントに祝杯をあげたくなり またよ。 この物語は、主人公の心情が徐々に変化していくことを、とても興味深く見せてくれますが、ラストが謎です。考えオチの類になるのかなぁ。でも私の想像通りだと、ちょっと悲しすぎる気がします。
2投稿日: 2014.08.23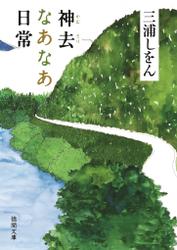
神去なあなあ日常
三浦しをん
読楽
GOOD JOB!WOOD JOB!
通常、気になる映画は、その鑑賞の前に原作を読むようにするのですが、今回は逆になってしまいました。映画のレビューは、ヤフーの方に投稿してあります。 いや~、この原作あっての映画でしたねぇ。映像を先に見ると、登場人物のイメージが出来上がってしまっているのが難なのですが、そんなことは、まったく気になりませんでした。それに、原作の方にも、こんな破天荒なお祭りが描かれているとは…。 実は私、かつて林野庁事業の「緑の雇用」にも関わったことのある行政マンでありました。TPPが問題となっている昨今ですが、木材はすでに完全自由化になっており、全国の林業地は、大変な思いで日本の山を管理しています。そりゃ確かに、これは小説ですから、面白おかしく書かれてはいますが、山には山の良さ、楽しみがあることも事実です。それに、森の中に一人ではいると、どこか神秘的な感じがするのも確かです。実際に働いている人から見れば、色々ご意見もあるとは思いますが、山の生活がよく描かれていると思います。 唯一、不満な点は、現在の林業は、かなり高性能林業機械が導入されていて、全国的には女性の林業技術者も沢山活躍しているという点が、描かれていないことですかね。おそらく都会の人の想像を絶するような機械が各地で活躍していることも、関係者としては、広く知らしめて欲しかったかなぁ。でも、正直、チェーンソーで伐倒することは、確かに快感ですよ。 この小説がきっかけとなって、若い人の職業選択の一つに林業も加わってくれると、嬉しいと思います。
2投稿日: 2014.08.23
くっちゃね村のねむり姫さんのレビュー
いいね!された数863
