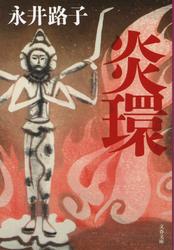
炎環
永井路子
文春文庫
4つの短編をあわせて炎環という一つの作品です
長編小説ではなく、それぞれ主人公が異なる4つの短編で構成された一つの作品というスタイルです。 作者の「あとがき」によれば、一人一人が自分が主役のつもりで思い思いの方向に時代を引っ張った結果、いつのまにかその流れが変えられていった歴史を描いたつもりと、書いておられます。 時は、鎌倉。武家政権が初めて成立した時代です。4つの短編を読んだ後見えてくるのは、鎌倉時代という、新しい秩序ができあがるまでの胎動というところでしょうか?なんとなく、頼朝の家系が3代しか続かなかった理由もわかる気がします。 いつも思うのですが、この時、天皇家をなぜ滅ぼそうとしなかったのでしょうか?どこの国の歴史でも、前の王朝を滅ぼして新しい王朝を築いていくのに、頼朝はそれをしなかった。もし、この時滅ぼしていたならば、後の歴史は確実に変わっていたと思います。でもそうなると、世界で最も古くからある国「日本」というのは、存在しないことになりますけど。 分類としては時代小説にはいるものですが、時代物はちょっとという人にも、話の筋立ては週刊誌のゴシップネタのような話ですので、入り込め易いとは思います。しかし、ライトノベルでは決してありません。直木賞受賞の作品ですが、格調高い文体と表現も随所に出てきます。たとえば、瞼に「うかぶ」を「浮かぶ」ではなく、「泛ぶ」という漢字が当てられています。私はこの字を初めて見ました。 その他、内容については、julia-kさんのレビューに全面的に賛同いたします。 ただ、この電子ブックには、ひとつ気に入らないところがあります。それは、本文の後に掲載されている作者による「新装版に寄せて」という一文に起因します。その中で永井路子は、こう書いておられます。「題名は恣意による造語です。進藤純孝氏が解説の中で、じつに的確にその意図に触れておられるので、更につけ加えることはありません。」 しかーし、にもかかわらず、その解説はこの電子データの中には含まれていません。これはすごく欲求不満が残ります。早々に本屋さんに駆けつけたくなりますよね。
2投稿日: 2015.04.29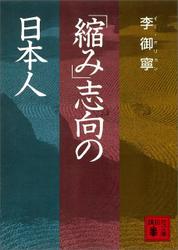
「縮み」志向の日本人
李御寧
講談社文庫
異色の日本人論。結びは感動的ですらあります。
日本人ほど日本人論が好きな国民はいないと言います。そして数多くの本が出てはいますが、どれを読んでも、ふ~んとは思いますし、納得できる部分もありますが、ま、そんなもんかなというのが、誰しも思う正直な感想ではないでしょうか? それでこの本です。このタイトル、そして著者が韓国の人であることから、批判的な本なのかと思っていました。ところがどっこい、そうではありません。読み終わってみて、まさか、この手の本で感動するとは思ってもみませんでした。流石は名著と言われるだけのことはあります。 まず、著者の膨大な知識と教養に驚かされます。古事記、日本書紀等は勿論、国寄せ神話も出てきますし、俳句、短歌は言うに及ばず、古典落語にも精通していらっしゃることがわかります。そして、当然、日本文化には欠かせない歌舞伎、茶道、華道、庭園造り等々においては、私の知らない人の名前や事柄が沢山出てきて、それを一つ一つ調べながら読み進めていると、興味深い内容に先が読みたいにもかかわらず、なかなか前に進まなくて閉口しました。 さて、内容の方はというと、日本人論を語るには西洋との比較ではなく、隣国である中国、韓国と比較した方が明確になるというコンセプトに基づき、日本文化を鮮やかに論じていくものです。 最初の内は、「縮む」というより「小さい」ものが日本人は好きなのかな?つまり志向は、嗜好ということかなと思いながら読み進めていきました。雛人形、扇子、こけし、姉さま人形(若い人わかるかな?)、お弁当文化に盆栽。勿論、うん?そうかな?と思う部分もありますが、トランジスターラジオや電卓、ウォークマンの発明まで、至極納得のいく事柄ばかりでした。ことに、啄木の歌からの入れ子志向を説かれる辺りは、まさに目から鱗が落ちます。 そして次第に論点は、日本人のまさしく「縮み」志向に移っていきます。この「縮み」とは小さくするというより、一つに集約するということですね。「詰めていく」という言葉にも、それは現れているというわけです。そうでないものは、「つまらない」と言いますな。この一つに集約していく文化の特性を忘れた時、日本は不幸になると説きます。 日本の領土的拡大路線は先の大戦によって、とりあえず終わりました。でも、その後、西欧文明に追いつき追い越せと駆け足で生きてきた日本はどうなのでしょうか。 著者は言います。どうあがいても日本人は白人にはなれないのだから、もっと東洋人であることを自覚すべきである。このままではコウモリになってしまう。「縮み」から「拡がり」に転換し、それが失敗する時、日本ばかりでなく隣国も不幸になる。秀吉の朝鮮出兵、韓国、満州の植民地化、太平洋戦争等々。んじゃ、どうするか? そこで最後に引用されるのが「古事記」のなかに出てくる「枯野の船」の話です。この話は、最後に木から琴をつくり、その音色があまねく世界に響き渡ったと結んでいます。木で船を作って世界中に行動範囲を広げて交易したところで、たかがしれている。それよりも、形の上では縮んだ姿である琴のように、その音色、つまりは美しい日本文化こそを世界中に広めて欲しいと、著者は結んでいるのです。また、一方、マザー・テレサの言葉も引用されいます。「この地球上では二つの飢えの地帯がある。一つはアフリカであり、いま一つは日本である。前者は物質的な飢えであり、後者は精神的なそれである。」 この本は20世紀に書かれたベストセラーです。そのため、現状の分析や解説は、現在とそぐわない箇所もありますが、逆に、その頃と何も変わっていない実情にもびっくりもします。まぎれもない不朽の名作でることは間違いありません。
3投稿日: 2015.04.25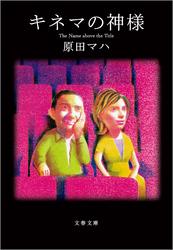
キネマの神様
原田マハ
文春文庫
映画館には神様が宿る!映画好きは読むべし。ただし……
話の中には、映画のタイトルが数多くで出来ます。私も知らない映画が沢山ありました。でももし、これからこの本を読まれるならば、少なくとも「フィールド・オブ・ドリームス」と「ニュー・シネマ・パラダイス」だけは、必ず見てから読まれることをオススメします。そうでないと、面白さが半減しますのでご注意を。 さて、小説の内容は、書籍内容で紹介されている通りです。付け加えるとすれば、今はとんと見かけなくなってしまった「名画座」に対するオマージュと、映画に対するあふれんばかりの愛情が詰まっているということです。 物語の中に、ダメ父が書いてきた数百冊の感想ノートが出てきますが、かくいう私も、学生時代から書いてきた感想ノートが37年間で11冊目が終わろうとしています。昨年からヤフーの映画レビューにも投稿するようになりましたが、自筆のノートはノートで続いています。感激した映画は、その思いを何かに留めておきたくなるんですね。 さて物語の方は、人生、こんなものだとあきらめかけていたアラフォーの女性が、ひょんなことから、自分の人生も、家族も、そして周りの人達もまきこんだ奇跡の立役者になるというストーリーです。それは勿論、ウソの様なファンタジーなのかもしれません。現実にはあり得ない話でしょう。でも、映画好きには涙が出るほど、嬉しい、そして楽しい、そうあって欲しいと思える小説でありました。 寺山修司は、「書を捨てよ町へ出よう」と言いましたが、「書を読んで映画館へ行こう!」と叫びたくなる作品でありますよ。
2投稿日: 2015.04.11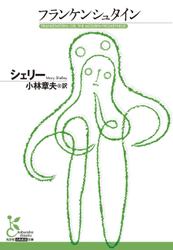
フランケンシュタイン
シェリー,小林章夫
光文社古典新訳文庫
怪奇小説?いやいや、これは哲学小説だったのだ!
読むきっかけは、Eテレ「100分de名著」であります。勿論、映画やドラマ等で名前は知ってましたし、フランケンシュタインとは怪物の名前ではなく、それを作り上げた人物の名前ということも知ってはいました。しかし、まさかこんな内容の話だとは思ってもいませんでした。 メアリー・シェリーという、あのバイロンとも交流があったという美しい女性が19世紀に書いた小説なのですが、とても怪奇小説などと言うカテゴリーに当てはまるものではありはまりません。ヨーロッパ各地の様子、大自然の描写はまさに純文学ですし、その内容は、読み手の意識によって、いかようにも解釈することが出来る、とんでもない小説でありました。 まず、構成が凝ってます。語り手という人が最初に登場しますが、この人は探検家で、北極探検に向かう途中、故郷イギリスにいる姉に書いた手紙の内容が小説になってます。 曰く、北極探検の途中で、おぼれかけているフランケンシュタインを救助した。そしたら、この男がとんでもない話をしだした。という形で話が始まります。なにしろ、なかなか怪物は登場しないし、また、怪物を作り上げてしまった後、フランケンシュタインは、その場からすぐ逃げ出しますので、これまた、ず~と怪物は登場しない。そして、本筋である、知恵も知識も何も与えられなかった怪物が、どのように自我を芽生えさせ、成長し、狂気に到ったかについては、後にフランケンシュタインと怪物が対峙した際、怪物がフランケンシュタインに語り出した告白を、フランケンシュタインが探検家に話したことで初めて明かされます。つまり、物語の内容は、すべて又聞きの又聞きというスタイルなんですね。 怪物は、自分の醜さに悩み、そのために、人と交わることが出来ません。それで狂気に陥るわけですが、人間は誰しもコンプレックスを持っていますから、この怪物には容易に感情移入できてしまいます。また、19世紀という、おそらく輝かしい科学の発展と産業革命で世間が沸いていた時代の最中に、科学者が作り上げてしまった造形物の悲劇という内容には、核兵器を開発してしまった20世紀の世界を予言しているかにも見えます。 また一方、フランケンシュタインは、自分が作り上げたモノがあまりに醜いため彼を見捨てたわけですが、もしそれが、この世に二つとない、とてつもなく美しいモノだったら、どうなっていたのでしょうか。そして、フランケンシュタインの言うことだけを無条件に受け入れる様な怪物だったら……。それはそれで、とんでもなく恐ろしい話になりそうです。 この本は古典の部類に入りますので、様々な人の訳で出版されています。是非、そのうちの一つでも手にとって読んでみてはいかがでしょうか。きっと何か考えさせられる部分があると思います。
3投稿日: 2015.04.11
【合本版】王妃の館 上・下
浅田次郎
集英社文庫
ドタバタの末のハッピーエンド
浅田次郎の作風の広さには目を見張らざるを得ません。「鉄道員」で涙し、「蒼穹の昴」では、あまりにスケールのデカイ想像力に驚愕いたしました。その一方、私の大好きな「椿課長の七日間」みたいな作品もある。頭の中はどうなっているのでしょうか。 さて、この小説を手にしたのは、映画公開前に原作を読んでおこうと思ったからでありますが、こんな集団劇だとは思いもしませんでした。映画の宣伝では右京が前面に出ていましたから。 読み始めから、はちゃめちゃな設定に驚かされ、三谷幸喜の戯曲かと思いました。そして、時々挿入される時空を越えたルイの話が最初は少々うっとうしかったのですが、次第にそれが融合し、とにかくどっちの話も結末が知りたいと、ページをめくる手が早くなります。こうなると、完全に浅田次郎ワールドに引き込まれた証拠です。 一人一人がそれぞれの問題を抱えていたバラバラの集団が、いつしか一つの果実に集結する展開。いやはや、まいりました。軽めの作品ですけど、笑わせてくれて、ハラハラさせてくれて、そしてホロっとさせてくれる。やっぱり、まぎれもなく浅田次郎の小説でありました。 さてこれがどんな映画になるのかな?
4投稿日: 2015.04.03
邂逅(かいこう)の森
熊谷達也
文藝春秋
物語文学を堪能できます!
マタギを題材にした小説は数多くあります。しかし、これはただのマタギ物語ではありません。大正年間、近代化の波の裏側で必死に生きた男の半生を描いた大河ドラマであります。 「邂逅」とは国語辞典によれば、「思いがけなく出会うこと」とあります。読み始める前は、当然、クマとの出会いを指していると思っていましたが、さにあらず。おそらくそれは、主人公が様々な人々と出会うことをも指していると思います。数奇な人生に翻弄されながら、なんとか生き抜こうと抗う中で、主人公は実に多くの人と出会います。時には、その人から生き抜くヒントをもらい、また、ある時は、その生き様を通じて多大な影響を与えていきます。その描写が本当に素晴らしい。このあたりが、直木賞だけでなく、山本周五郎賞を受賞した所以でしょう。 勿論、最後の森のヌシである神の様なクマとの死闘は、ページをめくる手が休まることはありません。ここに到るまでの彼の人生を共に体感してきたからこそ、我々読者は彼と一体化するのです。小説の面白さ、ここに極まれり!と言っても良いでしょう。たぶん、映像で表現することは無理ではないでしょうか。 主人公が、朝霧たなびく谷から妻の待つ村を見下ろしますシーンで物語は終わりますが、読者である我々も彼と一緒に見下ろしていることに気がつきます。読み終えた後の満足感は、半端じゃありません。 民俗学的にマタギに興味もある人も、また、長編本格的物語を好きな人も、是非一度、手にとって欲しい小説であります。
5投稿日: 2015.03.24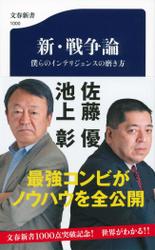
新・戦争論 僕らのインテリジェンスの磨き方
池上彰,佐藤優
文春新書
2014年刊行の書籍。読むなら今でしょ!
「はじめに」を池上彰が、「おわりに」を佐藤優が担当する対談集です。対談だと二人の会話にこちらがついていけるかどうかが問題になりますが、その点は心配ありません。二人には共通認識であろう事柄も、我々にわかるように解説しつつ対談が進んでいきます。 それぞれの漠とした分野ごとに対談というか二人で解説する形式で展開しますが、さすがに希代の論客らしく、その内容は示唆に富んでいます。たとえば、尖閣諸島の問題にしても、色々な本を読みましたけど、ここで佐藤優の示されたような視点は、私にとっては初めてでありましたし、さらに、問題の解決には、流血の規模がキーとなる。その流血の規模というのは、国によって異なるのだ、との指摘には、納得せざるを得ないモノがあります。樺美智子さんの例が象徴的でした。 そして、お二人が紹介してくれたマルクスの言葉、「ヘーゲルは歴史は繰り返すといったが、そのとき一言付け加えるのを忘れていた。一回目は悲劇として、二回目は喜劇として。」 ならば、そうならないためにはどうしたらよいのでしょうか? 各分野とも、突っ込み不足の感はありますが、それは別のモノで自ら学べと言うことでしょう。 タイトルは戦争論となっていますが、あまりこれにはこだわらなくても良いと思います。また、副題の「僕ら」というのはお二人のことを指していますが、さすがに、我々庶民がお二人の様な真似はできません。でも、大変な時代になってきたことだけは、理解できます。たぶん読んでみれば、現在ベストセラーになっている理由はわかります。 また、文藝春秋2015年3月号(芥川賞掲載の号)には、イスラム国に特化して、お二人が「新・戦争論」を展開しています。イスラム原理主義者の下降史観や日本の当事者感欠如について対談しているモノですが、あわせてお読みになることをオススメします。
4投稿日: 2015.03.09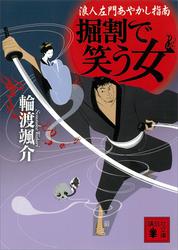
掘割で笑う女 浪人左門あやかし指南
輪渡颯介
講談社文庫
狐狸妖怪、幽霊お化けの話と思いきや…
最初は怪談話だと思いました。しかし、だんだんそれがいかがわしいものになってくる。では、本当のところ何なのか?ただの幽霊話じゃなさそうだぞ、てな感じでストーリーが始まります。 自分たちが、ある目的のために故意に流した怪談話が本当になってくるって、結構、恐怖でしょうね。また、途中に本編とは関係ない(と思わせる)怪談話などが挿入され、やはり幽霊は本物かな?なんて、ますます読者は乗せられていきます。そのうち、どーもこりゃ違うぞ、事の本質は何?黒幕は誰?という謎解きの方に気を向かされ、途中で、あーこの人があの人なのかもと思いついても、そんなことは忘れてしまって、推理の方に意識が集中してしまいました。 そして最後に、実は…と明かされ、そうそう俺もそんな気はしていたよ、なんて思ったりなんかしたりして。。。いやいやなかなか楽しませてくれますよ。 メフィスト賞受賞はダテじゃぁありません!
1投稿日: 2015.03.09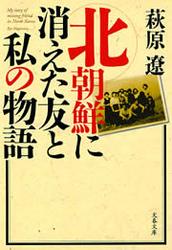
北朝鮮に消えた友と私の物語
萩原遼
文春文庫
「祖国」 この甘美な響きに騙された悲劇
渾身のルポルタージュであり、ご自身の半生を描いた自伝でもあり、命の危険を顧みず書き上げたノンフィクションの傑作であります。とにかく一度読んでみて下さいとしか言いようがない本です。 これは、けっして朝鮮半島の歴史を書いたモノではなく、もう一つの日本の戦後史でもあります。ただ、構成の仕方が時系列に沿っているわけではないので、その点では少々読みづらい点もあります。 理想的な世界を作るはずの社会主義革命は、なぜ、恐怖と独裁にまみれてしまうのでしょうか。本の中では、「銀河鉄道999」のメーテルの台詞や松本零士の言葉も引用され、その本質に迫っていきます。 とにもかくにも、私にはまだまだ知らないことが多すぎ、もっともっと学ぶ必要を感じます。
5投稿日: 2015.03.01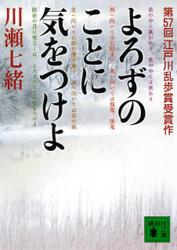
よろずのことに気をつけよ
川瀬七緒
講談社文庫
タイトルからは想像つかない内容であります
冒頭は、横溝正史ばり。そのうち荒俣宏っぽくなってきて、時折宮本常一が見え隠れ。とんでもない発想の小説を読んでしまったといった感想です。ただ、エンディング近くの手に汗を握る急展開にくらべ、解決後はなぜか急に現実的になってしまって、勿論安心はするのですが、どこかガッカリ感がなきにしもあらずという感じでした。 主人公は、文化人類学者と女子大生。この二人が「呪い」が関連したであろう殺人事件を探ります。いざなぎ流の古神道、陰陽道など、その手の話の好きな人にはぞくぞくするような話題が目白押しです。そしてついに、失われた、いや消された歴史にたどり着き、彼らは、そもそもの発端になった東北の一角にある村に赴きますが、そこで彼らを待ち受けるモノは……。ってな感じで話は展開していきます。さすがに乱歩賞を受賞した作品らしく、読者を最後の大団円まで引っ張ります。和物ミステリーのお好きな方にはオススメですよ。
0投稿日: 2015.02.16
くっちゃね村のねむり姫さんのレビュー
いいね!された数863
