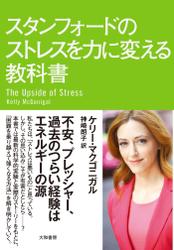
スタンフォードのストレスを力に変える教科書
ケリー・マクゴニガル,神崎朗子
大和書房
ストレスがあった方が長生き?ストレスがあった方が、パフォーマンスが高くなる?
前著の「自分を変える教室」を読んで、かなりの衝撃をうけたのえで、今回の本も購入してみました。 内容としては、ストレスがあることは体にとって悪なのか、というお題に対して、 前回同様、科学的アプローチによって検証をしていく流れです。 ストレスが多い方の方が、長生きしている可能性がある。 ストレスが多い方の方が、より幸福感を感じている可能性がある。 ストレスが多い方の方が、より高いパフォーマンスを出せている可能性がある。 上記のようなお題がたくさん出てきます。具体的にどんな調査をしてどんな結果が出たか、は実際に読んでみて下さい。 科学的アプローチによって、検証を進めていくスタイルは、納得感も高く、すぐに実践してみようと思えるものが多いので、個人的にすごく好きです。 ただ、今回ストレスというちょっと曖昧なもの(書籍内ではきちんと定義してますので読んでみてください)ということもあり、 「少し違うのでは?」とか、「影響を与える要素がほかにもあるのでは?」と思うようなところも少しありました。 ただ、ストレスを感じずに生活をするように頑張るよりも、 ストレスはさまざまな画面でよくあるもので、ストレスがあった方が、幸せになれると思いながら生きた方が、最終的に楽になると、僕も思います。
4投稿日: 2016.07.30
2052 今後40年のグローバル予測
ヨルゲン・ランダース,野中香方子,竹中平蔵
日経BP
これから来る未来は変えられないかもしれないけど、何ができるのか、そして、想定される未来になった時に、どうすべきか。
人口データ、資源のデータ、経済成長率、生態系、気温、などなど、様々な専門家が、未来を予測したものをまとめ、丁寧に説明してくれます。 本書では、現在から40年先をターゲットに描かれていますが、根底にあるものは、40年前に現在を予測している同様の文献です。 もちろん科学的な予測精度含めて上がっているので、今回の予測精度は高いのだと思いますが、一番興味深かったのは、「人」はどのように判断・意思決定をしていくのか、という点を、40年前に描いた予測と 現実の乖離から学び、改めて今回の予測に反映をしていること。 正直読んでみて、未来に対して希望を持てるようになったかというと、そんなことはありません。 正直、無力感を改めて感じました。 ただ、微力ながら何ができるのかを考えること、もしこの予測通りの世界になった時に自分はどうするか、を考えることができたので、この本によってすごく貴重な体験ができたと思います。
5投稿日: 2016.07.30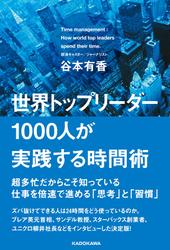
世界トップリーダー1000人が実践する時間術
谷本有香
KADOKAWA
体系的ではないですが、刺激を受ける内容が詰まった本です。
著者と経営者や、実力者と会った経験、インタビューをした経験から ・経営者や実力者が、時間をどのようにとらえているのか ・そのようにとらえられている理由、背景 ・具体的な時間活用、時間短縮のエピソード ・真似をするためにはどうしたらいいのか が分かりやすくまとめられています。 そんなに長い本でもなく、比較的さらっと読める本だと思います。 また、書いてある内容自体は、時間管理まわりの本で、書いてあることも多いですが、経営者の方々のエピソードがあるので、説得力があります。 体系的にまとめられている本というわけではないので、カチッとした理論を知りたいという方よりも、時間管理に関して何かヒントがほしい、刺激がほしいという方にはすごく合った本だと思います。
4投稿日: 2016.05.08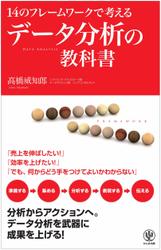
データ分析の教科書
高橋威知郎
かんき出版
分析は得意じゃないけど、やらないといけなくなった!そんな方にオススメです。
定量分析・定性分析とは何か。 そもそも、分析するにしても、何を分析すればいいのかわからない。 分析はできるけど、そのあと何をすればいいのかわからない。 そんな方にオススメの本です。 そもそも分析をするまでに何を軸に考え、定性と定量の違いはどう把握するべきか。 例を挙げながら、どういったステップで進めていくのが近道なのかを詳しく説明してくれます。 とはいえ、分析しなければいけないものは、目的も異なれば、データの構成も変わるため、すごくケースバイケースであることが多いため、なかなか体系化するのは難しいと思います。 その中でもすごく分かりやすくまとめられていますし、著者も言っているように、初めて分析業務をやるかた向けとしては、すごく役に立つ本だと思います。
2投稿日: 2016.05.08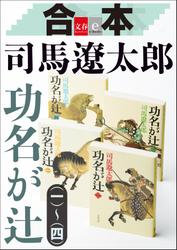
合本 功名が辻【文春e-Books】
司馬遼太郎
文春e-Books
凡人の中の凡人。天才には出来ない成功。
信長・秀吉・家康と同じ時代を生きた山内一豊と千代を中心とした出世物語です。 山内一豊は、戦でこれといった手柄を立てたわけではないものの、いつも何かしら手柄はちゃんと立ててくる。そして、自分には能力がないことを分かっているからこそ、人の話を聞き、それを尊重する。 自分ができることを愚直にやる、約束・義理は守るという性格。 律儀だけが取り柄の凡人が主人公。しかし、それを千代がうまく操作をしながら、出世を果たしていく物語です。 凡人だけれど、義理堅い、よくある物語ならば、ここからスーパースターへと変わっていくのでしょうが、この小説では本当に凡人のまま終わります。 最後の最後まで過ちを犯すこともありますし、最後の最後まで情けない主人公が見え隠れします。 なかなかこういう主人公の小説は読む機会がないため、すごく身近に感じられます。そして、読んだ後に、色々と考える小説でした。自分は凡人だな~と感じる方にこそ、読んで頂きたい本です。
2投稿日: 2016.05.08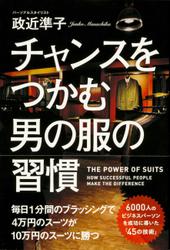
チャンスをつかむ男の服の習慣
政近準子
中経出版
おしゃれにもマナー、ルールがある。
スーツにも、色々なルールがあるのは知ってはいるつもりでしたが、本当に奥が深く勉強になることばかりでした。 スーツの色、柄、組み合わせ、靴、ネクタイとルールがあり、そしてメンテナンスもこまめにしないといけない。 しているつもりではありますが、この本に書いてあるレベルでやろうと思うと、結構手間がかかり、そもそものおしゃれを何ととらえるのかも、考えなおさないといけないと思います。 もしかすると、そのルールにも特に意味もなく、そういうもんだと納得するしかないものなのかもしれないですね。 全部は難しいかもですが、もっとシンプルにファッションを楽しむ意識で、少し取り入れてみようかなと思いました。
3投稿日: 2016.05.01
コーチングのプロが教える 「ほめる」技術
鈴木義幸
日本実業出版社
ただほめりゃいいいってもんじゃないんですね。
アクノレッジメント=存在承認。 をキーワードに、褒めることによるマネジメントを様々な角度から教えてくれる本です。 入口はある課長さんのエピソードから始まるのですが、聞くと「あるある」と思わず言ってしまいそうなシチュエーションです。 そこから、ほめる・認める、が何故必要なのか、のテクニックが多く記載されています。 無意識に実行している方もいらっしゃるかもしれませんが、それを体系的に整してくれています。 ただ、ほめるのではなく、相手のタイプに合わせて「ほめ方」を変える。 そうすることで、相手に「伝わる」褒め方になる。 そして、あくまでもスタンスはForMeではなく、ForYouの精神で行うこと。 一度実践をしてみようと思います。
2投稿日: 2016.05.01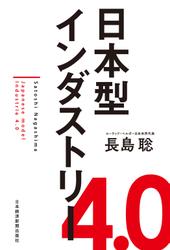
日本型インダストリー4.0
長島聡
日本経済新聞出版
インダストリー4.0を勉強するにはすごくいい本でした。
インダストリー4.0を勉強しようと思って読んでみましたが、すごくわかりやすく説明されていて、良い本でした。 特に、インダストリー4.0が何故ドイツで推進をされていて、IICが何故起ち上げられたのか、そうした背景から詳細に説明されていて、今なぜここまで問題になっているのかがよくわかります。 そして、これまでのデジタル化とは何が違うのか、 日本のものづくりにとって、インダストリー4.0が本当に脅威なのかどうか、 これからの日本のものづくりの勝ち方、 まで著者の想いとともに、語られています。 この流れは、日本の国際競争力を、今後左右する大きな流れだと思います。そして、日本のものづくりが現状負けている訳ではない。 むしろ進んでいる。 しかし、この潮流が世界で進んだ時には、戦いにくくなることは容易に想像ができます。少なくとも、この戦いに参加をし、対応できるようにしておくことは必須なのだと思います。 ものづくりにかかわる方々はぜひ一度読んでみて損はないと思います。
1投稿日: 2016.05.01
オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件 増補改訂版
小川紘一
翔泳社
日本の産業が、今後国際競争力を持つためには。
日本のものづくりに関して、電機業界が何故苦戦しているのか、そして、なぜまだ自動車・材料系は強いのかを例に、それを生んでいる要因を詳しく説明してくれる本です。 特に、特許数を指標に、国が進めてきた施策が、結果的に利益につながっていない現状を電機業界を例に詳しく説明しています。それぞれの事例で、韓国や台湾をはじめとしたアジアの企業に大きくシェアを奪われている現状に、驚きます。 そして、それが技術力の差や、アップルの様な革新的な商品が無いから、という理由ではなく、全体戦略の弱さがそれを生み出していることに納得させられました。 そして、そのために今後必要な戦略・人材、それを国として育てる環境を早急に作ることが、今後の日本の産業の競争力に大きな影響力を与えることを感じ、現状に強い危機感を抱く方が多いのではないでしょうか。 インダストリー4.0、IoTと、時代が変わったことで、事業の強みの持ち方も変わる。それに併せて働き方、求められるものも変わる中で、個人も変わっていかないといけないですね。
4投稿日: 2016.05.01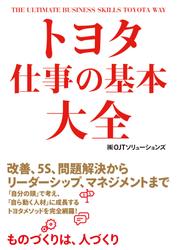
トヨタ 仕事の基本大全
(株)OJTソリューションズ
中経出版
トヨタの強さの源泉。
現地現物、カイゼン、何故を5回、5sなど、有名なトヨタのカルチャーだけでなく、実際にトヨタの社員の方々でどんなエピソードがあったのかが、98個載っています。 聞いたことがあることや、他のビジネス本にも、載っていること、似ているものはたくさんあるかもしれません。でもこれを企業として大切にし、文化の領域にまで本当にしているとしたらトヨタはとんでもない企業だと思います。 個人的には、トヨタの一番の強みは、現場で人を信じることではないかと感じました。
1投稿日: 2016.04.01
あきばさんのレビュー
いいね!された数403
