
新訂 孫子
孫子,金谷治
岩波文庫
紀元前から読み継がれている兵法書、いまやビジネス書
言わずと知れた兵法書であるが、その著者は紀元前500年頃春秋時代の孫武とも、紀元前340年頃戦国時代の孫臏とも言われ諸説あるようだ。 兵法書でありながら紀元前から現代まで読み継がれているということは、真理が述べられているからだろう。 有名なところでは武田信玄の「風林火山」、また「呉越同舟」、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」といった四字熟語や故事成語も孫子が出所である。 本書は原文(漢文)とその読み下し分、口語訳といったシンプルな構成で解説は無い。読み方としては、ビジネスや指導といった自分なりの活用シーンを思い浮かべながら、現実に即した解釈をするのがよいと思われる。
1投稿日: 2015.07.09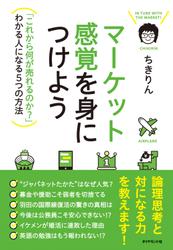
マーケット感覚を身につけよう
ちきりん
ダイヤモンド社
モノやサービスが持つ価値に気づく
市場の仕組みと、モノやサービスが持つ価値を理解する重要性を改めて認識させられた。 マーケット感覚とは非伝統的なものも含めてそれが持っている価値に気づき、見極めることである。 本書ではその重要性を身近な事例でわかりやすく説明している。 たとえば、カリスマ収納アドバイザー、不満の買い取り、本を選ぶセンスなど、 普通の人でも売れる価値を持っている。 また規制によって守られている事業であっても、消費者が妥当と感じる価値から掛け離れていると、 市場によって変えられることにも注意。 (例として、日本の地方に住む人たちが海外旅行に行く際に、地方空港→羽田空港→成田空港→海外へという非常に非効率な移動を強いられていることに目をつけた仁川国際空港。)
1投稿日: 2015.07.05
宇宙は何でできているのか 素粒子物理学で解く宇宙の謎
村山斉
幻冬舎新書
「宇宙の起源を知ろうと思ったら、素粒子のことを理解しなければいけません」
膨張を続ける宇宙も時間を逆行してその起源をたどれば、物質をこれ以上分解できない最小単位に行き着く。つまり広大な宇宙を知るには素粒子を理解することになる。この両極端なものの結びつきを著者は「ウロボロスの蛇」にたとえる。 大学で力学、電磁気学を少しかじったが、素粒子物理学の前提にあるのは常識を超えた数々の概念だ。たとえると、太陽は自分の頭上を東から西へと移動しているように見えるが(天動説)、実は自分が動いているのだよ(地動説)、と告げられたようなイメージだ。本書は入門書ということでそれを平易に解説している。途中で素粒子の名前が多数出てきて混乱したが、どのようにして宇宙が解明されているかを知るにはうってつけだ。
1投稿日: 2015.05.23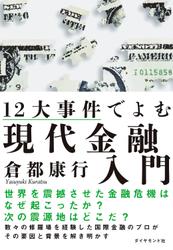
12大事件でよむ現代金融入門
倉都康行
ダイヤモンド社
戦後の各金融危機をわかりやすく解説
1970年代のニクソンショックに始まり2013年のバーナンキショックまでの12の金融危機について、その背景とともに解説されている。危機に学んだこともあれば、今だに危機を起こしかねない事案もある。それぞれの事件について適度に掘り下げられていて、背景となる時代の流れとのつながりを理解しやすく、まさに入門にふさわしい。
0投稿日: 2015.04.01
ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼
松尾匡
PHP新書
70年代以降の経済の変化を読み解く1つの切り口として興味深い
1970年代までの先進資本主義国では不況になると経済に政府が介入するケインズ政策がとられていたが、70〜80年代にかけてこの政策は行き詰まりを見せるようになる。(不況であるにもかかわらずインフレが進行する)そこで70年代までのやり方から脱却する動きが出てくる。 本書ではケインズ、ハイエクを中心に様々な経済学者の考え方を紹介し、そこに共通している「リスク・責任・決定の一致」、「人々の予想を確定させる」ということが、この動きに則った政策だとしている。 70年代以降の経済の変化を読み解く1つの切り口として興味深いと思うし、第2章ソ連型システム崩壊が教えてくれること、は分かりやすい。
1投稿日: 2015.02.27
現場主義の競争戦略―次代への日本産業論―(新潮新書)
藤本隆宏
新潮新書
日本の製造業悲観論に対して、マクロの視点に加えて現場の視点から産業を論じている
デジタル化の波、不況、円高、内外賃金格差等のハンデによって90~2000年代は特に電機・電子産業で競争優位性を失ったが、2010年代以降は新興国の賃金高騰により状況が変わってきている。賃金格差が解消してくると新興国に工場を移せば競争力が高くなる時代は終わり、生産性のさらなる向上によって国際競争で優位に立てる可能性が高くなってきた。現場の視点というのが新鮮。「良い設計の良い流れ」という言葉が印象に残った。
0投稿日: 2015.01.01
「売り言葉」と「買い言葉」 心を動かすコピーの発想
岡本欣也
NHK出版
聞いたこと、見たことのあるコピーのオンパレード
広告コピーを売り手目線の「売り言葉」、買い手目線の「買い言葉」に分類して、それぞれの特徴を解説。「伝える」という行為に役立てようとしている。スッと染み込んでくる多くのコピーの紹介とともに丁寧な解説がされ、読み進めやすい。
0投稿日: 2015.01.01
トヨタの伝え方
酒井進児
幻冬舎ルネッサンス
情報を集めて詰め込むだけではだめ、集めた情報をどう使うか
近年インターネット等から情報を簡単に入手できるようなったが、情報は集めるだけでは使いものにならない。 思想を持って取捨選択をし、溜め込んだ情報を頭の中で繋げ、”発酵”させることで使えるものになる。 トヨタではかつて一覧性、携帯性に優れているA3用紙1枚にその発酵させた情報を詰め込んで、 意思疎通、意思決定に使っていたという。 情報が氾濫している今は、むしろ一度完全に情報の流入をシャットアウトして、 自分の頭の中にある情報をあれこれつなげ直して考える時間をとってみたいと思った。
0投稿日: 2014.10.04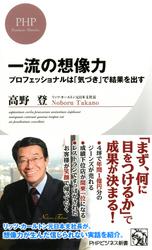
一流の想像力 プロフェッショナルは「気づき」で結果を出す
高野登
PHPビジネス新書
このシチュエーション、あなたならどうしますか?
元ホテルマンの著者が様々な実例を挙げて想像力の大切さを説いている。「レストランでお客様の待ち合わせの相手が来なかったら?」「真夜中に現れた親分をどうもてなすか」等、自分だったらこのシチュエーションでどう対応するだろう、と考えながら読み進めると楽しい。マニュアルにはないシチュエーションでは、「その場にいるお客様にとって何がベスト」かを想像して対応する必要がある。「一人前の先にあるもの、それが一流」というフレーズが印象的だった。
0投稿日: 2014.09.07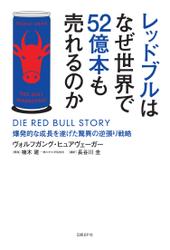
レッドブルはなぜ世界で52億本も売れるのか
ヴォルフガング・ヒュアヴェーガー,長谷川圭,楠木建
日経BP
マーケティングのハウトゥー本ではない
レッドブルの製品はコンビニ、自動販売機でよく見かけるが、その企業についてはあまり知らなかったりする。レッドブルは飲料であるが、レッドブル社は飲料を売るだけではなくエキサイティングな体験を提供している。つまり飲料メーカーというよりむしろマーケティングの会社だ。創業者ディートリッヒ・マテシッツがどのようにしてレッドブルを成功させたか、読み進めていくとその唯一無二の戦略に唸らされる。
0投稿日: 2014.08.27
asphericさんのレビュー
いいね!された数30
