
情報機関を作る 国際テロから日本を守れ
吉野準
文春新書
日本はインテリジェンスに対する認識が甘いという警鐘
インテリジェンス収集手段の基本は古来より 人手(ヒューミントHUMINT:human intelligence)であり、 情報交換はヒューミント同業者間のギブ&テイクが原則となっている。 先進国で例外的に情報機関を持たない日本では事実上警察組織がその役割を担っているが、 情報機関とはみなされない。 それゆえ国際テロや防諜、外交・防衛政策の面で不利な状況にあり、 著者の経験に基づく「情報機関を作る」提言がなされる。 しかし本書で一番刺激的だったのはゾルゲ、ペンコフスキー、ゴルディエフスキーといった 「歴史を動かした大物スパイ」達の鮮やかな手口である。
0投稿日: 2016.06.11
新宿駅はなぜ1日364万人をさばけるのか
田村圭介,上原大介
SB新書
新宿駅東西の抜け道を攻略する
この本を手にする2週間前、私は新宿駅西側で用事を済ませ、友人達との待ち合わせ場所に急いでいた。待ち合わせは東口。ギネスに認定されるほど乗降客の多い駅だから、駅の反対側に抜けるのは容易いことだろうとタカをくくっていた。しかし新宿駅は鉄壁のディフェンスで立ちはだかった。5分遅刻しての到着である。 本書で新宿駅の構造を理解すると東西への抜け道は7つあり(うちJR新宿駅構内が2つ)、その時にようやく見つけた抜け道は角筈ガードという戦後闇市の面影が残る1927年開通の通路であった。 本書で新宿駅に対する苦手"意識"はやや薄くなった。でも人の多さは、、、
0投稿日: 2016.05.31
「快速」と「準急」はどっちが速い?~鉄道のオキテはややこしい~
所澤秀樹
光文社新書
鉄道には不可解なことが多数ある
本書のタイトルでもあるがどちらが上位かわからない列車種別、自社線は走らずひたすら他社線を徘徊する電車、「普通」と「各駅停車」はどう違う、JRの乗車券原紙に"小田急電鉄"と印字されている指定券などなど、鉄道にまつわるオキテのややこしさ、ものめずらしさを「へぇー」と楽しむ1冊。怪現象を具体例で解き明かしてくれる。 時々挿し込まれている往年の特急車両の写真は、最近の無表情・クールな顔つきの車両に比べると愛嬌がありなぜかホッとする。個人的には阪神電車の生い立ちが「へぇー」だった。
1投稿日: 2016.05.14
ソラリス
スタニスワフ レム,沼野 充義
ハヤカワ文庫SF
ソラリスの不思議な"海"のことを想像するのが楽しい
存在するかしないかはさておき、 知的生命体といえば外見はどうあれ 人間に準じた形態の生物を想像してしまう。 人間と似たような思考回路を持ち、 私達が合理的と考える行動様式を取ると予測する。 ここに描かれているのは惑星ソラリスの "海みたいなもの"とのコンタクトである。 それは生命体かどうかもあやしく、 挙動は長年の"ソラリス学"の研究成果もむなしく、 意味不明である。 いかなる意思疎通方法も持たない 絶望的に遠い”他者”とのコンタクトの描写が 素晴らしい。
1投稿日: 2016.05.13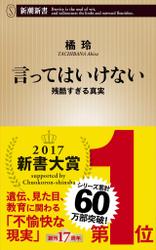
言ってはいけない―残酷すぎる真実―(新潮新書)
橘玲
新潮新書
きれいごとに隠されている残酷で不愉快な真実とは
「最初に断っておくが、これは不愉快な本だ。」という書き出しで始まるまえがきのとおり、 敢えて耳障りなことを聞きたくなければ手に取らない方がよい。 きれいごとでコーティングされた今の世界はまんざらでもない。 しかし「政治的に正しい」行い・政策は幸福な結果をもたらしているだろうか。 前著「『読まなくてもいい本』の読書案内」のスピンオフという位置づけらしく、 遺伝・進化・脳科学の近年の研究成果をベースに残酷な真実を解き明かしている。 どうあるべきかという意見も提示されているが、 著者も言う通り現時点では実現は困難だろう。
6投稿日: 2016.05.02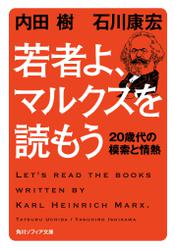
若者よ、マルクスを読もう 20歳代の模索と情熱
内田樹,石川康宏
角川ソフィア文庫
マルクスに興味を持ったので読んでみた
マルクスを読みたい、でもどこから手をつければ…という状況でとりあえず手に取った。本書はその役割を十分に果たしてくれたといってよい。読後もマルクスへの興味を失わなかったのだから。 元々共産主義というイメージしかなく、本書で取り上げられている1冊目もまさに『共産党宣言』であるが、マルクスを読むべき理由はむしろ「どれくらい因習的な思考の枠組みに囚われていたのか」気づかせてくれる点だという。 他に『ユダヤ人問題によせて』『ヘーゲル法哲学批判序説』『経済・哲学草稿』『ドイツ・イデオロギー』の読みどころを紹介している。
0投稿日: 2016.05.01
人生を面白くする 本物の教養
出口治明
幻冬舎新書
「教養とは、人生におけるワクワクすること、面白いことや、楽しいことを増やすためのツール」
日本のリーダー層は世界標準からすると教養という点ではかなりレベルが低いという。それは戦後日本が、アメリカへのキャッチアップに邁進していた「ルートの見えている登山」であったことで、余計なことを考えて遠回りをするとロスが発生する、つまり自分の頭で考えないほうが都合がよい社会であったからだと分析する。そのことで日本は高度成長という恩恵を受け、「終身雇用、年功序列、定年」の特異な労働慣行を生み出してきた。しかし高度成長の恩恵を受けられなくなった今、このモデルは成り立たず、自分の頭で考えること、「教養」が要請されている。 著者は教養の源として「本を読む」「人に会う」「旅に出る」を挙げている。
5投稿日: 2016.04.16
世界最強の女帝 メルケルの謎
佐藤伸行
文春新書
「壁」崩壊後に突如政治家を志した、東ドイツ出身の物理学者
アンゲラ・メルケルは東ドイツ出身の物理学者で、1989年(35歳)の「壁」崩壊後に突如政治家を志したというが、それまでの半生は社会主義国家 東ドイツで育った故かドイツ国内でもあまり知られておらず、謎が多いようだ。 コール首相率いるCDU(キリスト教民主同盟)の元、36歳の時に初当選した後の上昇は目覚ましい。目をかけてくれたコール氏ら「師」を次々と踏み台にして首相にまで登りつめ、すでに10年以上も首相の座に居続けている。一見冴えないリケジョは今やフランスを下位に従えるドイツの「EU大統領」である。 ギリシャ問題では頑として緊縮政策を譲らず冷徹だと思ったが、難民流入については受け入れを表明するなど「情」を見せる一面もあった。(労働力不足を補う合理的な判断でもあったが) プーチン氏と向き合って斬り込んだ話ができる欧米の指導者はメルケル氏をおいて他におらず、オバマ政権もメルケルの力に頼っているが、ロシア訪問時にはプーチン氏の陰湿な嫌がらせを度々受けているようである。(犬のぬいぐるみ事件/愛犬で攻める)
0投稿日: 2016.04.10
コーランには本当は何が書かれていたか?
カーラ・パワー,秋山淑子・訳
文藝春秋
イスラム的な考え方を知りたい人に
連日イスラム国の脅威がニュースになっている。 メディアは過激な発言、行動に飛びつきがちなためイスラム教に対してずいぶん偏ったイメージを持たれていると思う。 本書ではイギリス在住アメリカ人フェミニストが、イスラム教の女性学者9000人を発掘したアクラム師との対話を通じてコーランについて学ぶ。 師はコーランを主義・主張のために利用する人が多いと嘆く。 コーランはそれが書かれた時期の時代背景も含めて解釈する必要がある。 西洋の世俗的な考え方と本来のイスラム的な考え方のコントラストが興味深い。
0投稿日: 2015.12.06
地図で読む「国際関係」入門
眞淳平
ちくまプリマー新書
世界情勢の教科書として読める
今現在の世界情勢をギュッと1冊の新書に押し込め、中学生にもわかるような平易な文章で著述されており、「教科書」的だ。タイトル通り極力地図を挿れた解説がなされており、世界情勢を「俯瞰」するには丁度よい。興味がある箇所は巻末の参考文献を漁ればよいと思う。
1投稿日: 2015.10.06
asphericさんのレビュー
いいね!された数30
