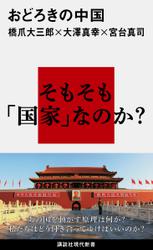
おどろきの中国
橋爪大三郎,大澤真幸,宮台真司
講談社現代新書
隣国を理解することは自分達の理解を深めることでもある
そもそも中国とは何か?から始まり、 日中のリーダー感の違い、毛沢東は皇帝か、 日中の歴史問題など、3人の社会学者が 中国について様々な切り口で鼎談する というスタイルである。 中国人の目線で日本はどのように見えるか という切り口は新鮮で興味深い。 日本の常識は中国では通用しない。 隣国への理解を深めるだけではなく、 相手の考え方や立場を知るという 相互理解の基本を改めて認識させられる。
0投稿日: 2015.09.06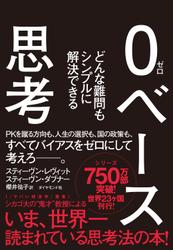
0ベース思考
スティーヴン・レヴィット,スティーヴン・ダブナー,櫻井祐子
ダイヤモンド社
フリーク(型にはまらない人)みたいに考えて課題を解決する
常人の発想では解決できなかったり、 逆に事態を悪化させる事案を実例とともにわかりやすく解説している。 PKを蹴る方向の決め方、なぜ人は「知らない」と言わないのか、ホットドッグの早食い大会で「突然変異」的な記録が出たのはなぜ、銃規制は「犯罪率の減少」と関係がない、ウソつきは人と違うインセンティブに反応するなど、事例は豊富でわかりやすい。 興味深いのはインセンティブを適切に設定することの重要性。環境汚染を防ぐために設定したインセンティブが、逆に汚染を助長させてしまう事例が紹介されている。政策でインセンティブを用いる場合はインパクトが大きいだけに十分な事前検証が必要だろう。
0投稿日: 2015.08.29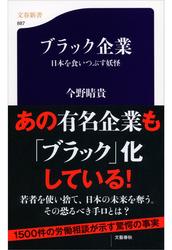
ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪
今野晴貴
文春新書
若者そして私たちから搾取した利益でグローバルに羽ばたくブラック企業
ブラック企業の実態を具体例とともに紹介し、跋扈する背景について論じている。 新興企業に多い印象だが、グローバル企業にもブラック企業は存在する。 日本型雇用の労使関係では雇用保障と命令権はセットで与えられる。ブラック企業は近年のその変化につけこみ、命令権のみを行使して徹底的に従属させ、労働力を搾取した上で意図的に鬱病に陥れて捨てる。ムチをハラスメントに持ち換えた奴隷制である。 当のブラック企業は本来負担すべき辞めた若者の治療費、社会保障費などのコストは全て社会に押しつけている。 著者はブラック企業を社会問題として捉え新しい「労使関係」の制度を構築することが重要としている。
0投稿日: 2015.08.22
サラリーマンは2度破産する
藤川太
朝日新書
将来の明確なリスクを事前に認識し、強い家計を作る
サラリーマンは子どもの教育費、そして老後の2度に渡って金融資産残高がマイナスになるという。 しかもそれは年収1000万円を超える世帯であってもだ。 本書ではどうすればお金の貯まる家計になるかを説明し、具体的なライフプランの作成を通して将来のリスクを認識する。 そして2度の破産を未然に防ぐ強い家計を設計する。 ローンは借りられる額ではなく返せる額を、生命保険の見直し、会社の福利厚生を活用する、パートで妻が働く、投資は余裕資金でなど、 わりと手堅く家計を見直していく。
0投稿日: 2015.08.19
コーヒーが廻り世界史が廻る 近代市民社会の黒い血液
臼井隆一郎
中公新書
コーヒーの生い立ちを廻る歴史の旅
安らぎのとき、旅に出るとき、集中して作業を行うときに飲む一杯のコーヒー。 自動販売機やコンビニ、街中のカフェで飲める手軽さとは裏腹に、ここまで生活に浸透するまでの生い立ちは、アロマのような穏やかなものではなく黒い血液そのもの。 15世紀アラビアから始まりイギリス、フランス、ドイツ、ブラジルへと、黒い血液は歴史と共に世界を廻る。
2投稿日: 2015.08.18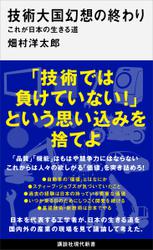
技術大国幻想の終わり これが日本の生きる道
畑村洋太郎
講談社現代新書
現実を直視し意識を変える
戦後50年間はどこに向かって進めばよいかが明確で高度経済成長を謳歌できました。しかしその後の20年間は行き先さえ分からずにただジャパンアズNo1という幻想を抱き、自信過剰、傲慢になりました。このことにそろそろ気づき始めたのではないでしょうか。原発の電源喪失に見る「想定外」、半導体産業での敗北、電機メーカーの不振と、事例は枚挙にいとまがありません。 本書では日本の置かれている現状、日本がこれから意識するべきこと、日本の生きる道について、失敗学の畑村洋太郎氏が三現(現地、現物、現人)を実践して語っています。 印象に残ったのは、品質幻想。高品質を誇り韓国製半導体を粗悪品と油断していた日本の半導体メーカーは何社生き残ったでしょうか。know/howにこだわっていると思考が停止します。大事なのはknow/whyまたはknow/what。
1投稿日: 2015.08.10
寝ながら学べる構造主義
内田樹
文春新書
「なるほど」となるのが快感
岡田斗司夫氏との共著「評価と贈与の経済学」を読んで以来気になっていた内田樹氏の著書。 構造主義に興味があったわけではないが、読み始めると翻訳文では何を言っているのかさっぱりわからないニーチェらの哲学的な主張も、独特のわかりやすい例えを引き合いに出して説明しているため、何となくわかった気になる。
1投稿日: 2015.08.05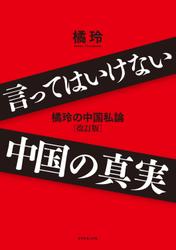
言ってはいけない中国の真実--橘玲の中国私論 改訂版--
橘玲
ダイヤモンド社
中国人を理解する
巻頭で中国10大鬼城(ゴーストタウン)の紹介から始まり、その壮大なスケールにお腹いっぱいになりかけるが、本編ではこの遺物を生み出した社会構造や錬金術、また中国人を体験するとはどういうことかを考察している。人が多すぎる、信用が不足しているために社会的秩序よりも幇とグワンシが優先される、中国共産党は地方を管理できない、役人の腐敗、、、ときどき飛び込んでくる中国人に関する不可解なニュースはこれを読めばなんとなく納得できるかもしれない。
1投稿日: 2015.08.05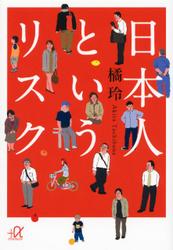
日本人というリスク
橘玲
講談社+α文庫
国家から個人のリスクを切り離す人生設計
戦後日本人の人生設計は「不動産神話」「会社神話」「国家神話」「円神話」を前提として築かれてきた。しかし、3.11の大震災、1997年の見えない大災害によって、そのリスクが顕在化してきた。不確実な未来を生き抜くには、人的資本のリスク、金融資本のリスクを分散し、国家から個人のリスクを切り離さなければならない。 詳細は氏のほかの著書でも読むことができるが、本書は日本人のリスクというタイトル通りのテーマでまとまっている。
1投稿日: 2015.08.04
スノーデンファイル 地球上で最も追われている男の真実
ルーク・ハーディング,三木俊哉
日経BP
「テロリストだけではない、一般市民も含めてみんな監視されている」
正義感の強いスノーデンによって明らかになった。 このリークがなければインターネットを通じたNSAの”支配”は歯止めが効かないままであっただろう。 スノーデンが盗み出したファイルをジャーナリストに渡すまでの用心深く緊迫したやりとり、 リークにより釈明を迫られる政府高官たちの様々な言い訳、米英政府と新聞社との駆け引きがなかなか興味深い。 しかし、すべてのデバイスが監視されていることを知っていたのはアメリカの友好国ではなく、皮肉にもテロリストだったようだ。
0投稿日: 2015.07.22
asphericさんのレビュー
いいね!された数30
