
ドナウよ、静かに流れよ
大崎善生
角川文庫
いかにも大崎氏らしい初期のセミノンフィクション
小説だと思い込んで読み始めた本。実は大崎氏の初期のノンフィションだったんですね。海外まで飛んで積極的な取材をかけたが、何せ『心中した当人たちの心的な部分』を関係者の誰も把握していないため、良くも悪くも大崎氏のイマジネーションが主になった感は否めない。ドナウに身を投げなければならなかった当人たちの想いに関して、美化しすぎる(現世からの逃避行ではなくて、むしろ積極的に)ような気もするが・・・、このあたりが大崎氏らしくてある意味で良いかもしれない。この取材を巡る旅が、後のアジアンタムブルーやユーラシアの双子を生み出すことになったんだろうな。大崎ファンにとっては、氏の原風景を探るには良い作品。
0投稿日: 2017.06.03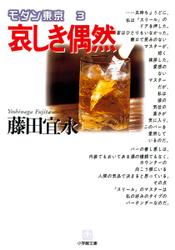
哀しき偶然(小学館文庫)
藤田宜永
小学館文庫
少しだけハードボイルドがかかったお洒落な探偵小説
ちょいハードボイルドタッチでお洒落な推理小説。やはり藤田宜永氏は恋愛小説を書くよりも、推理・サスペンス小説のほうがうまいと思う。モダン東京<3>という副題のとおり、大戦前の軍部が台頭しつつあるが、それでもモボ・モガと呼ばれた若者達が全盛だった古き良き時代(?)を背景にしているが、多分この設定を現在としてもまったく違和感が無く読める。独身貴族を謳歌する主人公の秘密探偵という職業名もよく、休日に寝そべりながら気軽に読むには良い作品。
0投稿日: 2017.05.21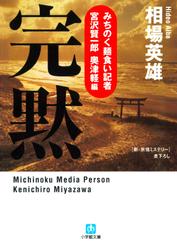
みちのく麺食い記者・宮沢賢一郎 奥津軽編 完黙(小学館文庫)
相場英雄
小学館文庫
何もしたくないときに気張らずにボーっと読むには楽しい小説
第一作の『因習の殺意』に引き続き、第三作『完黙』を読んだ。先の作品に比較して舞台設定のスケールは小さくなっているが、持田・遠山達の登場人物の心情に切り込んだ良い作品になっている。捜二の管理官・田名部(始めこそは大型の経済事件を追っていた)が何故か捜一の立場で動くことになるストーリーも面白い。それにしても、この作品での宮沢は浅見光彦張りの推理をみせるが、ある意味でこれ以上名探偵にはなってほしくない気もする。このシリーズ、気張らずに時間潰しに読みたい時にお勧め。
1投稿日: 2017.05.19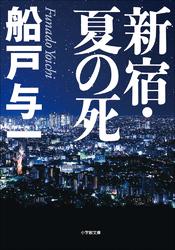
新宿・夏の死
船戸与一
小学館
船戸小説の真髄にどっぷりと浸ることのできる中編8つの物語。
題名のとおり、新宿・夏という共通項以外にはまったく関連性のない8つの中編からなる小説。サラ金・路上生活者・割烹料亭等々、長編の船戸作品だと出てこない舞台がテーマになっているのも面白い。私としては『夏の雷鳴』『夏の曙』が秀作だと思う。もう一つ、共通項として破滅・滅びといったテーマが通奏低音のようにすべての物語を貫いているのは言うまでもない。まさに船戸ワールドのエッセンスが詰まった短編・中編集。
0投稿日: 2017.05.07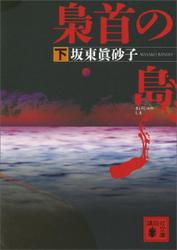
梟首の島(下)
坂東眞砂子
講談社文庫
まさに明治時代前半の自由民権運動にかかわる歴史書:主役の岩神兄弟の最後がなんとも切ないが・・・。
上巻の感想にも書いたが、まずはこの本が坂東眞砂子作品だという驚き。やはりプロの作家は筆力がある(何でも書けるんだ)。明治時代といえば、鹿鳴館や瓦斯灯などなど明るいイメージ(良くも悪くも西洋化)があるが、庶民の目線からすると、必ずしも江戸時代よりも良くなったわけではなかった(独裁政治の主役が変わっただけ)。この小説で、明治前期の底流に流れる自由民権運動の本質が少しだけ理解できた気がする。一方で、岩神親子の物語は、むめのたくましさ・したたかさを楽しみながら、面白く読み進められたが、大洋・東吉の最後がなんとも切ない。いつか再読しようと考えているが、それでも坂東氏が彼女の子宮で考えた物語の真意は、男にはわからないかも知れない。
0投稿日: 2017.05.07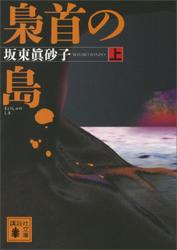
梟首の島(上)
坂東眞砂子
講談社文庫
これが坂東眞砂子の小説・・・いい意味での意外性
坂東眞砂子&題名だけで内容を確認せずに読み始める。例によってホラー含みかと思っていたが、明治期の自由民権運動に携わる庶民(上巻では土佐が舞台)の歴史が全うに書かれている。平行して、時間軸が少し遅れる形でロンドンでの二人の日本人の死(自殺?他殺?)に対する追跡も始まる。もともと坂東小説の舞台は四国が多いが、作家生活も後半に入り、故郷の歴史を紐解き・残そうと思われたのか・・・と考えつつ下巻へ。
0投稿日: 2017.04.29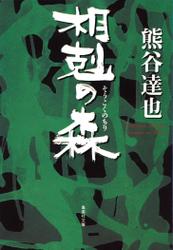
相剋の森
熊谷達也
集英社文庫
マタギと言う職業あるいは性を通して語りかける熊谷氏の生命への哀歌:邂逅の森よりも良いかも。
本書『相剋の森』が『邂逅の森』よりも先に書かれたものとは知らずに読んだ。何故、この時代になってまでクマ猟をして熊肉を食べる必要があるのかという、もっともな疑問に対して、マタギ文化に並々ならぬ思い入れのある筆者の答えは明確だった 。“山は半分殺(の)してちょうどよい”。人間を含めて生物が生命を繋ぐ行為は、他の生命の殺生と同一である。何処の家の食卓でも食塩以外は、生命の塊を食べていると言える。絶滅危惧種への対応は重要だが、うわべだけの動物愛護主義だけは慎みたいと思う。邂逅の森と併せて多くの方に本書を読んでもらいたい。
0投稿日: 2017.04.16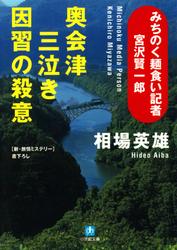
みちのく麺食い記者・宮沢賢一郎 奥会津三泣き 因習の殺意(小学館文庫)
相場英雄
小学館文庫
どこか内田康夫作品を彷彿とさせる気軽に読める推理物 : 旅行や出張のお供に最適
『震える牛』『血の轍』とハードでシビアな警察の世界を描いた2作を読んでいるが、これらとは全く異なる旅情ミステリーシリーズで、とても読みやすい。相場英雄氏の別の側面を見た感じ。大和新聞に勤務する自称ぼんくら記者・宮沢がいい味を出している。かってスター記者だった叔父の宮沢乙彦との関係性は、キャラは全く異なるが内田氏の浅見兄弟を彷彿とさせる。そういえば、二枚目だけど女性に疎い浅見光彦と宮沢は似ているかもしれない(宮沢記者は妻帯者で単身赴任中だが)。出張や旅行の折の移動中に読むのにうってつけ。旅のお供にどうぞ!
0投稿日: 2017.04.07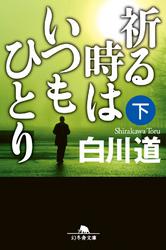
祈る時はいつもひとり(下)
白川道
幻冬舎文庫
本書の題名に納得:こんなにも内容を凝縮した題名は無いと思う。
上巻・中巻と何となくいらいらしながら読んでいったが、下巻に入り全ての伏線を収斂させるように物語は急激に展開する。香港の黒社会で暗躍するグループ通しの抗争・戦後の日本の黒幕と言われた組織・企業等々が複雑に絡み合い、スケールの大きな物語になっている(裏側も歩いたことのある白川氏らしい設定)。当初魅力に乏しいと思った調査屋・茂木が段々と格好良く思えてくる。鶴岡・永倉などの脇を固める登場人物も良い。白川作品なのでハッピーエンドは無いなと思いつつ読んでいったが、やはり最後は悲壮に満ちた終わり方だった(・・・というか、この作品ではプロローグの段階で純子の死は分かってしまうが)。『祈る時はいつもひとり』この題名が全てを語っている。
0投稿日: 2017.03.26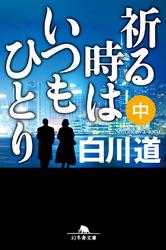
祈る時はいつもひとり(中)
白川道
幻冬舎文庫
主人公の洒脱な会話、ハードボイルドの典型的な文体だが、舞台設定が大きすぎて物語は遅々として進まない。
中巻を終了した段階(2/3)でも、まだ謎は漠としている。中国への香港返還を目前に控えた中国華僑の裏社会 vs 日本の裏側を牛耳る大物ブローカーとの対立だろうとの片鱗は見えてきたが、こんな単純な構図なのだろうか?ハードボイルドのきびきびした文体に助けられて読み進めているが、はたして下巻で物語が急展開するのだろうか。
0投稿日: 2017.03.26
ナチ_コチ_ショチさんのレビュー
いいね!された数92
