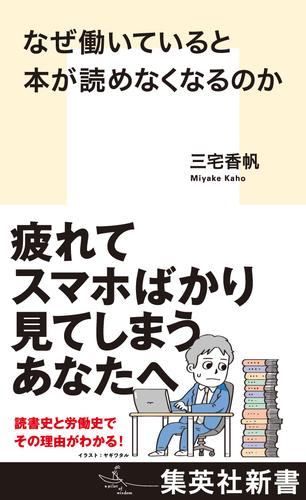
総合評価
(1418件)| 329 | ||
| 515 | ||
| 367 | ||
| 70 | ||
| 11 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在、題名の通りに本が読めなくなってる人にはお薦めしたくない本No.1。 結論は読まなくても分かる通り、働いていると余暇がなく、読書時間が作れないから。 全身全霊で働いている日本社会が、半身で働き、余暇で時間つくれるような社会になっていけたら良いねという本。 ------------------- 題名でだいぶ注目された本だと思うけど、 内容的には【日本の労働社会と読書論】といったまじめな感じで、前半は"読書"という位置付けが時代ごとに変わっていったこと。後半は"労働"の中で必要な情報と知識がわかれていった背景。 情報ではなく、知識(ノイズ)が多く、読み進めるのに時間がかかった。参考文献、多すぎる…。 誰にでも分かるように簡単に書いてくれ。 他の小説はすぐ読めたのに、 なぜこの本を開くと眠くなるのか。 (1ヶ月くらいかかりました)
13投稿日: 2026.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の問題なのに,なんか俯瞰で捉えられて自分は悪くない気持ちになれる 「本が読めない」と言ってる人にとりあえず1冊目で薦める本
0投稿日: 2026.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白い視点だなと思った。明治時代の話から始まって、それぞれの時代背景を踏まえて考察していて、なかなか納得感があった。 最終章での著者の提案は、ぜひ世の中に浸透していってほしい。
0投稿日: 2026.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ働いていると自分が好きだった本を読む時間・気力がなくなり、ライターとなってそれを実現した著者が、教養としての読書が社会構造の中に占める位置づけの変遷から分析した本。階級が固定された武士は名をあげ身を立てる「立身」(儒教背景)、名誉はないが階級突破できる商人は「出世」(仏教背景)であった江戸時代から、職業自由化された明治では立身と出世が統合され、修養がエリートが身を立てる手段とされた。修養はエリート層にのみ許された昇格手段であったが、円本の登場により書籍がやすくなり、新中産階級が出現した戦前戦後からは「教養」がエリート階級に追いつき学歴を得るための社会的成功の手段とされた。 三宅氏が引用したビデオと書籍が興味深かったので引用する。 「花束みたいな恋をした」では、新潟の地方公務員家庭に生まれた麦は正社員こそ社会的なステータスでありそれを維持するために必要な「情報」の収集に特化するあまり、気休めはパズドラ、啓蒙書ですらない空っぽの自己啓発書を読んでいる。一方の絹は、文化的豊かさが自分の一部であり自分を維持するために読書を続けようとしており、社会的地位と仕事に求める違いがかつて鏡の半身とされた2人を引き裂いていく。 バブル期ころまで高度経済成長の流れで、知識は会社が研修で与えてくれるものとなり、行き帰りの通勤電車でよむ文庫本が趣味としての読書を定着化させた。読書や映画は趣味であり、啓発書が流行したのもこの頃であった。 グローバリズムが定着してからは、自己実現の手段として仕事が定着し(働き方改革は仕事以外の自己実現を求めているが)、成功のために必要な「情報」とそれ以外の付加価値(ノイズ)を提供する読書や映画、という区分が自然とできていった。過去の書籍や音楽は趣味であり、ビジネスで必要なインデックス情報=ファスト教養を得るための要約本が流行した。啓発書は過去の成功体験から学ぶものであったが、成功するためのハウツーに特化した自己啓発本が増える結果となった。 このような世の中で、働きながら本を読むためにはどうすればよいかに対して、著者は仕事に依存しない半身労働社会を提言しているが、半身労働を実現した著者が、書籍では届かないはずの全身労働者に対して書籍で提言しているというのは、皮肉である。 広告代理店1990年のベストセラー「脳内革命」は様々なストレスを与える周辺環境を変えることができないが自分の受け止め方を変えれば成功できるという、閉ざされた情報社会における処方箋であると看破している。
0投稿日: 2026.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ私自身も思う事。 本読む時間作ろう!って 認識しないと結構時間ってないよね。 筆者が言ってたのを引用すると 働きながら本を読める社会の実現の為に、読書で自分に関係のないノイズの文脈を取り入れる余裕を持つことのできる半身の働き方を提案した 本は内容によって、自分を色々な所に瞬時に連れて行ってくれる そんな刺激を一生で逃すのは勿体無いね。 そんな時間が必要か不要かは 自分の判断、そんな贅沢な時間を切り出すのも 自分の判断だね。 さー明日も会社帰り、サクッとカフェ寄って 本読もうと‼️ 何がいいかしら〜
2投稿日: 2026.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ『弱さ考』に通づる。弱さ考を読んでから、もしくはこの本の後に『弱さ考』をぜひ読んでいただきたい。 これほど有名でベストセラーになったのに、なぜぼくの耳には「半身」の声が届いていないのだ? 2024年(レビュー時の2年前)からこの本の存在は知っていた。今では「三宅香帆」の名前と顔をどこでも目と耳にする。 なのに、それなのに、「半身」の「は」の字も聞こえないのはおかしい。この本をちゃんと読んでいるのか。 「半身」になるのが怖いのか?「全身全霊」にすがりたい(楽になりたい)のだろうか?でもそれは「楽」だが、楽ではないだろう? 全身全霊で働いているからこそこの本も読めなくなるのだろうか。 未来に目を向けすぎて、今を未来のために過ごしている。そして、いつかの今に燃え尽き、鬱になる。 ここ数年の「鬱」の言葉の多さには驚く。 社会福祉を学んだから「鬱」や「躁鬱」を知っていたが、社会に出て(2020年以降)からの「鬱」の言葉の多さには驚く。(『躁鬱大学』『弱さ考』然り。) 「日本人の15人に1人が鬱」ってことを「常識」として知っていることもかなりおかしな話である。 経済の論理(無駄なく生産性を高める)や資本主義(競争と負債による成長ファースト)による未来への不安から、仕事に打ち込み稼ぐことを第一とし、それが新自由主義(自己決定、自己責任)によりもともとの気質(OS)かのように錯覚(内面化)する。 (人類のもともとの気質かもしれないし、そうじゃないかもしれないが、人類史的には否定されるのかと思う) それでもなお働き続けたい人、そこに没頭したい人がいる。 年末年始は20人に1人が働いているらしい。逆に言えば19人休んでも年末年始は回るのだ。店舗によって忙しさは半端ないが、社会は回っている。20人に1人で社会は回るのだから、それで回し続ければ程よい回転に、いつかなるのではないかと思う。 ぼくの今年のテーマは「回り道」。それは「半身で生きる」ことにも通づると思っている。
0投稿日: 2026.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史の話や読み慣れない本の引用が多くて全然頭に入ってこなかった。 読書はノイズを含みつつ情報を手に入れる手段だが、自分が手っ取り早く「本が読めなくなる理由が知りたい」と思いながら読んでいることに気付かされた。 この本が持つノイズを受け入れられなかった。 自己啓発本を速読する術を身につけようと思っていたが、そんなことしたらますます本が読めなくなりそう。
7投稿日: 2026.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、読書量の問題ではなく、働き方と思考の構造そのものに原因があると気づかせてくれる一冊。忙しさに追われるほど、短期的な成果や効率に意識が偏り、深く考える余白が失われていく。経営においても、学ぶ時間を確保できない状態は危険信号だ。本書は、読書を「娯楽」ではなく、思考を取り戻すための行為として再定義してくれた。
1投稿日: 2026.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半は明治、大正、昭和時代に読まれた本についての解説。男性の教養としての自己啓発本、全集ブーム、サラリーマン小説…の流れが面白かった。実家に全集があったり、母が「世界文学全集を読んで育った」と誇らしげに語っていたのを思い出した。なるほどです。 後半は題名の通り、なぜ働いていると本が読めなくなるかの解説です。私も不思議にならなかったのですが、さすが三宅さん、言語化してくれています。ネットは必要な情報だけ、読書はノイズが含まれています。このノイズが人生を豊かに膨らましてくれる気がします!私自身ハウツー本ばかり読んでいたけど、最近小説が楽しくなりました。 じゃあどうやったらスマホ中毒から、読書をしたいモードになるか?まずは社会全体が働きすぎと言うことを三宅さんは言っています。全身全霊ではなく半身くらいでオッケーだよ、と言っています。例えば集5を週3、専業を兼業に、そんな社会になってほしいと。 とはいっても、急に社会が変わるわけではないので、まず私たちができる取り組みとしては、 1新しい本を見つけるためのSNS、読書アカウントを見つける 2iPadを持つ 3通勤帰りカフェに寄り読書習慣にする 4本屋さんに行く、新しいジャンルにも挑戦する でも無理はしない。嫌な時は休む。 なるほどです。本が読めないのは、社会の構造的な問題、働き過ぎてみんな疲れているせいもあるんだね。三宅さんはもやもやしたことをいつもスッキリさせてくれます!感謝!!
1投稿日: 2026.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分から遠く離れた文脈に触れること-それが読書なのである。 著者:三宅香帆氏がこの本で伝えたかったことは、この一文に込められている。 日本人と本との向き合い方を明治時代からふりかえり、 バックボーンの社会情勢にも踏み込んでいる。 仕事への過度な向き合いが読書を妨げていることを時間軸と社会軸で分析している。 半身で働く社会の実現が読書だけでなく、ライフスタイルそのものを変えていくと結論づけている。 時間もエネルギーも必要だと思うがそんな社会の実現を夢見る1人の読者です。
1投稿日: 2026.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ労働環境や時代の変革の中で読書がどのような位置付けになっていくかの流れが話されていて、とても面白かった。 特に読書がエリート層と労働階級との差別化のために使われていたり、知識の象徴としてインテリアに飾られていた点が興味深かった。現代でも読書は他の趣味に比べて崇高なイメージがあるが、それがずっと昔から脈々と続いていたのかと初めて知った。 また、読書は知りたい情報だけでなく、それ以外のノイズも含めて知識として蓄えているという話があった。それが現代では逆に不要なものとして認識されている点も改めて指摘されるとそうだなと感じた。自分としてはそのノイズが面白いと思っており、自分の知らない世界や感性を求めて読書しているのかもしれない。
1投稿日: 2026.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「全身」ではなく「半身」 で社会を生きること 今の自分には刺さる言葉だった 何度過労で倒れたか 仕事も趣味も「半身」でいいのかもしれない 読み終えたのが病院のベッドの上という皮肉さよ
3投稿日: 2026.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書史が面白かった。筆者の言葉を借りれば、現代ではノイズになった読書だが、それでも「読書」という言葉のイメージは、かつての明治や大正の時代から変わっていないのでは無いかと思う。 タイトルの問いの答えは私自身が薄々感じていたことで、それをきれいに言語化してくれており、そのおかげでさくさく読めた。 今、働きながら読書ができている私は、半身的な働き方をしているとも言えそうだが、未来はどうか分からないのが少し不安に感じた。
9投稿日: 2026.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の結論、「全身」ではなく「半身」で頑張ることが許される社会にしよう、にとても共感しました。今の時代、労働に役立つ純度100%の情報が重視されるのは仕方ないかもしれません。でも、自分は他人の文脈やノイズもすべて込み込みの「読書」を受け入れられる人間であり続けたいなと思いました。ちなみに、私も三宅さん同様に、帰宅途中にカフェなどに寄って行う読書は捗ります。
4投稿日: 2026.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の歴史パートではへぇーと頷き、後半今の時代に読書するにはという考えには共感から来る頷きを。 情報と知識の違いについてというパートが特に共感。自分は情報を得に行った際に入ってくるノイズを楽しみにしているのだと実感 趣味や仕事に対するスタンスとして、初心に戻るために定期的に読みたいそんな一冊
0投稿日: 2026.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
明治初期の出版黎明期から世代ごとの読書の位置付けを紐解いている。 比較的事実に裏打ちされた考証になっているが、ところどころに著者の好みの作品名が出てくるのが少しだけ気になった。 最終的な結論としては読書習慣を切り口に、全力で頑張りすぎる社会を変えていきませんか?的な提案で締めている。
0投稿日: 2026.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書と日本社会の歴史遍歴に触れつつ、読書の優先順位が下がったことだけでなく、働きすぎないことを提言 確かに自分も社会人になりたて、転職したての頃は人生の中で働く事がかなりのウエイト占めていたけど慣れてくると私生活にも余裕ができ読書や映画にも時間を使えるようになった 仕事だけが全てじゃないって思える気持ちと精神的ゆとりが重要だと思った
0投稿日: 2026.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書は苦手意識を持っていたので、読めるか不安になりながら読んだが、普通に新書だった。 本を習慣的に読むようになり、読む力がついたのか、以前よりも新書を読めるようになっていた。 以前から思っていたが、仕事はよい加減で取り組み、読書も継続していきたいと改めて思った。
0投稿日: 2026.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ単なる「読書術」の本ではなく 私たちの働き方や社会の構造に切り込んだ内容で とても興味深く読みました! 本を読めなくなったのは 「個人のやる気」のせいではなく 「全身全霊で働くこと」を求めすぎる 社会構造にあると指摘します 仕事に全てのエネルギーを注ぎ込み 余暇は受動的な娯楽(スマホやショート動画) でしか癒やせない この「ノイズを排除して効率を求める生き方」が 寄り道を楽しむ読書の時間を奪っていたのだと気づかされました 私は毎日読書する時間がないと落ち着かないが… 読書ができるということは 仕事と仕事以外のバランスが取れているから できることなのかもしれない これからは効率ばかりを求めず 自分の人生に「豊かなノイズ」を取り戻すために あえて立ち止まる勇気を持ちたいと 感じた一冊でした!
0投稿日: 2026.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりになんだこの本(怒)となってしまった。 帯に、スマホばかり見てしまうあなたへ。と言うようなことが書かれていたので、てっきり現代人の本離れはスマホやPCのせいであり、こうしたら本を読む時間ができ今までとは比べ物にならないくらい本が読めますよ。と言う内容を期待していた。 しかし蓋を開けたら、読書の習慣は明治時代から始まり云々と読書の歴史が語られ、都度都度「司馬遼太郎」と「花束みたいな恋をした」の話題が出てくる。好きなようですね、作者さん。 正直、かなり期待外れでKindle unlimitedじゃなかったらブチギレていたと思う。 なぜ、売れているのかさっぱりわからない。
1投稿日: 2026.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近では紅白の審査員など、テレビ出演も多くなってきた著者。初めて読みました。 作家ではなく、文芸評論家。読んでみて分かりました。自分の考察も交えながら、その時代を象徴するような著書からの引用の幅と量と深さに驚いた。なるほど、これが文芸評論家かと。 明治時代、生まれながらの身分が解放されて、教養が必要になり、昭和にはステータスになり、現代では、予期せぬ事柄を知る可能性があるノイズであると。故に、ノイズがない自分が望む情報だけを得ようとしてしまう。 そんな時代に警鐘を鳴らしている。そんな想定外のノイズも含めて許容できるよう、全身でなく、半身で働こう。働きながら本を読める社会をつくるため半身で働こう。それが可能な社会的にしようと締めている。 同感です。
8投稿日: 2026.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治以降の日本の読書史に触れながら、現代人の読書離れについて論じた本。仕事をしていると、スマホゲームくらいならできるけど、読書はなかなか難しいと感じる人は結構多いのではないだろうか。それぞれの時代の政治・経済と読書がどう関係があるのか、現代の読書離れを引き起こしているのは何か。働きながら読書ができる社会に、との筆者の主張はぜひ一読を!
1投稿日: 2026.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ思ってたんと違った。でも知らない知識も得られたので、そこは楽しめた。が、なぜ?に対する答えが…答えに辿り着くまでの道のりが自分はあまり腑に落ちるというか納得できるというか解決策でもないというか…ふーむ…だったので、星3つ!でした。
3投稿日: 2026.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の日本人の読書離れを考察する一冊。 序盤から延々と続く労働と読書の関係性についての考察はとても面白く読み進めることができたものの、終盤は少しだれてしまった。「半身社会」を提唱する著者のメッセージには、とても共感した。 ノイズではなく結論を求める人が多かったのか、「序盤が不必要、口説い」などの批判が見られたものの、本当の読書好きはむしろ序盤のノイズの方が楽しめたのでは? 最も共感できたのは、読書を「他者を理解するためのツール」としていた点。夥しいほどのノイズに触れることで、読書好きは無意識のうちに多様な価値観を受容できる人間になると僕は信じている。 以前勤めていた職場のパワハラ上司が、「仕事第一、本は自己啓発本しか読まない」人間で、部下にパワハラをしまくる前時代の遺物のような存在だった。 そんな人間たちは、本書を1ミリも理解できないのだろう。 おそらく日本の津々浦々にこうしたパワハラ脳筋人間は多数存在するものの、そうした存在を社会的に淘汰できるにはまだまだ時間がかかりそうだ。 完全に自論だが、自己啓発本ばかり読む人間は他者に対する期待が大きく、尊大に振る舞う傾向があるように感じる。やはり、ノイズまみれの趣味(読書)に触れておくことは必要だと考える。 まぁ、ここまで書いている時点で、自分自身がパワハラする人間の価値観を受容できていないのだが…。 もっともっと読書をする必要があると再認識。
1投稿日: 2026.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。 労働と読書(≒自分にとって新しい知)の関係性を分析していく一冊だと感じた。 現代では「読書=ノイズ込みの知、情報=ノイズ無しの知」の後者がもてはやされている。 だが、自己研鑽のために情報を効率よく収集したとて、その行き着く先は強迫観念にとらわれ疲弊した自分。 この本を読む時、大前提として三宅さんは「知的好奇心」がとても旺盛な方であると思いながら読むべきだと思った。 (ここから雑感) 世の中には活字を3行以上読めない人間がおり、「読書」に対するスタンスは世間で二極化していると個人的には見ている。社会全体を考えたときに、知的活動自体に否定的な立場の人間は今後どうなっていくんだろう。 三宅さんの読書量と批評力には驚かされるばかりで、三宅さんの出ているYouTubeもよく見てしまう。
0投稿日: 2026.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ働いていると本が読めなくなるのか。 「いや、仕事忙しくてこの本すら読めないわ〜w」というクソリプが発売当初は散見されたが、本書はまさにこのクソリプを送る人の深層心理、本を読む余裕もないほど働きすぎること、働きすぎることを賛美する風潮に疑問を呈した一冊だ。 前半では、読書にまつわる社会的な流行を概観し、後半は、現代人がなぜ読書を必要としていないのかを分析するという構造。 読書とはノイズを含む知識を取り入れることであり、そんなノイズを受け入れるために全身ではなく「半身」で働こうという提言に思わずハッとさせられた。
1投稿日: 2026.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校の時はインターハイ出場校の中で1番練習してない自信がありました。社会人になってもほぼ残業せず、残業している人が偉いような風潮に違和感を感じてました。 今も残業はほぼしていないですが、平均以上の評価をもらえてると思います。 確かに突き抜けたり1番になるためには全身全霊で打ち込む必要があると思いますが、今まで半身で生きてきた自分も悪くなかったと思わせてくれてありがとう
0投稿日: 2026.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本来、読書とは自分から遠く離れた未知の文脈に触れる行為であり、結果や効用が事前に予測できない「アンコントローラブルな娯楽」である。しかし、新自由主義的な価値観のもと、全身全霊で働くことを求められる現代社会では、そのような娯楽を楽しむ余裕が失われつつある。代わりに、人はパズドラのような、短時間で成果が得られ、コントロール可能な娯楽へと流れていく。これは個人の怠慢というより、時代背景を考えればある意味で必然なのだと本書は示している。 かつて読書は、修養や教養――人格や知性を高めるための営みとして位置づけられていた。しかし現代では、仕事を通じた自己実現が半ば強制され、「仕事に直接役立つ情報」だけが価値を持つようになった。その結果、自分から遠く離れた文脈に触れることの意義は軽視され、読書よりもSNSなど、即時的で実用的な情報取得手段が選ばれやすくなっている。 筆者はこうした日本の雇用環境に問題意識を示し、全身全霊で働くのではなく、「半身で働く」ような働き方を提案する。そうして初めて、人は再び読書や文化に向き合える余白を取り戻せるのだ、という主張が本書の核である。 この内容は非常に身につまされるものだった。私自身、未知の体験を得るはずの読書よりも、過去作の映像作品など、よりコントローラブルな娯楽を優先して楽しんでいることに気づかされた。もしかすると、心に余裕がなく、文化を受け取る体力が落ちているのかもしれない。そう言う時こそ無理に何かを享受しようとせず、まずはしっかり休み、心の余裕を取り戻すことが大切なのだと思う。その上で、また本や文化を楽しめる状態に戻れたら――本書は、そんな静かな自己理解と回復への視点を与えてくれる一冊だった。
5投稿日: 2026.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルとまえがきに惹かれて、するすると三宅香帆さんの世界観へ。 明治時代から順に現代まで読書の意味合いを当時ベストセラーとなった本の設定を背景に読み解いていきます。たしかに、時代と売れる本の内容はリンクするものだなー、ふむふむと読めました。 1990年代くらいまでの話は確かにと思いながら読めましたが、現代そして自分が働き出した2010年代と近くなるに連れて納得感が薄くなっているのは自分自身を客観視できてないからかもしれない。 最後の章の提言にも確かにと思いつつ、それじゃ生活できんよねとトレードオフを感じながら、でもそれでもそんなふうになれば心は穏やかに生きていけるだろうなとも感じました。
12投稿日: 2026.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ自身については、スマホを持つようになってから、やはり読書量は相対的に減ったとの自覚があるので、そのような方向性の内容が記載されているかと勝手に想像していましたが、明治維新以後の読書の歴史が俯瞰されていて、興味深く読みました。 ただ、もし今の時代を生きる私たちの読書量が、昔より減っているとすれば、労働が主たる原因というよりは、やはり読書以外に費やすもの(SNSや動画)が増えたからではないかと思います。そうすると、著者の提案するような半身社会を目指したとしても、空いた時間は読書以外で埋まってしまうのではないでしょうか。
1投稿日: 2026.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり検証に基づいた考察が書かれていて、エッセイというより論評のような著書。「仕事に全身全霊を捧げているからではないか。半身の働き方を取り入れてはどうか」「全身に傾いている人は他者にも全身を求めたくなってしまう」「しかし持続可能ではない。そこに待ち受けるのは社会の複雑さに耐えられない疲労した身体」「読書は自分とは関係ない他者を知る手段」という説に対し共感が持てた。これからはこのように考えて残業しないようにしたいものだ。
0投稿日: 2026.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書という行為が、明治から現代にかけてどのような価値として捉えられてきたのか、をわかりやすく説明している。 特に、「読書はノイズを生み出すものであり、現代はそのノイズを求めていない」という指摘はとても興味深い観点だった。 たしかに、疲れているときには、あえてノイズを取り入れたくないという感覚は良く理解できる。
1投稿日: 2026.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み初めは、何が『本が読めなくなる』や、スマホを置けば良いだけやないか。『働いていると』とは、とんだ言いがかりや、と思った。なにせこちらは40年前の新卒なので土曜日の大半は出勤し、勤務終了は20時過ぎ。そこから2時間自転車トレーニングし、閉店間際の銭湯に駆け込む生活だ。それでも本は読めた。スマホやSNSがなかったからだ。長じて管理職になったころは働き方改革前だ。朝は7時半から21時半まで仕事して、そこから自転車で鹿の飛出す山中を走り、24時にベッドに入り15分間読書して気を失うように寝入る生活を20年続けた。スマホやSNSから距離を取っていたからだ。 おっと自身を語りすぎたか。そんなわけで、スマホを置いたら良いだけやないか、何をごちゃごちゃ言うとんねんと思い読んでいくと、考察はどんどん深くなり面白くなっていった。ただ、結論が弱い。半身で働くような働き方をしていると年取った時後悔するでと声を掛けたくなる。せっかく労働時間が適切に管理できる時代なんだから、全力で仕事をしたうえで、それ以外の時間は仕事を引きずらず切り替えて生活することを強く意識する方が良いと思う。 価値観をどこに置くか、それを大切にできるかだと思う
2投稿日: 2026.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ流行から3周くらい遅れて読んだ。 2025年の私の目標の一つに、月5冊、年間60冊の本を読むことがあった。結果としては、年間60冊は達成できていたのだが、明らかに読めた月と読めなかった月の差が激しかった。 昨年の仕事の状況を思い返すと、明らかに忙しかったのは、夏と冬。みると7月と12月の読書量が他の月と比べて明らかに少ない。8月のお盆休み、そして9月に取得した休暇期間で一気に数を伸ばし、なんとか年間の目標を埋めた状況とも言える。 12月、年間の目標は達成したとはいえ、ペースが明らかに遅いことを危惧し、少し無理してでも読もうと思っていた。結果は惨敗。12月の読書カウントは1冊、それも年末の休暇中に一気読みしたものだった。 本書に書かれていたとおり、「半身」で働くことの重要性は身に染みて感じているものの、一方でどうすれば半身になるのかわからない。自分でも、一つのことにしか向き合えない、とても不器用な人間であることも理解している。読書時間の問題だけでなく、集中力が続かない、体がこわばっている、疲れやすい、など多方面に影響が出ているような気がする。「年齢を重ねるともう少し楽になる」と言ってくれた大先輩の言葉を信じつつ生きてはいるものの、もう少し早くその楽さに気づけないものかと四苦八苦している。 今年の目標は、均してではなく、月5冊。義務ではないけれど、半身を体得するための一つの方法仮説として取り組んでみたい。
0投稿日: 2026.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文芸オタクと自称される筆者の読書論。筆者は私の娘とほぼ同年代のお嬢さんだが、読書時間が取れないことに爆発して、リクルート社を辞めてしまったという行動力を持つ人。読書系ユーチューバーとしても有名なようで、ちょっと覗いてみると頭の回転の速さと小気味よい喋りに驚かされる。さて本書の内容だが、自らの体験と豊富な読書量に裏付けられた話で、読書と労働をめぐる明治から令和までの歴史書にもなっており、面白かった。本が読めないのは読書時間が無いのでは無く、ニーズがなくなったということ。読書で得られる体験が、ネット情報との比較でノイズまみれの使えないものになっているという指摘は鋭い。彼女が志向する「半身社会」。実現のビジョンは分からないとのことだが、大丈夫。中高年になれば自然とそうなります。そうならざるを得ない体力の衰えが悲しくもありますが・・・
1投稿日: 2026.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ働いていると本が読めなるメカニズムについて、納得感のある考察が綴られている。 本を読めなくなった実体験も重なり、共感の連続だった。
1投稿日: 2026.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ前から気になっていた本。 タイトルがいい。 “読めない人”を知りたかった。 でもわかった。 読みたい時に読みたい本を読む。それしかない。 心が整っていないと。って思う。
1投稿日: 2026.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」というキャッチーなタイトルがずっと気になっており、やっと図書館の予約が回ってきた。しかしこの本を手に取っている人は、時間がない中でも読書を優先したり、その方法を模索している層であり、どうにも本が読めない状態に押しつぶされている人ではないのかもしれない、と思わないでもない。前半はタイトルとは少し違う内容で、いわば明治に始まる「読書の歴史」。ここまでさかのぼって論じなくても、1980年代くらいから始めてもらえば十分かも。とはいえ後半、筆者の提案へ向かって、どんどん力強い内容になっていく。「自分から遠く離れた文脈に触れることーそれが読書なのである。そして、本が読めない状況とは、新しい文脈をつくる余裕がない、ということだ」「しかしこの社会の働き方を、全身ではなく、半身に変えることができたら、どうだろうか」「人生を信じることができれば、いつか死ぬ自分の人生をどうやって使うべきか、考えることができる。自分を覚えておくために、自分以外の人間を覚えておくために、私たちは半身社会を生きる必要がある。疲れたら、休むために。元気が出たら、もう一度歩き出すために。他人のケアをできる余裕を、残しておくために。仕事以外の、自分自身の人生をちゃんと考えられるように。他人の言葉を、読む余裕を持てるように。私たちはいつだって半身を残しておくべきではないだろうか」。最後に一言、「花束みたいな恋をした」の絹ちゃんと麦くんの切ないすれ違いの例が出たのは、驚きであり秀逸だった。
1投稿日: 2026.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログあれだけの文献を、日本国民の「読書」に焦点をあててまとめ上げたところに、価値と渾身さを感じる 『花束みたいな恋をした』が底流となって書かれているので、理解が進みやすい 「読書とは常に、階級の差異を確認し、そして優越を示すための道具になりやすい」 この文にはドキッとした ただし、その優越性は明確には否定しなかったと解釈している 「教養」と「修養」の二項対立から、「知識」と「情報」の二項対立へ スマホを触るのと本を読むことの差は、ノイズの有無が関係しているという指摘と、 内面から行動の時代に突入したことを、さくらももこの『そういうふうにできている』というタイトルが示していという指摘は、非常に面白かった 私たちは、自分の想像以上に時代や社会システムに思考を左右されていて、新自由主義や資本主義が高度に発達し続けているからこそ、コントローラブルなものに目を向ける本が流行る 半身社会の実現について、論を深めた本をまた読みたい 誰も傷つけない書き振りも令和っぽい
1投稿日: 2026.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ2026年最初の1冊。遅ればせながらようやく読みました。日本の労働と読書の歴史を振り返りつつ、現代人にとっての読書の意義やインターネットで得られる情報との対比が興味深かった。 最終的には作者が考える働き方改革まで披露してて、熱い思いが伝わる1冊だった。将来的に作者は政治家になってそうな気がする。
7投稿日: 2026.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ・読書の歴史とその時代ごとのベストセラーの傾向 ・他者の文脈をノイズと捉えてしまう「教養」と「情報」 ・全身全霊ではなく、半身で働こう など面白い提言があって楽しめた。が、 最初と最後の著者の語りの部分で、「立ち居振る舞い」 が「立ち振る舞い」の誤用で載っていて、これは校正通したの?と疑問に思ったのと、親しみやすさを出すためだと思われるが、「ぶっちゃけ」「めっちゃ」「待っててくれて」などの口語的な文章に面食らった。せっかく面白い内容なのだから、しっかりした言葉で、著者の想いを紡いで欲しかった。砕け過ぎた言葉を使わなくても、著者の力量で親しみやすさは表現できると思います。
1投稿日: 2026.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
明治からの日本読書歴史。「文脈というノイズ」は山口周氏「世界のエリートは〜」の美意識と共通。ショートカットではなくノイズを楽しみ、吸収しよう。
0投稿日: 2026.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこっちにたくさん書いた https://note.com/yurariho/n/n7a87b212ed22
0投稿日: 2026.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
話題になってたこちら。まさに休みに入って本が読めたというわけで手に取りました。 どうして働きながらでは本が読めなくなっていくのかに対する著者の答えを導きだした経緯を労働と読書の歴史に照らし合わせて辿っていく本書。ここでいう「本」は本そのものではなく、何らかの娯楽や趣味、労働以外のものを指す言葉として使われています。 新書なの忘れてた!というのもあるけど、なかなかに歴史のポーションが大きいので、特に前半はその辺多少パラパラと飛ばし読み。しかしこれこそが、読書は「ノイズ+情報」を得るもの、自分に不要だと思うところをノイズに感じて飛ばそうとするのが現代だ、ということの体現であり、ハッとする。おそらく著者はこれを意図的に書いていると思うのです。 労働に全身全霊をささげるのではなく「半身」で働こうという意見、確かになと思う反面、半身ってもう少しいい言葉はないのかなと思ってしまうね。余裕をもって、みたいなニュアンスだと思うのだけど。あと、「花束みたいな恋をした」は、今の労働と趣味の関係を表したとてもその通りの作品だけど、n=1を参考に使いすぎで気になったなーなど。
1投稿日: 2026.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
とても緻密な内容と思いながら読んでいたが、参考文献の数はハンパなく多かった。。。 読書史と労働史について、思った以上に勉強になった。 三宅氏の結論である半身社会、良いと思う。 だがしかし。個人的な話し。自分は社会福祉(障害福祉)の分野で働いているのだが、この分野では国が十分に対応していないせいで、目の前に大きな問題がたくさん実在している。それを少しでも改善したいと考えると、やる事、考えなければならない事は勤務時間内では到底収まらず、残業やプライベートの時間を割く事になってしまっている。 こういう事は、どの業界でも多いのではないかと思う。 半身社会は簡単な事ではないと思うが、自分の人生の豊かさを考えた場合、参考にしたい生き方であると思えた。
1投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
めちゃくちゃ納得する理由でなるほどな〜となった!本は読めないのにパズドラはできるっていう描写があって、たしかに読書はできないのにSNSや動画をだらだらと見ることはできるのはなんでなんだろうと日頃思っていたからその謎が解明されてすごく納得した!読書は(良い意味で)ノイズっていうのもすごくわかるし、欲しい情報だけを手に入れたいなら読書ではなく調べた方がいいっていうのもわかるな〜と思った!題材になっていた『花束みたいな恋をした』も読んだ後に観たら、より説得力が増したし三宅さんって言語化うまい〜〜と思いました
1投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログまとめには納得いかないが、それまでの「本」という立場の移り変わり、現代とのギャップが詳しく解説されており面白かった。
0投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトルに対する答えとしては概ね以下である。 現在はノイズの少ない「情報」によって勝ち上がっていく時代であり、ノイズの多い(≒知りたい情報に直結しないものも含む)本は選ばれにくい、ということのようである。 高度経済成長期のサラリーマン時代は円本が飛ぶように売れ人々は通勤電車で小説を読んだというが、これは時代が立身出世のために「教養」を求めたからだという。 スマホ=情報と語られやすいが、私にとってはスマホこそ多くの広告、おすすめなどが混ざりノイズの塊であり、疲れてる時にはより一層そのノイズが苦しく思う。 スマホにより情報を早く受け取り活用することが正となった現代において、少しずつ集中できる時間が短くなっている。読書はまるまる一冊読み終えるのに時間がかかるから、この集中力のない時代に相性が悪いのだろう....... でも、この本が飛ぶように売れたということはみんな働いて疲れていても本が読みたいということだし、そうなると、そういう層が本に求めるものってなんだろう?とちょっと興味がある。教養?癒し?孤独?
1投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本的に日本の読書に関する歴史を述べていく論述が主、そして筆者の「こういう社会なら良くない?」という提案がある。その主張には大賛成。文体も読みやすく、他の著作にも興味をもてた。
1投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログまず大前提として、この本は忙しい方がどうにかして本を読みたい時に手に取る書籍ではないということを述べておきたいと思います。 全体的に日本の歴史を遡り、読書という趣味がどういった変遷を辿るのかという話が9割。残りの1割が「こういう社会なら良くない?」という話。 改めて自分がどうして本を読めないのかという立場を振り返る書籍なので、これを読んだからといって本が読めるようにはなりません。 ただ、日本人が置かれている現状だったり過去の人たちにとって読書がどういったものだったのかということを振り返るのは少し面白かったかなと。 物価高で本にお金を使うのも憚られる現代に、本体価格1000円を払って読むには少しだけもったいないかなと感じました。この作者さんの他の本も気になっているので、また読んでみたいなと思います。
3投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ年末年始にかけて読んで良かった新書。三宅さんはyoutubeの出版区の「本屋で本気の爆買い」で知った。すごい読書魔だと分かり、彼女が書いた文章を読んでみたいと購入。自分自身も本を読む時間をどのように捻出すれば良いのかを知りた買ったので、まさにこれは私のための本だと思った。 「全身全霊で仕事しないで半身半霊で仕事をしましょう。そして、本を読みましょう。」というような最後の締めは、私にとって雷に打たれたかのような衝撃的な言葉だった。 何事にも全力で取り組みたい私にとって、今年は少し色んなことに対して全力じゃなくて良いのでは?と、肩を叩かれた気分になった。 2026年も全身全霊で馬車馬のように動きまくるぜ!と思っていたので、少し自分を見つめ直す良い機会になって良かった。 三宅さん!感謝です!
1投稿日: 2026.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
初めて新書をちゃんと読んだかも。。。 いつかのSNSで頻繁に目にしており、ついに実際に手に取った。タイトル通り、働いていて本が読めなくなっていたから。笑 労働と読書の関係を、時代に沿ってまとめられていた。 理解の深さは差があれど、後半の「読書とは自分から遠く離れた文脈に触れること。」やノイズの話はとてもしっくりきた。 自分自身、仕事と子育てに忙しい今、読書に限らず、物を減らしたり時短家電を活用したり、とにかくノイズを減らして疲れないように生きることに必死すぎると自覚がある。 半身で働く社会には賛成。実現に向けて自分ができることを小さく積み重ねていきたい。 そして最後に、そもそも新書ってなんなのだろうと思ってchat GPTに聞いたら「特に、忙しい社会人が**“知的に状況を把握するための最低限の装備”**として使うことが多いです。」という解説があり、苦笑してしまった。
1投稿日: 2026.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かに社会人になってから長く本を読めてなかったな… 年間数冊でおすすめされたからってので読んでましたね〜 最後の方に書いてあったように定期的に読みたくなる本の情報がどんどん流れてくるようにするのは本当に大事です!これで去年からガンガンに読むようになりました! 読書はノイズか〜ノイズを楽しめる人生に生きたいですね〜
1投稿日: 2026.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ新年早々いい本に出会えた!新書の面白さにハマりそう。感動した。浅いし論理の飛躍もあるけど目の付け所が良い。「半身」って大きなキーワードだ。全身全霊で働くのを辞めませんか、は勇気のいる提言。無理する自分や他者を称揚しないって難しい。美意識を変えなければいけないな。人生を信じるというニーチェの言葉、面白すぎる。共感しながら読んだ。三宅さんの文章は飾らず素直で今っぽいので、とっつきやすいなぁと思った。「私はいつでもあなたの読書を待っています!」には励まされて思わず笑顔になった。文章から愛嬌が見えて可愛い。 過去や他者をノイズだと考えて切り捨てたくないなぁ。他者の文脈に身を委ねる「半身」良い言葉だなぁ。文芸評論家、頑張ってほしい!いやー良かった
1投稿日: 2026.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史が並んでいるところは中弛みあって1ヶ月くらい放置してしまったけど、後半読んでると全部繋がってて構成うまいなーと感心して読了。 全身全霊で仕事することが正義みたいになるから余裕なくなって本が読めなくなる。ノイズが発生しないYouTubeやケータイゲームで流してしまう。疲れてくるとそうなるよなー。サボるわけじゃないけど半身で仕事して趣味も家族も大事にできるような生き方がいいよね。ここ数年大事に考えてることを言語化してくれてる気がしてとても好感が持てた。最終章読んでるころに紅白の審査員に出てたのも御縁かな。他の本も読みます!
1投稿日: 2026.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログかつてラッセルが『怠惰への讃歌』で説いたことを、労働史と読書史から令和版アプデしたような、してないような、って感じの本。 8ページに及ぶ参考文献一覧には狂気すら感じる。 著者の言う「読書とは自分から遠く離れた文脈(ノイズ)に触れること」という定義は結構しっくりきた。仕事に「全身」を捧げるあまり、未知のノイズを身体が拒絶し、手軽な情報やスマホゲームに逃げてしまう。読書ができないのは時間の問題ではなく、脳の「バッファ」の問題なのかもなー、と。 提示される「半身で働く社会」は、資本主義に全てを差し出したくない身には、なんかよさげだ。 ちなみに著者は働くのが大好きらしいが、私は大嫌いだ。体力のバッファが全然違うし。「そういう人もいるんだ、タフだなあ……」と遠い目になる。これもまた、本書を通じて「自分とは異なる他者の文脈」を獲得できたということ…かも?
12投稿日: 2026.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ消費社会分析に興味があると言ったら友人が勧めてくれた、読書と労働をめぐる社会分析の一冊。 タイトルは一見自己啓発に近いが、最終章を除き、明治から2010年代まで各時代における読書と労働の関係の変遷が記述されている。この点においては、各時代における労働・読書・娯楽に関する意識やトレンドの流れを理解することができ、「昔流行したもの」や「それがなぜ流行したのか」が好きな自分にとっては非常に面白かった。 しかし、最終的には「「全身」でなく「半身」で働くことで、読書というノイズを含む知を積極的に取り入れよう」という啓蒙に終始しており、そこには「本をもっと読んで欲しい」「自己啓発書を読まずに文芸本を読んでほしい」とった著者の願望も見え透いているように感じた。この点においては、結局その啓蒙こそが自己啓発本と同じ構造になってしまっている。 自分は今学生であるが、ついこの前まではスマホのリール動画や大学の課題、課外活動に走り、本を開くことはほぼなかった。しかし、「この人凄い」と思う大学の同期や教授、(ごく一部の)社会人に共通するのは、不意にみせる知識と、その知識に裏打ちされた独自の意見、そしてその意見を狼狽えずに主張できるだけの確固たる自我であった。そして彼らの魅力(料理だったらおそらく濃い味である)は、ノイズの無い情報だけでなく、多種多様なノイズを含んだ知を摂取し、咀嚼してきた帰結であると感じた。ノイズの無い情報は、早く得られる分、脳の咀嚼数が少ないように感じる。ノイズの無い情報へと辿り着く迅速さが評価される現代ビジネスに出向く前に、様々なノイズをできるだけ摂取して、ノイズと労働を共存する社会人になりたいと思った。もしくは、ノイズへの逸脱が許されやすい業界に行きたいと思った。
2投稿日: 2026.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題になっていた本ということもあって手にとってみた。 現代において、また働いている中で本が読めなくなるという事象について、読書と出版の歴史から紐解くというコンセプトが面白かった。 それぞれの章ごとに納得させられる点や新たに得る知識があり面白かったが、結論に関してはあまり共感できなかった。 誰もが「半身」で働くこと、働けることを目指すべきだという筆者の主張には賛同できるところもあるのだが、これもまた筆者の言うところの「他人の文脈」「ノイズ」を読むことを拒否してはいないだろうか。 「半身」で働ける環境というのはおそらく平和・平時を前提としている。その点は、誰かが「全身全霊」で取り組んでいることで維持されてはいないだろうか。「半身」で無せることは数多く、殆どはそうなのであるが、ごく一部の本質・本源的な価値は誰かの狂人的な「全身全霊」で生み出されているように思う。 社会に迎合するようで恥ずかしくもあるが、結局はダイバーシティなのではないだろうか。「半身」で働く人も「全身全霊」で働くことも尊重され、そこに優劣はないということではないか。 ここまででも自明であるが、私自身「全身全霊」で働く側の人間だ。この本を通しては「半身」であろうとする人の思想を理解することができた気がする。 それだけでもこの本を手にとって良かったと思っている。 「半身」であろうとする人には「そうだそうだ」という共感を、「全身全霊」であろうとする人には「そういう考え方もあるのだ」という気付きを提供してくれる本だと思う。 結論には納得がいかない部分もあったのだが、それにいたるプロセスの面白さ、筆者の文調に意義を感じたので星3つとしたい。
3投稿日: 2026.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近求めていたここ100年、数十年の間の歴史について読書史という観点から書かれていた。情報はノイズのない一点についての解釈であり、知識とは想定しない範囲の物事を新たに知ることである。とても納得をした終盤の章だった。 読書という文化が明治後期からエリート層(サラリーマン)により始まり、大正、昭和を経て私の生まれた平成まで続いた。ベストセラー、所謂流行った本とは時代による流行や思想が顕著に現れている。そもそもの良い人間像というものがここまで短い期間に変動するものなのかと思うと少し考えてしまう。そもそも生きる時代が同じだからこそ、向かう先が似通っていくのは当然だが、私にとっての理想像を追求する人生でありたいと思う。 職業に対する賭けの姿勢は私に取って共感できるものであった。半身の社会の実現はそう近いものではないと思うが、この時代の変動の速さを見ると意外とすぐそこの未来なのかもしれない。 若者は答えを求めるのが早いとあったが、情報のみを収集する若者にとって、思考を置き去りにしているためこれまでの時代の流れなどを鑑みることができないのかもしれないと感じた。それは自身にも思い当たる節がある話だが、世の中はノイズに塗れている事象で溢れかえっている。多方面から物事を考え、なんだってすぐに答えを決めつけるような人間にはなりたくないと感じた。だからこそ私はこれからもノイズを受け入れられる許容量で生きたいと思う。
1投稿日: 2026.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ全身全霊で働くことを美化しない。 著者も書いていたが、自分自身に強く言い聞かせたい言葉だと思った。 働くことで、自分の世界が広がったり、こうなってたんだ!と知的好奇心を刺激されたり、人から称賛されて嬉しくなったり、、ポジティブな感情になることが自分自身は多いなと思う。 ただそれは、周りのサポートや恵まれた環境などが重なっているからこそ感じられる感情でそれが人生の幸福の全てではない。 働くことにポジティブでいられないときもきっとくる。そんなときに働くことだけに全身全霊捧げていたら、自分を卑下してしまうだろうと思った。 実際自分が勤めている会社も「全身全霊」を求められているように感じるし、その方が称賛される傾向にあるだろう。 しかし、少し無理をしてでも「半身」になろうすることが大事なのだと痛感した。 年の瀬に読めて良かったと心の底から思える一冊。 全身全霊で頑張れない自分も好きでいれるようになろう。
8投稿日: 2025.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログまぁ疲れてれば読めないよねぇ……「じゃあなぜゲームやスマホはいじれるの?」に確かに!なんで! この疑問に対して明治以降の本の立場や扱いがどう変化しているか、からの語りも面白い。句読点が読みやすくするためのものであり結構最近のものであると知った時の衝撃たるや。 「読書=ノイズ」の表現がもっと利点を含む言葉にできまいかと感じつつも結論含め諸手を挙げて賛同。 働いてるけど、三宅香帆さんの著書をもっと読みたくなりました。
2投稿日: 2025.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ働いていると本が読めなくなるのか。三宅 香帆先生の著書。働いていると本が読めないなんて言い訳でしかない。そういう人は働いていなくたって本が読めない。一日中スマホをいじっているくせに時間がないから本が読めないなんてありえない。本が好きなら本を読む。本中毒読書中毒ならどんなに忙しくても本を読むもの。本を読むことを他人に強制するつもりはないけれど。
2投稿日: 2025.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書を通して社会の歴史を語る 決められた本を朗読することが主流だったが、活版印刷の普及により読書が民主化・個人化した。一部の男性だけのものだった本はすべての人が手に取れるものになった。疲労社会の現代では速読書と自己啓発本が売れている。 知識=ノイズ+知りたいこと 求めている情報だけをノイズのない状態で消費できるのがネットであり、事故や社会の複雑さに向き合うのが読書である。
0投稿日: 2025.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書とは、自身から遠く離れた文脈に触れること。 読書はノイズ込みの知であり、情報はノイズ抜きの知である。 「自己実現」=「やりたい仕事」の風潮のなかでは、効率よく合理的にノイズ抜きの知を求めるようになる。 労働と読書について、明治初期から令和までの社会情勢や労働市場の変遷と、それに伴いベストセラーとなった書籍の紹介が興味深くわかりやすかった。
0投稿日: 2025.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読めるようになる為の本というよりかは、読書を通して日本の労働の歴史を学べる本! まとめ方がわかりやすくて読みやすいし、働き方の歴史を知る事で今の働き方を見直せる本
19投稿日: 2025.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
感じていることが言語化されまくってた 全身全霊が正義ではない、ヘルシーに働けることこそが正義やと自分も思う 本をノイズ扱いしてしまう時点で疲れている、休まないと。
1投稿日: 2025.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログノイズの定義が本中でコロコロ変わる。各時代の流行語をとりあえずただなぞりたいだけのような感じ。筆者の独善的で的外れな論評、かと思えば唐突なお気持ち表明が始まったりと、とにかく読み進むのが苦行でしかなく、その苦行に見合うだけの得られるものは無い本。
1投稿日: 2025.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ■ この本のテーマ・キーワード 読書 労働 ■ 心に残った一文・言葉 読書は人生の「ノイズ」なのか? ■ 特に印象に残ったことや小さな変化 私も含め、現代人が本を読めなくなっているのは労働環境が影響している…。そして凄まじい勢いのネット社会で情報があふれているからこそ、読書という「すぐ答えに辿り着かないもの」への嫌悪感のような感情が芽生えている…。 そう聞くと、これまで自分が読書をできなかったことも仕方ないか、と思えた。 ただ最近では、やはり読書をすることの意義が大きいことを身をもって実感したので、能動的にノイズを摂取していきたいと考えるようになった。 ■ 感想や読書メモ 「なぜ働いていると本が読めなくなるのか?」という問いに対して、単純に「忙しいから」という答えを出すのではなく、過去の労働史をさかのぼるということこそが「ノイズ」であると感じた。 私も初めは「え…?労働史…?しかもそんな昔から…?」と思っていたが、その過去があるから今につながっていることが解説されたあたりでパッと霧が晴れたような気分になった。 そして、今後もし誰かに「なぜ~?」と聞かれたら、その背景まで語れるようになっている気がする。 これこそが読書の意義であり、知識の深みなのだろう。 これからも前向きに、能動的に読書を続けていきたい。
0投稿日: 2025.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
こうやって本を読んでいる自分自身が、階級を意識していることをまざまざと突きつけられた。労働だけに汲々とする毎日を送る労働者階級ではないぞ、知的階級だぞ、と思いたい気持ちがないとは言えない。 スマホによって集中力がなくなって本が読めない、かと思いきや、情報化によって奪われたのは集中力ではなく「未知を受け入れる力」なのか。 ゆとり世代なのでさすがに仕事に全身全霊なんて論外だけど、趣味にも全身全霊を求められているという指摘はまさしくそのとおりで耳が痛い。オタクや推し活の文脈ではよく、もっとイベントに行け、もっとグッズを買えと煽られるが、それは資本主義と自己実現が悪魔合体した現代病なのだな。 自分も趣味にもっと参加しなければと、仕事を犠牲にしてまでのめり込んでいたときもあったが、それってたまたま趣味と仕事が逆転してるだけで、理屈はワーカーホリックと何も変わらないわけだ。もっとゆるく、にわかで何が悪い、と半身で気楽に趣味を楽しみたい。そうしないと1人の時間がなくて本が読めない!
1投稿日: 2025.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最後の方からようやく面白くなった。自分が歴史にあまり興味がないというのもあると思うが、歴史を辿るシーンが7-8割の構成比となっており、この本の着地点がどこにあるのか、何を伝えたい本なのかが見えづらかった。 最終章の現代編のところに入ってから、結論として本が読めないのは「ノイズを入れたくないからである」というところは腑に落ちた。 だが、"半身で働く"はイマチイ自分にはしっくりこず、このフレーズが多用され、この世界を作ろうと強く訴えかけるクロージングに若干の宗教みを感じた。
0投稿日: 2025.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ労働史でたどる読書啓発とその変化という視点が興味深く、ここしばらくSNSで見る本書の批判が全く的外れに感じたのはいうまでもない。労働と読書啓発は経済成長とその停滞にも連動するようにも見え、特に80年代に若者の読書離れが言われた頃の(ちょうどその頃まさに当事者だった)読書傾向と、それ以降はリアルタイムで知ってはいたものの、実はこういう事情があったのかと気付かされることも多かった。結論の「半身で生きる」というのには共感する。本が読める環境がある仕事ではあるが、年ごとに読書の軽視と労働の厳しさが増してきていると感じるので、仕事ばかりの人生は過ごしたくない。もっと本を読ませろ。
0投稿日: 2025.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書では、労働と読書の歴史を振り返ることにより、それぞれの時代において労働と読書にどのような関係があり、人々が労働と読書をどのように認識してきたのかを整理している。 関連を見出すにあたって、所々やや強引な部分も否めなかったが、それでも大枠は作者の意見に同意である。 近年では、労働における成功に必要な要素として「行動」という自分にとってコントロール可能な部分への変化を促す「自己啓発本」が流行っている。本によって知識を得ることが目的ではなく、得た知識に基づいて自分の行動の変革を行うことが目的であり、その目的をより容易に達成するために人々は必要な情報以外をノイズとして除外する。だからこそ、今の自分に必要でない情報(ノイズ)も含む読書よりも、自ら求める情報に直でアクセスできるインターネットの方が流行る。 また近年では、好きなことを仕事にするのが望ましいとされる風潮があり、「仕事で」自己実現を図ろうとする人が増えているという点も作者は指摘している。それが故に、余暇の時間では娯楽としての読書を楽しむよりも、仕事に有益な情報を効率良く得ることに人々は注力してしまうと。しかしこれは、生活のあらゆる側面が仕事に変容する社会「トータル・ワーク」に繋がりかねず、バーンアウトを招く危険性がある。 本書は、仕事を始めとして、家庭や趣味などなにかしらに全身全霊で取り組むことはバーンアウトを招く危険性があるため、何事も「半身で」取り組むことが望ましいと結論づけている。 なにかひとつに絞って全力を注ぐことはある意味で楽だが、様々な文脈で生きることの余白を残しておくべきだと。 この本では、タイトルの問題提起にある現代の課題への答えを導くために、明治〜大正まで歴史を遡り丁寧に解説されているが、正直早く結論が欲しい!と度々なってしまっている自分がいて、やはり自分もノイズを嫌う現代人になってしまっているんだなぁと感じた。 でもやっぱり読んでいく中で、この文には同意するな、これはどうなんだろうか、と考える経験ができて、それが今知りたいことに直結する訳ではなくても、考えるという行為こそが重要であり、人生を豊かにするんだよなと、読書の面白さを改めて感じられた。 また、「ノイズは一見今の自分に関係ないように見えても、いつか自分に回ってきて役立つことがある」だからノイズを含む読書は大切だというような作者の話だったが、個人的には全て「何かに役立たなければいけない」訳でもないのではないかと思う。何にも役に立たないノイズも楽しんで良いのではないかと。読書好きの三宅さんにはそんな結論を導いて欲しかったなぁと個人的には。 「知は常に未知であり、私たちは『何を知りたいのか』を知らない。何を読みたいのか、私たちは分かっていない。何を欲望しているのか、私たちは分かっていないのだ。 だからこそ本を読むと、他者の文脈に触れることができる。 自分から遠く離れた文脈に触れることーそれが読書なのである。 そして、本が読めない状況とは、新しい文脈をつくる余裕がない、ということだ。自分から離れたところにある文脈を、ノイズだと思ってしまう。そのノイズを頭に入れる余裕がない。自分に関係あるものばかりを求めてしまう。それは余裕のなさゆえである。だから私たちは、働いていると、本が読めない。 仕事以外の文脈を、取り入れる余裕がなくなるからだ。」(p234)
0投稿日: 2025.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は働いていても多く本を読んでいるので、この本にあまり興味がなかったのですが、読んでみると、単に本を読める小手先のコツを紹介している訳ではなく、歴史を紐解き、根本から日本社会の働き方を見直すことを提案するという、予想外にマクロな視点で驚いた。
7投稿日: 2025.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトルだけ見て共感したのであらすじ等はよく確認せず購入。 本書は読書史と労働史を時系列で追いながら、なぜそのように至ったのか筆者の考察が描かれている。 参考文献の豊富さに驚いたとともに、最終章の提言には現代社会が抱える問題の解決にも繋がりうるようなものも書かれており、働き始めてから本が読めなくなったのはなぜかという素朴な疑問から、ここまで考察するかと素直に感心した。
0投稿日: 2025.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ### **まえがき** - 近代以降の労働史と読書史を並べて俯瞰することにより、歴史上日本人はどうやって働きながら本を読んできたのか、そしてなぜ現在、私たちは働きながら本を読むことに困難を感じているのか、と言う問いについて考えた本。 ### **序章 労働と読書は両立しない?** ### **第一章 労働を煽る自己啓発書の誕生 明治時代** - 明治時代に黙読が誕生。江戸時代、読書と言えば朗読だった。当時本は個人で読むのではなく、家族で朗読し合いながら楽しむものであった。明治時代になって活版印刷に大量に書籍が印刷できるようになり、大量の書籍が市場に出回り。個人の趣向に応じた読書が誕生。 - 明治の日本は職業選択の自由、そして居住の自由が与えられた。それまで住む場所すら選べなかった青年たちは、田舎から出て出世し、手柄を上げる夢を見るように。 - 明治時代のベストセラーとなった西国立志編。「修養」という言葉を日本で使った書籍。 ### **第2章 教養が隔てたサラリーマン階級と労働者階級 大正時代** - 明治時代にエリートの間で広まった「修養」は、大正時代には労働者階級の間に既に根付いていた。 - 大正時代は、自らを労働者階級とは区別する「読書階級」ことエリート新中間層が誕生。 - 大正時代のエリートの中では、「教養」が広まった。知識を身に付ける教養を通じて、人格を磨く事が重要だと考えるようになった。 - 行為を重視する「修養」と知識を重視する「教養」は違うものになり、教養=エリートが身に付けるもの、修養=ノンエリートが実践するもの、という構図になった。 - 「修養」=労働者としての自己研鑽(仕事のための自己啓発)、「教養」=(労働内容に関係なく)エリートとしてのアイデンティティを保つための自己研鑽、という二つの思考に分離した。 ### **第3章 戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか? 昭和戦前・戦中** - 「自分は労働者階級ではない」と誇示したいサラリーマン層にとって、円本全集は打ってつけのインテリアであった。 - 日給制の労働者と異なり、月給制のサラリーマンは、月額〇円、という円本の支払体系ともフィットしていた。 ### **第4章 「ビジネスマン」に読まれたベストセラー 1950~1960年代** - 戦後、じわじわと労働者階級にも「教養」が広がっていく。「教養」は家計の事情により学歴を手に入れる事が出来なかった層による、階級上昇を目指す手段。 - 高度経済成長期、サラリーマン階級(長時間労働して余暇が少ない)が増加。そのため、サラリーマンに特化した本、つまり英語力や記憶力を向上させるハウツー本や、読みやすく身近なサラリーマン小説が誕生し、結果的に労働者階級に読書を解放することになった。 ### 第5章 司馬遼太郎の文庫本を読むサラリーマン 1970年代 - 1964年の東京オリンピックの頃には9割以上普及した白黒テレビが、1970年代の娯楽の中心。テレビドラマ化(大河ドラマ等)によって小説が売れる、という循環が生まれる。 - 通勤電車の中の読書、という習慣もこの頃から。 ### 第6章 女たちのカルチャーセンターとミリオンセラー 1980年代 - 1980年代、出版業界の売上はピークを迎えつつあった。70年代に1兆円、80年代に2兆円に。 - サラリーマンの間で、学歴よりも処世術の方が大切である、という価値観が広がる。 - 80年代、カルチャーセンターに通う事は、一種のステータスになっていた。カルチャーセンターで学ぶことが、彼女たちにとって「教養」を身に付ける行為だったからだ。80年代になり、ようやく主婦やPLにも「教養」が開かれた。 ### 第7章 行動と経済の時代への転換点 1990年代 - 心への興味、その結果としての心霊現象への関心やスピリチュアル的な感覚が広まったのが1990年代前半。 - その結果、1990年代後半には、自分に対して、何か行動を起こす事で、自分を好転させる、つまり、「行動」を促す事で成功をもたらす「自己啓発書」が誕生。従来の自己啓発書は「行動」のプロセスはなく、内面の在り方(心構え、姿勢、知識)を授ける事に終始していたが、90年代の自己啓発書は、読者が何をすべきなのか、取るべき「行動」を明示している点で異なる。 - 「行動」が注目されたのは、新自由主義が関係している。バブル前の「一億総中流時代」が終わりを迎え、新自由主義的な価値観(成功も失敗も自己責任)を内面化した社会が登場。 - 「読書離れ」と「自己啓発書の売上の伸び」は反比例する。 - 自己啓発書の特徴は、自己のコントローラブルな行動の変革を促す事にある。他人や社会といったアンコントローラブルなもの(ノイズ)は捨て置く。読書は労働のノイズになりうる。 ### 第8章 仕事がアイデンティティになる社会 2000年代 - 「自己実現」という言葉には、暗に「仕事で」というニュアンスがつきまとう。 - 「好き」を活かした「仕事」。そのような幻想ができたのは、1990年代から2000年代にかけて、新自由主義が関係している。 - 1980年代と比較して、2000年代のフルタイム男性労働者の平日平均労働時間は長くなっていた。パートが増えたり週休2日制が普及したため、労働時間は短くなっているように見えるが、平日だと長期化している。自己実現という夢が若者を長時間労働へと導いていた。 - IT革命により読書離れがはじまる。求めている情報だけを、ノイズがない状態で読むことが出来る。それがインターネット的な情報。 - 自己啓発書は1990年代よりも売れていた。自己啓発書とインターネット的情報の共通点は、ノイズが除去された点。自己実現のためコントローラブルな行動に注力し、社会的階級を無効化して勝者になるべくして、若者が求めていたもの。 ### 第9章 読書は人生の「ノイズ」なのか? 2010年代 - 長時間労働が是正される一方、「やりたい事を仕事にする」幻想は、2010年代にさらに広まる。 - 生きていく上では他者と関わるのだから、他者の文脈も知る必要がある。読書は他者の文脈を知る事が出来る。余裕がないと、自分から遠く離れたところにある他者の文脈を、ノイズだと思ってしまう。だからこそ、半身で働く事で、余裕を持つ必要がある。 ### 最終章 「全身全霊」をやめませんか? - なし ### あとがき - なし
0投稿日: 2025.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分自身は今は働きながら本を読む生活が送れている。だけど、過去確かに全く本が読めていない時期があった。 その時のことを思い出すと、一人暮らしで気ままな生活だったし、労働時間も今より短かったような…。 自分の場合は、余暇の無さというより、読書から何を得るのか、なぜ本を読むのかということを明確に意識していなかったから、他の娯楽や、ジャンクに得られる情報に流れていたのかもしれない。 ここ数年で意識していることは、他者の思考様式や他者視点をインストールするための手段としての読書が、人生をとても豊かにするということ。他者の思考には、当然自分にはないノイズが多量に含まれていて、むしろこれを積極的な摂取するために読書するという意識でいると、安易な情報収集に流されずに、読書と向き合うことができるようになるのかもしれない。 読書をテーマに労働への向き合い方を考えるきっかけを提示してくれる本でした。
1投稿日: 2025.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこれ読んだら、Vlogのような生活できます!って訳じゃなかった。まぁ考えればなぜって言ってるからそうか!方法じゃなくて理由話してるよな!つまりは、働きすぎんなよってことですかね。社会人になったらもっかい読んでみようかな。学生の自分にはほへーって感じでした。色々な作品がされていて興味湧きました。
0投稿日: 2025.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読もうと思った理由】 タイトルが気になった、最近よく見る著者だった、売れてる?作品だと知って、手に取りました。読書の歴史が知れそうで面白そうに思えたためでもあります。 【感想】 この本を読めば読書が出来るようになる、というわけではなかったし、そういった点ではいまいちな内容でした。視点が独身者に偏っていて、家庭がある人や年配の人、若い人、などにはトンチンカンな回答になっている印象でした。 自分の生活の中で読書をする時間を確保するためには、結局は「仕事をする時間を減らす」というのが正解だと思うけど、自分ではなかなか解決が難しいし、これについては、あくまで自分で考えて行動しないといけないな、と改めて思いました。 ただ、日本の会社員を中心とする「労働史」としてみると、ものすっごく面白かったです。タイトルは興味を持って貰うために付けたものかもしれないが、内容を正しく反映するなら「日本人と読書の歩み」とか(つまらなそうに見えるが)にした方がしっくりと来ると感じました。そういった本だと思って読めば、ものすごく面白く興味深い本だと思いました。この点においては、読んで本当に良かったし、とてもとても楽しめました。 本書内の気になった箇所を以下にメモとして残しておく -------------------------------------------------------------------------- そんな明治時代初期に読書界に起きた革命と言えば、「黙読」が誕生したことだ。江戸時代、読書といえば朗読(!)だったのだ。当時、本は個人で読むものではなく、家族で朗読し合いながら楽しむものだった。 黙読は日本語の表記も変えた。黙読の普及によって「もっと目で読みやすい表記をつくり出す」という目標が出版界に生まれた。そうして普及したのが句読点である。句読点の使用が急速に増加したのは明治10年代後半~20年代のことだった。 明治時代に活版印刷が日本で普及し、それにともなう表記の変更により、本は急速に読みやすいものとなった 大正時代、日本の読書人口は爆発的に増大した。 前述のとおり、日露戦争後、国力向上のために全国で図書館が増設された。小学校を卒業した人々の識字率を下げないために採用された手段が、読書だった。地方に至るまで日本の隅々に図書館が誕生し、それによって爆発的に読書人口は増えた 読書人口の増加 大正時代、日本の読書人口は爆発的に増大した。 前述のとおり、日露戦争後、国力向上のために全国で図書館が増設された。小学校を卒業した人々の識字率を下げないために採用された手段が、読書だった。地方に至るまで日本の隅々に図書館が誕生し、それによって爆発的に読書人口は増えた エリート学生の間に広まる「教養主義」 「修養」が労働者階級の教育概念となった一方で、大正時代のエリート階級の間では「教養」が広まった。 ついあべよししげ大正時代、和辻哲郎や阿部次郎、安倍能成といったエリート階級の青年たちは、 新渡戸稲造に影響を受け「知識を身につける教養を通して、人格を磨くことが重要だ」と語るようになる。 そう、修養と教養の差は開いた。行為を重視する修養と、知識を重視する教養は違うものになった。 こうして「教養」=エリートが身につけるもの、「修養」=ノン・エリートが実践するもの、といった図式が大正時代に生まれていった 日本最初の積読本「円分」本 円本ブーム成功の理由①「書斎」文化のインテリアとしての機能 円本ブーム成功の理由②サラリーマンの月給に適した「月額払い」メディア 円本ブーム成功の理由③新聞広告戦略、大当たり 「郊外住宅地の発展による通勤時間という名の読書時間の発生」の2点を挙げている(前掲「モダン都市の〈読書階級〉」)。つまり戦前のサラリーマンたちは、企業に決められた休日と通勤時間に本を読んでいた、ということだ。たしかに、時代小説がよく売れているのも、当時のサラリーマンが電車のなかで読むのに適していたからだと考えると合点がいく。 もはや本を読むどころではない戦時中 その後、戦時中になると、もはや本を読むどころの話ではなくなってしまう。と言っても人々はすぐに本を読まなくなってしまったわけではない日中。戦争初期にはまだベストセラーが存在していた 紙の高騰は「全集」と「文庫」を普及させた もちろん旧制高校、あるいは大学を卒業していた都市部のサラリーマンたちも、 戦前から引き続き、同様に「教養」を求めていた。世は空前の教養ブームだったのである。戦前の「円本」ブームの再来かのように、戦後、「全集」ブームがまたしてもやってきた。 雑にまとめてしまえば、高度経済成長期の長時間労働は、日本の読書文化を、結果的に大衆に解放したのである。サラリーマンが増えた時代、みんな働いているのだから、働いている人向けの本を出すのが、一番売れるはずだ。出版社はそのように考え、余暇時間の少ないサラリーマンに売るために、サラリーマンに特化した本 ――つまり「英語力」や「記憶力」を向上させるハウツー本や、読みやすくて身近なサラリーマン小説を誕生させたのだ。そしてそれは結果的に、労働者階級に読書を解放することになった。読書が大衆化し、階層に関係なく、読書するようになる時代の到来である。 現代においては「若者の読書離れ」なんて言われても、スマホがあると本を読まないのは仕方ないよねうんうん、と頷くほかない。が、中 と頷くほかない。が、実は「若者の読書離れ」という言葉が定着したのはなんと40年も前のことだったのだ。 1970年代から言及され始めた「若者の読書離れ」という言説は、80年代にはすでに人々の間で常識と化していた。読売新聞と朝日新聞で「若者の読書離れ」を問題にした記事を調査すると、80年代に激増していた そしてもっと言えば、このような傾向は、さくらももこだけに限ったことではない。日本全体で、心への興味、その結果としての心霊現象への関心やスピリチュアル的な感覚が広まったのが1990年代前半だった。 つまり他人や社会といったアンコントローラブルなものは捨て置き、自分の行動というコントローラブルなものの変革に注力することによって、自分の人生を変革する。それが自己啓発書のロジックである。そのとき、アンコントローラブルな外 部の社会は、ノイズとして除去される。自分にとって、コントローラブルな私的空間や行動こそが、変革の対象となる。 読書は労働のノイズになる 自己実現が果たせる仕事に就けることが最高の生き方だ。好きなことを仕事にするのが理想的な生き方だ。―――そのような考え方はそもそもどこから来たのか? 答えは2000年代のベストセラーにあった 「13歳のハローワーク」 働いていて、本が読めなくてもインターネットができるのは、 自分の今、求めていない情報が出てきづらいからだ。 求めている情報だけを、ノイズが除去された状態で、読むことができる。それが 〈インターネット的情報〉なのである。 知識と情報の差異 情報=知りたいこと 知識 = ノイズ+知りたいこと ※ノイズ・・・・・・他者や歴史や社会の文脈 コントローラブルなものに集中して行動量を増やし、アンコントローラブルなものは見る価値がないから切り捨てる。 それが人生の勝算を上げるコツであるらしい いくら死ななきゃいいと思っていても、現実は、かすり傷ですら痛い。 そのことに皆が気づき始めたのが2010年代後半だった。 2015年(平成27年)に電通過労自殺事件が起こり「働き方改革」という言葉が叫ばれ始めた。2019年に施行された働き方改革関連法は時間外労働の上限規制の導入、年次有給休暇取得の一部義務化など、長時間労働にメスを入れる形になった。高度経済成長期からはじまった、この国の長い長い長時間労働の歴史がやっと変わろうとしていたのである。 読書を「娯楽」ではなく処理すべき「情報」として捉えている人の存在感が増してきているのだ。 稲田は現代人の映画鑑賞について、以下のような区分が存在すると述べる。 芸術鑑賞物――鑑賞モード 娯楽消費物――情報収集モード 早送りで映画を見る人たちの目的は「観る」ことではなく「」る」ことなのだと稲田は説く。 教養とは、本質的には、自分から離れたところにあるものに触れることなのである。 か? それは明日の自分に役立つ情報ではない。明日話す他者とのコミュニケーションに役立つ情報ではない。たしかに自分が生きていなかった時代の文脈を知ることは、今の自分には関係がないように思えるかもしれない。 しかし自分から離れた存在に触れることを、私たちは本当にやめられるのだろう 私たちは、他者の文脈に触れながら、生きざるをえないのではないのか。 つまり、私たちはノイズ性を完全に除去した情報だけで生きるなんて――無理なのではないだろうか。 自分から遠く離れた文脈に触れること――それが読書なのである。 そして、本が読めない状況とは、新しい文脈をつくる余裕がない、ということだ自分から離れたところにある文脈を、ノイズだと思ってしまう。そのノイズを頭に入れる余裕がない。自分に関係のあるものばかりを求めてしまう。それは、余裕のなさゆえである。だから私たちは、働いていると、本が読めない。 仕事以外の文脈を、取り入れる余裕がなくなるからだ。 マレシックは、バーンアウトの本質的な原因は、現代社会が「トータル・ワーク」文化になっていることだと語る。 「トータル・ワーク」とはドイツの哲学者ヨゼフ・ピーパーがつくった言葉だ。ピーパーは『余暇―文化の基礎』において、生活のあらゆる側面が仕事に変容する社会を「トータル・ワーク」と呼んで批判した。 半身こそ理想だ、とみんなで言っていきませんか。 それこそが、「トータル・ワーク」そして「働きながら本が読めない社会」からの脱却の道だからである。 「半身社会」こそが新時代である
0投稿日: 2025.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログあまり読んだことのないタイプの本だった。 センター試験の現代文に出てくるような説明文だな…と思いながら読んだ。 前半は「へぇえー」と言う感じはありつつ、歴史が苦手な自分はちょっと飽きてしまい読み進めずにいたが、図書館の返却日に慌てて最後まで読んだ。結果、最後まで読んで良かった!と思った。 最後まで読んだら、なんだか前向きになれた。その時代の価値観が全てではないんだな、と思えたから。 今この時代の価値観で、「こうあるべし」と思い込んでいたこと(例えば速読が善、とか)も、別のところから見たら正義ではなくなるんだなと思えたから。 自分は自分で良い、と思えた。
8投稿日: 2025.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書で言う「本を読む」とは、文字通り読書という意味でもあるが、それを含め、読者自身それぞれが生活に必要不可欠な文化のことである。 私はガッツリ読書が趣味なので、なおさらタイトルに惹かれた。ホント読めないんだよ、本。なんでだ、という思いで手に取った。 働いている(働きすぎな)ことで、そもそも物理的に時間がなくて「読めない。」 仕事に全身全霊で取り組むことで、こころに余裕がなくなり、働く私が求めている情報(仕事に役立つスキルだったり)じゃない情報を受け入れられなくて、そんな情報が集まっている本は「読めない。」 タイトルの言葉には、概ねこのような意味があると理解した。 あと、個人的に最近感じていることであるが、本が高くて買えないから「読めない。」も、SNSを見ているとけっこうあるなぁと感じる。 悲しいなぁ、と思う。 本を買うために働いているのに。趣味を楽しみたくて、働いているはずなのに。 働くに支配されてないか? 本書では最後に、今後の働き方についても提言している。大賛成である。読みながらいったん本を置き、拍手してしまった。 本すら読めない働き方なんて、悲しすぎるじゃないか。 働き方改革の規制が緩和されようとしている。 働きたい人は働いてくれ。そして大いに納税してくれ。ありがとう。先にお礼を言います。 私は、ほどほどに働き、新刊をそこまで悩まずに買えて読める生活が送れればそれでいい。 余談だが、私は推理小説やエッセイ、最近では新書を主に読むのだが、「そんな本を読んで何になるのか」はマジで言われたことがある。 その相手に、この本を投げつけたい気分でいっぱいである。
1投稿日: 2025.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代社会で生きる人達へのヒーリング本である。 読書がノイズと捉えられる社会構造自体へのアンチテーゼ。 私自身がこれからも本を読む事、そして本を読むことが好きな理由を見失わずに生きたいと改めて思えた本書だった。 ありきたりな結論かもしれないけれど、指標を示した著者と実際に売れているという事実に読書家として少し希望を持て世の中捨てたもんじゃないと感じた。
7投稿日: 2025.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
このような本が人気ベストセラー的な位置に並んでいるのが本当に悲しい。 ・働いていると本が読めなくなるのは何故か?それは仕事で疲れているから →当たり前すぎて、何を読まされていたのだろう感 小説だろうが論説だろうが、頭を使いながら読む行為であるのは違いない。仕事で頭が疲れたから頭を使わない行為に走りたいだけ。 (人の頭を使って考えている節もある…ショウペンハウエル参照) ・読書の時代の変遷 →ベストセラーの変遷を辿っているが、それは大衆小説という文学が広まってきただけ 故に読者層が広がって売れる本が変わっただけ 社会階級の格差社会が減った…というか、教養を必要とされていたエリート層が自分を守るために読んでいた古典以外の本がたくさん出てきただけの話 ・教養について →昔は情報源が本しかなかった、今は色々なツールがあるからノイズは不要になった? 確かに情報はネットで十分だが、故に情報の価値が下がってきている。これがファスト教養に近い? 教養=リベラルアーツは自由な人=奴隷以外になるための技術、自分の頭で考える技術なのだ。 多少の本を読んで得られる知識そのものではない。 この本が売れても、今後の本の売り上げが上がるとは思えず。著者の読む本もジャンク本ばかりなのかなと思ってしまう。最後に引用されているニーチェの文章と深みが違いすぎるのだ。
0投稿日: 2025.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書は知識すぎる!と苦手意識があり避けてきたが 本当に読みやすい!自分の興味がある新書というのはこの本で言うところのノイズの比較的少ない情報よりの本なのか…?と感じたほど。 花束みたいな恋をしたの視聴がここで役立つとは 思っていなくて驚いた。若者に優しい。 例えが柔らかくてわかりやすい。 説明文特有の作者の意図を読み取る みたいな作業の必要がなくてすらすらと読める。 他人とうまく繋がれないから物語を求めるというのはかなりぐさぐさきてしまったし、孤独だから本を読むと言っていた太宰治と通ずるものがある。 また、自己実現ときいて仕事を思い浮かべてしまうというのは本当に共感した。まさに!と思った。 たしかにそれは趣味でも良いものだ、目からウロコ。 何事にも浸りきれないことがコンプレックスで 何もないことと同じだと感じてしまっていたが 人生を信じきれてないだけなのかもしれない。 もっと自分に耐えられる自分になりたい。
14投稿日: 2025.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞広告を見て気になったので図書館で借りた。人気の本らしい。 以下メモ。 ⚫︎フルタイムで働いている男性が育児に関わろうとすると「育児休暇」を取れ、と言われる。しかし本来、育児は子供が家を出るまで十数年以上続く。が労働と育児を両立させる働き方の正解はいまだに提示されていない。 ⚫︎コロナ禍を経て政府は副業を推奨している。しかし週5フルタイムで働いている人がそれ以外に副業をしようと思ったら過労になりかねないはず。なぜ私たちはフルタイムの労働時間を変えずに副業を推奨されているのか。 ⚫︎現代の労働は労働以外の時間を犠牲にすることで成立している。 ⚫︎インターネット的情報は、「自己や社会の複雑さに目を向けることのない」ところが安直である。読書的人文知は「自己や社会の複雑さに目を向けつつ、歴史性や文脈性を重んじようとする知的な誠実さ」が存在している。 ⚫︎情報は知りたいこと。知識はノイズと知りたいこと。 ⚫︎就活している学生に伝えたいこととは、仕事は楽しい遊びやバイトと違って一生続く「労働」であり、合わなかった場合は精神や体力が毎日摩耗していく可能性があるということ。まつり。 ⚫︎自分で決めたことだから失敗しても自分の責任だ、と思いすぎる人が増えることはら、組織や政府にとって都合の良いことであることもまた事実である。市場という波にうまく乗ることだけを考え、市場という波のルールを正そうという発想はない人々。 ⚫︎芸術は、鑑賞物だから鑑賞モード。娯楽は、消費物だから情報収集モード。 ⚫︎読書はノイズ込みの知を得る。情報はノイズ抜きの知を得る。 ⚫︎iPadを買う。SNSアプリを絶対に入れないこと。
1投稿日: 2025.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ働いていると本が読めなくなるのか。自分自身は普段本を読む側として、自分自身とも重ねながら楽しく読むことができた。 著者の意見も交えながら感じたこと。ハッとさせられたこともあるので、言語化しておくための感想文 「なんで本?AIでいいやん」 これは、本を読まない友人からよく言われることだ。 その返答としてうまく言語化できないことは多かったが、今回この本を読んで感じた「本を読む理由」の自分の解は以下だ。 AI⇨問題解決、欲しい情報が最短で手に入る。 本⇨探求、欲しい情報+予想もしなかった学びや感情と偶発的に出会える 非効率ではあるが、私は探求したいのだ。 そして意外と、偶発的に出会える情報の方が今の自分にとって大切なことだったりする。そんな出会いにときめき、期待しているのだ。 作者の別書、考察する若者たちにはこう記載されている。 「今の若者たちは努力をしたくないのではない。報われない努力をしたくないのだ。」 かけた時間の総量が多いことに対して、対価を得られないイメージのある「本を読むこと」にネガティブな印象を抱く若者は多いかもしれない。未来が見えなくて不安な人にこそ読んで味わって欲しい。本がもたらす偶発的な出会いに。そこから広がる可能性に。
1投稿日: 2025.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログいろんな娯楽がある現代においての読書とは 菅田将暉好きなのかな 気楽に働いて本を読む時間も持とうね理論
1投稿日: 2025.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々に論文を読んでいる感じだった。 本を読むことの位置付けの変遷がわかって面白かった。 半身で働くこと。これから意識していきたいと思った。
1投稿日: 2025.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「半身で働こう」 三宅さんの主張には共感できる。 私は以前は残業が多く、仕事に全身で取り組んでいた。 しかしそんな生き方で、家族には苦労をかけ、自分の健康も害し、5年前に環境を変え、今はほとんど残業をせずに仕事を終えるようにしている。 仕事の手を抜いているわけではないし、むしろ短い時間で仕事を行うのだから、より大変なくらいだ。 しかし今は仕事が楽しい。 家族も自身も健康だ。 そうあれるように努力してきた結果ではあるが、この本で三宅さんの言うように、私はこれまで読んできたたくさんの本から得た文脈によって、今の状態に導かれたと思っている。 例えば星野道夫さんの『旅をする木』や、鴨長明の『方丈記』がそうだ。 これらの本を読み、『自分以外の場所がある』『自分ではどうにもならないことがある』ということを知った。 私がどれだけ残業しようが、正直社会はそれほど良くならない。 むしろそれによって家族や自分は健康を害し崩壊する。 余暇を楽しむ時間もない。 それなら、何が何でも仕事は仕事と割り切って、余暇の時間で家族と過ごし、自分の好きなことをすることを心掛けた。 だから今がある。 仕事は忙しいが、面白くて楽しい。 それは仕事以外の時間がちゃんとあって、家族と時間を分け合えているから感じられることだ。
3投稿日: 2025.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ全身で仕事に励む社会は家庭に全身で励む人がいるから成り立つと気付かされた。 読書できるくらい余裕を持って働きたいと感じる本だった。
1投稿日: 2025.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読む前はただ、余裕も時間もないからでしょ。ぐらいに思ってました。 でも、実際に書かれていたのは、労働の歴史から社会における読書の文化まで。本当に幅広く、そして私達にそれらについて興味を抱かせるように、かつ分かりやすく書かれていたものでした。 著者の読書量はYouTube動画などで知っていましたが、この方は本物の読書家で、そして知識人だと思います。 本当にこの本を読んで良かった!
1投稿日: 2025.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分自身、スマホを使って「ノイズのない知識」を求めようとしてしまう。なぜならそっちの方が楽だから。しかし、スマホでは得られない、タイパを重視していては得られない知識が読書から得られると考えさせられました。
12投稿日: 2025.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分はもっと頑張れる、もっと努力できると自分に言い聞かせて自発的に疲れてしまっている...これ俺じゃねえか! と読んでいる途中で気づいてしまった。YouTubeとかを眺めていても最初は何気なく娯楽として見ていたのにいつのまにか見たいチャンネルが増えすぎて、倍速で見るようになり楽しむというより知ることが目的となっている自分もいる。仕事が終わった後もこんな生活をしているからやっぱり疲れるのよね〜。 様々なことが多様化しているからこそ、全身全霊ではなく半身で取り組むことが心にゆとりを持つ秘訣なのかもしれないと思わされた。
1投稿日: 2025.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログAmazonランキングを見て気になり、本屋で購入。 タイトルだけで共感120%…。 帯の文面がさらに響いて、手に取らずにいられなかった。 趣味:読書 と、言うのに最近は躊躇する。 読書の中に、漫画やラノベは含めてはいけない気がして。 でも、最近の通勤時間はスマホのラノベや漫画ばかりで、「教養」「自己啓発」につながる本を読んでいないことに気づく。 そもそも、なんで本を読めないとダメなのか。 と著者に文面で問われて、とっさに頭によぎったのが、 「仕事ができなくなるから(自分の市場価値が下がる)」 「知識を入れていないと恥ずかしい」 「本を読むキャラと思われてるからなぁ」 といったネガティブな理由ばかりだった。 全然、「読みたい」じゃない。資格の本を積み上げても全然手につかないのはここにあるんだと気づく。 p234「自分から遠く離れた文脈に触れることーーそれが読書」 情報だけでノイズを聞く余裕がないから、自分に関係あるものばかりを求めてしまったり、単純作業のパズルゲーム(しかもお金と時間を使えば確実にレベルが上がる)や、欲しい情報がピンポイントで出てくるインターネットの情報をスマホでずっと見てしまう。 →これらは、新しい環境で、はじめまして〜ばかりで気を遣って疲れてしまうのに似ている。疲れていると未知の他者に会う気力がなくなってしまう。 →日本で無駄に社内資料を整えたり、根回しをしたりと過度な丁寧さを求める職場慣行があるのはこの現実逃避行動から派生しているのか? ビョンチョル・ハン著、現代の「疲労社会」というワードに衝撃 →社会の成長速度が落ちて不景気になったあたりから、日本は「好きを仕事に」「最高の生き方=好きな仕事」といった個性を活かせれば幸せだよ、という方針を打ち出してきた。そして、個性を大事にしつつ、市場の競争社会で勝つために、自己決定、自己責任の割合が徐々に増えてきた。 最近は副業、年金2000万、NISAなど、どんどん社会保障の割合が減っている。 仕事はフルで、余暇で“社会にとって“有意義な活動(介護、育児、副業、ボランティアetc…)をしてくれ、という見えない過重労働のメッセージに我々は振り回されている。 だから、“文化的な“読書などする時間があるわけがない。 → 全身全霊を求めてくる資本主義社会から、半身半霊でもいいのではないか、と著者が提言している。 自分が全身全霊で向き合えないくらい疲れているんだな、不安なことがあるんだな、という事実が見えてきて、少し自身を見直そうと思った。 疲れている現状とは別に、 仕事に全身全霊で行きたい人もいるだろうし、全力で部活や勉強に打ち込んでいる若者のことを思うと、何かに打ち込んでいる間、耐えている間に教養としての読書ができるわけがないので、それはそれとして気にしないことも大切だと思う。 ただ、全身全霊で行動中の人のサポート(金銭面以外に生活面でのサポートはかなり必要だと思う)しやすい環境、本人が燃え尽きないような柔軟な働き方がもっとできるようになって欲しいなぁ。 また、読書が趣味と一般庶民が言えるようになったのは最近で、活版印刷が普及して、本が安く買えるようになったからだ。 大正時代、ビジネス書がいつも人気だったらしいが、今までもずっとハウツー本はランキングに入っている。 これは、早く〇〇を知りたいという需要に対する供給から生まれている。 この読書は本人の立身出世のための学習手段であって、趣味ではないと著者はカテゴライズしたようだが、仕事でも趣味でも知的好奇心を持って知識や他者の知見を求める行為が読書であって、自分から遠く離れた文脈に触れることは教養の学びなのでは、と考える。 昭和になってブームになった円本は、装丁が揃っていてインテリア的に見栄えが良く、これだけ読めば教養習得間違いなしという内容ばかりが掲載されていること、月払いというサラリーマンの給与体系に合っていたことがヒットの要因とのこと。 また、長時間残業がスタンダードだった頃は、生活=職場なので、仕事に役にたつハウツー本(英語、記憶術など)や、気分転換になる立身出世のスカッとする小説(司馬遼太郎の歴史本(ある意味ファンタジー扱い))が売れたそう。 歴代のベストセラーを調べてみたら、1970年代は確かに全6巻程度の和本セットがベストセラーにランクインしていた。 1980年代になると、小説や税金に関するハウツー本、プロ野球や芸能人の著書もランクイン。 1990年代は、シドニィシェルダンやさくらももこなどのエッセイやゲーム攻略本もエントリー。不況だからか、後半からは生活習慣やビジネスマナーなどの自己啓発本が増えてきた。 2000年代はハリーポッターシリーズや金持ち父さん、貧乏父さんなどエンタメ用と実用書のメリハリがはっきりしている印象。国家の品格から、◯◯の品格や、◯◯のトリセツなどシリーズっぽいタイトルが激増。 2010年以降は、情報革命があったからか、メディアで取り上げられたもの、本屋大賞など、話題になったものがランキングされている印象。 段々とメディアやSNSの流行に左右されてる感じが強くなっているような気がする。 ChatGPTの台頭もあり、ますます答えがなくなる時代になるため、余計にエンタメ本や、成功の秘訣といった答えを得るためのハウツー本が売れそうだなと思った。
8投稿日: 2025.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代以降の読書史が労働観を交えよくまとめられています。僕の読書歴がこれにしっかり乗っかっていることが分かって笑っちゃいました。
1投稿日: 2025.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かに半身で働く事ができればもっと趣味に没頭できるだろうけど、半身で全員が働くとすれば困ることも多くはなるだろう だけど一人がこの考えを発信するだけよりかは本として世に出ることに意義があると感じた 個人的にノイズって言葉が多く出てきたことが気になる 久しぶりの新書でスラスラと読め情報を入れることの気持ちよさがあり、小説より頭を使わなかったので長時間読み続けられる そして意外と小説はイメージしそこから膨らませることに体力を使うのだと知れた
1投稿日: 2025.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
近代日本社会に、読書という文化がいかにして根付いてきたのかがよく分かった。 いや、でもタイトルの問いに対する答えはあるのかと読み進んでいくと、ありました、「半身社会」。 労働に全身全霊を傾けていたら、そりゃ本なんて読めないよ。そういう姿勢を労働者に求める企業側に、資本主義社会である以上まぁ無理もないかと思う反面、それに洗脳されたかのように、ある種肯定的に受け入れる労働者側の考えを改めるのは必要かも。少なくとも本を読みたい人は。 読書に必要なのは、やはり心の余裕。 私自身は、自分を取り戻すために本を読んでいることをこの本に気付かされた。
8投稿日: 2025.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自身が本が読めなくなる時期に陥っている環境と背景がクリアになり、腑に落ちました。三宅さんが訴える、半身社会=特定活動にフルコミットメントしない社会を構想することは非常に重要だと思います。社会的に仕事等にフルコミットメントする姿勢は称賛される傾向にありますが、一つのことだけを頑張るのはとても簡単。頑張っていることを言い訳に、家族・友人・恋人や余暇活動を遮断してしまう(身に沁みてわかります)。「一つのことだけを頑張る生き方は、不健康かつラク。フルコミットメントの全面的称賛は危険」と強烈に反省しました。
1投稿日: 2025.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自己啓発本はノイズのない情報だ。これは本当にそう思う。僕も小説はなかなか読めないが、自己啓発本ならスラスラと読めてしまう。論文だって読める。なんとなくかっこいい響きがあるが、論文も情報だしRFCも情報だ。知ではない。 結局この本を読んで、なぜ僕は本を読むのだろうと思ってしまった。楽しいから読んでいるなら、その本は情報であってもいいんだ。SNSであってもTickTockであってもいい。でもYoutube Shortを見終わった時の虚無感が嫌いで、僕は本を読んでいる。だがその本も情報なのだとしたら、本を読んだ後の達成感はまやかしなのかもしれない。 なんとなく意味のある時間を過ごせた気がしているだけで…… つまりまあ、本を読むことに大した意味はない。本を読む必要はない。
1投稿日: 2025.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ働いているとなぜ本が読めなくなるのか という題名から想像できないくらい、読書についての歴史書だった。インターネット社会になるまで、本は貴重な情報源だったし、ネットで時間を「溶かす」こともなかった。三宅さんが言うように確かに読書は「ノイズ」。著者が伝えたいことは何か、自分にとって有益な情報は何か、と考えながら読んでしまう。だけどもそうやって考えて読書してしまうことこそ自分に余裕がなく、やりたいことに没頭出来ていない。 現代の「自己実現」は大事だが、半身にして他者を知ることも重要だなと思った。
8投稿日: 2025.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書とは、自分から遠く離れた文脈に触れること。 本が読めない状況とは、新しい文脈を作る余裕がない、ということ。 仕事が忙しいと自分が求めている情報以外のノイズ(教養と呼ばれる古典的な知識や、小説のようなフィクション、読者が予想していなかった展開など)を頭に入れる余裕がないため。 「この世の知識はいつかどこかで自分に繋がってくる。他者は自分と違う人間だが、自分に影響を与えたり,あるいは自分が影響を与えたりするのと同じだ。」
3投稿日: 2025.12.10
