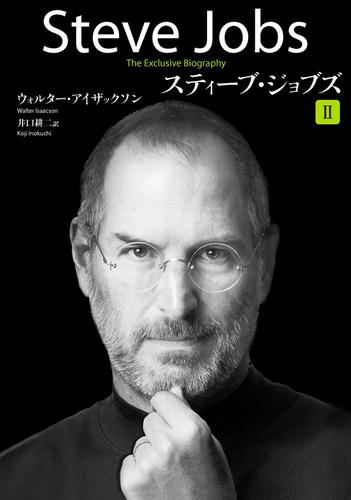
総合評価
(410件)| 195 | ||
| 134 | ||
| 39 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
意思とは、ものを作るとは。 兎に角、スティーブ・ジョブズは芯が通っていて、かつ太い。常人ではない。 本書抜粋 ジョブズがappleに戻ってきてからの広告の一節 「クレージーな人たちがいる。反逆者、厄介者と呼ばれる人たち。彼らは規則を嫌う。 ・・・ 反対する人も、賞賛する人もけなす人もいる。 しかし、彼らを無視することは誰にも出来ない。なぜなら、彼らは物事を変えたからだ。彼らは人間を前進させた。 ・・・ 自分が世界を変えられると本気で信じる人たちこそが、本当に世界を変えているのだから。」 こんなことを一般企業が提示するなんて。驚愕に値すると思う。 日本の企業でこんなことを世の中に提示できる企業があるのか。 過去にはソニー。今はユニクロくらいなものだと思う。 そして、その斬新さ、確信は一過性じゃなかった点が更に素晴らしい。 また、ジョブズは1 「何をしないのか決めるのは、何をするのか決めるのと同じくらい大事だ。」 さらに、ジョブズは2 また、プレゼンテーションのやり方にもこだわりがある。 「プレゼンテーションをする、パワーポイントを使う、スライドを駆使する そんなことの前に、ちゃんと問題に向き合って欲しい。課題を徹底的に吟味する。自分の仕事をちゃんとわかっている人は、そんなツールを使用しない。」 そして、ジョブズは3 「君達は優秀だ。優秀な人間がこんなお粗末な製品に時間を無駄遣いしてはならない」 方向性を提示し、優秀な集団に同じ方向を向かせる。 そして、これこそがジョブズの核心だと思うけど、技術者として、アーティストとして4 「製品が中心ではない。それを人がどうつかうか、どうしたいかが中心だ。」 これが全てであり、革新的、核心的だと思う。 俺達は、スティーブ・ジョブズと同じ時代に生きていたことを幸運を感じ、 その力が生んだ普遍性を受け入れ、自らの人生にフィードバックするべきだと思う。ジョブズのやり方の全てがそのとおりでもなく、時代によって変わるものもあるだろうけど、ここに書いたことは少なからず大事だ。
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ一気に読了。なぜ私たちがAppleに惹かれるのか。やはりジョブズの想いがプロダクトに現れているからだ。クレイジーで偉大な人だった。
0投稿日: 2011.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ『スティーブジョブズ』の下巻読み終えた。上巻に比べ、下巻はあっという間に読み終えてしまった感じである。 その下巻は、ジョブズ晩年の”突き抜け感”がスピード感をもってうまく表れているし、かつ上巻と同じように彼が大好きなプロダクト毎のカットで描かれているから、とてもSensefulであるなと感じた。実際に、下巻はジョブズがアップルに復帰した1997年から2011年までの約15年間が描かれている。 本書には知られざるジョブズの真実がたくさん散りばめられており、404-407ページの「ビル・ゲイツとの最後の対話」のエピソードもおもしろい。 そして、コーダの部分はなんともCoolである。 この本を読み終わったとき、彼がこの世からいなくなってしまったことを改めて実感した。彼が世界最高のCEOではなく、もはや「伝説」となってしまったことが、何とも悲しい。彼の意志を受け継ぐのは、アップルだけではない。ジョブズに感銘を受けた人々は、ジョブズの意志を受け継ぎ、世界を前へ前へ進めていかなければならない。
0投稿日: 2011.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログスティーブ・ジョブズのアップル復帰以降が描かれている。iMac、iPod、アップルストア、iTunes、iPhone、iPadといった数々の製品やサービスを成功へと導いていく。やはり、1巻と比べると華やかだし、成功への道やその理由が明確化していく。人格的な問題は相変わらずだけど、まぁそれがなければここまでの成功はなかっただろうな、とすら思ってしまう。病に倒れてしまったのは残念ですね。これからもいい製品を生み出せたはずなのに。 他社が失敗したオープンイノベーションとの違いが際立ち、なるほど、こういう成功の方程式があるのか、と非常に考えさせられました。私個人としては、オープンイノベーションが好みなのだけれど、オープンイノベーションだけだと、多分iTunesのようなサービスが立ち上がることはなかっただろうし、iPadみたいな製品も作られなかっただろうな、と思う。多分、社会に両方ある姿ってのがいいんだろうな。 お金に余裕ができれば、iPadを買おう。
0投稿日: 2011.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻が、一人の冒険家の栄光と挫折の物語だったとしたら、下巻は、ゴールを目指して失踪する短距離走者の記録といった印象。ドラマティックなのは圧倒的に上巻だけど、ジョブズのすごさ、恐ろしさがひしひしとわかるのは下巻だ。彼が答えを見つけて走り出すとどれくらい速く激しいのかを、iPod、iTunes、iPhoneといった今ではすっかり身近になった商品の誕生を絡めながら描いている。 権利関係が複雑で誰がやってもうまくいかなかった音楽配信事業を成功させたジョブズに、ビル・ゲイツは「どうやって音楽会社を巻き込んだんだ?」とつぶやいたというが、怒鳴り、押し掛け、脅迫し、おだてあげ、たらしこむ彼の激しさが、単に世界に類を見ないレベルだったというだけである。だからこの本は自己啓発書やビジネス書にはなりえない。普通の人が真似することは難しいからだ。 個人的には、同じ年のもう一人の天才、ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズの関係性が興味深かった。鼻がぶつかるほどの距離で怒鳴り合ったり、訴訟を起こしたり、常に互いにののしりあうライバルでありながら、どこか戦友のような、深い部分ではつながっているような複雑な関係のふたり。 下巻の最後の方で、病気療養中のジョブズの自宅をビル・ゲイツが訪れ業界の思い出話にふけるひとこまは、諍いや衝突、敗者たちの累々とした死体に満ちた、過酷な戦場の記録のようなこの本のなかで、最も心あたたまるシーンのひとつだ。この二人に関してもうすこし突っ込んで描いている本があったら買いたいくらいだ。 下巻ではジョブズの病との戦いも描かれているが、著者の流儀なのか、物悲しさはあまりない。それよりも、彼が一般的には若いと言える年に亡くなったとしても、普通の人の何倍も生きたし、ずっと遠くまで走ったということを描くことに注力しているかのように感じた。
0投稿日: 2011.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ジョブズのアップル復帰あたりからの今日まで。 前巻で扱った範囲でも充分革新を起こしていたと思うが、 本巻で扱われるiMac~iPod~iPhoneのほうが より身近で、より確信的で、よりドラマチック。 時代による技術進歩もあるのだが、 ジョブズの商品にかける情熱は輪をかけて熱くなっている。 終わりの方はがんに侵されて痛々しいが、家族とのエピソードもユニークで面白い。 内容としては本巻の方が面白いが、前巻あってのものでもあるので、 読むならぜひ通しで読んでほしい。
0投稿日: 2011.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
うそをつくのも真実を語るのも、通常のルールは自分に適用されないというニーチェ的な姿勢から派生しているものなのだ。p50 【復帰したジョブズが社員を集めて言ったこと】 「製品がボロボロ!セクシーじゃなくなってしまったんだ!」p57 ジョブズは何年もかけて、しっかりとしたリーダーをアップル取締役会に迎えていく。 アル・ゴア、Googleのエリック・シュミット、ジェネンテックのアート・レヴィンソン、ギャップにJ・クルーのミッキー・ドレクスラー、エイボンのアンドレア・ユンなどだ。p63 「アップルのコンピュータを買う人というのはちょっと変わっていると思う。アップルを買ってくれる人は、この世界のクリエイティブな側面を担う人、世界を変えようとしている人々なんだ。そういう人のために我々はツールを作っている」p65 【Microsoftと提携を取り付けた時のジョブズの言葉】 「ビル、この会社に対する君の支援に感謝するよ。おかげで世界は少し良くなるはずだと思う」p69 広告業界に二つの金字塔を打ち立てた、「1984年」と「シンク・ディファレント」 【ラリー・エリクソンの証言】 テクノロジー業界で唯一、ライフスタイルブランドを生み出したのがスティーブなんだ。車ならポルシェやフェラーリ、プリウスなど、持っているだけで誇りが感じられる製品がある。運転する車には自分が反映されるからだ。アップル製品も、ユーザーからそのように思われている」p79 「何をしないか決めるのは、何をするのか決めるのと同じくらい大事だ」p86 「考えもせずにスライドプレゼンテーションをしようとするのが嫌でねぇ。プレゼンテーションをするのが問題への対処だと思ってる。次々とスライドなんか見せず、ちゃんと問題に向き合ってほしい。課題を徹底的に吟味してほしいんだ。自分の仕事をちゃんとわかっている人はパワーポイントなんかいらないよ」p86 【ドイツの工業デザイナー、ディーター・ラムスの信条】 「より少なく、しかしより良く」p94 【アイブのシンプルさへの哲学】 「シンプルなものが良いと感じるのはなぜでしょうか?我々は、物理的なモノに対し、それが自分の支配下にあると感じる必要があるからです。複雑さを整理し、秩序をもたらせば、人を尊重する製品にできます。」p95 2011年の時点で、ジョブズが名前を連ねている米国特許は212件もあるそう。発明者としても超一流だった。p100 【ジョブズはクックについてこう評している】 ティム・クックは調達畑の出身で、これが良かったんだと思う。彼と僕はまったく同じ見方をしていた。僕は日本でカンバン方式の工場をたくさん見学したし、マックでもネクストでもそういう工場を作った。やりたいことははっきりしてたんだ。そしてティムに会い、彼も同じことをを望んでいた。しばらくいっしょに仕事をして、彼なら物事を間違いなく進めてくれると信用した。ビジョンも同じだったし、戦略的なレベルの話もできたからね。だから、彼が相談に来ない限り大丈夫だと、たくさんのことを意識から追い出すことができたんだ。p118 「ハードウェアからソフトウェア、オペレーティングシステムにいたるまで、ウィジェット全体を持っているのはアップルだけだ。我々なら、ユーザー体験のすべてに責任が負える。我々は、ほかにはできないことができるんだ」p152 【アップルが目指す目標デザイン】 詩心と工学の融合、芸術・創造性と技術の交わり、大胆でシンプルなデザイン。p169 【ビル・ゲイツ】 「大きな意味をもつごく少数のものに集中する力、優れたインターフェイスを作る人材を確保する力、製品を革新的にしてマーケティングする力という意味でスティーブ・ジョブズはとにかくすごい」p187 グレン・グールド演奏による「ゴールトベルク変奏曲」昼と夜のようだ。p202 チェロ演奏家ヨーヨー・マ p220 【ピクサー社屋設計の根底にあったコンセプト】 ネットワーク時代になり、電子メールやiChatでアイデアが生み出せると思われがちだ。そんなばかな話はない。創造性は何気ない会話から、行き当たりばったりの議論から生まれる。たまたま出会った人になにをしているのかを尋ね、うわ、それはすごいと思えば、いろいろなアイデアが湧いてくるのさ。p228 【スタンフォードの卒業スピーチ】 人生を左右する分かれ道を選ぶ時、一番頼りになるのは、いつかは死ぬ身だと知っていることだと思います。ほとんどのことが- 周囲の期待、プライド、ばつの悪い思いや失敗の恋の恐怖など- そういうものすべてが、死に直面するとどこかに行ってしまい、本当に大事なことだけが残るからです。自分はいつか死ぬという意識があれば、なにかを失うと心配する落とし穴にはまらずにすむのです。人とは脆弱なものです。自分の心に従わない理由などありません。p266 メメント・モリ=死を忘れるなかれ p271 「iPadのような製品をアップルが作れるのは、テクノロジーとリベラルアーツの交差点にいつも立ちたいと考えているからだ」p320 【iPad登場時の本質的な批判】 「コンテンツを消費するのには素敵な製品だが、コンテンツを生み出す助けにはあまりならない」p322 iPad「エンドツーエンドで統合したクローズドなシステム」p323 【シュミットの指摘】 「スティーブはあるひとつの方法でアップルを経営したいと考えているのですが、それは20年前から変わっていません。つまりアップルはクローズドシステムのイノベーターとしてすばらしく優れているということです」p347 「僕はユーザー体験に丸ごと責任を持ちたい。金儲けがしたいからじゃない。すごい製品が作りたいからやるんだ。アンドロイドみたいなガラクタじゃなくてね」p349 「革命を起こしたいと君はいう」 【結婚20周年の時にローリーンに送った手紙】 「20年前はお互い、あまりよく知らなかったよね。あのころ僕らは自分の心に導かれていた。僕は一目で君に夢中になったんだ。アワニーで結婚したとき、外は雪が降っていたね。月日が流れ、子どもたちが生まれた。いいときも厳しい時もあった。でも悪い時はなかった。僕らの愛も敬意も時の流れに耐えて成長した。ふたりでいろいろなことを経験してきたね。そしていま、僕らは、20年前にふたりで歩きはじめた場所に戻ってきた。年を取り、賢くなって、顔にも心にもたくさんのシワを刻んでね。僕らは人生の喜びも苦しみも秘め事も驚きもたくさん経験して、その上でこうしていっしょにいるんだ。僕はいまも君に夢中だ」p372 ジョブズのユニフォーム:イッセイ・ミヤケの黒いハイネックにフォンローゼンの黒いカシミヤセーター。ブルージーンズの下に発熱素材の下着。p376 第39章、「無限の彼方へ、さあ行くぞ- クラウド、宇宙船、そのまた先へ」 〈メモ〉集中と選択の重要性。 【自伝の執筆を依頼した理由】 「僕の事を子供たちに知って欲しかったんだ。父親らしいことをあまりしてやれなかったけど、どうしてそうだったのかも知って欲しかったし、そのあいだ、僕が何をしていたかも知っておいてほしい。そう思ったんだ。もうひとつ。病気になったとき、気付いたんだ。僕が死ねば、僕についていろいろな人がいろいろなことを書くはずだけど、ちゃんと知ってる人がいないって。間違いばかりになるって。だから、僕のことばを誰かにちゃんと聞いてほしかった」p411 第41章「受け継がれていくもの、輝く創造の天空」 【ジョブズの功績】 スティーブ・ジョブズの性格はその製品に反映されている。1984年の初代マッキントッシュからiPadにいたるまで、ハードウェアとソフトウェアをエンドツーエンドで統合するのがアップル哲学の中核であるように、ジョブズも、その個性、情熱、完璧主義、悪鬼性、願望、芸術性、中傷、強迫的コントロールといった要素すべて、ビジネスに対するアプローチにも、そこから生まれる革新的な製品にもしっかりと織り込まれている。p414 集中力もシンプルさに対する愛も、「禅によるものだ」とジョブズは言う。禅を通じてジョブズは直感力を研ぎ澄まし、注意をそらす存在や不要なものを意識から追い出す方法を学び、ミニマリズムに基づく美的感覚を身につけたのだ。p420 スティーブ・ジョブズの物語は、そのまま、シリコンバレーの創造神話となる- ガレージで起業し、世界一の会社に育て上げたのだから。p422 【ジョブズが産み落としたもの】 ・アップルⅡ:ウォズニアックの回路基板をベースに、マニア以外にも買えるはじめてのパーソナルコンピュータとした。 ・マッキントッシュ:ホームコンピュータ革命を生み出し、グラフィカルユーザインタフェースを普及させた。 ・『トイ・ストーリー』をはじめとするピクサーの人気映画:デジタル創作物という魔法を世界に広めた。 ・アップルストア:ブランディングにおける店舗の役割を一新した。 ・iPod:音楽の消費方法を変えた。 ・iTunesストア:音楽業界を生まれ変わらせた。 ・iPhone:携帯電話を音楽や写真、動画、電子メール、ウェブが楽しめる機器に変えた。 ・アップストア:新しいコンテンツ制作産業を生み出した。 ・iPad:タブレットコンピューティングを普及させ、デジタル版の新聞、雑誌、書籍、ビデオのプラットフォームを提供した。 ・iCloud:コンピュータをコンテンツ管理の中心的存在から外し、あらゆる機器をシームレスに同期可能とした。 ・アップル:クリエイティブな形で想像力が育まれ、応用され、実現される場所であり、世界一の価値を持つ会社となった。ジョブズ自身も最高・最大の作品と考えている。 〈メモ〉ソニーがアップルになれなかった理由を垣間見る。 【最後にもう一つ】 「僕は、いつまでも続く会社を作ることに情熱を注いできた。すごい製品を作りたいと社員が猛烈にがんばる会社を。それ以外はすべて副次的だ。もちろん利益を上げることはすごいことだよ?すごい製品を作っていられるのだから。でも、原動力は製品であって利益じゃない」 「〈顧客が望むモノを提供しろ〉という人もいる。僕の考え方は違う。顧客が今後何を望むようになるのか、それを顧客本人よりも早く掴むのが僕らの仕事なんだ。ヘンリー・フォードも似たようなことを言ったらしい。〈何が欲しいかと顧客に尋ねていたら『足が速い馬』と言われたはずだ〉って。欲しいモノを見せてあげなければ、みんな、それが欲しいなんてわからないんだ。だから僕は市場調査に頼らない。歴史のページにまだ書かれていないことを読み取るのが僕らの仕事なんだ」p424 「アップルが世間の人たちと心を通わせることができるのは、僕らのイノベーションはその底に人文科学が脈打っているからだ。すごいアーティストとエンジニアはよく似ていると僕は思う。レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロなどはすごいアーティストであると同時に科学にも優れていた。ミケランジェロは彫刻のやり方だけでなく、石を切り出す方法にもとても詳しかったからね」p425 「IMBのジョン・エーカーズは頭が良くて口がうまい一流の営業マンだけど、製品についてはなにも知らない。同じことがゼロックスでも起きた。営業畑の人が会社を動かすようになると製品畑の人間は重視されなくなり、その多くは嫌になってしまう。スカリーが来た時アップルもそうなってしまったし、バルマーがトップになったときマイクロソフトもそうなった」p427 「生きるのに忙しくなければ、死ぬのに忙しくなってしまう」(ボブ・ディラン)p429
0投稿日: 2011.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ期待以上の情報量で、非常に満足しました。 本書を読んで思ったのは、スティーブ・ジョブスが モノ作りに対して本当に純粋だったということ。 ・自分が使いたいモノが作りたいモノである。 ・作りたいモノは、世の中の人が欲しいモノになる。 ・だから、作りたいモノには絶対に妥協をしない。 ・そして、最適な技術を探し続け、得た(先見性)。 ・そして、必要な人を探し続け、得た(交渉術)。 ・逆に、阻害要因となる技術や人は排除した。 ・したがって、カリスマ性はあるが敵も多く作った。 自分が作りたいモノ=愛着のあるものだからこそ、 周りが共感できる夢を語ることも巧かったんだと思います。 自分自身は今、新しいサービスを企画する立場にいるのですが、 ・本当に自分自身が使いたいサービスを作っているのか? ・外圧に負けて妥協していないか? ・サービスに愛着を持っているのか? 等々を再考する良いきっかけになりました。 下巻は昨日届いたので、続きが楽しみです。
0投稿日: 2011.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブズが生み出した最高のものは、個々の製品ではなくAppleというチームであり、この伝記は子どものためにいやなことも含めて真実を伝えておきたいという思いから書かせたというのが伝わってきます。 ジョブズ不在の1994年からMacを使って以来、すべての製品とサービスを使ってきただけに、Macにオンオフスイッチがないという意味が最後に記されているように、Appleにはジョブズ亡き後もあっと言わせるモノを生み出し続けてほしいと思います。 この伝記をiPadで読んだのは必然だと思いますし、最後の取締役会の場面で涙がこぼれたのは、書物という形態でなくても感動は伝わるという大事な経験になりました。
0投稿日: 2011.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ上下巻に及ぶスティーブ・ジョブズ伝記の下巻。 アップル復帰後の快進撃を描いており、初代iMac以来の ある意味新参者ユーザーである自分にとっては、iMacの斬新さに驚いたことやapple storeに並んだり、各モデルの発売の際の狂騒的な雰囲気をふと思い出させてくれる内容に好感が持てます。 (あくまでも伝記ですからその時の喧騒を記してはいないのですが・・そう思い起こさせてくれるという意味で) ジョブズ無き後のapple社がこれからも、消費者をわくわくさせる商品を生み出し続けてくれることを祈ります。
0投稿日: 2011.11.01
