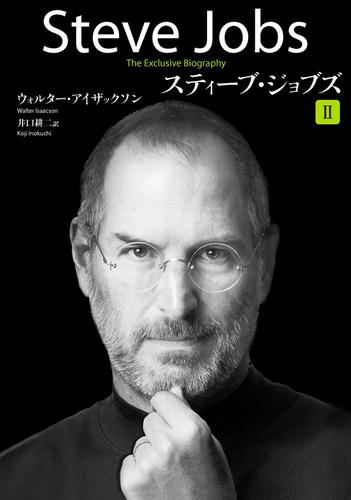
総合評価
(410件)| 195 | ||
| 134 | ||
| 39 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
評価:上 1がくそみたいに好きじゃなかったのけど、2は良いね。 かなり良い。 ジョブズの葛藤や心の移り変わりも良かったし製品も良い。 最後の引退してからの話が特に良いと思う。 ずっと読んだだけあって涙ぐんだ。 読むとしたら2からがオススメ。 2からが成功したジョブズで予想していたジョブズの話だからね。 著者が良いのか翻訳者が良いのかこの文章の良さはどっちの人かなぁ。
0投稿日: 2011.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻は読むピッチがすごいあがりました。私がAppleの製品を使いはじめてからの時代にほぼマッチするので、Appleについても、ピクサーについてもオモテ面的なことは知ってる内容だったからかもしれません。 ビルゲイツとの関係もなんか凡人には理解しにくい友情があったみたいで、そのあたりも面白いなあと思いましたね。 なので本当に非常に面白かったです。 決してジョブズ賛美の本ではなく、彼の欠点もきちきちと書かれてるのに、流れがうまくてよみやすかった。このライターを選んだのはさすがジョブズってことかもしれません。 息子さんのリードくんの高校卒業まで生きたいとのぞんで、その卒業式にでられた頃に、トイストーリー3の話がかぶったのはちょっとやられてホロリとしてしまいました。 育てのお母さんの死には触れてたけど、お父さんはいつなくなったのかなあ。私が読み落としたかな?ちょっと気になってます。写真はのってたけど。 ともあれ、面白かった。 そして改めて残念です。せめてあと10年生きていてほしかったなあ。 ちなみにこの感想はiPhoneで書いてます。
0投稿日: 2011.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログスティーブ・ジョブズという人間とアップル社の遍歴がジョブズを通してよくわかる。ジョブズがどういう人間なのかは他書でも伝わっているので、家族や友人との関係、競合他社との駆け引きなどは新しいエピソードがあった。 ジョブズがいなければ今のアップルはなかったし、iPhoneもiPadもこの世になかったのは確かである。彼が今のアップルの製品をあそこまで集中してすばらしいものに仕上げたのが本書からよくわかるが、やっぱり彼でないとできないし、これからのアップルが以前衰退したときのようになってしまわないか、これからも新しいイノベーションを起こし続けるか、ますます心配になった。誰もジョブズのマネはできないし、今後も彼のような人物はでてこないのではないだろうか。
0投稿日: 2011.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に面白い。 ジョブスについて今まであまり詳しくなかったけれど、ジョブスについてもアップルについてもいろいろよくわかった。 決してジョブス万歳ではなく、欠点も凄みもストレートに書いてあるのがよい。 会社の在り方、リーダーの在り方についても考える切り口を与えてくれる。 いい点も悪い点も際立っている為、いろいろ考えるきっかけを与えてくれる点で、伝記にとどまらない価値がある。
0投稿日: 2011.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブズがNewtonを高く評価していた。スタイラスペンを使うところが気に入らなかったためお蔵入りに。ある意味正解。
0投稿日: 2011.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログスティーブジョブズ氏の伝記の後半。 1990年代後半から2011年までのため、読んでいて 知っている・実際に使っている製品の話のため 前半に比べると、面白い。 iTunesにおける音楽業界へのアプローチや iPod、iPhone、iPadの開発に対する情熱はすごい。 また、病を通じて、死・生について向き合う姿勢にも とても刺激を受けた。
0投稿日: 2011.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ何か大作映画のエンドロールを見てるような、すごい読後感。 ジョブズブームが去って残り続ける本だと思います。
0投稿日: 2011.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログSteve Jobs II ・あれは僕の望む仕事ではなかった。誰かが作ったぼろいハードウェアにソフトウェアをライセンスするためにこの地球に生まれてきたんじゃない。ああいう仕事がおもしろいとはどうしても思えないんだ ・ジョブズはなんでも自分の思い通りにコントロールしないと気がすまない性格だが、同時に、先行きが不透明だと思うと優柔不断となり、前に進めなくなってしまう。完璧を求めるあまり、中途半端なもので妥協したり、可能なものでがまんしたりが上手にできないことがある ・長く存続する会社を作りたいとジョブズは考えており、そのためにはどうすべきかをマークラにたずねた。マークラは、長続きする会社は自らを再発明するものだ、と指摘する ・Think Differentとは違うコトを考えるということ。Think Differentlyでは微妙に意味がずれる ・まずケースのデザインを決め、そこにボードや部品が収まるようにエンジニアに工夫させた ・2011年の時点で、ジョブズが発明者として名前を連ねている特許は212件もある ・エンジニアリングからデザイン、製造、マーケティング、物流と順番に製品が流れていくのではなく、アップルの開発プロセスでは、さまざまな部門が協力しながら作業を進めていく ・自分に対しても、他人に対しても、卓越といえるレベルでなければがまんできない ・ユーザインターフェースをひとつずつチェックしては、厳しい基準で判断を下す。曲でも機能でも3クリック以内でたどり着けなければならないし、どこをクリックすべきか直感的にわからなければならない ・結局のところ、ユーザ体験の大半を他人に任せちゃいけないんだ。違う意見の人もいるはずだとは思うけど、僕は徹底的にそう思う ・「共食いを恐れるな」を事業の基本原則としている。自分で自分を食わなければ、誰かに食われるだけだからね ・ビートルズのメンバーはみんな完璧主義者で、とにかく何度も何度もやり直すんだ。このことに、僕は30代で強い印象を受けた。彼らがどれほど真剣に取り組んだのかがわかってね ・あの映画が好きなのは、リスクを取ること、自分が愛するものにリスクを取らせることを学ぶのがテーマだからだ ・ハードウェアとソフトウェアとコンテンツの処理を整然としたシステムに一体化し、シンプルなユーザ体験を提供するほうがよいのか。あるいは改造もできればさまざまな機器で使えもするソフトウェアシステムを作り、ユーザーやメーカーの選択肢を増やしてイノベーションを増やす道を拓くほうがよいのか ・「我々は完璧ではない。電話は完璧ではない。周知の事実だ。でも、ユーザーに喜んでほしいと我々は考えている」 ・僕らはこの移行にちゃんとついて行かなきゃいけない。クレイトン・クリステンセンは「イノベーションのジレンマ」という言葉で「なにかを発明した人は自分が発明したモノに最後までしがみつきがちだ」と表現したけど、僕らは時代に取り残されたくないからね ・みんな、自分が得意なことで忙しくしていて、僕らには僕らが得意なことをしてほしいと望んでいる。みんな、自分の暮らしには満杯状態なんだ。コンピュータと機器をつなぐにはどうしたらいいかを考える以外に、やることがたくさんあるんだよ ・もちろん、利益を上げるのもすごいことだよ?利益があればこそ、すごい製品を作っていられるのだから。でも、原動力は製品であって利益じゃない ・僕らは自分が持つ才能を使って心の奥底にある感情を表現しようとするんだ。僕らの先人が遺してくれたあらゆる成果に対する感謝を表現しようとするんだ。そして、その流れになにかを追加しようとするんだ。そう思って、僕は歩いてきた
0投稿日: 2011.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ最高。 特に、最後のスティーブ・ジョブズの言葉が涙無しに見れない。 これだけでも読む価値がある。 長いけど、ぜひ読んで感じるべきだと思う。 これを伝える言葉を持った人は、きっとどこにもいない。
0投稿日: 2011.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スティーブジョブズがこんなめちゃくちゃな人だとは知らなかった。 現実歪曲フィールドのパワーはすごい。
0投稿日: 2011.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むのに時間かかりましたが、ⅠよりⅡのほうが面白かったです。 彼の仕事の哲学というか流儀は凄まじいものがありますが、その根底に流れるものは、すごい製品を作りたいという情熱がまず優先されていたことなのだということがとてもよくわかりました。最後の章のジョブズの言葉が一番印象的でした。
0投稿日: 2011.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生の後半、どうやってアップルを引き上げてきたがが書かれています。1巻では、単に変わっている人物だと思っていたものが、2巻では年を取った事でだんだん変化し、その考えがどのように周囲の人間を引き付けていったのかが書かれています。読んでみて良かったです。
0投稿日: 2011.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ常に何かに抗うように、怒りを抑えることもなく、独自の思いを貫き通し、最後は病に倒れる。 全てを仕事にかけ、突き進んできた道のりは波乱万丈で、彼が力強く生きた証として残された。 その影響力には圧倒される。 家族にしてみれば辛いことも多かったのだろうが、彼の仕事への向き合い方や信念にはリスペクトに近い思いがあったに違いない。 たくさんの人達に愛され、惜しまれて命を全うしたスティーブ・ジョブズ。 オン・オフのスイッチの話にはホロリときた。
0投稿日: 2011.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログスゴ本。ただ凄い製品を作るという情熱、「卓越」未満はクソだっていうDNAが今後もアップルに残って欲しいな。Macに、ピクサー、アップルストア、iPod、iPhone、iPad・・・それぞれの開発秘話、会社間の交渉、ジョブズの変人ぶりなど、とても日本の大企業では考えられないような話ばかりで面白い。クローズドな製品の統合は好きでなかったけれど、ユーザー体験に丸ごと責任を持ちたいという考えにも納得しました。
0投稿日: 2011.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログアップルの創業者、スティーブ・ジョブズの人生後半が書かれている。30代で失敗しながら、それを糧に40代での成功が描かれている。 素晴らしいと思える物を作り出すのには、徹底的なこだわりが必要なのだと思う。アップルのクローズドシステムとマイクロソフトやアンドロイドのオープンシステムが対比されているが、この話で「美味しんぼ」という漫画のよろず鍋と至高の五大鍋を連想してしまった。 本当に命をかけて、自分の信じる道を歩んだ人生だと思う。人生を考えさせられる内容だった。
0投稿日: 2011.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログマッキントッシュからipadまで、クールな電子端末を誕生させた「哲学者」の伝記。エンジニアには「マシーン」が作れても「歴史」は創れないことを示した本。TIME編集長などを経験したジャーナリスト、ウォルタ―・アイザックソンが、ジョブズに請われて筆を執った、という。 「何をいまさら」と思いながら、手にとってみると、おもしろかった。昨今の日本の電機メーカーの業績不振をもたらしたのは、ジョブズだということがよく分かった。
0投稿日: 2011.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブズ本人が全面協力した自伝の下巻。コンピューターのシェア争いに敗れたアップルに戻り、iMac,iPodからiPhone,iPadまで次々とイノベーションを実現させて、アップルを世界をリードする企業に再生させる。全ての物や人を「史上最高」か「クソ」に二分し、後者に分類した物、人には容赦なかったジョブズ。だけど、その結果出来上がった物には、最高のお膳立てとプレゼンテーションで最高級の賛辞をあたえた。自分が作った物が世界を変える。物づくりの人ならどれだけの幸福かわかるはず。でも、その神がかり的な事業の裏の闘病と家族との絆、そして死は、明らかに人間「スティーブ・ジョブズ」だった。
0投稿日: 2011.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ敬遠していた電子ブックで読んでみた。 内容が面白いためか、iPadで読んでることを忘れるほど、夢中になれた。 ページをめくるスピードが速くなるので、電子ブックも良いもんだな。
0投稿日: 2011.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ私のブログへ http://pub.ne.jp/TakeTatsu/?entry_id=4031558
0投稿日: 2011.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻よりも下巻の方がもっと面白いかとおもったら、あまり面白くありませんでした。 期待した、iPhoneやiPadの詳しい話もなく、恐らくスティーブジョブズの体調の関係があり現在こそ詳しい話が聞けなかったんでしょうね。 上巻は過去の事なので調べたり以前本人に聞いたりしてたのでしょうが、現在はそれが出来なかったと感じます。
0投稿日: 2011.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり良かったです。後半はジョブズがアップルに復帰してからCEOを辞任するまでが書かれています。今のアップルを名実共に確実な存在にしたiMac、iPod、iTunes、iPhone、iPadなどの製品開発の裏側や家族との関わり、そして癌との苦闘が詳細に描かれていて、ビジネス面でも一人の偉大な人間の物語としても楽しめる内容になっています。特に病気との闘いは一般的には非公開だっただけに、2003年の癌発見以降は相当ハードな人生を歩んでいたことにも驚きました。終盤には名言のオンパレード、そしてラストも映画のワンシーンを思わせる様な締め括りとなっていて非常に印象的です。世の多くのクリエイターたちに読んでもらいたい名著ですね。
0投稿日: 2011.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログiPod, iPhone, iPad を世に送り出した天才スティーブ・ジョブズの伝記下巻。窮地に陥ったアップルにジョブズが戻るあたりから始まる。矢継ぎ早に打ち出す施策でアップルは復活、iPodリリース以降、大躍進を遂げていく。そんな中、ジョブズを蝕む病は進行し続け…。 上巻を読み、益々ファンになったので購入。サクセス・ストーリーな部分もいいし、それを実現したジョブズが何を重視していたか、何を考えていたか分かったのもいい。なんですが、最も心を動かされたのは、偉業を成し遂げたジョブズの人生に触れられた事です。後半は、本当に泣けてきました。 まるで台風のような強烈な個性を持つ人物、しかも偉業を成し遂げている、そんな人の伝記はなんて興味深いんだと思いました。オススメです。
0投稿日: 2011.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
上巻よりもだいぶ楽しめる内容だった。 iPod絶頂期のときに、危機感からiPhoneが構想されたことは非常に意外であった。 もともとアップルがそんなに好きなわけでは無かったが、スティーブ・ジョブズとアップルが生み出してきたものは別格だと改めて感じさせる。 それにしても、スタンフォードの卒業式スピーチと、本書最後の言葉、何度も見返したい内容です。
0投稿日: 2011.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ生前の氏の興味の一つに教科書を進化させることがあったという。やはり行き着くところは教育なんですね。 それにしてもアップルの一連のプロダクト群に共通するシンプルなデザインの裏に、あれほどまでの拘りがあったとは。他社製品との決定的な違いはその哲学だけでなく、それを実現する努力と拘り。さらにそれを組織として運用するための強烈なトップダウン。 ある意味奇跡の会社ですね。 合掌。
0投稿日: 2011.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログⅠとⅡの間には時間差があったんだ~ハードとソフトは一体であるべきだとの信念で作られたNeXTのワークステーションはサンに惨敗し,1991年ハードウェア生産を断念,95年にはマイクロソフトの支配を認めざるを得なかった。アップルにはDTPをほぼ独占していたが,Win95の発売で急落。オラクル会長エリソンが株価14ドルに低迷しているアップルを買い,ジョブズがCEOとして25%を持つ話を持ちかけられるが,ジョブズはアップルにNeXTを1株10ドル総額4億ドルで買わせる。支払いとして現金1億2000万ドルと3700万のアップル株でスカリーの後任アメリオから受け,ゲイツの激怒を背景に会長のアドバイザーにおさまる。アメリオが自爆し,ピクサーのCEOを引き受けながらアップルの暫定CEO(iCEO)に返り咲くと,非公式のアドバイザーウォズニックも魔法を取り戻せると喜ぶ。事業整理を進め,ウラードだけを残して取締役の自任を実現するが,その中にはマークラもいた。iCEOとして3000人以上を解雇し,1997会計年度10億4000万ドルの赤字,あと90日で倒産という瀬戸際で翌年には3億700万ドルの黒字,ジョブズが復活しアップルも復活したのだった。辞めようとしていたデザイナーのジョナサン・アイブと意気投合し,1998年5月6日に299ドルでiMacが登場する。2000年1月にOSXと発表,2001年5月19日にアップルストア1号店が開店(2011年んは317店舗)。コンピュータをデジタルハブにする構想で,iTunesを開発しiPodは2001年10月30日,1曲99セントのiTunesストアもレコード会社の説得に成功。Windows用も2003年10月に出荷。200年発売のパワーマックG4キューブは失敗するが,ディズニーとの関係を修復して,ピクサーの独立性を保たせる内容で喜んで売却する。2003年10月腎臓結石の治療をした医師に検査を勧められて,膵臓に影があると示されるが,精密検査は腫瘍をみつけ,膵島細胞腫瘍と診断される。拒否し続けた開腹手術は2004年7月31日に実施され,CEOにクックを指名し,肝臓への転移はひた隠す。iPodに電話機能を付けようとiPhone開発がスタート,同時にiPodのアイデアも出始める。当初はスタイラスペンを使うタブレット型をアップルに奨めてくるMSの攻勢に,タッチ式を強力に推進。ゴリラガラスという強化ガラスを得て,設計をリセットし,2007年1月iPhoneは発表され,6月に発売されると世界は変わってしまった。2008年ガンの治療と極端な食習慣で痩せ始め,カリフォルニアに加えてテネシーでも登録して,生体肝移植を受けたのが2009年3月21日,生死の境を彷徨いながらも3ヶ月で復帰。2010年1月27日にiPadを発表。実物がない,カメラやUSBが付いていない,Flashが使えないなどの酷評を得るが,4月に発売されると爆発的に売れる。社外にもアプリ作成を許すが,アップルが検査し,iTunes経由で配布することが条件とされた。ウォールストリートジャーナルのマードックとの関係も進み,新聞のデジタル化も進展した。グーグルのOSアンドロイドが登場するとジョブズは特許侵害で訴える。iPhone4でアンテナ問題が発生したときには高校生の息子を会議に同席させる。2011年6月iCloudを発表し,新社屋の設計を市役所で披露。リードが高校を卒業した翌日,トイストーリー3が公開される。2011年8月24日経営権をクックに委譲~完璧主義者。自己愛性人格障害,現実歪曲フィールド,禅に傾倒し,ミニマリストのベジタリアン。カウンターカルチャー・アントプレナー・ニッチ・アーキテクチャー・エンドツーエンド・コモディティー化など,カタカナ語を調べちゃったよ。あのアル・ゴアも社外取締役だった。私は魔法使いのような天才の作った製品を一度も持ったことがない。欲しいと強く思うこともない。どうしてだろうね
0投稿日: 2011.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブズは死ぬまでジョブズだったのだなぁ。 彼から学ぶことは出来ても真似ることは誰一人出来無いだろう、と改めて思わされた。 世界が変わった瞬間瞬間に立ち会えたことをとても意味の有ることに感じる。
0投稿日: 2011.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ前後編の後半。 アップル、ネクスト、ピクサーの話になるとやっぱりわくわくする。 最近アップルを知った人は後半だけでも良いかもしれない。
0投稿日: 2011.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学1年の夏、ジョブズのスタンフォード大学卒業式典で行ったスピーチを見て、気付いたら、知らないうちに涙が零れていた。その時の涙の意味を、思い知った下巻。 彼が人を魅了したのは、激しい性格だとか、カリスマ性だとか、それだけではなく、物事に対してごまかさず、逃げず、執拗なほどに向き合った結果なのだ。自分の好きなことを貫き通すことは、ものすごく労力のいることで、辛いことの方が多い。それでも、強い意志を持って、あらゆるものをなぎ倒し(それこそ、嵐のように)、進んで行ったジョブズ。彼と交渉していると、不思議と誰もが納得してしまったという。ものすごい熱意が、彼を魔法使いにしたのだ。 今、私の手元に1カ月遅れでやってきたi phone4Sがある。これが、どれだけのストーリーを背負っているか。 4S(for steve)、これを手に入れることができて、本当に良かった。
0投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
上巻は自らも持て余していそうな激しい情熱を持つ若いジョブズが描かれていて、下巻は彼の理想や信念がアップルへの復帰やその後の大成功と共に綴られていた。 やっぱりこの人については全然知らなかったんだな。 20年連れ添ってきた妻への手紙と、かつての恋人ティナ・レドセのメールがいい。 できる人っていうのはだいたい頭が切れるのと精神的なエネルギー量が大きいと思うんだけど、彼はほんっとに凄い。 何が僕を駆り立てたのか。クリエイティブな人というのは、先人が遺してくれたものが使えることに感謝を表したいと思っているはずだ。 そして、僕らの大半は、人類全体になにかをお返ししたい、人類全体の流れになにかを加えたいと思っているんだ。それはつまり、自分にやれる方法でなにかを表現するってことなんだ。
0投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログピクサーを買収し、アップルに復帰、世界のカリスマになるまでが書かれている。 彼が目指したクローズドの世界は、永遠のテーマである。 そして、世界に変革をもたらす人は往々にはして、強い信念を持っている事が、伝わってくる。
0投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログⅠとⅡ、2冊からなる大作、翻訳物のこの長さはかなり厳しいかと思いきや翻訳臭さが全く感じられず、とてもスムーズに読み進めることができた。ジョブズ氏の急折もあり発売が前倒しになりかなりの強行軍だったと思うのだが、とても素晴らしい翻訳、先ずは翻訳の井口氏に感謝したい。 ジョブズ氏は驚異のプレゼン、豪腕の交渉力、ミクロとマクロの同時洞察力など様々な天才的能力が備わっている。だが、それだけではこれほどの成功は覚束ないだろう、本書を読んでその秘密を考えてみた。 ひとつはアップルを放逐されたことだろう。そこでネクストやピクサーを通じて新たに出会った人々とコラボレーションにより、ジョブズ自身の創造性が更に飛躍したことではないだろうか。 もう一つは十代の頃ボブディランに憧れた気持ちをホールアースカタログに代表されるカウンターカルチャーとして持ち続けていたこと。それにより1969年以降消滅(以下の注参照)したとされているそのスピリットを提供できたことだと思う。 ※注 So I called up the Captain 'Please bring me my wine' He said 'We haven't had that spirit here since 1969' 「Hotel California by Eagles」 より抜粋。 ここでのスピリットがカウンターカルチャー魂と酒のダブルミーニングであることは、「ソーシャルメディア進化論(武田隆著)」より。 ジョブズ氏はマーク・ザッカーバーグ氏にも自分の経験などを伝えたいとの思いがあったようです。マーク氏のfacebookを推し進める哲学はオープンで透明性のある世界を目指しています。さてアップルは。。。 ※ⅠとⅡを分けるほどの感想では無いのでどちらも同じテキストです^^;
0投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ何かを発明した訳ではないが テクノロジーとリベラルアーツの交差点で絶対的な力を発する・・・ 彼は稀代の『天才』です。 Appleが成し遂げて来たこと。。。 デスクトップで当たり前となっているGUI(PCを感覚的操作ができるようにフォルダなど可視化したインターフェイス。ゼロックスが持っていた技術をAppleが開発し世にレビューした)、iTunes インターフェイス(SONYほか大手が作ったインターフェイスはどれもショボい)、iPod(小型HDDを開発しつつも市場での使い方を知らなかった東芝。AppleがそのHDDを買い占め市場を独占)、FDドライブを排除(Windowsパソコンも最近そうなっている)、iPhone・iPad(日本のスマホは2番煎じでインターフェイスが完全にいけてない。デジタル教科書時代もすぐそこ)等・・・数え上げたらキリがない。 クローズド理念でありながらAppleプロダクトは素晴らしいものばかり。Appleが作り上げてきた技術を大企業が模倣し、世の中成り立っている部分、往々にしてあります。 あと1ヶ月で実質つぶれていたAppleを救い、さらにAppleを追い出されてからのピクサー快進撃、多くを学んだ後にAppleにカムバックしたジョブズの選択と集中は目を見張るものがありました。 その他ジョブズの矛盾や、ビル・ゲイツとの対比、他社に比類ない製品へのこだわりをより深く知る事ができました。 2巻最後にジョブズが語った彼が想う経営やものづくりの本質。 これから持続可能となる企業の理念を言い当てているのではと感じました。 ある程度成熟し複雑化した世界は、よりシンプルで統一的な方向へ向くのかもしれません。そのことに一早く気づいた企業が持続可能となる気がしてなりません。 本書は、「名言」となる文句なども多く楽しめました。
0投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ【つくっているのは作品】 「事実は小説よりも奇なり」読んでいると面白いです。いろいろな場面で、さすがスティーブ・ジョブズ。 小説を説明することはできないので、読んでみてください。 (I,Ⅱ同じコメントです)
1投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログついに読み終わった! いつの間にか増えていたMAC製品へ漠然と感じていた魅力について、ちゃんと説明してもらった感じです。 元々工業デザインが好きですが、確かに僕にとってのMACの第一の魅力はその面での美しさだったのではないか。 今まで、MACユーザーを、「時代の流れに取り残された、そして、しかるべき移行を行わない、努力を怠っている人たち」とちょっとだけ思っていてごめんなさい。 本書より 「『顧客が望むものを提供しろ』という人もいる。僕の考え方は違う。顧客が今後、なにを望むようになるのか、それを顧客本人よりも早くつかむのが僕らの仕事なんだ。ヘンリー・フォードも似たようなことを言ったらしい。『なにが欲しいかと顧客に尋ねていたら、『脚が早い馬』と言われたはずだ』って。欲しいものを見せてあげなければ、みんな、それが欲しいなんてわからないんだ。だから僕は市場調査に頼らない。歴史のページにまだ書かれていないことを読み取るのが僕らの仕事なんだ。」
0投稿日: 2011.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタル製品との関わりを変えたApple社、その創設者であるSteve Jobsの伝記です。Jobs復帰以降が書かれた下巻はリアルタイムで見ていたので興味深く読めた。 たしか、初めて購入したAppleの製品はiBook G4でした。 その後、iPodを計4台、MacBook ProとすっかりApple製品の虜です。
0投稿日: 2011.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログボリュームが多かったですが、結構ハイペースで読み進められました。自分の身の回りにある製品に関するエピソードが多かったからでしょうか。 上巻は正直言って読むのに時間がかかりました。ジョブズのきっつい人格に慣れるのにエネルギーを費やしてしまいました(笑) ジョブズの言葉が多数引用されていますが、自分にとっては 「顧客が今後、なにを望むようになるのか、それを顧客本人よりも早くつかむのが僕らの仕事なんだ」 「欲しいモノを見せてあげなければ、みんな、それが欲しいなんてわからないんだ」 が胸にしみこみました。 マーケットインの先を行く考え方なんだろうな、と思います。
0投稿日: 2011.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
上巻は幼年期からアップル追放までを描いた昔の話と較べ 下巻は沈んだアップルの復活からiPad,iCloudまでのリアルタイムで追いかけていた時の話だけに、感情も入りやすい。 いつも気軽にサクサク読める本ばかり読んでいたので、 正直ボリュームが多かったんだけど、井上さんの和訳が直感的に情景が浮かび、サラっと集中して読むことができた。 『異端児』、『独裁者』とは聞いていたが、 まさか人間的欠陥を感じるほど、イカれた天才だったとはまで知らなかった。 特に印象的だったのがGoogleがAndroidを開発して携帯OS市場に参入してきた時のジョブズの怒りっぷりw このジョブズのコメント。 『我々の訴訟は、要するに「グーグルよ、よくもiPhoneを食い物にしてくれたな。なんでもかんでも我々から盗みやがったな」と言ってるんだ。凄まじくでかい盗みだ。この悪を糾すためなら、アップルは銀行に持つ400億ドルを残らずつぎ込むつもりだし、必要なら僕が死ぬ時の最後の一息だってそのために使ってやる。アンドロイドは抹殺する。盗みでできた製品だからだ。水爆を使ってでもやる。連中はいまごろ震え上がっているはずだ。罪を犯したと知ってるからね。検索以外のグーグル製品--アンドロイドやグーグルドキュメント---はみんなゴミだ。』 比較的早い段階で、歴史的経営者の伝記を読むことができてよかった。 これからのアップルの活躍に期待。
1投稿日: 2011.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずとしれたスティーブジョブズの伝記第二巻目。最近テレビでも特集として組まれていますが、本にしか書いてない真実があります。最後の締めくくりもAppleユーザなら「あっ」っと感じるはず。 僕はとにかく「シンプル」に直感力を信じよう、と。そう思った一冊。
0投稿日: 2011.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ最終章のジョブズの言葉に感動した。 「僕らは自分が持つ才能を使って心の奥底にある感情を表現しようとするんだ。僕らの先人が遺してくれたあらゆる成果に対する感謝を表現しようとするんだ。そして、その流れになにかを追加しようとするんだ。」 俺もそうするんだ…。
0投稿日: 2011.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログパート2は、あっという間に読み終わってしまいました。 スティーブの人生は、2005年のスタンフォード大卒業スピーチに集約されていますが、晩年の生き方はわれわれIT業界に携わるものやクリエイターに強いメッセージを与えてくれます。 ちょっと残念なのは、専門用語の日本語訳に?と思うものがいくつかあり、原書と読み比べました。 ところどころ違和感を感じた文章も原書ではクリアになります。 原書がやっぱり、おすすめ。
0投稿日: 2011.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ田と書いたシンプルさが素敵でした。「やつらはなにもわかっちゃいない。僕らはそれがわかってる」と言えるようになったら起業かんがえます。マークもにたようなことを言ってた記憶があるので。
0投稿日: 2011.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最髙の結果を出すためのチームを作る人は、自分のがんと戦う時もそうしたのだなぁ。ジョブズのおかげで、自分が信じるものを言い放ってもいいんだって思えた。そのうちiPhoneにしよう。道具は目的じゃなくて手段だもんな。
0投稿日: 2011.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログアップルはどうしても好きになれないけど、ジョブズが偉人だったことは間違いない。心からご冥福をお祈りする。
0投稿日: 2011.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ不覚にも泣いてしまった。 上巻から続く華々しいスタートから、自ら作ったAppleを追い出され、様々な経験を積み重ねて再度Appleに復帰。 その後のApple再生エピソードから、21世紀の最初の10年で繰り広げられた奇跡の10年間。 スティーブの社会やビジネスにおける貢献と問題のある性格が招くエピソードの数々。 ここまでの内容であれば、ビジネス書の一角を占めるジョブズ本と変りなかったはずだ。ただ、「本人公認」というお墨付きがスペシャルなだけの本だっただろう。 しかし、下巻中盤まで読み進めて改めて知った。本書はビジネス本ではない。 誰も気づかなかった「デジタルとリベラルアーツの交差点」に立ち続けた一人の男の人生のドラマ、まさに伝記本なのである。 癌発覚後顕著となる、スティーブ本人の病気との苦悩を初め、ほぼ初めて語られた家族の話を読むにつれ、偉大な伝道者ではなく、一人の男としてのスティーブに感情移入していく自分がいた。 特に、後半スティーブが妻のローレン・パウエルにこれまでの感謝と共に送ったとてもシンプルな一文には、シンプルで率直なスティーブらしさが全面に出ており、涙を誘う。 まさか、有名人とはいえ一CEOの伝記を読んで泣くとは思わなかった。
0投稿日: 2011.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログⅠよりも更にジョブズの超人ぶりがわかる。アップルの「再生」、病と闘いながらのイノベーションの連続。「統合」「卓越」という彼の信念の揺るぎなさに心が震えました。著者にも、世界同時発売を可能にした翻訳者にも大いに敬意を払いたい。
0投稿日: 2011.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログIよりもIIの方が今に近いだけに 自分がよく知っている製品や出来事が多く、 親しみやすかったこともありますが どちらかと言うと、このIIに関しては、 どういう製品を作ってきたかと言うよりも、 どういう考えでAppleという会社を経営しているのか ポストPCの時代にどうしていこうと考えているのか についての記述が興味深かったです。 そしてなにより、 病気になって自分の死に直面した スティーブが残りの時間どう生きたかについて 書かれた部分や彼の家族について書かれた部分などが 一番心に残りました。 素晴らしい本でした。 それ以外に言葉がありません。
0投稿日: 2011.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログⅠ、Ⅱまとめて。 これまで持っていたイメージは、当たり前だが表面的な物でしかなかったなあと痛感。 一見すると大部分の人には参考にならない考え方、情熱、集中力のような気がするが、本質にある考え方は非常に参考になると思う。 それをどのように表現するか、発信するかというところがだけなのではないか。 まあその違いが、この人が特別な人と認識される理由なのでしょうけど。
0投稿日: 2011.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「変人伝説」下巻は、apple への華麗なる復帰と様々な魅力的製品の開発、そして逝去までを描く。やはり身近な製品にまつわる逸話が出てくると読みやすく、こちらは★4つ。 自分がいかにして Macintosh ユーザーになりしか、理由を振り返ると音楽・映像・文章作成をシームレスに創造できる「デジタルハブ」構想を体現した製品にひかれたからだった。その製品は、「リベラルアーツとテクノロジーの交差点」に立ち、技術的スペックよりも「何ができるか」にこだわり、社員を叱咤激励し続けた Jobs 氏の境地無くしては実現しなかったのが、彼の偉大さだったと思う。 それを実現しようとする時、企業組織の長としてやはりマキャベリ「君主論」の理解は最低条件なのかなと思う。「いい人」だけでは、やはりリーダー失格。自分の勤務先の最高責任者もその最低条件は満たしているのだが、何だかなぁ(苦笑)
0投稿日: 2011.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ第2巻は、スティーブ・ジョブズがアップルに復帰してからの軌跡で、この辺りの活躍はアップルのファンならよく知っていると思います。 読みどころは、一見綿密な計画に則って進められたように見えるデジタルハブ戦略の裏にさまざまな葛藤があったことがわかるエピソードの数々で、例えばiPodをWindowsにも対応させるかどうかの議論など、要所要所で重大な決断があったことがわかります。 また、想像していた以上に過酷ながんとの闘いについても詳細が語られていて、(アップル製品に向けるのと同じような)独自の思い込みで手術をこばんで病状を悪化させてしまう部分など、読んでいて胸が痛くなります。 いわゆる経営指南本としては破格すぎですが、アップルが好きなら宝物と言えるような本だと思います。 (個人的に、著者がスティーブ・ジョブズのiPodの中身を見せてもらうエピソードがお気に入りです)
0投稿日: 2011.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ友達に上巻を借りて、下巻は自分で買いました。 すごく面白かった!! 中学3年生の時iPodを買って、そのデザインの良さに 感動していたことを思い出しました。
0投稿日: 2011.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
Steve Jobsがアップルに返り咲いてから、ガンとの闘病生活を送りながらも最期の瞬間まで世の中を変え続けたことが書かれた本 Ⅰに続き、Ⅱの方もとても刺激的だった。 彼は年齢とともに人付き合いを学びつつも、本質的なところは変わらずにiMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad , iCloudなどを世の中に出し続けた。 自身がガンだと宣告されても、それは変わらなかった。 相変わらず、気に入らないことは「くそったれ!」とののしるし、向き合いたくないことは無視してしまう。しかし、世の中を変えたのはアップルのエンジニアやデザイナーであり、彼らにビジョンを与え続けたのはJobsである。 「人生を全うする」とは彼のことを指すのだと、改めて実感した。 彼の最期に、30年以上のライバルであるビルゲイツが彼の家を訪れ、互いを認め合うシーンがあるが、その内容が泣ける。 自分もこんな生きざまにしようと決心した、人生で何度も出会うことはない本
0投稿日: 2011.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログアップル復帰後を描いたPART2はさらに面白かった。ジョブスにとっては、結婚したこととピクサーでの経験が、かなり大きく作用したように思う。自分も悔いのない人生を送りたいと感じさせてくれた。
0投稿日: 2011.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログSteve Jobsが亡くなる直前まで書かれていた。 本当に寂しい。辛い。 もう少し生きていたら、と思う。残念だ。 良いことも悪いことも正直に書かれているのは素晴らしい。 だから本人はチェックしなかった。 あと1年生きていたら読む予定だったと。 芸術と技術を統合させてまだ見ぬモノを生み出したように。 凄いモノを生み出せる者となっていきたい。 人は誰でもいつかは死ぬ。 残された人生で私は何を人類全体にお返しできるだろうか。
0投稿日: 2011.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログところで、君はなにかすごいことをした経験があるかい? なにか生み出したことはあるかい? それとも、ほかの人の作品にけちをつけて、作る人のモチベーションを引き下げてばかりいるのかい? 顧客が今後、なにを望むようになるのか、それを顧客本人よりも早くつかむのが僕らの仕事なんだ。 交差点
0投稿日: 2011.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブズが弱っていく姿を読んでいるとなんだか悲しくなってきた。 あんなすごいプレゼンをしていたときも、病気と闘って痛んだと思うと、さらにジョブズの凄さがわかる。 ジョブズはビショナリーな会社を作りたかった。 アップルがビショナリーな会社になったかどうかはこれからわかる。 どうなるんだろうか? この本を読んで、仕事をしている最中にふと思うことがある。 「ジョブズだったらどうするだろうか?」 自分にはジョブズと同じことはできないが、できることもある。 そんなことを考えてふと楽しくなる。 この本は本棚に残しておく一冊(二冊になるが)に加えようと思う。
0投稿日: 2011.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2巻目ではジョブス復帰後の新生Appleが手がけた数々のヒット商品の開発裏話と余りにも若すぎる晩年のがんとの壮絶な闘いの記録が中心となる。 印象に残るのは病室で医療器具のデザインにさえ拘ったというジョブズの美への拘り、Appleが他社との互換性に消極的だった理由の一つがジョブズが周辺機器やソフトのGUIまでも統一した美しさを求めたからだというのだ、ビジネスよりも美を求めたその執念ともいえる拘りと姿勢には深く敬服する。 しかし美とは主観的なものだ、一人の人間の美意識と哲学を貫こうとすればそれは全てのプロダクトを一人の人間が完璧にコントロールする事を意味する。 ルーツにカウンタカルチャーとの強い結びつきを持ちながら時としてビッグブラザー的な独裁者の顔を覗かせるApple社の矛盾は、誰よりも自由な精神を持ちながらその美意識の高さと完璧主義故に周りのものを全てコントロールしなければ居られなかった創業者の性格の反映とも言えるかもしれない。 また彼のiPodの中身を紹介した章も興味深い。 この本を読むと彼が経営者というより完璧な美を求めた芸術家であり革命家であった事、その最高の作品がAppleというプロジェクトであった事が良く解る。
0投稿日: 2011.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々な自伝を読んできたが、この本は少し毛色が違うように思える。 ここには、ただ純粋に事実がある。まるで聖者のように天才的なジョブスと、致命的なほどに他人の身を考えない悪魔のようなジョブスを。 自伝「Ⅱ」ではジョブスがアップルに戻ってからIpad2を出すまでを中心に書かれている。我々の生活に欠かせないデジタルアーツの数々の誕生秘話が非常に面白い。 どの製品作りのときにも、必ず技術的な問題に直面し、様々な人と対立する。その度にジョブスは非常な暴君となって乗り越えていく。 この本を読んで彼を「聖者」とあがめる人はいないだろう。これを読んでも彼を好きになる人は少ないにちがいない。尊敬はするだろうが。 その意味での中立な「事実」がしっかり書かれていた。 惜しむべくは、単なる事実のまとめになってしまい、ジョブスの、製品やエンドツーエンドのマーケティングに対する想いが掘り下がっていないことだ。我々が一番知りたい謎が結局未解明のまま終わっている。 だが、それでもこの人物の偉大さは変わらない。今後100年は称えられるだろう、「現代の魔術師」の自伝は、エジソンやルーズベルトのように一般常識になるに違いない。
0投稿日: 2011.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログガンの宣告から、iPhoneの発表。 そして再発してからのiPadの発表。 その2つとも楽しみにしながら手に入れ、今でも毎日のように愛用しているが、その背景に、ジョブズの並々ならぬ生命力があったのだと思うと、辛いとか悲しいとか言う前に、今 手にできている奇跡に感謝したい。 ジョブズはエジソンやフォードに並べ評されるような発明家として後世に名を残すだろう、と最後のほうに書かれているが、本当にそう思う。 そして、後年になってその賞賛を見聞することはできないだろうが、同じ時期を生き、その製品に触れることができたことをうれしく思う。
0投稿日: 2011.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ後半は、病気のことがたくさん書かれていた。病気と戦いながらもあれだけ情熱的に仕事ができるなんてメチャクチャスゴイと思った。Appleのすごいところは消費者が欲しいと思うものを先回りして提供できるとことだと思う。ただ、商品を絞りこむため、デザイン、機能が気に入らないと購入しないと思う。iPhoneは画期的である。それより先に出したiPodももちろん、画期的だが、音楽を聴かない人にとっては必要ない。しかしiPhoneは電話である。アプリにより色々なことに利用できる。そして何より他社より先んでた上にこのシンプルさ。メチャクチャスゴイのだ! ジョブス一人がすべて考えたのではもちろんないし、他の素晴らしい人材がいたからこそ出来上がったものだと思う。人材の集めかたがすごく優れていたんだと思う。 現実歪曲フィールドは笑える。 小飼弾さんも少し持っているのではないかと思う。何かを成し遂げる人は持っているのではないだろうか。 強い意思がなければいいものは創造できない。 ジョブズと会って話がしたかった。クソヤローと言われそうだけどね。
0投稿日: 2011.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ企画コーナー「追悼- Steve Jobs・北杜夫」(2Fカウンター前)にて展示中です。どうぞご覧下さい。 展示期間中の貸出利用は本学在学生および教職員に限られます。【展示期間:2011/11/1-12/22まで】 湘南OPAC : http://sopac.lib.bunkyo.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1606407
0投稿日: 2011.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューはブログにて http://ameblo.jp/w92-3/entry-11077537965.html
0投稿日: 2011.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻。2000年頃からこれまでについて述べられている。上巻と比べて社内の人との権力争いなどの記載が減り、最近発売された製品に対する思い・妻子との関わり等の記載が増え、想像しながら読むことができたためより一層楽しむことができた。本書においては一貫して以下4点について主張されている。1)シンクディファレント2)統合アプローチによる管理3)自分の意思(正義or正しいと思うこと)を貫く4)直感的でシンプルにする。非常に参考になるエピソードばかりであった。また読みたい。
0投稿日: 2011.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
Ⅱはジョブズがアップルに復帰してから、アップルを立て直しiMac,iPod,iPhone,iPad などヒット商品を次々に世に送り出すさまが描かれている。新商品の開発に立ち向かう様子は生き生きとしスピード感がある。とはいえ傲慢さや相手に対する尊大さは相変わらず。ジョブズに言わせると、真に素晴らしいものを完璧な形で生み出すにはしかないことだと。それも納得の物語だ。その集中力とシンプルさに対する愛は「禅」を通じて会得したものだという。しかし私の疑問でもある、「禅」の穏やかさ、心の平穏を保つ方法は得られなかったようだ。これもジョブズの一面だという。人格的には完璧ではなかった(完璧な人格って何?)部分もあるが本当にエジソンやフォードに並ぶ偉人には間違いないであろう。結婚20年目に妻にあてたメッセージに彼の本音があらわれているように思える。 この偉大な人物の仕事を彼の生み出した機器を通じて、生で体験できたことを大切にしたい。
0投稿日: 2011.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ上下巻とも本人の肉声が満載。カリスマと呼ばれる彼がその瞬間何を考えていたのかが詳細に書かれており非常に人間味が感じられました。とてもいい本です。
0投稿日: 2011.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかく読むべし!です。身の周りにいた強烈と言われる全ての人をいろんな意味で超える強烈な人。やっぱりジョブスは最強です。
0投稿日: 2011.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読み易い部類、サクサクと行けた。 一人の人間として書かれると思う、良くも悪くもそれだけ。強いて言えば比較的際新しいマック製品のコンセプトが分り易く解説されていたことだろうか。 前巻にも書いたように自分としてはこの著者は人間性としてかなりの面で否定的なタッチで書かれると感じるし、おそらくインタビューを通して受け取った素直な感覚なのだろう。それは恨みを持っている人物が多いのかもしれないし、他人の眼で見れば見るほど社会性としては受け取りがたい感覚をもってたのかもしれないし、この感想を書いている自分が単純に苦手な意識を持ったからであったということもあるとは思う。 「集中」に重点を置いた切落しとか交渉事とか人間関係の強烈さは、時代とタイミングとして会社がそれを必要とする場面にあったのもあるが、現実に目にしたらどうなるかと考えるとこのような行動は取れないなとも感じるだけにその影響力がわかる。本当に視点としてはかなり偏った所に据え置いて進んだ物だなと読めた。 ちょっと関係ないが作中に製品を分解して中を覗き込んだりすることが出来ない受け取るだけの道具になってしまっているという表現があったが非常に自分には合ってる物かもしれないという気もした。それは何故かというと目的ある行動に対してのみ道具はあればいいと思っているし、本当に気になる場合はそのプロテクトも突破していくだろうと思えるから。 ただその数多い本の中で比較的評判になったと受け取れるこの本が全体を通して(少なくとも自分の中でそう受け取れた内としては)功績と同時に悪評が相当な割合があるのは珍しい。
0投稿日: 2011.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
IIの方はAppleに返り咲いたあとの(iMacの発表やiPadなど)比較的近来の話が中心で、あまりの登場人物の多さと時代背景の理解のしづらさ(私が20代なので60年代のヒッピー文化や当時のカウンターカルチャー的のもの、あるいはその感覚がわからない)と比べて読みやすいです。 書いてある内容の多くは、やはりネットで拾えるレベルのものが多いのですが、改めて時系列に彼のエピソードを読み解いていくと、やはり壮絶なものがあります。 あまり自叙伝を読んだことが無いので想像が入りますが、自叙伝というものには描かれている人物の素晴らしさなどが語られており、結果として数箇所ぐらいは「こういうところは見習いたいなあ」と思えるものが見つかりそうなものだと思うのですが、スティーブ・ジョブズにいたっては全くそれが無い。 「すごすぎて見習えない」というよりは「見習いたくない」というか、彼のあまりの苛烈さに若干引いている自分がいます(笑)
1投稿日: 2011.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011/11/06-11/13今求められているリーダー像はスティーブジョブス。①自分のお気に入り②独裁者③全体から部分を見る
0投稿日: 2011.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログII は知らなかったエピソード満載。外野からのニュースは、あ、これ読んだことある!その時内部ではこーだったんた!という話満載。あとはゲイツの「やられた」という台詞にニンマリ。でもこれ裏取りして書いたんかなあ?
0投稿日: 2011.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログオープンとクローズ。ハッカー精神とは対局にあるApple製品。それを愛用しながらOSSに惹かれる人間としては複雑な思いをしながら本書を読んだ。 オープンな世界とクローズな世界、どちらも素晴らしい製品を生み出してきた実績がある。だから、どちらも見方次第では良いものなのだ。単純な白黒、善悪では判断できない。そんなに自分をはっきりさせる必要はないのかもしれないな、と少し気が楽になった。そういう事が書かれている本ではなかったけど。 読み物として面白かったし、人生の進み方について参考になることが結構あったように思う。きっと、誰もがジョブズの中に自分と似ている部分を見出すし、違う部分もたくさん見つけるんじゃないかな。そこから何を再発見できるのか。またしばらくしたら読みなおしてみたい。
0投稿日: 2011.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読み終えての感想は、「羨ましい」ということだった。 ジョブズ氏の独特な思考、価値観をたびたび、現実歪曲フィールドと表現され、自分のイメージに合わなければ、メッタ斬りにし、人に対してもとことんこき下ろす。結果として、iPod/iPhone/iPadとユーザーに歓迎される製品を世に送り出すことが出来たことは、現在の人たちにマッチしたものを提供できたこと、価値があると認められたことは、当然の出来事だったのかもしれない。 ジョブズ氏がパソコンでは、閉鎖的で、成長速度は低下してしまったと思うが、iPhoneを発売することで、コンピュータは、再び成長を加速できたのかと思う。 製品に、ONとOFFを付けたくないと思う気持ち、ジョブズ氏の他の考えを理解することは出来ていなかったが、最後に理解出来たと思う。 ◇購入
0投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ第一巻を読み終わり、第二巻に本日突入。 こんな勢いを持った人間が近くに存在したらと思うとホント、ゾッとする。読みながら何度も表紙の顔写真を眺めて見た。 Appleの製品を忘れ、スティーブジョブズの若き時代にのめり込んで読んだ。 第二巻は、Appleの製品とオーバーラップして、またビジネス書の意味合いを含めて、のめり込んでいる最中。 ぶ厚い書籍であるが、読み進み、赤い紐のしおりを先に先に挟んで行くことが楽しい。
0投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ癌を患ってからもジョブズはやはりジョブズであった。Ⅰのジョブスと変わらない。ゲイツですら、凡人に見えてくる。もっとも、ゲイツはiPhoneもiPadも、最初には、そしてもしかしたら今に至ってもその素晴らしさを過小評価しているんだけど。 様々な製品や、アップルという会社がビジョナリーになっていく過程が、すばらしい。すぱらしいパソコンやクラウドな環境までも作り上げたということとは逆説的だが、パソコンや、パソコンのネットワーク、それを通じた共同作業からは決して見たこともないような素晴らしい製品は出来あがらないのだ、ということがわかる。ジョブズが最後にアップルの本社の設計図に描いたように、人と人が実際に交わり合うこと、議論する中からしか、そんな製品は立ち上がってこないことをジョブズは証明して見せた。ジョブスの狂気は持ち合わせていないが、そんなところは学ぶことができるかもしれない。学んだところで、決してジョブズにはなれないんだけど。
0投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【読書メモ】 ■シンク・ディファレント クレージーな人たちがいる.反逆者,厄介者と呼ばれる人たち.四角い穴に丸い杭を打ち込むように,物事をまるで違う目で見る人達.彼らは規則を嫌う.彼らは現実を肯定しない.彼らの言葉に心を打たれる人がいる.反対する人も,賞賛する人もけなす人もいる.しかし,彼らを無視することは誰にもできない.なぜなら,彼らは物事を変えたからだ.彼らは人間を前進させた.彼らはクレージーと言われるが,私たちは天才だと思う.自分が世界を変えられると本気で信じる人たちこそが,本当に世界を変えているのだから. ■デザイン原理 シンプルさというは,見た目だけの問題ではないのです.複雑さを整理し,秩序をもたらせば,人を尊重する製品にできます.ミニマリズムでもなければ,ごちゃごちゃしていないということでもありません.本当にシンプルなものを作るためには,本当に深いところまで掘り下げなければならないのです.対象のあらゆる面を理解する,それがどう作られるのかも理解する.つまり製品の本質を深く理解しなければ,不可欠ではない部分を削ることはできません. ■デジタルハブ コンピュータがデジタルハブになると最初に見抜いたのはアップルだ.でもこの先数年でハブはユーザーのコンピュータからクラウドに移る. ■受け継がれてゆくもの 僕はいつまでも続く会社を作ることに情熱を燃やしてきた.すごい製品を作りたいと社員が猛烈にがんばる会社を.原動力は製品であって利益じゃない. IBMやマイクロソフトのような会社が下り坂に入ったのはなぜか,いい仕事をした会社がイノベーションを生み出し,ある分野での独占かそれに近い状態になると,製品の質の重要性が下がってしまう.売上メーターの針を動かせるのが製品エンジニアやデザイナーではなく,営業になるからだ.その結果,営業畑の人が会社を動かすようになる.営業畑の人間が会社を動かすようになると製品畑の人間は重視されなくなり,その多くは嫌になってしまう. スタートアップを興してどこかに売るか株式を公開し,お金を儲けて次に行く―そんなことをしたいと考えている連中が自らを「アントレプレナー」と呼んでいるのは,聞くだけで吐き気がする.
0投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ後半は、ジョブズのイノベーションの快進撃が続く、壮大な人生とビジネスの物語だ。反撃ののろしとなるiMacの投入、関係者全員に反対されたパソコン直営店のアップルストアの設置、iPodとiTunesを起点としたデジタルハブという新たなビジネスモデルの創造と音楽業界への革命的インパクト、ピクサーを巡ってのディズニーとの壮絶な闘いと勝利、そしてiPhoneからiPadの開発と大成功、iCloudという次なるデジタルハブへの執念と実行。その途中途中でのガンとの壮絶なバトル。 俺も使ったり観ているもの(iPhone、MacのPCやトイストーリーを筆頭とする一連のピクサーの映画)の誕生、制作の経緯や秘話が出てくることもあって、引き込まれるように読んでいった。 そしてこの痛烈苛烈な人物像(部品の納入が遅れそうになった供給会社にFucking Dickless Assholesという言葉を浴びせるような)、こういった人でなれけば上述の革命的な仕事はなし得なかっただろうと十分納得する。そういった人をトップに抱き、必死についていったアップルというアートとエンジニアリングが交差する企業に改めて感銘を受けた。
0投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人間的な、あまりにも人間的な」 読後、ニーチェの本のタイトルが浮かんだ。 余りにも自分に正直だった。 それは周りだけでなく、自分自身も削っていく人生だった。 しかしこの会社は何が出来るのか?何をするのか? ただ利益を出すという事ではなく、そこに向かって進んだ。 結果、オバマも言った様に彼の死を彼の創ったプロダクトで知るくらいの現象をもたらした。 自分も彼の創った作品でこのブログを書いている。 改めて、R.I.P.
0投稿日: 2011.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログⅡはここ約15年のジョブズの奇跡、そして病との戦いの中でのジョブズの姿が書かれています。 実際にみんなが使っている作品(Apple製品)が次々に出てくるので、今手元にある作品はこうやって誕生したのかと感動するしかありません。 そして、その作品作りへの情熱と仕事振りを読んでいると、正直日本の会社に絶望感を感じてしまいます。ソニーがダメだったのではなく、ジョブズやAppleが凄すぎた。そう思わざるを得ません。 この本は1企業の社長の伝記だが、経営学のような話を読んでいる感覚はまったくありません。それは彼がお金儲けをしたいのではなく、ただ凄い作品が作りたかっただけだからだろう。
0投稿日: 2011.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログアップル復帰後のジョブズの活躍が書かれています。上巻(Vol. I)を読まなくても十分楽しめました。最悪の状態のアップルに復帰したジョブズ。悩みながらも大胆な,そして時として野蛮な独自のやり方で,アップルを奇跡の復活に導きます。読み始めると途中でやめられなくて,ついつい夜更かしをして読みきりました。秋の夜長の読書におススメです。
0投稿日: 2011.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が普段働いている際に、どのように判断すべきか迷う時がある。けど、スティーブの考えを知れたことで、だいぶ判断に自信がもてるようになった。この本の影響はとても大きい。 本の内容は復活後かほんとに直近まで、想像した以上に、赤裸々な内容であり、ジョナサンアイヴの現在のアップルにおける影響力の強さも垣間見ることができる。 彼を中心に最高の製品を作り続けていれば、アップルという会社はこれからも輝き続けるだろう。ただ、最高のコンセプトをどのように導きだすかが、大きな課題だが。 一番印象に残ったのはTop100の焦点を絞るというくだりだ。 製品だけでなく、やるべきこともシンプルに絞り、深く追求する。 これこそ、スティーブジョブズが最も得意なところである。
0投稿日: 2011.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ感動した。名著だと感じた。途中まではよくできたルポという感じで、正直iConとの違いがそれほど感じられなかった。でも、ラストに向かうにつれてジョブス自身の言葉が増え、「彼の言葉をもっと聞きたい」という期待に応えてくれる。かれの功績だけでなく、人間としての彼を知ることができて満足。妻に送った手紙のところではついぼくも泣いてしまった。 製品だけでなく、生きざまを綴ったこの本自体も、多くの人に影響を与え、社会を変えていくんだろうな。
0投稿日: 2011.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログプロジェクトを成し遂げる中で、相当の抵抗があり、やり抜くにはかなり自分にも跳ね返ってくるものもあったと思うが、それを逆に飲み込んで高みに到達した人だと思う。何が危なくて、どちらに向かうべきなのか?の感度が違う人だと思うし、それは製品にも現れていると思う。
0投稿日: 2011.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログAppleの歴史は、ジョブズさんの歴史。 自身が去ったあとも生き残る会社。 引き継いだ人達は、Appleの歴史と自身の歴史と、シンクロするのか、交差をしていくのか? 魔法使いだと思う。 物語を聞くのは、胸踊る。 家族と、周りの人にとって、 魔法使いと一緒に生きていくって、どういう感じなのだろう? 少なくとも、こんな時、ジョブズさんなら、なんていうだろう?と、考えると、 「そんな事聞いてどうする?解らない奴がどうするって?!」 と、怒られるw どうにも、ジョブズさん側に回り込ませてもらえないw だから、魔法使いに、意見を求める想像は、辞めたw 現場にはいたくないがw、ベールを脱いだサプライズに、ワァー!と驚くことに何の躊躇もない。 もう少し一緒の時代に生きていて欲しかったな‥。 ところで。 ジョブズさんの日本の文化への好感は有名だが、そこに暮らす日本人のことをどう思っていたのだろう?
0投稿日: 2011.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ去年の1月にiPod touchを買って以来、すっかりアップル製品にとりかれてしまい、iPad、iMacなどアップル製品を次々と買ってしまった。 なぜ、アップルにこんなに惹きつけられたのかが今までよくわからなかったが、この本を読んでよく分かった。 アップルの製品にはスティーブジョブズのシンプルさの追求などの思想・哲学といったものを体現したもので、そうしたことを説明してくれている。 ごく最近の話なので話の順番などちぐはぐに感じられることがところどころみられたが、そういうわけで全体的に面白く読めた! 「自分も世界を変えるぞ!」と気持ちを大きくさせてくる本!
0投稿日: 2011.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログコンピューターに疎い人は少し読みづらいかもしれませんが、伝記としてだけでなく、経営書やビジネス書、小説としても、とにかく面白かったです。 この本は、著者の長い年月をかけた取材を通じ「クローズド」で、全てがまとまって一体となっているスティーブ・ジョブズらしい素晴らしい作品です。
0投稿日: 2011.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログアップルユーザーを四半世紀近く続けてきて、ただの一度もジョブズを尊敬したことはなかった。だけどその一方で、彼のことがとても大好きだった。 最初のMacを買った時にはジョブズはいなかったけど、彼の存在は感じられたし、いなくなった今でも、存在を感じる。 天才的なヴィジョナリーであり、稀代のペテン師である彼のことに少しでも興味がある人には必読の書だと思う。 それだけに、こういった形で出版した講談社にはがっかり。電子書籍をやる気がないわりに、紙の本にも愛情が足りないんじゃないだろうか。
0投稿日: 2011.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログアップルに復帰してからの成功が綴られている。一方で、病との戦いも克明に記されていて、段々切なくなる。強靭な精神力を持っていても、健康は別と言うこと。命と家族は大切にしなければいけない。
0投稿日: 2011.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本からいよいよAppleの快進撃が始まる。iPodの成功からiPadに至まですばらしい商品を世に送り出して行く。 だがジョブズの性格は常に変わらない。 だがデザイナーのアイブを筆頭とした優秀な部下によるサポートもありつつ、彼は自分の仕事をやり遂げて行く。 やはりほかと差別化できた1つの大きな要因がAppleのデザインへのこだわりだと再認識できた。 またジョブズ(いやApple全体か)の音楽への愛もよくわかる。自分たちの欲しいものを作るということがどれだけのモチーベーションになるのか教えてくれた。 ジョブズが妻に宛てた手紙や最後の言葉は是非読んでほしい。
0投稿日: 2011.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後の終わり方に鳥肌。やはり、自分がapple製品に触れた時代からワクワク感が止まらなかった。自分の人生の30%がappleで出来てる。とても良い時代に生まれたんだなと。
0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スティーブ・ジョブズは自分にとってキース・リチャーズやチャールズ・シミックやロベルト・バッジョやジャン=ポール・ゴルチェに近い存在なので、彼のプライベートな部分、とくに晩年の闘病期間が、あたたかく愛情に満ちたものであってほしいと思ってました。Apple製品のおかげで人生がゆたかに、楽しくなったことがいっぱいあったので、遠い存在なんだけど心の距離が近い—あくまで片想い的にだけど—ひとだから。 なので、家族やごく親しい(とジョブズが認めた)ひとたちとは、時間的にはそう多くはないけど、充実したときを過ごしていたようでほっとしました。いくらでもセレブな生活ができるのに、おもったよりずっとふつうの暮らしをしていたことにも安堵しました。自分が育ってきたように、子どもたちを育てたかったのかもしれません。 内容的には年季の入ったマカーにはおなじみの年代記ですが、本人や周辺のひとたちにちゃんと取材して、一方的にならないように、できるだけ客観的に書こうとしている著者の姿勢には好感がもてました。逆にいえば“カリスマ経営者”とか“神”みたいな部分(の、とくに謎解き)を期待して読むひとには肩透かしでしょう。元ヒッピーの反逆児がいかにしてテクノロジーの革命家になったかについて、本人の口からは語られていません。この本がビジネス書のコーナーに平積みしてあることになんの疑問や抵抗を感じないひとは、ぜひそれについて禅問答するべし。 ついでにいうと、個人的にはジョブズが“神”とか“カリスマ経営者”と呼ばれることに、ひと一倍抵抗があるんです。たしかにものすごく特別なひとで、彼が成し遂げたことは歴史をつくったわけだけど、それは彼が神でカリスマの持ち主だったからだけじゃなく、わたしたちが思ってる以上にずっとずっと“愛と努力”のひとだったからですよ。ジョブズを“神”に祭り上げることは、彼がたゆまず続けきた尋常でない努力とモノづくりに対する常軌を逸するほどの愛を否定することになるし、暗に凡人が努力することをも否定するようで嫌だ。相手は神なんだから、凡人が敵うわけないやん、みたいな・・・カリスマだって猛烈に努力するんだから、凡人がささやかな努力を惜しんでどうする(と己に云い聞かせる)。 まったくもってスティーブ・ジョブズは、いろんな意味でまともじゃないんだけど、誰かを愛するとき、彼が完璧だから好きになるわけじゃないよね。彼が彼だから惹かれる。困ったところも「あ〜あ〜、またやってるよ」なーんておもいつつ、まるごと受け入れるもの。実生活でジョブズを支えたひとたちも、またタダモノじゃない。ジョブズはジョブズだけなら、ジョブズになれなかったような気もします。 わかってはいても、病膏肓に入ってきたあたりは生々しい痛みが伝わってきて泣けてきました。でも、この伝記だけじゃなく、実妹モナ・シンプソンの弔辞や最後の日々に関するいくつかの報道がすこしは気持ちを晴らせてくれました。いつかモナがジョブズをモデルに小説を書いてくれたらいいのに、と思ってます。 ありがとう、スティーブ。 ■妹からスティーブ・ジョブスへの弔辞 A Sister’s Eulogy for Steve Jobs モナ・シンプソン (Mona Simpson) http://anond.hatelabo.jp/20111031223226 ■ジョブズ最後の日々(maclalala) http://maclalala2.wordpress.com/2011/10/08/ジョブズ最後の日々/ ■ジョブズ氏:すし屋で友人と「お別れ会」週3度も 今年夏(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/biz/it/news/20111024k0000e040039000c.html ■米アップルがスティーブ・ジョブズ氏追悼式典映像を公開中 http://rocketnews24.com/2011/10/24/145183/ http://events.apple.com.edgesuite.net/10oiuhfvojb23/event/index.html ■モナ・シンプソン公式サイト http://www.monasimpson.com/
0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブズI,II読了 IT業界にいて、ジョブズと直接仕事が出来なかったのは、残念だったと思う。 正直、ビル・ゲイツと一緒の仕事は「しょんべんちびりそう」だったけど、ジョブズとの仕事だったら、そんなの比でなく、もっとトラウマになる位だったんではないかなと。。。 ジョブズを超えていくのが、今生きる人々の使命ですな。
0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読んだ後悲しくなった。彼がこの世からいなくなってしまったことと何も出来ないでいる自分にと。何かを生み出すことは並大抵のことではない。生み出し続けた彼のように悔いのない一生を過ごしたいと思った。ありがとうスティーブ‼
0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功者として、洗練された製品の生みの親としての賞賛は スティーブジョブズのほんの一面のとらえたに過ぎない。 だれにでも欠点はあるが、こんなにひどい人間はなかなかいない。 だが、人々に求められ、世界を変えた事実。 魅力とカリスマ。 思いやりと協調性が「善」とされる現在に、冷や水をあびせる価値観。 何か目がさめる感じがする。
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半に比べると後半は急いでいる感じがする。iPod,iTune,iPhone,iPadが次々と登場し、そこに癌に侵されたジョブスが絡む。この10年の展開はよく知られるところであるが、その裏で、病魔に蝕まれている。心配はしていたし、どうなるかと思っていたが、この日がくるとは。しかし、この本には亡くなるところまで書かれていないが、明らかにその方向に向かっていて、また、そこが悲しみを誘う。このような生き方をするのは、今更むずかしいが、見習いたいところも多い。改めて、その業績を、その生き方がうらやまれる。
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みました、Jobsの伝記。いやぁ、面白かった。Ⅰで語られる何ともエネルギッシュでエキセントリックなJobsと、ⅡでAppleに戻ってきてからのiPod以降の成功をおさめていく姿との比較が面白い。ただ言えるのは、Ⅱの成功はⅠがないとなかったことと、周囲があきれるほどのビジョンに向かうエネルギーがJobsの魅力だったこと。こんな人がリーダーだったら自分はついていけるかな〜。一緒に夢が見られるなら、着いて行くかな〜。自分にこんなに夢中になれるのもはあるかな〜。いろいろ考えちゃいました。
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻では、パーソナルコンピュータ成立の過程を一連の歴史としてドラマティックに記述していたが、下巻では一転し、アップルへ復帰した後の数々の成功事例と、その裏で起きていたガンとの戦いとを中心に記述されている。 上巻から下巻まで一貫して述べられていることは、白と黒、最高に素晴らしいものかクソかに二分するジョブズの気質であり、極端なまでの完璧主義であり、また社会通念よりも自分の考えを優先する(しかもそれを直そうとしない)頑固な性格であり、それゆえの(大企業であるにも関わらず)非常に些細なことにも口を出すCEOの姿である。 これは一般的には非常に嫌なタイプの上司である。しかし、このような気質を持っていたからこそ、1000のことにNoを突き付け物事の本質を抽出できたのであり、全てを自分で管理するクローズド戦略を徹底できたのであり、クローズド戦略を堅持したからこそ瀕死の状態から1998年に起死回生のiMacを発表し(この時の衝撃は今でも鮮明に覚えている)、デジタルハブ構想を得てiTunes、iPod、iPhone、iPadへと続く一連のサクセスストーリを導き出せたのであろう。 下巻では特にアップルのクローズド戦略とマイクロソフトやグーグルのオープン戦略が対比されているが、両者はどちらか一方しか残らないのではなく、併存するものであるという合理的な論理が展開されている。 今後、iPhoneやiPadに関して、MacOS7の時のようにiOSが他社にライセンス提供されることがないように祈りたい。また、MacとPCの関係と同様、iPhoneとAndroid機がうまく併存してほしい。 最後に、このような異質な性格を本性とするジョブズであったにも関わらず、妻のローリーンがその一生を支えきったことはすばらしいと思う。 これまでジョブズに関する書籍は推測で書かれたものが多かったが、この本は上下巻とも事実に基づいており、記載内容も非常に深く、大変貴重であると思う
1投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ家族との話は涙腺にインパクトを与えるものがある。 オープンとクローズドも多様で良いのだと思う。 で、こうした企業が作る製品だからこそ好きなんだとも思う。 苛烈な人だったんだと再認識しつつ、 これだけの情熱を持って仕事に取り組むことの意義を感じ、でも少しだけ家族は大事にしなければ、とも。 『想い』だなぁ~。
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ購 口絵 ジョブズ家のファミリーアルバムから 第22章 再臨 野獣、ついに時機めぐり来る ●八方塞がり ●落ちたリンゴ ●クパチーノへにじり寄る 第23章 王政復古 今日の敗者も明日は勝者に転じるだろう ●舞台裏をさまよう ●アメリオ退場 ●社内改革 ●ボストンマックワールド(1997年8月) ●マイクロソフト協約 第24章 シンク・ディファレント iCEOのジョブズ ●クレージーな人たちがいる ●iCEO ●クローンの廃止 ●製品ラインの見直し 第25章 デザイン原理 ジョブズとアイブのスタジオ ●ジョニー・アイブ ●未来を創り出す工房 第26章iMAC hello(again) ●バック・トゥ・ザ・フューチャー ●発表(1998年5月6日) 第27章 CEO 経験を積んでもなおクレージー ●ティム・クック ●ハイネックとチームワーク ●プレゼンテーションの帝王 ●iCEOからCEOへ 第28章 デジタルハブ iTunes mからiPod ●点と点を結ぶ ●ファイアーワイヤー ●iTunes ●iPod ●「それだ」 ●クジラ白さ 第30章 iTunes ストア ハーメルンの笛吹き ●1曲99セント ●羊の群れを追い込む ●マイクロソフトの歯ぎしり ●ミスター・タンブリング・マン 第31章 ミュージックマン 人生のサウンドトラック ●ジョブズのiPodの中身 ●ボブ・ディラン ●ビートルズ ●ボノ ●ヨーヨー・マ 第32章 ピクサーの友人 ●『バグズライフ』 ●「スティーブ自身の映画」 ●絶好 ●決着 第33章 21世紀のマック アップルを際立たせる ●貝殻、角氷、ヒマワリ ●インテルはいってる ●報酬問題 第34章 第1ラウンド メメント・モリー死を忘れるなかれ ●がん ●スタンフォード大学卒業式 ●50歳の獅子 第35章 iPhone 三位一体の革命的製品 ●電話がかけられるiPod ●マルチタッチ ●ゴリラガラス ●すべてやり直し ●発表(2007年1月10日) 第36章 第2ラウンド がん再発 ●2008年の闘い ●緊急手術 ●死からの生還 第37章 iPad ポストPCの時代に向けて ●革命を起こしたいと君は言う ●発表(2010年1月27日) ●主張する広告 ●デジタル世界を根底から変えたアプリ ●出版と報道 第38章 新たな闘い 昔の仲間の余韻 ●グーグルーオープン対クローズド ●Flash 、アップルストア、コントロール ●アンテナガードーデザイン対エンジニアリング ●ヒア・カムズ・ザ・サン 第39章 無限の彼方へ さあ行くぞ クラウド、宇宙船、そのまた先へ ●iPad2 ●iCloud ●新キャンパス 第40章 第3ラウンド たそがれの死闘 ●家族の絆 ●オバマ大統領 ●三度目の病気療養休暇(2011年) ●ゲイツとの最後の対面 ●「その日が来てしまいました」 第41章 受け継がれてゆくもの 輝く創造の天空 ●ジョブズの功績 ●最後にもうひとつ ●コーダ
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ424ページの「最後にもう一つ……(原書p567 And One More Thing…)」に書かれたSteve Jobsの言葉はいいなぁ。 アップル製品が好きな人達には読んで貰いたい箇所だよ!
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ以下は最終章に掲載されているジョブズ氏の言葉です。 『文系と理系の交差点、人文科学と自然科学の交差点という話をポラロイド社のエドウィン・カンドがしているんだけど、この「交差点」が僕は好きだ。 魔法 のようなところがあるんだよね、 イノベーションを生み出す人ならたくさんいるし、それが僕の仕事人生を象徴するものでもない。 アップルが世間の人たちと心を通わせられるのは、僕らのイノベーションはその底に人文科学が脈打っているからだ。 すごいアーティストとすごいエンジニアはよく似ていると僕は思う。 どちらも自分を表現したいという強い想いがある。 たとえば初代マックを作った連中にも、詩人やミュージシャンとして活躍すてうる人がいた。 1970年代、そんな彼らが自分たちの創造性を表現する手段として選んだのが、コンピュータだったんだ。 レオナルド・ダ・ビンチやミケランジェロなどはすごいアーティストであると同時に科学にも優れていた。 ミケランジェロは彫刻のやり方だけでなく、石を切り出す方法にもとても詳しかったからね。 世間の人々は、僕らにお金を払って、いろいろなものを統合してらもっているんだ。みんな、そういうことを一日24時間、年中無休で考える暇はないからね。 すごい製品を作りたいと情熱に燃えていれば統合に走るしかない。 ハードウェアとソフトウェアとコンテンツ管理をまとめるしかいないんだ。 すべて自分でできるように、新しいところを拓きたいと考えるはずなんだ。 他社のハードウェアやソフトウェアに対してオープンな製品にしようと思えば、ビジョンの一部をあきらめなければならないからね。』
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕がmacを使い続けてから、まるまる14年間になるかな・・・。それはパソコンやネットの利用履歴とおなじ期間だ。この2冊にわたるスティーブ・ジョブズ伝記を読んで、自分がmacユーザであり続けていることを誇りに思えたし、納得もできた。ことに最後の一行がこの伝記のすべてを修飾しているように思えた。R.I.P. スティーブ・ジョブズ (Feb 24, 1955 - Oct 5, 2011)
0投稿日: 2011.11.06
