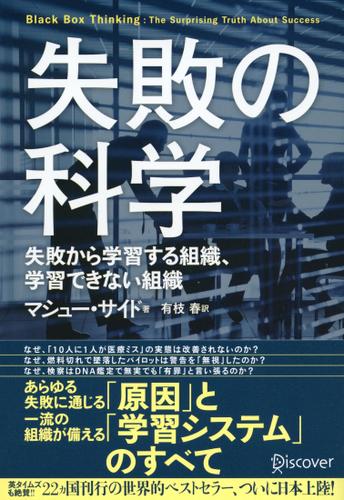
総合評価
(334件)| 185 | ||
| 93 | ||
| 34 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログつい隠してしまう失敗。 恥だと感じ記憶から消してしまうことが多いが、失敗にこそ成長するための要素が多く詰まっている事に気付かされた。 失敗はチャレンジしたことに対するフィードバックだ。 それを活かすマインドセットと環境作りがとても大切。 多くの紹介されている事例からそれを学びました。
1投稿日: 2026.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログAudible 失敗の本質は歴史書だったけど、こちらは現代社会における人間関係から解析している。聴きながら、自分の周りに溢れている事例だなぁ、と感じた。科学的に理由が分かっても人は変えられない
0投稿日: 2026.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ★学んだこと 実際に見たことより知ってることに記憶あわせる 講釈の誤り ★TODO 単純にすぐ誰かを非難するのをやめる 早計な非難をやめる 事前検死 マージナルゲイン
12投稿日: 2026.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は失敗にどう気づき、どう学ぶかが具体的事例とともに解説があるので非常に分かりやすかったです。 私は失敗を嫌うマインドがあるので、失敗を自己成長の糧として自然に受け入れるマインドに切りかえようと強く思いました。 個人としても組織としても成長の仕方がクリアになる良い本と思いますのでぜひ読んでみて下さい!
0投稿日: 2026.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国のビジネス書の割に読みやすくてよかった びっくりするくらい事例が載っててしかもそのどれもが恐ろしかった なぜミスした時に報告しにくいのか、認識がどうなってるのかが飲み込みやすかった ミスはするものだからのマインド大事
0投稿日: 2026.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログマシュー・サイド著の世界的ベストセラーで、航空業界のような「失敗から学ぶ組織(オープンループ)」と、医療業界のように失敗を隠蔽しがちな「学習できない組織(クローズドループ)」を比較し、なぜ組織や個人は失敗から学べないのか、どうすれば失敗を成長の糧にできるのかを、心理学と組織論を交え、具体的な事例(医療ミス、航空機事故、冤罪など)を通して解き明かす本です。成功する組織は、失敗を「恥」ではなく「貴重なデータ」と捉え、徹底的に分析・共有する仕組み(ブラックボックス思考)を持つと主張しています
7投稿日: 2026.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1章 失敗のマネジメント 第2章 人はウソを隠すのではなく信じ込む 第3章 「単純化の罠」から脱出せよ 第4章 難問はまず切り刻め 第5章 「犯人探し」バイアスとの闘い 第6章 究極の成果をもたらすマインドセット 終章 失敗と人類の進化 エピローグ 謝辞 注記
0投稿日: 2026.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説のように面白い。 認知的不協和…フェスティンガーが提唱した概念で、自分の信念と事実とが矛盾している状態、あるいはその矛盾によって生じる不快感やストレス状態を指す。社会的成功や努力した分だけ強くなる。 この概念を知れて良かった。 失敗を肯定的に捉えること。失敗を経験せずに成功するリスクについて考えさせられた。 失敗はたくさんした方が良い!
0投稿日: 2026.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織の失敗との向き合い方に思うところがあり購入。 認知的不協和と非難によるプレッシャーから人は失敗を隠すようになる。 蒸気機関は発明者も原理が分からず、後になって科学的根拠が誕生した。 → トップダウン式のプロセスから技術が生まれるわけではない。
0投稿日: 2025.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常にいろいろな気づきがあった。 特に業界ごとの失敗を改善する手法やリーンスタートアップなどの最近の手法に関する記述は自分の仕事でも活かせると思う
0投稿日: 2025.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ特定の業界についての失敗事例を小説形式で具体的に紹介した後、失敗へのアプローチについて一般化して記載されるため、読みやすく理解しやすかった。 失敗=判断ミスが命に関わる業界として、医療業界と航空業界があるが、失敗に対する考え方が大きく異なる。医療業界はクローズドループ(失敗や欠陥に関わる情報が放置や曲解され、進歩に繋がらない状態)であるが、航空業界はオープンループ(失敗に関わる情報を後日解析し、同じ失敗を繰り返さない)である。 航空業界は失敗を真摯に受け止める文化や体制が整っている(フライトレコーダー、航空システムでのリアルタイム監視、失敗を報告しても咎められない組織文化)のに対し、医療業界はそうではない所が起因している。 不都合な事実と解釈のすり替え(カルト信者が予言を外した教祖=失敗の再定義、裁判での冤罪=認知的不協和)が起こり、失敗を認めず信じ込み、その事に本人は気付かない。 イデオロギーが科学を殺す ひたすら試す(失敗する)ことでロジック無視のイノベーションを起こす 刑務所へのスケアードプログラム ランダム化比較実験、反事実が重要である 魔女狩り症候群 犯人探し、クビは問題解決しない 失敗はしてもいい、ではなく、欠かせないもの 究極の失敗型アプローチ 事前検死(あるプロジェクトが終わった後ではなく、実施前に失敗した状態を想定してなぜうまくいかなかったのかをチームで事前検証していく) 失敗するかもしれない、ではなく、失敗した状態から始めるのがポイント。
1投稿日: 2025.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ恥を捨てて失敗と向き合おうと感じました。 なんとなく失敗をするのは必要なことだよなぁ、くらいの認識で本書を読んでみました。 読んでみると、如何に人は失敗と向き合うのが苦手なのか、そしてなぜ失敗に向き合わないことで成長機会の損失に繋がるのかを理解できました。なお、科学的な検証が大切と本文でも述べられているくらいなので、ある程度関連研究によるエビデンスにも触れながら論理が展開されていました。 また、成長型マインドセット(人は努力で能力を習得できるというマインドセット)の人の方が失敗を受け入れやすいというのは、興味深かったです。個人的には運命論者なのでモノによっては才能がなくて成長できないこともあるでしょ、くらいに思っていたのですが、場面によっては成長マインドセットを自己洗脳してでも持った方が効果的なのかな、と感じました(一方で努力が報われなかった時に、才能という逃げ道を用意しておくのもメンタルヘルスケアとしては大事と思っています。バランスが難しい)。
0投稿日: 2025.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗とは成長とよりうまくやり直すためのチャンス ①犠牲を払って得た失敗は次の世代に伝えること。伝えないことは人道的に許されない ・進化とは失敗による淘汰の繰り返し ・質を高めるには量を行って改善を繰り返すこと ・失敗はより賢くやり直すためのチャンスに過ぎない(フォード) ・誤りは災厄ではなく好機 ・失敗、間違いなしに成長はできない。成長とは失敗や間違いから学ぶこと ・仮説が正しいか検証するにはあえて間違えること EX.2、4、6がどんなルールで並んでいるか検証するには、8、10、12と答えるより、7、8、9と回答してみる方が早い(偶数昇順ではなく、単なる昇順かもしれない) ②自分の信じているものと異なる事実を突きつけられると事実の解釈を変え、自分を正当化してしまう ・失うものが大きい人ほど、失敗から学ぶのではなく、事実を捻じ曲げて自分を正当化し誤りを認めない ③避難しても改善はせず、ミスを隠したり、自己防衛に走ったりするだけ ・失敗の責任を少人数に負わせることは失敗したら非難する、問題を起こしたらスケープゴートにするというメッセージと同じ。原因を明らかにして対策をとることが必要 責任をとらせる規律に厳しいリーダーは上の受けは良いが失敗をオープンにできず失敗から学ぶことを妨げる ④RCT ランダム化比較試験 ランダムにグループ分けして片方に介入、片方に介入せず結果の比較を行い、何が成果につながったか、何が成果につながったか、どちらが良いか明らかにする
0投稿日: 2025.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログまず興味深い事例がたくさんあり、読み物として面白い。かつ、組織運営する立場からすると、組織学習(フィードバック)をいかにデザインするか、多くのヒントと示唆に富んでおり、実務にも活かすことができる良書。おすすめです。
0投稿日: 2025.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗=悪、起きてはいけないこと、捉えるのではなく、改善への貴重なデータや情報収集の機会と捉えられるかどうか。医療界、航空界の対比がわかりやすく面白い。組織全体を変えるにはまずトップ層、リーダー層が失敗に対して個人責任のなすりつけあいや非難から入るのではなく、組織としての課題解決にまず目を向けるという、意識と行動が何より大切とわかった。
0投稿日: 2025.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログめちゃくちゃ勉強になりました。 ■ ポイント - 失敗を許容し、失敗経験を前向きに捉えてデータとして分析して次に活かす文化がない環境だと、認知的不協和、外的非難などにより失敗が隠される→クローズドループにより失敗が認識されない状況となる、すなわち失敗の再発防止がなされない=失敗確率が減らない - メソッド - マージナルゲイン→分割した小さい成功の積み重ね - リーンスタートアップ→アジャイル - RCT(ランダム化比較試験)→反事実取得 - 事前検死→実施前失敗シミュレーション ■ アクション - 失敗を認め、データとして分析、そこから学ぶ - そういった環境づくりをする、それがないと認知的不協和や外的非難によるクローズド・ループの温床となる - 行動してガンガン失敗しろ、そこから学べ - 失敗できるようアクションしろ、アウトプットしろ→アジャイル - 自分は神ではない、間違うこともあると信じる - 公明正大でいく - RCTで反事実データも取得する - 失敗指摘を愛す
0投稿日: 2025.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗はしていいんだと再確認。 ただしその失敗を組織内で共有しやすくして、改善していく仕組みが必要。 本書自体は若干冗長で飽きてくる。
3投稿日: 2025.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログわりと当たり前の事を様々な事例を交えて伝えているが、結論より事例のボリュームが多くて、若干読み飽きてしまった。 哲学者カール・ポパーの「真の無知とは、知識の欠如ではない。学習の拒絶である」という言葉が印象的だった。 失敗から学び、挑戦し続ける姿勢をいつも忘れないようにしたい。
0投稿日: 2025.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
とにかく面白いのでどんどん読める感じ。 失敗を恐れる、失敗を恥じる、社会に属する人間の心理。これにより失敗を隠してしまい改善のチャンスを逸してしまう。クローズドループ。もし、無人島に1人だったら人は何度も失敗してサバイバルするだろうに、と思った。それをうまく実践できているのが航空業界。 洗剤メーカーのノズル形状の改善の話では、流体や数学の専門家による改善案ではうまくいかず、生物学者らによる考えうる形状を多数試して、その中で一番良い結果が得られた形状をベースにさらに様々な改善を施した形状で試して、を繰り返して、最終的に改善に至る。まさに生物の自然淘汰である。採用されなかった形状は全て失敗である。要はたくさん失敗することで成功に辿り着く例である。宇宙もマルチバースなのではと思ってしまう。 その他にも、マージナル・ゲイン、リーン・スタートアップ、RCT、事前検死、など失敗から学ぶいろいろな手法があることを知れた。 著者は外国人であるが、なぜか日本の話が出てくる。
16投稿日: 2025.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ『失敗の科学』というタイトルですがビジネス書です。しかも、結構ありきたりな。原題は『Black Box Thinking: The Surprising Truth About Success』(後半を適当に訳すと『成功に関する驚くべき真実』…まぁ、ビジネス書ですね。勝手な日本語タイトル、つけないで欲しいなぁ。このレーベルの本、もう買わないかも。) 始めの章の医療事故と航空業界のベテランパイロットの出会いはエモーショナルなエピソードでしたが、それ以降は、よくある…というか、すでに周回遅れの陳腐化された教訓ばかりだったかなと思います。次読むべきは『測りすぎ』かも。 ※ …嘘です。『測りすぎ』読んでません(笑)。 息子が飛行機ファンなので航空業界の事例がたくさん載っていたのは楽しかったです。(しかし本書でベタ褒めされてる航空業界、今、システムの老朽化で問題続出なのだとか。Windows95とフロッピーディスクを使ってあることもあると『AIRLINE』12月号に書いてありました。どうしてこうなった…) でも、アメリカの医療と司法はヤバいですね。今回一番の学びは「ちゃんとフィードバッグループをまわせてる業界に身を置くように気をつよう!」だと思いました。自分はそこまで凝り固まった業界に属してなくてよかったなぁ、と思いました。その分、本書で書かれていることが「なんか当たり前なことをやたら仰々しく言ってる」と感じたのかもしれません。 「なぜ失敗を活かせる組織・業界と、そうでない組織・業界があるのか。失敗を活かせない業界はなぜ失敗を活かせないのか」あたりを深掘りして欲しかった(が、すでにそういう議論も私の知らないところで周回遅れになっていそう。)
6投稿日: 2025.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ“失敗は防ぐものではなく、活かすもの”という視点を徹底的に突きつけてくる一冊。成功企業ほど、失敗を隠さず共有し、学習し、改善する「オープンな仕組み」を持つ。ベンチャーを経営する中で、失敗を個人の責任にせず“学習の材料”として扱う文化づくりこそ、組織の成長速度を決定づけると痛感した。失敗にどう向き合うかが、未来の成果を左右する。
1投稿日: 2025.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ大切だと思ったこと ・質より量 用意周到に準備して臨むよりも、試行錯誤を繰り返しながら成功に近づく。最初の一歩をいかに早く実行に移せるか。 ・成長型マインド 失敗は欠かせないもの。学習のチャンスと捉え多面的に分析する人こそ成長していくということ。 ・データで分析 検証する時にイメージと感覚だけで行うと人間は都合のいいように作り替えてしまう。航空業界のブラックボックスのように動かし用のないデータで検証することでより信憑性の高い振り返りとなる。データがない場合は意図的にデータを取り入れる仕組みを作れ。 ・失敗を受け入れる風土作りが全て 懲罰ではミスの報告が減っただけで実際のミスは減らない。組織全体が失敗をウェルカムに失敗から学ぼうとするチームは必ず成長する。そのためには処遇を決める人への信頼が大切。 考えたこと かといってなんでもかんでも失敗していいわけではない。「失敗しました~」と軽く報告するヌルイ組織であってはいけない。 あくまで、前に進むために挑戦し考え創意工夫を凝らし、個人やチームが前に進むためにやろうとした行為に対しての話しかと思う。その辺りの線引きが難しい。
1投稿日: 2025.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗は成功のもと」が丁寧に解説されている。 実際の航空事故、医療事故などが臨場感たっぷりに描かれていて引き込まれるし考えさせられる。 ・進化・成功のカギは「失敗とどう向き合うか」 ・チームワークが機能すれば、緊急事態でも部下は意見を言いやすい。 ・フィードバックが無ければ何年訓練や経験を積んでも向上しない。 ・失敗に対してオープンで正直な文化があれば、組織全体が失敗から学べる。 ・失敗から学ぶには、システム(失敗を最大限に活かすシステム)、スタッフ(躊躇なく情報提供できる)の2要素が不可欠。 ・フィードバックを重視し新たな状況への適応を続ける姿勢が進歩や進化をもたらす。 ・認知的不協和=自分の信念と事実が矛盾している状態、或いはその矛盾によって生じる不快感やストレス。解決方法は自分の間違いを認めるか、否定。否定は簡単で認めるのは難しい。自分が認知的不協和に陥っていることには気づきにくい。 ・累積淘汰=選択・淘汰の繰り返しの結果。試行錯誤を経ないシステムは弾力を失う。だから計画経済は機能しなかった。 ・反事実=もし〜をしなかったら起きたかもしれないこと(結婚しなかったら、等)。反事実は目に見えないが、ランダム化比較試験(RCT。小さい要素に分けて比較する)で検証可能。 ・マージナルゲイン(小さな改善)を積み重ねると大きな進化になる。大きなゴールを小さく分解して一つ一つの改善を積み重ねる。 ・失敗から学べる人と学べない人の違いは失敗の受け止め方の違い。失敗を自分の成長に必要として受け止めるか、才能がないからと捉えるか。 ・最も早く進化を遂げる方法は、失敗に真正面から向き合い、そこから学ぶこと。
2投稿日: 2025.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ恐れず驕らず侮らず。常に慢心せず真摯に物事を観察し、勇気を持って行動する。 そんな人でありたいし、あり続けたい。
1投稿日: 2025.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は賞賛に値する! 互いの挑戦を称え合おう! 失敗せずに成功は手に入らない。 (安藤努先生) 日本大学図書館生産工学部分館OPAC https://citlib.nihon-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=1000253364&opkey=B176282653091240&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=0
1投稿日: 2025.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ1.失敗の捉え方 恥ずかしいことだめなこと悪いことだと思わない。 失敗から学ぶ。 失敗に向きあう。 失敗を恐れない。 失敗した人を批判しない。 2.単純化の罠 やらない場合、どうなっていたのか。 そもそも対象者が合っていたのか。 長い目で見たときに良かったのか。 後で振り返るデータを残したり振り返られるようにする。 臨床心理士が治療の内容が良かったのかは、患者のその後の経過を知る術がなかったことが原因で、治療の良し悪しを判断することができなかった。 3.犯人を探す 犯人を探して 懲らしめて 満足しても 失敗したことから目を背けていては失敗の経験が生かされない。 4.マインドセット 失敗の上に成功が成り立っている。 いくら才能があったとしても、努力をしなければ成功しない。 いくら才能があったとしても、失敗を恐れて、何もしなければ成功しない。 ベッカムのフリーキック、50,000本 ジョーダンのフリースローのミスの多さ。 彼らは失敗を成功に向けたトライアルにした。 失敗をただただ重ねるのではなく、改善を小さく小さく行ってきた。 Word1 RCTランダム比較テスト Word2 固定型マインド 成長型マインド
1投稿日: 2025.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗を前向きに捉え、失敗から学ぶことの重要性を論理立てて腹落ちさせてくれる。多くの人にとって失敗はネガティブなもので無意識のうち避けてしまうものだと思う。側から見れば明らかな失敗でも認知的不協和のために受け入れられないのも人間の性質かもしれない。しかし失敗を直視し、そこから学ばなければ進化は無い。本書で印象的だったのは失敗から学ぶカルチャーがある航空業界と反対に失敗を隠蔽し直視しない性質がある医療業界。どちらも人命に関わる重大な業界である点は共通しているが、失敗に対する姿勢が異なる。もちろん失敗を受け止め、改善する姿勢の航空業界の方が進歩を続けてきた歴史がある。個人としても失敗を恐れず、むしろ早めに挑戦と失敗を経験しようと思えた。
1投稿日: 2025.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ沢山の事例と共に失敗から学ぶことの大切さを理解させられた本だった。 最後に失敗を想定し、失敗ありきで設計することの大切さが書かれている。 まさにこの本が沢山の失敗の事例を並べ、そこから学びを得るという構成になっている。 失敗と向き合うことは時に難しいし大変だ。 失敗を公にすれば、人に非難され、自分の評価がさがるかもしれない。 大きな失敗になればなるほど人には言いにくい。 しかし、失敗と向き合わないと成長はない。失敗を前向きに捉える個人になり、組織もそのように変えていくことが大事なのだと感じた。
8投稿日: 2025.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗から学ぶことの重要性、いかにして失敗を活かせる組織に変えていくかを述べた、得るところの多い本。 失敗から学習することができた業界として航空業界が、学習できない組織として、医療業界や警察、検察が例示されているのも、すごく説得力がある。 "人は誰でも、自分の失敗を認めるのは難しい。•••特に、何かミスをして自尊心や職業意識が脅かされると、我々はつい頑なになる。" そして、"人は失敗を隠す。他人から自分を守るばかりでなく、自分自身からも守るために、失敗を記憶から消し去る"こともしているらしい。 だからこそ、検証すること、立場や組織の上下関係に関わらず、リスクを指摘し、打開策を相談し合える環境、そして上に立つ人ほどその指摘を受け入れられるマインドになることが重要。 失敗から学ぶことは最も「費用対効果」がよい。何か大きなプロジェクトを始めるときには、全てを「失敗ありき」で設計し、パイロット•スキームで検証する、ということを取り入れていきたい。 また、常に"誰でも、いつからでも能力は伸ばすことができる"と信じる「成長型マインドセット」でいることも重要。 日本は起業家が少ないと言われるが、それを打破するためには、子供や若手に成長型マインドセットの思考を植え付けていくことも大事だと思う。
26投稿日: 2025.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1982024120964690282?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
1投稿日: 2025.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ引きずり込まれるように一気に読んだ。 人は緊急時には、たとえその道に熟練していても、平時には考えられないようなミスをすることがある。一種の心理的なバイアスがかかるから。 ところがその道に熟練している人であればあるほど、そして権威になればなるほど、そうしたミスを認めようとしない。本人は本当に「ミスの原因はほかにあるのだ」と信じ切っているのだ。これも一種の認知のバイアス。 また正しいと思われていることでも、対照実験を行うと実は正しくなかったとか、効果がなかったというケースも実に多い。 だから失敗は重要な学びの機会なのだ。失敗を深く分析することによって人は進歩できる。 個人レヴェルでも組織や業界の風土としても、失敗に対してオープンな成長型マインドセットなのか、失敗に蓋をしてしまう固定型マインドセットなのかによって、結果は大きく違ってくる。 「失敗を科学する」-座右の銘にしたい。
8投稿日: 2025.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗することは恥ずかしいと思いがちだが、失敗なくして進歩はないと筆者は訴えている。本書の中でも言及があったが、日本では失敗は不名誉なものと見なされる傾向があり、そのため日本には起業家が少ないというデータが出ている。イノベーションなくして経済発展はないのであるから、日本人は失敗=不名誉という考え方を改めるべきであると思う。
1投稿日: 2025.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1章 医療事故と 航空機事故を比べている。 医療のほうは失敗に対するフィードバッグが少ない傾向にり、失敗の教訓から再発防止につながらない側面がある。 航空機事故は事故原因を究明し、対策が取られ、全パイロットがその情報にアクセスできるようになっている。またそれらを研修などで習得するシステムが出来上がっている のちのフィードバッグがない状況では、成長が鈍化する。検査技師は目の前の判断が時間を経てどんな結果につながったのかを確認する手段が少ない。医師は事故があっても「まれにあること」として原因究明につながらないことがある。また、「検死」の実施が少ない。検視はっ状況把握や、死の原因を探ることができる貴重な機会で情報の宝庫だ。しかしなされていない。 医療事故に対する医師の対応の差が書かれていた。 事故正当化をする医師は・・・?ここ内容忘れた 事故を認めた医師は、所属する病院全体の意識がかわり、事故対応や情報共有が進んだ。今全米で安心できる?病院の上位ランクにいるらしい。(手術中に造影剤と消毒液を間違って注入し、女性が片足切断、のちに12日ぐらいだったか?死亡する事故が起こっている。要因の一つに2種類の自販機が同じ色?形?の注射器に入っていたからだとされていた。◆なかなか衝撃的だ。改革の中で、ミスは自分で申告、ミスを見つけたら伝え合うことで、原因の共有対策が進んできた。はじめミスした人は叱責されるのでは?と不安に思っていたが、聞いた人より、そんな可能性があるのか、教えてくれてありがとうとプラスのフィードバックがあり、お互いにミスを報告しやすい環境になっていった。) 過集中では時間間隔がゆっくりになる。 航空機事故を起こしたパイロットは、危機対応中、副操縦士の燃料不足について申告があるも。時間はまだそんなに立っていないと無意識的に誤認し、時間を見誤っていた。予想より早く燃料が不足し・・・ 医療事故では、看護師は器官切開の準備をして声をかけたが、医師らは自分のできることに固執し、無視した。器官切開時点で危険な時間に入っており、医師の時間間隔が伸び、体感が長くなっていた。 礼儀正しさ、年上を尊重する気持ちが失懸念点を強く指摘できないことにつながる。 気管支切開を準備した看護師は、今処置しているベテラン医師はじぶにょり優れており、今話しかけると、集中を途切れさせると思い、強くいうのを中所した。 状況が切迫してきた航空機ピッtpでは副操縦士がパイロットに懸念をしっかり伝えられずにいた(◆ここの副操縦士の心境について覚えていない。後で確認して書こう) 2章 努力は事実を誤認させる 間違えを正当化する人は自分の考えに固執し、自分都合の言い訳を並べる。失敗を認めることは過去の自分を批判することにつながり、恐怖感を抱かせる。逃避行動として自己弁護に走る。 教祖の世界崩壊説を信じた信者の観察が載っている。 世界崩壊日に実際何も起きず、信者は何もなかったという事実を、リフレーミングし、自分都合の内容に思い直した。預言は正しく、世界崩壊を信じていた人々がいたので、神はお目こぼしで世界崩壊を阻止した。我々がいたから世界は救われた。世界崩壊は起こらなかったが、わたしたち崩壊を阻止し新しい世界が始まったの。今から素晴らしくなると主張している。(◆生存者バイアスでその当時はおかしかったが、今から見ると正しいかったとされることが多くある。過ちが正当化され、多くの人がそれに無関心か信仰を持つようになると一般化されることにつながる。・・・この感想自分で書いてるけど、世界崩壊が何度も出てきてゲシュタルト崩壊w) 読みたいこと 失敗とは、ある目的や目標を達成できなかった、期待した結果を得られることができなかったこと。そもそも、目的や目標を自分の中で把握していなければ起こらない事態だ。 だが失敗とは認識できない過ちがある。 今の失敗を見返して、あぁあの時も間違っていたんだと気が付くあれだ。 法律では知らなかったでは済まされず、自分に過失があれば裁かれる。 だが明文化されていない、自分でも気が付いていない思い込み、マイルールを大きく否定、破壊されたらどうなるのだろうか?もちろん否定し、考えを停止する。 その後人はどう行動しどうとらえていくのか・・・そんな答えがこの本にあるのかなぁ? 長い。事例が重い! ニアミスからので生還パイロットの話が泣ける(´;ω;`)ウッ…
2投稿日: 2025.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく面白かったしマインドセットのメリットをたくさん教えてもらった。人生のバイブルとして折々読み返したい。「失敗は成功のもと」「非難の前に状況を考える」当たり前のことしかないけど、その当たり前をできない人間が大半で、だからこそ常に心に留めておきたい。
1投稿日: 2025.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ掛け値なしに面白く、学びの多い一冊でした。 原題は「Black Box Thinking」というもので、「失敗」から学ぶことの大切さが、様々な興味深いエピソードから示されます。 あっ!という面白い気づきがあったのは、米軍の爆撃機について、装甲をどの部分に装着するのが良いのか、というエピソード。 軍司令部は、「無事に帰還した」爆撃機の損傷具合の検証データを元に、砲撃を受けていないコックピットと尾翼以外の、たくさん穴が開いていた部分に装甲を施せばいい、と判断します。 ところが、ある人物が、「帰還しなかった」爆撃機のデータを考慮していないことを理由に、その案に反対します。 すなわち、帰還した爆撃機のコックピットと尾翼に穴がなかったのは、「そこを撃たれたら帰還できなかった」という事実を示しており、逆に帰還した爆撃機の穴は、「そこなら撃たれても耐えられる」ということを示す検証データだったのです。 著者はこのエピソードを踏まえ、「失敗から学ぶためには、目の前に見えていないものも含めた全てのデータを考慮しなければならない」と言うのですが、これは本当に盲点でした。 旧共産主義圏での計画経済の破綻については、企業は補助金などで倒産の危険から守られている、つまり「誰も失敗しない」システムであったため、失敗による試行錯誤が出来ずに進化の機会を失ったゆえの帰結だと指摘します。 この点が、倒産による市場からの撤退という「失敗」があり得る自由市場との違いです。 自由市場は、倒産という進化のプロセスに必要な失敗を、そのシステムに組み込んでいるからこそ進化でき、今もなお継続しているのです。 こういったエピソードに加え、人は失敗した時に自分の過ちを認めずに事実の解釈を変えてしまったり、かえって自己を正当化してしまうこと、小さな改善(マージナル・ゲイン)こそが大きなゴールにつながることなどが示されています。 あと、「あるある」と頷いたのは、何か事故や事件があった際、それが様々な要因が絡み合ったものであるにも関わらず、脊髄反射的に出来事を単純化し、「誰の責任か」を追及することに躍起になったり、「魔女狩り」に陥ってしまうこと。 誰かのせいにして非難するだけでは、決して問題の解決にはつながらないのです。 自分自身もよく失敗を犯しますし、組織として時に失敗することもあります。 失敗から学ぶためには、ある意味では失敗に寛容になり、失敗についてのあらゆる情報を出し惜しむことなく、原因追求に向けフィードバックをきちんと行うことが大事です。 失敗から学ぶことは、進化のために必須なのです。
1投稿日: 2025.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはとても素晴らしい内容だった。 もっと早く知っていればと思った。 義務教育で失敗学として学べば世の中が優しくなると思わされるほど、少しずつ勇気が湧く内容だ。 第1章 航空業界はオープンで、失敗から学んでシステムを改善しているので、高い成果を上げている 医療業界はクローズドで、全く失敗から学んでいないし、学ぼうとする姿勢がない ヒューマンエラーの多くは設計が不十分なシステムによって引き起こされる フィードバックは道を示す「明かり」 整理された読みやすい報告書大事 第2章 認知的不協和 冤罪はこれのせいでなかなか解決しない エリートほど厳しい加入儀礼を通過しているため、失敗が認められず、自己正当化や保身の衝動に走ってしまう 認知的不協和が何より恐ろしいのは、自分が認知的不協和に陥っていることに滅多に気づけない点にある。 認知的不協和は「外発的な動機づけ(評価や賞罰などの外部要因)」によって起こると誤解されがちだ。しかし、これだけでは認知的不協和の影響を説明しきれていない。問題は「内発的な動機づけ(バイアスなどの内部要因)」にもある。むしろ内発的な方が影響が強い わざと間違える、失敗することが確証バイアスから抜け出せる 記憶は「編集」可能 第3章 試行錯誤がテクノロジーや発明やイノベーションを生み、それがのちに論理化・体系化されていく リーン・スタートアップなど失敗型の開発が結果的にはコスパが良い スティーブ・ジョブズでもフィードバックは必要だった ランダム化比較試験という特に重要な検証法 「反事実」は目に見えない RCTは「全体」を見ないといけない、長期的・包括的に 第4章 マージナル・ゲイン(小さな改善) 問題が大きいとRCTは機能しないので、問題を小さく分解する ホットドッグ早食いの小林尊もマージナル・ゲインのアプローチを行っていた 第5章 処遇を判断する立場の人間を、スタッフは信頼しているか? 「プロジェクトの6段階 1. 期待 2. 幻滅 3. パニック 4. 犯人探し 5. 無実の人を処罰 6. 無関係な人を報奨」 我々が非難の衝動と決別するためには、相当な努力と覚悟が必要 失敗からの学習が非難という外圧によって妨げられる 第6章 プロセスに失敗が欠かせないと強く認識する人に成功者は多い 失敗から学ばない傾向を克服する方法 失敗の受け止め方の違い(マインドセット) 成長型マインドセットの人は、失敗を自分の力を伸ばす上で欠かせないものとしてごく自然に受け止める 固定型マインドセットの人は、失敗を「自分に才能がない証拠」として受け止める グリット(GRIT)(やり抜く力)・スコアが良い指針 成長型マインドセットは「合理的」にあきらめる 失敗に対する恐怖心が日本人は高い 終章 究極の失敗型アプローチ「事前検死」 まずチームのリーダー(プロジェクトの責任者とは別の人物)は、メンバー全員に「プロジェクトが大失敗しました」と告げる。メンバーは次の数分間で、失敗の理由をできるだけ書き出さなければならない。その後、プロジェクトの責任者から順に、理由をひとつずつ発表していく。それを理由がなくなるまで行う。
2投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗に向き合って学べというシンプルなメッセージだが、丁寧な事例の説明によりとても分かりやすい。暗闇の中でのゴルフ練習という言い方が印象に残る。
2投稿日: 2025.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ事故やミスが起きたあとの処理の仕方や、今後への活かし方が、医療業界と航空業界では真逆であること。 トップダウン型がいいのか、ボトムアップ型がいいのか。 ただどこの業界でも、権力者や重鎮がみっともなく権力にすがるのはどうにかならないものか。
167投稿日: 2025.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗することの大切さを、具体的な事例とともにわかりやすく教えてもらえる良本です。 何度も読み返したい本です。 それでも間違えることが怖くて躊躇してしまったり、失敗したことを恥ずかしくて隠してしまう自分がいます。 なので、何度でもこの本を読み返し、失敗を恐れず、自分の成長のためにどんどん失敗して改善できる人になります!
6投稿日: 2025.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本に限らず失敗学の本は読んでみると、直接関係なくてもためになることが散りばめられている。 失敗学に触れてみるのオススメ。
1投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログミスを隠す傾向がある医療業界とミスを共有する風土がある航空業界が、結果としてこうも違ってくるのかと序盤から惹きつけられる内容だった。 個人としてももちろん、上に立つ立場の人には是非読んで欲しいと思った。 「失敗は成功の元」という言葉があっても、やはり失敗したくないと思うのが人間。でもこの本で失敗から学べることの多さや重要性を多くの具体的な事例から知ることができ、考えさせられることがたくさんあった。失敗を臆することなく、挑戦し続けるマインドが社会全体に広がれば、世界はもっと変わるだろうなと思わされた一冊。
1投稿日: 2025.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗の原因は、失敗を失敗と認めない思考回路、「クローズド・ループ」にある、とする。これにはまり込むと、「失敗から学ぶ」というフィードバックが止まってしまう。 誤審を認めない検察、医療過誤を認めない医療施設、犯罪者の更正プログラムが機能していると疑わない行政など例が続く。 逆に失敗を共有し再発防止に役立てる、「オープン・ループ」が機能すると目覚ましい成果が上がる。好例が航空業界、とする。 人は失敗から学ぶ姿勢がある人とそうでない人に分かれ、会社も成長型企業と固定型企業に分かれる。 ではどうする?という次の思考につながる、ヒントになる一冊。好著。
1投稿日: 2025.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は成功(結果)ばかりに目が行きがちだが、失敗にこそ目を向けるべきだ。寧ろ失敗からしか学べないし、成長するには失敗が欠かせない。
1投稿日: 2025.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗に対してはネガティブな気持ちがどうしても湧いてくるものであるが、健全で前向きな姿勢を保つことが失敗から学ぶことの本質のように思える。 バイアスからは誰も逃れることができない。一度、事象を経験すること、他者からの気付き(観察)、情報共有などによって事前にある程度対策を行うことができるが、初めてのケースについては、自分達が現場で判断しなければならない。その際は何を基準に正しいと思える行動をとることが可能になるだろうか。判断力の軸を作るには、様々な失敗事例を知っておくことが最短なのかもしれない。 本書は物語調で話が展開されていくため、一冊の読み物として興味深い内容である。客観的に見ればそれはおかしい、と気付けるものもある。 だが、主観的、言い換えればそのケースの当事者であるなら、加えてその業界の経験を多く積んできたベテランであるなら、自身の経験を優先して視野が狭くなってしまうこともあるのだろうと思う。 失敗を恐れるなとまでは言い切れないが、失敗からの学びは時に成功より勝るという考えを抱くに至った学びの多い一冊である。
12投稿日: 2025.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログミスは必ず起こる。ミスをした人を抜歯。完全に統制しておけば、物事は完璧に進むのだろうか? 本書は、そうではないと言う事の実例と失敗が起こったときに、人は何を感じるのか、またそれを避けるためには、どのようなマインドセット考え方を持たなければならないのか。読んでみれば当たり前のことではあるが、考え方を変えることの難しさは自覚しておく必要があるだろう
2投稿日: 2025.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語として語られるので、すごく面白かった。常に認知的不協和のバイアスがかかって無いか考えなきゃと思うものの、なかなかね
2投稿日: 2025.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
まあ、読み物的には面白かったと思います。 航空業界が徹底的に失敗をあぶりだし、機内デザインからオペレーションから要員配置など多くの日常業務を「失敗」から得られる教訓をもとに洗練化している、と。 それに対し、医療機関はミスを偶然と見做し、その間違いを分析せず、むしろ分析や調査結果を信じず、自分の考え(まさに信念?)に固執するという。 医療機関の旧態依然たる状況に背筋が冷えるとともに、英国自転車チームの「マージナル・ゲイン」の考えなど、勇気づけられるお話もありました。 またある事象とその結果との因果についてRCTという手法を使い、政策やアクションの効果の有無を確認し、「そうなると思う」をデータで検証(データで否定・肯定する)方法などは興味深かったと思います。 ・・・ では、この本を読んですぐに現実に応用できるかというと、それはちょっと難しいと感じます。 ・・・ 私のやっている仕事は数字をまとめるような仕事なのですが、DBからデータをダウンロード、エクセルを駆使してピボットテーブルを作る、マクロで集計をする、最後に報告用フォーマットにコピペするなど、兎に角マニュアル作業が多い(マクロを組んで大分楽になりましたが)。 私もかつてシコタマ間違いをしまくって、自分で作ったミスを発見するのに数時間かかるのが良く続いたものです。 いま部下が同じ状況ですが、やはり失敗に対して自己認知が出来ないと、失敗を生かすことはできないよなあ、と感じています。 彼女は、自分が作った成果物にも関わらず「これ、数字が合いません」とか平気で言います。「何故ですか? どうやって作ったのですか? 調べてください。手順を一つずつ追ってください」などと突き返し、時にミスは見つかるし、時に見つからない。 その間違いについて毎回ここがこうだああだと一応指摘してるのですが、一向に改善しません。むしろ彼女をうまく引き上げられない私がおかしい、と思われている節もあります。ただ、自己認知を促すべく禅問答みたいに質問に質問で返すことが多いのですがこれが悪いのかもしれません笑 かつて私が一人で業務をこなしていた時は「あー、こんなクソみたいな仕事で、しかも自分の仕出かしたミスで午前一時まで仕事するなんて耐えられない!」と切れたときから自分のミスを直したい、と強く感じ始め、どういうミスがどういうタイミングで起こるのか、自分に興味が出てきました。またこうやって省察できるとプロセスの余分な部分や時間がかかっている部分についても良く見えるようになったのですがねえ。 ・・・ で話は戻りますが、本書。 失敗に取り組むにはまさに組織的にやらないと難しいでしょうね。ミスを取り仕切るような人材が必要でしょうが、ただミスを指摘するだけの部署を作ってもどうしようもないでしょうし、所謂「(失敗を尊ぶ)カルチャー」の醸成も必要でしょう。でまたこれが難しい。 RCTについても統計の専門家がいれば、何らかのイニシアチブの効果を社内で確認する、或いは外注して調べることもできると思います。ただそういう余資があるような団体も今日び珍しいでしょうね。 ・・・ ということで、一時有名になったビジネス書を読んだという事でした。 ビジネス読み物としては面白いです。が、仕事に生かそうと意気込む人は空振りする可能性が高いと思います。 までも、参考にはなります。自分の仕事の在り方を改善したいという方は、読んでおいて損はない本だと感じました。
2投稿日: 2025.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログいろんな例があって興味がある分野の話は楽しく読めた。 子育てに活かせそうなところ 失敗しても感情のままに怒らずに次からどうするかを一緒に考えること。 ミスや失敗を言いやすい環境を作る。 ミスを許さない組織(家庭)・組織内で上下関係が厳しいと失敗しても言えない・失敗を認められなくなる。→助けを求めることも難しくなるかも。
2投稿日: 2025.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ各章で取り上げられる事象がわかりやすくまた興味深い。 この本で書かれた内容を日常業務に取り入れていくのは一度読んだだけでは難しいので、何度か読み返していきたい。
2投稿日: 2025.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ医療業界や航空業界などの失敗から、なぜこんなことが起きたのか、なぜ失敗は無くならないのか、具体例もあげてわかりやすかったです。 ちゃんと失敗の背景などを理解したり、しないとなと思った。
2投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ業界問わず「失敗」にまつわるエピソードを題材に、様々な角度から「失敗」を検証しており、まさに題名通り「失敗の科学」である。恐らくヒューマンエラーは無くならないであろう。しかし無くすための態勢作りと不断の努力が人類には求められている。そこに進歩がある。最後の「究極の失敗型アプローチ、:事前検死」は一度チャレンジしてみたいと思った。
16投稿日: 2025.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗にびびりまくってた気持ちが楽になりました。失敗を隠すこと。失敗した事実から目を逸らして逃げること。これが一番やってはいけないこと。失敗を成長の糧と捉えて、反省して次に活かす姿勢が重要。どんどん失敗して成長していく人生にしていきたい。
2投稿日: 2025.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログマシュー・サイドさんの失敗学に関する一冊。 失敗学は以前から興味ある分野なので楽しく拝聴。 以下備忘録。 人が失敗を認めない理由 ・認知的不協和(自分の信念と事実が矛盾していることによって起こる不快感やストレス状態)が生じて、この状態を回避するために自分に都合の良い解釈をつけるため、 ・他者からの非難 ↓ こうした環境を排除 ↓ 失敗から学ぶ→原因を分析してクリア→これを繰り返して成長のスパイラルとする
16投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の行動には、失敗はつきもの。この失敗から何を学ぶのか、学ばす隠蔽するかは、組織の失敗に対する姿勢で大きく変わる。 成長するには、失敗から何を学ぶのかが大事。
2投稿日: 2025.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗から学ぶ」という使い古されたとも言える教訓に対して、数多くの説得力のある裏付けと実例を基に徹底的に解説していて、とても面白かった。 私はこれまで、真の意味で失敗から学ぶ重要性を分かってなかったなと思う。 読めて良かった。
3投稿日: 2025.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ重要かな、と思ったのは「認知的不協和」のくだり。やはりメタ認知大事です。 あと、ヒトは単純化した方が安心するし、そのような憶測のコメント速報には需要がある、ということは常に頭に入れておいた方が良い。自分が発するもの、受けるもの、両方のケースにおいて。 ただの非難は思考停止と同じ意味なのだろう。 「真の無知とは、知識の欠如ではない。学習の拒絶である」(カール・ポパー)とはよく言ったものです。自戒、自戒。
2投稿日: 2025.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ章立てが細かく読みやすかったです。 失敗についての考察だが、批判でなく前向きな語り口で心地良く読めました。 考えるな、間違えろ! 一発逆転でなく、百発逆転
3投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書をAmazonでおすすめされていたかでたまたま見かけ、借りてみた気がする。本書は、『Black Box Thinking: The Surprising Truth About Success』を日本語訳したもので、失敗を科学的に考察したものと捉えている。一通り、ざっと読んだところではあるが、失敗から学ぶことの大切さ、特に人命に関わるような業界ではその重要さを認識した。仕事においても、先人の失敗を聞いて、自分の業務に生かせると効率的に働けるのかなと思った。 【メモ】 1. 失敗のマネジメント 2. 人はウソを隠すのではなく信じ込む 3. 「単純化の罠」から脱出せよ 4. 難問はまず切り刻め 5. 「犯人探し」バイアスとの闘い 6. 究極の成果をもたらすマインドセット 7. 失敗と人類の進化
2投稿日: 2025.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆所感 失敗こそ成長に繋がる糸口。失敗は居た堪れない気持ちから曲解したくなるものだが、敢えて素直に認められる人に自分が率先してなるべきだし、メンバー含めてそういう組織にしたい。 そのため、以下2点に取り組む。 ・失敗を振り返れる様にデータで定量的に可視化すること(歩留まり分析によるRC力の可視化やAGボトルネックの特定) ・失敗しても矢面に立ちチャレンジすることが讃えられる環境を作ること(褒めや定性評価) ◆学び ・あらゆることが当てはまるということは、何からも学べない。 常に通説を疑い、反証を立てることこそ成長に繋がる。科学には進歩があるが、宗教やイデオロギーは不変であるが故に、争いの種となる。自身が信じて疑わない当たり前こそ反証し続けるべき。 ・失敗は浅いうちに認めておくべき。 認知的不協和により、サンクコストをかけるほど、時間が経つほど、組織で上の立場になるほど、無謬主義(自分たちの思想に間違いはないという考え)的な思想に陥りがちである。 ・客観的なデータを如何に取り、参照するかで課題が見える。 明確に間違えた、正しかったと示せる状態にすること。データを参照して、判断の是非を問う機会を作り続けることが大事。 ・犯人探しや非難ではなく、失敗から学べる組織にすべき。 人は一番単純で直感的な結論を出す傾向にある。ただし、物事は得てして複雑。非難ではなく、組織として失敗から学ぶことに注力すべき。
3投稿日: 2025.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味深い実際の事例をもとに序盤は面白いと思ったが、時間をかけて読んでしまったこともあり疲れて読めなしなってしまった。参考になる考方は多く書かれている印象だった。
2投稿日: 2025.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶ、もしくは繰り返す。その経過について過去実際に発生した事例から分かりやすく解説されている。 知識を得すぎた人間が故に、過去の成功体験や凝り固まった考えや間違えを認めたくない野心などがある。特に日本人は団体心理が強く、間違っている方向でも、みんながそうするからと言う理由だけで考えを放棄する国民性も持っている。 失敗からの学びの考えを進め、失敗していないのに失敗した前提でその理由を考えてみる、そんな内容も紹介されていた。 ただ、文字数が多い割に同内容の繰り返しが多く感じたのがやや残念。
2投稿日: 2025.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗はなぜ起こるのか?を科学的、論理的に解き明かしていく内容。 主に医療業界、航空業界がサンプルとして紹介されており、業界は違えどパイロット、副パイロット、執刀医、助手みたいなチームで仕事にあたるケースが描かれている。 極度のプレッシャーで集中し過ぎて時間感覚を麻痺したり、権威あるベテラン医師に上下関係からアドバイス出来ない事例を紹介。 『気質効果』と言う言葉かあり、株でも含み損の銘柄は売却した瞬間、損失が確定する為、自分の判断か間違っていたという証拠になり認めにくい。まるで自分のようだ。 事実を片方からでなく、色んな角度からみることが重要で、人間は一番楽で単純な直線的な結論を出すよう傾向がある。 そこには、人の行動は性格的な要因が含まれており、決めつけで結果を求めてしまう危険がある。 本書のところどこに記載されている、『失敗の捉え方』という言葉で、でミスは起こるものとし、改善していく方法はある。 ミスを報告し罰則を与えるものではなく、次に役立てる組織が強くなると感じた。 舞台が外国なので、カタカナ多く読むのが大変だったけど、勉強になりました。
6投稿日: 2025.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ心理学等もまじえ、なぜ失敗が起こるのか、失敗からの学びをいかに生かす体制を作るか、を説明している。ただ、これを読んでいると思われる人がこの本から学んでいない。
5投稿日: 2025.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗」を取り上げている本をはじめて読みました!発生したこと(失敗)を取り上げ、なぜ起きてしまったのかが書かれており、まるで物語を読んでいるような感覚で読むことができました。読み終わった時、物語のように読んだけど、実際に起きたことなのかと改めて思ってしまいました。複数例が取り上げられており、学ぶことが多いように感じました!失敗をした時に振り返ることの大切さを知ることができました。読んでよかった1冊です。
8投稿日: 2025.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は忌むべきものではなく、そこから得られる学びは莫大。 むしろ成功しか経験していない個人や組織ほど弱いものはない。 単純に読み物としても面白かった。
2投稿日: 2025.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ●2025年2月22日、この本は前に表紙を見た覚えがある。YouTubeで「本を読むこととお金を貯めること」で検索して出たショート動画、「頭のいい人がこっそり読んでる本4選」のコメ欄に書いてある、皆のおすすめ本。 「マシューサイドの本。実践してこそ本である。」 https://youtube.com/shorts/xdxuWn5jcTA?si=HWLgoUfFBAqRCGMB
2投稿日: 2025.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は失敗をする。失敗への対応や再発防止への取り組みについて語られた本。 筆者は、失敗が活かされない業界として医学界を挙げ、失敗を活かすシステムが備わっている業界として航空業界を挙げる。そしてそれらを対比させ、どのような取り組みをすれば万事の失敗に対して有用に向き合えるかを論じていく。 といっても、個々の医療従事者を批判するする本ではない。個々人は十分に善良であることを前提とした上で、そのような人たちでも失敗を活かせない態度となってしまう構造的な不備について指摘していく。 一つの理想の形として挙げられる航空業界も万能ではない。そんな事例の存在もある。 科学的とまで言えるかは微妙であるが、読み物としては面白かった。
2投稿日: 2025.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分がした過去の失敗と照らし合わせると、アドバイスや過去の失敗例とそれからどう改善に繋げたのかが、自分事になって染みる染みる〜!! 特に、自分は他人より不利な特性を持つことは認めるが、失敗の原因を自分の変えられない要素に求めがちだ。これではいつまでたっても前に進めない。本書を読んで、少なくとも真実に興味があるのだから、原因を検証のもとに追求し、失敗は学びに活かし繰り返さない姿勢に変えたい 【以下、自分用メモ】 ※この読書メモは、読了後、ただ満足するのでなく現実で本書の知識を活かすために書く。だから、分かりづらいのであれば、是非ご自身で本物の内容に触れて欲しい ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 航空業界が奇跡的に事故が少ないのは失敗から学ぶプロセスを重視しているから。特にこの姿勢を持つ社は事故率が少ない。ブラックボックスで強制的に、一方で匿名でデータ収集される。他方で医療業界は回避可能な事故が原因の死亡者は毎年5-10万人に昇る 医療業界は適切な対策を知るためのパターンを知る術がなかった。理由は、日常的にデータ収集をしてこなかったから。航空業界は強い権限を持つ独立の調査機関を有する。医療は調査にしても当事者の視点に限られる。 一方で、"真実は独立機関によって明らかになる"。当事者視点では潜在的な問題に気づかないため、クローズドループが長引く。 (意志の強さは関係なく客観的に、残燃料、速度といったデータから調査する必要あり。ある航空事故は、操縦士は燃料切れが早かったと申告したが、実際は通常と変わりなく、機長が集中により没頭し時間感覚を忘れたためであった) 時間感覚を消失し必要な判断がとれなかった事故では、リソースマネジメント(チームワークを活用したリスク管理)が対策としてとられた。 チェックリストで部下と上司が緊急時に点検し合うことで、上下関係をなくし意見しやすくする。また、チームワークを機能させることで、部下が間違いに気づいても上司に物言いできない環境を回避する。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【過去の失敗から事故を回避した例】 航空機のバードストライクに遭うも無事着陸。成功要因は、上司と部下のスムーズな連携プレー、終始とられた円滑なコミュニケーション(スピードや高度、時間などで正確に情報認識できるよう)。 チェックリスト、コックピットの人間工学デザイン、CRM訓練は事故を教訓にしたもの ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【クローズド・ループ現象】 失敗や欠陥に関わる情報が放置され曲解され、進歩に繋がらない現象や状態。 (効果があるとされた瀉血は検証をされなかった。そのため、瀉血での死亡は、瀉血で死ぬのは余程重病、回復は瀉血のおかげとなる。結果が都合良く解釈される故に、学習機会を得ず有害という真実に辿りつけない) 【オープン・ループ】 失敗が適切に処理され、学習の機会や進化がもたらされる ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 混乱状態でも直感的に区別できるシステムが大事。 失敗から学ぶことは費用対効果が大きい。事故による死者は勿論のこと、医療過誤のコストはアメリカで1兆。事故対応と失敗対策への資金不足、金をかけるとしたら対策の方がコスパはいい ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【失敗しない理論の功罪】 アドラー心理学のような何にでも当てはる理論は成長を産まないし、何からも学べない。クローズドループ現象は言い逃れが原因で起きる。 水は100度で沸騰するが標高により沸点は変わる。1つの説に固執せず、新しい説を導き出すと、どの説も説明できる舞台が整う機会を得られる。 航空業界は検証と反証の繰り返しだ。毎回の飛行で検証し、事故は反証、いやでも安全性を改善せざるを得ない。だから事故率が小さい ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【経験値が能力に結びつかない理由】 チェス選手は失敗すれば相手に攻め込まれるため、常に自分の間違いがチェックされ、毎回考え直し適応する。しかしながら、心理療法師や放射線医師はフィードバックが歪んでいる。患者のその後を知らないし、自身の判断が正しかったかの査定も具体的でない。学習機会がなく暗闇でゴルフしてる状態。 *対策* "客観的なデータをもとに自身の判断を検証する"こと。正誤のデータが既出の、マンモグラフィで訓練し判断能力をつける。 「進歩が曖昧になりがちな分野も、客観的なデータをもとに日々正誤の査定をすれば進歩する」 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 組織が失敗にオープンで学ぶ姿勢があること 【事例】 医療事故を起因に組織のマインドが変化。不衛生による医療事故削減のため、簡単な5ステップのチェックリストを導入。運営から看護師が忠告できるバックアップをし、死亡率を減らした。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【浸透速度】 失敗のノウハウがあったとて、現場に行き渡らねば事故は起こり続ける。問題は"情報の量でなく形態"。 「"使用に適したシンプル、要点を押さえていて効果的な形に"置き換えられているべき」 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ なぜ人は失敗を認められないのか。 【認知的不協和】 恥をかいてまで、努力までして手にしたモノや座が無価値、誤判だと考えたくない。 この状態では統計データやDNA鑑定まで疑われる。エリートにこの傾向は強い。努力は判断を鈍らせる。失敗を認めず自己正当化する人間は、大抵データを出されても検討すらせず却下する。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【失敗の泥沼から抜け出す方法】 "あえて間違える"。 10,12,14の数列について本当の仮説を知るには?昇順か偶数か同じ確認をするより、間違っているか仮説に反する数列を答えた方がパターンが分かりやすい。早いのもあるが、答えを知りたいなら失敗が唯一の方法なこともある。 〚バイアスにより効果を都合よく肯定材料とするループから抜け出す方法。自分の仮説に溺れず健全な反証を行うこと。まだ"分かってないこと"を見出す方が重要〛 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【人間が記憶を改竄するプロセス】 人間の記憶は、実際に見たことより知っていることに記憶を寄せる、情報をすり替える、新たな記憶を作り出す 例1) 事故で何も割れてないのに「ガシャンとぶつかったか?」と聞かれると、割れたと答える。 例2) 事故直後知るはずもないのに、ブッシュ大統領が911で「飛行機は北棟に突入するのを見た」と言ったがために陰謀論者に狙われる。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【正解を導く試行錯誤の力】 数学者チームによるトップダウンは、理論をもとにモデルを1個しか作らなかったため芳しくなかった。449回モデルを作り、僅かな変更から結果が出たモデルを基準に製品を作ったボトムアップは、ノズルの詰まりを解消できた。 【複雑な問題への対処】 とはいえ試行錯誤は時間がかかるので、仮説を検証しつつ実践で方向性を定めるのが一般的。 進歩は論理的知識と実践的知識の両面で進歩する。現場のは反復的作業が多く面倒だが軽視してはならない。 "答えが分かってるからと試行に障壁を作るのは辞めるべき"。後付けで因果関係やストーリーを作ることも。現実は複雑で、同じ原因でも結果は違ったりする。 都合よく後講釈するのでなく自分のアイデアや仮説をテストし欠点を見つめ学ぶべき ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 質より量、脱完璧主義 【リーン・スタートアップ(小さく始める)】 検証と軌道修正の繰り返し。上手くなりたいなら下手な曲作れ。ソフトは"最低限の機能でアーリーアダプターから反応を受けるべき"。そうすれば、"本当に売れるのか、どう改良すればいいのか"分かる。 (コストがかかる試作品でなく、実装風にしたデモ動画でも良い、開発にユーザー参加型をとること!) ソフト開発で欠点に対応しながらも現場のFBを受けることで新たな発見を得ていった。ライバルが1機能足すこどに、10足せば10倍チャンスが得られる 【フェイルファスト】 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【もっともらしさに騙されるな】 同じぐらい説得力がある説も、検証すると如実に結果に差が出たりする。 例) 風邪の対処法 マスク***** ネギ枕* 判断は講釈の誤りでも発生する。少人数のストーリー的なエピソードより大きなデータを見るべき。直感は判断を誤らせるから、検証し続けるべき ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 瀉血が疑われなかったのは解釈に問題があったから 【反事実(しなかったら起こったこと)】 ・瀉血した場合…5人回復 ・しなかったら…7人回復 "しない方が良かった事実は、対照群、しなかった場合を設定しなければ判明しない"。 【反事実は目に見えない】 例) webサイトデザイン変えた ・変えたから利益伸びた? ・変えてなかったらもっと伸びた? 瀉血で回復した人のように、伸びた数のみでは効果が判別できない。 【ランダム化実験(RCT)】 原因が不明な事象を解決する手段。 "原因や介入手段(瀉血、デザイン変更)と結果(回復、売上増)を切り離し"、曖昧な要素を排除し客観的に評価できるようにする 例) 新旧デザインのサイトにユーザーをランダムに誘導する。 【RCTの注意点】 全体や長期的に見る視点。ある症状は抑えても根本的な解決になってないかもしれない ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【統計の歪み】 瀉血は死亡者は答えられない、刑務所体験のアンケートに答えた家庭は改善したもののみ。仮に全員答えたとしても、反事実というしなかった場合を無視してる ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【マージナル・ゲイン(小さな前進)】 分析単位が国など大きかった場合は検証で対照群を用意できない?→比較対象を分解する。 プログラム(マラリア予防、道路建設、インフラ整備)といった"小さなものを単位に"すれば、人や地域によるグループ分けは可能。 例) 教科書を配った場合とそうでない場合→差出ず 資格資料増と変化させず→差出ず 寄生虫感染の駆虫薬配布→差出た 一見効果がありそうなことに効果がなく、検証し続けたことで学習を阻む要因が見つかった。 【フィードバックを強化するのはデータの収集法】 戦略を創造しリハーサル段階に進むと、頭で考えていたより見過ごしていた要素に気づく。そこで、データの測定方法を見直す。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【非難の罪】 ミスは過失より複雑な原因による起こるため、罰則は効果がない。厳格なリーダーは課題の複雑さに向き合おうとしない、部下から信頼されずミスの隠蔽を助長し、失敗から学ぶ機会を妨げる。 【脳は非難のストーリーを勝手に作る】 航空業界の調査員ですら、ブラックボックスから検証する前に事故の理屈を考える。実際ミスは個人の性格より状況に起因する。特定の個人や機関を非難したために、現象を引き起こした原因について、広い目線を持てば見つかったことも見落とす。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【失敗から学ぶ人の特徴】 失敗を自己否定でなく成長と見る、やりきる。ただ、やりきると言っても、ただ粘るのでなく"合理的に諦める"。 自身にはこの問題を解決するスキルはないと、引き際を見極め自由に"他のことに挑戦する"。 【向き不向きで判断するリスク】 アメリカ:起業人口多い、「失敗は賢くやり直すチャンス」 日本:起業への恐怖心 アメリカ:数学は向き不向き 日本:数学は努力すれば誰でも可能 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【失敗から成長する】 ・あなたは判断を間違えるか? ・自身が間違った方向に進んでいることを知る手段は? ・客観的なデータから判断の是非を問うことは? 結果が曖昧で検証し難い職種、課題の場合は信頼性の高いベンチマークに頼ろう。 検証は裏付けをとるためでないので、"理想的な条件にしない"。 プロジェクトが失敗した前提でなぜ失敗したか理由が尽きるまで挙げ続ける。
3投稿日: 2025.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは現代人必読の書であると言える。犯罪とはいえない失敗によりいかに多くの人の命が失われているのか?医療過誤によって毎年40万人以上の人々が死んでいるという現実があり、死亡に至らない過誤まで含めれば、この10倍以上の人たちが苦しんでいる。 医療過誤以外にも多くの分野で失敗は隠されるのだ。犯罪や事故に対しては過剰なまでの責任追及する我々は、自らの失敗についてはその責任から逃れようとするのだ。失敗は隠されるから、何度も繰り返されるのだ。
84投稿日: 2025.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【具体から知る失敗がもたらす好転】 読書後のメモとして記載します。 ①我々は自分自身から失敗を隠す シンプルでドキッとした言葉です。 例えばメールの誤字のレベルであっても、少し注意不足だっただけだし大したことではないだろう、など。 これを失敗と捉えるか、ケアレスミスやたまたま不運だったと捉えるかで大きく違うと感じました。 ②集中力の高さが時間感覚を鈍らせる 大学時代を振り返っても確かに、と思う。 真剣にやっている時は時間感覚が溶けていく。 自分の中では刹那的な時間であっても、物理はあっという間に進む。そして恒常的ではなく、ある時突然やってくる。 言語化されてなるほどと思いました。 ③努力が判断を誤らせる 事実がどう、ではなく、自分が心血注いだことであるほどマインドや信念に沿ったものを正解にしていくことは、振り返れば何度もありました。 これはエゴだなと、猛省です。 ④マージナルゲイン とにかく量・数! やらない理由はたくさん見つかるけれど、ダメなものをダメと知ることの大切さはもちろん、ミニマムアップデートの繰り返しが大きな改善につながる考えは、次のアクションを少しやりやすくなると感じました。 またランダム比較実験(RCT)の話と合わせて、やった未来と・やらかなった未来を比較すること。ここは当たり前なのに、「アクションによって変わった未来」というご褒美に飛びつきがちな自分とも対峙するきっかけになりました。
3投稿日: 2025.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「記憶は脳全体に分散するシステムで、あらゆる種類のバイアスの下にある。つまりそれだけさまざまな影響を受けやすい。まったく別々の経験の一部を集めてひとつの出来事につなげてしまうことすらある。」
2投稿日: 2025.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ上下関係が時にチームワークを乱し、大惨事を引き起こす。冒頭からショッキングな事故の紹介で抉られる。緊急事態下では目の前のことに集中してしまい時間の感覚が無くなる。人は過去のショッキングな失敗に目を背けず真摯に向き合い学んで、改善の歴史を積み上げていくべき。スケアードストレートプログラムは逆効果。周りが囃し立てただけで選択バイアスと認知的不協和が生み出した忌むべき現象。マージナルゲイン。
2投稿日: 2025.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み物としても面白かったです。 ストーリーにも臨場感がありました。 人は自分の失敗を認めたがらない。 失敗を無視したり、自分を正当化してしまう。 大切なのは、自分の失敗を受け入れ、失敗から学び、同じ失敗を繰り返さないこと。
7投稿日: 2025.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「小説のように面白い」の前評判に違わない名著 題材にしているのは「失敗から学べ」というありふれたメッセージ。 本書ではこのメッセージが様々なエピソードをもとに繰り返される。 そのどれもが、身近に起こっていることに重なるものばかりだった。 自分自身、何か失敗をした時に、他人のせいにしたり、言い訳をしたくなることは多い。 が、この本を読んでからは、むしろ成長の機会として積極的に失敗をしていきたいようなメンタリティーになれた。
3投稿日: 2025.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織作りを進める上で、失敗からの学びをいかに活かすかということを解説している。プロダクト開発を進める上でも重要な考え方を学べる一冊。あとは、個人のマインドセットについて触れている箇所も興味深かった。成長思考マインドセットを身につけることで、常日頃からの失敗を糧に経験として積み重ねる習慣が身につくと感じた。事例も多めに掲載されているため、その部分を読み返そうと思います。
3投稿日: 2025.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗が許されない医療と航空の領域において、失敗への向き合い方が異なっていることに驚く。組織風土や感情の面で失敗を言い出しにくいのは何となく分かる気がするが、失敗から学べる組織は強いと感じる。
14投稿日: 2025.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ航空業界と医療業界の失敗に対する対処違いから説明が始まる。失敗とは「経験である」は理解できるが、科学と言い切る程内容は深くない印象を受けた。
2投稿日: 2025.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ航空業界と医学界を比較して、失敗を次に活かすことのできる組織についてわかりやすく解説していた点が良かった。失敗から学ぶとはどういうことか理解できた。
2投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
年末年始乱読1冊目 いまのところ一番面白かった ・失敗から学べ 航空業界は失敗を学びの機会と捉えて余すことなく検証するが、医療機関は隠蔽しがち。「そんなことを言っても患者には分からない」とか。 ・学ぶためのシステム作り 失敗を報告しやすくするシステム作りが必要 ・検証しろ 科学の世界では失敗から学ぶことが当たり前だけど、社会学の世界では検証がされないことが多い。 冤罪がなくならないのも、検察・裁判官がミスを認めたくないから。 「グレてる若者を刑務所に連れて行って、怖いところだぞと教えるプログラム」も、ずっと有効だと思われていたけど検証してみたら意味がなかったことが判明。むしろ、再犯率が上がっていた。 ・非難するな 非難することは簡単だけど、非難しても状況は好転するな。会社のマネジメント陣が懲罰ばかり考えても下が隠蔽するだけ。 地球が滅亡すると預言したカルト教団の信者は、滅亡の日に何も起きなかったのに「わたしたちが信心深いから神様は滅亡させなかった!」と思い込んで余計にカルトにハマっていった。自分の失敗を認めたくないから。自己正当化しないとやっていられない。 ↑これ面白い。 元卓球オリンピック選手がなぜこの本を書こうとしたのかが気になった。 わたしの会社は「ミスを許さない」会社だなと改めて思った。
2投稿日: 2024.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ【★5】何度も読み返したい名著!本作とは関係ないがふと思った、外国人の本の訳書には質の高い本が多いのでは。(良い本だから訳されるに至った)
2投稿日: 2024.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「多様性の科学」に続いて、この本もめちゃくちゃ面白かった。特に医療業界における「失敗」の捉え方が、どうして学びにつながらない仕組みになっているのかがよく分かった。 たとえば認知的不協和。これは、自分の信念と事実が矛盾したときに都合のいい解釈をしてしまい、失敗から目を背けてしまうこと。「偶発的なミスでした」「避けられない問題が発生しました」といった言葉で片付けてしまい、失敗の背景をきちんと検証しない。これでは学ぶ機会が失われてしまう。 もう一つは非難。悪意のないミスでも責め立てられることで、人は失敗を隠すようになる。「失敗は許されない」という文化が根付いてしまうと、隠蔽が当たり前になってしまう。 でも、そんな中で航空業界の取り組みがとても印象に残った。彼らは失敗を個人の責任にせず、徹底的に原因を追究し、業界全体で共有する仕組みを作っている。失敗を非難せずに学びにつなげる――それがどれだけ難しいことかも書かれていて、「確かにな」と納得した。事件が起きたとき、誰か一人を悪者にして非難するほうが楽だし、人はついそこに陥りがちだと思う。 医療も、航空業界のように徹底した安全性を目指すべきだし、そうする必要がある。でも、私が今いる業界は「ミスをしたら犯人探し」の世界だ。この文化を変えたいと心から思う。
3投稿日: 2024.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログさまざまな業界で起こる失敗を科学的に根拠づけてどう行ったプロセスで起こったのかエピソードを例にして話しています。非常に目からウロコのお話が多く面白いです。 失敗から学習するために必要なことを学べるのはもちろんのこと読み物として面白すぎるのでおすすめです。
2投稿日: 2024.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログRCT、マージナルゲイン、、 全て一切考えられていない組織で働いている自分が本当に嫌だ そして失敗を恐れて行動しない自分にグサグサと刺さるというより、冷静に説明されて納得しちゃう
2投稿日: 2024.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み始めたときは結構ボリュームがありそう、とひよったが、いざ読み始めると具体的な事例が臨場感あるかたちで表現されており、とても楽しみながら読了できた 私の会社は、本書内の典型的なNG例の通り、失敗は悪、犯罪、といった扱いをされてしまうが、そのマインドでは失敗を隠したくもなり、改善や成長につながらない 大事だと思った一文は、 「成功を収めた人々や組織の共通点は、みな失敗に対する前向きで健全な姿勢がある」 「開発者が直面する問題はときに複雑すぎて、理論や図面の上だけで答えを出すことはできない(トップダウンによる机上の判断だけではダメになる)」 「失敗は学習のチャンスととらえる組織文化が根付いていれば、非難よりもまず、何が起こったかを詳しく調査しようとする意思が働くだろう」 「子供たちの心に、失敗は恥ずかしいものではなく、学習の支えになるものだと刻みつけなければならない、互いの挑戦を称え合おう」 以下、自分用メモ 本書における、 クローズドループ:失敗に関わる情報が放置されたり曲解されたりして、進歩につながらない オープンループ:失敗は適切に対処され、学習の機会や進化がもたらされる 社会的な上下関係は、部下の主張を妨げる 失敗があったからこそ成功がうまれる 失敗に対してオープンで正直な文化があれば、組織全体が失敗から学べる、そこから改善が進む 人は自分が信じたいことを信じる 人は自分の信念と相反する事実を突きつけられると、自分の過ちを認めるよりも、事実の解釈を変えてしまう 上層部に行く人ほど失敗を認めなくなる 我々はつい自分がわかっていることの検証ばかりしてしまう、まだわかってないことを見出す作業のほうが重要 我々の脳は一番単純で一番直感的な結論を出す傾向がある
2投稿日: 2024.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ医療現場で働いているけど、インシデントレポートって書いた人の主観の塊で。航空業界はフライトレコーダーやブラックボックスが残っていて客観的に後からの検証にも耐えれるのが強いなと思う。
2投稿日: 2024.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗から学べ」 この言葉は昔からよく聞かされたが、本書は改めて失敗から学ぶことがいかに重要か、そして失敗から学ぶためのマインドセット、方法を教えてくれる。失敗に対する認識を大きく変えてくれた一冊だった
2投稿日: 2024.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
多様性の科学を読んだ時から気になっていた本。ようやく購入できた。いかに失敗から学べるかというのが、組織が適切にアウトプットを出せるかという観点でやはり重要であると実感した。そのような仕組み化、体制づくりが難しいところかと思うが、様々な事例から学べることが多かった。
2投稿日: 2024.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。具体例を交えながら失敗の大切さを改めて学ぶことができた。始まりの3章くらいで十分で残りは少し冗長気味だった、。
2投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は貴重な情報源。失敗から学ぶためには、適切なシステムとマインドセットが必要。自分の失敗を認める姿勢と、その失敗から学ぼうとする意思が重要。クローズドループ現象(瀉血、爆撃機など)は成長しない。指摘は成長のために必ず必要。小さな改善の積み重ねが大切。認知的不協和のため、人間は解釈を曲げようとする(一貫性の原理、宗教など)。非難は絶対にしてはいけない。結果を評価するのではなく挑戦を賞賛する!
2投稿日: 2024.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、アメリカの航空業界と医療業界を例に、失敗にどう向き合い、それをいかに組織の成長へとつなげるかについて解説しています。特に印象的だったのは、航空業界が失敗を「貴重な学び」として積極的にデータを共有し改善を重ねる一方、医療業界では責任追及が重視され、情報の共有が滞りがちである点でした。この対比が、いかに失敗へのアプローチが異なるかを鮮明にしています。 書籍の中では、「失敗データの重要性」について多くの事例が紹介されており、RCT(ランダム化比較試験)を用いて成功と失敗を比較することの重要性が強調されています。成功事例だけでなく、失敗事例を分析することで初めて見えてくる真実があるという視点は、多くの読者に新たな発見を与えるでしょう。 さらに、著者は「初めから完璧を求めるのではなく、小さな失敗を繰り返して改善を重ねることが、最終的には効率的である」と述べています。例えば、航空業界が日々の運航中の小さなミスを見逃さず、それを組織全体の安全対策に反映する仕組みを持っていることは非常に興味深いポイントです。 本書は、失敗を恐れず、それをいかに次の成功へとつなげるかの大切さを学べる一冊です。 読後は、自分の仕事や日常生活においても、「失敗は成長の一部」として捉える視点を持ちたくなるでしょう。事例が豊富で、具体的な学びを得られるため、ビジネスパーソンだけでなく幅広い読者におすすめです。
12投稿日: 2024.11.04面白かったです。全人類に読んで欲しい。
医療業界と航空業界の豊富な事例(事故とその対応)がメインですが、それ以外にも、教祖の予言が外れてもますます信仰を深めるカルト教団信者の例など、面白い話が盛りだくさんでした。 ・失敗は「してもいい」ではなく「欠かせない」。反証の検証がなされてはじめて進歩が始まる。 ・はたから見て明らかな失敗を当事者が認知すらできないことがある。心理バイアスや権威主義のつよい組織で起こりやすい。
0投稿日: 2024.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログめちゃくちゃおもしろかったですね〜。終始メモ取ってました。失敗から学ぶ、と一口にいっても、中々難しいですよね。そのためには失敗を認めなければいけませんし、そしてそれは自分の不足を認めることになります。間違いなく自分の失敗を認め受け入れられるように、心を広く、度量の大きい人間になりたいですね。 他、反事実の検証の話。これ本当にその通りなんですが、実行するのに難易度高すぎるんですよね〜。いつも無意識のうちに、わかっていることを確かめるための検証をしてしまいます。でもこれって。チェックするという意味では効果がありますが、進歩すると言う意味では全く効果ないです。わからないことを検証するマインドをこれからは強く持とうと思います。
57投稿日: 2024.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶ バイアスに支配されないで失敗やミスを認める、又はオープンマインドネス(引用: 深く信じていたことを否定する証拠を突きつけられたら考えを改めるどころか強い拒否反応を示す) 記憶は信頼できるものではない 航空業界と医療業界の対比
2投稿日: 2024.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ【失敗の科学】 人間は失敗した時の方が本能的に記録に残りやすい。 失敗は学習のチャンス。 航空業界は失敗から学ぶプロ。航空業界は失敗から学習するシステムがとられている。失敗はシステムの不具合とみなす。人間の心を考慮しないシステムの方が問題。部下は上司に主張するスキルも学ぶ(pace、確認探求、注意喚起、チャレンジ、緊急事態)。上司は耳を傾けて判断することを学ぶ。クルーリソースマネージメント。ニューマンエラーはシステムの設計ミスだと認識する。 失敗から学ぶのが一番効率がいい。失敗を不可能にするシステムはそこなら何も学べない。何にでも当てはまる、例えばアドラーの溺れた子供を助ける話。 フィードバックが無いと正解だったか判別できなくて改善できない。直感や感覚が研修時間と比例する職種とそうじゃ無いのがある理由。一万時間の法則が効果ある仕事かどうか。 失敗は理想と現実のギャップ。ギャップをいかに埋めるか。チェックリストの導入。 浸透速度。情報はシンプルで効果的な形にして共有する必要がある。現実的に要点をまとめる。そうしなければ取り扱いしにくい。その他の情報に埋もれる。 仮説が正しいか確認するには失敗するのが手っ取り早い。正しくないことを証明する。進化にそもそも計画などない。累積淘汰。大量生産した方が試行錯誤が繰り返されるので結果質の高い物が出来る。質の高いものを作ろうと思っていると試行錯誤回数が少なく良い結果につながらない。 素晴らしいアーティストになる為に駄作をいっぱい作ろう。強いアスリートになる為にたくさん負ける。すばらしい建築家になる為に非効率でダサい作品をデザインする。失敗から学ぶ。試行錯誤の量が必要だ。 ランダム比較試験(RCT)。細かく区切って小さな改善を繰り返す。放任と懲罰。 失敗は欠かせない。失敗からの学習が非難という外圧によって妨げられる。成長が遅い人は失敗は才能がないと受けとめる。原因を知性に求める。やり抜く力(グリッド)大切。合理的に諦められる。才能がないと認められる。批判を尊ぶ。
2投稿日: 2024.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶ 責めたり単純化したり能力不足だと諦めたりするのではなく、フィードバッグとして受け止める。
2投稿日: 2024.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ名著。2016年に出版された本だが、2024年の今でも古さを感じない。その後、認知心理学や、行動経済学の研究が進んで、もっと深く議論されているのかもしれない。 そもそも失敗はどういうときに発生するのか?そのメカニズムを、医療、航空、司法などの分野の例をあげて生々しい話を教えてくれる。 さらに、失敗は成長するための好機であるが、その成長を妨げるものが色々とあることも教えてくれる。制度や権威によるクローズドループ、検証の方法の不十分さ(確証バイアスなどによる)や解釈の間違い、イデオロギーや宗教による締め出し、非難、犯人探し、魔女狩りなどの恐怖からの隠蔽、認知的不協和から起こる記憶からの抹殺、マインドセットの型の違い、など。 とても大切なことを教えてくれる。ブクログに残したフレーズがかなり多くなった。 パイロットの夫が、奥さんを回避可能な医療事故で亡くしたところから始まること、その夫が医療事故撲滅の運動をしていることなど、物語としても工夫されている。2012年のツールドフランスのブルーレイを見始めた。著者が元卓球のオリンピック選手というのも面白い。
2投稿日: 2024.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすい内容で、自分に当てはめるのはもちろん、子どもとの向き合い方なども考えるきっかけになった。 例えるならば自分の子供には100点取ったらご褒美などの習慣はつけずに、間違えた問題をサラッと教えて終えるのではなく、どこでつまずいたのか(問題の読解力なのか、解く過程なのかなど)深掘りして一緒に見直しをするなど。 当たり前のことかもしれないが、夏休みの今改めていいタイミングだった。 日本の教育の中では難しいこともあるかもしれないが、間違えることは恥ずかしいことではなくむしろ成長できる良いきっかけであると伝えていきたいし、自分も実践していきたい。
2投稿日: 2024.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際に起きた事件や事故をもとに失敗が起きる要因について科学的な検証を行っていて、興味深い内容だった。 誰しも失敗をしたくてしているわけではなく、それぞれの正しさのもとに行動している結果であるのみである。 失敗を経験することも大事だが、どういうパターンにおいて失敗が起きやすいのかは把握しておいて損はないと思う。
2投稿日: 2024.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ産業・組織心理学の入り口としてちょうど良い内容である。トップが失敗を許容できないと、それに付き従う人間も失敗を指摘しにくく、防げたはずの失敗も防げずに一大事となる。とくに日本は、世界的に見ても失敗を許容しない文化らしい。失敗することを恐れて一歩を踏み出せないのは、貴重な学習の経験を逸してしまうことに他ならないが、失敗経験の積み重ねや上述のような文化が、実行に移せないことの足枷になっていることもあるだろう。事前検死という考え方は斬新で面白いなと思った。
4投稿日: 2024.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ翻訳本にしては読みやすい。 個人としても組織としても学びがありそう。 自尊心が高く自分の間違いを認めることができない人にならないように。 間違えた、できなかったを認めてそこから改善へ。 そんなことができる組織文化作りって難しい〜 組織としても反事実とかを使って、政策の効果検証に使えそう。
3投稿日: 2024.06.24
