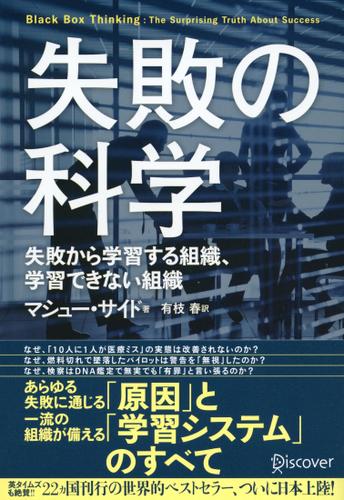
総合評価
(310件)| 173 | ||
| 84 | ||
| 32 | ||
| 0 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶものは多い。その学びを最大限活かすための姿勢について、医療や航空業界でのエピソードを交えて書かれている。読んで良かった。
2投稿日: 2024.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ要はPDCAサイクルを回す事だと思うけど、失敗を認めないとACTIONが実行されず、サイクルが回らない事と認識した。まぉ、素直に失敗を認めていれば、そこまで物事がややこしくならないのにな。と思うことは仕事をしてて思うことはある。反面教師として気をつけたいと思うけど。
2投稿日: 2024.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は努力不足や油断などからのみ生まれるだけではなく、一生懸命やった結果生まれることも当然ある。 そのときに、頑張ったがだめだった、仕方ない、で片付けるのではなく、なぜ失敗したのか分析し、繰り返さないことが重要。 失敗を恥ずかしいもの、恐ろしいものとして遠ざけるのではなく、恐れずに挑戦心を持つこと、失敗したとても失敗から学ぶことでみんなが幸せになれるよう活かしていくことが重要と感じた。 ・失敗があったからこそ、成功が生まれる ・成功には失敗というプロセスが欠かせない ・失敗にオープンな文化があれば失敗から学べる
2投稿日: 2024.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶ 業態が違うだけで航空業界、医療系と失敗に対する対策が違うこと RCTの必要性 正確なデータを持って裏付けられて調査の大事さを再認識した
3投稿日: 2024.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「失敗を活かして次に繋げることができない文化・組織は成長できない」 というのが本書の総論。 医療現場やパイロット、検察等を例に失敗に対するアプローチの違いがズバズバと記載されていて面白い。 自社(特にスクラム開発とか)でもこのような文化が根付いているのか気になる。 また、有害な固定概念は元の解釈を神聖化し続ける恐ろしさを持つ(=失敗にすら気づかない)ため、自身がこのような決めつけに囚われないように気をつけたい。 以下、印象に残った言葉 ------- ・失敗を味わわないと成長の機会がない(言い換えると失敗がなくあらゆるものが当てはまる世界だとそこから何も学べない) ・プロジェクト開始前等は「事前検死」で、そのプロジェクトが完全失敗に終わったケースを想像(事前に殺す)して、原因分析・対処を検討する。
2投稿日: 2024.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ【琉大OPACリンク】 https://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22819848
1投稿日: 2024.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ学びがたくさんある本でした。失敗は自分の成長のために大切なことだとは分かっているのですが、私は、自分や周りの人の失敗を100%受け入れる事はなかなかできていません。失敗の受け止め方を変えていきたいと強く思う一冊でした。
2投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々な業界の【失敗】を科学的に解説し、成長型マインドセットの重要性を教えてくれる本。 人は認知的不協和によって事実の解釈を変えてミスを正当化する、失敗を認めなければフィードバックし成長、成功には繋げられないというのは素直になるほどなと。実用書としてはもちろん、読み物としてもめちゃくちゃ面白かった
2投稿日: 2023.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。ミスを無くすためにはミスがあったことを報告したり認識したりして改善せなあかん。怒られそうならミスは隠されるよね。
2投稿日: 2023.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は、費やしたリソースが多いほど、失敗をしたことを認めない(認知できない) 偉い立場の人ほど、社会的立場なぉが邪魔をして、その傾向がある。 人は失敗すると、生まれながらの知性だと思う人がいるが、そう考えずに失敗から学ぶことを意識すべき。 失敗したときに犯人を探すことには意味がない。犯人を有罪にして解決したつもりになる一方で失敗から学べないリスクがある。 RCT(ランダム化比較実験)の具体例が気になる。
2投稿日: 2023.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶ重要性を改めて認識できた。 とは誰もが理解している(知ってはいる)が、実践することの難しさの背景に組織の構造上の問題や、思考の癖があると気付かされた。そこを変えないと真に失敗から学ぶことはできないんだな。
3投稿日: 2023.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗を恐れる全ての人に読んで欲しい一冊と私は感じました。 著者のいうクローズド・ループ現象の恐ろしさとその複数の要因を学ぶことができたことはとてもためになった。 犯人探しバイアスや認知的不協和による曲解は誰にでも起きることで、自分自身にも心当たりがありました。これらの不毛さを学び、できるだけそこから解放できるように組織的なシステム、個人的なシステムを失敗から学び、個人的なシステムだけでも洗練していくよう努力していこうと思いました。 「真の無知とは、知識の欠如ではない。学習の拒絶である。」というカール・ポパーの言葉を受け、物事を素直に受け入れる気持ちと、根気強さを持って、この人生を楽しもうと私は思う。
3投稿日: 2023.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白かった。 前半は海外物にありがちな若干冗長な感じではあるが、それぞれ説得力を持たせるために必要十分な分量だった。
2投稿日: 2023.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは名著 失敗を活かすためのテクニック、ピットフォールがいろいろな事例を元にわかりやすく書かれている 今日からでも活かしていこうと思う
2投稿日: 2023.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗するのは何も悪いことではない。 大切なのは失敗を認め、そこから学ぼうとできるかどうか。 細かいところまでフィードバックをして、改善に努められるかどうか。 一つの失敗から学習することが何よりも大切であり、成長への鍵である。 学習する個人、組織に。
8投稿日: 2023.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ名著である。さまざまな文献が参照されて説得力もあり、参照された数多の本を読んでみたくなる。本そのものもスートリー仕立てで大変楽しく読みやすい。 普段の生活では、認知的不協和や確証バイアスにより、クローズドループに陥り、うまくいかない事態の方が多く観測される。しかしながら、オープンループ目指して、失敗を恐れず受け止めて、糧にする必要がある。 その方法として、成長型マインドを意識して、小さなカイゼンを積み重ねるマージナル・ゲイン、リーンスタートアップ、ランダム化試験比較、事前検死などの道具とヒントが与えられる。
3投稿日: 2023.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ業界によって失敗に対する見方が異なる、というのは新鮮だった。また完璧主義における、失敗から学べるメリットよりも失敗しないことを求めることのリスクを取ってしまう姿勢には共感するところがあった。 小さなPDCAをたくさん回す事で見聞も深まるであろうから、行動する事に重きを置いていきたい。
2投稿日: 2023.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろかった 繰り返し読みたい本 認知的不協和、私にも思い当たる節はある、まずは自覚することが大事
2投稿日: 2023.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書のキーメッセージは、「①失敗を認知し、②成長の機会として活かす」でした。一見当たり前のような言葉ですが、失敗を認知することを妨害する要因や成長の機会として活かすために必要なことを多種多様な事例を交えて解説してくれています。 ①失敗を認識する 自分の失敗として認識することを阻害する要素は、 ・認知的不協和 ・批判(の回避) です。 認知的不協和とは、自分の信念と事実が矛盾している状態のことを指し、本書ではカルト教団の例が挙げられています。カルト教団で、教祖がある時期に大変な災厄に人類が見舞われると予言します。信者はそれを信じ行動します。しかし、実際にその時期になっても何もなく、予言は外れたとします。しかし、信者たちは予言が外れたから教祖を信じなくなるのではなく、「自分たちが祈りをささげたから、災厄から人類を救われた」とますます教祖を信じ込みます。また、性にまつわる討論を見学するという実験で、負荷の高い事前学習をしてきたグループ(Aグループ)とそれほど事前学習をしてこなかったグループ(Bグループ)を作り、それほど盛り上がっていない討議の映像を見せたところ、Bグループはつまらないと回答したが、Aグループは素晴らしい討論だったと回答した。自己の払った労力無駄ではなかったと信じ込みたいバイアスがかかるという解釈である。 批判とは、失敗を認識することで犯人にされたり、組織的な失敗のスケープゴートにされたりすることを恐れ、失敗を認知できない場合がある。 認知的不協和が起きていないか、フラットに事実を眺める姿勢と、批判に対し、毅然と立ち向かう気持ちが大切であると感じた。 第三者として、失敗を認識させるうえで注意すべきポイントは、 ・健全な指摘を妨げる権威に注意する ・安易に他人を批判しない が挙げられる。 本書では手術室での医師の明らかに偏った判断に対し、周囲の看護師は強く指摘ができない例が挙げられている。またコクッピット内で、機長に対して副機長が意見しづらい構造的な問題が挙げられている。 安易な批判に関しては、民間航空機追撃事件を例に、一つの事柄も視点が変わると見え方が大きく変わり、実際には複雑に認識が絡まっているため、安易に誰かを悪者にはできないことが紹介されている。 ②成長の機会として活かす ・ランダム化テスト 失敗を正しく認識するためには、ランダム化テストが有効であることが挙げられている。Googleの青色フォントの選択の話やユニリーバのノズルの最適化の事例が紹介されている。 ・マージナルゲイン(一発逆転よりも、百発逆転) 失敗を効率よく成長に結びつけるには、マージナルゲイン(=小さな失敗と改善の積み重ね)が紹介されている。F-1のメルセデスベンツやイギリスの競技自転車チームのチームスカイの話が紹介されている。 ・固定型マインドセットと成長型マインドセット 失敗を活かすためには、成長型マインドセットを持つことが重要と説く。 固定型マインドセットとは、人間の能力は才能で決まっており、失敗は自分に才能がないことの証拠として捉える。一方で、成長型マインドセットでは、人間の能力は努力により伸ばすことができ、失敗は学習の機会として捉える。 その他として、事前検死という考えも紹介されている。事前検視とは、あるプロジェクトを開始する前に、メンバーに対し、リーダーがこのプロジェクトが失敗に終わったと告げ、各自はその状況を想像し、失敗した理由をできるだけあげるというものである。そうすることで、事前に失敗が想定され、対策が講じられる。
2投稿日: 2023.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白かった 失敗の向き合い方について学ぶことができた エピソードがハラハラドキドキするものが多く読み物としても面白かった
2投稿日: 2023.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ学術書のように固い表紙だけど小説のように読めて面白い。 300ページほどあって少し長めなので、寝る前の時間を利用して少しずつ読み進めました。 成長のカギは『失敗は隠ぺいせず、成長への一歩だと捉えること』とのことです。 航空業界で起きたミスは会社間を問わず世界中に共有され、改善策が整えられるということにとても驚きました。 降格とじゃあ医療業界は隠ぺい体質なのかと言いたくもなりますが、勿論書籍は医療業界を糾弾するような内容にはなっていません。医療業界が担っていることの複雑さも踏まえて、現状が冷静に分析されています。 だからこそしっかりと腹落ちし、未来に対してどのようなアクションを取っていけばいいのかを前向きに考えることが出来ました。 私は医療業界にも航空業界にも属していません。しかし話の道筋がとても論理的であり、事実を踏まえながらストーリー仕立てで進んでいくので、「自分だったらこの時こう考えそう」とか「この時の基調の気持ちはとても分かるなぁ」と経験にあてはめながら読み進めることが出来ました。
2投稿日: 2023.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗というのは小さいことも大きいことも個人でも団体でも頻繁に起きてしまう 失敗が起きる要因として本書の中で大きな要因として ①コミュニケーション不足 ②プライドが高く失敗を認めない ③失敗した時の懲罰が怖い が個人的に重要だと感じた どの要因も社会で働いていると、自分自身もそうだし他人もやっていることだからと思いそうになるが、大きな失敗というのは小さな失敗の積み重ねの上に起きるとされているので、気づいたことは素直に伝えていくような環境を作ることが重要だと再認識をさせられる一冊
2投稿日: 2023.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ不幸な医療事故から、計器トラブルによる航空機事故など ベテランのミスや上下関係の作用など実際の事故を通して 検証がされる。 現状維持のバイアス 確証バイアス 有害な固定観念が神聖化する。事例として、地動説と天動説。 失敗から学ぶ。古臭く陳腐化された言葉だが わかりきった事だけど、なかなか実行できない。
2投稿日: 2023.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗を恐れずにというのでなく、失敗は起こりうるものという観点で失敗しても隠すこと無くその原因を見極め次に繋げていく。誰かの責任にしないこと、スケープゴートを作らないことなど当たり前のことだが自分に降りかかるとできなかったりする。 航空業界と医療現場での対処の仕方違い、犯罪捜査での冤罪など具体的な例でわかりやすく解説。刑務所を見学した不良少年達のその後の人生など、非常に興味深かった。
2投稿日: 2023.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ読者に誤解を招かせないように、丁寧な記載を心がけていることが伝わり、とても読みやすい。過度な単純化や思い込みについて警鐘を鳴らしているが、わかりやすく伝える参考になりそう。 自分の会社でも、ミスが起こっていることすら気づかない、隠蔽しているとすら思っていない、失敗者は吊し上げというのは見かけるのだけど、どうしようもなくて徐々に絶望している。 ゴムアレルギーを指摘した医者のように、知識に裏付けされた責任感が必要なのだろう。
2投稿日: 2023.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗が価値のあるものだと感じさせられると同時に、失敗の与える負の感情、認知的不協和へ向き合う難しさを感じた。そして今の日本は失敗を見つけると条件反射で責め立てる人がまだ多いように感じる。様々な背景を想像すると、短絡的に批判する人を観ているだけで悲しくなる。また、より良くしていくためには、1%の改善を積み重ねるマージナルゲイン、あえて完璧でないものを世に出してフィードバックをもとに改善するリーンスタートアップ、成長型マインドセットなど、失敗から得られるポジティブな要素もたくさん。この本の内容から自分が学ぶとともに、これを他人にどう伝えていくかが自分の課題。 哲学者カール・ポパー 「真の無知とは、知識の欠如ではない。学習の拒絶である」 ヘンリーフォード「失敗は、より賢くやり直すためのチャンスにすぎない」 が刺さった。
2投稿日: 2023.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ完全に失敗を回避することは不可能であるということを強調しています。代わりに、失敗から学び、改善することが重要であるということが示されています。つまり、失敗を回避することに注力するのではなく、失敗が起こった際に、失敗から学び、改善するための取り組みを行うことが大切です。また、失敗を起こしやすい状況に陥らないためには、リスクを事前に見極め、予防策を講じることが重要です。
2投稿日: 2023.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗を認めることへの心理的抵抗を除去し、失敗した原因を検証し、次への改善に繋げることの重要性をすごく感じた。
2投稿日: 2023.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
印象に残っていること ・「小さな改善の積み重ね」により大きく前進する ・分かったつもりになるより明確な答えを求める ・人がもっともらしいと感じるのは、抽象的ではなく具体的で、偶然よりも誰かの意図や愚かさや才能が重要。ほんの少しの目を引く現象 ・失敗型アプローチをとるには、物事を素直に受け入れる気持ちと、根気強さが欠かせない 気付きや感想 ・今まで私が働いてきた環境は、失敗型のアプローチを取りやすい環境だったと思った。特に1社目は、失敗は新しいマニュアルを作るための進歩であり、クレームはサービス改善のヒントが詰まってると言ってた。新卒1年目でそういう環境で働けたことは幸運だと思う。 ・同時に、そういう環境を例えばクライアントに提案する必要に迫られた時、どうやって作ったら良いんだろう?啓蒙が必要なのはもちろん、仕組みも必要。本書でも仕組みに触れられていたけど、自分が提案できるように思わない…特に、課長・部長クラスから事業部長・役員クラスを巻き込みに行って提案しなければならないような環境の場合、イメージがつかない。。 ・たくさんの失敗に触れるので読みながらドキドキソワソワした。でも前向きに前進していく人が多かったので読み進めて気持ちよかった。自分もそういう気持ちの良い前向きさを持った人間でありたい。
2投稿日: 2023.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は学びの種。 失敗を隠蔽する体質の組織、個人は成長できない。 失敗を肯定し、原因を分析し、再発防止に努めることが成長への近道。 失敗を否定する姿勢からは、失敗を公表しない、誤魔化そうとする心理が生まれてしまうので、失敗を肯定することが大事。 バイアスによってどんなに科学的な証拠や客観的な確信があろうとも失敗を認められない「認知的不協和」が興味深かった。
2投稿日: 2023.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
僕が思っている以上に失敗を重要視する必要があると感じた。マイケル・ジョーダンもベッカムも失敗を学ぶもの、成長する糧にしてきた。失敗したときに悔しがるのと同時に新しく学べる。成長できるチャンスやと思ってワクワクできるくらいのマインドで行こう。 固定型マインドセット(才能は生まれつきと考える傾向の強い人)と成長型マインドセット(努力で才能伸びると考える人)では脳波で大きな違いが見られることがわかっている。またその実験の成績も後者ではより良い成績が出ている。 認知的不協和とは自分の信念と事実とが矛盾している状態、あるいはその状態によって生じる不快感やストレス状態を指す。こういう状態に陥ることはよくある。その時に2つの解決策がある。一つは自分の信念が間違っていたと認める。これが難しい。これができる人間になりたい。もう一つは否定。事実を否定して自分に都合の良い解釈をつける。これをすると人は成長できなくなる。自分が認知的不協和に陥った時はこれを思い出そう。 やり抜く力「GRIT」について軽く言及されていた。GRITの高さは知性や体力を凌駕するものであると。GRITについての本も読んでみよう。 日本人は失敗をビビりすぎている。日本の文化は失敗を不名誉なものと考えるので年間起業率も先進国で最下位らしい。アメリカの自動車王ヘンリフォードは2回も自動車の会社で失敗して三回目であの有名なフォードを作ったて成功させている。そんな彼の言葉は「失敗はより賢くやり直すためのチャンスに過ぎない。」 「自分の考えや行動が間違っていると指摘されるほどありがたいものはない。その御蔭で間違えが大きければ大きいほど大きな進歩を遂げられるのだから。批判を歓迎し、それに対して行動を起こす者は友情よりもそうした指摘を尊ぶと言っていい。己の地位に固執して批判を拒絶するものには成長は訪れない。」この言葉を忘れずに。
4投稿日: 2023.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ私たちが現代で快適な生活を送れているのは、先人たちが多くの失敗と誠実に向き合い、進化・成長を遂げてきたからだと実感しました。「失敗は成功のもと」という言葉があるが、それを具体的な事例をもとに科学的に解説してくれるような本書。 個人的には第4章のマージナル・ゲイン(大きなゴールを小さく分解して、小さな改善を積み重ねることで大きく前進できる)は仕事における目標設定をする際にも活かせると感じた。 具体例ベースで話が進行するので理解しやすい良書です。
2投稿日: 2023.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生、社会人問わずすべての人に読んでもらいたい良書 失敗から学ぶことの重要さや、 それを妨げる様々な要因(周りからの非難、自己正当化、認知的不協和など)が丁寧に書かれておりとても参考になった
2投稿日: 2023.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしい。スタンディングオベーション。手と足が足りないや。それくらい楽しく、深く読ませていただきました。 物事は複雑。しかも想像以上に。例えばもし、たった今飛行機事故が起きたら、まずは操縦を握っていた機長に責任があると人々(特にSNS)は吠える。だって、安全な着陸に必須の誘導電波を受信していなかったのだから。 しかし、本書曰く、本質を見抜くには、2週間前、5年前、あるいはもっと前までさかのぼって全体像を把握する必要がある。そこで初めて、裁判にかけられた機長が魔女狩り(犯人捜し)の対象として適任であったのか、そもそもその行為自体がどれだけ無意味/正しかったかの議論がなされる。 (ちなみに本書に出てくるエピソードたちはすべて衝撃的、悲しい、かつ腹立たしいため、より失敗に対する真剣度合が深まる。) なぜ私たちは失敗してもポジティブに捉えて前進するべきなのか。女子会のように、「既に理解してはいるけど、ただこのつらい気持ちを共感してほしくて...」という感覚で自己啓発書を求めている人たちはそれで良い。 でも、この本は論理的に、心の底から「そうなんだ」と読者を理解させたうえで、失敗に対する勇気を与えてくれる。だんだん聖書のようにさえ見えてくる(ちなみに私は無宗教です)。 実際読んでいる途中で、私は背中を押されて、仕事である自分の業務に対する周囲の評価が気になって、フィードバックアンケートを作成、次の日にはチームメンバー全員に記入するようお願いした。いつもの自分なら、悪い評価の内容を見るのが怖い(厳密には見るまでが怖い)のに、失敗に対する意識が変わり、恐怖がまるでなくなった。 定価2090円と決して安くはないけど、それ以上の価値なのか確実。4000円くらいでも買ってたかな。 注記が割と雑なのが個人的にはまた推せる。 おそらく注記の数が多すぎて、WEBリンク関連までタイトルをつけるのはページ数などの兼ね合いがあったのだろう笑 ずっとシリアスな話が続いていただけに、最後の最後で少し笑ってしまった笑 ちなみに著者はオックスフォード大を首席で卒業した、卓球の元オリンピック選手。現在はジャーナリスト。
5投稿日: 2023.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ『失敗』に対するアプローチをどのように行うか。どう評価するのか。 医療業界と航空業界では人の命を扱うという部分では共通しているが、『失敗』に対するアプローチが全く異なる。 自身の業務においても失敗に対するアプローチを変える事で、ネガティブな感情に支配されずに次に繋がるリアクションに変えていきたい!
4投稿日: 2023.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗という厄災は自然界の累積淘汰による進化のプロセスに過ぎず、計画的失敗の繰り返しが功を奏するようだ。 厄災を好奇にするのは個人では容易だが懲罰ある組織だと話が変わるだろう…
4投稿日: 2023.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ魔女狩りは簡単だけど、効果がない。それどころか本当の問題を隠す目眩ましになるだけということを、多くの人に気がついて欲しい。とりあえず「失敗の科学」を読もうか。そんな気持ちになる。 ひょっとすると極端な表現もあるのかもしれないけれど、この本で紹介されている医療や司法でのミスを隠蔽する体質を知ってしまうと、医者や検察にはまともなのがいないのかと感じるかもしれない。でも、その感覚がすでに目くらましにハマっている。 失敗を学びに変えるため必要なこととは。 ・安易に人のせいにしない ・原因が一つだと思い込まない ・ファクトやデータを確認する ・語られていない事象にも目を向ける ・そのために、失敗そのものではなく、その周辺の構造を良く観察する 特に最後は重要と思っていて、この本では「クローズドループ」という言葉で表現されているが、これは「システムシンキング」の考え方そのもの。 「失敗の科学」は、実際に起こった色々な事件を、巧みな文章構成で紹介していて、「失敗」を一元的な見方からひっくり返してくれる。そこからさらに勉強したければ、「システムシンキング」の領域に進んでいくと効果的かと思われる。 冤罪、医療過誤だけでなく、差別、民族紛争、戦争、あらゆることが、周辺の構造を観察することで、より深く理解できる。そのきっかけが得られるということで、この本は多くの人に読まれるべき本だと感じる。
4投稿日: 2023.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者のマシューサイドさんの本はどれもとても面白いです。 本書は「失敗」について考察した本です。 「失敗」は、誰にとってもつらいものだと思っていましたが、「失敗は、なくてはならない大事なものだ!」という本書の論旨はとても参考になりました。 「失敗したことを正直に話し、その問題解決に取り組むという」という姿勢は、日本人がもっとも苦手なことだとも思います。 「日本の長期低迷の原因がそこにありますよ!」とも書かれていて、とても納得できました。 「失敗してもいいんだ!」ではなく、「失敗は必要なもの!」というマインドが大切だとわかり、とても参考になりました! とてもよい良書なので、ぜひぜひ読んでみて下さい。
11投稿日: 2023.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログうまくいくためには進んで失敗をするべし!といった内容で、企業の具体的な失敗事例、成功事例が書かれていて非常に面白かった。 なぜ失敗をするべきなのかについても論理的に書かれていて面白かった。
3投稿日: 2023.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗許容の組織文化」の重要性 失敗から学習する風土は意識して作らなければ、本能には反する価値観 人は失敗を隠す。しかし失敗は、学習に欠かせない貴重な情報源。 ということは「失敗情報」を積極的に評価しないと組織にオープンにする風土はできない。 航空業界 徹底して失敗から学ぶ 失敗の事実を集め・分析・公表する 医療業界 認めたがらない 言い逃れの文化 「上下関係」(ヒエラルキー)がチームワークを崩壊させる 科学は常に「仮説」である カール・ポパー「反証可能性」 科学は自らの失敗に慎重に応えることにより発展を遂げる 「無謬」は進歩を止める(野口悠紀雄) ⇒試行錯誤し、進化せよ 計画経済は衰退する 企業淘汰がない 日本型社会主義経済も同じ運命 市場経済対計画経済(卒論のテーマ) 市場の失敗ではあったが「組織の学習」の視点はなかった 野中郁次郎 「検証」による修正の重要性 市場には試行錯誤のメカニズムが内在している 真の無知とは、知識の欠如ではない。学習の拒絶である。(K.ポパー)
3投稿日: 2022.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ名著と名高いので仕事に活きればいいなと思い読みました。各エピソードが刺激的でおもしろく、一般書なのに小説のように楽しく読めました。説教くささもなく説得力があり、仕事や私生活問わず意義あるメッセージが多くありました。失敗から学ぶこと、成長型のマインドセットを持って今日を取り組んでいきたいと思いました。
3投稿日: 2022.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ書店で見かけて興味持ち、購入。 失敗を恥ずかしいと思わず、改善のためのヒントにしていく姿勢が大切だと教えてくれる一冊。 第1章は航空機や医療など比較的聞く話だが、2章の認知的不協和の話は裁判の事例含め大変興味深く読むことができた。
3投稿日: 2022.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
業界特有の失敗への向き合い方等については、 航空業界の失敗の後の向き合い方を意識し、 大きな成長、その後の失敗をなくすことに 注力していきたい。 意識したいこととしては、 1)失敗を正直に捉えて、隠さず、むしろ表に出して 謝ることのできる人間になろう。 (失敗しても当たり前) 航空業界対医療業界 日本人はミスを恐れて、発言したがらない 2)あえて間違えることで、正解を探ろう (理論では分からないような解決法もある。 パターンを何個か用意して、実験的にやってみる) ユニリーバ 3)本当の解決策はそれなのか、物事を疑って考える (良いと思ってやっていることは、 対象者、非対象者で実験をしてみないとその仮説に よっての良い影響なのかわからない。 刑務所でのプログラムの事例 4)難問は切り刻もう (大きな目標を達成するためには 小さい目標を設定して、小さな仮設を立てて 実験していこう) ホットドッグ大食いの事例 5)物事は失敗ありきで、進めよう (完成形で進めるより、早いうちに叩き案を提示し、 お客さんに見ていただく方が、早いうちに 聞かないとわからない意見を聞くことができる) ボトムアップ型思考
3投稿日: 2022.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗はしてはならないもの、隠すもの…ではなく、学習の機会、どうしても起こってしまうものとして捉えていくといった内容の本だった。 こうしたマインドはなかなか日本だと受け入れられにくいのかなとも思ったが、組織でも個人でも成長のためには必要だろう
3投稿日: 2022.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶ姿勢、考え方が変わる一冊。 失敗やミスは必ず起きるから、そこから学ぶにはマインドを変えなければならない。 トライ&エラーで人類は進化してきた。 でもエラーを恐れて安全な道を行ったり、そのエラーを許容する組織でなければ隠したりもする。 人間は都合の良い生き物ですね。 なぜ失敗したか、どうすればよかったを考える力を持っているのが人間です。 そういう雰囲気や環境を作ることが組織としてまず第一に優先すべきことかなと思いました。 とても面白いのが起業することを恐れている人が多いのが日本人で、逆に少ないのがアメリカ人。 極端に起業の失敗を恐れてないアメリカではどんどん新陳代謝が起こり、今や世界の中心はアメリカですね。 すごい文化なんだなと思いました。 遅れを取らないように少しずつ変わっていきましょう。
3投稿日: 2022.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログトップダウン方式で決定されることの多くや知識は効果が実証されないまま見過ごされるという点に全く同感。今の日本の政治や企業文化そのものだと思う。ボトムアップで物事を動かすにはどうしたらいいだろうか、本当に考えさせられる。 失敗を葬り去るのではなく検証し役立てる、日本人の価値観はなかったことだけど、今こそすべきではないだろうか?
3投稿日: 2022.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗が嫌いなので、敵を知る意味で読む。 結論、失敗を歓迎しようということらしい。自分が取り組んでいることが、あくまで試作レベルのものでトライandエラーの途中にあるという認識を持って仕事をすれば失敗も歓迎できるのかなと思う。今自分がやってること、上司に相談していることはベータ版の話であって、指摘を食らうのは当然と思えれば、フットワークも軽くなるか
5投稿日: 2022.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は学習の機会でありポジティブなものとして捉えないといけない。隠すのではなく、勇気をもって開け広げることが自分と周囲の成長と気付きになる。前向きな気持ちになれる本だった。 以下、印象的な一文。 ・己の地位に固執して批判を拒絶する者に成長は訪れない。
3投稿日: 2022.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかくめちゃくちゃ面白い! 医療ミスを認めない医療業界と失敗は全てオープンにして改善してきた航空業界の違いからスタート。 「失敗から学ぶ」ことがいかに大事かをさまざまなエピソードを交えて解説している。 まるでNHKスペシャルを見ているような場面展開に 終始ドキドキワクワクが止まらない。 これを読んだら失敗するすることを恐れず、何事にも前向きに挑戦できる気がする。 問題なのは「認知的不協和」だ。気をつけよう。 とっても良書。
7投稿日: 2022.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ起きてしまった結果だけを聞くと「なぜそんな事が起きる?」と感じてしまう事を科学的に掘り下げた例をいくつも紹介してくれる。 内容の規模は違えど、自分の仕事でも似たような事は多々ある。 大きな失敗は心理的な側面に大きく左右されるようだ。 この本から学べた事は、失敗は悪い事ではなくかならず起きるもの。 悪い事はその失敗を認めない事、ちゃんと失敗を認めてフィードバックできる、失敗したと言える環境を作ること。 例として出てくる飛行機の事故。 航空業会はブラックボックスと言われる墜落後に墜落直前の機内の音声を聞くことができる極秘の箱があるという。 その箱で事故直前に何が起きていたかを確認、分析して全航空業界へ報告とこう言った事故をどうすれば防げるかが共有される。 その内容は飛行機本体のボタンの配置にまで及ぶという。本当によくできた仕組みだ。 人は誰しも失敗はする。 この本を読む前と読んだ後では、自分も含めて失敗した人への態度も随分変わる。 松下幸之助も「雨が降ったら傘をさす」と言っているが正にその内容に近い。 雨が降ったらみんな傘をさすのに、なぜかビジネスの世界では大雨なのに傘もささずに自らずぶ濡れになる行動を起こす人の多い事。 素直になって、感情に流されず、ずぶ濡れにならないように行動するのがいかに難しい事か。 ちょうど、並行で読んでいたものと偶然にも内容がリンクした。 こういったところも読書の楽しさであると実感した。
4投稿日: 2022.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ良書であることは知ってたけれど、時間がなくて先送りしていた本。 固定型マインドセットと成長型マインドセットは、他の文献ではカチコチ・マインドセットとしなやか・マインドセットと紹介されていたり、事前検死は悪魔の代弁者(デビルズ・アドボケート)というチェック方法になってたりする。 失敗から学ぶ姿勢と、失敗を責めるのではなく学習機会にするという個人や組織のマインドって大切だと改めて考える。
3投稿日: 2022.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗を恐れるな、とはいうものの現実問題としてそれは難しい。 自分のプライドは崩れるし、周りには迷惑がかかり評判はがた落ち。その失敗が人の命にかかわるものなら世間一般からも大バッシングを浴びる。しかしどれだけ注意しても、どうしても失敗は起こってしまうもの。 悲惨な医療事故や航空機事故、冤罪事件、プロスポーツ選手など様々な事例から失敗に至る過程や心理の分析。そして失敗を生かすことができる社会や組織、個人に必要なものは何か。失敗を生かすメリットはどこにあるのか。それらを徹底的に考察したのがこの一冊です。 まず失敗に至る過程にはまず何があるのか。様々な事例から見えてくるのは、失敗する人が自身の間違いを認められなかったり、他の意見を受け入れられないケースが目立ちます。 突発的な事態に集中するあまり、他の手段や危険な点に思い至らなかった医療事故や航空機事故の事例は、詳細な描写もあいまって思わず心が冷え込むほどの怖さを感じました。そして冤罪事件の事例では、自身の判断が絶対というバイアスがかかって、自分の判断ミスに気づかなくなる。 そういう失敗を防ぐにはどうすればいいのか。ポイントは過去の失敗の事例を集め、それをつぶしていくこと。そのためには失敗に寛容な組織であることが大切。 失敗の報告を受けたら
5投稿日: 2022.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗をすることはとても重要であり、そこから学ぶことでのみ成長をすることが出来ると説く本です。とても引き込まれて、一気に読むことができました。 たくさんの事例と共に話が進み、そこから私たちは何を学ぶことができるかを説明してくれます。宗教的考えの脆さ、失敗は許されないという思想、医療業界の問題点など、なるほど〜が連発でした。 失敗を恐れるマインドセットが顕著な国として、私たちの母国日本がピックアップされていたのにはビックリでした。日本で育つとなかなか自分たちのことを客観的に見ることは難しいですが、このような気づきを与えてくれるのは読書のいいところだなと思います。
3投稿日: 2022.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ事例が多く、読み応えがありました。 当方、ミスや失敗が多く「このミス報告するのやめとこかな」と思ったこともあります。(隠蔽が発覚したときのリスクのほうが大きいので、いちおう報告はします) 医療ミスを繰り返してしまう医療現場と、事故を徹底的に分析する航空機業界。その違いは「システム」と「マインド」です。 難しいのが、いくらシステムをととのえても、失敗に対してオープンで正直な文化が根付いていない組織の中では運用されないというところ。上層部含めたスタッフたちの失敗に対する捉え方を変えて隠蔽体質をなくす仕組みやマインドセットがまず必要になってきます。 …これができないから失敗は繰り返されるんですよね。 「訓練」というかたちで定期的に研修に取り入れるなどが良いのではないでしょうか。その際は課題図書に本書を読んでもらいたいものです。 この本の中には失敗を活かすアプローチとして • マージナル・ゲイン • リーン・スタートアップ • RCT • 事前検死 このような手法を紹介していました。 私は事前検死(プレモータム)がプロジェクト内で実施しやすく、メンバー全員で知恵を出し合うことで効果が最大になる興味深いアプローチだと思いました。個人でやっても有効だと思いますが、個人レベルのアイデアだと限界がありますが、チームで行うとプロジェクトに対して否定的だと受け止められることを恐れず、懸念事項をオープンに話し合うことができるのです。 本書にも究極の「フェイルファスト」手法だと書いてありましたが、新人社員に対してベテランたちが、「早く失敗しろ」という意味あいで使うことがあり、「失敗ありき」の文化を作るにはとても良いと思いました。
3投稿日: 2022.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗とは何か。。停滞と保身しか生まない失敗と、進化に繋がる失敗の違いとは何か。 体面とか面子とかプライドとか、というものは、失敗から何かを得ようとするための 障害にしかならないのだけれど、そういうものっていざって時に顔を出すからまぁ厄介ですよね…特にことムラ社会気質の強い日本人にとっては。
3投稿日: 2022.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗から学ぶ」大切さを強く感じた。マージナルゲインを継続するための成長思考を持ち続けたい。 そのために正しいデータを取ることを意識したい。 →自分の実生活に活かせること ・ドラムを毎日少しずつでも練習する。録音を撮り、変化を記録する ・元々目指していた成功と、現状のギャップを知る。なぜその結果になっているか分析し、毎日少しずつ改善してみる。記録に残す。 ・他人の失敗を聞き、次の活かし方を一緒に考える。
4投稿日: 2022.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗を恐れちゃあいけない。 恐れるべきは、失敗から学べずまた同じ失敗をし続けてしまうこと。 本書は、医療業界、航空業界の事例を挙げる中で「失敗」に対してどういうマインドを持つべきか学べる本だ。 僕は失敗を恐れる方だ。 できれば失敗したくないと思うし、もし失敗したら自分を責めるタイプだ。 でも失敗は学習のチャンスだと思えるのなら、それは自分の成長に対して失敗を恐れてあれこれ考えるより大きな学びとなるのだと感じた。 ○改善の最強の原動力は、失敗から学ぼうとする姿勢にある ○改善すべきは、人間の心理を考慮しないシステム ○失敗を見過ごせば、学習も更新もできない ○完璧主義よりも実践あるのみ。失敗から学ぶ検証作業が成功のカギ ○データに基づいた検証を行う ○分からなければ、とりあえず実践 ○組織づくりでは、失敗を学習のチャンスと捉える文化づくりが大切。 失敗に対する非難だけでは何も生み出せない。 失敗を隠したくなる環境ではダメ。 ○裁く側の人間を信頼することが出来て初めて、人はオープンになり、結果失敗を報告出来るようになる ○成功に向けて努力するが、そのプロセスに失敗は欠かせないと認識する。
4投稿日: 2022.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログめちゃくちゃ面白いし参考になる。 職場の全員に読んでほしい。 職場が失敗をこの本のように捉えられるように なれば働きやすいしどんどん環境が良くなると思う。
6投稿日: 2022.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
挑戦を繰り返すから失敗がある。じゃぁ、挑戦しなければ失敗に向き合わなくても良いのではないか?と思えばそうもいかない。これだけ方法論へのアクセスが簡単になり、かつどの先進国も成長率が頭打ちとなる中、挑戦しないことには満足な成長を続けることができなくなっているからだ。つまりこのような本を失敗から常にポジティブなメッセージを抽出して解決力のレベルを上げようと心がける習慣を支えるハンドブックとしたい。 私は、失敗に対して重要な点は3つあると考える。 1.失敗を「厄災」としてではなく、学びの機会として捉える「成長マインドセット」を持つこと 2.致命的な事態となる前に、小さな失敗の段階で対処すること 3.最も困難な課題として、失敗する前に気づくことができるか――これは「無知の無知」から「無知の知」への転換と言える 本書では、上記のうち1と2に焦点が当てられている。具体的な手法として、マージナル・ゲイン、リーン・スタートアップ、RCT、事前検死などが紹介されている。これらはすべて、人間が持つ「認知バイアス」から脱却するための方策だ。 私たちは「仮説」に過ぎないものを真理として信じ込んだり(無謬性)、問題を過度に単純化しすぎたり、犯人探しに固執したりする傾向がある。こうしてプロジェクトは、「期待」から「幻滅」し、ついには「パニック」に陥って「犯人探し」が始まり「無実の人が処罰され」「無関係な人に報酬が支払われる」(プロジェクトの6段階P.160)のである。 これらは「無知の無知」状態にあるときであり、いかにして失敗のシグナルを察知し、周囲からの忠告に耳を傾け(批判は友情より尊い!)、「無知の知」へと転換できるかが問われている。
3投稿日: 2022.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の失敗だけでなく他人の失敗からも学ぼう。なぜなら自分だけの経験では得られない量と質を得られるから。 認知的不協和の影響で最も失敗から学ぶ事が出来ていないのはトップの人間。 プロジェクトの6段階→1.期待 2.幻滅 3.パニック 4.犯人探し 5.無実の人を処罰 6.無関係な人を報奨 何より重要なのは、失敗に対する考え方に革命を起こすこと。 失敗することは何も恥ずべくことではない。失敗を経験しそれを修正する(トライアンドエラー)事が重要。 まずは自分の失敗を探し、埋もれさせないこと。 見つけたら即座にフィードバックを行う。 関係する仕事についても同様。
3投稿日: 2022.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学習できる者と、失敗を失敗と受け止めてそれを活かそうとしない者、言葉にするのは簡単であるが、前者が成長していくのである。前半だけで読み疲れて飽きてくるが、自己を改めるキッカケになる。日本人は失敗を恥と思ったり、批判の対象とするが、その失敗を改善して前に進むことが大きくなる力だとしっかり肝に銘じるべきである。
3投稿日: 2022.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ数々の失敗事例が紹介されている。どれか1つぐらいは身近に感じるのがあると思う。 なぜ失敗するのか、失敗を隠すのか、失敗を非難するのか、多くの学びがある。 「第6章 究極の成果をもたらすマインドセット」で失敗に対する姿勢を紹介しているのも良い。人は学び成長できると考えることが大事。
3投稿日: 2022.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ0 どんな本? 組織の成長に関する知見を失敗という切り口から 実例を通して紹介する本。ミスを意義深いものにし た実例とミスで悲しい結末を迎えた実例を紹介して いる大事な本。涙ながら読みました。 1 何で読んだの? (1) 何かのオススメで登録していたから。 (2) 自己成長や子育てに役立てたい。 (3) ミスに対する具体的な対処方法を学んだ状態に なりたい。 2 構 成 全7章構成330頁 マーティンの妻に起こった悲しい医療過誤からはじ まり、マーティンの取り組みの10年後の取材シーン で終わる。 3 著者の問題提起 失敗をどうすれば成長出来るか?失敗とは何か? 4 命題に至った理由 成功を収めた人々や組織には共通点があることに 気づいたから。 5 著者の解 失敗に対する前向きで健全な姿勢 6 重要な語句・文 (1) 認知的不協和 (2) 犯人探しバイアス (3) フィードバック (4) RCT (5) 反証 (6) マージナルゲイン (7) リーンスタートアップ (8) 事前検死 (9) 暗闇でのゴルフ 7 感 想 子供が大きくなったら読んでもらいたいと思った。 1番刺さったのはマーティンが妻の死を世界の医療に 役立てた事。深く知りたい事はマージナルゲイン。人 に勧めるなら犯人探しバイアス。グラフからRCTを 学ぶ事ができた。失敗の科学と言うタイトル通りの素 敵な本。哲学とも通じている。 8 todo (1) 失敗を感知したら改善策成長策を講じる習慣を 作る。(オープンループ) ア フィードバック イ 具体的な事後の行動(マージナルゲイン) ウ RCT取り入れる事が出来るならやってみる。 (2) 事前検死をやってみる。(とりあえず趣味で) 9 問 い 失敗とは何か? 10 答 え 人類に内在するバイアスが影響する悪い結果。 悪い結果を前向きで健全な姿勢でいる事により、良 い結果にする事を組織、世界で共有出来る。
4投稿日: 2022.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・『小説のように面白い』という帯は確かに!という内容で、失敗のエピソードはどれもハラハラドキドキさせるものが多く、ビジネス書らしくなくて面白かった。 ・本書の中でわたしがこれから取り入れたいと思うことは「事前検死」という考え方。『心理学者ゲイリークラインが提唱』した考え方で、『検死(post-mortem)」をもじった造語で、プロジェクトが終わったあとではなく、実施前に行う検証を指す。あらかじめプロジェクトが失敗した状態を想定し、「なぜうまくいかなかったのか?」をチームで事前検証していくのだ。』 思えば、前職ではプロジェクト開始時点で同じようなことをやっていたな、と(当時は、形式的にやるのみだったけれど)思い出し、独立した今、目の前の仕事をやる際にどうしても視野が狭まるので、多角的に考えるためにも、立ち止まって「失敗した」と仮定して自分の仕事を見直す機会を作ろうと思った。
3投稿日: 2022.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は恥ずべきことではなく、進化の過程に欠かせないもの。失敗を受け入れる体制を作り、共有することが必要。
3投稿日: 2022.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰しも失敗はしたくない。 失敗しても何らかなもっともらしい理由を付け回避不可能だったこととして精神の安定を保とうとする。 失敗から学ぶものとそもそも失敗と認識しない、できないものとの差は広がるばかりだ。 失敗を改善へのアプローチとする姿勢について学ぶことは成長への近道だと思い本書を読んだ。 失敗を活かせない原因は何か。 間違ったことに対するフィードバックがない。 自分の信念に固執するあまり事実をねじ曲げる。 自分の知っている特定パターンにはめて後付け解釈して真実まで辿り着かない、また単純化し過ぎて本質を見誤る。 なぜこのようなスタンスになるのか。 多様性に欠けた単一、同一な思考で見てしまう。 すばらしいアイデアも試されることなく机上の空論と化している。 立場、権威があるほど失うものが大きく保身に向かう。 どのようなアプローチで失敗を改善へつなげるか。 表れていないデータも含めあらゆる情報を検証し、真実を見抜く意志を保つ。 理想と現実のギャップを埋める仕組み作り。 裁く側の人間と信頼関係を築き隠蔽体質を回避する。 シンプルだが常に失敗を失敗と認め学ぶ姿勢が大事。 特定の思考に固執することなく様々な視点、データを検証する探究心や多様性を持ち躊躇なく申告できる信頼関係の構築が必要だ。
3投稿日: 2022.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は成長には不可欠である。 失敗を失敗のままにしておくのは、多くの犠牲者を出したままにしているのと同じ。 ●組織 失敗を活かせる組織であるかそうでないかは、 失敗が起こった時、適切に問題が解明され、改善策がとられるのかどうか、もしくは失敗をひた隠しにするか。 間違いを教えてくれるフィードバックがなければ、長い訓練や経験は意味をなさない。 だから人事や心理療法などは、蓄積がしにくい なぜなら正解が証明されないから。 企業や組織が失敗から学ぶためには、失敗を次に活かそうとするシステムと、スタッフからの情報提供が必須。 ●個人のマインドセット 失敗をどう捉えるかという個人のマインドセット が成長に大きく影響する。 成長型マインドセットの性質がある人は、知性も才能も努力によって伸びると考える。 失敗を次への成長と喜び、批判を歓迎する。 ●知性の獲得とは 宗教が第一義だった時代は知性は与えられるものであり、その間人間の発展は止まった。知性は自ら探究し、検証し続けることで獲得できる。 今の幸福や技術は多くの先人の失敗の積み重ねの成果なのだ。次の時代を生きる誰かを助けるために、失敗を検証し続けるべし!
3投稿日: 2022.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログきちんと検証を行いましょう 大きな問題は小さな問題に切り刻んでマージナルゲインを目指せ 失敗への非難は思考を停止する。失敗の数を増やせ
3投稿日: 2022.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ自社を含めて日本の企業には、「失敗を恐れて挑戦しない」、「失敗した時は犯人探しの挙句、推進者が責任を取らされる」企業風土が根付いている。 石橋を叩いても渡らない品質審査、責任者を不明確にするための稟議システムなど欧米企業だけでなく中国韓国企業の後塵を排する有様。 全てを「失敗ありき」で設計する、商品開発の場合では初期段階でフェイルファースト手法「事前検死」を組み込む、、、など。
3投稿日: 2022.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ英『タイムズ』紙の第一級コラムニストの著作。『多様性の科学』に先行する著作 でもある。 原題は、Black Box Thinking なので、失敗の科学というのは、ちょっとずれているが、あらゆる失敗に通じる一流の組織が備える「原因」と「学習システム」のすべてを語っている。
3投稿日: 2022.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学べない業界(例:医療業界)では大きいものも小さいものも含めると毎日相当な医療過誤が起こっている。一方で、失敗から徹底的に学ぶ業界(例:航空業界)ではほとんど事故は発生しない。航空業界ではパイロットのミスは罰せられることはないし、積極的なミス/ニアミスの開示が奨励されている。ミスの報告ができない最悪の状態(墜落など)に陥っても、ブラックボックスの録音記録を掘り起こして徹底的な原因究明の調査が行われるそうだ。すげー。 失敗に付属するネガティブイメージを払拭しなくてはならない。これからは失敗って言わずに反証って言おう。失敗した、ガーン!ではなく、これにトライしたから、これが正しくないことがわかった、よかった、反証できた!というマインドで生きていこう。
3投稿日: 2022.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ思っていた以上に良い本だった。最後に筆者も言ってる「失敗から学ぶ」というよくある格言を本当に理解して、思考と行動に落とし込む為のヒントを事例を交えながらの説明で分かりやすかった。繰り返し読みたいと思います。
3投稿日: 2022.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 以前失敗した状況と同じシチュエーションにいるか気づく能力。教訓を得ることはできても、それを活かせるか否かでパフォーマンスは決定する。
3投稿日: 2022.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルは、ちょっと難しそうなイメージだが、中身は様々な事例に基づいた内容で、わかりやすかった。失敗に対するアプローチについて考えさせられた。仕事、家庭、子育てなど、人生に置いてどんなことにも共通する内容だと感じた。 周りにも進めたいと思う素晴らしい本!
3投稿日: 2022.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗から学ぶこと=成長 企業や学習、国政に至るまで、理念の根幹に関わるお話 【瞬読79冊目 40文字 9行(1ページ) 毎分8800文字】 失敗を肯定、恐れない。失敗から学び、改善していくことが大事。 上下関係で下の者が意見を言えるか、上の者が意見を受け止められるかが重要(航空業界ではクルー・リソース・マネジメント)訓練がある。 マージナル・ゲイン(小さな改善)リーン・スタートアップ(小さく始める) RCT(ランダム化比較試験)が重要。 事前検死(失敗をしたらと仮定して原因を考える)を行う。 失敗が許されない、国政、医療、裁判に最も欠けている考え方。失敗しても改善していく、成長マインドセット。 失敗を罰すると隠すようになる。今の社会問題に発展している。医療過誤、国政の失敗など。失敗が許されない人ほど、失敗を恐れ、失敗から学ばない。 固定マインドセットは成長を阻害する。宗教的に弾圧された科学の衰退によって、世界は進化を止めている(地動説の否定、瀉血治療など)今はそれが国政、医療、裁判で起こっている国が多い。 失敗から学び、安全を保っているのは航空業界。 最初の医療過誤で犠牲になった家族の十年後に筆者がインタビューを行っている様子が書かれている。悲劇から成長し力強く進んだ先に届き始めた世界中の医療従事者からの信頼と称賛、患者の感謝の声に胸が熱くなった。
6投稿日: 2022.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ激推し! 失敗は恥ずかしいものでも汚らわしいものでもなく、賢くやり直すためのチャンスに過ぎないという本。事例として挙げられるエピソードが全部衝撃的⚡️ 目から鱗の本。 Kindle Unlimited対象です
3投稿日: 2022.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
目新しいことは書いてない。 「失敗は成功の元」とするための組織、仕掛け の重要性を様々な実例が記載されている 以下備忘メモ 成功は仮説の修正 つまり失敗によってしか成し遂げられない 失敗を認めることは、このうえなく屈辱的 ゆえに、失敗から学ぶためには収集する仕組みが必要 失敗を報告することに対しては称賛を与える 失敗の報告は正義と言ってもいい 犯人探しで安易な安堵を手にしてはいけない それに早期から気づいたのが航空業界 失敗が報告されなければ、 当然次の改善に活かされることはない 人はサンクコストによって認知的不協和に陥る ここまで頑張ったから、自分はこんなに優秀だから 間違えているわけがない。と解釈や記憶を編集する 優秀な人ほど、これに陥る 失敗成功の因果関係は、 ランダム化比較試験によってのみ判断できる 毎回これを行うことはできないかもしれないが 安易にこれが成功・失敗要因と考えないこと とにかくたくさんの失敗と 修正検証を行なった人だけが成功する 事前検死という手法 プロジェクトが失敗したという体で、 なぜ失敗したのか理由を出し続ける →通常見えてこなかった要因が出てくる
3投稿日: 2022.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ単なる自己啓発本ではない。膨大な事例とその語り口によって新たな事実が休むまもなく突きつけられる。 また、事例一つ一つが実に興味深く、ページをめくる手が止まらなかった。 読んで後悔しない一冊だと思う。
7投稿日: 2022.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ得られるものの多い一冊だった。 第2章「人はウソを隠すのではなく信じ込む」の冒頭に凄惨な強姦殺人事件の描写が数行含まれるので、苦手な方やトラウマを持っている方はご注意を。
4投稿日: 2022.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「進んで失敗する意志がない限り、このルールを見つけ出す可能性はまずない。しかしほとんどの人は間違った仮説から抜け出せない。間違った仮説から抜け出す唯一の方法は、失敗をすることだ。」 ■感想 ・失敗の本質も良いがこの本もなかなか。失敗から学ぶこと、その本質は飛行機のブラックボックスのようにデータを取ることとフィードバックがあることか。 ・戦時の飛行機の撃墜検証。その飛行機が集中的に銃で打たれてるところではなく、打たれていないところこそ補強する話(つまり、当たれても帰還できる、打たれたら帰還できてないという、目の前にないデータを見ること)の納得感はやばい。目に見えるデータだけが全てではない。盲目になってはならないし多面的に物事が見られると良い。 ・認知的不協和の章も納得がいく。一度信じたことを手放せない。サンクコストバイアスに近いか。手放すこと、積み減らすことができる勇気を持とう。 ・全体的にバイアスの話も多く、論調としてはファクトフルネスに似てる印象。だから売れてるのかも ・ランダム化比較試験大事。とにかく行政も失敗を見ようとしない、成功側面だけ捉えがちだから本質に至れないのかも。
3投稿日: 2022.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗」をどのように受け止めて活かしていくかを教えてくれる本。 「失敗は成功のもと」という言葉があるように、成功するために失敗することが必要なのだと、失敗に対する考え方を変えてくれる本だと思う。
3投稿日: 2022.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗についての事例がたくさん書いてあり、参考になった。 失敗を認められない組織、ミスを責めることでよりミスの発覚が遅れてしまう話、耳が痛い 自分の発言や見たものさえも無意識に歪めてしまう可能性があるのは怖いなと思った
1投稿日: 2022.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗のメカニズムとその後の対応の重要さを具体例をまじえて説く本 失敗は恥ずかしいので、失敗した時は隠したり事実の解釈を捻じ曲げる(認知的不協和)ことはさまざまな場所でよくあることである。 さらに人は事件が起こると表面を見て犯人を探し非難したがるのでなおさら失敗を認められない。 失敗を認められない人は成長しない。 成長するには失敗を繰り返すことが欠かせないものであることを理解することがとても大切。
1投稿日: 2022.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ医療業界と航空業界の失敗に対するアプローチの違いから始まり、様々な業界・職種の失敗に関するエピソードを紹介、失敗をすることと失敗を認めることの重要性を説く。 成長と成功のために失敗を認めよう、積極的に失敗しよう、人の失敗を非難しないようにしよう。 自分の考えと事実が違っているときに起こる認知的不協和、これを緩和しようとするため人は間違いを認めなくなる。有名人であればあるほど認知的不協和が大きくなり余計に間違いを認めなくなる。しかもその失敗を活かさないので成長しなくなるとのこと。確かにこういう人はよく見る。
1投稿日: 2022.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功する人はつい、才能があるからだとその人固有の能力が要因だとされがちである。しかし、成功者のほとんどが幾多の失敗を繰り返し、その失敗に対してイライラしたり癇癪を起こしたりしながらも耐えて、そして努力し続けてやっと辿り着ける道のりなのだと。デイビッドベッカムなど種々の人の例を通して紹介されていた。 そういう人たちのマインドセットは得手して、成長型と呼ばれ、失敗が大前提にある。失敗して試行錯誤を繰り返していくことが成功につながる。 昔から言われているありきたりの言葉ではあるが、心から受け入れて実践している人は少ないように思う。そういう私も、失敗を恐れるあまり一歩が踏み出せないことがよくあって、この本を読んでみて改めて、失敗する勇気をもらえた。 ちなみに、マシューサイドさんの本で「多様性の科学」があるが、この2冊に共通することがあると感じた。 それは、「寛容さ」だ。 自分だけでなく、他者に対しても寛容になること。それが組織の発展や個人の成長につながっていることを種々の論文や科学的研究によって証明されている。 とはいえ、深く理解せずにエビデンスがあれば大丈夫というエビデンス信者になるわけではなく、一つ一つのケースに合わせて考える批判的吟味が大切なのだろう。 昨今ビッグデータからAI分析し、エビデンスを大量生産できる時代になってきたが、その抽象化の中で削ぎ落とされる具体性の中にある価値も忘れずに、マス的発想と個々のストーリーの両方を行き来しながら、両方大切にできるようになりたい。
6投稿日: 2022.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の「多様性の科学」を先に読んで非常に面白かったので、これも読んでみた。これもとても良い。ナシーム・タレブと同じく失敗を活かすことの重要性を科学的・実証的に証明してくれる。ノズルの開発の部分などは白眉。日本はこの考え方と真逆の文化なので、是非政策に取り入れてもらいたい。
1投稿日: 2022.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は権威のある人ほど隠す、または失敗していると認知しない 失敗したことをデータから判断できるといい。主観的なそれらしい意見に流されないように。 人は犯人探しをしたがるが、失敗の本質を見極めて。 そしてあえて失敗するのが大事。
1投稿日: 2022.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗の原因及び対処法について科学的に書かれた本。 ただし、単純に失敗の原因を追求しているので、思わぬ原因が失敗の原因となっていることに驚きを隠せない。 対処法もただただ追求するのではなく、改善するための方法がそっち?と思う程、世の中の当たり前を覆す本だ。 組織を運営する人は絶対読んでいてほしい!
1投稿日: 2022.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗から物事を見るという普段あまり意識しない観点について具体的なデータなどを通じて納得することができた。あえて失敗することでそこから何が足りないかを学び、これからにいかすことは意識的にやらないとなかなか習慣化しにくいと思う。 以下ハイライトのコピー 何か失敗したときに、「この失敗を調査するために時間を費やす価値はあるだろうか?」と疑問を持つのは間違いだ。時間を費やさなかったせいで失うものは大きい。失敗を見過ごせば、学習も更新もできないのだから。 失敗から学ぶためには、目の前に見えていないデータも含めたすべてのデータを考慮に入れなければいけない。次に、失敗から学ぶのはいつも簡単というわけではない。そんなときはこのケースのように、注意深く考える力と、物事の奥底にある真実を見抜いてやろうという意志が不可欠だ。これは爆撃機や軍の問題だけでなく、ビジネス、政治、その他さまざまな分野に当てはまる。 正しいかどうか試してみる」を実行に移すには大きな障壁がある。実は我々は知らないうちに、世の中を過度に単純化していることが多い。ついつい「どうせ答えはもうわかっているんだから、わざわざ試す必要もないだろう」と考えてしまうのだ。 「失敗型」のアプローチでとくに注目すべきは、成果そのものよりも、トップダウン方式を重視した従来の価値観に風穴を開けたことだ。「失敗型」アプローチをとるには、物事を素直に受け入れる気持ちと、根気強さが欠かせない。 「小さな改善の積み重ねですよ」彼の答えは明快だった。「大きなゴールを小さく分解して、一つひとつ改善して積み重ねていけば、大きく前進できるんです」 成長型マインドセット( growth mindset)」の傾向がある人は、知性も才能も努力によって伸びると考える。先天的なものがどうであれ、根気強く努力を続ければ、自分の資質をさらに高めて成長できると信じている。 失敗から学べる人と学べない人の違いは、突き詰めて言えば、失敗の受け止め方の違いだ。成長型マインドセットの人は、失敗を自分の力を伸ばす上で欠かせないものとしてごく自然に受け止めている。一方、固定型マインドセットの人は、生まれつき才能や知性に恵まれた人が成功すると考えているために、失敗を「自分に才能がない証拠」と受け止める。人から評価される状況は、彼らにとって大きな脅威となる。
1投稿日: 2022.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗から学ぶこと」の難しさと生み出す効果の大きさがよく分かりました。 「失敗は成功のもと」という慣用句はその通りなんだけど、成功のもとにするためには非難や懲罰を課すのではダメで、謙虚に学ぶことが大事と言うことがよくわかる事例満載。辛い事例も多いからこそ、学ばなければならないことが身に染みる。 F1の事例が出てくる。NetflixでF1のドキュメントを同時期に見たこともあり、背景がわかってよかった。
1投稿日: 2022.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶ。よく聞く言葉だが、その意義がよく分かる本。誰もが失敗をしたくないと思う。しかし、失敗からこそ沢山のことを学ぶことができる。 失敗を責めず、嫌がらず、冷静に分析して次に繋げていきたい。 失敗が怖くなったら、また読み返したい。
1投稿日: 2022.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗って何だろう? そもそも失敗することは恥ずかしいこと、間違っていることという認識がおかしいのだと思う。どんな事でも失敗するという前提で物事を進めていき、どのようにリカバリーをするべきかにフォーカスを当てる必要があるのではないか。 学びが多い本でした。これからの行動に落とし込んでいきます。
4投稿日: 2022.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗の、、、というタイトルだが、成功するための意識改革になりそうだ。 全ては失敗ありき。 だからこそ慎重にシステムを構築できる。 検証して次に生かす、ということの大切さ。 とてもわかりやすく多くの事例を挙げて説明されている。 RCT 、マージナルゲインなど、耳慣れない言葉だったが、日常生活にも応用できる。 私の場合、特に家事と仕事の両立に応用できるのではないか。 あー、もうやることいっぱいで疲れるーとなっている1日を、小さく分解してみようと思った
1投稿日: 2022.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルから失敗についての研究なのかという印象を受けましたが、良い意味で期待を裏切られました。原題のBLACKBOX THINKINGの方から想起される、成功のための思考法という方が良いかも。 イギリスの自転車チームで有名なマージナルゲインの考え方を、アフリカへの支援が実際にもたらす影響を検証するランダム比較試験RCT、メルセデスのF1チームがタイヤの交換用工具にセンサーをつけてPDCAをまわしていく等の例から説明していたのがとても分かりやすかったです。
3投稿日: 2022.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学んでいくためにはどうすればいいのか、色々な例が取り上げられている。 発言のしやすい雰囲気、RCT、間違えることを前提とすべき、細かい単位で検証することで大きな成長が得られる。
1投稿日: 2022.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ何か失敗が起きた時に、安易に人を非難するべきではない。 誰かに責任を押し付けるという、最も簡単な結論に逃げることで、組織はその失敗から学ぶ機会を失ってしまう。 また、非難の文化が根付くことにより、ミスにつながる行動をしてしまった人は、隠蔽工作に走ることがある。 各人が、何が起こったのかを正確に報告することによって初めて、失敗を分析することができ、根本原因を解決することができる。 みたいなことが書いてあった。 僕も仕事でよく隠蔽工作をしていたため、刺さった。
3投稿日: 2022.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み応えのある良書でした。 ただ、個人的にはカタカナ名前が頻出する文章が読みづらく、読み切るまでにかなり時間が掛かってしまいました。 クローズドループ現象や、根本的な帰属の誤りによる課題を説明し、失敗から学ぶ姿勢が人類の進歩するために重要であるのこと。 マージナルゲイン、事前検死、RCTなどによる手法でバイアスから逃れて前に進める意義は学びになりました。 アクションプランとしては、 いますぐできる、事前検死からスタートしていこうと思います。
1投稿日: 2022.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際に起きた事件の事例を通し、様々な分野の企業の失敗との向き合う姿勢を紹介している。 物語の中から教訓を学ぶのが好みの人にはおすすめ。個人的には事例が長すぎるうえ、科学的なアプローチによる解説がほぼなかったのがマイナス。 得られることも多々あるので、読み方を工夫すれば 積読できるかな。 エッセンス ・失敗に向き合うために必要な2つの要素は、適切なシステムとマインドセット ・真の無知とは、知識の欠如ではない。学習の拒絶である ・成長型マインドセットの人は、失敗を自分の力を伸ばす上で欠かせないものとしてごく自然に受け止めている
1投稿日: 2022.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログまず自分たちの失敗を認めない限り、我々はそこから学ぶことはできない。 失敗に真正面から取り組めば成長できるが、逃げれば何も学べない。 失敗は、より賢くやり直すためのチャンスにすぎない。
1投稿日: 2022.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログまとめ 1 失敗は学び、放置せずにフィードバック 2 認知的不協和の恐ろしさ、反証すること 3 進化=選択の連続、経験的知見、発明か理論か・トップダウンかボトムアップか・行動か思想か、量か質か、ランダム化比較試験、反事実の検証、選択バイアス、リーンスタートアップ 4 マージナル・ゲイン=小さな改善、大きい要素でも小さく分解してランダム化比較試験で最適化 5 非難をしない 6 失敗から学ばない傾向を克服する方法 成長型マインドセットであること(⇔固定型) ①失敗の受け止め方「失敗は成長のために必要だからと自然に受け止める」 ②合理的に諦める 終章 自由市場⇔計画経済 自由主義社会⇔社会的同調 個人においては「生活の実験」を行うこと マージナル・ゲイン=大きなゴールを小さく分解、小さな改善に リーン・スタートアップ=早期の段階から検証と軌道修正の繰り返し RCT 事前検死 クローズドループ現象 失敗を放置、進歩なし オープンルーズ現象 失敗を適切に対処、進歩 失敗から学ぶ要素 ①システム ②マインドセット 1 医療業界は失敗を放置、航空業界失敗をは徹底分析 失敗をデータの山と捉える 上下関係でもはっきりと言う、ベテランでも間違える 集中しすぎによって時間を食う、時間感覚 熱意が足りないからとかモチベーションのせいではない、慢心していたで片付けてはいけない、その時の心理的な原因とかもある、しっかり原因を特定してシステム化 航空業界と医療業界 第二次世界大戦の帰還した爆撃機、帰還しなかった爆撃機の話、全てのデータを見ること ハドソン川の奇跡の話 フィードバック、結果が分かることの重要性、失敗から学べる、暗闇でゴルフの練習と同じこと 科学は失敗の連続 失敗はやる気とかの問題ではなく、物事の捉え方である、失敗への考え方 2 なぜ人は失敗から学ぶことが困難なのか、失敗を認めない、失敗を隠すのはなぜ 司法制度、冤罪、DNA鑑定という発明によって多くが冤罪であると判明 ★カルト集団、教祖の予言外れてもさらに熱心に信じる、不都合な真実と解釈の塗り替え ①過ちを認める ②真実の解釈を変える このうち②を選んでしまう、自分は頭がいいと思っている、自尊心が脅かされる、【認知的不協和】 ⚠️ネクステ入ってそんな解釈をしてしまっていないか? 隠すのではなく、信じ込む 「加入儀式」が大変なものほど 認知的不協和状態に陥っていることを自覚できない 自尊心が学びを妨げる 株の話、損失はその株を買った自分の判断が間違っていたという動かしがたい証拠、下落した株を持ち続ける、いつかきっと利益出ると。逆に値上がり株はすぐ利益出したい、自分が合っているという証拠が手に入る 2,4,6の数列の並ぶルールを見つける話、10,12,14で確かめるより、失敗例を確かめなければ分からない、例えば4,5,11、12,10,8、間違っているかどうかを確認すること 自分の仮説に溺れないこと、反証=自分の仮説に反する数列をみつけること ルイセンコの悲劇 記憶は「編集」可能 バイアス 3 考えるな間違えろ、失敗を超高速で繰り返せ 失敗から学ぶには①システム、②マインドセット この章は②マインドセットについて 進歩や革新は頭の中だけで美しく組み立てられた計画から生まれるものではない。生物の進化もそうだ。進化にそもそも計画などない。生物たちが周りの世界に適応しながら世代を重ねて変異していく。 進化とは選択の繰り返し、これが自然淘汰 自由市場のシステムが支持されているのも生物学的進化をなぞっているから 計画経済は誰も失敗しないから進化しない 頭で考えた仮説を検証、実践で失敗と選択を繰り返す 発明は理論に先立つ、蒸気機関の発明から熱力学第二法則の例※行動は思考に先立つと言ってもいいかもね 「ユークリッドがユークリッド幾何学を発明して建築が発達したのではなく」「ユークリッドが建築の経験的知見からユークリッド幾何学を編み出して建築が発達した」 論理的知識と実践的知識の両方が存在して、それぞれが交差し合って前進している ★数学的トップダウン式か生物学的ボトムアップ式か 世界を単純化しすぎている、正しいかどうかを確かめていない、、、 ★完璧主義の罠①トップダウンに重きおきすぎ、理論、思想ばっか、、、、②失敗への恐怖 例:陶芸クラスの実験、量か質か 検証と軌道修正の繰り返し 反事実は目に見えない、Webサイトのデザインを更新したら売り上げ伸びた、本当にそうか?、ほかのよういんでたまたまそうなっただけ? ランダム化比較試験(RCT)、反事実の検証 選択バイアス、瀉血で生き残った人の意見だけの偏ったデータ 4 難問はまず切り刻め ツール・ド・フランス アフリカへの経済的援助は必要か不必要か、ランダム化比較試験難しい、地球温暖化も→分解する、教科書は配るべきかなど 大きな目立つ要素よりも小さな要素を極限まで最適化 大食い選手権、日本人の話 5 犯人探しバイアスとの闘い この章は心理的・組織文化的要件について 何か間違えが起きると誰の責任かを追求することに気を取られる 内因→認知的不協和、外因→非難 根本的な帰属の誤り=人の原因を性格的な要因に求め、状況的な要因を軽視する傾向、例 車が隣車線から割り込んでくる 非難は単純、世の中はもっと複雑、我々はシンプルで都合の良いストーリーが好き 失敗から学ぶ、失敗の報告を促す開放的な組織文化を目指せ、そのためには非難をやめること 非難することで、相手は責任感を強く持つようになると言う思い込み、逆効果 6 マインドセット、失敗から学ばない傾向を克服する方法、内的=認知的不協和、外的=非難な問題を乗り越えるには ベッカムの例、失敗は欠かせない 失敗から学べる人と学べない人の違い=失敗の受け止め方 固定型マインドセット→自分に才能がない証拠と受け止める、成長型マインドセット→成長のために必要だからと自然に受け止める ○日本に起業家が少ないのは「失敗=恥」という文化 →アメリカ8人に1人が起業意識あり、日本は1.9% →起業失敗に対する恐怖心が最も高かったのは日本人 終章 失敗と人類の進化 宗教で新たな思想は認められず批判排除、変わったのは古代ギリシャから、誤りは厄介から好機へと変わった、言語の誕生以来の大進歩 その後また固定マインドセットの時代に ガリレオ 自然科学は発展したが社会科学は未だ停滞、検証・誤りを認めてきたかどうか 正解を出した者だけを褒めたら「一度も失敗せずに成功を手に入れられる」という誤った認識 失敗型アプローチ=事前検死 失敗を想定して、なぜうまくいかなかったのか事前検証する
1投稿日: 2022.03.14
