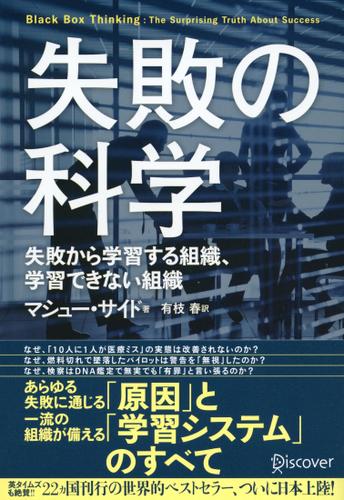
総合評価
(310件)| 173 | ||
| 84 | ||
| 32 | ||
| 0 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜか以前に読んだ「失敗の本質」の焼き直しの本かと思い込んで、しばらく手に取らなかった本 読んでよかった 医療業界、航空業界が「失敗」をどのように活かしたのかの例から始まって、法曹界が失敗に学ぼうとしないことが痛烈に批判されている その通り なんとかならないかと思う 裁判にはランダム化比較試験が使えないし、マージナルゲインを導入する糸口も考えつかない 自分の仕事を少しずつ改善していくしかないんだろうなぁ 日本社会の失敗を許さないマインドセットについて特に言及されていて、世界的に共有された認識なんだと恥ずかしくなる とりあえず、今日から自分の失敗を毎日ピックアップする作業から始めよう
1投稿日: 2022.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に良い本です。組織の中で働く人は全員読んだ方が良いくらい、学びの多い内容でした。 具体例と、そこから導き出される結論の割合がとても良く、読んでいて楽しいですし、単に楽しいだけでなく、理論に裏打ちされた中身になっています。 自分が働く場所も航空業界のように学び続ける仕組みを持ちたいと強く思いました。
1投稿日: 2022.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ『社会全体で考えても、失敗に対する姿勢は矛盾している。我々は自分の失敗には言い訳をするくせに、人が間違いを犯すとすぐに責め立てる』 『失敗に対してオープンで正直な文化があれば、組織全体が失敗から学べる。そこから改善が進んでいく』 『多くの場合、人は自分の信念と相反する事実を突き付けられると、自分の過ちを認めるよりも、事実の解釈を変えてしまう。次から次へと都合のいい言い訳をして、自分を正当化してしまう』 『我々は、反復作業が多くて面倒なボトムアップ式の前進をついおろそかにしがちだ。トップダウン式で考えたほうが楽なのだがら仕方ない』 『一発逆転より百発逆転、いきなりホームランを狙ってはいけない』 『問題は「誰の責任か?」でも「責任の追及すべきミスと、偶発的なミスとの境界線はどこにあるのか?」でもない…「処遇を判断する立場の人間を、スタッフは信頼しているか?」だ。裁く側の人間を信頼することができて初めて、人はオープンになり、その結果、勤勉にもなる』 失敗をどう捉えるか?次の成果に導くためには失敗から学ぶ事は、あまりにも多すぎる。 でも何故それができないのか?誰もがその事をわかっていても。 失敗をオープンにする風土、組織文化がそこにはあるだろうか?失敗した者を非難したり、無能だと決めつけていないだろうか? 『ビジネスリーダーや教師ばかりでなく、我々も社会人として、また親として、失敗に対する考え方を変えていかなくてはならない。子どもたちの心に、失敗は恥ずかしいものでも汚らわしいものでもなく、学習の支えになるものだと刻みつけなければならない』
1投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ・事例の記述で何度も泣いてしまった ・人命に関わる業務でなくとも、失敗に真摯に向き合い教訓とすることは極めて大切 ・本書を通して自分達が暗闇でゴルフをしていたのではないかと気付かされ、ゾッとした ・今後はRCTによる結果検証はマストとしてアプローチの見直しを図りたい
1投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗に対する考え方が変わった。成長のカギは失敗とどう向き合うか。本書は自分で失敗の全部を経験するには人生が短すぎるとし、様々な失敗例を学ばせてくれる。失敗から学ぶ姿勢が人生を飛躍させるのだろう。
1投稿日: 2022.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2022/02/18 読了@Kindle Unlimited 「失敗」は「成功の素」だよね、と改めて思った本。 驚きだったのは、単純な医療ミスで奥さんを亡くした人ですら、その失敗を認めてそこから学ぼうとするのであれば、許していること。 絶対許せないような内容だと思っていたけど、人はそんなに冷たくはないんだね。 素直に「失敗」を認めた人を断罪するのではなくて、 失敗を許して、そこから学ぼうとする社会になればいいな。
1投稿日: 2022.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ航空業界の失敗に対するアプローチ よく飛行機事故に遭う確率は自動車事故に遭う確率よりも低いって言われる。それは徹底的に失敗から学ぶシステム整備がなされていたから。。
1投稿日: 2022.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗の本質読了後、日本的官僚組織(今時の言葉で言うとJTC的な)について、学びを進めたいと考えて「組織」、「失敗」というキーワードで辿り着きました。 近年の言葉を使うのであれば、「アンラーニング」が引っかかってきます。今までの学びから脱却し、メタ認知をすることが重要で、かつそれが個人の問題に矮小化せずに「組織」の問題として捉えることが必要だと感じました。 構造が読み進めやすいです。キャッチーな、よく言えば感情的なインパクトのあるエピソードを踏まえつつ、そこからの学びを抽出して紹介していく流れです。 逆に言えば、感情によって読者の納得を得ようとする構造は好みが分かれるような気がしました。自分はあまり好きではありませんでした(この本の論理が劣っているということは意味しませんが)。
1投稿日: 2022.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗したことを分析し、より良い改善を続けていくことがいかに重要かというのが分かる内容だった。本書の事例で扱われているような、航空業界や医療業界などの話だけでなく、自身の日常生活も小さなことから失敗を恐れずにいろんなことにチャレンジしていきたいと思えるような内容だった。
1投稿日: 2022.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗をしたくない、いつもいつもそう思って生きてきた。 むしろ今もそう。 なぜか? ・恥ずかしい ・自分の無力さを思い知って落ち込みたくない ・スムーズに進まず時間を浪費するのがイヤ などなど… そしてそのように思ってきた分、自分にとっての挑戦は事前準備をして臨みある程度満足する成果も出せてきた。 ただ、自分が成功できるモノにしか挑戦してきていないとも言える。 本書で登場する著名人は「失敗しても良いではなく、失敗は必須だ」と語る。 本当にそうだと思う。 そして取り組みとして面白かったのがPJに取り組む際、「このPJは失敗した。なぜか?」と問い、考えること。 そうすることで、想定していない「失敗」も事前に想定できて対応出来ること。 私は「反証」が苦手なので、この考えはそんな私でも想像しやすく感じた。 失敗を極力避ける私は自分では中々チャレンジ出来ない… その分、今の仕事で「チャレンジ業務」として与えられるミッションは大変だがとても助かっている。 (本来はもっと自分から飛び込むことが望ましいと思うが…) 苦戦して失敗しながら進む分、謙虚にもなれるし、他者へ助けや助言を求めることも少しずつ出来るようになってきた。 「失敗」 やっぱり好きではないが、挑戦し、そこから学ぶ人でありたい。
1投稿日: 2022.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログとても良い本。別途、ちゃんと書評をまとめる。 失敗を受け入れるマインド、それを反映する仕組みが大切。 航空業界にはあって、医療業界にはなかった。自分の心は、失敗を素直に受け入れられているだろうか?
1投稿日: 2022.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗から学ぶ」という学習において最も重要だが見過ごされがちなトピックを解説した本。ミスが大きな事態につながる医療や航空業界、科学の歴史などの事例をもってミスが起こったときの人間心理、なぜ人は失敗から学べないのかなどを紐解いていく。 科学読み物の中でもかなり読みやすく面白い本です。
1投稿日: 2022.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗すること、それを真正面から受け止め次に生かすこと、がなぜ重要かを数多くの実例と共に明らかにした良書。なぜ重要か?に力点が置かれており、じゃあ今からどうしたらいいのか?への回答は十分ではないと感じるかもしれない。その答えは読者一人一人に委ねられているのだろうし、それっぽい答えを安易に用意していない点に好感が持てる。
3投稿日: 2022.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗した際に大切なのは、原因の追究と学習である。組織や業界によって失敗から学びを得る力に差はあるが、これらは失敗した原因を追究できるシステムと個々のスタッフの意識によって左右される。特に責任感や影響力が高いトップ層の人間は、失敗を認められず方向転換できない場面が多い。 ビジネスマンとして常々言われる、失敗からの学びの重要性について様々な実例を挙げながら分析している。経営トップ層として自分の芯を曲げないことも大切だが、暗雲が立ち込めた際に過ちを認め迅速にプロジェクトの舵を取ることも容易ではないだろう。
3投稿日: 2022.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶ。子供でも知っている事が出来ていない。学ぼうとしていない。保身や非難やめて失敗から学んでより良い人生を歩みたい。
1投稿日: 2022.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事していると、失敗に対して寛容でなかった自分を反省した。寛容というのも間違えた表現かもしれない。失敗は、成功するまためのプロセスとして重要なデータとして扱うことにしよう。 また失敗すること前提が自分にとって金言である
1投稿日: 2022.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は成功(失敗)プロセスを科学的に分析しており、個人のマインドセットとして以下の点を持つよう説いている。 ⑴失敗ありきで物事を考える ⑵何事にもやり抜くことを意識する ⑶常に仮説を持ち、当たり前の事にも疑いを持つ 本書は様々な事例を列挙することで、「失敗の捉え方」を示している。 本来、失敗は悪であり容認するべきでないと考えるが、最初から正解に辿り着く事象など、この世にない。現状当たり前とされていることも、幾多の失敗を積み重ね、それを分析・仮説立て・検証したからこそ今の姿が確立されたと言える。 つまり、失敗したことが悪ではなく、その失敗を科学的に分析し、どう活かすかが大事なのである。 また、成功も偶然の産物ではなく、なぜ成功できたのかを掘り下げることで、確実性がより増す。 その為には、仕事やプライベートにおいても、①失敗を許容するマインドや雰囲気を持ち、②各事象を分析することーで更なる成長を図れると考える。 本書を通して、失敗の捉え方を再構築できたとともに、成功事例にも目をむけ、「次より良くするには」の視点で自省・分析し、行動していきたい。
3投稿日: 2022.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は災厄ではなく機会である。成長マインドセットを持って、日常生活で、マージナルゲインを意識して、小さい改善を積み上げていくべし‼️ 組織についての本だけど、個人の生き方の指針にもなる、超名著‼️
5投稿日: 2022.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「また親として、失敗に対する考え方を変えていかなくてはならない。子どもたちの心に、失敗は恥ずかしいものでも汚らわしいものでもなく、学習の支えになるものだと刻みつけなければならない。」 失敗に対する見方が変わった。子供を育てる上でも、子供が失敗した時の、親としての対応を考え直すきっかけになった。
3投稿日: 2022.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ登録わすれ 去年から読み終わったと思います。 仕事面においても、 生活面においても 大変刺激された本だった。 読んだ時期が丁度私の状況と合っていたこともあり、 星5個
1投稿日: 2022.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗を非難せず共有することで、社会はより良くなっていく。せめて自分の失敗からは目を背けず、成長の糧にしようと思った。失敗の理由を知ることは大事。
1投稿日: 2022.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ【感想】 誰しもミスは報告したくないものだ。 ミスを報告するとその対応に追われるし、もちろん自らの評価も下がる。自分が100%悪いと分かっていても、「相手側にも過失があった」と都合よく解釈をねじまげ、自分の行いを正当化する。言い訳を重ねるうちに、ミスがいつしか「不運」になり、そのうち「巻き込まれ事故」に変わっていってしまう。そうすると、もはや間違いを犯したという意識が無くなり、よくある一つのトラブルとして改善されることなく闇に消えていく……。 本書では、各業界で起こった重大事故をもとに、このような「失敗を活かすことができない典型例」を浮き彫りにしつつ、人や組織が失敗からどのように学ぶことで成功につなげられるかのメソッドを論じている。 文中で大きくピックアップされるのは航空業界と医療業界だ。この2つはどちらも「一つのミスが利用者の命に直結する」仕事をしている。ジャンボジェット機の墜落事故や医師の誤認による医療事故等のエピソードを交えながら、失敗を招いた原因と、その後各業界はどう対策を行っていったか(orなぜ対策しようとしなかったのか)について紹介していく。 結論から言ってしまうと、失敗を成功につなげられるか否かを決めるのは、失敗そのものに強く注目することではない。「失敗に対する」姿勢を前向きにすることだ。 具体的には、 ①失敗を「不名誉なもの」として捉えない ②失敗を調査し、改善につなげるためのシステムを構築する。一つのミスから組織や業界全体が学べる体制を整える。 ③失敗を正直に認める。同時に、周囲も失敗を非難したりせず、ミスを報告しやすい土壌を作る。 ④失敗を幾度となく繰り返す。そして失敗を真正面から受け止め、「やはり自分はダメなんだ」ではなく、「自分を進化させるチャンスだ」というマインドセットを身に着ける。 である。 航空業界ではこの仕組みが整備されていた。 墜落事故が起こっても、機内に搭載したブラックボックスによって事故直前の飛行データとパイロットの音声データを解析し、事故の原因を調査できる。事故調査は強い権限を持つ独立の調査機関が行い、調査報告書には勧告が記載され、「航空会社」にそれを履行する責任が発生する。事故をパイロットやクルーだけの問題にしない風土があり、例えば、パイロットはミスを起こすと報告書を提出するが、10日以内に提出すれば処罰されないという制度が存在する。 一方医療業界では、事故が起こった経緯について日常的なデータ収集をしていない。医療ミスは医師の責任として医療訴訟を起こされる。また、医師は看護師よりも権限が強いとみなされ、トップダウン型の指揮系統のもとで多様な意見が阻害される。医療スタッフは失敗を不名誉なモノと決め、エラーマネジメントの訓練をほとんど受けていない。 こうした「失敗に対する姿勢」の差が、両業界における事故率の差となって現れているのだ。 さて、では組織の進化のために些細なミスでも報告してもらおう、と考えるが、そう上手くはいかない。人はミスを「隠す」からだ。 ここからは私個人の意見だが、人が失敗を報告しないのは、失敗のメリットが短期的に実感できないことが一因だと思っている。 上手い失敗は成功に繋がるが、その効果が現われるのはずっと後。ミスの要因を分析し、それをシステムに吸収して改善を促し、新しく運用を始めてからである。成功のためには長い道のりを我慢しなければならない一方で、失敗は今まさに身の上に降りかかっている。この現実に直面すると多くの人が「今苦労してまで改善する必要がある?」という考えに走り、短期的な楽さを選んでしまう。しかも自分が引き起こした「過失」なのか、致し方ない事情により発生した「不運」なのかはっきり判断がつかない場合は、なおさら自分の行動を正当化して包み隠してしまう。そのほうが早いし、隠蔽したほうが「短期的」には得だからだ。 また、「迅速すぎる」後処理を求められることも原因の一つだと思う。 不祥事が起こると必ず、「二度と失敗をしないための対策」を課される企業が多いだろう。例えば個人情報の流出であれば、データ管理方法の見直しやデータ消去時の二重チェック体制の構築などだ。こうした対策に本当に効果があるのかは、検証に長い時間を費やす。しかし、世間はそこまで長いこと待ってくれない。ミスを改善するのは「今」であり、求められているのは「いかに迅速に対応する姿勢を見せたか」である。結果として、効果の不明瞭な対応を場当たり的に行い、ヒューマンリソースが削られ、似たようなミスが再び起こってしまう。いずれもミスのデメリットとメリットのタイムラグが引き起こす悲劇である。 これらも全て「失敗に対する姿勢」だとするならば、おそらく、失敗を成功につなげるのは相当に忍耐強く鍛錬を積まなければならないだろう。人は楽をする生き物だし、得になるか分からない失敗の後始末など誰しもつけたくない。個人で意識的に行っていくのは中々ハードなため、組織ぐるみでミスへのリカバリー体制を整えていくのが必須なのではないかと感じた。 ―――――――――――――――――――――――――――――― 【まとめ】 1 失敗による損失 アメリカでは毎年4万4000~9万8000人が、回避可能な医療過誤によって死亡している。また、1日1000件の回避可能な死亡事故が起こり、1万件の回避可能な合併症が起こっている。 なぜそこまで些細なミスが起きるのか?過労や医療の複雑性といった要因が考えられるが、本当の原因はもっと奥深いところにある。誰もが失敗を隠そうとするからだ。 失敗を隠そうとするのは、それを「不名誉なもの」とする考えが古くからあるからに他ならない。本書の目的は、失敗のとらえ方を根本から覆し、仕事や日常生活で「究極のパフォーマンス」を引き出すことにある。我々は今、個人として、組織として、社会として、失敗との付き合い方を見直さなければならない。 2 クローズドループ 「クローズド・ループ」とは、失敗や欠陥にかかわる情報が放置されたり曲解されたりして、進歩につながらない現象や状態を指す。逆に「オープン・ループ」では、失敗は適切に対処され、学習の機会や進化がもたらされる。 航空業界はオープン・ループにより航空事故を防いでいる。ヒューマンエラー(人的ミス)の多くは設計が不十分なシステムによって引き起こされるため、ブラックボックスを用いて数々の事故原因を、機長たちのやりとりや航空データをもとに解明している。 一方、医療業界はこれまで、事故が起こった経緯について日常的なデータ収集をしてこなかった。医療業界では当事者の視点でしかものを見ていないため、潜在的な問題に誰も気づかない。彼らにとって問題は存在さえしていない。クローズド・ループ現象が長引く原因のひとつがこれであり、失敗は調査されなければ失敗と認識されないのだ。 何か失敗したときに、「この失敗を調査するために時間を費やす価値はあるだろうか?」と疑問を持つのは間違いだ。時間を費やさなかったせいで失うものは大きい。医療過誤のコストは、控えめに見積もってもアメリカだけで170億ドルにのぼる。2015年3月現在で、英・国民保健サービス訴訟局は、過失責任の賠償費用として261億ポンドの予算を計上した。 失敗から学ぶことは決して資金の無駄使いではない。むしろ、最も効率的な節約手段だ。資金だけでなく、人命も無駄にせずに済む。 失敗に対してオープンで正直な文化があれば、組織全体が失敗から学べる。そこから改善が進んでいく。 失敗から学ぶにはふたつの要素が不可欠だ。1つ目はシステム。失敗は、いわば理想(したいことや起こってほしいこと)と現実(実際に起こったこと)とのギャップだ。最先端の組織は常にこのギャップを埋める努力をしているが、そのためには学習チャンスを最大限に活かすシステム作りが欠かせない。2つ目に不可欠な要素はスタッフだ。どんなにすばらしいシステムを導入しても、中で働くスタッフからの情報提供がなければ何も始まらない。 3 情報の形 医療業界の大きな問題は、失敗から学ぶシステムが整っていないことに加え、たとえミスが発覚しても、学びが業界全体で共有されていないことにある。 医療業界では、必要な知識や情報が、使用に適したシンプルで効果的な形に置き換えられていない。 航空業界でも、もし何ページにもわたる要領を得ないデータを共有するとなれば、臨床医が医学雑誌で毎年ほぼ70万件も発表される論文と闘っている状態と変わらなくなり、学びが「形」として共有されなくなってしまう。幸いなことに、航空事故の調査レポートでは、情報を(精製して)現実的に要点をまとめてある。 4 人は失敗を認めない 失敗に対する事例は、医療業界に限ったものではない。刑事司法制度における冤罪もその一例だ。 イリノイ州ウォキーガン市で起こった少女殺害事件。その犯人として服役していたのがフアン・リベラという青年だった。 服役してからすでに13年が経とうとしていたが、2005年、DNA鑑定によって遺体に付着していた性液がリベラのものではないことが判明する。しかしながら、彼はさらに6年間を刑務所で過ごすことになった。 DNA鑑定によって無実の人が自由を取り戻す道のりは、耐えがたいほど困難だ。自分たちが間違っていたという明白な証拠を突き付けられてもなお、誤りを認めようとしない制度がそこにある。 しかしどうしてそんなことになるのだろう? 「失敗を認められない」というその心理は、いったい何がどうなれば、人の心や制度にそこまで深く根を張るのか? それは多くの場合、人は自分の信念と相反する事実を突き付けられると、自分の過ちを認めるよりも、事実の解釈を変えてしまうからだ。 カギとなるのは「認知的不協和」だ。これはフェスティンガーが提唱した概念で、自分の信念と事実とが矛盾している状態、あるいはその矛盾によって生じる不快感やストレス状態を指す。 人はたいてい、自分は頭が良くて筋の通った人間だと思っている。自分の判断は正しくて、簡単にだまされたりしないと信じている。だからこそ、その信念に反する事実が出てきたときに、自尊心が脅され、おかしなことになってしまう。 そんな状態に陥ったときの解決策はふたつだ。自分が間違っていたと認める。しかしこれが難しい。理由は簡単、怖いのだ。そこで出てくるのが2つ目の解決策、否定だ。事実をあるがままに受け入れず、自分に都合のいい解釈を付ける。あるいは事実を完全に無視したり、忘れたりしてしまう。そして認知的不協和に陥っている人間は、そのことに滅多に気づかない。 事実をありのままに受け入れることは難しい。大きな決断であれ、小さな判断であれ、当人の自尊心を脅かすものなら何でも認知的不協和の引き金になる。いや、むしろ問題の規模が大きければ大きいほど、自尊心への脅威も大きくなっていく。だから手術中の事故は「よくあること」と処理され、DNA鑑定の結果は「未起訴の射精者」を生み、教祖の予言が外れると「自分たちが信じたから、神様が世界を救ってくれた」と感激するのだ。 明晰な頭脳を誇る高名な学者ほど、失敗によって失うものが大きい。だから世界的に影響力のある人々(本来なら、社会に新たな学びを提供するべき人々)が、必死になって自己正当化に走ってしまう。保身への強い衝動に駆られ、潤沢な資金を自由に使って、自分の信念と事実とのギャップを埋めるのだ。失敗から学ぶことなく、事実のほうをねじ曲げて。 5 失敗し続ける 失敗からうまく学んでいる組織は、どこも例外なく、ある特定のプロセスを実践している。「試行錯誤」だ。 進化は自然淘汰によって、つまり「選択の繰り返し」によって起こる。適応力の強い個体が生き残って子孫を残すと、その中から突然変異によってさらに強みを得た個体が生まれ、その後次々と世代を重ねて進化が進んでいく。 こうした適応の積み重ねは「累積淘汰(累積的選択)」と呼ばれるメカニズムである。累積淘汰は世代ごとにおこなった選択を記憶し、それを次世代へ、また次の世代へ、と引き継いでいくシステムだ。自然界における進化のプロセスであり、自由市場における倒産と起業のプロセスでもある。 つまるところ、テクノロジーの進歩の裏には、論理的知識と実践的知識の両方の存在があって、それぞれが複雑に交差し合いながら前進を支えている。 我々は知らないうちに、世の中を過度に単純化していることが多い。ついつい「どうせ答えはもうわかっているんだから、わざわざ試す必要もないだろう」と考えてしまう。「正しいかどうか試してみる」を実行に移す、つまりボトムアップ型の検証をおろそかにしてしまうのだ。 大切なのは完璧主義者にならないことだ。早い段階で試行錯誤し、いくつも失敗を重ね、検証と軌道修正を繰り返し、ユーザーのフィードバックを得続けることが肝心である。 6 小さな改善 大きなゴールを分割し、「小さな改善(マージナルゲイン)」を積み重ねていけば、大きく前進できる。 7 非難 何かミスが起こったときに、「担当者の不注意だ!」「怠慢だ!」と真っ先に非難が始まる環境では、誰でも失敗を隠したくなる。非難すると、相手はかえって責任を果たさなくなる可能性がある。ミスの報告を避け、状況の改善のために進んで意見を出すこともしなくなる。 しかし、もし「失敗は学習のチャンス」ととらえる組織文化が根付いていれば、非難よりもまず、何が起こったのかを詳しく調査しようという意志が働くだろう。 適切な調査を行えば、ふたつのチャンスがもたらされる。ひとつは貴重な学習のチャンス。失敗から学んで潜在的な問題を解決できれば、組織の進化につながる。もうひとつは、オープンな組織文化を構築するチャンス。ミスを犯しても不当に非難されなければ、当事者は自分の偶発的なミスや、それにかかわる重要な情報を進んで報告するようになる。するとさらに進化の勢いは増していく。 8 失敗から学ぶためにはどうすればいいのか? 失敗から学べる人と学べない人の違いは、突き詰めて言えば、失敗の受け止め方の違いだ。成長型マインドセットの人は、失敗を自分の力を伸ばす上で欠かせないものとしてごく自然に受け止めている。 成長型マインドセットについては大きな誤解がつきまとう。成長型マインドセットの人は、無理なタスクにも粘り強くがんばり続けてしまうのではないか、達成できないことに取り組み続けて、人生を無駄にするのではないか、と。 しかし、実際はその逆だ。成長型マインドセットの人ほど、あきらめる判断を合理的に下す。 ドウェックは言う。「成長型マインドセットの人にとって、『自分にはこの問題の解決に必要なスキルが足りない』という判断を阻むものは何もない。彼らは自分の〝欠陥〟を晒すことを恐れたり恥じたりすることなく、自由にあきらめることができる」 我々が最も早く進化を遂げる方法は、失敗に真正面から向き合い、そこから学ぶことなのだ。
32投稿日: 2022.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学びましょうね、という説教くさい本なのかな〜という予想は裏切られた。 事例が豊富で読みやすく、説得力がある。自転車、F1、ベッカムといったスポーツ関係の事例も出てきてとっつきやすい。 最初に出てくるエレインの医療事故は読んでいて胸が痛くなった… 本書で再三、失敗を学習機会と捉えて向上を続ける理想的な環境として扱われる航空業界ですら、魔女狩りの誘惑に耐えられないこともある。それがもたらした結末はあまりにも悲劇的。 失敗の短絡的な非難と犯人探しはつい反射的にとってしまう反応だが、そのクセが組織の風土を作り上げていくということは肝に銘じなければいけないなと思った。
3投稿日: 2021.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学習するためには、正しい観測とフィードバックが大事。 認知的不協和により冤罪や犯人探しが生まれる。 失敗を非難するのではなく共有することを奨励する文化・心理的安全性が、組織には必要。
1投稿日: 2021.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗とは 責任の所在を、人を非難しがちだか 問題はどこにあるのか 弁明でなく情報を 根本的な帰属の誤り
1投稿日: 2021.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ人に失敗かは学びましょう、自分で全て経験するには短すぎます 失敗から学ばなければいけない。そのためには失敗を認知し、なぜおこったのかを振り返ることが重要である。人は時々、ミスしたことを認めないように振る舞ったり責任転嫁したり犯人探しをしたりしようとする。しかし、それは自分を守るための行動で組織として、また個人として成長していくためには振り返ることが重要である。それによりまたトライすることでマージナルゲインを獲得していくことができる。 心理的安全性の本でも書かれていたが、組織としてオープンにすることでミスに向き合うことができる。 それらの手法としてこの中ではRCTや事前検死があげられている。これらによってミスをしたとしても暗闇でゴルフの練習をするのではなく、光のもとでフィードバックを得ながら取り組んでいくことができる。
4投稿日: 2021.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗を活かす重要性と方法を、多様な実例を交えて説いた良書。 人は自分を守るため嘘を本当と思い込む生き物。成功したと思っていても、客観データで確認することで、実は失敗だったということも起こりうる。 失敗のほとんどは他者が経験したものであり、他者の失敗を活かすことが成功の近道。 人は単純化して悪者を作る傾向があるが、失敗の多くは複合的な何かの組み合わせであるため、単に責任を問うだけでは失敗を隠すようになる。 失敗を成長に活かすには小さな失敗を繰り返して少しずつ改善を繰り返すことが重要。
1投稿日: 2021.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログマージナル・ゲイン、リーンスタート・アップ、RCT、事前検死、などなど。個人の話で言うと、結局マインドセットになってくるなー
0投稿日: 2021.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログまず冒頭の事例からグイグイ世界観に引き込まれて一気に読み終わってしまった。様々な失敗の事例が色んな角度から検証されていてまさに「目からウロコ」状態だった。 確かに、失敗は成功の基という故事が昔からあるように失敗することは改善のチャンス。それは当たり前で誰しもが理解してると思う。 が、ほとんどの人ができない理由が詳しく述べられている。 わいも該当する。どうしても直視できない。失敗を認めることの難しさ。さらに、失敗を分析して次に繋げる難しさ。何度も読み返したくなる本です。
1投稿日: 2021.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗が成長につながることを頭ではわかっているももの、行動に移せないのが自身の課題だった。 失敗=学習する機会を逃す方が長い目で見ると損失であると認識。 失敗した瞬間はしんどいけど、一時の恥は受け入れないといけないな、と。
3投稿日: 2021.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いー!難しい内容なのかなと構えて読んだけど、面白くて一気に読んだ。 自己啓発、仕事に活かすためにビジネス本読むようになったけど、この本のおかげで単純に読書が好きになったかもしれない。知的好奇心が満たされる!
1投稿日: 2021.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は成長するための資本である。ボトムアップ型、トップダウン型。固定型マインドセット、成長型マインドセットなど。読みやすく面白い。
1投稿日: 2021.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのような本を読むときは参考文献が気になるのですが、科学的に検証するために沢山の文献が記載されてました。その参考文献を調べるだけでもおもしろい! 「成功するためには」のようなハウツー本は沢山ありますが、この本は「失敗」から科学的に検証して成功へと導くものでした。トップダウンからボトムアップへ、失敗を繰り返しながら進化をしていこうと想う一冊。
9投稿日: 2021.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ医療過誤、航空機墜落事故、犯罪···色々な事例をもとに失敗から学ぶ重要性を説く。 医療現場や検察·警察の間違いを認めない(と言うかそう信じ込んでいる)権威主義と不都合な事に対する隠蔽体質、またアフリカでの開発援助が実際効果があったのか、それを判断するマージナルゲインと言う手法等を知ることが出来勉強になったし、あらためて単純化することでのバイアスには注意が必要だと感じた。 また日本人の起業家が少ない背景には、恥の文化と同調性が高いことによるものだと納得。幼児教育から、改革が必要だろう。
1投稿日: 2021.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最近、自覚しているのはどんな失敗をしても、昔ほど焦らず、むしろ謙虚にその事実を受け止め、その原因を考えるようになったこと。 GRITに繋がっているから、本当に成功したいから、無我夢中だからあれこれ考えなくなったのかもしれない。 そう思っていた頃にこの本に出会った。 最後の事前検死は面白かった。 ちょっと明日からやってみよう…
1投稿日: 2021.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ凄く前向きになる本。論旨も翻訳も読みやすく読者フレンドリーである。 失敗から学ぼうと言えば、ありふれた話に聞こえるだろう。本書では事例を元に、「人間の脳がいかに原始人の脳であり、失敗から学ぶことができないのか」を繰り返し説明する。 認知不協和、単純化の罠、犯人探しバイアスにより、脳の構造的に「学ばないバカ」になるように人間は作られている。 失敗から学ぶ前に、自分が「学ばないバカ」であることを学ぶことから始めないといけないのだ。 その上で、成長型マインドセット、失敗で進歩する科学的手法で成長することが可能になる。 中世暗黒時代に人類の進化は一度止まっていること、同じ状況が医療分野や刑事司法分野といった分野で起きていることは、はっとした。
1投稿日: 2021.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗との向き合い方の大切さを、多数の事例を通してこの本は教えてくれる。所属する会社の人に読ませたい本No. 1
1投稿日: 2021.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗の取扱説明書」と言っていい一冊。 過去の事例を元に、失敗に対する誤った認識、それが起きる原因、活かし方など、失敗に対する教訓が書かいてある。 本書では「日本では失敗を不名誉なものと見なされる傾向があり、失敗を恥と感じる。」と世界的に見ても日本人は失敗を恐れる傾向があると指摘している。 この本は失敗に対しての視野を広げてくれる。それだけで一読の価値はある。そして少しでも自分や他人の失敗に対して寛容な社会になって欲しいと思った。批判するのは簡単だけど、赦すのは難しいもん。
1投稿日: 2021.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗についての科学的な分析と、どうしたら失敗から学べるかを教えてくれるすごい本です。失敗した人を責めても効果がないこと。中立的な立場の人から意見を求められるしくみが必要なこと。人類の進化は失敗を改善してきた歴史であることなどが、実例を踏まえて分かりやすくまとまっています。
1投稿日: 2021.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々な失敗の例を上げながら説明されていて、とても面白かったです。 チーム内でミスが起こると、言葉に出さずとも、犯人探しをしがちです。でも「誰が」ではなく、「なぜ」と考えることが大事で、そうすることによりチーム内に、失敗に対して寛容な文化が生まれるのだと学びました。
1投稿日: 2021.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶことができる組織である航空業界。 そして失敗から学ばない医療業界。 この対比だけでも本書を読む価値あり。
20投稿日: 2021.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知的不協和の話、非常に興味深い。失う物が大きく自尊心が強い人や立場であるほど認知的不協和に陥りやすい。自分の考えが正しいと思いこんでしまう、思いたいがあまり事実を正確に認識できない、事実を歪めてしまう認知状態であること。常に、自分の仮説に溺れずに健全な反証を行うことが重要。大切なのはわかっていることの検証ではなくわかってないことを見出す作業。欲しいもの、見たいものだけを探し出して確証だと思いこむことに意味はない。これでは間違った仮説に都合の良い証拠を何となく集めてしまうことになる。 リーンスタートアップ。最初から完璧に作り込むなんて無理。実際にやってみてユーザーや顧客からのフィードバックを開発に反映させた方が成功に近づく。失敗を想定して試行錯誤してゴールに近づいていく。進化のプロセスと同じ。頭でっかちにトップダウンでやるのは限界がある。失敗を恐れず試行錯誤して検証する。何かを開発するために必要なステップ。いくら計画を作り込んだり想定したとしても必ず思いもよらない事態が発生する。それを織り込んでおく。うーん、うちの会社ができていないことだらけだな。。 やり抜く力(少し前に話題になったGRIT)と成長型マインドセット。これは子育てにも通ずるモノがある。自分はどうせ、と思わせずにいかに向上心を持たせるか。やり切った先の達成感や成果感をどう理解させるか。採用でもそういう要素や素養を指標に入れてもいいかも。やはり大事なのは失敗を学習の機会と捉えて失敗すること自体を恐れないこと。失敗を恐れて挑戦することすら諦めては成長の機会すらない。ミスを非難する文化の中で失敗が奨励される訳がない。 事前検死。プロジェクトが始まる前に、プロジェクトが大失敗に終わったと仮定してその失敗理由をとにかく挙げるというもの。確かにこれは有用かも。往々にして、肝いりのプロジェクトって精神論的に絶対成功させるという意気込みや思い込みが強すぎて、前提を覆すようなリスクや懸念点まで真剣に考えられていないことってあるよね。
1投稿日: 2021.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶ業界は成長して、そうじゃない業界は成長しない。人は非難バイアスを持っており、何か悪いことが起こったらだれかのせいにしがちだ。そうならずに、失敗をオープンにして、失敗から学ぶことが大切だ。 失敗から目を背けない組織にしなければならないと思った。悪いことが起こってもだれかを非難することがないようにしたい。
1投稿日: 2021.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすくためになりました。 成長型マインドセット:知性も才能も努力で伸びる。 固定型マインドセット:失敗を知性に求める。
3投稿日: 2021.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「失敗を恐れるな」とはよくいわれるがわかっていても失敗を責められることを恐れてしまうもの。自分の考えに固執したり犯人探しをすることは害毒でありあらためるべき。 失敗から学ぶには ◎マージナル・ゲイン・・・小さな改善の積み重ね ◎リーン・スタートアップ・・・小さく始める、「最低限実装した製品」(MVP)を使い検証と軌道修正を繰り返す、たくさん失敗して試行錯誤する ◎RCT・・・ランダム化比較試験、ランダムに選んだグループの片方は介入群、もう片方は対象群(何もしない)として実験し比較する ◎事前検死・・・プロジェクトの実施前に失敗した(すでに死んでいる)状態として検証(検死)する、なぜ失敗したか理由をできるだけあげていく この本で少しばかりショックをうけたのは最近観たテレビでもやっていた「スケアード・ストレート」(非行少年達に刑務所の現実をみせ、凶悪犯と対面させ罵倒されるなどの恐怖体験によって更生を促す)がずいぶん前に効果がないどころかむしろ再犯率があがってしまった(怖くなかったと仲間や自分自身に証明するためにわざわざ罪を犯す)ことが証明されていたことだ。それなのに今回だけでなくこの数年以内に同じプログラムの映像を2、3度観た記憶がある。何かを素晴らしいと思い込んでいる人は否定を受け付けないというまさにこの本がいっていることそのものが起っていた。
1投稿日: 2021.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ使い古された「失敗は成功のもと」という言葉、「そんなことみんな知ってるよ!」「何をいまさら!」なんて思うかもしれないが、それをみんなができていない!では、なぜできないのか?それをエビデンスを元に証明してくれる本だと思う。 ストーリーもわかりやすく面白いので、洋書特有のまどろっこしさも感じることなくスラスラと読むことができた。 実生活にも落とし込める役立つ知識だと思うので、今後の自分の行動に活かして行けるよう努力したい。
1投稿日: 2021.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ航空業界と医療業界の比較を用いてデータや過去を分析するかがいかに重要かがわかる。 事前検死、マージナル・ゲインなど失敗に対する手法も学ぶことができる。
3投稿日: 2021.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ・どうせ答えはもうわかっているんだから、わざわざ試す必要もないだろうとつい考えてしまう ・人は嘘をつくのではなく信じ込む ・認知的不協和 ・大きなゴールを小さく分解して、一つ一つ改善して積み重ねていけば、大きく前進できる ・事前検死
3投稿日: 2021.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の要旨は、『失敗は成功の母』という極めてシンプルな内容なのに、面白すぎて一気読み。 ユナイテッド航空173便(燃料切れ墜落)、リビアンアラブ航空114便(イスラエル領空侵犯で撃墜)、ブリティッシュエアウェイズのノベンバーオスカー(トラブルが重なった中での機長の危機回避行動がルール違反としてスケープゴートにされ有罪判決)と、3つの飛行機事故(三つ目はニアミス)が取り上げられていて、それぞれ学ぶところが多い。著者は学者だと思って読んでいたら、元卓球のオリンピック選手権で、Timesのコラムニスト。 印象に残った箇所 P261 哲学者カール・ポパーは言った。 『真の無知とは、知識の欠如ではない。学習の拒絶である。』 P318 計画経済が不毛なのは、失敗を許容する力が欠けているからだ。
4投稿日: 2021.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗から学ぶには、マインドセットと適切な学習システムが必要。 失敗から学習できない人は、そもそも自分の失敗を認めることが苦手である。期待していた結果にならなかった(失敗した)場合、認知的不協和が起こり、これを解消する為に事実の解釈を歪め、自分の正しさに固執するあまり、確証バイアスが発生する。 人間にはそのような特徴があることを認識した上で、仮説検証、実践による失敗や選択を繰り返していくことが重要である。 失敗も選択(その先に失敗する可能性があるから)もしたくないと思う私に刺さったのは以下の文言です。 |「信念を貫く勇気」と、「進んで自分を試して成長し続けようとする謙虚さ」とを兼ね備えなければならない。 勇気と謙虚さ。人生のテーマにしたい。 RCTにより、因果関係をより正確に捉えることを怠らない。原因、介入手段、結果を分離し、客観的評価を行う。 思い込み、主観によるものではないか。自分の仮説が間違っている可能性を検証する。 わかったつもりを疑い、小さな改善を積み重ねていくことで、大きな問題に立ち向かい、大きな進化を遂げることができる。 自分は成長できると信じる(成長に必要な失敗や選択から逃げない)覚悟と勇気を持ち、客観的な仮説検証、改善の積み重ねをシステマチックにできるか、が個人でも組織でも必要になってくる。
1投稿日: 2021.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
航空業界は、事故の原因がブラックボックスによって徹底的に分析されて生かされる。 医療ミスは、失敗を隠し勝ち。人間は自分の失敗を認めることは難しい。 クローズドループ現象=失敗や欠陥が放置、曲解されて進歩につながらない現象。瀉血の例。 医療事故のミスは「複雑な事態、不測の事態」と言いかえられて隠ぺいされる。 エレノアルーズベルト「人の失敗から学びましょう。自分で経験するには人生は短すぎます。」 上下関係がチームワークを崩壊させる。手術室でも操縦室でも起きる。上司には逆らえない。 ガリレオはピサの斜塔でポパーのいう「反証可能性」を実証して科学になった。科学とは反証可能性の潜在性を持つ仮説の集まり。 アドラーの心理学の中心は「優越コンプレックス」=優越性の追求から生まれる。 1万時間の法則=習熟するには膨大な時間が必要。しかし時間をかけても習熟しないものもある。レスポンスが返らなければ習熟できない。見えないゴルフのようなもの。 心理療法士は、患者の反応を観察するしかない。また治療の長期的な効果を知ることができない。時間をかけても臨床能力が向上しない。 壊血病は1601年には解決方法が見つかっていたが、浸透しなかった=シンプルで効果的な形にまとめられていなかった。 医療業界は複雑多様で人的ミスが出る場面も多い。しかし失敗を不名誉なものと考えられている。 第一種過誤=過剰のミス(擬陽性)、第二種過誤=不足のミス(偽陰性)。 DNA鑑定は、犯罪調査史上最大の発明。 人は嘘を隠すのではなく信じ込む。 自分の信念と反する事実を突きつけられると、過ちを認めるのではなく、事実の解釈を変えてしまう。 =認知的不協和=自己正当化。 過去は事後的に編集される。認知的不協和は、陥っていることにめったに気づけない。 入学試験が厳しかった場合は、入学に価値があると思い込みやすい。 高名な学者ほど失敗によって失うものが大きい=認知的不協和に陥ると、自己正当化に走りやすい。自尊心が邪魔をする。 あえて間違える=確証バイアス。 2,4,6と並んだ数字の次の数字は?仮説を証明するために、正しい答えを見ても証明できない。間違っている仮説の答えを見れば、証明できる。進んで失敗する意志がない限り、正しいルールを見つけ出せない。仮説の正しい例を数多く出しても、証明できない。 瀉血療法を肯定する材料は確証バイアスそのものを強化するだけ。健全な反証を行わない限り、正しい答えにはならない。 実際に見たこと、より、知っていること、に記憶を一致させる傾向がある。ブッシュ大統領は、小学校で航空機が突入するのを見た、といったが、生放送でとらえた映像は存在しない。記憶を修正している。 進化とは選択の繰り返し。試行錯誤の力。進化の方法がわかっているのではなく、試行錯誤によって適応能力が高いものが生き残った。試行錯誤を地道に行う。 計画経済は誰も失敗しない=ありえない。企業の淘汰は進歩のために必要。自由市場では数えきれない失敗が、潤滑油となって、あるべき方向へ導かれる。自由市場は失敗が多くても機能する、のではなく失敗が多いからこそ機能するもの。 正しいかどうか試す、ためには、単純化しやすい心理傾向を乗り越える必要がある。後講釈は誰にでもできる。 周りの出来事には、何らかの意味付けを見出そうとする=後講釈の題材になる。少しの目を引く現象に着目しすぎる。 完璧主義の罠=ひたすら考えれば最適解が得られる、という誤解=テストをしなくなる。失敗の恐怖=隠したりなかったことにする。クローズドループ現象。 バビノーとクランボルツは、たくさん失敗することを進めている。リーンスタートアップ。 3M ブレストではなくユーザーに聞く。ドロップボックスも同じ形でサービスを改善した。 トップダウン式に頼らない。失敗型アプローチで改善する。 瀉血が有効だと思われた理由は、対照群を含んだ調査をしていないから=RCT(ランダム化比較試験)客観的な検証を可能にした。 小さな改善を積み重ねると大きな飛躍につながる。F1レース、ツールドフランス、など。 アフリカの援助では、何が効果があるか=RCTでわかる。小さなプログラムに分けて検証する。 マージナルゲイン=小さな改良。ホットドッグの早食い競争でも勝利に貢献した。 犯人捜しの心理=非難の心理。非難を恐れて失敗を隠す。失敗は学習のチャンスととらえる組織文化が必要。 避難しない組織、懲罰しない組織のほうがミスが少ない。 根本的な帰属の誤り=一番単純で一番直観的な結論を出す傾向。早計な避難をやめること。 真の無知とは、知識の欠如ではなく学習の拒否である。 失敗から学ぶために。 固定型マインドセットではなく成長型マインドセットを持つ。合理的にあきらめる=成長型マインドセットの表れ。 すべて失敗を前提に考える。失敗ありきで設計する。 ーーーーーーーーーーーーーーー 20240903再読 航空と医療との安全性の違い=検証する仕組みがあるかどうか。 クローズドループ現象=結果を検証しない。思い込みで結論を出す。 医療では、上下関係に配慮しがち。 航空機のコックピットでも同じことがいえる。 人は信念と違う事実を突きつけられると、信念ではなく解釈を曲げる。ときには事実を無視する。 固定型マインドセットに陥ると知性才能は生まれついたモノ、と考えられ、成長型マインドセットなら、努力によって伸びると考える。 失敗ありき、のアプローチ=事前に検死する=うまくいかない状況を考え、なぜなのか、をあらかじめ探る。その対策を練る。
1投稿日: 2021.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗を受け入れ、正しく原因を理解する。 世界の煩雑さを受け入れ、単純に考えて批判しない。関係を深く追って、何があったのかを突き止める。 固定的なマインドを外し、成長的なマインドをセットする。 エリートほど自らの失敗を受け入れられない。 不都合な真実を勝手な解釈のぬりかえで防御×。 失敗を自己正当化で防御×。 失敗を隠すのではなく、上記のように信じこむことを認知的不協和という。 目に見えない反事実を意識する。 失敗を受け入れ、失敗をオープンにする組織作りをしないと、皆が隠し、皆が判断を間違え、失敗が連鎖する。 現代は、失敗で批判されるのが特定の人物になっている魔女審判。人間は生物学的に直感的・単純に批判をする。
1投稿日: 2021.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から学ぶのが大事、って誰もがどこかで聞いたことがある言葉だけど、それがいかに難しいか、この本で書かれている実際にあった出来事(事件)とそこで起こる人々の心の葛藤や変化を読めばよく分かる。自分の過ちを認めたくないというプライドや、会社やチームに迷惑をかけたくないという恐れや、相手の間違いを指摘するのは失礼だといった誤った気遣い、あるいは様々な勘違いが元で大きな事件になることがある。 失敗を受け入れ、それをより良い未来につながるデータだと捉えるには色んな訓練が必要だけど、それをしていかないと自分の経験だけから学んでいては時間がいくらあっても足りない。まずは自分の身の回りで起こる出来事に対して、もうちょっとアンテナを張って観察してみようと思った。
4投稿日: 2021.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界仰天ニュースが100話ぐらい集結して、そこから得られる教訓をぐぐぐっと圧縮したような本。 マインドセットの話が特に心に沁みた 固定マインドセットと成長マインドセットは、 個人が元々持つものもあるし、組織によっても左右される。だから、スタートアップ界隈のような成長マインドセットが集う環境に身を置こうと思った。
1投稿日: 2021.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から如何に学ぶか。 医療業界と航空業界を主に比較して考察する。 どれも秀逸だが、特に第5章「「犯人探し」バイアスとの戦い」、第6章「究極の成果をもたらすマインドセット」は繰り返し読みたい。 ・自分の間違いを認め、失敗から学べるか ・組織が失敗をオープンに出来るか ・マネジメント層が失敗を許容出来るか その重要性と難しさを学ぶことが出来る。
1投稿日: 2021.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗を有効利用する航空業界と、有効利用できない医療業界の対比から始まり、文字通り失敗を「科学」することの有益性と有効性がしっかりと理解できる良書です。 失敗という状況を忌み嫌うのではなく、最も費用対効果の高い学びができるものとして捉え、そのメカニズムを科学的に解明していく。 なぜ、組織は不祥事を隠蔽するのか。組織を構成する個人のパーソナリティに失敗の責任を転嫁してしまうと、失敗は活かされずに終わってしまう。 何かしらの組織を率いていて、その組織が失敗を積極的に認めず、隠蔽されがちであると認識するのであれば、この本を利用して、失敗を有効利用できる仕組みを模索してみるのもいいかもしれない。
4投稿日: 2021.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ失敗を生かすことができないのか? その原因を「組織文化」といった根本にまで求めた良作である。 組織論については、正解を軍隊や航空、医療業界などに求めることが多いが、失敗から学び取る姿勢はやはり航空業界が一番優れている、と感じた。 「失敗は罪ではない。失敗を隠すことこそ罪なのだ。」というのは、この本で得られた非常に良い教訓の一つである。ただ、その組織文化を作るには具体的に何をすべきなのか、その文化育成を阻む障害の克服方法などがあれば、もっと良かったように思う。 世の中には「失敗を活かそう」と言いながら「目標:クレーム0」といったことを平気でぶち上げる社長がいる。失敗の原因をを他社や他部門に求める人もいる。「失敗には蓋をし、中の人が忘れてくれるように取り計らうことこそが正しい」と考える人もいる。そういった人こそ目を通してほしい。
3投稿日: 2020.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログヒューマンエラーが仕事に直結する公共交通で働く自分にとって、重要なテーマだと思い読んだ。 失敗から学ぶことによる便益だけでなく、失敗を無かったことにすることによる損失や悲劇、失敗に対しどのように取り組むべきかが、実例を揚げながら述べられており、我が身に置き換えながらストレスなく読み進められた。 サマリーを掲示したり、簡単なゼミを開催して、周りの同僚にシェアしたいと強く思った。特に、ミスに対して処罰を与えることの損失については、自分もそういう思考に陥らないようにしなければならないと肝に銘じた。
1投稿日: 2020.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際に起こった医療事故や航空機事故、そしてスポーツチームの取り組みを通じて、失敗が起きる原因や、失敗が発生した後の行動を科学的に考察する作品。 人の行動には失敗がつきものなのだが、失敗を活かすオープンループの好事例として、航空会社の事例が挙げられている。航空会社では事故が起きるたび、第三者機関によってその原因が徹底的に検証され、機材や運用の改善を速やかに行い、その結果を業界全体で共有しているそうだ。同様にユニリーバやメルセデスF1チームにおいても、検証と改善のプロセスが上手く働いていて、失敗を活かす好循環を作り出している。 それに対し医療や司法の世界では、医療事故や冤罪事件から失敗を学ぶ機会が少ないクローズドループとなっている。航空業界のような原因を解明する第三者機関が無い事に加え、人間に働く認知的不協和という作用によって、失敗を失敗として認めづらい心理状態に陥ってしまう事が原因らしい。 ヒューマンエラーはシステムの不備から発生すると理解する事、恐れずに小さな失敗を繰り返して解決策を見出す事、そして失敗の報告者を罰してはいけない事。意外と単純な事のように感じるが、これが出来るか出来ないかが、成功と失敗を分ける鍵になるのかもしれない。
3投稿日: 2020.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログひと言で表すなら、 「ヒューマンエラーは、エラーから逃げた時に始まる」 この本は、すべての業界、すべての業種の人が読むべき。なぜなら、失敗と無縁な仕事なんてひとつもないはずだから。 失敗をどう活かすか、失敗からどうやって逃げない組織を作るか、を教えてくれる良質な一冊。 おすすめ。
3投稿日: 2020.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ使い古された失敗に学ぶべきという本だが、やはり本質的だと思う。実践は難しいし、失敗した当事者は、解釈を変えて失敗を認めようとしない、という指摘をごもっとも。 ためになりました。 気になった点。 ・失敗から学ぶ、またはフィードバックが適切に行われると、その教訓を活かして、成功に至ることができる。 そのためにはRCT(randomized controlled trial)により、結果を正しく分析すること。そして、マージナル・ゲインの考え方(いわゆるKAIZEN)で、小さいが目に見える結果を得ることが重要。 ただし、失敗に対する考え方に革命を起こさないといけない。互いの挑戦を称え、実験や検証を行うこと、根気強くやり続けることなどなどに賞賛を向けるべき。正解を出したものだけを褒めているだけでほだめ。
1投稿日: 2020.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ2018年に読んだ本の中で1番心に残った本。 「失敗は成功のもと」 とは子供の頃から何度も聞いた言葉ではあるが、実際、学校や社会で「失敗」は嫌われ者。 自分の失敗は受け入れ難いもの。 でも、それを認めて改善していかないと成長は無い。 内容とてもわかりやすく、為になるので、是非とも多くの人に読んでもらいたいと思う。
1投稿日: 2020.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗(ミス)は仕事でも私生活でも誰にでもつきもの。 そのミスをどう捉えて、どう扱うのか。 各業界の詳細な事例と共に、納得しながら読み進められました。 自戒も込めて、数年に一度読み直したい。
1投稿日: 2020.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「失敗」に着目した名著です。 冒頭の医療業界と航空業界の比較が何よりも説得力があります。かつて航空業界では事故が多発していましたが、自らの否を認め、原因を追究し続けてきたからこそ、安全が保たれるようになりました。 一方、医療分野ではなく、未だに権威主義による組織体制が根付いていて、自らのミスを認めることが難しくなっています。 そのことが何を生んだかと言えば、真の原因の追究を阻んでしまい、発展できなくなっていることです。 本書の中でも度々指摘されていますが、社会科学の分野においても、この傾向は強く、政治、経済でも同様の動きが見られます。 本書で述べられている通り、失敗は悪ではなく、進化するために不可欠な学習の機会なのです。 逆に言えば、失敗のない世界に成長や進化はありません。
8投稿日: 2020.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗についての本質本。 失敗の取り扱い方や俯瞰の仕方、活用方法を実際にあった事例を持って学べる。 特に本書であった事前検死については普段の仕事に活かせる方法だと考える。
1投稿日: 2020.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
航空機事故、医療事故の分析や、ツールドフランスでの成功要因の分析など、過去の実例から失敗することの重要さを説いた本。マージナルゲインなど、すぐに実践できることが書いてあり、非常に有用。 失敗をしない・恐れるのではなく、いかに失敗から学ぶか。自分自身、失敗することには強い抵抗があるので、マインドを変え、次に活かせるようにしたい。 プロジェクトの6段階 1.期待 2.幻滅 3.パニック 4.犯人探し 5.無実の人を処罰 6.無関係な人を報奨
1投稿日: 2020.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は自分の失敗を正直に受け止めにくいものですし、公にすることも敬遠しがち。 また、他人の失敗についてはやたらと責任所在はっきりさせ、避難ばかりしていては次の成功へ結びつかない。 そんな社会では失敗から学び、改善していくことはなかなか難しい。 またその失敗も共有しなければ、他人が同じ失敗を繰り返してしまう。 私自身も失敗に対する考えを改めたいと感じた。
1投稿日: 2020.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・失敗に学んだ航空業界、失敗に学べない医療業界 ・失敗ありきで設計する ・事前に失敗の理由を書き出す。
1投稿日: 2020.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗に対してどう向き合うか、それによって、企業も個人も成長マインドセットと固定マインドセットに分かれるということ具体例を踏まえて説明している。 特に人々は失敗を恐れて、隠し、またスケープゴートを探して、犯人を探すことがしばしばあり、それによって成長を妨げられるという。 失敗から学び、改善することで、マージナルゲインが得られ、成長していける。 固定マインドセットの典型が医療界に対して、成長マインドセットの典型を飛行機業界を挙げている。また嘘や問題が、適切に検証されてこなかったため、長い間放置されてきて、人類が不利益を被ってきたことも指摘している。 最後に失敗ありきで物事を考え、失敗しいた場合にそれを検証、改善することで、マージナルゲインを得ることでき、成長できると解く。
1投稿日: 2020.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗からどのように学び、成功へつなげるかということを事例とともに紹介している。 医学会と航空業界という、ミスが死に直結する業界においてのミスへのアプローチの方法の違い(「オープンor クローズド・ループ現象」)というのは私の部署でも当てはまるものがあり、激しく首肯した。 人は複雑さから目を逸らし、物事をシンプルに考えたがるというのはその通りであるものの、物事の単純化というのも物事を進めるのには重要であったりする。また、失敗に対して時間を掛けたがらない傾向や、失敗の説明を懲罰的と考える担当者も多いことから、失敗を起こさないようにするには何よりも文化と体制の醸造が重要であると感じる。 「この失敗はしょうがなかった」 「これは避けようがなかった」 「結局、○○が悪い(※〇〇には特定の個人や部署、変えようのない仕組みが入る)」 という、現場ではよく聞くあの言葉には違和感を感じることがあったが、その直感は正しかったのだとこの本を読んで思った。 失敗したときにその問題をより深く追求することは時間的・精神的に難しい場合が多いが、その重要性を認識している人間(つまり本書の読者)が分析を推し進めることが重要である。
1投稿日: 2020.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知的不協和、成長型マインドセット、固定型マインドセット、試行錯誤、、、キーワードがたくさん。組織文化の大切さ。人間は試行錯誤しながら進化してきたのに、いつの間にか失敗を受け入れる態度や文化が広まってきた。これらを意識的に排除して、健全な組織文化、学ぶ文化を作っていくことが大切。 この本で俯瞰されていることを念頭に、自分の行動を見直していく、組織文化を変えていく、、、。2020年の最初に読んだのはいい本だった!
5投稿日: 2020.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ検証はとても大事。 医療業界と航空業界の「失敗に対する姿勢」の違いを柱に、失敗をどうすれば(社会に)生かせるかを考える内容。 失敗を生かすために腐心してる航空業界ですら”いけにえ”を求める心理からは完全に逃れられていないと言った話もあり、精神論や技術論にはまらない、「失敗の科学」はどうあるべきか、失敗を繰り返さない組織の在り方について考えるにとてもいい内容でした。
1投稿日: 2020.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗をしたいと行動している人はいない、それでも失敗は必ずいつか起こるもの。大事なのは失敗が起こったあとの行動、恐らくそれは皆わかっているが、失敗を許さない環境があるために誤った行動を取ってしまう。。 失敗が起こった際に、まわりの意見に同調したり、流されたり、非難するのではなく、自分の目、自分の耳で何が起こったのか、なぜ起こったのかを調べ、原因を追求し、次に繋げることの重要さを改めて感じた。 それができる個人でありたいし、それができるチーム作り、組織作りをしていきたい。
1投稿日: 2019.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗の科学 失敗から学習する、学習できない組織 著作者:マシュー・サイド タイムライン https://booklog.jp/timeline/users/collabo39698
1投稿日: 2019.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の伝統的な企業のような減点主義がいかに成長を遠ざけているかを考えさせられる。 デザイン思考のルールにも、プロトタイプを早く作成し、早く失敗する、失敗を繰り返すとあるがこうしてプロダクトやサービスは洗練されていくと理解している一方で、実際に失敗が起きた際には、本書にも指摘があるように”魔女狩り”が行われ、往々にして魔女として犠牲になるのは、次の成功や改良の鍵を握る当事者であるように思う。 対照的に、実証実験やデータで明らかに反する結果や事実が明らかになっているにも関わらず、自身の失敗を認めない厚顔な当事者には甚だ笑止である。 本書からの学びは、昨今の政治にも当てはめられる。事実を明らかにし、国民に説明責任を果たし、当事者はそれを認め、不法行為は裁かれ、再発防止の仕組みを定める、裁かれたものにもチャンスを与える環境を作る、そうした当たり前のことを実行してほしい。
6投稿日: 2019.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ[出典] Think Clearly, ロルフ・ドベリ 2019秋の所総会にて川村さんの紹介
0投稿日: 2019.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ冒頭で医療ミスのエピソードが語られる。信じ難いヒューマンエラーがいくつも重なりエレインという女性が37歳の若さで亡くなった。続いて「生命を預かる仕事」の代表である医療業界と航空業界を比較して医療業界の杜撰さと被害者の多さを検証する。エレインの夫マーティンは死までの経過を知りたかった。決して医療ミスを見抜いたわけではなかった。ただ知りたかったのだ。マーティンの職業はパイロットであった。 https://sessendo.blogspot.com/2019/10/3.html
1投稿日: 2019.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗を認めよ、試行錯誤(失敗せよ)失敗を共有せよ。成功志向だからこそ。どんどんゆるゆるになる私とは対極的かも。 我ながら学習が遅いたちのようだ。読んでよかった。
1投稿日: 2019.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗を学びに変えるとは、言うは易しだが実行にはし難い。しかしその言葉を実行している企業がいることも事実であり、どのような取り組みをしているのかを一冊にまとめた良書。事実ベースの話の展開のため、実行に移しやすい。
1投稿日: 2019.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗に対するスタンスとして様々な示唆が得られました。 教育者やチームリーダーはエッセンスだけでも一読しておくと良さそうに思います。 #翻訳本なので、要点に比してボリュームは多めに感じます。
1投稿日: 2019.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ随分前に読み終えていた1冊。以前お手伝いしていたプロジェクトの部長さんが紹介してくれて、読んでみたところ非常に勉強になった。特に事前検死のアプローチは、今後の自分のプロジェクトマネジメントでも1つのヒントになると思う。失敗を超高速で繰り返せとか、頭に残りやすいフレーズやエピソードも多くて、読みやすくてためになる1冊でした。自分もたくさん失敗しながら学びを得て、前に進めんでいけるといいと思います。
1投稿日: 2019.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ【工学部図書館リクエスト購入図書】 ☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22819848
0投稿日: 2019.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログp.41 かつて米第32代大統領夫人、エレノア・ルーズベルトはこう言った。「人の失敗から学びましょう。自分で全部経験するには、人生は短すぎます」 わかったつもり↔マージナルゲイン リーン・スタートアップ RCT (Randomized Comparison Test) p. 260 プロジェクトの6段階ーーー(リパブリック・ナショナル・バンク・オブ・アメリカ) 1.期待 2.幻滅 3.パニック 4.犯人探し 5.無実の人を処罰 6.無関係な人を報奨 事前検死 (pre-mortem)
1投稿日: 2019.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
サブタイトルは「失敗から学習する組織、学習できない組織」。なるほど、航空業界は学習する組織、医学界や検察はなかなか学習できない組織の例としてあげられていた。失敗をしっかり受け止め、そこからきちんと学習していくことは進歩するために必要な過程。だから本来なら失敗をしながら、改善を積み重ね、同時並行的にそれを理論が実証するという形で進歩が進むらしい。良くわかる話だ。 キーワードは「認知的不協和」。これはフェスティンガーが提唱した概念で、自分の信念と事実とが矛盾している状態、あるいはその矛盾によって生じる不快感やストレス状態を指すらしい。認知的不協和が、誰の心にも根深く潜むことを最初に明らかにしたのは、フェスティンガーの最大の業績で、人は自分の信念にしがみつけばしがみつくほど、相反する事実を歪めてしまう傾向があるということ。そして、認知的不協和が何より恐ろしいのは、自分が認知的不協和に陥っていることに滅多に気づけないところらしい。人間は外発的な動機より、自尊心を守りたいという内発的な動機のほうに支配されやすい傾向があるようだ。 さて、失敗から学ぶにはふたつの要素がカギとなる。ひとつは、適切なシステム。もうひとつは、その適切なシステムの潤滑油となる、マインドセット。現実世界では、頭で考えたアイデアがどれほど秀逸でも、成功のためには実際の試行錯誤が欠かせない。そして、テクノロジーの進歩の裏には、論理的知識と実践的知識の両方の存在があって、それぞれが複雑に交差し合いながら前進を支えているということらしい。まずは失敗してみること。そしてその失敗を真摯に捉えて、次のステップに活かすこと。あきらめないマインドセットがとても重要ということでしょうか。
1投稿日: 2019.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
航空機にはすべて、ほぼ破砕不可能な「ブラックボックス」がふたつ装備されている。ひとつは飛行データ(機体の動作に関するデータ)を記録し、もうひとつはコックピット内の音声を録音するものだ。事故があれば、このブラックボックスが回収され、データ分析によって原因が究明される。そして、二度と同じ失敗が起こらないよう速やかに対策がとられる。この仕組みによって、航空業界はいまや圧倒的な安全記録を達成している。( p.18) 航空業界においては、新たな課題が毎週のように生じるため、不測の事態はいつでも起こり得るという認識がある。だからこそ彼らは過去の失敗から学ぶ努力を絶やさない。(p.19) ミスは、自分のプライドすらも激しく脅かす。医者に限らず、政治家が政策に失敗したときも、ビジネスリーダーが戦略に失敗したときも、あなたの友人や同僚も同じだ。あなた自身もときどき使うのではないだろうか?私も例外ではない。(p.30) まず、失敗から学ぶためには、目の前に見えていないデータも含めたすべてのデータを考慮に入れなければいけない。次に、失敗から学ぶのはいつも簡単というわけではない。そんなときはこのケースのように、注意深く考える力と、物事の奥底にある真実を見抜いてやろうという意志が不可欠だ。これは爆撃機や軍の問題だけでなく、ビジネス、政治、その他さまざまな分野に当てはまる。(p.55) 実質的に占星学の予測とほとんど変わらないものもある。しかし重要な違いは、科学が反証可能であることだ。だからこそ新たな理論が常に現れ、消えていった過去の理論は現在の理論の貴重な踏石となった。 ところが吾々はもうこれらの「失敗した」科学理論を学ばない。たしかに、淘汰された説など学んでいる暇はないのかもしれない。しかし、生き残った説だけを見ていたら、それをもたらす土台となった失敗には気がつかない。(p.70) (浸透速度が遅い)原因は(中略)必ずしも怠惰や意志の欠如というわけではない。それより問題なのは、必要な知識や情報が、使用に適したシンプルで効果的な形に置き換えられていないことだ。航空業界でも、もし何ページにもわたる要領を得ないデータを共有するとなれば、(中略)臨床医が医学雑誌で毎年ほぼ70万件も発表される論文と闘っている状態と変わらなくなるだろう。(p.80) 多くの場合、人は自分の信念と相反する事実を突き付けられると、自分の過ちを認めるよりも、事実の解釈を変えてしまう。次から次へと都合のいい言い訳をして、自分を正当化してしまうのだ。ときには事実を完全に無視してしまうことすらある。 (中略)そんな状態に陥ったときの解決策はふたつだ。1つ目は、自分の信念が間違っていたと認める方法。しかしこれが難しい。理由は簡単、怖いのだ。自分は思っていたほど有能ではなかったと認めることが。 そこで出てくるのが2つ目の解決策、否定だ。事実をあるがままに受け入れず、自分に都合のいい解釈を付ける。あるいは事実を完全に無視したり、忘れたりしてしまう。そうすれば、信念を貫き通せる。ほら私は正しかった!だまされてなんかいない!(pp.102-103) 記憶は我々が思っているほど信頼できるものではない。我々は、自分の経験をすべて高画質の動画で頭の中に保存して、好きなときに観られるわけではない。記憶は脳全体に分散するシステムで、あらゆる種類のバイアスの下にある。つまり、それだけ様々な影響を受けやすい。まったく別々の経験の一部を集めて、ひとつの出来事につなげてしまうことすらある。いわば記憶の「編集」をしているのだ。(pp.144-145) 完璧主義者の罠に陥る要因はふたつの誤解にある。1つ目は、ベッドルームでひたすら考え抜けば最適解を得られるという誤解。この誤解にとらわれると、決して自分の仮説を実社会でテストしようとしなくなる。ボトムアップよりトップダウンの方式に重点を置くと生まれやすい問題だ。 2つ目は、失敗への恐怖。人は自分の失敗を見つけると、隠したり、はじめからなかったことにしたりする。しかし完璧主義者はいろんな意味で更に極端だ。失敗をなくそうと頭の中で考え続け、気づけば「今欠陥を見つけてももう手遅れ」という状態になっている。これが「クローズド・ループ現象」である。失敗への恐怖から閉ざされた空間の中で行動を繰り返し、決して外に出て行こうとしない。(p.168) シドニー・デッカーによれば、問題は「誰の責任か?」でも「責任を追及すべきミスと、偶発的なミスとの境界線はどこにあるのか?」でもない。そんなことに一律の線引きは不可能だ。ここで問うべき責任は、「処遇を判断する立場の人間を、スタッフは信頼しているか?」だ。裁く側の人間を信頼することができて初めて、人はオープンになり、その結果、勤勉にもなるのだから。(p.256) 成長型マインドセットの企業では誠実で協力的な組織文化が浸透しており、ミスに対する反応もはるかに健全だった。また次のような項目に同意する傾向が見られた。「この会社ではリスクを冒すことを純粋に奨励していて、失敗しても非難されない」「この会社にとって失敗は学習の機会であり、それが付加価値となるととらえている」「この会社では革新的に考えることが奨励され、想像力が歓迎される」(p.296) アメリカの哲学者ヒラリー・パトナムはこう言った。「科学とそれ以前の思想とでは、真実を発見する方法が異なる。科学者は自らの理論を進んで検証し、自分が万能だとは考えない。(中略)自然に問いかけ、うまく理論が成り立たなければ、その考えを進んで改めていかなければならないのだ」(p.316) 失敗から学ぶことには、深遠で道義的な目標がある。人の生命を救い、支え、強化することだ。マーティン・プロミリーは言う。「医療の多くの分野で、間違いなく進歩が見られます。10年前はMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)感染症のような院内感染症は、『よくあること』として片付けられていました。ほぼ対処のしようがない、避けられない問題だと思われていたのです。しかし今では、この種の問題に立ち向かって予防方法を見つけ出そうという、強い意欲が感じられます。(p.330)
3投稿日: 2018.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗は組織論、仕事術、心理学などにまたがる幅広いテーマであり、興味深い内容が満載だった。事例として盛り込まれているいくつかのストーリーも、読み物としておもしろい。 失敗への対処方法によって進歩が得られるかどうかが異なることは、航空業界と医療業界を対比することによって明確になる。航空業界では、パイロットは自分のミスと向き合い、事故調査に強い権限を持つ独立の調査機関が存在する。失敗は特定のパイロットを非難することにはならず、すべてのパイロット、航空会社、監督機関の貴重な学習の機会となる。1979年の事故後、各航空会社はチームワークを重視したリスク管理に習熟する処置を講ずることを勧告され、機長は参加型管理の技術、その他のクルーは主張の技術を習熟することが求められた。人的ミスの多くは、設計が不十分なシステムによって引き起こされることを理解したことによって、進歩につながった。 一方の医療業界は、事故が起こった経緯について日常的なデータ収集をしてこなかった。医療過誤による死病者数は、年間40万人以上にのぼるとの推計もある。失敗や欠陥に関わる情報が放置されたり曲解されたりして、進歩につながらないクローズド・ループに陥っていた。また、心理療法士、大学入学審査員、企業の人事担当者、臨床心理士では、自らの対応や決定による結果を知る機会がないため、訓練や経験が活かされず、能力の向上につながらないことが多い。 人は自分の信念と相反する事実を突き付けられると、過ちを認めるよりも、事実の解釈を変えてしまう。これは、自分の信念と事実との矛盾によってストレス状態となり、自尊心が脅かされるためにとってしまうもの(認知的不協和)。実験では、大変な努力をして行った行為であるほど、自尊心を守るために都合よく解釈することがわかっている。検察官が冤罪を認めようとしないのは、司法試験を受け、何年もの実務経験を積み、事件を解決するために懸命に働いたことが、強烈な認知的不協和を起こしているからだろう。高名な学者、有名な専門家、企業の上層部、世界的に影響のある人々ほど、失敗を認めず、自己正当化に走る傾向にある。 失敗を繰り返すことによって、進化のプロセスに似た実践的知識が得られる。技術の進歩の裏には、論理的知識と実践的知識の両方が交差しあいながら前進を支えている。論理的に考える方が楽なので、反復作業が多い実践的知識をおろそかにしがちだが、革新的と言われる企業の多くは実践的知識を取り入れている。 大きなゴールを小さく分解して小さな改善を積み重ねることによって、大きく前進できる。ツールドフランスで優勝したイギリスチーム、1万以上のセンサーからのデータによって改善すべき点を探すF1レース、ウェブデザインのABテスト、大食いコンテストで優勝した小柄な日本人といった事例が印象深い。 脳は直感的な結論を出したがるため、問題が起きると人は犯人捜しや非難に躍起になる。しかし、懲罰志向の組織とそうでない組織を比べると、懲罰志向の組織の方がミスの報告は少ないが、実際のミスは多くなる。 失敗に対する反応が強い人ほど、失敗から学ぶ傾向がある。反応の強さによって、知性や才能は固定的と考える固定型マインドセットの人と、努力によって伸びると考える成長型マインドセットの人に分かれる。 <この本で学んだことを実践につなげる> 自分のアイデアを世に問うことを続ければ、それを磨いていくことができるだろう。ネットでもどんどん発信していこう。大きな目標を小さく分解して、小さな改善を積み重ねる。大食いコンテストで優勝した日本人のやり方に倣う。
0投稿日: 2018.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ悲惨な失敗事例がたくさん読める本。 やはり、標準や基準を定めて、そこから外れた失敗があれば、見直し改善して標準や基準を変えていき、より失敗の少ないやり方にしていくという話。 ただそのためには、失敗したら恥ずかしいとか、失敗は許されないもの、という考え方から変えていく必要がある。ここが一番難しいのではと思います。 人命が失われた結果、多くの命が救われるような話を聞いても、その失われた命は唯一のものだったんだよなとか考えるといたたまれない気持ちになりますね。
1投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書を読むのが辛かった。でも読むのは止められなかった。 思い当たる節(失敗から目を背けること)が多すぎて心苦しくなった反面、今こそその失敗(失敗から目を背けてきたこと)に正面から向き合う時だと思い、誠心誠意取り組むことを決意した。 全ての人に薦めたい。
3投稿日: 2018.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織。マシュー・サイド先生の著書。人間は失敗をする生き物。失敗を謙虚に反省して、次に生かせるかどうかはその人次第、その組織次第。失敗と謙虚に向き合えない傲慢な人間、傲慢な組織は失敗から学習できずに同じ失敗を繰り返す。耳が痛いお話だけれど、とても参考になりました。
1投稿日: 2018.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
失敗から学べれば進化する 失敗ありきで設計 客観的に評価することが学習 成長型マインドセット、失敗は学習の機会で付加価値となる 考えるな、間違えろ。選択と淘汰が進化 世の中を過度に単純化している。どうせ答えはもうわかってる、わざわざ試す必要もない 後付け 批判的なものの見方を忘れると自分が見つけたいものしか見つからない。
1投稿日: 2018.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ホテルにぶつかりそうになって寸前で避けきったのに有罪になった機長が気の毒。 失敗を責めても物事は解決はしないし、失敗を責めることは失敗を検証する必要性を隠してしまう。 児童相談所の事例も今の日本と同じだ。 ミスを犯した犯人探しと犯人を責めることで検証すらされない。 もっと失敗には真摯に向き合ったほうがいい。
1投稿日: 2018.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログyet another 気分が悪くなる本。おもしろく読んだが、最後の方で「成功マインドセット」とかでてきてずっこけた。
0投稿日: 2018.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ20180424読了。 会社の先輩のおすすめで読んだ。 失敗をどう活かすか、という本。 大きくは下の2点について 1.失敗からの学びをどう反映させるか 2.よりよい成果物のための失敗の有効性 ① 失敗を全世界で効率的・迅速に学び共有している航空業界の取り組みを例に、他の業界でなぜそれが実施できていないのかを解説。 例えば、 ・失敗の報告をあげても処罰されない仕組み ・失敗を自動的に気づける仕組み ・失敗を迅速に共有するための仕組み ・失敗からの学びを実アクションとして落とし込み・展開する技術の不足 ② 成果物をつくるために失敗フェーズを意図的に組み込んだほうが、最終的に質は良くなる、という話。 量をたくさん作ってフィードバックをたくさんまわしたり(フェイルファスト、スクラム)、RCTによるABテスト、マージナルゲイン。 新しくこれはいいな、と思ったのは「事前検死(pre-mortem)」。 プロジェクト実施前に「プロジェクトは大失敗した」という前提で 「なぜ失敗したのか」理由を考えるというもの。 これは低コストで、主なリスクを考え出せそうで有効に感じた。
3投稿日: 2018.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログBlack Box Thinking: The Surprising Truth About Success http://www.d21.co.jp/shop/isbn9784799320235
1投稿日: 2018.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の主張は「できるだけたくさん失敗して、その原因を検証してフィードバックし、成長につなげる」という事で、それがどのような要因によって阻害されるのかを様々な視点から述べています。 個人レベルの問題としては失敗を認めることができないこと、誤った考えを捨てきれないことの心理学的な要因について、組織レベルの問題としては安易に失敗やミスの犯人捜しに奔走してしまうこと、それらを隠蔽してしまって問題が表面化しない体質に陥ることの危険性、失敗のデータの解釈の仕方などについて解説をしています。 「失敗すること=恥ずべき事」ではなく「失敗すること=成長の機会」と捉え、より効果的に失敗を成長につなげるために必要な組織づくりについて、様々な業種の実例を挙げています。この実例については航空業界、医療業界、法曹界、教育、IT、軍事など広範に及び非常に分かり易くかつ具体的に書かれており、大変参考になりました。 訳も読みやすく、この手の本としては内容の充実度、読みやすさともに素晴らしいと感じました。
4投稿日: 2018.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ<目次> 第1章 失敗のマネジメント 第2章 人はウソを隠すのではなく信じ込む 第3章 「単純化の罠」から脱出せよ 第4章 難問はまず切り刻め 第5章 「犯人探し」バイアスとの闘い 第6章 究極の成果をもたらすマインドセット 終章 失敗と人類の進化 <内容> もうちょっと失敗の原因が描かれるのかと思ったら、失敗を糧に進歩するには、という内容の本だった。自然科学分野では、失敗をしっかりと分析しながら進化しているようだが、社会科学分野、とくに司法や政治、教育の分野ではこのエピデンスが使われておらず、相変わらず直感や自らの経験のみにたよった判断が下されているようだ。『学力の経済学』んも書かれていたが、教育の分野は結構深刻だと思う。 さて、失敗を成功に変換するためのテクニックとして、著者は①マージナル・ゲイン(小さな改善を繰り返す)、リーン・スタートアップ(小さく始め、検証と軌道修正を繰り返してまとめていく)、RCT(ランダム化比較実験)で検証する、事前検死(あらかじめ失敗した前庭で検証を行う)などを上げている。最後の事前検死などは、いろいろな分野で応用できる気がする。
3投稿日: 2018.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリス流失敗学。ここでも、特徴的な事例を具体的に深く掘り下げている。失敗から学ぶのは、決して過去トラDBを集めるのではない。第一章から、失敗から学ぶことが文化として根付いている航空業界と、権威が幅を利かせて失敗を隠蔽する医療業界の対比が出てきて刺激的だ。データよりも発言が重きを置かれる場合、どうしても後者になってしまう。品質管理の業務でも、医療業界は審査官とそのための文書が重んじられて、技術者の言語である(審査官や上司には理解できない)データが軽んじられていることが気になる。
1投稿日: 2018.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は題名で成功したと思う。原題よりも内容を的確に表していると思う。 航空業界は今や滅多に事故が起きず、医療事故は減る気配がないのは、失敗を客観的に分析し原因や対策を共有しているかいないかの違いだと説く。具体的な事例も多く納得してしまう。失敗は非難や魔女狩りにつながるが、それは解決にはならず更なる悲劇を生むので止めようという。 また、大きな飛躍は小さな改善(マージナルゲイン)の積み重ねだとか、RCT(ランダム化比較試験)で効果を確認しようとか、納得いくことばかりである。 「真の無知とは知識の欠如ではない、学習の拒絶である」byカールポパー、は至言である。科学は失敗を繰り返し修正しながら進歩してきたが、社会もそうだろうか。行動経済学のナッジユニットが英国で動き出したばかりだ。 ここでナッジが出てくるとは思わなかったし、話の展開が後半は早くなってしまったのがやや気になったが、本書は多くの人に読んでほしい。失敗こそが進化の基礎であると思えば、みんな前向きになるに違いない。
1投稿日: 2018.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗から積極的に学ぶ。現実の事例からその大切さを学ぶことができた。「失敗のすすめ」と言えるこの本は間違いなく素晴らしい一冊。 ただ、より成果の高い方法を模索するにあたり全ての要因を試すと言うのは少し非効率かな?このあたりは生産性を重視した考え方、例えば「仮説思考」や「クリティカルシンキング」などとバランス良く使うのがベターかと考える。
1投稿日: 2017.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ学習する組織の超基礎編として読むと○ ・「クローズド・ループ」とは、失敗や欠陥に関わる情報が放置されたり曲解されたりして、進歩につながらない現象や状態を指す。逆に「オープン・ループ」では、失敗は適切に対処され、学習の機会や進化がもたらされる ・失敗から学ぶためには、目の前に見えていないデータも含めたすべてのデータを考慮に入れなければならない(帰還した戦闘機が受けていた銃撃はクリティカルではないところ) ・失敗に対してオープンで正直な文化があれば、組織全体が失敗から学べます ・多くの場合、人は自分の信念と相反する事実を突きつけられると、自分の過ちを認めるよりも、事実の解釈を変えてしまう。次から次へと都合のいい言い訳をして、自分を正当化してしまうのだ。(認知的不協和*自分の信念と事実が矛盾している状態、あるいはその矛盾によって生じる不快感やストレス状態) ・自分の仮説に反する数列で検証する ・われわれはつい、自分が「わかっている(と思う)こと」の検証ばかりに時間をかけてしまう。しかし本当は「まだわかっていないこと」を見いだす作業の方が重要だ。 ・あえて失敗することで学ぶ ・進歩や確信は、頭の中だけで美しく組み立てられた計画から生まれるものではない。生物の進化もそうだ。進化にそもそも計画などない。生物たちが周りの世界に適応しながら、世代を重ねて変異していく ・世界を変えた画期的な機会は、地道な試行錯誤の末に発明された。科学者ではなく実践的な知識を備えた職人たちが、生産性の壁を打破するために、失敗と学習を繰り返しながら開発に取り組んだのだ。発明の論理的な根拠は彼ら自身も十分に理解していなかっただろう ・われわれは世界を「単純化」しすぎる ・現実の複雑さを過小評価する人間の心理的傾向のひとつ:講釈の誤り。物事が起こってから、後付けで因果関係やストーリーを組み立てること ・何かミスが起こったときに「担当者の不注意だ!」「怠慢だ!」と真っ先に非難がはじまる環境では、誰でも失敗を隠したくなる。しかし、もし「失敗は学習のチャンス」と捉える組織文化が根付いていれば、非難よりもまず、なにがおこたのかを詳しく調査しようという意志が働くだろう。 ・非難すると、相手はかえって責任を果たさなくなる可能性がある。ミスの報告を受け、状況の改善のために進んで意見を出すこともしなくなる ・懲罰文化のものでは、誰かをスケープゴートにしなければ、自分たちのみに危険が及ぶかもしれない。 ・失敗から学べる人と学べない人の違いは、突き詰めていえば、失敗の受け止め方の違いだ。成長型マインドセットの人は、失敗を自分の力を伸ばすうえで欠かせないものとしてごく自然に受け止めている。一方固定型マインドセットの人は、生まれつき才能や知性に恵まれた人が成功すると考えるために、失敗を「自分に才能がない証拠」と受け止める ・失敗は恥ずかしいものでも汚らわしいものでもなく、学習の支えになるものだと刻み付けなければならない。 ・「正解」を出したものだけをほめていたら、完璧ばかりを求めていたら、「一度も失敗せずに成功を手に入れることができる」という間違った認識を植え付けかねない。ふくざつすギル社会では、逆にそうした単純化が起こりがちだ。 ・事前検死:プロジェクトがはじまる前に、大失敗を想定し、その理由をできるだけ多く書き出すことで、予防する
1投稿日: 2017.11.18
