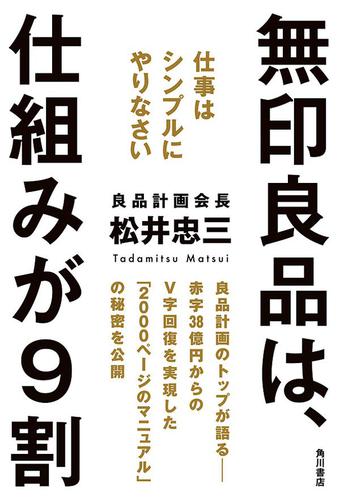
総合評価
(192件)| 38 | ||
| 73 | ||
| 54 | ||
| 6 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近月イチではいく無印、昔もハマっていた時期がありましたが しばらくいかない時期もありました。 何となく、魅力を感じていなかった時期、その理由がこの本を読んで分かりました。 僕は2年ぐらい前からまた行くようになりましたが 今は無印で商品を見るのがけっこう楽しい。 接客も心地よい。 この前もカレーを2つ買っただけなのに レジの人が持っていた2つの袋を大きな無印の袋にまとめてくれました。 そういうサービスがけっこううれしかったりする。 後は、商品を選んでいる時に薦められないのもうれしい。 時間を気にせずゆっくり選べるのがいいですよね。 松井さんがこの本にも書いた仕組み作り、マニュアル作りというのは どんな仕事にも通じると感じました。 自分の仕事に活かせそうなことがけっこうあります。 分かりやすく読みやすい校正もとってもいいです。 難しい言葉も少なくて、ビジネス書の良本です。
0投稿日: 2015.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ無印良品の仕組み化について書かれている。トップが率先して行っていることと、継続して更新する仕組みを作っていることが印象に残る。マニュアルは一度作ってしまっておしまいではない。
0投稿日: 2014.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
無印良品がなぜV字回復したのか?という話。 あんまりビジネス書は読まないんだけど、弊社がちょうど業務マニュアル化に取り組んでいる最中だったため、読んだ。 本当にでよかった。 以下、自分用メモ。 ******* ・戦略よりも実行の方が大事である。 ・一人ひとりの社員に頼るだけだと社内にノウハウが蓄積しないので、会社は滅びる。マニュアル化が大事。 ・現場で自由にモノを言ってもらい、それをマニュアルにどんどん取り入れていく ・優秀な社員を採用するのではなく、社員を育てる仕組みを作る。そして「適材適所」を意識する。 ・7割できていれば善しとする。走りながら考える。ITの仕組みも、7割完成した後で追加・変更を加えていった。 ・マニュアルは全員で作る。 ・目的を明確にする。 *MUJIGRAM(無印良品の店舗マニュアル)の目的 1:知恵を共有する。 2:標準化することで、改善していく 3:上司の背を見て育つ文化との決別 4:チームの顔の向きを揃える 5:普段の作業を見直す ・アルバイトにも理解できるようなマニュアルにする ・店舗用(MUJIGRAM)の他に、業務基準書もある。仕事の内容を誰にでも引き継げるようにしてある。そのおかげで、新人がすぐに育つ。「どのように教えるのか」までもマニュアル化 ・トラブルは全体で共有して、チャンスに転化 ・マニュアルの定着までは時間がかかる。無印良品は5年かかった。 ・挨拶を徹底する⇒コミュニケーション活性化⇒不良品が減る ・「さん」付で呼ぶ。役職名or呼び捨てにはしない。 ・会議は必ずデッドラインまで設定する。 ・部下の「性格を変える」のではなく、「行動を変える」 ・仕事のデッドラインを見える化する ・「部下への注意の仕方」までもマニュアルにする! ・マニュアルは作ってからがスタート。そこから何度もしつこく定着化させる。
0投稿日: 2014.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者の会長さんは本を書き慣れていないのか、同じような内容があちこちに出てきたり、最後のほうでは妙に手順書っぽくテイストが変わっていたりと、ビジネス読み物としてイマイチ。 * マニュアルには「なぜそれをするのか?」の目的を、必ず明記。作業毎にすべて。 * 参考図書・・・「経営は実行」日本経済新聞社 * いきなり意識改革はできない。仕組みを変え実践し、効果を出していく中で意識を変えていく。 * 無印でのマニュアルのテーマ→「顧客視点」と改善提案 * 標準仕様を写真入りで→(自社の5S活動にも使えるかも) * マニュアルというとよくないイメージもあるので、作業標準とか標準作業手順とか呼び名を変える工夫も * 標準なくして改善なし。教える側のためのマニュアルも。→新人教育なども。 * マニュアル自体の改善が重要。それによって、血の通ったマニュアルになる。 * 実行力のある会社にするためには何をすべきかは、シンプル→企業の風土を変える。だいたい、問題の原因の大半はチームの能力ではなく、コミュニケーション不全である。 * 問題の構造を見つけたら、それを仕組みに置き換える。問題を探るのをやめたら思考停止。 * ドラッカーの言葉「人間社会において唯一確実なことは変化である。自らを改革出来ない組織は、明日の変化に生き残ることはできない」 * 残業をなくすために・・・無印では「夕方に新しい仕事を人に頼まない」というルールをつくった。さらに、上司からだけでなく他部署からの依頼事も午前中の早めにするようにした。これによって、指示を出す方もデッドラインを意識して仕事をするようになった。 * 形だけの会議はなくす・・・発言する人はどうしても2,3人に決まってしまう。議長を務める際はできるだけあちこちに話を振るようにしている。そうすると、話の内容が頭に入ってないとパッと答えられないので、緊張感を持って会議に臨むようになる。 * マニュアルに沿った仕事をすると、受け身になると言われる。それは他人がつくったマニュアルをなぞっているだけだから。自分のマニュアルをつくれば、自分を仕事を俯瞰してみれるので問題や課題を見つけられる。
0投稿日: 2014.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ『マニュアルの各項目の最初には、何のためにその作業を行うのかー「作業の意味・目的」が書いてあります。これは、「どのように行動するのか」だけではなく、「何を実現するのか」という仕事の軸をぶれさせないためです。 作業の意味を理解できれば、問題点や改善点も発見できるようになります。マニュアルは、実行力を養うテキストであり、自分が「どう動くか」を考えるための羅針盤にもなるのです。』 マニュアルを活用するということは、こういうことなんだろうと思う。 マニュアルは作ればいい、というものではないが、マニュアル化できないマインドが重要だとか言って作らなくてもいいものでもない。凄く勉強になりました。
0投稿日: 2014.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこんな仕事をシステムチックに出てればいいな。と自分が思っている仕事の仕方の一つの理想形だと思った。 仕組みがうまく機能しているメリット: ・シンプルに仕事ができる仕組みがあれば、ムダな作業かなくなる。 ・情報共有する仕組みがあれば仕事にスピードが生まれる。 ・経験と勘を蓄積する仕組みがあれば自然と生産性が上がる ・残業が許されない仕組みがあれば自然と生産性が上がります。 仕組みマニュアルの効果 ・知恵を共有する ・標準なくして改善なし ・上司の背中だけ見て育つ文化との決べき ・チーム員の顔の向きをそろえる ・仕事の本質を見直せる 気に入った言葉 遠い道ほど心理がある 未来はリスクを取らない限り開きません プロの世界では頑張っても結果が出せなければ力不足だったと判断される リーダーは努力すれば結果が出せる仕組みを考えなくてはいけない 逆境こそだからもの あせらず、くさらず、おごらず
2投稿日: 2014.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアルといえばかたいイメージになるが、業務標準化のためには細かい点までマニュアル化するのが良いと思う。
0投稿日: 2014.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ良品計画のマニュアル文化のDNAがぎっしり詰まった本でした。 どんな人でも同じようなサービスができるようにするために、細かい作業まで徹底的にマニュアルに落とし込んであることに驚きました。 また、マニュアルでは各項目の冒頭に「なぜ」これが必要なのかが記載されています。 これを疎かにしないことが、マニュアルが形骸化しないでいられるひとつのポイントだと思いました。 一見、なんでも「マニュアル」で動く、というと、自分で考えられないというようなネガティブなイメージがありますが、 誰でもある一定の均一なサービスができるようにするためには、まずは「マニュアル」に書いてあることに忠実に動ける、ということが大事なんですね。 また、良品計画のマニュアル文化のいいところは、「もっとこのように改善したら良いのではないか」という点を吸い上げて、それをマニュアルに反映していくという点です。 だから、マニュアルはいつまでも最新で鮮度を保ったままでいられます。 こうした文化を根付かせるのはとても根気のいる取り組みだったと思いますが、この文化を根付かせたことが無印良品の強さになっているのだと思います。 どの企業でも、ある一定の規模になったらこうした「マニュアル化」が必要になるタイミングがくるので、 そのようなタイミングにある企業にかかわる方にはとても参考になる本だと思いました。 私はいいなと思ったページの端を折って読み進めたのですが、折り目がついたページばかりになってしまいました。 また時折読み返したい本です。
0投稿日: 2014.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味深い内容だった。業務をマニュアル化し、それを常に更新する所まで運用整備した所が素晴らしい。しかしボトムアップだけで本当に顧客の要求に応えられるのか、また運用をどのように定着するか自分に置き換えた時にトップからの方針が欲しいと思った。この本を読んでそのままやった社長がいたならばこけてしまう、そこが難しい。
0投稿日: 2014.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ無印良品の良品計画会長の松井氏の一冊。 マニュアル化する仕組み作りで組織を成長させる術や円滑に組織を運営するためのリーダー論が書かれています。 本書でかかれている通り、個人の裁量で行われている仕事というのは本当に多いと感じると共に、その知識の伝承がなされないことはよく感じます。 そのために無印良品が行っているMUJIGRAMや業務基準書といったものを作って知識の共有化をすることは非常に共感しました。 同社のような小売業で多岐にわたる業務のマニュアルを作り上げたところに凄さを感じましたが、それと同時に現場の意見の風通しもよかったのであろうとも感じました。 日々改善を重ねていくことや自分達だけの知識に頼らないことなど誰もが納得できるマニュアルの作成や運用していくうえでの注意点も書かれており、非常に参考になりました。 また、リーダーとしての哲学や日常生活の応用方法なども書かれており、氏の人となりも感じさせる部分もあって好感の持てる一冊でした。
0投稿日: 2014.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ*マニュアルは仕事内容を制限するものではなく、マニュアルをつくれる人になることが目標。 *ノウハウは個人で独り占めするのではなく、組織で共有。 *マニュアルは現場(使う人)が作る。 *計画力より実行力。スピードが大事。 *さん付けで呼ぶ。呼び捨てや役職呼びは意見を言いにくい風潮を作ってしまう。 *他社から知恵を借りる、他社から学ぶ。 *自分の仕事を仕組み化してみる。基本があって応用ができる。 企業名、数値、命令口調。これらがタイトルに入っていると脅し文句のように思えて敬遠していたのですが、無印大好きだし、著者が同じ静岡出身だしということで読んでみる。 マニュアルに関する考え方がだいぶ変わった!他業種の本を読むのもいいなと思いました。 自分の仕事を仕組み化することから始めよう。
0投稿日: 2014.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアルと言うとあまり良いイメージを持たなかったが、属人化の排除、個人の経験を企業の財産へ転化させるという風に考えればとても理にかなっていると感じた。 まず業務の標準化があり、そこから応用が生まれ、それらの意見を吸い上げ常にアップデートされたマニュアルなら、確かに意義がある。 活用されないと意味がないから、定着までに時間と労力はかかりそうだけど、特に個人の裁量が大きい業務に的を絞って、マニュアル、ガイドラインを導入してみようと思った。
0投稿日: 2014.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014/10/8 戦略1流より実行力1流(P.32) ブランドの根幹にあたる部分を変えてはいけない(P.54) 良いマニュアルは新入社員でも理解できる(P.82) 締切を守り、ごみを拾う(P.114) 性格を変えるのではなく、行動を変える(P.152) 行き過ぎたホウレンソウは部下の成長を止める(P.178)
0投稿日: 2014.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログいかにも回覧されそうな本である。マニュアルは型にはめるもの、ではなく、意識の共有と改善のベース。アナログで過度なホウレンソウの否定。
0投稿日: 2014.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアル化すること、仕組み化するとこで 仕事の効率が上がる 合理的になる 努力が成果に結びつきやすくなる 良いマニュアルは新入社員でも理解できる マニュアルの形式 何、なぜ、いつ、誰が マニュアルで人材育成する 人材育成する人を育成する 仕組みはシンプルに 机はきれいに 報告書はA4一枚 残業をなくすには、仕事を減らす
0投稿日: 2014.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014.9.10 実行95計画5 マニュアル作りの重要性 意識改革より仕組み作り マニュアル作りをしながらいつでもupdateして行くことが大切。 もう少し、具体的に種明かしも欲しかった。 一日で変わらない、何年もかけて変わっていく、変えていく!
0投稿日: 2014.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ実体験に基づき仕組みとそれを定着させる実行力について記されている。至極普通な事をしっかりと実現している事が経営の神髄と分からせてくれる。
0投稿日: 2014.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
無印良品の仕事はすべてMUJIGRAMというマニュアルにされている。 優秀な人材でなくても育てるしくみがある 新入社員でも理解できること 日々改善更新をしていく 人材育成する人のためのマニュアル 迷った時は難しいほうを選ぶ 性格を変えるのではなく、行動を変える 机の上がきれい 提案書はA4一枚
0投稿日: 2014.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログウチはスーパーなマニュアルがあるぜっ!ドヤッ! ──ではなく、マニュアルを作る方法、保守・運用する方法、それによるメリット・デメリットこそがこの本から学ぶべき事と感じた。 日々蓄積されていくデータを見事に情報に変換して、それらをマニュアルという形で体系化して、仕組みとして一般化して浸透させるプロセスが実に素晴らしい。
0投稿日: 2014.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ良品計画の「仕組み化」の解説・事例紹介を通じたマネジメントのあり方についての本。 ただの定型化のためだけのマニュアルではなく、業務水準の標準化とノウハウの可視化、更にそこからの改善を促すことを目的とした「生きたマニュアル」作りの重要性とその方法について、非常に示唆に富んでいたように思います。 属人的富んで思われる業務やそのノウハウについて、どうすればマニュアル化(=標準化と可視化)出来るかという視点を常に持っておくことがポイント。 実態として、日本ではマネージャー=プレイングマネージャーないしみんなより出来るリーダーとみなされがちですが、マニュアル化の重要性を通じて、マネジメント及びマネージャーがどのようにあるべきかについて学ばさせて頂きました。
0投稿日: 2014.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアル作成の重要さとその手法と効果について述べている。 マニュアルにMUJIGRAMという名前をつけた。 実行95%、計画5%。 仕組みに納得して実行するうちに意識が変わる。 徹底して具体化する。丁寧にとは何か。 現場が作る。 行動により理念を浸透させる。
0投稿日: 2014.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ無印良品には分厚いマニュアルが二冊ある。 口頭で言えば良いような事まで、わざわざ文章で書き記す。 何事も基本がなければ応用がないのと一緒で、会社の仕組みが可視化されてなければ、知恵も売上も生まれない。ベースが出来れば改善も出来る。
0投稿日: 2014.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社の仕組みを真剣に考えさせてくれる1冊 以下レバレッジメモ マニュアルは仕事に潤いさえ与えてくれます。無印良品のマニュアルは現場で働くスタッフたちがこうした方が、いいのにと感じたことを積み重ねることで生まれた知恵です。また現場では毎日のように問題点や改善点が発見され、マニュアルは毎月、更新されて行くのです。仕事の進め方がどんどんブラッシュアップされるし、自然と改善点がないかを探しながら働けるようにもなります。このように仕事が停滞せず常に動いている様子を私は血が通うと表現しています。そしてMUJIGRAMや業務基準書は無印良品にとっての血管です。血管が詰まれば組織も人も動脈硬化を起こします。常に成長し続けないとあっという間に衰退するのが企業という生き物です。現状維持はあり得ません。反対にマニュアルが更新され続ける限り成長は止まりません。仕事のマニュアルは成長を測るバロメーターでもあるのです。 戦略二流でも実行力一流なら良し 戦略一流の企業と実行力一流の企業。この二つの企業が戦った時勝つのは間違いなく後者です。戦略を考えることももちろん重要ですが、実行に移せなければ意味がありません。「議論を重ね保養地での会議を何度も開くが行動は起こさない。これが実行力のある企業都内企業の違いの一つだ」毎日何時間もの会議を開き、けれども結論は出さずに次回鵜に持ち越す。そのような企業は多いのではないでしょうか。戦略や計画をいくら綿密に練っても、実行しない限り、絵に描いた餅にすぎません。多少の戦略の間違いは実行力で取り戻せます。まずは、第一歩を踏み出す切断が必要です。 経営にまぐれはない。これは私が経営者になってからつくづく実感していることです。業績が好調なのは景気が良かったから、ブームが起きたからといったたまたまではなく、そこには何かしらの理由があるはずです。そして業績が悪化したのも時代の流れなどの漠然とした原因ではなく、たいていは企業や部署の内部に問題が潜んでいます。それを掘り起こして対処できれば業績に反映されるでしょうし、そうでなければ対処法が間違っているのです。実行してみて、結果が出ないのであればまた改善するという繰り返して、組織は骨組みをしっかりと固めていけます。安易な成功法則などありませんし、痛みを伴わない改革もありません。リーダーが腹をくくれば必ずV字回復を成し遂げられるものなのだと、私は信じています。 無印良品では、店舗で使うマニュアルをMUJIGRAM、本部(本社機能を持つ)で使うマニュアルを業務基準書と呼んでいます。「マニュアル」と呼ぶと仕事を厳密にコントロールするツールのように思われてしまいそうなので独自の名前を付けることにしたのです。MUJIGRAMも業務基準書も目的は業務を標準化することです。 実行力のある企業にするにはオペレーションをもっと科学的にしなければならないと考え、取り組んだのがMUJIGRAMでした。機動力のある現場にするためには、仕事を標準化すること。誰もが実行できる素地を整えなければ、その先の発展もないと考えたのです。 このように、冒頭で何、なぜ、いつ、だれがの4つの目的を説明してから、ノウハウの説明に入っていくというフォーマットになっているのです。これぐらいのこと言わなくてもわかるのではと思うかもしれませんが、その一方的な思い込みこそ個人の経験や勘に頼りがちな風土を作ってしまうのです。コミュニケーションとは言えば伝わるのだと思いがちですが、実際は言ってもなかなか伝わりません。明文化して初めて意識できるものです。さらにそれを繰り返し教えることで、本当の意味で体得したというレベルになるのだと思います。 マニュアルは業務を標準化した手順書であるだけではなく、社風やそれぞれのチームの理念とも結びついています。マニュアルがこの2つの懸け橋としての役割を担っていると言ってもいいでしょう。ですからマニュアルは時間がかかったとしても自分たちの手で一から作り上げていくしかないのです。MUJIGRAMも軌道に乗るまでは5年ほどかかりました。遠い道にこそ心理があるのです。これは私の信念の一つですが、迷った時は大変な道を選ぶと結果的に正しい道を歩めます。マニュアル作りは手軽にできるとは言えませんが、必ずチームの変革を実現できるはずです。それを信じて作り続けた人にだけ結果はもたらされます。 チームの根本的な問題は能力ではありません。社員同士のコミュニケーションや信頼関係の希薄さが不振要因になっている場合が多いのです。そのような状態では、どんな改善策を講じても、勝てるチームにはなりません。部下に訓示を垂れるよりも朝のおはようございます、退社するときのお疲れ様でしたのたった一言を徹底する。これだけでも、信頼関係は築けるものです。一流の起業、一流のチームを作り上げるには、毎日小さなこと、例えば挨拶名を徹底して実行するしかありません。それも部下に指示を出すだけではなく、まずはリーダーが率先して行動することが大事です。 経営の神様と呼ばれるピータードラッカーも、人間社会において唯一確実なことは変化である。自らを変革できない組織は、明日の変化に生き残ることはできない。と語っています。変化こそ成長の源泉であり、組織やチームに内向き志向が定着すると、死に至る病になると言えるでしょう。自分のチームや部署を成長させたいと、努力されているリーダーは多いと思います。そして同時に思うように成長しない部下に頭を悩ませているかもしれません。私も社長に就任して1年ほどたったころ同じような悩みを抱えていました。そして最終的にはこういう結論に至りました。自分の器以上には組織はよくならないのだ、と。いくら組織の仕組みや体制を変えても結局リーダーの器以上には成長していかないものです。それならば、リーダーは、チームメンバーが異文化に触れられる環境を積極的に作り上げることが責務なのではないでしょうか。 実行力のあるチームを作るにはメンバーのモチベーションが高いことは必須条件です。当たり前の話ですが、やる気と積極性のあるメンバーで泣ければ、ビジネスにおける困難な課題に立ち向かえません。部下のモチベーションを保つためには、給料を上げることが一つの方法ではあります。しかし一時的にモチベーションが高まるだけで持続させることはできません。部下のモチベーションを上げ、チームや部署全体の引きを上げるのに必要なポイントは二つあります。それは、①やりがいを与えることそして、②コミュニケーションです
0投稿日: 2014.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ意識改革より仕組みを変えることで部下を変える。 この部分には膝を叩いた。 熱いメッセージだけでは人は変わらないのだ。
0投稿日: 2014.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアルには賛否両論があろうが、それは内容と使い方だ。無印を立て直すには必要であったということ。全てには当てはまらない。
0投稿日: 2014.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ無印良品には、「MUJIGRAM」と「業務基準書」というマニュアル(仕組み)があり、どちらも200~600ページあり、常に更新されている。マニュアルは利益を出し続けるための原動力であり、初心を忘れないためのものである。日々の習慣をマニュアルに落とし込むと面白いです。
0投稿日: 2014.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ神は細部に宿る ミース・ファン・デル・ローエ ディテール=仕組みに拘ることが企業の力を決める MUJIGURAMと業務基準書 まず目的と意味を認識させる。 戦略2流でも実行力一流ならよい。 実行力が95%ならだいじょうぶ。 リーダーは徹底力が必要。 ビジネスモデルを見なおして、仕組みを作る 現場の意見を仕組みにする。 走りながら考える。 マニュアルを作るプロセスが大事。 現場の人たちがマニュアルを作る。 仕事のやり方を最新版にする。 マニュアルを常に作り変える 商談のメモ、名刺の管理をマニュアル化。 迷った時は、大変な道を選ぶとたいていは正しい道。 挨拶をする ゴミを見つけたら拾う 締め切りを守る 常に組織が変化することを考える。 ゆでガエル方式で、変える。 モチベーションは、やりがいとコミュニケーション。 部分最適の集積は全体最適にはならない。報連相だけでは全体の連帯を考えなくなる。 自分の生活もマニュアルで常にアップデートする。
0投稿日: 2014.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアルに対しての考え方が面白い。ここまでこだわらなくてはうまくいかないのかというレベル。 後は他の自己啓発本でも知ることの出来る内容。 ただ読んでよかった。
0投稿日: 2014.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログKindle版を読みました。 マニュアル化、の、「どこまで詳しく説明するか」「どの程度時間をかけて作るか」など色々難しいところに対して、具体的な例でスパッと説明されています。姿勢も「徹底的にやらねば」という鬼気が感じられて、重い腰が上がったところです。
0投稿日: 2014.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事を標準化(マニュアル化)をすることで、仕事の仕組みを作り効率的な働き方を促す本。とことん具体的にやるのがポイント。 非常に共感が持てた。経験を自身の中のみに蓄積するのは 周りのためにも自分のためにもならない(結局忘れるから) これを真似しようとしている企業は多々あると思うが、中の人のマインドが変わらないまま実行しようとするので中途半端になっている気がする。 自身もできるところからはじめたい。
0投稿日: 2014.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログぼくも仕組み作りはとっても大事なことだと思うのね。中でもマニュアルはとっても大事。作る目的は二つあって、ノウハウを目に見えるように明文化していくと、やらないといけないことが何かってとってもよくわかる。だからその先のこと、つまり問題点や改善点も見えてくることがあるのさ。 もう一つは、マニュアルを手に取れば、たちまちに誰でもできるようになるということ。いってみれば、プラモデルの説明書みたいなもの。順番に必要なパーツを組み立てていけばできてしまうもんね。 実際、今仕事でこの仕組みが残されていなくって、とっても困っているの。上司が登校拒否になってしまい、どこまでやっているのかすら共有情報として残されていないの。この本で言うMUJIGRAMが残されていれば、なんのこともなくできるのにって思っているのさ。仕事ができない人もマニュアルを作れば褒められるのにね。ちゃんとしたやつをね。 でも仕組みも、仕組みとして、何も考えずに惰性でやってしまう習慣がついてしまうと、逆に経年劣化していって害悪にもなってしまうから気をつけてね。 でも、やっぱり仕組みを作るとお金も整然と流れるようになるし、必要なものなのだと思ったよ。
0投稿日: 2014.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログうちの会社が、いかに仕組みを軽視しているか、痛感しました。 誰がやっても一定の質を保つためのマニュアル、みんなで作るマニュアルなど、とても参考になりました。 今後の仕事に役立てたいと思います。
0投稿日: 2014.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログテレビ東京系の経済番組で著者が、無印良品のV字回復、現状の好成績の理由を独自のマニュアルにあることを言っていたので、気になり読んでみた。 内容的には、企業の風土にあった、誰でもわかるようなマニュアルを、現場からのボトムアップで、逐次更新していくことが大切であるということだと思う。結果的に、個人の能力のみに頼らない、業務の効率化が達成されることになると思う。 どんな組織でもそうだが、個人の資質を生かす形で組織を作ると上手くいっているときはよいが人事異動で動くと後任者が苦労したりする。逆に、個人を生かさず組織の歯車とすると閉塞感がでる。このバランスをどのようにとるか、それらの1つの解答があると思った。 また、マニュアル化するというのは、口承伝的な業務の内容を整理するというのはその通りだと思った。
0投稿日: 2014.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ定型業務に関わっている方、定型業務を管理している方には、この本の内容がいかに重要な意味を持つかが理解できるはず。 組織の構成員に、毎日つつがなく業務を実施させることに難しさと、その対策のヒントが詰まっている。
1投稿日: 2014.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直今の自分において、本の内容をどのように消化すればよいのか分かりません。おそらく、仕組み化したときの効果が腹に落ちていないからだと思います。 結局のところ、仕組み化をやり切れば効果がでるのだろうけど、やり切るプロセスの部分が困難であり、仕組み化のミソだと思うのです。なので、この本はトップやトップに近い方が読むと良いのかもしれません。私のように現場でやっている人間からすると、やり切るプロセスの部分をどのようにするか?をもっと知りたいと思いました。
0投稿日: 2014.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ○マニュアルの各項目の最初には、何のためにその作業を行うのか「作業の意味・目的」が書いてあります。これは「どのように行動」するかだけでなく、「何を実現するか」という仕事の軸をぶれさせないためです。(15p) ○業績が好調なのは景気がよかったから、ブームが起きたから、といった”たまたま”ではなく、そこには何かしらの理由があるはずです。そして業績が悪化したのも時代の流れなどの漠然とした原因ではなく、たいていは企業や部署の内部に問題が潜んでいます。(66p) ○モチベーションを維持する二つ目のポイントが「コミュニケーション」です。とにかく伝達経路をシンプルにし、社員の意見や行動に対してしっかりフィードバックすることがカギです。(145p) ★マニュアルといっても受け身ではなく自らが作る。自発的社員を育成し、現場からあがった改善点を全社で共有する。
0投稿日: 2014.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「標準なくして、改革なし」 2000ページに及ぶMUJIGRAMというマニュアルを作成、日々改良していくことで、仕事のカイゼンにつなげる。その実例。 言葉の意味を明確にし、必ず「何」「なぜ」「いつ」「誰が」を明確にしている。 ex.「レジ対応」 (何)お客様が購入される商品の代金をいただき、商品をお渡しするお客様対応です。 (なぜ)レジは店舗業務の20%を占める重要な仕事なため。 (いつ)随時 (誰が)全スタッフ このMUJIGRAMを現場からの改善提案でブラッシュアップする。まずエリアマネージャーが選別し、その後本社が採用不採用を検討し、MUJIGRAMを更新する。現場だけでも本部だけでも無く、エリアマネージャーが中庸を押さえる。 著者は例えば家事や、部下への注意方法などを個人でマニュアル化してみることを勧めているぐらいだから徹底している。膨大な量だから周知と実行が一番難しいのだと思うけれど、うん、現状がコミットされてはじめて改善の議論が出来るようになる。確かに。 ・堤氏は大変なマーケッターですから、その域に達する企画書をつくるのは困難を極めます。現場からのヒアリングだけを材料にしてつくった企画ではとても通りません。構想を最大限に膨らませ、時には現場のニーズを斟酌することすらできませんでした。 したがって、晴れてその企画が通っても、膨大な企画書をつくり上げるだけで疲れてしまい、実行する気力がわいてこないのです。しかも、現場を無視した机上のプランなので、現場に提案しても「これは無理ですよ」と一蹴される始末です。 …私が仕組みづくりを重視したのは、無印良品を実行力で一流にするためでもあります。当時のスローガンは「実行95%、計画5%」「セゾンの常識は当社の非常識」でした。 ・私が良品計画の無印良品事業部長に就任したころの話です。 千葉県の柏高島屋ステーションモールに新規出店することが決まり、開店の前日に現場を訪れました。開店前日はいつもそうですが、店長もスタッフもみな高揚感があり、忙しそうに駆け回ります。 夕方の6時頃には商品を並べ終え、スタッフは「お客さん、たくさん来てくれるといいね」「この商品、私も欲しいな」などと話しながら一息ついていました。 その時、他店の店長が応援に駆けつけました。 そして売り場を一目みるなり、「これじゃあ、ダメだよ、無印らしさが出ていない」と、いきなり商品の並べ替えを始めたのです。新しい店の店長は戸惑っていましたが、ベテラン店長に物申すわけにもいかず、結局スタッフ総出で並べ替えました。 ようやく並べ替えが終わったころ、今度は別の店長がやってきました。そして、「ここはこうしたほうがいい」と、直しはじめました。 …当時は、店長の数だけ、店づくりのパターンがあったのです。 その光景を見ながら、私は「まずいな。このままでは無印良品の未来はないんじゃないか」と感じていました。 ・社員、あるいは部下の意識をどう変えればいいのか。これは多くのリーダーが直面する問題でしょう。たいていは教育から変えようとして、外部からコンサルタントを招き、社員に研修を受けさせて、意識改革をしようとします。しかし、それでうまくいく試しはありません。 私が西友で人事を担当していたときの話です。 業績が悪化していくにつれ、社内でも段々と危機感が生まれました。まずは幹部の意識改革をしようということになり、取締役から部長まで300人ぐらいの幹部が二泊三日の研修に参加することになりました。 これは、グループ分けし、同じグループになった人から、一人ひとり長所や短所を指摘されるという”360度評価”をする研修でした。 幹部になるくらいの人たちは、それなりにプライドや実績を持っているので、他人から思ってもいない短所を指摘されるのは不愉快なものです。研修の夜の懇親会の席で、私は幹部に呼び出され、「お前、なんだってこんな研修をやろうと思ったんだ!」と叱責を受けたりもしました。 そこまで苦労して行った意識改革の研修―その効果は、どれほどだったと思いますか? 成果は、まったくありませんでした。 結局、このショック療法も効かず、意識改革も進まず、西友は持ち直せませんでした。その後、西友はウォルマートに買収されています。このことからわかるのは、いきなりの意識改革は難しいということ。そもそも、ビジネスモデルが世の中のニーズと合わなくなっているから業績が悪化しているのであり、社員の意識だけを変えようとしても根本的な解決にはなりません。ビジネスモデルを見直して、それから仕組みをつくっていく。その仕組みに納得して、実行するうちに、人の意識は自動的に変わっていくものなのです。 *** カンブリア宮殿でほぼ同じ視点で放映が。 村上龍曰く、 「マニュアル」は創造性と相反するイメージがある。 だが、小説が、普段誰もが使う言葉を組み合わせて書かれるように、創造とは、組み合わせであり、空想的で身勝手なアイデアなどではない。 (当著者の)松井会長がロシアに生まれていたら、社会主義は今も存在したかも知れない。 ああ、改善に繋がるマニュアルと結びついた社会主義は、面白いな、本当に。
1投稿日: 2014.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ努力を成果に結びつける仕組み作り、についての教科書。 自分の仕事についてもマニュアライズの工程にかけてみることで、振り返りとアップデートをすべきということが1番勉強になった。
0投稿日: 2014.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者の強い確信が随所に出ていてそのパワーを感じました。前半はとても楽しく読めたのですが、後半少し飽きてしまいました。 ただやり方を示すのではなく、何のためにやるのかまで示すことはとても大切だと共感した。
0投稿日: 2014.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなかよくできたビジネス書に仕上がっている。ただ同じことを言ってるだけなので途中で飽きる。とりあえず前書きと目次読んで想像した内容で間違いございません。人には何故やるかを意識させることと仕組み(マニュアル)を作ること、アップデートして、最後までやり抜く。これを無印の例で何回も話してる感じ。やり抜くことが大事だと思うけど、そのノウハウはほとんど書いておらず、松井さんがそういう点で優れた人だったという印象。 本で、自分が経験できないことから経験値が得るってのには良いっすよ。以上レポッス。
7投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこの手のビジネス本の内容を、自分のものにしようとするのは難しい。 続きはブログで。 http://nekura-tohsan.blogspot.com/2014/01/9.html
0投稿日: 2014.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアルを無印良品が使って、業績が、回復したという話。製造業では普通にやられている標準化ということだと思うが、それを徹底するっていうのが難しい。そこをやり抜くトップの意思とそれで成果があるという実績がモチベーションになってるのだとおもう。
0投稿日: 2014.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕組み化の重要性を説いてくださる一冊。実際に私の立場柄、改めて見える化の大切さを実感した書籍でした。
0投稿日: 2014.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ赤字に陥った時の意識改革のお話、要は仕事の標準化ができていなかったという話です。こんな大企業でも個人の感性で仕事をしていたことが驚きでした。もっと驚いたのはこの本がベストセラーということだれが読むのでしょう。
0投稿日: 2014.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアルというと画一的なものととらえがち。ここでいうマニュアルは仕事の基準を定めたもの。基本があるから応用がきく。更に進化する。まずは、自分の仕事を仕組化してみようと思う。
0投稿日: 2014.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くの人が携わる職場で、効率良く・間違いなく仕事を 進めるために、マニュアルは非常に役立ちます。 でもマニュアルをみて仕事をするのは単なる作業に なりますので、すぐに陳腐化して企業の競争力が落ちます。 この本では、職場の全員で絶えずマニュアルを更新して行き、 現場に基づいた最新のやり方を提唱しています。 マニュアルを作ることは、皆んなのルールを決める事ですから、 相当考えなくちゃいけないです。 この「考える」ということは これから日本の企業が生き残るためには、非常に重要な事だと 思います。 でも一番共感したのは「あせらず、くさらず、おごらず」という 言葉だったりしました(笑)
0投稿日: 2014.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ無印良品復活の原動力 ・努力を成果に結びつける仕組み ・経験と勘を蓄積する仕組み ・ムダ。徹底的に省く仕組み ・変化こそ成長の源泉 ・チャレンジしろ、リスクを取れ、冒険しろ→成長 ・給料UPは、短期的なモチベーションUP、必要なのは、①やりがいのある仕事、②コミュニケーション ・育てる仕組み>優秀な人を集める仕組み ・Invest existing people > Hiring new people ・メンバーが経営層にダイレクトにモノが言える仕組み
0投稿日: 2014.01.11社員が自発的に考え、仕事をさせる環境を作る仕組み
要点が分かりやすく書かれており、読みやすく、参考になる本。 ただ、「もっとやる気を出せ」と言うのではなく、どうすればその「やる気を出させるのか」を考える。 人から言われて動くのではなく、自発的に考えさせて動く仕組み作る。という内容が書かれていました。 具体的な仕組みの作り方も書かれていましたが、一番重要なことは、常に前進すること。 今までにない考え方は、社内では生まれない。 この本だけではありませんが、様々な本、実際に話しを聞いて、 今まで思いつかなかった考え方を自分の頭にインプットするのは組織を変える上で良いことだと思います。 その上でこの本は、新しい考え方を強くインプットする方法として、良質の本と思いました。おすすめです。
2投稿日: 2014.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事のマニュアルって何だっけ?って悩んでる方にオススメ ・チームリーダーがやるべきこと ・勝ち続ける仕組みの作り方 ・締め切りを設定していない作業は、仕事とは言わない など、マニュアルの概念が変わった。勉強になりました。 私個人が「なるほど」と思ったところは、付箋、折り曲げがあります。
0投稿日: 2014.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ押し付けではなく吸い上げ、外に目を向け他社の知恵を借り(=改善余地を探る)、問題の根っこをつかみ努力をすれば結果を出せる仕組みをつくり、何を実現するかという目的・小さなことを大事に、地道な仕事の習慣を根づかせる… ということのようだ。 当たり前の内容が多いのかもしれないが、「ビジネスモデルが世の中のニーズと合わなくなっている」、「社員同士のコミュニケーションや、信頼関係の希薄さが不振要因」ということを素直に認め、これをトップ主導で、押し付けではない姿で実際に改革したという実績の説得力はデカイ。 当たり前の内容のようで、実際に真似をするのは容易くはない。 「反対勢力が積極的に関わらざるを得ない状況にした」というのは なるほど である。
0投稿日: 2014.01.06マニュアルづくりをしてみたくなる
マニュアルがあることの良さ、その活かし方を知ることができる。 マニュアルと聞くとネガティブな印象を受けていたが払拭された。 具体的で誰にでも同じように解釈のできるマニュアルを運用、活用していくことで、ノウハウの蓄積やクオリティを一定に保つだけでなく、見えていなかった問題の発見や実行力の向上も見込めるようになる。 仕組みを作ることの大切さを実感できた。 ルーチンワークやなかなか抜け出せない仕事をしている方は一度読んで見ると仕事の取り組み方や、考え方が変わるかも。
1投稿日: 2014.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
bossより借本 MGIGRAM 自分を常にアップデート 膜煩悩-あせらず、くさらず、おごらず- ああ、自分でも実行したいことが結構ある。 当たり前といえば当たり前だけど、こうして再確認することが大事かと。
0投稿日: 2014.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕組みをマニュアル化するというと響きはネガティブに取られる可能性もあるが、今の時代に必要なテーマを明文化、言語化している良書。オススメ。応用して自分用マニュアルをつくろうと思う。
1投稿日: 2013.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社で支給された書籍ですが、なかなかよい本でした。 いいマネジメント、いいティーチング、いいコーチング、 そしていい働き方のエッセンスが詰まっている本です。 加えてどのような人材を使ったとしても、 少なくとも失敗しない方法論のヒントを示してくれています。 自分も基本的には2:6:2の法則は現実だと思っているので、 いかに6の人、下の2の人の能力を発揮させるかで、 その企業が伸びるのかどうかが決まると思っています。 そのための一つの解に触れたような気がします。 あとはこれをいかに実践できるかでしょうね。 さ、もう一冊のコトラーも早めに読んでしまおう。
0投稿日: 2013.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は無印良品の社長の著作。業績が悪化した時期に社長に就任し、数々の改革で再びトップブランドに成長させた手法が描かれています。 業績が悪いときに彼が取り組んだのは「仕組み作り」。普通は経費カット、リストラなどのマイナスアクションを行うところ、プラスアクションに変わる土台作りに没頭されました。 具体的に仕組みづくりというのは、細かなところまで記載された「マニュアル」でした。 小売業も対面販売という面ではサービス業。質の高いサービスをするには「質の標準化」が必須です。そういう意味でマニュアルをきちっと整備することを改善の筆頭に挙げた著者の手腕に感服しました。
0投稿日: 2013.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアル人間などと揶揄される『仕事の仕組み化』についてですが血の通ったマニュアルとはここまで仕事をイキイキとした環境に持って行ってくれるものだと感心させられます 危機感をもって仕事をする 高い目標に向かって前進する 赤字企業からのV字脱却にはこんな根性論がつきものに思えますが事実はもっともっとロジカルであるのも面白い 『経営にまぐれはない』P.66 本の内容は正直、薄いのですが無印良品での実例も多く紹介されていて得られるものはシンプルですが厚いです 仕組み化・マニュアル化された無印良品が『「働きがいがある会社」ランキング』で2011年から3年連続で25位以内にランクインされているのも興味深い結果 もし自身が経営者サイドで会社に取り組む立場であったら賃金カットでもなくリストラでもなく事業の縮小でもない仕組みづくりは試してみる価値はとてつもなく大きいかもしれません ここからは本書では書かれていない雑感 仕組み化最大のメリットは『忘れる』ことのようにもとれる マニュアル作りとは勘や記憶に頼るのではなく記録として蓄積させていくこと 忘れていても必要なときにマニュアルから思い出す 知らないことでもマニュアルを見て経験者の要領を復元できる そして体が覚えていく これは毎日新しいことでも同じことをするでも頭で考えることをしないので楽である 楽をした頭は仕事で必要なことに向けて集中できる そんないいサイクルがMUJIGRAMにはあります 無印良品にとって仕事で必要なことに向けて集中とは新たな仕組みづくりだったりする つまりはMUJIGRAMが更新されていく限りは景気の影響などで波はありますが長期的にみて良い方向にしか行かない自己増殖プログラムなのだ
0投稿日: 2013.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ・マニュアルを作り上げるプロセスが重要で、全社員で問題点を見つけて改善していく姿勢を持ってもらうのが大切。 ・マニュアルを作る目的を意識すること。 ・担当者が異動になっても同じレベルで業務がなされるようになる。 ・リーダーの器以上に組織は成長しない。
1投稿日: 2013.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ■マーケティング A.無印良品は、仕組みづくりの一環として、経営から接客まで仕事の全ノウハウを記した2つのマニュアル ――「 MUJIGRAM 」(店舗で使うマニュアル)と「業務基準書」(本部の業務のマニュアル)を整備し、徹底的に見える化を図った。 B.●MUJIGRAM は、個人の経験や勘に頼っていた業務をノウハウとして蓄積させるためのもので、その特徴は、次の通りである。 ・写真や図が、ふんだんに盛り込まれている。 ・「顧客視点」と「改善提案」の2 つを大きな柱とする。 ・本部も現場も、全てが関わってマニュアルをつくっている。 ・誰が読んでも理解できるよう、徹底して具体化されている。 ・スタッフを指導する立場の人のための内容も盛り込まれ、「教えるためのテキスト」としても使える。
1投稿日: 2013.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕組みを作ることが効率化になるだけでなく、改善のヒントにもなる。具体例が書いてありスッと入ってくる。
0投稿日: 2013.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕組みを作ることの重要性とそれを運用、継続、進化させる方法を認識させてくれる1冊。 もう少し、具体的なマニュアル部分を見たい気持ちになったが、内容は十分伝わる。自社にもあてはめて取り組んでみたい。
0投稿日: 2013.11.07無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい
具体的な内容が載っているので仕事に活かしやすいと思います。無印良品が好きな方は楽しく読めるかもしれません。
0投稿日: 2013.11.07無印にしたいくらいつまらない本
アリの中には一見ムダな行動をするアリがいる。 それはムダではなく必要な行動であるらしい。 全てをシンプルに合理化することに違和感を感じた。
0投稿日: 2013.11.07仕組みづくりとともに人づくりも必要
情報経験の共有など、組織を運営していく上で、マニュアル化は有意義だし、不可避。無印のような業態にあっては特にそうなんだと思う。 マニュアル化は米国のような多様な文化的背景を持つ者が共存する移民社会では必須なものなんだろうし、そこで発展してきた文化だと思う。しかし、彼の国で、その行き着く先は、人をいつでも取り替え可能な部品と化することになっていると、個人的には思う。 日本ではマニュアルによる情報経験の共有がともすれば軽視されてきた嫌いもあるのだろうが、この本が示すように、適切にマニュアルを活用しつつ人を生かすという文化が日本には合っているのだろうと思うし、また、この本に書かれているようなことは日本人社会だからこそ円滑に遂行できたのだと感じた。
1投稿日: 2013.11.07単純ですみません
単純に無印ファンなので・・・。 好きな会社の本だと読みたくなりますね。
0投稿日: 2013.11.05私の借金も...
「決まったことを、決まった通り、キチンとやる」だけ。 実はこれが一番難しい。 その難しい難題に取り組み乗り越えた者だからこそ書ける、経営の極意本。
0投稿日: 2013.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕組み(マニュアル)の重要性を再認識できる書。 社員全員が天才であれば仕組みなど必要ないが、そのような会社は皆無で、やはり仕組みは必要となる。 その際、どのよう点を意識して仕組みを作っていくかを本書では無印での事例を交えながら解説している。なかでも、「現場発のアイデアを仕組みにしていく」という点は非常に参考になった。 以前、優秀な上司が「マネジメント層は会社がうまくいくための仕組みを作るのが仕事だ」と言っていたが、本書を読むことでその言葉が腑に落ちた。
0投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「すべての店が同じクオリティのサービスを提供する」というスローガンのもと、全てがマニュアル化されているそうです。なんとも無印良品らしいと思いました。改善を反映する仕組みもしっかりと整っているようで、素晴らしいとおもいました。仕事にも役立つ良本でした。
0投稿日: 2013.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
一度できてしまった仕組みやらマニュアルの更新がつらい。(現在進行形) いっそ最初から作りたいと思うほど。 職場でも利用できそうな考えがたくさんあり、勉強になりました。 素晴らしい仕組みを作っても、メンテしないと棚でホコリを被って 使われなくなるとのこと。 頑張って更新します・・
0投稿日: 2013.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアルがいかに大切か、マニュアルを作る時にきをつけなればならないことを教えてくれる。 マニュアルを作ったところから仕事が始まる。 定期的に改善をしていく。 など、大変参考になった。
0投稿日: 2013.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際のマニュアルの見本があるのかと思いきや、マニュアルの作り方、考え方、ばかりです。 正しいことが書いてあるのですが、物足りないというのが、正直な感想です。
0投稿日: 2013.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったなぁ。仕組みが9割、マニュアル主義、ってどうなのよ?っと勘ぐって読み始めたけど、読み終えた感想は、マニュアルすげぇーな!でした。 以下、参考になった点。引用、自己解釈含む。 ・マニュアルを作ることで、現在の仕事の内容を深く棚卸することが出来、問題点の発見、改善につなげることが出来る。 ・マニュアルは一度作って終わりではない。常に最新版にアップデートしていく必要がある。また、現状の仕事が整理されているからこそ、そこを基軸としたアップデートが出来る。 ・一度作ったマニュアルに対して現場が常に改善提案を行い、アップデートすることが、当たり前になるように仕組化をしていく。これが仕組化されて、初めてマニュアルが血の通った使えるものになる。 ・多くの企業はマニュアルを作ったことに満足し、一生懸命作ったマニュアルだけに固執し、内容を押し付け、且つ更新することを怠る。結果、日々変化する現場とのギャップが発生し、マニュアルそのものが形骸化するだけでなく、害にすらなる。 ・リーダーたるもの、個々人の努力そのものが成果として結びつくように、いかに「仕組み化」できるかを考えるべき。個々人の知恵が暗黙知にならぬように留意する必要がある。 ・社員の「意識」を変えようと思って、訓示をいくらたれたところで意識は変わらない。日々の行動の変化の先に意識の変化が生まれる。意識を変える為には、日々の行動を修正していくような仕組みを取り入れなければならない。仕組み改善→行動変化→意識変化、の順番を間違えないこと。逆ゆでガエル作戦。 ・ミスが起きた時こそ、マニュアル化。1つのミスの先に潜んでいるであろう、いくつものミスを先回りして潰せる手を打つ=マニュアル化のアップデート。ミスを追求して、犯人捜しをしても、組織としての成長は無い。
0投稿日: 2013.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本で書かれているのは、主に無印良品で使われている「マニュアル」を用いた運営の仕組みについて。 正直、最初の章で全てマニュアルをもとに仕事をしているというのが書いてあるのを読んで、この会社は面白くないだろうなぁと思ったが、読み進めていくうちに、この会社の仕組みはすごいなぁと思うに至った。 マニュアルと聞くと、上から押し付けられたものをただ現場が従うだけというような印象を持つが、無印良品のマニュアルは全然違う。マニュアルに従って仕事をするというのは変わりないが、そのマニュアルに対して現場から意見を上げていくことが推奨されているし、そうして吸い上げた意見をもとにマニュアルが頻繁に改訂される。 無印良品で使われているのは単なるマニュアルではなく、現場での英知を取りまとめた、巨大なノウハウ共有の仕組みになっている。 何年か前に、やれ属人性の排除だとかいって業務プロセスの標準化や ISO20000のようなフレームワークがもてはやされたことがあったけど、そういうのを何も考えずに導入した企業が軒並み形式だけで終わってしまうのとは異なり、無印良品ではみんなが理解して継続的改善 (CSI) の領域まで具現化されているようだ。これははっきりいって驚異的。 この本を読むと、無印良品の松井さんは理系の感性を持ちつつ経営者としての手腕を持った人だというのが分かる。そして、いろんな事をすごく勉強している。無駄を排除して効率を高めつつ、みんなが最大のアウトプットを出せる仕組みを見ていると、弊社にも通じるところがあると感じた。 とても面白かったし、こういう考え方もあるんだという感じで大変勉強になった。
1投稿日: 2013.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ【目的】 経営者、会社の部課長クラスのチーム・リーダーに対し、「努力を成果に結びづける仕組み」、「経験と勘を蓄積する仕組み、「ムダを徹底的に省く仕組み」を伝える。 【収穫】 マニュアルの必要性と、それが活かされ継続的に改善されるための仕組みについて知ることができた。 【概要】 本書は、無印良品における以下2つのマニュアルの一部を公開しながら、「仕組みを大切にする働き方」を紹介する。 ・無印良品の店舗で使っているマニュアル―MUJIGRAM ・店舗開発部や企画室など、本部の業務をマニュアル化した―業務基準書 このような仕組みとマニュアルを作るメリットとして、以下5点を挙げている。 ①「知恵」を共有する→すぐれた個人の経験を組織に蓄積 ②「標準なくして、改善なし」→標準を固めることで、それを応用して自分の頭で考えられる ③「上司の背中だけ見て育つ」文化との決別→マニュアルという見える形にすることで、効率的に指導できるようになる ④チーム員の顔の向きをそろえる→目的と理念を共有することで、志を一つにできる ⑤「仕事の本質」を見直せる→作成の段階で普段何気なくしている作業を見直せる また、一般的にこのようなマニュアル作成に対して、考えられる批判に対しては以下のように回答している。 批判1:マニュアルで全て決められていると面倒だし、仕事がルーティンだらけになりそう 回答1:現場のスタッフが感じた改善点を取り入れられる仕組みであれば、マニュアルは毎月更新され、仕事の進め方がどんどんブラッシュアップされて、仕事に潤いが出る。 批判2:わざわざマニュアル化しなくても、口で伝えた方が早いのでは? 回答2:口で言うと細部が個人個人の判断で微妙に異なってしまう。また、明文化されていれば、上司がいなくても判断でき、担当者の引継ぎも早くなるなど人材育成が効率的になる。 批判3:マニュアルに依存すると受け身の人間が増えて指示待ちになりそう 回答3:マニュアルは社員の行動を制限するものではなく、マニュアルを作り上げるプロセスが重要で、全社員・スタッフで問題点を見つけて改善していく姿勢を持ってもらうのが目的。もし受け身になるのなら、マニュアルを作ること自体ではなく、方法に問題がある。 批判4:マニュアルを作っても使われなくなってしまう 回答4:マニュアルを作ったことで満足し、問題点が報告されてもすぐに改良されないことが原因。リアルタイム、最低でも月に一度は見直しをする必要がある。 【感想】 どこの会社でもマニュアルや手順書といったものを作る機会はあると思うが、それを全社単位で仕組み化したというところに興味を惹かれて読了。自分自身もマニュアルを作成して使ってもらおうと試みたことはあったが、他者の意見を吸い上げてマニュアルに反映する仕組みを作らなければ、早晩使われなくなるというのは、実に納得できる話だった。組織として取り組むにあたっては、チーム全員を巻き込むことがポイントと感じた。
1投稿日: 2013.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ業種が違うとはいえ、仕事内容をすべての人にわかるように《標準化》するという発想はとても大事だと思う。ただ、形だけの会議や膨大な企画書などなかなか脱却できなさそうと感じるものも。机周りの整頓はかなり心がけているので一番共感できた。
0投稿日: 2013.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「情報を末端の方々にまで浸透させる。」そんな方法を今考えているのですが、ちょっとわかってきた気がします。 「どこの企業でもある話ですが、同じ作業でも、指導する担当者によって方法が違ったり、教え忘れていることがあったりと、ムラが出るものです。そのムラをなくし、どこの店のどのスタッフにも同じ知識とスキルを身につけてもらうために、「教えるためのテキスト」が指導者には必要なのです。」(p.105) 読んだその人が、その人以外に教えるためのテキスト。 教えるための方法を考えて、明文化。 勉強になりました。
0投稿日: 2013.10.05大事なことを読みやすくまとめています
読みやすさ:★★★★☆ 実用性 :★★★★★ 無印良品をV字回復させた松井会長の書籍。 従業員管理、オペレーション、戦略などをとても判りやすく、平易な言葉でまとめています。 無印良品に友人がおり、誠実に取り組んでいる社内事情も聞いていました。その内容がどうまとめられているかという個人的関心で読みましたが、参考になる点が多数ありました。 経営者、ビジネスマンにお勧めです。 あと、無印ファンの女性にもお勧めかな。店舗に行って、見る目が変わるかもしれません。
3投稿日: 2013.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ良品計画会長 松井忠三氏による、「組織の仕組みづくり」の記録。 無印良品には2冊の分厚いマニュアルがあるらしい。まあ普通の会社ならどこでも、業務マニュアルくらいありそうなものですが、他社との決定的な違いはその活用度合いのようです。 無印良品ではほぼ全ての店舗業務を、約2000ページの「MUJIGRAM」というマニュアルで管理しているそうです。 物凄いページ数ですが更に凄いと感じたのは、そのマニュアルを精査する部門が存在している事と、現場からのアイデアをもとに毎月マニュアルを更新している事です。 商談内容の共有方法までマニュアル化されているとは、チョット驚きでした。 自分も過去何度か業務マニュアル作成に関わってきましたが、どうしてもマニュアルが完成した時点で、妙な達成感を感じてしまうんですよね。 本来であればマニュアル活用の推進や、定期的な内容更新に心血を注がなければいけないのですが、まあいつも寿命は約1年という結果でした・・・ なんか言い訳になってしまいますが、やはり業務改革には現場の実行力だけではなく、組織全体の意識を変える仕組みづくりと、トップの強い意思が必要なのかなと思いました。
0投稿日: 2013.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なにはともあれ、実行することが一番大事。 その指針となるのが「血の通った」マニュアル。 マニュアルって、なんか形式ばったイメージで、気持ちが伴わないものだって決め付けてたけど、 「なぜそれをするのか」を明記することと、どんどん現場の意見を取り入れてアップデートしていくこと、確実に実行することに寄って、血の通ったものになる。 マニュアルどおりの対応をするためのものではなく、基礎をはっきりとさせて、応用していくためのもの、という部分で目からウロコ。 会社組織の改革についての本は、読んでも私には実行できずモヤモヤするけど、個人レベルから出来ることも最後にちらっと書かれていたので、出来ることからやってみよう。
0投稿日: 2013.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログV時回復の原動力は、努力を成果に結びつける仕組み、経験と勘を蓄積する仕組み、ムダを徹底的に省く仕組みを作ったことにある。人を変えるのではなく。 人の責任ではなく、仕組みの責任、その徹底。
0投稿日: 2013.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「マニュアル」は、無印良品の「仕組み」の象徴、『“無印良品のすべて”が詰まったもの』です。 マニュアルと聞くと「無機質で、冷たい印象がするもの」とイメージしますが、無印良品のマニュアルは、むしろ、日々の仕事に生き生きと取り組みながら、成果を出していくことができる、最強の“ツール”です。 詳細なレビューはこちらです↓ http://maemuki-blog.com/?p=1257
0投稿日: 2013.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログチームや、家庭を改革したいとう時に読み直したい。 無印良品をV字回復させた人のお話。 無印良品のマニュアルの話かとおもったら違った。 参考になるキーワードは、「実行95%、計画5%」、「仕組み(行動)を変えれば人の意識も変わる」、「知恵は他社から借りる」 「反対勢力はゆでガエル状態で染めていく」 マニュアルって否定論もあります。何か問題があったら、改善をしますが、するために考えるにはベース(個人の経験と勘であるノウハウ)がないと、考えられない。マニュアルはベースを全社員にみにつけさせ、改善への実行力を高めるためにあると捉えているようでうす。 あと、おもしろかたのが、家庭での夫婦円満の秘訣として、家事をマニュアル化しましょうって話。
0投稿日: 2013.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログうちの会社に合っていると思う。 もちろんアレンジは必要たけど。 みんなのノウハウを集めて マニュアルを作ってみたい。
0投稿日: 2013.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕組み化までには、ひたすら実践だな。それしかない。 以下備忘録 ・それぐらい口で言えばわかるのでは?も明文化する ・経験至上主義はダメ、仕事のノウハウ、スキルを蓄積する仕組みが必要 ・戦略二流でも、実行力一流ならOK ・実行95%、計画5% ・現場の意見を仕組みにしていく ・仕事を標準化させること ・新入社員でも理解できるマニュアルを作る ・マニュアルで人材育成する人を育成する ・MUJIGRAMも軌道にのるまで5年 ・同質の人間が議論をしても、新しい知恵はでてこない ・社員が満足できる商品を揃える ・認めるフィードバック ・夕方には新しい仕事を人に頼まない
0投稿日: 2013.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ率直にいうと、著者の信念が伝わらなかった本だった。 仕組みづくりや、輝かしい功績は数多く書かれているが、それ以上のものは感じなかった。 内容の中で、吉越さんが紹介されていたが、ノー残業デーの部分などは、吉越さんの本と文章が似過ぎていて気持ちが悪いほどだった。 無印良品の商品も、仕組みづくりも上質だと思うが、松井さんには残念ながら興味が湧かなかった。 ・イトーヨーカ堂が強いのは、本部から通達があると翌朝にはすべての店の売り場が出来上がっているという実行力 ・徹底したマニュアルの具体的化。「丁寧」ひとつも具体化する ・会社の理念紙に書き、朝礼のたびに唱和する会社もあるでしょうしかし、理念や価値観は、ただ言葉で語って聞かせても、具体性や実践を伴わなければただの言葉です。 ・クレーム7000件から1000件に。マニュアル化、情報の共有化 ・「同質の人間同士がいくら議論しても、新しい知恵は出てこない」 ・タグ(値札)を見直し、2億5000万円と50%のコストダウン ・ギャンブルの手発注から、自動発注へ ・根回し主義の改善 ・ネットによる先行販売
0投稿日: 2013.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白かった。 何も難しいことは書いてなくて、すぐ実践できそうなものばかりだった。 当たり前のことをやる。 行動を変えれば、意識は変わる。 作られたマニュアルにそっていくのではなく、自分たちでマニュアルを作って、そのマニュアルをもとに仕事に取り組む。 マニュアルは常に更新していくもの。 見える化がいかに大切か。 『あせらず、くさらず、おごらず』とても大切なことだと思う。まずは、とにかくできることから、始めてみようと思う!!
0投稿日: 2013.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ無印良品の仕事の進め方を紹介しているが、いまの自分にも役に立つ情報がたくさん。 割と最近は仕事で歯がゆいことが多く、いくつかハっとさせられた。 現場の人がマニュアルを更新して行ってる話が良くて、昔マニュアルで仕事をしていたときは、本部だけが更新権限を持っていてやりづらかったから。 結局何もない場所で自主性が生まれる人っていないんだろうな、だったらある程度線を引いてあげる。それを漫然とこなす人、疑問をもって取り組む人がいていいんだろうなと思ったり。 自分自身、今の業務はすべて意味があってすべて繋がってると理解してるのだけれど、理解できてない人には無印レベルまではっきり示してあげることも必要なんだろうな
0投稿日: 2013.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営状況の悪化した良品計画(無印良品ブランドの運営企業)をV字回復へ導いた著者が、構築してきた2000ページものマニュアルや、徹底的に標準化にこだわったシステムの一部を開陳しつつ、背景にある本質的な考え方を指南した一冊。 すでに名の通った企業の事例ですが、家業として経営しているスモールビジネスを次のステージへ成長させたいとお考えの経営者へおすすめします。
0投稿日: 2013.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ無印良品のマニュアルの作り方 MUJIGRAM 〜とは 何 なぜ いつ 誰が マニュアルは作った瞬間から陳腐化が始まる 無駄を省くこと、生産性を上げること、難しい方の選択肢に問題の本質があること 基本を整えておくと応用が円滑になる コミュニケーション ジョブズは洗濯機を決めるのに家族で一週間話し合った
0投稿日: 2013.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ無印良品が好きでよく利用する。店のコンセプトといい、コストパフォーマンスといいデザインといい、「いいなぁ~」と思うことが多い。そんな無印良品の本が偶然にも本屋に置いてあったので、買ってしまった。 無印良品の成功の裏には、「MUJIGRAM」という2000ページ以上に及ぶマニュアルが存在していることがわかった。そこには店舗設計からサービスから商品開発から人材育成まで、誰がやっても同じようにできる仕組みがあった。もちろん常に更新更新で、MUJIGRAMに終わりはない。 「へ~」と思うようなことも書かれてあったが、しかし!ちょっと僕にはつまんなさそうな企業に感じた。というか合わないだろうなと。というのも、何かの改善を思いついたなら、それが全社的に変化してしまうからだ。「お店のあの人に喜んでもらえるサービス」というのは、この規模の会社ではなかなか実行できないだろうなと思った。 根回し主義の箇所はびぶびっ!!ときた。公務員の組織はTHE,根回しやなと苦笑いですわ!!
0投稿日: 2013.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ・マニュアルは使うものでなく、つくるもの ・ノー残業デー、やるなら、17時以降は新しい仕事を頼まない、仕事にはすべてデッドラインを設ける、どうしても残業する人は10パーセントに抑えるなど、関連する工夫が大事
0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアル導入の際には是非読んでみて頂きたい良書。 無印良品の業績改善におけるマニュアルの効果を具体的なエピソードに沿って説明してくれる。エピソードが解りやすく、またマニュアルの作り方だけでなく、生かし方にも触れている所が興味深い。
0投稿日: 2013.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ・仕事は、マニュアル化がスタート地点。 ・企画書は、A4一枚。 ・関係部署は、3つまで。適切な部署が即決。 ・あせらず、くさらず、おごらず。
0投稿日: 2013.07.13
